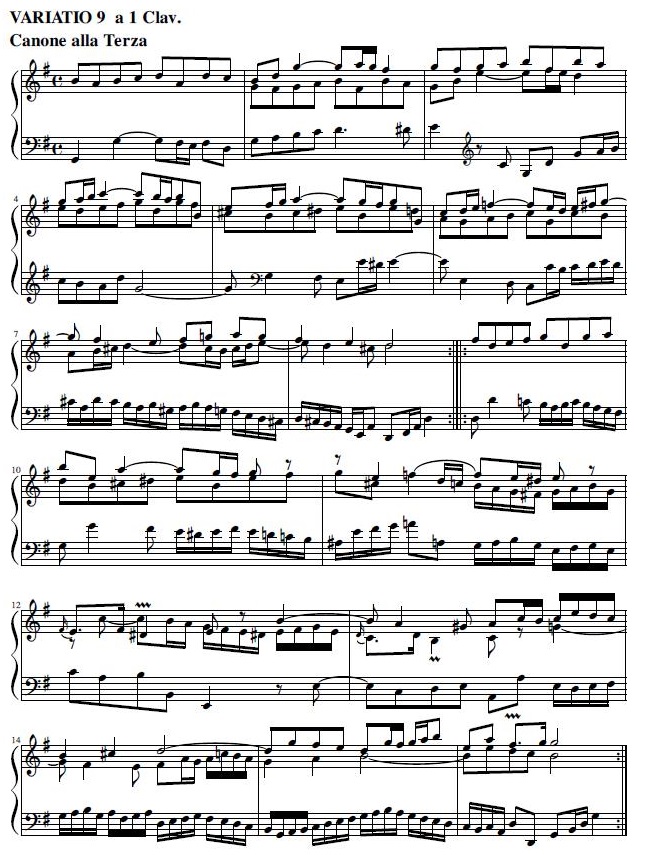|
第5章 第3群(第7変奏〜第9変奏) ゴルトベルク変奏曲の30の変奏を前半と後半とに分けた場合、前半は第15変奏までということになります。そして、ここ第7〜第9変奏によって構成される第3群れは、ちょうど前半の中間点にあたります。 アリア−第1群−第2群とテンポを徐々に速くしてきたのが、第5及び第6変奏でピークに達し、この第7変奏ではテンポを落とします。この変奏の特徴であるモルデントはチェンバロ曲では常套的につかわれる装飾で、音を延ばすことのできないチェンバロのためのものです。したがって、ピアノであれば装飾ではなくてペダル操作で音を延ばす(ケンプがやってます)ことで代えることはありえるのですが、グールドはあえてモルデントの装飾をピアノでやっていました。チェンバロのように細かく連打することはできないので、16分音符のスタッカートで、それらしくやっています。それゆえか、装飾は控えめで、後半はほとんど装飾をつけていません。そして、おそらく他のピアニストはグールドに倣って装飾をつけているのではないかと思います。曲の終わりではテンポと落とし、音を弱くして伸ばすようにして、次の第8変奏につなげています。それによって、落差をきわだたせようとしています。 ・グレン・グールド(1955年録音) 第6変奏からつづいているようなテンポでしっとりと弾いています。次の第8変奏で一転して急速テンポになるので、小休止といったところでしょうか。 シフのピアノの音(録音での音)は、このような装飾的な動きに最適なのかもしれません。トリルの細かい装飾的な動きにおいて少し残響を残しつつ程よい粒立ちで軽快に転がるかのようです。そして、シフの場合メロディを装飾するというよりも、装飾の動きとメロディの流れが一体不可分のようになっていて、トリルがメロディの流れに乗っているようなのです。しかも、この変奏では、高音部で低音部、右手と左手がともにトリルをかけるので、トリルの流れが掛け合いをしたり、並行して流れたりしているときに、このトリルが音楽の推進力を作っているような印象を受けます。それゆえか、シフのテンポは速めなのですが、急いだ印象はありません。また、後半ではリフレインをオクターブ高いところにしたりと遊び心を、ここでは発揮しています。 第7変奏がジーグという舞曲であるという性質を踏まえた演奏と言えるのではないか。それぞれの声部の線をくっきりと浮かび上がらせ、その反復のさいに様々なニュアンスで聴く者を飽きさせないのですが、トリルの装飾も、基本的には、その一環のようにして最小限に抑えて長く伸ばさないように弾いているように思えます。そこでは、旋律の線を生かしていることが、ペライアの、この変奏の演奏に対する基本姿勢となっていると思います。ただし、この変奏では、フレーズという節目をかなり意識していて、フレーズの終わりを念押しして切るようにして弾いています。聴いていると、フレーズの終わりでプツンと途切れるような感じになります。それが歯切れのよさで舞曲という性格を尊重してのことなのだろうともいます。それが、フレーズごとの変化を分かり易くしています。踊りの際に、ステップを即興的に変化して遊ぶのと同じで、例えば、繰り返しの際に、ペライアは装飾を加えたり、変奏の中で強弱をフレーズごとに変えたりしています。この姿勢は、この後の第8変奏にも同じように続きます。ペライアの演奏では、この第7変奏と第8変奏とをセットで考えられると思います。 ・ヴィルヘルム・ケンプ テューレックの第6変奏は、他のピアニストたちとは違ってピアニッシモで静かに始める、しっとりとした演奏だったため、その後である第7変奏は中庸の音量で弾いても、相対的に音が強くなった印象を受けます。しかも、硬質で輪郭がハッキリしたテューレックの音は、この変奏の装飾的なトリルを弾くと角張った感じになって、ぎごちない感じを避けられません。しかも、ポリフォニーの線を明確に際立たせているのが、この変奏では刺々しさと紙一重なのです。シフノのように装飾の靄のようななかでメロディが動いているのとはちがって、メロディがギザギザになって却って聴きにくくなっています。 ディナースタインのピアノの音はシフに近いもののようなので、雰囲気はシフに近い。しかし、トリルは極力短めにして装飾を抑制し、弱音を駆使して、ゆっくりと弾いているので、ジーグ(舞曲)の感じではなくて、他のピアニストの弾き方とは方向性が全く異なる、この人でしか聴けない演奏だと思います。この変奏で、こんなにもしっとりと落ち着いた、ある意味では瞑想的な演奏をしてしまっているのですから。静かに、ゆっくりと、バスは控えめで、右手のトリルは最小限にして、ペダルを踏み込んでヴェールのかかったような柔らかい音でポツリ、ポツリと左右の手のボソボソと会話するような始まり方で、繰り返しの部分ではピアニッシモに音量を落として囁き合うような、しかも、音と音の隙間をあけて囁きの間に静寂の間があく。しかも、ディナースタテンは小節が終わると、そこで一旦音楽の流れを休めるような切り方をします。まるで、無口な人どうしが、一言しゃべって、後が続かなくて、そこで話が途切れる。そこで沈黙が流れ、また言葉をしゃべる。それを互いに繰り返すといった、訥々とした会話を交わしている雰囲気です。静寂だけれど、寂しくはない。後半では、さらに音量を小さくして、タッチを柔らかくしていくので、内面に沈潜していくような印象です。これは、ディナースタイン独自の世界と言っていいと思います。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) 第6変奏をアグレッシヴに始めたのに対して、この第7変奏は柔らかく、静かに始めます。ジーグの指示が楽譜にあるので、軽快な雰囲気はありますが、基本的にはしっとりとした穏やかな演奏です。楽譜で指示されていても、トリルは極力短めにして装飾を抑えて、フレーズの形を、そのままで明らかにすることを心がけているようです。その2小節規模のフレーズをテーマにして、次は6度あがったところで、その次は音を分解して、といった、この第7変奏自体を変奏曲として聴こえてきます。しかも、5小節目から6小節目のところ、右手が32分音符の4連符で、この変奏のなかで一番高い音に駆け上がるところで音を強めます。その後、いったん静かな音に戻りますが、2小節あとの高い音でトリルをつけながらスラーと音を伸ばすところでも音を強めます。この変奏の中で強弱がつけられてドラマチックな展開がうまれています。前の第6変奏が下行するフレーズが繰り返され、下がっていく方向性なのに対して、続く、この第7変奏の上行するフレーズの高い音になったところで音を強めているので、この二つの変奏による一連のドラマとして捉えることができると思います。 ・アンジェラ・ヒューイット 基本的には速くもなく遅くもなく、ジーグの指示が楽譜にあるので、それらしいといテンポで、ノンレガートの弾んだタッチで音色は抜けのいい澄んだ音で、いかにも舞曲といった弾き方をしていると思います。とくにヒューイットはその透明なタッチでトリルの装飾をきれいに揃えて弾いていて、この変奏の特徴であるトリルを活かしている。また、右手が最初のテーマの繰り返しをしたあとの4小節目で32分音符の4連符でスラーがかかって上昇する動きをまるでトリルのように細かく速く弾きます。ヒューイットは、この変奏ではそういうフレーズをトリルのように弾いていて、さらに即興的にトリルを加えたりするので、そこかしこにきれいなトリルが、ひとつひとつはタップリではないのですが、それが変奏のリズムを作っています。そして、前半の繰り返しになると、ヒューイットは右手のタッチを柔らかくして、音色も籠もらせます。そして、バスできっちりリズムを刻んでいたのを、トリルが柔らかく浮き上がってくるような、フレーズの頭の音をはっきり弾かなくなります。つまり、一回目はいかにも華やかな舞曲だったのが、繰り返しでは幻想的なゆったりとしたものにへんかします。そして後半に移ると、この変奏ではもっとも強いタッチで決然と打鍵します。それまで、幻想的な夢うつつの世界にいたのを、ここで目を覚さまさせられて、バスの強いビートで身体を踊らされる。それが、また、繰り返しになると、一転して柔らかいタッチになって幻想の世界に入ってしまいます。まるで、身体を躍動させる(といっても華やかで優雅なダンスですが)ところて、幻想的な夢に寝入るという両極端を行ったり来たりする感じです。 ・マルティン・シュタットフェルト ここでも、バスの独立した動きが前面に出ます。ただ、第6変奏や第3変奏と同じようなので、この人にはバスの弾き方についてパレットの貧しさを少し感じました。変奏全体を通しても変化がなくて、単調に陥る傾向があるかもしれません。この変奏では仕掛けで救われていますが。繰り返しの際に、左手のバスのところを1オクターヴどころか2オクターヴ高いところ、つまり、右手よりもオクターヴ高いところを弾いています。たしかに音色は変化しますし、同じフレーズでもバスで弾いていた時とは別ものになったような印象です。前半部分では中間部分以外のところ、後半部分でははじめのところでそれをやっています。 ・セルゲイ・シェプキン シェプキンのピアノは変わった調律をしているのか、少し甲高いというのか、アップライトピアノのような歯切れのよさ、あるいはちょっとラグタイムに似た感じもします。それが、この変奏ではとても目立つし、それがよく特徴を活かしている演奏になっています。このトリルが多く出てくる変奏を、シェプキンは、それだけでなくて細かい音のパッセージもまるでトリルのように高速で浅い打鍵で軽く弾いています。そのために、特に全体はトリルのオン・パレードで、随所で出くるトリルを繋ぎ合わせているような全体の印象です。その繰り返しではタッチを変えてソフトにしています。最初は、その特徴的な調律の利点を生かしてギャラントな雰囲気を守り立てて、繰り返しでは、それを落ち着かせている。最後のところでは装飾を加えず、フレーズとして落ち着いた終わり方にしています。 ・イム・ドンヒョク ジーグという指示を無視するように、遅いテンポで(しみじみとした味わいのディナースタインよりも遅い)弾いています。弱音で、こもり気味の音で残響をたっぷり取りながら、ポツリポツリとゆっくり弾いていて、トリルもゆっくりひいているので分散和音のようにも聴こえます。それゆえ、ジーグの弾むような感じとは反対の重い足取りでトボトボ歩くような弾き方です。トリルや細かい音の動きの伴ったフレーズが繰り返されて前半の中間あたりで8分音符が基調の橋渡しのような小節を境に一段と音を弱くして、消え入るような、印象としてテンポも遅くなるように感じで、さらに淡々としたものとなっていきます。まるでモノローグのような。それが後半に移ると、変奏の冒頭の印象に戻りますが、真ん中あたりで、8分音符が基調のトリルのような動きのないところからは、前半の終わりのようになって、消え入るようになっていて、終わります。多少感傷的に聴こえるかもしれませんが、ディナースタインとは違った、しみじみとした第7変奏になっていると思います。聴く人によっては、遅すぎる、それゆえに緊張感や音楽の推進力がなくなってしまうと感じる人もいるかもしれません。 ・アンドレイ・カヴリーロフ この第7変奏はジーグという舞曲の指定で、付点のついた軽やかなリズムとシンコペーションのアクセント、そして随所にあるモルデントの装飾によって、軽快で雅やかな装飾的な演奏をするような変奏です。従って、おおくのピアニストは、それに沿う弾き方か、それに反発するようなしっとりとした演奏をしている人がほとんどです。しかし、カヴリーロフは、右手によるモルデントの装飾がたっぷり含まれる声部を機械的と言えるほどきっちりと弾いて、それで演奏全体をリードするペースメイカーにようにして、左手で弾かれるフレーズが、そのペースメイカーから逸脱していくような奔放で即興的な動きをさせています。以前に、このピアニストは身体に音楽が溢れているような人で、機械的に正確に弾いていると、歌いたいとか弾みたいというような身体から音楽が溢れてくるのを抑えきれなくて、機械的な正確さから漏れ出てくる、言ってみれば人間的なところが演奏の設計を壊してしまうところがあると指摘しました。この変奏でのガヴリーロフの演奏は、まさにこの人のそういう傾向を、そのまま演奏の形として、まるで自己パロディを演じているかのように演奏のパターンにしてしまった演奏だと思います。この演奏では、左手の動きが、今にも逸脱してとんでもないところに行ってしまいそうな奔放さがあって、しかし、それが単なる雅やかな装飾などというところに収まりきらない真正な音楽を紡いでいこうとしているのです。 ・エウゲニイ・コロリオフ コロリオフは、右手と左手がモルデントを含めた細かくてブリリアントなフレーズを交互に、掛け合いをしているように弾いています。ただし、それはシフがよくやるような対話しているように、ああきたら、こう返すというキャッチボールのような生き生きとしたものではなくて、タッチとか音色の変化を交互にやりとりしているという掛け合いです。一回目は残響をとって響かせるような豊かで輝かしいタッチで弾いていて、繰り返しの二回目では残響をデッドにしてソリッドなタッチで弾いていて、この変奏を響きの違いで聞こえ方が違ってくる変化を楽しむことができます。そして、両手の掛け合いの間を、一回目と二回目とでは微妙にずらしていて、ノリも微妙に違ってきていて、その趣向の変化を楽しむことができる演奏になっています。
・グレン・グールド(1981年録音) 第1変奏、第4変奏で、グールドは区切りをつけるような決然とした打鍵で曲を始めています。ちょうど三曲の変奏のグループのなかでアクセントとなるような効果を上げていると思います。それほど、最初のバスの強打はインパクトがあります。最初の8小節ではバスが4連符で直線的に下降する動きを強打するように強調していて、それに続いてバスが細かく上下に動くところは、今度はバスを抑えめにして右手の高音の細かい動きが代わって現れてきます。その交替はまた、バスが抑制されると、全体の強弱もフォルテからピアノに移る、その強弱の切り替えがコントラストをうんでいます。それだけ、最初の音とバスの下降する動きの印象が強くなるのです。そして、変奏の最後にバスが4連符で直線的に上昇する動きをするところで、変奏の最初と同じようにバスが強調されます。それで全体がフォルテとなって盛り上がったところで終わります。これらの変奏は1955年の録音では快速で弾いていますが、ここでのグールドは以前のように弾き急がず、手堅く、どっしりと構えています。その代わり、強弱のコントラストとメリハリによって劇的な展開をするように聴こえてくるのです。 ・グレン・グールド(1955年録音) 第7変奏はしっとりと弾いていたのが、この第8変奏に入ると一転して快速に駆け抜けるように弾いています。しかし、テンポをあげても強打することはなく強弱の点では抑え気味で、冷静さすら感じさせる演奏です。しかし、1981年の録音のようなメリハリはなくて、抑制したまま快速で弾き切る、平板にも聴こえるところがあります。 ・アンドラーシュ・シフ(1982年録音) 第7変奏の遊び心ある舞曲から、テンポが上がり疾走する感じです。方向性としては、グールドの弾き方をスピードアップし、強弱のアクセントを控えめにした流線型の演奏です。シフはここでは、ヴィルトゥオーゾになりきっている感じです。シフの癖なのでしょうか、グールドが第1音をわざとらしいほど強調したのに対して、シフは最初の音を弱めにして、むしろ2つ目音にアクセントを置くようにしているようです。そのため、フレーズの入りは滑らかにそっと入ってくるので、快速テンポで弾いていても、聴いている感じは穏やかで静かなのです。続いても、途中バスが前面に出ることがあっても、強弱のアクセントを控えめにしているので穏やかな表情は崩れません。とくに、繰り返しの際には、たとえば、前半の最初のところとか、後半のバスが上昇の動きをするとか、1回目のときとは異なる部分で前面に出して変化を与えて、動きはあるのだけれど、全体としては穏やかなまま、次のカノンに続きます。 グールドが右手のアクセントを強調したのに対して、ペライアは左手のバスが攻撃的で鋭く切れ込むようにフォルテでリズムパターンを強調します。第7変奏がジーグという舞曲でタッタタというリズムを際立たせたのと対称するようにタッタッタッという刻み。右手の細かいパッセージはリズムの装飾的な背景のように控えめで、したがって、この変奏に中で、左手がバスを弾いているときは、このようにバスが攻撃的で打楽器的と言えるほどビートが強調されリズム的なのですが、左手が右手と同じ高い音域の鍵盤を弾くときには、バスのように強調しないので、しかも、このときの左手の弾いているのは、右と同じような16分音符の細かな動きになるので、バスのときのような切れ味鋭くリズムを刻むことはなく、音が連なって流れるような弾き方になります。つまり、この変奏においては、ビートが強調されるリズミックな部分と、リズムが休んで音楽が相対的に流麗になる部分とに分かれてしまっているのです。これは、メヌエットのような舞曲でもダンスパートの間にトリオとして、演奏者も踊り手もひと休みする部分があるのと同じかもしれません。いずれにせよ、それがあるため、この変奏の演奏の全体がメリハリをつけられていると言えます。 グールドが決然と強打で開始したのに対して、ケンプは、優しくさり気なく、ゆっくりと始めます。グールドのようにフレーズに強いアクセントをつけて区切るのではなく、横の線をつなげて流れるように弾きます。その結果、姿をあらわすのは、右手の分散和音の美しい流れと、繰り返しながら、少しずつ上昇していくのにつれて開放されていくような広がりです。しかも、ゆっくりとしたテンポは、しみじみと内心から開放感がにじみ出てくるような、他のピアニストとは、おそらく正反対に近い方向性ですが、味わい深い演奏です。 第7変奏からテンポを速めますが、これは、次の第9変奏をじっくりと弾くための対照かもしれません。とはいっても、シフやグールドに比べればゆっくりとしたテンポで、疾走感とか派手なテクニックを披露することとは無縁な演奏です。ここではもの足りなさを感じてしまいます。この人の演奏では曲の真ん中あたりの両手でそれぞれに分散和音を弾くところなど特にそうなのですが、複合リズム的な響きが、チェンバロで弾くときの響きに近い聞こえ方をさせているところがあります。 第7変奏と同様に、シフに近い弾き方をしていると思います。この人もテクニックがあるのだということがわかります。シフほどの疾走感はありませんが、次の第9変奏をしっとりと弾いているので、連続性を考えているのではないかと思います。1小節目から右手は「レーソ−シ−ラ/ソ−シ−レ−ド/シ−レ−ソ」「レーファ♯−ラ−ソ/ファ♯−ラ−ド−シ/ラ−レ−ファ♯」というように動いて、左手は、それとは別に、それぞれの小節の最後で「ソーファ♯−ミ」「ファ♯−ミ−レ」となります。という右手の動きと左手の動きを並立させて、それぞれの動きが、この最初の形をスタートに変化しながら何度も繰り返すように現れて、曲を進めていく、二つの線として浮きあがらせて演奏しています。例えば、後半最初の左手のフレーズは、最後の4小節目では上下反転していて、それが終わりの盛り上がりをつけていくのですが、そのことをはっきり分かるように弾いています。この変奏は、技巧的で外に向かって発散するような性格の演奏をするピアニストは多いのですが、ディナースタインは一度は外に向かっても、還ってくる。つまり外に向かおうとして、却って内に還元されていく性格の演奏をしようとしていると思います。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) 一部を除いて変奏全体としてバスを抑えめにして、高音部の流れが前面に出てきているように聴こえます。最初の4小節目までの上昇音型を細かいところで変化しながら繰り返すところ、次いで反転するように下降の音型を繰り返していくところは、右手による高音部のフレーズが強調されるように前面に表われ、上がり、上がり、上がり、次いで、下がり、下がり、下がりという動きが伝わります。次いで、左手が高音部に移り、同じ高音部の中で両手が鏡像のように分散和音型で共鳴するように交錯するところでは、少し音を柔らかくしています。そして、後半の始まりで、右手が上昇音型を繰り返すところでは、ここでは左手のバスが右手に対抗するように強く弾かれます。その後では、音が弱まり、柔らかいタッチに変わって両手の線が交錯するようになっていきます。これは、上昇する動きと下降する動きを軸として、その軸をはっきりと示して、それが交錯していくところは緊張感が高くなりすぎて穏やかでなくなってしまうので、そこでは音を弱めて緊張を抑制しているのではないかと思います。そこで、この変奏の特徴である緊張感と、全体としての穏やかさとの両立を図っている、そういう演奏になっていると思います。 ・アンジェラ・ヒューイット この人はテンポなどでは、とくに個性的になろうということは考えていないようです。だから注意して聴いていないと、あまり引っかかるところがなくて、聴き流してしまうところがあります。この人の演奏の面白さは繰り返しになって、演奏が変化したところに気が付いて、どのように変化したのかを追いかけると、後になって分かってくるのです。前半の演奏は繰り返しになって、強いアタックで攻撃的にリズムがアクセントをつけて弾かれる。これに応じるように左手のバスも突っかかるように8分音符を強いアクセントで切るような鋭いタッチで、なおかつ休止を挟んで続く16分音符の下降するパッセージもはっきりと右手に対抗するように弾いている。これが分かると、最初のときには、右手は、リズミカルでしたが、これほど強打していなかった。まして、バスはリズムを支えて、フレーズのはじめの方の音はアクセントをつけて前面に出ていましたが、休止を挟んで続く16分音符の下降するパッセージなどはつなぎのように右手の動きの背後に隠れるようだったことに思い至ります。つまり、最初、ヒューイットは第8変奏はこういう内容だと聴き手に概要を見せてから、聴き手が分かったところで、繰り返しでこの変奏の特徴を強調して弾いて見せたというわけです。この演奏からは、「どうだい!!分かっただろ!?」というヒューイットの得意げな声が聞こえてきそうな気がします。 ・マルティン・シュタットフェルト この変奏では繰り返しをしていません。テンポも意外性はなくて、卒なく弾いています。後半で、少し装飾を加えているところが多少目立つところでしょうか。 ・セルゲイ・シェプキン シェプキンの本領発揮とばかりに華麗でゴージャスに美音を駆使してバリバリ弾いています。ひとつひとつの音は抜けが良くて、歯切れよく、音の輪郭をくっきりさせているので、リズムの縦の線がしっかりしています。それが、繰り返しになると、音は弱く、タッチは柔らかめにして、レガートで弾き始めると、弾き始めは幻想的なもやがかかったような響きで、その後はタッチはソフトなままですが、音の輪郭をくっきりさせて弾いているので、フレーズは明確です。しかし、繰り返しの最初の幻想的な響きのイメージが頭に残っているので、そのイメージで聴いてしまいます。それが後半になると、再び華麗な音で幻想を突き抜けます。それがとても爽快なのです。そして、後半の繰り返しでは、前半の繰り返しと同じように弾いています。 ・イム・ドンヒョク 快速テンポです。他のピアニストと比べると、とくに速いテンポで弾いているわけではないのですが、前の第7変奏が遅く重い演奏だったので、その直後のため、快速に感じられます。しかも、歯切れのいい音です。そういう演奏で、実際には、最初から右手が分散和音のような形で上昇していく音型が、小節ごとに繰り返していくのですが、その上昇していく音型が、繰り返しのたびに全体として低くなっていくのですが、他のピアニストであれば、楽譜を見ないで聴いている限りでは気づくことはないのですが、ドンヒュクは、それを響きの変化、つまり音色の変化で分からせるように弾いています。とくに、下降する音型が繰り返すにつれて、その音型全体が高い音の方に移っていくのを、音色が甲高くなるように変化させて、その移り行きが顕著に聴いてわかるのです。それが、後で、上昇するのと下降するのが交互になって、左手と右手が上昇と下降で交錯するようになるときに、この音色の変化が加味されて、非常にカラフルな、響きが生まれます。ポリフォニーというと音色はモノクロというイメージがありましたが、それからすると、ドンヒュクの演奏では極彩色といってもいいほど多彩に聴こえます。 ・アンドレイ・カヴリーロフ 第7変奏では機械的なほど正確な右手の演奏と、そこから音楽が溢れるように逸脱しようとする左の演奏のせめぎ合いのような演奏をしていましたが、カヴリーロフは第7変奏での右手と左手の共時的なせめぎ合いを、今度は通時的な関係に置き換えて演奏を組み立てていると思います。その通時的という、この第8変奏とその後の第9変奏を対立するに扱うことで、それぞれの変奏の性格を際立たせて、特に第9変奏においてメロディを歌わせることが際立つ結果となっているということです。そのために、この第8変奏は、機械的に弾いていて、さらにメカニカルな技巧を誇示するかのように速いテンポで弾いて、聴く者が目を丸くするような演奏をしている。ただし、それだけでは第8変奏は第9変奏の前奏曲のようになってしまうことになります。そんなことはないのですが、カヴリーロフは、この第8変更では冒頭から右手で繰り返される16分音符の4連符の上昇する動きが、この変奏全体のモチーフになって変奏を通して繰り返されているのを、他のどのピアニストよりもしっかりと聞かせてくれます。例えば、変奏前半の終わり近くなって、左手が低音の鍵盤から高音の鍵盤に移ったところで、この繰り返しを弾いているのですが、他のピアニストは、このとき右手が下降するフレーズを印象的に繰り返しているので、そっちを前面に弾いていて、左手はベースの位置付けにしています。それは、このとき左手はフレーズの一節のたびに低音の鍵盤と高音の鍵盤を行ったり来たりするので、どうしても影の脇役のようになってしまうのです。しかし、カヴリーロフは、ここで左手が繰り返しをしていることをさりげなく分かるように、右手の邪魔にならないようにしながら、しっかり弾いています。したがって、この高速の演奏が、実はひとつのフレーズがずっと繰り返されているということで、親しみ易い曲であることをしっかりと示している、そういう演奏をしています。 ・エウゲニイ・コロリオフ コロリオフは、弾むような弾き方で、この変奏のモチーフともいえる上昇するフレーズをスタッカートで弾きます。このときバスもいかにも弾んでいるような弾き方で、全体として楽しげな雰囲気になっています。そして前半の中間を過ぎて、右手がモチーフを裏返したような下降するフレーズを高い音から降りてくるように繰り返して弾くときになると、音色をかえて、よく響かせる派手めな音色で弾き始めます。ここで楽しげな雰囲気は高まります。そして、前半部分の繰り返しになって冒頭のモチーフを二回目に弾くときには、一回目の後半の派手めな音色で、しかも、スタッカートのポツリポツリした音から響きがのびる音で弾いていくと、二回目の中間すぎの下降するフレーズを右手がひくところでは、さらに輝かしい音色に変えて祝祭的な雰囲気を作り上げていきます。コロリオフは音色と弾き方に変化をつけていって、この変奏では祝祭的な雰囲気を作り出しています。
決然とした第8変奏から間をおかず、第9変奏を訥々と始めます。で、グールドは区切りをつけるような決然とした打鍵で曲を始めています。ちょうど三曲の変奏のグループのなかでアクセントとなるような効果を上げていると思います。これらの変奏は1955年の録音では快速で弾いていますが、ここでのグールドは以前のように弾き急がず、手堅く、どっしりと構えています。とはいっても、ゆっくりしたテンポまでは落とさずに、スタッカートでポロポロ弾くのが、この曲の場合には訥々とした語り口のように聴けてしまいます。最初、右手がカノンのテーマを弾き始めると、左手のバスが負けじとカノンのテーマを反転したような動きをして絡んでくるところなどは、グールド以外の人では聴くことがありません。1小節遅れて、右手の二声部目がカノンのテーマを追いかけていくところの三声の絡み合いはフーガを聴いているかのようです。堅実なテンポで抑制して弾いているのですが、聴いている側からすると耳がついていくのがやっとで、速い感じがします。それが、後半では動きが細かくなって各声部が絡み合いだすと、メロディが上行する音型なので、テンションが少しずつあがっていきます。それには、手堅いけれど、ゆっくりでないテンポが関係していると思います。基本的に、この曲は基本テンポの設定の違いが、ピアニストの弾き方の違いの大きな要素になっていると思います。 ・グレン・グールド(1955年録音) 第8変奏の快速テンポから一息して、この第9変奏には休止をおいてから入るような感じで、そっと入り、1981年録音のようにスタッカートの音の区切りをはっきりさせて訥々とした感じにするのではなく、滑らかにながれるように弾いていきます。テンポも速めなので、カノンの重なるような構造性というより、メロディが滑らかに流れることを重視した演奏になっていると思います。聴いていると、その勢いと流れとで、関心は先へ先へと誘導されます。 第8変奏とおなじようなテンポでも、落ち着いた感じに聴こえてきます。テンポなどはグールドの1955年録音につうじるところがあります。しかしシフはカノンのテーマを歌わせます。そのため繰り返すフレーズが他のカノン以上に聴き分けられて、耳で追いかけているうちに、あっけなく終わってしまうという印象です。とくに、カノンのテーマを弾いている右手の声部を強調して前面に出して、バスを抑えています。そのせいもあって、はかない美しさを湛えている変奏になっていると思います。 そんな中でも、装飾的なことはさり気なくやっています。例えば、最初のところでテーマを提示して、1小節遅れて右手のもう一つの声部(中声部になる)がカノンで追いかけるところで、シフは、この中声部で追いかけてテーマを弾く声部を前面に出します。そうすると、冒頭は最初高い声部でテーマを弾くのが分かるので、その後、中声部で続くように同じフレーズを弾くのがよくわかり、いかにもカノンだというのが聴き手にわかります。そして、この部分の繰り返しになると、今度は右手の二つの声部をバランスよく弾いて、1回目は影に隠れていたバスの動きを聴き取れるように弾いています。そうすると、ここは1回目でカノンであることを分かってもらっているので、そのことをことさらに明らかに示すことから進んで、三つの声部が絡むように動いていく複雑さが強調されるようになります。この変奏は落ち着い雰囲気で短いのですが、実は密度の濃い内容であることを、さりげなく示している、と言えます。 第8変奏で快速なテンポで弾いていたのを、ここでグッと落として、ゆっくりとカノンのメロディを聴かせるように弾いています。ペライアはバスを聴かせることを忘れていなくて、中間でバスがカノンのテーマを弾くところではバスにも歌わせ、後半の16分音符がタカタカ動いているところでは即興演奏のような自由な動きをしているように聴こえてきます。そのバスの動きがよくきこえるので、変奏の終わりに向かって、バスが上行していく動きがよく聴こえて、演奏全体が上行するようなところに至って、その空気が次の第10変奏に引き継がれていきます。 おそらく最もゆっくりした演奏の部類に入るのではないかと思います。ゴルトベルク変奏曲では珍しいうたうメロディをケンプはゆっくりと語りかけるように歌わせます。語りかけてくるような歌わせ方で。前の第8変奏が声高にならず、ゆっくり、静かに弾いていたのに続いて、ここでさらにゆっくりと、しみじみとした演奏がつづくことになります。 テューレックは全体としてじっくりと弾く人なので、この変奏を弾くテンポが他のピアニストに比べて遅いのですが、この人の弾くほかの変奏に比べると、それほどゆっくりとした印象ではないと思います。ケンプの演奏とテンポは同じくらいではないかと思いますが、印象はまったく違ってきます。テューレックの演奏には、ケンプの演奏のようなゆっくりと語りかけるような歌は聴こえてきません。そのかわり、硬質のくっきりした音でポリフォーの構造を構築しているテーマが明確にされていて、カノンの各声部が重なるように繰り返していく様子がガラス張りのように目に映るようです。 第7変奏、第8変奏、第9変奏とまとめた全体のテンポのとり方はシフの弾き方に似ているとおもいます。ただ、この第9変奏の弾き方は、シフのような第8変奏と第10変奏の間の間奏曲のような感じではなくて、ペライアのような第8変奏から第10変奏への橋渡しのような位置づけで捉えているように感じられます。というのも、この変奏の後半の弾き方が、バスが細かく動き回り、最後に向けて上行していくのを浮き上がらせるように聴かせようとしているからです。ここに、ディナースタインの手堅さが見て取れます。 それだけでなく、ディナースタインはペライアやケンプのようにテンポを落としてカノンのテーマの旋律を歌いこむわけでもなく、ある程度のテンポで弾いていながら、しみじみと聴かせる演奏になっています。テンポは落とさなくても、優しいタッチで右手がカノンのテーマをはじめて、前半部分ではバスを抑え目にして右手の二声によるカノンの掛け合いを浮き上がらせます。8分音符主体で構成されているカノンのテーマを音の隙間を空けるようにして、ポツリポツリと音が聞こえてくるような弾き方で、ただでさえ弱い音が、少なく聴こえるように。さらにこの前半を繰り返す際には、音をもっと弱めてピアニッシモで弾きます。それが後半に入ると、隠れていたバスを右手の二声と並べ立つように出してきて、一方右手の方では最も高い声部を押さえ目にして中声部を浮かせように弾いています。それによって、全体として、中声部とバスが前に出ていると、真ん中から下の音がよく聴こえるようになって、バスが細かく動き回る最後近くではバスのリズミカルなところが、結果的に強調されるようになって、次の変奏につなぐように終わらせます。つまり、単にしんみりと聴かせるだけの演奏をしているわけではないのです。 ・ピーター・ゼルキン(1994年録音) 第8変奏からはテンポも音の強さも落として、ゆったりとして、とはいっても勢いを失わないテンポでたんたんとカノンのテーマを訥々と聴かせる演奏をしています。はじめのところでは右手で二声のカノンとして、追いかけっこしているのが、演奏が進むにつれて交錯してひとつの流れとして、息の長いフレーズがたんたんと続いているように聴こえてきます。これに伴い、バスが同じように16分音符の動きがつながって音楽が流れ始める。ゼルキンはレガートっぽく弾き方を変えていったのではないかと思います。それが後半になると、同じようなテーマを、たんたんしていながら、スラーで音を伸ばすところでほんの少し息継ぎのような間をおいて、音をひそめるようにして、息の長い流れのなかに、微妙なうねりを加えます。これは並行するバスも一緒です。そのために、前半のたんたんとしたスタティックだったのが、後半は息づくように、かすかに動くのです。そこに、生き生きとした息づかい、人の声をきくような感じを与えるものになっていると思います。しかも、二つの流れは二つとも独立していて、決して交わることがないのです。 ・アンジェラ・ヒューイット この変奏のような3声部のそれぞれのメロディが互いに絡み合う様相では、ヒューイットがどの声部を、他の声部に比べてどのように扱うのかという、この人の腕のみせどころのような演奏が期待できます。まず、前半は一番高い声部をソプラノとしましょうか、そこでカノンのテーマがしっとりと始まります。このテーマが2小節にわたる長さで、その後半は2小節目になりますが、その2小節目から、右手の一つ低い声部をアルトとすると、このアルトが追いかけるようにテーマを始めます。そこでソプラノの音が強くなって、アルトの前に出てきます。普通、カノンではテーマがでてきて、次の声部で追いかけるようにテーマが始まると聴き手の注意がそっちに移るのですが、この演奏では、そうはさせじとソプラノがテーマをはじめるアルトの前面にでます。そして、そのままソプラノが前面にでてアルトがカノンで模倣しているのですが、ソプラノの伴奏、あるいはソプラノの合間をぬって聴こえてくるという印象です。これが繰り返しになると、始まりからソプラノに対してバスの動きが対等に聴こえてきます。2小節目ではアルトがソプラノに負けじとカノンのテーマの弾き始め、ソプラノの前に出ます。その後、ソプラノとアルトが対抗するように絡み合う中で、左手がバスから鍵盤を移ってきて第三の声部、かりにテノールとしましょうか、でカノンのテーマを追いかけるように弾き始めると、今度は、このテノールが前面に出てきます。そとて、前半の終わりで左手がバスに戻ると、三つの声部が対抗し合うように緊張感が高まって、後半に移ります。後半は、もっと複雑に変化させています。 ・マルティン・シュタットフェルト 軽快なテンポで、とくにカノンのテーマを歌わせるということなく、サラッと弾いている。この人の癖なのか、バスを同じような音で独立させていて、そのバスの音がぶっきらぼうな感じがする。それでカノンであるとかポリフォニーであるとかといった構造として演奏の力になっていなくて、散漫になっているもったいない感じがします。それで、繰り返しのところで、全体を1オクターヴ下げて弾きはじめると、何か低音のドスがきいたような感じになりますが、普通では左手が右手と同じ鍵盤を弾くように移るところで、の繰り返しの際には、逆に1オクターブ高いところを弾いて、完全に逆転して、音色も声部のかみ合わせも別の音楽になってしまったような感じです。前半の終わりもそうです。後半の繰り返しでも、1オクターヴ下がって、この入りと変奏の最後のところでは左手は逆に1オクターヴ上を弾いています。 ・セルゲイ・シェプキン シェプキンはカノンのテーマをたっぷりと歌わせます。始まりの音を伸ばし目にしてその後を後拍気味にして、ちょっと感傷的な印象で、それへの照れでしょうか、カノンで模倣するときにトリルをつけて模倣します。それが繰り返しになると、歌わせ方を抑制し、トリルをつけないようにして、カノンをしっかりと弾きます。後半も少ないですが、歌わせて、トリルも少しつけます。それが繰り返しになると、中声部とバスを浮き上がらせて、カノンを背景にして、それが演奏のリズムを作っている前で、中声部とバスの動きが即興的な掛け合いをしているかのように聴こえてきます。それは、この変奏では新鮮な響きでした。 ・イム・ドンヒョク かなり遅いテンポで、ロマン派のピアノ曲のアダージョのようです。とは言っても、ケンプのように腰を落ち着けて、じっくりと語りかけるようにカノンのテーマを歌わせるように弾いているわけではありません。しかし、しみじみと聴かせようとして弾いていることは間違いないと思います。というのも、この人の引き方と独特のようで、普通にメロディを歌わせることをしていません。しかし、テンポを落として、例えば、最初のカノンのテーマを提示するところで、8分音符の4連符の最初の音を附点気味に伸ばして、続く3つの音を短めにして全体の帳尻を合わせるようにするように弾いています。それ以外に、とくに表情をつけたりせずに、音は坦々としています。小節の中では、最初一つ目の4連符と二つの目の4連符とでは、同じ長さでなくて、心持ち1つ目を長めにする分2つ目で帳尻を合わせています。そこで生まれるリズムのずれ、簡単にいうとテンポ・ルバートですが、左手がポリフォニーの対向するフレーズを弾いているので、リズムの刻みがなくて、さりげなくやっているわけです。それが、右手と左手の微妙なずれをうんでいます。テンポがおそいので、音と音の間に空白ができて、それでズレが分かります。そこに、幅は狭いですが強弱が加わり、呼吸しているような感じを与えます。また、ノンレガートでひとつひとつの音の粒立ちをハッキリさせていることによって、これらの効果を合わせて、ポツリポツリと語っているような雰囲気をつくりだしています。 ・アンドレイ・カヴリーロフ この前の第8変奏の高速演奏からかわって、この変奏では、ガヴリーロフは殊更にテンポをゆっくりさせたりはしません。むしろ少し速いのではないかと思わせるテンポで弾き始めます。淡々としていて動きの幅の少ないカノンの主題をしっとりと弾くピアニストもいますが、カヴリーロフは淡々としてはいますが、速めのテンポでさっと弾いていきます。そこに何の細工があるわけではないのですが、例えばモーツァルトの音楽を疾走する悲しみ評した人がいましたが、一定のスピードで走るように動くことで却って聴く者に痛切に受け取られるような音楽があるとするならば、このガヴリーロフの演奏は、それに当てはまるのではないかと思います。これは個人的見解です。この主題がカノンで繰り返されるというのか、別の声部に受け渡されることによって、音楽が蓄積されていくようになって音楽の厚みが大きくなって、訴えかけるものの厚みが増していく、そこでの演奏にスピードがあることで重苦しくならず、ある種の透明さが失われないでいる。それが変奏の後半部分に移っていくと、左手のバスの動きが細かい音のフレーズを弾いている様子が即興的な、まるでショパンの即興曲のような指が勝手に動き出して音楽を作っていくような、きちっとしたカノンの形式的なところから逸脱するような動きを見せ始めます。まさに、弾いているガヴリーロフ自身から溢れ出した音楽がひとり歩きしていこうとする。それが、この変奏自体の音楽の痛切さを逆に聴き手に想わせる、そういう演奏になっていると思います。 ・エウゲニイ・コロリオフ コロリオフは、この変奏でも繰り返しの変化で聴かせます。最初にカノンを受け渡していく時には淡々としてしっとり弾いていきます。そのときには、このカノンの主題の演奏を浮き上がらせて、それが声部を変えて受け渡されていくのを前面に出します。そして、それ以外の声部の動きは、カノンの主題の演奏の背後に控えるようにしていて、その主題と掛け合いをするようにして出入りしているような弾き方をしています。それが繰り返しになって二回目になると、冒頭はびっくりするほどバスが前面に出てきます。むしろカノンの主題が背後に引っ込んでしまったかのようです。この二回目の前半では終始バスが浮き上がって前面に出て演奏されます。そうすると、最初の一回目では、カノンの主題がしっとりとした演奏で、少ししんみりとした印象だった演奏が、二回目でバスの動きが前面に出て、しかもバスの動きは上昇するフレーズだったりするので力強い、肯定的な印象が強くなってきて演奏の印象が変化してします。それが後半の演奏になると、右手と左手がほぼ並び立つような演奏になって、しんみりしたところと力強いところが同居しているのです。そして、後半の繰り返しになると、それが落ち着いたような音が弱くなって落ち着いた演奏になります。しかし、静かな演奏ではありますが、しんみりしたままで終わるのではなく、具体的に示されているわけではないのですが、雰囲気として前向きな印象で終わったという印象です。
リンク 。 |