(2)教養小説としての『説得』 まず、読み始める前に作品の題名について少し述べておきます。この小説を買おうとして本屋さんに行って書棚を探してみると、この「Persuasion」という原題の小説は、岩波文庫では『説き伏せられて』、ちくま文庫では『説得』と違う日本語の題名になっているのに気がつきます。これらは、別ではなくて、同じ小説ですので間違いないように。こんなことは珍しいのではないかと思います。ジェーン・オースティンといえば英文学では大メジャーで、日本でもファンは少なくありません。英文学の女性作家といえば、ブロンテ姉妹、ヴァージニア・ウルフらと並んでオースティンというくらいのメジャーな人のはずです。エミリー・ブロンテの『嵐が丘』は多くの人が翻訳していますが、題名はどれも『嵐が丘』です。ところが、オースティンの場合は、代表作ですら『高慢と偏見』『自負と偏見』『プライドと偏見』などと日本語の題名が翻訳者によってバラバラなのです。それぞれ翻訳者に拘りがあって、譲れないのかもしれませんが、オースティンの小説には、翻訳者に拘らさせる何かがあるから、と考えられると思います。 「Persuasion」という英語のタイトルを『説き伏せられて』という日本語にするのと、『説得』という日本語にするのとでは、何となく日本語の受け取り方のニュアンスが違ってくるのではないでしょうか。実は、この小説は、二人の主人公の間で、この小説の舞台より8年前にヒロインがPersuasionをうけたことについて、その意味合いが二人の間で食い違い、8年を経て再開したことで、その意味合いについて微妙なやり取りが交わされて、変化していくという話でもあるのです。それ以外にも、この小説の中に、大きなものから小さなものまで、様々なPersuasionが散りばめられています。この小説の中では、それらのPersuasionが関わり合ったり、対比されたり、そこから駆け引きが生まれたりという話として読むことも可能なのです。だから、Persuasionというタイトルの小説を『説き伏せられて』として読むか、『説得』として読むかによって、微妙に小説の読みのニュアンスが異なってくる可能性があるのです。だから、翻訳者が日本語タイトルを自分流で押し通したくなるのです。 この日本語の題名が食い違うという話題ですが、ここで少し述べたことは、そもそもジェーン・オースティンの小説の基本的な性格の特徴にかかわることではないかと思います。小説の読み方は、読む人によって様々にことなるもので、一律にこうだというものではありません。だから、これは、あくまでも私の読み方であることを先に、お断りしておきます。ジェーン・オースティンの小説というのは、主人公が行動し、何かが起こるというその内容、つまりはストーリーが魅力というよりも、そのストーリーをいかに語るかという語り口が大きな魅力となっているということなのです。例えば『嵐が丘』はヒースクリフという強烈な存在感をもった人物や彼とキャサリンとの荒唐無稽なストーリーといった小説の内容が大きな魅力であると言えます。これに対して、ジェーン・オースティンの小説は、当然ストーリーはあります。ストーリーの中で何らかの出来事はあります。しかし、その出来事が小説の中で語られる、その語られ方によって、読み手の受け取り方が変わってくるのです。その関係が、小説の中の登場人物たちの間でも同じようなことがあります。そこで生まれるすれ違いや共感といったことが、あらたなドラマを生んでいくのです。出来事が語られるということは、語り、つまり、会話が小説の中で重要な位置にあることになります。実際、オースティンの小説の登場人物たちは、それほど行動的ではありませんが、みなおしゃべりです。そして、小説の中でも、晩餐会での議論から、散歩でのちょっとしたやりとりまで、会話の場面の比重が大きくなっています。それは、小説の中で何らかの出来事があって、それを語られたものとして、小説の読者に語りというフィルターを通して表わしているのです。その語られたものを通して、読者はストーリーを、自分でも作っていくことができるようになります。おっと、少し先走りすぎました。これは、実際の小説を読みながら、体験してもらうべきことです。
2.あらすじ その体験をするまえに、予備知識として、簡単に小説のあらすじを紹介しておきます。オースティンの小説は波乱万丈とか荒唐無稽とは正反対の、平穏で単調な日々の生活の繰り返しのなかで、些細な事実を淡々と綴っていくものです。だから、日常の細かな叙述を追いかけることになります。そのあまり大きな物語の流れを見失ってしまうことがあるのです。そうならないように、あらすじの骨格をまず、がっちり掴んでもらって、今自分が読んでいるのは、全体の流れの中のどの辺りにいるのかを絶えず確認しながら読んでいくことができるようにするためです。 サー・ウォルター・エリオットの次女アン・エリオットは27歳の独身で、8年前の19歳の時に海軍軍人のフレデリック・ウェントワースと恋に落ちますが、周囲に結婚を反対されて、婚約解消に至ります。彼は当時、知性と活力と才気あふれるすばらしい好青年であったが、23歳の若さでまだ将校にもなっておらず、家柄も財産もなく、将来の見込みも未知数であったため、アンは母親の親友ラッセル夫人の説得を受け入れて、結婚を諦めました。しかし、彼女はその痛手と後悔から抜け出ることが出来ず、結婚適齢期を過ぎてしまいます。 彼女の家は父親の浪費癖から債務がかさんだ末、ついに長年住み慣れた屋敷を他人に貸して、家賃収入を借金の返済にあてることになります。その時に、屋敷の借り手として現われたのが海軍のクロフツ提督でした。そのクロフツ提督の夫人の弟が、あのフレデリック・ウェントワースでした。いまや、彼は海軍大佐で戦艦の船長であり、多額の財産を手にしていました。地位も財産もあるひとかどの人物となった彼は、アンとの失恋以後独身を貫き、いまや、結婚相手を探しに、クロフツ提督のもとにやってきます。 アンは屋敷を出ると妹のメアリーの嫁ぎ先で、近所の地主であるマスグローヴ家に一時身を寄せます。病気がちのメアリーが体調を崩したので、その世話が名目です。マスグローヴ家には娘が二人いて、たちまちウェントワースの相手として名乗りをあげます。アンは、ここでウェントワースと再会しますが、彼は8年前のことを屈辱として忘れておらず、二人の間には、冷たい空気が流れます。かれらをとりまく、マスグローヴ家の人々、ウェントワースの海軍の親しい友人たち、そして、アンの家族とラッセル夫人といった人々の思惑と動きが絡んで、舞台は、避暑地ライムから、有名な保養地バースに移り、二人、それぞれの捉われていた過去の桎梏から現在の自分を見つめなおし、お互いの存在を見出していきます。そして、相手がかけがえのない存在であることに、あらためて気がついて、8年の時を隔てて、愛を結実させるのです。
以上で、この小説のストーリーを紹介しました。波乱万丈の話でもないのに、長いものになってしまいました。というのも、細部がストーリーに関連して、ものがたりを豊かにしているからです。この小説では、その細部の表わし方を、どのように読み取っていくかによって、サイドストーリーが生まれてくることもあるのです。そのような読みを、これから試していってみたいと思います。その前提として、本来は作品を読んでもらうのが一番なのですが、それができなかった人もいるのであろうから、細かくストーリーを紹介したわけです。ここで、実際に読みを試みるのは、この小説のメインのストーリーである、アン・エリオットとフレデリック・ウェントワースのラブ・ストーリーです。 まず、作者であるオースティンの、この小説の語り方について、最初に簡単に指摘しておきます。この小説は、地の分と会話の二つの部分からなっていて、これは一般的な小説の書き方です。そして、地の文は話者が語るものですが、この小説では、この話者の視点が三つに分かれているようです。ひとつめは客観的に出来事や場面を記述する視点です。この視点では、誰が何をしたという行為の外形や出来事が起こったこと、風景の描写を鳥瞰するように客観的に述べています。ふたつめはヒロインのアン・エリオットの内面を語る視点です。話者が第三者の立場で、アンが何を思い、何を考えているかを客観的な地の文の中で述べているのです。そして、三つ目はアンが捉えた出来事という視点です。これは客観的ではないのですが、アンが見た出来事や世界が述べられるのです。そして、これらは明確に区別されていません。ある、人まとまりの文章のなかで、ある文が客観的な出来事を紹介した後に、突然アンの感想が挿入されていたりするわけです。読者は、だから、読み進めていくうちに、三つの視点の区別が曖昧になり、錯綜していくことになります。そこにストーリーの誤解を生まれ、これだけ淡々としたストーリーなのに、驚くことがあったり、ミステリアスに先が見なくなったりすることを体験することができるのです。また、客観的な出来事の叙述のすぐ後にアンが見たできことが続くこともあり、それは、客観的な事実と、アンによって認識され言及された言説が、同列に並べられ、しかも、紛らわしくなって、区別がつきにくくなってきます。小説の中の出来事が、客観的事実とアンによって言及されることはズレがあるはずです、それが同列に述べられることで、読者は同じように受け取ると、後になって、そのズレの影響が現われてくる時に、読者の側に驚きや戸惑いが生まれます。それが物語を劇的にしていくことになっていくのです。 また、この小説の背骨はアンとウェントワースのラブ・ストーリーであるはずなのですが、この小説の中で、二人が直接的に愛を語るラブ・シーンはひとつもありません。愛の告白ついても、最後近くの結婚の申込みのところぐらいしかありません。では、どうやって二人の恋愛が進行するのか。そこに間接的なやりとり、つまり直接的な出来事ではない、間接的な言及によって事態が進むのです。 そのようなことが、小説の中で、実際に、どのように体験できるか、それは、個々の細部を拾っていくことで、その一端に触れることができるのです。ここでは、アンとウェントワースが再会し、互いに相手を意識しなおし、最後の大団円となる結婚の約束となる筋をメイン・ストーリーとしてピック・アップとして、その部分を追いかけるように読んでいきたいと思います。なお、この小説をよむというとは、これだけに限られるものではなく、この他にも多彩で魅力的な読書体験をすることができます。ここでは、私の読みの体験として、このような魅力的な読みがあるということを述べていきます。なお、その他の魅力については、あとで、簡単に一部を紹介してみようと思います。全部を紹介することは不可能ですから。 ウェントワースが姉夫婦の借りたケリンチ・ホールにやってくると、その近所でアンが一時的に滞在している妹の嫁ぎ先のマスグーヴ家を訪問し、ディナーに招待されます。そこが、二人の再会の時となるのか、というところで、妹夫婦の子供が木登りに失敗して大怪我をし、アンが看病することになり、まずはすれ違いということになります。アンは、とりあえず再会を回避できて、ほっとします。その反面で、アンはウェントワースが自分と再会することをどう思っているのかを知りたがります。
ウェントワースがディナー翌日の朝食に招待されたのを辞退したことについて “アンには、ウェントワース大佐の気持ちがよくわかった。「彼は私に会うことを避けているのだ」とアンは思った。ウェントワース大佐は、昔のちょっとした知り合いのことを訪ねるみたいに、ついでにアンのことをたずねたそうだ。アンは、大佐をほんの少し知っていると言ったらしい。「たぶん私と同じ考えなのだ。つまり、ふたりが顔を合わせたときわざわざ紹介されるのを避けるためにそう言ったのだろう」とアンは思った。” ウェントワースとの再会はアンの朝食に、あいさつに立ち寄るというものだったが “「終わったのだ!終わったのだ!最悪の事態は終わったのだ!」とアンは、興奮と、感謝の気持ちで何度も自分に言った。(中略) 私はあの人に会ったのだ!私たちは再会したのだ!私たちはまた同じ部屋の中にいたのだ! だがアンはすぐに「もっと冷静にならなくては。感情を鎮めなくては」と必死に自分に言い聞かせた。あれからもう八年が経ったのだ。すべてをあきらめてから、もう八年が経ったのだ。長い歳月が忘却の彼方へと追いやったはずの、あの心乱れる思いをまた蒸し返すなんて、なんと愚かなことだろう!八年も経てば、何もかもかせ変わるのが当然ではないか。あらゆる種類の出来事、変化、疎遠、移動…何が起きても不思議ではない、そして過去の完全なる忘却も…なんと自然で、なんと確かなことだろう!八年といえば、私のこれまでの人生のほぼ三分の一ではないか。(中略) では、あの人の心はどう受け取ったらいいのだろう?私を避けたいと思っているのだろうか?だがつぎの瞬間アンは、こんな問いを発した自分の愚かさに呆れた。” これに対してウェントワースについては “フレデリック・ウェントワース大佐は、アン・エリオットを許してはいなかった。アンは彼にひどい仕打ちをしたのだ。彼を見捨て、彼を裏切ったのだ。さらに悪いことに、その行為によって、アンの性格の弱さが暴露されたのであり、そういう弱さは、決断力と自信にあふれたウェントワース大佐には我慢できないものだった。アンは、家族や友人たちの願いを入れるために彼を見捨てたのだ。強引に説得されて彼を見捨てたのだ。それはまさに、弱さと臆病さ以外の何物でもないのだ。八年前、ウェントワースはアンを熱烈に愛していたし、それ以後も、アンに匹敵するような女性に出会ったことはなかった。しかし、昔の恋人がいまどうしているかという、人情として当然の好奇心くらいはあったけれど、とくに再会したいとは思っていなかった。ウェントワースのアンに対する恋心は、すでにすっかり消え去っていたのである。”
ただし、オースティンは読者に対して、ウェントワースの隠れた真情を少しだけ匂わせています。つまり、彼が結婚を目的として行動しているのであり、ただし、アンだけは対象から外すという、逆説的に強く意識していたということ。しかも、結婚相手への好みとして「意志が強くて、気立てのやさしい人」という説明をしています。それは、周囲の説得に負けてしまったアンへの反発であり、気立てのやさしい人というのは、まさにアンの性格であるわけで、ここにアンへの愛憎が強く反映していた、というのは、この時点では分かりませんが、後になって、それが伏線であったことがわかります。 その後のディナーの席に二人は出席しますが、ウェントワースの周りには相手の候補者のような位置づけで年齢の若いマスグローヴ家の姉妹が、まとわりつくように相手をし、彼もまんざらではない様子を、描写しています。それを、アンは冷静に見ている。彼女は八年前の記憶から逃れられないでいます。彼と同席しているのが辛い。気まずい思いをしている。 ふとしたきっかけで、アンとウェントワースがふたりきりになる場面。アンが怪我をした子どもの看病しているところに、ウェントワースが見舞いに訪れます。他の家族がたまたま席を外しているところで、彼は驚き、いつもの落ち着いた態度を失う。気まずい時が流れる。そのとき、もうひとりの子どもが来て、アンにまとわりつきます。アンは看病の邪魔になるので、離れるようにいいますが、子どもはききわけがありません。そこで困っていると、次の瞬間、彼女は突然、子どもから解放されます。ウェントワースが、彼女にまとわりつく子どもを抱き上げ、引き離してくれた。 “それがわかると、アンは感激して口もきけなかった。お礼を言うことさえできなかった。気が動転し、気持ちが混乱し、そのままチャールズ坊やのそばに屈んでいるのがやっとだった。あの人は私を助けきてくれたのだ。何も言わずに、ウォルター坊やを引き離してくれたのだ。なぜこういうことになったのだろう。…でもあの人はいま、ウォルター坊やを相手にわざとらしく騒いでいる。たぶん、私にお礼を言われるのを避けるためにとうしているのだ。私と話をしたくないということを示すためにそうしているのだ。こうした考えが頭の中をぐるぐると回り、アンの心は千々にみだれ、どうしてよいのか分からなかった。” この文章は、地の文の客観的な記述の中に、さり気なく挿入されるように、続けられています。ここにも、客観的に視点とアンの視点のまぎらわしさがあります。おそらく、オースティンは意図的に、紛らわしく記述しているのだと思います。これは、そういう記述方法と、読み手に、それに馴れさせるために、このような些細なエピソードでも用いていると思います。 アンは、少し離れた立場で、ウェントワースと彼の周囲のマスグローヴ姉妹との関係を観察して、彼女なりの判断をします。それは、彼女の感想でありながら、客観的事情としてもそうであるように、オースティンは記述しています。個々にも、客観的な記述とアンの内心の記述の紛らわしさがあります。 “アンの意見はざっとこういうものだった。どちらかと言えば、ヘンリエッタよりルイーザのほうがウェントワース大佐に気に入られていると思うが、アンの記憶と経験から推測すると、ウェントワース大佐はどちらにも恋をしていないと判断せざるを得ないのだ。ただしヘンリエッタとルイーザのほうが大佐に恋をしているのだ。ただしこれも、恋とは言えないかもしれない。でも、いずれは恋になるということもあり得るし、ほんとうはそうなるかもしれない…。(中略)ウェントワース大佐は、自分が誰かに苦痛を与えているなどとは夢にも思っていないし、アンにはそれが一番うれしいことだった。大佐の態度には、勝ち誇ったような得意そうな態度はまったく。ないのだ。…大佐に悪いところがあるとすればただひとつ、ふたりの若い女性の愛情を、一度に同時に受け入れたところである。たしかに、「受け入れた」としか言いようがないのだから。” アンは、ウェントワースがマスグローヴ家の若い姉妹に対して恋愛感情を抱いていないことをアンは冷静に分析しています。物語は、まだ始まったばかりです。この時点で、アンはすでにウェントワースと若い姉妹の関係を見透かしているのです。これでふたりのすれ違いにやきもきするという恋愛物語は続けられるのでしょうか。しかも、この後で、アンはウェントワースと姉妹の妹ルイーザが婚約したと誤解して絶望的になるのです。それでなくても、アンはウェントワースの行動にやきもきし続けます。アンは、この分析の結果、ウェントワースを冷静に見ることができているかといえば、そんなことはないのです。それでは、この時点の分析は誤りだったのでしょうか。それとも、後になった情況が変化してしまったのでしょうか。 おそらく、読者は、この記述を読むことは読むのですが、さりげなく書かれているので、はじめてこの作品を読むような人は、記憶に残らないように読み流してしまうのではないかと思います。その後に、ウェントワースとルイーザの仲睦まじげな様子が何度となくでてくるので、読み手の注意は、そちらに移ってしまうことになるでしょう。しかも、アンがやきもきしたりするところが出てきます。それでなおさら、ウェントワースとルイーザに注目するように導かれることになります。だから、この部分は、最後のアンとウェントワースが結ばれる時に思い出される伏線となります。しかし、この作品を二度目以降に読む人は、結末がわかって読むので、この部分を素通りできなくなります。そこで、はじめて読む場合と、二度目以降に読む場合とでは、この部分を押えているかどうかの違いになって現われてきます。その違いは、ウェントワースとルイーザの関係の見方の違いに結びついていくことになるわけです。こういうところが、オースティンの小説を何度も読みたくなる要因のひとつなのです。 このような書き方は、ミステリーであれば倒置法のテクニックでしょう。つまり、当事者を話者としてしまうことによって、読者の視点を限定して、読者の前に展開される世界を絞って、客観的な世界とのギャップに犯罪のトリックが隠されているという手法です。ジェーン・オースティンの小説は、『高慢と偏見』『分別と多感』『マンスフィールド・パーク』など、ヒロインが巧みな戦略で男性をゲットするという狩りの物語の構造になっているという見方もできると思います。そして、この作品も、まさに、その仲間に入ります。言ってみれば、アンという聡明な女性がウェントワースという一度逃した獲物を、その失敗をうまく利用して求婚せざるを得ないように追い込んでいく、いわば完全犯罪の物語になっていると言えるのです。しかし、普通に、この小説を読むと、そのように感じる人などいないでしょう。おそらく、聡明な女性が正しい行いをしていて、最後に幸運に恵まれるという物語といえば、納得する人は多いのではないかと思います。しかし、完全犯罪の物語と幸運の物語は同じ内容の裏表で、主人公が能動的か受け身かによる違い程度でしかありません。一見幸福な物語の、その裏に完全犯罪が隠されているというところに、この作家の毒があるといえるのです。 その倒置法の毒は、さらにもうひとひねりの細工が加えられています。それは、語っている当のアンが信頼できない語り手であるということです。それは、アンにはウェントワースに関する情報が間接的にしか与えられないことと、アンが中立的な立場にないため客観的な認識ができないからです。後者の場合、アンはウェントワースへの思いを持ち続けており、かつて彼の婚約を解消したことに対する負い目もうるので、彼を見る目にはバイアスがかかってしまってしるのです。ただし、読者には、それが不正確であるということよりも、物語の展開のもどかしさ、歯がゆさとなって表われてくるのです。それを可能にしているのは作者オースティンの語り口なのです。その語り口を追いかけているところで、いよいよ前半の佳境に入って行きます。 そして、前半の重要な示唆的なシーンのひとつ、マスグローヴ家のいとこチャールズ・ヘイターを訪ねての散歩に、アンとウェントワース、マスグローヴ姉妹、そして彼女の妹とその夫が出かけます。この訪問は、姉妹の姉のヘンリエッタがヘイターとのちょっとした仲違いから、彼への愛に気がついて、仲直りをするために姉妹で企画したものです。ヘンリエッタは気が弱いところがあるので、妹のルイーザか協力した。それに偶然、他のメンバーが加わったという事情です。その途中で加わったメンバーは事情を知りません。とくに、アンの妹メアリーはわがままな性格でヘイターを嫌っています。散歩の途中で、行き先がヘイターを訪れることが分かると、メアリーは、異議を唱え途中で引き返そうとします。ヘンリエッタはメアリーに引き摺られて、決心を鈍らせ引き返そうとします。ルイーザは、姉を説得し、ヘイターを訪問させることとし、アン、メアリー、ルイーザそしてウェントワースで休憩して待っているということに話をまとめます。ウェントワースは、そういうメアリーを軽蔑の眼差しで、冷たく見ていたのをアンは見逃しません。いつしか、休憩していた4人はばらばらになり、アンは木陰でルイーザとウェントワースの会話を、聞くともなく耳にします。 “「それで、私がやっと姉を行かせたの。あんなこと(メアリーが異議をとなえた)を気にして訪問を中止するなんて耐えられないもの。まったく!私は自分で決めたことは、そしてそれが正しいと思ったことは、何が何でもそうするわ。あんな人ニ偉そうに何か言われたくらいで、尻込みしたりしないわ。いいえ、誰が何と言っても自分の思ったとおりにするわ。あんな人に偉そうに何か言われたくらいで、尻込みしたりしないわ。いいえ、誰が何と言っても自分の思ったとおりにするわ。あんなに簡単に人の言うなりになるなんて信じられない!私は一度決心したら絶対にそうするわ。ヘンリエッタだって、今日はウィンスロップのヘイター家を訪問すると決心していたのよ。それなのに馬鹿なことを気にして、もう少しでやめるところだったの!」 「それじゃ、あなたがいなかったら、ヘンリエッタさんは引き返していたんですね」 「そのとおりよ。お恥ずかしいはなしですけど」 「ヘンリエッタさんは幸せですね、あなたのようなしっかりした妹さんがそばにおられて!ぼくはこのあいだ、チャールズ・ヘイターと同席したときに、あることに気がつきました。そしていまあなたのお話を聞いて、ぼくの観察が正しかったことがわかりました。だからもう、チャールズ・ヘイターとヘンリエッタさんのことを知らない振りをする必要はないでしょう。つまり、このウィンスロップ訪問は、単なる儀礼的な「朝の訪問」ではないんですね。しかし、チャールズ・ヘイターもヘンリエッタさんも、これでは先が思いやられますね。もっと重大な問題が起きても、勇気と決断力が必要な状況に立たされたらどうするんでしょう!こんなに些細なことでも、ちょっと何か言われたくらいですぐに引き下がってしまうようでは、先が思いやられます。ヘンリエッタさんはとても気立てのいい、心のやさしい人です。でもあなたは、決断力と意志の強さを持った人です。もしあなたがヘンリエッタさんの振る舞いと幸せを大切に思うなら、あなたの力強い精神をたっぷり吹き込んでおあげなさい。でも、いつもそうなさっているんでしょうね。従順すぎて優柔不断な人の一番困った点は、どんな影響力も当てにできないということです。どんなにいい影響力でも、長続きするかどうか分からないからです。つまり、どんなにいい忠告をしてあげても、ほかの誰かに何か言われると、すぐに気持ちをぐらついてしまうんです。幸せになりたいと思ったら、気持ちをぐらつかせてはいけません。(中略)」 「ぼくのまわりのすべての人たちに第一に望むことは、気持ちをぐらつかせず、強い意志を持つことです。」”
“「メアリーお義姉さまは、いいところもたくさんおありですけど、ときどきものすごく癪に障ることがあるんです。ときどきすごく馬鹿なことをおっしゃるし、ものすごく気位が高いんですもの。エリオット家の気位の高さですわ。准男爵家というエリオット家の家柄をものすごく自慢にしているんです。チャールズお兄さまがアンさんと結婚してくれていたら、ほんとによかったのに。チャールズお兄さまがアンさんにプロポーズしたのはご存知でしょ?」 一瞬の間があって、ウェントワース大佐が言った。 「つまり、あの人が断ったのですか?」 「ええ、もちろんそうよ」 「それはいつごろのことですか?」 「正確には知りません。ヘンリエッタも私もまだ学校にいたときですから。でもたぶん、兄がメアリーさんと結婚する一年くらい前だと思うわ。アンさんが兄と結婚してくれたらよかったのに。そうしたら、みんなアンさんをもっともっと大好きになったと思うわ。アンさんが断ったのは、彼女の大の仲良しのラッセル夫人のせいだと、お父さまとお母さまは思っているの。うちのチャールズお兄さまは、ラッセル夫人に気に入られるほど学問もないし、本好きでもないから、それでラッセル夫人が、アンさんを説得して断らせたんだって」” ここで、ポイントとなる事は二点あります。一点目はウェントワースが、アンに彼以外に求婚者があって、それをアンが断ったという事実を知ったということです。それは、ウェントワースがアンに注意を向ける契機となるものと言えます。慥かに、この前の時点でも、ウェントワースがマスグローヴ家の若夫婦のコテージを訪ねたときに、偶然アンと二人となり、看病をしているアンにまとわりつく子どもを抱き上げで、アンを助けたことがありました。しかし、これは室内で、アンと二人の状態であったので、アンが困っているのはすぐ分かる状況であり、心優しいウェントワースは彼女を助けたということだろうし思います。アンは、そこで八年前と変わらぬウェントワースの姿を確認するわけですが。しかしウェントワースは、この散歩の帰りの途中で、たまたま通りかかったクロフト夫妻の馬車に、疲れた様子のアンを乗せるように手配します。それは、室内で二人の状態で当然のように見えてしまったアンの窮状ではなく、クループで散歩している中でアンが疲れているのを分かるということは、グループの中でアンを継続的に注意していなければ、分からないことです。つまり、それまでのウェントワースの振る舞いは、アンに対する恋心は消え失せて、避けていた。だから、偶然、アンと会っても、そそくさと別れてしまう。アンを見ないようにしていたと言えると思います。そのようなウェントワースが散歩の間、アンを見ていたはずがありません。それが、アンが疲れていることに気付いたのは、彼女を注意するようになったからです。というのも、彼には、ルイーザがいつも話しかけていたでしょうし、帰りは、ウェントワースとマスグローヴ姉妹、そしてメアリー風とアンという二つのグループになっていたので、ウェントワースは、意識的にアンに注意を向けなければ、彼女が疲れていることに気付かなかったはずです。それには何かのきっかけがあったはずです。それが、この会話の中にあったと思います。 二点目は、この会話でルイーザが話した内容は、事実と異なる部分があるということです。アンが、チャールズ・マスグローヴの求婚を断ったことは、小説の前のほうでも説明されていました。しかし、その説明では、この会話とは違ってアンが自身の意志で断ったのであり、ラッセル夫人の説得を受けたわけではなかったのです。つまり、ウェントワースは、正しい事実を伝えられなかったのです。実は、この後も、ウェントワースはアンに関して本人以外の誰かから話をきいて何らかの情報を得ることが何度かあるのですが、それが事実が正しく伝わらないのです。そして、それらは、物語の進行にとって重要な事実なのです。例えば、この後で、アンとエリオット氏が婚約したということを聞くのですが、それは事実ではありません。事実とその言説のずれがここにあります。つまり、ウェントワースは、アンに関する間違った情報を聞くことによって、彼女に対する感情や認識を改め、新たな行動に出ているのです。このずれが、ウェントワースを突き動かす原動力となってと言えるのです。はじめのところで、少し触れましたが、ジェーン・オースティンの小説は、事実として起こった出来事と、それを言葉に表わした言説のずれが物語を生んだり、進めさせているという特徴があります。この場面などは、その典型的でわかりやすい例と言えます。
“アンは激しい感情に襲われ、金縛りにあったようにうずくまったままだった。まず気持ちを落ち着かさなくては、動くこともできなかった。でもアンは、立ち聞きする者の運命だけは免れた。つまり、自分の悪口だけは聞かずにすんだ。しかし、胸を突き刺されるような言葉はたくさん聞かされた。自分の性格がウェントワース大佐にどう思われているかよくわかったし、彼の話し方には、アンに対する思いと好奇心がたっぷり感じられ、アンは激しく心を揺さぶられずにはいられなかった。” そして、さきほども少し触れましたが、散歩の帰り、疲れたアンはウェントワースの気遣いにより、クロフト提督夫妻の馬車に乗せてもらうことができたわけです。 “そう…みんなあの人がしてくれたのだ。アンは馬車の中で思った。あの人が私を馬車に乗せてくれたのだ。あの人の意志と、あの人の手が、私を馬車に乗せてくれたのだ。あの人は、私が疲れていることに気がついて、私を休ませてあげようと思ってそうしてくれたのだ。これらのことで明らかになったウェントワース大佐の気持ちを思うと、アンは激しく心を動かされずにはいられなかった。この最後の小さな出来事は、これまでのすべての出来事の結論であるように思われた。アンはウェントワース大佐のいまの気持ちを理解した。あの人は私を許すことができないのだ。でも、私に対して冷酷な気持ちにもなれないのだ。私の過去の振る舞いを責め、不当なほど激しい慎みを懐いてはいるけれど、そして、もう私への愛情は冷めてほかの女性を愛しはじめてはいるけれど、それでもあの人は、私の苦しんでいる姿を見ると、救いの手をさしのべずにはいられないのだ。これはかつての愛情の名残なのだ。本人も気がつかない純粋な友情が衝動的に示されたのだ。あの人の心の温かさとやさしさの表れなのだ。こうしたウェントワース大佐の気持ちを思うと、アンは、喜びと苦しみに引き裂かれたような感情に襲われたが、喜びと苦しみとどちらが大きいかは自分にもわからなかった。” (4)アンとウェントワースが相手を再認識する(ライムへの旅行) この後、物語は大きな転換点を迎えます。散歩をしたメンバーたちが今度は、近くの避暑地であるライムに小旅行することになります。そのきっかけは、ウェントワースが海軍での親しい友人であるハーヴェルから冬の季節をそこで過ごすから一緒にどうかという誘いを受けたのを、他のメンバーが、彼の話をきいて同行することになったというわけです。
“「でも」とアンは、四人がこちらに近づいてきたとき、ひそかに思った。「たぶんこの人は、私ほど深い悲しみを抱いているわけではないわ。この人の将来は永遠に閉ざされたわけではないんですもの。この人は私より若い。実際の年齢はどうあれ、気持は私より若い。人間として若いのだ。いずれ元気を取り戻して、他の女性と幸せになるに決まっている」” ということは、ベニックは亡くなった婚約者への思いであるとか、婚約者を失った悲しみをアンにある程度語っていなければ、アンはこのような評価・判断はできなかったはずです。その際に、アンはベニックを慰めたり、励ましたりして反応をみているはずです。そのあったはずのやりとりをオースティンは省略して、すっ飛ばしてしまいます。しかし、読者は書かれていなくても、何となく分かる。想像できる。ということは、読者は、先ほどの『高慢と偏見』のジェインとビングリー氏もそうですが、読者は想像することで、物語を膨らませていくことができる。オースティンは恋愛小説の肝心なところを敢えて省略して、読者の想像に任せているともいえますし、また、それによって展開がスピーディーになっているという効果もあると思います。では、作中の、この場面を想像してみると、皆があつまって食事か団欒の語らいをしているなかで、ウェントワースとハーヴェルが中心になって海軍の話題を語り、マスグローヴ家の姉妹や若夫婦が参加して盛り上がっている。その輪から離れて、もともとシャイなところがあり、今は婚約者を失った悲しみの中にいるベニックは楽しい会話の輪には入らず、詩を吟じていて、傍らにアンがいて、ベニックの相手をして、落ち着いた会話をしている。その二人を遠目に、ウェントワースが時おり注意を向けている、といった風景です。それは、以前に触れましたが、翌日の散歩でハーヴェルがアンにベニックと話をしたことを感謝するという場面がありました。それは、ウェントワースはハーヴェル以上に二人を見ていたことを暗に示していると想像することに無理はないでしょう。一方、アンはといえば、ウェントワースに見られていることは、分かっていたと想像できます。そこでは、アンは現実の場ではベニックと会話をしていましたが、その背後のウェントワースの存在を意識していたと思うのです。それは、小説のラスト近くの山場で、アンはハーヴェルと愛の永遠性について議論をしますが、それは直接の相手はハーヴェルでしたが、真の相手は背後に座って手紙を書いていたウェントワースだったという場面に通じていると思います。つまり、オースティンは語りに工夫をするだけでなく、語らないことによって物語を進めてもいるのです。
“最後に突堤に行ったのは無分別だったし不運だったとヘンリエッタが嘆き、あんなことを思いつかなければよかったと後悔の涙を流すと、ウェントワース大佐が突然打ちのめされたようにこう叫んだのである。 「そのことは言わないでください!ああ!あのときぼくが譲歩しなければよかったんだ!ぼくが止めればよかったんだ!でもルイーザは、どうしても飛び降りると言って聞かなかったんだ!ああ、ルイーザ!」 大佐のこの言葉を聞いて、アンは思った。大佐は以前ルイーザに向かって、「幸せになりたいと思ったら、強い意志も持たなくてはいけません」と言い、断固たる性格こそ幸せをつかむ道だと言ったけれど、彼はいま、その意見が正しいかどうかは疑問に思ったのではないだろうか。人間のすべての性質と同じように、断固たる性格といえども、釣り合いと限度が必要だと思ったのではないだろうか。他人の意見に従う性格も、断固たる性格と同じように、ときには幸せをつかむことがあるかもしれないと思ったのではないだろうか。” しかし、これによって二人の関係はかなり進展するはずですが、オースティンは馬車の中の二人について読者の想像に任せているようで、記述を省略してしまっています。しかし、上で引用したのは、オースティンにとっては、記述を省略できないところ、絶対必要だから書いたところです。それは、他人からの説得を聞くこと、説得に応じることと、自己の意志を貫くこと、それにたいして自己中心なわがままで周囲に迷惑をかけてしまうこと、それらの分別について、ウェントワースが以前の考え方について誤解していたことに気付くことになっている場面です。強い意志を持っていると誉めたルイーザが、周囲に多大な迷惑をかけるだけでなく、自身も傷つけ、自己中心で周囲を顧みないメアリーの体たらくと、相手を第一に考えるアンの行動を見比べて、8年前の説得に応じたアンの行動を見直すだろうことが、何も書かれていませんが、読者は想像に導かれる。そこで、二人の関係はどうなるのか。また、アンは説得されるだけでなく、ライムではベニックを励ますために散文を読むように説得をする側にもいたのです。それをウェントワースは見ています。最初のところで、この小説の日本語の題名を『説き伏せられて』と『説得』と訳者によって異なると述べましたが。ここでのべたように、この小説には説得ということをめぐって、様々な場面がでてきて、それどれの場面で説得の意味合いや、人々の受け取り方がさまざまに変わってきて、そのことを巡って言説が様々に呈示されます。だから、見方によっては、この小説は説得を巡って言説が交わされ、それによってうまれるドラマと捉えることができる側面を持っています。だから『説得』という題名をつけている。それを単に『説き伏せられて』としてしまうと、19歳のアンが説き伏せられてウェントワースとの婚約を解消したことからスタートするラブストーリーということだけになってしまいます。それは、訳者が、そういう小説として翻訳したということのわけで、読者としては、そのどちらを選択するか、この小説をどのように読むかと大きく関係していると思います。 そして、物語は最後の舞台であるバースに移り、そこで急展開があって大団円を迎えることになるわけです。その前に、アンとウェントワースはライムからマスグローヴ家に戻ると、ウェントワースは折り返すようにライムに引き返します。ルイーザに対する責任も彼は感じていたでしょうから。そこで二人は分かれます。アンは、ウェントワースがライムに引き返して、ルイーザを見守り続け、ルイーザが回復することになれば、ウェントワースとルイーザが結婚するものとみなすことはわかっていたと思います。ここで、作者は読者をやきもきさせるのです。ウェントワースをめぐってアンとルイーザの三角関係が出来上がります。しかし、周囲はウェントワースとルイーザが結婚すると見ていて、ここにアンは入ってきません。三角関係と考えているのは、アンとそしてウェントワースは、この時点ではどうなのか分かりません。また、唯一三角関係を確信しているアンは、だからといってウェントワースとルイーザとの間に横槍を入れようとは考えていません。一般的(という言い方はおかしいかもしれませんが)な恋愛小説で、主な登場人物が三角関係にあれば、男の奪い合いになったり、すくなくとも、その三角関係が人物たちの行動の起爆剤になってくるのですが、この小説では、そういうことは一切ありません。この小説では、実は、同じような構造の三角関係が、このあとバースでつくられます。アンをめぐって、ウェントワースとエリエットの3人で、周囲の人々はアンとエリオットは結婚すると見ている。しかし、アンには、この三角関係が、それとして認識できていない。これをエリオットは気付いていないので、意識しているのはウェントワースのみです。つまり、これらの三角関係は事実として客観的に存在しているというよりも、当事者のうちの一人が主観的に意識しているという体のものです。しかし、また、読者は、アンの視点で認識された三角関係が、地の文で語られるので、読者は、それがあるものとして物語を読み進めていくものとなっています。ところが、後になって、ウェントワースが説明したのは、彼はルイーザと結婚する気などなかった。それで、ほとぼりを冷ますために兄のところに逃げていたのです。だから、ウェントワースには三角関係は存在しなかった。さらに言えば、ルイーザはウェントワースではなくベニックと結婚することになります。この二人の出逢いはライムでの事故です。だから、ルイーザも三角関係はなかったどころか、その関係に参加もしていなかった。そう思っていたのはアンだけだったのです。それを読者は、あたかも、それが存在しているかのように、アンの運命をやきもきしながら見守るわけです。何度もいうようですが、このような小説の事実と語りのズレがドラマを作り出しているところです。読者は、劇的な緊張を高めて、読みながら自身の手でカタルシスをつくりだすように小説の叙述がリードしているといえます。例えば、この二つの三角関係を起因として、アン、ウェントワースがそれぞれ背水の陣に追い込まれ、決然した行動を促されるように見えてくるわけです。 バースに移動してからは、しばらくアンのひとり舞台となり、ここでアンをめぐるサブキャラクターたちが、それぞれにアンに関係してきます。とくに、ここから本格的に登場してくるエリオット氏はアンにアプローチしてくるのは、8年前のアンとウェントワースの場合に対する陰画(ネガ)のような意味合いにあり、対比的にみることができる構造になっています。そこで、また説得ということが行われ、この小説のなかで手を変え品を変え呈示され、登場人物たちの間で弄ばれてきた説得が、こでは、従来のものの鏡像のように表われてきます。 また、ルイーザがウェントワースではなくてベニックと結婚することが、アンに伝わります。これもマスグローヴ家の人からの手紙という間接的な手段ですし、最後に、ウェントワースがルイーザの結婚を祝福しバースにやってくることをクロフツ夫妻から聞く、というこれまた間接的に知ることになるわけです。 物語、最後近くになって、ようやくウェントワースがバースにやってきます。雨の中で二人が出会い、この物語ではじめて、落ち着いて二人で会話をする場となりますが、久しぶりの再会と、途中でエリエットが邪魔に入るので、事項の挨拶程度の会話で終わります。その後の音楽会でのすれ違い、クロフツ夫妻の伝言を伝えにウェントワースがアンを訪ねるという場面、それらでは、二人はまともな会話ができません。それで、それぞれの思いは、どのように伝わるのでしょうか。恋愛小説で、これほど愛の語らいのないというのも、珍しいのではないかと思います。そこでは、二人は、周囲に人がいるところで、二人の関係が悟られないように、また、互いの真意が見えていないところで肚の探りあいのような、他の話題にかこつけて、ニュアンスや仄めかしで表現するような間接的なやり取りを行います。例えばこんな風です。バースのマスグローヴ家の人々の宿にアンもウェントワースもいるところで、チャールズが劇場の切符を入手してきたところが、アンの父と姉からのイーヴニング・パーティーの招待とダブルブッキングになってしまったときの会話です。 “メアリーが血相を変えて大きな声で言った。 「チャールズ!呆れたわ!よくまあそんなことを思いついたわね!明日の晩のボックス席を予約するなんて!明日の晩はカムデン・プレイスに招待されていることを忘れたの?(中略)エリオット家の大切なご親戚の方々に紹介していただくために、特別に招待されたのよ!そんな大切なことをなぜ忘れるの!」 「ふん!」とチャールズは言った。「何がイーヴニング・パーティーだ!そんなもの覚えていられるか!きみの父上がもしぼくたちに会いたいなら、ぼくたちをディナーに呼べばいいじゃないか。きみは好きにすればいいさ。とにかくぼくは芝居に行く」 (中略) 「でも行かなきゃだめよ、チャールズ。行かないなんて許されないわ。わざわざ皆さまに紹介されるために招待されたんですもの。エリオット氏とは特にお近づきにならなくてはいけないわ。あの方にはあらゆる心づかいを示さなくてはいけないわ。だって御父様の跡継ぎで、いずれはエリオット準男爵家の当主になる方なんですもの!」 「やめてくれ!」チャールズは声を荒げていった。「跡継ぎだの当主だの、そんな話は聞きたくないね!それにぼくは、現在の当主をないがしろにして、将来の当主に頭を下げるような人間じゃない。ぼくはきみの父上のためにも行かないと言っているのに、その跡継ぎのために行ったとしたら、それこそひどい話じゃないか。ぼくにとってエリオット氏が一体何だって言うんだ?」 この何気なく言われた最後の言葉は、アンにとっては救いの言葉だった。それまでウェントワース大佐は全神経を集中するかのようにチャールズを見つめていたその話を耳を傾けていたのだが「ぼくにとってエリオット氏が一体何だって言うんだ?」という言葉を聞いたとたん、アンに何かを問いかけるような視線を向けたのである。” ここにマスグローヴ夫人が仲裁に入り、それを機会にアンが発言します。 “「奥さま、もし私の気持ち次第ということでしたら、うちのパーティーは─妹のメアリーのことは別にして─私には何の障害にもなりません。私はああいうパーティーはあまり好きではないんです。ですから、パーティーの代わりに芝居見物に行けるなら、しかも皆さまとご一緒に行けるなら、こんなにうれしいことはありません。でもやはり、そうしはないほうがよろしいでしょうね」 アンはこの言葉を、間接的にウェントワース大佐に向けて言ったのだが、言い終ったとき体が震えていた。その言葉をウェントワース大佐がじっと聞いているのがわかったが、彼の顔を見てその言葉の効果を確かめる勇気はなかった。 (中略) ウェントワース大佐は席を立って、暖炉に歩み寄った。だがすぐに暖炉を離れてアンのそばに腰を下ろした。すぐにアンのそばに来るのは露骨すぎるとおもったのだろう。 「あなたはバースに来てまだ間もないから、ここのイーヴニング・パーティーを楽しむ気にはなれないんですね」とウェントワース大佐は言った。 「いいえ、違います。私はもともと、イーヴニング・パーティーというものが好きではないんです。私はトランプ遊びはいたしませんから」 「そうですね。たしか以前はそうでしたね、あなたはトランプ遊びは好きではなかった。でも時が経てばいろいろ変わるでしょう」 「いいえ、私はそんなに変っていませんわ」とアンは大きな声で言ったが、あわてて口をつぐんだ。どんな誤解をされるかわからないと思ったからだ。 ウェントワース大佐はちょっと待ってから言った。「ずいぶん昔の話です!八年半といえば一昔前です!」いまこみあげた感情をそのまま言葉にしたかのようだった。” この終わり近くのやりとりは、アンが8年前からの思いをずっと持ち続けているということを間接的に仄めかしているのでしょう。それと、前の方で「ぼくにとってエリオット氏が一体何だって言うんだ?」という発言はアンとエリオット氏との結婚話に対してのことのニュアンスを仄めかしているようです。しかし、これらは会話の文脈の流れと、場面やシチュエイションなどによって、その受け取られる意味合いが変わってくる、たいへんデリケートなやり取りです。それを小説の描写のなかで、さりげなくやってしまうオースティンの手腕は、すごいとしか言いようがありません。これを読者として読み取っていくのも大変です。おさらく初読で、これらに気付くことのできる人は、かなりの読み巧者ではないかと思います。それだけに、何度か読んでいくうちに、こういう物を見つけていくところに、オースティンの小説の醍醐味があります。さらに、昂じていくと、読者は作者の意図していないところに、勝手に深読みしていって、伏線や仄めかしを読者が作っていってしまうのです。そういう罠が随所に仕掛けてあるのが、この小説なのです。それは、小説の事実と言説が意識的にずらして作られているという基本構造だからこそ可能になっていると言えます。 そして、クライマックスは二人の熱い恋愛シーン!!…とはいかずに、アンとハーヴェルとの会話をウェントワースが脇で聞いてしまうという、これがクライマックスといえるのか、という場面です。ここでアンが話していることは、一般論の議論ですが、ハーヴェルを通り越して、ウェントワースに向けられています。そして、ウェントワースには、アン自身の思いを語っているのです。
“「ええそうですわ。女性はそんなに簡単に男性を忘れることはできません。男性がすぐに女性を忘れるようにはね。それは女性の長所ではなくて、女性の運命なのだと思います。そうするより他ないのです。女性はいつも家にいて、狭い世界で静かに暮らしていますから、どうしても感情の虜になってしまいのです。男性は世間へ出て活動しなければなりません。つねに仕事や趣味やいろいろなことがあって、すぐに世間へ戻っていかなくてはなりませんし、絶えずすることがあって変化もありますから、感情もすぐに弱まってしまうのです。」 「男性は世間に出て活動するからすぐに女性のことを忘れるというあなたの意見を、いちおうは認めるとしても(ぼくは認めようとは思いませんが)、それはベニック大佐にはあてはまりませんね、彼はあれから何の活動もしていなかったんですから。あのときちょうど戦争が終わって、陸に上がって、それからずっとぼくたちと一緒に、狭い家庭に閉じこもってくらしていたんですからね」 「そうですね、そうでしたわね」とアンは言った。「それを忘れていましたわ。でもそうすると、どう考えたらいいのかとら?ベニック大佐の心変わりが外的事情によるものでないとすると、内的事情ということになりますね。つまり彼の本性のしわざ、あるいは男の本性のしわざということになりますね」 「いや、それは男性の本性じゃない。愛する人や、かつて愛した人をすくに忘れるという移り気な性格は、女性の本性ではなくて、男性の本性だという意見には賛成できませんね。ぼくは逆だと思います。男性の肉体と心はじつによく似ていると思います。つまり男性は、肉体も感情も同じように頑健にできているんです」 「たしかに男性の感情のほうが頑健かもしれませんね」とアンは答えた。「でもその論法でいくと、女性は肉体も感情も、男性よりやさしくできているということになりますね。それに、男性は女性より頑健ですけど、女性より寿命は短いということになりますね。でもそうでなければ、男性があまりにもかわいそうですわ。男性はつねに困難や不自由や危険と闘わなくてはならないんですもの。労働と苦労の連続で、つねに危険と困難にさらされなくてはならないんですもの。過程からも祖国からも友達からも切り離されて、時間も健康も命も、自分のものとは言えないような過酷な状況に置かれて、ほんとにあまりにもかわいそうですわ。そのうえさらに、女性の愛情からも見放されるとしたら」 「問題はいくら話しても平行線でしょうね─」” (中略) それはウェントワース大佐が鵞ペンを落とした音だった。アンはおもったより彼が近くにいることに驚き、ふと、こう思わずにはいられなかった。もしかしたら、ウェントワース大佐はふたりの話に聞き耳を立てていて、そちらに気を取られてうっかり鵞ペンを落としたのではないだろうか、と。でもアンは、ウェントワース大佐がふたりの話を聞き取れたとは思わなかった。 (中略) 「さてミス・エリオット、さっき言ったように、この問題はいくら話しても平行線でしょうね。男性と女性がいくら話しても、意見が一致することはないでしょう。でも、これだけは言わせてください。散文でも詩でもいいですが、どんな物語を見ても、すべてあなたの意見とは逆です。ぼくにベニック大佐くらいの記憶力があれば、ぼくの意見の正しさを証明してくれる実例をすぐに五十くらい引用できるでしょう。ぼくが読んだ本には、たいてい女性の移り気なことが書かれていましたからね。歌にもことわざにも、たいてい女性の移り気のことが書かれています。でもあなたはこう言うでしょうね。それは全部、男性が書いたものだって」 「ええ、そう言うでしょうね。ですからどうぞ、本からの引用はおやめ下さい。自分たちの物語をつくる点で、男性は女性より断然有利だったし、教育程度も男性の方がはるかに高かったし、ペンも握ってきたのはほとんどが男性ですもの。男性と女性とどちらが移り気かという問題に関しては、本なんて何の照明にもなりませんわ」 「では、どうやって証明するんですか?」 「証明なんてしませんわ。こういう問題を証明するのは無理だと思います。こういう問題を証明するのは無理だと思います。こういう意見の相違は、どちらが正しいかなんて永遠に証明できないと思います。男性は男性、女性は女性、それぞれ自分の性を贔屓目に見て、その贔屓目の上に立って、自分の性に都合のいい実例を積み上げていくんですもの。そしてそういう実例の多くは、人の秘密を洩らさずには持ち出せないし、言ってはいけないことを言わなくては持ち出せないものなんですもの」 「ああ!男のこの気持ちをあなたにわかってほしい!」とハーヴェル大佐は、たっぷり感情をこめて言った。「男が妻と子供たちに最後の別れをし、妻子を乗せたボートが陸へ引き返すのを最後まで見送り、それからくるりと陸に背を向けて、「ああ、これが今生の別れになるかもしれない!」とつぶやくときの男のつらい気持ちを!それに、妻子に再会するときの男の熱い思いもわかってほしい。一年間の航海を終えて帰国の途についたけれど、ほかの港に立ち寄らなくてはならなくなったとする。そういうときの男は、その港に妻子が迎えにくるには何日かかるかを計算し、わざと計算を間違えて「その日までにはとても来られないな」などとつぶやき、心の中では、それより半日も早く来てくれることを祈り、そしていよいよ妻子の姿を目にすると、まるで神が妻子に翼でも与えてくれたみたいに、何時間も早く着いたと言って喜ぶんです!こういうことをすべてあなたにわかってほしい。そして男は、自分の宝物である妻子のためならどんなことでも耐えられるし、どんなことでもできるし、どんなことでも喜んでするということを!でももちろんことは、男らしい心を持った男たちの話です!」ハーヴェル大佐はそう言って、感極まったように自分の胸に手を当てた。 「まあ!」とアンは激しい調子で言った。「あなたやあなたに似た男性たちのお気持ちは、私はよくわかっているつもりですわ。男性たちの熱烈で誠実な感情を過小評価するつもりなどまったくありません。真の愛情と貞節は女性の専売特許だなんて言うつもりはありません。もし私がそんなことを考えたら、自分で自分を軽蔑します。もちろん私は、男性も結婚生活において立派ないいことをたくさんできると信じています。世間へ出て重要な活動をすると同時に、家庭生活のあらゆる重荷にも耐えることができると信じています。でもそれは愛する対象があった場合の話しです。つまり、あなたの愛する女性が生きていて、あなたのために生きている場合です。でも私が言いたいのは、女性だけに与えられた特権があるということです。その特権とはつまり、女性は愛する男性と死に別れても、愛し合える希望がなくなっても、その男性をいつまでも愛し続けることができるということです」 アンは胸がいっぱいになり、息が詰まってこれ以上何も言えなかった。”
以上が、アンとウェントワースの二人の物語をメインとして取り出してこの小説の特徴的な体験を追いかけるという試みをやってみました。 なお、この小説の楽しみは、これだけに限られるものではありません。個々までで切り捨てたことはたくさんあります。 廣野由美子という人が『深読みジェイン・オースティン』という著書のなかで、『説得』の特徴的な表現方法について、興味深い指摘をしています。作品を読む面白さが広がると思うので、かいつまんで紹介しておきます。興味のある方は直接著作を読むことをお奨めします。 最近の物語論においては、語り手の役割を、「語ること」と「見ること」に区別して考えるといいます。つまり、見る人と語る人を別々にするわけです。その「見ること」の方は物語全体を外側から眺める、いわば客観的な視点と、作中人物の視点で見る視点があります。オースティンの小説では、全知の語り手という物語の外側にいて神のような立場ですべてを知っている語り手が、語るという三人称形式が書かれています。したがって、「語ること」は全知の語り手が行っています。これに対して、「見ること」は物語の外側と登場人物である女主人公の見たことや感じたことが語りの内容に混じってくる。これによって、語り手が巧みに情報を制限し、盲点や謎を作る仕掛けを施していると言います。 とくに『説得』では、女主人公であるアンの視点の混入が、他の作品に比べて圧倒的に多くなっていることが特徴的です。ここでは、アンの知覚や認識を通して情報が伝えられ、彼女の内面が読者の前に晒される結果、彼女が知覚しなかったり、認識していない情報が制限され、読者には隠されることになります。それに加えて、オースティンは、全知の語り手の語る情報も意図的に制限しています。つまり、オースティンは物語の中に隠す仕掛けを施していると言います。 例えば、冒頭では全知の語り手がアンの父や姉、あるいはラッセル夫人といって登場人物を紹介していますが、アンについての記述は僅かです。続いてエリオット家の窮状が説明され、ラッセル夫人が屋敷を他人に貸すという提案と、一家がバースに引っ越す経緯が説明されます。ここまでの記述は、語りによる説明と、エリオット家とその周辺の人々の会話となっていますが、そこにアンが二言三言だけ口を挟むのですが。それまでほとんど記述のなかったアンの存在が浮かび上がってきます。しかも、繰り広げられていた愚かしい会話をアンが注意深く聞いていた、つまり沈黙する聞き手としての存在としてです。その最後につぎのような文章をいれています。 “アンは、この話の一部始終に熱心に耳を傾けていたのだが、この結論に達したことを聞くと、ほてった頬を心地よい冷たい空気で冷やそうと、すぐに部屋を出た。そして屋敷内の、お気に入りの小さな森の散歩道を歩きながら、そっとため息をついて言った。「あと数ヶ月するとあの方がここをあるいているかもしれないんだわ」”
その謎は次の章で明かされますが、「あの方」とはウェントワース大佐です。そして8年前の二人に起きたことが説明されますが、しかし、その後の8年間アンは、おそらく若さや生彩をなくしてきたであろう人生は、省略され、全く説明されません。オースティンは、情報を制限し、アンの過去を隠したまま物語をはじめていくわけです。 また、二人の再会のシーンはどうでしょう。ウェントワースが朝食をしているアンを訪ねる短い会見を、淡々と記述しています。ここではアンはウェントワースをまともに見ていません。お辞儀を交わした後は聞こえてくることしか書かれていません。アンが、ざわめく一座に混じってウェントワースの声を注意深く聞き、彼がマスグローヴ家の姉妹と親しくなっている様子を聞き分けています。この記述は視覚情報を制限し、視覚以外の知覚である聴覚や思ったこと・考えたことの描写にうつり、次第にアンの内面が前面に出てくることになります、そこで、アンがウェントワースへの思いを引きずっていることが間接的に明らかに出てくるのです。知覚情報を制限することによって、アンの内面の心の動きの激しさや記憶の鮮烈さを際立たせることになるのです。 これも些細な描写ですが、アンがマスグローヴ家に人々が集まったところでピアノを弾くところです。 “アンは、ピアノの演奏はマスグローヴ姉妹よりはめかに上手だった。でも、そばに座ってうれしそうに聞いてくれるやさしい両親はいないので、アンが弾いてもみんなの反応はなかった。アンもただ礼儀上、あるいはほかのお嬢様たちに休息を与えるために弾くだけであり、それは自分でもよく分かっていた。自分のピアノ演奏を聴いて楽しんでいるのは自分だけだということは、アンにはよくわかっていた。しかし、こうした感情に襲われるのはこれが初めてではなかった。正しい鑑賞能力やほんものの趣味を持った人にじっくり聴いてもらったり、励まされたりする幸せを感じたことは、十四歳のときに母を亡くして以来─あの束の間の一時期を除いて─ただの一度もなかった。だから、みんなの前でピアノを弾くときにひとりぼっちの寂しさに襲われることにはすっかり慣れていた。” この箇所はアンの自己認識で、内心の声にちかいでしょうか。この文章の中の「あの束の間の一時期」という曖昧な表現は具体的に何時をさすのか。十四歳のときに母を亡くして以来の束の間ですから、一時的に「正しい鑑賞能力やほんものの趣味を持った人」に聴いてもらったということですからウェントワースであり、彼と交際していた8年前の短い期間ではないかと、つよく推測できますが、確かではありません。しかし、このことでアンの失われた過去の存在が厚みを増してくることになります。 また、バースで再会したエリオット氏の印象について、アンは次のように記述しています。 “ライムで見たときの印象そのままの美男子で、話をしている顔はいっそう魅力的だった。態度もまったく非のうちどころがなく、とても洗練されていて、とても自然で、とにかく非常に感じがよかった。これと比較できるような立派な態度の持ち主は、ほかには一人しかいないアンは思った。タイプは同じではないが、立派さという点ではたぶんまったく同じだと思った。” この「ほかには一人しかいない」のほかの一人は誰か具体的に示されてはいませんが、ウェントワースでしょう。アンは、バースに来てからウェントワースに会っていません。それが、このような暗示的に言い回しで、新たに出会った男性によい印象をもつやいなや、ウェントワース氏と比較してしまうのです。それだけアンの心中にウェントワースの占める場所が大きいか分かるようになっています。このようなあいまいな言い回しでウェントワースが隠されたことがら何度も繰り返しでてきます。それらのことは、アンの内心の動きの中に、しばしばウェントワースに対する執着が紛れ込んでいる、しかも、断片的ではなく、一貫して連続して持ち続けているのが分かります。このとき、アンはウェントワースはルイーザと結ばれるだろうと考えていた時期でもあるので、ウェントワースを諦めきれない心情が、明言されることなく浮かび上がってくるように仕掛けられているのです。 このように、オースティンの語り口は、「隠されたもの」を探り当てるように読者を誘惑するレトリックに満ちているのです。その「隠されたもの」こそが、実は重要なものであることを暗示しています。 ジェーン・オースティンの小説には、理屈っぽい議論がよく見られます。この作品でも、終盤のヤマ場でアンとハーヴェルが男女の愛し続ける姿勢に対して観念的なやりとりが交わされていました。これは、他の作品でもそうで、『高慢と偏見』でも『マンスフィード・パーク』でも、男女が愛を交わす場面で、甘い言葉ではなくて、道義について議論をたたかせたりしているのです。おそらく、オースティン自身そういう理屈が好きだったのではないか、と私には思えるのです。その反面、この小説では、アンにとって愛着の深いケリンチ・ホームの屋敷について、どのような建物だとか、部屋の様子とかといったことの具体的な描写は一切ありません。華やかなパーティーやバースの社交場についても、アンやラッセル夫人の会話は書かれていますが、人々の着飾った様子等は無視といっていいほど、何も書かれていません。これは、表現の抑制などといった次元のことではなく、もともと、作者自身が、そのようなものに対する興味がなかったとしか考えられません。他の小説には、よく見られる風俗描写がほとんど見られません。おしゃれとか、そういうものへの興味があまりなかったのでしよう。それだけに、彼女の理屈好きは、観念的な志向性として、目立っていると思います。 前にも少し触れましたが、オースティンの小説は、ある概念をめぐって作られているように見えるところがあります。例えば、代表作と言われる『高慢と偏見』ではプライドということが作中でも、プライドについて議論がたたかわされ、様々なキャラクターの登場人物のプライドが物語のそこかしこに散りばめられ、とくに主人公のリジーとダーシーは物語が進むにつれて、自身のプライドが高慢さからプライドに自己変革させていく成長の物語ともとれるところがあります。また、『マンスフィールド・パーク』では、道義的な正しさとはどういうことかをめぐって、副主人公のエドモンドが相手のミス・クロフォードとの、他の作家であれば恋愛の場面で議論を繰り返します。そして、この小説の最後の補足のように作者が各々の登場人物の後日譚と正しかったのかの論評がなされます。物語全体を通して、主人公ファニーの一貫した行動が当初は自分勝手な振る舞いとされて居たのが、状況が変化し、他の人々の立派とみなされた行為が実は悪意や打算に裏打ちされたものであったのが明らかになってくるのに反して、彼女の正しさが理解されてくるといった内容になっています。物語のなかで、何が正しいかが変化してくるのを、そのたびに追いかけていくのは、まるで観念的な議論を展開しているようでもあります。このように書くと、オースティンの小説が何か堅苦しい議論のように思われるかもしれませんが、これは、読みようによっては、そうことが見えてくるということで、実際に、この二つの小説は、恋愛小説としても、ピリッと辛口の風刺のきいた笑いが満載の楽しい小説です。 それで、この『説得』という小説は、ここまで書いてきた流れで言うと、説得ということをめぐる議論が小説の底流にあると言えるのです。説得といいますが、ロマンとか小説の主流は恋愛で、その恋愛に不可欠なものが口説きです。恋愛小説というのは、主人公がいかに相手を口説くかということに、古来、幾多の作家はそれを見せるのが腕の見せ所であったわけです。その説得ということ自体について、小説で扱うということは、オースティンの時代にはなかったと思いますが、一種のメタ小説のようなところがあるのです。それだけ、この作品には、もともと屈折があるのです。 さらに主人公のアンは説得に負けて恋愛を放棄した女性です。これは、普通の恋愛小説の王道とは正反対です。オースティンと同時代の作家たちをみれば、ブロンテ姉妹はいうまでもなく、周囲の反対に反発して、愛を強くもって愛を貫く主人公を描いているのです。当のオースティンだって、『高慢と偏見』のリジーは身分が違うという反対をはね返してダーシーと結ばれるのです。ということは、設定の時点で他の恋愛小説とは一線を画している、というよりあり得ない設定なのです。近代の自己に目覚めた主人公が旧態依然で現状に固執する周囲という障害を乗り越えて(時には戦って)、自己を貫く、その格好の題材が恋愛というのが、小説、とくに恋愛小説なのですが、『説得』のアンは、その周囲に絡め取られてしまっている人物です。だから、アンは周囲と戦うとか乗り越えるといった行動を起こしません。実際、この小説は大事件も、というより事件らしい事件は起こりません。せいぜいが、家族の中で口論があっとか、旅先で怪我したとか、そんな程度です。平穏な日常が淡々と続くのです。よく言えは平穏ですが、ぶっちゃければ、単調です。読者はそんなものを読んでも、面白いのでしょうか。しかも、理屈っぽい議論が交わされる。単調を通り越して退屈してしまうのではないでしょう。しかし、そうではない。それがオースティンの小説のユニークな点であり、魅力なのです。前項では、その秘密のひとつとして、オースティンの小説の語り口、小説の事実と語られていることが微妙にズレていて、それが読者の想像力を巧みに刺激して、物語の推進力や劇的な緊張を生んでいることを体験的に示してみました。ここでは、それ以外の点、退屈と言っていい素材で、読者を惹きつけてしまう秘密を追いかけてみたいと思います。 それで、前置きのように述べてきましたが、この小説は「説得」ということをめぐる議論が小説の底流にあるということ。たんにそれを指摘するだけであれば、大学生の卒業論文のような“指摘してみました”のような知ったか振りで終わってしまいます。そんなもの、ここにアップしても面白くないでしょう。ここでは、まず、その事実を示した上で、それが小説的な面白さにどれだけ貢献しているのかを見ていきたいと思います。 説得をするとか、説得をされるということは。その行為としては、言葉を話す、そして相手に聞いてもらう、聞かせる、その結果、言ったことに従わせるというように分解できると思います。また、説得される側に立てば、話を聞く、聞かされる、その話に納得する、押し切られる、その結果話の内容に従う、従わさせられるということになります。そこで、ヒロインのアンについて見ていきましょう。とくに小説の初めの方で、彼女が行っていることは、上の分解した行為の中で言うと、聞くということばかりであることが分かります。物語のはじまりに先立つウェントワースとの婚約を破棄したことがまずそうなのですが、ただし、このことには単純にそうだとは言い切れないところがあるようなのですが、とりあえず、ここでは深く追求しません。例えば、エリエット家の借金がかさんで財政状態が苦しくなったので、屋敷を他人に貸すことになったとき、一家は保養地であるバースに移ることになりますが、アンは置き去りにされます。しかも、他人であるクレイ夫人を同道させながらです。当主である父親と姉である長女のエリザベスからは、前もって相談されることもなく、ただ言われただけです。その理由は、バースに来ても役に立たないというのと、妹のメアリーから体調を崩したので助けてほしいと言う連絡があったので、アンが行くと手紙を出したということなのです。そして、一家がバースに出発する時に、アンは、細々とした用事を一切引き受けています、大切なもののリストアップや教区の家を一軒ずつ回って別れの挨拶をすること。これは本来は当主か主婦のすべきことで、それをアンは黙々とこなすのですが、そういうアンを姉のエリザベスは役に立たないといって、バースには連れて行かず、代わりに他人のクレイ夫人を連れて行きます。そもそも、エリエット家の借金がかさんで財政状態が苦しくなってきたことについて、一家のなかで唯一現状を認識し、危機感をもっていて現実的で有効な対策を考えているにもかかわらず相談はおろか、意見を求められることはないのです。アンは家族に対して発言しても聞いてもらえず、ただ何事かを言い渡されるだけ。それだけ、アンの存在が稀薄なのです。 また、妹のメアリーのところに看病に行きますが、そこでは妹の一歩的な愚痴を聞かされます。そして、メアリーは我がままで気位の高い性格ゆえに嫁ぎ先であるマスグローヴ家とはうまく行っていないのですが、婚家にあいさつにいっても、義母たちのメアリーへの愚痴を一方的に聞かされます。そこで、エリオット家の窮状やそれに伴う苦労ついての慰みやねぎらいは最低限の儀礼的なものに過ぎませんでした。ここでも、アンは自分から何かを言うことは認められず、人々が言うことを一方的に聞くだけという存在です。それは、メアリーの息子の幼いチャーリーが木から落ちて大怪我をしたときに、手当てや医師の手配をしたのはアンでしたが、その夜、子どもの両親は楽しみにしていたパーティーに出掛けてしまいます。大怪我の子どもは、しかたなくアンが看病したということです。後に、ライムに出かけたときにルイーザが大怪我をしますが、同じようにアンが手当てや医師の手配をします。その後、ルイーザの看病を人々はアンに頼みますがメアリーが自分がやると言い出し、そのとおりになります。ただし、メアリーは役に立たず、他の人に代わられてしまう。それを人々(アンを含めて)は分かっていた。このどちらの場合もメアリーのわがままが通り、アンは言われたとおりに従う。アンという女性はそういう存在であったわけです。まるで、みんなの我がままを受け容れてくれて天使のような存在といえるでしょうか。あるいは、言えばなんでもやってくれる便利な存在でもあります。 どうやら、アンはそういう自体を甘んじて受け容れている、そのことに対して反抗するそぶり見えません。本人にそういう自覚はないのか、しょうがないと諦めているのか、分かりません。でも、このような状態、彼女の主体としての人格を認められていないで、一方的に押し付けられるというのは、視点を変えれば、虐待と変らないわけで、20世紀文学なんかであれば不条理ともいえる状態ではないでしょか。まるでカフカの長編小説にでてきそうな状態です。話は少し脱線しますが、日本の文学者で真っ先にジェーン・オースティンを写実の大家として絶賛したのが夏目漱石でした。彼の文壇デビュー作は有名な『吾輩は猫である』ですが、これはユーモア小説とか風刺小説と言うことになっていますが、この猫の境遇を考えてみて下さい。弱っていたところを拾われた猫は、先生の庇護がなければ生きていけません。いわば生成与奪の権を握られている境遇です。しかも、猫はどういうわけか人間の言葉を理解できます。しかし、猫の言葉は人には理解できない。つまり、自分のことは誰にもわかってもらえない。しかも、その分かってくれない人間に依存しなければ生きてゆけないのです。これってかなりの状態ではないでしょうか。そういわれてまず思うのは孤独ということではないでしょうか。同じことは、『説得』のアンにも言えるのではないでしょうか。猫とアンの境遇には共通するところが少なくありません。(『吾輩は猫である』が猫から人間の世界を見ているという作品であるのと同じように、『説得』はアンの視点が語りの視点と重ねあわされています。そこにも共通点があります。このことは具体的な前項で説明しました)しかも、両方の場合、作者は不条理な状況にあるとか、孤独であるとかいうことは一言も言及していません。 そのように考えてみると、アンの境遇について19世紀という昔の他人事でなくなってくるとは思いませんか。2世紀を跳び越えて、現在の管理社会での孤独な存在として共感できる状態にあると思いませんか。そうすると、一気にアンの行動や思いとか考えが身につまされるほど身近に感じられてこないでしょうか。アンは優れた知性と繊細な感受性を併せ持つ優しい女性です。彼女は、そういう自分ことをよく分かっているでしょうが、周囲の誰にも彼女の真価を理解されないのです。そのなかで、一人で突っ張っても無駄なあがきでしかありません。そこで、彼女は限られた僅かな可能性のなかで 一見何もしていないようでいたり、問題解決にはならないような行動をしたりします。それは、まるでカフカの小説の主人公たちの無意味な行動に似ているように思えてくるのです。アンは一方的に聞くという存在から、一歩一歩、徐々に言う存在に変わっていきます。まず、説得の性格が変化します。この物語に入る前に8年前において、彼女は周囲の説得によって婚約を解消しました。この場合の説得の性格は「〜するな」というものが中心になっています。つまり、出しゃばるな、ということ。存在を主張するなという方向です。この物語が始まってからも、バースに移る父や姉からついて来るなと言われ、倹約について口出しするなということになっていました。それが、妹のメアリーのところに看病に行って、マスグローヴ家では、話を聞いてくれ、坊やの看病をしてくれ、散歩に一緒にいってくれ、ルイーザの看病をしてくれ、といったような「〜してくれ」という行為を起こすように説得されるようになります。ここでは、存在を主張できるようになります。それは、エリオット家からマスグローヴ家へと場所が移動し、環境の変化とともに、変化したということになります。そして、アンは聞くだけから、言うことへの変化を始めます。そのは、場所をライムに移動したところからで、そのきっかけは、ウェントワースの友人のベニックに対してでありました。ベニックは、従来のアンにとってはまったく新たにコミュニケーションを始める人であったので、彼女の家族や知り合いたちと違って、彼女に対して先入観なしに接することができた。それで、アンは、ベニックに初対面での会話の際に、詩に淫していた彼に散文を読むようにすすめる(言う)ことができたわけです。そして、ルイーザが突堤から落ちて怪我をしたときに、慌てふためく人々に冷静に指示をします。そのときに、彼女は言うという行為を、周囲に対して行うようになります。それは、物語が始まって半分以上過ぎた後です。それだけのことに前半全部を費やしたわけです。そして、子爵家のパーティの出席を父に言い渡されたのを断って友人であるスミス夫人訪問の約束を果たしたり、最後には、周囲の期待や説得を振り切って、エリオット氏からの結婚申込みを断り、ウェントワースと結婚するわけです。このプロセスは、カフカ的不条理の閉塞状況に閉じ込められていたアンが、存在を回復し、最終的には解放されるという自己の存在を獲得していく神話的なストーリーということができると思います。これは、言い換えると、人物が自らの在り方を変えていくことにより自己実現していく教養小説の性格の見られるということです。これについて、別に項を改めて考えてみたいと思います。 『説得』は、周囲から存在を無視されるほど軽視され、便利な道具のように面倒でつまらない役割を押し付けられていたという、いわば閉塞状態にあった主人公が、状況を打開し、自己の存在を解放するという、例えば山姥伝説や灰かぶり姫のように神話的な要素があると考えられます。そしてまた、『説得』は近代的な小説でもあります。単なる神話ではなくて、そこに合理的な解釈で読者が納得できるように作られています。それは、主人公が状況を打開するのと同時併行して、主人公自身が自己変革をしていって、そのことによって周囲の人々の彼女を見る目が変化していった、つまりは、主人公が自己を成長させていったゆえだ、ということが、表裏一体となってものがたりが作られていると考えられます。 まず、物語の開始時点のアンは、状況が状況ですが、本人もパッとしない女性でした。もともと、優れた知性と繊細な感性に恵まれた、いわゆる才能豊かな女性だったのですが、謙虚で内気な性格ゆえに、自身の才能をひけらかすようなことはせずに、周囲に見る目を持った人物に恵まれず、才能を発揮する機会がなかった。そういう潜在的なものを持っていたけれど、8年前にウェントワースとの婚約を解消したことを後悔し、その痛手から立ち直れないでいる。端的にいえば、8年間失恋にくよくよこだわり、後悔しつづけ、次第に27歳であるのに若さをうしない、容色の面でもくたびれてしまっていた。つまり、誤解を恐れずに言えば、地味で暗いババくさい女。合コンでもやれば、隅っこでポツンと取り残されて、誰からも相手にされないようなタイプです。8年前の婚約破棄については、ウェントワースは当時は23歳で将校にもなっておらず、家柄も財産もなく将来の見込みも未知であった。エリオット家の人々は家柄や財産の釣り合い、実はエリエット家としての外聞から反対したといいます。それに対してであれば、アンは反対を押し切ってウェントワースのもとに奔ったでしょう。アンはラッセル夫人の誠心誠意アンの将来の生活を危惧した説得を受け止めたわけです。そして、アンは彼女なりに、ウェントワースの実力を信じてはいたけれど、戦争で活躍する機会に恵まれなければ結婚することはできず、結果的に彼が辛くなる。そのことを考えて判断した。だから、アン自身も、8年前の判断は正しかった、と言っています。それは、次の文章に明らかです。 “アンはまだ若くておとなしい性格だが、父の意地の悪い無言の反対には逆らうことができたかもしれない。姉からもやさしい言葉やまなざしは一切なかったけれど、なんとか逆らうことができたかもしれない。しかし、自分があんなに愛しかつ信頼しているラッセル夫人から、あのような首尾一貫した反対意見を、あのようなやさしい態度で何度も言われると、アンはとても逆らうことはできなかった。この婚約は無分別で不適切で、成功する見込みもないし、成功しなくて当然の間違った婚約だと、だんだんほんとうにそう思うようになった。しかしアンは、自分のことだけを思ってこの婚約を解消したわけではなかった。自分のことよりも相手のためを思って婚約解消するのだという気持ちがなかったら、とうていウェントワースをあきらめることはできなかっただろう。自分は何よりも「あの方」のためを思って慎重に振る舞い、自分を抑えているのだと信じることが、最後の別れの悲しみに対する一番大きな慰めだった。”
しかし、相手のウェントワースの側からは、8年後の再会したあとで振られてしまった怒りを忘れられずいて、アンの意志の弱さや家柄にこだわる気位の高さによるものだと思っていたようです。それは、物語の中で、彼が結婚相手の女性に求めるのは意志の強さだと明言していたのは、8年前のアンへの反発が起因しているのは明白でした。それが、ウェントワースのアンに対する冷たい態度に表れており、アンについて「彼女は変ってしまった」という発言にも表われています。 アンとしては、8年前に結婚を断って以来、くよくよ後悔していたわけですから、当然未練たらたらで、再会に期待していたはずです。それが再会への躊躇という態度に表われています。しかし、ウェントワースのアンへの態度は、彼女にとって冷や水を浴びせられたようなものでした。 “「すっかり変ってしまって、つい気がつきませんでした!」この残酷な言葉は、アンの脳裏にこびりついて離れなかった。でもアンは、この言葉を聞いて良かったとすぐに思った。この言葉は、私の頭を冷やしてくれる効果はありそうだ。興奮を静め、気持ちを落ち着かせ、結局は私を幸せにしてくれるにちがいない。”
このとき、アンは8年経ってようやく自分を冷静に見ることができるようになったのではないでしょうか。ウェントワースのことも思って結婚を断ったということが、相手のウェントワースには裏切りとして受け取られ、彼を傷つけていたことに思い至った。8年前に彼のことを思ってと考えていたことが、実は自己弁護でしかなかったという冷徹な事実を認めざるを得なくなります。そして8年間くよくよ後悔していた自身について、事実と向き合っていたのではなく、自分にとって都合よく解釈して慰めていたことに気付いたのではないか思います。 この小説は、前にも触れましたがアンの視点で語られているところもあって、読者はアンという人物を内向的で人見知りするところはあるけれど、誠実で優しい性格、つまり善い人であるととらえがちですが、実は、けっこう矛盾を内包している人物でもあるのです。例えば、父や姉の身分や家柄に固執する見栄っ張りなところを快く思っていませんが、その一方で、平民のクレイ夫人が父親と付き合おうとしていること、それに対して父親が満更でもないことを、アンは父親自身の気持ち以前に家名が汚れることを心配しています。それについては、内心では軽蔑しているエリオット氏の共犯者となることも辞さないのです。そのことに関しては、彼女自身は矛盾に気付くこともありません。アンという人は、家族でも友人でも他人を思いやる優しさを持っている人なのですが、それが、ひとりよがりになっていることがあって、それに本人が気付いていないのです。しかも、自分を冷静に見ることのできる能力や感覚の鋭さをもっているにも拘わらずです。それが、端的にあらわれたのが8年前の婚約破棄における判断と自己正当化だったのではないでしょうか。そのことをアンは、ウェントワースの態度から気付かされたというわけです。 これに対して、ウェントワースの方はどうでしょうか。下の引用にあるように、彼はアンを許してはいません。だから、彼女と再会しても、ことさらに冷たい態度をとります。そして、彼女に対する恋心は消え去ってしまったと思っています。しかし、アンに対して冷たくあたるということは、彼女への関心の裏返しであるのです。彼は、自分で意識していないで彼女のことを見てしまうのです。それが、メアリーのコテージを訪ねたときに、子どもを看病しているアンにまとわりついて邪魔をしているもうひとりの子どもをアンから引き剥がす行為にあらわれています。それで、アンの方がウェントワースの心の動きに気がつくのです。 “ウェントワース大佐はアン・エリオットを許してはいなかった。アンは彼にひどい仕打ちをしたのだ。彼を見捨て、彼を裏切ったのだ。さらに悪いことに、その行為によって、アンの性格の弱さが暴露されたのであり、そういう弱さは、決断力と自信にあふれたウェントワース大佐には我慢できないものだった。アンは、家族や友人たちの願いを入れるために彼を見捨てたのだ。強引に説得されて彼を見捨てたのだ。それはまさに、弱さと臆病さ以外の何者でもないのだ。” 一方のウェントワースは、結婚相手を探していることを明言していたこともあり、成り行きから、マスグローヴ家のルイーザと一緒にいることが多くなります。後で、彼自身が告白していますが、彼女に対しては何とも思っていなかったらしい。ただし、それは、後になって、アンへの愛情を自覚してからのことなのでこの時点では分かりません。アンは、このようなウェントワースを次のように観察しています。 “アンはそのあとまもなく、四人全員と何度か席を共にし、四人の関係について自分なりの意見を持つことができた。(中略)アンの意見はざっとこういうものだった。どちらかと言えば、ヘンリエッタよりルイーザのほうがウェントワース大佐に気に入られていると思うが、アンの記憶と経験から推測すると、ウェントワース大佐はどちらにも恋をしていないと判断せざるを得ないのだ。ヘンリエッタとルイーザのほうが大佐に恋をしている。ただしこれも、恋とは言えないかもしれない。一時的な熱病のようなものかもしれない。でも、いずれは恋になるということもあり得るし、ほんとうにそうなるかもしれない…。” これは、アンの主観的な視点ですが、読者は、アンがそう見ているとは読まずに、ウェントワースはそうなのだろう読んでしまうでしょう。アンは、ウェントワースへの未練やひけめがありますから、すでに客観的に見ることはできないはずです。それででてきた意見です。それを事実のように読者に受け取らせてしまう。そこにオースティンという作家の巧みさがあると思います。 これは、ひとつにはアンが語ることによって、アンがウェントワースのことが常に心から離れず、気になってしょうがない、しかも、彼の周囲に若い女性がまとわりついていることに心穏やかでないこと。その一方で、ウェントワースがどう考えているのかを、ここで明らかにしてしまわないことで、アンの心理状態が読者に切迫感をもって感じることができる。しかも、アンの内心の声を客観的な事情と、読者が混同してしまえば、読者は自然とアンに感情移入して読むように導かれるわけです。また、ウェントワースに目を転じてみれば、このときの状態を彼自身が告白していますが、それはずっと後になってからのことで、その時はアンを愛していることを自覚していた時なので、その状態に至る過渡的な状態として、本人が物語を作っているものであると言えます。おそらく、後で語ったときのような整理されて、彼自身にそういう状態であるという自己認識はなかったのだろうと思います。このときのウェントワースは何も考えていなかった、と言えると思います。といったも、頭が空っぽだったというのではなくて、アンに対する考えや若い女性をどう見るか、どうふるまうかについては、自身の答えがない状態、答えを出す以前の問いかけもできていない状態で、言うなれば成り行き任せで、小説においては、彼は、このとき、こんな心理状態ですて明確に書けない、あいまいな状態だったのではないでしょうか。私には、曽思えます。 実際、ウェントワースは常に受け身で、ルイーザの方が積極的に彼にアプローチをしかけているのです。ルイーザは、ウェントワースが意思の強い性格の女性がいいと言ったことから、彼女自身、自分にピッタリだと思ったと言えるでしょう。彼女は、感情のおもむくままに、思ったことや感じたことをストレートに話し、行動する。それはウェントワースとの会話にも表われています。ただし、そこに悪意や虚飾がなく、正直であるで、エリオット氏やクレイ夫人のように軽蔑されることはありません。ただし、分別に欠けるところがある。チャールズ・ヘイターを訪ねての散歩やライムへの旅行においても、ルイーザはウェントワースと二人になるように行動し、彼に積極的に話しかけます。ここでのウェントワースはルイーザに対しては受け身で、作者の書き方も、どっちともとれるような微妙な書き方をしています。つまり、ルイーザを満更でもなく思っているのと、積極的なルイーザに辟易している両方に受け取れるようです。ウェントワースは、自己を把握できていないのです。だから、彼の行動は刹那的で、行き当たりばったりです。ライムでルイーザが突堤の上から飛び降りるのを止められなかったのは、彼がルイーザを本気で止めなかったからです。それは、ルイーザに積極的にアプローチされていても、何とも思っていないで、受け身でいた、そのことについて、彼自身明確に自覚していなかったからです。ルイーザに正対していなかったから、彼女の振る舞いに対して、どうしても投げやりな対応をしてしまう。だから、ルイーザが危険にことをしようとして、彼は制止しようとしますが、それはお座なりで、彼女が怪我をしたときに茫然として、うろたえるしかなかったのです。その後で、アンの前で、ウェントワースは強い後悔を語りますが、その時に、自身の曖昧さに、はじめて気がついた(その時に隣にアンがいたことは象徴的です)。 つまり、アンとウェントワースは、8年前以来、この件に関しては自分の世界に閉じこもって、ひとりでくよくよ考えていたのです。客観的に距離を置いて、冷静に事実を見ることができないでいた。それを、アンはウェントワースに再会し、彼の態度をみることでショックを受け、自分が未練を捨てられなかったという事実をつきつけられます。また、ウェントワースは、自分の現実をみようとしない姿勢が、ルイーザの怪我という事故を招いてしまったことに、深刻な反省を迫られたというわけです。 このライムの旅行を機に、二人はいったん別れます。小説の中では、ウェントワースは一時的に舞台から退場します。しばらくは、アンがバースに移り、その地での家族と保養地での生活となります。 アンは、バースで父や姉と再会します。このとき、アンは屋敷で二人と別れたときと同じではなくなっていました。それを、オースティンは、間接的にアンが見えたものや心の動きで表わします。それは、もしかしたら、以前のアンの視野にも入っていて分かっていたことだったのかもしれませんが、オースティンが書かなかった、隠したことかもしれませんが、ここでは、アンについて隠さないほうがよくなった、ということではないかと思います。バースで再会した父と姉が予想以上に機嫌がよく、愛想がよいことについて、二人は立派な家と家具を自慢し、多くの人々が交際を求めてくると自慢します。それに続いて、次のように記述します。 “サー・ウォルターとエリザベスの上機嫌の理由はこれだったのだ!アンはそれがわかると、ものすごく上機嫌な父と姉を見ても不思議とは思わなかったが、ため息をつかずにはいられなかった。父は自分が落ちぶれたなどとはこれっぽっちも思っておらず、自分の屋敷を人に貸して、大地主の義務と尊厳を失ったことを悔しいとも思っておらず、都会生活のたわいないことで虚栄心を満足させてこんなに喜んでいるのだ、ほんとうに情けないではないか。アンは姉のエリザベスを見ても、ため息とほほえみと驚きを禁じえなかった。” ここでのアンは辛辣で、父と姉に対して容赦ない批評をしています。これまで、屋敷を貸しに出すときも、あるいは妹メアリーの愚かな我がままの被害にあったときでも、いっさい批評的なことを表わしてこなかったアンが、ここでは、父と姉に対して軽蔑の視線を送っています。もしかしたら、以前から、アンは内心では家族を軽蔑していたかもしれませんが、それを作中では触れられていませんでした。それをオースティンはあからさまに書いています。それは、オースティンは書くべきと判じたからでしょう。そこに何らかの事情の変化があったはずです。それは、アン自身の変化ではないでしょうか。 それは、受け身の姿勢に終始していたアンが、少しではあるけれど、自分からアクションを起こし始めたという変化を表わしているではないかと思います。たとえ思ったとしても、父や姉への評価をあらわすことは、直接的には行動にならないかもしれませんが、以前であれば、アンは、ため息をつくことすらしなかったでしょう。 このあと、アンは父や姉が積極的にすすめようとするダルリンプル子爵夫人と令嬢との交際の機会に、パーティーに出席するようにという二人の命令に逆らって、友人のスミス夫人を訪ねます。その時のアンには、以前にはない決然としたところがありました。このようなアンの姿勢は、ウェントワースがバースに来たときに、街中で歩いているのを見つけて、彼女のほうから声をかけることをします。音楽会に誘うのもアンです。実際に、演奏会場にウェントワースが入ってきたとき、アンは後方に彼を軽蔑する父と姉がいることにもめげず、さっと進み出て声をかけるのです。また、休憩時間には、ウェントワースから話しかけられやすいようにと、端の席に移動するのです。このあたりのアンが積極的に変貌していくのは加速度がつくようです。そのような姿勢があってこそ、最後のクライマックスで、ウェントワースを脇において、ハーヴェルと永遠の愛について自分の考えを語ることで、ウェントワースに間接的に愛の告白をするところまでいくのです。このアンの変貌は劇的です。 これに対して、ウェントワースの方はどうだったのでしょう。オースティンは、物語の中でウェントワースが何を思い、何を考えているか、ほとんど明かしません。読者は、わずかに、彼のアンに対する振る舞いの変化や、それをアンが分析したことから間接的にうかがい知ることができるだけです。ましてや、バースではしばらく、彼の登場がないので、おそらく彼の最も劇的に変貌した時期であるはずなのに、そのことか全く書かれていません。これは、最後の最後で、彼がアンに渡した手紙と、その後の告白で、初めて明らかにされることになります。それは、まるで推理小説の最後の名探偵による推理の開陳ですべての謎が明らかにされて真犯人が捕らえられるカタストロフィと似たような劇的な効果をもたらします。読者はこの語りを聞きながら今までの彼の言動を振り返って納得することができるという仕掛けになっているのです。 “「ぼくはほんとうに、あなた以外の女性を愛したことはありません。ほかの女性を好きになったことはないし、あなたに匹敵するような女性に会ったこともありません。でも、これは正直に認めなくてはなりません。つまり、ぼくは無意識のうちに、いや、自分の意思に反してあなたへの愛を貫いたのです。ぼくはあなたを忘れようと思ったし、忘れることができると思っていました。しかし、ぼくはただ腹を立てていただけなのに、あなたに無関心になれたと思い込んでいました。ぼくはあなたの美点を認めようとしませんでしたが、それはあなたの美点がぼくを苦しめたからです。ぼくはいまあなたを、心の強さややさしさをみごとにかねそなえたすばらしい女性だと確信しています。でもこれも正直に認めなくてはなりません。つまり、ぼくはアパークロスでやっとあなたのほんとうのすばらしさを知ったのです。そして、ライムでやっと自分のほんとうの気持ちにきづいたのです。」 ウェントワース大佐は、ライムでいくつもの教訓を得たのだった。エリオット氏がアンとすれ違うときに、アンに賛嘆のまなざしを向けたことが、ウェントワース大佐の目を覚まさせ、あの突堤での出来事や、ハーヴィル大佐の家でいろいろな出来事を見たおかげで、ウェントワース大佐はアンのほんとうのすばらしさを確信したのだった。 その前に、ルイーザ・マスグローヴを好きになろうとしたことについて(これは傷つけられたプライドが腹いせに行ったものだったが)、ウェントワース大佐はこう言った。 「ぼくは最初から、そんなことは不可能だと思っていました。ぼくはルイーザを愛していたわけではないし、彼女を愛することなど不可能でした。でもあの日までは─つまり、ライムの事故のあとゆっくり反省するまでは─ルイーザの心など比べものにならないあなたの心のほんとうのすばらしさを、ぼくは理解していなかったし、あなたのすばらしい心がぼくの心を完全にしっかりとつかんでいるということにも、気がついていませんでしたあのライムでの事故でぼくは学んだのです。断固たる心の強さと、片意地な強情さの違いを。そして、向こう見ずな大胆さと、冷静な決断力との違いを。ぼくはライムで、自分が失った女性のすばらしさをあらためて思い知らされたのです。そしてその女性が目の前にいるのというのに、自分のくだらないプライドと、愚かさと、執念深い恨みのために、その女性を取り戻そうとしなかったことを、やっと後悔しはじめたのです。」” 長い語りなので引用は一部になりますが、この部分以外では、ルイーザとの関係から引き下がることができなくなり身動きがとれなくなって、兄にもとに逃げていたこと。ルイーザがベニックと婚約したことで、解放されてアンのもとにいさんでやってきたこと、アンとエリオット氏の振る舞いを見て嫉妬に苛まれたこと、アンとハーヴェルの会話に励まされて告白に至ったことなどが明らかになっていきます。 その夜自宅のパーティーで、ウェントワースに再び会ったアンはこう言います。 “ラッセル夫人の忠告に従ったのは正しかったと思っています。もしラッセル夫人の忠告に従わないで、あのまま婚約をつづけていたら、結婚をあきらめた場合よりももっと苦しい思いをしたと思います。母親代わりのラッセル夫人の親切な忠告に逆らったという良心の呵責を感じて、思い悩むに決まっていますもの。もし、人間がこういう気持ちを持つことを許されるなら、私はいま、良心に恥じることは一切ありません。もし私の気持ちが間違っていなければ、強い義務感は、女性の立派な持参金の一つだと思います。」” これをきいたウェントワースは、次のようにいいます。ここにウェントワースのビルドゥンクス・ロマンが隠されていたことがあきらかにされると思います。 “「じつはぼくも過去のことを考えていたんです。つまり、ぼくにはラッセル夫人よりも大きな敵がいたのでしないかと、ふと思ったんです。そしてその敵とは、ぼく自身です。」 (中略)「ぼくがもう一度プロポーすすれば、あなたはまたぼくと婚約して下さったんですね!でもぼくも、それを考えなかったわけではないんです。つまり、あなたとの結婚によって、ぼくの有終の美を飾りたいと、心の中では思っていたんです。しかし、一度断られた女性にもう一度プロポーズするというのは、ぼくのプライドが許さなかったんです。ぼくはあなたの気持ちが分かっていなかった。自分で自分の目を閉じてしまって、あなたの気持ちを分かろうとしなかったし、あなたを公平な目で見ようとしなかったのです。そのことを思い出すと、誰よりもいちばん赦せないのはぼく自身だと思わざるを得ません。ぼくがくだらないプライドにこだわらなければ、あなたもぼくも、六年間の別離と苦しみを味わわずにすんだかもしれないのです。」” ここに至って、ウェントワースの言葉ではありますが、これはアンにも当てはまることで、二人は、自身の内にある敵を自覚し、自己変革によって乗り越えることができた結果、結婚することができたという、教養小説的なサクセスストーリーとして、読むこともできるのです。ただし、一言附言しておけば、二人の結婚が必ずしも世間的な成功であるかといえば、それには留保がつきますし、そのことは小説の最後のところでオースティンが断りを入れています。単なるサクセスストーリーではないということには、留意しておいて下さい。
リンク . |
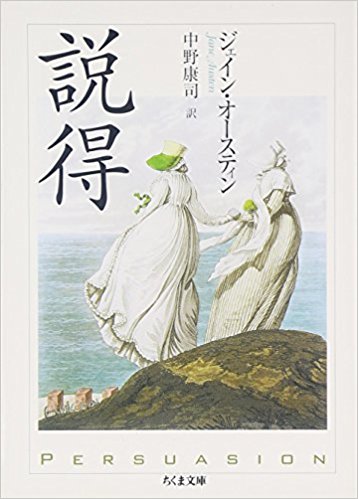

 このようにウェントワースの内面に対しては、アンの書き方のような繊細な書き方はなされず、類型的といえるほど形式的で大雑把な書き方です。つまり、全体としてはアンからの視点から書かれているのであり、ここでウェントワースについての記述は、その捕捉的なものと客観的な筋をおうために必要な程度ということなのです。ただし、これが類型的で客観的な書き方であるのは、読者はさもありなんと納得し易いものであるということもあるでしょう。というのも、少し先走りですが、後に物語が佳境に入っていくと、間接的に、実はそうでないと読者に想像させる叙述が現われてくるからです。そのためには、このような形式でそっけない書き方をしておくのが適切です。しかも、たしかに、この時にはアンからはウェントワースの、そのように見えたのは事実でしょう。だから、ここで読者は、客観的な状況と、アンの視点がゴッチャになっているのを、そうと知らずに、物語の中にいるわけです。
このようにウェントワースの内面に対しては、アンの書き方のような繊細な書き方はなされず、類型的といえるほど形式的で大雑把な書き方です。つまり、全体としてはアンからの視点から書かれているのであり、ここでウェントワースについての記述は、その捕捉的なものと客観的な筋をおうために必要な程度ということなのです。ただし、これが類型的で客観的な書き方であるのは、読者はさもありなんと納得し易いものであるということもあるでしょう。というのも、少し先走りですが、後に物語が佳境に入っていくと、間接的に、実はそうでないと読者に想像させる叙述が現われてくるからです。そのためには、このような形式でそっけない書き方をしておくのが適切です。しかも、たしかに、この時にはアンからはウェントワースの、そのように見えたのは事実でしょう。だから、ここで読者は、客観的な状況と、アンの視点がゴッチャになっているのを、そうと知らずに、物語の中にいるわけです。 私が、この散歩のエピソードが前半の佳境のひとつと言ったのは、このエピソードを通じて、今後の物語の展開が、ウェントワースをめぐってルイーザ・マスグローヴとアンの三角関係という基本構図で、しばらく進むことがハッキリしたからです。少し先走りになりますが、この三角関係が消失した後で、今度は別の三角関係が作られて、この小説は、これから三角関係を軸に物語がつくられていくことになります。議論を戻すと、姉妹の姉のヘンリエッタは、いとこのチャールズ・ヘイターとの関係が、この散歩を通じて確立し、二人はほとんど婚約したということが本人にも周囲にも周知されることになりました。その結果、ウェントワースの相手として妹のルイーザが残り、彼女はウェントワースに対して積極的なアタックを始め、周囲の人にも、それが明らかになっていくのが、この辺りからなのです。ルイーザがウェントワースへのアタックで、自身をアピールしていた売りは、「意志の強さ」です。それは、ウェントワースが結婚相手の女性に求める性格であった、まさにそのものです。つまり、ここで、ウェントワースの求めるタイプとして意志の強い女性であるルイーザ・マスグローヴがクローズ・アップされたというわけです。そして、この時点では伏線なのですが、ルイーザ以外にもうひとり意志の強い女性がいたのです。アンの妹メアリーです。彼女は、この散歩でも夫チャールズの説得にもかかわらず、ヘイターを訪ねることを拒絶します。彼女の拒絶によって、気の弱いヘンリエッタがヘイターを訪ねることを躊躇し始めます。メアリーの行為は意志が強いというよりは、わがままを押し通して周囲に迷惑をかける行為だったわけです。これが、後に、意志が強いことと、わがままであることは区別しなければならないことであることが、示されることになりますが、ここでのメアリーの行為は、その前触れであり、伏線となっています。このメアリーをウェントワースは軽蔑の視線で冷たく見ていました。さて、さらに物語を追いかけましょう。散歩している二人の会話は、アンがかつて妹メアリーの夫であるチャールズからの求婚を断ったことに及びます。
私が、この散歩のエピソードが前半の佳境のひとつと言ったのは、このエピソードを通じて、今後の物語の展開が、ウェントワースをめぐってルイーザ・マスグローヴとアンの三角関係という基本構図で、しばらく進むことがハッキリしたからです。少し先走りになりますが、この三角関係が消失した後で、今度は別の三角関係が作られて、この小説は、これから三角関係を軸に物語がつくられていくことになります。議論を戻すと、姉妹の姉のヘンリエッタは、いとこのチャールズ・ヘイターとの関係が、この散歩を通じて確立し、二人はほとんど婚約したということが本人にも周囲にも周知されることになりました。その結果、ウェントワースの相手として妹のルイーザが残り、彼女はウェントワースに対して積極的なアタックを始め、周囲の人にも、それが明らかになっていくのが、この辺りからなのです。ルイーザがウェントワースへのアタックで、自身をアピールしていた売りは、「意志の強さ」です。それは、ウェントワースが結婚相手の女性に求める性格であった、まさにそのものです。つまり、ここで、ウェントワースの求めるタイプとして意志の強い女性であるルイーザ・マスグローヴがクローズ・アップされたというわけです。そして、この時点では伏線なのですが、ルイーザ以外にもうひとり意志の強い女性がいたのです。アンの妹メアリーです。彼女は、この散歩でも夫チャールズの説得にもかかわらず、ヘイターを訪ねることを拒絶します。彼女の拒絶によって、気の弱いヘンリエッタがヘイターを訪ねることを躊躇し始めます。メアリーの行為は意志が強いというよりは、わがままを押し通して周囲に迷惑をかける行為だったわけです。これが、後に、意志が強いことと、わがままであることは区別しなければならないことであることが、示されることになりますが、ここでのメアリーの行為は、その前触れであり、伏線となっています。このメアリーをウェントワースは軽蔑の視線で冷たく見ていました。さて、さらに物語を追いかけましょう。散歩している二人の会話は、アンがかつて妹メアリーの夫であるチャールズからの求婚を断ったことに及びます。
 ライムで、彼らを待っていたのは、ウェントワースの親友であるハーヴェルと、その夫人。そして、ハーヴェルの妹ファニーと婚約していたベニックです。なお、ファニーは結婚を前にして亡くなってしまったため、ベニックは婚約者を失った悲しみの中にいました。親友との再会や旅行の高揚で盛り上がるグループの中で、ベニックは一人悲しみの中に閉じこもりがちであったのに対して、アンが話しかけました。ここで、アンが少し変化しました。それまで、アンは話の聞き手でした。8年前にラッセル夫人から説得されたのもそうで、アンは説得する側ではありませんでした。父や姉に対しても、彼らから話をされるだけで、彼らはアンの話を聞くことをしませんでした(彼らがアンの話にしたがっていれば、屋敷を他人に貸すような事態に陥ることはなかったといえます)。また、マカグローヴ家においても、アンは人々の愚痴を聞いてあげていたのでした。ところが、ここでは、アンはベニックに話しかけて、会話の糸口をつくります。彼女の変化は、おそらくウェントワースの注意を引いたのではないと思います。小説の中では、そのことには全く触れられていません。しかし、同じ部屋の中にいるわけです。さらに、ウェントワースは、数日前の散歩を契機にアンに注意を払うようになっていたわけです。だから、アンが今までになかったこととして、初対面に男性に自ら話しかけるという異変に気付いたと推測しても、無理とは言えないでしょう。そこで、アンがベニックに語ったことは、ウェントワースにも聞こえたと考えてもおかしくはありません。つまり、アンがベニックに語ったことは、ウェントワースにも伝わっていると言えるのです。それは、アンがベニックに話しかけた翌日、ハーヴェルがアンに対して、ベニックが雄弁に会話をしているのを久しぶり見たとして、友人としての感謝の言葉を述べています。アンに、とりわけ注意を払っているわけでもないハーヴェルですら、その程度は見ているのです。散歩以来、アンに注目しはじめているウェントワースが気がつかないはずがありません。しかし、オースティンは、ウェントワースがアンを見ていたとも、会話を聞いたとも、何の記述もしていません。また、アンはベニックと何を話したのでしょう。ベニックは詩を愛好する読書家で、とくに婚約者を失った自身の境遇をスコットの恋愛の詩やバイロンの絶望的な苦悩の詩に仮託して語るのに対して、アンは詩に耽溺するのは毒であり、道徳的かつ宗教的忍耐に関する最高の教えと最強の実例によって、精神を鼓舞し逞しくしてくれるような散文の本を勧めたと書かれています。そこで、具体的にどのような言葉が交わされたのかは書かれていません。オースティンの他の作品『高慢と偏見』では、ヒロインであるエリザベスの姉ジェインとビングリー氏が舞踏会の席で互いに一目ぼれの相思相愛になるところで、恋愛小説としてはひとつの見せ場であるはずなのに、そこで、どのようにビングリー氏がジェインを口説き、ジェインが応えたかということは一切書かれていません。オースティンという作家は素っ気ないほど禁欲的なのです。ここでも、アンとベニックの会話を具体的には何も書いていません。ただ、アンはベニックの抱えている悲しみについて次のように考えました。
ライムで、彼らを待っていたのは、ウェントワースの親友であるハーヴェルと、その夫人。そして、ハーヴェルの妹ファニーと婚約していたベニックです。なお、ファニーは結婚を前にして亡くなってしまったため、ベニックは婚約者を失った悲しみの中にいました。親友との再会や旅行の高揚で盛り上がるグループの中で、ベニックは一人悲しみの中に閉じこもりがちであったのに対して、アンが話しかけました。ここで、アンが少し変化しました。それまで、アンは話の聞き手でした。8年前にラッセル夫人から説得されたのもそうで、アンは説得する側ではありませんでした。父や姉に対しても、彼らから話をされるだけで、彼らはアンの話を聞くことをしませんでした(彼らがアンの話にしたがっていれば、屋敷を他人に貸すような事態に陥ることはなかったといえます)。また、マカグローヴ家においても、アンは人々の愚痴を聞いてあげていたのでした。ところが、ここでは、アンはベニックに話しかけて、会話の糸口をつくります。彼女の変化は、おそらくウェントワースの注意を引いたのではないと思います。小説の中では、そのことには全く触れられていません。しかし、同じ部屋の中にいるわけです。さらに、ウェントワースは、数日前の散歩を契機にアンに注意を払うようになっていたわけです。だから、アンが今までになかったこととして、初対面に男性に自ら話しかけるという異変に気付いたと推測しても、無理とは言えないでしょう。そこで、アンがベニックに語ったことは、ウェントワースにも聞こえたと考えてもおかしくはありません。つまり、アンがベニックに語ったことは、ウェントワースにも伝わっていると言えるのです。それは、アンがベニックに話しかけた翌日、ハーヴェルがアンに対して、ベニックが雄弁に会話をしているのを久しぶり見たとして、友人としての感謝の言葉を述べています。アンに、とりわけ注意を払っているわけでもないハーヴェルですら、その程度は見ているのです。散歩以来、アンに注目しはじめているウェントワースが気がつかないはずがありません。しかし、オースティンは、ウェントワースがアンを見ていたとも、会話を聞いたとも、何の記述もしていません。また、アンはベニックと何を話したのでしょう。ベニックは詩を愛好する読書家で、とくに婚約者を失った自身の境遇をスコットの恋愛の詩やバイロンの絶望的な苦悩の詩に仮託して語るのに対して、アンは詩に耽溺するのは毒であり、道徳的かつ宗教的忍耐に関する最高の教えと最強の実例によって、精神を鼓舞し逞しくしてくれるような散文の本を勧めたと書かれています。そこで、具体的にどのような言葉が交わされたのかは書かれていません。オースティンの他の作品『高慢と偏見』では、ヒロインであるエリザベスの姉ジェインとビングリー氏が舞踏会の席で互いに一目ぼれの相思相愛になるところで、恋愛小説としてはひとつの見せ場であるはずなのに、そこで、どのようにビングリー氏がジェインを口説き、ジェインが応えたかということは一切書かれていません。オースティンという作家は素っ気ないほど禁欲的なのです。ここでも、アンとベニックの会話を具体的には何も書いていません。ただ、アンはベニックの抱えている悲しみについて次のように考えました。 そして、この小説の中で唯一ともいえる大事件、ルイーザが怪我をして、意識を失うという事態が起こります。ライムから帰る日の朝、一行は見納めにと突堤を散歩します。突堤の石段を降りて海岸を歩こうとした時に、ルイーザは飛び降りてウェントワースに抱きとめてもらおうとします。一度は上手くいったのですが、その成功に味をしめた彼女は、周囲の制止の声をきかず、もう一度、こんどは、もっと高いところから飛び降ります。しかし、失敗して頭を打って意識不明に陥ります。抱きとめるはずだったウェントワースは茫然としてなす術も知らず、「誰も助けてくれないのですか」と悲痛な叫びをあげる。パニック陥る中で、アンだけが冷静になって、チャールズとウェントワースに指示を与え、ハーヴィル大佐の家に寄宿しているベニック大佐に医者を呼びに行かせ、ルイーザをひとまずハーヴィル家に運ばせます。危機にあって、アンの的確な判断能力に全員が救われたのです。アンのおかけで、初期対応の応急措置はなんとかできました。しかし、その後の善後策、つまり、本家に事故を伝えなければならないし、残ってルイーザの看病をしなければなりません。そこで、ウェントワースはアンとチャールズに看病を頼み、自身は一行の他の人たちと帰り、事故の連絡をすることにします。そこで、メアリーがごねて、自分が看病で残ると言い出します。周囲の説得にも耳を貸しません。アンはあれこれ揉めるよりも,自分が折れることを選択します。大佐は馬車の用意を済ますと,アンの役が無能のメアリーに代わっていることに憤慨するのですが,彼も無用な紛糾を起こすことを好まず、アンとヘンリエッタをつれて帰ることに。その馬車の中で、ヘンリエッタが疲れて寝てしまったので、図らずも、アンとウェントワースが、再会以来はじめて二人だけになれたのです。
そして、この小説の中で唯一ともいえる大事件、ルイーザが怪我をして、意識を失うという事態が起こります。ライムから帰る日の朝、一行は見納めにと突堤を散歩します。突堤の石段を降りて海岸を歩こうとした時に、ルイーザは飛び降りてウェントワースに抱きとめてもらおうとします。一度は上手くいったのですが、その成功に味をしめた彼女は、周囲の制止の声をきかず、もう一度、こんどは、もっと高いところから飛び降ります。しかし、失敗して頭を打って意識不明に陥ります。抱きとめるはずだったウェントワースは茫然としてなす術も知らず、「誰も助けてくれないのですか」と悲痛な叫びをあげる。パニック陥る中で、アンだけが冷静になって、チャールズとウェントワースに指示を与え、ハーヴィル大佐の家に寄宿しているベニック大佐に医者を呼びに行かせ、ルイーザをひとまずハーヴィル家に運ばせます。危機にあって、アンの的確な判断能力に全員が救われたのです。アンのおかけで、初期対応の応急措置はなんとかできました。しかし、その後の善後策、つまり、本家に事故を伝えなければならないし、残ってルイーザの看病をしなければなりません。そこで、ウェントワースはアンとチャールズに看病を頼み、自身は一行の他の人たちと帰り、事故の連絡をすることにします。そこで、メアリーがごねて、自分が看病で残ると言い出します。周囲の説得にも耳を貸しません。アンはあれこれ揉めるよりも,自分が折れることを選択します。大佐は馬車の用意を済ますと,アンの役が無能のメアリーに代わっていることに憤慨するのですが,彼も無用な紛糾を起こすことを好まず、アンとヘンリエッタをつれて帰ることに。その馬車の中で、ヘンリエッタが疲れて寝てしまったので、図らずも、アンとウェントワースが、再会以来はじめて二人だけになれたのです。
 このあと、ウェントワースは思いのたけをぶつけた手紙をアンに渡して、二人の思いが通じ合うということになります。
このあと、ウェントワースは思いのたけをぶつけた手紙をアンに渡して、二人の思いが通じ合うということになります。