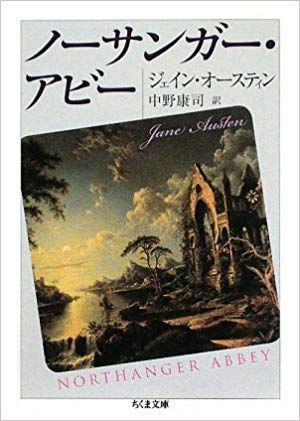『ノーサンガー・アビー』はジェーン・オースティンの処女作とされています。それまて、いくつかの習作が書かれましたが、作品として完成し、原稿を出版社に持ち込まれた最初の作品が、この作品ということです。諸事情から、この作品はオースティンの存命中は出版されることがなったそうです。よく言われることに、処女作に作家のすべての要素の萌芽が含まれているということがあります。作家の以後の創作活動の出発点となって、後の作品がそこから派生して生まれる原型のようなものということなのでしょうか。しかし、この作品には、むしろ、オースティンの後の作品とは一味違う作品となっています。つまり、オースティンが完成した6つの作品の中でも、この『ノーサンガー・アビー』は、他の5作品に比べて異質な作品です。 その異質さの大きな点、この作品が当時流行していたゴシック・ロマンスのパロディとして作られたということです。それは、さきに述べた、この小説の執筆や出版の経緯などともあわせて考えると、この小説が、オースティンという作家にとっての「方法序説」だったのではないかと思われるからです。17世紀のルネ・デカルトは、中世の神を中心にした世界観から個人を主体とした近代的な哲学を始めた人と言われていますが、その新しい哲学を最初から打ち立てるためには、不確実だったり疑いの余地があったりするような要素は、あらかじめ排除しようとしました。そして、排除しきれず残ったものこそが疑いの余地のないもの、つまり確かなものだということになります。その確かなものから、新しい哲学が始まるというのです。それが方法的懐疑です。デカルトは何もない白紙の状態から、自分の考えを作り上げたのではなくて、既にある哲学(中世の神を中心にした世界観)やまわりの世界を前提に、それを疑っていくという批判をしていくことで、自身の新しい哲学を始めようとしました。極言すれば、デカルトの始めた新しい哲学のスタートは中世の哲学のパロディだったわけです。まわりくどい説明になりましたが、オースティンが『ノーサンガー・アビー』をゴシック・ロマンのパロディとして書いたことを「方法的懐疑」とした意味が、なんとなくお分かりになったでしょうか。 では、改めて説明して行こうと思います。オースティンの小説は、イギリスのリアリズム小説の系統に位置づけられて語られていることが多いように見えます。このリアリズムというのは目の前の現実をありのままに描くというものだと説明されています。実際、オースティンの小説は、彼女自身が実際に生活し、目にしていた、いわゆる「田舎の村の三、四軒」を舞台にしたものです。しかし、それはオースティンが最初から、そういう小説を書こうとして、形式とか表現ができていたというのではないということを示しているのが、『ノーサンガー・アビー』がパロディとして作られたということであると思います。おそらく、オースティンという人は文学が大好きで、多くの作品を読んでいたと思います。その小説を読んでいるうちに、どこか物足りない、あるいは何か違う、しっくりこないものを感じていたと思います。しかし、そういうことは、小説を読めば、誰でも感じるものです。まあ、普通は、そういう違和感を気にせず放置してしまうものです。あるいは、違和感が残ったとしても、それが新たな作品への興味をおこす原動力となるくらいです。ところが、オースティンは、既存の小説では物足りないのなら、満足できるような小説を自分で書こうとした。そのときに、彼女が行ったのは既存の小説から違和感を起こさせるところを抜き出して、それを除いていったということです。その除いたところに残るものが、彼女にとって除くことができないもの、つまり、彼女にとっての小説の除いてはいけないもの、いわば本質ということになります。それは17世紀のデカルトが確かなものを求めて、疑わしいものを片っ端から除けていって、最後にこれだけは疑うことができないとして、疑っている自分がいるということに行き着いたと同じような作業と言えると思います。そのようにして形成されたのが、オースティンのリアリズム小説だったのではないかと思います。そのプロセスが『ノーサンガー・アビー』に表われていると思えるのです。例えば、作品の冒頭からヒロインのキャサリン・モーランドをする際に、「子どものころのキャサリン・モーランドを知っている人は、彼女が小説のヒロインになるように生まれついたなんて絶対に思わないだろう。」と、既存の小説のヒロイン像を否定する言い方をしています。これが、『ノーサンガー・アビー』がパロディとして作られている例として、よく例示されるところです。でも、これはパロディという体裁をとっていますが、先ほど触れたように、オースティンが小説を読んでいて、違和感を持ったところとして、抽出して、それを否定したものと言うこともできると思います。オースティンのリアリズム小説のヒロインが普通の女性であるのは、このようにゴシック・ロマンや恋愛小説のヒロインを否定した結果なので、既存の小説で普通のヒロインが、オースティンの小説で、従来の小説としては普通でないヒロインが、現実では普通の女性そのものだったいうことになります。そのような否定から。この場合であれば「〜でない」ヒロインによって、小説を作り始めているのです。このようにして、既存の小説に対して「〜でない」を繰り返していって、残ったのが、オースティンの小説の形、例えば、リアリズムだったり、「田舎の村の三、四軒」を舞台にすることだったりという特徴だったと思えるのです。『ノーサンガー・アビー』は、その既存の小説の形を出して、それをひとつひとつ否定していくというプロセスを小説の中で行っています。そのため、小説の中で、そのようにして否定をくり返していれば、そんなものまで否定してしまって、それが小説なのか、それでは小説とはどのようなものなのか、という疑問が湧いてくるのは自然なことです。そのために、『ノーサンガー・アビー』の中で、小説とは何かということを作者が自分の考えを語っている場面がでてきます。それをメタ小説というのでしょうが、『ノーサンガー・アビー』では、この小説を書きながらオースティンは、自分の小説をどのようにつくりあげるかという問いかけを、その都度行っていると思うのです。おそらく、小説について違和感を持った者を拾い上げて除いていくうちに、彼女自身、そんなものも否定してしまうのか、と危惧を感じ不安になったこともあると思います。そういう時に、小説とは何と、問いかけ、それに作者が答えている。言ってみれば、オースティンの小説家としてのアイデンテティを問う作業を、『ノーサンガー・アビー』の中で行っているといえるのです。おそらく、彼女は、この作品を執筆しているのと併行して、作家としての自己を形成していったのだと思います。 しかも、オースティンは既存の小説を読むのと同じように、自身の執筆中の、この小説も読んでいて、しかも同じように批判の対象にしていたと思われます。証拠があるかと問われれば、私の想像にすぎないと答えざるを得ませんが、おそらく、小説を読むのが好きで、読んでいるだけでは飽き足らずに小説を書き始めたとすれば、その小説の最初の読者はオースティン自身であったというのは自然なことです。その読むというのは、作家として文章を推敲するために読むのではなくて、あくまで読者として小説を楽しむために読んでいる。小説好きという、そういうものでしょう。それゆえに、小説が進行してゆくにつれて、オースティン自身が読者として制作に介入してくる、つまり、オースティンが『ノーサンガー・アビー』を既存の小説のパロディとして作りはじめ、メタ小説の様相を呈していたものを、オースティン自身が読者になって読み始めることになると、執筆中の『ノーサンガー・アビー』も既存の小説の仲間入りをしてしまうようになるのです。つまり、既存の小説のプロディとしてつくられた『ノーサンガー・アビー』自身がパロディの対象となって行きます。それに伴い、『ノーサンガー・アビー』自体が方法的懐疑の対象となって問いかけられることなる。いわばメタ小説である『ノーサンガー・アビー』の対してのメタ小説となっていくのです。例えば、小説の最初のキャサリンの設定は、ゴシックロマンスのヒロインの要素をひとつひとつ否定して設定されていました。しかし、そのヒロインにゴシックロマンスと同じさせるのではなく、ゴシックロマンスを読み耽させて、ゴシックロマンスの荒唐無稽ではない平凡な現実世界にいるという当初の設定を、もうひとつ逆転させて、その現実を見ないでゴシックロマンスの荒唐無稽の想像の世界の入り浸ってしまわせるのです。そして、ヒロインのキャサリンは、その想像の世界に現実を作り替えようとします。つまり、ゴシックロマンスの世界を否定しようとした『ノーサンガー・アビー』の世界を、再度ゴシックロマンスの世界から見て、そっちに強引に引き入れようとするのです。また、方法的懐疑の面から言えば、疑わしいものを取り除いていく作業は、舞台がノーサンガー・アビーに移った後半では、どんどん小説の世界が絞られて、例えば、登場人物はヒロインと相手の男性と、その障害となるティルニー将軍というヒロインの恋の進行に直接関係する人物だけに限られていきます。エレノアは別としてですが。そして、ストーリーとしても余計な説明すらも省略されてしまうようになり、最後は、拍子抜けするほどの素っ気ない、駆け足で呆気なく終わってしまったようなものとなるのです。つまり、自己否定のようなものです。だから、『ノーサンガー・アビー』はオースティンの他の小説のように形が、最後まで決まっていないのです。それは、視点をかえれば、読者が物語に参加しているように錯覚させるところがあるということです。それは、物語の先が見えないというところに現われています。読者はヒロインのキャサリンが自宅で家族に囲まれて無知で無垢な子供であったところから、アレン夫妻に連れられてバースに行き、社交界にふれる。そして、ノーサンガーアビーに招待される。というように、まるでRPG(ロール・プレイング・ゲーム)のように、彼女のいる場所がゲームのステージのようで、自宅からバース、ノーサンガーアビーと移動することで、ステージが変わり、その都度、新しい世界が開け、そこで主人公があらたな能力を獲得していく、そういうプロセスを楽しむようになっている。そこに読者の参加していると意識させるところがある。そういうところが、他の小説と一線を画した、この小説の特別なところです。
2.あらすじ その体験をするまえに、予備知識として、簡単に小説のあらすじを紹介しておきます。オースティンの小説は波乱万丈とか荒唐無稽とは正反対の、平穏で単調な日々の生活の繰り返しのなかで、些細な事実を淡々と綴っていくという特徴があります。しかし、この『ノーサンガー・アビー』は、物語の主な舞台が、前半がバースというリゾート地で、日常生活から人工的に隔てられた祝祭的な空間で、後半はノーサンガー・アビーという、主人公のキャサリンにとっては招待されて訪れるところです。したがって、物語は主人公のキャサリンにとっては非日常的な空間が舞台となっています。それゆえに、キャサリンは日常生活にはないウキウキとした情態、言ってみれば軽い躁状態にあります。そういう状態から、他のオースティンの作品にはない、主人公が騒動を繰り返し起こすという、比較的起伏のある物語になっています。 リチャード・モーランド牧師の娘キャサリン・モーランドは、貴族でも裕福な家の娘でもない、自身も目立ったところのない平凡な女性です。それが隣人のアレン夫妻から誘われて、イギリス南部の保養地バースを訪れることから物語は始まります。そこでアレン夫人の友人のソープ夫人の娘であるイザベラ・ソープと親しくなり、共に舞踏会に行ったりして楽しいときを過ごすのです。イザベラの兄で、キャサリンの兄ジェームズの大学の友達でもあるジョンソープに、キャサリンはしつこく迫られることになります。一方、イザベラ・ソープはキャサリンの兄のジェイムズを結婚相手として狙い、婚約に至ります。そしてキャサリンは、社交パーティでヘンリー・ティルニーと知り合い、想いを寄せるようになります。ヘンリーの妹であるエレノア・ティルニーとも友達になります。ヘンリーは自身の小説観や、歴史世界についての知識でキャサリンを魅了していく。キャサリンはヘンリーとエレノアの父であるティルニー将軍によって、ヘンリーの実家であるノーサンガー・アビーに招待されます。ゴシック小説『ユードルフォの秘密』の愛読者であるキャサリンは、その屋敷はどこか暗く、古めかしく、魅力的な謎に満ちているのだろうと期待して、さまざまな空想に耽ります。しかし、その期待は次々と外れるのです。キャサリンはこの屋敷に関する数々の謎を指摘してヘンリーに披露するが、彼はそれら全てに反論して否定していきます。例えば、ティルニー将軍が過去に妻を虐待したのではないかと疑って、亡くなったティルニー夫人の部屋を秘かに探索するのですが、ヘンリーに現場を見つかってしまい、愚かな妄想をたしなめられます。キャサリンは愚かな自身の姿に気付いてゆきます。そんな中で、兄のジェイムズからの手紙でイザベラとの婚約が解消されたことを知ります。イザベラは、ヘンリーの兄のティルニー大尉に乗り換えてしまったのです。そして、ヘンリーの留守中に、突如ロンドンから戻った将軍は、キャサリンに翌朝出て行くように命じます。追い出される理由もわからないまま、キャサリンは屈辱感を覚えつつ、落胆して帰郷していきました。ヘンリーに彼女と別れるよう言い付けるが、ヘンリーはそれを拒否して彼女の後を追い、彼女と結婚するというハッピーエンドで終わります。
3.『ノーサンガー・アビー』を読む体験(引用はちくま文庫版の中野康司訳より) 子どものころのキャサリン・モーランドを知っている人は、彼女が小説のヒロインになるように生まれついたなんて絶対に思わないだろう。彼女の境遇、両親の人柄、彼女自身の容姿と性格など、どこから見てもヒロインとしては完全に失格だった。 という冒頭の文章。ジェイン・オースティンの小説の書き出しはどれも面白いが、この『ノーサンガー・アビー』の書き出しも小説の世界に一気に引き込まれてしまう文章です。しかし、他のオースティンの小説と比べると、この文章は特異です。そのような他の彼女の作品と違っている書き出しが、この小説の特異性と密接に関係していることでもあり、ひとつのシンボルとして見ることができるものなので、まずは、そのことについて考えていきたいと思います。例えば『説得』の書き出しはヒロインの父親で当主のサー・ウォルター・エリオットの紹介です。彼は家系を記した記録しか読まないという文章で、事実を客観的に記述しているような文章ですが、その素っ気ないほど簡潔な文章の中に、彼の人柄と現在のヒロインの窮状を招いた要因が集約されて表わされていて、さらに、その冷徹な記述が、ヒロインが置かれているあたたかいとはいえぬ雰囲気すら伝えている出だしです。そこでは、作者の語りが、神様のような超越した視点で、小説の人物を冷たいほど突き放した客観的な視点を徹底されています。これに対して、『ノーサンガー・アビー』の書き出しの文章は、“誰も〜なんて思わないでしょう?”と読者にかたりかけ、同意を求める書き方をしています。これは事実を客観的に記述しているのではなくて、判断を読者に委ねているのです。ここでの作者は神さまの視点にいません。しかも、この文章の内容には具体性がなく、事実を客観的に記述しているのではなくて、作者という個人が小説の登場人物のひとりになって、ヒロインを見た印象を語っているようなのです。では、なぜ『説得』のように具体的な事実を客観的に語らないのか。それが、『ノーサンガー・アビー』をオースティンの他の作品から画然と隔てられている違いなのです。簡単にいうと、オースティンの他の作品はヒロインが如何に相手を掴まえるかという手練手管のやり取りを活写しているのに対して、『ノーサンガー・アビー』は手練手管以前の、ヒロインが手練手管を出す以前の人を恋するところを中心に描いた作品だからです。だから、ヒロインは相手に向けて行動する物語でなく、相手をどのように思っていくかの物語なのです。したがって、ヒロインの行動は外形のアクションですから外側から客観的に描くことが出来ます。これに対して、『ノーサンガー・アビー』のヒロインは妄想する、つまり思うという内面のアクションが中心なので外側からは分かりません。したがって、主観的に、どうなの?と問いかけるようにして描いていくようになります。どう思っているのか、当人に聞いてみるか、あれこれ想像するかしかないのです。だから、この書き出しで、作者は主観的に見た目を語り、評価を読み手に問いかけているのです。 書き出しの文章について、いいたいことは、これだけではありません。この小説に対する解説でよく言われている小説のパロディとして読むことができるということが、この書き出しから、すでに窺うことができるということについてです。この゜書き出しの文章の中で“ヒロインとしては完全に失格だった”と小説の設定についてもここで評価的なコメントを付しています。むしろ、それが文章の記述の中心です。これは、当時の小説、とくにゴシック小説のヒロインの姿に対する揶揄的な姿勢の表れであると解説されているようです。この文書でヒロインと言っているのは当時の小説の多くで用いられていたヒロイン像のことで、『ノーサンガー・アビー』のキャサリンは、そのヒロイン像に当てはまらないことを小説の冒頭で明言している。そういう差別化が、当時の小説とは違うということを宣言しているのであり、当時の小説の一様なヒロインへの皮肉になっている、ということです。 他方で、“ヒロインとしては完全に失格だった”という書き出しは、では小説のヒロインとはどのようなものなのか、という問いかけを内包しているということも出来ます。この小説を読み進めていくと、作者オースティン自身が小説についてああでもないこうでもないと、いろいろ作品の中で語っていて、この小説が小説について語る小説、つまりメタ小説でもある。それが、この書き出しでは。小説のヒロインとは何かという問いかけをしていることが、メタ小説として小説とは何かの一環であると捉えることができるというわけです。 書き出しについて、長々と書いてきましたが、この書き出しには、この作品の様々な要素が集約されているということなのです。それをオースティンがたったひとつの書き出しの文章に込めてしまって、それを読者との出会い頭にぶつけてきている。それが、この小説のおおきな特徴のひとつです。 そしてキャサリンも、生まれてこのかた誰にも負けないくらい不器量だった。みともないほどの痩せっぽちで、青白い肌でひどく血色が悪いし、髪も美しい巻き毛ではなくて、まっすぐな黒い貧弱な髪で、目鼻立ちすごくきつい感じだった。容姿はこんなところだが、性格のほうも、小説のヒロインとしてはまことに不向きなものだった。男の子なの遊びなら何でも大好きで、お人形さん遊びよりもクリケットのほうが大好きだし、ヒロインが幼いころに熱中しそうな遊び、たとえばヤマネを飼ったり、カナリアに餌をあげたり、バラに水をやったりすることよりも、クリケットのほうが断然好きだった。園芸趣味はまったくなくて、たまに花を摘んでも、たいていいたずらが目的だった。摘んではいけないと言われた花ばかり摘むのだから、そうとしか考えられない。性格はこんなところだが、勉強や芸事の能力も、じつに驚くべきものだった。誰かに教えてもらわないと何も覚えられないし、何も理解できないし、教えてもらってもどうしても駄目なときもあった。しばしば集中力に欠け、本質的に知能がついてゆけないときもあるからだ。(p.9) 父はごくふつうの牧師で、“娘を監禁する癖はなく”、母は“誰もが予想するようにキャサリンを産んで死ぬ”、ということもなく生き続けて」、10人もの子どもを生んだ健康的な女性という、平凡な“それ以外に何の取り柄もない”家庭に、キャサリンは生まれ育ったのです。この“娘を監禁する癖はなく”とか“誰もが予想するようにキャサリンを産んで死ぬ”といったことは、ゴシック小説の定番的な設定であって、ここでは、わざわざそうでないということ、否定的な表現を繰り返しています。これは、ゴシック小説に対する皮肉という言い方と説明されていることのあるようです。 ゴシック小説に限らず当時の小説のヒロインは生まれながらに美しいというのが決まり事のようになっていて、それゆえに、キャサリンが不器量だということ、しかも。ヒロインの容貌が具体的に描かれていること自体が、それまでの小説では稀なことで、通常はヒロインの美しさが強調されても、具体的なイメージは曖昧で、それは読者の想像に委ねるという場合が多かったといいます。また、ヒロインは聡明であって、その能力で困難を乗り越えたり、危機を回避したりするということからも、キャサリンはそういう具体的な才能にかけていることを列記されています。つまり、ここではキャサリンは取り立てて美人でもなく才能もない平凡な娘だったことを具体的に、従来の小説からするとヒロイン失格であることをキャサリンの生い立ちを通して強調されます。しかし、皮肉の意図があったとはいえ、小説の冒頭で、ヒロインについて、これほどまでにないない・・と否定の言葉をくどいほど繰り返すというのは、かなり変わっているというか、普通では、最初からそんなネガティブであるというのは読むほうも、それほど感じのいいものでもないだろうし、決してノーマルなやり方ではなかったのではないかとおもうのです。だから、オースティンは、このような始まり方を、覚悟をもってやった、あるいはそうせざるを得なかったのではないかとおもうのです。少なくとも、パロディっぽくやりましょうといった安易な気持ちでやったのではないと思います。というのも、そのあとで、つまり、最初の何章かはプロットの説明に終止してストーリーが始まらないのです。例えばこうです。 なんとも奇妙で不可解な性格である!というのは、10歳にしてこれだけ十分な堕落の兆候があったにもかかわらず、キャサリンは心も性格もけっして悪くはないのだ。ぜんぜん強情ではないし、すぐに喧嘩するようなこともないし、妹や弟たちにはとてもやさしくて、ほんのときたま姉貴風を吹かせる程度なのだ。さらに付け加えるとキャサリンは騒々しくて乱暴で、束縛されることと、清潔なことが大嫌いで、家の裏の丘の斜面を転がりおりるのが何よりも大好きだった。(P.10) オースティンの他の作品と比べてみると、このことは特異と言えます。他の小説では、最初からストーリーが展開し始めて、その物語の中で手際よく登場人物が小説の中で実際に動いて、こういう人なのだなということが分かるようになっているのが常なのです。“キャサリンは騒々しくて乱暴で、束縛されることと、清潔なことが大嫌いで、家の裏の丘の斜面を転がりおりるのが何よりも大好きだった”などいう説明をまじえないで、物語の中で、それが表われるような効果的な場面があって、それに触れてキャサリンはこういう性格なのだということが具体的に示されるというのが、他の作品の場合なのです。そもそも小説の読者というのは気紛れだし、小説を読むことだけが愉しみというわけではないのですから、ストーリーが始まらず、いつまでもプロットの紹介ばかりでは、退屈になって放り出してしまいかねません。オースティンという作家は、そういう読者の性向をよくわかっていたと思います。それが証拠に、他の作品では、はじめからヒロインとヒーローは両方とも登場していて、この二人のやり取りがはじめから展開するという本題に入っているのです。それが、この『ノーサンガー・アビー』に限っては、退屈になってしまう恐れのあるプロットの紹介を延々と続けて、なかなか物語が始まらないのです。これは、単にパロディだからということだけで説明がつくのでしょうか。だいだい、当時の読者は、パロディだからと許してくれるでしょうか。私には、オースティンはパロディとして意図的にこのような長いプロットの紹介を行ったとは思えません。むしろ、そうせざるを得なかったのではないかと思います。それは、この作品が若書きで、作家としての巧みさが備わっていなかったということでもなく、この『ノーサンガー・アビー』という作品の特異さゆえに、そうせざるを得なかったと思うのです。 オースティンは、この『ノーサンガー・アビー』において、17世紀のルネ・デカルトが哲学で行ったことを、小説で行ったのではないかと思うのです。いわゆる方法的懐疑です。デカルトが確かなものを求めて、疑わしいものを片っ端から除けていって、最後にこれだけは疑うことができないとして、疑っている自分がいるということに行き着いたように、オースティンは、ここで小説について、何が本質的になくてはならないものなのか、そこで、どうしても必要かどうかを問いかけて、本質的でないものをひとつひとつ否定していくという作業、この中で実際に行っているのです。父は“娘を監禁する癖はなく”、家庭は平凡な“それ以外に何の取り柄もない”というようにです。それは、プロットの設定だけにとどまらず、物語の展開についても物語の中の波乱万丈か平凡かという分岐点で、ことごとく波乱万丈の選択肢を外しているのです。言ってみれば、小説を彩っているお飾りをことごとく取り除いていって、残された、これを取り除いてしまうと小説として成立しなくなってしまう、というものだけを残して、それだけで小説が成立するか、読者を楽しませることができるか、という本質の追究を試みている作品になっていると思うのです。もちろん、オースティンは自覚してそんなことをしているとは考えられません。おそらく、未だ自身の方法が摑めていない中で、自身のスタイルを手探りで試しているうちに、こんなことになってしまったのだろうと思います。『ノーサンガー・アビー』についてメタ小説的な言及を作中でオースティが述べているところがありますが、それは、この作品全体がそういうものなので、その中で出てきたものと考えられないでしょうか。つまり、そういう言及があるからメタ小説なのではなくて、もともと、そういう構造なので、それに従って言及が出てきているという作品なのです。それゆえに、小説の構成において無理がかかってしまって、そのひとつが、長いプロットの説明ということになると思います。 第1章の物語も未だ始まっていないところで、あまり長居すると、この後が始まらなくなってしまいます。このへんで、次に移りましょう。 この第2章から物語は始まるといっていいのです。オースティンの他の小説であれば、第1章などなくて、この第2章からはじまるように書かれるでしょう。この第2章では村の地主であるアレン氏が療養のために保養地であるバースに逗留することになり、アレン夫妻と親しくしていたキャサリンがバース行きに誘われ、同行することになります。そこから物語は、実質的に始まります。しかし、この第2章でも未だにキャサリンの紹介をやっています。ヒロインであるキャサリンの紹介について、オースティンはキャサリンについて否定的な文章を繰り返し、ヒロイン失格であることを強調するようにのべています。しかし、第1章のところで引用したように、決してキャサリンというキャラクターに対して悪意があるというわけではいことが分かります。この引用では17歳のキャサリンが“優しい心をもち、明るく素直な性格で、自惚れや気取りがまったくない”ということを言っています。このように控えめながら述べられているわずかな長所は、小説のヒロインとして地味で目立たないものですが、実は人間にとって本質的に大切なものだということが、物語が進んでいくに従って次第に明らかになってくるのです。廣野由美子は『深読みジェイン・オースティン』のなかで、これは平凡な女性がいかに恋愛を経験するかというプロセスを通して、「ヒロインとは何か」を追求する物語であると言える、と述べています。私には、それ以上に、現実の日常生活のなかで、人として大切なもの、しかも平凡な日常で普段は気付かないのが物語をとおして浮き上がってくる、そうものを目指している作品であるように思えるのです。少し、先を急ぎすぎました。 例えば、こんな風にです。 彼女がどういう人物か、いまここでしっかり説明しないと、説明しそこなってしまうかもしれない。まず、彼女は愛情深い心を持ち、とても明るい率直な性格で、うぬぼれや気取りはまったくない。態度は、少女時代のぎこちなさと内気さがやっと抜けたところで、容姿はとても感じが良くて、きれいに見えるときは美人の部類に入る。そして頭のほうは、17歳の娘の例に漏れず、無知で無教養だった。(P.16) 第1章では触れることができませんでしたが、上の文章は翻訳なので、原語ではどのような文体で語られているのか分かりませんが、この文章を読むかぎりでは、語り手が冷静で事実を客観的に語るというスタイルではなくて、キャラが立っているというのか物語の登場人物のように生きいきとした性格をもった人物として、読者に向けて語りかけてくるスタイルをとっています。実は、第1章も第2章も、ヒロインのキャサリンをはじめとした小説の登場人物たちは、生きて動いていません。この段階では、将棋の駒のように単にストーリーの設計図のなかで動かされているだけです。いってみれば、おばあさんが子供に昔話を語りきかせるように、語り手である作者が、そのおばあさんのように生きていて、子供ならぬ読者に語っている。ヒロインのキャサリンなどの登場人物は、作者の語りのなかのコマにとどまっています。そのため、キャサリンの人物の説明をすることになっているのです。それはどうしてかというと、小説の語り口が否定を連ねているからです。例えば、次のように。 あまり幸先はよろしくないけれど、とにかくこうして出発し、キャサリンの旅が始まった。何事もない平穏無事な旅であり、強盗にも風にも見舞われなかったし、馬車が転覆してヒーローが助けに現われることなかった。ひやりとしたのは一度だけ、アレン夫人が宿屋に木底靴を忘れて大騒ぎしたときだが、それ結局は夫人の思い違いで、ちゃんと荷物の中に入っていた。(P.18) 引用した文の内容は、バースへの移動は何も起こらず無事だったということです。事件も何もないわけなので、物語の進行の上で必要のない文章のはずです。しかし、小説には不要な文章などありません。この文章も必要なのです。それは、“強盗にも風にも見舞われなかったし、馬車が転覆してヒーローが助けに現われることなかった”という否定を連ねたところ。〜も起こらなかったということ。この起こらなかったことは波乱万丈のストーリーで使われるような事件や事故です。そのようなことは、非日常的で、通常では起こることのない例外的なことです。万が一といいますが、一万回のうち一回あるかないかということです。しかし、手に汗を握るような波乱万丈のストーリーでは、そのような万が一のことがつづけざまに起こるから、読者はそういうものに巻き込まれるように、日常を忘れ、刺激に翻弄されていくのです。オースティンは、そういうことをここで、あれもないこれもない、と断るように敢えて否定を重ねます。それをパロディと考えることもできるでしょう。しかし、ここでは何も起こらない、いわば万が一の9999回の平凡な日常的な事例の一つであったわけで、当たり前なので、あえて書く必要のないことのはずです。オースティンという作家は、その9999回の方を小説にしようとした人であるわけです。『高慢と偏見』や『エマ』といった作品には、そういう日常の、いつもと変わらない毎日のこまごまとしたことが描かれています。但し、それらの作品では“〜などは起こらなかった”というアクシデントの発生を否定するような断りを入れていません。それは、これらの作品では、非日常的な特別な事件という刺激がなくても、読者は面白く物語を追いかけられるように、作者は書けているし、読者もそういうものとして作品を受け容れているからです。しかし、『高慢と偏見』や『エマ』が波乱万丈のストーリーとは違う小説として受け容れられる以前は、そもそも、そういうものがなかったので、オースティン本人としても模範としてならうようなものがなく、自身で新たなスタイルを切り拓いたということになるはずです。おそらく、何もないところから新たなものを生み出すことはできないはずなので、おそらく、既存の小説をもとにして、それに変革をほどこしていくというプロセスで、最終的には『高慢と偏見』や『エマ』のようなスタイルに行き着いたと思います。オースティンが、そういうスタイルを会得する前、その時に既存の波乱万丈のストーリーのスタイルに従わないで物語をつくっていくために、そうでないという、いわば既存のものをいったん否定するという段階があったはずで、それは多くの作家の場合には、習作のようなもので、世には出てこないことが多いのですが、それが出ている作品。それがこの『ノーサンガー・アビー』ではないか。この作品を読み進めていくと、後半では登場人物たちが生き生きと動き始めていきますが、この作品を制作しているさなかに、オースティンは、何か摑んだのかもしれません。その点で、オースティン自身も、この作品に捨て難い魅力を感じていたのではないかと思います。 また、視点を変えて考え見ると、この引用した文章のように、否定を連ねて、何も起こらなかったというだけで読者を読ませてしまうという、かなり過激で実験的な試みをしているともいえるわけです。だからこそ、小説の中に作者が登場して、小説とはこういうもので、こういうこともできるという、いわば弁解ともいえるようなコメントを加えることも敢えて行った、と言えるのではないかと思えるのです。 少しくどいかもしれませんが、他のセンチメンタルン小説では、ヒロインが生まれて初めて旅に出る際には、うら若い乙女が道中で出会う様々な危険を心配する家族たちによって、大げさな別れの場面が繰り広げられるのですが、キャサリンの家族はいたって平然としていて、それが日常の普通のことなのですが、淡々と彼女を送り出すわけです。それを、“幸先よくない”というように、引用の文章ではのべているわけです。あるいは、強盗や嵐に襲われること、馬車が転覆することなどが、“助け”“幸運”であるとされたりするような言い方は、キャサリンが小説を読みすぎて、これまでの読んだ小説の中で起こったような出来事、そこでヒロインは運命的な出会いをすることになったりするわけですが、そんなことを期待するキャサリンの現実ばなれした物事の捉え方の歪みを浮かび上がらせているところでもあります。そういうキャサリンの歪みは、パロディとして捉えることもできますが、平凡な淡々とした日常を対照的に浮かび上がらせる効果も果たしていると思います。 バースに到着して、いよいよキャサリンは小説の中で動き始めます。 一行は無事バースに到着した。馬車はバース周辺の美しい景色の中を通り過ぎ、それから町の通りを走って宿へと向かったが、キャサリンはうれしさいっぱいで、わくわくぞくぞくしながら、あちこちきょろきょろ見まわした。もとちん幸せになるためにバースに来たのだが、これだけで十分幸せだった。(P.18) この文章だけでも、キャサリンという女性が、好奇心旺盛で、生き生きとした目で馬車の中から周囲の景色を見ていたのが分かります。オースティンは、このようなさり気ない場面で生身の人間としてのキャサリンの、それまでの小説にない魅力を生き生きと描き始めます。また、引用の二つ目以降の文章についてみて見ると、最初のところは馬車の客観的な状況の描写で、キャサリンのことになると、語っているのは作者ですが、そこにキャサリンの行為だけでなく、内面の感情の描写も入ってきます。そして、次の文章の“もちろん幸せになるためにバースに来たのだが、これだけで十分幸せだった。”は完全のキャサリンの思いになっています。このように作者は、ここでは、状況を客観的に語る鳥瞰的な視点と、キャサリンの感情に踏み込んで説明する語り、そして、キャサリンになり代わって思いを語る立場を、かわるがわる、時には複合させながら語っています。これ以外のところでは、作者が自身のキャラクターとして登場人物のように思いを語ったりと、語る視点を多重的に、いったりきたりしながら語っています。しかも、注意しないで読み流してしまうと、どこまでが客観的な状況の語りで、どこからがキャサリンの内面なのか区別がつきにくくなっていて、時には、その状況も客観的なのか、キャサリンから見えている状況なのか判然とし難い区なっているところも出てきます。このような語りの多重性、多層性は、日本の少女マンガでもあって、ふきだしに入っていないナレーションが、客観的な説明なのか、キャラクターの内心の声なのか、作者が闖入してきたのか判然とし難く、それが渾然一体となって、読者の感情移入を誘うようになっています。それと似たような、ことをこの作品で、オースティンはすでに行おうとしている。それは、この小説が、とくに前半では細かなエピソードはありますが、おおきなストーリーの起伏というのが見られないので、その代わりに平凡に設定されたヒロインの内面の感情や考えの動きを活写することで、その日常の細かなことが生々しいものとして、意味をもってくる。それが小説の動きを作り出すものになっていると言えます。 しかも、ここでさり気なく、キャサリンがバースに来たのは“幸せになるため”
ということ、すくなくともキャサリンはそれを期待しているという大事なことが示されています。この、この後のキャサリンの行動の動機となるものです。実に、この小説は平凡な少女が幸せを求めて努力していく物語であるというものであるからです。 しかし、物語はキャサリンの期待した通りには進みません。現実なんてそんなものです。バースに着いた興奮のままに、衣装を買いにいったり、髪を整えたりして、準備をしているうちはよかったのですが、いざ社交界に打って出ようと舞踏会場に出かけてみれば、人ごみに右往左往し、便りのアレン夫人はキャサリンをエスコートしてくれず、人ごみでこったがえす会場で誰も知り合いがなく、ダンスもできず、期待した出会いの気配もなく、かすかな居心地の悪さすら味わされるというものでした。いってみれば散々なものとして終わるはずが、最後の最後、二人の紳士が、彼女の聞こえるところで「きれいな子だね」と言ったのが耳に入り、そのことによって、今夜はとても楽しい舞踏会だったと思い始めるのでした。 この単純な賛辞をささやいてくれたふたりの紳士に彼女は心から感謝した。そしてその感謝の気持ちは、彼女の美しさを称えた15編のソネットに対して感じる感謝の気持ちよりも、はるかに大きいものだった。こうしてキャサリンは、会場のすべての人に好意を感じながら椅子駕籠へとおもむき、今夜の舞踏会で自分が注目を浴びたことにすっかり満足したのだった。(P.26) これは、キャサリンの純真さ、すなおさそして前向きな姿勢を表わしているものですが、このよさをキャサリンは小説を通じて持ち続けていくことになります。それがキャサリンのヒロインとしての魅力をつくっていくものではあるのですが、この時点では世間知らずのこどもが浮かれて有頂天になっている喜劇的な場面にもなっているのです。 バースに着いてしばらくは、小説らしい事件はおこりそうもなく、ロマンスの気配もありません。頼りになるはずのアレン夫人は知り合いを見つけることができず、キャサリンの舞踏会デビューは首尾よく終わるというわけにはいきませんでした。それにもかかわらず、キャサリンはとくに失望することないのは、彼女のすなおで前向きなところであり、それは反面からみれば鈍感ということになるのでしょうが、そのあたりも、波乱万丈のロマンス小説のヒロインからはほど遠いことが、彼女の具体的な態度や行動からも強調されるように書かれています。 そして、ここでキャサリンは、小説のヒーローであるヘンリー・ティルニーに出会います。その出会いも、ドラマチックにはほど遠いもので、社交会館の司会進行役である儀典長が、キャサリンのダンスのお相手として紹介したのがヘンリーだったというわけです。 青年の名前はヘンリー・ティルニー氏といい、年齢は二十四、五歳で、かなりの長身で、とても感じのいい顔立ちで、知的な生き生きとした目をし、絶世の美男子まではいかないが、かなりそれに近い美男子だった。それに態度も申し分ないし、こんなすてきな人を紹介されて、自分は最高に運がいいとキャサリンは思った。踊っている間は言葉を交わす暇はなかったが、お茶の席について話をすると、思ったとおりの好青年だった。とても流暢に元気よく話し、茶目っ気たっぷりで、冗談好きな感じで、よくわからないが面白い人だと思った。(P.27〜28) この紹介も、作者の客観的な事実の記述に、キャサリンの印象(主観)が入り込んでいます。しかし、この紹介は颯爽としたところも、殊更にヒーローとして印象的なところもなく、ヘンリーという人物もヒーローとするにはもの足りなさが残る人物として、オースティンも些かの留保をのこすような紹介をしています。キャサリンは、そんなヘンリーを“よくわからないか面白い人物”という好感は持ったのでしょうが、ロマンスにあるような最初の出会いで運命的な恋に落ちるということはなく、ユーモアの視点も含ませつつ、どちらかというと、どこにでもあるような月並みな出会いの形になっていると思います。この出会いで、キャサリンとヘンリーの間で会話の場面があって、ここで初めて説明的でない会話、作者の手を離れて登場人物が自身の会話を始めます。人物たちがようやく生き生きとし始めます。ヘンリーは、オースティンの他の小説のヒーローたち(エドワード・フェラーズ,ブランドン大佐,ダーシー,エドモンド・バートラム,ナイトリー)にはない流暢さの反面皮肉たっぷりなおしゃべりには、彼自身の弱さとそれを隠すような斜に構えた態度だということが徐々に明らかになってくるのですが、そういう相反する面を抱えた人物であることが、この会話の中で仄めかすように示されています。しかし、初めて読む読者はそのことには気付かず、後になって、思い出すと、たしかに最初のところからそういう風に書かれていたと後から気付くような、いわば伏線として記述されています。このあたりの用意周到さは、とても若書きとは思えない技巧的なところです。二人の初対面の場面で、ヘンリーは舞踏室にふさわしいちょっとした会話を彼女に教授するように話しかけます。彼女が書いてもいない日記の内容を提示して見せたり、女性の手紙の書き方についての批評をしたりします。それに対して、キャサリンは、彼が予想した一般的な女性とは違って、非常に素直で直截に答えます。彼女は何のてらいもなく、日記はつけていないし、女性の手紙の書き方が男性より上手だと思わないと言うのです。 キャサリンは性格はよいが、ヘンリーとの知性の差は明白で、知的レベルでは彼女は彼の足下にも及ばないのが、この会話のやり取りからも明らかです。女性向きのお決まりの会話をわざとらしく模倣しようとしたり、女性の日記や手紙の書き方を嘲ったり、女性の言葉遣いや読書の趣味について論じるヘンリーの「冗談」に対して、キャサリンは時々、「笑うべきかどうかわからず、顔をそむける」というように、戸惑いを示したり、無反応だったりするのですが、これは彼の言葉がユーモアとして機能していないことを示すものです。キャサリンの弱点を皮肉るために彼女をからかうヘンリーは、そのからかい方はいささか意地が悪く、時として彼は、女性蔑視の傾向を示すこともあるのです。しかし、キャサリンは、そのことに気付くこともありません。それは、ある面ではヘンリーの知性の引き立て役でもあるのですが、この鈍さが彼女の魅力であることが徐々に明らかになって、それがヘンリーを動かすことにもなっていくのです。ここでは、この二人の出会いの際に、その萌芽が、登場人物の二人にも、読者にも気付かないところで示唆されているのです。 それだから、というわけではないのですが、この小説はゴシック小説のパロディという言い方がよくなされますが、この小説のストーリーには謎解きの要素があって、読者の気付かないところで巧みな伏線が張られているのです。それには、読者も読んでいて最後まで謎解きの性格に気付いていない、そういうさり気ないもので、それこそがジェイン・オースティンという作家の面目躍如たるところです。 第4章 翌日、キャサリンはヘンリーとの再会を期待して張り切ってポンプ・ルームへ出かけますが、結局ヘンリーは現れません。下の文章はキャサリンのヒロインらしかならぬところが、皮肉を交えて表わされています。こういう表現はオースティン独特のものでしょう。 翌日キャサリンは、いつもより張り切った気持ちで大急ぎでポンプ・ルームへ出かけた。午前中は絶対にティルニー氏に会えると思い、ほほえみ浮かべて今か今かと待ち構えた。だが残念ながらほほえみは必要なかった。結局ティルニー氏は現れなかったのである。(P.36) その代わりにアレン夫人が学生時代の旧友であるソープ夫人と再会し、キャサリンはその三人の娘を紹介されます。たまたま、キャサリンの兄ジェイムズがオックスフォード大学でソープ家の長男ジョンと親しく、ソープ家のクリスマスに招待されたという機縁から、とくに長女のイザベラとは意気投合するように仲良しとなります。 第5章 キャサリンはヘンリーとの再会を期待しているのですが、ヘンリーは姿を見せません。その一方で、イザベラとの親交を深めていきます。“友情のあらゆる段階をあっという間に通過し、友情のあらゆる証拠を短期間に全部示してしまい”という端折った書き方で、オースティンは、最初のヒロインや周囲の登場人物の紹介もそうでしたが、下手な小説のような紋切り型の常套的なフレーズをパロディのように使いまわしています。それは、パロディとして皮肉を表わすと同時に、物語の余計な描写を適当に端折り、物語の展開をスピーディーにしています。オースティの力量をもってすれば、もっとさりげなく巧みに書くこともできるのに、あえてこんなたどたどしいやり方をとって、読み手に意識させている。それは、ひとえにこの第4章の半分以上を占めている作者による小説論を導くためです。 物語としては、キャサリンとイザベルは二人で過ごす時間が長くなり、ついには二人で部屋にこもって小説を一緒に読むようになります。そこで、唐突に以下のような作者の長大な小説論が挿入されているのです。 われがヒロインは作品の中で小説を読んだのである。なぜならば私は、小説家たちのあのけちくさい愚かな慣習に従うつもりはないからだ。小説家は、自分も書いてその数を増やしている小説というものを、自分で軽蔑して非難して、その価値をおとしめたり、自分の敵と一緒になって、小説に情け容赦ない悪罵を浴びせ、自分の小説のヒロインが作品の中で小説を読むのを許さず、ヒロインが偶然小説を手にしても、つまらないページをつまらなそうにめくる姿ばかりが描かれる。ああ!小説のヒロインが、別の小説のヒロインから贔屓にされなければ、いったい誰が彼女を守ったり、尊敬したりするだろうか?私はあのような愚かな慣習に従うつもりはまったくない!想像力の営みを罵倒し、新刊小説が出るたびに、最近の新聞雑誌を埋め尽くす陳腐な言葉であれこれ論評するのは、批評家の先生方にお任せしよう。私たち小説家は、虐げられた者たちなのだから、お互いに仲間を見捨てないようにしようではないか。小説家が生み出した作品は、ほかのどんな文学形式よりも多くの真実と喜びを読者に提供してきたのに、小説ほどひどい悪口を言われたものはない。プライドや無知や流行のおかげで、小説の敵は、小説の読者の数と同じくらい存在するのである。長大な英国史の9百分の1の縮約版をつくった人。ミルトンとポープとマシュー・プライアーの詩の十数行の抜粋と、『スペクテイター紙』のエッセイの一編と、スターンの小説の一章を集めて一冊の本にした人。こういう人たちの才能は、千人のペンによって称賛されるのに、どうやら世の人々は、小説家の才能をけなしてその努力を過小評価し、才知と機知と趣味のよさにあふれた作品を無視したいらしい。私たちはこういう言葉をよく耳にする。「私は小説など読みません─小説はめったに開きません─私がしょっちゅう小説を読むなんて思わないでくださいね─小説にしてはよくできていますね」などなど。あるいはこういう会話をよく耳にする。「ミス・××、何を読んでいらっしゃるの?」と聞かれ、「あら!ただの小説よ!」と若い女性は答え、関心なさそうに、恥ずかしそうに本を閉じる。「なんだったかしら。『セシーリア』だか、『カミラ』だか、『ベリンダ』よ」 つまり小説とは、偉大な知性が示された作品であり、人間性に関する完璧な知識と、さまざまな人間性に関する適切な描写と、はつらつとした機知とユーモアが、選び抜かれた言葉によって世に伝えられた作品なのである。ところで、もとその若い女性が、小説ではなく『スペクテイター紙』を読んでいたら、誇らしげに本を差し出して題名を言ったことだろう。ただし、趣味の良い若い女性がほんとにその分厚い本を読んだら、その内容にも文章にも嫌悪感を抱くことだろう。現実にあり得ない出来事や、ひどく不自然な人物や、現代人には関心のない話題が多いし、それに、下品な言葉がたくさん使われているので、そんな下品な言葉を許容した時代にたいしても不快感を抱くことだろう。(P.45〜47) ここでは、当時の文学界を構成するさまざまな要素に対して、批判が浴びせられています。まず、自分自身が行っている小説を書くという行為を「軽蔑して非難し、貶めて」、「敵といっしょになって、小説に罵声を浴びせかけている」小説家自身。「小説における想像力の発露を、言いたい放題にののしり、新しい小説が出るたびに、最近の雑誌を埋め尽くす陳腐な駄文で論評する」批評家たち。歴史書の簡略版や古典を抜粋した書物などを過大評価するジャーナリズムの風潮。小説を読むことを恥じ、自分が低級な読者ではないように装う読者たち。とりわけ、アディソンとスティールによる文学論が掲載された『スペクテイター』紙については、さも高級な読み物であるかのようにもてはやされていましたが、それは「趣味のよい若い読者なら、内容も書き方もうんざりする」ようなもので、「ありえない状況、不自然な人物、誰も関心をもたないような話題から成り立っていて」、使用される言葉も、耐えがたいほど「下品」であると、このあと酷評が続きます。 つまり、ここでオースティンは、価値ある小説を不当に貶めるすべてのものに対して、ここで厳しい告発を行っています。彼女が「価値ある小説」として称賛しているのは、若い女性読者が、自分が読んでいるのは「ただの『セシリア』や『カミラ』、『べリンダ』にすぎない」と謙遜するような作品、「つまり、知性の偉大な力が示され、人間性に関する完璧な知識や、さまざまな人間性の楽しい描写、機知とユーモアの生き生きとした発露が、選び抜かれた言葉で世に伝えられた作品にすぎない」と、語り手であるオースティンは皮肉るように言います。ここでは、小説がいかに優れた文学ジャンルであるかという、作家としての信念が掲げられるとともに、それを解さないあらゆるものに対する諷刺が行われている。実は、オースティンが優れた小説の実例として挙げた『セシリア』や『カミラ』の作者フランシス・バーニー、あるいは『べリンダ』の作者マライア・エッジワースさえ、たんなる称賛の対象ではなく、実は諷刺を免れていません。バーニーは、『エヴリーナ』の序文において、作家のなかでも小説家は「数は多いが、尊敬に値しない」ことを認め、『カミラ』の出版時には、自らの作品を「小説」と呼ばねばならないことを遺憾としているのです。また、エッジワースも、『べリンダ』の宣伝文で、「この作品は教訓話として世に示されたものであり、作者は小説であるとは認めたくない」と述べています。したがって、彼女たちは、優れた小説を書きながらも、同時代の小説蔑視の風潮におもねって、自らの作品が「小説」であると取られることを避けたがっていたのです。したがって、オースティンがここで揶揄している作家
― 小説を書くという自らの行為を貶め、敵といっしょになって小説を罵倒し、傷ついた仲間を見捨てている小説家
―のなかに、優れた同時代の女性作家たちも含まれていることになってしまうのです。 ですから、この長大な小説擁護論はかなり毒のきいた皮肉がたっぷりと籠められているのですが、むしろ八方塞の出口なしのような状況にあるわけで、オースティンはその冷厳な事実を分かっているので、このような皮肉な書き方しかできないと思います。皮肉というより、むしろ、やけっぱちと言った方が当を得ていると思います。そういう小説の現状に対する認識をもっているなかで、その小説を擁護し、そのためにいままで貶められてきた小説とは違うものを書こうとしているのが、まさにこの作品であり、既存の小説と同じようなものであれば、同じように貶められてしまうので、そうでないもの、という〜でないという発想を持たざるを得なくなって、否定を積み上げてしまう結果を招いている。それが、ここでのオースティンの小説擁護論です。この時点では、この新しい小説も、未だ、こういうものだと示すところまで至っていません。オースティンとしては、この作品こそ価値ある小説となるもののはずだからです。 そこが、オースティンの他の作品にない、小説とはどういうものかという自己回帰的なところが、この作品の独特なものなのです。 第6章 前章に続いて、キャサリンとイザベラの二人が登場します。しかし、前の第5章では、作者による紋切り型のような紹介で、イザベラはこういうタイプの女性ということと、二人が仲良くなっていくプロセスで、小説のプロットの説明のようなものでした。これに対して、この第6章では、会話を中心に二人の女性が生き生きとして存在しはじめて、具体的な行動でキャサリンとイザベラの対照的な性格が明らかになってきます。読者には、前章の作者による説明よりも、ここにきて小説の場面での動きの中で表われる二人の女性の方が印象的にイメージできるのです。 イザベラは誰もが目を瞠るような派手なタイプの美人で、ファッショナブルな服装とスタイルにキャサリンはたちまち魅了されます。しかも、美辞麗句のような言葉を度々口にします。“私は親友のためなら何でもするわ。”“中途半端に人を愛することができないの。それが私の性分なの。”“私の愛情は過剰なほど強烈なの。”といった具合です。そんなイザベラは、実は自ら感傷小説のヒロインを演じていると言えます。暖かくて、寛大な、溢れ出る愛情を持ち、友情に忠実で、お金に興味がないというヒロイン役です。『ノーサンガー・アビー』についてはキャサリンは、しばしば小説のヒロインになりきってしまって、虚構と現実を混同してしまうことが言われますが、実は、イザベルもキャサリンとは違った意味で小説のヒロインになりきっているのです。感傷小説のヒロインの最後には金持ちの男性や貴公子と結ばれるハッピーエンドに行き着くわけです。イザベラはキャサリンと話している最中でさえも抜かることなく周りに気を配り、少しでも自分の気を引くような男性がいないか注意を払っている様子をオースティンは、生き生きと描いています。例えば、ポンプ・ルームでイザベラは、自分のほうを見ている二人の嫌な若い男たちを避けたがっている素振りを示しつつ、彼らが立ち去ったと知ると、一方はとてもハンサムな青年だったと矛盾した発言をして男性への興味を漏らし、彼らを追いかけて行こうとする。相手の本心が見抜けないキャサリンは、男たちに追いつかないようにと気遣うのですが、イザベラは同じ方向にある帽子屋に立ち寄りたいという口実と、男性をつけあがらせないという方針を主張して譲りません。“キャサリンはこんな道理には反論できなかった。それで、ソープ嬢の独立心と男に負けないという意地を示すために、彼女たちは直ちに出発して、二人の青年のあとを早足で追いかけた”という最後の一節では、上品さを装いつつ、誰彼となく異性に関心をもって油断なく目をつけ、追いかけようとするイザベラの姿を活写しています。対照的に、彼女に騙され言いくるめられているキャサリンの鈍感さ、あるいは純真さが際立たされるのです。この作品は小説の世界に魅了された夢見る少女が現実に目覚めていく話というひとつの大きな流れがありますが、それはキャサリンという一筋だけではなく、イザベルのように別の流れもあるのです。作者のオースティンは、それを一見しても分からないように巧妙に隠すようにしていますが、それが、小説の流れを豊かなものにしているのです。これは、こじ付けかもしれませんが、ミハイル・バフチンがドストエフスキーの小説を分析してポリフォニー構造ということをいいましたが、オースティンにその先駆を見てもいいのではないかと思うのです。 ただし、イザベラの行動には現実的な理由があるのです。イザベラの母ソープ夫人は未亡人で、金持ちではなく、その上、イザベラを含む娘三人とジョンを含む息子三人という合計六人の子どもがいます。ソープ夫人は明るく善人でありますが、子どもに甘いひとです。また、当時は一般的に母親は娘の結婚相手探しに奔走するものですが、そうすることもなく、物語にはほとんど登場しません。したがって、イザベラは自分の将来を考え、よりよい結婚相手を獲得するためその美貌を最大限に利用し、自らの計画を実行する必要があったのです。しかも、小説の影響で自身を小説のヒロインに同化して幸せな結婚をするというゴールを強く意識するようになっていた。だから、この作品におけるイザベラの役回りは悪女役を割り当てられたていますが。ゴシック小説の登場人物とはひと味もふた味も違うと言えます。オースティンはイザベラを普通の一人の女性として描いていると言えます。読者はイザベラの内心をちゃんと想像できる、ということは、共感することも可能なのです。それまでの男性作家による、物語のお飾りのような善玉の美しいだけヒロインとか、憎まれ役の悪の化身といった薄っぺらな女性ではない。そこに女性でもあるオースティンという作家のもっていた新しさが、こういうところに表われていると思います。オースティンは、女性を内側から知り抜いた女性作家の目で、普通の女性を諷刺の対象として、結婚市場における女性の策略や俗物根性を暴き出していきますが、イザベラは、打算的嫌らしさという点で『分別と多感』のルーシー・スティールや『高慢と偏見』のビングリー嬢、またコケティッシュな誘惑者として『マンスフィールド・パーク』のメアリ・クロフォード等の先駆けとなる人物と言っていいのではないでしょうか。ちょっとイザベラ・ソープを持ち上げすぎたかもしれませんが。 それは、前章で作者が展開した小説論について、この第6章で登場人物から異論が提示され、この小説が作者の小説擁護論を単純に提示するだけのものではないのです。まずは、二人の会話の中で、キャサリンはイザベラからラドクリフ夫人の『ユードルフォの謎』を薦められます。それが、キャサリンがゴシック小説にのめり込んでいくきっかけになるのです。つまり、後半のキャサリンの行動の基点となっているのが、ここで『ユードルフォの謎』を薦められ、読み始めて、惹きこまれて行くのです。それが、ここでさり気なく書かれています。ここでは、同時に小説について、二人の会話が挿入されています。イザベラは、ゴシック小説を沢山読んでいて、ゴシック小説の典型である『ユードルフォの謎』を読んだことがないキャサリンをとても奇妙に思うと、見下すように会話は始まります。イザベラは、その原因をキャサリンの母が小説に反感を持っているからと推測するのですが、ここでキャサリンは『サー・チャールズ・グランディソン』を持ち出すと、即座にそれを退屈な小説だとイザベラはこの作品を全く受け入れる気はないことを示しています。実は、『サー・チャールズ・グランディソン』は人間関係を中心とした市井の人の営みを主題とし、細部性具象性実証性を具えた話的性格が色濃い作品で、その作者であるサミュエル・リチャードソンというイギリス小説の父と言われ、オースティンが大きな影響を受けたと言われています。つまり、前章で、作者の言葉として“つまり小説とは、偉大な知性が示された作品であり、人間性に関する完璧な知識と、さまざまな人間性に関する適切な描写と、はつらつとした機知とユーモアが、選び抜かれた言葉によって世に伝えられた作品なのである。”とのべていた、ひとつの実例が『サー・チャールズ・グランディソン』と言えるのです。それを、こともあろうに、すぐ後で、登場人物に退屈といって否定されているのです。この『ノーサンガー・アビー』では、作者が作品中で小説についてしばしば言及し、メタ小説の要素がありますが、それは必ずしも作者の小説に対する考え方をモノローグのように開陳して読者に聞かせるというのではなくて、小説については様々な立場があり、それに従って意見も多様です。そういう異なる意見をここでは作者の考えとは相容れないところもあるかもしれませんが、ダイアローグのように登場人物たちに議論をさせています。このあとでも、ティルニー兄妹とのキャサリンとの会話で歴史と小説を比べながら議論するところが出てきます。これらによって、小説とはどういうものかという議論が分厚くなり、メタ小説としての豊かなひろがりが、登場人物たちの行動の様々な方向性とリンクするように(例えば、キャサリンとイザベラ、エリイとの生き方の違いと小説観の違いが、リンクするように対照されています。)読み取ることができます。従って、メタ小説といっても観念を弄ぶようなものではないのです。 なお、『サー・チャールズ・グランディソン』に関しては、キャサリンの母が呼んでいた小説として紹介されていて、キャサリンの両親は、平凡ではあるけれど、正直で、実直な人柄で、田舎での日常生活の現実には対処できる充分な道徳観念を持った人々で、そういう人が読んでいた小説として紹介されているわけです。つまり、軽薄で打算的なイザベラには拒まれるが、キャサリンを育んだ分別のある常識人には受け容れられる小説というわけなのです。その『サー・チャールズ・グランディソン』の良さが分かるキャサリンも、母親の資質を受け継いでいることが分かるのです。 第7章 キャサリンは、兄であるジェイムズと再会し、同時に、兄の友人でありイザベラの兄であるジョン・ソープと出会います。それは道路をあるいていたキャサリンとイザベルの二人とトラブルを起こした馬車に乗っていたのが彼らだったという、出会いです。ジョンソープはでっぷり太った中背で、自分が美男子だと思い込んでいるような自分を知らない人で、後で明らかになりますが、自分勝手で他人のことを思い遣るということのない人です。会話の話題は馬車など自分の持ち物の自慢話か金銭に関することのみです。例えば、キャサリンとソープとの会話で、ソープが馬車の話題が途切れると話すことがなくなったので、黙りがちになったので、キャサリンが話題をかえて小説の話をしようとすると、次のような会話となります。 「あのソープさん、『ユードルフォの謎』をお読みになったことはありますか?」 「『ユードルフォの謎』?とんでもない!読んでいません。ぼくは小説なんて読みませんよ。ほかにすることがありますからね」 キャサリンは恥ずかしくなって小さくなり、そんな質問をしたことを謝ろうとしたが、ジョンがさえぎってこう言った。 「小説って、馬鹿なことばかり書いてありますね。『トム・ジョーンズ』のあとは、ろくな小説はありませんね。まあ、『修道士』くらいですね。『修道士』はこのあいだ読みました。でもほかは、どれもこれも馬鹿な小説ばかりです」(P.63〜64) ここで、小説に関する別の意見が出てきました。このようにこの小説では、物語中の至る所に、このように意見が分散してあらわれます。第4章で作者がまとまった小説論を開陳しましたが、あれは例外的なことで、小説の中の登場実物たちが、それぞれが置かれた環境の中で、その人物のあり方にかさなるように、それぞれの小説に対する考え方が、とくに会話の中で明らかにされます。この作品は、前の章においてポリフォニー的の先駆ではないかということを述べましたが、むしろオースティンは点描のように、作品中でポツリポツリと登場人物たちに、それぞれの立場、場面で、例えば小説について語らせているのです。それが登場人物たちで議論をたたかわせて、それが物語を進めていくということにはなりません。ドストエフスキーの長篇小説では、その議論が物語の骨格になっていたりして、例えば『罪と罰』ではラスコーリニコフの思想に対して他の人物達との論争のような議論が物語のひとつの中心になっていますが、この作品では、そういうことにはなりません。むしろ、ドストエフスキーの小説が、議論の部分が大きくなって多少観念的で(議論のための議論になってしまいそうで)、登場人物たちの生身の動きが地に足がついていない理想化しすぎているように見えるところがあります。オースティンは、そうなってしまうのを避けたのではないかと思えるところがあります。それが、議論をたたかわすことを前面にするのではなくて、それぞれの場面でそれぞれの人物たちに、それぞれ語らせて、あとは読者に任せるというのか、この小説でとられているやり方ではないかと思います。この場合も、イザベラ・ソープという、軽薄で享楽的なところのある俗物的な人物の発現ですが、当時の社会で現実的な男性が一般的に抱いていたであろう小説に対する意見はこんなところではないか、と納得できてしまうのです。端的に言うと、差別的な言い方ですが女子供の娯楽という考え方で、そういう風潮に媚びるようにして作家は作品を制作していかなければならなかった。おそらく、この時代に量産された読み物としての小説の大半はこのジョン・ソープのような外野の意見と、イザベラ・ソープのような読み手に消費されることを想定して制作されたと言えるのではないか。オースティンは、ジョン・ソープの意見に対して、風刺的な扱いをしていますが。決して否定はしていません。それは、そういう一般的な風潮があって、オースティンもそれを一旦受け容れざるを得なかったからではないでしょうか。 ジョン・ソープという人物は、この後でキャサリンを振り回し、騒動に巻き込んでしまうような人物で、悪役に位置付けられる役回りですが、たんなる狂言回しとしてだけでなく、一人の人間として一般性のあるように書かれていることが、この小説に対する意見のところなどに表われている。それが、この小説の特徴なのです。ジョン・ソープは友達にしたくない、なるべくなら遠ざけたいような人物ですが、こういう人いますよね、たしかに。 なお、この会話の中で、キャサリンはジョン・ソープに対して不愉快な印象を持ちつつも兄の友人で、親友イザベラの兄だからと、ダンスの申込みを受けて断りなかったことが、あとになって辛い思いをすることになるのですが。 第8章 この第8章の冒頭で『ユードルフォの謎』を読み耽るキャサリンの様子から始まります。 キャサリンは『ユードルフォの謎』を読みふけり、仕立て屋の到着も多少遅れたけれど、アレン夫妻とキャサリンは、約束の時間どおりアパー・ルームに到着した。(P.70) ほんの短い一説ですが、実は、この直前、第7章の終わりはキャサリンが帰宅して『ユードルフォの謎』を読み耽るところなのです。第7章から第8章は、章をまたぎますが、キャサリンが読書に耽っているので続いています。読者は、キャサリンが『ユードルフォの謎』に熱中しているのが、一度にいわれるのではなくて、このような短い描写が、この前にも何度も出てきます。それがボディーブローのように徐々にきいてくる。そういう小出しにして、最初に出会うときには、読者はそれほど気に留めることはないのに、それが手を変え品を変えで繰り返すように、例えば、キャサリンはイザベルとの会話で『ユードルフォの謎』を読んでいることを話題にしたり、ジョン・ソープとの会話でも持ち出します。散発的にでてくると、無視できなくなり、徐々に印象が強くなってくる。まるで、キャサリンは四六時中『ユードルフォの謎』に夢中になっているように見えてくるのです。そういう点描的な手法とでもいい手法を、オースティンは、この作品で、いろいろと使っています。小説の議論なんかもそうですが、ここでは、確認のために、キャサリンが『ユードルフォの謎』を読み耽るのに関係した文章を引っ張ってきましょう。 ソープ家とアレン家の一行が社交会館のオクタゴン・ルームで落ち合う時間も決まったので、キャサリンは『ユードルフォの謎』を読みはじめ、ワクワク、ハラハラ、ドキドキのすばらしい想像力の世界に浸った。舞踏会のための着替えのことも、食事のことも、俗事はいっさい忘れ、仕立て屋の到着の遅れを心配するアレン夫人をなだめることもせず、今夜の舞踏会のダンスの相手がすでに決まっているわが身の幸せさえ、一時間の間にたった一分思い出しただけだった。(第7章 P.69) 「今日はいままでひとりでなにをしていたの?『ユードルフォの謎』を読んでいたの?」 「ええ、今朝起きてからずっと読んでいたの。いまちょうど黒いヴェールのところよ」 「ほんとに?まあ、すてき!でも、黒いヴェールのうしろに何があるか、ぜったい教えてあげないわ!ものすごく知りたいでしょ?」 「ええ、すごく知りたいわ。いったい何かしら?でも言わないで。言ってもぜったい聞かないわ。たぶん骸骨ね。きっとローレンティーナの骸骨だわ。『ユードルフォの謎』はほんとに面白いわね。一生読んでいたいくらい。あなたに会う約束がなかったら、ぜったいに途中でやめたりしなかったわ」(第6章 P.49) 今日の計画が決まったので、キャサリンは朝食を終えると、静かに座って本を読み始めた。時計が1時を打つまでは、ここを動かず本を読み続けるのだ。(第9章 P.84) こんな具合ですが、これらが、後半でキャサリンがノーサンガー・アビーに招待されることへの興味の伏線となっているのです。 さて、物語は舞踏会の場面に移ります。楽しみにしていたダンスも、昨日、ダンスを申し込まれたジョン・ソープはキャサリンを置き去りにしてどこかへ行ってしまいます。兄のジェイムズとイザベルはダンスを楽しんでいます。その間キャサリンは、ダンス相手のいない女性と周囲の人びとに思われてしまった上に、せっかく申し込まれたヘンリーからのダンスを断らざるをえず、悔しい思いをするのです。これは、後日、ジョン・ソープがキャサリンをドライブに強引に連れ出して、ティルニー兄妹との散歩の約束を自分の都合を優先させるために破らせてしまうことの前触れとなっています。それは、ジョン・ソープという人物の自分勝手で、不誠実な性格の現われなのですが、まだ、このダンスの申込みの段階では、それほど悪質なものとして目立つものではないのです。それが、あとになって、徐々に質の悪さが露わになってくると、そう言えばと想起される伏線となってきます。それは、不誠実さだけでなく、第7章で出会ったときのキャサリンとの会話で、馬車と馬の話題を自分勝手にひとしきり話した後で話題がなくなり、キャサリンの話をきくでもなく、通り過ぎる女性の品定めをするという行為が、ここで繰り返されます。つまり、キャサリンを放ったらかしにして屈辱的な思いさせたことにも気付かず、彼女を待たせたあと、無神経にそれまで会っていた友人の馬や犬の話や、その友人と犬を交換するなどの話を、キャサリンが興味を持つかなど、お構いなしにこまごまと始める。キャサリンが視線をヘンリーのいた場所に向けるのに気づかないのです。 一方、そのような理不尽な扱いをされた側のキャサリンは、相手がどうあろうと約束を破ることはできない。そういう常識を両親からしつけられていて、無意識のうちにも秩序ある社会においては慣例的な礼儀を果たさなければならないということを認識しているのです。それが、このときの彼女の振る舞いに表われています。そういうキャサリンですが、ジョン・ソープの不誠実に不快感を持ち始める。それが、後に決定的な場面でソープを拒絶することになる、伏線となっています。 一方、キャサリンはヘンリー・ティルニーとの再会を果たし、彼の妹であるエレノアと出会います。イザベラとはまったく違った女性ですが、キャサリンはヘンリーの妹ということだけでなく好感を持ちます。 ミス・ティルニーはスタイルがよくて、美しい顔立ちで、とても感じのいい表情をしていた。イザベラ・ソープのような際立った派手さはないし、流行の最先端という感じもないが、ほんものの優雅さが感じられた。その態度には、良識と育ちの良さが現われ、すこしも内気な感じはしないが、必要以上にあけっぴろげなところもなかった。とても、魅力的なお嬢さまだと誰もが思うだろうか、本人は、舞踏会で男性の注目を集めようとは思っていないし、ちょっとしたことで有頂天になって狂喜したり、信じがたいほど怒り狂ったりすることもなさそうだった。(P.76) ここでエレノアはイザベラと比較しながら紹介されています。この二人は対照的で、敢えて言えば、ゴシック小説の悪女がイザベラでヒロインがエレノアに当たるような書き方で、ここにゴシック小説のパロディと見られている要素が表われているかもしれません。では、キャサリンはどうなのでしょうか。おそらく、キャサリンは読者であってゴシック小説の外にいるのです。つまり、キャサリンとエレノアの関係は、小説をワクワクしながら読んでいて、ヒロインに感情移入している読者と、小説のヒロインの関係になぞらえることができるのではないでしょうか。だから、エレノアがヘンリーの妹であることとは別に、キャサリンがエレノアをひと目で気に入ってしまうのは、そういう構造にこの小説が作られているからだと言えます。キャサリンという人物は受け身で、自分から行動を起こすということは少ない人物です。ヘンリーと出会っても、ひたすら待つだけなのに、エレノアに対しては、自分から彼女を探し、エレノアのもとに自ら赴いて、交際を申し込むという積極的な行動をとります。一方、エレノアは小説のヒロインで読者に読まれるだけですから、キャサリンに対して受け身の姿勢なのです。 ヘンリーとの再会を果たし、妹のエレノアとも出会ったこの夜の舞踏会は、しかしキャサリンにとっては、あまり楽しくはないものでした。それはジョン・ソープの自分勝手な振る舞いに振り回されたためでした。 ところで、この章について述べた最初のところで、キャサリンが『ユードルフォの謎』を読み耽るという記述が短いのですが、何回も繰り返し出てくるということを指摘しました。この小説の中で、とくにバースでの場面に顕著なのですが、(実は、後半でキャサリンがノーサンガー・アビーに招待され時の描写にも、繰り返しのパターンがあるのですが)、繰り繰り返しが多いのです。というよりも、バースでのシーンは基本的にはすべて繰り返しで構成されているのです。舞踏会を例にあげれば、バースについてすぐ、不慣れな状態でアレン夫妻に連れられたキャサリンは舞踏会デビューを果たします。その時は、知り合いもなく、会場の混雑に圧倒されて、身の置き場も分からず困惑するばかり。踊ることも、会話もできず、疲れてだけという経験。次が、儀典長にダンスの相手を紹介されてヘンリー・ティルニーと出会うことになる。そして、第3回目が、この章での舞踏会で、この後にも舞踏会の場面が出てきます。このように舞踏会の場面は繰り返すように現われて、その繰り返しのたびに、キャサリンは前回と同じではなく、舞踏会のたびに変わってきます。それは社交界に慣れてきたというのもありますが、彼女の成長が前回と比べると同じではないということで、分かるのです。だいたい成長というのは、階段を上がるようなステップアップではなく、スロープを上がるように緩慢で滑らかな変化を続けるようなもので、ずって見ていると成長したことが分かり難くなります。ところが、この舞踏会のように場面で区切って前回と比較すると、前回との間の時間は断絶しているため、ギャップがあり、変化していることが見えてくるのです。しかし、それはキャサリンという人物だけに注目してのことで、それだけでなく、舞踏会の繰り返しのたびに舞踏会に登場する人間関係が変わってきます。最初の時は、アレン夫妻に連れられてとはいえ、キャサリン独りという状況でした。舞踏会という皆が楽しんでいる場所でキャサリンは独りの部外者のように取り残されていた。それが二回目の時にはヘンリーというパートナーが現われて、キャサリンは漸く舞踏会にコミットすることができた。さらに、ヘンリーとの関係が始まるわけです。そして、この章での舞踏会では、キャサリンはすでに常連のメンバーのように振る舞い、ソープ家の人々や兄という仲間もできて次第に舞踏会での存在感が生まれてきます。また、ジョン・ソープのようなキャサリンに対して害をなすような人物との関係も生まれます。最初は独りぼっちだったキャサリンが、2回目では相手をできて、3回目には仲間という関係ができていく、その拡がりが他方では恋の相手と彼女に災厄をもたらす人物との関係もできていくという物語の展開も作っていく。これは、舞踏会だけでなく、ジョン・ソープの馬車に乗せられるということも最初にバースの街中での事故でのことから、兄やイザベルとともに遠乗り、その2回目ではティルニー兄妹との約束があったにもかかわらず合意うに連れて行かれるといったこと。あるいは、ポンプ・ルーム等でのイザベラとのおしゃべりの時間。あるいはティルニー兄妹との散歩。それらが、変化しながら繰り返される。まるで、複数の主題を変奏させながら交互にいり変わり立ち代り繰り返し、各主題の綾が絡んで、一つの大きなものがたりになっていくのです。まるでクラシック音楽の交響曲のソナタ形式のようです。これは、同じオースティン作品で『高慢と偏見』でも、舞踏会は何度かありますが、物語の中のエピソードとしてであり、『ノーサンガー・アビー』のように繰り返すことで変化が分かるようになるという構成にはなっていません。ししかも、そういう変化しながら繰り返すのがある一方で、『ユードルフォの謎』を読み耽るという同じ行為が短いながら、何度も現われます。その他にも、夜寝たとか、朝起きてアレン夫人の相手をしたとか、日常的な繰り返しが飽きずに挿入されます。まるで、頭の悪い小学生の夏休みの日記のようです。しかし、それは舞踏会のように変わっていく繰り返しがある反面、日常的なところは毎日同じ繰り返しがあること、それをわざわざくどいほど挿入しているのは、繰り返し同士の対照をつくって、変化を際立たせているのだろうと思います。また、ゴシック小説のような波乱万丈のロマンスでは、日常の細々としたことは、むしろ、そういうことを忘れさせて、非日常の世界に誘うので、そういうことは書かれることはないでしょう。ここでオースティンがほんの短い文章ですが難解も繰り返したのは、リアルな日常との接点を作ろうとしたのではないかとも思います。 第9章 昨夜の舞踏会では、みじめな気分なりましたが、一晩ぐっすりと眠ったキャサリンは、翌朝は爽快に目ざめます(これも繰り返しですね。お決まりの読書の記述の短く挿入されています。)。前向きな気持ちになり、エレノアとの親交を深めようと、あれこれ計画を考え始めます。昼にポンプ・ルームへ赴き、そこにエレノアも来ているであろうから、そこで、昨日の会話の続きをしようと考えます。 しかし、その計画に、思わぬ横槍が入ります。ジョン・ソープから馬車の遠乗りに誘われたのです。昨夜、そういう話をしたことになっていますが、キャサリンにははっきりとした記憶がありません。小説には明確に書かれていませんが、この後で明らかになってくる彼の行動パターンから、おそらく急に思い立って馬車に乗りたくなり、キャサリンの都合などお構いなしに誘いに来たのでしょう。昨夜、そういう話をしたというのは、それらしい口実ではないでしょうか。そのあたりは、強引さといい、この時点では、未だ、それほど目立っていません。しかし、結局、気乗りがしないままキャサリンが強引な誘いに押し切られるように馬車に乗せられると、馬車でのソープとの会話に、不愉快な思いを募らせていき、徐々にソープという男の招待が明らかになってきます。 「アレン老人はものすごい金持ちなんでしょうね?」 キャサリンは何のことかさっぱり分からなかった。ジョンはもう一度質問を繰り返し、「アレン老人ですよ。あなたと一緒にいる」と付け加えた。 「あら、アレン氏のことですか?ええ、お金持ちだと思います」とキャサリンは言った。 「それで、子どもは一人もいないんですか?」 「ええ、一人も」 「子供のつぎに権利がある相続人にはおいしい話だな。アレン氏はあなたの名親なんでしょ?」 「私の名親?いいえ、違います!」 「でも、あなたはいつもアレン夫妻と一緒にいるじゃないですか」 「ええ、いつも一緒にいますけど」 「やっぱりね。それが聞きたかったんです。」(P.88) ジョン・ソープは、どうやら子供のいない財産家のアレン氏の保護下にあるキャサリンを彼の相続人だと思っているらしいことが、この会話から分かってきます。しかし、キャサリンは単にアレン氏のことを話していると思っていて、彼の質問の隠された意味が理解できません。つまり、ジョン・ソープがなぜキャサリンに接近してきたか、その真意を理解できず、単に親友の妹だからという程度のことしか思えないのです。そのキャサリンの鈍感さについては、作者による紹介でストレートに指摘されてきましたが、それにつづく馬車についての会話で、ソープがジェイムズの二輪馬車はおんぼろで、「僕は5万ポンドくれるといっても,あんなものに乗って2マイルも行きませんよ」と言ったすぐ後で、おびえるキャサリンを見ると、「僕なら5ポンドで,あれに乗って,釘一本失くさずに,ヨークまで行って帰ってみせます」と宣言する。キャサリンはひとつのことに関して、まったく異なる二つの説明を聞いて驚くだけです。それについて、作者は改めて次のように述べています。 キャサリンはその生まれ育ちゆえに、おしゃべりな人間の癖を知らないし、過剰な虚栄心を持った人間がくだらない主張をしたり、恥知らずな嘘をついたりするということを知らなかった。キャサリンの両親は、ごく平凡な現実的な人たちで、機知を楽しむ習慣はなく、父親はときどき駄洒落を言う程度だし、母親はときどきことわざを口にする程度だった。だから彼女の両親は、自分を偉く見せるために嘘をついたり、いまこう言ったのにつぎの瞬間に正反対のことを言ったりすることはいっさいなかった。(P.92) このようにキャサリンの鈍感さを、正直さとして、ある意味で彼女が純真であるというニュアンスを作り出しています。従来のヒロインの類型に当てはまらない、普通の少女として設定しているというようですが。実は、この純真さのニュアンスと示すということで、作者オースティンは巧みに理想化をしていると思います。このところで、最初に、ソープはアレン氏が金持ちであることを確認し、キャサリンはその財産を相続するという思いを強くします。その裏には、いわゆる逆玉ねらいの意図が透けて見えますが、キャサリンはそれに気がつきません。また、この小説の読者にも、この時点でははっきりさせていません。作者は、その後ですくに馬車の話題に会話を流してしまいます。そして、上記のようなキャサリンの鈍感さを指摘するコメントを入れるのです。ここで、読者はキャサリンの率直さは印象に残ると思いますが、ソープの陰謀(?)は仄めかされますが、すぐに引っ込められて、伏線のようになっています。このあとでソープがキャサリンを探るように、似たような質問をする場面ができますが、それも繰り返しのテーマです。しかも、多くの場合、そういう繰り返しのテーマが最初に表われたとき、この場合のようにさり気なくして、読者には、それと分からないように努力している。それが後になって、繰り返されるのを読者が気付くと、そういえば・・・と思い起こそうとする、そいういうものとなっています。 その遠乗りから戻ってくると、思いの外時間がかかってしまって、夕方近くなっていました。そのため、昨夜から経過していたポンプ・ルームに出かけるには、もう遅すぎる時刻となってしまいました。しかも、アレン夫人はキャサリンがジョン・ソープたちに誘われて遠乗りに出かけていた間に、ポンプ・ルームに出かけてエレノアと会っていたことを夫人から聞きます。キャサリンは、エレノアと出会って、すぐに気に入って、親しくなりたいと望みますが、なかなか会うこともできません。このパターンはヘンリー・ティルニーと似たようなパターンです。つまり、このはじめの方の物語の一つの推進力として、キャサリンがヘンリーに会いたいと、あれこれ考えたり、いろいろなところに出かけたりしても、なかなか会えない。その縮小版がエレノアとの関係といえそうです。これに対して、イザベルとジョンのソープ兄妹とは常に一緒であり、キャサリンが求めて会いに行くというより、ジョンがキャサリンに会いに来るのをキャサリンが避けるという、ティルニー兄妹とのパターンと対照的なパターンで、それぞれのパターンが対照されるようにキャサリンをめぐって繰り返されます。 第10章 その晩、キャサリンはイザベルたちと会います。ここでは、イザベルと兄のジェイムズが仲睦まじい様子が描写されていて、それ横目に、キャサリンは、明日こそは、エレノアと会おうと決意を新たにして翌日、キャサリンは意を決して、勇躍ポンプルームに向かいます。そこでまた、イザベラと会いますが、彼女と兄の様子を見ているうちに、二人の会話に入って行けない雰囲気を感じます。 キャサリンはいつものように、すぐにイザベラと一緒になった。最近いつもイザベラに付き添っているジェイムズも一緒になり、三人はほかの連中から離れて、しばらく三人で部屋を歩き回っていたが、やがてキャサリンは疑問を抱きはじめた。こうして三人だけでいて、しかも、ふたりから除け者同然の扱いをされている自分の状況は、はたして幸せなのだろうか?イザベラとジェイムズは、感傷的な議論や活発な口論に夢中だが、感傷的な議論はささやき声で行われ、活発な口論は大きな笑い声が混じるので、キャサリンはその内容をひと言も聞き取れなかった。だから、たびたびふたりから賛同を求められても、意見の言いようがなかった。(P.102) これは微妙ですね。キャサリンもイザベルも、いつもと変わらないつもりでいるのに、それまでとは、どこか違ってしまっている。それをイザベルは気付いていないが、キャサリンは微妙に感じ取っている。しかし、明確にそうだとは言えない。その微妙な変化は、それまで、キャサリンとイザベルの様子を繰り返し表わしてきたからこそ、ここで生じている小さな変化を書くこともできたし、キャサリンが何となく感じたということを書くことも可能になったといえます。もしこれが、二人の場面がものがたりのエピソードとして、何かの事件の場面のときだけ書かれるというのでれば、この変化はひとつの事件ということになって、こんな微妙なニュアンスではなくて、もっと決定的な場面ということになってしまったでしょう。波乱万丈のゴシック小説はそういう事件の連続で物語ができています。これに対して、オースティンは、日常的なもの、ゴシック小説に比べれば事件らしい事件も起こらないところで小説を書いているわけです。そこでは、こういう微妙な変化ともいえないような変化を捉えて、そこで心が移ろっていく、それが行動となって、物語に推進力を生む、ということを試みているわけです。実際、この後キャサリンは、意を決して、エレノアを探し、キャサリン自身からエレノアに話しかけるという積極的な行動を起こすことになるのです。 しかも、この引用した文章は、作者による説明ですが、これが客観的な外形描写なのか、キャサリンの内心なのか、明確に区分できないような微妙な文章です。最初の“キャサリンはいつものように、すぐにイザベラと一緒になった。”は明らかに客観的な描写です。これに続く文章の前半、“最近いつもイザベラに付き添っているジェイムズも一緒になり、三人はほかの連中から離れて、しばらく三人で部屋を歩き回っていたが、”までも同じです。そして、この後の部分、“やがてキャサリンは疑問を抱きはじめた。”はキャサリンの心理状態の描写に変わります。次の“こうして三人だけでいて、しかも、ふたりから除け者同然の扱いをされている自分の状況は、はたして幸せなのだろうか?”はキャサリンの内心の声、モノローグです。次の文章の前半、“イザベラとジェイムズは、感傷的な議論や活発な口論に夢中だが、感傷的な議論はささやき声で行われ、活発な口論は大きな笑い声が混じるので、”は客観的な描写なのか、キャサリンが感じたことなのか、どちらとも受け取れる文章なのです。この文章の受け取り方が違うと、これに続く“キャサリンはその内容をひと言も聞き取れなかった。だから、たびたびふたりから賛同を求められても、意見の言いようがなかった。”はキャサリンの心の状態なのか、客観的な状況なのかかわってくるのです。おそらく、オースティンは、その両方に取れるように意図していたのではないかと思います。翻訳なので確かなことは言えませんが。しかし、この状況変化が、キャサリンをエレノアとの交際に促すことにつながっているのです。だから、この文章は作者が鳥瞰的な立場で客観的に語っているのではない。この文章はキャサリンを動かしています。この文章は客観的な状態でもあり、キャサリンの内心でもあります。この『ノーサンガー・アビー』で、オースティンは、このような語りをいたるところで行っています。その理由のひとつとして考えられるのは、この小説の本質的なところに関連しているところではないかと思います。 それは、こういうことです。この小説は、この物語の中でキャサリンが読み耽っている『ユードルフォの謎』等のゴシック小説のような荒唐無稽の設定で波乱万丈の物語手に汗を握るという物語ではありません。むしろ、その正反対の、平凡な主人公が普通の人々の中で日常的な毎日を繰り返していることを題材にした物語です。読者は、波乱万丈で先の見えない物語の展開にワクワクするのでもなく、ヒーローやヒロインの活躍やピンチの胸を躍らせるわけでもありません。この物語の主人公であるキャサリンは、行動的であるわけでもなく、受け身の行動パターンでもあるので、彼女がアクションを起こすということも期待できません。しかし、実は、人というものは、何か行動をする時、あるいは、何も行動していないように見えても、実は、その時に考えたり、何かを思ったりしている。もっと後の時代の言葉でいえば、内面をというものをもっていて、それは絶えず動いている。そこにこの小説は足を踏み入れようとしている。それは、内心ということが発見された現代からの視点で見ているので、そう見えるのかもしれません。そうは、後年の心理小説を経験しているからでしょうか。しかし、そういう小説、例えばドストエフスキーの小説の人物たちは、反省的で、絶えず、ウジウジするほど、色々と考えていて、その反省しているのは内心の声として、人物のモノローグのように語られています。それに比べると、この小説のキャサリンはドストエフスキーの人物たちのように反省的ではないし、そもそも内心なんてものを持っていません。そんな屈折もしていないし、そんなめんどくさいことをやっていられません。例えば、ジョン・ソープに強引に遠乗りに連れて行かれて、遠乗りが楽しくなくて、不愉快な思いをしても、楽しみにしていたエレノアとの再開が果たせず、アレン夫人は会えたということも、そういうことは後を引きずるように気にしないで、気を取り直して眠りにつく、そういうキャサリンの姿は、何度も出てきます。それが、こういう日常的なところで小出しするように書かれています。これは、ひとつには、おそらく、キャサリンや両親というのは、ひとつの理想化された素朴で実直な庶民、堕落した有閑階級に対して、しかもキャサリンは未だ子供で、そこに無垢な存在として、それが周囲の汚れた大人たちに囲まれて変容していく、アダムとイブが楽園を追放される旧約聖書以来の神話的な物語のパターンとしてオースティンは意識してはいないかもしれませんが、ベースにあるように思えるのです。聖書の楽園を追放される前のアダムとイブには内心なんてありません。知恵の実を食べてはじめて羞恥を覚えたのですから。それになぞられているようなキャサリンに、内心のモノローグなんて無理です。とはいえ、ゴシック小説のヒーローやヒロインのように心は空っぽで類型的なパターンで行動するハリボテではありません。普通の人間として思い、感じている、そういう人物です。そういう人物が小説の中にいて、自分で感じ、考え、行動する。いわば、読者が共感するようなパターンの部分的には生まれてきているのではないか。そういうところに、この小説の本質的な魅力がある。そのキャサリンが思い、感じることを、キャサリンは、自身で語ることのできるような存在ではない。むしろ、キャサリンの内心は語ることができるほど自立も自律もしていない。そこで、オースティンが採った方法が、このような語り口なのでないかということです。作者がキャサリン本人に代わって、キャサリンの内心をすくい上げて、作者の言葉として語っている。この時に、キャサリン自身は、こう思っているという自覚はないかもしれないのです。だから、作者が語るのです。ちなみに、これは日本の少女マンガ、とくに24年組といわれる作家たち、例えば大島弓子、萩尾望都、倉多江美といった作家達が思春期やそれ以前の内面が確立する前の未分化の内面を表現するときに、少女の内面と現実世界の境界が曖昧になって、その間を行き来するような表現をつくっていったのと、このオースティンの試みには共通点があるように思えるのです。それ以外にも明治の初めに言文一致の小説の試みで、二葉亭四迷が落語の語りを『浮雲』の中で試みているのはいかかでしょうか。 さて、キャサリンは、ポンプ・ルームでエレノアと再会を果たし、親交を深めます。そして、翌日の晩の舞踏会での再開を約束します。その場には、エレノアの兄であるヘンリーも出席するであろうことも。そして、舞踏会の場面です。この小説の中で繰り返し現われる場面です。これで何回目となるでしょうか。 キャサリンが木曜日の晩にアパー・ルームに入っていったときの気持ちは、この前の月曜日の晩とは全く違っていた。あの晩は、ジョン・ソープとのダンスの約束で有頂天になっていたが、今度は、また、彼から申し込まれたら大変だと思い、ジョンの視線を避けることばかり考えていた。ティルニー氏から三度目の申込みを期待することはできないし、期待するのもかしいが、それでもやはり、今夜の彼女の願いと希望と計画は、その一点に集中しているのだ。若い女性なら、このような危機的状況に立たされたヒロインは必ずや同情してくださるだろう。若い女性なら、同じような心の動揺を経験したことがおありだろう。会うのを避けたい男性に追いかけられる危険を経験したことが、少なくともそういう危険を感じたことがきっとあおりだろう。そして、好かれたい男性の関心を引こうと必死になった経験もきっとおありだろう。(P.106) ここでも作者は、キャサリンになり代わって語っています。しかし、作者はキャサリンではなく、キャサリンとして語るわけではありません。そこで、どうしても突き放した語りになってしまう。それが、この文章にも感じられる皮肉です。これは考えの飛躍ですが、この小説全体がパロディとして書かれていることは、批評家や研究者は指摘していますが、その理由はこういう内在的なところにあるのではないでしょうか。 さて、ここでさらにもうひとつ、キャサリンは内心を自分で語ることはなく、作者が説明してあげるということ以外に、キャサリンの行動に仄めかしとして表われている。そうてないと、キャサリンはは自身を他人に伝えることはできないわけで、読者はそこからキャサリンの気持ちなどを推測できるのです。それをオーステインが意識的な使っているのが視線の動きではないかと思います。上の文章でも、ジョン・ソープからのダンスの誘いをさけるために、“度は、また、彼から申し込まれたら大変だと思い、ジョンの視線を避けることばかり考えていた。”と言っています。この視線について、少しまとめて述べてみましょう。この視線の中心となる人物はキャサリンです。彼女は思ったことを十分言葉で語ることがない代わりに、作品の中で視線で語っているところがあります。読者は彼女の視線を何度となく追いかけていると思います。たとえば、それによって彼女が気持ちを伝え合うことができる人物と、そうでない人物をはっきりと書き分けれていることに気付くことができると思います。彼女の気持ちを伝え合うことのできる人物の第一に数えられるのが兄のジェイムズです。第一部の終盤でキャサリンの友人であるイザベラと、ジェイムズの婚約が成立する場面において、キャサリンは素直に喜んで、その気持ちを兄に伝えようとするのは、言葉ではなく視線です。婚約を祝うための的確な言葉が見つからないキャサリンの目から、それゆえに最も表現の豊かな言葉の欠片となってその感情が溢れ、それらを兄のジェイムズはたやすく結びつけて、その視線に込められた気持ちを正確に読み取っている。この場面を見るだけでも、彼女と兄との良好な関係がうかがえるのです。しかし、この物語でジェイムズ以上にキャサリンの視線を向けられるのはヘンリー・ティルニーであることは明らかでしょう。例えば、第4章から5章にかけて、ヘンリーとの再会を願って、キャサリンの視線はアッパー・ルームとロウアー・ルーム、盛装と平服の舞踏会、街を歩く人、馬上の人、馬車の中の人々にも向けられるが、ヘンリーを見つけることさえできず、さまよいます。そして、第8章で再開した二人の間の視線のやり取りが活写されています。 これに対して、キャサリンは、ジョン・ソープとは視線を避けようとする姿勢が目立ちます。同じ第8章でキャサリンはソープとその約束をしているがために、ヘンリーからのダンスの申し出を受けることができません。しかしソープとの会話があまりにも他愛のないものであるため、ダンスの間、ヘンリーと別れた方向に視線を向けざるをえないのです。上で引用した文章もそうでした。この第十章で、舞踏会が始まっても、キャサリンはソープにその相手をすることを申し込まれないように、彼の視界に入らないように、視線を避けることに躍起になって、ソープと視線が合いそうになると、うつむいて扇を見つめるのです。しかし、ソープは、そういうキャサリンの思惑などお構いなしに、ヘンリーの誘いを受けてダンスをするキャサリンに、「やぁ、ミス・モーランド!」という言葉とともにキャサリンに背後から話しかけ、自らの無神経さを露呈するとともに、ソープにもキャサリンにも、相手の目を見て話そうとする意思が全くないことが分かります。しかも、背中から突然話しかけたり、相手が何か言おうとしているときに後ろを向いて去っていったりというソープの非常識な態度から、この二人の間には友情にせよ愛情にせよ、この先友好的な関係が結ばれことはないことを暗に示しています。 そて、何回目かの舞踏会、キャサリンは念願かなってヘンリーとのダンスに興じます。このヘンリーとのダンスについて、第8章の舞踏会でのジョン・ソープと踊った時と対照されています。パターンをくりかえすことで、その差異が際立つように強調されるわけです。ジョン・ソープとのダンスでは、キャサリンは視線をソープと合わせることをせず、別れたヘンリーの方に向けられます。相手のソープは、それを気にすることなく、ということはキャサリンをちゃんと見ていないからでしょうが、一方的に自慢話を話し続けます。これに対して、ヘンリーとのダンスは会話が弾み、ダンスとの共通点があるとして結婚についてまで及びます。この間のオースティンの描写は、二人の発言だけで数ページ続きます。二人の間には作者すら介入することができないと言わんばかりです。おそらく、会話の話題が結婚のことに及んでいるのは、伏線としての意図があったのかもしれませんが、それは考えすぎでしょうか。ここでは、些細な例かもしれませんが、二人の会話の話題は様々なところに向かいますが、例えば、バースでの滞在ついて退屈するかという他愛もない会話もありました。 「バースに6週間も滞在したら、退屈するのが当然なんだけど」 「いいえ、私は6か月滞在したって退屈しないわ」 「いや、バースはロンドンに比べると変化に乏しい町です。毎年みんなこう言います。「バースは6週間くらい滞在するには楽しい町だけど、それ以上滞在すると、世界一退屈な町になるね」って。彼らは毎年冬にバースにやってきて、6週間の滞在を10週間か12週間に延ばし、そろそろ金がなくなると帰っていくんですが、みんなそう言いますよ」 「他人は他人、私は私ですわ。ロンドンへたびたび行く人にとっては、バースなんてつまらないかもしれないけれど、私は片田舎の小さな村に住んでいるので、自分の村よりバースの方が退屈だなんて思いません。ここには面白いものがたくさんあるし、一日じゅう見たりしたりすることがありますけど、私の村には何もありませんもの」 「あなたは田舎が嫌いなんですか?」 「いいえ、大好きですわ。私は生まれた時から田舎に住んでいますけど、とても幸せです。ても、田舎の生活はバースの生活より単純です。田舎の生活は、来る日も来る日もまったく同じですもの」 「でも田舎の生活の方が、時間の過ごし方が理性的ではありませんか?」 「私が?」(P.113) 会話はまだまだ続きますが、同じ章でイザベラがキャサリンに同じ話題での発言が下の引用です。 「私がもうバースにうんざりしたのはご存じ?今朝、あなたのお兄さまと私は完全に意見が一致したの。バースは、二、三週間過ごすにはとてもいい所だけど、ここに住みたいとは思わないって。どんな都会よりも田舎のほうが好きだという点で、お兄さまと私は完全に意見が一致したの(P.100) 些細なことですが、バースに退屈するとか、田舎の生活を話題にしてお喋りするというパターンで、繰り返しをするようにして対照させ、発言しているキャサリンとイザベルの二人の資質や性格の違いを明確に示しています。イザベルの発言には真意が伴っていない口先だけなのが明白で、都会や田舎を抽象的にしか語っていません。また、イザベルにはバースでは刺激が足りず退屈しはじめているのが、そのことばからも分かります。これに対して、キャサリンの発言は具体的で、田舎をかたってもそこに彼女自身がいることが生き生きと語られています。そこに心から村か好きなことはわかるし、二人の女性の発言を比べると、実はキャサリンは賢い人ではないか思えてくるのです。 そして、この章の最後で、ダンスが終わり、ティルニー兄妹と別れる際に、翌日、連れ立って散歩にでかけることを約束します。 第11章 翌朝はどんよりと曇った空模様で、天気がよかったらという散歩の条件が今さらながらに思い出されて、キャサリンは願いがかなうどうか、やきもきするところから始まります。午前中の天気はおもわしくなく、雨さえ降ってくる。しかし、今日の散歩は諦めかけたところで、次第に天気が好転して晴れ間が見えてくる。実に、この描写にオースティンは、翻訳ですが文庫本で3ページを費やします。物語の進行に、それほど必要なのかという雑事のように思われる描写です。しかし、オースティンは必要だったから書いたはずです。キャサリンは、これまでティルニー兄妹に好意を寄せていながら、なかなか会うことさえできず、本人もやきもきするということを繰り返してきました。例えば、舞踏会でヘンリーに出会った後、キャサリンは彼の姿を求めてバース中を探し回るようにしますが、見つけることはできません。また、エレノアと出会った翌日。ポンプ・ルームでの再会を図りますが、ジョン・ソープに遠出に誘われて、その機会を逃します。その間、キャサリンは会えないことを残念に思う。そういうことを繰り返します。このように思う人に会いたいと願いつつ、行き違いや何らかの障害が起こって会えなくて、その間会いたいという思いは、むしろ募っていく。これは、現代に至るまで、通俗的なロメドラマのパターンです。おそらく、そのルーツのひとつはシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』あたりなのでしょうが、ジュリエットの場合には旧家どうしの対立関係という障害が明らかです。しかし、庶民であるキャサリンには、そんなしがらみはありません。そこで、日常的な些細な行き違いが、いくつも用意され、それが手を変え品を変えて立ちはだかることで、ジュリエットと同じような状況を作り出しています。これは、『ロミオとジュリエット』のパロディではないか、しかも、それを日常的な場面に置き換えているわけです。 さて、天気がよくなったけれど、約束の散歩の時間を過ぎてしまったので、どうしようかというときに、不意に、ソープ兄妹とジェイムズが馬車での遠乗りに誘いにきます。ティルニー兄妹との約束を理由に断るキャサリンに対して、ジョン・ソープはまったく理由にならないとして猛烈な勢いで却下し、イザベラはキャサリンの弱みにつけこみ、行き先が小説に出てきそうな古城であると言って誘惑します。さらにジョンは、ティルニー兄妹が馬車で別の方向へ出かけていたという嘘をでっち上げます。ようやく諦めてジョンの馬車に乗ったキャサリンは、まもなくティルニー兄妹が歩きながら自分のほうを見ているのに気づいて、馬車を止めてほしいと叫びます。しかし“ジョン・ソープは笑いながら馬に地を当てて、ますます速度を速め、奇声を発して馬車を走らせ続けた。(P.126)”のです。なにも、奇声を発することもないと思いますが、これは男性が嘘をついて騙してまで、女性を無理やり馬車に乗せて連れ去るというゴシック的題材のひとつである「誘拐」になぞらえて、さしずめジョン・ソープはゴシック小説の悪漢のパロディというわけです。 第9章での遠乗りに続いて、この遠乗りでも、結局はティルニー兄妹の人々と会うことへの妨害となりました。このような遠乗りは、この後もう一度繰り返されますが、繰り返しを重ねるたびに、キャサリンを誘うジョン・ソープの手口は、より強引になり、悪質になっていきます。それとともに、ジョン・ソープのキャサリンを二人に合わせまいとする意思が明確になり、小説の中での悪役としての位置がハッキリしてきます。一方で、キャサリンはソープの人間性を理解していって、彼への嫌悪を募らせていきます。それまで、兄の親友であり、イザベルの兄だからということで、ソープを信頼しようと努め、ソープへの嫌悪を抱くことに負い目を感じていたキャサリンが、兄の親友だからというような先入観を捨てて、真っ直ぐに彼を見ようとする契機になりました。その中で、約束を守るとことを貫こうとするキャサリンの誠実さが、ここでは対照的に際立たせられます。例えば、次のキャサリンの発言に端的に表われています。 「ソープさん、なぜ私をだましたんですか?ふたりが馬車でランズダウン・ロードへ走っていくのを見たなんて、なぜ嘘をついたんですか?こんなことは我慢できません。ふたりは私を変な人だと思ったにちがいないわ。礼儀知らずと思ったにちがいないわ。ふたりがすれちがったのに、私は声もかけなかったんですもの!私がどんなに怒っているか、あなたにはわからないでしょうね、私はクリフトンにもどこにも行きたくありません。馬車から飛び降りてでもふたりのところへ戻りたいんです。ふたりがフェートン馬車で出かけたなんで、なぜ嘘をついたんですか?」(P.167) キャサリンは、意識しないでも、秩序ある社会においては慣例的な礼儀を果たさなければならないということが身についているのが分かります。だから、他人を尊重せず、自分本位に行動して、平気で嘘をついたり、人を騙して、社会のルールを無視するジョンの欺瞞を直感的に見抜いて、彼への嫌悪を確信するに至るのです しかも、この遠出は無謀なことであると、後でアレン氏から忠告され、途中で引き返すことを提案したジェイムズを賢明だったことが明らかにされます。ソープは、そのジェイムズの判断に対して、ジェイムズがのろまで、自分の馬車を持たないせいだと自分勝手な悪態をつくというおまけもついてくる。 第12章 キャサリンは翌朝、エレノアを謝罪と説明のために訪問します。ここでのキャサリンは積極的で、まず、ポンプ・ルームで芳名帳で、彼女の住所を調べて、一刻も早くと急ぎ足で宿へ向かいます。しかし、結果として居留守を使われて面会を断られてしまいます。帰ろうとしていたキャサリンが振り返ると、玄関から出てくるエレノアの姿を認め、すぐあとに父親のティルニー将軍がついて、二人で散歩に出かけるのを見たからでした。キャサリンは屈辱感に打ちのめされます。ここに、すれ違いのパターンが繰り返されます。このティルニー兄妹とのすれ違いの繰り返しは、回を重ねるしたがって、キャサリンがより積極的になり、それにともなって、すれ違った時のキャサリンの落胆が相対的に大きくなってきます。徐々にキャサリンの思いが募ってくるということで、ここでは、さらにティルニー将軍という登場人物が絡んでくることで、この人物は表裏のある人物として、この人物が関係することは、常に表面的な見た目と、そこに隠された真相が、実は…というようなかたちで、食い違っている。いわばゴシック小説では、悪の陰謀の黒幕のような存在として現われます。キャサリンが居留守を使われて面会を拒絶されたのは、実は、自分の外出が妨げられるのを嫌ったティルニー将軍が、娘は不在だと無理にキャサリンに告げさせたというのが事の真相だったのです。エレノアはむしろキャサリンに失礼になると気にしていたが、父親に意見することはできなかったということ、そこにティルニー将軍の権威的な性格が暗示されているのですが、この時点ではそこまではわからず、あとになって、そういえば、そういうこともあったと想起される伏線として、ここに張られているようです。 キャサリンは、率直な性格で、見たまま、聞いたままをそのままストレートに受け取り、その裏を想像するという、いわばスレたところのない純粋な(鈍感な)性格として設定されていますから、そういう実は…ということは分からずに、この経験から、しょげかえってしまい、その気分の晴れないまま、その日の晩、みんなと芝居見物に出かけます。ティルニー家の人々とは劇場で会うこともなく、キャサリンは芝居に集中することができていましたが、第5幕がはじまったところで反対側にボックス席にティルニー将軍とヘンリーの姿を見つけてしまいます。それで、キャサリンは芝居に集中することができなくなり、一時的に忘れていた苦悩にとらわれます。キャサリンは何度となくボックス席に視線を向けますが、ヘンリー・ティルニーは一度もキャサリンの方を見ませんでした。 だがとうとう彼もキャサリンの方を見て、軽く会釈した。ああ、しかし、なんという軽い会釈だろう!まったくにこりともせず、ほんのちょっと見つめ合うこともせず、すぐに舞台のほうへ視線を戻してしまったのだ!キャサリンはあまりにもみじめで、どうもじっとしていられない気持ちだった。彼が座っているボックス席にすぐに駆け寄って、きのうの行き違いの説明をいますぐ聞いてもらいたいと思った。小説のヒロインのような感情ではなく、ごく自然な感情が彼女を襲った。彼の非難がましい冷たい態度によって自分のプライドが傷つけられたとは思わなかった。「自分は無実であり、疑う彼が悪いのだから、こちらが怒っていることを示すべきだ」とは思わなかったし、「きのうの件は彼の方から聞いてくるべきであり、こちらは彼を避けたり、他の男性とたわむれたりして、彼の過ちを悟らせるべきだ」とも思わなかった。キャサリンは、今回の行き違いという不幸な出来事の責任を、すべてわが身に引き受けた。少なくともそういう態度で、弁明の機会をただひたすら待つことにした。(P.136〜137) この文章で例によって、オースティンは客観的な描写にキャサリンの内心を織り交ぜています。最初の文章はヘンリーの様子ですが、それに続く文章はキャサリンの内心の声で、そこから、最初の文章を振り返ると、ヘンリーの軽い会釈は、いかにもすげないものに思えてきます。ヘンリーは芝居に熱中していて、キャサリンへの会釈がつい、うつろになってしまったかもしれないのですが。この流れで読むと、彼の態度にキャサリンへの怒りが秘められているように見えてくる。つまり、視線をキャサリンに同化するような文章になっていると思います。それを、以前にも述べましたが、視線のやり取りを会話のように扱って表現しています。そして、キャサリンの感情の動きを説明する中で、オースティンは“小説のヒロインのような感情ではなく、ごく自然な感情が彼女を襲った。”という小説についてのオースティンのコメントをさりげなく挟んでいます。このあたりがパロディと言われる由縁でもあるのでしょうが、敢えて小説のヒロインのような、他人には分かりやすいような大げさなポーズではない真正なもの゛と断っています。そのために、繰り返しによって、キャサリンの喜びと落胆の振り幅を徐々に大きくしてきて、自然に見えるように、全体として配慮して物語を作ってきていて、ここで敢えて断っている。そのあとの文章でくどいかもしれませんが、小説のヒロインによくある内省的な反省をしていくと、“「自分は無実であり、疑う彼が悪いのだから、こちらが怒っていることを示すべきだ」とか、「きのうの件は彼の方から聞いてくるべきであり、こちらは彼を避けたり、他の男性とたわむれたりして、彼の過ちを悟らせるべきだ」”といった方向に流れてしまう。内心の語りのロジックとはそういうもので、当時の小説のヒロインの主体性というとそういう方向になってしまって、現実の平凡な市井の女性の、あまり物事を突き詰めて考えないという実態とはかけ離れているという、オースティンの認識がここで、くどいほど述べられていると思います。そうでない、ああでない、というこの小説に特徴的な否定的な言い方です。それによって、平凡であることをポジティブに表わそうとしているというわけです。あれこれ、面倒なことを言いましたが、要はキャサリンの反省が真正なものであるということを、そういう平凡なことを言うために、これだけの文言を重ねないと、平凡であるということが表わせなかった、ということで、当時の小説のありかた、小説の言語について、オースティンは、ここで、かなり考えていて、言葉を重ねていたのではないかと思います。 そして、芝居が終わって、ヘンリーが挨拶に席を訪れたときに、堰を切ったように謝罪と説明の言葉を連ねます。そこで、ヘンリーの口から、視線の会話は、その時にも成立していたことが説明されます。「僕ら兄妹の楽しい散歩を願うため」に「わざわざ振り返ってくれた」というヘンリーの言葉をもらい、それによってキャサリンの気持ちは救われるのです。小説としては、この件に関して、そこで初めてキャサリンの視点からではない解釈が披露され、キャサリンにも読者にも、ヘンリーの怒りは彼女の勘違いであったという事実が伝わるという構造になっています。そこで、ヘンリーの口からエレノアの居留守の真相が伝えられます。面白いのは、その後で、「でも,ミスター・ティルニー,どうしてあなたは,妹さんみたいに寛大ではないのですか」と彼に無邪気に質問をするところです。ヘンリーは単刀直入に尋ねられてうろたえるのですが、彼女のこの率直さという無邪気は、それまでの小説のヒロインには考えられないものではないかと思います。こういうところがキャサリンのという女性の新鮮な魅力だと思います。 落胆の後で、回復すれば、その喜びをより大きなものとなります。この小説では、小さな繰り返しを重ねることで、その振り幅を徐々に大きくしていって、キャサリンのヘンリーに対する好意が次第に恋心になっていくも、この反復パターンのプロセスで、ドラマチックな恋愛小説に対するアンチテーゼにもなっているのではないかと思います。ともあれ、キャサリンは信頼を回復したついでに、散歩をすることを再び約束することもできたのでした。 だから、彼が去った寂しさを別にすれば、このときのキャサリンは、世界一幸せなお嬢さまと言っても過言ではなかった。(P.140) しかし、この第12章はそれだけでは終わりません。ジョン・ソープとティルニー将軍が、面識のないはずの二人がなにやら話し合っている様子を、しかもキャサリンのことを話題にしているらしいことを、彼女が気づきます。 第13章 前章で、キャサリンは誤解を解いて、再びティルニー兄妹との散歩の約束を取りつけることに成功しました。しかし、その当日になって、またしてもソープ兄妹が彼女を遠出に連れ出そうと誘いに来ます。ティルニー兄妹との散歩をしているところに、横槍のようにソープ兄妹から遠出に誘われるというエピソードの反復です。しかも、この反復は短期間で間をおかず繰り返されます。読者は、それゆえ繰り返しであることが分かるようになっています。実のところ、我々自身の生活を顧みれば、日常などは同じことの繰り返しであるし、人生の転機となるような出来事ですら、過去に似たようなことの繰り返しであるような場合が多いのです。ただ、そのことに気づいていないだけで、この『ノーサンガー・アビー』では、物語を短期間のものに収縮してしまうことで、そのような繰り返しであることを明らかにしている作品で言えるかもしれません。 さて、これで読者の皆さまは、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、そして土曜日のすべての出来事をご覧になったことになる。この六日間にキャサリンの身にふりかかったすべての出来事と、その希望と不安と苦しみと喜びが、すべて述べられた。つづいて、日曜日にキャサリンを襲った苦悩について述べれば、めでたく一週間を終えることになる。(P.144) と作者が自ら述べているように、この小説では、毎日の事件を綴っているので、そこに作者が人為的に時間を凝縮させている操作が施されているわけです。これは、物語のテンポとか、ただでさえ、ゴシック小説のような波乱万丈の展開がないのですから、小さなエピソードの積み重ねで物語を展開させていくための操作ということでしょう。しかし、読者はあまり、そうは感じないのではないか。それは、小説の中に、些細な日常性の記述が反復されているからではないでしょうか。つまり、キャサリンが朝目覚めたとか、夜寝たという。どうということのない描写です。そこで、出来事だけでない描写が、日常の平凡な時間を読者に想起させる。そこで、事件ばかりではないことを示しているというわけです。 また、繰り返しということであれば、同じオースティンの作品で『説得』においては、主要な登場人物たちが、それぞれの過去において同じような経験をしたことが、現在、目の前で起きている事態に対して、どれたけ、その経験を教訓として対処しているかということで、それぞれの運命に差が生まれる、というのがストーリーの大きな骨格になっています。この物語でも、基本的には繰り返しが骨格にあるのですが、スパンが長いのと、スケールが大きいので、なかなか読者には気付きません。それはそれで、まるで見えない運命のように登場人物たちが直面させられるという叙事詩的な作品に似つかわしくなっています。これに対して、『ノーサンガー・アビー』の場合には、繰り返しであることが誰にでも分かるように、ストーリーもコンパクトに凝集されています。これは、『説得』のようなスケールよりも、繰り返しのバリエーションが物語を展開させていく、音楽のような作品となっているからです。 さて、物語に戻りましょう。一旦は途中で引き返したために実現されなかった遠乗りの計画がイザベルとジェイムズの間で再び持ち上がり、ジョン・ソープをまじえた3人でキャサリンを誘いに来ます。キャサリンは、ティルニー兄妹との散歩の先約があるからと、行くことはできないと断ります。ここまでは、前回と同じことの繰り返しです。しかし、今回は、キャサリンは強い意志を示して固辞しているのに対して、3人の誘いは執拗で強引です。ソープ兄妹し散歩の約束を取り消すように要求し、猛烈に抗議してくるのです。 イザベルとジョンは「いや、取り消さなくてはいけないし、絶対に取り消すべきだ」と猛然と抗議した。「明日は絶対にクリフトンに行かなくてはならないし、キャサリン抜きでは行きたくないし、散歩なんか一日延ばしたってどうってことはない」とイザベラとジョンは言い、キャサリンがいくら断っても耳を貸そうとしなかった。(P.145) 先約があるから散歩の約束を延ばすことをイザベラから求められ、先約などなかったのだから嘘はつけないとキャサリンは譲りませんが、ここで、嘘をつくことに対して何のわだかまりないイザベルと虚偽を嫌うキャサリンの差異が表われています。これが後々、二人を分かつ大きな要因となっていくのですが、これも小さな伏線というべきか、小さな予告、仄めかしを、作者が用意周到に準備しているといえるでしょう。ただし、読者は、始めて読んで、後の展開が分からない人は、気付くことはないでしょう。 「あなたはミス・ティルニーと知り合ってまだ間もないのに、一番の親友で旧友の私よりも、ミス・ティルニーのほうが好きになったのね。私のことなんてどうでもよくなったのね。ね、キャサリン、私は悔しいわ。あなたをこんなに愛している私が、赤の他人のためにこんな侮辱を受けるなんて、ほんとに悔しいわ!私は誰かを愛したら、どんなことがあってもその人を愛し通すわ。でもきっと、私の愛情は誰の愛情よりも強いのね。愛情が強すぎて、心の平和が得られないのね。あなたの愛情を赤の他人に横取りされたと思うと、この身を引き裂かれたような気がするわ。あのティルニー兄妹に何もかも奪われてしまったような気がするわ」(P.147) 約束という重要な社会のモラルを守ろうとしているキャサリンに対して、このような不当な責め方をするイザベラは“心が狭くて、自分勝手で、自分の欲求を満たすことしか考えない人”だと、キャサリンは初めてイザベラを疑い始めることになります。しかも、キャサリンが板ばさみにあって、つらく悲しい思いをしているのに対して、イザベラは“でもたいした心の葛藤はなさそうね”と低い声で呟くのでした。 その一方で、ジョン・ソープは勝手にエレノアのところに行って、キャサリンからの伝言だと偽り、散歩を延期する約束を取りつけて来てしまいます。キャサリンがティルニー嬢を追いかけて申し開きに行こうとすると、“イザベラが彼女の一方の手を掴み、ソープがもう一方の手を掴んで”、抗議の声を浴びせかけるのです。自らの欲望を満たすために、相手の気持ちや事情はいっさい考慮しようとせず、文字どおり力づくで連れ去ろうとするソープ兄妹の暴力的なやり方は、ゴシック小説に間々見られるヒロインを、よってたかっていじめる悪党の振る舞いのようです。しかも、ソープ兄妹をふりきってエレノアを追うキャサリンに対して、ソープは口にできないような下品な言葉を投げつけます。 結局、今度の繰り返しでは、キャサリンはティルニー兄妹との約束を守ることができました。ティルニー兄妹にひどい人と思われたくないという強い思いが、彼女に必死の行動をさせたことになるわけです。そのひどい人だと思われたくないということのベースには、約束を破るのはひどい人だという倫理が彼女に備わっているということの表れでもあるわけです。こうしてキャサリンは、自己判断に基づき行動したのですが、兄をはじめとする三人の怒りは収まらないわけです。不安になってアレン氏の意見を聞きにいき、キャサリンは自分の判断に自信を持つまでに成長したのである。 一方、キャッサリンは、必死になってティルニー兄妹を追いかけ、一家の宿に飛び込むことになってしまいます。そこで、二人の誤解をはらすことができた。それだけでなく、兄妹の父親であるティルニー将軍に紹介されます。その将軍から愛想よく相手をされて、キャサリンは嬉しく思いますが、前の章において劇場でジョン・ソープとキャサリンのことを話していたことの影響であり、これが後半の展開への伏線となっていきます。 第14章 翌朝はとてもいい天気で、キャサリンは念願のティルニー兄妹との散歩に出かけます。“新たな問題が持ち上がることもなく、突然何かを思い出すこともなく、思いがけない呼び出しもなく、計画をめちゃめちゃにする無遠慮な侵入もなく、われらがヒロインは、無事に約束を果たすことができたのだった。約束の相手はヒーローその人なのに、ヒロインの運命としてはまことに珍しいことである。(P.159)”という極めて皮肉な書き方で、この書き方が小説に対する揶揄も含まれています。 雑木林の丘を散歩しながらの、兄妹との会話は、アラン夫人あるいはイザベルたちのお喋りとは異質の知的なもので、最初はゴシック小説についてから始まり(この部分は、作者がこの作品中の散在する様々な小説論のひとつとして、教養ある男性はゴシック小説など読まないということに対する、ヘンリーを借りたオースティンの一つの考え方かもしれませんし、第7章でジョン・ソープが小説は馬鹿なことばかり書いてあるといったことと対照的に扱われている事も、小説をめぐっての態度が正反対であることも、ヘンリー・ティルニーとジョン・ソープをヒーローと悪漢として対比的に見ることのできる表われとも思えます)、エレノアが歴史書をよく読むことに話は移ります。キャサリンは、小説は好きだが、歴史は好きになれないとして、次のように言います。 「私も(歴史を)好きになれたらいいんですけど」とキャサリンは言った。「義務的にすこしは読みますけれど、いやなことや退屈なことしか書いていないんですもの。どのページを開いても、教皇や国王たちの争いや、戦争や疫病のことばかりで、男はみんなろくでなしで、女はほとんど出てこなくて、ほんとにうんざりするわ。でも、よく不思議に思うの。歴史書の大部分は作り話なのに、なぜこんなに退屈なんだろうって。英雄の言葉も考えも計画も、ほとんどが作り話だと思うわ。それなのになぜあんなに退屈なのかしら。ほかの本に書かれた作り話はすごく面白いのに」(P.163〜164) 話は脱線しますが、現代の視点で引用したキャサリンの発言をみると、かなり鋭い指摘で、彼女は鋭い知性の持ち主と見なされてもおかしくはないと思います。例えば、歴史の虚構性のことは歴史というものの本質的な問題を突いているし、女は出てこないというのは、歴史の虚構性に伴う偏った視点の指摘でもあります(当時はフェミニズムという視点から歴史をみることはなかったのでしょうから)。話をもどしますが、キャサリンにこう言わせて、これに応ずる、エレノアの発言でも、歴史に作り話があることを否定していないのは、作者のオーステインが、そういう考えを持っていたということで、これは広い意味での小説論=虚構論のひとつとして、オースティンが扱っているだろうことは想像できます。また、この引用した会話の前半で“争いや、戦争や”とそんなことにうつつをぬかす男はろくでなしだということはば、この後で政治に話題が飛んで、“恐ろしいこと”について話されることの伏線と見ることができます。 その後、兄妹は風景について話し合いますが、キャサリンは絵画の知識がなくて、二人の会話が理解できず、自分が無知であることを正直に話します。キャサリンの素直に性格は。彼女の行動のいたるところにあらわれますが、これもそのひとつでしょう。友人のイザベラと違うのもこの点で、この違いが、この後で二人を分かつことになる根本的な要因だと思います。キャサリンは、自分の無知を認めることができて、それを恥ずかしいと感じることができる人だということです。イザベルは、第6章で『サー・チャールズ・グランディソン』を読んでもいないのに、つまらないと知ったかぶりして切り捨てたり、自分の趣味に閉じこもるように、気に入らないものは認めません。だから、キャサリンは、遠乗りをめぐる意見対立でも、イザベラの自分勝手な屁理屈をおかしいと冷静に判じ、正しいという一点で譲らず、ティルニー兄妹の信頼を勝ち取ることができわけです。一方は、作者のオースティンは、そのキャサリンに対するヘンリーの好感を“器量が良くて、心がやさしくて、無知な頭をもった女性は、よほど運の悪い事情がないかぎり、頭のいい青年の心を必ず引きつけるものだ”と皮肉った書き方をしていますが、この点もパロディとして考えればいいのかもしれません。(これはファニー・バーニー『カミラ』のパロディだそうです) 会話の最後は政治の話になって、ヘンリーが一方的に話すだけになり、キャサリンが小説の新刊書の情報として“とにかくものすごく恐ろしいものなんですって”というのをエレノアが誤解して、ロンドンで暴動が起こると勘違いして驚きます。その誤解をヘンリーが説明して解きます。このときエレノアが誤解したのは、理由がないわけでなく、ヘンリーは次のように言います。 「ミス・モーランド、ぼくの愚かな妹は、あなたのあんな明快な言葉を誤解したんです。あなたはもうすぐロンドンで恐ろしいものが出るといいましたね。すこしでも理性のある人間なら、これは貸本屋な関係した話だと察しがつくはずだけど、なんと妹の頭には、“セント・ジョージ広場に集結した三千人の暴徒の姿が浮かんだんだ。三千人の暴徒がイングランド銀行を襲撃し、ロンドン塔に押しかけ、ロンドン死骸が血の海となり、国民の希望の星である第12軽騎兵隊が、暴徒鎮圧のためにノーサンプトンから召集され、そしてわれらが勇敢なる兄フレデリック・ティルニー大尉が、騎兵隊の先頭に立って突撃を開始した瞬間、二階の窓から飛んできたレンガのつぶてに当たって落馬するんです。ね、愚かな妹を許してやってください。女性の弱さと、軍人の兄の身を心配する妹の恐怖心が、こんな妄想を生んだんです。でも妹は、ふだんはこんなに愚かではありませんよ」(P.170〜171) ここで、ヘンリーがエレノアの誤解は当時の世相からは現実味のあるものだったそうです。例えば“線と・ジョージ広場”というのは、1780年に起きたゴードン暴動の集会の場であり、1795年に政府に抗議する市民のデモの起きた場所でした。フランス革命の影響でイギリスでは大衆の不満が増大し、革命勃発の機運が漲り、1795年、議会開会に向かう途中の国王の馬車が襲撃されるなど事件が相次ぎました。それに対する政府の抑圧は強化されていました。また、“ノーサンプトン”には実際に騎兵隊が駐留していました。ちょうど『ノーサンガー・アビー』が執筆されていたが、この1790年代後半でした。これに対して、廣野由美子は、同時期の1790年代に、イギリスのゴシック小説作家たちが、このような自国の状況から目を逸らすかのごとく、過去の異国を舞台とした物語を書くことによって、読者の恐怖を煽ろうとしていたと指摘します。そして、オースティンはそのような流行作家たちの文学的姿勢、そしてそれに対して盲目的な読者の姿勢に対して、批判の目を向けていたと。つまり、この会話での「“恐ろしいこと”はイギリスの足元の現実にこそあるのではないか?」というメッセージをテキストに潜ませることによって、彼女はゴシック小説が描く恐怖の嘘っぽさを諷刺しているとも解釈できる。そのように読むと、このくだりの直前に挿入された「政治」の話題のあとの「沈黙」は、特別の意味を帯びてくる。と。(廣野由美子『深読みジェイン・オースティン』P.69〜70) この散歩の最後に、キャサリンは正式にディナーに招待され“あまりのうれしさに、どうしよいかわからぬほど”となりました。 この第14章のほとんどは散歩の場面でした。それまで、エピソードを細切れのようにして、それらを出し入れするようにして、モザイクのようにして全体をつくっていた物語のつくりが、ここではひとつのエピソードをじっくりと読ませることを初めて行いました。ここで、小説のテンポが変化してきました。キャサリンの周囲が、ソープ家の人々やアレン夫妻から、ティルニー家の人々に替わるにつれて、小説自体が変化してきます。その点で、この第14章は転換点となるところです。 第15章 キャサリンは、イザベルから手紙で呼び出され、兄のジェイムズと結婚を約束したことを告げられます。キャサリンがティルニー兄妹と散歩をしていた日に、兄とソープ兄妹は馬車の遠出に出かけ、そこで愛の告白があったということです。キャサリンは、最愛の兄と親友が婚約したことに感激します。兄は、両親の了解をえるために故郷のフラートンに急ぎ出発することになります。そこでのイザベルとキャサリンの会話がすれ違いなのは、今後の展開を予想させるものではありますが、この時点では、先のことは読者はわからないので、後になって、ああやっぱりねと納得する時に、この二人の会話のすれ違いが思い起こされる、そういった類の伏線になっていると思います。 イザベルのジェイムズに対する思いを語っている言葉には、そのうらに彼の財産への期待という打算があるのでしょうが、この時には真意あふれるように情熱的です。それは、キャサリンがたじろくほどです。しかし、イザベルの情熱的すぎる言葉には、ある種の過剰があり、自分で自分に酔っている、あるいは煽っているところも垣間見えます。ただし、これは、この後でのイザベルの行動を知っているから分かることであって、この時点では、すこし我が儘なところのある、夢見がちなお嬢さんが。結婚の約束が成立したことに有頂天になっているとしか見えません。しかし、キャサリンは、何となく、イザベルの過剰さについていけないものを感じています。それは、結婚後の生活と財産の話についての二人の見解のすれ違いにあらわれています。二人とも、財産なんて必要ないといいながら、キャサリンが語る生活プランは財産を前提にしたものであるの対して、キャサリンは自分の実家の生活がそうなので、それをモデルにして考えているところです。おそらく二人は、意識していないでしょうが、イザベラはキャサリンの言っている田舎の質素な生活をするということは、最初から想定外であることは明らかです。このようなイザベラの下心を隠してキャサリンと接しているのは、彼女自身のしたたかな巧妙さもありますが、おそらく、その巧妙さを自身でも意識していないところのあるのでしょう。これに対して、イザベルの兄のジョン・ソープは意識的です。策略的であるのを自覚しています。それだけに、策略はあからさまで、読者には、はっきりと分かるのです。しかし、キャサリンは、それに気づきません。キャサリンは、鈍感ということになっていて、人の言葉には裏があるということが分からないからです。言ったとおり、言葉の表層だけをとらえてしまうのです。少し長くなりますが、ジョン・ソープの策略的な愛の告白を、キャサリンは、それと分からず受け容れてしまう形になっています。 「この結婚はほんとにすごいな!あなたのお兄さんとぼくの妹はうまいことを思いついたもんだ。ね、ミス・モーランド、あなたはどう思います?ぼくはなかなかいい考えだと思いますね。」 「ええ、とてもいい考えだと思いますわ」 「ほんとに?ずいぶん素敵なお返事ですね。でも、あなたが結婚の敵でなくてよかった。「一度結婚式に出たら、また出たくなる」という昔の歌をご存じですか?ね、イザベラの結婚式にはでてくれますね?」 「ええ、できれば出席したいって、イザベラさんに約束しました」 「あの、それじゃ」とジョンは、体をよじって馬鹿みたいに笑いながら言った。「それじゃ、その昔の歌がほんとかどうか、ふたりでためしてみましょうか」 「ふたりで?でも、私は歌はだめなんです。では、どうぞご無事で。私は今日、ミス・ティルニーにディナーに呼ばれているので、もう返らなくてはなりません」 「いや、そんなに急ぐことはありませんよ。こんどいつ会えるかわかりませんからね。といっても、二週間後には帰ってきますけど、ぼくには死ぬほど長い二週間になるだろうな」 「それじゃ、なぜそんなに長く行っているんですか?」相手が返事を待っているらしいので、キャサリンは仕方なく答えた。 「いや、あなたは親切な人だ。すごく親切なやさしい人だ。ぼくは絶対に忘れない。あなたは誰よりもやさしい人だとぼくは思っています。ものすごくやさしくて、ただやさしいだけじゃなくて、あらゆるすばらしいものを持っています。そしてあなたは…いや、ほんと、あなたのようなすばらしい人はいません」 「あら、とんでもないわ!私のような人間ならいくらでもいるわ。もっとすばらしい人がたくさんいるわ。それでは、さようなら」 「あの、ミス・モーランド、もしご迷惑でなければ、近いうちにフラートンにごあいさつに伺うつもりです」 「ハイ、どうぞいらしてください。父も母も、あなたにお会いしたらとても喜ぶと思いますわ」 「そしてミス・モーランド、あなたもぼくに会うにはおいやではないでしょうね」 「とんでもない!私は会うのがいやな人なんていませんわ。人と一緒にいるのはいつだって楽しいわ」 「いや、それはぼくの考えとまったく同じですね。「ぼくに楽しい仲間をお与え下さい、愛する仲間をお与え下さい。好きな人と好きな場所に一緒にいられたら、ほかのことはどうでもいい」というのがぼくの考えです。あなたはいま、ぼくとまったく同じことをおっしゃいました。いや、それを聞いてほんとにうれしい。ミス・モーランド、どうやらあなたとぼくは、ほとんどの点で同じ考えを持っているようですね」 「沿うかも知れませんけど、私はそんなことは考えたことありません。それにほとんどの点といっても、正直言って、私は自分の考えなんてよくわからないんです」 「いや、そうですとも、それはぼくだって同じです。自分に関係ないことで頭を悩ますなんてことはしません。ぼくの考えは非常に単純です。居心地のいい家に、好きな女性と一緒に住むことができれば、それ以上のぞむものはないということです。財産なんてどうでもいい。ぼくには十分な財産があるから、相手の女性が一文無しなら、かえってそのほうがいいんです」 「そうですね。その点は私も同じ考えです。男性か女性か、どちらか一方に十分な財産が在れば、もう一方には財産なんて必要ないわ。どっちが持っていようと、とにかくあればいいんですもの。大金持ちが大金持ちを求めるなんていやだわ。それに、お金のために結婚するのは一番いけないことだと思うわ。それでは、さようなら。どうぞ、ご都合のいいときに、いつでもフラートンにお出かけください」 そう言ってキャサリンは立ち去った。 後に残されたジョン・ソープはこう確信したのだった。 「よし、愛の告白はうまくいった。明らかに前途有望だ」(P.187〜191) 上記の引用の中での、キャサリンの受け答えはしっかりとしたもので、決して彼女は愚かとは思えません。むしろ、イザベルの会話などと比べるとストレートですが話の筋道は明確で、本質的に頭のいい人の話し方です。それが、言葉の表層の意味を直接的に捉えるしかできないというのは、現実では考えられないことです。それをあえて設定してのは、作者オースティンの意図的なものでしょうか。前のところで述べましたように、この作品は、従来の小説に対して、ネガティブに「〜でない」を積み重ねて、小説の要素を否定して排除していって日常の平凡な生活という、それまでの小説にないものが残ったところで作ろうとした作品です。そこで、ヒロインであるキャサリンも、小説のヒロインである要素を排除していったアンチ・ヒロインとして設定されているように見えます。そこで施してある仕掛けが、キャサリンのそういう矛盾したところではないかと思います。それは、小説の虚構と現実との区別がつかなくて、後半では、それが物語を展開させていく大きな要素となっていきます。しかし、それだけでなくて、単にキャサリンが子供だからというのではなくて、小説というのは虚構、つまり嘘です。それが現実を表わしてしまう。そういう構造的な矛盾があります。オースティは、そのことを分かっていて、あえて他人の嘘を信じてしまうキャサリンというヒロインを設定して、このキャサリンそのものが、オースティンの小説論、虚構論を体現していたのではないかと思えてくるのです。その意味では、後年のオースティンが作家として成熟していった『高慢と偏見』などよりも、こちらの『ノーサンガー・アビー』の方が知的に屈折した点の多い複雑な作品と捉えることもできるのではないでしょうか。 第16章 このあたりから、キャサリンの他人に対するやさしさと、言葉の表層の意味しか捉えないということが目立ってきて、小説の物語に大きく作用するようになってきます。 キャサリンはティルニー家のディナーに招待され、訪問します。しかし、期待とは裏腹にもの足りなく思う結果となります。ディナーは文句のつけようもなく、ティルニー将軍も丁重に彼女を迎えてくれたのに、ミス・ティルニーとの親交が深まったわけでもなく、ヘンリー・ティルニーとも以前ほど楽しめなかった。その理由は、物語が進むにつれて次第に明らかになってきますが、それを、この出会いの当初の時点でキャサリンが直感的に感じ取っていたわけで、彼女は決して鈍いわけでも、愚かでもないのです。ここで、オースティンは、それまで、キャサリンが何かを感じた場合、たとえつまらない日常のことでも具体的に詳しく、その事態を描写していたのに、このディナーの模様については、具体的なことはすべて省略して、キャサリンがそう感じたということを、後から回想するように記述しているだけです。つまり、オースティンは、このディナーの模様については意図的に隠蔽していると言えます。しかし、そうしているとは読者は、あまり感じないでしょう。それが、従来の小説のやり方だからです。それまで、オースティンは、この作品において、そういうやり方を否定するように、キャサリンをめぐる事態は細かく記述してきました。そこで、このディナーの部分の大きな省略です。しかも、さりげなく、です。 それに次いで、イザベルとの会話に場面は転換し、そのディナーについてイザベルに話すと、それはティルニー兄妹の高慢さのせいだと言いますが、それは半分は当たっているわけで、キャサリンは兄妹の親密でない態度にもの足りなさを覚えたのは事実で、キャサリンはそれを元気がなかったと好意的に受け取っていますが、その背後にいたティルニー将軍については、イザベルが高く評価しているのが、この後の物語の伏線を補強していることになっています。この二人の会話で、もうひとつ、大きな伏線となっているのが、今夜の舞踏会でイザベルが40マイル離れたところにいるはずのジェイムズのことが心を占めていて、ダンスなんか絶対しないと言っていることです。この伏線は、読んでいる時には気付かず素通りしてしまいますが、後で、重要な意味を持ってくることになります。 この日の晩の舞踏家では、キャサリンは、ティルニー兄妹と再会し、前日のディナーとは打って変わって、親密な楽しいときを過ごします。そして、新たな登場人物として、兄妹の兄である、長男のティルニー大尉が登場します。凄く美男子でお洒落な男性ですが、キャサリンは、うぬぼれが強そうで、好感がもてないと感じます。彼は、「ぼくはダンスなんてするもんか!」と大きな声で言い、「ダンスなんてしている弟の気が知れない」とあからさまにヘンリーを嘲笑しているのを、キャサリンは見ます。何か、このシーンは、オースティンの後年の作品、『高慢と偏見』で、ダーシーがビングリーと村のダンスパーティーに現れて、ダンスをしないでいるのを、ヒロインのエリザベスが見咎めるシーンがダブリます。それでは、好感をもてるはずはないですが、キャサリンの直感は当を得ているのは、物語が進むにつれて明らかになってきます。 ティルニー大尉はヘンリーを通じて、イザベラにダンスを申し込みたいので紹介して欲しいとキャサリンに頼みます。これに対して、キャサリンはためらうことなく断ります。彼はダンスなどしないと言っていたのを覚えていたし、イザベルもダンスをしないといっていたからです。そして、キャサリンは、ティルニー大尉がイザベルの事情を知らず踊らないのでいるのをかわいそうに思ってダンスに誘ったと考えた。それをヘンリーは「あなたは他人の行動の動機を実に簡単に理解しますね」と評する。そして「あなたは、こういうことはいっさい考えないんですね。「人間の行動はどういうことに影響される可能性があるのか」。「ある人物の感情、年齢、境遇。生活習慣などを考慮すると、その人物の行動派どうこうことに影響されるか」ということを全く考えないんですね。そしてあなたは、「自分はどういうことに影響されるか。ある行動をする場合、自分はどういうことに影響されるか」ということしか考えないんですね」と言います。 二人の会話がなされている一方で、ティルニー大尉は自らイザベラに話しかけ、イザベラは微笑んで応じているのです。キャサリンは、それに驚いてしまいます。これについて、ヘンリーは次のように言います。さっきの、キャサリンには分からないといった説明を具体的にしてものです。 「いままでイザベラさんは、気が変わったことは一度もないんですか?」 「えっ?でもそれは…それにあなたのお兄さまだってそうよ!イザベラは踊らないという私の言葉を、あなたから伝えていただいたのに、お兄さまはなぜイザベラに申し込んだのかしら?」 「その点にいては、ぼくはまったく驚きませんね。イザベラさんについては、あなたが驚けと言うから驚きますけど、ぼくの兄については、はっきり言って、あの程度のことは平気でやると思っていました。イザベラさんはたいへんな美人で、誰が見てもとても魅力的ですからね。そして彼女の意志の固さは、あなたにしかわかりませんからね」 「あなたは私を笑っているのね。でもイザベラは、ふだんはとても意志が固いのよ」 「ある程度はだれだってそうです。何があっても絶対に気が変わらないというのは、ただ強情なだけかもしれない。必要なときにいつ譲歩するかによって、正しい判断力が試されるんです。ぼくの兄のことは別として、ミス・ソープがいま譲歩したのは正しい判断だと思いますね」(P.200) その後で、キャサリンとイザベルの会話に場面は移りますが、キャサリンがどう思って、どんな気持ちでいるかは、いつもと違って、一切書かれていません。このあたり仄めかし方、読者の想像に任せるという省略の仕方は巧みです。 そこで、場面は急に飛んで、後日、二人が次に会ったときになります。兄のジェイムズからイザベルに二通目の手紙が届いたところです。 ジェイムズ・モーランドから二通目の手紙が届き、父親の気前のいい贈与の意思が明らかになったのだ。現在モーランド氏は、年収約400ポンドの聖職禄を持っており、その贈与権も持っているのだが、息子ジェイムズが十分な年齢に達したら、その聖職禄を譲るというのである。これでモーランド家の収入はかなり減ることになるし、子供はほかに9人もいることを考えると、これは決してケチくさい額ではない。そのうえ、少なく見積もっても400ポンドの値打ちのある土地も、将来ジェイムズに譲るというのである。(P.202) これは、作者による説明的な文章ですが、モーランド家に立った視点での説明で、キャサリンの視点も一部反映しているものだと思います。というのも、これに対してイザベラはひどく暗い表情になったからです。それをとりなすようなソープ夫人も、イザベラの気持ちが分かっているからこそ、慰めようとしているわけです。あきらかに、イザベルは第15章でジェイムズとの結婚で財産なんて必要ないと言ったことと矛盾する態度を示しているわけです。ここでのイザベルは、明らかに当てが外れた失望感をあらわにして、モーランド氏をケチだと仄めかしているわけです。当然、キャサリンは不愉快になります。キャサリンは、持ち前のやさしさから、イザベルを信じようとします。 第17章 キャサリンは、ティルニー将軍から我が家であるノーサンガー・アビーに招待されます。ティルニー兄妹との交友を続けられるわけです。それだけでなく、ノーサンガー・アビーというゴシック小説に出てくるような名前に好奇心で一杯になるわけです。つまり、後半の始まりです。 第18章 キャサリンは、ノーサンガー・アビーへの招待についてバースでの後見人の立場であるアレン夫妻に承認してもらい、故郷の両親に事情を説明する手紙を書いて許可を求めたり、あるいは荷物を整理したりと雑事に追われていたことから、数日振りにイザベラに再会します。この第18章は、キャサリンがノーサンガー・アビーに行ってしまう前の、前半の状況に一区切りつけるのと、後半の場面転換に向けての伏線が用意されます。これまでの前半では、小さなエピソードが散発的におこって、その中で、いくつかのエピソードは何度か形を変えて繰り返されました。しかし、それらは、一つの大きな話の流れを作り出すに至らず、モグラ叩きのゲームのように、物語の場で各々のエピソードが別個に起こっていました。後半では、最後近くになって、それらのいくつかが関連していることが明らかになり、ティルニー家の謎とキャサリンの運命に集束していく展開に換わっていきます。つまり、物語が動き出していきます。 ポンプ・ルームでイザベラと再会したキャサリンは、イザベラからジョン・ソープがキャサリンに愛の告白をして、いろよい返事を受けたという手紙を受け取ったと話されます。これは第15章で、イザベラとジェイムズが婚約したことを祝福したあとのどさくさに紛れて、ジョン・ソープが巧妙に、それとなくキャサリンに話したことです。したがって、キャサリンは愛の告白を受けたという認識はまったくないものでした。このような、ジョン・ソープとキャサリンの間のスレ違いは、ダンスの申込みや馬車での遠乗りの誘いといった、ソープがキャサリンを誘う行為で繰り返されます。そのとどめが、この求婚のスレ違いです。キャサリンが、ソープから愛の告白を受けたことを否定し、ヘンリー・ティルニーという男性への思いを持っているから、仮にソープから愛を申し込まれても当然断ると主張します。それを聞いたイザベラの対応が、ジョン・ソープの妹で、似た資質を持っていること、つまり、真意と言葉が必ずしも一致しないことが反映したものでした。それはまた、これから行われる、キャサリンから見れば、ジェイムズに対する裏切りとも、浮気とも見えてしまう行為をするイザベラの性格や姿勢が表われるものでした。しかし、キャサリンには、ジョン・ソープの求愛を受けても、それと気付かなかったのと、同様に、イザベラの言葉にジェイムズへの態度が見え隠れしていることに気付くことはありません。 「正直言って、兄の手紙を読んですぐに思ったわ。この結婚はものすごく愚かで軽率で、ふたりのために絶対よくないって。だってもし結婚したら、一体どうやって暮らしていくの?ふたりとも多少のお金はあるでしょうけど、最近は家庭を持つのはそう簡単ではないわ。小説家がどんなに甘いことを言おうと、お金がなくてはどうしようもないわ。」(p.218) このイザベルの言葉には、第16章でジェイムズが父親から400ポンドの聖職禄を受け継ぐことになったときの彼女の暗い表情が見え隠れしています。この言葉で「どうやって暮らしていくの?」というのは、実は彼女自身に向けられた言葉であることにキャサリンは気付いていません。そして、キャサリンがヘンリーへの一途な思いの一方で、ソープを愛することはないと断言したことに対して。 「あなたの過去の考えや意図を私が決めるつもりはないわ。それは本人のあなたが一番よく知っていることですもの。無邪気な恋のたわむれはよくあることだし、自分はそのつもりでなくても、相手に気を持たせてしまう、というのはよくあることよ。でも安心してね、私はあなたを厳しく裁くつもりはないわ。こういうことは元気な若い人にはよくあることだかに大目に見るべきよ。今日こう思っても、明日は気持ちが変わるかもしれないわ」(p.218) このイザベルの言葉は、キャサリンに向けられているようで、ジェイムズに対する気持ちが恋の戯れのようなことで(ジェイムズとの婚約に幻滅し始めている)、ティルニー大尉には自分にそのつもりがなくても、相手に気を持たせてしまっている(だから自分は悪くない)。これらは若気の至りでよくあることだ、と自分のことを正当化しているような発言にもとれるものです。このような言葉の使い方は兄のジョン・ソープと似ていますが、ジョンは作為的に行っているのに対して、イザベラは無意識の内に行っているのが違います。結果としては、イザベラの方が巧妙なのです。それゆえ、キャサリンはジョン・ソープへの嫌悪を募らせますが、イザベルには好意を持ち続けます。 そして、二人が会話をしているところにティルニー大尉が入ってきて、彼とイザベルが恋人同士のような仲睦まじく話し合いを始めたのを、キャサリンは目にします。そして、不安になります。キャサリンはイザベルを疑うようなことはしません。ティルニー大尉がイザベルに恋をしていて、イザベルは自分では気付かずに、それを助長してしまっていると。「今日のイザベラはなんだか変だった。いつものイザベラらしくしてほしいし、あんなにお金のことばかり言わないでほしいし、ティルニー大尉を見てあんなにうれしそうな顔をしないでほしい(P.219)」と思ったので、違和感は持っていた。ただ、この時点では、心配していた。イザベラが軽薄な振る舞いをすると、ティルニー大尉も、兄も困った立場になるというもので、キャサリンが人々を好意的に表面的にしか見ていないこと、つまり子供であることがよく解ります。これは、他のオースティンの作品のヒロインたち、例えば、同じ子供でも『マンスフィールド・パーク』のファニー・プライスのように、一見おとなしいが、透徹しているようにものごとを見ているのと比べて、特異な女性と言えます。 第19章 キャサリンはイザベラの挙動に疑いを持ち始めます。ジェイムズと婚約したにもかかわらず、ティルニー大尉の好意に応じるイザベラの振る舞いは、キャサリンには無節操に映ります。キャサリンは、イザベルがジェイムズの父親から譲渡される財産が予想に反して少ないことに失望し、彼を軽視し始めていることに気付いていません。兄のジェイムズが苦しんでいるのにイザベルは心を痛めるのですが、それでも親友であるイザベルの誠意を疑うまでには至らず、もっぱら恋の火遊び相手を務めるティルニー大尉にばかり非難の矛先を向けるのです。そして、ヘンリー・ティルニーに、イザベラがジェイムズと婚約している限りはティルニー大尉に勝ち目はないので、彼が傷つく前にバースを立ち去るように言ってくれないかと頼みます。 「説得はむずかしいですね。申し訳ないけど、ぼくは兄を説得するつもりはありまぜん。イザベラ・ソープは婚約していると、兄にはすでに言ってあります。兄は自分のしていることはわかっているし、人の命令など聞きませんよ」 「いいえ、お兄さまはご自分のなさっていることがわかっていません」キャサリンはちょっと声を荒げた。「ティルニー大尉は、私の兄にどれほどの苦痛を与えているかわかっていません。兄がそう言ったわけではありませんが、兄はほんとうにくるしんでいます」 「それはティルニー大尉のせいだとおっしゃるんですか?」 「もちろんそうですわ」 「その苦痛を与えているのは、ティルニー大尉がイザベラ・ソープを好きになったからですか?それとも、イザベラ・ソープがその愛情を受け入れたからですか?」 「それは同じことではありませんか?」 「ジェイムズ・モーランド君ならその違いがわかると思いますよ。自分の愛する女性に別の男性が恋をしたからと言って、腹を立てる男なんていませんからね。それが苦痛になるかどうかは、女性の態度によって決まるんです」 キャサリンはイザベラのために顔を赤らめて言った。 「たしかにイザベラは間違っています。でも彼女は、兄に苦痛を与えるつもりはないんです。だって、イザベラは兄をとても愛しているんですもの。初めて会ったときに一目惚れして、父の同意の手紙を待っているときは、ものすごく不安で高熱を出しそうになったほどよ。ね、イザベラが兄をどれほど愛しているかわかるでしょう?」 「よくわかります。つまり、イザベラ・ソープは、ジェイムズ・モーランドを愛していて、ティルニー大尉とたわむれたわけですね」 「えっ?違います!たわむれてなんかいません!ひとりの男性を愛している女性が、別の男性とたわむれることなんてできません」 「それじゃたぶん、されほど真剣に愛していないし、それほど真剣にたわむれていないんでしょう。だから愛することもできるし、たわむれることもできるんでしょう。つまりどちらの男性も、彼女の愛とたわむれを、それぞれ少しずつあきらめなくてはなりませんね」(P.226〜228) キャサリンとヘンリー・ティルニーのイザベラをめぐっての会話を長くなりましたが引用しました。ヘンリーは、財産のイザベラがいずれ自分の兄から捨てられるだろうと見越して、冷淡ともいえる態度をとります。その一方で、イザベラがジェイムズと婚約したことについて財産をあてにした打算があって、キャサリンの考えているような純粋な愛情のみによるものでないことを遠回しに忠告します。そういう点で、ヘンリー・ティルニーは牧師ではあっても、『マンスフィーメド・パーク』のエドモンドのような純粋な人物ではなく、『高慢と偏見』のコリンズや『エマ』のエルトンといった人々に連なる性格を備えていると言えます。このようなヘンリーの忠告は、キャサリンには通じません。それは、キャサリンが、小説の虚構と現実の区別がつかないような、世間知らずの子どもだからで、人というものを表面的にしかみていないからだ、ということになります。まあ、その純粋さにヘンリーは惹かれていくわけですが。この小説は、17歳の田舎もので正直だけれど無知なキャサリンをヘンリーが教え、導くというのがひとつの太い筋となっていて、この場面は、その典型的なあらわれと言えます。恋愛小説のようなたてまえの愛情を信じているキャサリンは、したがってイザベラに対する見方も一面的です。それが見えているヘンリーは、懇切丁寧にキャサリンを教え諭すように語ります。 しかし、この一見常識的なヘンリーの説得は、視点を変えて現代の例えばジェンダー的な立場の人から見ると権力的な発想で、むしろキャサリンの言っていることの方が、当時の女性の被抑圧的な状況を踏まえているように見えてくるのではないでしょうか。例えば、ヘンリーが、ジェイムズが苦痛に感じるのはティルニーがイザベラを好きになったからか、イザベラがそれをうけいれたからかと、問うのに対して、キャサリンは、それは同じことだと答えます。この文脈では、キャサリンはイザベラを信じたいと思っているからティルニー大尉に非を押し付けたいので、そもそもイザベラにちょっかいを出したのが邪まなことで、それさえなければ、こんな事態は起こらなかったはすで、だから同じだといっている。それに対して、ヘンリーは、イザベラには、ティルニー大尉がちょっかいをだしてきても、それを拒絶すれば、問題とはならないはずだと答えるわけです。そこで、イザベラの正体をキャサリンに遠回しに伝えようとするわけです。しかし、このヘンリーの答えは利にかなっているようで、フェアではありません。というのも、そういうことが言えるのは、男女の立場が平等である場合です。仮に、反対に、イザベラとティルニー大尉の立場が逆で、婚約しているティルニー大尉にイザベラがちょっかいをだす行動をしたとしたら、ティルニー大尉が応じてもイザベラの行為はふしだらということになるでしょう。そんなことは、当時は常識として誰も疑問に思っていないし、ヘンリーもそういう常識に従っている。たしかにそうです。しかし、それを無知で世間知らずであるがゆえに、キャサリンは、我知らず明らかにしているのではないか、思えるところがあるのです。この場面を読んでいて、私は、ジェイン・オースティンが、これは敢えて、そういう意図をもって書いているように思えてならないのです。そのために、キャサリン・モーランドという人物に設定を考えたのではないか。おそらく、キャサリンをこういう人物設定しないと、こういう当時としては常識外れだけれど、正論を追求すれば当然出てくる発想をおおっぴらに語らせることはできなかったはずです。私が、こんなことを考える理由は、もう一つあります。それは悪役にされているイザベラという人物の描き方です。イザベラは単なる財産目当ての欲張り女ではないのです。若い女性としては多少軽薄なところはあるかもしれませんが、どこにでもいる、ごく普通の少女なのです。その点ではキャサリンとは変わらないのです。二人の大きな違いは、イザベラは父親がいないため、財産上の保証が何もないということです。未亡人となった母親の元で育てられて、経済的に不安定な境遇は身に沁みているはずです。愛することだって、食べられて生きていられればこそです。当時では女性が自活して職業をもって生きていくことは不可能に近かったわけですから、母親のように相手が亡くなってしまった場合に生活に行き詰ってしまうということを切実に考えてしまうでしょう。そのときに財産があるということは必要なのです。それは、たとえ貧乏に生活をしていたとしても、田舎で食べることには困ることはなかったキャサリンには、考えられないと言えます。それゆえに、後日、イザベラはティルニー大尉に捨てられてしまいますが、堕落した女として当然の報いを受けるというのではなくて、そういう自分として生きていく女性として退場していくのです。作者のオースティンにフェミニズムの思想があっということはありえないでしょう。しかし、何となく、理不尽なことを感じ取っていたではないかと思います。それは、オースティン自身の若さという点もあるでしょうし、当時の社会もフランス革命の余波が及んでいて社会が不安定であったことにも原因していると思います。その後、社会が安定して近代社会に移っていくと、個人の責任ということに転嫁されてしまって、キャサリンが図らずも露呈させてしまった矛盾は、個人の道徳にすり替えられてしまいます。オースティン自身も、この後の作品では作家として熟練していく一方で、キャサリンのような破天荒なキャラクターの人物設定をしなくなり、リアリズムという、個人の道徳にすりかえて物語を作っていく技術を練磨させていきます。したがって、この後の作品の、キャサリンよりも賢明なヒロインたちは、ある意味で悟ってしまって、キャサリンのような本質的な問いをすることがなくなってしまいます。 したがって、この会話の後で、ヘンリーがキャサリンに次のような忠告をしますが、それは慥かにもっともらしいものではあります。しかし、キャサリンが納得できないのは、分かるのです。ただし、当時の読者は、そういう読みをすることはないでしょうが。 「あなたはお兄さんの幸せを心配するあまり、ちょっと思い違いをしていませんか?すこし心配しすぎではありませんか?あなたのお兄さんにたいするイザベラ・ソープの愛情は、少なくとも彼女の品行は、ティルニー大尉に会わなければ安全だと、あなたは考えているようですね。でもお兄さんは、自分のためにもイザベラさんのためにも、自分たちの愛情がそんなふうに思われることを喜ぶでしょうか?いつものふたりでないと、お兄さんは安心できないんですか?ふたりの愛情は、ほかの男性から誘惑されるとすぐにぐらついてしまうんですか?緒人さんはそうは考えていないでしょうし、あなたにも考えてほしくないでしょう。ぼくはあなたに「心配するな」とは言いません。現にあなたは心配しているんですからね。でも、できるだけ心配しないほうがいい。ふたりが愛し合っていることをあなたは疑っていないんでしょ?それなら大丈夫、ふたりの間にはほんとうの嫉妬なんて生ずるはずがない。絶対に大丈夫、たとえ喧嘩をしても、その喧嘩は長続きするはずがない。愛し合っているふたりなら、お互い相手のことはわかっているはずです。あなたにはわからなくてもね。愛し合っているふたりなら、自分が相手から要求されていることは何か、相手が我慢できる限界はどの程度か、ちゃんとわかっていますよ。限界以上に、つまり、相手を怒らせるまでからかうことはしませんよ」(P.229) 第20章 キャサリンは、いよいよ、ノーサンガー・アビーに向けて出発します。アレン氏に送られて、キャサリンは早朝にミルソム・ストリートの館を訪ねます。そこで、一家と朝食をともにしてから出発するのです。朝食で、キャサリンは、第16章でディナーに招待されたときと同じように窮屈な思いを繰り返します。ここでまた、繰り返しがありました。この窮屈な食事は、ノーサンガー・アビーに着いてからも繰り返されます。その繰り返しのたびに、キャサリンは将軍に対する違和感を、最初は気付かなかったのが、繰り返すたびに自覚し、疑念を抱いていくことになります。その疑念自体は、ゴシック小説に諸靴はされた妄想のよるもので誤解なのですが、別の方向では、将軍の下心が不審な態度となって表われたものだったということになります。それは、この先の物語で明らかになってくることです。 第16章では、このディナーの模様については、具体的なことはすべて省略して、キャサリンがそう感じたということを、後から回想するように記述しているだけです。彼が非の打ち所のないほど愛想が良く,善人で,全体的にとても魅力的な人物に見えるのに、なぜかヘンリーやエレノアが父親の前では口数が少なくて元気がなく、キャサリンも居心地が悪いのだろうかという疑問を抱いたのでした。将軍が悪いはずはないので、それは自分が愚かだからと理由づけしていた。しかし、オースティンは、このディナーの模様については意図的に隠蔽していました。それが、この朝食では、その場面が素描されます。 ティルニー将軍は、19世紀の転換期の典型的な家庭の暴君で、ヘンリーやエレノアといった子どもたちには抑圧的な父親です。将軍は、キャサリンに対して、洗練された物腰で慇懃に振る舞います。たとえば、「どうぞこれを召し上がってください」と彼女にひっきりなしに食べ物をすすめ、「お口に合えばよろしいのですが」と気を遣います。しかも、朝食で出されたものは、キャサリンが朝食で食べたこのないご馳走ばかりで、キャサリンがお客であることを一瞬も忘れさせないようなものでした。端的にいえば、いかにも歓待していますといわんばかりの、押し付けがましいものだったと言えます。だから、キャサリンは、自分はこんな丁寧なもてなしを受けるような人間ではないと思うし、どう返事していいかわからなかった。というようになります。 また、将軍の子供に対する抑圧的な面は、例えば異常なほど神経質に時間を守ることに固執する様子にあらわれます。彼は、ティルニー大尉がなかなか現れないのでいらいらし、やっと大尉が二階から下りてくると、そのだらしなさを激しく非難します。キャサリンの目の前で、しかも、ティルニー大尉は彼の小言を黙って聞いて、弁解はいっさいしなかった。これは、それまでのティルニー大尉の印象とは違います。ということは、彼の前では従順であるように強いられているということになります。キャサリンにとっては、自分の父親とはまったく異なったタイプなので、そういう状況が理解できず、ただ、何となく居心地が悪いと感じることしかできません。 朝食を終えると、2台の馬車に分乗してノーサンガー・アビーに向けて出発です。途中で休憩したあと、キャサリンは、ヘンリーと二人でオープン型のカリクル馬車に乗ることになります。そこで道中は一気に楽しいものになりました。キャサリンは、ノーサンガー・アビーに招待されたときに、その古めかしい名前から、ゴシック小説の世界を想像して胸をときめかせたのでした。それを、ヘンリーは煽るように、馬車でキャサリンにゴシック小説まがいの作り話をして、彼女に恐怖を植え付けてからかいます。馬車の旅が終わりに近づくと、キャサリンは曲がり角ごとに、ゴシック様式の高い建物が鬱蒼とした森のなかにそびえ立っているのを期待するのですが、実際のノーサンガー・アビーは、背の低い現代的な建物だった。期待外れに対して、キャサリンは何の障害も、恐怖も、厳粛さもなしに到着できたのは、奇妙で、辻褄が合わないという思いを抑えられません。 オースティンは、この道中のことは、キャサリンのこと、彼女が楽しかったか、何を思ったかを記述していて、ノーサンガー・アビーに対するゴシック小説の舞台に入っていくような期待を募らせ、それが幻滅に変わっていくプロセスとして描いています。つまり、ここではキャサリンの主観的な風景を描いています。オースティンの他の作品、例えば、『マンスフィールド・パーク』で、主人公のファニー・プライスたちがサザトン・コートを訪問したときの描写は、サザトン・コート周辺の風景を詳しく描写し、馬車が近づくにつれて、建物の建築様式や角度によって様相が変化していく移り行きを詳細に描いています。また『高慢と偏見』ではエリザベスが叔父夫婦と、ダーシーのペンバリーの館を訪ねるときも、同じように詳しく描写しています。そういう風景のくわしい描写は、この道中ではなく、ひたすらキャサリンの描写に終止しているのが、この作品の特徴的なところです。それは、この作品が、キャサリンが虚構と現実を同じように見てしまうという主人公で、彼女が主観的に見ているというところで、この物語の世界が作られているからです。前にも触れましたが、外形的な事件とキャサリンの内面の動きの境界が曖昧で、それだけに、この小説では客観的な描写に彼女の内面、ときに作者の個人的な思いの吐露が混入しているのです。その反面、他の作品にあるような客観的な描写の占める割合が少なく、書かれているのはキャサリンの視界のなかという狭い世界に結果的に、なってしまっているのです。 第21〜23章 部屋に案内されたキャサリンは、すぐに食事が始まるので、とるものもとりあえず、道中で着ていた乗馬服から室内用のドレスに着替えなければなりません。その部屋は、道中の馬車でヘンリーが彼女を恐がらせようと語ったようなものとは、全く感じが違うものでした。 キャサリンはその部屋をひと目見ただけで、ヘンリーが彼女を怖がらせるために話して聞かせた部屋とは、全く感じが違うことがわかった。異様なほど広くはないし、タペスリーもビロードもなかった。壁には壁紙が張られ、床には絨毯が敷かれ、窓も完璧で、一回の窓と同じように明るかった。(P.247) この部屋の説明の文章ですが、とくにゴシック小説にでてくるような廃墟のようなものではなく、現代的なふつうの部屋であるというのを、「…でない」という否定を積み重ねて説明しています。この説明の仕方は小説の初めの方で、この物語のヒロインであるキャサリンを紹介するときと同じ語り方です。キャサリンの紹介は、従来の小説のヒロインとは違って平凡な、ごくふつうの少女であることを明らかにする者で、ヒロインの要素をひとつひとつ否定していきました。その手法を、ここでも使っているのです。実は、この前の章でノーサンガー・アビーに到着した時にも、この書き方を使っていました。それらのことから、作者のオースティンは、このような否定を積み重ねる書き方を意識的に用いていることが解ります。考えてみると、この小説の中で、このような書き方をしているのは、ゴシック小説で使われる要素をこの物語では、パロディとして敢えて持ち出して、そんなわざとらしいのではない、この小説のヒロインや舞台を説明するのに使っているのです。したがって、ゴシック小説の大げささへの皮肉として否定的な言辞を使っているのは明らかです。でもそれだけではない。例えば、ここでの部屋の紹介は、単に作者が客観的に場面の説明をしているのではないのです。この説明は、キャサリンの視線でもある。つまり、キャサリンは虚構と現実を一緒くたにしてしまう。しかも、来る途中でヘンリーからあることないこと散々吹き込まれているので、期待感に溢れかえっている状態です。その視線で、タペスリーはあるだろうか、ビロードはあるだろうか、と期待のものを探し回る。それを現実が期待を裏切る、と言うプロセスをひとひとつ追いかけて行っているのです。小説冒頭のキャサリンの紹介の場合は、ゴシック小説を楽しみにしている読者の視線にたって紹介している、そういう動きがあると思います。さらに例えば、この部屋についてであれば、部屋は期待したものとは違って現代的で快適な部屋だったと簡単に説明できてしまうのです。それにもかかわらず、このようにひとつひとつ、具体的要素を否定するように紹介していくと、必ず説明し残してしまうものがある。実際に、キャサリンはこの時に古い箪笥に気付かず、後刻、ベッドに入ろうとして気がつくのです。そういう、もしかしたら、まだ何か残っているかもしれないという余韻を持たせている。それが、物語に謎を残すように、先の展開への興味を読者に喚起させることになっていると思います。また、ヒロインの紹介のところでは、その紹介し残したことがあるかないか分かりませんが、キャサリンというヒロインは、一見平凡な女性だけれど紹介しきれない何かを持っている人なのだということを暗示することになっていると思います。 さて、ゴシックロマンスを愛読するキャサリンは,しばしばゴシックロマンスの舞台となる修道院がティルニー家の現在の屋敷であることに興味津々である。しかも、彼女の好奇心を煽るようにヘンリーからゴシックロマンス風のつくり話を道々ふきこまれました。しかし、いざノーサンガー・アビーに到着してみれば、キャサリンの期待は裏切られ現代風の快適な空間になっていました。しかし、彼女の期待はやむことなく、何かしらゴシック小説風の出来事に出会うものと想像をたくましくするのです。しかし、その都度期待はずれにおわります。 ます、到着してまもなく、部屋に案内されて、急いで食事のために着替えをしなければいけないときに、寝室の隅に大きな衣装箱が置かれているのに気づきます。彼女は、次のように思います。 「ほんとに変だわ!こんなものがあるとは思わなかったわ!ものすごく大きな重そうな箱!いったい何がはいっているのかしら?なぜこんなところに置かれているのかしら?しかも、人目に触れないように部屋の隅に押し込んである!中を見てみよう。どんなことをしても見てみよう。今すぐに、外が明るいうちに、夜まで待っていたら、ろうそくがなくなってしまうわ」(P.248) 食事の時間は迫っています。早く着替えなければなりません。将軍は時間に煩いので、遅れることは許されません。この辺の書き方は、まるでスパイ小説のサスペンスを彷彿とさせるもので、オースティンのペンは水際立っています。きっと楽しんで書いているんだろうなと思わせる。キャサリンは恐怖と好奇心をますます募らせて、決然として箱の蓋を開けます。おそらくは、ラドクリフ夫人の『森のロマンス』に書かれている、「奥のほうに置かれた大きな箱のほうへ彼が近づいて行き、中身を調べようと蓋を開けると、目にしたのは人間の骸骨だった」というような箇所の影響を受けて、キャサリンは恐ろしい物を発見すると予想した。しかし、実際に中に入っていたのは、畳んだベッドカバーにすぎなかった。ここでオチがつきました。それをエレノアに見つけられて、恥ずかしい思いをします。 次は食事の後です。部屋に戻ったキャサリンは背の高い古風な黒い飾り箪笥が置かれていることに気がつきます。鍵の掛かった引き出しをあけて、その奥から出て来た巻紙を発見したとき、彼女の心臓はどきどきし、膝はがくがくし、頬は青ざめるちという状態でした。その書かれている文字を読もうとして、蝋燭の芯を切ると、火が消えてしまい、暗闇のなかに取り残されたキャサリンは、恐怖に慄きながらも好奇心に駆られ、悶々と夜を過ごすのでした。彼女は、これがゴシック小説の題材としてよく出てくる「隠された古文書」であると、信じて疑わなかったのでした。しかし、翌朝確認すると、それは、洗濯物の請求書にすぎなかったのでした。(ここで第21章から第22章に、章をまたいで、読者の好奇心を書き照るようにして、興味をさきへひっぱる手法など、まるで大衆小説で、ここでもオースティンは楽しんで書いていることが想像できます。)作者オースティンのここでの筆致は、キャサリンの視点でのサスペンス、それを皮肉を込めておもしろおかしく見る客観的な視点を織り交ぜて、描写しています。読者もワクワクしながら、思わず微笑がこぼれるところです。 その極めつけがティルニー将軍にたいして抱きはじめた疑惑です。もともとは、キャサリンが将軍に感じた違和感でした。その違和感の内容とは、将軍が非の打ち所のないほど愛想が良く、善人、全体的にとても魅力的な人物に見えるのに、なぜヘンリーやエレノアが父親の前では口数が少なくて元気がなく、彼女自身も居心地が悪いのだろうかとい居心地の悪さからでした。最初のうち、将軍が悪いはずはないので、それは彼女自身が愚かだからと理由づけすることで納得させていました。ノーサンガー・アビーでは,キャサリンは将軍をもっとしっかり観察する機会をえることができました。なぜあんな魅力的な人が子供たちに威圧的なのか、なぜ大袈裟なほどていねいなのに,みんなが彼を恐れるのか。彼女には彼が謎である。それがゴシック小説につきものの疑惑のある人物です。まず、将軍がなかなか屋敷の中を案内してくれないという不満を募らせながら、そうするには何か隠された秘密があるのではないかと考えるようになったことがその発端となりました。その後、将軍が亡き妻の好んだ散歩道を避けるとか、亡き妻の肖像画を自分の部屋や居間ではなく娘の部屋に飾っている事実などを知る。そして、これらの事実から、彼に対して次第に嫌悪感を覚えるようになっていきました。亡き妻によく似た肖像画が夫に大事にされていないのは,彼が冷酷な夫である証拠に思えるし、ティルニー夫人の部屋をなかなか見せてもらえないキャサリンは、将軍が良心の呵責に苛まれて、妻の臨終以来、その部屋に入っていないのだと早合点してしまいます。パンフレットを読むのだといって将軍が夜遅くまで起きているのも、別の目的、すなわち、みなが寝静まったあと幽閉した妻に食物を運ぶための理由に思えるというのです。つまりキャサリンは、将軍を、『ユードルフォの謎』に登場するモントーニのようなゴシック的悪漢だと想像するのである。将軍が、眉をしかめて、黙って、居間を行ったり来たりしている姿を見たキャサリンは、「それこそモントーニの様子であり態度」だと断定するのです。 このことは、キャサリンの妄想に近い目ら映った将軍の姿ですが、しかし、そのキャサリンの思い込みを差し引いてみても、将軍という人物は権威主義的な性格であることは間違いないようです。将軍は家庭の中でいわば暴君として君臨し、その権力を振りかざし横暴に振る舞っていると推測できます。そして、ここで注目すべきは、子供たちの中でも、その直接的な犠牲となるのが息子たちではなく娘であるという事実です。長男のティルニー大尉はそんな父親のことを意に介していないだけでなく、軍隊生活のためにほとんど父親と一緒に過ごすこともありません。次男のヘンリーもノーサンガー・アビー近郊の教区の牧師館に住んでいて、いつも父親と一緒にいる訳ではないのです。こうした兄たちとは対照的に、娘であるエレノアには逃げ場所がないのです。それに加えて、彼女を守ってくれそうな母親もすでに失っているため、そんな父親と常に二人きりで過ごさざるを得ないのである。彼女の時間のほとんどが父親の便宜のために費やされていたことは容易に想像され、そのために娘であるティルニー嬢には自由な時間がほとんど与えられていなかったのではないかと考えられる。それは、例えば、以前に散歩の誘いをすっぽかしたキャサリンが謝罪にバースの館を訪れた際に、父親と一緒に散歩するために居留守をつかってまでキャサリンとの面会を避けざるをえなかったことにも表われています。彼女の置かれたこの状況は作品の冒頭で語られるキャサリンのものとは対照的な映ってきます。この二組の父娘を対比することでエレノアの置かれた状況を際立たせる役割も果たしていると言えます。このティルニー嬢の置かれた状況は、まさにゴシック小説の囚われのヒロインと呼ぶことさえできるのです。それゆえ、キャサリンの妄想は、あながち的外れでもない。 作者オースティンは、将軍やエレノアの内面は、ほとんど語ってくれません。将軍に関しては、キャサリンにノーサンガー・アビーを見せる際に、何を自慢したかったといった表面的なことは語ってくれていますが、そもそも、こんな権威主義的な人、おそらくお山の大将でいたいような人が、自分の権威の箔付けにもならないキャサリンを歓待する動機が不明です。子供たちの友人だから親切にしてあげようなどと考える人物でないことは明らかです。ですから、キャサリンは将軍に疑惑を持ちますが、読者もいささか不審に思うはずです。キャサリンが呑気に妄想に耽っている間に、その裏で、実は物語が進行している。そして、語られない謎が最後に明らかにされる。このような点が、この小説が単なるゴシック小説のパロディに終わっていない、一筋縄ではいかないところです。 第24章 キャサリンは、だんだんと行動的になります。自ら謎を解明しようと探索を始めるのです。まずは、その機会を窺います。将軍に見つかってはならないからです。将軍が早朝の散歩をしている間に、エレノアの部屋に飾ってあるティルニー夫人の肖像画を見せてもらいます。そして、夫人の部屋に案内してもらいますが、その直前にあやうく将軍に見つかりそうになり、すんでのところで部屋に逃げ帰るのです。キャサリンは、これに懲りることなく、自分で自分の恐怖心を募らせ、将軍の正体を暴くことを半ば期待しながら、ついに、ひとりで屋敷を探索し、ティルニー夫人の部屋にたどり着きます。この行為は,晩年の作品『エマ』において単なる勘違いにより妄想を構築し,ハリエットを振り回し,ジェイン・フェアファックスを傷つけ,さらに自らを窮地に追い込むエマを彷彿とさせる無謀な行為です このような小説の読みすぎで、現実か正しく見えなくなっているキャサリンの姿は、ロマンスをたくさん読みすぎ手、現実の世界との区別がつかなくなり、滑稽な過ちを繰り返す人物の物語である『ドン・キホーテ』をなぞらえている、と廣野由美子は指摘しています。キャサリンが将軍を『ユードルフォの謎』に登場するモントーニのような悪漢だとして、その正体を暴こうと行動するのは、自分が正義のために悪と戦う勇敢な騎士であると想像したり、田舎娘ドゥルシネーアを美しい貴婦人として崇拝したりするなど、現実の人間をロマンスの登場人物に仕立ててしまうドン・キホーテの習性に通じる傾向が、見られるといいます。そして、錯誤を繰り返し続けたドン・キホーテは、ついに結末で死を迎える前に自分の狂気に目覚めたように、『ノーサンガー・アビー』の終盤でも、「ロマンスの幻影は終わり、キャサリンは完全に目覚めた」という地点に至るのである。このように、キャサリンのノーサンガー・アビーへの旅は、ドン・キホーテの遍歴のパターンを模倣することによって、空想的物語に洗脳されて現実を見る目が曇ってしまった読者の姿を諷刺していると言えます。さらに、廣野は指摘します。同様の試みとして、先行のシャーロット・レノックスによる『女キホーテ、あるいはアラベラの冒険』と比べます。フランスのロマンスを大量に読み、その世界で頭がいっぱいになった女主人公アラベラは、ドン・キホーテが自らの思い姫のために命を捧げるべきだと思ったと同様に、アラベラに魅せられた男性は、彼女のために試練に遭う務めがあると思い込んでしまいます。つまり、騎士道精神を貫こうとする男性ドン・キホーテではなく、彼に崇拝される女性ドゥルシネーアの側の立場に、彼女は身を置くのである。アラベラは貴族の娘で、聡明な美女です。それに比べると、『ノーサンガー・アビー』の場合、そもそも人物設定自体からして、キャサリンはヒロイン失格です。キャサリンはアラベラとは、自分をヒロインに相応しい人間であると自惚れてはいない点で大きく違います。キャサリンは、ただ物見高い好奇心からロマンスに似た出来事や状況に遭遇したいと、恐いもの見たさにワクワクしているに過ぎません。このように、ロマンスの精神自体が骨抜きになったキャサリンの願望は、先行する『ドン・キホーテ』や『女キホーテ、あるいはアラベラの冒険』の主人公とちがって、ロマンスを消費する、現代の読者に近いものです。 キャサリンがようやく辿り着いたティルニー夫人の部屋は期待を裏切り、明るく感じの良い部屋でした。そして、将軍がキャサリンを案内しなかったのは、単にこの部屋が館の端にあるからであることを理解します。それでもキャサリンは、将軍が証拠を残すはずはないと思い込むのでした。しかし、部屋を探り歩いていたキャサリンは、その時、予定より一日早く帰宅したヘンリーに見つかってしまいます。ヘンリーは、キャサリンの驚きや戸惑いから、彼女の妄想を見破り、ティルニー夫人の病と亡くなったときの様子を説明し、次のように諭します。 「ぼくの理解が正しければ、あなたは、僕がとても口にできないような恐ろしいことを考えていたんですね。ねえ、ミス・モーランド、自分がどんなに恐ろしい疑惑を抱いていたか、考えてもごらんなさい。いったい何を根拠にそんなことを考えていたんですか?ぼくたちが住んでいる国と時代を思い出してください。ぼくたちはイギリス人でキリスト教徒です。あなたの知性と理性と観察能力に相談してごらんなさい。そんなことがあり得ると思いますか?自分のまわりでそんなことが起きると思いますか?現代の教育を受けた人間に、そんな残虐行為ができると思いますか?現代の法律が、そんなことを黙認すると思いますか?今のこの国で、そんな残虐行為が誰にも知られずに行われると思いますか?社交も郵便もこんなに発達し、自分から進んでスパイ活動をする隣人たちに囲まれて生活し、道路網と新聞の発達のおかげで、何でも明るみに出てしまう今のこの国で、そんなことがあり得ると思いますか?ねえ、ミス・モーランド、なぜそんな恐ろしいことを想像したんですか?」(P.299〜300)) キャサリンは、思いを寄せていた男性から、このように厳しい調子で叱責をされて、ようやく目が覚め、そして自身の愚かさを恥じて、心から反省するのです。 一方、ヘンリーは、ゴシック小説かが日常からかけ離れた荒唐無稽なことを題材にしていること、そのような作り話と現実との区別ができないことの愚かさを批判していますが、その論調に対して多少の違和感を覚える人はいるかもしれません。残虐事件は宗教や教育や法律の力によって食い止めることはできない、むしろ、残虐事件を引き起こしていると現代では認識されています。だから、社会が発達したとしても防ぐことができものでないことを、現代の我々は知っているからです。イギリスがほかのどの国よりも政治・経済・文化が発展した安全な場所であると主張するヘンリーの口調は、美化しすぎでかえって現実が見えていないように感じられます。しかも、当時のイギリスではン句名の機運が高まり、各地で暴動が頻発していたことは第14章の散歩の時の会話のところで見た通りで、ヘンリー自身が語っているはずです。したがって、ヘンリーの現実認識は、すこし甘いといえます。実際、ヘンリーの不在中、キャサリンは疑惑の張本人である将軍から突然追放されるという虐待をうけることになるのです。このとき、キャサリンはゴシック小説のヒロインのような立場に立たされると皮肉な事態が起こります。 第25章 夢から覚めたキャサリンの後悔と反省が始まります。しかし、オースティンの小説のヒロインで、これほどストレートに自身の非を認め、謙虚に反省してしまう、しかも、一時的には落ち込むけど、ポジティブに立ち直る逞しさも持っている。まるで、聖なる愚か者です。そういう点では、キャサリンという人物は非現実的なところがあります。無知ゆえの滑稽な行動をすることはありますが、人間的な欲がない薄っぺらいところが、この反省がいかにも模範的というのか、教科書を読んでいるようなものです。それが、この作品についてオースティンの若書きと感じられるところでしょうか。 そして、キャサリンの反省は、そのままゴシック小説やそれを読み耽る読者への批判に連なっていきます。この見解は、キャサリンの心の声のようにかかれていますが、キャサリンのものか、作者のものか区別がつかなくなっています。 あれはすべて自分の妄想の産物なのだ。何もかも恐ろしがるのだと決意した想像力が、取るに足らぬ出来事の一つ一つに、むりやり重大な意味を帯びさせのだ。恐怖を渇望する心がノーサンガー・アビーに行く前から芽生え、その目的のために、すべてのことをねじ曲げてしまったのだ。ノーサンガー・アビーはどんなお屋敷かしら、想像したときの自分の気持ちを彼女は思い出した。バースを去る前にすでに頭がのぼせ上がって、この愚行の準備がすっかりできていたのだ。そして、どうやらそのすべての原因は、バースで読みふけっていた小説の影響ではないかと思われた。 ラドクリフ夫人の小説はすごく面白いし、その模倣者たちの小説もとても面白いけれど。たぶんああいう小説には、人間性の忠実な描写を期待してはいけないのだ。少なくとも、イングランド中央部に住む人間の忠実な描写を期待してはいけないのだ。アルプス地方やピレネー地方のことなら、その松林も悪徳も忠実に描写されるかもしれない。イタリアやスイスやフランス南部なら、ああいう小説に描かれたような恐ろしいことが、実際にたくさんあるかもしれない。よその国のことまで疑うつもりはない。いや、自分の国でも、北の果てや西の果てのことはわからない。でもイングランド中央部では、夫から愛されていない者といえども、国の法律と時代の風俗習慣によって、生命の安全はある程度保証されているはずだ。殺人は絶対に許されないし、召使は奴隷ではないし、毒薬や眠り薬を、胃腸薬みたいに薬や簡単に買うことはできない。アルプス山中やピレネー山中には、善と悪が入り混じった人間はいないのかもしれない。そういう山中には、天使のような汚れなき人間と、悪魔のような邪悪な人間の二種類しかいないのかもしれない。でもイギリスはそうではない。イギリス人の心と習慣は、みんな同じというわけではないが、たいてい禅と悪が入り混じっているとキャサリンは思っている。だから、ヘンリー・ティルニーとエレノア・ティルニーの性格に多少の欠点が現れたとしても、彼女は少しも驚かないだろう。それに、ティルニー将軍の性格にかなりの欠陥がみとめられたとしてね、すこしも不思議はない。彼女は将軍にとんでもない濡れ衣を着せてしまったが、その疑惑は晴れても、いくら考えても、将軍が心のやさしい立派な人だとは到底思えなかった。 キャサリンは、こういういくつかの点で気持ちの整理をし、これからはしっかりと分別をもって判断し行動仕様と決心した。これかに自分がなすべきことはただひとつ、自分を許して、いままで以上に幸せになることだ。(P.303) この引用を読む限りでは、キャサリンが内省的で感情に左右されることなく、理性で論理的な思考をしていることがわかります。例えば、ティルニー将軍に対する評価などは、濡れ衣を着せたのは悪いが、そのこととは別に、彼は心のやさしい立派な人物ではないと冷静に判断しています。自身の愚かしい行動について、冷静に分析できている。ここでのキャサリンは冒頭で紹介された無知な少女とはまったく異なる女性に変貌しています。これはキャサリンの成長と考えることができるのでしょうか。私には、何か、すこし無理があるように思います。 ただ、それで、キャサリンというヒロインは一貫して、ポジティブなたくましさのようなものを備えている人であり、それはすぐに卒倒したり、悲しみのあまり世をはかなんだりするような、小説のヒロインとは異なる、その意味でアンチ・ヒロインです。最初のころは、アンチ・ヒロインということが否定の積み重ねでネガティブに描かれていたのが、ここでは反転して、ポジティブに描かれるように変わっています。なお、アメリカのハウエルズという作家は「キャサリン・モーランドは馬鹿な女であるが、とても愛嬌がある。そして、その誠実さ、正義感、他人を信頼する寛大さ、試練をこらえる忍耐力ゆえに、敬意を払うべき馬鹿な女である」と述べ「彼女は純真さと優しさという点で秀でていて、空想にふける愚かさにもかかわらず、分別の代わりとなる立派な心の持ち主である」と言っています。ここでハウエルズは馬鹿な女という本来はネガティブな言葉を、キャサリンを形容する中でポジティブな意味合いで使っています。つまり、この小説では価値の反転が内包されている。その転換点が、この第25章になっていると、私には思えます。しかも、この後で「ロマンスの世界の恐怖が去ると、すぐに日常生活の心配事が始まった。」(P.304)とわざわざ断っているのですが、ここから、ゴシック小説のパロディから、19世紀の心理小説あるいはリアリズムに様相が一転します。しかも、これまでのゆっくりとしたストーリー展開で、毎日の生活を克明に追いかけていたものが、ストーリーが急転し物語のテンポが速くなります。つまり、上の引用は、その意味でキャサリンの内心の声であるとともに、作者オースティンの読者に向けての宣言でもあるのではないかと思います。 その「日常生活の心配事」の始まりを告げたのは、兄のジェイムズからの手紙で、イザベラの裏切りと婚約の解消を告げるものでした。このときのキャサリンも、理性的で建設的です。一時的な悲しみにとらわれますが、一番傷ついたのは兄であるからと、兄を心配し、イザベラへの行動の動機が野心にあることに気付き次のように言います。 「そういえば、思い当たることがあるわ。ふたりが婚約したあと、父からの贈与の額を知らされたとき、イザベラは、額が少なくてがっかりした様子だったんです。あのときのことは忘れられません。わたし、こんなに人を見損なったのは生まれて初めてです。」(P.313)) と、友人に失望したにしては冷静なのです。従来の小説のヒロインであれば、打ちひしがれて、なみだながらに支離滅裂に失望を口にするのでしょうが、キャサリンはそうでなく、そういうものとして心配するヘンリーに対して次のように返答します。 「いいえ、そんなことありません。そういう心境でないといけませんか?私とても傷ついたし、とても悲しいけど、みなさんが思うほどひどいショックは受けていません。もうイザベラを愛すことはできないし、もう手紙ももらえないし、もう二度と会うこともできないと思うと悲しいけど、ほんとに、みなさんが思うほどひどいショックを受けてはいません」(P.314) そんな彼女について、いつも上から目線で相手をしていたヘンリーをして次のように言わせるのです。 「あなたはいつも、人間性の名誉となるような実に立派な感じ方をしますね。みんな自分を知るために、あなたのそういう気持ちをよく研究すべきですね」(P.315) 第26章 ヘンリーが牧師を勤める教区であるウッドストンへの小旅行です。日帰りですが、馬車で片道3時間弱の工程で、牧師館とまわりを散策して、その日のうちにノーサンガー・アビーに戻るという工程です。これは、ノーサンガー・アビーへの道中と、その館の紹介の繰り返しということになります。おなじような馬車での道中と初めての館を案内してもらうのですが、キャサリンが現実に生きる女性に変化した後ということで、臨む姿勢が違うものとなり、その描き方が異なってきています。実際、キャサリンにとってノーサンガー・アビーに対しては、ゴシック小説の呪縛が解けたしまった後では、見方がかわって、それに憧れていた自分を思い出す後悔を誘うものとなっていたのでした。 ノーサンガー・アビーの建物も、もう普通の建物と何の変わりもない。むかし修道院だったと思っても、もう何も感じない。この建物のおかげで愚かな想像をして、愚かなことをしてしまったという、苦い思い出がよみがえるだけだ。なんという変わりようだろう!こういう古い屋敷にあんなに憧れていたのに!キャサリンの塑像力にとって今いちばん魅力的なのは、快適で素朴で、居心地のいい牧師館だった。(P.322) こんどの道中では、ノーサンガー・アビーへの道中ではまったくなかった風景の描写が少しだけ挿入されています。ウッドストンの村をすてきな村だとキャサリンは思います。ここでのキャサリンは、以前とちがって虚構の思いに閉じこもっていないで、現実の風景を見ています。それに伴って、小説の描写でも村の風景の描写が加わってきている。それはまた、キャサリンはヘンリーとの結婚を実際に考えるようになってきている。それによって、もし結婚したとすれば、この村で、そしてまた、これから訪ねる牧師館で生活していくことになるので、そういう意識が、キャサリン自身には明確ではないのかもしれませんが、ここでの視線に加わっていると思います。 牧師館を案内する将軍には下心があって、この時点では、ヘンリーとキャサリンの結婚を目論んでいて、牧師館をキャサリンの気に入るように印象付けようという意図が、将軍の発言の節々に感じられます。おそらく、それに気付いていないのはキャサリンだけなのです。他方で、キャサリンは、そんな動きとは別に、牧師館を自分のいたフラトーンの牧師館と比べて、つまり、住んでいる感覚で見ているようです。部屋の感じとか、整理されているとか、窓からの眺めといったことを見ているのです。ノーサンガー・アビーを案内されていたときの、ゴシック小説のような古びたものの残滓を探して、つまり、妄想との一致点を探すのみで、そこで生活している空間として見る事をしなかったのと大きな違いです。 他方では、将軍については疑惑が晴れたところで、現実の将軍の実像が徐々に明らかになってきます。前述の、キャサリンに牧師館を案内しているときの下心のあらわれもそうです。その象徴的なものとして、牧師館への小旅行について、牧師館でディナーを取る提案をして、食事は家にあるもので十分だから特別な用意をしなくてもよいとヘンリーに言います。ヘンリーはそれを受けて5日前から準備しに帰る。実際に出されたのは豪華な料理でした。キャサリンは,将軍の言葉を真に受けて、なぜヘンリーがそんなに早くから準備をしなければならないのか、また、将軍は、自身の言葉とは裏腹に、豪華な料理を見ても全然驚かないのを疑問に思います。 しかし、キャサリンは未だ中途半端です。イザベラが兄ジェイムズを捨ててティルニー大尉にはしったことについて、ヘンリーとエレノアは兄であるティルニー大尉がイザベラと結婚するはずがないと確信しているのは,イザベラにはお金がないということに基づいているのです。そういう、ティルニー家の結婚の方針を聞かされて初めて、キャサリンはジェイムズの年収を聞いてからイザベラの気持ちが変わったことに気づいたのでした。しかし、イザベラと同じく財産も地位もない自分は、はたしてヘンリーと結婚できるのだろうかということを、キャサリンは少しは自分のことに思いを巡らすのですが、将軍が特別な好意を示してくれており、金の問題には寛大であるという彼の言葉を真に受けているので、子供たちが誤解していると考えてしまう。そのことは、ウッドストンの牧師館のディナーについて将軍の言葉はいった通りに受け取るものでなく、裏があるということに、キャサリンは気付いていないのです。そして、自分がなぜノーサンガーに招待されたのかという疑問を抱くまでに到らないのである。それが、この後でキャサリンの身の上にふりかかる事態の不気味な伏線となっているのです。敢えて言えば、ゴシック小説の妄想ではない、恐怖の現実がひたひたと忍び寄っているのです。 第27章 翌朝、思いがけずイザベラからの手紙が届きます。ティルニー大尉との結婚に成功しなかったイザベラは、その手紙で、ジェイムズに取りなしてくれるように依頼してきたのです。その手紙は冒頭から二度手紙を受け取っていることと、それに返事をしようと思って毎日ペンを取ったが、毎回何かしら邪魔が入ったという言い訳から始まります。これは、バースでの別れのときに手紙を書くことを約して、キャサリンから手紙を書き送ったのに対して、放っておいて、自分の都合のいい時にだけ手紙を書くという、はなはだ自分勝手なことが明らかです。キャサリンにとっては、兄に対して自身の行動の誤りを認め、謝罪をするべきあるのに、「あなたのお兄様は、私がこれまでに愛した、いいえ、私が愛することのできたただ一人の男性です」「ティルニー大尉とあなたのお兄様は、えらい違いね!」と、抜け抜けと書いてきて、キャサリンにジェイムズの誤解を解くよう、とりなしてほしいと書いてくるのです。そこから話題が、自分に言い寄ったティルニー大尉への悪口、帽子の流行についての噂、自分はジェイムズの好みの色の服を着るつもりだという決意等脱線して言って、次元の異なる話が入り乱れます。しかもそのなかに、「昨夜、ホッジズ家の人たちといっしょに劇場へ遊びに行った」という情報が織り込まれているのですが、以前イザベラは「チャールズ・ホッジズは私と踊ってほしいと、死ぬほどせっつくだろう」と口走ったことがあるため、この男性との交際の可能性も視野に入れていることが暗示されているのです。このように、イザベラの最後の手紙には、手練手管を講じる女性の不誠実さ、軽薄さが隅々まで表れているものです。手紙の最後で、「今は(お兄様のお気に入りの)紫しか身に着けていないけれど、ひどい見栄えであることは分かっている」と始まります。この言葉は何とも皮肉で、キャサリンはおそらく現実のイザベラが紫など身に着けていないであろうことも、もし身に着けていたとして、自分に紫が似合わないなどとは思ってもいないことも感じ取っています。そして、イザベラはできる限り「着飾った」はずのこの手紙で、キャサリンの心を動かすことができると思っているが、事実それはあまりに「ひどい見栄え」の手紙であるがために、「いっそ出会わなければ良かった」とまで言われてしまうので、イザベラの言葉はそのまま自分の状況を言い当てていると
も受け取れるのです。 キャサリンは、この手紙を読んで矛盾と嘘だらけの手紙と断じ、こんな見え透いた戦略にはだまされないと、イザベラ恥ずかしく思い、彼女の求めには従いません。 そして、ヘンリーとエレノアに、キャサリンは次のように思います。 「イザベラのことはこれでおします!彼女とのおつきあいもこれでおしまい!彼女は私のことを馬鹿だと思っているのね。そうでなければ、こんな手紙を書けるはずがないわ。でもこの手紙のおかげで、私がどう思われているのか解ったし、イザベラがどういう人間かわかってよかったわ。何もかもはっきりしたわ。イザベラはうぬぼれの強い浮気女なのね。そしてその手練手管がうまくいかなかったのね。彼女は私の兄のことも私のことも、なんとも思っていなかったのね。あんな人と知り合わなければよかったわ」(P.331) キャサリンは、イザベラの本性を知り、嫌悪感を覚えるのです。 しかし、イザベラはゴシック小説の場合とは違って、ことさら堕ちた女として罰を受けることはなく、たんに物語から退場していくだけです。つまり、オースティンはイザベラを、「ふつうの女性」として、こういう女性は周囲を見渡せば、どこにでもいる人として描いているのです。それまで作家の多数は男性であったため、小説に登場する女性たちは、気欲正しく美しいヒロインかそうでなければ悪女で、悪女は最後に社会的懲罰を受けるか天罰があたるものでした。しかし、イザベラは、このあとは懲りもせず、格好の結婚相手をゲットすべく新たな獲物を探し始めるでしょう。 また、キャサリンがノーサンガー・アビーで手紙を受け取り、それについてヘンリーとエレノアが慰めるというのは、第25章で、兄のジェイムズからの手紙を受け取ったことであったパターンの繰り返しと言えます。この手鏡をうけとるという繰り返しパターンですが、第25章の兄からの手紙を受け取った時と、ここでのイザベラからの手紙を受け取った時のキャサリンは、状況が変化しています。イザベラの本性を兄の手紙で知ったということもあるのでしょうが、キャサリンは、ジェイムズからの手紙を受け取った後、ゴシック小説の呪縛を脱したのでした。そこでキャサリンの変容が、手紙を受け取ったキャサリンの対応の違いの変化として端的に現れています。ここでのキャサリンの冷静さとイザベラに対する断固たる姿勢、そして彼女自身がふたりの慰めに甘えないで毅然としているところは、平凡なアンチ・ヒロインにおさまりきらないものです。おそらく、ここではキャサリンのキャラが立ってきて、作者の手を離れて独り歩きし始めているのだと思います。それをヘンリーが評して次のようにいいますが、これはヘンリーがキャサリンへの称賛をあきらかにするところではあり、作者自身のキャサリンというヒロインへの驚きの告白と言えるのではないかと思います。 「あなたは、うまれつき気高い心を持っているので、普通の人とは違った考え方をする。普通の人は、自分の家族をえこひいきしたり、自分の家族にひどいことをした人間に復讐したくなるけど、あなたはそういうことができないのです」(P.333) 第28章 将軍は1週間ほどロンドンに出かけることになり、その間、ティルニー兄妹とキャサリンの3人は親密な時間をすごすことになります。将軍が居なくなった途端に束縛から解放されたように三人は伸び伸びとしたくつろぎの中で親交を深めていきます。とくに、エレノアは物語の最後に作者から明かされますが、将軍の家庭内での暴君の最大の犠牲者だったのです。二人の息子達、長男のティルニー大尉はそんな父親のことを意に介していないだけでなく、軍隊生活のためにほとんど父親と一緒に過ごすこともないし、次男のヘンリーもウッドストンの教区の牧師館に住んでいるので、いつも父親と一緒にいる訳ではなかったのです。こうした兄たちとは対照的に、娘であるエレノアには逃げ場所がない。それに加えて、彼女を守ってくれそうな母親もすでに失っているため、そんな父親と常に二人きりで過ごさざるを得なかったです。彼女の時間のほとんどが父親の便宜のために費やされていたことは容易に想像され、そのために自由な時間がほとんど与えられず、同性の話し相手さえおらず、自宅で孤独に過ごさなくてはならなかったと想像されます。このエレノアの境遇は冒頭で紹介されたキャサリンのものとは対照的に読者の目に映るのではないでしょうか。この二人を対比することで、エレノアの境遇を際立たせる役割も果たしています。このエレノアの置かれた状況は、まさに、ゴシック小説の囚われのヒロインという監禁状態にあたるものではないでしょうか。つまり、作者のオースティンは、ゴシック小説のパロディであるかのように、アンチ・ヒロインのような性格のキャサリンを主人公にして、ゴシック小説によって現実と物語の区別がつかない少女のドタバタ騒動を描く傍らで、現実にゴシック小説の恐怖に遭遇しているヒロインを登場させていたと言えるのです。その恐怖は、この直後にアンチ・ヒロインであるキャサリンの身にも降りかかってくることになります。つまり、ティルニー将軍から屋敷を追放され、危険な一人旅を余儀なくされるという最大の現実的〈恐怖〉に遭遇するのです。当時の社会では、若い女性が、付き添いもなく、召使の同伴もなしに、ひとの駅馬車で長旅をするのは、非常識ともいえ、運が悪ければ事故に巻き込まれかねない危険な事態だったのです。しかもそれは、キャサリンが、ティルニー将軍に対してあらぬ嫌疑をかけていたことがヘンリーに知れて非難され、迷妄から目覚めた直後の、悪夢のような出来事でした。後にことの真相を知ったとき、キャサリンは自分は将軍の人柄をそれほど見誤ったわけでもなく、彼の残酷さを誇張したわけでもないと思い至ることになれます。これは、現実のティルニー将軍の振る舞いが、ゴシック小説に描かれる悪漢のそれに勝るとも劣らず恐ろしいものであることを暗示していて、平凡な女性の日常生活に恐怖が潜んでいることをさり気なく描いていて、それがゴシック小説への風刺(事実は小説より奇なり)となっているという、複雑に小説の構造になっていると思います。少し先回りしすぎました。 その恐怖の前に、二人の女性の親密さ、とくにエレノアにとっては唯一の同年代の女性の友人としてキャサリンはかけがえのない存在となっていることは、想像てきます。また、キャサリンの誠実さは、そのエレノアの友人として十分、その資格を満たしていたのは、とくにゴシック小説の呪縛から脱したことで一皮剥けたことも親交を深めることを後押ししたと思います。とくに、ヘンリーが用事でウッドストンに戻っていった後は彼女達ふたりで夜更けまで語りあうような生活をしていた。 そこに、深夜、将軍が帰宅し、その恐怖の命令をキャサリンに伝えたのがエレノアでした。この辺りはドラマですね。何の説明もなく、付き添いもつけずに、早朝に駅馬車の乗り場まで馬車を手配しただけという最も無礼なやり方で,彼女を直ちにアベイから追放することを、エレノアが告げさせられる。その理不尽さは、その内容もさることながら、エレノアの言葉にあらわれない仕草に象徴的に表れています。まず、キャサリンの部屋を訪ねるエレノアは、扉をノックすることができません。扉の前に立ちすくんでいるのを、気配を察したキャサリンが気付いてドアを開けます。この場面は、外形としては部屋の外に無言で人が立っているというのはゴシック小説の恐怖のシチエィションを模したものであると思います。部屋に招き入れられたエレノアは昼間の散歩のときにキャサリンの滞在を延長することを約束させたことを、将軍の命令で実現できなくなったことを、まず伝えます。その場面においてエレノアは、キャサリンの目を見ることができず、下を向いたまま話をします。ここには、エレノアの苦渋だけでなく、今までに築いてきた彼女らの信頼関係が揺らいだことが表れていると思います。というのも、キャサリンにははっきりと伝わっていないまでも、賢明なエレノアは将軍の決断が、キャサリンとヘンリーの結婚を無きものにしてしまうという決断であることに気付いているからであり、目を合わせればそういった考えが伝わってしまい、兄妹とキャサリンの関係が今以上に悪化してしまうと考えていたと思われるからです。 キャサリンは、その夜、つまりノーサンガー・アビーでの最後の夜、危険な旅となる現実の恐怖や理由がわからず追い出され、ヘンリーと別れができず去ってしまう理不尽さに、眠れぬ夜を過ごします。それは、妄想ではなく、現実に目覚めたがゆえの仕打ちということになるのでしょうか。 その晩は重苦しく過ぎていった。ぐっすり眠ることなど不可能だし、睡眠の名に値する休息をとることもできなかった。最初の夜は、この部屋で恐ろしい妄想に苦しめられたが、最後の晩もこの部屋で、興奮と不安に満ちたまどろみの一夜を過ごすことになった。でも最初の晩と最後の晩と、不安の原因はなんという違いだろう!悲しいことに、今夜の不安のほうがずっと現実的で、ずっと深刻だった。今夜の不安は事実に基づいたものであり、その恐怖は、現実に起こりうることだからだ。そして、その現実に起こりうるわが身の不幸に思いをめぐらせていると、ひとりぼっちの寂しさも、部屋の暗さも、屋敷の古さも、何の感情ももたらさなかった。外では突風が吹き荒れ、奇妙な物音がときおり屋敷じゅうに響きわたったが、眠れぬままに何時間聴いていても、何の好奇心も恐怖心も感じなかった。(P.345) ここでのキャサリンには、ゴシック小説の世界は消えてしまい、現実にしっかりと足をつけて、しかも冷静に客観的な目で事態を観察することができています。キャサリンの変容は、この引用にハッキリと表われています。 ここで、すこし脱線します。これまで、この『ノーサンガー・アビー』という小説がゴシック小説のパロディであるということを散々触れてきました。しかし、そのゴシック小説について、ひとつ想定されているのは、この作品の中で直接言及されている『ユードルフォの謎』です。一口にゴシック小説といっても、そのジャンルの中には言うまでもなく様々な作品があり、『ユードルフォの謎』はその中のひとつであるに過ぎません。したがって、『ノーサンガー・アビー』でパロディの対象としたのは、ゴシック小説の中の一部と言えます。そこには、オースティンが『ノーサンガー・アビー』の物語を作る際に都合の良かったものを取り上げたと思います。それがちょうど、この章でのエレノアが実はゴシック小説のヒロイン的な要素を持っていたということと、キャサリンがその読者を皮肉る滑稽さを持っていたということから、それに適した性格のゴシック小説をターゲットにしていたのが分かります。それが『ユードルフォの謎』だったわけですが、その特徴を少し考えてみたいと思います。それは、ヒロインが苦難を受けて、それに耐えているとモチーフ、とくに、その苦難は監禁されるというパターンです。それは、まさに、ノーサンガー・アビーという古い館で父親の権力に拘束されているエレノアの現実ですし、キャサリンが拉致されるように連れて行かれて閉じ込められるという妄想をしたもののベースです。ゴシック小説の中でも男性がヒーローとなって活躍するものは、ヒーローが閉じ込められるというパターンではなく、状況に外からやってきて飛び込んでいくというパターンです。これに対して、女性のヒロインのパターンは、最初平和に暮らしていたヒロインは強力な男性によって拉致され監禁され、そこで苦難に遭い、脱出しようとするというパターンです。 これは『ノーサンガー・アビー』においては、まさに強力な男性である父親の将軍の権力によってエレノアが監禁されているというわけで、パターンが当てはまります。将軍の権力は娘のエレノアだけに留まらず、一家の客人として招待し外形上は丁重にもてなしていたキャサリンにも及んだ。それは、将軍がロンドンに出かけた際にキャサリンは束縛から解放されたように感じたことで潜在的な束縛であったことが明らかになります、そして、突然帰宅した将軍によって、唐突に館を追い立てられてしまったわけです。その意味で、キャサリンがティルニー将軍のことをゴシック小説の悪漢と同一視したことについて、彼女が判断を大きく誤ったと非難することができるのでしょうか。エレノアのように、当時の女性たち、特に娘にとってもっとも身近な存在である父親こそが、その立場を有する権力を行使することによって、まさにゴシック小説の悪漢のように娘を精神的な監禁状態に置いて抑圧していることは正確にティルニー将軍の正体を見抜いていたと言ってもよいのではないか。しかも、現実に強権的な父親が珍しいものではなかった当時の父権的な社会が、実はゴシック小説がシンボリックに物語としたのを、逆にリアリズムの表現として現実的なものにしてしまったのが、『ノーサンガー・アビー』の将軍という人物ではないか。つまり、夢物語であるゴシック小説を皮肉ることが逆に、現実にあるのだということを明らかにして、小説の悪役はいないかもしれませんが、世間の欲望にとらわれて意識することなく結果として悪人のように振る舞っている現実の中の平凡な人は、将軍に典型的ですが、どこにでもいるのです。それを図らずも、『ノーサンガー・アビー』はリアリズム的に明らかにしてしまっている。また、イザベラ・ソープも、そういう視点で捉えることができると思います。 第29章 キャサリンは出発します。その時にヘンリーはウッドストンの教区に出かけていました。その間にノーサンガー・アビーを追放されてしまったキャサリンは、ヘンリーに別れの言葉さえ告げることができないまま、悲しみをこらえて出発することになりました。馬車がヘンリーの今いるウッドストンの牧師館の近くを通りかかったときに、 ウッドストン村に1マイル近づくたびに、彼女の悲しみは激しさを増し、村から5マイル手前にある曲がり角を曲がらずに通り過ぎるとき、「ああ!ヘンリーはすぐそばにいるのに、私のことを何も知らずにいるのだ」と思い、彼女の悲しみと苦しみは頂点に達した。(P.350) そして、キャサリンの様子を次のように描いています。 ヘンリーが明日ノーサンガー・アビーに戻って、彼女が屋敷を去ったことを知ったら、彼はどう思い、どう感じ、どういう顔をするだろう?彼女にはこれが何よりも重大な関心事であり、絶えず頭につきまとって、彼女をいらだたせたり慰めたりした。「私が去ったことを、彼は黙って冷静に受け入れるだけかもしれない」と思っていらいらしたり、「いや、彼は私が去ったことを残念がり憤慨するにちがいない」と思って自分を慰めたりした。(P.352) このときのキャサリンの心の悩みは、これまでになく複雑で、大人びているように映ります。このように傷心の道中で、ひとり悶々と考えていた時、キャサリンのヘンリーへの片思いは、恋愛小説にヒロインに憧れるような、恋に恋するといったものから、いわば自己完結したものから、相手を心から思い遣る本物の恋に変わって行ったのでないかと思えるところがあります。これまで、小説のパロディのように進んできた恋愛遊戯が終わってしまって、言ってみれば初恋が断たれたことで、キャサリンは大人に成長し、恋をすることができるようになっていった。その試練が、この追放だったとも考えられるのです。 キャサリンは実家に戻り、家族の歓迎に心を慰められても元気を失ってしまうようです。これは、キャサリンの変化を表わしているのではないでしょうか。もはや、キャサリンは子供のように無邪気に野原を駆け回ることはできない大人に変貌している。それは、疲労困憊した彼女を見て、両親は、以前の彼女のように一晩眠れば元気になると期待したが、そうならず、彼女は以前にはなかった深刻な悩みを抱え、しかも、それを両親もわからないほど心に深く秘めていた。それを彼女は自覚していました。それは、次の文章に明確に表われています。 私はヘンリー・ティルニーを忘れることはできないし、愛情が薄れることも絶対にないけれど、彼は私のことなんか忘れてしまうかもしれない。(P.359) これは、物語の前半、バースでヘンリーに出会ったころ、彼の姿を社交場で見つけることを楽しみにしていたり、やイザベルに素敵な男性がいると打ち明け、二人で盛り上がっていたころとは、全く違います。この文章のようにストレートに「ヘンリーへ愛情」という言葉が使われることは、長い物語の中でありませんでした。それが、最後近くになって、てできた。ということは、最後のたった数ページが恋愛小説になっているということなのです。そして、おそらく、ジェイン・オースティンの他の5つの作品は、この短い部分が引き伸ばされて長大な小説になっているのです。そう考えると、オースティンが、『高慢と偏見』に代表されるような彼女らして小説を書くために、その前の段階を書いた『ノーサンガー・アビー』のような小説が必要だったと考えられるかもしれません。いってみれば、これは恋するヒロインが誕生するところを描いていると言えるのです。 たしかに、これ以前でもキャサリンとヘンリーの結婚ということは実際のこととして、受け取られていたことは事実です。例えば、将軍がヘンリーとキャサリンを結婚させるべく暗躍したのは、もともと二人のそういう兆候があったのを察したからこと可能性があると判断して動いたわけです。また、エレノアは二人が結婚することを暗々裡に認めていた節があります。したがって、キャサリンのヘンリーに対する思いは、片想いで、キャサリンの心の中のみのことだったとは限りません。しかし、キャサリン自身は、ヘンリーがどう思っているかなどということを考えていなかった、ひたすらヘンリーを思っている自分に閉じこもっていたところがありました。 その点では、当初のキャサリンはイザベラとよく似ていたのです。二人はゴシック小説の愛好者という点でも精神構造に似ている点があります。たしかにイザベラは美人で魅惑的で、次々と男を征服しようとするところもあり、男女が微笑を交し合っているのを見ただけで、戯れの恋を見つけることのできる世間ずれした女性です。キャサリンはイザベラのそのような能力に対して讃嘆の目を向けたり、イザベラの手練手管に振り回されたりします。しかし、イザベラの恋は相手を征服させるという点で、相手の人格が対象に入ってこない。相手のことを思うことがないのです。その点で、キャサリンとは違った意味で恋をしている自分に向いているのです。だから、ティルニー大尉との破局があっても自身が傷つくことがない。この点ではキャサリンも同じたったと思います。それが、ヘンリーに将軍に対する疑惑を責められて現実に目覚め、ノーサンガー・アビーを追放されたことでヘンリーを失った大きさに思い至り、彼女は傷つき失恋を知ります。同じように最初の恋に失敗するところまでは共通していても、そこから先で、二人は大きく別れていくのです。イザベルは、『分別と多感』のルーシーや『説得』のルイーザに連なっています。 他方で、キャサリンは、理由もわからぬまま(後で理由は明らかになりますが、キャサリン本人は帰責すべきものは何もない、将軍自身のひとり相撲によるものです)、若い女性を独りで放り出すという不当な仕打ちをした将軍に対しては、屈辱を覚えながらも、ひたすら耐えるのです。 キャサリンが将軍に対して申し訳ないと思っていることがひとつあるが、それが将軍の耳に可能性はないはずだ。彼女の妄想が生んだ、将軍に対する忌まわしい疑惑を知っているのは、ヘンリーと彼女だけ出し、彼女はもちろん、ヘンリーもこの秘密を口外するはずがない。少なくとも故意に口外するはずがない。彼女が考えたことや行ったこと、つまり、あの証拠のない妄想や、彼女が夫人の部屋を家捜ししたことが、運悪く、何かの偶然で将軍に漏れたとすれば、将軍がどんなに怒り狂っても不思議はない。彼女が将軍に殺人者の汚名を着せたことが将軍にしれたら、彼女が屋敷から追い出されても不思議はない。(P.351) とキャサリンは反省的なのです。自分に対してひどい仕打ちをした将軍を恨むことをせず、ひたすら仕打ちに耐えているのです。いかにひどい仕打ちを受けたとしても、彼女自身に非がなかったかと反省する謙虚さは、彼女の特徴です。もっとも、キャサリンは急に家に戻った理由を家族に説明する際に、将軍の仕打ちを隠すことはできず、正直に伝えたとき、両親は将軍の行動に非は認めたものの、それについてとやかく言うことはせずに、「将軍は変人だ」ということで済ませてしまいます。もともと、キャサリンの家族は他人に対する寛容さを備えた人々であることは確かで、キャサリンもその資質を受け継いでいると言えると思います。とは言っても、キャサリン自身は危険な目に遭っているわけで、それを許すということは、この試練によって、キャサリンの成長があったと考えてよいのではないかと思います。 第30章 キャサリンは実家に帰り、以前の生活に戻りますが、彼女自身は以前の彼女ではなくなっていました。その変化に、母親のモーランド夫人が気付いて心配するのです。そんなとき、何の前触れもなく唐突にヘンリーが訪ねてきます。キャサリンが無事に帰ることができたのか心配で来たというのが訪問の名目上の目的ですが、キャサリンにプロポーズをしに来たのでした。 彼の第一の目的は、自分の気持ちをキャサリンに伝えることだった。そして彼はじつにみごとにそれを実行した。キャサリンはヘンリーのその言葉を、何度聞いても飽きないと思ったほどだった。キャサリンはヘンリーの愛を確信した。そしてつぎに彼女の愛が求められたが、彼女の愛が完全にヘンリーのものだということは、ふたりともすでに十分すぎるほど知っていた。というのはこういうことだ。ヘンリーは今たしかにキャサリンを心から愛し、彼女の性格のすばらしさに魅了され、彼女といつも一緒にいたいと心から願っているけれど─ここで私ははっきりと言っておくが─彼の愛情は、彼女に対する感謝の気持ちから生まれたものなのである。つまりヘンリーは、キャサリンから愛されていると確信したために、彼女のことを真剣に考えるようになったのである。これは、恋愛物語としては新しいパターンかもしれないし、ヒロインの名誉を著しく傷つけることになるかもしれない。しかし、世の中にはこういうパターンはよくあると思う。もしこれが、現実の生活においても珍しいパターンだとおっしゃるなら、私の奔放な想像力をぜひ称賛していただきたい。(P.370) この引用のように、ヘンリーがキャサリンとの結婚を決意した動機は、「キャサリンから愛されているという確信」と「感謝の気持ち」のみであると、作者は説明しています。そして、もしこれが恋愛物語のみならず「現実の生活においても珍しいパターンだとおっしゃるなら、私の奔放な想像力をぜひ称賛していただきたい」と述べています。これは、自らの力量を誇る作家の言葉とも受け取れますが、世の中には男性が一時の気紛れで結婚することはよくある、という事実を皮肉っているようにも解釈できます。若さのはずみで、感じのよい女性とする
―そして、彼を待ち受けているのは、平凡で退屈な結婚生活かもしれない ―
という点では、ヘンリーは作品中のアレン氏のみならず、『高慢と偏見』におけるベネット氏とも共通点があります。 ここで、ヘンリー・ティルニーという人物を改めて見てみましょう。彼は最初に登場したときからつねに、物事に対して斜に構えた態度を取っていました。彼は、しばしばキャサリンの弱点をからかいますがそのからかい方はいささか意地が悪く、時として彼は、女性蔑視の傾向を示すことがありました。女性向きのお決まりの会話をわざとらしく模倣しようとしたり、女性の日記や手紙の書き方を嘲ったり、女性の言葉遣いや読書の趣味について論じるヘンリーの冗談に対して、キャサリンは時々、「笑うべきかどうかわからず、顔をそむける」というように、戸惑いを示したり、無反応だったりで、これは彼の言葉がユーモアとして機能していないことを示しています。衣装に対して目のないアレン夫人を相手に、ヘンリーは布地についての詳しい知識を披露して、彼女を感嘆させますが、その陰でキャサリンに対しては、アレン夫人との交際は「知的貧困を絵に描いたようなもの」だと言ってはばかりません。また、キャサリンは、兄ジェイムズの婚約者イザベラがティルニー大尉と親密な関係になってゆくことを危ぶみ、二人を引き離してほしいとヘンリーに懇願するのですが、彼は、財産のないイザベラがいずれ自分の兄から捨てられるだろうと見越して、無視します。このようにヘンリーには、やや冷淡とも言えるような、世事に通じた面があります。女性の趣味に詳しかったり、ダンスに対して熱心だったりする点で、ヘンリーは世俗的な牧師であり、この特徴において、『高慢と偏見』のコリンズや『エマ』のエルトン氏等に連なる、オースティンの聖職者諷刺の出発点を成す人物であるとも言えるかもしれません。 その一方で、キャサリンを導く役割を担っています。オースティンの小説の聖職者の中で、『マンスフィールド・パーク』のエドワードの出発点とも言えるのです。あるいは『エマ』のナイトリーがエマの過ちを指摘して軌道修正したように、物語の最初から最後まで一貫して、ヘンリーはキャサリンを導く役割を果たしていました。例えば、キャサリンが、不用意にナイスとアメイジングリーという言葉を使うのを聞いて、正しい単語の使い方を教えたり、彼女が「ピクチュアレスク」に関してまったく無知で、教えてもらいたがっていることを知ると,さっそく講義を始めたりします。その彼がもっとも、導き手の役割を果たすのは、ゴシック小説の幻想にとりつかれて、彼の父である将軍が妻を幽閉している悪漢だと誤解しているキャサリンを現実に目覚めさせたときのことです。彼女はフィクションと現実を混同していました。彼は、その愚かさを指摘し、彼女の空想が途方もないものであったことに,目を開かせたのです。そういうものとしてヘンリーを見ると、ヘンリーがキャサリンを愛したのは、感謝ということもあるのでしょうが、ミュージカル『マイ・フェア・レディ』のヒギンズ教授が花売り娘イライザを自分の理想の女性に育てて、好きになってしまうパターン(ピュグマリオン・コンプレックス)という側面もあると言えるかもしれません。 こうしてみると、キャサリンが従来の小説のヒロインに対するアンチの平凡な女性ということが意識されていたのと同じように、キャサリンの相手であるヘンリー・ティルニーも、完全無欠のヒーローではなく、弱さや多少の歪みをもった、どこにでもいるような平凡な人物として設定されていると思います。 したがって、この小説で描かれている恋愛は男性ヒーローが熱例な恋によって美しいヒロインを獲得するというものではなく、純な心を持った17歳の田舎育ちの平凡な少女が、華やかな温泉リゾート地で田舎にはいないタイプの男性とめぐり会い、夢見るように自身を小説のヒロインのように男性を憧れを、自身の成長によって本物の恋にして、その勢いに押し切られて、いってみれば多少軽薄な草食系の男性がひっかかってしまうものです。現代の少女マンガのラブコメに通じるような話です。だからこそ、ヒロインもヒーローも平凡で、どこにでもいるようなタイプでなればならなかった。上の引用した文章の中で、作者オースティンが「ヒロインの名誉を著しく傷つけることになるかもしれない。」と述べているのは、ヒロインを美化しつつその尊厳を保とうとする従来のロマンスの嘘っぽさに対する皮肉が含まれている言い方ですが、要するにキャサリンは、いやしくも小説のヒロインなら美人で、おしとやかで、頭が良くて、みごとなピアノの演奏で、客間の人々をうっとりとさせ、思いを寄せる男性の横顔のひとつも描けなくてはならない、そして願わくば、できるだけかわいそうな境遇のほうがいい、そういうものを一切備えていない、ないないづくしのヒロインであることを裏返しに言っているだけのことです。そして、「世の中にはこういうパターンはよくあると思う。もしこれが、現実の生活においても珍しいパターンだとおっしゃるなら、」と述べているのは、いつも男性のほうから女性を強く思うとは限らない、女性は男性の恋のハンティング対象になっているだけではない。女性の側から男性を強く思うことだってある。それを物語とするためには、従来のハンティングの対象となるのに適したタイプのヒロインではうまくいかない。そこで、どうしても、男性を強く片想いをして、その思いを自覚し男性に届けて、結果的に獲得してしまうことができるタイプが必要になる。そこで創られたのがキャサリンというヒロインです。 他方で、ヘンリーはキャサリンが唐突にノーサンガー・アビーを追放された理由を明らかにします。ヘンリーとエレノアの父である将軍の実像は、人間の心よりもお金を優先させる貪欲で、残酷で利己的な人間なのです。子供たちにも金持ちと結婚するように教育しているほどです。将軍は、ヘンリーに「なんとしてもキャサリン・モーランドの心を射止めよ」(P.374)と命令さえしていたのです。そして、彼はキャサリンがアレン氏の相続人であるというジョン・ソープの誤った情報を信じ、彼女をヘンリーと結婚させようともくろんで、彼女を邸宅に招待しました。ところが、ロンドンに出たティルニー将軍は,キャサリンの財産についてソープに騙されたことを知ります。彼は、その誤報を信じた自分を恥ずかしいと思うどころか、騙されたことに怒り狂うのです。その怒りの矛先は何も知らないキャサリンにも向けられました。その結果、何の説明もなく、付き添いもつけずに、最も無礼なやり方で、彼女を直ちにアベイから追放したのです。キャサリンは、自分が多額の財産の相続人でないという身に覚えのない過失によって、将軍の怒りを買ってしまい、突然追放されたというわけです。そして、将軍はヘンリーにキャサリンのことは忘れるように命令しました。ヘンリーが、これを拒絶すると、将軍は烈火のごとく怒り狂います。おそらく、ヘンリーがキャサリンへのプロポーズを実行することになったのは、この父親とのやり取りがあって感情的に煽られたことも原因しているかもしれません。それについて作者は何も言及していませんが、妹のエレノアの結婚について次のように言及していて、それがヘンリーの行動にも当てはまるようにも読めるからです。 さらに私はこう思う。将軍の不当な干渉は、ふたりの幸せをじゃましたどころか、むしろその助けになったのではないだろうか。つまり、将軍の不当な干渉のおかげで、ふたりはより一層お互いを知ることができ、より一層お互いの愛を深めることができたのではないだろうか。(P.383) この事情を聞いたキャサリンは、「私はティルニー将軍に妻殺しや、妻幽閉の嫌疑をかけてしまったけれど、将軍の性格をそれほど見誤ったわけではないし、将軍の残忍性をそれ程誇張したわけでもない」(P.376)と思い至るのでした。これは、欲深い金権主義や階級差別によって暴挙に出たティルニー将軍の振る舞いが、ゴシック小説に描かれる悪漢のそれに勝るとも劣らず恐ろしいものであることを暗示していると言えます。「キャサリンが遭遇しなければならないのは、あんなに想像力を働かせたゴシック小説の何よりも、おそらく,悪意があって恐ろしい、アベイにおける、この無分別な情け容赦のない怒りである。ノーサンガー・アベイでの怒りこそ,本当の隠れた恐怖なのである」と評する人もいるくらいです。 第31章 最後は大団円です。ヘンリーのプロポーズはキャサリンの両親に報告され、両親は将軍の同意を条件に二人の結婚を認めます。ヘンリーは将軍の怒りを買っていて、難問ではありますが、妹のエレノアが爵位をもった裕福な男性との結婚を決めます。の有利な結婚に気をよくした将軍は、キャサリンがそれほど貧しくもないことを知り、やっと二人の結婚を認めます。将軍は「空虚な美辞麗句をつらねた」同意の手紙をミスター・モーランドに送るのでした。 この大団円に水を差すつもりはなく、気持ちよく終わりたいのですが。かなり穿った見方ですが、これまで、作中でパロディとか皮肉をかましてきたオースティンが、物語一巻のおわりをメデタシメデタシの大団円で締めてしまうのは、何となくもの足りないというのか、最後に、もうひと捻りくらいしてもよさそうなものだろうに、思ってしまうのです。 はじめのところで、この小説はゴシック小説に代表される従来の小説をパロディとして揶揄的に扱い、ヒロインのキャサリンを、そういう小説のヒロイン像を否定するようなアンチ・ヒロインとして創造したと指摘しました。そして、それを従来のものでないからということで、〜でないを繰り返す書き方で一貫されています。ここでは、そういうネガティブでなく、積極的に、こういうものだというものが提出されずに、仄めかすだけで終わりました。それは、この後続々と制作される作品群を、お楽しみにということになるのでしょうが…。そのヒントを、この作品の中に探っていくこともできるのではないかと思います。それは、ゴシック小説にのめり込んでいたキャサリンが、現実に触れて大人となったときに、具体的にヘンリーとどういう生活を作っていくかということを想像してみるのです。 そのヒントとして、例えば、キャサリンがノーサンガー・アビーに招待されて、館内を将軍に案内されますが、ゴシック小説にかぶれていたキャサリンは、ゴシック小説的な痕跡をばかりを探し、他の部分には目もくれませんでした。そして、ヘンリーに諭されて現実に目覚めた後でウッドストンの牧師館を訪ねたときには現実の生活の場として興味深く見ています。そこで考えてみると、キャサリンがノーサンガー・アビーを案内されて無視していたのは、例えば最新式に整備された台所でした。キャサリンが、現実に目覚め大人となる第一歩を踏み出したときに、ひとつのシンボルとして見えてきたのは台所があった。しかし、台所というのは近代の家庭において女性が押し込められた場所でもあるわけです。ゴシック小説ではヒロインが囚われて監禁される場面がよくありますが、近代の現実社会において女性は台所というスペースに縛り付けられ、社会的な自立を阻まれ、従属的な状態に抑えつけられる。いってみれば、形をかえてゴシック小説のヒロインの虐げられた状態が続いていたわけです。キャサリンが大人となって、この後、ヘンリーと結婚し家庭を作っていくということは、台所に縛り付けられに行くことに他なりません。それを受け入れるということが、この社会では大人になるということです。逆に言えば、彼女が大人の女性にならない限り、幸せな結婚という結末の付け方もうまくいかなくなってしまうのです。結婚市場の中で勝ち残っていくためには異性から好かれるような大人の女性でなければならず、幼少期の彼女は、子供で異性を惹きつけるようなタイプではありませんでした。それゆえに、彼女は「大人の女性らしさ」を身につける必要があった。なぜなら、キャサリンは従来から社会が女性に強く求めてきた役割という枠組みを超越してしまうほどの精神的な成長をする主人公とは考えにくいからです。それは、ノーサンガー・アビーでヘンリーの結婚相手として考えていたキャサリンに、台所を見せたがった将軍の考えるような理想の女性像へとキャサリンが変わっていくということです。 このことは、次のような議論とつながってもいくことになります。結婚後の女性が興味を持つべきは家事を円滑に行うことであると言わんばかりのティルニー将軍のこの態度は、そしてこの根本にある考え方は、果たして将軍のようなタイプの人間に特有のものであるのか、ということです。キャサリンが結婚したヘンリーが、こうした考え方に縛られていないと断言することは、はたしてできるでしょうか。慥かに、キャサリンに対する自分の父親の仕打ちに真っ向から反発し、将軍に猛反対されながらも怯むことなく彼女との結婚を推し進めたことからも、ヘンリーの意志の強さは認めるべきでしょう。しかし、ひとつ言えることは、彼の言葉にはどこか女性を見下したようなものが多く、たとえば、アレン夫人との交際は知的貧困を絵に描いたようなものと公言してはばからないことがありました。このように、ヘンリーは確かに才気煥発な人物であるが、彼の言葉のうち、どこまでが冗談で、どこからが本気なのかを読み取るのに難しいところがある。そういう側面を考えるならば、彼の中にも父親と同じような一面がないとも限らないと言えませんか。 その上、キャサリンの側にも問題がないとはいえません。謙虚にことは称賛されるべきですが、彼女にはヘンリーのことを批判的に見る力がほとんど備わっていないのです。そんなキャサリンの傾向は作品の結末に至ってもなお変わらない。ヘンリーの態度次第でキャサリンはどのような状態にでも置かれることになるだろうと容易に想像することができるのです。そういう意味では、結末に至ってもなお、キャサリンがこの点において精神的に成長したと言い切ることは留保せざるを得ない。敢えて言えば、キャサリンという女性は、ヘンリーにとっては甚だ都合のいい女性でもあるわけです。 以上の点からすると、ヘンリーとの結婚を通して彼女が手に入れることができたのは、ゴシック小説でいえば囚われたヒロインがヒーローに救出された得られる自由などではなく、以前と同じような狭い場所(女性に求められる家庭内のことを司る場所)に精神的に監禁され続けることである可能性も捨てきれないのです。 つまり、この小説はスタイルとしてのゴシック小説を批判するものではあるのですが、そういうゴシック小説を生み出した社会や文化そのものに深く根差したものであるかぎり、その批判は「目糞鼻糞を笑う」というものである可能性は否定できないのです。
リンク . |