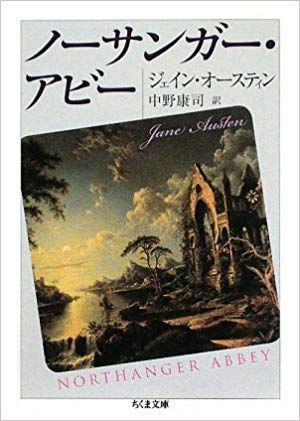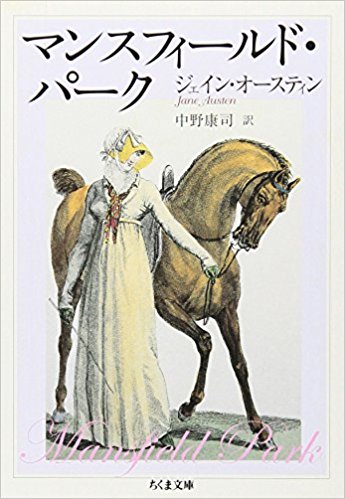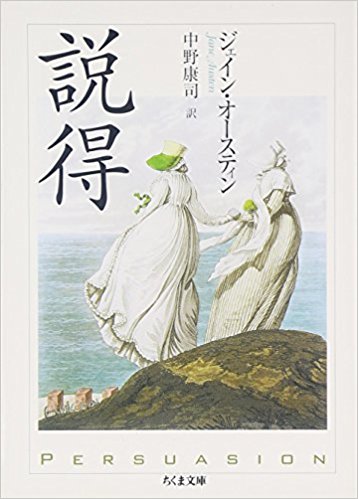小説の魅力の中に、ストーリーがどうとか、小説の人物がどうとか、テーマがどうとかいったことがありますが、ジェーン・オースティンの小説の愉しさというのは、実際に小説を読むという行為そのものが愉しいという点に大きな特徴があると思います。それは、小説の本に印刷されている活字を見て、文章を追いかけて、ページをめくるという肉体の動作、そのものの快楽とでもいうべきものです。小説を読むこと自体といっても、読んでいる内容が主で、その内容がストーリーだったり、人物だったり、テーマではないかという人もいます。ほとんどの小説はそうなのです。しかし、それでは、読むということが、ストーリーとか人物とかテーマといった、いわば情報を伝えるための手段ということになってしまいます。でも例えば、スポーツを考えてください。走るというのは、移動するための手段です。しかし、その走るという肉体の動きそのものを追求して、移動という目的を切り離して手段である走ることに愉しさを見出したのがスポーツです。同じように、小説を読むという行為そのものが愉しいということがあるのです。それを堪能させてくれるのが、ジェーン・オースティンの小説なのです。 それは、いったいどういうことなのか、それは、実際に小説を読んでみればわかることです。と突き放してしまっては、理解してもらえませんよね。それで、実際にオースティンの小説を、私は、このように読んでいるというように、具体的に作品に沿って、愉しんでいるところをドキュメントしてみました。それを作品ごとに、したにあげてあります。それぞれの作品については、リンクで、それぞれ見てください。
それぞれの作品で見てみました。以下では、それらをまとめて、オースティンの小説の特徴的な魅力を概説してみました。なお、こういう紹介にありがちな、オースティンの生い立ちとか、時代背景とかいったことは、他にたくさんの説明がなされているので、ここでは省略します。ここでは、そういうのは他で読んでもらって、私はこう思うというところだけ載せることにします。だから、これからオースティンを読む参考にしたいと思っている人や、作品を読んだけれど理解の参考にしたいと思っている人には、たいして参考にならないし、面白くないと思います。そういうのなら、さっきも述べましたように、他にたくさんの説明があるので、そういうのを探して読むことをお勧めします。以下は、オースティンの作品を、ある程度読んでいて自分かなりの捉え方とか、自分にとってのオースティンの魅力について、自分の考えを持っている人でないと、分かり難いかもしれません。
1.パロディの結果としてのリアリズム 1−1.パロディという形式 オースティンの第一作目の作品と言われる『ノーサンガー・アビー』は、当時の社会で流行していたゴシック・ロマンスのパロディとして作られたと言われています。また、次の作品である『分別と多感』もロマンチックな恋愛小説のパロディとしての側面が強い作品になっています。これらの他、彼女の初期の習作はパロディの性格の強い作品になっていると言われています。オースティンという女性が機知に富んだ人で、ジョークや皮肉をよく口にしたと言われているので、彼女の性格からパロディという形式を択んだと言えるかもしれません。しかし、そんな単純なのでしょうか。ここでいくつか疑問があります、少し調べてみたのですがパロディというのを物語において始めたのは、ジョナサン・スィフト(『ガリバー旅行記』の作者)といわれているそうです。ということは、あまり、お行儀のよいこととはいえないのではないか、ミドルクラスの未婚の女性が出版するなどしておおっぴらに行っていいことだったのか、疑問に思えるのです。 そもそも小説を執筆して出版するということが、しかるべき家柄の女性として社会的に認知されていたのか、はなはだ疑問です。実際、『ノーサンガー・アビー』で小説家として言及されているラドクリフ夫人はいわれなき中傷を受けたり、社会的ないじめにあって、小説家を続けることができなくなったということらしいです。周囲の環境がそんな状態で、小説を出版する、しかも、を茶番(バーレスク)や嘲弄とほとんど同じようにみなされていたパロディをそこで行うというのは、かなり過激なことをやろうとしたといえると思います。しかし、たとえ家族の理解があったとしても、オースティンは、そのような過激なことを、そうと知っていて敢えて行ったのでしょうか。これは、私の想像でしかありませんが、パロディを作ろうとしたのではなくて、書いているうちにパロディのようになってしまった、結果としてパロディになってしまったのではないかと思うのです。 おそらく、オースティンという人は、小説の書き手である前に小説の読み手であったではないかと思います。作家の中には他人の作品をあまり読まない人、読書が好きでない人もいますが、オースティンは、小説の熱烈な読者で、そのうちに読んでいるだけで飽き足りなくて、小説を書き始めたのではないかと思わせるところがあります。例えば『ノーサンガー・アビー』で、小説とはどのようなものかということについて何度も言及しています。ということは、オースティン自身がかなり量の小説を読んでいたことが推測できます。小説が好きで、作品を読んでいるうちに、読んでいるだけでは物足りなくなってくる。これは、現代のマンガやアニメファンなどを見ているとアニメを見ているだけでは飽き足りなくなって、作る側に回って参加するようになる。それが、同人誌のかたちになって、コミケットという大きなイベントに結実しているわけです。そのコミケットで取り扱われている同人誌の内容の大半はパロディだと言われています。そこで作られているパロディは、既存のマンガやアニメの登場人物や設定を借りて、サイドストーリーを二次制作するというものです。浄瑠璃の台本をつくるときの「世界」という概念に似ていると思います。浄瑠璃や歌舞伎の作品をつくるときに、例えば曾我兄弟の話という前提のもとで、その人物や設定を借りて、曾我五郎が仇討ちの機会をうかがうあいだに、身元がかたきにばれないように他の人を演じるというサイドストーリーが「助六」という作品になったりするわけです。少し話が飛躍しましたが、パロディの同人誌をつくる人たちは、好きなマンガやアニメに参加したいので、その作品の好きな登場人物(この場合はキャラという言い方をします)で、自分の物語をつくっていくという盛んの仕方をするわけです。そしてまた、そういう人たちは、何もないところからオリジナルな物語を作るということは大変なので、手近なところで、既存の設定を使って物語を作っていくのが、手っ取り早いのです。 では、オースティンの場合しどうだったのか想像してみましょう。彼女は小説が好きで読んでいるだけでは物足りなくなり、自分でも小説を書いてみようと思うようになった。しかし、当時は大学の文学部もないし、創作理論のようなものもなく、小説を書く方法は誰も教えてくれなかった。したがって、小説を書こうと思ったら独学で書いてみるしかなかった。そこでどうしたか、とりあえず、既存の小説をお手本にして、見よう見まねで書いてみた。それが習作なのではないでしょうか。しかし、彼女は、もともと既存の小説では飽き足りなくて、自分で小説を書こうとしたのであるから、お手本をなぞっているうちに、そうじゃない、ああじゃない、というところがどんどんでてきた。その結果が、お手本である既存の小説をベースにしていたら、それとは違うもの。スタートは同じでもゴールが違うものになっていった。それが、結果としてパロディのようになってしまったということなのではないかと思います。したがって、そういう意味で考えると、オースティンの作品というのは、パロディがベースになっていると言えるのではないでしょうか。 (注)北脇徳子「ジェイン・オースティンの読書観」(http://www.kyoto-seika.ac.jp/researchlab/wp/wp-content/uploads/kiyo/pdf-data/no35/kitawaki_tokuko.pdf)にはオースティが古典を中心とした500冊程度の父の蔵書を読んでいたことや、父の死後、貸本屋の会員となっていたことが説明されています。 1−2.パロディとリアリズムの関係 話は変わって、オースティンの小説は、当時の荒唐無稽な小説に比べてリアリズムだったと言われています。このリアルということと、パロディの関係について考えてみたいと思います。上でも述べたように、オースティンは小説が好きで、読んでいるだけでは物足りなくなって、書き始めた。つまり、小説を書くということが、最初だった。ということは、現実を描写しようとして書いたのではないということです。順番が違うのです。この違いは何か。これを少し考えてみましょう。まず、現実を描写するために書くという場合。これは絵画の場合に置き換えて考えると分かり易いと思います。リアリズムといい現実をありのままに描くというためには、目の前にある事物を客観的に詳細に観察し、その見たままを描くことが必要です。その場合、絵画を描くときの約束事は、つまり様々な絵画の技法や方法はときに、見たままを見たとおりに描くこととは反対のこともあります。例えば、遠近法という技法は奥行きを平面であるキャンバスで、みえるように描く技法ですが、必ずしも、実際に見えたままと同じではありません。実際に見るときは左右の二つの目を使って立体的に見ていますが、そのままをキャンバスに写すことはできないのです。しかし、リアリズムはそういう既存の方法をいったん棚上げして、見えたままをキャンバスに写そうとします。そこで、既存の方法や技法になかった新しい方法がうまれたりして、見たままを写すことの技法が飛躍的に進歩したりするわけです。これに対して、まず書くことが第一で、書いているうちにリアルに読めるように書くようになる。この場合は、絵画でいえば、まず描くこと。これは既存の手法を白紙にしてみたままを描くのではなくて、既存の方法を総動員して、まずは描く。そして、描いたもののうちで、結果として見る者にとってリアルに見える手法を選択していくということになると思います。したがって、そこにはリアルに描くという手法の飛躍はあまり生まれません。その代わり、見たままではないかもしれませんが、見る人にとってリアルに見えるという効果が洗練される、つまり、絵画のリアルな画面とはこういうものだという先入観が明確になると思います。絵画とちがって、小説は言葉を使います、言葉は絵の具のように特に説明がなくても目で見ることができます。言葉とは違うのです。言葉はそれ自体と見ることは出来ません。言葉はコミュニケーションの手段として、書き手が書いた内容が読み手に伝わることで始めて成立します。そこで、書き手から読み手に伝わらないと成立しないのです。だから、絵画の場合のように、見たままを描くといっても、見る者が、それをリアルだと受け取らないとリアルであることにはならないのです。そこに言葉の特徴があります。オースティンの場合は、既存の小説をお手本にして、見よう見まねで小説を書き始めたわけですから。小説の言葉とか描写は、お手本の小説からスタートしているはずです。そのお手本を出発点に書き始めて、こんなの現実にないとかいったような取捨選択を、既存の小説の様々な表現や技法からもってきて、それらを様々に使う試行錯誤をくり返したと思います。その結果、読む人がリアルと感じることができるような表現になった オースティンのリアルというのは現実そのままではないということになります。オースティンの小説のリアル、あるいは小説の中での現実というのは、様々な小説の言葉とか小説の表現の中から、あれとこれとこれといったようにいくつかの特定のものを選択して、それを組み合わせて小説の中で使った、その結果なのです。それを読者は、リアルであると感じさせたものだということです。それは、オースティンにとってのリアリズムというのは、現実そのままということではなくて、小説の表現としてリアルに感じられるということなのではないか、ということなのです。 1−3.オースティンのリアリズムの理由を考える オースティンのリアリズムとはどのようなものかという性格について述べましたが、もう少し、その内容に踏み込んで考えてみたいと思います。つまり、オースティンの小説の中で、どのようなところが、読者がリアルと感じるのかということです。オースティンのリアリズムというのは、一般には、彼女が生きた狭い世界、つまり、当時のイギリスの自営業の「田舎の三、四軒の家庭」の日常生活を丹念に描写した、しかも、彼女が実際に見たり聞いたりしたことをもとに表現したということと言われています。そのエピソードとして、会話の場面で女性のいない場での会話は、女性であるオースティンが聞いたことがないので、書かなかったというのです。たしかに、作品を読んでみると、そういう場面はありません。そういう事実はいろいろなところで解説されていますが、オースティンは、どうしてこのようなリアリズムの表現を択んだのかの説明は、見ません。イギリスのリアリズムの伝統とか、当時の荒唐無稽の小説に満足できなかったからといった説明はあるようですが、それは結果を言っているのであって、理由の説明になっていません。 そこで、少し想像して見ましょう。オースティンは、その作品を読めば、物事の特徴をつかむ視点や鋭い観察眼をもっていたことが分かります。そういうオースティンからすれば、実際に小説を読み進めていて、「違う!」という感じを、いくつもの場面で持ったのではないかと思います。それは、荒唐無稽な設定やストーリーに対してではなく、細部の描写に対して気になってくるのではないか。例えば、ヒロインの仕草だったり、服装だったり、部屋の様子といったような些細なところです。これらは小説のストーリーとは関係のないところです。しかし、現代の小説の読者の中でも、そういう細部がいい加減に書かれていると、小説の登場人物にシラけてしまったり、行動がうそ臭く見えてしまうという人は少なくないと思います。けっこう小説を読んでいると、そういう細部をお座なりに書かれている作品に出会うことか少なくありません。些細なことなんですが、例えば、都心に勤めるサラリーマンが会社で残業した後、同僚と酒場で盛り上がって郊外のマンションに帰宅して、その後恋人と会話をするというような、夜が何十時間もあるような行動をしたりといったことを読んだりすると、「ありえない」と引いてしまうし、その人物の行動に共感できなくなるというようなことです。おそらく、伝えられるオースティンの性格から考えて、そういうところは気になってしまうだろうと思います。オースティンが、小説を読んでいるだけでは飽き足りなくなって、書くことを始めて、その際に既存小説のパロディから始めたというのは、このように小説を読んでいて、「違う」というところを、自分で矯正するという意味合いがあったのではないかと想像します。しかも、その「違う」というのは、例にあげたよう些細なこと、それを直すということは、結果としてリアリズムのような形になった、と私には考えられます。 オースティンの小説の読者は、おもに女性、とくに当時の社会では、文字を読むことができて、小説を読む時間と生活の余裕のある女性が想定されていたと思います。それは、オースティンが小説の舞台とし、自身も属した中産階級の女性たちで、この人びとが読んで、細部について「違う!」とシラけてしまうことがなく、むしろいまでいう「あるある!」という声があがることで、登場人物に感情移入できたりできる、それが最終的には作品に対する共感に結実する。オースティンの作品というのは、そういう読まれ方をしたのではないかと思います。それは、オースティが小説を読むことに飽き足らなくなり、既存の小説では満足できなくなって、自分で書き始めた。しかし、そう考える人は、当時の社会ではオースティン以外にも存在した。しかし、オースティンように実行する人はいなかったし、オースティンのように才能がある人もいなかった。そういう人々がオースティンの背後にたくさんいて、それが彼女の小説の読者にもなったのではないかと思います。それは、現代のマンガやアニメのファンの広がりの中から、二次創作の人たちによる同人誌が作られ、コミケットという場で評価がされて、その中から新たな作家が生まれていったのと同じような(それほどシステム化されているわけではないでしょうが)、径路だったのではないかと思います。 2.共感とリアリズム、そしてキャラクター 2−1.オースティンのロマン主義 ここでオースティンが小説を執筆していた当時の文学の状況を簡単に眺めてみましょう。イギリス文学史の年表を見て、オースティンと同時期に活動している人々を拾い上げてみると、ワーズワース、コールリッジ、バイロン、シェリー、キーツといった人々が上げられます。ちなみに、イギリスの小説家としてオースティンと並べて上げられることの多い、ブロンテ姉妹やディケンズといった人々はオースティンの一時代後に活動したので、同時代ではありません。オースティンの活動していた時代は文学史ではロマン主義の詩人たちの活動していた時代でもありました。オースティンも、それらの詩人の作品は、近しいとはいえないかもしれませんが、読まなかったということはなかっただろうし、彼らのロマン主義とは創作においてまったく関わりがないとはいえないでしょう。 あるいは、ロマン主義に近しいゴシック・ロマンスの小説はオースティンの『ノーサンガー・アビー』のヒロインであるキャサリンはラドクリフ夫人の熱狂的な読者であるという設定で、この作品自体がゴシック・ロマンスの小説のパロディの体裁をとっています。そのようなまわり道をしてはいますが、間接的にロマン主義の影響の痕跡を、オースティンの作品に見出すことはできると思います。 ロマン主義とは一言でいえば、個人の主体、とくに感情とか感受性の重視です。オースティンの『分別と多感』というタイトルをそのままのようですが。それを物語の場合に置き換えてみれば、様々な登場人物が行動して、関わってドラマやストーリーが生まれるというのに対して、個々の人物がそのように行動するにはその人なりの理由がある。そういうことを深く追求する。例えば、恋愛の物語では、恋人が出会って、事件が起こる。そこに行き違いがおこったりして、結果が悲劇か喜劇か。それで物語ができます。しかし、個人の主体を重視することになれば、恋人になるのは、その二人で、他の誰でもないわけです。そうなるには、他の人でなく、その二人である理由がある。それはその二人が、このような性格であったり、このように感じたり、思ったから。そういう二人が愛し合うのは、読者が読んでいても、そうだと思う。そこに共感が生まれる。それが、今までの物語のように単にストーリーを追いかけるだけとは違う読みを生むことになるわけです。 そういう物語を作るためには、恋人どうしになる二人の人物を細かく描写して、二人が出会って、愛し合うまでの感情の動きを細かく描写する必要があります。それは、波乱万丈に物語を動かしていけば、零れ落ちてしまうようなものです。零れ落ちてしまうもの、具体的には、出会ったときに、どのような服を着ていたとか、その印象とかいったような、細かい描写を積みあげていくことになるでしょう。そういう、日常の些細ともいえる小さなことを描写するというのは、まさにオースティンの小説の方法論そのものではないでしょうか。つまり、オースティンはロマン主義には分類されてはいないようですが(むしろ、ロマン主義とは正反対に位置づけられているようです)、彼女の作品には彼女が生きた狭い世界、つまり、当時の英国の田舎に住む紳士階級の自営業の日常が坦々と描かれていて、大きな事件とか歴史的な出来事がおこるわけではありません、それなのに、その小さな世界の人々の営みが物語をつむいでいくのは、人びとの感情を丁寧にすくい取って描いているからです。そこに、個人の感情や内面に注目して、読み手の共感を誘うロマン主義の影響があると言えるのではないかと思います。ただ、ロマン主義についてまわる、個人の内面でもネガティブな方向、例えば不安とか、そこから派生した無軌道な行動とかいった極端なイメージはオースティンにはないので、両者を結びつけて考えられていないと思います。例えば、オースティンの作品で『マンスフィールド・パーク』では、ヒロインのファニー・プライスは、ほとんど自分から行動を起こさないで、常に受け身でいるという物語で、この場合受け身のヒロインが、何を見た、どう思ったということで物語が進むのです。そこには、登場人物の個人のキャラクターを掘り下げて描き込み、そういうキャラクターの思いが交錯する、特にヒロインが何を思うという、内面の動きが物語を作っていくのです。 それはどうしてか、オースティンの同時代人として名前をあげた詩人たちは、理念としてのロマン主義を標榜して創作しました。これらは産業革命や重商主義への反動として、それまで合理主義とか理性によって抑圧されてきた個人の根本的独自性を解放するといったことでしょうか。それゆえに、『説得』でアン・エリオットが詩に惑溺するベネットに深入りしないで散文でも読みなさいと忠告するところがありますが、抽象的な概念を弄ぶ言葉遊びをして自己満足して、読者をそれに巻き込むようなところがあります。しかし、オースティンの作品にはそういうところはなく、理念から入ったのではなくて、個人の日常的な振舞い、当たり前の行動を仔細に見つめていくうちに、個人の生活に分け入って、その奥のプライベートなところが浮かび上がってしまった。それが心情だったり感情だったりというものです。それは、あくまでも具体的な事物で、けっして抽象的な理念や概念で語られるものではなかったのです。 2−2.リアリズムといってもすべてを描写しているわけではない オースティンは、自身も属する中産階級の人々の生活を忠実に描写しました。それゆえにリアリズムと言われるのでしょう。しかし、オースティンはリアリズムといっても、人々の生活を全部描いたわけではありません。つまり、書かれたものと書かれなかったものがあるというわけです。そもそも、それまでの文学では、統治者とか英雄を描いていたのであり、そうでない普通の人々の日常的な生活を描いた作品というのはなかった。そこで、オースティンのような、そうでない人びとの日常生活を描いたものはなかったのです。だから、そういうものを描いたオースティンは目立っていました。 では、オースティンは、そのリアリズムの描写をどのように行ったのでしょうか。中産階級の人々の日常の生活を描写するといっても、そのすべてを忠実に描くわけではありません。そこに書かれるものと、書かれなかったものがあるのです。ここで考えるのは、どのようなものが描かれたのかということです。そこにはオースティンの意図的な選択があったと考えられます。彼女は計算したうえで、選択をしていたと考えられます。 その選択の一つは、彼女が実際に見聞きすることができたことなら十分な知識がありましたが、そうでないもの分かりようがないので書かれなかった。例えば、女性であるオースティンが入ってゆけない男の世界。例えば、男同士の会話やビジネスの場面は、オースティンの小説に登場しません。 その反対に、オースティンは同じような場面をくり返し描きました。例えば、舞踏会の場面は男女の出会いの場であり、恋愛小説では重要な場面になるところで、夢のように描かれます。それが、『ノーサンガー・アビー』では、ヒロインのキャサリンがアレン夫人に舞踏会に連れて行かれるところで、素敵な男性との出会いや煌びやかなスポットライトを期待して行ったところが、会場は非常に混雑していて、人ごみにもみくちゃにされ、しかもアレン夫人は知り合いを見つけることができなかったので、落ち着くこともなく、パートナーを紹介してもらうこともできませんでした。結局、人ごみのなかで右往左往しただけで、パートナーがいないのでダンスをすることもできず、ただ壁ぎわに立っていて疲労だけが残ったという散々なものとなったというのです。夢もへったくれもない、身も蓋もない現実が容赦なく描かれているわけです。しかし、それだけでは読者にとっても面白くもなんともないので、この小説では、この後も舞踏会の場面があり、キャサリンはヘンリー・ティルニーという男性と出会うことがあったり、その後の舞踏会では思いを寄せるヘンリーと踊ることができるように計略をめぐらしますが失敗してみじめな気持ちになったりします。また、『高慢と偏見』では、エリザベスとダーシーが出会い、喧嘩をすることがあったり、エリザベスがコリンズに振り回されて辟易させられたり、『分別と多感』ではマリアンとウィロビーの恋人同士の無軌道な振舞いがめだったりします。これらは、恋愛小説の夢のような場面というワンパターンに終わらずに、現実の舞踏会で起こっていることを女性が思いの人と踊るためにめぐらしている計略や駆け引き、あるいはハプニング、有形無形のしきたり、裏方の苦労などを描くことによって舞踏会での登場人物の行動が多彩になって、そこで起こる出来事のバリエーションが豊かになって、そこで人々は出会いの喜びに限らず、幻滅したり、疲れたり、怒りに駆られたり、様々な思いが交錯することになるのです。その結果、舞踏会に参加している人々が、人びとという群衆にとどまらず、その中から誰と誰というように個人が浮き上がってくることになるのです。この場合、舞踏会というのは現実の描写ではあるのですが、ひとつの象徴的なものとして作者によって取り出されて、そこで現実に起こったパターンをバリエーションとして物語の展開に沿って活用されて、物語を活性化させたり、伏線をつくったりして使い回されているのです。 ですから、リアリズムの描写と言われていますが、オースティンは類型的な描写ではできないバリエーションをリアリズム的な描写によって作り出して、そのバリエイションを物語の進行のために使いまわしている。つまり、物語を構成するツールとして、そこに新しい意味を生み出すことまで行っています。その実例を、少し見ていきましょう。 2−2−1.恋愛、結婚 オースティンの小説は若いヒロインが様々な出来事を経て自分にふさわしい男性と恋をして結婚し、幸福になるというパターンを踏んでいます。したがって、恋愛し結婚するというのは、すべてのオースティンの小説の中心的な事柄です。ということは、ヒロインの恋愛はすべて結婚というハッピーエンドの結果と結びついているのです。それで、恋愛と結婚をまとめて、セットとして見ていきたいと思います。 『高慢と偏見』の第1章冒頭の有名な書き出しで、語り手はこう述べています。「財産のある独身男性なら、妻をほしがっているにちがいないということは、普遍的真理である」と。これはまさに、当時の結婚に関する通念です。「普遍的真理」として大上段に振りかざすような哲学的命題でもなんでもないところに、皮肉がこめられています。どちらかというと男性側よりも女性の家族側からの見方のようですが、とにかく女性にとって結婚とは、人生において絶対に確保すべき要素である、ということが冒頭から宣言されているのです。また、第22章には、ヒロインであるエリザベスの友人シャーロットが、年齢的に婚期を逸しかけているため好きでもないコリンズの求婚を受け入れる、という箇所があります。そこで語り手は、彼女が結婚を決めた理由について、こう述べています。「教育があっても財産の少ない若い女性にとっては、結婚は、名誉を保ちながら生きてゆく唯一の道であり、たとえ幸せになれるかどうかは不確かでも、欠乏を免れるための最も望ましい方法だった」と。これはシャーロットの考え方の表明であると同時に、当時の社会状況を映し出す言葉であるとも言えるでしょう。19世紀の一般的な女性にとって、社会的地位と経済力を確保するには、通常、結婚という選択肢しかなかったといいます。中産階級以上の女性にとって、淑女としての品位をどうにか保てる職といえば、世紀末になって教職や公務員、看護職などの地位が上がるまでは、文筆業か女家庭教師(シャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』の主人公は家庭教師です)くらいでした。何と言ってもいちばん高く評価されていたのは、結婚して主婦になること。妻が「家庭の天使」であるべきだという価値観が通底していた19世紀において、結婚とは女性にとって、職業と同義だったとも言えるのです。 しかも、実家がそれほど裕福ではなく、持参金があまり期待できない女性にとっては、何らかの方法で夫と家庭を手に入れないと、将来の生活も保障されない。上で上げられている家庭教師でも決して楽なものではなく、最後の砦でしかなかったことは『エマ』のジェイン・フェアファックスが家庭教師の職に就くのに決死の覚悟でいる様子でいるのが描かれています。だからこそ、『ノーサンガー・アビー』のイザベラ・ソープや『分別と多感』のルーシー・スティールのような良い条件の男性を手に入れるために、ときにはライバルとなる他の知恵を女性を蹴落としてまで、知恵を働かせて、手練手管を弄する女性もでてくるのです。 作者のオースティンも、このような女性たちの一人です。彼女は当時の絵空事のような恋愛小説の満足できなかったとすれば、同じような女性たちもいたはずです。そういう女性たちにとって、現実の自身と同じような女性をリアルに描いた小説は、絵空事ではなく、自分の物語として現実の自分の身の上に置き換えて読むことができたかもしれません。その時に、悲劇だったりしたら身に詰まされてしまう。だからこそ、コメディ・タッチで最後はハッピー・エンドの作品になっているのではないか。少なくとも、皮肉はあっても、基本線はポジティブで、当時の女性たちへの応援歌を、オースティンは心の底で、読者に送ろうとしたのではないか、と想像してしまいます。 なお、ヒロインは恋愛が結婚と結びつきますが、枠役ではそうでないケースもあります。それは、ヒロインでは絶対に描かれなかった恋愛の形態、例えば不倫や駆け落ちといったケースです。『分別と多感』では、ブランドン大佐の初恋の人イライザは不幸な結婚を強いられた結果、駆け落ちをすることになります。その遺児ミス・ウィリアムスはウィロビーに誘惑され捨てられてしまいます。これは、この話を聞いたマリアンがウィロビーと決別する援けと、ブランドン大佐に好意を持つ契機となります。『高慢と偏見』ではエリザベスの妹のリディアがウィッカムと駆け落ちをしますが、ダーシーの奔走で汚名だけは免れました。この件でエリザベスはダーシーへの感謝の気持ちと、ペンバリーでの再会依頼もった好意を恋愛感情に高めるのを援けることとなるわけです。『マンスフィールド・パーク』のマリア・バートラムはラッシュワース氏の妻となりながら、ヘンリー・クロフォードと駆け落ちし、サー・トーマスから追放同然の扱いを受け、また、ヘンリーは不道徳の烙印を負いファニー・プライスが彼からの求婚を拒んだことが正当化されることになるという、ヒロインの恋愛成就のバックアップをする結果となります。あるいは『ノーサンガー・アビー』イザベラ・ソープがキャサリンの兄ジェイムズと婚約の身でありながら、ティルニー大佐に誘惑されて、捨てられてしまいます。このように、これらはすべて、当事者たちは因果応報ではありませんが、不道徳ゆえの報いとして何らかの制裁を受け、他方でヒロインが恋を成就する際の、伏線としてのエピソードとなっています。 この恋に挫折する脇役たちとハッピー・エンドを迎える主人公たちとの違いはどこにあるのでしょう。物語の上での主人公と脇役ということは別にして、この人物たちの違いのひとつは、その道徳性の有無にあります。主人公たちは不正をしないのです。これは、ある意味でオースティンの作品が上品で、教科書に載っているような作品と誤解されてしまう要因でもあると思います。それは、女性たちが置かれている現実を真正面から見つめながら、むしろ、それゆえにこそ愛情ということを心から求めるゆえからではないと思います。『高慢と偏見』で、コリンズと結婚したシャーロットについて、エリザベスが愛というものの大切さを説いています。これは、オースティンの本音ではないかと思います。だから、リアリズムの描写と言われるオースティンの小説ですが、単に現実を見たままに描いていのではなく、その現実を見る視線に、理想主義的な視点が隠されているといえるのです。この小説の、主人公たちは、単に道徳的なだけでなく、そういう正しさをもっているがゆえに、小説の中で、一度困難に直面し、それを乗り越えていくことによって、自身を変えていく、いわば自己変革を行っていて、それによって、相手に受け入れられる、あるいは相手を受け入れることができるようになって、ハッピーエンドにたどり着くことができることになっています。いわば、オースティンの小説は恋愛小説であると同時に教養小説でもあるのです。例えば、『ノーサンガー・アビー』のキャサリン・モーランドは夢見る少女から現実の男性を認識する大人の女性に脱皮します。『分別と多感』のマリアン・ダッシュウッドは感情の赴くまま周囲を顧みない自己中心的な振舞いに気がつき、姉と和解します。『高慢と偏見』のエリザベス・ベネットは自分が賢明であると調子に乗っていたことに気づき、相手のダーシーも偏見を克服し、二人は結ばれます。『説得』のフレデリック・ウェントワースはかつて自身をふったアンを恨んでいましたが、アンの分別と変らない愛情に気づくことで、愛を求めることができるようになるのです。 その一方で、いわゆるラブ・シーンというのがオースティンの小説には皆無で、恋人たちが愛を語らい、互いに育んでゆくというところがありません。それぞれが愛情に気づいたら、それを自然のこととして受け止めてしまっている。むしろ、オースティンの恋人たちは、その愛に気づくまでがドラマで、物語は、そこを丹念に追いかけています。それは、結婚についても、結婚するまでは描いても、結婚したあとで、二人が夫婦関係をつくりあげていくところは全く書かれていません。 2−2−2.恋愛相手をゲットする場として、舞踏会、遠足 この時代の中流階級の女性たちにとって結婚は生きていくために必要な手段でもあったことは、前で述べました。しかし、その結婚には相手が必要で、その相手は家系の利益を優先して親が相手を選ぶ結婚の形態がすたれはじめ、当事者である若い男女が相手を選ぶよう変わってきていました。家父長が子供に自分の意志をおしつける結婚は、もはや時代遅れになったのです。つまり、かつては親が相手を用意してくれていたのが、当時の人々は自分で相手を見つけなければならなくなっていたのです。しかし、とくに女性は勝手に出歩いて、若い男性の集まりそうなところで相手を探すなどということはできませんでした。男女の出会いの場は限られていたのです。とくに女性に関しては、そういう限られた場でもコンダクト・ブック(淑女教育のための行儀作法書)が次々に刊行され、厳しいマナーとモラルが要求されていました。 例えば、男女の出会いの場である舞踏会での未婚女性の振舞いが自分の立場にふさわしいか否かは、その人物を判断する基準となっていた、といいます。当時の女性は自分から男性を踊りに誘うことはできず、しかも、踊りに誘われず、年輩の夫人たちとともに「壁の花」になることは、若い女性にとっては不名誉なこととされていました。「壁の花」がつづくということは、男性と親しくなる機会を得ることができないことになって、結婚も遠のくことを意味してしました。ではどうしたら踊りの相手を確保できるのか、知り合いが多ければ踊りの誘いを受ける可能性が高くなります。そこで、女性の両親の責任となり、親の知己がいかに多いか、それによって娘に男性をどれだけ紹介できるかは両親や親戚の腕にかかっていたのです。『高慢と偏見』の冒頭で、近所に引っ越してきたビングリーの情報を聞きつけいち早く訪問して知り合いになってくれ、と夫を促すベネット夫人の行動は当然のことなのです。あるいは『マンスフィールド・パーク』でファニー・プライスがサー・トーマスに舞踏会を開いてもらって社交界デビューを果たしますが、サー・トーマスというバックがあって、ファニーは舞踏会で主役として疲れるほど踊りに興じることができたのです。また、さきほども触れましたが『ノーサンガー・アビー』のキャサリンは折角出かけた舞踏会で踊ることが叶わず、その後公営の舞踏会で進行係を務める紳士が踊りの相手に男性を紹介するシステムのおかげで、ようやく相手に出会うことができた、それがヘンリー・ティルニーだったというわけです。 一方、女性は誘われるだけで、自分から誘うことが出来ないであっても、女性に与えられた選択の権利は嫌な相手から誘いを断るだけでした。しかし、これにも制約があって、はっきりした理由が必要とされていました。誘われた男性が気に入らないからという理由で断るのは礼儀に反しているとして、すでに先約があるとか、疲れているので踊れないという理由しか認められなかった。そして後者の理由でことわった場合は、その後に気に入った男性から誘われた場合もいったん疲れているからと他の男性を断った手前、断らざるを得なくなるのでした。『高慢と偏見』ではエリザベスがコリンズに「あなたは牧師だから踊らないのでしょうね」と余計な言葉をかけてしまい、「とんでもない、それどころかぜひ最初の踊りを私と踊ってください」と誘われてしまい、ウィッカムと踊りたいのに、コリンズの申し出を断ると、一晩中踊れなくなってしまうので、しぶしぶコリンズと踊ることになるのです。『ノーサンガー・アビー』では、キャサリンが最初の踊りをジョン・ソープと約束したのはいいが、ジョンが舞踏会に現われないので、踊ることができず、せっかくヘンリー・ティルニーから誘われても先約があるからと断らざるをえません。 また、舞踏会は、より多くの異性と知り合うための大切な場として、で、同じパートナーと2回以上踊らないのが暗黙のルールで、あえて同じパートナーと2回以上踊るのであれば、そのふたりは結婚を意識している証拠と見なされました。『高慢と偏見』で、ビングリーがジェイン・ベネットに2回ダンスを申し込むのを目撃すると、母親のベネット夫人はジェインの結婚を確信し、有頂天になって大騒ぎをするのです。『分別と多感』ではマリアン・ダッシュウッドがウィロビーがお互い同士でしか踊らないのは、マナー違反であると同時に二人の強い意思表示で、周囲の人をあきれさせるのです。 2−2−3.恋愛の語らい、手紙 恋愛小説で恋人たちが語り合うツールとして手紙、いわゆるラブレターがあると思います。フランス文学ですが、ラクロの『危険な関係』は書簡体小説で、相手に誘惑の手紙をおくり、そのやり取りによって女性が恋に落ちていく様子が活写されています。そういうものをオースティンの小説に期待すると、肩透かしに遭います。というのも、当時のイギリスの中流以上の社会の慣習では、男女間で手紙のやり取りができたのは、婚約している場合に限られていたのです。だから、『高慢と偏見』で、ジェインがビングリー氏を追いかけるようにしてロンドンに来て滞在していても、婚約しているわけでもないので、直接彼に手紙で知らせることはできずに、代わりに妹のミス・ビングリーに手紙を書くしかなかったのです。ミス・ビングリーはこのことを兄に伝えず、ジェインはビングリー氏に会うことができませんでした。『エマ』では、秘密に婚約していたフランク・チャーチルとジェイン・フェアファックスは自分たちの文通が人に知られないように、十分注意をしていました。『ノーサンガー・アビー』ではティルニー大尉に捨てられたイザベラ・ソープがキャサリンに手紙を送って、兄とのよりを戻すように仲介を頼むのは、婚約が解消されてしまったので、直接彼に手紙を送ることができないためです。また、『分別と多感』でウィロビーに去られてしまったマリアンが、彼を追いかけるようにしてロンドンにやってくると、彼に手紙を書いているのをエリナーが見て、二人が婚約していると確信して安心するのは、手紙を書くことは婚約していないとできないという慣習からです。同じ『分別と多感』で、ルーシー・スティールはエドワードと交わした手紙を二人の婚約の証拠としてエリナーに示すのです。このように、手紙の内容よりも、手紙を書くという行為そのものに、意味がある。その手紙のもつシンボル的な意味が人びとに生み出す波紋を、オースティンは物語を作る際に巧みに利用しています。例えば、手紙によって婚約が成立していると人々が誤解してしまったり、手紙を書くことの制約が男女のスレ違いを生んでいくといったことです。 また、リアリズムとは別に、オースティンの抑制のきいた表現と言われているのは、『危険な関係』のように手紙の内容を、そのまま明かして、どのような言葉が交わされたかを一切書かれていないということです。例外的に、手紙の文面が直接書かれているのは、『高慢と偏見』で、ダーシーがエリザベスに求愛して、手痛い拒絶に遭い、さらにウィッカムのことで追及されたことに対して、真実を説明して自身の潔白を明らかにする手紙です。これは、恋愛の言葉とは全く違うものです。また、手紙ではありませんが、同じ『高慢と偏見』で、互いに一目ぼれのようにジェインとビングリー氏が親しく語り合うという描写がありますが、その語り合う内容は省略されています。単に、周囲の人びとが二人が親しく語り合うのを見たという描写だけで済ませてしまいます。反対に『説得』のアン・エリオットとフレデリック・ウェントワースはほとんど二人だけの会話らしい会話もしません。 2−2−4.恋愛の語らい、遠足 『分別と多感』では見事な庭園で知られたウィットウィル屋敷をみんなで見に行くことが計画されます。当時は、他人の家や庭を観光目的で訪問することがはやり始めていました。もちろん、訪問を許されるのは、服装や立ち居振る舞い、そして言葉から、紳士淑女と判断される人々に限られたものでしたが。たとえ主人が不在でも、ハウスキーパーや執事が、訪問客に家の中を案内するのは珍しいことではなくなっていました。『高慢と偏見』では、求愛を拒絶したはずのダーシーと劇的に再会するのは、このような屋敷の観光訪問の習慣のおかげでした。事情を知らない叔父夫婦にペンバー屋敷を観光しようと持ちかけられ、ダーシーが不在であることを確かめた上で、好奇心から訪れる。そこへ、ダーシーが急に予定より早く帰宅したために、再会することになってしまいます。そこでのダーシーが以前とは変わって、エリザベスに対しても彼女の親戚に対しても驚くほど礼儀正しく、敬意と親愛の情を示すので、エリザベスはダーシーを新たな目で見るようになるという、重要な展開の場面です。ちなみに、『分別と多感』では出発の朝にブランドン宛に手紙が届けられ、それを読んだブランドンは顔色が変わりロンドンへ行くことになります。ウィットウィル屋敷はブランドンがいなければ入ることができないのですが、ブランドンは皆の懇願を押し切ってロンドンに向けて出発してしまい。この計画はお流れとなるのです。物語では、その機会を悪用して、ウィロビーがマリアンを誘い出し、自分が相続するはずの屋敷に二人だけで訪ねるという自分勝手な行いをすることになるのです。『マンスフィールド・パーク』では、マリア・バートラムが婚約者ラッシュワースの屋敷であるサザトン・コートを主要な登場人物が遠乗りします。その庭園の散歩であらわれる人間模様をファニー・プライスがベンチに坐って、まるで演劇の舞台を見るように観察し、その前で、マリア・バートラムは婚約者ラッシュワースを蔑ろに扱い、その一方で、マリア・バートラムとヘンリー・クロフォードの不倫の萌芽があり、エドワードはメアリ・クロフォードに惹かれるものの、どこか違和感を残している、といったことが露わになってきます。『説得』では、ライムへの小旅行で、ウェントワースが以前のアンと違って強い意志をもっている故に好感をもっていたルイーザが、周囲の忠告を無視して事故に遭ってしまいます。それを見て、ウェントワースは意志の強さと分別とは別であると、かつてアンに求愛を断られたことを冷静に見直し、アンを愛していることを再自覚する契機となります。 これらのように、屋敷の観光訪問など、主な登場人物が集まって馬車に分乗して遠出をするというのは、比較的新しい慣習で、オースティンは、それを巧みに小説に取り入れています。ここでは親しい仲間だけのうちうちの環境で、しかも、日常的な社会から離れた場所で、相対的に社会のしきたりから解放された(言ってみれば、旅の恥はかき捨てのような状態)特別な空間です。そこで、人々の普段は隠されていた思いや、本性が垣間見えてくる。それをオーステイィンは、主人公たちが自身の恋心に気がついたり、相手への誤解を解いたりする、物語全体の転回点として巧みに生かしています。 2−2−5.恋愛の語らい、晩餐、サロン 『分別と多感』では、ダッシュウッド母娘がバートン・コテージに引越すと、サー・ジョンが食事に招待し、そこでブランドン大佐を紹介されます。『高慢と偏見』では、引っ越してきたビングリー氏を一家の父親のベネット氏が訪問し、食事に招待する。あるいは、舞踏会とビングリー氏や、その姉妹に気に入られたジェインが食事に招待されるところがあります。『説得』ではマスグローブ家のディナーにフレデリック・ウェントワースが招待されて、アンが子供の看病でいけなくなり、翌朝、マスグローブ家の娘たちが彼の印象を話しているのを聞く場面があります。これらのように、食事への招待と、そこでの紹介も男女の出会いの場であり、交際を深める場でもあったということでしょう。当時の領主たちにとって、ディナーは、その家の地位、洗練度などを示す大事な機会でありました。ディナーは時間、中味が重要で、とくに客を招く場合は贅沢な材料を使って、客が食べ切れないほどのご馳走を何コースも用意することでもとなし側の富や地位を誇示していたといいます。但し、当時の食事のコースは現代とは違って一皿ずる料理が各自に運ばれ、食べ終わると次の料理が出てくるというのではなくて、肉やスープや野菜等がテーブルに並べられて各自が好きな料理を好きなだけ取って食べるという方法でした。食事が済むと、男女別に男は喫煙室で煙草を一服したり、女は談話室でお茶や菓子をつまんだりして、そこで会話があり、『高慢と偏見』ではエリザベスがキャサリン・ド・バーグと議論するのは、このような場でした。あるいは、『分別と多感』でエリナーがフェラーズ夫人に苛められるのは同じような場でした。 2−2−6.プロポース、愛の告白 前にも触れましたが、当時のイギリスの中流階級の社会では、恋愛において厳しいマナーとモラルが求められていたといいます。まず個人の愛情に対する「社会的おすみつき」としての「婚約」が発表され、晴れて後、ようやくカップルは節度ある態度で愛情を世間に示すことが許されたそうです。「婚約」は個人的愛関係を社会で是認させるもの、即ち、個人的関係に社会的意味を付与するもので、若い女性が婚約もしていない男性と浮名を流すことは社会のコードに違反し、「浮気女」とか「男たらし」のそしりを受けることになり、最悪の場合は「堕落した女」として社会から追放の憂き目にあうこものだったそうです。つまり、男女が公然と互いに愛を語るのは婚約を世間に公表してはじめて許されたというわけです。その婚約のためには、プロポーズがあって、それを承諾して、初めて契約、つまり婚約成立です。この場合、プロポーズするのは常に男性です。これは、舞踏会で踊りを申し込むのは専ら男性で、女性はその申込みに対する拒否権としてしてしか自由がなかったと、前に触れましたが、同じことはプロポーズにも言えます。だから、女性は、男性からのプロポーズを待っていた。しかし、実際は待っているだけでは始まらないので、女性の方から男性にプロポーズしてもらうために、様々な働きかけする。それが戦略だったい手練手管で、その段取りを活写したのがオースティンの小説で、それが大きな魅力になっています。例えば『説得』のアン・エリオットは、ウェントワースの目の前でハーヴィル大佐と男と女のどちらが長く愛情を持ち続けられるかという議論をはじめ、そのなかに、ウェントワースのことを変わらずに思い続けているということを、脇で聞き耳をたてているウェントワースには分かるように含ませて語ります。それで、ウェントワースに求婚する勇気を与えます。『マンスフィールド・パーク』のファニー・プライスは、ただひたすら耐え忍び、待ち続けるヒロインです。相手のエドワードは彼女を妹のように思っていたのが、メアリー・クロフォードとの恋に破れた彼を慰め、慕ってくれていることへの感謝が愛情に変わっていったのです。『分別と多感』のエリナー・ダッシュウッドもファニーと同じように、エドワードを信じて待ち続けます。また、『高慢と偏見』のエリザベス・ベネットとダーシーの場合は、エリザベスがアグレッシブにダーシーに突っかかるようにして、会話のやりとりをしていくうちに互いの高い趣味や教養そして人柄を理解しあうようになる、それはオースティンの見事な会話の描写に鮮やかに表われています。このように、オースティンの小説ではヒロインが相手にプロポーズさせるプロセスが一番の中心と言ってよく、そこがもっとも力を入れて書かれています。そのもっとも典型的な作品が『高慢と偏見』です。しかも、ヒロインのエリザベスは、物語の中でプロポーズを二度も断っています。ひとつはダーシーからのプロポーズで、これによってダーシーは自身の高慢に気がついて、自己を見直す契機となります。もうひとつはコリンズからのプロポーズを拒絶したことで、これは作品の皮肉を笑いの全開するような場面でした。その他に、オーステインの小説のヒロインでプロポーズを断ったのは『マンスフィールド・パーク』のファニーで、ヘンリー・クロフォードからのプロポーズを拒絶します。ヘンリーの不道徳で誠意に欠ける性格をファニーは見抜いていたためですが、周囲には理解されず、そのためマンスフィールド・パークを追い出され、実家に帰らされることになってしまいます。
2−3.オースティンが描いていないもの オースティンはリアリズムといってもすべてを描写しているわけではないとして、彼女が実際に見ていないこと、例えば男性の会話とかは描かず、実際に見たものをパターン化して描いているということを述べました。しかし、オースティンは、実際に見たものを見たまま全部描いているわけではない。そこには、見たけれど描いていないものがあるわけで、その場合、描いていないのは、見ていないからではなくて、見たけれど描いていない。そこに意図的な要素があります。つまり、オースティンが敢えて描いていないものがあります。それを探っていくと、側面からオースティンの小説の特徴が炙り出されてくると思います。 例えば、舞踏会の場面では、会場がどのくらい広いかとか、そのインテリアや飾りつけがどうだとか、出席している女性たち、とくにヒロインはどのような服を着て、どのように装っているかということは、あまり描かれていません。そういう説明があったとしても、贅沢に飾られた豪華な舞踏会だったとか、人で溢れていたとかというような抽象的な書き方しかなされていません。そこで描かれているのはヒロインがどのように振舞い、人びとと会話を交わし、どのようことを思ったかということです。つまり、物語を進めることに集中している。別に偏見があるわけではありませんが、作者のオースティンは女性です。舞踏会でヒロインが着る衣装や装身具などに興味がないはずがありません。ましてや、小説の読者として女性、とくに若い女性が想定されているはずで、そういう人々はオースティン以上に、そういうものへの関心は高いはずです。実際に、そういうものを詳細に描写した小説もあったはずです。現代でも映画が流行ると、その中でヒロインが着ていたファッションを真似る人が続出する現象はありますが、それと同じようなこともあっただろうし、そういうことを作品の魅力のひとつとしていた小説もあったはずです。そういうなかで、オースティンの小説が、そういうものを切り捨てていることには、表現の抑制のためというようなことでは言い切れない、意思を感じます。積極的な理由がいくつかあげられます。ひとつは、そもそも、オースティンは既存の小説に飽き足りず、小説を書き始めたとしたら、既存の小説のそういうところにも不満はあったかもしれないということです。『ノーサンガー・アビー』のキャサリンやイザベルが小説のヒロインの真似をすることの滑稽さを皮肉る描写などからも、そういう小説の読み方には批判的な目をもっていたと考えられます。そのようなオースティンが、そういう小説の読み方を誘発するような要素を自作に取り入れようとしたかどうか、避けようとしたと考えるのが自然に思えるということです。そして、二つ目の理由として、こちらの理由の方が大きいと思いますが、ファッションなどは敢えて書かないことによって、読者に自由に想像させようとしたのではないか、ということです。つまり、オースティンの小説がリアルに感じられるところは「あるある」と思わせるところだと述べましたが、ことファッションについては人それぞれの好みがあったりします。また、ファッションには色々な傾向があって、そこで特定してしまうと、そこで登場人物、とくにヒロインのイメージが偏ってしまうおそれがある。それは、読者の周囲の身近な人に当てはめるようなリアルな感じが、ファッションを特定してしまうと、少しでもテイストが異なると身近な感じが失せてしまうおそれがある。それならば、敢えて具体的なことは描かずに、読者が自分で想像してファッションを当てはめるようにした方が、自分のほうに登場人物を引き寄せて読むようになると図ったのではないかという理由です。そして、さらにもうひとつの理由として、オースティンの小説の語りが、しばしばヒロインの声と重なるという語りからです。大半のオースティンの小説は全能の神のような立場で作者が客観的な語りをしていないのです。したがって、舞踏会の場面を描写するときに、客観的な視点と同時にヒロインの視点で語られることが多い。その場合、ヒロインの視点は客観的な視点とは違って視野が限られ、その限られた視野というのはヒロインの主観に起因するものとなります。その場合、どうしてもヒロインの主観の価値判断が入ってくることになる。その視点でファッション等を描こうとするとヒロインの価値判断、つまりファッションのセンスが問われることになる。そうすると、例えば『高慢と偏見』のエリザベスは趣味と教養の高い女性ということになっていて、教養の点では客観的な基準をクリアしていればいいのでしょうが、趣味の点では、主観的な好みが混じることになってきます。その要素としてファッション・センスもあるわけで、好き嫌いが分かれるものをはっきりと出すことにはリスクがあります。話は変わりますが、同じ作品の中で、ベネット一家の人々の振る舞いや会話でダーシーを失望させるような不作法については詳細に具体的に描かれていますが、反対にエリザベスやジェインの振舞いは作法にかなっているという抽象的な描き方をされています。それと同じです。 また、このような小説の語りが客観的でないことに起因するものとして、他に、作者オースティンが敢えて小説の中で書くことをしないことが、ヒロインの思いを寄せる相手の男性が、どう思っているかということについて、作中では直接的に説明されることは、ほとんどありません。それらは、終わり近くなって彼らがヒロインにプロポーズするときに内心も告白されるのです。その間、小説の語りには、ヒロインの立場に立つことがあって、その場合には、客観的な視点ではないので、相手の男性がヒロインのことをどう思っているのか分からない不安定な気持ちが表われることもあります。例えば『分別と多感』ではヒロインのエリナーが思いを寄せるエドワードが、彼女の思いを裏切るような行動をしたり、彼女の思いに応えることを逃げようとする素振りを見せたりするので、エリナーは不安に耐えることになります。小説では、エドワードについての記述がほとんどなく、エリナーに噂が聞こえてきたとか、エリナーが推測したこととか、そういう記述が多くなります。そこでは、エドワードの真意は、敢えて描かれない。それによって、読者はミステリー小説を読むようなサスペンスを味わうことにもなるのです。あるいは、『説得』では、ヒロインのアン・エリエットが元カレのウェントワースと再会するのですが、彼女は未だに彼のことが忘れられないので、彼の一挙手一投足に目が行ってしまう。しかし、彼はアンを避ける素振もみせる。それを作者は、アンが見たという視点でウェントワースを描きます。そこで、読者はやきもきしながら小説を読み進めることになるのです。これは、読者にヒロインの相手の心のうちを想像させるようになっているということです。それらよって、読者はヒロインと同じ視点に立って物語に参加することになり、ヒロインに感情移入して小説を読むように誘われるわけです。これは、また、小説の中の人物の描き方がパターン化されているので、読者としても、そのような想像をやりやすくなっている、と思います。オースティンは、登場人物をキャラクターピースのように系統化して使いまわすということに連なっていると思います。 2−4.人物個人の掘り下げリアルに描写するためのキャラクターピース これまでみてきたのは、場面や事物をリアリズム的な描写によってバリエーションを作り、物語を広げてきたということですが、オースティンは、それを人物でも行っています。むしろ、人物では、それをさらに追求していると言えます。そのために、人物を類型化して、その類型化したものを典型的な人物としてまとめあげていわばキャラクターピースとして、各作品の中で適宜、状況に当て嵌めて使いまわしていると言えます。オースティンは、単なる類型化にとどまらず、そのことによって描く人物を絞り込みことができるので、それを利用して現実の人間観察に基づいて人物を深く描き込むことができるようになっていると思います。例えば、品性にかける人物、性格の悪い人物、浅はかな人物たちの、性格があらわれるような会話や振舞いがストックされていて、物語のなかで、味わいのある脇役として、主人公を困らせたり、場に笑いを供給させたりしていると言えます。これは脇役にとどまらず、物語の主役であるヒロインと、その相手の男性にも言えることです。 オースティンの小説は、こういう人物を描きたいと主人公の造形から物語がつくられていくというよりも、キャラクターピースとして、映画のキャスティングのように人物のパターンをストックとしてもっていて、それを組み合わせて、物語に当てはめる、あるいは組み合せの関係で物語ができていくという構造になっていると思います。その理由は、リアリズムの描写ということが関係していると思います。というのも、リアリズムの描写というのは、目に見えて現われているだけを描写するというのが原則です。それは目の前に現われていないものは表現しないということです。したがって、小説で書かれることは目の前に現れているもの、人間の場合は、外面に現われているものです。典型的なものは行動です。抽象的なこと、例えば性質を抽象的に書くのではなくて、実際にそれが行動にどのように現われるかを書くということです。その場合には、あいまいな表現は、避けなければなりません。例えば、分別のある人というと曖昧ですが、実際の行動に落とし込むと、このようなケースで、とこまで感情を抑えられるかによって、あるように振舞うことができるか、この程度のことしかできないか、細かい差がでてきます。それをパターンのバリエーションとしてストックしてあれば、その細かい差異を具体的に表現することができることになります。それは、その人物の性質について細かく表わすことができることになる。それは、人物の造形の深さにつながることになります。 一方読者としては、オースティンの一つの作品だけにとどまらず、全6作品を読んでしまって、それぞれの作品の登場人物を把握してしまうと、人物の系列化ができます。例えば、ヒロインを導くパターンの男性の系列として、『エマ』のナイトリー、『ノーサンガー・アビー』のヘンリー・ティルニー、『分別と多感』のブランドン大佐、あるいは『マンスフィールド・パーク』のエドワードも一部当てはまるといえますが、その人物たちを相互に比較してみると、共通点と違いが明らかになってきます。そうすると、その違いが、彼らの個々の特徴なわけ、ひとつの作品だけを読んでいては気づかない、彼らの性格の特徴を深く掘り下げることができるのです。それを実際に、どのような系列があるのか、少し見てみましょう。 2−4−1.ヒロインの系統 オースティンの小説はすべて女性が主人公であり、6篇の小説で6人のヒロインということになります。ただし、ヒロインと同格扱いの姉妹が、その内数編で登場するので、それを含めると8人と数えることができると思います。これらのヒロインたちは、大きく2つのタイプに分けることができると思います。 ひとつは、『ノーサンガー・アビー』のキャサリン・モーランドのような純粋でナイーブな系統です。このタイプの系統の女性は、純粋であるがゆえに性格の点では誠実で曇りのない人物です。しかし、分別に欠けて失敗を重ね、それが小説では滑稽の種にされます。しかし、このタイプは物語のなかで自ら成長していきます。そして、この系統の女性は、ヒロインを教え導くタイプの男性が相手になります。時には、ヒロインにとって年齢が上の男性です。この系列に入ってくるのは、キャサリン・モーランドのほかに『エマ』のエマです。その他に、『分別と多感』のマリアン・ダッシュウッドも、この系列に入ると思いますが、この女性は前の二人に比べて悲劇的なところがあります。彼女は、手痛い失恋の後かなり年上のブランドン大佐の愛を受け入れます。ヒロインではありませんが、同じ小説の中で、マリアンと相手から捨てられるよく似た女性イライザ・ウィリアムは脇役ですが、マリアンと同じタイプです。この小説の中では、同じような不幸に遭いながら立ち直るマリアンと対照的な存在として、マリアンを際立たせています。このタイプは脇役にもいるのですが、イライザとおなじように悲劇的な運命になるか、分別に欠けたところかエスカレートして不道徳な行為に走る女性たちがいます。例えば、『マンスフィールド・パーク』のサー・トーマスの二人の娘、マリアとジェシカ。ファニーを嘲笑するような二人は、遊び人の男性と駆け落ちをしてしまいます。『高慢と偏見』のエリザベスの妹リディアはウィッカムと駆け落ちして家族に大きな迷惑をかけることになります。このような不道徳ではありませんが『説得』のルイーザ・マスグローブは旅先で無鉄砲な行為によって事故を引き起こし、みんなに迷惑をかけます。ただし、彼女はこの事件がきっかけでベニックという男性と出会い、結ばれます。男性の系統として、『分別と多感』のマリアン・ダッシュウッドと結ばれるブランドンのタイプは、エマと結ばれるナイトリーも同じ系列で、キャサリンと結ばれるヘンリー・ティルニーも年齢は若く、前の二人に比べて未熟なところはありますが、この系列に連なるでしょう。つまりもこの系列のヒロインは、同じ系列の男性と結ばれています。 そして、ヒロインのもうひとつの系統は賢明なタイプの女性です。この典型は『高慢と偏見』のエリザベス・ベネットでしょう。彼女に対して『分別と多感』のエリナー・ダッシュウッドは分別のある女性でエリザベスのような行動力はありませんが、現実に家族をまとめ支えています。また、『説得』のアン・エリエットはオースティンの小説のヒロインの中でももっとも成熟した大人の女性です。彼女もエリエット家を現実に切り盛りしています。彼女たちに比肩するほど賢明な女性は数少ないでしょうから、小説の中でも、他にほとんどいません。最初のタイプの女性か脇役でもバリエーションとして様々なひとがいたのと対照的です。強いてあげるとすると、『マンスフィールド・パーク』のメアリ・クロフォードは趣味も教養も申し分ないのですが、道徳的な面でエドワードと結ばれることなく別れてしまいます。『エマ』のジェイン・フェアフックスで、小説のなかでは脇役ですが、主人公のエマよりも優れた女性といえます。『高慢と偏見』のエリザベスの親友シャーロットはエリザベスがプロポーズを断ったコリンズの妻となる女性で結婚は愛情よりも生活であるということを小説の中で示しました。端役になってしまいますが『ノーサンガー・アビー』のエレノア・ティルニーは、登場の機会は少ないのですがヘンリー・ティルニーの妹で、主人公のキャサリンを助ける存在で、彼女が貴族の男性と結婚できたおかげで、キャサリンとヘンリーとの結婚を彼の父親が許すことができました。この系列のヒロインの相手となる男性は、ナイーブなタイプのヒロインが女性を見守り導くタイプの男性と結ばれたのに対して、相手の男性のタイプは多様です。まあ、賢明な女性はどのような男性とでも上手くやっていけるからでしょうか。ダーシー、エドワード、ウェントワースの三人はそれぞれタイプが違います。 さて、ヒロインは大きく二つの系列に分けられると言いましたが、これに当てはまらない人がいます。『マンスフィールド・パーク』のファニー・プライスです。彼女は小説の前半では二つの系列のナイーブで純粋なタイプの女性だったのですが、成長して大人になると観察していて人を見る目を養い、周囲の若い男女が誘惑に負けていくなかで一人だけ誠実さを保ち続けます。つまり、成長して賢明なタイプになっていった、いわば両方の系列に入る女性です。このような女性はオースティンの他の小説にも見られません。また、『高慢と偏見』のエリザベスの姉のジェインも、両方のタイプであるようなところがありますが、彼女はそれが目立たないでバランスがいい。したがって、強いて言えばどちらのタイプにも属さないユニークな女性です。これは、オースティンの小説の中でも理想の女性なのではないかと思います。彼女のような女性も他の小説のどこにも出てきません。 2−4−2.女性のサブキャラの系統 オースティンの小説には様々なタイプの女性が脇役として出てきます。前のところで、純粋でナイーブなヒロインと似たタイプは既に紹介しました。その反対の腹黒いタイプを紹介していきましょう。系統は、ほとんど悪役でヒロインのライバルかヒロインの恋の障害となる存在がほとんどです。まず、『分別と多感』のルーシー・スティールをあげましょう。おそらくオースティンの小説の中で、最も悪賢い女性です。彼女は若くて世間知らずだったエドワードに巧みに取り入り、婚約を勝ち取って、4年間じっと待ち続けます。その間に大人になったエドワードは彼女に自由を束縛され、婚約が露見すると勘当されてしまいます。ヒロインのエリナー・ダッシュウッドに嫉妬し、既得権益を奪われないために、エドワードの仲を陰険な手段で妨害するのです。彼女ほど悪辣ではありませんが、ヒロインの恋の強力な障害となるタイプとして『マンスフィールド・パーク』のメアリ・クロフォードもそうです。彼女は賢明な女性の脇役として既に紹介しました。彼女は最終的にエドワードを諦めます。メアリ・クロフォードは自身の財産が有していているのに対して、ルーシー・スティールは有力な男性の妻となることが生きていく道なので必死さが違います。似たような境遇は、愛ではなく生活のために結婚した『高慢と偏見』のシャーロットもそうです。彼女は既に紹介しました。『ノーサンガー・アビー』のイザベル・ソープも未亡人の娘として財産がないことから有力な男性との結婚に望みをかけるしかない境遇で、そのためには手段を選ばないのと、本人がもともと軽薄な性格のためにキャサリンの兄と婚約していながら他の男性に乗り換えたりします。キャサリンを裏切ることになります。 このほか、意地悪キャラです。その筆頭は『高慢と偏見』のキャサリン・ド・バーグ夫人です。ダーシーの叔母にあたる尊大な女性で保守的な階級観と娘とダーシーとの結婚を目論んでエリザベスを訪れてダーシーをあきらめるように命令します。結果的に、これに反発したエリザベスは、ダーシーへの愛を自覚することになります。同じく、ミス・ビングリーはジェインと結ばれるビングリー氏の妹で、ダーシーに思いを寄せてエリザベスの悪口を吹き込みます。結果的に、これが逆効果となってダーシーは彼女と比べてエリザベスの教養や人格の優れていることに気づくことになります。また、彼女はジェインとビングリー氏の邪魔もします。それら悉く失敗し、小説の中では滑稽な存在でコリンズとともに作者に徹底的に皮肉られるキャラです。『分別と多感』のフェラーズ夫人は、キャサリン・ドバーグ夫人とよく似た存在ですが、男性主人公のエドワードの母親です。階級、傲慢で頑迷、家柄や財産の維持を優先するという、それでエドワードとエリナーが愛し会ってしまうことを警戒し、二人の結婚の障害となります。同じようにエリナーの腹違いの兄ジョンの妻であるファニー・ダッシュウッドは夫人の娘でエドワードの姉にあたります。母親のフェラーズ夫人と同じようにエリナーの前に立ちはだかります。その前に、エリナーの一家を屋敷から追い出し、ダッシュウッド家の遺産を独占しようとしました。このタイプの人たちに対してはオースティンのペンは容赦なく皮肉をこめて笑い飛ばしています。 これに対して、戯画的に描かれていますが、作者の視線は暖かいのが、愚かではあるが善良な人々です。この人たちは、主人公たちに迷惑をかけることもありますが、基本的には暖かく見守っている人々で、タイプも似ていると思いもス。『説得』のマスグローブ夫人、『分別と多感』のジェニングズ夫人、『ノーサンガー・アビー』のアレン夫人。この人たちほど愚かではない人々として、時にはヒロインの相談相手にもなる『説得』のラッセル夫人、クロフト夫人、『高慢と偏見』のガーディナー夫妻がそうです。 そして、最後にヒロインの親については、不思議なことに、ほとんどが欠落をかかえているのです。頼りがいがあってヒロインをバックアップしたり支えたりする親は皆無なのです。『ノーサンガー・アビー』のキャサリンの両親はその中でも、いたって常識的ですが、生活は豊かではなく、キャサリンが社交界にデビューできたのは近所のお金持ちのアレン夫妻のおかげです。『分別と多感』は父親が亡くなって、母親のダッシュウッド夫人は現実の生活面ではヒロインのエリナーに支えられ、『説得』では母親が亡くなり、残された父親のサー・エリオットは生活力のない見栄っ張りで破産しても贅沢をやめられない人物です。『マンスフィールド・パーク』のファニーの父親は怠け者で、子沢山の母親はファニーをそだてきれずに、姉の嫁ぎ先のサー・トーマスに預けたわけです。『高慢と偏見』の母親のベネット夫人は愚かな人でエリザベスとジェインの足を引っ張り続け、父親のベネット氏は賢明な人ではあるものの人生を諦めてしまい娘を助ける気力はありません。これは、ヒロインの相手の男性の親にも言えることで、立派な人物が皆無なのです。強いて例外としてあげられるのは『マンスフィールド・パーク』のサー・トーマスと『説得』のクロフト提督くらいでしょうか。 2−4−3.男性の人物の系統 今度は男性を見ていきましょう。さきに、ナイーブな系統のヒロインの相手となる男性が同じパターンであることは述べました。そして、それ以外のヒロインの相手となる男性はバラバラであることも。むしろ、脇役や端役となるサブキャラクターとあわせて分類できると思います。しかも、複数のタイプを兼ねている人物がいたりして、錯綜した分類になってしまいます。これに対して、女性の登場人物がヒロイン、憎まれキャラ、といったように機能別に分類され、それぞれの分類の中でタイプわけされて一種の階層化されているのと対照的です。 例えば、『ノーサンガー・アビー』のヘンリー・ティルニーはナイーブなヒロインを指導し導く男性の系統に入ると、さきに述べました。しかし、同じ系列のナイトリーやブランドンに比べると、若くて独立した実力に欠ける面があります。キャサリンと結婚しようにも父親の将軍の反対に遭って、すごすごと引き下がるのです。それは、彼が聖職禄を有して、これから牧師になろうとしている境遇にあるからかもしれません。そういう弱さは『分別と多感』のエドワード・フェラーズにも共通します。ふたりとも、ヒロインへの愛情をはっきりと表わさず、愛している素振は見せるのだが、いまひとつはっきりしないのです。エドワード・フェラーズが牧師となって結婚生活をする様子をヒロインのエリナーが想像する場面がありますが、多くの収入は期待できないので倹しい生活になり、また領主に対して謙譲の姿勢をとらざるをえない身分でもあるわけです。それを現実に行っているのが『高慢と偏見』のコリンズです。この人は、牧師ということで、ここにあげたヒーローたちの裏返し、陰画のような存在で、作者からは容赦ないほど滑稽に描かれ、徹底的に笑い飛ばされています。コリンズと、この人たちとの大きな違いは愚かで鈍感であるということと成り上がりの上昇志向で、ヒロインのエリザベスからは軽蔑され、求婚を拒絶されます。しかし、キャサリン・ド・バーグ夫人へ阿諛追従する卑屈さや、勿体ぶったような身振りは、この人たちが生きていく上で必要となってくるものを、大袈裟に戯画化してえがいているだけです。これは、『エマ』のフリップ・エルトンも同じです。これは、『マンスフィールド・パーク』のエドワード・トーマスも似ています。但し、彼の場合はヒロインのファニーを妹のように愛していたため結婚の対象と考えていなかったという点で、すこし違いますが。 また、コリンズはオースティンの小説の中で最も滑稽な人物でしょうが、彼ほどではありませんが、皮肉られ笑いの対照となる人物たちがいます。『説得』のアンの父親であるサー・エリエットは小説の冒頭で印象的に笑い飛ばされますが、浪費のために領地や屋敷を追い出される人物で、その見栄っ張りぶりが滑稽ですが、アンからの視線も混じると悲哀の影が漂います。一方、『高慢と偏見』でジェイン・ベネットと結ばれるビングリー氏は優柔不断だが好人物でジェインに首ったけとなる様子を暖かい視線で滑稽さをまじえて描かれています。また『分別と多感』のロバート・フェラーズはエドワードの弟で、いわゆる俗物で、しかも愚鈍である点はサー・エリオットにもコリンズにも共通する点です。とくに、彼とサー・エリエットは見栄っ張りで贅沢に目がない。そして、ロバートは贅沢のためでもあり、金持ちであることに価値をもっている。それが悪役に転じた系統があります。例えば、『高慢と偏見』のウィッカムは放蕩を続け、ダーシーから金をせびり、女性を騙し、リディアと駆け落ちまでします。口がうまく巧みに女性を誘惑しますが、嘘つきでエリザベスも騙されてしまいます。悪辣という点で負けていないのは、『説得』のウィリアム・エリオットで浪費のために親友を食い物にして破産させ、金持ちの女性と結婚します。容姿や立ち居振る舞いにそつがないのでアンの周囲は騙されますが、アンと結婚して身分と家柄を奪おうと計略を謀りますが、アンに求婚を拒絶されます。『ノーサンガー・アビー』のヘンリーの兄、フレデリック・ティルニーそして父のティルニー将軍も、贅沢好きで、お金持ちの女性と息子たちを結婚させようとします。これまでは善意が感じられない人たちでしたが、このタイプでも、一部に善意が垣間見える人物もいます。それが、『分別と多感』のウィロビーで、ヒロインの妹のマリアンを誘惑しますが、金持ちの女性と結婚します。しかし、マリアンに謝罪しようとして、弁解には一部誠意があります。また、『マンスフィールド・パーク』のヘンリー・クロフォードは女たらしで、行動パターンは、このタイプの人と同じですが、マリア・トーマスと駆け落ちしますが、ファニーにプロポーズして、道徳的なファニーとの結婚で人生をやり直そうとしたところがありました。そして、この系統の末端に『高慢と偏見』のダーシーを加えることには異論があるかもしれません。しかし、物語の最初の頃は、傲慢でエリザベスを見下し、ジェインとビングリー氏の結婚の妨害を行ったりと意地悪な人でした。それが物語の後半でエリザベスと愛し合うようになり印象が大きく変わります。オースティンの小説の主人公の男性としては、似たタイプのないユニークな存在といえます。 そして、小説の中で滑稽な人物は他にも、『高慢と偏見』のベネット氏、ヒロインの父親ですが、人生を諦めたところがありますが、皮肉な態度とものいいで母親のベネット夫人と場面は思わず噴き出してしまうところがあります。力にはなりませんが、ヒロインたちを暖かく見守っています。よく似ているのが『ノーサンガー・アビー』のアレン氏です。また、『高慢と偏見』のルーカス氏は、シャーロットの父親ですが、舞踏会やパーティーを開いて男女の出会いを作ろうとする面倒見のいい人です。ヒロインには多少迷惑だったようですが。これは、『エマ』のウェストン氏、『分別多感』のサー・ジョンも同じです。この系統の人たちは、女性の善意の端役の人々の男性版といえると思います。 2−5.読者にリアリズムと受け取ってもらえる陳腐な語り 私の見るオースティンの小説は、当時彼女が読んでいた小説に対する物足りなさから、そのような小説を分析して違うと感じられたものを排除していって残ったものが、あるいは違うものをそうでないものに置き換えて、残ったものが本質として、オースティンの小説のパターンではないかと、というのがここでの見方です。オースティンの小説に対して言われるリアリズムについても、そういう結果としてそうなったもので、最初から、オースティンがリアリズムの小説を書こうとしていたというのではない、ということになります。それは、書いているオースティンの側でいえることで、リアリズムが成り立つためには、読者がリアルであると感じる必要があります。その要素として、身近なものをピックアップして題材としてくり返し取り上げたり、登場人物を類型化して読者の周囲のどこにでもいそうな人に当てはめやすいような設定にしているなどのことをとりあげてきましたが、それらが読者に伝わらなくては効果はありません。そのために、オースティンの小説は、独創的な表現とか、典雅で格調高い文章とかいったいわゆる文学的な文章ではなく、使う言葉は平易で、誰にでも伝わるような文章になっています。夏目漱石やサマセット・モームなどの作家たちはオースティンの語り口を絶賛していますが、ひとつひとつの文章を取りだしてみれば、陳腐といっていいほど、誰でも読めるし、書けるような文章や言葉遣いをしています。しかし、そういう語り口で日常の事物を語られるからこそ、読者はいつものままにように受け取ることができるし、「あるある」と頷くことができるわけです。それがオースティンのリアリズムであるように思います。逆に独創的な表現で、日常の事物に、それ以上の意味づけをされてしまってはリアルにならないのです。おそらく、そんな文章が続いていたら、オースティンの小説を読み進めていくのに疲れ果ててしまって、最後まで読めなくなってしまっているかもしれません。私は、オースティンの小説を翻訳で読んでいる小説ファンで、原語で読めるほど英語に堪能ではなく、英語の文章を吟味することはできません。しかし、翻訳された文章でも、そういうことは十分に感じられることで、オースティン自身、意図していたことではないか思います。 それはまた、文章を書く前提として、日常の事物を見る視点、つまり書く切り口のようなものも、独創的ではなく、読者もわかるように共通の視点を意識しているようです。逆に、読者は自身の視点を明確に意識しているわけではないので、オーステインのリアリズムというのは、現実を見たまま、と言う内容が、読者が曖昧にそうしているのを明確化し、意識化した、つまり共通性の高い標準的な視点、敢えて言えば陳腐であることを意識的に明確にしていると言えると思います。 したがって、オースティンは陳腐を戦略化しているといえると思います。
3.細部を積みあげた結果としてのワンパターンの物語 このように見てきた、キャラクターピースのような登場人物は、パターンとして系統化されています。そのことによって、突出した個性のユニークな人物ではなく、一般化された、どこにでもいるような人として想像できる存在となります。『高慢と偏見』のベネット夫人や『説得』のサー・エリオットのような人物は、読者が周囲を見渡せば、○○夫人に似ているという想像ができて、身近に感じられるのです。それが、オースティンの小説のリアリティの性格ではないかと思います。エミリー・ブロンテの『嵐ヶ丘』のヒースクリフやキャサリンのような特殊ともいえる、他にはいないような人物はでてきません。ヒースクリフには、あの特殊な環境で、非現実の物語の中でしか生きられない。これに対して、オースティンの人物たちは、前述の設定の上で、ワンパターンの物語をくり返すのです。それは、どこにでもいるような人物が、現実の周囲を見回せば、見たままを忠実に写し取ったような設定で、そこで荒唐無稽な物語を展開するのは無理です。それに似つかわしいのは、読者の毎日と同じような展開です。そこに、ピタリとはまるのです。このような人物や設定がそうだから物語がそうなのか、逆に物語が要求したから人物や設定がこうなったのかは分かりません。鶏が先か卵が先かのような話になってしまうので、どちらともなくなんでしょう。いずれにしても、オースティンは既存の小説に飽き足りずに、それに違う、そうじゃないと呟いていくうちに、このようになっていったのではないかと思います。しかし、このようなワンパターンで、読んでいる人は面白いのでしょうか。同時代の人であれば、「あるある」とさわぐ面白さがあったかもしれませんが、時代を越えた現代では、陳腐化してしまっているはずです。ところがそうではない。 では、オースティンの小説のワンパターンが陳腐化どころか、それこそが魅力を作り出しているのですが、それは何か。じつは、これまで述べてきたことが、逆に物語を作り出していると言えるのです。そのためには、小説全体の筋は荒唐無稽でなくワンパターンの方がいい、そういう決まった舞台の上で、細部や類型的な人物たちが生きいきと動き回り、物語を生み出している。その場面場面を読者は、驚き、笑い、面白がり、それらが重なり、絡み合うのを、読者は想像して参加していく、そういう構造になっている。それを、ある人は物語にたいして説話論的という概念付けをしました。それに全部当てはまるとは言えないかもしれませんが、オースティンの小説の魅力を「語りくち」という人はモームをはじめ少なくありませんが、そういうことではないかと思います。炉辺はお婆さんから「むかしむかしあるところに…」と語られる昔話は、同じ話のくり返しでも、子どもは飽きることなく聞いています。それに通じるのがオースティンの小説の特徴ではないかと思います。
リンク . |