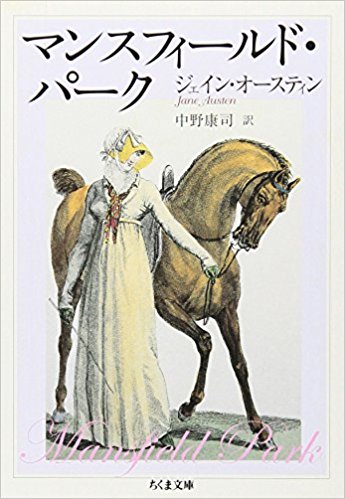�S�D�w�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�x�̑��ʂȖ��� �i�P�j�ߌ��Ƃ��Ắw�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�x �i�Q�j�w�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�x �W�F�[����I�[�X�e�B���̏����́A���炷���������Ɩʔ������ɂ͎v���Ȃ��̂ɁA���ۂɏ�����ǂݎn�߂�ƁA����Ɏ䂫���܂�ė�����Ȃ��Ȃ�ƌ����܂��B�ЂƂɂ́A�ޏ��̏����͔g������̃X�g�[���[�ŁA���̐�ǂ��Ȃ邩�ڂ������Ȃ��Ȃ�Ƃ��A�h���}�e�B�b�N�ȓW�J�ɓx�̂����Ƃ��A�r�����m�Ȑݒ�Ƃ������I�ȃ��}���X�Ƃ��A�����������ǎ҂��Ђ����镨��̗v�f�͑S������܂���B�ޏ��̏����ɂ��āA����Șb���ƏЉ��ƁA�����Ă��͖��C�Ȃ����Ƃ����������A�Ƃɂ����A���ۂɓǂ�ł݂āA�Ƃ������A���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂���ł��B �w�}���X�t�B�[�h��p�[�N�x�Ƃ�����i�́A�ޏ��̏�����i�̂Ȃ��ł��A�����炭�͂��炷�����ł����C�Ȃ���i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�����̒����̓_�ł́A�ޏ��̏����̒��ŁA��Ԏ����̑��������Ȃ̂ł��B���C�Ȃ��ŁA��Ԓ����̂ł��B�������A���͍�i��ǂ�ł��Ă��ދ����邱�Ƃ͂Ȃ��B����͂Ȃ����A���̂Ȃ����Ƃ������Ƃ��𖾂���ƁA����́A���̏����̖��͂𖾂炩�ɂ��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�I�[�X�e�B���̏������Љ��Ƃ��ɁA�Ƃɂ������ۂɓǂ�ł݂āA�Ƃ����ȊO�ɁA�����������Ƃ����́i�����j�Ȃ̂��ƌ������Ƃ��ł��邱�Ƃ��A���ꂩ��l���Ă݂����Ǝv���܂��B ���炷�������C�Ȃ��āA�ʔ������łȂ��B����ɂ�������炸�A���ۂɓǂ�ł݂�ƁA�~�܂�Ȃ��Ȃ�B�Ƃ����̂́A���ۂ̏����ɖ��͂�����Ƃ������Ƃł��B����͂��炷���Ƃ͊W�Ȃ��ł��傤�A�Ƃ������Ƃ̓X�g�[���[�ł͂Ȃ��B���܂�A����肵�āA���������Ԃ��Ďv�킹�Ԃ肷��͍̂D���ł͂Ȃ��̂ŁA�����Ō��_�������܂��ƁA�������傫�Ȗ��͂ɂȂ��Ă���̂ł��B���ꂾ�������������A���������炷�������C�Ȃ��̂��A�����œǂ܂��Ă��܂��B���ꂾ���A�������������Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B�ŁA�����ł̖ړI�́A���̌����̖��͂��A���ۂ̏�����ǂݐi�߂Ȃ���A�����ő̌����Ă����悤�ɂ��āA�ꕔ�ł����炩�ɂ��Ă݂悤�Ƃ������̂ł��B ���̂܂��ɁA���炷�����Љ�Ă������Ƃɂ��܂����A���̑O��Ƃ��āA���炷���̖��C�Ȃ��Ƃ���������w�E���āA����ɑ��āA��肪�ǂ̂悤�ȊW�ɂ��邩�Ƃ����A�T���I�Ȃ��Ƃ��A�����ŏ����������Ă��������Ǝv���܂��B �i�P�j�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̒������̃X�g�[���[�������̕���̃��^�t�@�[ �w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�Ƃ������������̃X�g�[���[�́A�قƂ�ǃ}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ƃ����@��Ői�߂��܂��B�ꕔ�̗�O�́A��ȓo��l���������T�U�g���E�R�[�g�ɏo������Ƃ����G�s�\�[�h�ƃt�@�j�[���|�[�c�}�X�̎��ƂɈꎞ�I�ɋA��Ƃ����G�s�\�[�h�ł��B���̗�O�I�ȃP�[�X�ł��A�T�U�g���E�R�[�g�̃x���`��v���C�X�ƂƂ����Œ肵���ꏊ�ɒ�_�J������u���Ă��邩�̂悤�ł��B����͐l�X�����ɃJ���������Ĉړ����čs���̂ł͂Ȃ��A�Œ肵���J�������ݒu���Ă����āA���̃A���O���̒��œo��l����������b������A�������肵�܂��B����ȊO�́A�A���O���ɐl���������o�����������Ƃ������������܂��B�ɒ[�Ȃ��Ƃ������ƁA���ꂪ���̏����̊�{�I�Ȑl���̓����Ȃ̂ł��B ���̓T�^���A��҂����ɂ��f�l�ŋ��̃G�s�\�[�h�ŁA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ƃ�������ɂ����ĕ��䌀���s����Ƃ����������̂悤�ȓ���q�\�����\����̂ł��B�����̐l���W���A�o��l�������̐l�ԊW�ɏd��A���̓��e���A�l�������̂��̌�̉^���ɊW���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����Ȃ�A���̏����̍\���̏k�}�̂悤�ȏ�ʂȂ̂ł��B����ȊO�ł́A�o��l���̎�v�ȉ�b�́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̎����Ō��킳��A�O���ŋN���������́A�莆�⎺���̉�b�Ŗ��炩�ɂ���܂��B�Ⴆ�A�}���C�A�ƃw�����[��N���t�H�[�h�̏o�z�Ƃ����厖���͓����҂̍s�������ڏ�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�t�@�j�[�����A���[����莆��ǂނ��ƂŖ��炩�ɂ���܂��B����́A�����ɂ����ĕ���O�̎������ϋq�ɒm�炳���ꍇ�̎�@�Ɠ����ł��B ���̂��߁A���ꂪ�A���A�ǂ�����A�ǂ̂悤�ɕ���ł���}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɓ��ꂵ�A�ޏꂵ�����Ƃ������Ƃ������̃h���}������Ă���ƌ�����̂ł��B �i�Q�j�Ȓ��S�Ƃ��Ă̏���l�����t�@�j�[��v���C�X�̓h���}�̐G�} ���̂悤�Ɂw�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�̃h���}�A�l�X������ł���}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɓ�������A�o���肷�邱�ƂŐ��܂�܂��B�܂�A�h���}�͏�Ƀ}���X�t�B�[���h��p�[�N�̊O���玝�����܂��̂ł��B�������A�������܂ꂽ�h���}����̂���Ȃ��ƁA�����Ńh���}�ƂȂ�܂���B�ł��l�X�͓�������A�o���肷�邾���Ȃ̂ŁA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̎�l�ł���T�[��g�}�X�ł���A�A���e�B�O�A�ɂQ�N�ԏo�����Ă����킯�ŁA���̋A�҂͕���̂ЂƂ̓]�@���������킯�ł��B�ł́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɏo���肵�Ȃ��ŁA��ɂ����l�Ƃ����̂͒N���Ƃ����A�o�[�g�����v�l�Ȃ̂ł��B���̐l�͉������Ȃ��l�ŁA����ɑ��ē����������������܂���B�����A���邾���Ƃ����l�ł��B�������A���̃o�[�g�����v�l�̂Ƃ���ɓo��l�������͉��̈ӎ������邱�ƂȂ��A���āA�����ďo�čs���B�����Ă݂�ΐ_�Ђ̂��_�̂̂悤�Ȏ��͂�������Ȓ��S�Ȃ̂ł��B���̃o�[�g�����v�l�̖T��ɂ�������̂��t�@�j�[��v���C�X�ł��B�ޏ��́A�o�[�g�����v�l�Ƃ������S�̖T��ɂ���ޏ��̂悤�ȑ��݂Ƃ����܂��B�t�@�j�[�́A�o�[�g�����v�l�Ƃ͓����ł͂���܂��A�s�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B���ɓI�ŁA���I�Ȃ̂ł��B���͂̐l�X���s�����A�E����������̂ɑ��āA�ޏ��͂����Ɨ��܂��āA���̈ꕔ�n�I�������ƌ�����āA�Ƃ��ɂ͐l�X�̕������◝���҂ƂȂ�܂��B�܂�́A�t�@�j�[�̓h���}���N�������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�G�}�̂悤�Ȗ����ŁA�t�@�j�[���W���Ă͂��߂ăh���}�Ƃ��Đ��܂��Ƃ���������S���Ă���̂ł��B ������t�����ōl���Ă݂�ƁA�����̒��Ŕޏ����S���Ă���@�\���l����ƁA��l���Ƃ��ĐϋɓI�ɍs�����N�����ăh���}�̉Q���ɂ����ẮA�@�\���ʂ����Ȃ��Ȃ�܂��B�]���āA���݊��������Ƃ��A�g�Ƃ��Ƃ����̂́A�����̍\����̕K�R�ƌ�����̂ł��B�G�}�́A�������R����̂ł͂Ȃ��A�f�ނ�R�₷���̂Ȃ̂ł��B �i�R�j�t�@�j�[�������̌��ɉ������ �ӂ��̏����ł́A�G�}�̖����͍�҂��S���܂��B���ۂ̂Ƃ���A�����̌���Ƃ��āA��������A�o��l���̍s����v������邱�ƂŃh���}�̌`������Ă����킯�ł��B������u�S�m�̌���v�Ƃ��ĎO�l�̌`���ŁA�_�l�̂悤�ɏ����̂��ׂĂ����ʂ��Ē��ՓI�Ɍ��܂��B�������A���̍�i�ł́A���̑S�m�̌���̉���x�����Ȃ荂���A���肪�u���v�Ɩ�����Ċ���o���A�ӌ����q�ׂ�ӏ����o�Ă��܂��B���̍�i�ł͌��肪�A�P��̎x�z�I�Ȉӎ��ɐ�������邱�ƂȂ��A���ׂĂ̓o��l���̈ӎ��̒����o���肵�A�u���̃I�[�P�X�g���C�V�����v���`�����Ă��܂��B���ɖڗ��̂��A�����āA�t�@�j�[��ʂ��Č������Ƃ╷�������ƂȂǂ��`����A�ޏ��̈ӎ���S��������̌��ɍ��݂��Ă���ӏ��������̂ł��B���̂��܂�̑����ƁA�q�ϓI���_�ƃt�@�j�[��ʂ������_�m�ɋ�ʂ��Ă������Ă��Ȃ����߁A�ǎ҂͂��̓���A����ɋC�t�����ɍ������Ȃ���A���Ƃł��̂ӂ��̃Y���ɋC�����Ƃ������Ƃ�����̂ł��B���̃Y�����A�ǎ҂̕���ւ̋������������āA�h���}�����I�Ȃ��̂ɂ��Ă���̂ł��B����́A�t�@�j�[���G�}�I���݂ł��邱�ƂŁA�͂��߂ĉ\�ƂȂ������̂Ȃ̂ł��B �i�S�j�Y�������ޓǂ݂̐[�݂ƍL���� �ǎ҂��A���̃Y���ɋC�Â��Ă��܂��ƁA���͐^����`������Ă��Ȃ����ƂɎv������܂��B�Ⴆ�A��҂͖��炩�ɈӐ}�I�Ɍ��Ȃ��Ő^�����B�����Ƃ��܂��B����́A�Ⴆ�A���ꂪ�i���ɁA�����������̎��A����͂ǂ��������̂��ƁA�B����Ă������ƂɁA��ɂȂ��ċC�Â����ƂɂȂ�܂��B����́A�O�̂Ƃ���ŁA��肪�\�i�^�`���̂悤�ɓW�J����邱�Ƃɑ��āA�ǎ҂́A�悪�ǂ̂悤�ɂȂ��Ă������Ƃ����������O�Ɍ������Ă�������������܂��B����ɑ��āA��ɂȂ��āA����͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��Ƃ����A�V���������ɂ��āA���łɓǂy�[�W�ɏ�����Ă������ƂƊ֘A�Â��ēǂނƂ��������̌��Ɍ������Ė߂����������̂ł��B�܂�A�ǎ҂́A���̐�ǂ̂悤�ɓW�J����̂��Ƃ�����������ƁA���̐�ǂ��Ȃ�̂��Ƃ����b�̐�̕����A�����āA�b���i���ƂŊ��ɓǂƂ����U��Ԃ�Ƃ��������ƁA�l�X�ȕ����ɋ������Ђ낰�āA����������߂̐����͂�L���͂�ǎ҂ɋ��߂Ă���̂ł��B�ǎ҂��A��������p���邱�ƂŁA����̐��E�͏d�w�I�Ȑ[�݂ƖL���ȍL����������ēǎ҂ɂ���������̂ƂȂ��Ă���̂ł��B
�Q�D���炷�� ���̑̌�������܂��ɁA�\���m���Ƃ��āA�ȒP�ɏ����̂��炷�����Љ�Ă����܂��B�I�[�X�e�B���̏����͔g������Ƃ��r�����m�Ƃ͐����́A�����ŒP���ȓ��X�̐����̌J��Ԃ��̂Ȃ��ŁA���ׂȎ�����W�X�ƒԂ��Ă������̂ł��B �Ƃ��ɁA�w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�̓I�[�X�e�B���̑��̏����Ɣ�ׂĂ��A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ƃ�������ꂽ��ԂƂ���������������ɁA�����炵�������Ƃ����A����̍Ō�ɑ����ċN���邭�炢�ł��B����䂦�A����̂��炷�����ȉ��ɂׂ̂Ă����ƁA����̖{�҂̃X�g�[���[�̕��ʂƕ���̂͂��܂�o�܂�ݒ�Ƃ������O�u���̕��ʂ��قƂ�Ǔ��ʂɂȂ��Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B����́A�P�X���I�̏����̂Ȃ��ł͋ɂ߂ē��قȂ��̂Ƃ�����Ǝv���܂��B �e�������Ȍ������������߂ɁA�n�R�l�̎q��R�̉Ƃň�����t�@�j�[�E�v���C�X�́A�P�O�̂Ƃ��ɁA�e�ʂ̏y�j�݉ƂɈ�������邱�ƂɂȂ�܂��B���̌o�܂͂����ł��B�t�@�j�[�̕�v���C�X�v�l���܂ގO�o���́A�����ɂ���Ă��ꂼ��傫���^���������ꂽ�̂ł����B���l�̎����́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̕x�T�ȗ̎�T�[��g�}�X��o�[�g�����ƌ������A��l�̑��q�Ɠ�l�̖��̕�ƂȂ�A�����̓T�[��g�}�X�̗F�l�Ŗq�t�m���X���ƌ������}���X�t�B�[���h��p�[�N�̕~�n���̖q�t�قŕ�炵�܂��B�����āA�t�@�j�[�̕�ł��閖���͊C�����̒��уv���C�X�ƌo�ϓI�Ȋ�Ղ������Ȃ������ʂȌ������A�|�[�c�}�X�Ŏq��R�̕n�R��炵�����邱�ƂɂȂ�܂����B����Ȓ��ŁA�v���C�X�v�l���X�x�ڂ̂��Y���}�����Ƃ��A�ޏ����ꋫ����~���ׂ��A�����t�@�j�[���o�[�g�����ƂɈ������Ƃ����b�������オ��܂��B�v���C�X�v�l���o���������������߂��̂ł��B ����ȑ̎��œ��C�ȏ����́A����̂����߂ƁA���Ƃ������̂��炩���ɂ����Ȃ���A�����ЂƂ�̔���ł���y�j�ݕv�l�̂����b�W�Ƃ��āA�Ђ�����ς�����X�𑗂邱�ƂɂȂ�܂��B�B��̖����́A���Ƃ��̃G�h�}���h�ŁA�t�@�j�[�͔ނ̓����œǏ��̊�т�m��A���h�ȓ����S��g�ɂ����A���L���ȏ����ւƐ������Ă����܂��B�����ăt�@�j�[�̓G�h�}���h�ɑ��āA���h�Ɗ��ӂƐM���ƈ�����荬���������S������悤�ɂȂ�܂��B����́A�D���ɂȂ��Ă͂����Ȃ��l���D���ɂȂ��Ă��܂�����߂�����ł����B �t�@�j�[���P�W�ɂȂ����Ƃ��A�T�[��g�}�X�͔_��o�c�̎d���̂��߂ɁA���j�̃g�����Đ��C���h�����̃A���e�B�O�A�֕����܂��B�ނ̕s�ݒ��A����m���X�v�l�̌v��ɂ��A�o�[�g�����Ƃ̒����}���C�A�ƕx�T�Ȓn�僉�b�V�����[�X�Ƃ̉��k���i�݂܂��B�m���X�t�̌�C�̖q�t�����C���Ă���ƁA���̐e�ނŃ����h���̈��ɐ��܂����w�����[�ƃ��A���[�Ƃ����N���t�H�[�h�Z�����}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ���Ă��āA���̕��a�ȕ�炵������������邱�ƂɂȂ�܂��B�o�[�g�����Ƃ̎��j�G�h�}���h�́A�q�t�ɂȂ�\��ł����A�����h���d���݂̋@�m���ӂ����I�Ȕ��l���A���[�E�N���t�H�[�h�̖��͂Ɍ��f����܂��B�}���C�A�́A���b�V�����[�X�ƍ��܂����A���������h���d���݂̃v���C�{�[�C�A�w�����[�E�N���t�H�[�h�Ɍ����������Ă��܂��܂��B�����Ęb����₱�����Ȃ�̂͂��̐�ŁA�����h���̏㗬�Ќ��E�Ő��m��ʗ��̂���ނ���o�������w�����[�E�N���t�H�[�h���A�}���C�A�ƋY�ꂽ���ƂŁA���^�ʖڂȃt�@�j�[�����炩������Ŗ{�C�ōD���ɂȂ�A�Ȃ�Ɛ����Ƀv���|�[�Y���Ă��܂��̂ł��B������x��������Ƃ����Ȃ�B����҂̂���}���C�A���v���C�{�[�C�̃w�����[�E�N���t�H�[�h�ɖ����ɂȂ�A�v���C�{�[�C�̃w�����[�͐��^�ʖڂȃt�@�j�[�Ƀv���|�[�Y���A���^�ʖڂȃt�@�j�[�͖q�t�u�]�̃G�h�}���h�ɔ�߂���v�����A�����Ėq�t�u�]�̃G�h�}���h�́A�q�t�Ƃ����E�Ƃ��y�̂��郁�A���[�E�N���t�H�[�h�Ɍ��f����Ă���Ƃ����A�����ւ����Ⴍ��������q���̊W�ɂȂ�̂ł��B����͂Ƃ������A�w�����[�͔N���S��|���h�̗̒n����������Ƃ����a�m�ł����A����҂̂���}���C�A�Ɍ��R�ƌ������悤�Ȑ^���������l���ł���A�t�@�j�[�̓G�h�}���h�ɑ����߂��v���ɉ����A�w�����[�̐l�Ԑ���M�p�ł��Ȃ��Ƃ������R����A���̃v���|�[�Y��f�Œf��܂��B�������A����ȋʂ̗`�̗lj�����Ȃɋ��ރt�@�j�[�ɑ��āA�e����̃T�[�E�g�}�X�͌��{���A�t�@�j�[���|�[�c�}�X�̎��Ƃɗ��A�肳���Ă��܂��܂��B�\�ʏ�̓T�[�E�g�}�X�̂₳�����S�����ł����A���̂Ƃ���A�T���ȕ�炵�̗L����t�@�j�[�ɑ��邨�d�u���Ȃ̂ł����B�����ăT�[�E�g�}�X�̑_���͓�����A�t�@�j�[�͎��ƂłЂǂ����ł𖡂키���ƂɂȂ�܂��B���������͂��̉䂪�Ƃ́A���i�ȕ��e�Ƌ����ȕ�e������A�����ƍ����Ɏx�z���ꂽ�s�����̑��A�̂悤�ȉƂł���A�t�@�j�[�́A�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̐Â��ŏ�i�Ȑ����̂��炵�������炽�߂Ď�������̂ł����B���Ƃł̑؍݂��Q�������߂������A�t�@�j�[�́A�g�����d�a�ɂȂ��ċA������ƁA�}���C�A���w�����[��ǂ��ĕv�̉Ƃ��o�����ƁA�C�F�C�c�ƃW�����A���삯�����������ƒm���ċ����܂��B�G�h�}���h�́A���A���[�̌Z�ɑ��閳�ߑ��ȑԓx�Ɍ��ł��āA�ޏ��Ƃ̌�����f�O���܂��B�t�@�j�[�͒��������߂����߂ɕK�v�ȑ��݂Ƃ��āA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɍĂь}��������܂��B�g���͕a�C������A�W�����A�̓C�F�C�c�ƌ������邪�A�w�����[�Ɏ̂Ă�ꂽ�}���C�A�́A���A�҂Ƃ��ăm���X�v�l�ƂƂ��ɕ�炷���ƂɂȂ�܂��B�����āA�G�h�}���h�́A�t�@�j�[�ւ̈��ɖڊo�߁A�������܂��B�����āA�t�@�j�[�́A���E�\���G�h�}���h�ƂƂ��ɁA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̖q�t�قŌ��������𑗂�Ƃ�����c�~�ŕ���͏I���܂��B
�R�D�w�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�x��ǂޑ̌��i���p�͂����ܕ��ɂ̒���N�i����j �@��P�� ����̖{�͑�Q�͂���n�܂�A��P�͕͂���̔��[�ƂȂ�G�s�\�[�h�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����q���C���ł���t�@�j�[���}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ɉ������ꂽ�o�܂ł��B�q�ϓI���_��������������ɂ��n�̕��ƁA�T�[��g�}�X�A�o�[�g�����v�l�A�m���X�v�l�̉�b�ō\������Ă��܂��B �܂��A���̂R�l�̊W�Ɍo�܂Ƃ��ăm���X�v�l�������A�o�[�g�����v�l�������̎O�o���ɂ��āA�����͍K�^�ɂ��y�j�݂̖ڂɎ~�܂荋���Ȍ��������ɏ��o���A�����͓������K�^��_�������v���ʂ�ɂ͍s�����A�o�̕v�ł���y�j�݂̗F�l�̖q�t�Ɂu��ނȂ�������悹��v���ƂƂȂ�A�O���͂���ȏ�Ȃ��قǂ̉^�̈����ŏ����u�����������v�Ƃ����܂������Ă��܂������Ƃ�����܂��B���̓����́A���������̍K�s�K�������Ɏ���d�Ŋ낤�����̂��Ƃ������Ƃ��A�e�̐���̌�����ʂ��Ď�����Ă���Ƃ��ł��B�����������ő��ʂɏグ���Ă���͖̂��炩�ɁA�o�ϓI��Ղ�Ȃ������̋������A�����ʂ��ł��B���Ɏ����ƎO���̂��ꂼ��̌����́A�ޏ������̂��̌�̐l���ɓV�ƒn�قǂ̋����̈Ⴂ�������N�����A��������Љ�K���܂ł��قȂ���̂ɂ��Ă��܂����Ƃ𖾂炩�Ɏ����Ă��܂��B�����āA�O���̃v���C�X�v�l�i�t�@�j�[�̕�e�j�̖����ʂȌ����́A���p�̒����ȂǕ��������Ȃ��̂ŁA��������������܂ŁA�Ƒ��ɂ͂��������m�炳�Ȃ������̂ł��B����́A����̏I�ՂŃo�[�g�����Ƃ̎o�����Ƒ��̏������Ȃ��삯���������Ă��܂����Ƃ̐�G��̂悤�ȍs�ׂł��B���̕���́A�O�ɂ��q�ׂ��悤�Ɍ���ꂽ��Ԃ̂Ȃ��œo��l�����s�����藈���肷��\���ɂȂ��Ă��܂����A���̍s�ׂɂ��Ă�����ꂽ���Ƃ��J��Ԃ��Ƃ��������\���ɂȂ��Ă��܂��B�����āA����̏I�Ղő傫���]�����鎖���ł���o���̋삯�����ɂ��Ă��A�ŏ��̓����̎��_�Ńv���C�X�v�l�̖����ʂȌ����Ƃ����A��G�ꂪ�z�ɂȂ��Ă���̂ł��B����Ɍ����A���̖����ʂ̌��ʐ��܂ꂽ�̂��t�@�j�[��v���C�X�ŁA�ޏ����o�[�g�����ƂɂƂ��Ċ�@�̋~����I�ȑ��݂ƂȂ�̂ł��B���̔���I�������A���̕z�͍Ō�̍Ō�ɖ��炩�ɂȂ�̂ŁA���������x���ǂ܂Ȃ��ƕz�Ƃ��Č����Ă��܂���B������A���̏����͉��x���J��Ԃ��ǂ�ł��邤���ɁA���̂悤�ȍו��ɖ��ߍ��܂ꂽ�z�������Ă���̂ł��B �����̔����́A���̍�i�����Ɍ��������̂Ƃ͌���܂���B�I�[�X�e�B���̍�i�̃t�@���ł���A�ޏ��̂U��̏��������f���āA������ǂނ��Ƃ��\�ł��B�Ⴆ�A�v���C�X�v�l�̖����ʂȌ����́A���肪�C�R�̎m�����ł��邱�Ƃ���A�w�����x�̃A���E�G���I�b�g���t�F���b�N�X�E�E�F���g���[�X�Ƃ̌������P�X�̂Ƃ��Ɏ��͂̔����������ċ��s������A�����Ȃ��Ă��܂����\���Ƒz�����邱�Ƃ��ł��܂��B �����āA�R�l�̉�b���A���ꂼ��̐l���ƈ��������t�@�j�[���ǂ��������݂Ƃ��Ĉʒu�t�����邩���A�����Ŗ��炩�ɂ���܂��B�������b�Ńj���A���X�܂ŕ\�킵�Ă��܂��I�[�X�e�B���̐��ۗ�������r�ɂ͍ŏ�����E�X���Ă��܂��܂��B�܂��A�t�@�j�[���������Ƃ������Ƃ��m���X�v�l���v�����A���̃o�[�g�����v�l���ȒP�Ɏ^������B�����ŁA�o���̌y�������o�܂����A�T�[��g�}�X�����l�̎q�ǂ����������ɂ͂��ꑊ���̐ӔC�����ƂɂȂ�Ƃ����T�d�Ȏp���������܂��B�������A���̐^�ӂ͂Q�l�̑��q�����ƕn�����]���Ƃ̌������뜜����Ƃ������̂ŁA�����ɔނ̐����Ȑl���ł���̂ł����A���O�����U������ŁA����̕ېg��D�悷�鏬�S�Ȑg���肳��������Ă��܂��B���̂��Ƃ��A���̌�̕���̓W�J�Ƃ�������Ė��炩�ɂȂ��Ă���̂ł��B ����ɑ��ăm���X�v�l�̎��̂悤�Ȍ��t�ɊȒP�ɐ�������Ă��܂��܂��B ���Ȃ��́A�������̓�l�̑��q����̂��Ƃ�S�z�Ȃ����Ă����ł��傤���ǁA���Ȃ����S�z���Ă���悤�Ȃ��Ƃ��N����͂����Ȃ���B�����āA������������Z���̂悤�Ɉ�Ă����ł����̂ˁB�ˁA�����v���܂���H���Ȃ����S�z���Ă���悤�Ȃ��ƂɂȂ�킯���Ȃ���B�Z���̂悤�Ɉ�Ă�ꂽ�j��������������Ȃ�ĕ��������Ƃ��Ȃ���B�������A�ނ���A������������ꏏ�Ɉ�Ă��邱�Ƃ����A���Ƃ����m�̌������ӂ����B��̊m���ȕ��@����B�������̎q�����l�ɂȂ��āA���Ȃ��̓�l�̑��q����A�܂�g�����G�h�}���h���A���ꂩ�玵�N��ɏ��߂Ă��̎q�ɉ������ǂ��Ȃ邩����H���ꂱ���A���Ȃ����S�z���Ă��邱�ƂɂȂ邩������Ȃ���B�i�����j�ł��A���܂��炻�̎q�ƈꏏ�Ɉ�Ă�A���Ƃ����̎q���V�g�̂悤�ɔ������Ă��A�Z���ȏ�̊W�ɂ͂Ȃ�Ȃ���B�i�o.�P�S�`�P�T�j �����āA�O�l�Ƃ��Â��������s�ׂ̑P�ӂ��ɂ����C���ɂȂ�܂��B���̎O�l�̐[���l�����ɁA�ꎞ�̗~���ɓs���悭�Ë����Ă��܂����Ȃ́A���̐���Ɏ��͈����p����Ă��ăo�[�g�����Ƃ̌Z��o�����N���[�t�H�[�h�Z�����m�ɂ������Ȃ���ʂɎ���Ă��܂����Ƃ̕z�ɂȂ��Ă���Ƃ������܂��B���ړI�ɂ̓T�[��g�}�X�̐S�z�͍ŏI�I�Ȃ͓������Ă��܂����ƂɂȂ��āA���̂Ƃ��̔[���͗����āA�t�@�j�[�ƃG�h�}���h���������Ă��܂��̂ł��B �܂��A�����ł��������A�m���X�v�l����p��t�@�j�[����������ďZ�܂킷�ӔC���T�[�E�g�}�X�ɉ������Ă��܂��A���ۏ�̕��S��Ȃ����݂����ꂽ�Ƃ���A�������A�t�@�j�[����������Ă����Ă��ƂŁA���̑P�s�͂��ׂĎ����̎蕿�ɂ��Ă��܂����ς���������܂��B���̎O�l�̉�b�́A�܂�ł��ڏo�x���Ԕ����Ȉ��}���A�����̌v��̑ł����킹�����Ă���悤�ȏ�ʂɌ����Ă���̂ł��B �@��Q�� ����̖{�҂͂�������ł��B�P�O�̃t�@�j�[���}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ���ė���Ƃ��납��n�܂�܂��B ���ӂ��ׂ��́A���̏͂�����肪�S�\�̐_�̂悤�Ȓ��ՓI�Ȏ��_�ŋq�ϓI�Ɍ�邱�Ƃ���A�o��l���̓��S�ɏo���肵�͂��߂�̂ł��B������u���̃I�[�P�X�g���C�V�����v�ƕ]����l�����邻���ł����B�Ȃ��ł��A�t�@�j�[�ւ̉�����������A�ޏ���ʂ��Č������Ƃ╷�������Ƃ��`����A�ޏ��̐S����ӎ������̂Ȃ��ɍ�������悤�ɂȂ��čs���܂��B�Ⴆ�A �o�[�g�����Ƃ̎q�������݂͂�Ȋ�ʂ��ǂ��āA��l�̑��q�͂ƂĂ����j�q�ŁA��l�̂��삳�܂͖ڂ̊o�߂�悤�Ȕ��l�������B���܂��Ɏl�l�Ƃ����炪�ǂ��āA�����Ƃ����̌^�����Ă����B���̂��ߋ�����x�̈Ⴂ���琶���镨���̈Ⴂ�����łȂ��A�e�p�̓_�ł��A�t�@�j�[�Ƃ͗�R����Ⴂ���������B��l�̂��삳�܂ƃt�@�j�[���قړ����N���Ƃ͒N���v��Ȃ����낤�B�ł����́A���̂��삳�܂ƃt�@�j�[�͓�������Ȃ������B�܂�A�o�[�g�����Ƃ̎����W�����A�͂܂��P�Q�ŁA�����}���C�A�͂P�R�������B����ȃo�[�g�����ƂɈ������ꂽ�����t�@�j�[�́A�܂��ɕs�K�̂ǂ��ɓ˂����Ƃ��ꂽ�悤�ȋC���������B�N���ނ��|���āA�������p���������āA�������ꂽ�䂪�Ƃ��������āA����グ���Ȃ����A��̖��悤�Ȑ��ł����b���Ȃ����A�����J�����тɗ܂��j��`�����B�i�o.�Q�R�`�Q�S�j ���̗�͌���ɂ��n�̕��ł��B�O���͎������q�ϓI�Ɍ���Ă���̂��A�g����ȁ`�h�̕��ł̓t�@�j�[�̋C������`�ʂ��A���̕��ł͌��肪�t�@�j�[�̓��S�ɂȂ��Ă��܂��B�������A��̗�𒍈ӂ��Ȃ��Ŗ��R�Ɠǂݐi�߂�A���̎�̂��ς�������ƂɋC�Â��Ȃ��ł��傤�B���̏ꍇ�A�t�@�j�[�̓��S�̂��ǂ��ǂ������_���A�q�ϓI�Ȏ����̓����ł��邩�̂悤�ɑ�������悤�ɂȂ�̂ł��B���̂悤�ɂ��āA�t�@�j�[�͂����߂����T�[�E�g�}�X�ɂт��т����A�}���C�A�ƃW�����A����s�v�ɂȂ�������т₨�������^�����A�t�����X���n�����j�̖��m��o���A�v�͐l�i����������̂Ƃ��ĔF�߂đ���ɂ��ꂸ�A�ЂƂ�ڂ����ł���Ƃ������Ƃ��A����̓t�@�j�[����̎��_���������Ă���̂ɁA�q�ϓI�Ȏ����ł��邩�̂悤�ɓǂ߂Ă��܂��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������ɁA�ޏ��͌����͑������ł͂Ȃ����A�����I�Ȑ��i�ł͂��邩������܂���B�������A�펯�ōl���Ă݂Ă��������B�킸���P�O�̏��̎q����������Ƃ��Ȃ��e�ނ̂Ƃ���ɁA�ЂƂ�ŕs����ȓ������o�āA��������Ƃ܂�����������@��ɁA�����āA���e�������ė��ݍ���ň������ꂽ����͕����Ă��邾�낤���A�m���X�v�l���炭�ǂ��قNJ��ӂ���悤�ɐ�������āA��������ĒH������}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�ŁA�������Ȃ��͂����Ȃ����A�z�[���E�V�b�N�ɂ�����͓̂��R���낤���A�s���ł��傤�B���������A�q�����V�^ࣖ��Ɍ�����Ƃ��Ă��A�P�O���炢�̔N��ł���A���͂����n���āA���g�̗�����킫�܂��āA�ǂ��܂ł��Ύ��͂͏��ċ����Ă���邩�����v����Ă�����̂ł��B���̎��͂��݂��Ȃ���A�܂��͗l�q���f���͕̂��ʂ̂��Ƃł��B����������ɁA�ŏ�����ނ�݂Ɏ��Ȏ咣����̂̓��A�P�[�X�ł͂Ȃ��ł��傤���B������A�t�@�j�[�́A���̎��̗l�q�́A��ʓI�Ȃ��̂ł��B�����ǎ҂ɂ́A���̂悤�Ɍ����Ȃ��悤�Ɍ���Ă��܂��B���ꂪ�I�[�X�e�B���̌����̔閧�ł͂Ȃ��ł��傤���B �t�@�j�[�̂悤�ɕ�������ŁA��������͘b�����Ƃ��Ȃ��q���C���Ƃ����̂̓I�[�X�e�B���̍�i�̒��ł́A���ɂ��A�w�����x�̃A���A�w���ʂƑ����x�̃G���m�A�������ł��B�������A�ޏ������͑�l�����Ƃ��A�g�ł͂����Ă��A�t�@�j�[�̂悤�ɖ��͂Ƃ����݊��������Ƃ����͂ɖR�����Ƃ͌����܂���B�t�@�j�[�������A�����Ȃ��Ă��܂��̂́A�����炭�I�[�X�e�B�����Ӑ}�I�ɁA���̂悤�ɏ����Ă��邩��ŁA��̓I�ɂ́A���̑��͂Ń}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�ɓ����������̂��ǂ��ǂ��āA���������Ȃ��A�����߂������̂悤�ȑ���ۂ̃C���[�W���A�t�@�j�[�̍�i��ʂ��Ă̈�ۂ����߂Ă��܂�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ȃ��A�I�[�X�e�B���͂���Ȃ��Ƃ������̂��́A�����������������i�߂鎞�ɕ֗�������ł��B�����̌��ʂ́A���̌�̕���̓W�J�ɂ����āA�o�Ă��܂��̂ŁA����͒ǂ������Ă��������Ǝv���܂��B �����ŁA�ǎ҂ɉf��t�@�j�[�̃C���[�W�́A�n�����q��R�̃v���C�X�Ƃ̒����ŁA��Ƃ��ꋫ����~�����߂́A����Ό����炵�̂��߂ɁA�T���Ȕ���̉ƒ�o�[�g�����ƂɈ������ꂽ�Ƃ����A���g�̋�������̐g�ł���Ƃ������Ƃł��B���̓_�͂܂���Ȃ�ɂ��Ƒ��̈���ł���A����G���m�A�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�����Ĕޏ��͖����Ȑl���ɂ��邱�Ƃł��B�ޏ��͌������������ł͂���܂���A��b�̏�ʂł��A�قƂ�Ǖ������ɓO���Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���炭�o��l�������̉�b�������Ă����ʂŁA�������͂����ɔޏ������邱�Ƃ����Y���Ƃ�������܂��B�Ƃ��������A�ޏ��̂��Ƃ�������Ă��Ȃ����Ƃ��炠��܂��B����͌�肪�ޏ��̎��_�ɂȂ��Ă���A���R�����̂��Ƃ͌����Ȃ�����ŁA���ꂪ�q�ϓI�Ȍ��ł���Ɠǎ҂͓ǂ�ł��܂��̂ŁA�ޏ��̑��݂�������Ă��Ȃ��Ɠǂ�ł��܂��̂ł��B ���āA���̑�Q�͂̍ł��d�v�ȃG�s�\�[�h�́A�t�@�j�[�ƃG�h�}���h�̏o��ł��B�t�@�j�[�ɂƂ��ăG�h�}���h�̓}���X�t�B�[���h��p�[�N�̒��ŗB��A�S��ʂ킷���Ƃ̂ł���l���ŁA���̌�A�ޏ����Ԃߗ�܂��A���A�����������݂ƂȂ��Ă����܂��B���̃t�@�j�[���G�h�}���h�ɐS���J�����������ƂȂ����̂��A�t�@�j�[�̒��ǂ��̌Z�ł���E�B���A�����W���܂��B�܂�A�t�@�j�[���₵�����Ă���v���͉Ƒ��Ƃ̕ʗ������邱�ƂȂ���A��Ƃ��ăE�B���A���ɉ�Ȃ����ƂɋN�����邱�Ƃ��G�h�}���h�������o���A�ޏ��ɌZ�Ɍ����Ď莆��������`�������Ă��������Ƃł����B���̂Ƃ��́A�G�h�}���h�͎₵����t�@�j�[�ɂƂ��čň��̌Z�E�B���A���̑���ƂȂ鑶�݂Ƃ��ĉf�����悤�ɏ�����Ă���̂ł��B�����ŁA�t�@�j�[�ƃG�h�}���h�̊W�͌Z���ɋ[�����邱�ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃɂ���āA�ǎ҂́A�G�h�}���h�̓t�@�j�[�ɂƂ��ČZ�̂悤�ȑ��݂ŁA����͌Z�������甭�W���āA�₪�Č����ւƎ���������Ȃ̂��Ƃ����悤�Ɉ�ۂÂ�����B���ꂪ�A�����t�@�j�[���G�h�}���h�Ɋ��т����v��̕���ł��邱�Ƃ��ŏ����疾�炩�ɂ��ꂽ�Ƃ�����A����̍\���Ƃ��ẮA����́w�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�x���t�@�j�[�ƃG�h�}���h�̃��u��X�g�[���[�ƂȂ��āA�t�@�j�[�̑��݊����O�ʂɏo�Ă��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�Ⴆ�w�����x�̃A���̂悤�ɂł��B�������A��҂ł���I�[�X�e�B���́A�������邱�Ƃ͂Ȃ��A�t�@�j�[�̎v��͏����̒��ŕ����̂悤�ɗ���Â��āA���鎞����l�X�̖ڂɐG���悤�ɂȂ�܂��B��Q�͂̍Ō�Ŏ��̂悤�ɏ��q����Ă��܂��B �t�@�j�[�́A���̂悤�Ȑe�ȓ����Ɋ��ӂ��A�Z�̃E�B���A���X�������A�G�h�}���h�𐢊E���ł�������悤�ɂȂ�A�������t�@�j�[�̐S�́A���̓�l�ɓ����Ɍ�������悤�ɂȂ����B�i�o.�R�W�j ���̕��͂̏������ł̓t�@�j�[�̓G�h�}���h�Ɋ��ӂ��A�Z�̃E�B���A���X�Ɠ����Ɉ�����Ƃ��Ă���̂ŁA�Z�����ƈ�ەt�����܂��B �܂��A�t�@�j�[�ƃG�h�}���h�͌Z���̂悤�Ɉ�ەt�����Ă��܂����A�����̒��ŁA�ނ�ɑΔ䂷��悤�ɒ��̗ǂ��Z�����z������Ă��܂��B����̓N���t�H�[�h�Z���ł��B����ɂ܂��A�����Z���ł��ΏƓI�ɁA�����ǂ��Ƃ͂����Ȃ��̂��o�[�g�����Ƃ̌Z���ƃt�@�j�[�ɑ���E�B���A���ȊO�̃v���C�X�Ƃ̒�▅�����Ƃ̊W�ł��B���́A���ꂼ��̌Z����Δ䂷��悤�ɕ��ꂪ�����Ă����\���ɂȂ��Ă���̂ł����A�����ł͐摖��߂��܂����B �@��R�� �����Ȏ������N�����āA����������̎��Ԃ������n�߂܂��B�t�@�j�[�̔����ɂ�����m���X�����S���Ȃ�܂��B�q�t�̃m���X�v�Ȃ̓}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̖q�t�قɏZ��ł��܂������A����ɂ���Č�C�̃O�����g���m������Ă��܂��B���Ƃ��Ƃ̗\��̓o�[�g�����Ƃ̎��j�G�h�}���h���q�t�ƂȂ��āA�����ɓ���͂��ł������A���j�̃g�����Q��ɂ���đ��z�̍�������A���̐��Z�̂��߂Ƀ}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̐��E�\������������Ȃ��Ȃ�A����ŁA�z��O�̃O�����g���m������Ă��邱�ƂɂȂ����Ƃ����킯�ł��B �����ŁA�o�[�g�����Ƃ̓��������炩�ɂ���Ă��܂��B�Ⴆ�A�����܂łR�͂������ăo�[�g�����Ƃ̐l�X���Љ�A�{�҈ȑO�̌o�܂Ƃ������w�i��������Ă��܂������A�̐S�̑薼�ɂ��Ȃ��Ă���}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ��Ă͉�������������܂���B���̌�ɓo�ꂷ���n��̃��b�V�����[�X���̏ꍇ�́A�y�n�̍L����N�����A�����Ă܂��w�����[��N���t�H�[�h�͕s�ݒn��ł����N���L���āA�ǂ̒��x�̔_�����z�������悤�ɏ�����Ă��܂��B������ɁA��ȕ���ŁA�q���C���̃t�@�j�[��������������ɕ���������}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ȃ̂ł��B�܂��A��P�͂Ōo�ϓI��Ղ�Ȃ������̋��������ʂƂ��Ă����炢�A�쒆�ł��A�����ɂ��Č����Ƃ��ɂ͌o�ϓI�ȗv�f����ɍl������Ă���̂ɁA����̍Ō�ɂ̓t�@�j�[���������Ă���}���X�t�B�[���h��p�[�N�̌o�ϋK�͂ɂ��ẮA�ꌾ���G����Ă��܂���A����͖��炩�ɁA��҃I�[�X�e�B�����Ӑ}�I�ɏ����Ȃ��������Ƃł��傤�B�܂�A�I�[�X�e�B���͉B�����̂ł��B �������A�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N���̂̕��i�`�ʂ��S���Ȃ��킯�ł͂���܂���B�Ⴆ�A����̏I�ՂŃt�@�j�[���|�[�c�}�X�̎��ƂŃ}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̂��Ƃ�lj�����Ƃ��������S�Ɗ֘A�Â����A�܂�A�t�@�j�[�̎v������̃t�B���^�[�ɂ���ė��z�����ꂽ�p�ŋL�q�����̂ł��B������A���ۂ̍L���Ƃ��A�ǂ̂��炢�̐l�X�������Ă���̂��Ƃ��A�̎�ł���T�[��g�}�X�������łǂ�ȍєz��U����Ă���̂��͈�؏�����Ă��Ȃ��̂ł��B���������āA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�͎��̂��������ɓo��l�����G�ꍇ������ł����Ȃ��̂ł��B �I�[�X�e�B���Ƃ��������Ƃ͕K�v�Ȃ��Ƃ��������Ȃ��l�ł��B������A�K�v�Ȃ��Ƃ͏����̂ł����āA���������ׂ������ᖡ���č�i�����M���Ă���l�ł��B�����Ȃ����Ƃɂ͗��R������̂ł��B��قǂ��G�ꂽ�悤�ɁA���b�V�����[�X����w�����[��N���t�H�[�h�ɂ��Ă͊ȒP�ɏ����Ă���킯�ł����A�o�[�g�����Ƃ̏Ɋւ��邱�ƂȂ̂Łi�̎�̌p����o�Ϗ̎����T�[�E�g�}�X�͐A���n�ɏo�������ƂɂȂ�A���ꂪ����̑傫�ȓ]�@�ƂȂ�j�A���炩�ɂ��ׂ����Ƃ̂͂��ł��B������I�[�X�e�B���͏����܂���B���̗��R�͉��ł��傤���B����́A�����炭�o�[�g�����Ƃ͂��n����傽��������Ƃ���P�W���I�ȗ��̓`���I�Ȓn��w����C���ԂƂ��Ă͖f�Ղ܂菤���ɂ����v�Ɉˑ�������ƉƑw�ɕϖe���Ă��Ă���̂ŁB�T�[�E�g�}�X�͐��C���h�����̓����ɂ���A���e�B�O�A�iAntigua�j���Ƀv�����e�[�V���������L���Ă���C���̔_���o�c�ɂ���Ď傽������Ă��܂��B�܂�C�C���O�����h�ɂƂ��ĕs���_�ƂȂ肤��z��f�Ղ��܂ށA������O�p�f�ՂɃo�[�g�����Ƃ̗̓y�Ǘ��͈ˑ����Ă���̂ł��B����́A�����ɂ����ẮA���܂�\�ɂ͏o�������Ȃ�����ɑ����Ă����Ǝv���܂��B�����ɁA�t�@�j�[���G�h�}���h�ɑ��ĕ\�ʓI�ɂ͌Z���̈���Ƃ��āA���̂����ɂ͖����ɗ��S��������̂Ɠ����悤�ɁA�o�[�g�����Ƃ͕\�ʏ�̓}���X�t�B�[���h��p�[�N�̗̎�Ƃ��ĐU�镑���Ȃ���A�����I�ɂ͐A���n�ւ̓����Ƃɕϖe���Ă����Ƃ�����d�\���ɂȂ��Ă������Ƃ�������܂��B�����āA���̏����ł́A���̂悤�ȓ�d�\�������邱��Ɍ���āA�����Ɠ��̌���ɂ���ē�d�\���Ō����Ƃ������ƂɂȂ�A���ŁA�ǎ҂͕���ꂽ�z�[���h���}�ł���ׂ����̂��A�_�C�i�~�b�N�ȓ���͂����Ƃ��Ď�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂ł��B �����āA�o�[�g�����Ƃ̐l�X�Ɋ��]���܂��傤�A���j�̃g���́A�����̓T�[��g�}�X�̐Վ��ƂȂ�ׂ��l���ł��B�������A�ނ͗̎傠�邢�͊�ƉƂƂ��Ă͖��\�ŁA���܂��ɘQ��Ƃł����B�ނ�����Ă��܂�������Ȏ؋��̎x���̂��߂Ƀ}���X�t�B�[���h��p�[�N�̖q�t�ق��ꑰ�̎�𗣂�A���j�G�h�}���h�́C���̊���H���āC�{�������������p�����ƂɂȂ鉮�~�������܂����B�����āA���̖q�t�قɂ���Ă����̂��O�����g���m�ł����B�g���̓T�[�E�g�}�X�Ɏ��ӂ��܂����A���i�ȕ��e�̑O�ł͑����̔��Ȃ̐F�������Ă��A���̎��A���e�̒��������A���ς�炸���g�̍��{�I�ȕ������Ђ��������͂Ȃ��悤�ł��B����䂦�A�A���n�ł̃v�����e�[�V�����o�c���v�킵���Ȃ����āA�T�[��g�}�X�̓T�[�E�g�}�X�͎���_�n�Ǘ��̎w��������ׂ����C���h�����̓����ɂ���A���e�B�O�A�iAntigua�j���ɕ������ƂɂȂ�܂��B���̍ۂɃg�����������邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A���̑�R�͂̍Ō�̂Ƃ���ŁA�t�@�j�[���P�U�ɂȂ����Ƃ��ł��B�T�[��g�}�X���A���e�B�O�A�ɕ��������Ԃ͂Q�N�ɋy�сA���̊Ԃ͎��j�̃G�h�}���h���㗝�߂�̂ł����A�̎傪�Q�N�Ԃ����������Ƃ������Ƃ́A�o�[�g�����ƂɂƂ��āA�A���e�B�O�A���d�v���Ƃ������ƂƁA��N�̃G�h�}���h�ɑ㗝���Ƃ܂��Ă��܂��Ƃ����}���X�t�B�[���h��p�[�N�̗̎�Ƃ��Ă̕��S�́A����قǏd���Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�������ɑz���ł��܂��B�܂�A�I�[�X�e�B���́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ��ċL�q���Ă��܂��ƁA���̂悤�ȋ����Ă��Ă�����Ԃ������炩�ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����āA�����Ȃ������Ƃ������Ƃ��z���ł��܂��B ����́A�T�[��g�}�X���}���X�t�B�[���h��p�[�N����ꎞ�I�ɑޏo���邱�ƂƁA�q�t�قɃO�����g���m������Ă������ƂŁA���̕v�l�̐e�ނɂ�����N���t�H�[�h�Z�����}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ���Ă���L�b�J�P���ł������ƂɂȂ�܂��B �����āA��R�͂Ō��߂����Ȃ��̂��A�m���X�v�l���q�t�ق��o��̂ŁA������_�@�Ƀt�@�j�[���}���X�t�B�[���h��p�[�N���o�ăm���X�v�l�ƕ�炷���ƂɂȂ�Ƃ������ƂɂȂ��āA�t�@�j�[�ƃG�h�}���h�̉�b�ł��B�t�@�j�[�́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N���o�����Ȃ����ƂƁA�m���X�v�l�ƕ�炷���Ƃւ̋�s�������܂��B���̉�b���番���邱�Ƃ́A�܂��A�t�@�j�[���m���X�v�l�ɑ��āA���ډՂ߂��Ă��邱�Ƃ̋�s�������ڂ��܂��A�m���X�v�l�Ƃ����͈ꏏ�ɕ�炵�����Ȃ��Ɣޏ����������Ƃ�\�����܂��B�����ŁA�t�@�j�[�̋������Ȏ咣������̂ł��B�������A�����S�̂̈�ۂƂ��ăt�@�j�[�͎��͂ɋC�������Ď��Ȏ咣���Ȃ��Ǝ���Ă���̂ƁA�ŏ��߂�����A�����łȂ��s�������͂Ƃ��Ă���B�������A�t�@�j�[�̃C���[�W�͕ς��Ȃ��B����́A�ŏ��̂��������Ȉ�ۂƁA�G�h�}���h�Ɠ�l�̏�ʂŎ��Ȏ咣���Ă��邩��ł��傤���B�����āA���̏�A�G�h�}���h���m���X�v�l�ƕ�炷�̂͂���قLj������Ƃł͂Ȃ��Ə𗝂������Đ������Ă���̂ɑ��Ă��A��łɎ���������܂���B����́A��ŁA�t�@�j�[���w�����[��N���t�H�[�h����̃v���|�[�Y�����₵�����Ƃɑ��Ď��͂������甽���Ă��f�łƂ��ď���Ȃ����Ƃ̐�삯�̂悤�ȏ�ʂł��B�܂�A��ɂȂ��āA�t�@�j�[�̈ӎu�̋��������炩�ɂ���܂����A����́A���̎��ɓˑR�����Ȃ����̂ł͂Ȃ��A���łɂP�U�̏����̂���ɂ��łɂ����ł������̂ł��B�������A���̂悤�ȏ�����\������悤�Ȃ��Ƃ́A������Ă��邯��ǁB�ǎ҂́A����Ńt�@�j�[�̐��i���C���[�W���Ȃ��œǂ݉߂����Ă��܂��܂��B�����ɁA�I�[�X�e�B���̏����̎d�|��������ƌ�����̂ł��B �����Ă���ɁA���̂悤�ȏ����ȃG�s�\�[�h�ł����A���̏����̃q���C���ł���A���g�ɍ~�肩�����Ă����@���Q�Ȃ̂ł�����A��������������Ώ����邽�߂̍s�����N�������̂ł��B�Ƃ��낪�A�t�@�j�[�́A���̍s�����N�����Ȃ����A�s������������Ȃ��Ȃ����ۂɁA���R�̂悤�Ɏ���ω����āA�ޏ����s�����N�������ƂɎ���Ȃ��̂ł��B���̏ꍇ�ł��A�t�@�j�[�̓}���X�t�B�[���h��p�[�N���o�ăm���X�v�l�ƕ�炷���ƂɂȂ�Ɛ�]�I�ɂȂ��Ă����Ƃ���A�m���X�v�l���t�@�j�[���������J�͂Ƌ��K���S������邽�߁A�t�@�j�[���}���X�t�B�[���h��p�[�N�ł̐����𑱂����悤�ɉ�A���������Ă��܂����B�܂�A�t�@�j�[�̗^��ʂƂ���ŁA���Ԃ͉�������Ă����̂ł��B���̌�̃G�s�\�[�h�ł��A�t�@�j�[�̔N�V�����n������ł��܂����Ƃ��̂��Ƃ�f�l�����Ƀt�@�j�[���Q��������ꂻ���ɂȂ������ƁA���邢�͈�U�|�[�c�}�X�̎��Ƃɖ߂��ꂽ��}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɋA���悤�ɂȂ������ƂȂǁA���ׂăt�@�j�[���g���s�����N�����Ă��܂���B�ޏ��͊O�ʓI�ɂ͎����I�ȍs�����N�����Ă���悤�ɂ́A�����Ȃ��̂ł��B�����ɁA�ޏ����g�ł��邱�ƁA���ƂȂ����Ƃ�����ۂ�ǎ҂ɑ��ċ��߂Ă������ƂɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B ���̑�R�͂̏��q�̂Ȃ��ŁA�o��l���̉�b����������A���ۂɓ����Ă����ʂ�����̂́A�t�@�j�[���m���X�v�l�ƃ}���X�t�B�[���h��p�[�N���o�čs�����Ƃɂ��Ẵt�@�j�[�ƃo�[�g�����v�l�Ƃ̂�����Ƃ�����b�ƁA�t�@�j�[���G�h�}���h�ɓ��X�ɑ��k����Ƃ��낾���ŁA����ȊO�̕����͌��肪�������Ă����܂��B������A�T�[��g�}�X���o�����Ă��܂����Ƃ��A�m���X�����Ȃ��Ȃ��ăO�����g���m�����C���Ă��邱�Ƃ��A�w�i�̎����̂悤�ɓǂ܂�Ă��܂��܂��B�܂�A�ǎ҂ɂ́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̎��͂ł͕����������Ă���Ƃ����C���[�W�ŁA����ɑ��āA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�͑䕗�̖ڂ̂悤�ɕ����������Ă���悤�ɉf��̂ł��B �@��S�� �T�[�E�g�}�X�ƃg�����A���e�B�O�A�ɏo�����܂����B���j�̃G�h�}���h���T�[��g�}�X�̑㗝�Ƃ��ė����a����܂����A���Ă��邱�Ɓu�H��ł̎�l�����Ƃ߂���A�����Ƒ��k������A�㗝�l�ٌ�m�Ɏ莆����������A���g�Ƙb�������肵���B�v�́A����͗̒n���o�c����̎�̂��邱�ƂȂ̂��A�Ƃ����قǍ����Ȃ��ƂŁA�o�[�g�����Ƃ̃}���X�t�B�[���h��p�[�N�̗̎�Ƃ��āA�n��Ƃ����������A�������Ă��Ȃ��Ɠ����ł��B�����̒��ōŌ�܂ŁA��X���h�������}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̎p�͂ǂ��ɂ��`����Ă��Ȃ��B���h�ł���Η̎�̑㗝�ł���G�h�}���h�̖����́A�����ł��낤�Ƃ���A���Z�ɂȂ�͂��ł��B�������A�G�h�}���h�̖����́A����ȕn��Ȃ̂ł��B�I�[�X�e�B���͊ԐړI�ɁA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̉h���̎p�́C�t�@�j�[�̏����ȓ��ɂ̂ݑ��݂��Ă���̂�������Ȃ����Ƃ��A�ÂɌ���Ă���̂łȂ��ł��傤���B���̕����͌���ɂ��n�̕��ŏ�����Ă��܂��B �o�[�g�����Ƃ̎o���}���C�A�ƃW�����A�́A�����邨�N���ƂȂ��āA�Ќ��E�Ƀf�r���[���A�m���X�v�l�ɕt���Y���ĕ������p�[�e�B�[�ɏo�����܂��B����ɑ��āA�t�@�j�[�͂P�W�Ƃ����N��ł����A����Ԃƃo�[�g�����v�l�̑���߂܂��B����́A�V���f�����Ǝo�����Ƃ̊W�ɋ[�����āA�t�@�j�[�����ʂ���Ă���\�}�����o���Ă��܂��B����ɑ��āA�t�@�j�[�͂ނ����������邵�A�]���������畑����̘b����̂��y���݂ɂ��Ă���Ƃ����悤�ɁA�������Ă��鈵���ɂ��Ă̕s������؍�҂͏����Ă��܂���B�����̃G�s�\�[�h�͌���ɂ��q�ϓI�Ȍ��ŁA�W�X�ƌ���܂��B�����ɂ́A�I�[�X�e�B���̏����Ȃ��Ƃ����I�����A���Ȃ�l���Ĉׂ���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�Ќ��E�ɘA��čs���Ă��炦�Ȃ��t�@�j�[�̋C������A����ɑ��ă}���C�A�ƃW�����A�ɂ��ẮA�}���C�A�͍���҂Əo��킯�ł����A�T�[��g�}�X���}���X�t�B�[���h��p�[�N���炢�Ȃ��Ȃ������Ƃœ���ꂽ���������̓�l�̍s���Ɍ��т��Ă����킯�ł�����A���̂Ƃ��̓�l�̓��S�ɂ��ĐG����Ă��Ă����������͂Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��A�Ќ��E�̖͗l��A��l�������łǂ��U���������Ȃǂ��A�S��������Ă��܂���B�����āA����ɁA�}���C�A�́A��ɍ���҂ƂȂ郉�b�V�����[�X�ɏo��܂��B���̂Ƃ��A�}���C�A�����b�V�����[�X���ǂ��v�����̂���������Ă��܂���B�ޏ��̊���̋L�q�͂Ȃ��A���̂悤�ȊO�ʓI�Œʂ��Ղ̂��Ƃ���������Ă��܂���B ���b�V�����[�X���͂ƂĂ������̂����N�ŁA���̕��́A�܂��܂��펯������Ă���Ƃ������x�����A�e�p���ԓx������قNJ����̈����Ƃ���͂Ȃ��̂ŁA�}���C�A�͎����������߂�ꂽ���Ƃ���B�}���C�A��o�[�g�����͌��݂Q�P�ł���A���낻�댋�����`���ƍl���n�߂Ă����B���b�V�����[�X���ƌ�������A���̃T�[��g�}�X���������̑����g���ɂȂ�邵�A����ɁA���܂͂��ꂪ�ޏ��̂�����傫�Ȋ肢�Ȃ̂����A�����h���ɂ��Ƃ������Ƃ��ł���̂ŁA�u�����K����̏����͌������ׂ��v�Ƃ��������I�`�������猾���Ă��A�ł��邱�ƂȂ烉�b�V�����[�X���ƌ������邱�Ƃ��A�ޏ��̖��炩�ȋ`���ƂȂ����B�i�o.�U�P�j �Ō�́u�ޏ��̖��炩�ȋ`���ƂȂ����v�Ƃ������͂ɂ���悤�ɊO�ʂ��Ȃ���悤�Ȃ��Ƃ���������Ă��܂���B�܂�ŏ��������}���X�Ƃ������ɓ���Ă���悤�ȍl�����ł��B���̂Ƃ��̃}���C�A�̓��ʂɂ͎�̐����m������Ă��Ȃ������̂��A�}���C�A���g�����b�V�����[�X���ǂ��v�����̂��ɂ͈ꌾ�����y����Ă��܂���B �������A�c�ɋM���̂��삳��ʼn��s���R�Ȃ�������}���C�A���A���͂̂����߂�܂܂Ɍ��������āA���̌�A�^���I�ȏo��ŁA�w�����[��N���t�H�[�h�Ɨ��ɗ����āA���Ȃɖڊo�߁A���������ł��̂Ăė��ɐ�����Ƃ������Ƃł���A����͓T�^�I�ȋߑ㏬���ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ⴆ�A�u�{���@���[�v�l�v�u�A���i�E�J���[�j�i�v�Ȃǖ����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��ł��傤�B���ꂾ���łȂ��A�����̒ʑ��I�ȃ��}���X�ł��A���̂悤�ȃV�`�G�B�V�����̕��ꂪ�������ꂽ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�I�[�X�e�B���͂�����s�킸�A�Ђ˂���������āA���������q���C���̍s���ɂ���Ď��c���ꂽ�Ƒ��������̑�ނƂ��܂����B��̂��ƂɂȂ�܂����A�����ł̓}���C�A�̓��ʕ`�ʂ͂���܂���B�Ƒ�����݂�A�ޏ��̍s���͖��f�Ȃ��ƂŁA�y���Ŗ����ʂɈڂ�ł��傤�B�������A���C���ł͂Ȃ��T�u��X�g�[���[�ɂ��āA�t�@�j�[��v���C�X�����̑���̒j������̋�����f�Œf�������ƂƑΔ�I�Ɉ����Ă��܂��B�]���āA�ߑ�I�ȗ��ɖڊo�߂������̃��}���X���A�����ł̓V���f�����̈Ӓn���Ȏo�̈��ʉ���̌����ɔ��]���Ă��܂��Ă���̂ł��B�����ɁA�}���C�A�̃G�s�\�[�h�̏�����̍���ƁA���̂悤�Ȉ����Ă���Ƃ����ʔ���������Ǝv���܂��B �s�v�c�Ȃ��ƂɃG�h�}���h���A���̍���ɔ��ŁA�ނ̓��b�V�����[�X�̂��Ƃ��u���̒j�́A�N���P���Q��|���h�̋������łȂ���A�����̔n�����v�i�o.�U�R�j�Ǝv�����Ə�����Ă���̂ɁA�ł��B�����́A�����������Ȃ����ɂ��ẮA�I�[�X�e�B���́A���Ȃ�Ӑ}�I�ł������Ǝv���܂��B ����A���̏͂Œ��ڂ��Ă����̂́A�t�@�j�[�̔n�Ɋւ���G�s�\�[�h�ł��B�ޏ��̏�n�p�ɂ��Ă���ꂽ�N�V�������т̃|�j�[�������Ƃ����Ƃ̎n�܂�ł��B����̎��̃t�@�j�[�́A�^���̂��߂ɏ�n��i�߂��܂��B�������A�V�n�̎��ɂ���n���ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�m���X�v�l�́A�^���ł���t�@�j�[�ɎU���Ƃ��āA���g�̉Ƃւ̗p���������ĕ֗��Ɏg�������̂ł����A����̓t�@�j�[�ɂƂ��Ă͉d�ȕ��S��g�̂ɂ����邱�ƂɂȂ�܂��B����ɋC�t�����G�h�}���h���t�@�j�[�̂��߂ɐV���ɔn�����Ƃ��Ă��܂��B����́A�G�h�}���h�ƃo�[�g�����v�l�ƃm���X�v�l�Ƃ̉�b�Ƃ��ď�����Ă��܂��B�G�h�}���h�͓�l�̔������Ƃ͂ł����A�����̎����n���R�����邤���̂P�����t�@�j�[�̂��߂ɐU�蕪���邱�ƂőË����܂��B�����Œ��ӂ��ׂ��́A��b�̒��Ƀt�@�j�[�̈ӌ����܂������o�Ă��Ȃ����Ƃł��B�L�q�ɂ̓t�@�j�[�Ɋւ��邱�Ƃ������Ȃ��̂ŁA���̏�ɂ����̂��A���Ȃ������̂����n�b�L�����܂���B�܂�A�����������݊��Ȃ̂ł��B���̉�b�̒��ŁA�t�@�j�[���g�͂ǂ̂悤�Ɋ�]����̂����S����������Ă���킯�ł��B�����Ő}�炸���A�G�h�}���h���t�@�j�[�̂��Ƃ��v���A�D�������Ă���l���ł͂��邯��ǁA�t�@�j�[�̐l�i�d���Ă���܂ł͂����Ȃ��āA�\�ʓI�ȃ��x���ł���Ƃ������ƁA���̓G�h�}���h�Ƃ����l���̔����炳�Ƃ������Ƃ̈�[�������ŁA�I�[�X�e�B���͓��킹�Ă��܂��B�Ƃ����̂��A�����Ńt�@�j�[�ɐV���ɂ��Ă���ꂽ�n�́A���̌�ŁA���A���[��N���t�H�[�h�ɏ�n�������邽�߂Ɏg�����ƂɂȂ�A���A���[��������Ɛ肷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��āA���ǂ̓t�@�j�[����n�ł��Ȃ��Ȃ邱�ƂɂȂ�킯�ł��B���̃��A���[�ɏ�n��U���āA�n�̎�z�������͓̂��̃G�h�}���h�Ȃ̂ł�����B���̂悤�ɁA�I�[�X�e�B���̌����̓����̂ЂƂƂ��āA���̏ꍇ�ɂ́u�n�v�ł����A����̑�ނ�G�s�\�[�h�ɂ��āA��������グ�Ďg���܂킷�B�Ⴆ�A�������ʂɎ����čs������A�������`��ς��Ă݂��肵�āA�����ŊW�����o���āA����ɂ���ĈӖ������o���Ă����Ƃ�����@�ł��B���y�ł����A�\�i�^�`���Ŏ�����āA���̎������낢���������ēW�J�����Ă����̂Ɏ��Ă���ƌ����܂��B ����ŁA�t�@�j�[�̕��̓G�h�}���h�Ɋ��ӂ���̂ł����A�����ɗ�������ǂݕ��ɂ���Ă͂���������悤�ȏ����������Ă��܂��B�����ł̌��́A�t�@�j�[�̓��S����̂ɂȂ��Ă��܂��B �������A����͂��ׂăG�h�}���h�̐e�̂��������Ǝv���ƁA��т͂܂��܂��傫���Ȃ�A�ƂĂ����t�ł͌����\���Ȃ������B�t�@�j�[�ɂƂ��ăG�h�}���h�́A�P�ƈ̑傳�̌��{�̂悤�Ȑl�ł���A�ޏ��ɂ����킩��Ȃ����l���������l�ł���A�ޏ����ǂ�ȂɊ��ӂ��Ă�����Ȃ��l�������B�G�h�}���h�ɑ���t�@�j�[�̋C�����ɂ́A���h�ƁA���ӂƁA�M���ƁA����̂��ׂĂ����荬�����Ă����B�i�o.�U�O�j ���̏������͔����ŁA�u�G�h�}���h�̐e�̂��������Ǝv���ƁA��т͂܂��܂��傫���Ȃ�A�ƂĂ����t�ł͌����\���Ȃ������v�Ƃ������Ƃ́A�n��^����ꂽ���ƈȏ�ɃG�h�}���h����^����ꂽ���Ƃ̕����ޏ��ɂ͊�����Ƃ������Ƃɂ����܂��B���̌�ɑ������͂��G�h�}���h�ւ̊��ӂ���A�ނւ̎v���ɗ��ꍞ��ł����܂��B�u�ޏ��ɂ����킩��Ȃ����l���������l�v�Ƃ������Ƃ̓G�h�}���h�̒l�ł��͎����ɂ����킩��Ȃ��Ƃ������ʂȊ�����t�@�j�[�������Ă����킯�ŁA����Łu���h�ƁA���ӂƁA�M���ƁA����̂��ׂĂ����荬�����Ă����v�C�����������Ă����Ƃ����킯�ł�����A�t�@�j�[�ɂƂ��ăG�h�}���h�͓��ʂȐl�ł��邱�Ƃ́A���̎��_�Ŗ����ł���A���ړI�Ȍ��t�͂Ȃ��Ă��A���S�ł��邱�Ƃ͊�������킯�ł��B�����āA�킸���P�y�[�W��ɂ́A�}���C�A�����b�V�����[�X�Ƃ̉��k�̐���������ɂ�������炸�A�ޏ��̑���ɑ���v�����ꌾ��������Ă��Ȃ��̂ł��B���̑ΏƂł��B �����āA�N���t�H�[�h�Z�����}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ���ė��܂��B �@��T�� �O�͂Ń}���X�t�B�[���h��p�[�N�̖q�t�قɂ���Ă����N���t�H�[�h�Z�����A�o�[�g�����Ƃ̌Z��o���Əo��Ƃ���ŁA�݂��ɍD����������o�����A�q�t�قł̌Z���Ɠ�l�̎o�̃O�����g�v�l�̂R�l�̉�b���O���ł��B���̒��������̑S�̂�ʂ��āA�����炭�A�ł������ɉ�b�����Ă���̂��A���A���[��N���t�H�[�h�ł��B�����āA�Z�̃w�����[������ɑ����܂��B����́A��l���ł���t�@�j�[�̔��������Ȃ��āA�ޏ��̂��Ƃ͂����ς�n�̕��Ō����̂ƑΏƓI�ł��B���̌Z���̂���Ƃ���ł́A��ɉ�b��������A���ꂪ�����ɂ����ĉ�b���ŕ`�ʂ���Ă��܂��B���������āA�ǎ҂ɂ́A���̌Z���̓o�[�g�����Ƃ̌Z��������萶�ʂ��鑶�݂Ƃ��ĉf��܂��B�������A���̌Z���Ɋւ���n�̕��ɂ��L�q�͊O���Ƃ���l�̍s���Ƃ��������Ƃ���ŁA�t�@�j�[��G�h�����h�A�T�[��g�}�X�Ɋւ���L�q���A���ꂼ��ɒ��x�̍�����������ʂɓ��ݍ����̂ł���̂ƈႢ�܂��B���������āA���̌Z���́A���ꂩ�畨��̓W�J�ɂ�āA�s�������Ă������Ƃ��A���������邱�Ƃɂ���āA���X�ɐl�������炩�ɂȂ��Ă���Ƃ����o��̎d�������܂��B����́A�t�@�j�[��G�h�����h���A�قڍŏ��̒i�K�łǂ̂悤�Ȑl�������ǎ҂ɕ������Ă��܂��āA���̃C���[�W�ŏ�����ǂݐi�߂Ă����̂Ƃ́A�܂������Ⴄ������ł��B���̂��߁A���̌Z���͕��ꂪ�i�ނɂ�ĈӊO�Ȗʂ������Ă�����A�l�������ω����Ă��܂��B �Ⴆ�A�w�����[�̗e�p�ɂ��Ă̔����ȕω� �Z�̃w�����[��N���t�H�[�h�͔��j�q�ł͂Ȃ������B����ǂ��납�A�ŏ��݂����́A���S�ȏX�j���Ƃ݂�Ȃ��v�����B�F���̏X�j�Ȃ̂��B�������A����ł���͂�a�m�ł���A�ԓx��b�����͂ƂĂ��������ǂ������B��x�ڂɉ���Ă݂�ƁA����قǏX�j�ł͂Ȃ��Ƃ킩�����B�������ɏX�j�ł͂��邯��ǁA�ǂ������͓I�ȕ\������Ă��邵�A�����ƂĂ����ꂢ�ŁA���ɗ��h�ȑ̊i�����Ă���̂ŁA�X�j�ł��邱�Ƃ����Y��Ă��܂��̂��B�O�x�ڂɉ�������Ƃ́A�����N���ނ��X�j���Ƃ͎v��Ȃ������B�i�o.�V�O�j �������A�t�@�j�[�͂����v���Ă��Ȃ��� �������N���t�H�[�h���̂��Ƃ̈́��}���C�A�ƃW�����A�����x���̎^�����ɂ�������炸���ˑR�Ƃ��ďX�j���Ǝv���Ă���i�o.�V�V�j �����Řb��ɂȂ��Ă���̂̓N���t�H�[�h���̗e�p�ɂ��Ăł����A��������x���o�[�g�����Ƃ̐l���������Ă���ƁA���̌��������ς���Ă��邱�Ƃ�������Ă��܂��B���̏ꍇ�ɁA�����Ă��邤���ɐl�Ԑ����������ėe�p���C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�ނ̐a�m�Ƃ��Ă̑ԓx��b�����A���邢�͕\��Ƃ��������ƂŁA�X�j�Ƃ͎v��Ȃ��Ȃ����Ƃ����������̕ω�������Ă��܂��B����͌�ŁA�N���t�H�[�h���ɂ͉��Z�҂̍˔\�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A���ŋ��̉��Z��N�ǂ̍I�݂ȂƂ��낪�o�Ă��܂����A�����Ă݂�A�X�j�ł���ɂ�������炸�A�X�j�łȂ��悤�ɑ������Ƃ��ł���l���ł��邱�ƁB�������A����͕\�ʓI�ȃ��x���ł��邱�Ƃ�������܂��B�����āA�o�[�g�����Ƃ̐l�X�́A������x����Ă��܂��l�X�ł��邱�ƁB����ɑ��āA�t�@�j�[�̓N���t�H�[�h�����ˑR�Ƃ��ďX�j���Ǝv���Ă����Ƃ������ƂŁA�ޏ��̓N���t�H�[�h���̑����i���Z�j���x����Ȃ��Ő��̂����Ă����A�Ƃ������Ƃ��A���̎��_�Ŏ�����Ă��܂��B�����炭�A���̎��_�ł́A���̂��ƂɋC�t���l�͏��Ȃ���������܂���B�������A���̌㕨�ꂪ�i��ŁA�o�[�g�����o�����ނɖ����ɂȂ�A�T�[��g�}�X�܂ł����ނ𗧔h�Ȑa�m�ƕ]�����钆�ŁA�t�@�j�[��l���ނ���̃v���|�[�Y����Ƃ��ċ����B���̕������A�����ɒ����Ă���킯�ł��B�Ƃ������A�����ǎ҂���œǂݕԂ��āA�u�����������̂��v�Ɣ�������悤�ɏ�����Ă��܂��B �b��߂��܂����A�����ɁA���̌Z���̏����̒��ł̓Ɠ��̈ʒu�Â�������Ǝv���܂��B�܂�A�N���t�H�[�h���̌��������ς���Ă����́A�ނ����̂悤�ȐU�镑��������ȂǁA�����Ă�������ł��B���̃N���t�H�[�h���̑����ɂ܂�܂��x���ꂽ�o�[�g�����Ƃ̐l�X�́A�N���t�H�[�h���Ɠ������x���̕\�ʓI�ȂƂ���ł������������Ă��Ȃ��l�����ł���Ƃ������ƂȂ̂ł��B�܂�A�N���t�H�[�h�Z���͌��������ω����Ă���̂ł����A���́A���������ω����Ă���Ƃ������Ƃ͔ނ�����Ă���l�X�̔ނ���ǂ̂悤�Ɍ��邩���ω����ė��Ă���킯�ł��B�܂�A�����̐l�X�̎p���A�N���t�H�[�h�Z�������̂悤�ɉf���o���@�\��S���Ă���Ƃ����܂��B�܂�A���̌Z��͏����̒��Ől�X�̎p���f���o�����̂悤�Ȗ������ʂ����Ă���Ƃ�����̂ł��B �܂��A�ނ�̉�b��ǂ�ł���ƁA�\�ʓI�Ƃ����̂��A�b���Ă�����e�����A�ǂ̂悤�Ȍ��t���g���āA�ǂ̂悤�ɒ��邩�A�Ƃ������Ƃ��d�_��u����Ă��邱�Ƃ�������܂��B���Ƃ��A���̂悤�ȉ�b�́A���t�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ̓��e�͖����e�ɋ߂����̂ł��B �u�o��A�ڂ��̓o�[�g�����o������������C�ɓ���܂�����B�ӂ���Ƃ��ƂĂ���i�ŁA���Ă��Ȃ��삳��ł��ˁv �u���Ȃ��̂��̌��t���Ă��ꂵ����B�ł��A�ǂ��炩�ƌ����ƁA�W�����A����̂ق������D���ł���H�v �u�����A�������I�ڂ��͒f�R�W�����A����̕����D���ł��ˁv �u�ł��A�ق�ƂɁH�����ĕ��ʂ́A�}���C�A����̂ق������l���ƌ����Ă����v �u�܂��A�����ł��傤�ˁB�}���C�A����̂ق����ڕ@�����������Ă��邵�A�\����ƂĂ����͓I���B�ł��ڂ��̓W�����A����̂ق����D���ł��B�������Ƀ}���C�A����̂ق������l�����A�}���C�A����̂ق����f�R���Ă����B�ł��ڂ��̓W�����A����̂ق����D���ł��B�����Ďo��̖��߂ł�����ˁv �u�������Ȃ��Ƃ͌��������Ȃ���A�w�����[�B�ł����Ȃ��́A�Ō�ɂ͂����ƃW�����A����̂ق����D���ɂȂ��v �u�ڂ��͍ŏ�����W�����A����̂ق����D�����ƌ����Ă�ł��傤�H�v �u����ɁA�}���C�A����͂������Ă���̂�B�����Y��Ȃ��łˁA�w�����[�B�������܂����l������̂�v �u�}���C�A����͂����������͓I�Ȃ�ł��B���Ă��Ȃ����������A���Ă��鏗���̂ق��������Ɩ��͓I�ł��B���Ă��鏗���͎����ɖ������Ă��܂�����ˁB�����S�z�̎킪�Ȃ��Ȃ��āA�����̖��͂��v�������U��܂��Ă��A���肩��悯���Ȏא��������S�z������܂���B���������͐�Έ��S�ł��B��Q����������S�z�͂܂���������܂���v ���̉�b�̌��t�ォ��́A�N���t�H�[�h�����o�[�g�����o���̂ǂ��炪�D���Ȃ̂�������܂���B�b�̗����A���������y���̂悤�ɗ�����b�A�������A�o�[�g�����o���ɂ��ĕ\�ʓI�ȊO�`�����b��ɂȂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ��������Ƃ���A���ړI�ȋL�q�͂���܂��A�N���t�H�[�h�����o�[�g�����o���̂ǂ���̏������h�ӂ������Ă��Ȃ����Ƃ�������܂��B����Ӗ��A���g�̗~�]���[�����������̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ă����������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B����́A�b�̓��e�Ƃ������A�b�������Ȃǂŕ������Ă��鏑�������I�[�X�e�B���͂��Ă��܂��B ���̌�̓W�J�ɂ����āA�N���t�H�[�h�Z���́A���̂悤�ɖ����e�ȉ�b�����Ă���悤�ȁA�\�ʓI�ɐ����Ă���A�܂�͐l�ԂƂ��Ă͖����e�̂悤�Ȑl�ł��邽�߂ɁA���̏ꂵ�̂��ř��ߓI�ɁA���g�̂�����ߑ��ɕω������Ă����܂��B���̔ނ�ɑ���l�X�̑������A�����ŕ\���āA�l�X�̎p�����̂悤�ɉf���Ă���̂ł��B�����ł́A�N���t�H�[�h�����o�[�g�����o�����������Ă��邱�Ƃ���A���́A��҃I�[�X�e�B���́A�o�[�g�����o���̐l�ƂȂ�́A���������Ă��������̂Ȃ��悤�Ȍ��Ă��ꂾ���́A�l�i�I�ɂ͂��̑���Ȃ��l���ł��邱�Ƃ��ԐړI�ɓǎ҂Ɏ����Ă���ƌ�����̂ł��B���ہA�����̒��ł́A�}���C�A�ƃW�����A�̔����́A�قƂ�Ǐ�����Ă��炸�A�N���̊ԐړI�Șb���n�̕��ɂ������ōς܂���Ă��܂��Ă���̂ł��B �@��U�� �o�[�g�����Ƃ̎c���ꂽ�l�X�A�N���t�H�[�h�Z���Ƀ��b�V�����[�X����������āA��b�����킵�Ȃ���A���ꂼ��̃L�����N�^�[������ɂ��Ă����܂��B �����ŁA���b�V�����[�X���}���C�A�̍���҂Ƃ��āA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɓo�ꂵ�܂��B�L��ȗ̒n��L���Ȃ����݂Ȑl���ŁA��b�̐Ȃł��b��ɖR�������߁A�b�����Ƃ��݂���ƁA�������b��ɂ���Ƃ�����ʂ�����܂��B���̘b��Ƃ����̂��A�ނ̉��~�ł���T�U�g����R�[�g�Ƃ��̎��ӂɎ������A���ǂ�������Ƃ������Ƃł��B�ނ������ɂ́A�F�l�̃X�~�X�������L����R���v�g����R�[�g�̉��ǂɐ��������Ƃ������ƂŁA�Ƃ��Ƀ��v�g���Ƃ����l���ɗ���Ŏd�グ���뉀���f���炵�������B���b�V�����[�X�́A���̃��v�g���ɂȂ�����T�M�j�[���Ă��ɂ����Ȃ��ƌ����܂��B���̂��Ƃ���A���b�V�����[�X�͒N�ɂł�����ꂽ�炳�����Ə]���Ă��܂��悤�ȁA�������肵�����ȂƂ������̂������Ȃ��A�}�����₷�������҂Ƃ����Ƃ������i��ǂݎ�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������A���b�V�����[�X�́u�����ł͂ǂ����Ă����̂��킩��Ȃ��v�Ɖ��ʂ��Ȃ��q�ׂĂ���̂ŁA�ǂ̂悤�ɉ��ǂ������̂��Ƃ������B�W�����������Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ł��B�펯�ōl����A�̒n������͂��̂悤�ɂ������Ƃ������B�W���������邩��A����ɂ��������āA����ł͕s�s��������������ǂ��悤�Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł��B������ɁA���b�V�����[�X�́A�F�l�����ǂ������ƂɎh���������āA���ǂ��邱�Ƃ��^����ɍl�����Ă���B���������_�ɁA�ނ��̒n���}�l�W�����g�ł��Ă��Ȃ����A���̎��o���Ȃ����Ƃ�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B �����āA���̃T�U�g����R�[�g�̉��ǂɂ��āA�b��L�x�ȃw�����[��N���t�H�[�h����ƌ�����悤�Ȕ������������ƂŁA���b�V�����[�X�����T�U�g���E�R�[�g�̒뉀���ǂɊF�̈ӌ��������ꂽ���Ƃ������ƂɂȂ�A���̂��߂ɂ̓T�U�g����R�[�g�����ۂɌ��Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ��Ă����܂��B���̂��Ƃ���W�͂ŁA�t�@�j�[�ƃm���X�v�l���܂ރo�[�g�����ƂƃN���t�H�[�h�Z�����A�T�U�g����R�[�g�ɏ��҂���邱�ƂɂȂ�킯�ł��B �@��V�� ���̏͂ŁA�������̃|�C���g�ƂȂ�G�s�\�[�h���N����܂��B�܂��A�t�@�j�[�ƃG�h�}���h�̉�b������A�����ŃG�h�}���h�����A���[��N���t�H�[�h�ɑ����ۂ��悢���Ƃ��t�@�j�[�Ɍ��A�t�@�j�[�͌������قɂ�����A����������Č�炸�A��l�̊ԂɔF���̃Y�������܂�n�߂��ʂł��B���̎��_�ł́A�G�h�}���h�̓��A���[��N���t�H�[�h�ɑ��ė������������܂łɂ͎����Ă��܂��A���������͓I�ȃ��A���[�E�N���t�H�[�h�Ɏ䂩���悤�ɂȂ�A���A���[�Ɋւ���b����A�����t�@�j�[�̑O�Ŏ����o���悤�ɂȂ�܂��B���̘b�̓��e�����A�G�h�}���h�̓��A���[���̎^��������ɐi��ł䂫�A�t�@�j�[�̂��Ă䂯�Ȃ����܂ōs���Ă��܂������ɂȂ�܂��B�����ɁA�G�h�}���h�ƃt�@�j�[�̊ԂɁA���A���[�ɑ���ӌ��̕s��v�������n�߂܂��B�����ŁA�t�@�j�[�́A��������ЂƂɂ��Ă����Ɗ����Ă����G�h�}���h�Ƃ̘������ӎ�����悤�ɂȂ�܂��B�����Ő��܂ꂽ�������A�t�@�j�[�̃G�h�}���h�ɑ���C���������o����������ɓ�����Ă������ƂɂȂ�܂��B�������A�G�h�}���h�̃t�@�j�[�ւ̎p���͕ω����Ȃ��i�ω����ė�������Ɉڍs�����̂̓t�@�j�[�����ł��j�A�t�@�j�[�́A���ꂪ�������Ă���䂦�ɁA���o�������g�̋C�������G�h�}���h�ɂ��A�ވȊO�̂���ɂ������邱�ƂȂ��A���g�̓������ɔ�߂āA���������Ă����̂ł��B�����ɁA�t�@�j�[�̃G�h�}���h�ɑ���O�ʓI�ȑԓx�ƁA���ʂ̋C�����̃Y�������܂�A�t�@�j�[�Ƃ����l���̓�ʐ������炩�ɂȂ��Ă��邱�ƂɂƂ��Ȃ��āA���̊������h���}��ł����܂��B �t�@�j�[�́A�G�h�}���h�������ߑO���ɖq�t�قɏo�����Ă��A�ׂɋ����͂��Ȃ������B���҂��Ȃ���������s���ăn�[�v�̉��t����Ȃ�A���������ōs�������Ǝv�������炾�B����ɁA�ӂ̎U�����I����āA���Ƃ̐l�������ʂ��Ƃ��A�N���t�H�[�h�����}���X�t�B�[���h��p�[�N�̏��������̂���������Ă���ԂɁA�G�h�}���h�́A�����O�����g�v�l�ƃ~�X��N���t�H�[�h��q�t�ق֑����Ă䂭�̂����A�t�@�j�[�͂��̂��Ƃ������͂��Ȃ������B�ł��t�@�j�[�́A����͎����ɂƂ��Ă͂��̂��������Ȍ������Ǝv�����B�G�h�}���h�������Ƃ��ɂ��Ă���āA���C���̐����������Ă���Ȃ��̂Ȃ�A���C���ȂLj��݂����Ȃ��Ǝv�����B�G�h�}���h�������Ƃ��ɂ��Ă���āA���C���̐����������Ă���Ȃ��̂Ȃ�A���C���ȂLj��݂����Ȃ��Ǝv�����B�������A�t�@�j�[���������̂͂��̂��Ƃ������B�܂�A�G�h�}���h�͂���Ȃɑ����̎��Ԃ��~�X��N���t�H�[�h�ƈꏏ�ɉ߂����Ă���̂ɁA�������w�E�����ޏ��̗�̌��_�ɁA����Ȍ�͂���C�����Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂��B�t�@�j�[�̓~�X��N���t�H�[�h�Ɠ��Ȃ��邽�тɁA���̂Ƃ��Ɠ����ޏ��̌��_�ɋC�����āA��Ɋւ��邠�̕s�ސT�Ȕ������v���o���̂����A�G�h�}���h�͂���C�����Ȃ��悤�Ȃ̂��B�ނ̓~�X��N���t�H�[�h�̂��Ƃ����т��уt�@�j�[�ɘb�������A��̘b�肪�o�Ȃ��Ȃ��������ŏ\�����ƍl���Ă���悤�������B����Ńt�@�j�[���A�Ӓn���Ǝv��ꂽ���Ȃ��̂ŁA�����̈ӌ��������͍̂����T�����B ���̃G�s�\�[�h�́A���A���[����n���K�������o���������ƂŁA�t�@�j�[����ɂ𖡂키���ƂɂȂ������Ƃł��B���ꂪ�A���̌�A�t�@�j�[���x�X��`���r�߂�悤�Ȏv�����������邱�ƂɂȂ�o���̍ŏ��ƂȂ�G�s�\�[�h�ł��B�G�h�}���h�̓��A���[�̊肢�����Ȃ��Ă����邽�߂ɁA�t�@�j�[�̔n�����X���A���[�̗��K�p�ɑ݂��Ă����邱�Ƃ�\������A�t�@�j�[�́A�����͉����������܂��B���������A���A���[�̗��K���I�������Ńt�@�j�[�����ۂł����n�ɂ��^�������邱�Ƃ��ł��܂����B�������A����ڈȍ~�A���A���[�͏�n�̏�B�����������ɁA�G�h�}���h���t���Y���ċ����Ă����̂��y�����āA����~�߂����Ȃ��Ȃ�A�\��̎��Ԃ߂��ăt�@�j�[��҂�����悤�ɂȂ�܂��B�������傭�A�t�@�j�[�̏�n�̎���͍l������Ȃ��Ȃ�܂��B���̈���ŁA�t�@�j�[�����A���[���n���g���Ă��邽�߁A�����̏�n���ł��Ȃ��āA������܂˂��đ҂��Ă���̂��A�m���X�v�l������߂āA�ɂȂ̂�����ƌ������������邱�ƂɂȂ�܂��B �t�@�j�[�͏�n�̎x�x�����đ҂��Ă����B�m���X�v�l�́A�t�@�j�[���Ȃ��Ȃ��o�������Ȃ��̂ŏ����������͂��߂����A�n���߂����Ƃ����m�点�͂܂����Ȃ����A�G�h�}���h���p�������Ȃ������B�t�@�j�[�̓m���X�v�l������āA�G�h�}���h��T�����߂ɉƂ��o�Ă������B�i�o.�P�O�U�j �q�t�ق̖q���n�ɂ���݂�Ȃ̎p�������Ƀt�@�j�[�̖ڂɓ������B�G�h�}���h�ƃ~�X�E�N���t�H�[�h������Ŕn�𑖂点�A�O�����g���m�ƃN���t�H�[�h���Ɠ�A�O�l�̔n�����A�܂��ɗ����Ă�����������Ă����B�ƂĂ��K�������Ȉ�c���ƃt�@�j�[�͎v�����B�݂�Ȃ���̂��ƂɊS���W�������āA�ق�Ƃ��Ɋy���������B���̏؋��ɁA�ƂĂ��z�C�Ȑ����t�@�j�[�̂Ƃ���܂ŕ������Ă����B�ł�����́A�t�@�j�[�ɂƂ��Ă͂���y�������ł͂Ȃ������B�G�h�}���h�͎��̂��Ƃ�Y��Ă���̂�����A�ƃt�@�j�[�͎v���ċ����ɂB�ł��q���n����ڂ𗣂����Ƃ��ł����A�ڂ̑O�̌��i�������ɂ͂����Ȃ������B�ŏ��A�~�X�E�N���t�H�[�h�ƃG�h�}���h�́A�q�t�قɂ��Ă͍L���q���n����ݑ��ň�������B���ꂩ��A���炩�Ƀ~�X�E�N���t�H�[�h�̒�ĂŁA���ʂ̋삯���ւƑ��x���グ���B���a�ȃt�@�j�[���猩��ƁA�~�X�E�N���t�H�[�h�̏����͂т����肷��قǏ�肾�����B���ꂩ�琔����ɁA��l�̔n�͒�~�����B�G�h�}���h�̓~�X�E�N���t�H�[�h�̂��֍s���ĉ����b�������A��j�̎g�����������邽�߂ɔޏ��̎��������B�����Ă悭�����Ȃ��Ƃ���͑z���͂ŕ�����̂����A�t�@�j�[�̖ڂɂ͂����������B�ł�����Ȃɋ����Ă͂����Ȃ��B�G�h�}���h�͂����̂悤�ɐl�ɐe�ɂ��āA�����O�̂₳���������Ă��邾�����B����قǎ��R�Ȃ��Ƃ����邾�낤���H�ł��A�t�@�j�[�͂����v�킸�ɂ͂����Ȃ������B�G�h�}���h�ɑ����ăN���t�H�[�h���������Ă���������ł͂Ȃ����B�����ɏ�n��������̂͂��Z����̕����ӂ��킵�����A��V�ɂ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƁB�ł��N���t�H�[�h���́A���������̂₳�����������ɂ��A�n�Ԃ̉^�]�����ӂ��ƌ����Ă��邯��ǁA���Ԃ��n�̂��Ƃ͒m��Ȃ��āA�G�h�}���h�قǂ₳�����Ȃ��̂��낤�B���ꂩ��t�@�j�[�́A���̖Ĕn�ɓ�d�̂��߂�������̂͂��킢�������Ǝv���͂��߂��B���̂��Ƃ͖Y����Ă����܂�Ȃ����ǁA�Ĕn�̔�J�̂��Ƃ͖Y��Ȃ��łق����Ǝv�����B�i�o�P�O�U�`�P�O�V�j ����́A���Ƃ��ƁA��S�͂Ńt�@�j�[���m���X�v�l�̂��g���A�܂�A�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N����v�l�̏Z���܂œk���ʼn������邱�Ƃ��A�t�@�j�[�̋���Ȑg�̂ɂƂ��ĉߏd�ȕ��S�ł��邱�Ƃ���A����ɑ���^���Ƃ��ď�n�����邽�߂ɃG�h�}���h�����Ă������n�ł����B���������āA�t�@�j�[�ɂƂ��ẮA�m���X�v�l�̂��g���͐g�̂ɂƂ��Ă̋�ɂŁA��ő̒���������ƂɂȂ���̂Ȃ̂ł��B�i�m���X�v�l�́A���̂��ƂɊւ��ăt�@�j�[�ւ̔z����S�����܂���B�ނ���A����Ȃ��Ƃő̒�������Ȃ�ĂƁA�t�@�j�[��ӂ߂�̂ł��j�t�@�j�[�́A�m���X�v�l�ɒǂ����Ă���悤�ɂ��āA��ނȂ��o�����܂��B���̓r���ŁA�G�h�}���h����������Ń��A���[����n�̗��K�����Ă����i�ɏo��܂��B��҃I�[�X�e�B���́A������t�@�j�[�̖ڂ�ʂ��āA�ޏ������āA���������ƂƂ��ĕ`�ʂ��܂��B��n���K�̐l�X�̊y�������Ȑ����������Ă���ƁA�u���̊y�������Ȑ��̂����߂��́A�t�@�j�[�ɂ͊y�����Ȃ��v�Ƃ����F��������B����́A�������a�O����Ă���Ƃ����t�@�j�[�̈ӎ����f���o�����̂ŁA�u�G�h�}���h�͎����̂��Ƃ�Y��Ă��܂����̂��낤���v�Ƃ����v���ɁA�ޏ��́u�S�̒ɂ݁v����������̂ɂȂ��Ă���̂ł��B�t�@�j�[�́A�u���̌��i�̈ꕔ�n�I����ڂ������Ȃ��v�B�Ƃ�킯�A���A���[���ǂ�ȏ��������Ă��邩�A�G�h�}���h����ǂ������ӂ��ɋ�����Ă��邩���A�ꋓ�ꓮ�A�ڍׂɊώ@���܂��B�G�h�}���h�����A���[�̋߂��ɂ��Ęb�������A��j�̈������������Ă���ƌ����A�ޏ��̎������Ă��鄟�u������t�@�j�[�͌����B���邢�͖ڂ̓͂��Ȃ��Ƃ���́A�z���͂ŕ���Č����v�B�������猩�����߂Ȃ̂ɁA�ٗl�ɍׂ����`����Ă��邱�̕ӂ�̉ӏ��ł́A���������t�@�j�[�̎��͂����債�Ă��邩�̂悤�ł��B�����Ȃ����̂܂ŁA�S�̖ڂŌ�����Ƃ����t�@�j�[�̏́A�G�h�}���h�ƃ��A���[�̊W���e���ɂȂ邱�Ƃւ̕s���������Ă��āA����Ɍ����Ȃ�A�ޏ��������Ɏ����̋ꂵ�݂𖡂���Ă��邩��\�I���Ă���ƌ����܂��B�����ɂ���\���̌֒��́A�t�@�j�[�̐S����Ԃ̕s���肳���\��ꂽ���̂ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B���̈���ŁA�t�@�j�[�̓G�h�}���h�������v���܂��ƁA�����Ɍ�����������悤�ɁA�u����Ȃӂ��Ɂi��l�̏���ɂ���āj��d�Ɏd����������ꂽ�̂ł́A�n�ɂ͐h�����낤�v�Ɣn�ɓ����悤�Ɏ����̎v����]�ł����Ă����āA���ǁA�u�����͖Y���ꂽ�Ƃ��Ă��A���킢�����Ȕn�̂��Ƃ͖Y��Ă�����Ă͍���̂��v�Ƃ����A�����Ɣn��ɕ��ׂāA���߂Ĕn�̂��Ƃ͎v�������Ăق����ƁA�ƃt�@�j�[�̌������ł��B����́A�n�ւ̎v�����̌����āA���̂Ƃ���A���ȗ����ƂЂ��݂̓��荬����������ł��B�����ɁA�t�@�j�[�Ƃ��������́A�ꌩ���ƂȂ����A�i�s�����Ȏp�̉��ɂ�����܂�������}�O�}�̂悤�ɉQ�����āA���܁A���ˌ�����łĂ��ƁA���̂悤�Ȍ`�ɂȂ��Č����̂ł��B ����ɐ����A���A���[�̏�n�̗��K���Â�����肪�ł���܂łȂ�܂��B������A�G�h�}���h�͉���肩��A���ƁA�t�@�j�[���A���Ԃ̋��ɂ���\�t�@�[�ŋx��ł��āA���ɂ̂��߂Ɍ��C�̂Ȃ��l�q�����Ă��邱�ƂɋC�Â��܂��B�G�h�}���h�́A�m���X�v�l��f�B�[�E�o�[�g�����̘b���āA�t�@�j�[�����炭�n�ɏ�邱�Ƃ��ł����A�m���X�v�l�̏���ȗp���ɐU���āA�����������̂Ȃ����������Ă������Ƃ�m��܂��B�G�h�}���h�́A�t�@�j�[�����̂悤�ȏ�Ԃ̂܂ܕ����Ă��������Ƃ������A���ݕ�������ė��āA�ޏ��Ɋ��߂܂��B����ƁA�t�@�j�[�́A�u���݂����Ȃ��ƒf�肽����������ǁA���܂��܂Ȏv�������ݏグ�܂��o�Ă��āA�������������ނق����ȒP�Ȃ̂ŁA���ނ��Ƃɂ����v�̂ł����B �t�@�j�[�̕s���́A�m���X�v�l�ɖ������������Ă��Ƃ�����܂����A�ނ��됸�_�I�ȗv�����傫���̂ł��B�u�ޏ��͂��̐����ԁA��������������Ă���悤�Ɋ����A�s���Ǝ��i�Ɛ���Ă����̂��v�ƌ���͐������܂��B�����ł́A�u�N�́v�Ƃ��u�N�ɑ���v�Ƃ�����̓I�Ȏ�̂͏Ȃ���Ă��܂����A�G�h�}���h�ɖ������ꂽ���Ƃ������āA�ޏ����s���������A�ނƃ��A���[�̊W�Ɏ��i���Ă������Ƃ������Ă���̂́A���炩�ł��B�u���ɂ����A�S�̒ɂ݂̂ق��������Ƒ傫�������B�����āA�G�h�}���h�̐e�ɂ��ˑR�̕ω��ɂ���āA�t�@�j�[�͂ǂ�����Ď������x������悢�̂��킩��Ȃ��Ȃ����v�����ɂ́A�G�h�����h�ւ̎v���ƁA���̍��܂ɂ�鎸�]�ƃ��A���[�ւ̎��i�Őg�̂ɉe����^���̒�������Ă��܂��قǂ̎v���̋����A�t�@�j�[�����ƂȂ������ȊO���̉��ŋ���������߂Ă��邱�Ƃ���������Ă���̂ł��B ���̌���t�@�j�[�́A�G�h�}���h�����A���[�ւ̗��S���点�A�����̈ӎv���ł߂Ă䂭���܂��A�d�����S�ŁA�T����A���邢�͊ԋ߂Ŋώ@�������邱�ƂɂȂ�܂��B���̈���ŁA�ޏ��̓��A���[�̌��_���ׂ����ώ@���A���̖{�������ɂ߂悤�Ƃ��܂��B���A���[�̂ق��́A�T���āA�t�@�j�[�ɕ\���̂Ȃ��D�ӂ������Ă���̂ɑ��āA�t�@�j�[�̂ق��́A�\�ʂ̑ԓx�ƐS�̒��͐����Ȃ̂ł��B ���̓�̃G�s�\�[�h�́A�ʁX�ł����q�����Ă���悤�ɏ�����Ă��܂��B����ɂ���āA�����ł̓t�@�j�[���G�h�}���h�ɗ������������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�̂ł��B�܂�A���̏͂����ɂ��āA�t�@�j�[�̔�߂�ꂽ�v���͌`�ɂȂ��ēǎ҂̑O�Ɍ���Ă��܂����B ���̏ꍇ�̂悤�ȁA�G�s�\�[�h�̂ЂƂЂƂ�[���@�艺���ăX�g�[���[���W��������A�G�s�\�[�h����ׂāA����炪�A�����Ă���悤�Ɍq�����킳��āA�����̍\�����`�Â�����B���ꂪ�A�I�[�X�e�B���̃��j�[�N���ł���ƃi�{�R�t�͂����܂��B�����̃G�s�\�[�h���l���̓����≽�炩�̑f�ނɂ���Č��т����A���̌��т����X�g�[���[��ł����A�Ⴆ�A��S�͂ł̃G�s�\�[�h�ŁA����̎��̃t�@�j�[�̉^���̂��߂ɂƂ��Ă����Ă����|�j�[�̘V�n������ł��܂��A�G�h�}���h�������̎O���̎����n�̂����̈ꓪ���u���ƂȂ����Ĕn�v�ƌ������A�t�@�j�[�Ɏg�킹�邱�Ƃɂ��Ă����܂����B�Ƃ��낪�A���̑�V�͂Ń��A���[����n�̗��K�����邽�߂ɁA�n������G�h�}���h���A�t�@�j�[���炻�̔n����邱�Ƃ�\���o��B���ʓI�Ƀt�@�j�[�͏�n�ɂ��^���̋@���D���āA�m���X�v�l�̍��g�ɒ����ԑς��E�̂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B�G�h�}���h�͂��̂��ƂɌ�ŋC�����Ĝ��R�Ƃ��܂��B�i�{�R�t�͂��̂悤�ȃG�s�\�[�h�̘A���ɂ��āA����͔n�ɊW�������ƂȂ̂Łu�n�̎��v�ƌĂ�ł��܂��B�i�{�R�t�����ڂ���̂́A���̌�ŎႢ�l�X���n�ɏ���ă}���X�t�B�[���h���L�n�ɂł��������ƂŁA��������A�������Z�ȏꏊ�ɉ��o����v��ɔ��W���܂��B���ꂪ�A�T�U�g���E�R�[�g�K��̌v��Ɍ������Ă����܂��B�i�{�R�t�́A�u�n�̎��v����u�E�o�s�̎��v�ւ̈ڍs�ƌĂ�ł��邱�Ƃł��B �d�v�ȏ�ʂł���T�U�g���E�R�[�g�ւ̖K��͂R�͂ɕ����Č���Ă��܂��B�T�U�g����R�[�g�̓o�[�g�����Ƃ̒����}���C�A�ƍ������b�V�����[�X�̗̒n�ŁA�o�[�g�����Ƃ����L��ŁA�����̎����������炵�Ă���Ƃ���ł��B���ꂪ��U�͂ɂ����ă��b�V�����[�X���}���X�t�B�[���h��p�[�N�K�₵���Ƃ��̉�b�����������ƂȂ��āA�o�[�g�����Ƃ̐l�X�ƃN���t�H�[�h�Z�������҂���邱�ƂɂȂ�A���傤�ǃw�����[��N���t�H�[�h����^�n�Ԃ����L���Ă������߁A���̔n�ԂŖK�₷�邱�ƂɂȂ�܂����B�����́A���̖K����o�[�̒��Ƀt�@�j�[�͓����Ă��Ȃ������̂ł����A�o�[�g�����v�l�ƃm���X�v�l�̔����G�h�}���h����������Ƃ����A��S�͂Ńt�@�j�[�̔n�����Ă������Ƃ��Ɠ����悤�ȋc�_���R�l�̊ԂŌ��킳��A�t�@�j�[���G�h�}���h�Ɋ��ӂ���A���ꂾ���ɏI��炸��������߂Ă����Ƃ����A�������Ƃ��J��Ԃ���܂����B�����悤�ȏ�ʂ́A�q�t�ق̃O�����g���m����̐H���ւ̏��҂ɉ����邱�Ƃ�F�߂邱�Ƃ�A�_���X��p�[�e�B�[���J�����ƂȂǁA�J��Ԃ���邱�ƂɂȂ�܂��B�����āA���̌J��Ԃ����ɂ��������āA���A�܂�̓t�@�j�[�ɑ����Q���キ�Ȃ��Ă������ƂɂȂ�܂��B����́A�܂�A�t�@�j�[�̗��ꂪ�A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ����ďd���Ȃ��Ă����A���̒i�K���Ⴂ�Ƃ��Č����Ă���J��Ԃ��ł�����̂ł��B���̎��_�ł́A��Q�͋������̂ŁA�G�h�}���h�̐����͂����ւ�ł����B ���̃T�U�g����R�[�g�̖K��͓�̎O�p�W�����Ă��܂����ƂɂȂ�܂����A���̑O����̂悤�ɁA�s�������̔n�Ԃɂ����āA��ҐȂ̃w�����[��N���t�H�[�h�ׂ̗ɒN�����邩���߂����āA�o�[�g�����o���̐S�Ɋm���������܂��B���̂Ƃ��ȍ~�A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ł̂��ŋ����������T�[��g�}�X�̋A�҂ɂ���Ē��~�������Ă��܂��܂ŁA�o���̊m���́A�����炳�܂ɑ������Ă������ƂɂȂ�܂��B ���̏����̒��̑傫�Ȍ�����̂ЂƂ��A�T�U�g����R�[�g�̒뉀�̎U���A�Ƃ�킯�A�x���`�ɍ������ċx��ł���t�@�j�[�ɑ��āA�o��l��������ւ��o�ꂵ�ċ����Ă����A�܂�Ńx�P�b�g�́u�S�h�[��҂��Ȃ���v�̂悤�ȃt�@�j�[�̂���x���`�Œ�_�ϑ����Ă���悤�ȏ�ʂł��B����́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɐl���������o�������������J��Ԃ��Ƃ��������S�̂̍\���̏k�}�̂悤�ȏ�ʂŁA���ꂾ���Ɋe�l���̂���悤�⑊�֊W���Ïk����Ė��炩�ɂȂ�܂��B�Ƃ�킯�A�G�h�}���h�A�t�@�j�[�Ƀ��A���[��N���t�H�[�h���������O�p�W�ƁA�}���C�A�ƃW�����A�̃o�[�g�����o���ƃw�����[��N���t�H�[�h�̎O�p�W�Ƃ����Ƀ��b�V�����[�X������ł���W���A�����Ŗ��m�Ɏ�����āA����̕���̗�������������Ă������̂ƂȂ��Ă����܂��B��s�͌��������w������́A�뉀���U�n�߂܂��B�X�̒��̂��˂��˂����a������Ă��邤���ɁA��s�͎O�̃O���[�v�ɕ�����Ă䂫�܂��B���̓}���C�A�ƃw�����[�A���b�V�����[�X�A���̓G�h�}���h�ƃ��A���[�A�t�@�j�[�A��O�̓W�����A�ƃm���X�v�l�A���b�V�����[�X�v�l�̎O�ł��B�a��i��ł����ƓS�傪����C�����������Ă��Ă������ɐi�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B���̖�̘e�Ƀx���`������܂����B���̃O���[�v�͐擪������A�G�h�}���h�ƃ��A���[�ɔ�ׂđ̗͂ŗ��t�@�j�[�͕������A���ꂾ���łȂ��A��l�̉�b���͂���ł���̂�����I�ɕ�������邱�ƂɁA�a�O���Ǝ��i�ɂƂ��ꂽ���_�I�Ȕ����������̂ł��傤�B��b������オ���Ă����l�́A��������Ȃ��̂��A��ꂽ�t�@�j�[���x���`�ŋx�e�������܂܁A����ɐX�̒��ւƓ����čs���Ă��܂��܂��B�ЂƂ���c���ꂽ�t�@�j�[���A��l�̋A���҂��Ă���Ƃ���ցA���̃O���[�v������ė��܂��B���̂��������S��̌������ɂ���p�[�N�ɓ���A���~�S�̂����n����u������ƌ����}���C�A�̒�Ăł����A���b�V�����[�X�́A�����Ȃ��ƂɓS��̌���Y��Ă��āA�F���O�ɑ҂����āA�����͉��~�܂ŋ}���Ō������ɋA�邱�ƂɂȂ�܂����B�{���Ȃ�A�̎�ł���F�����҂����z�X�g�ł���͂��Ȃ̂ŁA���̐X�̌a�̂��Ƃ͂悭�m���Ă���͂��ł���A���҂����q���ǂ̂悤�Ɉē����ׂ�����\�ߍl���Ă���̂����R�ł���͂��ł��B�����Ŋ̐S�̌���Y�ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�n��Ƃ��āA�̒n��c��������Ă��Ȃ����A�ނ̋�݂����A�}�炸�����炩�ɂȂ��Ă���Ƃ���ł��B�ނ����̏�����������ƁA�c���ꂽ�w�����[��N���t�H�[�h�ƃ}���C�A���ǂ̂悤�ȉ�b�����킵�A�����Ȃ�s�����Ƃ������A���̈ꕔ�n�I���t�@�j�[�͂����Ɗώ@���Ă��܂����B �u�T�U�[�g��������قNJy�������邱�Ƃ́A�����Ȃ��ł��傤�B���N�̉Ăɂ́A�������ڂ��ɂƂ��āA�悢�ꏊ�ɂȂ��Ă���Ƃ͎v���Ȃ��v�ƁA�w�����[�͓y�n�̉��ǂɂ���߂āA�}���C�A�Ɏv�킹�Ԃ�Ȃ��Ƃ������܂��B��������}���C�A��͂�����Ƃ��܂��B�܂�A���N�̉Ăɂ́A���Ȃ����������Ă��܂��Ă��邩��A�ʔ����Ȃ��A�Ƃ������̈Ӗ����A�}���C�A�ɓ`������킯�ŁA�ޏ����܂݂̂��錾�t��Ԃ��āA�w�����[�̐^�ӂ��m�F����̂ł��B ���̂��Ɠ�l�́A���̂悤�ɁA��g�I�ȕ\����ʂ��āA����ɈӖ��[���ȉ�b�𑱂��܂��B �u���������֗���Ƃ��̃h���C�u�́A�ƂĂ��y�������ł����ˁB����ȂɊy�������Ȃ��Ȃ���q�����āA�������ꂵ��������B���Ȃ��ƃW�����A�͂����Ə��ǂ����ł������́B�v �u�����A�����ł����H�����ł��ˁA�����ł����ˁB�ł��A�Ȃ�ŏ��Ă����̂��o���Ă��Ȃ��ȁB���A�������A�ڂ��̏f���̉Ƃ́A�A�C�������h���܂�̔N�V�����n���̂��ƂŁA���������b�����Ă�����ł��B���Ȃ��̖�����́A���̂���D���ł�����ˁv �u����薅�̂ق����z�C���Ƃ��v���Ȃ̂ˁv �u�킹��̂��ȒP�Ȃ�ł��v�ƃN���t�H�[�h���͓������B�����Ăقق��݂Ȃ���A�u������A�����������̂��ȒP�Ȃ�ł��B���肪���Ȃ��Ȃ�A�\�}�C���̃h���C�u�̂������A�A�C�������h�̔n���b�Ŋy���܂��悤�Ƃ͎v��Ȃ��ł��傤�ˁv �u�ق�Ƃ͎����A�W�����A�Ɠ������炢�z�C���Ǝv����B�ł����͂��낢��l���邱�Ƃ�����܂�����v �u��������ł��傤�ˁB����ɁA�z�C������͖̂��_�o���������ꍇ������܂�����ˁB�ł����Ȃ��̏����͏��������Ȃ���A���Ȃ����z�C���������Ȃ�Ă��Ƃ͂��蓾�Ȃ��ł��傤�B���Ȃ��̑O�ɂ͐���₩�Ȍ��i���҂��Ă����ł�����v �u����͌��t�ǂ���̈Ӗ��ł����H����Ƃ���g�I�ȈӖ��ł����H���t�ǂ���̈Ӗ��ł���ˁB�����ˁA�������ɁA�������Ɏ��̑O�ɂ͑��z������ƋP���A�Ђ�т�Ƃ����p�[�N���ƂĂ��C�����悳��������A�ł��c�O�Ȃ��ƂɁA���̓S��̖�ƉB��_���A���ɑ����Ƌ��̓��������������B���̃��N�h���������悤�ɁA�u���͂�������o���Ȃ���v�v �}���C�A�́A�v�����ꂽ���Ղ�ɂ��������ƁA�S��̖�̂ق��֕����Ă������B�N���t�H�[�h�������ƂɂÂ����B �u���b�V�����[�X����́A��������Ă���̂ɂ����ԂԂ�������̂ˁI�v�ƃ}���C�A�͌������B �u���Ȃ��͂��̌����Ȃ���A�����āA���b�V�����[�X���̋��ƕی삪�Ȃ���A��ɂ�������o���Ȃ��Ƃ����킯�ł��ˁB�ł��A�ڂ���������Ǝ��݂��Ă�����A��̒[����ȒP�ɏo���܂���B���Ȃ����ق�Ƃ��Ɏ��R�ɂȂ肽���Ǝv���Ă���Ȃ�ˁB�����āA����͋ւ���ꂽ���Ƃł͂Ȃ��Ǝv����Ȃ�ˁv �u�ւ���ꂽ���ƁH���������I������͂�������o���邵�A��ɏo�Ă݂����B���b�V�����[�X����͂����ɖ߂��Ă���ł��傤����B�����������������Ƃ͂Ȃ���v �u���Ƃ��������Ă��A�~�X��v���C�X�ɂ��ƂÂĂ����Ă����Α��v�ł���B�ڂ������͂��̏����ȋu�ɂ�����āB�u�̏�́A�I�[�N�̖ؗ����̂����肢����āv �t�@�j�[�́A����͂����Ȃ����Ƃ��Ǝv���A��߂����悤�Ǝv���đ傫�Ȑ��Ō������B �u�}���C�A����A����Ȃ��Ƃ����������������B�E�ѕԂ��ʼn���������B���������������Ĕj����B�B��_�̍a�ɗ�����댯�������B����Ȃ��Ƃ͂�߂��ق���������v�i�o.�P�T�Q�`�P�T�S�j ���̕����͂قƂ�lj�b�����ڏ�����Ă��܂��B�Ō�̈ꕶ�ŁA�t�@�j�[����b�����ׂĕ����Ă������Ƃ��킩��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�����Ńt�@�j�[�̓x���`�ɍ����Ă����̂ł����A�ǂݎ�̎��삩��Ӑ}�I�ɊO����Ă���悤�ɂ�����Ă��܂��B�����炭�A�w�����[��N���t�H�[�h�ƃ}���C�A�̎��삩����O��Ă������̂ƍl�����܂��B�}���C�A�́A�������Ă̒��̒��̂悤�ɕs���R�Ȑg���Ƃ���������ʂ��āA�����ɂƂ��ă��b�V���[�X�Ƃ̌������u�����Ƌ�Ɂv�ɂ����Ȃ����Ƃ߂����܂��B����ɑ��ăw�����[�́A�����Łu���v�ɏے������v�̌��Ђƕی삪�Ȃ��Ƃ��A�}���C�A���g���]�ނȂ�A�����̏�������Ė�̘e��ʂ�������֍s����Ƃ����悤�ȁA���Ȃ�I���Ȍ����ŗU�f���Ă��܂��B����ƁA��_�ɂȂ����}���C�A�́A�u�����͋ւ����Ă��Ȃ��v�ƌ��������A���b�V���[�X��҂����Ƀw�����[�Ɠ�l�ŁA��̒[��ʂ��čs�����Ƃ���̂ł��B���̏o�����́A��Ɍ��������ɍs���l�܂����}���C�A���A�w�����[�Ƌ삯�������邱�Ƃ�\�����Ă���ƌ�����ł��傤�B �u����͂��ׂĂ悭�Ȃ����Ƃ��Ǝv�����t�@�j�[�́A���̍s�����~�߂����悤�Ɠw�߂�����Ȃ������v�Ƃ��邱�Ƃ�����A�t�@�j�[���A��l�̊댯�ȕ��͋C�⌾�t�̉��Ɋ܂܂ꂽ�Ӗ����A���ׂēǂݎ���Ă������Ƃ��킩��܂��B�t�@�j�[�́A�����ɉ������̓�����k������Ă��܂��B ��l�����������ƁA�x����Ƃ����W�����A������ė��āA�������ɓ�l�̌��ǂ��Ă䂭���܂��A�t�@�j�[�͊ώ@���Ă��܂��B���ɁA��������ė������b�V���[�X������A�������ЂƂ���c���ꂱ�Ƃ�m���āA���J���Ǝ��i��I��ɂ��܂��B���̉ӏ��́A���b�V���[�X�ƃt�@�j�[�̉�b�ł��B ���炭�̒��ق̂��ƁA�u�ڂ���҂��Ă��Ă���Ă悩�����̂Ɂv�ƃ��b�V�����[�X�����������B �u�}���C�A����́A���Ȃ������Ƃ��痈�Ă����Ǝv���Ă��܂���v�ƃt�@�j�[�͌������B �u�ޏ����҂��Ă��Ă��ꂽ��A�ڂ����ǂ�������K�v�͂Ȃ��v �������ɂ��̂Ƃ���Ȃ̂ŁA�t�@�j�[�͉��������Ȃ������B�܂����炭�̒��ق̂��ƁA���b�V�����[�X���͂Â����B�u�˂��A�~�X��v���C�X�A�݂�Ȃ̓N���t�H�[�h�����������_�߂邯�ǁA���Ȃ����ނ����Ă����Ǝv���܂����H�ڂ��͂����͎v��Ȃ��Ȃ����ǁv �u�����A�N���t�H�[�h�����j�q���Ƃ͎v���܂���v �u���j�q�H����Ȕw�̒Ⴂ�j����j�q���Ȃ�āA�N���v���܂����B�T�t�B�[�g�W�C���`���Ȃ���������Ȃ��B�ނ͏X�j�ł���B�ڂ��̈ӌ��ł́A���̃N���t�H�[�h�Z���͉��̖��ɂ������Ȃ��B���̂ӂ��肪���Ȃ��Ă��A�ڂ������͏\���ʗ��h�ɂ���Ă�����v �t�@�j�[�͏����Ȃ��ߑ������炵�A�ǂ������Ă����������Ă��܂����B�i�o.�P�T�V�`�P�T�W�j �t�@�j�[�̓��b�V���[�X���Ȃ��߂Ȃ�����A�ނ̌������������Ƃ����Ɣ[�����܂��B�u�N���t�H�[�h�Z���ȂA�����Ȃ��Ă��悩�����B���Ȃ��Ă��A��X�͊y��������Ă����̂�����v�Ƃ������b�V���[�X�̌��t���āA�u�t�@�j�[�͂������ȗ��������炵���B�ǂ����_���Ă悢���킩��Ȃ������̂��v�ƍ�҂͏����܂��B���̍Ō�̈ꕶ�́u�����v�Ƃ͉����B���A���[��N���t�H�[�h�Ȃ���Ȃ���A�G�h�}���h�̐S���D���邱�Ƃ��Ȃ��A�y��������Ă����̂Ʉ��Ƃ�������̑z���ƁA���b�V���[�X�̌��t���d�Ȃ荇�������߁A���_�ł��Ȃ��Ƃ������A�ނ��듯�l�ɒu������ɂ��ꂽ����ɂ���g�Ƃ��āA������������v�킸�R�ꂽ�����������B ���̃x���`�̏�ʂɂ����āA�S��Ōa�̐悪�Ղ��Ă��āA���̐�ɒ��߂̗ǂ��u������Ƃ������ƁA���̓S�̖�͍�̂悤�Ȍ`��A�܂�͒������ɋ[��������̂ł��傤�B���̓S��ɂ͌����������Ă���B������z����ɂ́A�S��Ɉ����|���ĉ����������A�ߕ���j�����肷�郊�X�N������B�����́A�܂�ʼn����̕��䑕�u�̂悤�ɏے��I�ȈӖ����������������Ă��܂��B�������A������x���`�ɍ����Ă��ׂăt�@�j�[�������������ċq�ϓI�Ɋώ@���Ă���Ƃ�������̊ϋq�Ȃ̂ł��B���̊ϋq�ɂ��o��l���ƊW���鋫��������B�����ǎ҂����Ă���Ƃ������^�����Ƃ����\���������ɂ���܂��B���X�N���������ēS����������w�����[��N���t�H�[�h�ƃ}���C�A�́A���̌�̋삯�������A�W�����A�̓C�F�C�c�Ƃ̋삯�������ے��I�ɗ\�����Ă��邵�A�S��������Ȃ��Ŗ߂��Ă����G�h�}���h�ƃ��A���[��N���t�H�[�h�͍Ō�܂ōs�����ɂ���ł̂Ƃ���ň����Ԃ��A�܂�͌����Ɏ���Ȃ��������Î����Ă���ƌ����܂��B ���ɋ������邱�Ƃ́A�T�U�g����R�[�g�̕`�ʂƂ��̈Ӗ��ł��B�����̒��ō�҂̓}���X�t�B�[���h��p�[�N�̌�����̒n�̏�i�`�ʂ������ď����Ȃ��ł���悤�Ȃ̂ɑ��āA���̃T�U�g����R�[�g�̏�i��O����ɕ`�ʂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�}���X�t�B�[���h��p�[�N����P�O�}�C���قǂ̗������o�āC�n�Ԃ̓T�U�g���̗̒n�ɓ���A�X�̒�����ƁA�G���U�x�X���ɏv�H�������h�ȉ��~���n�Ԃ���̎��E�ɓ����Ă��܂��B�t�@�j�[�͂���Ȃӂ��ɂ��̕��i�ɖ����ɂȂ��Ă��܂��B �u���͂��������ӂ邢�����~������ƁA���h�̔O��������ɂ͂����܂���B���͂ǂ��ɂ����ł����H�����~�̌����͓������ł��ˁB��������ƁA���͂����~�̗����ɂ����ł��ˁB���b�V�����[�X����́A�����̐����ɕ�������Ƃ���������Ă��܂�������v�i�o.�P�Q�X�j �����͏��L�҂ւ̌h�ӂ��������Ă闧�h�Ȃ��̂ŁA���x���K�₵���}���C�A�̐����ɂ��C���ɋ���̐듃���D���Ȏp���ւ��Ă���炵���B�~�̗т̓��b�V�����[�X�Ƃ̔ՐȌo�ϊ�Ղ̔��f�̂悤���Ƃ����A���h�ȑ����̎�̈Е����X�Ƃ����Ɖ��~������Ă��܂��B �Ƃ��낪�C�������̗��h���Ƃ͑ΏƓI�ɁC���~�̓����͌h�ӂ��������Ă���̂ł͂Ȃ������悤�ł��B���]���y���߂�v�ɂȂ��Ă��炸�C�s�K�v�ɕ����������������B����ł͑��ł̎x��������ς����C�����̎d���𑝂₷����Ǝv�������̂ł��B���ɂЂǂ����̂͗�q���ł����B��Ƃ̍��̋��菊�Ǝv�����q�����܂������d�X�����������Ă���C�₽��ɍL���ă}�z�K�j�[�̉Ƌ�x�i�������C��q��������u���Ă��邾���������̂ł��B���̉��~�ɂ��Ă̌��́A�t�@�j�[�̎��_�Ō���Ă���Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A�t�@�j�[�͖T��ɂ����G�h�}���h�ɁA����Ȃӂ��Ɏ����̍l���Ă�����q���̃C���[�W�ƌ����̗�q���̎p�Ƃ̃Y������������ł��B �u�����l���Ă�����q���Ƃ���Ⴄ��B���̗�q���ɂ́A�h�i�Ȋ������A���߂����������A�����Ȋ������Ȃ����A���L��A�[�`���Ȃ����A�蕶��R�����Ȃ���B�u�V�̖镗�ɂȂт��v�R�����Ȃ����A�u�X�R�b�g�����h�̉��A�����ɖ���v�Ƃ����蕶���Ȃ���v�i�o.�P�R�R�j ���́A���̗�q���͖{���ɌÂ��i��������̂ł������̂ł����A�����ɂ킽���Ďg�p���ꂸ�A�������邾���̐ݔ��ɕς���Ă��܂������߂ɁA�t�@�j�[���b���Ă���悤�Ȃ��̂Ɍ�����̂ł��B�Ɛl�����Ɏg���Ă����`�������̗�q���ɂ͌����Ă���Ƃ������Ƃł��B��q���͗��h������ǐM�Ƃ������g���Ȃ���̂悤�Ȃ��̂ł��B�����ł́A���̂��ƂɋC�t���Ă���̂̓t�@�j�[�ƃG�h�}���h�̓�l�����ł��B�ނ���A���A���[��N���t�H�[�h�͂��̓`�������ꂵ�������Ƃ��Ď�X�ɔᔻ���Ă݂��܂��B����́A�ޏ����A���̂Ƃ��G�h�}���h�Ɉ���������n�߂Ă���A��������Ƃ��Ĕނ��l����ƁA�ނ��������Ă���q�t�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��A�ޏ��ɂƂ��Ďe�����Ƃł��邱�ƂƊ֘A���Ă̂��Ƃł��傤�B���̂��ƁA��قǐG�ꂽ�X�̒��̎U���ɂ����āA���A���[��N���t�H�[�h�ƃG�h�}���h�̓�l�́A�ނ��q�t�ɂȂ鎖�ɂ��ĔM���c�_���������킷���ƂɂȂ�܂��B �����Řb���܂Ƃ߂�ƁA�T�U�g����R�[�g�̕`�ʂ́A�ԐړI�Ƀ}���X�t�B�[���h��p�[�N�����K�͂��傫�����ȉ��~��뉀�A�L��ȗ̒n���ڂ����`�ʂ��Ă��āA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̕`�ʂ������Ĕ����Ă���悤�Ɍ�����͕̂s�ލ����ł��B�T�T����R�[�g�������t�@�j�[�̋����Ԃ肩��A��r���ă}���X�t�B�[���h��p�[�N�����ɑ���Ȃ����̂ł��邱�Ƃ��A�����Ŏ������Ă���B�����ɁA�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N������Ȃ������Ă���t�@�j�[�̑ԓx�ɂ���\��Ă���A�C���j�[�ƁA�t�@�j�[�ł��炻���Ȃ̂ł�����A����ȊO�̐l�X�̐S�̓}���X�t�B�[�h��p�[�N���痣��Ă��Ă��邱�Ƃ��Úg�I�ɗ\������Ă���B���ꂪ�A��藧�h�ȃT�U�g����R�[�g�ł͎����I�ȓ���ł��郉�b�V�����[�X�v�l�̐S������Ă��Ă��邱�ƂȂǂ�������i��ł���킯�ł��B���ꂪ���̉������̂���q���Ȃ̂ł��B �@��P�P�� �A���e�B�O�A�̃T�[��g�}�X����莆���͂��A�d�����I���āA�悤�₭�A���Ă��邱�Ƃ��m�炳��܂��B�������A�ނ̖��ł���o�[�g�����o���́A��������R�ʼn�����ꂽ���Ԃ̏I���Ǝ~�߂܂��B�Ƃ��ɁA�}���C�A�́A�T�[��g�}�X�̋A��ɂ��A���b�V�����[�X�Ƃ̌������������邱�ƂɂȂ�̂ł��B���̎��_�ł́A�w�����[��N���t�H�[�h�Ƃ̊W�������g���A���Ƃ��Ė��i���悤�Ƃ����̂ł��傤���A���ꂪ�A���̌�̎ŋ��������̐���オ��̂ЂƂ̓��@�ɂȂ��Ă����܂��B �����āA���̏͂̑唼�̓��A���[��N���t�H�[�h�ƃG�h�}���h�Ƀt�@�j�[�̉����������āA�q�t�Ƃ����E�ƂɊւ���c�_�ł��B����́A���A���[���D�ӂ������Ă���G�h�}���h���q�t�ɂȂ鎖�ɑ��ă��A���[�����ł��邩��ł��B�ޏ����q�t�Ƃ����E�Ƃ��������R�́A�o�̃O�����g�v�l���q�t�̍ȂƂ��ċ�J���Ă���̂����Ă��邩��ł��B �u�����A�������A�q�t�ɂȂ�l�͂ƂĂ��^����B��J���Ď���������A���肵���������D�ނƂ����_�ɂ����Ă͂ˁB�����Ĉꐶ�A�H�ׂ邱�ƂƁA���ނ��ƂƁA���邱�ƈȊO�͉������Ȃ��Ƃ����_�ɂ����Ă͂ˁB�ł�����͑ӑĂƂ������Ƃ���A�o�[�g��������B����͑ӑĂȐ����ł���A������ނ��ڂ�Ƃ������Ƃ���B���h�Ȗ�S���Ȃ����A���炵���F�B�悤�Ƃ����Ȃ����A�l���y���܂��悤�Ƃ����w�͂����Ȃ��̂�B���������l���q�t�ɂȂ�̂�B�q�t�͂����s���ł킪�܂܂Ȃ�����B�V����ǂ�ŁA���V�C�����āA������ƌ����܂��Ĉꐶ���I����̂�B����̎d���́A���q�t���S�����Ă���邵�A�{�l�̑厖�Ȏd���́A�����������y����H�ׂ邱�Ƃ�������v�i�o.�P�U�X�j ����ɑ��āA�G�h�����h�ƃt�@�j�[�́A�O�����g���m�̔��F�߂��A�q�t�Ƃ����E�Ƃ��̂��̂͑��h�ɒl����ƐH��������̂ł����A���A���[�̖q�t�����͉��܂�C�z���Ȃ��B ���A���[���A�����܂Ŏ��X�ɖq�t�ւ̌��������̂̓O�����g���m�ւ̌��������ɂƂǂ܂炸�A�G�h�}���h����������Ƃ��čl���鎞�Ƀ����h���̎Ќ��E�ł̋��y�I���������݂��Ă̂ŁA�q�t�ق̑ދ��Ȑ����ɑς����Ȃ��Ƃ����A���ۓI�ȗ��R���������ƍl�����܂��B����́A���A���[�������ɋ��߂���́A�ޏ����}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ɍ��ꂽ�Ƃ�����A�u�L���Ȍ����v���ޏ��̐l���̖ړI�ł��邱�Ƃ��������Ă������Ƃɂ����̂ł��B�ޏ��ɂƂ��āA�����͑��肩��ő�̂��̂����҂��Ȃ���A�������g�͈�ԕs�����ɐU�����Ƃ����삯����������Ȃ̂ł��B���A���ɂƂ��ẮA�G�h�}���h���A�����Ƃ��Ă���q�t�Ƃ�������́A�ٌ�m��R�l�Ɠ������P�Ȃ�E�ƑI����̑I�����̈�ł������肦�Ȃ����A��������Ԗ����l�Ŗ��Ӗ��ȐE�Ƃł����Ȃ��Ƃ����킯�ł��B���̂悤�ȕ������ŁA��ʘ_�Ƃ��Ėq�t�Ƃ����E�Ƃ�ᔻ���Ă��܂��B �u�q�t�ɉ����ł�����Č����́H�j���݂͂�ȗL���ɂȂ肽���Ǝv���Ă��邵�A�ق��̐E�ƂȂ�A�撣��ΗL���ɂȂ�邩������Ȃ�����ǁA�q�t���Ⴞ�߂���B�q�t����A�L���ɂȂ��]�݂͂܂������Ȃ���v�i�o.�P�S�Q�j ���A���[�́A�q�t�ł͎Љ�I�ȃX�e�C�^�X���Ȃ��ƌ����܂��B����ɑ��ăG�h�}���h�́A�q�t�Ƃ����d���� �u�����I�Ȗ��ɂ����Ă��A�i���I�Ȗ��ɂ����Ă��A�l�ԂɂƂ��čł��d�v�Ȗ��ɂ�������d�v�ȔC���ȔC���������Ă���̂ł��B�܂�q�t�́A�@���Ɠ��������C���������Ă���̂ł��B�����āA�@���Ɠ����̉e���͂̏��Y�ł��镗���K�������C���������Ă���̂ł��B���̂悤�ȔC���ɂ܂������Ӗ����Ȃ��ȂǂƂ͌����Ȃ��͂��ł��v�i�o.�P�S�Q�j ���A���[�ƃG�h�}���h�̎咣�͕��s���̂܂܂ł��B �u�q�t������ȏd��ȔC����w�����Ă���Ȃ�Ă��������Ƃ��Ȃ����A���ɂ͂܂����������ł��Ȃ���B���Ȃ��̂��������悤�Ȗq�t�̉e���͂�d�v���́A�Ќ��E�ł͂��܂肨�ڂɂ�����Ȃ����A���������A�q�t���Ќ��E�Ɋ���o�����Ƃ͂߂����ɂȂ���ł�����B����ȉe���͂�������͂����Ȃ���B�v�i�o.�P�S�Q�j �����A�ӂ���̎咣�̓ǂ�ł���ƁA����̐��������ꂽ���{��`�Љ�̐l�Ԃɂ́A���A���[�̎咣�͎��ɐ^���������B�ׂ̂Ƃ���ŁA���A���[���u�������܂܂ŕ������Ȃ��ł́A�����������Ƃ������Ƃ��A�K���ɂȂ邽�߂̈�Ԃ������@���Ǝv����v�i�o.�R�Q�P�j�ƒf�����܂��B�G�h�}���h�����Ȃ��͂��������ɂȂ���肩�Ɩ₤�ƁA���A���[�݂͂�Ȃ����ł���A�Ɠ����܂��B�����āA�G�h�}���h���咣����悤�ȁu�ߖ�ƌ���ɓw�߁A�����ɍ���������������v�Ƃ��������Ő����Ȑ�������F�߂��A�u�ł��A�˂��ƍ����Ƃ����]�߂�̂ɁA���̒��ԂŖ�������悤�Ȑl�͌y�̂����B���������h�_����ɓ�����邩������Ȃ��̂ɁA�Ⴂ�g���Ŗ�������悤�Ȑl�͌y�̂����v�i�o.�R�Q�R�j����́A����̎��{��`�Љ�ł͌���S�Ƃ��ē�����O�̂��Ƃł��B����ɑ��āA�G�h�}���h��ނɖ�������t�@�j�[�̎咣�͒����ێ��̂��߂̌��O���咣���Ă���A������Ƌ\�Ԃ̂悤�ɉf��܂��B����́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ƃ����ނ炪�����Ă���ꂻ�̂��̂��A�����̋\�Ԃ̏�ɐ��藧���Ă�����̂ƁA���ォ��͌����邩��ł��B���́u�}���X�t�B�[���h��p�[�N�v�Ƃ��������̓t�@�j�[��v���C�X�ƃG�h�}���h�̃��u�X�g�[���[�Ƃ����ʂƂ͕ʂɁA�o�[�g�����Ƃ̋��_�ł���}���X�t�B�[�h��p�[�N�Ƃ����\�Ԃ̏�Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ̎�����L�q�����������Ƃ����ʂ�ǂނ��Ƃ��ł���̂ł��B�����������_�ł́A�N���t�H�[�h�Z���͌y���ŕs�����Ȑl�X�Ƃ��������A���ԈˑR�̂܂܉������Ă���}���X�t�B�[���h��p�[�N�̋\�Ԃ�˂��āA����đ��鎟�̐���i�����̒��ł͑ޏꂵ�Ă��܂��܂����j��\���Ă���Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���̂ł��B ���̏͂̍Ō�ɁA���̂悤�ȋ\�Ԃ��h���Ȃ�����A�����ɂ���l�����ɂƂ��Ă͊|���ւ��̂Ȃ��Ƃ���ł���A���̂��Ƃ��t�@�j�[�����݂��݂Əq�����Ă��܂��B�������A������ӎ����Ă���̂́A���̒����̈ێ��ɖ�N�ɂȂ��Ă���ƃT�[��g�}�X�ƃt�@�j�[�̓�l�Ȃ̂ł��B �u�����ɂ͒��a�������B���炬�������B�G�≹�y�ł͕\���ł��Ȃ����́A���ɂ����\���ł��Ȃ����̂������B�l�Ԃ̂�����Y�݂�Â߂Ă���āA�l�Ԃ̐S����тŖ������Ă���鉽���������B����������̌i�F�߂Ă���ƁA���̐��Ɉ���߂��݂Ȃǂ���͂����Ȃ��Ǝv���Ă����B�l�X�����R�̐������ɂ����Ėڂ������āA���Y��Ă��������i�F�߂�A���̐��̈���߂��݂͂����Ə��Ȃ��Ȃ�͂���v�i�o.�P�V�S�j �@��P�Q�� �A���e�B�O�A����T�[��g�}�X���}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɋA��̂͂P�P���̗\��ł����A���s���Ă������j�̃g���͈ꑫ�����X���ɖ߂�܂����B ����O���̍ő�̌�����ł���f�l�ŋ��̑����ł��B����ɁA�I�[�X�e�B���͂V�̏͂��₵�Ă��܂��B �܂��A���̑����̂��������猩�Ă����܂��傤�B�A���e�B�O�A����ꑫ�����߂����g���ł����A�����ǂ��T�[��g�}�X�ə�߂��b�������ړI�ŃA���e�B�O�A�ɓ��������킯�ł��B���������āA�g���̑����A��́A���炪�������������Ƃ��C�ɂȂ����T�[��g�}�X���A�}���X�t�B�[���h��p�[�N����邱�Ƃ����҂���Ă̂��Ƃ������͂��ł��B�Ƃ��낪�A�g���̓��]�[�g�n�Œm�荇�����C�F�C�c�Ȃ�l����A��ė��܂��B�C�F�C�c�͋M���̎��j�����A�y���ȕ����҂ŁA�ނ������f�l�ŋ����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���ʓI�ɁA�g���̓}���X�t�B�[���h��p�[�N�̒�������邽�߂ɑ����A�邱�ƂɂȂ����̂ɁA�t�ɑ������������ޒ����C���҂ƂȂ��Ă��܂��킯�ł��B�����ɍ�҃I�[�X�e�B���̔���Ȗڂ�z�����邱�Ƃ��ł��܂����A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�������̓o�[�g�����Ƃ̕��������Ȃ��������I�ȃG�s�\�[�h�ł���i����ɂ��Ă͔���Ŋ쌀�I�ł���̂̓I�[�X�e�B���Ƃ�����Ƃ̐��i�Ȃ̂ł��傤���j�ƌ����܂��B ����ɑ��ẮA�G�h�}���h�ƃt�@�j�[�������܂��B���̗��R�́A���ɁA�T�[�E�g�}�X�A�[���Ȍo�ώ���̂��߂Ɋ댯���������ĉ����̒n�ɕ����Ă��闯�璆�ɗǑ��ɔ�����h��ȐU�镑�������邱�Ƃ͍D�܂����Ȃ����ƁB���ɁA�����̏��������āA�������}���C�A�͍��Ƃ����厖�Ȏ����ɕs�ސT�Ȃ��Ƃ͐T�ނׂ��ł��邱�ƁB�������A������͓̂�l�ȊO�ɂȂ��A�o�[�g�����Ƃ̐l�X�͎��̓o���o���ł��邱�Ƃ������炩�ł��B�ŋ������邱�Ƃ̐���Ɋւ��ẮA���̌�ʼn��ڂ��w���l�����̐����x�Ƃ����s�����ȍ�i�Ɍ��܂�ƁA�t�@�j�[�̓G�h�}���h�̕��ʂɊ��҂��܂��B���P�̏ꍇ�Ƃ��āA���ڂ����₩�Ȃ��̂ɕύX�����邱�Ƃ��܂߂āB�t�@�j�[�ɂƂ��ẮA�G�h�}���h�������Ă��邱�Ƃ��A�����̔����Ă��闧��̋��菊�ł�����܂����B�Ƃ����̂��A�t�@�j�[�̖{�S�ɂ͖���������A���̂Ƃ��뉉�Z�̂悤�Ȑl�O�Ŕh��Ȃ��Ƃ�����̂͐����I�Ɏt���Ȃ��Ƃ������Ƃ��{���ɂ������Ǝv���܂��B�g������悭���������邱�Ƃ𗊂܂�A�m���X�v�l���猙��������ꂢ�����܂�Ȃ��Ȃ����Ƃ�����A���A���[�ɏ������A���̂悤�ɖ������ЂƂ育����̂ł��B �u�݂�Ȃ��炠��ȂɔM�S�ɗ��܂�č��肳��Ă��邱�Ƃ�f��̂́A�ق�Ƃ��ɐ��������Ƃ��낤���H���̖������������邱�Ƃ́A���̌v��ɕK�v�Ȃ��Ƃł���A���������̌v��́A�����ō��ɂ����Ԃ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��l�������A��ɂ��ƌ��߂��v��Ȃ̂��B�����f��̂́A�ق�Ƃ��ɐ��������Ƃ��낤���H����ɗ����Đl�O�ɏo��̂��|�������ł͂Ȃ����낤���H�G�h�}���h�́A�T�[��g�}�X����ɔ�����Ɗm�M���āA���̌v��ɔ����Ă���B�ł������G�h�}���h�̔��f�ɏ]���āA�ق��̂��Ƃ͂��������f��̂́A�{���ɐ��������Ƃ��낤���H�v�i�o.�Q�R�R�j �܂�A�t�@�j�[�͗ϗ��I�ɐ������ԓx���Ƃ葱���Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ł��B����́A��ŗB��̔��Ύ҂Ƃ��ăT�[��g�}�X�ɕ]������A�����̌㔼�ł̓t�@�j�[�̎�l���Ƃ��Ă̑��݊��������Ă���̂ɏ]���āA�ޏ����ϗ��I�ł��邩�̂悤�ɕ`�ʂ���Ă����܂����A���́A�ޏ����g�ɂ������������Ă̂��Ƃł���A�G�h�}���h�����݂������Ƃ����̂��������̂ł��B�������A�G�h�}���h�́A���A���[�̖��͂ɍR���ꂸ������������Ă��܂��܂��B�T�[��g�}�X���s�����Ɏv���͖̂��炩�ł��邵�A�����Ǝ����ѐ��̖����ɁA�t�@�j�[�̓��A���[�̉e�����������܂��B�i��̋L�q�͒��ژb�@�ɂ�锭���ł����A���̋L�q�͒n�̕��ŁA���S�̐��ɂȂ��Ă��܂��j �G�h�}���h���ŋ��ɏo��Ȃ�āI�ŏ����炠��Ȃɔ����Ă����̂ɁI������̂����R�����A�݂�Ȃ̑O�ł���Ȃɔ����Ă����̂ɁI���͔ނ̈ӌ������������A�\����������A�ǂ�ȋC�������S���킩���Ă�����肾�B����Ȃ��Ƃ����蓾�邾�낤���H���̃G�h�}���h�ɁA����Ȗ����������Ƃ��ł���̂��낤���H�ނ͎�����������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�ނ͊Ԉ�������Ƃ����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���H�����I����͂��ׂă~�X��N���t�H�[�h�̂����Ȃ̂��I�t�@�j�[�̓G�h�}���h�̌��t���ɁA�~�X��N���t�H�[�h�̉e�����͂�����Ɗ������A���̂������߂��������A���������܂Ŏ������ꂵ�߂Ă����A�����s���ɑ�������ƕs���́A����̘b���Ă��邠���������Y��Ă������A���܂͂����ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă��܂����B�i�o.�Q�R�X�j �t�@�j�[�̓G�h�}���h�̐S�ς����������Ƃ͂ł����A�������߂����C�����ɂȂ�Ƃ������i�Ɠ��h�ł����ς��ɂȂ�܂��B�������A�G�h�}���h���ŋ��ɎQ�����邱�ƂɂȂ������ƂŌǗ����Ă��܂��܂��B���̂悤�ȗ���ɒǂ����܂ꂽ���Ƃ��u�T�[��g�}�X�̂��Ƃ��l����ƁA��ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ̑f�l�ŋ��ɁA�����Q������킯�ɂ͍s���Ȃ��̂��v�i�o.�Q�S�R�j�Ƃ������Č��ӂ��ł߂邱�ƂɂȂ�܂����B�t�@�j�[�͎Q�������ۂ��邱�Ƃɂ���āA�T�ώ҂ɂȂ�܂����B �܂��A�ŋ��̂��߂̕�������炦�邽�߂Ƀ}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ɏ��������Ƃ����ڂɌ�����j��s�ׂ��s�Ȃ��邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�T�[��g�}�X�Ƃ����}���X�t�B�[���h��p�[�N�̒����ƌ��Ђ��ے����镔�����y���ɂ��A�ӓׂƌ����̏�ւƕς��Ă��܂��̂ł��B����́A�����̕�����O�`�����ďے��I�ɕ\���Ă���ƌ����܂��B���̂��Ƃ́A�܂��A�����Łu��������v�Ƃ������̂Ȃ���ŁA������Ă��Ă���A����́A���b�V�����[�X�̃T�U�g����R�[�g�̉����A����̓t�@�j�[�������o�����ĉ�����������ł�����܂��A�Ƃ̊֘A�������Ă��܂��B ���̌�A��l�̔��ɂ�������炸�f�l�ŋ��̘b�͐i�߂��Ă����܂��B�����ʼn��ڑI�тŎ��́A�N���ǂ̖��������邩�Ƃ������ł��߁A�w�����[�̑�������߂����ăo�[�g�����o���������A���ǁA�������W�����A���C�����Q���Ē��Ԃ��甲����Ƃ������ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B�v����ɁA�ŋ����߂����Đl�X�̃G�S�C�Y�����Փ˂����������̂��A�l�Ԗ͗l�̃h���}�̂悤�ȗl����悵�Ă��āA������A�t�@�j�[���ЂƂ�ϋq�Ƃ��āA�T���璭�߂Ă���Ƃ����ɂȂ�܂��B �����ŁA���ڂł���w���l�����̐����x�ɂ��ĊȒP�ɐ������Ă����܂��傤�B�P�W���I�h�C�c�̌���ƃR�c�F�r���[�̌�����A�C���`�{���h�v�l�ɂ���ĉp��łɖ|�Ă���A�P�V�X�W�N�ɏo�ł��ꂽ���̂ł��B���̔z���͎��̂悤�ɂȂ�܂��B �E�B���f���n�C���j�݁F�C�F�C�c �J�b�Z�����݁F���b�V�����[�X �A���n���g�F�G�h�}���h�E�o�[�g���� �t���f���b�N�F�w�����[�E�N���[�t�H�h �����C�Ǝ�C�_�v�F�g���E�o�[�g���� �A�K�T�F�}���C�A�E�o�[�g���� �A�~���A�F���A���E�N���[�t�H�h �_�v�̍ȁF�O�����g�v�l ���̍�i�ł́A����M���̕��Ɩ������ꂼ��A�{���̑���ƘA��Y�����ƂɂȂ�܂��B�E�B���f���n�C���j�݂͏����̃A�K�T�ƊW�������A�j�q�t���f���b�N���������܂����B�����C�j�݂͉Ƃ̎���̂䂦�ɃA�K�T���̂āA�M���̖��ƌ������Ȃ���Ȃ�܂���B�A�K�T�͐��������t���f���b�N���Ɏ���A�n���̂����ɓ|��Ă��܂��܂��A�ĉ�����q�ɋ~���܂��B���ŁA�A�K�T�͑��q�ɕ��e���E�B���f���n�C���j�݂ł��邱�Ƃ������܂��B�j�݂͑��q�ɖʉ�A�ނ�������邱�Ƃɂ��܂��B �����āA�q�t�A���n���g�Ɋւ��؏������A�����Ō��̐i�W�ɉ�����Ă��܂��B�E�B���f���n�C���j�݂ɂ̓A�~���A�Ƃ����������܂����A�ޏ��͖q�t�A���n���g�ƈ����������Ȃ̂ł��B�A���n���g�ƃA�~���A�͒j�݂�������A�A�K�T���ȂƂ��Č}���邱�Ƃɓ��ӂ����܂��B�j�݂͉Ƃ̂��߂ɖ����J�b�Z�����݂ƌ��������悤�Ƃ��܂����C�A�~���A�͋��݂܂��B�ޏ��̓A���n���g�ւ̈������ł��邱�Ƃɍ����A�q�t�Ƃ̌����ɏ��������܂��B�������������e�̉ƒ대�ł��B ���̎ŋ��́A�A�K�T�ƒj�݂̌����A�A�����A�ƃA���n���g�̌����Ƃ����n�b�s�[�E�G���f�B���O�ŏI���܂����A�s�`���ʂƂ����s�����ȃe�[�}���܂܂�Ă��܂��B�j�݂������̃A�K�T��U�f�����������Ɏ̂ĂĂ��܂��A���܂ꂽ�s�`�̎q�t���f���b�N���A�����ĕ��ɍĉ��Ƃ����b��A�j�݂̖��A�~�[���A���A�q�t�A���n���g�Ɉ�����������Ƃ����b�ȂǁA�w�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�x�̕���S�̂ƁA���e�̂����Ŕ����Ɍĉ��������v�f���܂�ł���Ƃ����܂��B ���̂����A�w�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�x�̕���̐l�ԊW�Ǝŋ��̔z���Ƃ������ɏd�Ȃ荇���܂��B���̔z�����l�ԊW�����悤�ɉe�����y�ڂ��Ă������ƂɂȂ�̂ł��B�A�K�T��������}���C�A�̓��b�V�����[�X�ƍ��Ă���ɂ�������炸�A�w�����[��N���t�H�[�h�Ɏv�����Ă���A�ނ̉�����t���f���b�N�Ƃ͕�Ǝq�Ƃ��Đe���ɐS��ʂ킹��W�������邱�ƂɂȂ�܂��B���̔z�������܂������ƂŁA�T�U�g����R�[�g�K��Ŗ��炩�ɂȂ����w�����[��N���t�H�[�h���߂���o�[�g�����o���̎O�p�W�Ɍ����������ƂɂȂ�A�W�����A�̎���������I�ɂȂ�܂��B �w�����[��N���t�H�[�h�́A���邢���d�Ȍ��t�Â����Ō��������A�W�����A�Ƃ��ẮA�b�����������e�̂ق����d��Ȗ�肾�����B����ɃW�����A�́A�o�̃}���C�A�ւ̖ڔz����ڌ����A���������J����Ă��邱�Ƃ��͂�����ƌ�����B�ŏ����炻�������v�悾�����̂��B�������������������̂��B�ނ͎��Ȃǂǂ��ł��悭�āA�}���C�A�̂ق����D���Ȃ̂��B�}���C�A�͏����̂قق��݂�K���ɂ��炦�Ă���B�}���C�A�Ɣނ̊Ԃł������藹�����݂Ȃ̂��B�����v���ƃW�����A�͓{�肪���݂����āA�����ɂ͌��������Ȃ��قǂ������B�i�o.�Q�O�U�`�Q�O�V�j ���̈��p�̍ŏ��̕��͂̑O���͋q�ϓI�ȗ���Ɍ���͂��܂����A�㔼�ȍ~�̓W�����A�̖ڂŌ����Ƃ��������Ă��܂��B�����ɂ��I�[�X�e�B���̌��̓������\���Ă��܂��B�w�����[��N���t�H�[�h�ƃ}���C�A���������킹�Ĕz�������߂�悤�ȊW�ɂ������Ƃ������Ƃ��W�����A�����A�s�k���v���m�炳���Ƃ������Ƃł����A�����Œ��ڂ��ׂ��́A�O�p�W�̉�����s�k�҂ł���W�����A�̎����ŏ����Ă��邱�Ƃł��B���̎ŋ��̌m�Â�ʂ��āA�}���C�A�ƃw�����[��N���t�H�[�h�̐e�����������Ă������Ƃ��ǎ҂ɂ͂킩��܂����A���̂��Ƃ͏����̒��Œ��ڂɂ͏�����Ă��Ȃ��̂ł��B����̓W�����A�̎��i�Ǝ��]�̌��i��������A���b�V�����[�X�̎��i�̋�s�A���邢�̓t�@�j�[�̊ώ@�̒��ŊԐړI�Ɍ����̂ł��B �t�@�j�[�������Ƃ���A�}���C�A�����b�V�����[�X��������Ă���͖̂��炩�ł���A�܂��A�}���C�A�ƃN���t�H�[�h�����o�ꂷ�����̌m�Â��K�v�ȏ�ɑ������Ƃ����炩�������B�i�o.�Q�T�P�j ���Ȃ݂ɑ���͕�Ƒ��q�������̍ĉ�����ĕ���������ʂ�����̂������ł��B���̃}���C�A�ƃw�����[�̔z���ɑ��āA���b�V�����[�X��������J�b�Z�����݂͋�݂Ȓj�ŁA���b�V�����[�X�͂���������邱�ƂŌ����̉��l���܂��܂��Ȃ߂邱�ƂɂȂ�A���ۂ̂Ƃ���S�Q�̑䎌�Ɍ˘f�����b�V�����[�X�͋�݂������炯�o���Ă��܂��̂ł��B����͂܂�C�}���C�A���ނ��������Ƃ͂���������̂ɗ��R�����������̂ƂȂ��Ă��܂��܂��B�����āA�q�t�A���n���g�ɐϋɓI�ȏ����̃A�~���A���������̂́A�G�h�}���h�����������Ƃ��郁�A���[�̎p�f���Ă��܂��B�����A���A���[�͉Ɠ����҂ł��钷�j�̃g������������Ƃ��đz�肵�����̂��A���j�̃G�h�}���h�ɈƑւ����A�ނɑ��Ėq�t�Ƃ����E�Ƃ̖����l��������A�����I�����ɓ��������킹�悤�Ƃ����̂��A�����Ɠ������x���܂Ŕނ̉��l�ς��Ȃ߂悤�Ƃ����s���̈�Ƃ����܂��B�܂�C�G�h�}���h�ɂ����E�\���^�����邱�Ƃɂ͊ԈႢ�͂Ȃ��ł��낤���A������͋����҂̃g���̐Ռp���ƂȂ��ă}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̉ƒ��ɂȂ邱�Ƃ����҂ł���̂ŁA���̎��j�V�ł�����قLj����I���ł��Ȃ��Ƃ������f�ł��B�ޏ��́A���̎ŋ��̌m�Â�ʂ��Ė{�C�ŃG�h�}���h���������p�������߂Ă������ƂɂȂ�܂��B ����A�t�@�j�[���A���̎ŋ��ւ̎Q�����g�����͂��߂Ƃ����l�X�ɋ��������܂�邱�ƂɂȂ�܂��B�ޏ��ɋ��߂�ꂽ�͔̂_�v�̍Ȃ̖��ŁA�_�v���̂��̂��e��������A���̍Ȃ͒[���ɂ����܂���B�������A����Ȓ[���ł��t�@�j�[�͊拭�ɋ��ۂ������܂��B�o�[�g�����v�l�̖Âɂ�����o�[�g�����Ƃ̒��ł��j�S�̈���ł͂Ȃ��}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̒����̈ێ��ɖ{���ł������ʒu�ɂ���t�@�j�[���A�T�[��g�}�X���v������A�ł����������̈ێ��ɂ������͔̂���ȊO�̉����ł�����܂���B�������A�{���Ȃ�ē҂̗���Ŏŋ��ɔ����ׂ��m���X�v�l���B��s�߂���Ώۂł���t�@�j�[���Ђǂ��ӂ߁A�F�̂��߂ɔ_�v�̍Ȃ�������悤�ɔ���̂ł��B���Ƃ��A����ȕ��ɂł��B �u����A���͖��������Ȃ�Ă��Ă��܂����v�m���X�v�l�͉s�����q�œ������B�u�ł��A���₢�Ƃ������́A����ȊȒP�ȗ��݂������Ȃ��悤�Ȃ�A�t�@�j�[�͂���������ŁA���m�炸�Ȏq���Ǝv���܂���B�����̐��܂�炿���l���Ă����Ȃ����A�ق�Ƃɉ��m�炸�ł���v�i�o.�Q�Q�T�j �G�h�}���h������Ă���Ă��A�m���X�v�l�͈��������낤�Ƃ��Ȃ��̂ŁA�Ƃ��Ƃ��A�t�@�j�[�͗܂𗬂������ɂȂ��Ă��܂��B�����ŁA�N���[�t�H�h�삪��u�̔��f�ŁA����Ȏv�������Ȃ��s���ɏo�邱�ƂɂȂ�܂��B �~�X��N���t�H�[�h�͖ڂ��ۂ����ăm���X�v�l�����߁A���ꂩ��A�ڂɗ܂��ׂ͂��߂��t�@�j�[������ƁA������Ƃ������q�ŁA�u�����A�g�F�̂��͂��₾��B���ɂ͏��������v�ƌ����Ď����̈֎q���A�e�[�u���̌��������̃t�@�j�[�̂��ֈړ������āA�����ɍ������낵�A�₳���������₫���Ńt�@�j�[�Ɍ������B�u�C�ɂ����Ⴞ�߂�A�~�X��v���C�X�B�����͂���ȔӂˁB�݂�ȋ@���������āA�Ӓn���Ȃ��Ƃ��茾����ˁB�ł��C�ɂ����Ⴞ�߂�v �~�X��N���t�H�[�h�́A�������̃G�h�}���h�Ƃ̂��ƂŁA�������C�������Ă����̂����A�t�@�j�[�ɂ������Ă₳�����S�Â����������A�₦�����t�������Č��C�Â��Ă������B�����āA�e�[�u���̘A��������ȏ�t�@�j�[�ɐ��������Ȃ��悤�ɂƁA�Z�̃w�����[�ɖڔz���������B�i�o.�Q�Q�T�j ���A���[�́A�G�h�}���h�ɋC�ɓ����悤�Ƃ��ăt�@�j�[�ɏ����D���o�����̂�������܂���B�����ł͂Ȃ��C�{���ɏ����ɏՓ������҂̃t�@�j�[�ɑ��Ă������܂�Ȃ��C�����ɂȂ��āA�u�ԓI�ɔޏ����m���X�v�l�̈��ӂ���~���o�����̂�������܂���B���Ƃ������܂��A���A���[�ɂ͂��Ƃ��ƑP�ǂȂƂ��낪�����āA���̏�̙��ߓI�Ɍ����ĂƂ������������̂ł����A�f���̒�ɂ�鈫�e������h���Ќ��E�̌y���ȕ����Ȃǂɂ���āA�G�h�}���h��t�@�j�[�̂悤�ɗϗ��Ƃ��ē��ʉ�����Ȃ������l�ł��邱�Ƃ������Ă���ƌ��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�I�[�X�e�B���́A�l�Ԃ���ʓI�ɂł͂Ȃ��A�����������G�Ŗ��������l�Ԑ�������l���̓����ɋ��݂��Ă��邱�Ƃ�����������Ƃł��B�����ɖ�������������A���[�Ƃ����l�����A����䂦�ɁA�A���`��q���C���ł���Ȃ���A���̏����̒��ł��A�����Ă����ʂ�����A���͂���l���Ƃ��ĕ`����Ă���̂ł��B�G�h�}���h���A���n���g�����������̂́C���̕��G�ȃ��A���[�̐l�Ԑ��ɋ������o��������Ƃ��l�����܂��B�Ƃ���Ȃ�A�G�h�}���h�̓N���[�t�H�h��̔��e������ǂɂ܂�܂��x����ĉ����ւ̎Q�������߂��Ƃ������邵�A�ޏ��̐^�̐l�Ԑ����������Ă��������̂��Ƃ������܂��B�����œ����Ă���̂͒P���ȕ��ȃ��u��X�g�[���[�ɂƂǂ܂炸�A�l�Ԑ��̕��G���͈�`�I�Ɍ���s�\�ł��邱�Ƃ������A�����ɂ���Ă͂��낢��Ɍ����Ă��闧�̓I�Ȑl�ԃh���}�ł��B �t�@�j�[�̐S�͎��i�Ɠ��h�ł����ς��������B�~�X��N���t�H�[�h�͂�������z�C�ȕ\��ɂȂ��āA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ���Ă������A���̂��܂�ɂ��z�C�ȕ\��́A�t�@�j�[�ɂ͕��J�Ɏv�������A�ޏ��ɐe�����ɘb���������Ă��A�t�@�j�[�͐S���₩�ɓ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�i�o.�Q�S�R�j �������A���G�ł��B�t�@�j�[�͎����ւ̐e���A�G�h�}���h�̃��A���[�ɑ���F�������悭�����Ă��܂������ƂɋC�t���A���i��}���邱�Ƃ��ł����A���A���[�̐e��f���Ɋ��ӂł��Ȃ������ɑ��錙�������܂�܂��B���������āA�t�@�j�[�̐S�������ł��낤�͂�������܂���B�܂��A�ŋ��ւ̎Q���������ӂƂ͗����ɁA�ޏ��́A�a�O���Ǝ��i�S�ɋꂵ�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B�\�ʏ�͒��R�Ƃ��āA�����I��D�ʐ����ێ����Ă��Ȃ���A�S�̉��ł͂��̂悤�ȓ����I�D�ʐ��̑㏞�Ƃ��Čo������a�O���ɋꂵ�ނ̂ł��B���͂̐l���F�A�z�C�����ɖZ�������ɑ��k������A�������Ă��Ă��钆�ŁA���������������l�Ȑl�ԂƂ��Ď��c����A���S�Ȓ��ԊO��̏�Ԃɒu����Ă��邱�Ƃւ̉����́A�܂��A���A���[�ɑ��Ă�范�����{��ƂȂ��Č������邱�ƂɂȂ�܂��B�I�[�X�e�B���̓t�@�j�[�Ƃ����ꌩ�A���ƂȂ������ȏ����̓����ɕ��G�Ō���������Q�����āA�ޏ����g�ł����䂵����Ȃ��Ƃ�����A����ƂȂ��`�ʂ��Ă��܂��B���̂�����̋@�����A���ӂ��Ă��Ȃ��Ɠǂ݉߂����Ă��܂��Ƃ���ł��B�������A������Ƃ����āA�ǂ݂Ƃ��Ă��܂��Ă��A���̏������܂�Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ��̂ł��B�������A�����ɋC�t���Ă��܂��ƁA���̏����̖����݂͔{�����܂��B�����ɁA�I�[�X�e�B���̂�����݂�����A�����������Ƃ��ł����܂��ޏ��̖��͂ɍR����Ȃ��Ă��܂��̂ł��B �b�ɖ߂�܂��傤�B�t�@�j�[�́A���̂悤�ɌǗ�����[�߂Ă����܂��B���̌��ʁA�ŋ����߂���l�X�̃G�S���Փ˂������l�ԃh���}���A�t�@�j�[���ЂƂ�ϋq�Ƃ��āA�T���璭�߂邱�ƂɂȂ�̂ł��B�ώ@�ҁA�����Ď��Ƃ��ĕs���̕������Ƃ��āA�t�@�j�[�͐l�X�̂��܂��܂ȏɋC�Â��Ă䂫�܂��B �݂�ȂɂƂ��ăt�@�j�[�͂ƂĂ����������̂��長�����ł���A��߂ɂ���B��̕������Ȃ̂ŁA�قƂ�ǑS������A���ꂼ��̕s����Y�݂�����邱�ƂɂȂ�A���Ƃ�����Ȏ�����m�炳�ꂽ�B�C�F�[�c���̐⋩���̃Z���t�͂Ђǂ�����Ƃ݂�Ȃ��v���Ă���B�C�F�[�c���̓w�����[��N���t�H�[�h�Ɏ��]���Ă���B�g���̃Z���t�͑������ĕ������Ȃ��B�O�����g�v�l�͂��炰����Ďŋ����Ԃ����킵�ɂ��Ă��܂��B�G�h�}���h�͂܂��Z���t����������o���Ă��Ȃ��B���b�V�����[�X����Ɏŋ�������̂͊��ق��Ă��炢�����B���b�V�����[�X���ɂ͂��ׂẴZ���t�̃v�����v�^�[���K�v���B�ȂǂȂǁB�i�o.�Q�T�P�j ���̒��ŁA�t�@�j�[�͉��Z�҂Ƃ��ĎQ�����Ă��܂��A�Â��ɊF���䎌���o�����`����������A���n�[�T���ŕ⏕���߂��肵�āA�v�����v�^�[�߂���ƁA�����Ƃ��Ďŋ��̗��K�ɎQ�����Ă����܂��B�ޏ��́A�ŋ���o���҂����̑S�̑������݁A�ނ�𗝉����A�A�Ŏx����Ƃ�������t�̉��������Ă���̂ł��B�ޏ��̖����́A����߂Č�����������A����ɁA�ޏ��𗊂��ĊF������ė��邱�Ƃ́A�ޏ����A���X�ɁA�l�ڂɂ��Ȃ����A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ŕs���ȑ��݂ɂȂ��Ă��铹����\����������̂ł��B �������Ƀt�@�j�[�́A�ˑR�o���𗊂܂ꂽ�肵�āA���ɋ��S�n�̈����s���ȋC�����𖡂��������ǁA�ق��ɂ����Ԃƒ��ӂ�����邱�Ƃ��������������ł����Ԃ������B�݂�Ȃ̒��Ɍ������āA���������������邱�Ƃ��Ȃ��āA���������������邱�Ƃ��Ȃ��āA���̖��ɂ������Ȃ��Ƃ����݂��߂ȋC������A�ЂƂ�ڂ����̎₵���C�����͖���킸�ɂ��B�����̎��ԂƓ������قNj��߂���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��������A�ŏ��̈Â��\���͂܂������̞X�J�ɏI������B�t�@�j�[�́A�Ƃ��ɂ݂͂�ȂɂƂ��Ĕ��ɗL�p�ȑ��݂��������A���Ԃ�A����̒N�ɂ������Ȃ����炢�C���������������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�i�o.�Q�T�R�j �t�@�j�[�͊ԐړI�Ɏŋ��̗��K�ɎQ�����邱�ƂŌǗ������������Ă����܂����A���̈���Ŋώ@�҂Ƃ��Ă̗�O�Ȗʂ��\���Ă����܂��B���̈�߂ł́A���̈ꕔ������Ă��܂��B ���Ƃ����킯�ŁA�݂�Ȃ��������Ċy����ł���ǂ��납�A�S�����Ȃ����̂˂����������A�݂�Ȃ̕s���̌������������肵�Ă����B�݂�Ȏ����̃Z���t����������ƌ�������A�Z������ƌ�������s�������炵�A�����̂��ׂ����Ƃ���낤�Ƃ��Ȃ����A���������E�̂ǂ��瑤���畑��ɏo�邩�����o���Ă��Ȃ����A����i���Ă���{�l�ȊO�́A�N�������̎w���ɏ]��Ȃ������B �t�@�j�[�́A�������݂�ȂƓ����悤�ɖ��C�ɂ��̎ŋ����y���߂�Ǝv�����B�w�����[�E�N���t�H�[�h�͉��Z���ƂĂ����܂��̂ŁA�t�@�j�[�͕��䂪���ꂽ�����ɂ�����������āA��ꖋ�̌m�Â�����̂��y���݂������B�������A�}���C�A�̂��Ƃ��S�z�ɂȂ�悤�ȏ�ʂ��������B�������A�}���C�A�̂��Ƃ��S�z�ɂȂ�悤�ȏ�ʂ�����������ǁB�}���C�A�����Z����肾�ƁA����A��肷����ƃt�@�j�[�͎v�����B�ŏ��̈�A���̌m�Â̌�́A���Ă���̂̓t�@�j�[�����ɂȂ�A�Ƃ��ɂ͊ϋq�ɂȂ����肵�āA���\�ӂ���̖��ɗ������B�i�o.�Q�T�P�j �t�@�j�[�́A���ꂼ��̐l���̔\�͂�S����ԁA�u���ꂽ�����Ȃǂ��ώ@���܂��B���p�ŁA���̏œ_�l���t�@�j�[�̐S����F�����H���Ă��āA���R�Ԑژb�@�̕��̓I�������\��ƌ����܂��B�����ł́A���b�V�����[�X���A���\���䂦�ɁA�ЂƂ蕂�������݂ɂȂ��Ă��邱�ƁA�}���C�A������҂�����āA�w�����[�E�N�t�H�[�h�Ɠ�l�ő�ꖋ�̌m�Â�����A�s�K�v�ɌJ��Ԃ��Ă��邱�ƂȂǂ��A�t�@�j�[�͌��Ď���Ă��܂��B���̑�ꖋ�Ƃ́A�t���f���b�N���ƃA�K�T���̓�l�������荇����ʂ�����̂ł��B��������Ă��郉�b�V���[�X���A����Ɏ��i�S������A�s�������点�Ă䂭�Ƃ����A�댯�Ȉ��q���܂܂ꂽ�ӏ��ł�����܂��B �������A�t�@�j�[������������ʂ���ɍD��Ō��Ă����Ƃ����������A�����ł͘R�炳��Ă��܂��i�u��ꖋ�̌m�Â�����̂��y���݂������v�j�B�u�t�@�j�[�́A�������݂�ȂƓ����悤�ɖ��C�ɂ��̎ŋ����y���߂�Ǝv�����B�v�Əq�ׂ��Ă��܂����A�Ⴆ�A�ޏ��́A���䕔���ɂ����Ɠ����čs���āA�w�����[�̌����ȉ��Z�����\�����т�}������Ȃ��l�q�ł��B���̊y���݂́A�u�}���C�A�̂��Ƃ��S�z�ɂȂ�悤�ȏ�ʂ�����������ǁv�Ƃ����������ł����A�����ŞB���ɕ\������Ă��邻�́u����v�����A��l�̒j�����߂��ւƓ����댯�ȕ��͋C���w���Ă���킯�ŁA�t�Ɍ����A�t�@�j�[�͂���������Ă��Ȃ��A�������Ă����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������ޏ��́A�u�}���C�A�̉��Z����肷����v���Ƅ��܂�A��l�������荇���V�[�����A����Ȃ鉉�Z�����^�ɔ��������̂��܂�ł������Ƃ����A��������Ă��܂��B�܂�A���̓�����k������������Ċy���܂��ɂ͂����Ȃ��t�@�j�[�̐S���́A���ӂ�����Ƃ����Ă��ے�ł��Ȃ�����ŁA�ƂĂ����C�Ƃ͌����Ȃ����̂ł��B���̂悤�ɁA�t�@�j�[�̓w�����[�ƃ}���C�A�̊ԂɊ댯�ȊW���萶���A����Ă䂭���܂��A��ʂ���Ƃ����Ċώ@���A�s���@�m����̂ł��B�ޏ��͌����āA���ꂩ��ڂ𗣂����Ƃ����A���Ƃ����đj�~���悤�Ƃ������A�l�Ԃ̈����̐���s�����Ђ����猩��葱���܂��B �����ŁA�ЂƂ^�₪�c��܂��B�t�@�j�[�̓��b�V�����[�X�̌m�Â̑���ɂȂ�����A�G�h�}���h�ƃ��A���[�̌m�Âɗ����������ƁA�݂�Ȃ̏����ƂȂ�s�ׂ����Ă����̂ɁA�ǂ����ă}���C�A�ƃw�����[��N���t�H�[�h�̊W���i��ł��܂����Ƃ��ώ@���邾���ŁA������܂˂��Ă����̂ł��傤���B�����ɂ́A��O���ȏ�ɁA�t�@�j�[�Ƃ����l���̈��ӂ������܂��B���ʘ_�ł����A���ƂŃt�@�j�[���w�����[��N���t�H�[�h����̋����������ɂ����ۂł������R�̈�́A�����Ŕނ̐��̂������Ă�������Ƃ�������킯�ł��B����̎��_�ł����A����L���Ɋ��p�������ς��Ƃ�������̂ł��B������������������܂��A�t�@�j�[�́A���̑f�l�ŋ��̑����ɂ����Ă��A���Z�ւ̎Q���ɑ��ċ��ۂ��邱�Ƃňꎞ�I�ɒǂ��l�߂��邱�Ƃɂ͂Ȃ�܂����A����Ӗ��Ŏŋ����\���y���̂̓t�@�j�[�ł���A���ƂɂȂ��ăT�[��g�}�X���A����Ƃ��Ƀt�@�j�[�݂̂��ŋ��̑����ɎQ�����Ȃ������Ƃ��ĕ]������܂��B����͌��ʂƂ��āA�ЂƂ肾�����S�n�тɂ��āA�y���݂����������Ƃ����A���ɗv�̗̂ǂ��U�镑���������ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B�t�@�j�[�͏����̃q���C��������A��������܂��A���̂ЂƂ́A���͂����āA���������ςɗ�����錫��������Ă���ƌ����邩������܂���B�ꉞ�A���̃}���C�A�ƃw�����[��N���t�H�[�h�̊W�ɑ��ẮA�T�U�g����R�[�g�K��̍ۂɁA�X�̃x���`�ɍ����Ă����t�@�j�[�́A�S����z���悤�Ƃ����l���~�߂悤�Ɛ��������A�������ꂽ���Ƃ��e�����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B�܂�A�t�@�j�[�́A��l�ɑ��ĉ����������Ă����ʂȂ��Ƃ�O��̌o���Ō���Ă����Ƃ������Ƃł��B ���̂悤�ȃt�@�j�[�̈ʒu�́A�o�[�g�����Ƃ̐l�������T�U�g����R�[�g��K�₵���Ƃ��ɁA�X�̃x���`�ɍ����āA�ʂ�߂���l�X�̂���悤���A������݂�ϋq�̂悤�ɒ��߂Ă������Ƃ̋K�͂�傫�������J��Ԃ��ƌ����܂��B�t�@�j�[�́A���̏����ł́A�ώ@����l�ł���킯�ł��B ���̎ŋ��́A�ʂ��m�Â̍Œ��ɁA�s�ӂɃT�[��g�}�X���A������Ƃɂ���āA�ˑR���~�ɂȂ�܂��B���̐���s���́A�킴�Ƃ炵���قNJ��m�ɉ��o����Ă���悤�Ȋ����ł��B�����m��Ȃ��T�[��g�}�X�ɁA���b�V�����[�X�Ƃ̐l�X�͌˘f���Ȃ�����A�Ȃ�Ƃ�������U�����Ƃ������Ȃ��Ή������܂��B�T�[��g�}�X�͒����̔��Ɖ䂪�ƂɋA��Ăق��Ƃ������ƂȂǂ���A�l�q�������������ƂɋC�t�����A�Ƒ��Ɗ��k���ƈ����𖡂킢�܂��B���̌�A�ނ͏��ւŗ����������Ƃ��āA�ŋ��̕���ɉ������ꂽ�ς��ʂĂ��p�ɏo��܂��B�T�[��g�}�X�ɂƂ��ẮA�l�I�Ɋ�����ꏊ�ł���A����̈Ќ��̂��܂��ꏊ�ł��铰�X�Ƃ������ւ́A�r��ʂĂ��݂��߂Ȏp�ɕς��ʂĂĂ��܂����B�����ł͉����m��Ȃ��C�F�C�c���C���萺���グ�čŌ�̃��n�[�T���ɗՂ�ł����B�T�[�E�g�}�X�́A���C�Ɏ���āA�ڂ̑O�̕����ŋ��щ��C�F�C�c�����܂��B���̙��߁A�g���������̕ʂ̒[���猻��C�O�҂������Ŕ����킹�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����A�I�[�X�e�B���͌����Ɋ��m�ȕ�����ʂŁA�C�F�C�c���ƃT�[�E�g�}�X�̏o���`���Ă��܂��B �@��Q�O�� �T�[�E�g�}�X�́A�����Ɏŋ��̒��~�𖽂��A�����̑��݂��Y����Ă��������𑁂��Y��邽�߂ɁA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�����̐���ȏ�Ԃɖ߂����Ƃɐ�O���܂��B�ނ͎ŋ��ɊW���邷�ׂĂ̂��̂����~�����|���āA�ڂɌ�������̂�ǂ������Ė������A�����Ďq�������̓��ʂɂ܂ŗ������낤�Ƃ��܂���B �T�[��g�}�X�́A�����̕s�ݒ��ɂ��̂悤�ȃ����o�[�őf�l�ŋ�������ȂǂƂ����̂͌��ꓹ�f���ƍl���Ă����B���܂�ɂ��s�����ŁA���������C�ɂȂ�Ȃ��قǂ������B�i�����j���̕s�����ȋC�����𑁂��ǂ������A�����̑��݂��Y����Ă��������𑁂��Y��邱�Ƃɂ����B���̂��߂ɂ͂܂��A���̂���Ȃ��Ƃ��v���o��������̂����~�����|���A���~�����̐���ȏ�Ԃɖ߂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�T�[��g�}�X�́A�ق��̎q�������ɂ���������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ������B���낢��₢�������āA����ɕs�����Ȏv��������댯��`�������A�q�ǂ������������Ŏ����̉߂��ɋC�t���Ă���邱�Ƃ�������B�i�o.�Q�W�P�j ���́u���낢��₢�������āA����ɕs�����Ȏv��������댯��`�������A�q�������������Ŏ����̉߂��ɋC�t���Ă���邱�Ƃ�������v�Ƃ����̂́A�ނ��q�������̗ǎ���M�����Ă���킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B�ނ́u����ɕs�����Ȏv���v���������Ȃ������B���́u�s�����Ȏv���v�Ƃ́A�ނ��Nj����邱�Ƃɂ���āA�����̈Ќ������Ȃ��邱�Ƃł͂Ȃ������̂��B�ނ́A�������ɓ���Ƃ��ă}���X�t�B�[���h��p�[�N�����̂��`�����ƐS���A�����ŁA�P�ӂɈ��A�ӔC���������A�������Ќ���厖�ɂ��Ă��܂��B�������A�ނ͈����\�ɏo���l�ł͂Ȃ����A�T���߂ȑԓx�ł��邱�Ƃ���A�q�������ɂƂ��āA���e�Ƃ��ė]��ɂ��������݂ňЈ��I�ł����B���̂��߁A�G�h�}���h�ȊO�͎��R�����߁A���������ȉƂ��o�������Ă��āA�}���X�t�B�[���h�ɉƒ�Ƃ��Ă̈��炬�ƈ��S�������Ă��܂���B�����炱���A�ނ�́A���e�̕s�݂���сA���璆�ɑ傢�ɉH��L���āA������𖡂�����̂ł��B�T�[��g�}�X�́A���̐^���������炩�ɂȂ邱�Ƃ��u�s�����Ȏv���v�Ƃ��Ĕ������̂ł��B �����āA�C�F�C�c�ƃw�����[�E�N���t�H�[�h�́A���̒n�����邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��ɁA�w�����[�E�N���t�H�[�h�����邱�Ƃɂ���āA�}���C�A�̊�@�͉������܂����B�w�����[�E�N���t�H�[�h�́A�����̐g�̊댯��`���Ă܂ŁA�}���C�A�̗��S�ɕ����͂Ȃ���O�ȗ��Ȏ�`�҂ł���ƌ����܂��B����A�}���C�A�����Ȏ�`�ł���_�ł͓����ł����A�����ƃi�C�[���ł���A�ނ̂悤�ɐ��Ԋ��ꂵ�Ă��܂���B�}���C�A�́A�ނ��������Ă���邱�Ƃ����҂��Ă����̂ł����A�ޏ��̊�]�͌��ł���A���Ȃ����Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B���́A�w�����[�E�N���t�H�[�h���߂���o�[�g�����o���̎O�p�W�ŁA���A���[�ƃw�����[�̒��ɋC�Â��Ă����̂́A�����҂̂R�l�ȊO�ɂ́A���A���[�ƃt�@�j�[�����ł����B���A���[�̓w�����[�ƌZ���Ŏ������̂ł���̂ŁA�w�����[�̕s��������m���Ă����킯�ł����A�t�@�j�[�̓T�U�g���E�R�[�g��ŋ��̌���ʂ��ė�O�Ȋώ@�����Ă������邵�ƌ����܂��B����䂦�ɁA�t�@�j�[�͎��������W�����A�ɓ���邱�Ƃ��ł��܂����B��҂ł���I�[�X�e�B���́A�W�����A�Ƃ����l���̕`�ʂ́A����قǏd�_��u���Ă͂��Ȃ��̂ł����A�ޏ��̎��������S��ɑ��Ă̓o�����X�������قǒ��J�ɏ����Ă��܂��B���̂悤�ȂƂ���ɁA�I�[�X�e�B���Ƃ�����Ƃ̈Ӓn�̈�������Ȑ��i���\���Ă���Ǝv���܂��B �Ⴆ�A�ŋ��̔z�����߂����Ďo�ɔs��A��������������� �w�����[�E�N���t�H�[�h�́A�������ɃW�����A�̋C���������Ă����B�ł��W�����A�̂ق����A�����������ނ̗��̂���ނ�������A��������߂��������B�����Ă����ɂ́A���̃}���C�A�ɑ��鎹�i�ƐS�z�̋C�������傫���W���Ă����B�����Ă��܁A�w�����[�E�N���t�H�[�h�̓}���C�A�̂ق����D�����Ƃ͂����肵���̂ŁA�W�����A�͎d���Ȃ����̎��������ꂽ���A���Ƃ����o�̗����S�z���邱�Ƃ��Ȃ��������A�����̂��߂ɗ�Âɗ���������ۂƂ��Ƃ����w�͂����Ȃ������B�i�o.�Q�S�S�j ������Ɏŋ��̏������i�Ƃ��ɂ́A �����A���̓W�����A�͋ꂵ��ł����B�ł��W�����A�̉Ƒ��̒N���C�����Ȃ������B�W�����A�̓w�����[�E�N���t�H�[�h�́[�ɗ������A���܂ł������Ă����B���C�ɖ������ӂꂽ�A�M��Ȑ��i�̎Ⴂ�������A�����Ȗ�������Ȗ������킳��āA�Ђǂ��ꂵ�݂𖡂킢�A�s���Ȏd�ł������Ƃ�������Ȕ�Q�҈ӎ��ɋꂵ�߂��Ă����B�W�����A�̐S�͒ɂ݂Ɠ{��ɐk���A����ɓ{����������ĂĎ������Ԃ߂邵���Ȃ������B����Ȃɒ��̗ǂ������o�}���C�A�́A���܂�W�����A�̍ő�̓G�������B�o���̐S�͂������藣��A�W�����A�́A�}���C�A�ƃw�����[�E�N���t�H�[�h�̗��̂���ނꂪ�ߎS�Ȍ������}���邱�Ƃ���킸�ɂ͂����Ȃ������B�����āA�����ɑ��Ă��A���b�V�����[�X���ɂ������Ă��A���̂悤�Ȓp���ׂ��U�镑���������}���C�A�ɁA�V�������邱�Ƃ���킸�ɂ͂����Ȃ������B�i�o.�Q�S�W�j �����āA�����Ɏ����āA�w�����[�E�N���t�H�[�h���������������Ƃ�m�������� �W�����A�́A�w�����[�E�N���t�H�[�h�����Ȃ��Ȃ��Ăق��Ƃ����B�ޏ��ɂ́A�ނ����܂킵�����݂ɂȂ�͂��߂Ă������炾�B����ɁA�����}���C�A���ނ���ɓ���邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂Ȃ�A����ŏ\���������B�}���C�A�ɂ������Ă���ȏ�̕��Q������C�ȂNjN���Ȃ��قǁA�W�����A�̐S�͗�߂Ă����B���ǃ}���C�A�͔ނɎ̂Ă�ꂽ�̂�����A���܂܂ł̂��Ƃ�\�I���Ēp����������悤�Ȃ��Ƃ����悤�Ƃ͎v��Ȃ������B�w�����[�E�N���t�H�[�h�����Ȃ��Ȃ�ƁA�W�����A�̓}���C�A���C�̓łɂ����v���Ă����̂������B�i�o.�Q�X�P�j ���̂悤�Ȉ��p�̕����������݂�A���̌�̎���̗��������̎�l���̂悤�Ȉ��P�̑�����������ɂ���Ď���ɖڊo�߂Ă����q���C���̂悤�ȏ������ł��B�I�[�X�e�B���́A�����ƑO�̃T�U�g���E�R�[�g�K�₩��A������̎��_�ł���ȃW�����A�ւ̎v�����������Ă��܂��B �Ƃ��ɃW�����A�́A�}���C�A�ɂ������鎹�i�S��F�߂Ą��܂�A�N���t�H�[�h���͎������}���C�A�̂ق����D���炵���Ƃ���������F�߂Ą��ނ̋����ȂǐM�p�����A�ނ���x�Ɩ߂�Ȃ��悤�Ɋ肤���Ƃ��K�v���ƋC�����ׂ��������B�i�o.�P�V�U�j �@��Q�P�� �T�[��g�}�X�̋A�҂Ń}���X�t�B�[���h��p�[�N�͗������������߂��܂������A������D�ӓI�Ɏe���̂̓t�@�j�[�����̂悤�ŁA�T�[��g�}�X�ƃt�@�j�[�̋������߂Â��n�߂܂��B����̌㔼�ł́A�t�@�j�[���q���C���Ƃ��Ċώ@�҂��畨��̒��S�ƂȂ��ē����n�߂܂����A�����ł͂��̒���Ƃ��āA�T�[��g�}�X�̃t�@�j�[�ɑ���ԓx�̕ω����\���n�߂܂��B����ɋC�t�����̂̓G�h�}���h�ŁA���̗��R�̓t�@�j�[�����ꂢ�ɂȂ�������Ɛ������܂��B���̃o�[�g�����Ƃ̐l�X�͏�Ƀt�@�j�[�����Ă������߁A�p���ĕ�����Ȃ��������Ƃ��A���N�Ԃ�ɍĊJ�����T�[��g�}�X�́A�t�@�j�[���ȑO�̎�X�����A�ǂ��炩�ƌ����Εn��ȏ����������̂��A��l�O�̎Ⴍ�����������ɐ����������ƂɋC�t�����Ƃ����킯�ł��B���̂��Ƃ́A�t�@�j�[������̃q���C���Ƃ��Ă̎��i���Ƃ������Ƃ��A��҃I�[�X�e�B���������āA���ꂩ��㔼�Ɉڂ낤�Ƃ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�����Ă݂�A�t�@�j�[�̕���́A�������炪�{�Ԃƌ����܂��B �����āA���̏͂ɂ�����傫�ȏo�����̓}���C�A�ƃ��b�V�����[�X�̌����ł��B���̓�l�́A�T�[��g�}�X�̕s�ݒ��ɁA�m���X�v�l���悭�����i�߂č���ƂȂ��Ă������̂ł��B�T�[��g�}�X���A���̍���ɑ��āA�莆�œ��ӂ�^���Ă��܂����B����̃��b�V�����[�X�́A����܂łɉ��x���o�ꂵ�A������Ă��܂����A�G�h�}���h���u���̒j�́A�N���P���Q��|���h�̋������łȂ���A�����̔n�����v�Ƃ����悤�ȋ�݂Ȓj�ł��B��b�ɂ����āA�b����R�����A�̎��n����̎����b�A���������������܂�ׂ����Ƃ����b���蕷�����ꂽ�}���C�A�͂��肵�A�y�̂�������Ɏ���܂��B�ނ̓}���C�A�ɑ��Ă��O���������Ă��Ȃ��A���̌������ɑ��݂��邩������Ȃ����̂�����Ƃ������Ƃ��A�������������ł��Ȃ��l�ł��B�������A���̂悤�ȃ��b�V�����[�X�̖{���I�Ȑ��i��p���́A�}���C�A�������ɐS����w�����[��N���t�H�[�h�������ł���悤�Ɍ����܂��B��l�̈Ⴂ�́A���b�V�����[�X�ɂ́A�w�����[��N���t�H�[�h�̂悤�Ȃ��̏����u�Ŏ��U���@�]�Ǝ��g�����f���悭�����鉉�Z�͂������Ă���Ƃ����_�ł��B�I�[�X�e�B���́A�����悤�Ȑl���𑼂̍�i�ɂ��o�ꂳ���Ă��āA�L�����N�^�[��s�[�X�Ƃ��Ďg�����肪�悩�����̂�������܂���B�Ⴆ�A�w�����ƕΌ��x�̃r���O���[��R�����Y�A�w�����x�̃`���[���Y�E�}�X�O���[���Ƃ������l�X�������Ɏv�������т܂��B �T�[��g�}�X�́A���b�V�����[�X���u���ɔ\�̗͂�����N�ł���A�d���Ɋւ��Ă����{�Ɋւ��Ă��܂��������m�ł���A�����ɂ����Ă���������Ƃ����ӌ��Ƃ������̂������Ă��炸�A�������A�����ł��̂��Ƃɂ܂������C�Â��Ă��Ȃ��v��݂ł���A�}���C�A���ނɓ������ŗ₽���ԓx�ł��邱�Ƃ�m��܂��B�����ŁA�ޏ��̖{�S���m�F���܂��B�������A�w�����[�E�N���t�H�[�h�Ƃ̋Y��̗��̐��A������Ă����}���C�A�́A�ނɎ̂Ă��A�v���C�h���������A���b�V�����[�X�Ƃ̌����ɂ���Ď����Ŏ����ɕ��Q���悤�ƌ��ӂ��Ă����̂ł����B�ޏ��́A���̂悤�Ɍ����̈ӎu�������ς�Ɛ������܂��B �u�������܂̐[�����S�Â����A���e�Ƃ��Ă̂₳�������S�Â����ɂ́A�ق�Ƃ��Ɋ��ӂ������܂��B�ł��A�������܂͊��Ⴂ���Ȃ����Ă��܂��B���͍���������������ȂǂƂ͎v���Ă��܂��A��������Ă���A�l����C�������ς�������Ƃ�����܂���B���́A���b�V�����[�X����̐l����l�����������]�����Ă��܂����A�ނƌ������āA�K���K���ɂȂ��Ǝv���Ă��܂��v�i�o.�R�O�P�j ���̃}���C�A�̐����ɑ���T�[��g�}�X�̔[���̎d���́A��ȋt���ɖ��������̂ł��B �ނ͎����ɂ����������������B���b�V�����[�X���͂܂��Ⴂ�̂�����A�����Ɨ��h�Ȑl�ԂɂȂ�\��������B���h�Ȑl�����Ƃ�����������A�ǂ�ǂ�ǂ��Ȃ�ɈႢ�Ȃ����A���ۂɗǂ��Ȃ邾�낤�B�����ă}���C�A�{�l���A���ɖڂ�ῂ�ł���킯�ł��Ȃ��A���̐���ς��Ȃ�����Ȃɂ͂�����ƁA�ނƌ������čK���ɂȂ��ƒf�����Ă���̂�����A�{�l�̌��t��M���Ă��ׂ����B���Ԃ�}���C�A�́A����قNJ��̉s���q�ł͂Ȃ��̂��낤�B���������A���͂��܂܂ł��A���̎q�����̉s���q���Ǝv�������Ƃ͂Ȃ��B�������A���������݂�����Ƃ����āA���ꂾ���K���̓x�������Ⴍ�Ȃ�킯�ł͂Ȃ��B����Ɏ����̕v������Ȃɂ��炵���l���łȂ��Ă��\��Ȃ��Ƃ����̂Ȃ�A���̑��̓_�ł́A���b�V�����[�X���͎Љ�I�n�ʂƂ����A���Y�Ƃ����A�}���C�A�ɂƂ��ẮA�܂������\�����̂Ȃ���������Ȃ̂��B�i�o.�R�O�Q�j ���̂悤�ɃT�[��g�}�X�́A��ƂɂƂ��đ�ϗL���Ȍ�����ނȂ�ɔ[�����A�j�k�ɂȂ炸�ɂ����Ƃ���S��肷��̂ł��B���Ȃ��ƂɂȂ炸�ɍςƁB����̓T�[�E�g�}�X�̎��ȋ\�Ԃł���A��������}���C�A�̐S�̒��ɓ��ݍ���ŁA�ޏ��̋C������₢�������ׂ��ł�������������܂���B���̈��̖��������������Ƃ߂��Ȃ������̂́A�Ќ��Ƒ̖ʂ�����d�镃�e�̐ӔC�ł���Ƃ����Ă��A�ߌ��ł͂���܂���B�����āA�T�[��g�}�X�́A���̓����߂����t�@�j�[�ɑ��Ă����������ƂɂȂ�܂��B �����ŁA�����E�����܂����A�ȑO�Ɏw�E���������}���X�t�B�[���h��p�[�N���A�����̋\�Ԃ̏�ɐ������Ă���Ƃ������Ƃ��l���Ă݂����Ǝv���܂��B�O�̂Ƃ���ŁA�o�[�g�����Ƃ͑����̎�̖��X�Ƃ��ĈЌ���ۂ������Ă��Ă���͂��ŁA����T�[�E�g�}�X�E�o�[�g�����͏��j�݂ł��B�������C�I�[�X�e�B���̓o�[�g�����Ƃ̉ƌn�ɂ��Ă͑S���G��Ă��܂���B�o�[�g�����Ƃ̉ƌn�������o���Ќ��̕`�ʂ��C�Ӑ}�I�Ɋ�������Ă��܂��B�܂��A�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̒뉀���܂ޑ�@��̗l�q�́A�قƂ�Ǖ`�ʂ���Ă��܂���B����́A�o�[�g�����Ƃ͊O���I�ȈЌ��͂��낤���Ĉێ����Ă��܂����A���͓���͕ʂł���Ƃ������邩��ł��B���̂悤�ȃo�[�g�����Ƃ̖������T�[��g�}�X���̌����Ă��āA���̏ꍇ�̖̑ʂ����U���悤�ȋ\�ԓI�ȍs�������Ă��邱�Ƃ́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̋\�Ԃ̕\��Ƃ݂邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B����䂦�ɁA�I�[�X�e�B���̓o�[�g�����Ƃ̈Ќ���\�킷�`�ʂ�������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����ƍl������Ƃ��낪����܂��B �����ōl�������ԂƂ��āA�o�[�g�����Ƃ̍����͊�@�I�ł���ƍl�����܂��B���̗��R�Ƃ��āA�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̖q�t�C�����́C�O�����g���m�v�ȂƂ����o�[�g�����ƂƂ͉����䂩����Ȃ���Ƃɏ����Ă��܂������Ƃ��w�E�ł��܂��B�{���Ȃ�A�T�[�E�g�}�X�͖q�t�C������q�t�u�]�̎��j�G�h�}���h�̂��߂ɕێ����Ă�������ł����B�ȑO�́A�M�p�̂�����Ǘ��l�Ƃ��ėF�l�ł��������m���X���Ɉς˂��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���j�̃g�[�}�X�����z�̎؋�����������Ƃ�����A�̒n�̊Ǘ��ێ����o�ϓI�ɋꂵ�����̂�����A�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̖q�t�ق̓O�����g���m�v�Ȃɏ����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B�ꑰ�̐l�Ԃ��ێ����ׂ����Y�����l�̊Ǘ��Ɉڂ炴��Ȃ������킯�ŁA�o�[�g�����Ƃ̌o�ϓI������\�I���鎖���ł���ƌ����܂��B ���Ɏw�E�ł���̂́A�o�[�g�����Ƃ��n����傽��������Ƃ���P�W���I�I�Ȓn��w����C���ԂƂ��Ă͖f�Ղ܂菤���ɂ����v�Ɉˑ�������ƉƑw�ɕϖe���Ă���Ƃ������Ƃł��B�o�[�g�����Ƃ̌o�ϓI��Ղ��z�ꐧ�x�Ɉˑ����Ă���v�����e�C�V�����o�c�ɂ���Ƃ������Ƃ́A����̒��ł͂͂�����ƕ`����Ă��܂���B�t�@�j�[�������ɓz�ꐧ�x�ɂ��Ď���������ƃG�h�}���h�ɘb���Ă����ʂɎ�������Ă��邾���ł��B�������A����ł���T�[��g�}�X������Q�N�Ԕ�₵�č����̌��Ē����̂��߂Ɍ��n�ɕ����Ƃ������Ƃ��A�ˑ����Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B�i�|���I���푈���ł�����A�T�[�E�g�}�X���o�ϓI�ɂ��l�I�ɂ���@�I�ȏɂ��邱�Ƃ́A�u����͍��O���ɂ��āA�₦���g�̊댯�ɂ��炳��Ă���̂�����v�Ƃ����G�h�}���h���f�l�ŋ��ɔ������Ƃ��̍����ƂȂ������t�ɂ��\���Ă��܂��B�܂�C�C���O�����h�ɂƂ��ĕs���_�ƂȂ肤��z��f�Ղ��܂ށA������O�p�f�ՂɃo�[�g�����Ƃ̗̓y�Ǘ��͈ˑ����Ă���̂ł��B���̂��Ƃ́A�T�[��g�}�X�̐����ȍs�ׂ��댯�ȕ�����N�����Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B���Ȃ킿�A�ނ̓C���O�����h�ɂ�����n���̉��l��M���Ă��Ȃ���A�������A�܂��z�ꐧ�x���������f�Ղ��瓾������Z��̎��v�ɗ��炴��Ȃ��̂ł��B�T�[�E�g�}�X�́A�^�̃C���O�����h�̒n��K���̉��l�ς�\�ʓI�ɂ͋��łɎx�����Ă���̂ł��B���ꂪ�A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̕\�ʓI�Ɏ��U���Ă��镽���ł���Ќ��Ȃ̂ł��B�����l����ƁC�I�[�X�e�B�����}���X�t�B�[���h�E�p�[�N���̂̕`�ʂɂ͂قƂ�ǎ�����Ă��Ȃ����Ƃ́C���͎����ɍl���o���ꂽ���ʂƍl���Ă�������������܂���B�o�[�g�����Ƃ̑����͗��h�Ȃ��̂ł͂Ȃ��������ꂸ�A�܂����ɗ��h�ȑ����ł͂����Ă��C���̈�Ƃ������������̂��p������ɒl�����Ƃł͂Ȃ����Ƃ��I�[�X�e�B���͈Î����Ă���̂�������܂���B �����l����ƁA�T�[��g�}�X���}���C�A�̌����Ɋւ��āA���b�V�����[�X�Ƃ����l�����ǂ��ł���A�P���Q��|���h�̔N���ƃT�U�g����R�[�g�Ƃ������h�ȉ��~��L���āA�������ۏႳ��A�Љ�I�ȈЌ���ۂ��Ƃ��ł��邱�Ƃ͉������d��Ȃ��ƂƂ��đ��d������Ȃ������Ƃ����킯�ł��B ����́A�}���C�A�������ɂ��}���X�t�B�[���h��p�[�N�𗣂�A�W�����A�������̊��K�ɂ��}���C�A�̐V�����s�ɕt���Y���܂��B�g���͕����Ȃ����炸�A�����h���ɏo��B�����āA�G�h�}���h�͖q�t�ƂȂ邽�߂ɁB���̂悤�Ƀo�[�g�����Ƃ̎q�������͈�x�Ƀ}���X�t�B�[���h��p�[�N�𗣂�Ă��܂��܂��B�c���ꂽ�o�[�g�����Ƃł́A����܂œ��A�҂ł������t�@�j�[�̑��݊������܂��Ă��邱�ƂɂȂ܂��B�������畨��͌㔼�ɓ����Ă䂫�܂��B �@��Q�Q�� �}���C�A�ƃW�����A���o���������ƁA�t�@�j�[�̑��݂��d�v���𑝂��Ă��܂��B�o�[�g�����Ƃ̋q�Ԃł͗B��l�̎Ⴂ�����ƂȂ�A�݂�Ȃ̎����ƁA�v�l�ƁA�z���̑ΏۂƂȂ����̂ł��B�ޏ��̓}���X�t�B�[���h��p�[�N�����łȂ��A�q�t�قɂ����Ă����A���[��N���t�H�[�h�̘b����i���A���[�̓t�@�j�[��F�l�Ǝv�����j�Ƃ��Ă��т��я��҂���悤�ɂȂ�܂��B��҃I�[�X�e�B�����t�@�j�[���A����̃q���C���Ƃ��āA�����ƃX�|�b�g���C�g�Ă悤�ƍl���n�߂��̂ł��傤�B�t�@�j�[�͖q�t�ق̒�����A���[�ƎU�����Ȃ���A���߂Ď����I�Ɏ���̍l�������܂��B �u���̎U�����ɗ��邽�тɁA�X�̐����Ɣ������Ɋ��������B�����͎O�N�O�́A�q���n�̒[�ɉ����đe���Ȑ��_�����邾���ŁA�N���ڂ𗯂߂Ȃ��������A����ȗ��h�Ȃ��̂ɂȂ�Ȃ�Ďv���Ă����Ȃ�������B�i�����j���Ԃ�O�N��ɂ́A�������̂͂ǂ�Ȃ��������Y��Ă��܂��ł��傤�ˁB���̓�����A�l�Ԃ̐S�̕ω����ĕs�v�c�ˁA�ق�Ƃ��ɂ��̂������s�v�c�ˁI�v �u�l�Ԃ����܂�������Ă���\�͂̂Ȃ��ł�����s�v�c�Ȕ\�͂́A�L���͂��Ǝv����B�L���͂̋����ƁA�コ�ƁA�����̑����ɂ́A�l�Ԃ̑��̒m�I�\�͂������{���s���Ȃ��̂������B�l�Ԃ̋L���͂́A�Ƃ��ɂ͂��������������āA���������ɗ����āA�������]�������ǁA�Ƃ��ɂ͂������������āA��������X�����Ƃ������邵�A�Ƃ��ɂ͂��������\�ŁA����s�\�ɂȂ�Ƃ��������B�l�Ԃ͂�����_�ŕs�v�c�Ȑ������̂����ǁA���낢��Ȃ��Ƃ��v���o������Y�ꂽ�肷��\�͂́A�Ƃ��ɕs�v�c�Ȕ\�͂��Ǝv����v�i�o.�R�P�R�`�R�P�S�j ����܂ł́A�G�h�}���h�̖₢�ɓ����āA�l���Ă��邱�Ƃ̈ꕔ��̔������݂Ȃ������Ă����̂ł����A�����ł́A����邱�Ƃւ̓����ł͂Ȃ��A���R�Ɍ��n�߂܂��B�����ɁA�t�@�j�[�Ƃ����l���̉B����Ă������{�Ɛ��_�I�ȌX�����\���ė��܂��B�����炭�A�I�[�X�e�B���̏����̎�l���ŁA���̂悤�ȋ��{�ƍl���[���������Ă����̂́A���ɂ́w�����x�̃A���E�G���I�b�g���炢�ł͂Ȃ��ł��傤���B�ނ���A�I�[�X�e�B���́A�w�����ƕΌ��x�ł́A��l���G���U�x�X�̂������̖����A���[�E�x�l�b�g�̂悤�ȗ�����e�e�����{�ŃJ�o�[���悤�ƕK���ɂȂ��Ă���Ƃ�������ɝ������Ă��܂��B�������A���̃t�@�j�[�̌��t�͘b������̃��A���[�ɂ͑S���ʂ��܂���B�����ɓ�l�̐l���̖{���I�ȈႢ���A�I�[�X�e�B���͍ۗ������Ă��܂��B���̃��A���[��N���t�H�[�h�Ƃ����l���́A�w�����ƕΌ��x�̎�l���ł���G���U�x�X�Ǝ��Ă���Ƃ��낪�����l���ł��B���邭�A�����Ƃ��Ă��āA�ˋC�����ŁA�����̍l�����͂�����Ǝ����Ă��āA�㏸�u���܂�ŎZ�I�ȂƂ��낪����B�������A���A���[�ƃG���U�x�X�̈Ⴂ�́A���̃t�@�j�[�Ƃ̉�b�𑱂����邩�ǂ����A�܂�A�����̌������ɂ�����́A���_�Ƃ����z�I�Ȃ��̂�F�߂��邩�ǂ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���A���[�͓O���O�������I�ŁA�ڂ̑O�ɂ����ŐG��邱�Ƃ̂ł��镨���痣��邱�Ƃ�����܂���B���ꂪ�B�����̑ŎZ�ɑ����邱�Ƃł�������A�l�͂ǂ�������ׂ����Ƃ������Ƃ����A�ǂ̂悤�ɂ��܂�����Ă��������l��������ɓ������B�i�Ⴆ�A���̌�ɁA�G�h�}���h��������Ẳ�b�ŁA���A���[�́A�������������Ƃ��K���ɂȂ邽�߂̈�Ԃ������@���Ǝv���i�o.�R�Q�P�j�Ɩ������Ă��܂��B�j���̕���_���A�����ł̉�b�ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B���������āA���̏����́A���͊ϔO�I�Ȃ��Ƃ���舵���Ă���v�z�����̖ʂ�����̂ł��B���Ƃ��ƁA�I�[�X�e�B���̏����́w�����ƕΌ��x�ł̓v���C�h�Ƃ͉����A�w���ʂƑ����x�ł͕��ʂƊ���ɗ������Ƃ����悤�ɕ���̂Ȃ��ŁA����T�O���e�[�}�̂悤�Ɏ�舵���āA���̂������l�X�̊Ԃł̎���������̓W�J�ɏd�Ȃ��āA�����ǂ������Ă��邤���Ɏ��R�ƍl���Ă��܂��悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂����B�����āA���́w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�Ƃ�����i�ł́A�ȑO�̓���̊T�O�����g���L���āA�l�������邱�ƁA�����������邱�ƂƂ����悤�Ȃ��Ƃ��A���m�ɂł͂���܂��A�ʑt�ቹ�̂悤�ɂ��āA����̒�ɗ���Ă��܂��B���ꂪ�A�����ŁA�}�炸���t�@�j�[�̔�����ʂ��āA���������p���������Ɠǂނ��Ƃ��ł��܂��B�Ȃ��A�t�@�j�[�̂��̂悤�ȓ_�ɑS���C�����Ă��Ȃ��̂��A�w�����[��N���t�H�[�h�ƃm���X�v�l�ł��B ���A���[�ƃt�@�j�[�̈Ⴂ�́A�G�h�}���h�̌Ăѕ��̍D�݂̈Ⴂ�ɂ��͂�����ƕ\���܂��B���A���[�̓o�[�g�������Ƃ����o�[�g�����Ƃ̓���ł��邱�Ƃ������Ăѕ����D�ނ̂ɑ��āA�t�@�j�[�̓G�h�}���h�Ƃ����ތl���w�������D�݂܂��B���A���[�̓G�h�}���h�Ƃ����l�������ł͂��̑���Ȃ��ăT�[�̂悤�ȏ̍����������ƌ����܂��B�v����ɁA�t�@�j�[�̓G�h�}���h�Ƃ����l�����D��ł���̂ɑ��āA���A���[�͒n�ʂ⌨�������u�����Ă��邱�Ƃ��A���O�̍D�݂̈Ⴂ�ɏے��I�ɕ\���Ă���Ƃ����킯�ł��B���̂悤�ȂƂ���ŁA�ӂ���̈Ⴂ�����肰�Ȃ��\�����Ă��܂��I�[�X�e�B���̎�r�́A�ق�Ƃ��ɂ������Ǝv���܂��B ���̌�A�t�@�j�[�͖q�t�ق̃f�B�i�[�̐����ȏ��҂��܂��B���̂��Ƃ́A�t�@�j�[���i���Ƃ��ă}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̊O�̐��E������F�߂�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B���̏��߂Ă̐����ȏ��҂������Ƃ��_�@�ɁA�}���C�A��W�����A�Ɣ�ׂ�Ƃ����₩�ł͂���܂����A�t�@�j�[���Ќ��E�Ƀf�r���[���A������^���ɍl���Ă������Ƃ��n�܂�܂��B���ꂪ�㔼�̕���̓W�J�Ƒ傫���W���Ă���̂ł��B �@��Q�R�� �t�@�j�[���q�t�ق̃f�B�i�[�ɏ��҂��ꂽ���Ƃɂ��Ă̂ЂƖ㒅������܂��B���x�̂��ƂɂȂ�܂����A�t�@�j�[�Ɏ���������ׂ悤�Ƃ��铮��������ƁA�o�[�g�����v�l��m���X�v�l�̔�������A�G�h�}���h�Ƃ̊ԂɃo�g�����N����̂ł����A����̓T�[��g�}�X���t�@�j�[�������鑤�ɗ����܂����B�A���e�B�O�A����̋A�҈ȗ��A�T�[��g�}�X���t�@�j�[��]�����A�D�����������Ă��Ă��邱�Ƃ��A���ۂɍs���ɕ\���Ă��܂��B���̃f�B�i�[�ւ̏��҂́A���l���猩������₩�Ȃ��Ƃ�������܂��A�t�@�j�[�ɂƂ��Ă͑傫�Ȋ�тƂȂ�܂����B �������A�����q�t�قɂ��Ă݂�ƁA�w�����[��N���t�H�[�h���߂��Ă��܂����B�f�B�i�[���̂͊y�������̂ł���܂����B�t�@�j�[�̓}���C�A�Ƃ̂��Ƃ�m���Ă����̂ŁA�ނ��߂��Ă������Ƃ�K���������}�ł��܂���B����A�ނ͉������Ȃ������悤�ɁA���A���[�Ƃ̉�b�Ńo�[�g�����o����b��ɂ��܂��B�������A�Ӗ����肰�ȏ��������ׂāB�����e�Ō��Ă����t�@�j�[�́A�ނɑ��錙�������������܂��B�ނ̓t�@�j�[�ɑ��ẮA�ޏ��������Ă����f�l�ŋ����������ނ悤�Ȕ��������܂��B����ɑ���t�@�j�[�̔����́A����������I�ł��B �u�܂�Ŗ��̂悤���I�y�����������Ă����悤���I�i�����j�ڂ��͂��̑f�l�ŋ��̂��Ƃ��v���o�����тɁA�y�����C���ɂȂ邾�낤�ȁB�Ƃɂ����ʔ����������A���C�����������A�݂�Ȍ��C�����ς��������I�S�������������Ă����B�݂�Ȑ����������Ă����B������イ�d���Ɗ�]�ƁA�S�z�Ɗ��C�ɂ��ӂ�Ă����B�˂ɁA�������ׂ������Ȕ��Ƌ^��ƕs�����������B�Ƃɂ����ڂ��́A����ȂɍK���Ȏv���������̂͐��܂�ď��߂Ă��v �t�@�j�[�͖����̓{��������Ȃ���A�S�̒��łԂ₢���B�u����ȂɍK���Ȏv���������̂͏��߂āH��ɋ�����Ȃ�����ȂɂЂǂ����Ƃ������̂ɁA����ȂɍK���Ȏv���������̂͐��܂�ď��߂āH����Ȕڗ�Ȏc���Ȃ��Ƃ������̂ɁA����ȂɍK���Ȏv���������̂͏��߂āH�����I���̐l�͐S�̒�܂ŕ������l���I�v �u�~�X�E�v���C�X�A�ڂ������͉^������������ł��v�N���t�H�[�h���́A�t�@�j�[�̋C�����ɂ͂܂������C�Â����ɁA�G�h�}���h�ɕ������Ȃ��悤�ɐ����߂ĂÂ����B�u�ڂ������́A�ق�Ƃɉ^�����������B������T�ԁA�ق�̂�����T�Ԃ���A�ŋ��͂����Ƃł����B�i�����j�v �N���t�H�[�h���̓t�@�j�[�̕Ԏ���҂��Ă���悤�������B�t�@�j�[�͊�����ނ��āA������肵�����肵�����Ō������B �u�������A���͔������܂̋A�����A���Ƃ�����ł��x�点�����Ƃ͎v���܂���ł����B�������܂͋A���Ȃ����āA�����ɂ��̑f�l�ŋ��𒆎~�ɂ�������ł�����A����͂��ׂĂ��߂��������Ǝv���܂��v �t�@�j�[�̓N���t�H�[�h���ɂނ����āA��x�ɂ���Ȃɂ�������̂��Ƃ��������̂͏��߂Ă����A�N�ɑ��Ă��A����Ȃɓ{��������ɂ��Č����������̂͏��߂Ă������B�i�o.�R�R�X�`�R�S�O�j ���̌�A���˂Ƀ��A���[��N���t�H�[�h���{�C�ŃG�h�}���h�������A�ނƂ̌������l���Ă��邱�Ƃ���������܂��B�G�h�}���h���q�t�ɂȂ邱�Ƃɂ��āA�w�����[��N���t�H�[�h���e�Łu��\�l�A�܍ʼn��������ɔN�����S�|���h����ɓ���v�i�o.�R�S�Q�j�Ƃ����̂ɑ��āA���A���[�͓��S�ŁA�u�N�����S�|���h�̐��E�\����ɓ����ɂ́A��͂艽�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A����Ȃ�̋�J�����邵�A������y���l����킯�ɂ͂����Ȃ��v�i�o.�R�S�Q�j�Ŏv���܂��B����́A�G�h�}���h�ɑ��āA�q�t�Ƃ����E�Ƃ�ے肵�Ă݂������A���[�ɂ��ẮA�ӊO�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B���A���[�́A�G�h�}���h���q�t�ɂȂ鎖�Ɍ��܂������Ƃɂ��ăV���b�N���܂����A����́A�������ނ̂��Ƃ�^���Ɏv���Ă���̂ɁA�ނ͎����̂��Ƃ�^���ɍl���Ă���Ȃ��B�ނ͎������q�t�̍ȂɂȂ�C�͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�m���Ă���̂ɂ�������炸�A�q�t�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃł��B ���̓~�X��N���t�H�[�h�́A�G�h�}���h�ɂ������Ă͂�����ƍD�ӂ������͂��߁A�{�C�Ō����̂��Ƃ��l���͂��߂Ă����̂��B�ł����ꂩ��͔ނɉ���Ă��A�ނƓ����₽���C�����ڂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ނ͎��̂��Ƃ�^���ɍl���Ă��Ȃ����A����{�C�ň����ĂȂǂ��Ȃ��̂��B�����q�t�̍ȂɂȂ�C�͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�ނ͒m���Ă���̂ɁA�q�t�ɂȂ�Ƃ����̂�����A����{�C�ň����Ă��Ȃ��͖̂��炩���A���ꂩ��́A�ނ̖��S���ɕ����Ȃ����炢�ɁA�����ނɑ��Ė��S�ɂȂ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ꂩ��́A�ނ���ǂ�ȂɍD�ӂ�������Ă��A���̏�̊y���݈ȏ�̂��Ƃ��l���Ă͂����Ȃ��B�����A�ނ��A�����̈��������Ȃӂ��ɗ}���邱�Ƃ��ł���̂Ȃ�A�����A�����̈���������ŏ�����悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B�i�o.�R�S�S�j ����������ǂނƁA�����͑ŎZ�I�Ȍ_��ł���ƌ�������v�Z�������A���[�Ƃ����l�����Ƃ͐����̈�����r�ɋ��߁A�����������₷���S�������������Ƃ����t�@�j�[�ɋ߂��l�����Ɍ����Ă��܂��B���̂��Ƃ�O���ɂ����Ȃ���A���̌�̃��A���[�̍s���́A�t�@�j�[�ɂ͌�������܂����A�B���ꂽ�Ӗ������������Ă���ƍl�����܂��B�܂�A���A���[�ɂ͓�̖ʂ������āA�ޏ����g�����̕�������邱�Ƃ��o�����ɁA���l����͋C����Ƃ��A���̏ꂵ�̂��ɂ݂���s�����A���͕����ǂ��炩�̖ʂ��\�ʂɏo���䂦�ƁA���̎��̉B�ꂽ�ʂ̖ʂɂ��ޏ��̖{�S�͂���ƍl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤���B�Ō�߂��ŁA�G�h�}���h�����A���[�ƌ��ʂ���ۂɁA�ޏ��̏Ί�����낵���ƌ`�e���܂����A�����l����ƁA���̎��̔ޏ��̏Ί�͕ʂ̈Ӗ����������Ƃ������Ƃ��l�����邱�ƂɂȂ�܂��B������������A�I�[�X�e�B���������̂Ȃ��ő��`�����l���̂Ȃ��ŁA�����Ƃ����G�Ȑl����������Ȃ��Ƃ������܂��B����́A�ЂƂ̉����ł��B�I�[�X�e�B�����A�ǂ��܂ňӎ����ă��A���[�Ƃ����l���`���Ă��邩�͋^��ł��B����́A���̈��p�������͂̈�߂�����̂Ȃ��ł����˂ɑ}��������ۂ��邩��ł��B ���̊ԁA�t�@�j�[�́A�G�h�}���h�����A���[�ւ̗��S���点�A�����̈ӎv���ł߂Ă䂭���܂��A�d�����S�ŁA�T����A���邢�͊ԋ߂Ŋώ@��������B���̈���ŁA�ޏ��̓��A���[�̌��_���ׂ����ώ@���A���̖{�������ɂ߂悤�Ƃ��Ă��܂��B���A���[�̂ق��́A�T���āA�t�@�j�[�ɕ\���̂Ȃ��D�ӂ������Ă���̂ɑ��āA�t�@�j�[�̂ق��́A�\�ʂ̑ԓx�ƐS�̒��͐����Ȃ̂ł��B���̂悤�Ɍ���ƁA�t�@�j�[�ƃ��A���[����ׂāA���ׂƂ����ϗ��I�Ȏ��_�őΏƓI�ɂ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ��킩��܂��B���ɂ́A�t�@�j�[�̑ԓx�͉A���Ŏ��O�[���_�͔ے�ł��܂���B �@��Q�S�� �㔼�̕��ꂪ�A���悢��{�i�I�ɓ����o���܂��B�w�����[��N���t�H�[�h���q�t�قł̑؍݂��������邱�Ƃ������܂��B����́A�؍݂���y���݂�����������ŁA����̓t�@�j�[��v���C�X��U�f���邱�Ƃł��B �u���܂̃t�@�j�[��v���C�X�́A�H�Ɍ����Ƃ��̃t�@�j�[��v���C�X�Ƃ͂܂������̕ʐl���B�H�Ɍ����Ƃ��́A�ޏ��͂��ƂȂ����T���߂ŁA����قǕs��ʂł͂Ȃ����̎q�Ƃ����������������ǁA���܂͊��S�ɔ��l�ƌ����Ă������B�ȑO�͂ڂ����A�ޏ��͕\����ς��Ƃ��Ȃ��Ǝv���Ă����B�ł����̂������Ƃ��́A�_���̖j�����т��тۂ��ƐԂ����܂��Ăق�Ƃ��ɔ����������B����ɖڂ������A�����\���������Ƃ��ɂ́A������\���\���ł���\�͂������Ă���B�p���A�ԓx���A�S�̓I�Ȉ�ۂ��A�ق�Ƃ��Ɍ��Ⴆ��قǔ������Ȃ����B�g�����A�\���ȗ���C���`�L�т���Ȃ����ȁv�i�o.�R�S�T�`�R�S�U�j �����ŁA�w�����[�������Ă���̂́A�t�@�j�[�̊O����e�e�Ɋւ��邱�Ƃ����ł��B����́A�ɂԂ��ɂ��̏����ɂ�����������o���Ă݂悤���Ƃ��������ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��ł��傤�B����̃f�B�i�[�̐ȂŁA�t�@�j�[���{��ɋ��ꂽ���Ƃɂ��Ă��A���������������̃w�����[���g�������C�t���Ă��Ȃ��̂ł��B�t�@�j�[�̋C�������v������Ƃ����p���͔��o������܂���B �u�ڂ��́A�t�@�j�[�̂��Ƃ��ǂ��l���Ă������킩��Ȃ��B�ޏ��͂ǂ����������Ȃ̂������ς�킩��Ȃ��B���̂����A�ޏ��̑_���͉��Ȃ̂������ς�킩��Ȃ������B�ǂ��������i�Ȃ̂��H���^�ʖڂȂ̂��ȁH�ς��҂Ȃ̂��ȁH��i�Ԃ��Ă���̂��ȁH�Ȃ�����ȂɐK���݂��āA�Ȃ�����Ȃɂ��킢��������̂��ȁH�ڂ���������b�������Ă��A�قƂ�nj��������Ȃ������B�Ⴂ����������Ȃɒ������Ԉꏏ�ɂ��āA���낢��w�͂����̂ɂ��܂������Ȃ������̂́A���܂�ď��߂Ă��B����Ȃ��킢������Ăڂ������鏗���ɉ�����̂͏��߂Ă��B����͂Ȃ�Ƃ����Ȃ�����B�ޏ��̊�͂��������Ă���݂����������B�u���͂��Ȃ����D���ɂȂ�܂���B��ɍD���ɂȂ�܂���v���āB������ڂ��͂��������B�u�悵�A����Ȃ��ɍD���ɂ����Ă݂���v���āv�i�o.�R�S�V�j �@�܂�œ�U�s���̍Ԃ��U������Q�[���̂悤�ł��B���ꂩ��A�ނ͎����ǂ���g���čI�݂Ɍ������܂��B�t�@�j�[�́A�ނ������Ă���Ƃ͂����A�₳�������i�Ǝ�̂悳����A�ނ̋��������S�ɂ͂˂���͓̂�������̂�������܂���B�������A�ޏ��ɂ̓G�h�}���h�Ƃ��������Ɏv������j�������܂����B����Ȑ܂ɁA�t�@�j�[�̎��Z�ł���E�B���A�����C�R�̌R�͂ɏ�荞��ł̊C�O�Ζ�����A�����A�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�ōĉ�܂��B�ޏ��ɂƂ��Ă͍ň��̌Z�ŁA�ĉ�̂Ƃ��͏�ɂȂ�������ԂƂȂ�܂��B�w�����[��N���t�H�[�h�́A�t�@�j�[�ɂ����猾������Ă����������Ȃ��Ȃ��ŁA�_���ڂ����o���܂����B �@��Q�T�� �w�����[��N���t�H�[�h���t�@�j�[�ɓ��ʂȊS���Ă��邱�Ƃ́A���͂ɋC�t����͂��߁A�T�[��g�}�X���C�t�����ƂƂȂ�܂��B����́A�o�[�g�����Ƃ̐l�X���O�����g���m���珵�҂��āA�q�t�قł̃f�B�i�[�̂��ƁA�J�[�h�V�т������ʂŁA����I�ƂȂ�܂��B�T�[��g�}�X�́A���̎����ƃt�@�j�[�����~�����ȑԓx���Ƃ��Ă��Ȃ����Ƃ����āA�ޏ��ɑ���]���ƍD���������������߂邱�ƂƂȂ�܂��B�i���̂��Ƃ́A���̌コ��ɃT�[��g�}�X�̓t�@�j�[�ɑ��Đe�ɂȂ��ĕ�������J�����肷�����ŁA�ޏ����w�����[�̋�����f�����Ƃ��̎��]�����傫�����̂ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��j�����̃J�[�h�V�т̏�ʂ́A�T�U�g����R�[�g�K��ɂ�����x���`�̏�ʂ�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ł̃T�[��g�}�X�s�ݎ��̑f�l�ŋ������Ƃ����������̕���̂悤�ȁA�ЂƂƂ���Ől�Ԗ͗l��l�X�̎v�f�̌������������邩�̂悤�����肾������ʂ̈�ł��B����������ʂ��I���ɂ����Ă���̂��A���̏����̑傫�ȓ����ł��B���̏�ʂł́A�O�̓�̏�ʂł͊ϋq�̂悤�ȖT�ώ҂̈ʒu�Â��������t�@�j�[���A����̒��S�ŕ����ʼn�����l���̈�l�ɂȂ��Ă��܂��B�����ɑ傫�ȕω�������܂��B���̎��_�ŁA�t�@�j�[���T�ώ҂��畨����������闧��ɕω��������Ƃ������Ă���ƌ����܂��B �����ł́A�t�@�j�[���T�ώ҂��畨����������闧��ɏ��X�ɕω������Ă��Ă��邱�Ƃ������Ă���ƌ����܂��B�Ƃ͂����A���̎��_�ł͍ň��̌Z�ł���E�B���A���Ƌv���Ԃ�̍ĉ���ʂ������K�����ɂ���A�������N�����Ă��܂���B���̏�ʂŁA�̂��҂��Ȃ�Ȃ���ԂɂȂ��Ă������Ƃ��Ă���̂́A�G�h�}���h�ƃ��A���[�ł���A�Վ�ἁX��忂��Ă���̂��w�����[��N���t�H�[�h�ł��B�����ŁA�y�����ȃJ�[�h�V�т̐��ʉ��łЂ����ȓ������i�s���Ă���B���������ǂݕ�������ƁA�ٔ����̂����ʂƂ��āA�J�[�h��Q�[���̋��X���X�̋삯�������A����̌����̃G�h�}���h�ƃ��A���[�Ƀw�����[�ƃt�@�j�[�������ł̋삯�������d�ˍ��킹�Č����Ă���d�|���ɂȂ��Ă��܂��B����́A�f�l�ŋ��̃G�s�\�[�h�ʼn����̔z���̓����ɕ���̌����̐l�X�̐l�Ԗ͗l���d�Ȃ荇���Ă�����@�ɒʂ�����̂ł��B �Ⴆ�A�w�����[��N���[�t�H�[�h���t�@�j�[�ɑ��čD�ӂ��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���T�[��g�}�X�A�\�[���g���E���C�V�[�̉��njv��Ɉӗ~�������w�����[�A�G�h�}���h���\�[���g���E�g���C�V�[�Ɉڂ�Z�ނƂ��܂��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƌ����t�@�j�[�A�q�t�̖��߂�����߂Đ^�ʖڂɎƂ߂Ă���T�[��g�}�X��G�h�}���h�ɕs�������������A���Ƃ�������ɁA�l�X�̗l�X�Ȏv�f�����G�ɗ��ݍ����Ă��܂��B�������A�����̎v�f�͌��ǂ̂Ƃ���������邱�Ƃ��Ȃ��A���҂�\�z�Ƃ͈قȂ�A�����}���邱�ƂɂȂ�B���ꂪ�w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�̕���Ȃ̂ł��B���̏�ʂŃv���C�����J�[�h��Q�[���̓z�C�X�g�ƃX�y�L�����C�V�����ŁA���ł��X�y�L�����C�V�����͎v�f�������Ӗ����錾�t�ł��B�ے��I�ł��B�������A��āA�v�f���������Ȃ��Ƃ����p�^�[���́A�n���̉��ǁi�T�U�g����R�[�g�K��j�A�f�l�ŋ��A�����ăg�����v��Q�[���ƌ`�������ČJ��Ԃ����̂ł��B �@��Q�U�� �t�@�j�[�̌Z�ł���E�B���A���́A�T�[��g�}�X�̍D�ӂ�������邱�Ƃɐ������܂��B�E�B���A���͂₪�ċx�ɖ����ɂ͘A���ɖ߂�˂Ȃ�Ȃ��g�̏�ł���A�t�@�j�[�̗x���Ă���p���������Ƃ����肢���k�炵�܂��B������������T�[��g�}�X�́A�E�B���A���̊肢�ɉ����āA�t�@�j�[�̋C������a�炰�悤�Ƃ���D�����������āA�d�ꂵ�����͋C����|���悤�ƁA�N���X�}�X�O�̈ٗ�Ȏ����ɕ�������Â����Ƃ����S���܂��B�t�@�j�[�͏���������͌Z�ƃ_���X�����ėV�Ԃ悤�Ȏq�ǂ��ł��������Ƃ���A�_���X���͍̂D���ŁA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ŕ��������Â��A�����ɎQ������Ƃ������Ƃ́A�z�X�e�X���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���C�ȃt�@�j�[�ɂ͋C���d�����Ƃł��B�������A�ޏ��ɂ͈ߑ�����i�̎������킹���Ȃ��A���k���鑊������܂���B�ޏ��́A���A���[�ɑ��k���܂��B�����ŁA�w�����[����v���Ă����̂��l�b�N���X�ɂ܂�錏�ł��B�t�@�j�[�́A�����i���������Ă��炸�A��������l�b�N���X�̂����ɌZ���瑡��ꂽ�\���˂����ɂ��悤�Ƃ��܂����A�����݂���������܂���B�w�����[�́A���̂��ƂɋC�t���Ă��܂����B�ނ́A��������n������t�@�j�[�͎��Ȃ����낤����A���A���[��ʂ��Ĕޏ��Ƀv���[���g���Ă�낤�ƍl�����̂ł��B���A���[���莝���̃l�b�N���X�̈��ޏ��ɑ���Ƃ����`�ɂ���̂ł����A���̃l�b�N���X�͂��Ĕނ����A���[�փv���[���g�������̂������̂ł��B���A���[�͂��̃l�b�N���X�͂��Ă̌Z����̃v���[���g���������Ƃ��t�@�j�[�ɍ����܂��B�t�@�j�[�͂����ɂ����Ԃ����Ƃ��܂����A�����������������̂�Ԃ��̂�����ɓ�����܂��B���̌�B���R�ɃG�h�}���h�����̍����t�@�j�[�Ƀv���[���g���Ă���āA���ꂪ��̏\���˂ɒʂ��ɂ͂҂����肾�����B�G�h�}���h�́A�t�@�j�[���玖����ƁA���A���[�̍D�ӂɂ���͎̂��炾����ƁA�l�b�N���X�����邱�Ƃ������߂܂��B���̂Ƃ��ɃG�h�}���h���u�ڂ��ɂƂ��āA���̐��ň�ԑ�Ȃӂ��肾����ˁv�i�o.�R�X�W�j�Ƃ����āA�t�@�j�[�ɂ����A���[�d���邱�ƂŁA��l�����h���������Ƃ����߂܂��B���̌��t�����t�@�j�[�͐S����܂��B ���͔ނɂƂ��āA�������Ȃӂ���̂����̂ЂƂ�Ȃ̂��B���̌��t��S�̎x���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ł��ނɂ́A��Ȑl�������ЂƂ肢��̂��I�������Ȑl������̂��I�G�h�}���h���t�@�j�[�̑O�ŁA����Ȃɂ͂�����Ƃ��̂��Ƃ����ɂ����̂́A���ꂪ���߂Ă������B�t�@�j�[�͂����Ԃ�O���炻�̂��ƂɋC�Â��Ă͂�������ǁA�������Ėڂ̑O�ł͂�����ƌ�����ƁA�Z���ŋ���˂��h���ꂽ�悤�Ȍ��ɂ��������B�Ȃ��Ȃ炻�̌��t�́A�G�h�}���h�̊m�M�Ə����̌v����͂�����ƌ���Ă��邩�炾�B�������ׂāA�͂�����ƌ��܂��Ă���̂��B�܂�A�G�h�}���h�́A�~�X��N���t�H�[�h�ƌ����������Ȃ̂��B�����Ԃ�O����\�z�������Ƃł͂��邯��ǁA����͂�͂�A�t�@�j�[�̐S��˂��h���悤�Ȍ��t�������B�u���͔ނɂƂ��āA�������Ȃӂ���̂ЂƂ�Ȃ̂��v�ƃt�@�j�[�A���x�����x�������Ɍ����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B�������Ȃ��ƁA���̌��t���^���銴���������邱�Ƃ��ł��Ȃ����炾�B�����I�~�X�E�N���t�H�[�h���ނɂӂ��킵���������Ǝv������ǂ�Ȃɂ������낤�I���������v������A����͂������Ă��邵�A����ȑς��������C�����ɂȂ炸�ɂ��ނ��낤�I�ł��ނ́A�~�X�E�N���t�H�[�h��������Ă���̂��B�~�X�E�N���t�H�[�h�������Ă��Ȃ�������������ɗ_�߂����邵�A�ޏ��̌��_�͐̂̂܂܂Ȃ̂ɁA���܂̃G�h�}���h�ɂ́A�ޏ��̌��_���܂����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��B�i�o.�R�X�W�j ���̂悤�ɁA�������ނ̍ň��̓�l�̂����̂ЂƂ�Ȃ̂��Ƃ����v����䍂��Ȃ���A�t�@�j�[�͂���ɂ����݂����Ƃ��܂��B�������A���Ƃ����ЂƂ肪���A���[���Ƃ����������A�ޏ��ɂ͑ς��������������A�ޏ��̐S���h���т��������ɂ݂������炵�܂��B�t�@�j�[�́A���A���[���G�h�}���h�̌�������Ƃ��đ��������Ȃ��ƒf�肵�A�ނ��x����ޏ������Ԃ��Ă���̂��ƍl����̂ł��B���p�������͂ɂ́A���x���������t�����A���Q����J��Ԃ��\���ȂǁA�����ł͎��R�Ԑژb�@�̓����������A�t�@�j�[�������ɉ����������Ă��邩���`����Ă���悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̉��ɂ́A���G�ɑ��錙����������ł��邱�Ƃ��z���ł���̂ł��B �܂�A�l�b�N���X�́A�t�@�j�[�ɂƂ��āA�����������A���[���瑡��ꂽ���̂ł�����̂ł��B�G�h�}���h�ɐg�ɂ���悤�ɐi�����ꂽ�t�@�j�[�̋C�����́A���G�������͂��ł��B�������A�w��ł̓w�����[��N���t�H�[�h�̉��S�����������Ă���̂ł��B�����ŁA�K���Ȃ��ƂɃE�B���A�����瑡��ꂽ�\���˂ƃ��A���[�̃l�b�N���X�̓T�C�Y�����킸�A�q�����Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ�������܂����B�t�@�j�[�͑�`�������ł������ƂŁA�G�h�}���h�̍����\���˂ɂȂ��܂��B����ŋC�����������������̂��A���A���[�̃l�b�N���X���A�ׂɎ�ɂ����邱�Ƃɂ��āA���A���[�̍D�ӂɌ`����͉����邱�Ƃɂ��܂����B �@��Q�V�� �G�h�}���h�͕�����̗����A�����ɖq�t�ƂȂ��ă\�[�g���E���C�V�[�ɍs�����ƂɂȂ�܂��B�܂��A�E�B���A���������悤�ɗ����Ɋ͑��ɋA�͂��邽�߂ɏo������\��ł��B���������āA������̓t�@�j�[�ɂƂ��ẮA�ł�������l�X�ƕʂ��O�̍Ō�̃C�x���g�ł�����킯�ł��B �w�����[��N���t�H�[�h�̓����h���ŏf���̒�ɉ�\�肪����Ƃ����āA�E�B���A���Ɏ��g�̔n�Ԃňꏏ�Ƀ}���X�t�B�[���h��p�[�N�o��悤�ɗU���܂��B�w�n�Ԃ����p���s�ւ��ɔ�ׂĉ��K�ȗ����ɂȂ邽�߁A�E�B���A���͊��œ��ӂ���̂ł����B�w�����[�̃����h���s���́A�E�B���A�����f���ɏЉ�āA���тւ̏��i�̐��E�������邽�߂ł��B���̃w�����[�̍s���́A���Ȃ����A���̃t�@�j�[�̊��S�����S���炾���Ƃ͌�����Ȃ��Ƃ��낪����A�ނ��E�B���A���̐l���ɍD���������e�ؐS���������ʂ�����Ǝv���܂��B�w�����[���g�̓��@�̓n�b�L�����܂��A���ߓI�ɁA�ς��ƂЂ�߂��āA�\�ʓI�ɂ悭�f��U�镑��������Ƃ����N���t�H�[�h�Z���̍s���p�^�[���ɏ]���čs�����Ă��邱�Ƃ͂������ł��傤�B�w�����[�́A���ƂŁA�t�@�j�[�ɋ�������Ƃ��ɁA���̂��Ƃ���������藘�p����킯�ł����B �����h������̋A�Ҍ�C�w�����[�̓t�@�j�[�ւ̔R����v�������A���[�ɑł������܂��B �u�ڂ��̓t�@�j�[��v���C�X�ɂ݂��Ƃɂ��܂��Ă��܂����B�ڂ��������V�є����Ŏn�߂����Ƃ́A���݂��m���Ă���ˁB�������A�V�тŎn�߂����Ƃ̌��������ꂳ�B�ޏ��͂��Ȃ�ڂ����D���ɂȂ��Ă��Ă���Ǝv���B�ł��ڂ��̋C�����͂����������茈�܂����v�i�o.�S�S�S�j �w�����[�ɂ��A�t�@�j�[�͒�̕Ό�����苎�肤��B��̏����ł���Ƃ����܂��B���Ȃ킿�A���l���͂����ƂɂȂ��̒�R�������Ȃ���̏����ς�ς��邱�Ƃ́A�t�@�j�[�ɂ����ł��Ȃ��ƌ����܂��B �u�t�@�j�[�́A��̂悤�Ȓj���������ɑ��Ď����Ă���Ό������ׂĎ�菜���Ă���鏗�����B�܂��Ƀt�@�j�[�́A����A���̐��ɂ͑��݂��Ȃ��Ǝv���Ă���悤�ȏ������B�܂��ɒ�̌����A�H�L�Ȃ鏗�����̂��̂��B��������A���z�̏�������\���ł���悤�ȑ@�ׂȌ��t���������킹�Ă���̘b�����ǁB�ł��b�����S�Ɍ��܂�܂ł́A�����āA��Ɏז�������Ȃ����Ƃ��͂����肷��܂ł́A��ɂ͉����m�点�Ȃ����肾�B�v�i�o.�S�S�T�j �u���̐��ɂ��Ȃ��Ǝv���鏗���v�Ƃ́A��̏��Ȃ̋����ɂ͂����Ă��̏����ł���ƌ����܂��B��̐������N���t�H�[�h�Z���ɂƂ��Ė��ƂȂ��Ă���\����������_�̉����ւ̈Ӑ}���t�@�j�[�ւ̋����̒��Ɋ������͊܂܂�Ă���͂��ł��B �t�@�j�[�ւ̔R����v���ɁC�w�����[��N���t�H�[�h���g�̎��ȉ��P�ւ̈ӗ~���܂܂�Ă������Ƃ́C���̒n�̕��ɖ����ł��B �w�����[�́A�����̂��܂̋C������b���āA�t�@�j�[�̖��͂��̂���ȊO�ɘb�����Ƃ͂Ȃ������B�t�@�j�[�̔�������Ǝp�A��i�ȑԓx�A�P�ǂȐS�A����͂܂��ɐs���邱�Ƃ̂Ȃ��b��ł���A�w�����[�́A�t�@�j�[�̉��₩�ōT���߂Ȃ₳�������i���A�M���ۂ����q�ŗ_�߂��������B�����̂₳�����́A�j���������̉��l�f����Ƃ��̍ł��d�v�ȗv�f�ł���A�j���͂Ƃ��ɂ́A�₳�����̂Ȃ������������邱�Ƃ����邯��ǁA�����ɂ₳�������Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ͐M�����Ȃ��̂��B�����ăt�@�j�[�̂������肵�����i�ɂ��ẮA�w�����[�͂����M�����ď̎^���邾���̏\���ȗ��R���������B�t�@�j�[���}���X�t�B�[���h��p�[�N�ł炢�ڂɂ����āA���̔E�ϋ������i����������ʂ����x���������Ƃ����邩�炾�B�o�[�g�����Ƃ̐l�����̈́��G�h�}���h�������Ą��݂�ȉ��炩�̂������ŁA�₦���t�@�j�[�ɔE�ςƉ䖝�����v���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B����ɁA�t�@�j�[���ƂĂ�����[�����i�ł��邱�Ƃ��ԈႢ�Ȃ��B�Z�E�B���A���ƈꏏ�ɂ���Ƃ��̃t�@�j�[�����邪�����I�t�@�j�[�͂₳�����S�̎�����ł���Ɠ����ɁA���̂������M���S�̎����傾�Ƃ������Ƃ��A���̂قق��܂������i����ڌ���킩�邾�낤�B�����āA�t�@�j�[���s�q�������Ȓm���̎����傾�Ƃ������Ƃ��ԈႢ�Ȃ����A�������ޏ��̑ԓx�ɂ́A��i�Ō����ȐS���͂�����\���Ă���B���������ꂾ���ł͂Ȃ��B�w�����[��N���t�H�[�h�͂��������̕��ʂ�����Ă���̂ŁA�����̍Ȃ͗��h�ȓ����S�ƐM�S������������łȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���B�����A�����������Ƃɂ��Đ^���ɍl���邱�ƂɊ���Ă��Ȃ��̂ŁA�����K�Ȍ��t�Ō������Ƃ͂ł��Ȃ������B�������ނ͂����������B�t�@�j�[�͎u�����łŁA���_���d�A��V��@����������Ƃ킫�܂�������������A�����Ȃ�j�����A�ޏ��̒�߂Ɛ����Ȉ�������S�ɐM�����邱�Ƃ��ł���A�ƁB�܂�ނ́A�t�@�j�[�����h�ȓ����S�ƐM�S�̎����傾�Ƃ킩�������炱�������������̂ł���B�i�o.�S�S�V�`�S�S�W�j �w�����[��N���t�H�[�h�ɂ���ĔM���ۂ������t�@�j�[�ł����A���́A�����̂Ȃ��ō�҂ɂ���āA�ޏ��̂��Ƃ��܂Ƃ܂��ďЉ�ꂽ���Ƃ͂���܂���ł����B�N���t�H�[�h�Z���̏ꍇ���́A�o�ꂵ���Ƃ��ɍŏ��ɊO����琫�i���������Ă����̂ƑΏƓI�ł����B�t�@�j�[�̏ꍇ�́A�ŏ��́A�|�[�c�}�X�̕n�������̉Ƃ���}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�ɂ���Ă��āA�o�[�g�����Ƃ̉Ƒ��Ǝg�p�l�̒��Ԃ̂悤�Șe�ɍT����݂��ڂ炵�������������̂��A���X�ɐ������Ă����Ƃ���������������Ƃ������܂��B����ɂ��Ă��A�o�[�g�����Ƃ̐l���G�h�}���h�ȊO�͔ޏ��̂��Ƃ͐l�Ƃ��Ď���ɓ����Ă��Ȃ������Ƃ������݂���������������ł��傤�B�]���āA�ǎ҂͔ޏ��ɂ܂��G�s�\�[�h����l�ƂȂ�����Ă����Ƃ����ǂݕ�������悤�ł����B���ꂪ�i��ŁA�t�@�j�[���������A�Ⴂ�����ƂȂ����Ƃ���ŁA���܂���l���Љ������̂����������A�Ƃ����킯�ŁA�����Ńw�����[��N���t�H�[�h�̎^�����܂������Љ�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����͂܂��A�ǎ҂ɑ��āA�t�@�j�[�͂��̂悤�Ȑl���ł���Ƃ����C���[�W��A���t������ʂ��^���Ă���Ǝv���܂��B�����ł̃t�@�j�[���́A�ޏ��ɗ�����w�����[��N���t�H�[�h�̖ڂɉf�����p�ŁA�����ɕ肪����܂��B�������A���̕�́A���́A��ɔޏ����w�����[�̋��������₷��s�ׂƖ������Ȃ��p�Ȃ̂ł��B�����ŁA�ǎ҂͔[�����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�t�@�j�[�́A���̂��Ƃ̖{����[���ώ@���A�������������Ƃ����ϗ������g�ŕێ����Ă��āA�������Ƃ��������Ƃ������O�ʂɍ��E����Ȃ��Ƃ����C���[�W���Œ艻������@�\���ʂ����Ă���Ǝv���܂��B����ɂ���āA����ȑO�̏����̂���̃t�@�j�[�ɂ��k���āA���������l���������Ƃ����C���[�W���㏑������邱�ƂɂȂ����Ǝv���܂��B�I�[�X�e�B���̏����̃q���C�������́A�w���ʂƑ����x�̃G���i�[�����鎖���G�h���[�h�ւ̎v�������ɂ��邱�Ƃꂽ�ȊO�́A���x�̍��͂��ꎩ�g�̊���ɂ��Ȃ��Ȑl�X�ł��B�ޏ������́A�l�X�ȍs�����Ƃ�܂����A���̓��@�́A�ǎ҂ɂƂ��ẮA�V���v���ŕ�����Ղ��̂ł��B�������A�t�@�j�[��v���C�X�̏ꍇ�́A����̂Ȃ��ł��G�h�}���h�ւ̎v���͍Ō�߂��ŃG�h�}���h���C�Â��܂ŁA�����ƉB���ʂ��܂��B�܂��A���A���[��N���t�H�[�h�ɑ��Ă��\�ʏ�͐e�����ł����A�S�̒��ł͗�O�Ȋώ@�Ǝ��i�A����������Ă��܂��B����������ؓ�ł͂����Ȃ����܂������i�̏����ł��B�������A�I�[�X�e�B���͔ޏ����A�����ɑ����Ƃ��́A���̎��X�ɋN������������ׂ����`�ʂ��܂����A�ޏ��̑S�̑��A�܂�A�������������͔ޏ��̂ǂ̂悤�Ȑ��i����N���Ă���̂��������܂���B�Ⴆ�A�w�����ƕΌ��x�ɂ����ăG���U�x�X���A���ʂȊ���̓��������܂����A����͏����̑薼�ł�����A�ޏ��̃v���C�h�i����𗠕Ԃ����̂��Ό��j���瓱���o����悤�ɏ�����Ă���A���̃v���C�h�ɂ�������̂��t�@�j�[��v���C�X�̏ꍇ�͉B����Ă���̂ł��B���̂����ɁA�^�e�}�G�Ƃ��Đ����������߂铹���������Ă����Ă�����x�ł��B�������A����ł͕\�ʓI�����Ĕޏ��̌������������������ł�������͂Ɍ����܂��B���ꂪ�A�X�g�[���[�����s����`�ɉf������A�t�@�j�[�Ƃ����l���̕������A�Ђ��ẮA�I�[�X�e�B���̏����̂Ȃ��ł͓���Ɋ�������v���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���āA����̓w�����[���ł��������t�@�j�[�Ƃ̌��������A���[�͎^�����܂��B �����A�w�����[��N���t�H�[�h�̓E�B���A����v���C�X�̏��i��������莆���͂��ƁA����������ăt�@�j�[�̂��Ƃ�K��܂��B�����āA�ނ́A�t�@�j�[�ɌZ�̏��i�ƁA����Ɏ��g���s�͂������Ƃ�`���܂��B���̌o�܂����킵����������Ȃ��ŁA�������ǂ�ȂɐS�z��������M���ۂ����A�u�ł��[���S�v�Ƃ��u��d�̓��@�v�Ƃ��u���ł͌����Ȃ��قǂ̎v���Ɗ肢�v�Ƃ��������t��A�����܂��B�ނ́A�I���Ɏ��g�̃t�@�j�[�ɑ���v����D������āA��R�Ȃ��������悤�ɓ`���悤�Ƃ���̂ł��B����ɑ��ăt�@�j�[�̓E�B���A���̏��i�̊�тƋ����œ����ڂ����Ƃ��āA�ނ̘b�R�ƕ��������Ă��܂��܂��B�w�����[�́A����ɋC���悭���āA���悢��{��̈��̍����ɓ���܂��B����ɑ��Ẵt�@�j�[�� �ł��t�@�j�[�́A����͂��ׂĔn���ȏ�k�ł���A���̂���ނ�̐^�����ł���A���������܂����߂̈ꎞ�̋Y�����Ǝv�����B����͎����ɂ���������Ɏ��炩�s���ȐU�镑���ł���A�����͂���Ȏd�ł����闝�R�͂Ȃ��Ǝv�킸�ɂ͂����Ȃ������B�ł�����́A�����ɂ��w�����[��N���t�H�[�h����肻���Ȃ��Ƃ����A�ނ��}���C�A��W�����A�ɑ��Ă������ƂƂ܂������������B�ł����܂̎����́A���Ƃ��w�����[�ɕs�������o���Ă��A�����\�ɏo���Ă͂����Ȃ��B�ނ̓E�B���A���̂��߂ɂ���Ȃɍ��܂��Ă��ꂽ�̂�����A���Ƃ��ނ�����ȐU�镑�������Ă��A���̉���Y��Ă͂����Ȃ��B�E�B���A�����i�̒m�点���āA�t�@�j�[�̐S�͊�тƊ��ӂ̋C�����ł����ς��������B������A�����̋C������������ꂽ���炢�ŁA����ȂɃ��L�ɂȂ��ĕ��𗧂Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�i�o.�S�T�X�j �t�@�j�[�̓E�B���A���̏��i�ɂ��Ă͊��ӂ��܂����A�����ɂ��ẮA���Ĕނ��}���C�A��W�����A�����Ă����Y��ŁA�����J���鎸��Ȃ��Ƃ��Ƃ����l�����܂���B�������A�Z�̏��i�ւ̐s�͂ɂ͊��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���Ȃ��ƂɂȂ����ƌ˘f������ł��B�ޏ��͋�������k�ł���Ƃ��āA�܂Ƃ��ɑ�������邱�ƂȂ��ɁA���炾�Ƃ����Ȃ߂܂����A�w�����[�͋����Ɍ�����\�����݂܂��B�ނ́A�t�@�j�[�������������Ă��邱�ƂɋC�Â��Ă��܂���B �ނ͂��̌��Ɋւ��āA���Ɋy�ϓI�Ŏ��M�����Ղ�ł���A���������߂�K�������Ȃ킿�����ƃt�@�j�[�Ƃ̌������̎ז������Ă���̂́A�t�@�j�[�̌����ȋC�����������Ǝv���Ă����B�i�o.�S�U�O�j ���̃w�����[��N���t�H�[�h�̌����̐\���݂͓�����҂́w�����ƕΌ��x�ɂ����āA�G���U�x�X�ɑ��ăR�����Y���������Ď茵�����f���Ă��A���������₳�ꂽ���ƂɋC�Â��Ă��Ȃ���ʂ�A������i�ŁA�_�[�V�[���R�����Y�̖q�t�قŃG���U�x�X�ɋ������Ēf��ꂽ��ʂɂ悭���Ă��܂��B�w�����ƕΌ��x�̏ꍇ�́A��l�Ƃ����x�̍��͂���܂����A�������䂦�ɂ����Ă̏������������A���̋C�����Ɏv������Ȃ������������ɏ��̂߂��Ă��܂��B���̏ꍇ�́A�w�����[�������ł��B��҂���݂�A�w�����[�ɂƂ��ẮA�t�@�j�[���}���C�A���W�����A�������悤�Ȃ��̂ŁA���̂Ȃ��ŏ����t�@�j�[�̒l�i�������Ƃ������x�̍��Ȃ̂��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B����́A�O���̃w�����[�ƃ��A���[�̉�b�ŁA���A���[���A�ނ��t�@�j�[�ɖO���Ă��܂��Ă��ȂƂ��Đ�����ۏႳ��K���ł�����Ƃ�����|�̔��������Ă��āA�ނ��t�@�j�[�������Ă���ƌ����Ă��邱�Ƃ͈ꎞ�̋C����ɉ߂��Ȃ����Ƃ����j�������������Ă��܂��B�������A�w�����ƕΌ��x�͊쌀�I�ȏ�ʂł����A���̍�i�ł͔ߌ��I�ȗl����悵�܂��B�܂�A����܂Ŕޏ��͖T�ώ҂Ƃ��Ă̗���ŁA�l�X���v���ς��A�s�����邳�܂߂Ă��������ł����B�������A���̋����͔ޏ���l���̖T�ώ҂���I���҂̗���ւƓ]����������̂ł��B�ޏ��́A�ˑR�A�l���̊�H�ɗ�������A���f�𔗂��邱�ƂɂȂ����킯�ł��B �܂��́A�t�@�j�[���A�w�����[�̋������ǂ��~�߂����A���̂悤�ɏ�����Ă��܂��B �t�@�j�[�͂����邱�Ƃ������A�l���A�����Đg�k�������B������������Ԃ̂܂܍K�����ɖ������ꂽ���Ǝv���ƁA�ˑR�݂��߂ȋC�����ɂȂ�A�[�����ӂ̔O���o�������Ǝv���ƁA�ˑR�������{�肪���݂������B�N���t�H�[�h�����Ƀv���|�[�Y����Ȃ�ĐM�����Ȃ��I�ˑR����Ȃ��Ƃ������o���Ȃ�ċ������������A�܂����������ł��Ȃ��I�ł��ނ͂��������l�Ȃ̂��B����������Ƃ��́A�K�����Ȃ��Ƃ������Ȃ��Ă͋C�����܂Ȃ��l�Ȃ̂��B�i�o.�S�U�P�j �t�@�j�[�̐S�̒��ŁA�Z�̂��Ƃ�z�����ӂƊ�т��A���h��S�߂���{��ƍ����荇�������̋ɂɂ���Ȃ���A�����Ƀw�����B�ɑ��Ēf�߂���̂ł��B���R�A�ޏ��̓w�����[�ƌ����������͂���܂���B �������A�T�[��g�}�X�͔ނ̐M��`���I���l�ς��猩��A�w�����[�̃t�@�j�[�ւ̋����͔ޏ��ɂƂ��Ă͂���ȏ�]�ނׂ����Ȃ��قǂ̍K�^�ł���A�t�@�j�[���������͓̂��R�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���������ċ�����f��t�@�j�[�ɁC�T�[�E�g�}�X�͗����ł��܂���B �u���܂��͎��̊��҂����Ƃ��Ƃ��������B���O�̐��i�́A�����v���Ă����̂Ƃ͐������Ƃ������Ƃ��悭�킩�����B�������ˁA�t�@�j�[�A�ŋ߂̎��̑ԓx�ŁA���܂��ɂ��킩���Ă����Ǝv�����A���̓C�M���X�ɖ߂��Ă���A���܂��̂��Ƃ���ɍ��������Ă����̂��B���܂��́A�킪�܂܂�A���ʂڂ��A�ߍ��̎Ⴂ�����ɗ��s���Ă���A���R�Ȑ��_�ȂǂƂ������̂Ƃ͂܂����������ȏ������ƁA���͎v���Ă����̂��B���R�Ȑ��_�ȂǂƂ������̂�U�肩�����Ⴂ����������ƁA���͒���������B�Ƃ��낪�A���܂������������A���Ɠ����悤�ɁA�킪�܂܂ŋ���Ȗ����Ƃ��������͂����肵���̂��B���O������������l���������āA�Ђƌ��̑��k�������ɁA���ł������Ō��߂��܂������Ƃ������Ƃ��͂����肵���̂��B�����z�����Ă����悤�Ȗ��Ƃ͂܂������Ⴄ�Ƃ������Ƃ��͂����肵���̂��B�v���C�X�Ƃ̐l�����A�܂�A���܂��̗��e��Z��▅�̗��v��s���v�̂��Ƃ́A���܂��̓��ɂ͈�u�������Ȃ������悤���B�N���t�H�[�h�N�Ƃ̌��������܂�A���O�̉Ƒ��͂ǂ�قlj��b�������ނ�A�ǂ�قNJ�Ԃ��낤�B����������Ȃ��Ƃ́A���܂��ɂ͂ǂ��ł������̂��B���O�͎����̂��Ƃ����l���Ă��Ȃ��̂��B�v�i�o.�S�W�Q�`�S�W�R�j �u�������̖����N������v���|�[�Y����āA���̈ӌ����������������ɒf�����焟���Ƃ����̑��肪�A�N���t�H�[�h�N�������������N�������Ƃ��Ă������͂т�����V���邾�낤�B��������Ȃ��Ƃ���������A���͂ق�Ƃ��ɂт����肵�ĂЂǂ��������Ƃ��낤�B����́A�e�ɑ���`���ƌh�ӂ�`瀆����U�镑�����Ǝv�����Ƃ��낤�B���������O�̏ꍇ�͎���Ⴄ�B���܂��͎��ɑ��āA�q���Ƃ��Ă̋`��������킯�ł͂Ȃ��B�������t�@�j�[�A�݂����܂����A���m�炸�ȍs�ׂ����Ă��悤�Ǝv���Ă���̂Ȃ焟�v�i�o.�S�W�S�j �t�@�j�[�̓G�h�}���h���D���Ȃ��Ƃ͌����Ă������܂���B�����A�t�@�j�[���o�[�g�����ƂɈ��������ۂɂ��Ƃ����m�̌������뜜���ꂽ���Ƃ̓t�@�j�[���������Ă���͂��ł��B�܂��A�w�����[���}���C�A��W�����A�ɑ��Ă����Ȃ������Ƃ͔ޏ������̖��_�̂��߂ɖق��Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���������āA�T�[��g�}�X�ɂ̓t�@�j�[������ȗlj���f�闝�R�������ς�킩�炸�A�ޏ����������Ă���Ƃ����v���܂���B�������A�T�[�E�g�}�X�����ł͂Ȃ��A���f�B�[�E�o�[�g�����A���A���[�E�N���t�H�[�h���t�@�j�[�ƃw�����[�̌��������߂܂��B�G�h�}���h�܂ł��A
�w�����[�Ƃ̌������t�@�j�[�ɐ������悤�Ƃ��܂��B�t�@�j�[�́A�f�l�ŋ��̗��K�Ńw�����[������҂̂���}���C�A�Ɍ�������Ă������Ƃ��G�h�}���h�ɐ������܂����A�G�h�}���h�͑f�l�ŋ����u�F�̋����ȐU�镑���v���ƍl���Ă��āA�ނ�̍s����c�����Ă��Ȃ��̂ł��B�t�@�j�[�́A�w�����[��]������G�h�}���h�Ƀ��A���[�̉e�����������܂��B���A���[�̓G�h�}���h���Ԉ���Ă��邱�Ƃ�m���Ă��܂��B�ނ̔��f���炠�Ăɂł��Ȃ��Ȃ����t�@�j�[�́A�Ǘ��������߂Ă����܂��B�ޏ��́A���܂ňȏ�ɓƗ��S�������n�߁A���͂�G�h�}���h�ɑ��k�����Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B���̈���ŁA�t�@�j�[�̓w�����[�ɓ{����o���܂��B�u��������Ŏv�����̂Ȃ��A�N���t�H�[�h���̂������ɑ��ē{�肪���݂����Ă��āv�A�����Ĕނ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���̂ł��B �t�@�j�[�͂����o�[�g�����Ƃ̐l�����̖��ɗ��������Ɗ���Ă������A�����ꂽ���Ǝv���Ă����B�������A�t�@�j�[�ƃw�����[�E�N���t�H�[�h�Ƃ̌������A���̐l�����̊肢�ł���A���̊肢������Ȃ��t�@�j�[�́u�킪�܂܂ʼn��m�炸�v���Ɣ����Ƃ����ɒǂ����܂�܂��B�w�����[�́A���̂悤�ȏ𖡕��ɂ��āA�܂�A�o�[�g�����Ƃ̐l�����̌㉟�����āA�f���Ă��t�@�j�[�Ɍ�������Ă���̂ł��B ���鎞�A�w�����B�͘N�ǂɂ����Ă��ۗ������˔\�����Ă݂��܂��B�f�l�ŋ��̍ۂɂ��A�ނ̉��Z�͑�z�������̂ł������A�V�F�C�N�X�s�A�̘N�ǂɂ����Ă��A�ނ͉��ł���A�����A�Ɛb�ł���A�v���̂܂܂ɂ��ꂼ��̐l���ɂȂ肫��A�Ќ���ւ�A���������A�ǂ̂悤�Ȋ�����I�݂ɕ\�����Ă��܂��˔\�������Ă��邱�Ƃ������܂��B�ނ́u������v���ƂŁA�l�X�Ȑl�Ԃɕϗe���قȂ�l�����^���̌����邱�Ƃ��ł���킯�ł���A�ނ���ɒǂ����߂Ă���ω��ƐV�����ɓ���邱�Ƃ��ł���̂ł��B�������I�݂Ɏ��������������A����ɍ��킹�đΉ���ς���w�����B�̊�p���́A�t�@�j�[�ɂ͔ނ̕s�������A���ߑ��̌���Ƃ����f��܂���B�u�����͑S�Ă̐l�ɂƂ��Ĉ�ԑ�ȑ��݁A�����ɂƂ��đ��͊F���ɑ���ʐl�ԁv�ƍl����w�����B�̎��Ȗ{�ʂ����A�t�@�j�[�̕s�M�����点��̂ł��B�w�����[�́A��z�������Z�̍˔\�������Ȃ���A�t�@�j�[�̑O�Ŗ̂ЂƂł��鐽���Ȑl���̖��������悤�Ƃ��Ă���̂ł��B�������A���ӂ���w�͂ɂ�������炸�A�ނ͂�������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����āA�t�@�j�[�͉��Z���̂��̂�ے肷��̂ł��B�t�@�j�[�͑f�l�ŋ��ɎQ������悤���߂�ꂽ�Ƃ��A�u���͐��E��^����ƌ����Ă��A������������ȂǂƂ������Ƃ͂ł��܂����B�����A�{���Ɏ��ɂ͂ł��܂����v�Ɠ����܂����B����́A�ޏ����A��Ȃ܂łɎ��Ȏ��g�ł��邱�Ƃɂ�����邩��ŁA�w�����[�́A���̂悤�ȃt�@�j�[�ƍۗ������ΏƂ������Ă���ƌ����܂��B�m�ł��鎩�Ȃ������Ȃ��w�����B�͂��̏ꂻ�̏�̏Ƒ���ɉ����āA��������@�m�ɕx�ޓs��I�ȗ��l����^���ȗ��l�܂ŁA���ǂ͂��̌`�����������Ă���ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�����Ŏ����Ă��܂��B�w�����B�̓t�@�j�[���{���̊�������Ă�l�Ԃł��邱�Ƃ𗝉��ł��锻�f�͂�����Ȃ���A�ނ̏�M�͋C����ŁA�ڂ̑O�Ɍ����Ȃ��Ȃ�Ɨe�Ղɂ��̑Ώۂ����ւ��Ă��܂��قǐƂ��̂ł��B�w�����B���t�@�j�[�ɌŎ�����̂́A�ޏ����ނ���̗U���|���ɑS���������A�����܂ł��ނ̋��������ݑ�����p���ɔނ̐����~���������Ă�ꂽ����ɉ߂��Ȃ��Ƃ����v�f�����Ȃ�����܂���B�t�@�j�[���w�����B�ɕ����s�M���́A�ނ��s���K�͂ƂȂ�ׂ����������������A�Ȃ̗~�]�݂̂ɓ˂���������Đ�����l�Ԃł��邱�Ƃ��������Ă��邱�Ƃ��炫�Ă���Ƃ����_���w�E�ł���Ǝv���܂��B���������āA�t�@�j�[���w�����[�ɕ��݊��]�n�͂܂������Ȃ��ƌ����܂��B ���������A�w�����[�Ƃ����l���́A���ꂾ�����X�Ɍ�������Ă��Ȃ���A�t�@�j�[����Ȃȑԓx��������Ƃ��Ȃ����ƂɁA���g�Ȃ���Ƃ����p�����S���݂��Ȃ��Ƃ���ɁA���̐l�����t�@�j�[�Ƃ��������̂��Ƃ��l���Ă��Ȃ����ƁA���P����ɂ��Ă�������ς��Ă����\�����Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��܂��B����́A�w�����ƕΌ��x�ɂ����ă_�[�V�[���G���U�x�X�ɑ���ڂ̋������茵�������₳��āA���g�̍������ƕΌ��Ɏv�������āA���������l�����Ă��������ƂƑΏƓI�ł��B���̓_�ŁA�w�����[�͓�����i�̃R�����Y�ɒʂ���Ƃ��낪����܂����A�R�����Y���쌀�I�ł���̂ɑ��āA�ނ́A���̌�Ŕj�œI�ȋ��s��Ƃ����ƂɂȂ�ߌ��I�ȑ��݂ƌ����܂��B �T�[��g�}�X�́A�t�@�j�[����x�n�������Ƃ̃|�[�c�}�X�ɋA�����Ƃɂ��܂��B�ނ́A�u�t�@�j�[�͂��łɔ��A��N�A�T���Ȍb�܂ꂽ���������Ă������߂ɁA�������r�����蔻�f�����肷��\�͂������������Ă���̂��B���Ƃ̃v���C�X�Ƃł��炭��点�A�\���Ȏ����̂���T���ȕ�炵�̉��l���A���炽�߂Ă悭������͂����v�i�o.�T�U�S�j�ƍl�����̂ł��B �I�[�X�e�B���̏����ł́A�q���C�������_��ς��ĊO������q�ϓI�Ɏ��Ȃ����ߒ����ߒ����A�X�g�[���[�̒��ɐ݂����Ă��܂��B����ɂ���āA�q���C�������́A���ȂȂ��A���ɋC�Â�����A����܂ŔF���ł��Ȃ��������������邱�Ƃ��ł���悤�Ȃ��Ă����̂ł��B�Ⴆ�A�w�����ƕΌ��x�ł́A�G���U�x�X���_�[�V�[�Əo����Ƃɂ��A�������g�̋����o���͈͂�������o��������̗���͂┻�f�̗͂D�ʐ��ւ̎��M���X�Ȏv�����݂���o�������悤�ɁA�܂��w�G�}�x�ł́A�G�}���E�b�h�n�E�X�Ƃ̊Â₩���ꂽ������A�n��Љ�̈���Ƃ��Ď���̈ʒu���m�F���邱�Ƃɂ��A���Ȓ��S�I�Ȏ��_�����萬�n�������_�ւƐ������Ă����悤�ɁA�w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�ł��A���Ԃ���u�����ꌾ��Ώ����|�{�̂悤�Ɉ�����t�@�j�[���A������x�O������}���X�t�B�[���h��p�[�N�����߂Ȃ����A�Љ�̒��̈���Ƃ��Ă̈ʒu���Ċm�F����v���Z�X�Ƃ��āA���̃|�[�c�}�X�ւ̗��A��̃G�s�\�[�h��ǂނ��Ƃ��ł���Ǝv���܂��B ���Ƃ��ƁA�t�@�j�[�Ƃ����l���̓I�[�X�e�B���̓o��l���̒��ł��A�w�m�[�T���K�[�E�A�r�[�x�̃L���T��������[�����h�ƕ���Ŗ��������Ȑ��i�̃q���C���ł��B�ȑO�A�T�U�g����R�[�g�K�₩��A����Ƃ��ɁA�t�@�j�[�͉_�ЂƂȂ����̋P���߂Ȃ���A�G�h�}���h�Ɍ��|����B �u�����ɂ͒��a�������B���炬�������B�G�≹�y�ł͕\���ł��Ȃ����́A���ɂ����\���ł��Ȃ����̂������B�l�Ԃ̂�����Y�݂�Â߂Ă���āA�l�Ԃ̐S����тŖ������Ă���鉽���������B����������̌i�F�߂Ă���ƁA���̐��Ɉ���߂��݂Ȃǂ���͂����Ȃ��Ǝv���Ă����B�l�X�����R�̐������ɂ����Ėڂ������āA���Y��Ă��������i�F�߂�A���̐��̈���߂��݂͂����Ə��Ȃ��Ȃ�͂���v�i�o.�P�V�S�j �G�h�}���h�̃��[�h�̂������̂ł��傤���A�w�m�[�T���K�[�E�A�r�[�x�̃L���T��������[�����h�̂悤�ȃS�V�b�N�����̋��\���E�ɓ��荞��ł��܂��̂Ƃ͈���āA���Ԓm�炸�ŗ��z��`�I�ȃ^�e�}�G��f�p�ɐM���Ă���Ƃ��������i�ł��B ���̂悤�Ȗ��������ȃt�@�j�[���A�|�[�c�}�X�Ƃ����������E�̒��ɕ��荞�܂�邱�ƂŁA�T�[��g�}�X�������ʂ�Ɏ��Ƃɂ��肵�A��������������Ă����̂ł��B�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ŏ�ɑa�O���𖡂���Ă��镪�����t�@�j�[�́A�{���̋��ꏊ�ł�����Ƃւ̎v���͔M��ł��B�ޏ����u�Ƒ��݂̂�Ȃ���A���܂܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��قǂ����Ղ�ƈ������̂��B���̕s�����������Ȃ��Ƒ��̈���������A�����͎����̉Ƒ��Ƃ܂������Γ��Ȃ̂��Ɗ����v�i�o.�T�U�U�j�邱�Ƃ��v���`���A���S�n�ɂȂ�̂ł����A�ޏ��̕`����������闝�z�I�Ƒ����ւ̌��z�͖��c�ɑł��ӂ���邱�ƂɂȂ�܂��B ���N�Ԃ肩�ɋA�������t�@�j�[�́A���̗��e��햅�����Ƃ̍ĉ���ʂ����A���炭�ނ�Ɛ��������ɂ���킯�ł����A����͔ޏ����g�̊��҂ɔ����A������̌��ł͂Ȃ������̂ł��B�v���C�X���������Ɏ����݂ŁA�吺�ň��Ԃ����A�e��ʼn��i�ȕ��e�ł��邩�B�v���C�X�v�l�������Ɉ�������A�s���s���ɖv���������́A���\�ȕ�e��������́A���e�Ɏ��]�����t�@�j�[�̖ڂ�ʂ��āA�˂��������悤�ɕ`����Ă��܂��B�܂��A�N���̒햅�����̐g�Ȃ肪�s���ł݂��ڂ炵�����܁A�Ƃ̒������X�����A�������y���������Ă��邳�܂Ȃǂ��A�t�@�j�[�̖ڂ��Ƃ����ĕ`����A�ޏ��������ɋ���������A�_�o���܂��肫���Ă��邩������������B�ƒ��̎҂��݂ȗ��������Ȃ��A�N�����t�@�j�[�ɑ��Ė��S�ł��邱�Ƃɑ��Ă��A�ޏ��͎��]��������̂ł��B �t�@�j�[����a�����o����̂́A����Ɉ�Ƃ̐l�X�ɑ��Ă����ł͂Ȃ��A�Ƃ̋��ꂵ����Ƌ�̕n�コ�Ƃ����������I���ɑ��Ă��A�ς��������v���𖡂킢�܂��B �����L�т��̂ŁA���܂͂낤�����͕K�v�Ȃ������B�������ނ܂ł܂��ꎞ�Ԕ�����B�|�[�c�}�X�ɗ��Ă�������O�����������̂��ƁA�t�@�j�[�͂��炽�߂Ďv�����B���Ԃɍ������ދ����������́A�t�@�j�[�𖾂邢�C�����ɂ�����ǂ��납�A�܂��܂��J�T�ɂ����B�s��Ɠc�ɂł́A���z�̌����܂������Ⴄ���̂Ɍ��������炾�B�s��̑��z�́A�����܂Ԃ��������ŁA���������ꂵ���Ȃ�悤�ȕs���Ȃ܂Ԃ����ŁA�����Ȃ���݂��Ȃ��悲���ق����ڗ������邾���������B�s��̑��z�ɂ́A���N�I�Ȋ��������邢�������S���Ȃ������B���ꂵ�����炬�炵�����ƁA�ӂ�ӂ�ƕY���ق���̂Ȃ��Ƀt�@�j�[�͍����Ă����B�����Ĕޏ��̖ڂ́A���e�̓����̃V�~�������ǂ���A�킽���������炯�ɂ����e�[�u���ւƂ��܂�����B�e�[�u���̏�ɂ́A��x�����ꂢ�ɐ�������Ƃ��Ȃ����~�A�@�������Ƃ̋��c���Ă���g�����q�ƎM�A�����āA���x�b�J�������Ă����Ƃ��������������ׂƂׂƂ��Ă����o�^�[�t���p�����u����Ă����B�i�o.�U�V�U�j ���Ԃɋ�����������������ŗ����Ƃ��A�t�@�j�[�͋C�������邭�Ȃ邩���ɁA�܂��܂��J�T�ɂȂ�܂��B�z���̌��ʂ������A�c�ɂƓs��Ƃł͈Ⴄ�̂��Ƃ����悤�ɁA�Ⴂ����������܂��B�ނ��ނ��Ƃ���悤�ȔM�C�ƁA���̕����Ȃ��ɍ���Ȃ���A�t�@�j�[�́A���e�̓����������Ăł����ǂ̐Ղ�A�킽�������������H��A�s���Ȃ��~�A�@�������ȏ�ɂȂ����J�b�v��M�A���̕������~���N�A�o�^�[�łׂ��ׂ��Ƃ����p���Ȃǂ�ڂŒǂ���i�ł��B�I�[�X�e�B���́A�s������e�͂Ȃ������яオ�点��Ƃ��������̈��������ʂ��A�����I�ɕ`���o���A���̂܂Ԃ����ɑς�����Ȃ��������t�@�j�[�̐_�o�̕a���w�I���ۂ����A���X�e�B�b�N�ɕ`�������܂��B�����ł́A�t�@�j�[�ɂ���ďœ_�����ꂽ���̂悤�Ȍ��̕���������A�ޏ��̎��Ƃɑ��錙�����ɂ�������a�����A�����яオ���Ă���̂ł��B �t�@�j�[�͌��ǁA�|�[�c�}�X�̎��Ƃւ̗��A��Ƃ����̌����o�āA���̂悤�ɁA�}���X�t�B�[���h�����A���⎩���ɂƂ��Ă͐^�̃z�[���Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�F������Ɏ���܂��B ���ꂪ���A�肵���킪�Ƃ̎p�������B�t�@�j�[�Ƀ}���X�t�B�[���h��p�[�N�̂��Ƃ�Y�ꂳ���Ă���āA�G�h�}���h�̂ЂƂ����₩�ȋC�����ōl����悤�ɂ����Ă����͂��́A�킪�Ƃ̎p�������B�������Ńt�@�j�[�́A�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̂��Ƃ�Y���ǂ��납�A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ƁA�����ɏZ�ނ��Ƃ����l�����A�����̍K���Ȑ����̂��Ƃ����l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���܂���䂪�Ƃƃ}���X�t�B�[���h��p�[�N�́A�����牽�܂Ő����������B�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̏�i���A��V�������A�K���������A���a�������Ă��̕��a�ƐÂ������A�₦���t�@�j�[�̓��ɕ����B�܂�A�����Ɛ����̂��̂��A�|�[�c�}�X�̉Ƃ��x�z���Ă��邩�炾�B�i�o.�T�X�X�j �}���X�t�B�[���h�E�p�[�N��G�h�}���h���狗����u�����Ƃ����t�@�j�[���g�̈Ӑ}�ɂ�������炸�A�ޏ����|�[�c�}�X�Ŕ��������̂́A���̑����ƕs��@�A�����̐��E�Ƃ͑ɂɂ���A�}���X�t�B�[���h�̗D��ŗ�ߐ��������a�̐��E�ɂق��Ȃ�Ȃ��������Ƃ��A���̕��͖͂��炩�ɂ��Ă��܂��B�����Œ��ڂ������̂́A�t�@�j�[���u�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ƁA�����ɏZ�ނ��Ƃ����l�����A�����̍K���Ȑ����v�ƌĂԂƂ��A���̉����������E���\������̂́A�G�h�}���h�ЂƂ�ł͂Ȃ��A�o�[�g�����Ƃ̖��������܂܂�Ă��āA�m���X�v�l�������O����Ă��Ȃ����Ƃł��B�������A�t�@�j�[�́A��e�ł���v���C�X�v�l�̓m���X�v�l�����A�ʂ̗`�ɂ̂����o�[�g�����v�l�ƁA�C�������Ă���B�������A�v���C�X�v�l�́A���̐����ɂ���āA�v���Ɍ����s���ȏ����ւƕi�ʂ𗎂Ƃ��Ă��܂����Ƃ����悤�ɁA�t�@�j�[�͕�e���O�ɕ��͂��炵�Ă��܂��B ����ɃI�[�X�e�B���́A���̍�i�ŁA�g������̑��Ⴊ�A�l�Ԃ�l�ԊW��ς��Ă��܂����Ƃ��A������������i�߂ĕ`���Ă��܂��B�Ⴆ�A�|�[�c�}�X�ɑ؍ݒ��A���A���[����̎莆���͂����Ƃ��A�t�@�j�[�͎��̂悤�ɔ������܂��B �ޏ�����莆�����Ȃ��Ȃ�ق��Ƃ��邾�낤�Ǝv���Ă����t�@�j�[�̗\�z�͊Ԉ���Ă����B�����ł��A�t�@�j�[�̋C�����ɂ����ւ�ȕω����������̂ł���I�܂�A�t�@�j�[�́A�v���Ԃ�Ƀ~�X��N���t�H�[�h����莆��������āA�ق�Ƃ��ɂ��ꂵ�������̂ł���B���܂������ď㗬�Љ��Ǖ�����āA���܂܂ŊS�̂��������ׂĂ̂��̂���藣����Ă݂�ƁA�����̐S���Z��ł������E�ɑ�����l���痈���莆�A����������ƁA������x�̏�i����������莆�́A�ق�Ƃ��ɂ��ꂵ�������B�i�o.�U�O�P�j ����قnj������Ă������A���[����́A���܂�~�����Ȃ��Ǝv���Ă����莆����ɂ����t�@�j�[�͊������v�����̂ł��B�|�[�c�}�X�̂悤�Ȉِ��E�ɂ���ƁA���A���[�͂ނ��듯���Ƃ������ƂɂȂ�A���ΓI�Ɋi�グ����Ă���̂ł��B�ނ���A���̐��E�Ƃ̊W�Ɍq���Ƃ߂Ă������̂Ƃ��đҖ]�����̂ł��B�����ł́A�t�@�j�[�ɂƂ��ẮA�ϗ��I�Ȋ�����A�ނ���K���I�Ȋ�̂ق����A�l�Ƃ̋���������Â�����傫�ȗv���ƂȂ��Ă���킯�ł��B���́A�t�@�j�[���g�̖��������ȗ��z��`���A���̂悤�ȊK���I�Ȋ�̏�ɗ����Ă������Ƃ��A���炩�ɂȂ��Ă���̂ł��B����́A�ޏ����|�[�c�}�X�ł̐����𑱂��邤���ɁA�����ł��v���m�炳���̂ł��B ����Ȏ��A�w�����[���ˑR�|�[�c�}�X��K�˂ė��܂��B�t�@�j�[�́A�������ь������A������f��������̒j�����A�͂邩�ɐg���̗�鎩���̕n�������Ƃ�K�˂Ă����Ƃ��A�����̐g����p����̂ł��B ���̎U���̓t�@�j�[�ɂƂ��ẮA�����ւ�ȋ�ɂƍ����̘A���ƂȂ����B�Ƃ����̂́A�O�l����ʂ�ɏo���Ƃ��e�ɏo��������炾�B�����͓y�j���Ȃ̂ŁA�v���C�X���̐g�Ȃ�́A������肢���������炵�Ȃ������B�v���C�X���͗����ǂ܂����B�a�m�ɂ͒��������e�����A�t�@�j�[�̓N���t�H�[�h���ɕ��e���Љ�Ȃ��킯�ɂ͍s���Ȃ������B�N���t�H�[�h�������e�����Ăт����肷��̂͊ԈႢ�Ȃ��ƃt�@�j�[�͎v�����B�N���t�H�[�h���͒p���������ƕs�����ɏP���āA�����Ɏ��̂��Ƃ�������߂āA���ƌ����������ȂǂƁA������ۂ������v��Ȃ��Ȃ�ɈႢ�Ȃ��B�i�o.�U�P�U�j �t�@�j�[�́A�݂��ڂ炵���g�Ȃ���������i�ȕ��e���A�w�����[�Ɉ������킹�邱�Ƃɑ��āA�ɓx�̋�ɂƍ��f���o���܂��B���݂̂��ڂ炵�����т�p���Ă��邾���łȂ��A�a�m�łȂ��e���A�a�m�Ɍ�����̂��p���������āA�ł��邱�ƂȂ�e�q�ł��邱�ƉB�������Ƃ����t�@�j�[�̊K���ӎ��̕\��Ƃ��A���߂ł��܂��B�܂��t�@�j�[�́A�w�����[�������Č��C�������A�����ƌ����������Ƃ����C���Ȃ��Ȃ邾�낤�Ɨ\�z����ƁA�ς��������C�����ɂȂ�̂ł��B����́A�{���ł���A�t�@�j�[�ɂƂ��Ė]�܂������ʂł���͂��Ȃ̂ɁA�ł��B����܂Ŋ�Ȃ܂łɎ����̉��ʂ����Ȃȃt�@�j�[�̎p�����Ă����ǎ҂Ƃ��ẮA���̊��ɋy��Ńw�����[�Ɍ��h�肽����ޏ��̂Ȃ��ɁA�����⑭������F�߂邱�Ƃ��\�ł��B �t�@�j�[�͗c������e�Ɏ̂Ă�ꂽ�悤�Ȃ��̂ŁA�a�O�������������Ă����̂ł����A���̗��A��Ƃ����̌����o�āA�t�ɔޏ��̂ق����A���������]�������e���A�S���I�Ɍ��̂āA���Ƃ�a�O�����Ƃ������܂��B�����Ă݂�ΐe����ł��B�����Ƃ��t�@�j�[���g���A�������������̊������ɑ��āA�߂̈ӎ���@�����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�������A��������L���Ȋ��Ɋ��ꂽ�҂��A�n�����≺�i���ɑ��Ċ������a���͂ǂ����悤���Ȃ��ƌ����܂��B�l���u�Ă���̑���Ƃ����ǂ́A���Ƃ��ď��z���������ꍇ������Ƃ������ƂɁA���̍�i�͖ڂ�w���Ă��܂���B �����ŁA�t�@�j�[�̎��ȔF���̉ߒ��͑�ϊɂ₩�ł������Ƃ������̂ł��B�I�[�X�e�B���̑��̍�i�A�Ⴆ�w�����ƕΌ��x��w�G�}�x�ł̓q���C��������u�ԂɌ��I�Ȏ��ȔF����o�����o������悤�ɂ͂����܂���B�t�@�j�[�̌����͏�ɐ������T�܂��₩�ł���A����̎�����⍂������p������悤�ɔ��Ȃ����ɂ��邱�Ƃ͌����Ă���܂���B������������u�����łł����Ă��A�Љ���Ȃ��ɂ͂��̌��ł��͉��̈Ӗ��������炳�Ȃ��B�ꌩ��̑ł����̂Ȃ��t�@�j�[�ł����A�I�[�X�e�B���̂ق��̏���l���Ɠ��l�Ɍ����Љ�̔F�����ď��߂āA�t�@�j�[�͎��Ȃ����ߒ������Ƃ��ł��邽�킯�ł��B�l�ƎЉ�̊W�A�Љ�̒��̈���Ƃ��Ă̌̑��݁A�����̔F���Ȃ��ɂ͎��Ȃ̐����͂��肦�Ȃ��B�t�@�j�[�̎��ȔF���ɂ́A�����������z�I�ŗ��z��`�I�X���̂��錉�Ȃ�����A�����Љ�̐������̎�e�ւƁA�ω����Ă����܂��B�����ɂ́A�������g��Ƒ��ɑ����O�Ȋώ@�ƔF�߂����Ȃ�������F�߂Ă�����ꂽ�Ƃ����ꂳ�������܂����B ���̂悤�ȃt�@�j�[�̕ω��́A�|�[�c�}�X�ł̕Ǐ̒��ɂ����āA����܂łł���A�Ђ�����ς��E��ŏ�����҂Ƃ����g�̎p���ɏI�n�����͂��̂��̂���A���C�Ȑ��i���ە����āA�̉��P�Ɍ����čs�����N�����Ƃ������Ƃɕ\���܂��B�t�@�j�[���Ƒ���|�[�c�}�X�̂��Ă̒m�荇���l�X�̂Ȃ��ŁA�B��A�������̖��̃X�[�U���ɈԂ߂����o���܂��B�t�@�j�[�͓�T�Ԃ����āA�X�[�U����T�d�Ɋώ@���A�ޏ��̓v���C�X�Ƃ����Ƃ����P���������ƌǗ������̐킢�����Ă��邱�ƂɋC�Â��܂��B�����Łu�t�@�j�[�ɂ͏��߂Ă̌o�������A�������l������A��������������ł���ȂǂƎv�������Ƃ��Ȃ����A�Ƃɂ����A�X�[�U���ɂƂ��ǂ�������^���Ă����悤�ƌ��S�����B�����āA�u�݂�Ȃɂǂ��������Ƃ����Ă�����ׂ����B�����ɂƂ��Ă������Ȃ��Ƃ͂ǂ������Ƃ��v�Ƃ������ƂɊւ��鐳�����l�������A�X�[�U���̂��߂Ɏ��H���悤�ƌ��S�����B�v�i�o.�U�O�V�j�t�@�j�[���A�����łƂ��čs���́A�X�[�U���ƃx�b�c�C�̃y���i�C�t�̒D���������������邽�߂ɁA���̃x�b�c�C�Ƀy���i�C�t���Ă��A�X�[�U���������̂��̂ł������y���i�C�t�����Ԃ���悤�Ɍv�炢�܂��B���ׂȂ��Ƃł����A���̂��Ƃɂ���ăt�@�j�[�̓X�[�U���̑��h�ƐM���āA�ޏ��ɑ݂��{���̖{����Ă��A���j�������A�ޏ������炵�A���P�ɋ��͂���̂ł��B �t�@�j�[���w�����[��N���t�H�[�h���狁�����ꂽ����ŁA�ޏ��̈�Ԃ̌��O�ł������G�h�}���h�ƃ��A���[�̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B�����A���Ԃ�k��܂����A�G�h�}���h���q�t�ƂȂ��ĕ��C����\�[�g������C�V�[����}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɖ߂����Ƃ��i�ޏ��͂��łɃw�����[����v���|�[�Y����Ă��܂����j�A��l�̌�����A���[�ɂ��āA�t�@�j�[�̌��O�Ƃ��āA���̂悤�ɏ�����Ă��܂��B �~�X��N���t�H�[�h�ƃG�h�}���h�Ƃ̌����́A���܂ňȏ�ɏ����ɐi�݂���悤�Ȃ̂��B�G�h�}���h�̓~�X��N���t�H�[�h�Ƃ̌������܂��܂������]��ł��邵�A�~�X��N���t�H�[�h�̂ق����A�ȑO��肸���Ɛ^���ȋC�����ɂȂ��Ă����悤�������B�G�h�}���h�ɂƂ��Ă̏�Q�A�܂荂���Ȑ��_���琶���邽�߂炢�́A���͂₷�������菜���ꂽ�̂��͂悭�킩��Ȃ��B�����āA�~�X��N���t�H�[�h�́A�����Ƃ��������̖�S�ɂ�������^���Ɩ������A�����悤�ɍ������ꂽ�悤�������B�������A�Ȃ��������ꂽ�̂��́A��͂�悭�킩��Ȃ��B���݂��̈���������Ƃ��������悤���Ȃ��B�G�h�}���h�̑P�ǂȐS�ƁA�~�X��N���t�H�[�h�̈������S�����S�ɋ������̂ł���A���̗��S���ӂ�������ѕt�����Ƃ��������悤���Ȃ��B�G�h�}���h�́A�\�[�g���E���C�V�[���ł̗p�����ς݂����������h���֍s���\�肾�B���Ԃ��T�Ԉȓ��ɍs�����ƂɂȂ邾�낤�Ɣނ͌����Ă������A���̂��������ꂵ�����Ɍ����Ă����B�����ă����h���Ń~�X��N���t�H�[�h�ƍĉ��A�ǂ��������ƂɂȂ邩�A�t�@�j�[�ɂ͂悭�킩���Ă����B�G�h�}���h�͊ԈႢ�Ȃ�������\�����݁A�~�X��N���t�H�[�h�͊ԈႢ�Ȃ��������邾�낤�B�ł��A�~�X��N���t�H�[�h�̈������S�͂��̂܂c�邾�낤�B�t�@�j�[�͂�����v���Ɣ߂����Ȃ����B�����̂��Ƃ͕ʂɂ��Ă��A�����A�����̂��Ƃ͕ʂɂ��Ă��ق�Ƃ��ɔ߂����Ȃ����B �~�X��N���t�H�[�h�͍Ō�̉�b�ŁA�₳���������A�S�̂��������e������������ǁA�~�X��N���t�H�[�h�͂�͂�~�X��N���t�H�[�h�Ȃ̂��B�{�l�͋C�����Ă��Ȃ����A���ɖ������������S�̎�����ł���A�ق�Ƃ��͈ł̒��ɂ���̂ɁA�����ł͌��̒��ɂ���Ǝv������ł���̂��B�~�X��N���t�H�[�h�̓G�h�}���h�������Ă��邩������Ȃ����A����ȊO�̊���ł́A�G�h�}���h�ɂӂ��킵�������ł͂Ȃ��B���̂ӂ���̊Ԃɂ́A���S�ȊO�ɂ͋��ʂ̊���͂Ȃ��ƁA�t�@�j�[�͊m�M���Ă���B������ޏ��������v�����Ƃ��Ă��A���ɂ����̌��l�����͋����Ă���邾�낤�B�܂�A�t�@�j�[�͂����v�����̂��B�u�~�X��N���t�H�[�h�̐S�����シ��\���͂قƂ�ǂȂ��B���݂��ɂ���ȂɈ��������Ă���Ƃ��ł����A�G�h�}���h�́A�~�X��N���t�H�[�h�̔��f�͂̓܂���ʂ����Đ������l���ɓ������Ƃ��ł��Ȃ��̂�����A���Ƃ��ӂ��肪�������Ĉꏏ�ɕ�炵�Ă��A�G�h�}���h�̑P�Ȃ�S�͋���邾�����낤�v�ƁB�i�o.�T�U�P�`�T�U�Q�j �u�G�h�}���h�̑P�ǂȐS�ƁA�~�X��N���t�H�[�h�̈������S�����S�ɋ������v�Ƃ��A�ނ̋���������Ă��u�~�X��N���t�H�[�h�̈������S�͂��̂܂c�邾�낤�B�t�@�j�[�͂�����v���Ɣ߂����Ȃ����B�v�Ƃ����悤�ȕ\���ɂ́A���A���[�̐S���u���v�ƒ���������t�@�j�[�̌������[�I�ɕ\��Ă��܂��B�u�~�X��N���t�H�[�h�̓G�h�}���h�������Ă��邩������Ȃ����A����ȊO�̊���ł́A�G�h�}���h�ɂӂ��킵�������ł͂Ȃ��v�A�u�~�X��N���t�H�[�h�̐S�����シ��\���͂قƂ�ǂȂ��v�Ƃ����悤�ɁA�t�@�j�[�͏�݂�����悤�Ɍ������ْf�������B���G�ɑ���ޏ��̔ᔻ�́A�e�͂̂Ȃ����̂ł��B�����ɂ́A���i���瑞���ɂȂ��ꂱ��ł����A�t�@�j�[�̋�������M���܂��B�I�[�X�e�B���́A���̕��͂��t�@�j�[�̎��_����ޏ��̓��S�̐��̒��ژb�@�荞��ŁA��ϓI�ȏ����������Ă��܂��B�܂�A�����ł́A�����͂ǂ��Ȃ̂��ł͂Ȃ��A�t�@�j�[�́A�ǂ������Ă���̂��A�Ƃ������Ƃ�����̒��S�ɂȂ��Ă��Ă���̂ł��B �����ŁA�w�����[��N���t�H�[�h���|�[�c�}�X�̃v���C�X�Ƃ�K�˂���̃��A���[����̎莆��ǂ�A�t�@�j�[�͂ӂ���̌����̌����݂ɂ��āA�v�����߂��点�܂��B ���̎莆��ǂ�ŗB��͂����肵�����Ƃ́A�G�h�}���h�ƃ~�X��N���t�H�[�h�̌����Ɋւ��ẮA����I�Ȃ��Ƃ͂܂������N�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B�i�����j�t�@�j�[�̓��Ɉ�Ԃ��т��ѕ����l���͂����������B�~�X��N���t�H�[�h�̓����h���̐����ɖ߂��āA�G�h�}���h�ɂ������鈤���߂āA�C�������������������Ȃ����A���ǂ͈ȑO�̈����݂������āA�G�h�}���h�Ƃ̌�����������߂���Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��B�~�X��N���t�H�[�h�́A�����̐S�������ȏ�ɖ�S�I�ɂȂ邾�낤�B���߂������A���炵����A�������o������A���낢��ȗv�����o�����肷�邩������Ȃ����A���ǂ̓G�h�}���h�̃v���|�[�Y������邾�낤�B���ꂪ�t�@�j�[�̓��Ɉ�Ԃ��т��ѕ��������������B�����h���ɉƂ����H�܂�������͕s�\���낤�B�ł��~�X��N���t�H�[�h����A�ǂ�ȗv�����o�����킩��Ȃ��B�G�h�}���h�̏����͂܂��܂��Â��Ȃ���肾�B��������������j���ɂ��āA�e�p�̂��Ƃ����b���Ȃ������Ȃ�āI�����A�Ȃ�Ă܂�Ȃ�����낤�I�~�X��N���t�H�[�h�́A�G�h�}���h�Ɣ��N���e���������������Ă����Ƃ����̂ɁI�t�@�j�[�̓~�X��N���t�H�[�h�̂��Ƃ��p���������Ȃ����B�v�i�o.�U�R�X�`�U�S�O�j �u�~�X��N���t�H�[�h�́A�����̐S�������ȏ�ɖ�S�I�ɂȂ邾�낤�B���߂������A���炵����A�������o������A���낢��ȗv�����o�����肷�邩������Ȃ����A���ǂ̓G�h�}���h�̃v���|�[�Y������邾�낤�B�v�Ƃ����\�z�ɂ́A�t�@�j�[�������Ƀ��A���[���������ׂ��l�Ԃ��Ǝv���Ă��邩���A���肠��ƕ\��Ă��܂��B�u��������������j���ɂ��āA�e�p�̂��Ƃ����b���Ȃ������Ȃ�āI�����A�Ȃ�Ă܂�Ȃ�����낤�I�v�Ƃ�������B�����ɂ́A�G�h�}���h�̒l�ł����킩���Ă���͎̂��������Ȃ̂ɁA���A���[�ɔނ�����̂͂��������Ȃ��Ƃ��������������ݏo�Ă��܂��B �����ł́A������j�����A������艿�l�̂Ȃ��Ǝv���Ă��鏗���ɗ����邳�܂��A�����ƌ��Ȃ���ς��˂Ȃ�Ȃ��t�@�j�[�̋�Y���J��Ԃ��`���Ă��܂��B���̂Ȃ��ł��A�t�@�j�[�̋�Y�����_�ɒB���������́A���̂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B�I�Ջ߂��A�G�h�}���h���A���A���[�ɑ���Y�܂����Ȏv���������Ԃ����莆���A�t�@�j�[�ɑ����Ă��܂��B�����ɂ́A�u�Ƃɂ����t�@�j�[�A�ڂ��̓~�X��N���t�H�[�h�Ƃ̌�����������߂邱�Ƃ͂ł��܂���B�ޏ��́A�ڂ����ȂƂ��čl������B��̏����ł��B�v�i�o.�U�S�U�j�Ƃ����悤�ȍ��������q�ׂ��Ă���B�����ǂt�@�j�[�̔����́A���̂悤�ɕ`����܂��B �u�������A�莆�Ȃ�Ăق����Ȃ��B������x�Ǝ莆�Ȃ�Ăق����Ȃ��v�t�@�j�[�͎莆��ǂݏI����ƁA�S�̒��ł����ς�ƌ������B�i�����j�ޏ��̓G�h�}���h�ɑ��ĕ��������A�s�����Ɠ{����o�������ɂȂ����قǂ������B�u�v���|�[�Y����������ɂ��Ă��A�����Ȃ�Ȃ���v�ƃt�@�j�[�͐S�̒��Ō������B�u�Ȃ������͂����肵�Ȃ��̂�����H�G�h�}���h�͗��ɖڂ������ŁA���������Ȃ��Ȃ��Ă����B�N���������悤�ƁA�ނ̖ڂ��J�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ���B����Ȃɒ����Ԑ^����ڂ̑O�ɂ��Ă���̂ɖڂ��o�߂Ȃ���ł����́B�G�h�}���h�̓~�X��N���t�H�[�h�ƌ������āA����ł݂��߂Ȉꐶ�𑗂��B�ޏ��̈��e���ŁA�G�h�}���h�̕i�i�܂ŗ����邱�Ƃ�����܂���悤�ɁI�v �t�@�j�[�͂�����x�莆�ɖڂ�ʂ����B�u�~�X��N���t�H�[�h�͎��̂��Ƃ���D���ł����āH�Ƃ�ł��Ȃ���B�ޏ��������Ă���̂́A�����Ƃ��Z��������B�i�����j�u�ޏ��́A�ڂ����ȂƂ��čl������B��̏����ł��v�����A�����ł��傤�ˁB�G�h�}���h�����̈���Ɉꐶ�x�z������B�v���|�[�Y��������Ă��f���Ă��A������ɂ��Ă��A�G�h�}���h�̂���͉i���Ƀ~�X��N���t�H�[�h�ƌ��т��Ă����B�u�~�X��N���t�H�[�h�������Ƃ������Ƃ́A�w�����[��N���t�H�[�h�ƃt�@�j�[�������Ƃ������Ƃł��v�������A�G�h�}���h�A���Ȃ��͎��̂��Ƃ��킩���Ă��Ȃ���B���Ȃ����ނ��茋�т��Ȃ���A�w�����[��N���t�H�[�h�Ǝ��͐�Ό��т����Ƃ͂Ȃ���B�����A�ǂ�ǂ�莆�������Ă��������B�����đ������ׂďI���ɂ��Ă��������B���̒��Ԃ���̏�Ԃ𑁂��I���ɂ��Ă��������B�������f���čs�����āA���������̉^�������߂Ă��������v�i�o.�U�T�P�`�U�T�Q�j �����ł́A�t�@�j�[�̐S�̎v���́A���ژb�@�Ŏ�����Ă��܂��B�u�������A�莆�Ȃ�Ăق����Ȃ��B������x�Ǝ莆�Ȃ�Ăق����Ȃ��v������͒Z�����t�ł����A��]�I�Ȏ����Ə��S�A���ł����߂�ꂽ�\���ł��B�����Ńt�@�j�[�͏��߂āA�G�h�}���h�ɑ��āA�s�����Ɠ{����o����B�u�Ȃ������͂����肵�Ȃ��̂�����H�G�h�}���h�͗��ɖڂ������ŁA���������Ȃ��Ȃ��Ă����B�N���������悤�ƁA�ނ̖ڂ��J�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ���B����Ȃɒ����Ԑ^����ڂ̑O�ɂ��Ă���̂ɖڂ��o�߂Ȃ���ł����́B�G�h�}���h�̓~�X��N���t�H�[�h�ƌ������āA����ł݂��߂Ȉꐶ�𑗂��B�ޏ��̈��e���ŁA�G�h�}���h�̕i�i�܂ŗ����邱�Ƃ�����܂���悤�ɁI�v�ƁA�������Ȏv����f���o���Ă��܂��B������j�����A����̏�������Ƃ��n�ɓ˂����Ƃ����t�@�j�[�̋�Y�́A����ȂƂ���܂ōs���Ă��܂��܂��B ���������̂��ƁA����Ȏ莆�ł��A��͂�t�@�j�[�ɂ͗L���悤�Ɏv���Ă���B�������Ė����������A�ǂ����Ă����S���̂Ă���Ȃ��t�@�j�[�̐S�̂��܂��悭�`����Ă���Ǝv���܂��B ����́A�t�@�j�[���A����܂ł̎g�̖T�ώ҂��玩��I�ȍs���ɂ����͂�ς��邱�ƂɋC�Â��A���ȕϊv�𐋂������Ԃɂ����āA���̂��Ƃ����o���Ȃ�����A�|�[�c�}�X�Ƃ������u�n�ɂ��邽�߂ɁA�����ł͉����s�����N�����Ȃ��ł������Ǝv���܂��B����́A�҂��Ă��邵���Ȃ������ȑO�̃t�@�j�[����A�s�����N�������Ƃ��ł��鎩���ɕς�����Ƃ��ɂ́A���̍s�����y�ʂƂ���ɃG�h�}���h������Ƃ����A����܂ł̃t�@�j�[�ł͊����邱�Ƃ̂Ȃ��������͊��ɁA�����ő���ꂽ���䂦�ɁA����������������ɂ��邱�ƂɂȂ����ƍl�����܂��B�܂�A�ȑO�̃t�@�j�[�ł���A���߂Ă������Ƃ��A������ς�����̃t�@�j�[�͒��߂���Ȃ��Ȃ��āA�����Ō����������f���o�����ƂɂȂ����ƍl�����܂��B���ꂾ���A�����ł̃t�@�j�[�̌���̓G�h�}���h�ւ̎����Ƃ�������v�����A�����������Ԃ��Ȃ��āA�s�����Ƃ��ă��A���[�����łȂ��G�h�}���h�ɂ��Ԃ��Ă��܂��B���̂悤�ȁA������l���Ɏ����ȊO�̏����������ł����Ԃ��A�����͎莆�Œm�邱�Ƃ����ł��Ȃ��Ƃ���Ƀq���C����u���Ƃ����V�`���G�[�V�����́A�I�[�X�e�B���͍D���Ȃ悤�ŁA�w�����x�̃A����G���G�b�g���E�F���g���[�X�̏�Ԃ���̎莆�Œm��܂��B�܂��A�w���ʂƑ����x�̃G���m�A��w�m�[�T���K�[��A�r�[�x�̃L���T�����́A����Ƃ͉����͂Ȃ�Ē��O�Ǝ��]�̓��X���߂����܂��B�ޏ������́A�t�@�j�[�ƈ���āA����������ɑ����邱�ƂȂ��A���O�̂Ȃ��ŐÂ��ɐ�]�I�ȉ^�����e��悤�Ƃ��Ă��܂��B�����ɁA�t�@�j�[�E�v���C�X�Ƃ����l���̃��j�[�N��������Ǝv���܂��B�������A���̂V�T�O�y�[�W�̏����̂Ȃ��ŁA�U�T�O�y�[�W������܂Ői��ŁA�͂��߂ăt�@�j�[�͌����S�J�ɔ�����̂ŁA����܂ł͊����\�ɏo���Ȃ��A���ƂȂ��������Ƃ��Ă��葱����킯�ŁA�ޏ��̃C���[�W�͍Ō�̂P�O�O�y�[�W�ł͂Ȃ��A�O�̂U�T�O�y�[�W�Ō��߂��Ă��܂��Ă���̂ł��B �t�@�j�[������̋��菊�ƂȂ�ꏊ���͂�����ƔF�����A���z��`�I�ŊϔO�I�ȍl�������O���C���������Ƃ��A�ޏ��͍ĂіT�ώ҂̗���ɒǂ������邱�ƂɂȂ�܂����B�������w��Ŗ�p�����ɋN����̂ł����A�ޏ��͎��X�ɑ����Ă���莆�̓ǂݎ�̗���ɗ�������A�|�[�c�}�X�̎��ƂłЂƂ�C���킵���ɐ���s��������邾���Ȃ̂ł��B����́A�g���̗��n�ɂ�����Ǝ����Ȑ����𑱂������Ƃɂ���Đg�̂��Ă��܂������ƁA�}���C�A�ƃw�����[��N���t�H�[�h�̕s�`���ʂɂ��o�z���Ă��܂������ƁA�����ăW�����A�ƃC�F�C�c���삯�����������ƂȂǂł��B���̈�A�̎����̓t�@�j�[���}���X�t�B�[���h��p�[�N�̐����ȏZ�l�Ƃ��āA�㗬�K���Ɍ}���������𐮂��邽�߂̉������̖������ʂ����Ă���ƌ����܂��B�g���A�}���C�A�A�W�����A�Ƃ������o�[�g�����Ƃ̎q�ǂ��������s�s�ՂŒE�����Ă��������Ƃɔ���Ⴗ��悤�ɁA���ΓI�Ƀt�@�j�[�̉��l���ω������킯�ł��B����́A���_��ς���A�t�@�j�[�����z�I�Ȑ��_��`���猻�����Î������������ւ̕��݊������߂���悤�ɁA�g������Y���d������T�[��g�}�X�́u���Ԓq�v���̂��傫�Ȏ����ɂ��炳��A�O���C�������߂��邱�ƂɂȂ�̂ł��B �ŏ��́A�g�������n��������̎蓖�Ă������ɕ����𑱂��Đ��サ���������ɁA�a�C�ƂȂ����Ƃ������Ƃ��A�o�[�g�����v�l����̎莆�Œm��܂��B�o�[�g�����v�l�͑��q�̐S�z�ƕs���̈Ԃ݂����߂āA�t�@�j�[�ɖ�p�����Ɏ莆�������܂��B���t�@�j�[�̓g���ƃo�[�g�����v�l��S�z���Ȃ���A�����̂悤�Ɏ莆�������Ă��邱�Ƃ��A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ƃ̐S���J��[�߂Ă����܂��B����A�v���C�X�Ƃ̐l�X�̓o�[�g�����ƂɌ`����̓���������݂̂ŁA�t�@�j�[�̋C�����𗝉��ł����A�t�@�j�[�̋C�����̓v���C�X�Ƃ��痣��Ă����܂��B����A�o�[�g�����Ƃł̓g���̊ŕa���Ƃ߂���̂̓G�h�}���h�Ƃ����Ȃ��̂ŁA�t�@�j�[�͎������}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�ɖ߂�A���ɗ��������Ƃ�����̓I�Ȏv�������܂�܂��B���ۂɁA�����ł���A��̓I�ɍv���ł��邱�Ƃ�������̂ɁA���ꂪ�ł��Ȃ��Ƃ����ő��������킯�ł��B�����炭�A�G�h�}���h��T�[��g�}�X�́A����ȂƂ��Ƀt�@�j�[�����Ă��ꂽ��Ǝv�����낤�A�ƃt�@�j�[�͕������Ă��邾�낤����A���X�ł��B �O�����O�Ƀ|�[�c�}�X�ɋA���Ă����Ƃ��A�t�@�j�[�́A�|�[�c�}�X�̎��Ƃ��u�킪�Ɓv�ƌĂсA�u�킪�ƂA��̂��v�Ƃ��ꂵ�����Ɍ����Ă����B�u�킪�Ɓv�Ƃ������t�́A�t�@�j�[�ɂƂ��Ă͂ƂĂ���Ȍ��t�������B�����Ă��܂ł���Ȍ��t�����A���������܂́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ������Ďg���錾�t�ɕς���Ă��܂����B���܂̃t�@�j�[�ɂ́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N���킪�ƂȂ̂��B�|�[�c�}�X�̎��Ƃ͂����܂ł����Ƃł���A�}���X�t�B�[���h��p�[�N���킪�ƂȂ̂��B�ЂƂ�łЂ����ɕ��v���ɂӂ���Ƃ��A�t�@�j�[�͂��������ԑO����A�}���X�t�B�[���h��p�[�N���킪�ƂƌĂԂ悤�ɂȂ��Ă����B�����āA�t�@�j�[�̐S���������Ԃ߂Ă����̂́A�o�[�g�����v�l���莆�̒��œ������t�Â��������Ă��邱�Ƃ������B �u��������Ȃɔ߂����炢�v�������Ă���Ƃ��ɁA���Ȃ����Ƃ𗯎�ɂ��Ă���Ȃ�āA�ق�Ƃ��Ɏc�O�łȂ�܂���B���Ȃ�����x�Ƃ���Ȃɒ����ԉƂ𗯎�ɂ��Ȃ����Ƃ����͐M���A�肢�A�S����]��ł��܂��v�i�o.�U�U�R�j ���̂悤�Ƀt�@�j�[�́A�������^�ɏ������ׂ��ꏊ�͎��Ƃł͂Ȃ��}���X�t�B�[���h��p�[�N�ł��邱�Ƃ��͂�����Ǝ��o���܂��B�W�N�Ƃ����Ό����o�߂��邤���ɁA�����̒��Ƀ}���X�t�B�[���h��p�[�N�̈���ł���Ƃ������o���A�t�@�j�[�̍s�������͋����A��莩�M������̂ɕς��Ă��������ƂɁA�t�@�j�[�͎��o�I�ɂȂ�܂��B ���������킪�Ɓi�܂�}���X�t�B�[���h��p�[�N�j�ɂ���A�݂�Ȃ̖��ɂ����Ƃ��ł��邾�낤�B�K���݂�Ȃ̖��ɗ����Ƃ��ł��邵�A�݂�Ȃ̓����̘J�͂��Ȃ��Ă����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B栂����ꂪ�A�o�[�g�����v�l�̋C�������x���āA�₵���点�Ă����邱�Ƃ����������Ƃ��Ă��A���邢�́A�����Ƒ傫�ȕs�K�A�܂�A�����̑��݊������߂邽�߂ɂ��낢��Ȋ댯���֒��������ȁA�m���X�v�l�̐₦�ԂȂ����߉��A�o�[�g�����v�l������Ă����グ�邱�Ƃ����������肵�Ă��A�����}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɂ��邱�Ƃ́A�݂�Ȃ̖��ɗ����낤�B�o�[�g���ƕv�l�̂��߂ɖ{�̘N�ǂ�������A�b������ɂȂ�����A���݂̍K����������菕����������A�����̏o�����ɑ���S�̏����̎菕���������肷�邱�Ƃ��ł��邾�낤�B����ɁA�o�[�g�����v�l�̊K�i�̏オ�艺����̖ʓ|���Ȃ��Ă����āA��������̓`����v�l�ɑ����ē`���Ă����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�����������Ƃ��v���ƁA�t�@�j�[�͂ق�Ƃ��ɂ��ꂵ���Ȃ����B�i�o.�U�U�T�j ���̂悤�Ƀt�@�j�[�̎v���́A��̓I�ȍs�ׂ����̂ŁA�������Ē��ۓI�Ȋ���ɂƂǂ܂���̂ł͂���܂���B���ꂾ���A�����Ɏ��Ԃ̂�����̂Ƃ��āA�}���}�t�B�[���h��p�[�N���ޏ��̐S�ɂ���܂��B����́A���ۓI�Ȃ�������ƂȂ��āA���ۂɂ��Ă݂���A���ł��Ă��܂����|�[�c�}�X�̎��Ƃɑ���v���Ƃ͂܂������قȂ���̂ł��邱�Ƃ��A�����ŕ�����܂��B ����̌��n���猾���A�����Ŏ莆�Ō�����A�̎����́A����Ƀh���}�`�b�N�ȏ�ʂ����o���f�ނł��B���ꂪ�����Ƃ����Ă͂܂�Ⴊ�A�}���C�A�ƃw�����[��N���t�H�[�h�̏o�z�́A���ꂾ���ŏ����ɂȂ�悤�ȃG�s�\�[�h�ł��B�������A����܂ŁA�W�����A���܂����Ă̎O�p�W��A�T�U�g���E�R�[�g��f�l�ŋ��ł̃G�s�\�[�h�ȂǂŁA��l�̌o�܂��A����܂ŋ����[�����グ�Ă��Ă��܂����B�������A���̃N���C�}�b�N�X�ɂȂ�ׂ��o�z���A�V���L���ɂ���ĕ\�킳��A���A���[�̎莆�ɂ���ĊT�����������邾���ŁA���̑���Ȃ��v���l�������̂łȂ��ł��傤���B�Ⴆ�A�i�{�R�t�́A���̂悤�ȃI�[�X�e�B���̏������ɂ��āA���ȑ̂Ɉˑ��������ȂP�W���I�̒��я����̗l���ւ̑ލs�ł���Ƃ��ĒQ���Ă��܂��B�������A�����̃G�s�\�[�h���ڂ��������Ă��܂��ƁA�������ꂪ�A����ɒ����Ȃ��Ă��܂��璷����������Ȃ����A�`�����ɂ���Ă̓����h���}�I�A���I�ɂȂ肩�˂܂���B���̂��߂ɁA�t�@�j�[�̑��݂�����ł��܂����ƂɂȂ�܂��B����ŁA�����Ŏ��������X�Ƃ����݂�����悤�ɁA����̏I�ՂɋN���邱�ƂŁA�����̓W�J�ɉ����x�����Ă������ʂ����o���Ă���Ǝv���܂��B�܂��A�I�[�X�e�B���́A�w�����ƕΌ��x�ł̓G���U�x�X�̖����f�B�A���삯�������������ɂ��Ďo����̎莆�Ō���Ă��܂��B�I�[�X�e�B���̓T�u��L�����N�^�[�̎������莆�ŊԐړI�ɕ`���Ƃ�����@���D��ł�����������܂���B����́A����̒��̎����ƁA���ꂪ�\������邱�Ƃœǎ҂��m�邱�ƂƂ̍������o���āA�����̎�@�Ƃ��Ĉӎ����Ă����I�[�X�e�B���炵�����ƂƎv���܂��B �t�@�j�[�́A�v���C�X������ǂ�ł����V���̒��ɁA���b�V�����X�v�l�i�}���C�A�j���w�����[�E�N���[�t�H�h�Ƌ삯���������L�������o�������Ƃ��������܂��B���ꂾ���ł����낵���X���ŁA�t�@�j�[�͐M�����Ȃ��ł��܂����A����Ɉ������ƂɁA�����h���ɂ���G�h�}���h����A�}���C�A�̋삯�����ɉ����ăW�����A���C�F�C�c���Ƌ삯���������Ƃ����莆���ǂ��ē͂����܂��B�������A���̎莆�̓t�@�j�[�Ƀ}���X�t�B�[���h��p�[�N�ւ̋A�҂����߂�莆�ł�����܂����B���̎莆��ǂݏI�����t�@�j�[�́A���̂悤�ɕ`����Ă��܂��B �������藎������ł����t�@�j�[�A���܂قNj��s�܂��K�v���Ǝv�������Ƃ͂Ȃ��������A���̎莆�قNj��͂ȋ��s�܂͂Ȃ��Ǝv�����B�Ȃ�ƁA�����|�[�c�}�X�����邱�Ƃ��ł���̂��I�݂�Ȃ��s�K�Ȃ̂ɁA��������яオ�肽���قǍK���ɂȂ�댯������ƁA�t�@�j�[�͎v�����B�݂�Ȃ̕s�K���A���ɍK���������炵�Ă��ꂽ�̂��I����ł́A�s�K�ɂ������Ė����o�ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƁA�ޏ��͐S�z�����B����Ȃɂ����Ƀ}���X�t�B�[���h�p�b�N�ɖ߂��̂��B�������o�[�g�����v�l�̈Ԃߖ��Ƃ��āA����Ȃɐe�Ɍ}������̂��B�������Ȃ�ƁA���̃X�[�U����A��čs�����܂ŗ^����ꂽ�̂��B����Ȃɂ������̍K�����d�Ȃ��āA�t�@�j�[�͊�тŋ����M���Ȃ�A��u������ꂵ�݂��������������̂悤�Ɏv���A�������Ɏv���Ă���l�����̋ꂵ�݂��ꏏ�ɕ������������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B�i�o.�U�W�R�j �t�@�j�[�́A�����̐l�������s�K�Ȏv�������Ă���Ƃ��A���������̂����Ȃ��K���Ɋ����邱�Ƃ��댯�ł���Ǝ��o�����A�l�X�ɂƂ��Ă̈����A�����ɂƂ��Ă͊�������̂��ƁA�v�킸�ɂ͂����Ȃ��̂ł��B�Ƃɂ����}���X�t�B�[���h�ɋA���A��������\�ȑҋ��ŁA����A��ād�d�Ɨ��_�𐔂��グ�Ă���ƁA�u�t�@�j�[�͊�тŋ����M���Ȃ�A��u������ꂵ�݂������������v�Ƃ����悤�ɁA�܂��ɍK���̐Ⓒ�ɂ���悤�Ȃ̂ł��B�l�X���s�K�ɒ���ł���Ƃ��A�K���̐Ⓒ�ɂ̂ڂ�߂�Ƃ����̂��A�t�@�j�[�̏����̌`�Ƃ����܂��B���̂悤�ȗ͊w�I�\���̂��Ƃɔz�u���ꂽ����l���ł���Ƃ���Ȃ�A�s������̃t�@�j�[�̃C���[�W�́A�^���̕������݂ɔ����Ĉꎞ�I�ɕ\��o�����̂ɂ����Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ邩������܂���B �A��R���q�̓A�E�o�b�n�̎咣�����p���Ȃ��玟�̂悤�Ɍ����܂��B�h�j�[�i�E�A�E�o�b�n�́A���̂悤�ȗ͊w�I�\���ɒ��ڂ��A�t�@�j�[���A�˂ɃA�E�g�T�C�_�[�Ƃ��ė��܂�u�Z�����j�[�ɊQ�������炷�ҁA�Ƒ��̕���̂��Ɓv�ł���ƌ��Ȃ��āA�ޏ������}����`���w����������A�w�t�����P���V���^�C���x�̉����Ɉ�����ׂ���A�u�H�ו����D�܂��A���l�̊�����S�łނ��ڂ�t�@�j�[�̌X���v���A�z���S�ɂȂ��炦�������Ă���B�u�t�@�j�[�������v���́A���������s���߂��̊ς�Ƃ�Ȃ����A��i�̑啔���Ŏ����I���݂ɗ��܂��Ă���t�@�j�[���A�͋����G�l���M�[���߂��l���ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���_�ł́A�����[���B�t�@�j�[�ɋ������o���邩�́A�ǎ҂̍D���D�����B���������Ȃ��Ƃ��A�ޏ��������������T�܂��������́u�ʔ����̂Ȃ���l���v�łȂ����Ƃ́A�f�����Ă��悢���낤�B�h�i�A��R���q�w�[�ǂ݃W�F�C����I�[�X�e�B���x�o.�Q�Q�W�j�j �t�@�j�[���A�G�h�}���h�A�X�[�U���Ɣn�Ԃ̒��ŁA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�������Ă����Ƃ��̕`�ʂ́A����܂łقƂ�Ǖ`����Ă��Ȃ������}���X�t�B�[���h��p�[�N�̕��i����ۓI�Ɍ���܂��B����́A�܂�Ń}���X�t�B�[���h��p�[�N���t�@�j�[�̊�тɂ���ċP���Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�ǎ҂ɗ^����̂ł��B �t�@�j�[�́A�c�ɂ̌i�F����������ς���Ă��邱�ƂɋC�����Ă����B�|�[�c�}�X���������̂���Ƃ͂���Ⴄ�̂��B�����āA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̍L��ȕ~�n�ɓ����Ă䂭�ƁA�ޏ��̊��o�͂܂��܂��s�q�ɂȂ�A���̊�т͍ō����ɒB�����B�ޏ����}���X�t�B�[���h��p�[�N�������Ă���A�O�����A�ێO�������������̂��B�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̍L��ȕ~�n�́A�~�̌i�F����Ă̌i�F�ɕς�����̂��B�t�@�j�[�͂�����Ƃ���ŁA�Œn��X�̂����₩�ȐV�ɖڂ�D��ꂽ�B���͂܂���������t�ŕ����Ă���킯�ł͂Ȃ����A���܂܂��ɂ��̂��炵����Ԃɂ������B�܂�A������������������Ȃ邱�Ƃ��͂�����Ɗ������A�������łɔ������i�F���ڂ̑O�ɂ���̂����A����ɔ������i�F������҂̑z���͂̂��߂Ɏc����Ă���Ƃ����A���̂��炵����Ԃɂ������B�������A���̊�т̓t�@�j�[�ЂƂ肾���̂��̂������B�i�o.�U�W�W�`�U�W�X�j �������A�t�@�j�[�̍K���͒P���}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɖ߂��Ƃ������Ƃ����ł͂���܂���B�ЂƂ́A�w�����[��N���t�H�[�h���猋���̐\���݂������ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B���ꂾ���łȂ��A�t�@�j�[�������̐\���݂����Ƃ������Ƃ����������f�ł��������Ƃ����炩�ɂȂ����킯�ł��B����́A�����ł́A�t�@�j�[�Ɍ��������������߂��T�[��g�}�X�̔��f�̌��ł�����܂����B�ނ̔��f�̌��̍��{�I�Ȍ����́A�}���C�A�ƃW�����A�̂ւ̉߂��ɂ����т����̂ł����B�ނ́A�}���C�A�̌����ɍۂ����A�u�}���C�A�����b�V�����[�X�������Ă��邩�ǂ��������A���b�V�����[�X�Ƃ̒n�ʂƍ��Y�ɖڂ��s���Ă��܂��A�o�[�g�����Ƃ̗��v�Ɛ��ԑ̂������l���āA���̌�����F�߂Ă��܂����v�i�o.�V�P�Q�j�Ƃ������f�̌��ł��B���̍��{�ɂ́A�����s��ŏ����ł����K�I�ɗL���Ȍ������ł���悤�ɁA�������̋�������������Ƃɂ���܂����B����Ȃ�����������ŋ��{��m����|����g�ɂ������܂����B�������A�̍قƊO�ʂ��d�āA�������ɕ\�ʓI�ȋ���������A�l�i�`���Ɉ�ԑ�Ȃ��̂�g�ɂ������鋳���ӂ����̂ł��B ���ʓI�ȋ��炪�����Ă����̂��B�����łȂ���A���̌��̈��e���́A���������傫���Ȃ�ɂ�Ĕ��ꂽ�͂����B�T�[��g�}�X�͂����v�����B�}���C�A�ƃW�����A�ɂ́A�l�ԂɂƂ��Ă�����d�v�ȓ����S�A�܂�A�����̐����Ŕ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������S�������Ă����̂��B�}���C�A�ƃW�����A�́A�����̋C�����₫����Ɛ��i�𐧌䂷�邱�Ƃ̑�����������Ȃ������̂��B�l�ԂƂ��Ă̋`������������Ǝ��o���Ȃ���A�����̋C������i��������Ɛ��䂷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B�}���C�A�ɂ��W�����A�ɂ��A�@���I�ȋ���͎{�������肾���A������̐����Ŏ��H���邱�Ƃ������Ȃ������̂��B�Ⴂ�����ɂƂ��đ�Ȃ��Ƃ́A�������ꂽ��V��@��g�ɂ��A�s�A�m��G��O����ɏG�ł邱�Ƃ��ƍl���A���̋���͂�������{�������肾���A���ꂾ���ł́A�l�Ԃ̓����S�ɗL�v�ȉe�����y�ڂ����Ƃ͂ł��Ȃ����A�l�Ԃ̐S�ɓ����I���ʂ������炷���Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B�T�[��g�}�X�́A�}���C�A�W�����A�𗧔h�Ȑl�ԂɈ�Ă����Ǝv�������A���̋���́A�����ɒm�͂Ɨ�V��@�Ɍ������A�l�i�`���ɂ͌������Ȃ������̂��B�}���C�A�ƃW�����A�́A�����S�〉�����̏d�v���ɂ��ẮA�N������L�v�ȏ�����^�����Ȃ������̂ł͂Ȃ����ƁA�T�[��g�}�X�͎v�����B�i�o.�V�P�T�`�V�P�U�j �������A�I�[�X�e�B���̓}���C�A�ƃW�����A�ɂ��āA�t�@�j�[�Ƃ͉��̉������E�ŋN���������ƂƂ͍l���Ă��܂���B���̎����̂��������́A�t�@�j�[�Ȃ̂ł��B�w�����[�E�N���[�t�H�h�̓t�@�j�[�ւ̑z������߂�ꂸ�A�|�[�c�}�X�܂ł���ė��āA�ޏ��̎��ƂɍD�ӂ������Ă��炨���Ɠw�߂܂����B�������A��������ʂ��������Ƃ����킯�łȂ��A�ނ̓t�@�j�[�ւ̈��������ꂸ�A�Ƃ��ς₵�āA�Ƃ��Ƃ������h���̃E�B���|�[���X�ł̕��������ɂ��ǂ��Ă��܂��U�f�ɕ����Ă��܂��܂��B���̍s�������悪�C�}���C�A�Ƃ̋삯�����ł����B�}���C�A�̑�߂������W�����A���܂������̐g����������邱�Ƃ�|��A�C�F�[�c���ƃX�R�b�g�����h�삯���������̂ł����B�t�@�j�[���w�����[������Ȃ��������Ƃ́A���W�ł͂Ȃ��̂ł��B�A��R���q�̏Љ���u�t�@�j�[�������v���́A����ȂƂ��납�琶�܂�Ă���Ǝv���܂��B �t�@�j�[�ɉ��������}���C�A�ƃw�����[��N���t�H�[�h�̏o�z�́A����ɃG�h�}���h�ƃ��A���[��N���t�H�[�h�̌����̘b������Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B�o�[�g�����ƂƂ��ẮA�����}���C�A�ɒp���������A���b�V�����[�X�ƂƂ̊W���Ԃ����N���t�H�[�h�ƂƂ͕t�������Ȃ��Ƃ������R���ЂƂB�G�h�}���h���g���A���A���[�̃w�����[��N���t�H�[�h�̎��Ԃɑ��ĂƂ����ԓx�Ɏ��]���āA�ޏ��Ƃ̌�����������߂�̂ł��B���Ƃ��I�������ŁA�G�h�}���h�̓t�@�j�[�Ɏ��̂悤�Ɍ��܂��B �v����ɔޏ��́A�ӂ��肪�n���Ȃ��Ƃ������ƌ����ē{���Ă���B���̂ӂ��肪�������Ƃ́A�ޏ��ɂƂ��Ă͂����́u�n���Ȃ��Ɓv�ɂ����Ȃ��B�܂�w�����[�́A�����Ă����Ȃ������̗U�f�ɏ���āA�ق�Ƃ��Ɉ����Ă��鏗���������H�ڂɂȂ�悤�Ȕn���Ȃ��Ƃ������ƁA�ޏ��͂��������ăw�����[������B�i�����j�~�X��N���t�H�[�h�͍���̎������A�P�Ȃ���s�Ƃ������Ă��Ȃ��B����������́A�I������������s�ȂB�܂�A�T�d���Ɨp�S����ӂ����̂������������Ƃ������Ƃ��B�����Ղ̋x�ɒ��A�}���C�A���g�E�B�b�P�i���ɑ؍݂��Ă����Ƃ��A�w�����[�������߂��̃��b�`�����h�ɑ؍݂��Ă����B�����Ăӂ���̊W�����g�Ɋ��Â���Ă��܂����B�v����ɁA���g�Ɋ��Â��ꂽ�̂��܂��������Ƃ������ƂȂB�����A�t�@�j�[�I�~�X��N���t�H�[�h�����Ă���̂́A�p�S��ӂ��ď��g�Ɋ��Â��ꂽ���Ƃł���A�ޏ��́A�ӂ��肪�Ƃ����߂���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�v�i�o.�V�O�P�`�V�O�S�j �u�p�S����ӂ����v�Ƃ��u�I������������s�Ȃv�ƌ����Ă��܂��C�v����ɏ��ɕ��C������ӂ���͋�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��킯�ł��B�G�h�}���h�́A�u�v�̂��鏗�����ق��̒j���Əo�z����Ƃ����s�����ȍ߁v�Ƃ��āA�f�߂��ׂ��Ƃ�����A���̂悤�ȗϗ����̂Ȃ���焈Ղ��Ă��܂��A���A���[��I�Ԃ̂͊ԈႢ�ł��邱�ƂɋC�Â��܂��B�G�h�}���h�́A�ʂ�̌��t�ɑ��ă��A���[�������Ƃ��u�ڂ��𐪕����邽�߂ɒ������Ă���悤�ȁA�s�ސT�Ȃ���������ۂ��قق��݂������v�i�o.�V�O�X�j�Ƃ܂Ƃ߂Ă��܂��B�}���I�ɂ܂Ƃ߂Ă݂�ƁA����̒��ŁA�}���C�A�Əo�z�����w�����[�ƁA�G�h�}���h��U�f���悤�Ƃ��Ď��s�������A���[�̃N���t�H�[�h�Z���́A�����h���Ќ��E�̋����␢���q�ɂ���āA���Ԃ�m��Ȃ������ȃo�[�g�����Ƃ̎q�ǂ�������U�f���A������������������Ă���悤�Ɍ����܂��B����ɑ��āA��т��ē����I�ɐ������p�����т��t�@�j�[���A�G�h�}���h���͂��߃o�[�g�����Ƃ��~���Ƃ������P�����̃X�g�[���[�ł��B�Ƃ����قǁA�P���őދ��ȏ����ł͂Ȃ��ł��傤�B���̃��A���[�ɂ��Č�����ʂł����A�I�[�X�e�B���́A�����ł́A���A���[�ɂ��Ă̋L�q�̓G�h�}���h�̔����Ƃ��Ē��ژb�@�ŏ�����Ă��܂��B���̃G�h�}���h�̕��������t�@�j�[�ł��B�����Ń��A���[�ɂ��Ă̌��́A��l�̎�ϓI�Ȃ��̂Ȃ̂����B����ɂ��q�ϓI�Ȍ��ł͂Ȃ��̂ł��B�G�h�}���h�͎����̑�������킯�ł����爤�����ł��傤���A�t�@�j�[�̓��A���[�������Ă��܂��B ����ɁA����̓ǎ҂��炷��A���A���[�ɂ���w�����[�ɂ���f�߂����قǕs�������Ɩ����A�������Ƃ͒f�������˂�̂ł��B����́A�����炭�I�[�X�e�B���ɂ��A������x�������Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ނ���A����̐����Ƃ��āA�t�@�j�[��G�h�}���h�͕ێ�I�ȓ����̗���ŁA�N���t�H�[�h�Z���͑�s����h���ɏے������o�ϐ����̐V���s���̑O�G��Ƃ�������悤�ȗ���ł��B���̏����͎��オ�ς�낤�Ƃ��Ă���ŁA�}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ƃ����`���I�ȑ���������̔g�ɍR���ď]���̐���������낤�Ƃ���b�Ƒ����邱�Ƃ��ł��܂��B �q���C���ł���t�@�j�[�́A�ޏ��ȊO�̓o��l�������ꂼ��̗~�]�ɂ����ĉE���������钆�ŁA�ޏ��ЂƂ肪�����I�D�ʐ����������A�����Ɨ��܂��Ă���B���������̑㏞�͔ޏ����s���Ɏ���⎶�ӁA����△���ł���A�[���ǓƊ��ł��B����ɂ�������炸�t�@�j�[�͌����Č�����s�������邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ�����l���ł��B����́A�}���I�ȏ����̊��P�����̃q���C���ł���A�ǎ҂ɂ́u�Ƃ肷�܂������������U�P�҂Ɋւ��ĉ�X�������Ă���C���[�W���ň��̌`�ŋ�������l���v�Ƃ��u���Ȗ����Ǝ����S�̉����v�Ƃ���������������ꍇ�����肤����̂ł��B�����ŁA��҂ł���I�[�X�e�B���́A�t�@�j�[���ꌩ�����̃R���_�N�g�E�u�b�N���甲���o���ė������̂悤�ɏ]���ōT���߂Ȑl���Ɏd���Ă��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ŏI�I�ɂ́A�t�@�j�[�́A�҂��]���肩�狁������A�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̏���l�ƂȂ�܂��B�ޏ��́A������ΏۂƂ��̎���̐��E���Ђ����猩�߂Ȃ���҂�������킯�ł��B�ޏ��́A���̉ǖقȓO�ꂵ���g�Ɏp���ɁA��������Ȃ����̑傫�ȒɎ�����}���X�t�B�[���h��p�[�N�̐l�������A�ޏ��̒��ɔޓ��̗ǂ�������A�ǂ������҂Ƃ��đS�Ă���e���悤�Ƃ���ޏ����g�̖{�������o���Ă����ɂ��������āA�ޏ��̐^�������炩�ɂȂ��Ă����A�ޏ��̑��݊����傫���Ȃ��Ă������ƂɂȂ�̂ł��B����́A����̒��ł��A�ŏ��͑��݊��ɖR�����T�ώ҂̃X�^���X�ł������ޏ����A�f�l�ŋ��ł̐U������{�l�̐����Ȃǂő��݂����͂���F�߂���Ȃ��Ă���ƁA�w�����[����̋����̔����A�ʂ̈Ӗ��ŖT�ώ҂ɂȂ��Ă����Ƃ����ޏ��̃}���X�t�B�[���h��p�[�N�ł̋�̓I�ȃX�^���X�ɂ��\���Ă��܂��B�t�@�j�[�̍K���́A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�̐l�X�̑���ȋꂵ�݂̒��œ���ꂽ���̂ł�����̂ł��B�G�h�}���h���t�@�j�[�ւ̋C�����ɑ��鈤���Ȃւ̈���ւƕϗe�����Ă����̂��A�ނ����A���Ƃ̕ʂ�̋�Y��ޏ��Ɍ��s�����ߒ���ʂ��Ăł��B�t�@�j�[����ɓ����K���̔w��ɂ́A�}���C�A�̃}���X�t�B�[���h��p�[�N����̒Ǖ��A�T�[��g�}�X�̐S�ɂƌ���A�G�h�}���h�̃��A���Ƃ̕ʂꓙ�A��Y�ƒɂ݂��B����Ă���B���������āA����̃n�b�s�[�G���h�Ɍ�����I�������A��a�������̂ƌ����܂��B ������A����̔ނ�̍s�����͏��������ł���Ƃ́A������Ȃ��Ƃ��낪����܂��B�G�h�}���h�́A�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̖q�t�Ɏ��܂�܂��B����ŁA�t�@�j�[�ƃG�h�}���h�́A�����Ƃ��Ƀ}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̒����̎��҂ƂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A���̃}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�̏������l����ƁA�T�[�E�g�}�X�����̐�����������A�����҂̃g���������l�ƂȂ�A�����̌o�c���茘����������Ƃ����ۏ�͂���܂���B�����āA��Ƃ̎�v�Ȏ������ł���A���e�B�O�A���̃v�����e�[�V�����́A���\�̃g���ɐ萷��ł���Ƃ͂Ƃ��Ă��l�����܂���B�܂��C���������C�v�����e�[�V�����o�c���̂��z��f�Ղ̏�ɐ����������o�ςł��B�q�t�v�Ȃ̃G�h�}���h�ƃt�@�j�[�Ȃ�A���̂悤�ȍ߂ޔ_�n�Ǘ��́A���R�Ȃ���������ׂ��s�ׂƂ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�Љ�I�ɂ��z��g�p�̃v�����e�[�V�����̑������K��������̂ƂȂ��Ă����ł��傤�B�܂�A�W���n�̗\�z�������Ă��Ȃ��̂ł��B���ꂾ����a���܂����ɂȂ��Ă���̂ł��B �@��S�W�� ����́A�O�̂S�V�͂܂łŏI���A�Ō�̏͂ł͌���k�̂悤�ɁA���ꂼ��̃G�s�\�[�h�̌������܂Ƃ߂Ă�������E���̂悤�ȂȂ��悤�ł��B���̂悤�Ȉ�߂��A�Ƃ肠�����̑�c�~�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����Ŏ��ƌ����Ă���͍̂�҂̂��Ƃł��傤�B �킪�t�@�j�[�́A���낢��Ȃ��Ƃ�����������ǁA�Ƃɂ������̂Ƃ��͍K���������ɂ������Ȃ��B���ꂾ���͎��������ł���B�ޏ��͂܂��̐l�����̋ꂵ�݂ɓ���A���Ȃ��Ƃ������ł͓���Ă���Ǝv���Ă������A�����͂����ւ�K���������ɂ������Ȃ��B���R�ɗN���o���т̌������������炾�B�܂�A��D���ȃ}���X�t�B�[���h��p�[�N�ɖ߂�A�݂�Ȃ̖��ɗ����A�݂�Ȃ����ɂ���A�����N���t�H�[�h���ɔY�܂����S�z���Ȃ��Ȃ������炾�B����ɁA�T�[��g�}�X�̓����h������߂��Ă���Ƅ����̂Ƃ��̗��������_��ԂŎ��������ɂ����Ă������N���t�H�[�h���̃v���|�[�Y��f�����t�@�j�[�̐����������炽�߂ĔF�߁A����܂ňȏ�̈���������Ă��ꂽ�̂ł���B�����������Ƃ��t�@�j�[���K���ȋC�����ɂ����ɂ������Ȃ����A�����������Ƃ��Ȃ��Ă��ޏ��͍K���������낤�B�Ȃ��Ȃ�G�h�}���h�̖ڂ��o�߂āA�����~�X��N���t�H�[�h�ɂ��܂����S�z���Ȃ��Ȃ�������ł���B �������G�h�}���h�́A�K���Ƃ͒�������Ԃ������B�ނ͎��]�ƌ���ɋꂵ�݁A���݂̏�Ԃ�Q���A���͂��ɂ��蓾�Ȃ����Ƃ�]��ł����B�t�@�j�[�́A�G�h�}���h�̂��̋C�������킩��̂Ŕ߂��������B���������̔߂��݂́A�傫�Ȗ�������y��ɂ��Ă���A�����Ɉ��炩�ȋC�����ɕς�邱�Ƃ��ł������A������₳��������ƒ��a���Ă����B���������߂��݂Ȃ�A�݂�Ȋ��ŁA�����̍ō��ɗz�C�ȋC���Ƃł������������Ƃ��낤�B�i�o.�V�P�P�`�V�P�Q�j �S�D�w�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�x�̑��ʂȖ��� �i�P�j�u�ߌ��v�Ƃ��Ă��}���X�t�B�[���h�E�p�[�N ����܂ŁA���̏����𒀈�ǂ�������悤�ɁA���������d���̋��������̂悤�ɁA�ו��������܂Ō��Ă��܂����B���ʂ�}�������ł������A�Ȃ��Ȃ������͂����Ȃ��āA���̏�����ǂ��Ƃ̂Ȃ��l�ɂ́A���������U���ŁA���������ǂ�ȍ�i�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��ڂ��Ă��܂�����������܂���B����ŁA���x�́A����܂ł̐����܂��āA���̏����̑S�̑�����Ă��������Ƃ������܂��B�������A������Ăق����Ȃ��̂ł����A���̏����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��Ƃ������Ƃ́A�ǂސl�������Ȃ�ɓǂ�ł��邤���ɃC���[�W���Ă������̂Ȃ̂ŁA�Œ�I�ȁA��ΓI�Ȃ����ł���Ƃ����C���[�W��������͂���܂���B�����Œ���̂́A���̂����̈���Љ��Ƃ������x�Ɏ���Ă������������Ǝv���܂��B �@���^�����\���`����ł���Ɠ����Ɋϋq�ł������l���̔����݊� �ŏ��́u�͂��߂Ɂv�̂Ƃ���ŁA�����̕���̂悤���Əq�ׂ܂����B�Ⴆ�A����͂����ς�}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ƃ�������ꂽ�Ƃ���ŁA����ꂽ�l���ɂ���Đi�߂��܂��B�����ǂސl�́A�����̕���̊ϋq�̂悤�ɁA����Ƃ�������ꂽ��ԂŁA�����ɔo�D���o���肷��̂߂�̂ɁA�����̌�������Ƃ������Ƃ��q�ׂ��Ǝv���܂��B����́A����̐i�ݕ��ɂ������邱�Ƃł���܂��B���̏����̎�l���̓t�@�j�[��v���C�X�ł��邱�Ƃ́A���̏�����ǂl�ł���A�ّ��͎�����Ȃ��Ǝv���܂��B�������A���̎�l���́A�قƂ�Ǎs�����܂���B���ʂ̕���ł���A��l�����s�����邱�Ƃŕ��ꂪ�i��ł����̂ł����A���̏����ł́A��l���͂قƂ�Ǒ��҂ɓ��������邱�Ƃ����Ȃ����A���牽�����������A�������N��������Ƃ������Ƃ��܂���B�t�@�j�[��v���C�X�����邱�Ƃ́A�����ς���͂̐l�X���ώ@���邱�Ƃ��炢�ł��B����́A�u�͂��߂Ɂv�ł��w�E�������Ƃł����A��l���ł���t�@�j�[�E�v���C�X������̒��S�ł���ׂ��Ȃ̂ɁA���畨���i�߂邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����قǑ��݂��ł���Ƃ������Ƃł��B�������A�����̌��ɂ����āA��҂̌��ɂƂ�����t�@�j�[���������Ƃ������Ƃ��q�ׂ܂����B����́A�����̒��ł́A�t�@�j�[���s�����Ƃ͂����ς�ώ@���邱�ƂƊ֘A���Ă��܂��B�܂�A�t�@�j�[��v���C�X�́A���̏����̎�l���ł���Ɠ����ɁA���̏����̓o��l�������̍s�����ώ@���Ă���T�ώ҂ł���킯�ŁB����́A�����ł���Ίϋq�̗���Ȃ̂ł��B�܂�A�t�@�j�[��v���C�X�̓}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ƃ�������ɂ��Ȃ���A�����Ől�X���J��L����h���}�̊ϋq�ƂȂ��Ă���̂ł��B����́A����Ӗ��ł͍�҂�ǎ҂Əd�Ȃ闧��ł�����܂��B�����炱���A�t�@�j�[�͍�҂̌��ɉ�����邱�Ƃ��ł���̂ł��B���������āA�t�@�j�[��v���C�X�͏����̓o��l���ł���Ȃ���A���̏����̕���̊O�ɏo�Ă���̂ł��B�O������o��l���������ώ@���Ă���B���̏ꍇ�A�t�@�j�[�͔��������̒��ŁA�����O�ɏo�āA�ǎ҂̑��ɂ���B�����Ɠǎ҂̒��ԓI���݁A���n���̂悤�ȑ��݂Ȃ̂ł��B ���̂悤�ȏ����̎�l���̑��݂́A���̍�i�Ɍ��������̂ł͂���܂���B��l������l�̂Ō�镨�ꂪ�����ł��B���̏ꍇ�ɂ́A��l���ƌ��肪�d�Ȃ�킯�ł��B���̂悤�ȏ����ł́A��l���͂����ΖT�ώ҂̂悤�ɐU�����A�ώ@�������Ƃ����A���ꂪ����ƂȂ�܂��B�Ⴆ�A�h�X�g�G�t�X�L�[�́u�n�������҂̎�L�v�A���邢�̓v���[�X�g�́u����ꂽ�������߂āv�Ȃǂ���\�I�Ȃ��̂ł��B�������A�����ƈ���āA�w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�̓t�@�j�[��v���C�X�̃��m���[�O�Ō���鏬���ł͂Ȃ��̂ł��B�����܂ł��A��҂ɂ���ċq�ϓI�Ɍ���镨��ł��B�������A���̏����̓��قȂƂ���Ȃ̂ł��B������Ȃ����藧�����Ă���̂��A�}���X�t�B�[���h��p�[�N�Ƃ�������ŁA�o��l��������������A�����o��l���ł���t�@�j�[���ώ@���A������܂��ǎ҂�����Ƃ����A�����̕�����݂�Ƃ������Ƃ����q�̂悤�ɓ�d�����������̍\���ɂ���ƍl�����܂��B����Ȍ��t�ɂ�����^�����I�ȍ\���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B ���̍\����������Ղ��o�Ă���̂���W�`�P�O�͂Ŏ�ȓo��l���������T�U�g����R�[�g��K�₵�A�R�`�S�l�̃O���[�v�ɕ�����āA�����̒뉀���U������Ƃ�����ʂŁA����̎��̃t�@�j�[���U���ɔ��ăx���`�ŋx��ł���ƁA�����ɗl�X�ȃO���[�v���ʂ肩����A�t�@�j�[�̖ڂ̑O�Ől�Ԗ͗l��������Ƃ�����ʂł��B�t�@�j�[�̑O�ɁA�}���C�A������Ńw�����[��N���t�H�[�h�ƃ��b�V�����[�X�̂R�l���A�܂�ŎO�p�W�̂悤�Ȕz�u�ł�����A��̌������̒��߂̗ǂ��u�ɍs�����߂ɁA���b�V�����[�X�͍���J���錮�����ɍs�����ߕ��������܂��B�c���ꂽ��l�́A�ނ�҂��ƂȂ���Ɏ���Ƃ��āA�����J����̂ł͂Ȃ��A������z����Ƃ������K�łȂ����@�Ō��������ɋ����Ă����܂��B���̌�ŁA�W�����A���o�ꂵ�A��l��ǂ������ċ����Ă����܂��B�����Ƀ��b�V�����[�X���߂��Ă��āA���c���ꂽ���ƂɋC�Â��B�܂�Ńt�@�j�[�̖ڂ̑O�Ńh���}���������Ă���̂��A�ޏ��͂��̊ϋq�ƂȂ��Ă���̂ł��B�����ŁA�t�@�j�[�i�����j�͎O�p�W�̐l�Ԗ͗l��w�����[��N���t�H�[�h�̕s��������m��̂ł��B���̗l�q�́A�ǎ҂͓ǂ�ł���킯�ł��B�����āA�w�����[��N���t�H�[�h�ƃ}���C�A�̍s�ׂ́A��̓�l�̏o�z�̑O���Ƃ��āA�ǎ҂͓ǂނ��Ƃ��ł��܂��B ���̂悤�ȓo��l����������b�����킷���Ƃ����ژb�@�ŕ`����Ă���̂́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�i�قƂ�ǁA�Ƃ����̂͗�O������Ƃ������Ƃł��B����͗Ⴆ�A�q�t�قł̃N���t�H�[�h�Z���̉�b�ł��B�j�A�t�@�j�[��v���C�X�����Ă���O�ł̏�ʂȂ̂ł��B����ɑ��ăt�@�j�[�̂��Ȃ��Ƃ���ł̉�b�́A�莆�œ`����ꂽ��A�N���̔����̒��Ō��y�����Ƃ����Ԑژb�@�ł����`����Ȃ��̂ł��B�]���āA�ނ�̔����͌����莆�̕��͂łЂƂ̎��_�ŗv��Č���܂��B�Ⴆ�A�G�h�}���h�����A���[�Ɏ��]���ĕʂ�����S����Ƃ��듙�d�v��ʂł���͂��Ȃ̂ɁA�G�h�}���h���t�@�j�[�ւ̘b�̒��ŊԐړI�ɐG����邾���Ȃ̂ł��B������A�G�h�}���h�����Ƃ�������I�Ȏ��_�Ō����̂ł��B�����ɂ́A���̃}���X�t�B�[�h��p�[�N�Ƃ����[���I�ȕ��䂪�A�t�@�j�[��v���C�X�Ƃ����ϋq�Ɍ����邱�Ƃł͂��߂Đ������Ă���Ƃ����\��������悤�ɂ�������̂ł��B�t�@�j�[�����̏����̎�l���ł��邱�Ƃ̈Ӗ��́A���́A�����ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B �ǂ����Ă���ȕ��G�ȍ\���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���B�ǎ҂Ƃ��ẮA����Ȗʓ|�ȍ\�������A�X�g���[�g�ɃG�h�}���h�ƃt�@�j�[�̐���s��������肽���Ǝv���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������l����ɂ́A�t�@�j�[���ϋq�ł���Ƃ��āA�ޏ��̑O�ʼn�������h���}�ɒ��ӂ���K�v������Ǝv���܂��B �A����ʼn���������́`�ߌ��Ő�������n�b�s�[�G���h �t�@�j�[�̑O�ʼn�������h���}�́A���������ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��B�����m��ɂ́A�w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�Ƃ�����������Ă����K�v������܂��B���̏����́A�Ō�̓t�@�j�[���G�h�}���h�ƌ����Ƃ����n�b�s�[��G���h�̌`���Ƃ��Ă��܂����A�S�̂Ƃ��ăn�b�s�[��G���h�ƌ�����̂ł��傤���B����́A�t�@�j�[�ȊO�̓o��l���ɂƂ��Ă͕K�������n�b�s�[�G���h�ɂȂ��Ă��Ȃ��B�Ƃ��������A���̏����Ńn�b�s�[��G���h�ƌ�����I���������Ă���̂́A���Ƀt�@�j�[�����ŁA���̐l���̓A���n�b�s�[���A�A���n�b�s�[�Ƃ͂���Ȃ��܂ł��A�d�����Ȃ��ƒ��߂�悤�ȏɂȂ��ďI�����}���Ă���̂ł��B�n�b�s�[���A�A���n�b�s�[���Ƃ����ƞB���ł�����A�����ƒ[�I�ɂ����ƁA����̊J�n�̎��_���炻�̐l���̒u���ꂽ�����ǂ����̂ƂȂ����̂́A�t�@�j�[�����ŁA���̐l�X�͖v�����Ă��܂�����A���������̂Ƃ��댻��ێ��A�ł������̌��ʂ������邢���Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��B�Ƃ������Ƃ���ł��B��ʓI�ɁA�n�b�s�[��G���h�̕���ł��A�n�b�s�[�ŏI���Ȃ��o��l���͕K�����܂��B�������A���������l���ɂ́A����̒��ł���Ȃ�̌������@�\�I�ɗ^�����Ă��܂��B���̓T�^�I�ȃP�[�X�������ł��B���̏ꍇ�́A�����̕s�K����l���̍K���Ƃ������Ԃ��̍\���ɂȂ��Ă���킯�ł��B���̈����Ƃ����̂́A����̕��̑��ʂ�̌����A�����A��l�����P�ӂŖ��C�ł���̂ɑ��āA�����͕��ł��邱�Ƃ��ӎ����Ď��o�I�ɍs�����܂��B�����āA����䂦�ɁA����ł̕s�K�͈�������g�Ɉ����邱�ƂŁA�߂ł����߂ł����Ƃ��������Ɏ���킯�ł��B������w�}���X�t�B�[���h�E�p�[�N�x�ɓ��Ă͂߂�ƁA���������Ȃ��̂ł��B�����Č����A�N���t�H�[�h�Z�����A����ɋ߂��ł��傤���A�t�@�j�[���G�h�}���h�ƌ���邽�߂ɂ́A���̌Z�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ŁA���ʂƂ��Ă����Ȃ��Ă��邩��ɂ����܂���B�����ɁA�w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�̓��قȂƂ��낪����Ǝv���܂��B�N���t�H�[�h�Z���́A�t�@�j�[���K���ɂȂ邽�߂ɂ́A�s�K�ɂȂ炴��Ȃ��̂ł��B�܂�A�t�@�j�[�̍K���̓N���t�H�[�h�Z���̕s�K�̏�ɐ��藧���Ă���̂ł��B�����悤�ɁA�o�[�g�����Ƃ̎o����T�[��g�[�}�X�Ƃ������l�X���K���ɂȂ����Ƃ�����A�t�@�j�[�̓n�b�s�[��G���h���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B�Ƃ������Ƃ́A�t�@�j�[�͌��ʓI�ɁA���g���K���ɂȂ邱�Ƃɂ���āA���͂̐l�X��s�K�Ɋׂ�Ă���A�����������݂ł�����̂ł��B�����������݂��A�Ӑ}�I�ɍs�����A�����̍K��������������Ƃ�����A�����������݂͕���̒��ł͈����ɂȂ�̂����ʂł��B�����Ȃ�ƁA���̏����͂P�O�ŗa����ꂽ�������P�W�܂ł̊ԂɃo�[�g�����Ƃ�������b�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B����Șb�A�ǎ҂͊��Ŏe���ł��傤���B�����ŁA�t�@�j�[�͖��C�ōs�����Ȃ���l���ł���K�v������̂ł��B�����ŁA�t�@�j�[������Ƃ����ϋq�̂悤�ȑ��݂ł���ׂ����R�̂ЂƂ��A�����ɂ���Ǝv���܂��B ���̂悤�ɍl���Ă݂�ƁA�t�@�j�[�͊ϋq�Ƃ��ăo�[�g�����Ƃ̐l�X��N���t�H�[�h�Z���A���̑��̐l�X���s�K�ɂȂ�Ƃ�������Ă����̂ł��B�ޏ��̖ڂ̑O�ʼn�������͔̂ߌ��ɑ��Ȃ�܂���B �����ŁA�m�F���Ă��������̂ł����A�s�K�Ȍ����ɂȂ邩��ƌ����āA����͔ߌ��ł���Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�A���P�����̕���ň������ł�ł��A���̈����ɂ͔ߌ��ł���ƒN���v��Ȃ��ł��傤�B�ߌ��Ƃ����̂́A���̓o��l���̕s�K�ɑ��āA����҂��u���܂��݂�v�Ɠ˂������̂ł͂Ȃ��āA���̐l�̉^���ɓ����悤�ȗv�f���Ȃ��Ɛ������Ȃ��̂ł��B�����قǁA�w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�ɂ͈������o�ꂵ�Ȃ��Ƃ����܂����B�����炭�A���̒��ōł������ɋ߂��̂̓N���t�H�[�h�Z���ł��B���̌Z��������I���߂��Ŋׂ����ɑ��āA�u���܂��݂�v�Ɖ��Ƃ����Ԑl������ł��傤�B�ł��A�S�����S���ł͂Ȃ��͂��ł��B���Ƃ����āA���̌Z���ɓ����l�͏��Ȃ��ł��傤���A���ׂĐg����o���K�Ƃ����Đ�̂Ă�ɂ��̂тȂ��悤�ȁA�ꕔ�łЂ������肪�c��Ƃ����l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�o�[�g�����Ƃ̎o���̎o�}���C�A�̏ꍇ�͂ǂ��ł��傤�B�ޏ��̃w�����[��N���t�H�[�h�Ƃ̏o�z�͎�������ȉ䂪�Ԃ�������܂���B�������A�ޏ��͔ޏ��Ȃ�Ɉ����т����̂ł���A�ޏ��̍s�ׂ��̂��̂́w���~�I�ƃW�����G�b�g�x�̃W�����G�b�g�Ɠ����ł��B�l�́A�N�ł��K���ɂȂ낤�Ƃ��܂��B���̂��߂ɓw�͂����܂��B���̂��Ǝ��̂́A������߂��邱�Ƃ͂Ȃ��͂��ł��B�������A���̍K���ɂȂ낤�Ƃ��邱�Ƃ��A���ɑ��̐l�̍K���Ƃ��������Ă��܂����Ƃ�����܂��B���̂Ƃ��ɁA���̋��߂�K���Ƃ����̂��������̂��Ԉ���Ă���̂��A�Ƃ����c�_�����܂�܂��B���ꂪ�ϗ��Ƃ������Ƃ��������Ƃ̋N���̂ЂƂł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�K���ɂȂ낤�ƈꐶ�����ȉQ���ɂ���l�́A���X�ɂ��Ă��̂��ƂɋC�Â��܂���B�Ⴆ�A�M���V���ߌ��́w�I�C�f�B�v�X���x�́A���Ƃ��Ă悩��Ǝv�������Ƃ��e�[�o�C�̐l�X�̕s�K�������Ă��܂��̂ł��B���̂��ƂɋC�Â����ނ́A�����Ŏ����̖ڂ�ׂ��āA����Ǖ�����邱�Ƃ�I�т܂��B�ǂ���Ǝv���ēw�߂Ă����������A���͏����̍����ł��������ƂɋC�Â����Ƃ��ɁA�ނ͂���܂ł̂��ׂĂ��Ђ�����Ԃ��Ă��܂��B�����Ȃ������ɐl�́A����܂ł̎����𑱂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B���ꂪ�ߌ��Ƃ����h���}�ł��B�ނ͂悩��Ƃ������đS�͂�s�������B�������ł���ł��傤���B�����A�ނɗ����x���������Ƃ���A�����ł������Ƃ������Ƃł��B�^����m��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B�������A�����̉^����m�蓾��l�Ȃǂ��Ȃ��ł��傤�B������A���̂���Ȃ��Ƃ������Ƃɑ��Č����łȂ������A�܂�͉^���ɑ��Ę����ł������A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B���̂��Ƃɂ����炭�A�ނ͋C�Â����̂ł��B�C�Â������炱���A���̂��Ƃ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����������̖ڂ�ׂ����̂ł��B�����ɁA�l�X�́A�^�������A�ނ̉^���ɓ���A��������A���ꂪ�ߌ��Ƃ������̂ł��B ���̂悤�Ȏ��_�Łw�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�̓o��l�����������Ă݂�ƁA�ǂ��ł��傤���B�����ő��ʂɂ����Ă���N���t�H�[�h�Z���B���̃��A���[�A�Ɛg�����̔ޏ��́A�����̏펯�ɏ]��������������߂Ă��܂��B����͌㔼���̐l���v�̂��߂ɂ͕K�v�Ȃ��ƁA�펯�I�Ȑl���ōK���ɂȂ邽�߂ɂ͓�����O�̂��Ƃł��B���̃^�[�Q�b�g���ăo�[�g�����Ƃ̌Z��Əo�����A�Ƃ��ɃG�h�}���h�Ɏ䂩��Ă����B�����āA�ނƌ������邱�ƂɈꐶ�����ɓw�߂Ă����B���̕��@�́A�ޏ��Ȃ�ō�����M�����肵�܂��B���̂��Ǝ��́A�ޏ��͗ǂ���Ǝv���Ă����Ȃ������Ƃł��B���ɂ́A�G�h�}���h���q�t�ɂȂ邱�Ƃɔ����A�ނ̐l���Ɏx�z������ڂ����Ƃ��܂����A����ƂĔޏ��Ȃ�ɁA�ނɂƂ��Ă悩��Ǝv���Ă̂��Ƃł��B�ޏ��ɐӂ߂��邱�Ƃ��������Ƃ���A�I�C�f�B�v�X���Ɠ����悤�ɁA���ꂪ�ʂ����ăG�h�}���h�ɂƂ��Ă̍K���ɂȂ�̂��Ƃ������Ƃ�m�炸�A�m�낤�Ƃ��Ȃ������������A�����Č����A�����������ƂɂȂ�܂��B �������I�C�f�B�v�X���͎��g�̋�������m��A����Ǖ�����A���ڂ�ׂ��̂ł��B���A���[�́A�����m�炸�A�����Ȃ܂܂ŁA�����߂����J��Ԃ���������܂���B������A�ޏ��͎��g�Œ��ڌ��̂́A�ߌ��ɂȂ�Ȃ��̂ł��B���A���[�̋�������m��̂̓t�@�j�[�����ł��B�]���āA�t�@�j�[�Ɍ���A�ޏ��������������߂����邱�ƂŁA���A���[�́A���߂Ĕߌ����邱�Ƃ��ł��邱�ƂȂ�킯�ł��B�����āA�ǎ҂́A�����ɐ��������Ƃ����ߌ���ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B���A���[�̌Z�̃w�����[��N���t�H�[�h�̏ꍇ�������ł��B�ނ͌y���Ŏ���̗~����}������Ȃ������Ȑl���ł����A���ӂ������Ă���l���ł͂���܂���B���̌��ׂɖ{�l�����͂̐l�X���C�Â��Ă��Ȃ��Ȃ��ŁA�t�@�j�[�������C�Â��Ă���B������A�}���C�A�Ƃ̏o�z�̐^�����t�@�j�[�������m�肤��̂ł��B�t�@�j�[�́A���̏����̎�l���ł��邾���łȂ��A�ޏ������邱�Ƃɂ���āA�o��l���������A�����̒��Ŕߌ��������邱�Ƃ��ł���Ƃ����@�\��S���Ă���Ƃ����܂��B ���̂悤�ȃt�@�j�[���A���̓o��l�������Ɠ����悤�ɔߌ��̉Q���ɂ���Ƃ�����A���̐l�X���ώ@���邱�Ƃ��A�ϋq�ƂȂ��Ă����邱�Ƃ��ł��܂���B�����ŁA�ޏ��͏����̋@�\��A�ǂ����Ă��ߌ��I�ȃh���}���痣��Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B���Ƃ����āA���S�ȖT�ώ҂ł���A�����̒��ɂ���K�v������܂���B�t�@�j�[�����Ȃ��Ă���҂�������Č������̂ł�����B�����ŁA�t�@�j�[�͏����̎�l���Ƃ��ď����̒��ő��݂��Ă������߂ɂ́A�����̒��Ŕޏ��������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�������A���̐l�X�Ƃ��Ȃ��ߌ��̉Q���ɂ��Ă͂����Ȃ��B�����Ȃ�ƁA���̐l�X�Ƃ͈���������������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�A�����̒��ŁA�t�@�j�[�������n�b�s�[��G���h�̌����ɂȂ��Ă���A�ЂƂ̗��R�ł���ƍl�����܂��B �B�Ȃ��ߌ��Ȃ̂� ��肭�ǂ����ƂɂȂ�܂����A�ߑ�̂͂��܂�̎���ŁA���A���Y���ɓ�������Ƃł���I�[�X�e�B���́A�M���V���ߌ��̂悤�Ȑ_�b�̂悤�Ȍ�������V������悤�ȍ�i���������Ƃ͂ł��܂���B�I�C�f�B�v�X���̂悤�Ȕ����_�̂悤�ȃX�[�p�[�q�[���[�������̒��ɓo�ꂳ���Ă����X���������ł��B�I�[�X�e�B���������l�������́A�ǎ҂̎���Ɏ��ۂɎ����悤�Ȑl�����z���ł���悤�ȁA�g�߂Ō����I�Ȑl�������ł��B���������l�������ɁA�M���V���ߌ��̂悤�Ȕߌ������������悤�Ƃ���A�ǂ��������āA����Ȃ�̎d�|�����K�v�Ȃ̂ł��B �ł͂Ȃ��A�I�[�X�e�B���́A����قǂ܂łɖʓ|�Ȏd�|�������Ă܂ŁA�����̒��Ŕߌ������������悤�Ƃ����̂ł��傤���B ����́A��l�̃W�F�C����I�[�X�e�B���̃t�@���Ƃ��Ă̌l�I�Ȗϑz�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�q�ϓI�Ȏ����̍���������킯�ł͂Ȃ��A���������ϓI�ɓǂݎ�����Ǝv�����Ƃł��B�I�[�X�e�B���̏����́A�ǂ���n���̒����̒n��K���̖����L���Ȍ��������߂邱�Ƃ��߂����đ�����������A�Ō�ɂ���Ȃ�̑�����l�����ăn�b�s�[�G���h�ŏI���Ƃ����p�^�[���ł��B��҂ɂƂ��Đg�߂Ȋ�������ŁA���̉ƒ���̏�i��o�ꂷ��l�X���A���ɂ��ׂŘb�������Ă������Ȑ��������Ƃ������A�����ŕ\������Ă��܂��B���ꂪ�ǂސl�ɐe�ߊ���^���A�����̉ߒ��̂����₩�Ȃő������Ȃ��悤�ȃG�s�\�[�h���A�����̃X�g�[���[�Ƃ��čL���ǎ҂��y���܂�����̂ƂȂ��Ă���A�Ƃ������̂ł��B����̏o�����������ƁA�L���ǎ҂����������悤�ɕ`�ʂ��邽�߂ɂ́A���Ȃ�˂����ώ@���K�v�ŁA���ɂ́A����̍s�ׂ��J��Ԃ��Ă���l�ɂ͌����Ȃ��悤�ȋ����[���Ƃ���������o���āA�������邱�Ƃ��������킯�ł��B���̂��߂ɂ́A�I�[�X�e�B���͓O�ꂵ���ώ@�╪�́A���邢�͐[���l�@�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������ƍl�����܂��B�������Ă��邤���ɁA�I�[�X�e�B���́A���͂́A�ӂ��̐l�X�́A���o�����ɂ͂����Ȃ��悤�Ȗʔ�������������o���A����͓����ɂ͂Ȃ������a�V���ł��������A��̐��ł��e����镁�Ր������������̂ł������Ǝv���܂��B�����������̂����ڂ���Ă����̂��A�Ⴆ�A��\��Ƃ����w�����ƕΌ��x�ł��B�������A�I�[�X�e�B���͐l�X�̖ʔ����ʂ��������o�����̂ł��傤���B����͂��܂�ɂ��肪����̂ł͂Ȃ����B�����炭�A�ʔ����Ȃ��ʁA�܂�A�V���A�X�ȖʁA�ߎS�Ō������A�v�킸�ڂ�w�������Ȃ�悤�Ȗʂ����Ă����͂��ł��B�����炭�A�I�[�X�e�B���́A�����ɃM���V���ߌ��̎�l�������ɂ��䌨����悤�Ȑ^�������������Ă����̂ł͂Ȃ����ƁA�Ǝv���܂��B�Ƃ��������A��ނƂ��āA�����������̂�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�������ʂ̐l�X�̐����̒��ɐ^���������āA����̓M���V���ߌ��̂悤�ɒN�ɂ�������悤�Ȍ`�ŕ\���Ă��Ȃ������̂��Ƃł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B�Ƃ������Ƃ́A����Ȃ�̍H�v�����āA�ʏ�ł͌����Ȃ����̂�������悤�ɂ��邱�ƂŁA���̐^���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���A�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B �Ƃ͂����Ă��A�×�����A�����Ȃ����̂��ނƂ��ď����Ă�����Ƃ͂������܂��B�C�M���X���w�ł̓~���g���́u���y���v�̂悤�ɐ����̑�ނ��Ƃ����s��ȏ������̓`��������킯�ł��B�������A�I�[�X�e�B���ɂ́A����͂���Ƃ��āA�����̎��������̐����Ƃ͂������ꂽ�A�������ꂵ�����̂悤�Ɏv�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ۓI�ȊT�O��_�w����j�̒m�����������āA�����Ƃ��炵���c�_������x�z�G���[�g�̐l���������{�Ƃ��Ă��Ă����ԁA�Ɲ����I�Ȍ������ɂȂ�܂����A�P�X���I���͂��܂�������A�ߑ�s�����o�ꂵ�Ă��悤�Ƃ����Љ�̐l�X�ɂ̓��A���e�B�[���A���͂⎝�Ă���̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B�w�Z�ł��₢��ËL��������悤�ȁA���d�����̋��{�Ƃ������猾���߂��������܂��A�����ł͂Ȃ��āA�M���V���ߌ��ł́A�����̎s���������|���X�̖�O����ɏW�܂��āA�����̐l�Ɏe����Ă����킯�ł�����A�]���ƂƓ����悤�ɁA�����̐l�X�Ɏe��Ղ����̂Ƃ��āA���A���X�e�B�b�N�Ȃ��̂��I�[�X�e�B���͍��o�����Ƃ����A���o���邱�ƂɋC�Â����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̎��݂��w�}���X�t�B�[���h��p�[�N�x�ł������B���ɂ́A�����v���܂��B �i�Q�j���{�����i�r���h�D���N�X�E�}���j�Ƃ��Ă� ���͂��瑶�݂��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃɂ́A���ӂ��Ă����ĉ������B
�����N�@�@�@�@�@�@�@. |