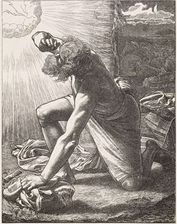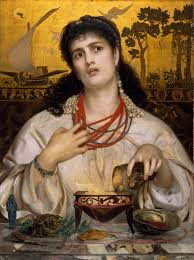���t�@�G���O�h�̏����̉�Ƃ����A�~���C�A���Z�b�e�B�A�n���g�Ƃ������l�����Ƃ͐���I�ɂЂƂ܂���Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���̏ے��I�ȍ앗�͔ނ�ƒʂ���Ƃ��������܂����B���̂������A�����̔ނ�ɓG���Ȃ������Ȃ���Ƃ����������ł��B���Ƃ����āA�ނ�̉^���ɎQ�������蓯�������肷�邱�Ƃ͂����ɁA�K�x�ɋ�����u�������A�Ǝ��̈ʒu�ɂ����Ǝv���܂��B���̂ЂƂ̌����́A���t�@�G���O�h�̂悤�ȕ��ʓI�ōז��ȉ敗���Ƃ炸�A���l�T���X�G��̉e����f���Ɏ����ÓT��`�I�ȑ��ʂ������Ă������炾�Ǝv���܂��B �i�P�j�`�L�I����
�P�W�T�V�N�Ƀ~���C���u���ɂ����̖�����n��C�T���v���X���v�̃p���f�B�Ƃ����~���C�A�n���g�A���Z�b�e�B��w���ɏ悹�����o�̃��X�L����`���A�u�����v�i�����}�j�Ƒ肵�Ĕ��\�����Ƃ���傢�ɎāA��������������ɂ��ă��Z�b�e�B�Ɛe�����Ȃ�܂��B�@
����A�T���Y�͏ё���ƂƂ��ď��Ȃ���ʎ�r��z���グ�A�Ƃ��ɗB����`�^�����x������M���I�ŕ��w�I���|�p�I�Țn�D�̒j���Ɉ��D����܂����B�T���Y�̑f�`���ו��܂Ő��m�Ƀ��f���̊�����L�^���Ȃ���A�����Ɍ����ƂĂ��悭�`���Ă������߂ł��B �i�Q�j�l���I�ȓ��� �@�ǂ�ȂƂ��납��e�������̂�
�����t�@�G���O�h�̉e�� ���t�@�G���O�h�̒��ł��A�l�I�Ȏx��������Ƃ��������Ƃ��������̂��A���Z�b�e�B����̉e���͑傫�Ȃ��̂ł����B����́A���ۂ̃T���Y�̍�i�̒��ɂ����炳�܂ɕ\���Ă��āA��ɓ��p�ői������قǂ̂��̂ł����B�Ⴆ�A�uRosamund�v�i���}�j�ɂ�����p�C�v�I���K���̕`�����́A���Z�b�e�B���uThe Palace of
Art�v�̐��Z�V���A�i�E�}�j�ŕ`����Ă�����̂Ƃ�������ł��B�T���Y�́uRosamund�v�̏����̂Ƃ��Ă���|�[�Y�̓��Z�b�e�B�̏����̌`�Ԃ���̗��p�Ƃ����Ă�������������܂���B�����I�ȏ�����\�킷�̂ɁA�������锯�A���m�Ȋ{�A�����̂悤�Ȏ�ƐO��L���Ă̏d�v�ȃL�[�|�C���g�ɂ��čČ�����Ƃ������Z�b�e�B�I�ȗ��z�́A���̂܂܃T���Y�̍�i�Ɏg���Ă��܂��B ���Z�b�e�B�̉e���́A���܂��ȃA�N�Z�T���[�̖��͓I�Ȉ����̓_�ł������܂��B�T���Y�̍�i�̂Ȃ��Ƀ��t�@�G���O�h�̔鎖������l�ߍ��܂�Ă���悤�ł��B�uRosamund�v�̑O�i�ɂ́A�����ȃX�g���b�v��w��ɂ��āA��̃n�T�~�A�������̃����ƒ������A�R����Δ��A����q�̃����[�t�A���U���I�Ȃǂ�����܂��B���i�ɂ́A�\���ˁA���˓��A�����I�ȕǎ��A�����Ĕw�i�ɂ́A�S�u���b�g�A�X�c�[���A��̉ԕr�A�����ЂƂ̉̓����Ă��郉���v�A�����Ă�����̎p������܂��B���̕��������x�l�ߍ��܂ꂽ�悤�ȕ`�����́A���Z�b�e�B���T�O�N��ɕ`���Ă������̂��v���N����������̂ŁA�T���Y�̓��Z�b�e�B�̂��炭���̂����ς��l�܂����}�������邱�Ƃɂ���āA�~�X�e���A�X�ł��Ƃ��b�̂悤�ȕ��͋C�ݏo�����Ǝ��݂����Ƃ͋^���ׂ�������܂���B�܂�A�T���Y�́uRosamund�v�̕��͋C�́A���Z�b�e�B�̃t�@���^�W�[�̈ꕔ�ł��閲�̂悤�ȉF�����瓾��ꂽ���̂Ƃ����܂��B
�������A���t�@�G���O�h�͎��R�𒉎��ɍČ�����ȏ�̂��Ƃ����߂܂��B�T���Y�����R�Ɨ��z��Z�������V���{���b�N����A���Y�����w�����܂����B�T���Y�́A�����͏ے��ł�����Ƃ��āA���A���Ȑ��E��\�킷�ƂƂ��ɑ��̈Ӗ���тт���̂ł�����܂����B�usleep�v�ɂ����āA���͂��̐�����̍��̉���́A�_�ւ̒ʘH���C�ɏے����A�I�̏�̉Ԃ͕����Ǝ��R�ւ̕��A���ے����܂��B�����āA���Ȃ艓���ł����ƌ������͕��ՓI�ȊC�ɒʂ��鍰�̗��̓`���I�ȃr�N�g���A���̏ے��ł��B ���B����`�̉e�� �T���Y���e�������̂̓��t�@�G���O�h�����ł͂���܂���B�P�W�U�O�N��̃t���f���b�N�E���C�g���AGF���b�c�A�ƃG�h���[�h�E�|�C���^�[�����̗B����`������e�����Ă��܂����B�T���Y�́A�����̐l�X�̃X�^�C��������Ƃ��Ď������ɓǂݑւ��Ď�����܂����B
�����̑�����̉e�� ������̉e���́A�R�O�N��ƂS�O�N��̃h�C�c�̃C���X�g���[�V�����ł����B������̑����Ɠ��l�ɁA�T���Y�́A�a�I�ȃC���[�W�ɑ傫���`�����A���t���b�h�E���[�e���A�����uAnother Dance of
Death�v�ɉe�����܂����B�����𐁂����܂ꂽ�悤�Ȏ��̂�[���̂��̑�\�I�\���ŁA���[�e�������o�����\���ł��B�T���Y���uUntil her death�v,�uYet once more�v ���uAmor Mundi.�v�uDeath the
friend�v�Ō����ɂ��ꂪ�����܂��B���̃x�[�X�ɂ̓A���u���q�g��f���[���[���u�������R���A�v������܂��B �܂�A�T���Y�͈�A�̌���I�ȓ����ɘA�����Ă���̂ł��B�����ŏ��̐��ƌ����邯��ǂ��A�ނ̌|�p�͂�����x���Ȃ��Ƃ������̃X�^�C���̐������ꂽ��@�ɂ����̂ł������[�����ƂɁA�ނ͂������t�@�G���O�h�ʒu�t�����Ă��܂����A�ގ��g�̎���ł̓Q���}���̃A�[�e�B�X�g�Ƃ݂Ȃ���܂����B�ÓT��`�Ƃ̔ނ̊W�͊ώ@���ꂸ�A�����͂قƂ�nj��y����Ă��܂���B �ނ̌|�p�́A�Ɠ��̉����A����ȕ`�ʁA�����Č���I�ȉe���̍����Ƃ����A��������Ă��܂��B�ύX�ƊJ���̏u�ԂɃr�N�g���A�������ɔz�u���ꂽ�ނ́A�����̕ω����z�����ăe�[�}�̏����ȃR�[�p�X�̃T�[�r�X�ɓ��Ă܂��B��ɉ��ʎ��M�����o�����邱�Ƃ��ϑ����ꂽ�ނ́A�����̌��O��T���i�Ƃ��ăC���X�g���[�V�����̎d�����g�p���Ă���B �A
�܂��A�����̎G���ɃJ���[����͂Ȃ��āA���̑}�G�͖ؔłō����Ă��܂����B���̂��߂ɃT���Y�͔Ŗɒ��ځA�u���V�������Ėn�ŕ`���Ă����Ƃ����܂��B�y����`���[�N�A�o�X�e���ł͂Ȃ��āA�u���V�Ŕ��ƍ��̓�F�ŕ`���B�������A���łł͂Ȃ��ؔłɍ���邱�Ƃ�O��ɂ��Đ��ʼn�ʂ��\�����Ă����A���������`�������T���Y�̊G����������Â����Ă������ƍl�����܂��B���̂��߁A�`������ʂ͐��ɂ���Č`���ꂱ�ƂɂȂ�Ƃ������ƁA���������ĕ�����ʂƂ��đ����āA�O���f�[�V�������قǂ����Ă������Ƃɂ͌��E���������Ƃ������Ƃ�����ł��傤�B���������āA��ԂƂ����s����\���Ƃ��ėp��������A��ʂɑ����̕�������ꍞ��ōs���X���ɂȂ�܂��B����́A�O�ŏq�ׂ����t�@�G���O�h�̉�ʂ̍����ɋ߂����̂ƂȂ�킯�ł��B�܂��A�ؔłł͓��ł̂悤�Ȕ��ׂȐ��������Ȃ��̂ŁA���ׂȐ��𖧏W�����鐸�k����Nj����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA���ɂ��`��Nj����邱�ƂɂȂ�܂��B�����ŁA���t�@�G���O�h�̃n���g��~���C�Ƃ́A�������ɃY��������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����āA������Ղ��Ƃ��ے��I�ȗv�f�̓��t�@�G���O�h�ɂ�����܂����A���̓��e�̐F�������قȂ���̂ƂȂ��Ă���킯�ł��B ���������`�����ŁA�T���Y�͂ǂ̂悤�ȃe�[�}���ނɊS�������Ă������̂��A�Ƃ������Ƃ����̉�Ƃ�����Â��Ă���Ǝv���܂��B�܂�A���j�╶�w�A�_�b���ނƂ��ĂƂ肠���Ă��A�ǂ̂悤�ȃG�s�\�[�h���A���̃G�s�\�[�h�̒��łǂ̂悤�ȏ�ʂ��Ƃ肠�����̂��Ƃ������Ƃł��B �T���Y���}�G�Ŏ��グ���e�[�}�͂���قǑ�������܂���B�Ɍ�����A�R���S�̃e�[�}�ł����Ď��X�̘b����ނƂ��Ď��グ�Ă����Ƃ������Ƃł��B���̂Ȃ��ł��A�ނ̊S�̎�v�ȂƂ���͐l�Ԃ̐S���I�ȃh���}�ł����B������A�j���͈ꕔ�ŁA�啔���͏������`����܂����B����������͉�ʒ����ɏ����̊炪�傫���N���[�Y�A�b�v����ĕ`����Ă���B���̊�̕\��͋ɒ[�Ȋ����ттĂ�����̂ł����B���̊���Ƃ͋��|���邢�͐�]�A�ߒQ�A�~��������Ȃ������A�����ɐ��I�ȋ�������킹��v�f������������̂ł����B
�ɓx�̐�]�⋰�|�̗l�q�́A�uThe Sailor�fs
Bride�v�i�E�}�j�ɂ����ė��l��҂����ċA�҂��Ă݂�ƁA���̗��l�̓x�b�h�ɉ�������ē����Ȃ��B���̔߂��݂ɐ�]����l���͗��l�̑O�ŕ��������p���ɕ\�킳��Ă��܂��B���̋��낵���́A�c���ꂽ���̔߂��݂��]�ւƌ��т����Ƃ𑨂��Ă��܂��B�uYet once more on the organ
play�v�i���}�j�ł̓I���K���̉��t�Ő��C�𐁂����܂ꂽ�悤�Ɏ��̂�����オ��l�͉��y�ɜ����ƂȂ�ے��ł�����܂����A���C��r�����Ƃł�����A���̒ɂ݂⋰�|������オ�����g�̂��\�킵�Ă��܂��B�����̐g�̂̓�����p�����\���I�ƌ����܂��B ���̋��|�͐��I�ȋ����ƑΔ䂳��܂��B�uYet once
more on the organ play�v�̂���オ�������̂͐��I�ȃG�N�X�^�V�[��z����������̂ł�����܂��B�܂��A�uRosamund�v�i�@�Q�Ɓj�̜����Ƃ����\��̏����́A�����炩�ɐ��I�ȗv�f�������܂����A�[������ɂ��āA���̉e�������\���Ă��܂��B�����āA
�T���Y�͌����������łȂ��A���̔��̐Â��Ȋ���ɂ��œ_�Ă܂��B�uThe
Little
Mourner�v�͗��e�̕�ɐς����������S�ɃX�R�b�v�ł̂��Ă��鏭���̎p�������������邱�ƂȂ��A�W�X�ƕ`���Ă��܂��B�����ł͐�̔w�i�͏����̊���̐Â������Î����Ă��܂��B�܂��A�uLife�fs Journey�v�ƁuThe Old
Chartist�v�ł́A�O�i�ƌ�i�ł͈قȂ������Ԃ�`�������Ď��Ԃ̌o�߂��ے��I�Ɏ�����āA�q�̓I�ȉp���̓c�����i�̋ɒ[�ɍׂ����`�����ƂŁA�����ɘȂސl�Ԃ̊��̕��G����ω����ے��I�ɕ\�킵�A�l���̕��G���Ɛl�Ԃ̌o���Ǝ��R�̂������̕��G�Ń��}���`�b�N�ȊW�̗���������҂ɑz�������܂��B �T���Y�́A�}�G�Ƃ����|�p�̂悤�ɑΏ۔͈͂����肳�ꂽ�������E�ł͂Ȃ��āA��ʂ̐l�X�Ɍ������A�Ώ۔͈͂��������m�ɂ��܂��Ă��炸�A����䂦�ɕ\���̗]�n�̑傫���c����Ă��镪�����Ȋ����ꏊ�Ƃ��A�����Ŏ��g�̊G�搢�E���`����Ă����܂����B�����ł͈��Ǝ��Ƃ����s��ȃe�[�}�ɊS�����Ȃ�����A��z�I�Ȍ�����������]�_�̑}�G�ɂ��邽�߂̃��A���Ȑ��E�܂ŁA�`�������ÓT��`�I�Ȃ��̂��烍�}���`�b�N�Ȃ��̂܂ŗl�X�ȃX�^�C���̃��@���G�B�V����������܂����B���ꂪ�A�T���Y�̍�i���E�̈ӊO�ȕ��̍L���������Ƃ��\�ɂ����Ǝv���܂��B�������A�S�̂Ƃ��ăT���Y�̍�i�́A���l���Ƃ��J�T���Ƃ������Â��ʂɌX���A�����������������\��������ɁA�ނ̎u�����`�����������Ă����Ǝv���܂��B ���[�K���E���E�t�F�C�́A�A�[�T�[������ɓo�ꂷ�鏗���ŁA�A�[�T�[���ٕ̈��o�ɂ��Ė����Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�P�T���I�ɏ����ꂽ�w�A�[�T�[���̎��x�ł͍����p���g�����Ȗ����Ƃ��āA�ٕ���A�[�T�[�̑O�ɗ����͂�����܂��B��ɖ��@�g���}�[�����́A�ޏ������͂��̂���`���n�߂�̂ł����A�ޏ��̓A�[�T�[�̏����ȐS���������A�A�[�T�[�ƃO�B�l���B�A�̊Q�Ɖ��ʒD�����ނ��Ƃ�m��A�A�[�T�[���̍ŋ��̓G�ƂȂ�܂��B�~��̋R�m�̈�l�A�����X���b�g�̍ȂƂȂ�y���X���̖��G���C���P�̔�������i�݁A�ޏ���H�������X���b�g��U�f���܂����B�܂��A�����G�N�X�J���o�[�̖��@�̏�i��������͂Ǝ��҂�s���ɂ���͂��ւ�j���A�[�T�[���瓐�݁A���l�ł���A�R�[�����ɗ^�������Ƃ���A�[�T�[���A�R�[������G�ɂ܂킵�Đ키���n�Ɋׂ邱�ƂɂȂ�܂����B��Ƀ��[�K�������@�̏���̒��ɓ��������A����ɂ���ăG�N�X�J���o�[�̓A�[�T�[�����s���̗͂������A�₪�ăA�[�T�[�̓����S�[�X�i���[�K���̎o�j�Ƃ̊Ԃ̕s�`�̎q�ł��郂���h���b�h�Ƃ̐킢�Ŗ��𗎂Ƃ����ɂȂ�܂��B �C�M���X�ł́A�A�[�T�[���̕���̓V�F�C�N�X�s�A�ƕ���Ől�X�ɒm���Ă��镨��ŁA���t�@�G���O�h���͂��߂Ƃ��郔�B�N�g���A���̉�Ƃ�������ނƂ��Ď��グ�邱�Ƃ����������悤�ł��B���̃��[�K���E���E�t�F�C�ɂ��Ă��A��\�I�Ȃ��̂����Ă݂܂��傤�B�o�[���W���[���Y�̉e��������Ƃł����X�^�i�b�v�ɂ��u�����K���E���E�t�F�C�v�i�E��}�j�B���̍�i�͔ޏ��̖��͓I�ȓ�����`���Ă��܂��B�ޏ��ٖ͋��Ƀt�B�b�g����Ԃ��h���X�𒅂Ă��āA���������Ȃ��炩�ɕ��łĂ��܂��B�ޏ��̌��ɂ����͔ޏ����L�������b�g�ɂ��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B
�E�H�[�^�[�n�E�X�i�E�}�j�̍�i�ł��B���̊G�́A���ɕs�g�ȁA�Â��A���n�I�Ȗ��@�g����`���Ă��܂��B�ޏ��̍����ۂ������͔��ɑf���Ŗ쐫�I�ŁA�����̓��I���_��\���Ă��܂��B�ޏ��͎����̉̎���ɉ~��`���A��������Z�����������яオ��B�ޏ��͍r��̐^�ɂ���悤�ł��B�J���A�J�G���A���W���A����ё��̕s��p�Ȓ���́A�ޏ��̎���̒n�ʂɎU����Č����܂��B
���₳�����t
�����̔����ߕ��͐F�̉��ǂ肪����A���̐܂�ڂɂ͉Ԃ���������Ă��āA�ޏ����g���t���^��ł����ے��I�Ȏp�ł��邱�Ƃ�\�킵�Ă��܂��B�ߕ����̂͂������Ƃ������̂ł����A���̐܂�ڂ����邱�ƂŁA�����̐g�̂̋Ȑ��A�Ⴆ���̓��[�╠�̂ւ��݂��_�Ԍ����āA�����Ɋ��\������������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����ł́A�t�Ƃ����G�߂̊��\�I�Ȑ��i���A�����ŕ\�킵�Ă���悤�ł��B�����̕������悤�ȕ\��������Ƃ�����B �ޏ��̊��̎���ɂ̓u�����h�̔��̓��̒��������сA�H�����A�ޏ��̏t�̗r�т̉��ɂ́A���ȐF�ʂƐ▭�ȃy�C���g���{����Ă��܂��B�S�̂̑g�����́A���a�ʼn��₩�ł��B ���̃y���Z�|�l���ނƂ��ē�����̉�Ƃ����̍�i�Ɣ�ׂ�ƁA�T���Y�̍�i�̊��\������߂����₩�������j�[�N�ł��邱�Ƃ��A�悭������Ƃ����܂��B
�����͂�B �����f�B�A ���f�B�A�̃M���V���_�b�ɓo�ꂷ��R���L�X�������f�B�A�̂��ƂŁA�G�E���s�f�X�̔ߌ��u�������f�B�A�v�ŗL���ł��B�R���L�X�̉������f�B�A�͕v�C �T���Y�͉A�S�Ȕߌ��Ƃ��ĕ`���Ă���悤�ł��B��ʑS�̂Ƃ��Ă̓��f�B�A�̔��g���ŁA�w�i���ɗ͔r�����ޏ��̂ЂƂ蕑��A�Ƃ�킯�߂��݂Ɏ�藐���A�s�g�ȉe��������̕\��N���[�Y�A�b�v����Ă��܂��B�ޏ��̎�O�A�܂�A���f�B�A�͌���҂̊Ԃɂ͑嗝�̃e�[�u���������āA���̏�ɖ��@�ɂ����f�̂��߂̗l�X�ȓ���u����Ă��܂��B�Ⴆ�A�P���k�̒��ɂ͋Ìł����l�Ԃ̌�������A�s�v�c�Ȍ`�̃K���X�̗e�킩��Δ��ɉ��𒍂����݁A���̋P���ɂ���ă��f�B�A�̔������Ɛ��߂���Ƌ��낵���ȊႪ�f���ďƂ炳��Ă���悤�Ɍ����܂��B�ޏ��͎X��ƃg���R�̃l�b�N���X��Ў�ň����Ă��܂����A�ޏ��̋ꂵ���O���狰�낵���͂̎��Ȃ����t���o�Ă��܂��B���̂悤�ȍו��̕`�ʂ͐▭�ŁA�Ƃ��Ƀl�b�N���X��M�Ԃ悤�Ȏ�̂������́A�M�ꂽ�l���m�������ނȂǂƂ����悤�ȋꂵ��ł�����悤�ɒ͂ދ��̕\���A�z�����܂��B���̃l�b�N���X�Ǝ����悤�Ȍ`��̃��f�B�A�̍������̖т�����ăo�����Ă���Ƃ�����A��̕\��Ƃ��킹�Ċ���̍��Ԃ�����������܂��B���ꂽ���Ɛ^���Ԃȃl�b�N���X�̊Ԃɔ��������肪�ג�������Ă��āA�Ԃ��q���ł��܂��B�����́A�A�����Ă���悤�ɁA��ʏ�ŊW�Â����Ă��܂��B�����āA���点��悤�ɂ��Ċ{���݂��A��i������҂́A���f�B�A�̊���p�Ō��グ��悤�Ȏp���ɂ����Ă��܂��B���̂��߂ɔ������������̕\��悭������킯�ŁA���f�̌��t���͂����Ă���ꂵ����������܂��B�Ⴊ�����������ɑ����Ă���悤�Ȃ̂́A�S�͂����ɂȂ��āA���f�̑ΏۂƂȂ�C�A�\���̂��Ƃ��S���߂Ă��邽�߂ł��傤�B �T���Y�Ɠ�����́A���t�@�G���O�h��B����`�̉�Ƃ����́A�ÓT��`�̌`�Ԃ��x�[�X�Ƃ��Ă����������A����`�ԂƂ��Ă܂��`���Ă����悤�ŁA���̏�ŕ\�����Ƃ����悤�ȕ`���������Ă��܂����B������A�{��Ƃ��߂��݂���������������A����������܂��`���Ă����Ǝv���܂��B����ɑ��āA�T���Y�͕\��𔗐^�������ĕ`�����Ƃ̕���D�悳�����A�ÓT��`�Ƃ�����胍�}����`�I�Ȏp���ŕ`���Ă����Ǝv���܂��B����䂦�ɁA�T���Y�͓�����̉�Ƃ����̒��ňٍʂ�����Ă����Ǝv����̂ł��B ��Danae in the Brazen Chamber �@
���l�X�E�B���o�[���͗H���ꂽ�_�i�G�̗J�T�ƌ��ӂ����G���e�B�b�N�ȓ�����o���[�h�ɂ܂Ƃ߂܂����B�ޏ��͗H���ꂽ�����ŁA�^�y�X���[�ɕ`���ꂽ�l�����ˋ�̗��l�Ƃ��Ė������܂��B�[�E�X���ޏ��̂��ƂɌ��ꂽ�Ƃ��A�^�y�X���[�̗��l�̎p�͏����āA�ޏ��̗~�]�ɉ�����悤�ɉ����̉J���ޏ��ɍ~�蒍���A�y���Z�E�X��g������̂ł��B �T���Y�́A���̏u�Ԃ���i�ɂ��Ă��܂��B�������A�X�E�B���o�[���̎����\�Ȍ��蒉���ɍČ����悤�Ƃ��Ă��܂��B��̓I�ɂ́A���̒��ŏ�����Ă��鎖������ʂ̒��ɕ`������ł��܂��B�Ⴆ�Ύ��̂悤�Ȃ��Ƃł��B �g�����r���ɌŒ肵�A����w���ɓ����A���𗬂��āh �g�J�������Ƒ������邭�����h �T���Y�́A�_�i�G�����\�I�ŁA���I�ɐ��n���������Ƃ��ĕ`���܂����B�����������炷�悤�ɂ��āA����̂悤�Ȕ��ڂŁA���r���Ђ炢�������Ƃ����|�[�Y����点�Ă��܂��B����́A���t�@�G���O�h�̃��Z�b�e�B�̑�\��u�x�A�^��x�A�g���N�X�v�̏����̃|�[�Y�Ƃ�������ł��B�������A���Z�b�e�B�͊��\�I�ȕ����ł͂Ȃ��ґz�I�ȕ��͋C�����o���Ă��܂����B���̈Ⴂ�́A�Ⴆ�T���Y�̏ꍇ�A�_�i�G�̌Ñ㕗�̈ߑ��̃x���g���A�ޏ��̐g�̂̐��A�Ƃ��ɋ��⍘�̂ӂ���݂��������A���炵�����ۗ������Ă��܂��B���ꂪ�A�_�i�G�̊��\�ɑł��k����g�̂̓�����z��������̂ł��B �T���Y�́A���̗H���ꂽ�A���J���ȏ�����ǂ���]�n�̂Ȃ���Ԃ�������ɉQ���������̖т₻�̑��ŕ\�킵�Ă��܂����A����̓��t�@�G���O�h�̕��ʓI���k���ȕ`�����ɒʂ�����̂ł��B�������A���t�@�G���O�h�ɂ́A����قǒ��ړI�Ɋ��\�I�ɏ�����`���Ă͂��܂���B�L���Ȕ����u���b�V���O����|�[�Y�̊��\���́A���Z�b�e�B���t�@���t�@�^�[����`���ۂɗp���Ă��܂������A�����ł̓_�i�G�̔��̖т��A�ޏ��̊��\��������ɋ������Ă���̂ł��B �����̉e
�T���Y�́A����܂ŁA�u�����K���E���E�t�F�C�v�i�P�W�U�R�N�j�A�u���f�B�A�v�i�P�W�U�W�N�j�ƌ��I�ȏɊׂ������Ɍ����A�͋��������̊��\�I�Ȕ��������A���̕�����ˏo������悤�ȏے��I�Ȏd���ŕ`���Ă��܂����B��̓I�Ɍ����ƁA�����̍�i�ł́A�U�f�҂��疂�p�t�ւƕϖe����u�ԂɁA�{��ɑł��Ђ�����A���߂��ꂽ�������`����Ă��܂��B�����悤�Ɂu�J�T���h���v�i�P�W�X�W�N�j�ł́A�ӎ��������ꂽ�u�ԂɁA����{�A�ڂ�͋����O�ɓ˂��o���A������~�߂邩�̂悤�ɂ��āA���C�ւ̓]�����瓦��悤�Ƃ���p���`����Ă��܂��B�����̍�i�̏��������̐��g�̐_�X�����͂Ɉ��ݍ��܂꜒���Ƃ����p�̃C���[�W�͕�����Ȃ����͓I�ł��B���̎���A�����͐��_�a�ɂ�����₷���ƍl�����Ă������߁A�q�X�e���[�⋶�l��������������Ə�ɋ�����Ă��܂����B���̌��ʁA��Â��Ɛߐ����ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ɑ傫�ȃv���b�V���[������A�ŏI�I�ɂ͔ޏ������́A���ȕ\�����]���ɂ��Ă����̂ł��B���̂悤�ȈÂ��w�i�̒��ŁA�u���̉e�v���܂߂��T���Y�̕`�������I�ȏ��������̗d�����������яオ���Ă���̂ł��B �u���̉e�v�ł́A�T���Y�͑Ώۂ̏����ɔE�ъ��悤�ɂ��āA����҂����������`�����̑̌���������悤�ȉ�ʂ�����Ă��܂��B���̒n�ʂm�Ɏ������߂ɕ���ґ�ɏ���ꂽ���̔����������́A�߂̏u�Ԃɕ߂炦���Ă���悤�Ɍ����܂��B�ޏ��̈Î����ꂽ�������ƁA�ޏ��̈Ӑ}�I�Ȏ����̑Ώۂ́A���̉e�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɔ�������Ă��܂��B�ޏ��̕\��͏�Ⴂ�Ȃ��̂ƂȂ�A�s�@���Ȋ�ɕς��A���ӎ��̂����ɉԂ̌s�����ł͂�����Ă��܂��̂ł��B�ޏ�������ł���Ԃ͈��ƌx���S�̏ے��ł�����X�~���ł���A�����炭�͌��g�̏ے��ł���w���I�g���[�v�����ނ悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B����͂܂��A���Ȃ̓��ȂƏz���̏ے��ł���E���{���X�i�K�������ގցj���Î����Ă���悤�ɂ������܂��B
���I���A�i
�k���̕����C��n���Đ����� �I���A�i�� ��͕��ށA���Ȃ����v���E�C�͂Ȃ� �I���A�i�� ���Ȃ��͋����}�̖̉��ɉ������ ��͎����Ă��Ȃ��̂��Ƃɂ䂭�E�C�͂Ȃ� �I���A�i�� �C�肪�������� �I���A�i�� �T���Y�̓e�j�X���̎��ɒ����ɏ]���̂ł͂Ȃ��A�g�ޏ��́A��̕ǂ̏�ɗ����Ă��܂����h�Ƃ����P�s�����Ƃɂ��đz�����Ђ낰�Đ��삵�܂����B�����̃T���Y�͂P�T���I�̃t�����h���G��ɐ[���X�|���Ă��āA�I���A�i�̐F���̔��A����т₩�Ȉߕ��A�����Ĕw��̕��i���k���Ȋώ@�Ԃ�ɁA�n���X�E���������N����E�t�@���E�G�C�N�Ƃ�������Ƃ̉e�������炩�Ɍ����܂��B����ƂƂ��ɁA�{�b�e�B�`�F����s�G���E�f�b���E�t�����`�F�X�J�ȂǂP�T���I�C�^���A�̉�Ƃ̕`������̏ё���A����ɂ͂P�W�T�O�N��㔼�Ƀ~���C�ƃ��Z�b�e�B����ڂ����A�G����̗B����`�^���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����A�ԋ߂��猩�ĉ�ʂߐs�����悤�ȕv�l�̓����Ƃ����\�}���A���̍�i�ł͂Ƃ��Ă��܂��B���̍��܂ł́A�T���Y�̓��t�@�G���O�h�̉e���̂��Ƃŕ`���Ă����悤�ŁA���̍�i���A���̂悤�ȌX���̏I���ɂ�����܂��B���̌�ƂȂ�ƁA���Z�b�e�B�̉e���������Ȃ��āA�앗�����Z�b�e�B���ɕς���Ă䂭���ƂɂȂ�܂��B |







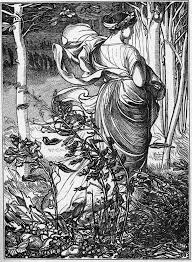 �T���Y�͌��z����ߑ��̌ÓT��`�̃A���e�B�[�N�ȑ������A���g�̍�i�̕��ꐫ�̋����ƐS���I���ʂ̂��߂ɁA��i�Ɏ�����܂����B����́A���C�g���̂悤�ɑ������{���Ă��܂����A�T���Y�͊���I�ȏ�蒅�����邱�Ƃɐ�ΓI�ɏW�����Ă��܂��B�u�J�b�T���h���v�Ɓu�w���l�v�łQ�l�̌��́A�Q�l�̑Η������悤�Ȕw�i�ɃA���x�X�N�Ŕj�ꂽ�c�������̃C���[�W�̂悤�ɁA�{��ɐg���������܂��B
�T���Y�͌��z����ߑ��̌ÓT��`�̃A���e�B�[�N�ȑ������A���g�̍�i�̕��ꐫ�̋����ƐS���I���ʂ̂��߂ɁA��i�Ɏ�����܂����B����́A���C�g���̂悤�ɑ������{���Ă��܂����A�T���Y�͊���I�ȏ�蒅�����邱�Ƃɐ�ΓI�ɏW�����Ă��܂��B�u�J�b�T���h���v�Ɓu�w���l�v�łQ�l�̌��́A�Q�l�̑Η������悤�Ȕw�i�ɃA���x�X�N�Ŕj�ꂽ�c�������̃C���[�W�̂悤�ɁA�{��ɐg���������܂��B