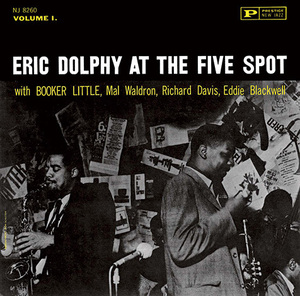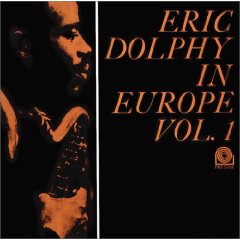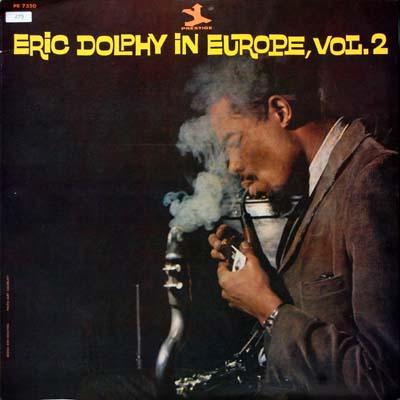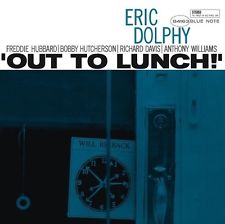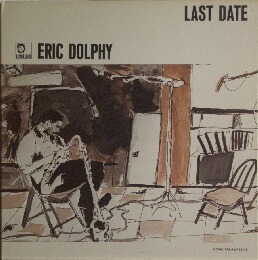|
エリック・ドルフィー(アルト・サックス)
下で紹介しているアルバムの、どの演奏でもいいので聴いてみていただきたい。はじめて人は驚くかもしれない。そこには、このホームページで紹介している他のプレイヤー、例えば、アート・ペッパーでも、ソニー・ロリンズでもリー・コニッツでもいい、ハード・バップ、クール・ジャズなどのスタイルの違いこそあっても、ジャズという音楽であるベースがある。しかし、ドルフィーの演奏は、そういうものが壊れてしまっている、アバンギャルドという言葉のイメージそのままの、「これって、音楽なの?」という感想がでてきても不思議ではない。フレーズはメロディという一般的なイメージには合わず、単に数個の音が続いているだけで、まとまった節に聴こえない(うたわない)。爆音のような音がむき出しでがなりたてている。そこで、かろうじてビートだけが単調に響いている。そんな感じではないかと思う。 それは、ひとつにはドルフィーが活躍した1960年代はじめから半ばという時代状況も影響している。ジャズの歴史でいえば、ハード・バップは下火になり、大衆音楽としてのジャズの人気が落ち始める中で、新主流派からフリージャズといった試みがなされていた。そして、ドルフィーは、そのハード・バップからフリージャズへの橋渡しのようなスタンスにいたということだ。フリージャズなどというと、難解で敷居の高い音楽とか、でたらめでギャーギャーいってるだけの音楽とかいったイメージで捉えられているのではないかと思うが、聴いていただいた、ドルフィーの演奏は、それに近い印象を受けるのではないだろうか。 「そんなののどこがいいの?」素朴にそう問いたくなるだろう。たしかに、ドルフィーの音楽は聴く人を選ぶ、誰にでも受け容れられるというタイプの音楽ではない。 しかし、その演奏の圧倒的なパワーは誰も認めざるを得ないだろう。騒音にしか聞こえない人もいるかもしれないが、それにしても、そのうるささが並外れていることは否定できないだろう。それが、ドルフィーの特徴のひとつを形作っている。 そのひとつの要素として、ドルフィーの音そのもののユニークさがある。例えば、ドルフィーの吹くアルトサックスは楽器が壊れてしまうのではないかと思わせるほどにビリビリと楽器自体が鳴りまくる。そこで響いている音はたとえようもなく硬質で、サックスの音の「芯」だけをそのまま大きくしたような、ギュッと中身の詰まった音。音にゆとりがないというか、遊びの部分がなく、聴いていると切迫感がある。うっとりと身を任せたくなるような心地よさなど微塵も感じさせない愚直なまでにシリアスで、そして、でかい、凄い音圧なのだ。とにかく、音をちょっと聴くだけで、あ、ドルフィーだとわかる個性的な音である。フリージャズのアルト奏者のなかには、演っていることはたしかに難解で、時代の先端を行くような立派な演奏かもしれないが、音そのものが貧弱で、フリーキーにブロウしても、その音が爪楊枝のようにこちらをちくちく刺すだけ、というひとがけっこういる。しかし、ドルフィーの音は太い槍のように我々の心臓を貫くのだ。 そして、メロディになっていない独特のフレーズ。ちなみに、上で説明したようなストレートで心地好さを感じさせない音でメロディをふいても、それに身を任せることができるだろうか。それよりも圧倒的なパワーで力ずくで攻めて来い、といいたくならないだろうか。まさにそうなのだ。あの音で、ビートに乗って、うねるように、巻き込むようにドライブ感に溢れるフレーズが繰り出される。彼独特の咆哮を思わせるような音が跳躍するようにカッ飛んでしまうフリーキーなトーンはデタラメに吹いているように聞こえる。 例えば、ドルフィーがノッてくると、必ず繰り出してくるパターンがある。それは・・・「パッ・パラ・パーラ・パーラ」というデコボコした起伏を持つフレーズで、ドルフィーは、この1小節4拍のフレーズを、それはもう重い音色でもって、何かが弾け飛ぶような感じで、吹き倒す。そしてこのフレーズが出ると・・・その瞬間、ビートが一気に「解き放たれる」ような感じがするのだ。バンド全体の感じているビート感も一気に爆発するとでも言うのか。そしてそれが、本当に気持ちいいのである。聴く者も突き抜けてしまうのである。だから、ドルフィーは決してデタラメに吹いているわけではない。どんなアルト奏者よりも、「きちんと考えて音を選んで、コントロールしたうえで吹いている」からこそできることなのである。サックスを吹いたことのあるひとならわかるだろうが、あんな極端にオクターブジャンプを繰り返すようなフレーズを吹くのはとてつもないテクニックが必要だ。しかもあのすごい音色であのフレーズを延々と吹き続けるのは、まったくもって人間業でない。 ドルフィーのアルトのあのフレーズは、いつまでたっても「慣れる」ということがなく、ひたすら我々の心をざわつかせ、いらだたせ、紙ヤスリでこすられるような不安感、不快感をあおる。ドルフィーの音色もそうだが、ドルフィーのフレーズというのもまた、愚直なまでにシリアスである。ソロの出だしを聴くと、ぎゃはははと笑いだしたくなるような演奏なのだが、しだいに「これは笑っていてはいけないのではなかろうか」と思えてき、だんだん聴いているほうも居住まいを正してしまう……そんな音楽である。 つまり、彼の演奏を聴く者は、聴いているうちに、ドルフィーのデタラメなフレーズのなかに「何か」を見つけて感じとってしまうことになる。同じフリージャズ黎明期の大物プレイヤーであっても、オーネット・コールマンの音楽はどちらかというとわかりやすい。つまり、彼は「そのとき吹きたいように吹く」のであって、言ってみれば、良い意味のデタラメである。そういう気分一発的な演奏というのは、聴く者にとっても、「ああ、もう、わけがわからん」という風にはならず、「なんだかわからないけど、とにかく彼は今、こう吹きたいのだろうな」と納得できる。しかし、ドルフィーの音楽は、どう聴いても、なんらかの楽理に基づいて演奏されているようである。しかし、その理屈がどういうものかさっぱりわからないので、難解ということになってしまう。そこで、ドルフィーの演奏が「何を言っているのかはわからないが、そこには確固としたセオリーが確実に存在していて、音楽総体が発する『意味』は確実にこちらに伝わってくる」という風になっているのだ。
バイオグラフィー エリック・ドルフィーは、アルト・サックス、フルートそしてバス・クラリネットにおいて特徴的なスタイルをもった真のオリジナリティのあるミュージシャンだった。彼の音楽は“アヴァンギャルド”のカテゴリーに分類されたが、彼自身必ずしもコード進行による即興を放棄したわけではなかった(コードに対する彼の譜面はかなり抽象的なものだったが)。彼以外のほとんどの“フリー・ジャズ”の演奏が非常に真面目で堅苦しく聞こえるのに対して、ドルフィーのソロは、多くの場合、恍惚と熱狂をもたらした。彼の即興は非常におおきな跳躍、非音楽的で演説のようなサウンドそして彼自身のロジックを使ったものだった。彼が主として演奏したのはアルト・サックスであったが、ハード・バップ以降の最初のフルーティストであり(ジェームス・ニュートンに影響を与えた)、ソロ楽器としてバス・クラリネットをジャズではじめて使った。彼は、(コールマン・ホーキンス以降)伴奏者なしのホーン単独の演奏による録音を行った最初の演奏者の一人で、それは、アンソニー・ブラクストンの5年も前のことだった。
|