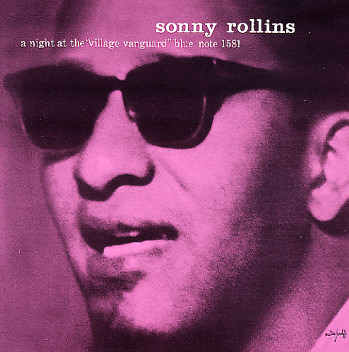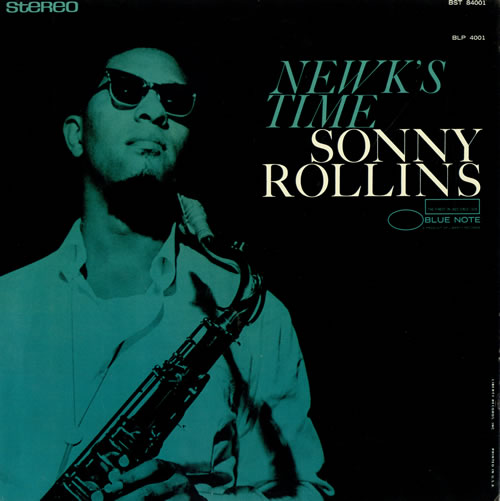|
テナー・サックス奏者。 ソニー・ロリンズのプレイの最も大きな特徴として、彼の創り出す音楽には歌がある、と言われる。 それは、ロリンズがメロディを情感タップリに嫋嫋と歌うように演奏するというのではない。端的に言えば、ロリンズの生み出すアドリブのフレーズのほとんどがメロディとして聴けてしまうということだ。試しに、他のサックス奏者のアドリブと聴き比べてみると、ロリンズのアドリブが突出しているのが分かる。普通、その場その場の即興で、そうそうまとまったメロディなど作れるものではない。かといって作り置いたものを用意しておいて使うにしても、そこで使えるとは限らないし、そもそも作り置いて新鮮さを失ってしまったものは、生ものであるアドリブとは相いれないだろう。著名なプレイヤーであっても短い節で、せいぜいがメロディのかけらのようなものをプレイしている。それと比べた時のロリンズの創造力の凄さだ。人間の創造力なんてたかが知れている。まとまったフレーズなんてそう簡単に作れるはずがない。仮に作れたとしても、そうたびたび目新しいものなど作れるはずがない。メロディというまとまった形をとれば、人の記憶に残り、似たようなものがあれば、すぐに見破られてしまうだろう。だから。そこで、プレイの度に瑞々しいアドリブプレイを重ねるロリンズが天才的だと言える。 さらに、ロリンズの歌い回しが絶妙で、クラシック音楽で、例えばショパンのピアノ曲を優れたピアニストは、左手で演奏する低音部でキッチリをとり、右手で演奏する高音部のメロディはそのリズムから間をとって心もちズラしたり、リズムを崩したりする。そこにピアニストの個性的な歌い回しが生まれ、独特の情感や余韻を作り出す。クラシックのピアノのテクニックでテンポ・ルバートと呼ばれるものだ。ロリンズにも、そこまで体系化されているわけではないが、おそらく本能的に独特の間の取り方や崩し方で個性を際立たせているところがある。それが、豪快で男性的とも言われるロリンズの演奏を味わい深いものにしている。それがロリンズの歌いまわしだ。
バイオグラフィー 40年以上の間、ソニー・ロリンズは、ジャズの巨人の一人であり、コールマン・ホーキンス、レスター・ヤングやジョン・コルトレーンといったジャズの歴史を通じての偉大なテナー・サックス奏者と並び称せられている。最初はピアノだったが、アルト・サックスに手を出したあと、1946年にテナー・サックスにかわり、そのまま現在に至っている。1949年、バブス・ゴンザレスとレコーディング・デビューを果たしてから、同じ年に、JJジョンソン、バド・パウエルとの数日間と後日のファッツ・ナバロも加わってのセッションは大きな衝撃を及ぼした。ロリンズの実力ははじめからジャズの世界では知れ渡った。そして1951年にマイルス・デイビスと2年後にはセロニアス・モンクとレコーディングを始めるのだった。1955年にマックス・ローチとクリフォード・ブラウンのクインテットに加わり、ブラウニーが亡くなる1957年まで続けた。それから、彼はつねにリーダーだった。 1950年代のプレステージ、ブルー・ノート、コンテンポラリーそしてリバーサイドのための一連の輝かしいレコーディングは、ロリンズが絶好調だったことの証だ。そしてジョン・コルトレーンが抬頭してくるまで最高のテナー・サックス奏者として絶賛されていた。それゆえ、1959〜60年に音楽の世界から離れるというロリンズの決心はジャズの世界に衝撃を与えた。1961年にジム・ホールをフィーチャーしたカルテットでカム・バックした時、彼のスタイルは変わっていなかった。しかし、オーネット・コールマンの革命をよく知ることとなり、フリー・ジャズのプレイーに間もなく変貌してしまう。時にはオーネットのコルネット奏者ドン・チェリーを起用さえしたのだ。彼のプレイは以前から少しエキセントリックなところがあったけれど、1968年に再び引退の決心をするまでメジャーには位置していた。 1971年にカム・バックすると、ロリンズは、リズム・アンド・ブルースのリズムとポップ・ミュージックの影響を進んで受けるようになり、彼のレコーディングは以前に比べて彼本来のものとは離れてしまう(サイド・メンが彼のレベルに追い付けていなかった)が、ロリンズ自身は不可欠のソリストであった。彼の手腕にかかれば、ふつうならありそうもない素材でもジャズになってしまうのである。彼のソロパフォーマンスにおける自由なリズムとテーマの崩しは、他の追随を許さず、90年代においても彼はジャズの達人であった。彼のたくさんの録音は現在でも、その多くを聴くことができる。 村上春樹はロリンズについて、以下のようなことを書いている。(「ポートレイト・イン・ジャズ」より)
ロリンズのテーマのメロディの崩し方、あるいは自由な間の取り方は、優れた歌手がメロディを自由に自分の個性に合わせて崩し、伴奏者にはきちんとリズムを取らせながら、好きなタイミングをとらえて歌に入り、自分なりの間を創造してしまうのに通じている。ロリンズは、それと同じことをサックスで行っているのだ。くずし、間の取り方のうまさに加えて、ほとばしり出るアドリブの奔流が凄まじい。ただ、ロリンズの場合は、嵐のような即興フレーズでも、原曲のイメージとかけ離れてしまわないところが、歌心を称賛される理由である。優れた歌手は、歌を自在に自分の懐に引き付けてしまう。つまり、個性的な表現だ。それは歌い手の声そのものとなって、一つの定型にまで高められるだろう。ジャズでも似たようなことは起こる。優れたジャズメンは楽器を通して自分の声を持っている。ロリンズももちろんそうした一人だ。しかし、本当に即興の精神に忠実なジャズメンは、それを日々新たな、そのときの自分の声としなければ満足しない。つまり、あらかじめ練習し、考え抜いた上で、定型的表現へ向かうということはやらない。一つ間違えれば収拾のつかない混乱に陥ることも恐れず、果敢にそのとき、この世に生まれ出る歌声を求めるのが、ジャズの歌心なのである。
ソニー・ロリンズは活動暦が長く、ずっとトップ・プレイヤー君臨し続けた巨人のようなプレイヤーと言えるでしょう。その間、時代の変化やジャズを愛ずる状況の変遷などによって、また、本人の伝記上の様々なエピソードは紹介やネットの検索によって容易に知ることができるでしょうが、その長い活動期間のなかでプレイスタイルを変化させてきている。それに対する好き嫌いは、ファンによって色々と分かれると思う。ここでは、私個人の主観で、つまりは好き嫌いでアルバムを紹介しているので、ここにコメントしているのは、あくまでも私の好みであって、そういうものとして読んでいただきたい。しかし、そのためには、私の好みとはどのようなものかを、明らかにしなければフェアではないだろう。そこで、私はソニー・ロリンズのプレイをこのようなものとして捉えているということを以下で簡単に述べておきたいと思う。 端的に申し上げると、ソニー・ロリンズのプレイ(アドリブ)の特徴は、“言うべきことを言い切ってしまう”潔さと責任感にあると思っている。このような言い方は、音楽の用語でもなく実際の演奏とは関係のない言葉の上での精神論のように受け取られるかもしれない。具体的に言うと、ロリンズのフレーズというのは、様々なヴァリエーションがあるけれど、そこに一貫して流れているのは、有節形式で終わらせることではないかと思う。つまり、フレーズというのは、2つ以上の音が続けば何かしら音形として受け取ることができるから、さまざまな可能性はあるけれど、ロリンズの場合は、基調となるコードの上で、最後の音は主調に必ず戻る形になる。聴く者にとっては、メロディが終わったと感じる形を必ずとっているということだ。ロリンズのアドリブのフレーズがうたうようだというのは、ここにひとつの大きな要因があると思う。しかし、このような形で徹底してフレーズを作るというのは、実は大変なことなのだ。まずは、そういう形でフレーズを作ることが出来とは限らないということだ。それはまた、フレーズを作る際に、その可能性を限定して絞ってしまうことになるわけだ。何しろ終わり方が決まってしまうのだから。その制約でフレーズを作るのが大変ということ。そして、もうひとつの困難として、そのようにフレーズを終止形にしてしまうと、後にプレイを続けるのが難しくなるということだ。プレイを続けるには、何時までも終わらない形で、つまりは、フレーズの尻を中途半端にして、次のフレーズに連続させれば、後から後からフレーズを繋ぐことができる。実際、そうやって延々とプレイする人もいる。しかし、いったん終止形のフレーズにしてしまうと、その後で新たなフレーズをつくって始めなければならない。したがって、このように終止形のフレーズにこだわるには、それなりの決心が要る。 他方で、そういう決心ができたからと言って、すぐにそれがプレイでできるとは限らない。そのためには、フレーズを作る即興的な創作力が要るだろうし、それがあってたとしても、例えば、ジョン・コルトレーンのようにいったんフレーズを作ったとしても、何か言いたいことを言い切れていないと感じてしまい、そのフレーズに満足できず、足りない分を付加するように、別のフレーズを足して行って、それが続いてしまう。結果として、プレイが音で埋め尽くされてしまうことになってしまう。コルトレーンの場合は極端な例かもしれないが、フレーズをつくっても、必ずしも満足しきれないケースは他のプレイヤーでも少なからずあろう。しかし、ロリンズの場合には、そこでコルトレーンのように次のフレーズを足すことをしない。そこには、求めたことをすべて満たしたフレーズを毎回作ってしまっているのか分からない。しかし、私には、そうとは思えず、そこではロリンズは、その場合には、あえて付加することを潔く諦めて、次の展開に移って知っているのではないかと思う。 その理由は、ロリンズのつくるフレーズはよくうたうといわれるけれど、陰影とか情緒的なニュアンスのようなものは混じっていないのだ。ロリンズはぶっきらぼうなほど、フレーズを朗々とストレートに吹く。もし、フレーズにもの足りなさを覚えれば、そこに陰影をつけたり、クラシック音楽でいうテンポルバートのようにリズムのズレといった小細工を施すこともできるだろうが、ロリンズはそういうことをすることはない。彼のフレーズがうたうと言われる一方で、彼のプレイが豪快とも言われるのは、そのためではないかと思う。チマチマとした小細工をあえて捨てているからだ。 このように、ロリンズは有節形式のフレーズをつくるということ1本で勝負している。そこに私の見るロリンズの特徴がある。その、私に言わせれば、ストレート一本勝負をもっとも直接的に聴くことのできるのは、1955年から1960年の沈黙までの間に録音されたアルバムということになると思う。 くどいかもいれないが、これは私の個人的な好みである。
|
 ソニー・ロリンズ(テナー・サックス)
ソニー・ロリンズ(テナー・サックス)