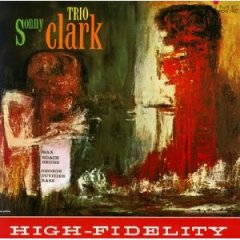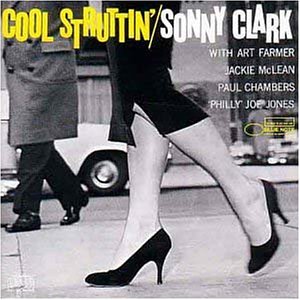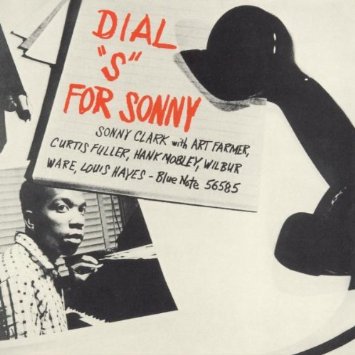|
クラークのピアノについて“哀感に満ちた陰翳の美、ピアノのタッチに込められた硬質な表現”と言われることがあるのは、そういう比較の上でのことで、彼がそういうスタイルを前面に出しているわけではない。例えば、ブルー・ノートに録音した「ソニー・クラーク・トリオ」というアルバムの最初に“朝日のようにさわやかに”という曲を演奏しているが、ウィントン・ケリきる、という感じだ。 クラークのピアノのタッチは深くて強い。それが重心のひくい重い音になって聞こえてくる。そのため音色は暗く沈んだ、渋く感じられる。それがクラークの印象を地味にしている。しかし、打鍵がつよいため音には芯があって音の輪郭は明確だ。だから、地味だからと言って、けっして存在が隠れてしまっているわけではないのだ。その明確なタッチは時に強弱のグラデーションが巧みに使い分けられ、「クール・ストラッティン」以降の録音で顕著になるアクセントを後ろにずらして独特の溜めをつくり、フレーズの尻尾が粘るような、“後ろ髪をひかれる”ような後ノリを生み出すことになる。そのノリで聴くバラードは、思いつめたようなロマンティックな気持ちを感じ、哀愁とも翳りとも感じることにつながる。 しかし、その一方、クラークのプレイは、明確なタッチで端正なのだ。あえて言えば、真摯にフレーズで勝負する姿勢といえる。クラークの即興演奏を聴いていると、バド・パウエルの短い分解されたリフを積み上げると言う行き方とは反対に、水平方向にうねうねとしたメロディラインを伸ばすように紡いでいくように聴こえる。まるで、レニー・トリスターノのように。クラークはそこで、意表を突くようなアクセントを施し、ひねりの効いたメロディにしているところがクラークとトリスターノの違うところだ。それを明確なタッチで、パウエルばりの速いテンポで突進することで緊張感をたかめる。多くの曲でクラークは躍動感のあるビートを押し出し、慌ただしさを強調し、緊張感の高いものにしている。これを例えばウィントン・ケリーだと、リラックスしたスイング感を得るために心もち打鍵を遅らせていた。また、スタカートによるアタックは、クラーク好みのヘビのように曲がりくねった構成とうまくマッチしている。そして、さらに、このような時クラークはバーン!とブロック・コードを叩く、これ見よがしのハッタリを使わずにハイテンポのフレーズを端正に演奏する。これによって、緊張感ある一方で、透明感のある演奏になっている。つまりは、劇的に盛り上がりを煽るようなことはせずに、フレーズで勝負しているのだ。そこに、地味だが味わい深い、という全体の印象が醸し出されるといえる。
バイオグラフィー 麻薬が寿命を大幅に短くしてしまったが、その短い人生でも、ソニー・クラークはバド・パウエルの系統に位置するバップ・ピアニストの中でも最高の一人だった。50年代前半、彼はサンフランシスコでヴィド・ムッソやオスカー・ペティフォードとプレイし、ロサンゼルスに居を定めるとテディ・チャールスと最初のレコーディングを行い、その後1953〜56年、バディ・デ・フランコのカルテットに加わった。彼のバディ・デ・フランコとの録音はモザイク・レコードから豪華限定盤のボックスセットで再発されている。同じ時期に、彼はソニー・クリス、フランク・ロソリーノとライトハウス・オールスターズともプレイしている。1957年にはニュー・ヨークに移り、ブルー・ノート・レコードの専属となった。そこで数枚のリーダー・アルバム(1957年の1年間だけで「Dial S for Sonny」「Cool Struttin'」「Sonny's Crib」の3タイトル)を録音し、ソニー・ロリンズ、ハンク・モブレー、カーティス・フラーやその他のたくさんのミュージシャンたちのサイド・マンとしてプレイした。享年31歳という早すぎる死はジャズにとり大きな損失となった。
|
 黒人ピアノ奏者。
黒人ピアノ奏者。