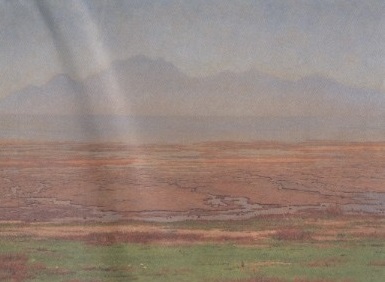�Q�O�Q�T�N�W���P�R���i���j��t�������p��
 �A���������ҏ����ꑧ�����Ǝv������A�O�A�x�͐��~���т̔����ő�J�B�O�A�x���I����������́A�V�C�������̂ŏo�����邱�Ƃɂ����B�i�q�����������t���ʂɂ͉��ʂ肩����B�������œ����w�܂ōs���āA���t���ɏ�芷������ԑ��������̂����A��芷���̕��������������̂ƁA�����f�B�Y�j�[�����h�ɍs���l�����̂ō��G�������ƍl���āA�������Ԃ͂����邪�A�䒃�m���ő������̊e�w��Ԃɏ�芷���Đ�t�w�ցB�����������m���[���Ő�t�݂ȂƂցB���̃��m���[���������H�c��`�̃��m���[���Ƃ������Č������Ƃ����A���[���̏�𑖂�̂ł͂Ȃ��A���[������Ԃ牺��������ŁA�������B�r���̊Ԃ�D���悤�ɑ���̂��A�ƂĂ��ʔ��������B���m���[���̉w���~��āA�i�q�̉��D�̕��Ɍ������ĉw���o��B
�A���������ҏ����ꑧ�����Ǝv������A�O�A�x�͐��~���т̔����ő�J�B�O�A�x���I����������́A�V�C�������̂ŏo�����邱�Ƃɂ����B�i�q�����������t���ʂɂ͉��ʂ肩����B�������œ����w�܂ōs���āA���t���ɏ�芷������ԑ��������̂����A��芷���̕��������������̂ƁA�����f�B�Y�j�[�����h�ɍs���l�����̂ō��G�������ƍl���āA�������Ԃ͂����邪�A�䒃�m���ő������̊e�w��Ԃɏ�芷���Đ�t�w�ցB�����������m���[���Ő�t�݂ȂƂցB���̃��m���[���������H�c��`�̃��m���[���Ƃ������Č������Ƃ����A���[���̏�𑖂�̂ł͂Ȃ��A���[������Ԃ牺��������ŁA�������B�r���̊Ԃ�D���悤�ɑ���̂��A�ƂĂ��ʔ��������B���m���[���̉w���~��āA�i�q�̉��D�̕��Ɍ������ĉw���o��B
 ��t�������p���͐�t�݂ȂƂ̉w����`�̕��ɕ����ĂP�O���قǁB�w�O�ɒn�}�������āA���̂Ƃ���ɑ�ʂ�����������B���͕�����₷���B�����A������������ɂ����B�n�}�ɂ͏ꏊ�Ɠ����͏�����Ă��邪�A�����͂����Ə�����Ă��Ȃ��B���ԏ�̈ē��ƕ��s�җp�����̈ē��̖��������邱�Ƃ��ł���̂ŁA����ɏ]���B���ԏ�ƕ��s�җp�͕������Ⴄ���A���ǁA�ǂ����ɍs���Ă�����ł���B���ԏ�̕������ʓ�����̂悤���B���p�ق̌����͍L���A�������W�����̓V�䂪�����̂��A�s�S�̔��p�قɔ�ׂĂƂĂ��L���A�J���I�ȕ��͋C�B�����̗��َ҂����Ă��A�W���̃R�Z�R�Z���Ă��Ȃ��̂ŁA�X�̓W����i�̊Ԃ��L������Ă���̂ŁA�C�ɂȂ�Ȃ��B
��t�������p���͐�t�݂ȂƂ̉w����`�̕��ɕ����ĂP�O���قǁB�w�O�ɒn�}�������āA���̂Ƃ���ɑ�ʂ�����������B���͕�����₷���B�����A������������ɂ����B�n�}�ɂ͏ꏊ�Ɠ����͏�����Ă��邪�A�����͂����Ə�����Ă��Ȃ��B���ԏ�̈ē��ƕ��s�җp�����̈ē��̖��������邱�Ƃ��ł���̂ŁA����ɏ]���B���ԏ�ƕ��s�җp�͕������Ⴄ���A���ǁA�ǂ����ɍs���Ă�����ł���B���ԏ�̕������ʓ�����̂悤���B���p�ق̌����͍L���A�������W�����̓V�䂪�����̂��A�s�S�̔��p�قɔ�ׂĂƂĂ��L���A�J���I�ȕ��͋C�B�����̗��َ҂����Ă��A�W���̃R�Z�R�Z���Ă��Ȃ��̂ŁA�X�̓W����i�̊Ԃ��L������Ă���̂ŁA�C�ɂȂ�Ȃ��B
�����A���߂��Ɍ��n�ɂ��āA���������W�������n�߁A�W���_���������A�����L���������������邪�A�������A�W����i�����Ă��Ď��Ԃ�Y��Ă��܂��A���H���Ƃ�@��������A�����ւ������A���X�g�������X���Ă��܂����B���͂Ɉ��H�X��������ꂸ�A���ǁA�w�܂ōs���Ă悤�₭�A���������H���Ƃ邱�Ƃ��ł����B
�܂��A�W����i�����Ȃ���A���z��C�Â������Ƃ��蒠�Ƀ������Ă�����A�W�����e�ɐ��������Ă���āA���M�Ƃ`�S�T�C�Y�̉��݂��Ă����Ƃ����B�����炩�牽������Ȃ��̂ɁA�C�����Đ��������Ă��ꂽ�̂́A���ꂵ���B
��Î҂����������̒ʂ���p���܂��B�g������\�Y(�P�W�X�O�`�P�X�V�T)�́A�������o�g�ŁA�����Ⓦ���A��t�ɃA�g���G���\���Ċ��������m��Ƃł��B���O�ɂ́A�قƂ�ǒm���邱�Ƃ͂���܂���ł������A�v��ɂȂ��ĕ]�������܂�A���a�U�P�i�P�X�W�U�j�N�ɕ����������p�قŏ��̉�ړW���J�Â���Ĉȍ~�A�e�n�œW����J�Â���A�ߔN�ł͑S���I�ɂ��悭�m���鑶�݂ƂȂ�܂����B
�����攪�����w�Z�i���E���É���w�j���o�ē����鍑��w�_�w�����Y�w�Ȃ���Ȃő��Ƃ��Ȃ���A���͂̊��҂ɔ����ĉ�Ƃ̓���I�т܂��B�Ɗw�ŊG���w�сA����̔��p�c�̂ɑ������ɁA���s�⎞��̐����ɂ����˂邱�ƂȂ��A����̗��z�ƐM�O�ɂЂ����璉���ł��낤�Ƃ����X�g�C�b�N�Ȑ������́A�o���̌����Ȃ����ׂ̎�����鎄�����ɂ����͓I�ɉf��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�v��T�O�N�̐ߖڂ��@�ɊJ�Â���{�W�́A����܂łɊJ�Â���Ă���������\�Y�W����ő�K�͂̉�ړW�ł��B��\��͂������̂��ƁA�ނ̌|�p���`�����ꂽ���[�c��k��A���U�ɂ킽�莩�g�̂��ǂ���Ƃ��Ă��������I�v�z��ǂ݉����A�N����؉����̍�i�ȂǁA�]���̓W����ł͑傫�����グ���邱�Ƃ��Ȃ����������ɂ��œ_�Ă܂��B
 �܂��A�����������p�ُ����̖�\�Y��W�҂ɂ�鏑�Ȃ���L�A�������̎��������ƂɁA�ނ��ЂƂ�̐l�ԂƂ��Ăǂ̂悤�ɐ����A���͂Ƃǂ̂悤�ȊW��z���A��ƂƂ��Ă̕��݂�i�߂����Ƃ��������ɂ����ڂ��A��\�Y�̐l�ԑ��ɂ����߂Ĕ���܂��B����ɂ́A���̌|�p�ς̔w�i�ɂ�����p�E�⎞��̓�����T�邱�ƂŁA���p�j�̂Ȃ��ɖ�\�Y�̉�Ƃ��ʒu�t���邱�Ƃ��߂����܂��B
�܂��A�����������p�ُ����̖�\�Y��W�҂ɂ�鏑�Ȃ���L�A�������̎��������ƂɁA�ނ��ЂƂ�̐l�ԂƂ��Ăǂ̂悤�ɐ����A���͂Ƃǂ̂悤�ȊW��z���A��ƂƂ��Ă̕��݂�i�߂����Ƃ��������ɂ����ڂ��A��\�Y�̐l�ԑ��ɂ����߂Ĕ���܂��B����ɂ́A���̌|�p�ς̔w�i�ɂ�����p�E�⎞��̓�����T�邱�ƂŁA���p�j�̂Ȃ��ɖ�\�Y�̉�Ƃ��ʒu�t���邱�Ƃ��߂����܂��B
�{�W���A��\�Y��i�̖��͂����L���`����ƂƂ��ɁA�u�Ǎ��̉�Ɓv�ƌĂ�Ă����]���̖�\�Y�������ߒ����@��ƂȂ�܂�����K���ł��B�h
������\�Y�ɂ��ẮA�Q�O�P�U�N�ɖڍ�����p�ق��u�v��S�O�N�@������\�Y�W�v�����āA���̍�i�ɖ����ꂽ�v���o������܂��B����A�܂��v��T�O�N�ʼn�ړW���J�Â����Ƃ������ƂŁA��i�ɍĉ�ł��邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă����B�P�O�N�O�̖ڍ�����p�قƓW���̋敪�͓����悤�ł��B�X�̍�i�̔z�u�͏����Ⴂ�܂����A�P�O�N�O�ƁA���̌������ς���Ă��邩�ǂ������m���߂Ȃ���A�W�������Ă������Ƃ��ł��܂����B
����ł́A��I�Ɍ��Ă����܂��傤�B
�v�����[�O�@��\�Y�Ƃ͒N��
������\�Y�̊T�v���Љ��R�[�i�[�ŁA���ꂩ��W�������e�͂���ЂƂ���i���s�b�N�A�b�v���āA����������i���Ƃ����悤�ȏЉ�ł��B�e�͂�����ɐ߂ɍו������ēW������Ă��܂��B
�N��

 �u���q���������鎩�摜�v�Ƃ����P�X�Q�O�N�̍����Q�X�̂Ƃ��̍�i�B�k�����l�T���X�̃A���u���q�g�E�f���[���[�̉e�����Ă����Ɛ�������Ă��܂������A���������f���[���[�̎��摜��͂����悤�ɁA���ʂ��������p�Ŏ������Ƃ炦�Ă��āA�܂������ɂ���������߂�܂Ȃ����̋����A�����Čł����ꂽ�����Ƃ́A�ƂĂ���ۂɎc��܂��B���q�́A�T�@�ŗp������@�߂̈��ŁA�f���[���[�̎��摜�ł̓K�E�����H�D���Ă����̂�͂��āA�g�p�����̂ł��傤���B�Q�O���I�̗l�X�ȊG��^�����N�������Ȃ��ŁA�����͏I���A�k���Ȏʎ����痣��܂���ł����B�Ƃ͌����Ă��A���O�Ƃ����j�Ƃ��Ďʐ��Ƃ����A���Y�������������Ƃ������A�G���n�߂��Ƃ��ɂ���{�ɂ�����Ƃ��ʎ��I�ȉ敗���������Ƃ���A�����������Ƃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A��ŁA�����̍�i�����Ă����ƋC�����Ǝv���܂����A�������Ɏʐ��Ȃ�ł��傤���A���̎ʐ�����Ώۂ̌��������A���Y���Ƃ������A�Ɠ��̊G��I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���̂ł��B���̂ЂƂ̗v�f���A�f���[���[�̍ז��ȕ`�ʂ����Ȃ����u�������R���A�v�̂悤�Ȑ_���`�I�ȍ�i�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B�W����`���V�ɂ���g���ł͂Ȃ��A�ł�`�����������B�ł�`�����߂ɁA����`�����̂ł��B�h�Ƃ������t�ɂ���悤�ɁA�P�Ɍ�������̂�`���������łȂ��A�����Ȃ����̂�`���Ƃ����v�f�ł��B����́A��������̂�`���Ă��Ă��A�����Ɍ����Ȃ����̂����f���Ă���B���������ʎ��ł��B���̎��摜�̍����̋��������́A�����Ȃ����̂Ɍ������Ă���̂�������܂���B
�u���q���������鎩�摜�v�Ƃ����P�X�Q�O�N�̍����Q�X�̂Ƃ��̍�i�B�k�����l�T���X�̃A���u���q�g�E�f���[���[�̉e�����Ă����Ɛ�������Ă��܂������A���������f���[���[�̎��摜��͂����悤�ɁA���ʂ��������p�Ŏ������Ƃ炦�Ă��āA�܂������ɂ���������߂�܂Ȃ����̋����A�����Čł����ꂽ�����Ƃ́A�ƂĂ���ۂɎc��܂��B���q�́A�T�@�ŗp������@�߂̈��ŁA�f���[���[�̎��摜�ł̓K�E�����H�D���Ă����̂�͂��āA�g�p�����̂ł��傤���B�Q�O���I�̗l�X�ȊG��^�����N�������Ȃ��ŁA�����͏I���A�k���Ȏʎ����痣��܂���ł����B�Ƃ͌����Ă��A���O�Ƃ����j�Ƃ��Ďʐ��Ƃ����A���Y�������������Ƃ������A�G���n�߂��Ƃ��ɂ���{�ɂ�����Ƃ��ʎ��I�ȉ敗���������Ƃ���A�����������Ƃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A��ŁA�����̍�i�����Ă����ƋC�����Ǝv���܂����A�������Ɏʐ��Ȃ�ł��傤���A���̎ʐ�����Ώۂ̌��������A���Y���Ƃ������A�Ɠ��̊G��I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���̂ł��B���̂ЂƂ̗v�f���A�f���[���[�̍ז��ȕ`�ʂ����Ȃ����u�������R���A�v�̂悤�Ȑ_���`�I�ȍ�i�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B�W����`���V�ɂ���g���ł͂Ȃ��A�ł�`�����������B�ł�`�����߂ɁA����`�����̂ł��B�h�Ƃ������t�ɂ���悤�ɁA�P�Ɍ�������̂�`���������łȂ��A�����Ȃ����̂�`���Ƃ����v�f�ł��B����́A��������̂�`���Ă��Ă��A�����Ɍ����Ȃ����̂����f���Ă���B���������ʎ��ł��B���̎��摜�̍����̋��������́A�����Ȃ����̂Ɍ������Ă���̂�������܂���B
 �������u�X�C�v�𑽐��`���Ă��܂����A����͍ł��Â��Ƃ�����i�B�P�O�N�O�̖ڍ�����p�ق̓W���ł́A�ЂƂ̕����ɘX�C�̊G���萔�\�_���W�߂āA�W������Ă����̂ŁA���͂͂����������̂ł����A�����悤�ȍ�i���Y���b�ƕ���ł����̂ŁA�ЂƂЂƂ̍�i������ӗ~�������Ă��܂������Ƃ�����܂����B����̓W���͂����ł͂Ȃ��A�ЂƂW������Ă����̂ŁA���������Č��邱�Ƃ��ł��܂����B�����ȉ�ʂ̒��S�ɂP�{�̘X�C�݂̂��`����Ă���݂̂ł��B���́g���͂��˂�Ȃ���V�Ɍ������ď㏸����B�Â��F���̂Ȃ��ɕ����яオ��悤�ɕ`���ꂽ�h��߂����A���̗͂z���������������ƈł̑Δ䂪�h���}�e�B�b�N�ɕ\������Ă���h�ƃL���v�V�����Ő�������Ă��܂����B�X�C�Ƃ��̉��͌�������̂ł����A�ł͌����܂���B���̌����Ȃ��ł�`�����߂ɁA����`���āA���̌����琶����A��`�����Ƃ��ł����A�Ƃ������̂ł��悤�B
�������u�X�C�v�𑽐��`���Ă��܂����A����͍ł��Â��Ƃ�����i�B�P�O�N�O�̖ڍ�����p�ق̓W���ł́A�ЂƂ̕����ɘX�C�̊G���萔�\�_���W�߂āA�W������Ă����̂ŁA���͂͂����������̂ł����A�����悤�ȍ�i���Y���b�ƕ���ł����̂ŁA�ЂƂЂƂ̍�i������ӗ~�������Ă��܂������Ƃ�����܂����B����̓W���͂����ł͂Ȃ��A�ЂƂW������Ă����̂ŁA���������Č��邱�Ƃ��ł��܂����B�����ȉ�ʂ̒��S�ɂP�{�̘X�C�݂̂��`����Ă���݂̂ł��B���́g���͂��˂�Ȃ���V�Ɍ������ď㏸����B�Â��F���̂Ȃ��ɕ����яオ��悤�ɕ`���ꂽ�h��߂����A���̗͂z���������������ƈł̑Δ䂪�h���}�e�B�b�N�ɕ\������Ă���h�ƃL���v�V�����Ő�������Ă��܂����B�X�C�Ƃ��̉��͌�������̂ł����A�ł͌����܂���B���̌����Ȃ��ł�`�����߂ɁA����`���āA���̌����琶����A��`�����Ƃ��ł����A�Ƃ������̂ł��悤�B
 �u��Ƃ�v�͂P�X�Q�R�N�̐Õ���ł��B
�����͑����̐Õ����`���܂����B�u���q���������鎩�摜�v���f���[���[�̉e���Ȃ�A���̍�i�̓t�@���E�S�b�z�̉e�����������i�ł��B�w�i�̕ǂɂ́A�����R���オ��悤�Ȃ��˂��˂������������Ɉ�����Ă��āA�S�b�z�̔ӔN�̓�t�����X�̕��i��`�����ۂ̐��������Ƃ��āA�����̂�������\�����Ă���悤�Ȑ���͂��Ă���悤�Ȋ������܂��B�܂��A��̃S�c�S�c�����Ƃ�����̉����c��ł���Ƃ���ȂǁA�S�b�z�̖͂��Ă���Ƃ��낪�M���܂��B����͑z���ł����A��B�̂�����s��ł͂Ȃ��Ƃ���ŏ��N������߂����A�����ɏo�Ă��Ă���w�_�w���Ŋw�Ƃ������Ƃ���A���m�̉�Ƃ̐G���`�����X�͏��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���̂悤�Ȓ��ŁA�o��邱�Ƃ��ł�����Ƃ��S�b�z�ł���f���[���[�ł�������ŁA���܂��܁A�ނ�̍�i�Əo����������́A���ꂪ�G��Ƃ������̂��Ƃ������̂�A���t�����Ă��܂����B���̌�A�����̓��[���b�p�ɗ��w����������邪�A���̎��ɂ͂�����x�̔N��ɂȂ��āA�G��ς͌ł܂��Ă��ėh�邪�Ȃ������Ƃ����̂ł͂Ȃ����B
�u��Ƃ�v�͂P�X�Q�R�N�̐Õ���ł��B
�����͑����̐Õ����`���܂����B�u���q���������鎩�摜�v���f���[���[�̉e���Ȃ�A���̍�i�̓t�@���E�S�b�z�̉e�����������i�ł��B�w�i�̕ǂɂ́A�����R���オ��悤�Ȃ��˂��˂������������Ɉ�����Ă��āA�S�b�z�̔ӔN�̓�t�����X�̕��i��`�����ۂ̐��������Ƃ��āA�����̂�������\�����Ă���悤�Ȑ���͂��Ă���悤�Ȋ������܂��B�܂��A��̃S�c�S�c�����Ƃ�����̉����c��ł���Ƃ���ȂǁA�S�b�z�̖͂��Ă���Ƃ��낪�M���܂��B����͑z���ł����A��B�̂�����s��ł͂Ȃ��Ƃ���ŏ��N������߂����A�����ɏo�Ă��Ă���w�_�w���Ŋw�Ƃ������Ƃ���A���m�̉�Ƃ̐G���`�����X�͏��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���̂悤�Ȓ��ŁA�o��邱�Ƃ��ł�����Ƃ��S�b�z�ł���f���[���[�ł�������ŁA���܂��܁A�ނ�̍�i�Əo����������́A���ꂪ�G��Ƃ������̂��Ƃ������̂�A���t�����Ă��܂����B���̌�A�����̓��[���b�p�ɗ��w����������邪�A���̎��ɂ͂�����x�̔N��ɂȂ��āA�G��ς͌ł܂��Ă��ėh�邪�Ȃ������Ƃ����̂ł͂Ȃ����B
�؉����B��O��
 �u�m�[�g���_���ƃ����^�[�j���ʂ�v�͂P�X�R�Q�N�A�����S�Q�̎��̍�i�ł��B�����̓��{�l��Ƃ͂Q�O��̎Ⴂ�����ɗ��w���āA����ȉe������̂ł��傤���A�����̏ꍇ�̂悤�ȂS�O��ł͌ł܂��Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����B����قlj敗�̖ڂ������ω��͌����܂���B���̂���̃p���ɂ́A�Q�O���I�G��̑�\�I�ȉ�Ƃ��W�܂��Ă��āA�Ő�[�̌|�p���Ђ��߂��Ă����Ǝv����̂ɁA�ł��B���̍�i�ł́A�p���̓s�s�̌��z������������ƕ`����Ă��āA��ʂ̍����Ƀ[���j�E���̐Ԃ��Ԃ����z�̒����I�ȕ`�ʂƑΏƓI�ɁA�S�b�z�I�Ȃ��˂��˂������Ő�����������悤�ȕ`����������āA��������ۓI�ł����B
�u�m�[�g���_���ƃ����^�[�j���ʂ�v�͂P�X�R�Q�N�A�����S�Q�̎��̍�i�ł��B�����̓��{�l��Ƃ͂Q�O��̎Ⴂ�����ɗ��w���āA����ȉe������̂ł��傤���A�����̏ꍇ�̂悤�ȂS�O��ł͌ł܂��Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����B����قlj敗�̖ڂ������ω��͌����܂���B���̂���̃p���ɂ́A�Q�O���I�G��̑�\�I�ȉ�Ƃ��W�܂��Ă��āA�Ő�[�̌|�p���Ђ��߂��Ă����Ǝv����̂ɁA�ł��B���̍�i�ł́A�p���̓s�s�̌��z������������ƕ`����Ă��āA��ʂ̍����Ƀ[���j�E���̐Ԃ��Ԃ����z�̒����I�ȕ`�ʂƑΏƓI�ɁA�S�b�z�I�Ȃ��˂��˂������Ő�����������悤�ȕ`����������āA��������ۓI�ł����B
 �u���炷����v�͂P�X�R�R�N�̍�i�ŁA�����͐A����`�����Õ���𑽂��`���Ă��āA���̂����̈ꖇ�ł��B�܂��u���炷����v�͉��_������A����́A���̂����̈�_�ł��B�����͑�w�_�w���Ō����҂Ƃ��ĉ߂������킯�ł����A�����̗��Ȍn�̌����҂͊ώ@�̋L�^���c�����߂ɃX�P�b�`�̋Z�p�����߂��Ă����͂��ł��B���݂����ɃJ��������ʓI�Ő��\�������Ȃ������̂ŁA������ώ@�������́A�Ⴆ�Ό������Ō������̂��A�ʐ^�ɑ����Đ��m�ȋL�^�ɂ̂������߂ɃX�P�b�`�����Ă����͂��ŁA�����̎ʎ��I�ȉ敗�̊�b�͂��������Ƃ���ɂ������̂ł͂Ȃ����ƁA�l�I�ɑz�����܂��B���ꂾ����A�`�m�ɂ͂����蕪����悤�ɏ����K�v������܂����A�������A����`���ۂɁA�s�Ȃǂ̗֊s�̐����ڗ��قǂ�������ƕ`���Ă���̂́A������������������Ă���̂ł͂Ȃ����B�������A�W�{�̂悤�Ɍ`�Ԃ𑵂��鑀�삪�ׂ���Ă���悤�Ɍ����܂��B���̍�i�ł́A���S�������߂āA��ʂ̏㕔����a���^�Ɏ}���Ђ낪��悤�ɐ��ꉺ����\�}�ň��芴�����o���Ă��܂��B
�u���炷����v�͂P�X�R�R�N�̍�i�ŁA�����͐A����`�����Õ���𑽂��`���Ă��āA���̂����̈ꖇ�ł��B�܂��u���炷����v�͉��_������A����́A���̂����̈�_�ł��B�����͑�w�_�w���Ō����҂Ƃ��ĉ߂������킯�ł����A�����̗��Ȍn�̌����҂͊ώ@�̋L�^���c�����߂ɃX�P�b�`�̋Z�p�����߂��Ă����͂��ł��B���݂����ɃJ��������ʓI�Ő��\�������Ȃ������̂ŁA������ώ@�������́A�Ⴆ�Ό������Ō������̂��A�ʐ^�ɑ����Đ��m�ȋL�^�ɂ̂������߂ɃX�P�b�`�����Ă����͂��ŁA�����̎ʎ��I�ȉ敗�̊�b�͂��������Ƃ���ɂ������̂ł͂Ȃ����ƁA�l�I�ɑz�����܂��B���ꂾ����A�`�m�ɂ͂����蕪����悤�ɏ����K�v������܂����A�������A����`���ۂɁA�s�Ȃǂ̗֊s�̐����ڗ��قǂ�������ƕ`���Ă���̂́A������������������Ă���̂ł͂Ȃ����B�������A�W�{�̂悤�Ɍ`�Ԃ𑵂��鑀�삪�ׂ���Ă���悤�Ɍ����܂��B���̍�i�ł́A���S�������߂āA��ʂ̏㕔����a���^�Ɏ}���Ђ낪��悤�ɐ��ꉺ����\�}�ň��芴�����o���Ă��܂��B
�����E������
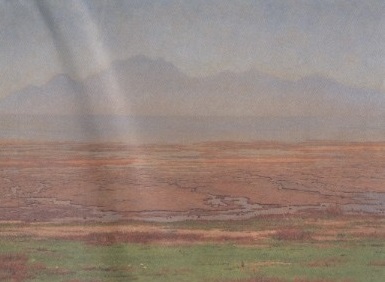
 �푈���A�����͌̋��̕������ɑa�J���A��B�̕��i��`���ƁA���ꂩ����{�����𗷂��āA���i���`���n�߂܂��B�u�t�̊C�v�i�E���j�͂P�X�T�Q�N�ɗL���C��`������i�ł��B���ƓD�������Ȃ��čL����L���C�̊����̌i�ς��A�t���ɉ���_��̃V���G�b�g��w�i�ɂ��ĕ`���Ă��܂��B�x���̍L����Ɨy���ɉ_����̂��މ��s�Ƃ̃R���g���X�g�B���̍�i�́A�P�O�N�O�̖ڍ�����p�قł��W������Ă��ċL���Ɏc���Ă��܂��B���̎��́A�h�C�c�E���}���h�̃t���[�h���q���u�h���X�f���ߍx�̑���v�i�����j�Ƃ�����i�Ɏ��Ă���Ǝv���܂����B���̃t���[�h���q�̍�i���Ă�����Ɍ��Ă����ƁA��ʂ͎�O�̎����i�����́u�t�̊C�v�͊����j�Ɖ��i�̋�̊Ԃɂ͋��E���̂悤�ɖX�̍����e�������āA���̋��E�����͂���őΗ��I�ȍ\�}�ɂȂ��Ă��āA�����͉��s�������������̕����A�܂莼���̍L����ɓ�����܂��B���̍s��������́A��ʂɕ`����Ă��Ȃ��A��ʂƂ����g�����O���̍L����ł��B�����́u�t�̊C�v�ɂ��A���炩�ɓ����悤�Ȏ����̕���������Ǝv���܂��B�������A�t���[�h���q�̍�i�̂悤�ȑΗ��I�ȗv�f�͍T���߂ɂȂ�A���̕��A�ْ����͊ɘa����A�������͎͂�܂�܂��B���̎����́A�ǂ��֍s���̂��Ƃ����ƁA��O�́A�t�̐V�̊C�݂̑��̍ז��ȕ`�ʂł��B����A�a�̂ł����{�̎��̂悤�Ȏ�@�ŁA���i�̍L����A�����ɓ_�݂���t�̑����Ɍ���҂̎������Ă���ƌ����܂��B
�푈���A�����͌̋��̕������ɑa�J���A��B�̕��i��`���ƁA���ꂩ����{�����𗷂��āA���i���`���n�߂܂��B�u�t�̊C�v�i�E���j�͂P�X�T�Q�N�ɗL���C��`������i�ł��B���ƓD�������Ȃ��čL����L���C�̊����̌i�ς��A�t���ɉ���_��̃V���G�b�g��w�i�ɂ��ĕ`���Ă��܂��B�x���̍L����Ɨy���ɉ_����̂��މ��s�Ƃ̃R���g���X�g�B���̍�i�́A�P�O�N�O�̖ڍ�����p�قł��W������Ă��ċL���Ɏc���Ă��܂��B���̎��́A�h�C�c�E���}���h�̃t���[�h���q���u�h���X�f���ߍx�̑���v�i�����j�Ƃ�����i�Ɏ��Ă���Ǝv���܂����B���̃t���[�h���q�̍�i���Ă�����Ɍ��Ă����ƁA��ʂ͎�O�̎����i�����́u�t�̊C�v�͊����j�Ɖ��i�̋�̊Ԃɂ͋��E���̂悤�ɖX�̍����e�������āA���̋��E�����͂���őΗ��I�ȍ\�}�ɂȂ��Ă��āA�����͉��s�������������̕����A�܂莼���̍L����ɓ�����܂��B���̍s��������́A��ʂɕ`����Ă��Ȃ��A��ʂƂ����g�����O���̍L����ł��B�����́u�t�̊C�v�ɂ��A���炩�ɓ����悤�Ȏ����̕���������Ǝv���܂��B�������A�t���[�h���q�̍�i�̂悤�ȑΗ��I�ȗv�f�͍T���߂ɂȂ�A���̕��A�ْ����͊ɘa����A�������͎͂�܂�܂��B���̎����́A�ǂ��֍s���̂��Ƃ����ƁA��O�́A�t�̐V�̊C�݂̑��̍ז��ȕ`�ʂł��B����A�a�̂ł����{�̎��̂悤�Ȏ�@�ŁA���i�̍L����A�����ɓ_�݂���t�̑����Ɍ���҂̎������Ă���ƌ����܂��B

 �u�������̒r�v�i�E���j�͂P�X�S�X�N�̍�i�ŁA�V�h�䉑�̒r��`�����Ƃ����A�U�O���T�C�Y�̑��ł��B���̃T�C�Y�ɂ�������炸�A�т�����ƍז��ɕ`�����܂ꂽ�Z���ȍ�i�ł��B�@�̒r��`�����G���i�Ƃ��Ă����l�i�����j���ӔN�ɑ����̍�i��`�������Ƃ͗L���ŁA���{�ł͈��D�҂���������Ǝv���܂����A���l�̕`�����Ɣ�ׂ�ƁA�����͙{���ʂȂقǘ@�̉Ԃ�t�A���邢�͒r�̎��͂ɖ鑐����т̗֊s����������ƕ`���Ă��܂��B�ǂ��܂ł��������肵�Ă��āA����͌��ʂƂ��āA��C���ߖ@�̉����ɂȂ�ɏ]���ĉ���ł����Ƃ����`�������Ƃ��Ă��܂���B���̂��߂ɁA��ʂ̋�Ԃɉ��s����������ꂸ�A���ʂȐ}�ʂƂ��}�Ă̂悤�Ɍ����܂��B��̓I�Ɍ����ƁA��ʎ�O���̓˂��o���y��ɉ������ɖ��Ă���Ƃ��낪�O�i�ŁA�r�̒����ɎR��������������܂��e���f���Ă���̂��ւĉE��ɂ������Ƃ������̖݂�����Ƃ��낪���i�A�����Đ��ʂ̒r�̉��Ɣw��̎��т���i�Ƃ��āA�O�̏�ʂ����ꂼ�ꂠ���āA�����r�̐��ʂ��Ȃ��ڂ̖������ʂ����āA�O�̌i�F��������Ԃɂ��邩�̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B���G�Ő��m�G��̕��i��̑̍ق��Ƃ��Ă���̂ŁA���܂�A����ȕ��ɂ͌����Ȃ������m��܂��A���́u�������̒r�v�Ƃ�����i�́A�O�i�A���i�A��i�ƁA�������Ȃ��r�̐��ʂƂ����S�̕��ʂ���\�����ꂽ��i�ł���Ǝv���܂��B������A�Ⴆ�A
�u�������̒r�v�i�E���j�͂P�X�S�X�N�̍�i�ŁA�V�h�䉑�̒r��`�����Ƃ����A�U�O���T�C�Y�̑��ł��B���̃T�C�Y�ɂ�������炸�A�т�����ƍז��ɕ`�����܂ꂽ�Z���ȍ�i�ł��B�@�̒r��`�����G���i�Ƃ��Ă����l�i�����j���ӔN�ɑ����̍�i��`�������Ƃ͗L���ŁA���{�ł͈��D�҂���������Ǝv���܂����A���l�̕`�����Ɣ�ׂ�ƁA�����͙{���ʂȂقǘ@�̉Ԃ�t�A���邢�͒r�̎��͂ɖ鑐����т̗֊s����������ƕ`���Ă��܂��B�ǂ��܂ł��������肵�Ă��āA����͌��ʂƂ��āA��C���ߖ@�̉����ɂȂ�ɏ]���ĉ���ł����Ƃ����`�������Ƃ��Ă��܂���B���̂��߂ɁA��ʂ̋�Ԃɉ��s����������ꂸ�A���ʂȐ}�ʂƂ��}�Ă̂悤�Ɍ����܂��B��̓I�Ɍ����ƁA��ʎ�O���̓˂��o���y��ɉ������ɖ��Ă���Ƃ��낪�O�i�ŁA�r�̒����ɎR��������������܂��e���f���Ă���̂��ւĉE��ɂ������Ƃ������̖݂�����Ƃ��낪���i�A�����Đ��ʂ̒r�̉��Ɣw��̎��т���i�Ƃ��āA�O�̏�ʂ����ꂼ�ꂠ���āA�����r�̐��ʂ��Ȃ��ڂ̖������ʂ����āA�O�̌i�F��������Ԃɂ��邩�̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B���G�Ő��m�G��̕��i��̑̍ق��Ƃ��Ă���̂ŁA���܂�A����ȕ��ɂ͌����Ȃ������m��܂��A���́u�������̒r�v�Ƃ�����i�́A�O�i�A���i�A��i�ƁA�������Ȃ��r�̐��ʂƂ����S�̕��ʂ���\�����ꂽ��i�ł���Ǝv���܂��B������A�Ⴆ�A �]�ˎ��㒆���̗Ԕh�̎v����f�t�H�������ꂽ�f�U�C�����̂悤�ț����G�A�Ⴆ�J�L�c�o�^�̛����Ɩ{���I�ɂ͂��Ȃ�߂��Ƃ���ɂ����i�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A��ʋ�Ԃ����͕��ʂ̑g�ݍ��킹�ł��邱�ƈȊO�ɁA�ז��ɕ`�����܂�Ă���r�ɕ����Ԑ��@�̉Ԃ�t�����m�ȗ֊s�ŁA�܂�ŐA���}�ӂ̐}�̂悤�ɕ`����Ă��邱�Ƃ��A�����I�ȑ��݊��A���A���e�B���ނ��댸�ނ����āA�}�Ă̂悤�Ɍ����Ă���̂ł��B���@�̔����Ԃ��r�ɕ�����ł��܂����A���̉Ԃ́A�܂�ŃR�s�[�E�A���h�E�y�[�X�g�����悤�ɁA�X�̉ԂɌ����Ȃ��̂ł��B���̓_�ł��Ԕh�̛����̃J�L�c�o�^�̃f�U�C���}�̂悤�ȁA���̋L���̂悤�ɕ`����Ă���̂ƁA��@�̖{���I�ȂƂ���͋��ʓ_�������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�����̏K��I�ȍ�i�����Ă������ł́A�����Ƃ����l�͎��̂Ƃ���A�܂�ו�����`���n�߁A���̌��ʂ��S�̂����߂�Ƃ����s�������Ƃ��Ă���悤�Ɍ����܂��B���̂��߉�ʑS�̂����G�ȍ\�����Ƃ��Ă����i�͂���܂���ł����B�����{�l�ɂ��A���̂��Ƃɑ��鎩�o�͂������̂�������܂���B���̏؋��Ƃ����킯�ł͂���܂��A�������n�������P�X�R�O�N��̃��[���b�p�ł̓Z�U���k�ɒ[���Ƃ���V���ȑ��`�����s�����Ƃ��������Ă�������ł��������킯�ŁA�s�J�\��u���b�N�͌����ɋy���A�G�R�[���E�h�E�p���̃��[�u�����g�⒊�ۂ������Ă����̂��A�����͖�������悤�ɁA���̉e���̂�����������܂���B�z���ł����A�����ɂ́A���������V�������`�ɕK�v�Ƃ���Ă����\�z�͂̂悤�Ȃ��̂����g�����Ă����Ƃ������o�������āA�����������̂Ɏ�o���ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����B�Ƃ��������A�n���������ƂŁA�������g�A���̂��Ƃɔۉ����Ȃ��C����
�]�ˎ��㒆���̗Ԕh�̎v����f�t�H�������ꂽ�f�U�C�����̂悤�ț����G�A�Ⴆ�J�L�c�o�^�̛����Ɩ{���I�ɂ͂��Ȃ�߂��Ƃ���ɂ����i�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A��ʋ�Ԃ����͕��ʂ̑g�ݍ��킹�ł��邱�ƈȊO�ɁA�ז��ɕ`�����܂�Ă���r�ɕ����Ԑ��@�̉Ԃ�t�����m�ȗ֊s�ŁA�܂�ŐA���}�ӂ̐}�̂悤�ɕ`����Ă��邱�Ƃ��A�����I�ȑ��݊��A���A���e�B���ނ��댸�ނ����āA�}�Ă̂悤�Ɍ����Ă���̂ł��B���@�̔����Ԃ��r�ɕ�����ł��܂����A���̉Ԃ́A�܂�ŃR�s�[�E�A���h�E�y�[�X�g�����悤�ɁA�X�̉ԂɌ����Ȃ��̂ł��B���̓_�ł��Ԕh�̛����̃J�L�c�o�^�̃f�U�C���}�̂悤�ȁA���̋L���̂悤�ɕ`����Ă���̂ƁA��@�̖{���I�ȂƂ���͋��ʓ_�������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�����̏K��I�ȍ�i�����Ă������ł́A�����Ƃ����l�͎��̂Ƃ���A�܂�ו�����`���n�߁A���̌��ʂ��S�̂����߂�Ƃ����s�������Ƃ��Ă���悤�Ɍ����܂��B���̂��߉�ʑS�̂����G�ȍ\�����Ƃ��Ă����i�͂���܂���ł����B�����{�l�ɂ��A���̂��Ƃɑ��鎩�o�͂������̂�������܂���B���̏؋��Ƃ����킯�ł͂���܂��A�������n�������P�X�R�O�N��̃��[���b�p�ł̓Z�U���k�ɒ[���Ƃ���V���ȑ��`�����s�����Ƃ��������Ă�������ł��������킯�ŁA�s�J�\��u���b�N�͌����ɋy���A�G�R�[���E�h�E�p���̃��[�u�����g�⒊�ۂ������Ă����̂��A�����͖�������悤�ɁA���̉e���̂�����������܂���B�z���ł����A�����ɂ́A���������V�������`�ɕK�v�Ƃ���Ă����\�z�͂̂悤�Ȃ��̂����g�����Ă����Ƃ������o�������āA�����������̂Ɏ�o���ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����B�Ƃ��������A�n���������ƂŁA�������g�A���̂��Ƃɔۉ����Ȃ��C���� ���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B����́A���̖ϑz��������܂��A�����œW������Ă��鍂���̕��i������Ă���ƁA��ނƂ��A���̑�ނ̎��グ���Ƃ������Ƃɂ̓��j�[�N�����Ȃ��āA�ނ���}�f�ł��炠��̂ł��B�[�I�Ɍ����A�����̕��i��͊G�t���I�Ȃ̂ł��B�������A�����̐^�����͂��������ɂ���܂��B���́u�������̒r�v���́A�R�s�[�E�A���h�E�y�[�X�g���ꂽ�悤�Ȕ������@�̉Ԃ̃��C�A�E�g�ŁA���̔����A�N�Z���g�ɂ����A�ꌩ�n���ȕ��i�̒��ŗl�X�ȐF�ʂ����؋��̂悤�ɓ_�`�ׂ̍��ȃ{�b�g�Ō������������G���ɂ���܂��B����́A�ςȔ�g��������܂��A�Ԕh�̑�_�ȃf�U�C���I�ț������������ŕ`���Ȃ������悤�Ȃ��̂ł��B���̍�i����P�U�N��̂P�X�U�T�N���u���@�v�Ƃ�����i�ł́A�P�X�S�X�N�̓_�`�̂悤�ȍו��̕`�ʂ������ߏ�Ƃ�������قǂ������̂ɑ��āA���{��̂悤�ɃX�b�L���Ƃ�����ʂŁA�������Ɉ���Ƃ�������捂Ȋ��������܂��B�ז��ȕ`�ʂ͑��ς�炸�ł����A�`�ʂ͐������Ă��āA���`����Ă��鐇�@�̉Ԃ͐A���}�ӂ̐}�̂悤�Ȑ��m�ɐ������Ă��܂��B�����������@�̉Ԃ����������Ă���͕̂���̂悤�Ɍ����Ă��܂��B
���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B����́A���̖ϑz��������܂��A�����œW������Ă��鍂���̕��i������Ă���ƁA��ނƂ��A���̑�ނ̎��グ���Ƃ������Ƃɂ̓��j�[�N�����Ȃ��āA�ނ���}�f�ł��炠��̂ł��B�[�I�Ɍ����A�����̕��i��͊G�t���I�Ȃ̂ł��B�������A�����̐^�����͂��������ɂ���܂��B���́u�������̒r�v���́A�R�s�[�E�A���h�E�y�[�X�g���ꂽ�悤�Ȕ������@�̉Ԃ̃��C�A�E�g�ŁA���̔����A�N�Z���g�ɂ����A�ꌩ�n���ȕ��i�̒��ŗl�X�ȐF�ʂ����؋��̂悤�ɓ_�`�ׂ̍��ȃ{�b�g�Ō������������G���ɂ���܂��B����́A�ςȔ�g��������܂��A�Ԕh�̑�_�ȃf�U�C���I�ț������������ŕ`���Ȃ������悤�Ȃ��̂ł��B���̍�i����P�U�N��̂P�X�U�T�N���u���@�v�Ƃ�����i�ł́A�P�X�S�X�N�̓_�`�̂悤�ȍו��̕`�ʂ������ߏ�Ƃ�������قǂ������̂ɑ��āA���{��̂悤�ɃX�b�L���Ƃ�����ʂŁA�������Ɉ���Ƃ�������捂Ȋ��������܂��B�ז��ȕ`�ʂ͑��ς�炸�ł����A�`�ʂ͐������Ă��āA���`����Ă��鐇�@�̉Ԃ͐A���}�ӂ̐}�̂悤�Ȑ��m�ɐ������Ă��܂��B�����������@�̉Ԃ����������Ă���͕̂���̂悤�Ɍ����Ă��܂��B
 �u���@�v�ƕ���œW������Ă����̂��P�X�U�V�N�́u�����v�Ƃ�����i�ł��B��捂œV��̌i�F�̂悤�ȁu���@�v�Ƃ͑ΏƓI�ŁA���{���̂����̉Ԃ����ĕ���ł��܂��B�Ԃ��x���邷�ׂĂׂ̍��s�ɗ֊s�����͂�����Ǝ{����Ă��邽�߁A�s�̏c��������������B�܂�ł����̉Ԃ���L�яオ�낤�Ƃ��Ă��邩�̂悤�ȕs�v�c�Ȉ�ۂ�^���܂��B�͂�����Ƃ����֊s�����s��t�̂��ׂĂɎ{����A�܂�Ő��`�̂悤�ȉ�ʂ́A���ʓI�ɂ݂��āi���͂����̌s�ƌs�̊Ԃ��牜���̎R���̕��i�����������āA���s��������j�A��ʂ���ŕ����s�������炢�̈�ۂ́A������ƍ앗���Ⴄ�̂ł����A�A�����E���\�[�̔M�ѕ��̔ɖ���W�����O����`������ʂ�f�i�Ƃ����܂��B
�u���@�v�ƕ���œW������Ă����̂��P�X�U�V�N�́u�����v�Ƃ�����i�ł��B��捂œV��̌i�F�̂悤�ȁu���@�v�Ƃ͑ΏƓI�ŁA���{���̂����̉Ԃ����ĕ���ł��܂��B�Ԃ��x���邷�ׂĂׂ̍��s�ɗ֊s�����͂�����Ǝ{����Ă��邽�߁A�s�̏c��������������B�܂�ł����̉Ԃ���L�яオ�낤�Ƃ��Ă��邩�̂悤�ȕs�v�c�Ȉ�ۂ�^���܂��B�͂�����Ƃ����֊s�����s��t�̂��ׂĂɎ{����A�܂�Ő��`�̂悤�ȉ�ʂ́A���ʓI�ɂ݂��āi���͂����̌s�ƌs�̊Ԃ��牜���̎R���̕��i�����������āA���s��������j�A��ʂ���ŕ����s�������炢�̈�ۂ́A������ƍ앗���Ⴄ�̂ł����A�A�����E���\�[�̔M�ѕ��̔ɖ���W�����O����`������ʂ�f�i�Ƃ����܂��B
 �u�����̍��v�͂P�X�T�T�N�̍�i�ł��B���J�̍��̉Ԃ̂ЂƂЂƂ܂Ő��k�ɕ`�����܂�Ă���̂ł����A�S�̂̕��i�͊G�t���I�Ƃ����Ă��悭�A���������Β��ł��B���ꂪ�A�ׂ������̉Ԃ̕`�����݂ƁA�R�l�̎q�����������J�̍����C�ɗ��߂�l�q���Ȃ��V�тɋ����Ă���l�q�́A���̖̑傫���Ǝq���̏������Ƃ̑ΏƂ����܂��āA�G�t���I�Ȓ������Ԃ��Ă��܂��B
�u�����̍��v�͂P�X�T�T�N�̍�i�ł��B���J�̍��̉Ԃ̂ЂƂЂƂ܂Ő��k�ɕ`�����܂�Ă���̂ł����A�S�̂̕��i�͊G�t���I�Ƃ����Ă��悭�A���������Β��ł��B���ꂪ�A�ׂ������̉Ԃ̕`�����݂ƁA�R�l�̎q�����������J�̍����C�ɗ��߂�l�q���Ȃ��V�тɋ����Ă���l�q�́A���̖̑傫���Ǝq���̏������Ƃ̑ΏƂ����܂��āA�G�t���I�Ȓ������Ԃ��Ă��܂��B
�u�䉑�̏t�v�i�E���j�͂P�X�S�W�N���̍�i�ŁA���S�ɕ`����Ă���̂͐V�h�䉑�̃��~�W�o�X�Y�J�P�m�L�̑���������ł��B���͂������ċ���ŁA�}���L������o���A���̎}�����Ȃ���l�q�͈��o��悤�Ȑ�����������܂��B�u�������̒r�v�Ɠ����悤�Ƀt���[�h���b�q���u�����̓����鑺�̕��i�i�ǓƂȎ��j�v�i�����j���v���o�����Ƃ��ł��܂��B�����ɑ���P�{���������ɛ�������\�}�ƁA�}�����˂��˂ƂЂ낪��悤�ɐL�тĂ���l�q���悭���Ă���悤�Ɏv���܂��B�t���[�h���q�́u�����̓����鑺�̕��i�i�ǓƂȎ��j�v�ł́A�����̒����Ƀ|�c���Ɨ���{�̘V�����I�[�N�̖��`����Ă��āA�w�i�ɂ͎R���L����A��ɂ͓܂�L�����Ă��܂��B�����̘V�͕��J�ɑς��Ȃ��璷�N�����Ă������݂ł���A���Ԃ̗���Ɛ����̙R�����Ɏ����Ă��܂��B����ɑ��āA���͂̕��i�͈ڂ낢�䂭���̂ŁA�V�͂���ɑ��ĐÂ��ɗ���������B�����ŁA�V�͌ǓƁA���ȁA���_�I�T�����ے����A�l�����R��_��
 ���������V���{���ƌ����܂��B����ɑ��č����́u�䉑�̏t�v�̃��~�W�o�X�Y�J�P�m�L�̑���́A�w�i�Ɏ�̗т��T����悤�ɖ��Ă��܂��B�����́u�䉑�̏t�v�̃��~�W�o�X�Y�J�P�m�L�̑���́A�t���[�h���q�̃I�[�N�̘V�Ɠ����悤�ɕ��J�ɑς��Ȃ��璷�N�����Ă������݂ł����A�w�i�̎�͈ڂ낢�䂭���̂Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���ꂩ�畗��ɑς��đ���ƂȂ��Ă����\���̑��݂ł��B�����ŋ��������̂͑���̌Ǎ����ł͂Ȃ��A���N�̕���ɑς��Ȃ�����}��ɖ����鐶���͂ł���A���R�̑傫���A�����āA����w�i�ɍT���鎩�R�̑傫���ł���A��ƑΔ䂳��鎞�Ԃ����߂��Ă���Ƃ������̂ł��B�����́A����ɑ���̍����̉��ɂ͂R�l�̐l�̎p���������`����Ă��āA���R�̑傫���Ɛl�̏��������Δ�I�ɕ`����Ă��܂��B�t���[�h���q�ɂ͂Ȃ������l�̎p������킯�ł��B����䂦�Ƃ����킯�ł͂���܂��A�����ɂ́A�t���[�h���q�̂悤�Ȓ��z�I�Ȍ����Ȃ����̂���ʂɒ��ɕ`���u���͂Ȃ������̂��낤�Ǝv���܂��B
���������V���{���ƌ����܂��B����ɑ��č����́u�䉑�̏t�v�̃��~�W�o�X�Y�J�P�m�L�̑���́A�w�i�Ɏ�̗т��T����悤�ɖ��Ă��܂��B�����́u�䉑�̏t�v�̃��~�W�o�X�Y�J�P�m�L�̑���́A�t���[�h���q�̃I�[�N�̘V�Ɠ����悤�ɕ��J�ɑς��Ȃ��璷�N�����Ă������݂ł����A�w�i�̎�͈ڂ낢�䂭���̂Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���ꂩ�畗��ɑς��đ���ƂȂ��Ă����\���̑��݂ł��B�����ŋ��������̂͑���̌Ǎ����ł͂Ȃ��A���N�̕���ɑς��Ȃ�����}��ɖ����鐶���͂ł���A���R�̑傫���A�����āA����w�i�ɍT���鎩�R�̑傫���ł���A��ƑΔ䂳��鎞�Ԃ����߂��Ă���Ƃ������̂ł��B�����́A����ɑ���̍����̉��ɂ͂R�l�̐l�̎p���������`����Ă��āA���R�̑傫���Ɛl�̏��������Δ�I�ɕ`����Ă��܂��B�t���[�h���q�ɂ͂Ȃ������l�̎p������킯�ł��B����䂦�Ƃ����킯�ł͂���܂��A�����ɂ́A�t���[�h���q�̂悤�Ȓ��z�I�Ȍ����Ȃ����̂���ʂɒ��ɕ`���u���͂Ȃ������̂��낤�Ǝv���܂��B

 �u�e�B�[�|�b�g�̂���Õ��v�i�E���j�͂P�X�S�W�N���̍�i�ŁA�����̐Õ���͐H���ʕ��̔z�u��T�d�ɍl���Ĕz�u�ɂ���ʂ��\������Ă��܂��B�����ɂ́A�ʎ��Ƃ����Ă��A���R�̂���̂܂܁A�J�I�X���R�X���X�Ƃ��đ����悤�Ƃ��鍂���̎u�������{�ɂ���Ǝv���܂��B���̍�i�ł��A�ꌩ�o���o���Ɍ����āA�����S�͂u���ɕ��ׂ��A�u�̗v�ƂȂ钆���̃����S�ƃO���X����ʂ̒��S����ɔz�u���Ĉ��肳���Ă��܂��B�����āA�i�q���̃N���[�X�ƖL���Ȗ͗l�̃h���[�v�����E�ɁA�֖������ԕr�Ɣ�������̃|�b�g�̐^�ɓ����ȃK���X�Ƃ����A�V�����g���[�I�ɑΔ������\���ɂȂ��Ă��܂��B���肵�����������o���Ă���Ǝv���܂��B�����āA�P�X�U�U�N���u���Ԃ��ƃ����S�v�i�����j�́A�u�e�B�[�|�b�g�̂���Õ��v����ʂ̎�O����̋������ł��̂̎�������݊���`�����Ƃ��Ă���̂ɑ��āA���̍�i�ł͉��₩�Ȍ��̉��o���{����Ă��܂��B����K���X�z���ɂ��炩�ȋt�����������݁A�����₩�Ȃ��Ԃ��̉Ԃ��������Ă����̑��ʂɂ̓����S�����˂��ĉf�荞�݁A���̔w�i�ɂ͉��O�̉Ԗ������Č����Ă��܂��B�W�����F�����p���ꂽ��ʂ́A�S�̓I�ɏ_�炩�����₩�ȕ��͋C�ƂȂ��Ă��܂����A������ƃ����S�̐Ԃ���ʂ��������߂Ă��܂��B
�u�e�B�[�|�b�g�̂���Õ��v�i�E���j�͂P�X�S�W�N���̍�i�ŁA�����̐Õ���͐H���ʕ��̔z�u��T�d�ɍl���Ĕz�u�ɂ���ʂ��\������Ă��܂��B�����ɂ́A�ʎ��Ƃ����Ă��A���R�̂���̂܂܁A�J�I�X���R�X���X�Ƃ��đ����悤�Ƃ��鍂���̎u�������{�ɂ���Ǝv���܂��B���̍�i�ł��A�ꌩ�o���o���Ɍ����āA�����S�͂u���ɕ��ׂ��A�u�̗v�ƂȂ钆���̃����S�ƃO���X����ʂ̒��S����ɔz�u���Ĉ��肳���Ă��܂��B�����āA�i�q���̃N���[�X�ƖL���Ȗ͗l�̃h���[�v�����E�ɁA�֖������ԕr�Ɣ�������̃|�b�g�̐^�ɓ����ȃK���X�Ƃ����A�V�����g���[�I�ɑΔ������\���ɂȂ��Ă��܂��B���肵�����������o���Ă���Ǝv���܂��B�����āA�P�X�U�U�N���u���Ԃ��ƃ����S�v�i�����j�́A�u�e�B�[�|�b�g�̂���Õ��v����ʂ̎�O����̋������ł��̂̎�������݊���`�����Ƃ��Ă���̂ɑ��āA���̍�i�ł͉��₩�Ȍ��̉��o���{����Ă��܂��B����K���X�z���ɂ��炩�ȋt�����������݁A�����₩�Ȃ��Ԃ��̉Ԃ��������Ă����̑��ʂɂ̓����S�����˂��ĉf�荞�݁A���̔w�i�ɂ͉��O�̉Ԗ������Č����Ă��܂��B�W�����F�����p���ꂽ��ʂ́A�S�̓I�ɏ_�炩�����₩�ȕ��͋C�ƂȂ��Ă��܂����A������ƃ����S�̐Ԃ���ʂ��������߂Ă��܂��B
���ƘX�C�@���ƈ�
 �u���v�͂P�X�U�Q�N�̍�i�ł��B����̕��i��`������i�͏��Ȃ����A���݂̂�`������i�Ƃ����̂͗ޗႪ�Ȃ��Ɛ�������Ă��܂����B�W����`���V�̎��ɂ������g���ł͂Ȃ��A�ł�`�����������B�ł�`�����߂ɁA����`�����̂ł��B�h�Ƃ��������̌��t�́A���̍�i���w�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ł̒��̖������`����Ă��܂����A�`�����������̂͂��̑ɂ̈ł������Ƃ����B�ŋ߂́A�ԉΑ��͓��₩�ɉԉ�A��������̂ɂȂ�܂����A���Ƃ��ƁA�ԉ�~�̎����ɍs���̂́A��̈ł����߂��ԉ��ԊJ�����āA����ɖڂ�ῂ��ƂŁA�ԉ���������̈ł����[���������邩��ŁB���̈ł�������苭�������邱�ƂŎ��҂𓉂ނ��̂ł��B�܂�A�ł���芴���邽�߂Ɍ����K�v���Ƃ������Ƃ́A�̂���m���Ă������ƂŁA�����͖~�̉ԉ̑���ɖ�����`�����B
�u���v�͂P�X�U�Q�N�̍�i�ł��B����̕��i��`������i�͏��Ȃ����A���݂̂�`������i�Ƃ����̂͗ޗႪ�Ȃ��Ɛ�������Ă��܂����B�W����`���V�̎��ɂ������g���ł͂Ȃ��A�ł�`�����������B�ł�`�����߂ɁA����`�����̂ł��B�h�Ƃ��������̌��t�́A���̍�i���w�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ł̒��̖������`����Ă��܂����A�`�����������̂͂��̑ɂ̈ł������Ƃ����B�ŋ߂́A�ԉΑ��͓��₩�ɉԉ�A��������̂ɂȂ�܂����A���Ƃ��ƁA�ԉ�~�̎����ɍs���̂́A��̈ł����߂��ԉ��ԊJ�����āA����ɖڂ�ῂ��ƂŁA�ԉ���������̈ł����[���������邩��ŁB���̈ł�������苭�������邱�ƂŎ��҂𓉂ނ��̂ł��B�܂�A�ł���芴���邽�߂Ɍ����K�v���Ƃ������Ƃ́A�̂���m���Ă������ƂŁA�����͖~�̉ԉ̑���ɖ�����`�����B

 �u���z�v�i�����j�͂P�X�U�P�N�̍�i�ł��B�u���v���ł�`�����Ƃ����̂ɑ��āA���̍�i�͌����̂��̂�`�����Ƃ����Ǝv���܂��B���z�́A���̉��\�킷���̂悤�ɊG����d�˂Đ���グ�`����A����������ˏ�ɐF�̓_�`��u�����Ƃɂ���āA���̂Ђ낪���\�����Ă��܂��B�������O�i�̎��͉e�ƂȂ��āA�����h���Ă��܂��B���̃R���g���X�g���A�������̑��z�̌��̂܂Ԃ������������Ă��܂��B�����u���z�v�i�E���j�Ƃ����^�C�g���ō����Ɠ����悤�ɊG���グ�ĉ�Ƃ��邱�Ƃŗz���̂܂Ԃ����A���̋�����\��������Ƃ��v���o���܂����B����́A�����N�ł��B���́u���сv�̃����N�ł��B�����N�͍����̂悤�Ɏʎ��̉�Ƃł͂Ȃ������̂ŁA������肳��Ɍ��̉���������܂����B�������A�����N���`�����Ƃ������z�́A�����̓V�̂ł͂Ȃ��A�����ƃG�l���M�[�̌���ł���A��ʂߐs�������z�̕��ː��́A����Ȑ����͂̏ے��Ƃ��āA���R�E�̈ꕔ�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̑��݂��������Ă���B�����ŁA�g�p����Ă���F�ʂɂ́A�g�F�Ɗ��F�����݂��Ă���A���z�̋���ȔM��\������ƂƂ��ɁA�F���Ƃ̐_��I�ȂȂ�����Î����Ă���ƌ����܂��B���z������o�����������l�������ɐL�сA����ɂ���Č`������镗�i�́A���z�̃G�l���M�[�ɂ���č\�z����Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�^���܂��B�܂��A�R���݁A���ʁA��̐F�ʂ����z�̎��͂ŕω����Ă���l�q�́A���z�����R�E�ɗ^����e�������o�I�ɕ\�����Ă��܂��B�܂�A�����N�̕`�������z�͑n���A��]�A�����̏ے��Ȃ̂ł��B�t���[�h���q�̔�r�̂Ƃ���ł��q�ׂ܂������A�����ɂ͒��z�I�Ȃ��̂��V���{���C�Y����Ƃ����u���͌���ꂸ�A�����N�ƈ���āA����`�����B���̌�A�����͌����Ȃ����̂�`�����Ƃ����Ƃ������Ƃ�������̂ł����A�����ɂƂ��Č����Ȃ����̂Ƃ́A���z�I�ȃV���{���ł͂Ȃ��āA�łƂ����Ƃ��������̂��낤�Ǝv���܂��B
�u���z�v�i�����j�͂P�X�U�P�N�̍�i�ł��B�u���v���ł�`�����Ƃ����̂ɑ��āA���̍�i�͌����̂��̂�`�����Ƃ����Ǝv���܂��B���z�́A���̉��\�킷���̂悤�ɊG����d�˂Đ���グ�`����A����������ˏ�ɐF�̓_�`��u�����Ƃɂ���āA���̂Ђ낪���\�����Ă��܂��B�������O�i�̎��͉e�ƂȂ��āA�����h���Ă��܂��B���̃R���g���X�g���A�������̑��z�̌��̂܂Ԃ������������Ă��܂��B�����u���z�v�i�E���j�Ƃ����^�C�g���ō����Ɠ����悤�ɊG���グ�ĉ�Ƃ��邱�Ƃŗz���̂܂Ԃ����A���̋�����\��������Ƃ��v���o���܂����B����́A�����N�ł��B���́u���сv�̃����N�ł��B�����N�͍����̂悤�Ɏʎ��̉�Ƃł͂Ȃ������̂ŁA������肳��Ɍ��̉���������܂����B�������A�����N���`�����Ƃ������z�́A�����̓V�̂ł͂Ȃ��A�����ƃG�l���M�[�̌���ł���A��ʂߐs�������z�̕��ː��́A����Ȑ����͂̏ے��Ƃ��āA���R�E�̈ꕔ�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̑��݂��������Ă���B�����ŁA�g�p����Ă���F�ʂɂ́A�g�F�Ɗ��F�����݂��Ă���A���z�̋���ȔM��\������ƂƂ��ɁA�F���Ƃ̐_��I�ȂȂ�����Î����Ă���ƌ����܂��B���z������o�����������l�������ɐL�сA����ɂ���Č`������镗�i�́A���z�̃G�l���M�[�ɂ���č\�z����Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�^���܂��B�܂��A�R���݁A���ʁA��̐F�ʂ����z�̎��͂ŕω����Ă���l�q�́A���z�����R�E�ɗ^����e�������o�I�ɕ\�����Ă��܂��B�܂�A�����N�̕`�������z�͑n���A��]�A�����̏ے��Ȃ̂ł��B�t���[�h���q�̔�r�̂Ƃ���ł��q�ׂ܂������A�����ɂ͒��z�I�Ȃ��̂��V���{���C�Y����Ƃ����u���͌���ꂸ�A�����N�ƈ���āA����`�����B���̌�A�����͌����Ȃ����̂�`�����Ƃ����Ƃ������Ƃ�������̂ł����A�����ɂƂ��Č����Ȃ����̂Ƃ́A���z�I�ȃV���{���ł͂Ȃ��āA�łƂ����Ƃ��������̂��낤�Ǝv���܂��B
��P�́@����ƂƂ���
�������敗���m�������Ă��������̍�i�ł��B
�S�b�z�ւ̓���

 ���@���E�S�b�z�͖�����������{�ɏЉ��A���\�l�C���������炵���B�����̂��A�S�b�z�͓��{�ŎĂ����悤�ł��B�n���o�g�҂ŁA�������Ɗw�ŊG������Ă��������������鐼�m�̉�Ƃ̏��Ȃnj����Ă������낤����A�h�����Ēm�邱�Ƃ��ł����̂��S�b�z�������Ƃ������Ƃł��傤���B���̓S�b�z�̊G�����Ă��A�P�ɉ��肭���Ƃ����v���Ȃ��̂ŁA�����́A�S�b�z�̑��ɑI�������Ȃ������̂ɂ́A������ւ����܂���B
���@���E�S�b�z�͖�����������{�ɏЉ��A���\�l�C���������炵���B�����̂��A�S�b�z�͓��{�ŎĂ����悤�ł��B�n���o�g�҂ŁA�������Ɗw�ŊG������Ă��������������鐼�m�̉�Ƃ̏��Ȃnj����Ă������낤����A�h�����Ēm�邱�Ƃ��ł����̂��S�b�z�������Ƃ������Ƃł��傤���B���̓S�b�z�̊G�����Ă��A�P�ɉ��肭���Ƃ����v���Ȃ��̂ŁA�����́A�S�b�z�̑��ɑI�������Ȃ������̂ɂ́A������ւ����܂���B
�u���̉ԁv�i�E���j�͂P�X�R�O�N���́A�S�b�z�̍�i�̉e����������i�ł��B�����ł́A�ׂ����֊s���͂����肳����\���͉e����߁A�f�����M�v�ő�G�c�ɕ`����Ă��܂��B�Ⴆ�A�S�b�z���u���̂��锞���v�i�����j�̐^�̋Ȃ��肭�˂�悤�ȓ��┨�̕`�����ȂǁA�悭���Ă��܂��B���邢�́A�g���ȏt�z�ŗ���������z���̂悤�ɋ�ɂ��˂�悤�ȕM�v���{����Ă���̂��S�b�z�ɒʂ���Ƃ��낪����܂��B���̂��˂�悤�Ȑ��́A����܂ł��u�����v��u�䉑�̏t�v�Ȃǂɂ����˂��˂Ƃ��˂�����ڗ����܂����A�����̍�i�ɂ͓����I�Ȃ��̂ł��B����́A�S�b�z�̉e���ɂ����̂ƌ��������ł��B
�ʎ��ւ̊o��

 �u�ւƃ����S�v�i�E���j�͂P�X�P�W�N�̐���A�����Q�W�̎��̍�i�ł��B��ƂƂ��ẴX�^�[�g���x�����������̏K����Ƃ������鎞���ɕ`���ꂽ���̍�i�́A�ݓc�������u�ь�O�v�i�����j�Ƃقڂ悭���Ă��܂��B�قړ������̗���i�B�ь�O�Ԋu�Ɉ꒼���ɕ��ׂ�Ƃ����Ӑ}�I�Ȕz�u�́A�������ݓc�ɕ�����ƍl���Ă悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ������܂��B���ꂾ���łȂ��A�ו��܂Ŏ��X�ɕ`�����ގʎ��I�ȕ`�����͋��ʂ��Ă��āA�����͊ݓc����{�ɂ��Ă����̂�������܂��B���������A�ݓc�����́A�A���u���q�g�E�f���[���[��ʂ��ČÓT�I�Ȏʎ��ɖڊo�߂��Ƃ̂��Ƃł����A�������f���[���[�̉e���������摜��`���Ă����̂́A�ݓc��ʂ��Ă̂��Ƃ�������܂���B
�u�ւƃ����S�v�i�E���j�͂P�X�P�W�N�̐���A�����Q�W�̎��̍�i�ł��B��ƂƂ��ẴX�^�[�g���x�����������̏K����Ƃ������鎞���ɕ`���ꂽ���̍�i�́A�ݓc�������u�ь�O�v�i�����j�Ƃقڂ悭���Ă��܂��B�قړ������̗���i�B�ь�O�Ԋu�Ɉ꒼���ɕ��ׂ�Ƃ����Ӑ}�I�Ȕz�u�́A�������ݓc�ɕ�����ƍl���Ă悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ������܂��B���ꂾ���łȂ��A�ו��܂Ŏ��X�ɕ`�����ގʎ��I�ȕ`�����͋��ʂ��Ă��āA�����͊ݓc����{�ɂ��Ă����̂�������܂��B���������A�ݓc�����́A�A���u���q�g�E�f���[���[��ʂ��ČÓT�I�Ȏʎ��ɖڊo�߂��Ƃ̂��Ƃł����A�������f���[���[�̉e���������摜��`���Ă����̂́A�ݓc��ʂ��Ă̂��Ƃ�������܂���B
 �u���ƒ��q�v�Ƃ����P�X�Q�Q�N�̍�i�ł��B�킪�R�����т́A�ꌩ���̕ϓN���Ȃ��Õ���ł��B�������A����ł���R�̔��ƒ��q���c��ł���悤�Ɍ����܂��B�R�Ƃ�����Ɉ���������悤�ɘc��ł��܂��B��Ƃ̎������߂���Ƃ����A��O�̃e�[�u���̉��͐����ł��B����ƁA�R�̊�̘c�݂̒��x���Ⴄ�悤�Ȃ̂ł��B��ʌ������ĉE�̒��q����ԍ���Ɉ��������Ă���悤�Ɍ����܂��B�����āA�R�̊�̘c�݂̒��x�Ɋ�̖͗l���֘A���Ă���̂ł͂Ȃ����B��Ԙc��ł��钃�q�͓����͗l�ł��˂��˂̖������тĂ��܂��B�^�̔��͐��̖͗l�����˂��Ă���B����ɑ��Ĉ�ԍ��̔��͗ΐF�ɍʐF����Ė͗l���n�b�L�����Ȃ��B���̉E���̔����c�݂����Ȃ��B����ɉ����āA�w�i�ƂȂ��Ă���ǂ�����̂����ł��傤���A�܂�ŁA���ꂼ��̊킩�牌���N���o�Ă���悤�Ȍ`�ԂɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�R�̊�͓���Ȃ̂ł��傤���A����̗₽���d�����G��̂悤�ȕ`������ł͂Ȃ��A�c�݂����邽�߂��A�_�炩�Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��B�����̂��Ƃ���A���̂R�̊킪�Õ��̌Œ肵�����̂ł͂Ȃ��A�������̂悤�ȏ_�炩���Ɠ����̉\������݂��Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B����́A�����܂܂�`���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����Ȃ����̂�`�����Ƃ���ݓc�����̉e�����A���������g�̎ʎ��Ƃ��Ă��������Ƃ��\��ꂽ��i�ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�u���ƒ��q�v�Ƃ����P�X�Q�Q�N�̍�i�ł��B�킪�R�����т́A�ꌩ���̕ϓN���Ȃ��Õ���ł��B�������A����ł���R�̔��ƒ��q���c��ł���悤�Ɍ����܂��B�R�Ƃ�����Ɉ���������悤�ɘc��ł��܂��B��Ƃ̎������߂���Ƃ����A��O�̃e�[�u���̉��͐����ł��B����ƁA�R�̊�̘c�݂̒��x���Ⴄ�悤�Ȃ̂ł��B��ʌ������ĉE�̒��q����ԍ���Ɉ��������Ă���悤�Ɍ����܂��B�����āA�R�̊�̘c�݂̒��x�Ɋ�̖͗l���֘A���Ă���̂ł͂Ȃ����B��Ԙc��ł��钃�q�͓����͗l�ł��˂��˂̖������тĂ��܂��B�^�̔��͐��̖͗l�����˂��Ă���B����ɑ��Ĉ�ԍ��̔��͗ΐF�ɍʐF����Ė͗l���n�b�L�����Ȃ��B���̉E���̔����c�݂����Ȃ��B����ɉ����āA�w�i�ƂȂ��Ă���ǂ�����̂����ł��傤���A�܂�ŁA���ꂼ��̊킩�牌���N���o�Ă���悤�Ȍ`�ԂɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�R�̊�͓���Ȃ̂ł��傤���A����̗₽���d�����G��̂悤�ȕ`������ł͂Ȃ��A�c�݂����邽�߂��A�_�炩�Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��B�����̂��Ƃ���A���̂R�̊킪�Õ��̌Œ肵�����̂ł͂Ȃ��A�������̂悤�ȏ_�炩���Ɠ����̉\������݂��Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B����́A�����܂܂�`���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����Ȃ����̂�`�����Ƃ���ݓc�����̉e�����A���������g�̎ʎ��Ƃ��Ă��������Ƃ��\��ꂽ��i�ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�ʎ��̍L����
 �u�����ɂ������摜�v�́A�P�X�Q�R�N�̍�i�ł��B�����Ɏ���ƁA��ϓI�ȈӐ}�ɉ������߂ɁA�ʎ��I�ȋZ�@�ɂƂǂ܂肫��Ȃ��Ƃ���Ɏ������悤�Ɍ����܂��B���łɌ����A�R�N�O�́u���q���������鎩�摜�v�Ɠ����悤�ɉ�Ƃ͑m�`�ɕ����Ă��܂��B��������ڂ��䂭�̂͑m�߂̕`�����ŁA�S�̂Ƃ��Ă��˂��˂Ɣg�ł悤�ɋ��Ȃ������œ��ꂳ�ꂽ�悤�ɕ`����Ă���Ƃ���ł��B�������āA����ɂ悭����A��̗֊s���g�ł��Ă���悤�Ɍ����܂��B���������̎w���߂��ςɋȂ���A������g�ł��Ă���悤�Ɍ����Ȃ�������܂���B���̂��˂��˂����Ȑ��Ŏx�z���ꂽ�悤�ȉ�ʂ́A���炩�ɈӐ}�I�ɕ`���ꂽ���̂ł��傤�B���̈Ӑ}�́A����ɓ`�L�I�ȃG�s�\�[�h����ł���A������ł��A���̂���������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B���邢�́A�ݓc����������۔h�̃t�@���E�S�b�z�̉e���ƌ������Ƃ��ł��邩������܂���B�ݓc�����͎ʎ���Nj������|�p�Ƃł����A�ʎ���ʂ��đΏە������u���݂̐_�鐫�v�������o�����Ƃ�_���ĕ`�����Ƃ���Ă��܂��B�Ώە������A���ɍČ����邾���ł͂Ȃ����g�̓��ʂ���ĂыN�����ꂽ�u���Ȃ���v�����̍�i�ɓ��e���Ă���B���̕\���Ƃ��āA��قnj��܂����u�ь�O�v�̕s���R�Ȕz�u�ł���A�f�t�H�������ꂽ�`�ʂł��B����������͊ݓc���������炳�܂ɁA�ӎ��I�ɍs���Ă���悤�Ɍ����܂��B����́A�ݓc�����݂̐_�鐫��\�킷��i�Ƃ��Ă����̂��A�ړI�Ɋ�点���悤�Ɏv���܂��B���������f�t�H�����A���邢�́A�c�݂��������Ƃ��琶�����a�������ʂƂ��čl���Ă����Ǝv����ӂ�������B����́A�ʎ��Ƃ����Ă��ʐ^�̂悤�Șg�g�݂ł͂Ȃ��A�G��Ƃ��Đ�������Ƃ����g�g�݂�O��Ƃ��Ă���Ǝv����̂ł��B
�u�����ɂ������摜�v�́A�P�X�Q�R�N�̍�i�ł��B�����Ɏ���ƁA��ϓI�ȈӐ}�ɉ������߂ɁA�ʎ��I�ȋZ�@�ɂƂǂ܂肫��Ȃ��Ƃ���Ɏ������悤�Ɍ����܂��B���łɌ����A�R�N�O�́u���q���������鎩�摜�v�Ɠ����悤�ɉ�Ƃ͑m�`�ɕ����Ă��܂��B��������ڂ��䂭�̂͑m�߂̕`�����ŁA�S�̂Ƃ��Ă��˂��˂Ɣg�ł悤�ɋ��Ȃ������œ��ꂳ�ꂽ�悤�ɕ`����Ă���Ƃ���ł��B�������āA����ɂ悭����A��̗֊s���g�ł��Ă���悤�Ɍ����܂��B���������̎w���߂��ςɋȂ���A������g�ł��Ă���悤�Ɍ����Ȃ�������܂���B���̂��˂��˂����Ȑ��Ŏx�z���ꂽ�悤�ȉ�ʂ́A���炩�ɈӐ}�I�ɕ`���ꂽ���̂ł��傤�B���̈Ӑ}�́A����ɓ`�L�I�ȃG�s�\�[�h����ł���A������ł��A���̂���������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B���邢�́A�ݓc����������۔h�̃t�@���E�S�b�z�̉e���ƌ������Ƃ��ł��邩������܂���B�ݓc�����͎ʎ���Nj������|�p�Ƃł����A�ʎ���ʂ��đΏە������u���݂̐_�鐫�v�������o�����Ƃ�_���ĕ`�����Ƃ���Ă��܂��B�Ώە������A���ɍČ����邾���ł͂Ȃ����g�̓��ʂ���ĂыN�����ꂽ�u���Ȃ���v�����̍�i�ɓ��e���Ă���B���̕\���Ƃ��āA��قnj��܂����u�ь�O�v�̕s���R�Ȕz�u�ł���A�f�t�H�������ꂽ�`�ʂł��B����������͊ݓc���������炳�܂ɁA�ӎ��I�ɍs���Ă���悤�Ɍ����܂��B����́A�ݓc�����݂̐_�鐫��\�킷��i�Ƃ��Ă����̂��A�ړI�Ɋ�点���悤�Ɏv���܂��B���������f�t�H�����A���邢�́A�c�݂��������Ƃ��琶�����a�������ʂƂ��čl���Ă����Ǝv����ӂ�������B����́A�ʎ��Ƃ����Ă��ʐ^�̂悤�Șg�g�݂ł͂Ȃ��A�G��Ƃ��Đ�������Ƃ����g�g�݂�O��Ƃ��Ă���Ǝv����̂ł��B
��Q�́@�l�ƂƂ���
�ŏ��Ɉ��p������Î҂������̒��ŁA�g�ނ��ЂƂ�̐l�ԂƂ��Ăǂ̂悤�ɐ����A
���͂Ƃǂ̂悤�ȊW��z���A��ƂƂ��Ă̕��݂�i�߂����Ƃ��������ɂ����ڂ��A��\�Y�̐l�ԑ��ɂ����߂Ĕ���܂��B����ɂ́A���̌|�p�ς̔w�i�ɂ�����p�E�⎞��̓�����T�邱�ƂŁA���p�j�̂Ȃ��ɖ�\�Y�̉�Ƃ��ʒu�t���邱�Ƃ��߂����܂��B�h�Ƃ��āA�ȑO�́g�Ǎ��̉�Ɓh�Ƃ��������̃C���[�W�����߂�Ƃ����Ӑ}���A���̓W����ɂ���悤�ŁA�������Ɏ��グ�Ă���̂��A���̏͂̓W���ƌ����܂��B�����A���͍����̍�i���������̂ł����āA�����Ƃ����l�����̂��̂ɂ͊S������܂���B�����ɍ�i�Ƃ͕ʂ̎��������낢��ƓW������A���������낢��Ƃ���܂������A�f�ʂ�ł����B�������Ǎ��������łȂ����ō�i�̌��������ς��̂ł��傤���B�ς��Ȃ��̂�������A����͎ז��ȎG���ł�������܂���B����䂦�A���̏͂œW������Ă�����i�̂��Ƃ��������Ƃɂ��܂��B
���y�̐l����
 �u�}��쉓�]�v�Ƃ����P�X�S�X�N�̍�i�ł��B�t�������Ȃт��Ăڂ��肩����ł���R���݂��o�b�N�ɁA���i�̗I�X�Ɨ����}�����͂���ŁA���J�̍��̎}�������яオ���i�ł��B�_�`�I�ȍׂ����́A���̍�i�ł͖��J�̍��̉Ԃł��B���q�̂悤�ȍ��̉Ԃ̃s���N��������ۂƂȂ��āA�ڂɔ�э���ł��܂��B�����ł́A�A���O���͑f�l�̎ʐ^���D�Ƃ��D�ނ悤�Ȍ����݂Ȃ��̂ł����A���̈ꕔ���\������悤�Ȉ�_���؎�`�̓ˏo������܂��B�������o�g�̍����ɂƂ��Č̋��̕��i�ł���킯�ł����A�����ɂ́A�̋��ւ̈���̂悤�Ȏv������͂Ȃ��A���l�̂悤�ȑ�O�҂���ÂƂ������A�₽������������܂��B����͊G�t���I�ȂƂ��낪�����ŁA�����̌l�I�Ȏ��������荞�ނƂ������Ƃ͌����܂���B
�u�}��쉓�]�v�Ƃ����P�X�S�X�N�̍�i�ł��B�t�������Ȃт��Ăڂ��肩����ł���R���݂��o�b�N�ɁA���i�̗I�X�Ɨ����}�����͂���ŁA���J�̍��̎}�������яオ���i�ł��B�_�`�I�ȍׂ����́A���̍�i�ł͖��J�̍��̉Ԃł��B���q�̂悤�ȍ��̉Ԃ̃s���N��������ۂƂȂ��āA�ڂɔ�э���ł��܂��B�����ł́A�A���O���͑f�l�̎ʐ^���D�Ƃ��D�ނ悤�Ȍ����݂Ȃ��̂ł����A���̈ꕔ���\������悤�Ȉ�_���؎�`�̓ˏo������܂��B�������o�g�̍����ɂƂ��Č̋��̕��i�ł���킯�ł����A�����ɂ́A�̋��ւ̈���̂悤�Ȏv������͂Ȃ��A���l�̂悤�ȑ�O�҂���ÂƂ������A�₽������������܂��B����͊G�t���I�ȂƂ��낪�����ŁA�����̌l�I�Ȏ��������荞�ނƂ������Ƃ͌����܂���B
��������Ȃ���
 �u���������摜�v�͏��������������͌��𗬂��A���Ԃɐ[��ᰂ��A�ڂ͋���ŁA���͕��S�����悤�ɊJ�����āA���C�ł͂Ȃ��悤�ȕ\��ł��B���摜�Ƃ������Ƃł�����A��Ƃ����ۂɂ���Ȋ�����Ȃ��玩����`���Ă���킯�͂Ȃ��̂ŁA�����ɍ�ׂ�����͖̂��炩�ł��B���̂悤�ɁA����Ӗ��ɒ[�Ƃ͌����܂������������Ă���i�܂������W����܂��A���̍�i�̃|�[�Y�ƕ\��͔\������Ƃ����܂Ƃ��悭�g���q�[���[�̃|�[�Y�ɂ�������ł��j�̂ł��B�����ɂ́A���炩�̎v���Ƃ��咣�Ƃ������Ƃ��A�{�l�͖��m�Ɉӎ����Ă���̂łȂ��ł��傤���A�����ɍ��߂Ă��܂���ƂƂ��Ă̎p�����A�����ɂ͂���Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŁA�敗�͑S���قȂ�̂ł����q��M�v�Ƃ�����Ƃ̎��摜�Ǝ��Ă���Ǝv���̂ł��B�q��͎ʐ��Ƃ����Ȃ����Ǝ��g�̌��z�I�ȑz������������悤�Ȑ��E���X�[�p�[���A���Y���̎�@�Ŏ��X�ɕ`����������Ƃł��B�q��͐��U�ɂ킽�萔�����̎��摜��`���Ă��܂����A�܂�ŃR�X�v���̂悤�ɗl�X�ȕ��������������g�̎p��`���Ă��܂��B�����ł̍����͕����������Ă��܂��A���g����l���ɂ������̂�����̎�l���ɂ悤�ɕ`���Ă��܂��B�Ǎ��̉�ƂƂ������`�L�I�Ȃ��̂����肪�D���Ȑl�ł���A�鍑��w�݊w���ɕ`���ꂽ�Ƃ������̍�i�ɂ��āA�G����w�т����Ƃ������g�̊�]�ɔ����āA���͂̊��҂���_�w���Ő��Y�ɂ��Ċw��ł���s�{�ӂ��ɜ�Y����p���������Ă���Ƒz����痂������邱�Ƃ��\�ŁA��ʂł͍����̍�i�ɂ́A�����������̂�����ɛZ�т鐫��������悤�ł��B�q��Ƃ͈���āA�����͏����ɂ����Ă͎��摜��`���Ă��܂����A����ȍ~�ɂ́A���摜��S���`���Ȃ��Ȃ�܂��B���̂��Ƃ́A�����Ƃ����l�̕`�����Ƃւ̎p�����ω��������Ƃɂ����̂Ȃ̂��A�P�ɑ��ɕ`���������̂��o�Ă������߂Ȃ̂��A������܂���B
�u���������摜�v�͏��������������͌��𗬂��A���Ԃɐ[��ᰂ��A�ڂ͋���ŁA���͕��S�����悤�ɊJ�����āA���C�ł͂Ȃ��悤�ȕ\��ł��B���摜�Ƃ������Ƃł�����A��Ƃ����ۂɂ���Ȋ�����Ȃ��玩����`���Ă���킯�͂Ȃ��̂ŁA�����ɍ�ׂ�����͖̂��炩�ł��B���̂悤�ɁA����Ӗ��ɒ[�Ƃ͌����܂������������Ă���i�܂������W����܂��A���̍�i�̃|�[�Y�ƕ\��͔\������Ƃ����܂Ƃ��悭�g���q�[���[�̃|�[�Y�ɂ�������ł��j�̂ł��B�����ɂ́A���炩�̎v���Ƃ��咣�Ƃ������Ƃ��A�{�l�͖��m�Ɉӎ����Ă���̂łȂ��ł��傤���A�����ɍ��߂Ă��܂���ƂƂ��Ă̎p�����A�����ɂ͂���Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŁA�敗�͑S���قȂ�̂ł����q��M�v�Ƃ�����Ƃ̎��摜�Ǝ��Ă���Ǝv���̂ł��B�q��͎ʐ��Ƃ����Ȃ����Ǝ��g�̌��z�I�ȑz������������悤�Ȑ��E���X�[�p�[���A���Y���̎�@�Ŏ��X�ɕ`����������Ƃł��B�q��͐��U�ɂ킽�萔�����̎��摜��`���Ă��܂����A�܂�ŃR�X�v���̂悤�ɗl�X�ȕ��������������g�̎p��`���Ă��܂��B�����ł̍����͕����������Ă��܂��A���g����l���ɂ������̂�����̎�l���ɂ悤�ɕ`���Ă��܂��B�Ǎ��̉�ƂƂ������`�L�I�Ȃ��̂����肪�D���Ȑl�ł���A�鍑��w�݊w���ɕ`���ꂽ�Ƃ������̍�i�ɂ��āA�G����w�т����Ƃ������g�̊�]�ɔ����āA���͂̊��҂���_�w���Ő��Y�ɂ��Ċw��ł���s�{�ӂ��ɜ�Y����p���������Ă���Ƒz����痂������邱�Ƃ��\�ŁA��ʂł͍����̍�i�ɂ́A�����������̂�����ɛZ�т鐫��������悤�ł��B�q��Ƃ͈���āA�����͏����ɂ����Ă͎��摜��`���Ă��܂����A����ȍ~�ɂ́A���摜��S���`���Ȃ��Ȃ�܂��B���̂��Ƃ́A�����Ƃ����l�̕`�����Ƃւ̎p�����ω��������Ƃɂ����̂Ȃ̂��A�P�ɑ��ɕ`���������̂��o�Ă������߂Ȃ̂��A������܂���B

 �u�x�j�X�̍`�v�i�E���j�͂P�X�R�O�N�̉��B���w���̍�i�ł��B���D�̔��������}�X�g�������̐��Ƃ��ě�������A��N�̍����̕��i��̍\�}�ɂ悭�\������ƌ����邩������܂���B����́A�h�C�c�E���}���h�̃J�X�p�[�E�_���B�b�h�E�t���[�h���q���u�`�̒��]�v�i�����j�̂�͂蔿�D�̃}�X�g�𐂒��̛����������Ƃ��đ������\�}�Ƃ悭���Ă��܂��B�O�Ɂu�䉑�̏t�v���t���[�h���b�q�́u�����̓����鑺�̕��i�i�ǓƂȎ��j�v�Ɏ��Ă���̂����b�����܂����B�����ŁA���̖ϑz�X�g�[���[�������}�����܂��B�l�I�ȓƒf�Ȃ̂ŁA����Ď��̍�i�Ɉڂ��Ă��������Ă����������ł��̂ŁA�����R�Ɋ肢�܂��B���āA�����ō����̍�i�Ƃ悭������i���c������l�̉�Ƃɋ��ʂ��Ă���Ƃ�����l���Ă݂����Ǝv���܂��B�����Ȃ�A�t���[�h���q�͕��i��Ƃł���A�S�b�z�̓A�����̔_�����i���D��ŕ`������Ƃł�����A��l�͕��i���悭�`�����Ƃ������Ƃɋ��ʓ_�����o�����Ƃ��ł��܂����A����ȏ�ɁA��l�́g�����Ȃ����́h��`���Ƃ����Ƃ������Ƃ�����������ƂƂ����_�ŋ��ʂ��Ă���Ǝv���܂��B�g�����Ȃ����́h�Ƃ͓�l�̉�ƂőS�������Ƃ͌������A�j���A���X�͈قȂ�܂����A��l�Ƃ��ڂŌ�����͕̂\�w�̌��ۂɉ߂����A���̔w��ɂ��鉽���̂��A����͐_���`�I�ł�������A������ƓN�w���ۂ����Ƃ��l���Ă����肵�Ă����悤�ł����B�ӂ���Ƃ��A���t�Ő�������T�O�Ƃ��v�z�Ƃ����̗ނ̂��̂��ڂŌ�������̂̔w��ɂ����āA�������i�ɕ`���������Ƃ����u�����������Ă�����ƂƂ����܂��B������A�ނ�͌����Č����܂܂�`���Ă���킯�ł͂���܂���B�ڂɌ����镗�i�́g�����Ȃ����́h��\�킷���߂̂��̂Ȃ̂ŁA�g�����Ȃ����́h��\�킷���߂ɂ͖ڂɌ����镗�i�Ɏ�������邱�Ƃ��}��Ȃ������l�����ł��B������A�ނ�̍\�}��^�b�`�Ƃ������`�����ɂ́A�Ӑ}�I�Ȃ��̂�����͂��Ȃ̂ł��B������A����������Ƃ̍\�}��`������������悤�Ƃ��������́A��l�̉�Ƃ́g�����Ȃ����́h��`�����Ƃ����p�����A���R�������Ă����Ǝv���܂��B����́A�����̍�i�����Ă������ł́A�����͎ʎ��I�ȕ`�����͂��Ă��܂����A�����Č����܂܂�`���Ă͂��܂���B�����ɁA�S�b�z��t���[�h���q�̂悤�ȁg�����Ȃ����́h��`�����Ƃւ̎u�������������͕�����܂��A�n�����āA�ނ�̍�i�Ɏ��ۂɐG�ꂽ�̂�������܂���B�����ŁA�g�����Ȃ����́h��`���Ƃ��������������Ƃ������ƁA����܂Ŏ����������܂܂�`���Ă��Ȃ����Ƃɑ��āA�������t�ł����_�Â���悤�ȉ�Ƃ����ɏo������Ƃ������Ƃ��A�l�����Ȃ����Ȃ��̂ł��B����́A�P�Ɍ��t�ɂ���Đ��������Ƃ����ԐړI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA���ڍ�i�ɂ���Đg�̊��o�Ƃ��ċ�̓I�Ɏ����ł����Ƃ����[���̌��������̂ł͂Ȃ����Ƒz������̂ł��B�������ɁA�S�b�z���t���[�h���q���A�ǂ��炩�Ƃ����A�J�f�~�[�Ƃ��|�p�^���Ƃ����悤�ȏO�ɂȂ��܂��ǓƂɋ߂���Ƃł������Ǝv���܂��B���ꂪ�����̋A����̐������ɉe����^�����Ƃ͌����܂��A�`���Ƃ����p���ɂ��ẮA���̕`�����̉e����ʂ��āA���炩�̓������̂��������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B�����A���̃R�[�i�[�̓W����i������ƁA���̉e���̂悤�Ȃ��̂��A�������Ă킩��قǂɕ\���Ă��܂���B������A�����ŏq�ׂ����Ƃ́A�܂������̌����͂���ŏo�L�ڂł���\���������̂ł��B����́A�ӂ��܂ł����̖ϑz�ł��B
�u�x�j�X�̍`�v�i�E���j�͂P�X�R�O�N�̉��B���w���̍�i�ł��B���D�̔��������}�X�g�������̐��Ƃ��ě�������A��N�̍����̕��i��̍\�}�ɂ悭�\������ƌ����邩������܂���B����́A�h�C�c�E���}���h�̃J�X�p�[�E�_���B�b�h�E�t���[�h���q���u�`�̒��]�v�i�����j�̂�͂蔿�D�̃}�X�g�𐂒��̛����������Ƃ��đ������\�}�Ƃ悭���Ă��܂��B�O�Ɂu�䉑�̏t�v���t���[�h���b�q�́u�����̓����鑺�̕��i�i�ǓƂȎ��j�v�Ɏ��Ă���̂����b�����܂����B�����ŁA���̖ϑz�X�g�[���[�������}�����܂��B�l�I�ȓƒf�Ȃ̂ŁA����Ď��̍�i�Ɉڂ��Ă��������Ă����������ł��̂ŁA�����R�Ɋ肢�܂��B���āA�����ō����̍�i�Ƃ悭������i���c������l�̉�Ƃɋ��ʂ��Ă���Ƃ�����l���Ă݂����Ǝv���܂��B�����Ȃ�A�t���[�h���q�͕��i��Ƃł���A�S�b�z�̓A�����̔_�����i���D��ŕ`������Ƃł�����A��l�͕��i���悭�`�����Ƃ������Ƃɋ��ʓ_�����o�����Ƃ��ł��܂����A����ȏ�ɁA��l�́g�����Ȃ����́h��`���Ƃ����Ƃ������Ƃ�����������ƂƂ����_�ŋ��ʂ��Ă���Ǝv���܂��B�g�����Ȃ����́h�Ƃ͓�l�̉�ƂőS�������Ƃ͌������A�j���A���X�͈قȂ�܂����A��l�Ƃ��ڂŌ�����͕̂\�w�̌��ۂɉ߂����A���̔w��ɂ��鉽���̂��A����͐_���`�I�ł�������A������ƓN�w���ۂ����Ƃ��l���Ă����肵�Ă����悤�ł����B�ӂ���Ƃ��A���t�Ő�������T�O�Ƃ��v�z�Ƃ����̗ނ̂��̂��ڂŌ�������̂̔w��ɂ����āA�������i�ɕ`���������Ƃ����u�����������Ă�����ƂƂ����܂��B������A�ނ�͌����Č����܂܂�`���Ă���킯�ł͂���܂���B�ڂɌ����镗�i�́g�����Ȃ����́h��\�킷���߂̂��̂Ȃ̂ŁA�g�����Ȃ����́h��\�킷���߂ɂ͖ڂɌ����镗�i�Ɏ�������邱�Ƃ��}��Ȃ������l�����ł��B������A�ނ�̍\�}��^�b�`�Ƃ������`�����ɂ́A�Ӑ}�I�Ȃ��̂�����͂��Ȃ̂ł��B������A����������Ƃ̍\�}��`������������悤�Ƃ��������́A��l�̉�Ƃ́g�����Ȃ����́h��`�����Ƃ����p�����A���R�������Ă����Ǝv���܂��B����́A�����̍�i�����Ă������ł́A�����͎ʎ��I�ȕ`�����͂��Ă��܂����A�����Č����܂܂�`���Ă͂��܂���B�����ɁA�S�b�z��t���[�h���q�̂悤�ȁg�����Ȃ����́h��`�����Ƃւ̎u�������������͕�����܂��A�n�����āA�ނ�̍�i�Ɏ��ۂɐG�ꂽ�̂�������܂���B�����ŁA�g�����Ȃ����́h��`���Ƃ��������������Ƃ������ƁA����܂Ŏ����������܂܂�`���Ă��Ȃ����Ƃɑ��āA�������t�ł����_�Â���悤�ȉ�Ƃ����ɏo������Ƃ������Ƃ��A�l�����Ȃ����Ȃ��̂ł��B����́A�P�Ɍ��t�ɂ���Đ��������Ƃ����ԐړI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA���ڍ�i�ɂ���Đg�̊��o�Ƃ��ċ�̓I�Ɏ����ł����Ƃ����[���̌��������̂ł͂Ȃ����Ƒz������̂ł��B�������ɁA�S�b�z���t���[�h���q���A�ǂ��炩�Ƃ����A�J�f�~�[�Ƃ��|�p�^���Ƃ����悤�ȏO�ɂȂ��܂��ǓƂɋ߂���Ƃł������Ǝv���܂��B���ꂪ�����̋A����̐������ɉe����^�����Ƃ͌����܂��A�`���Ƃ����p���ɂ��ẮA���̕`�����̉e����ʂ��āA���炩�̓������̂��������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B�����A���̃R�[�i�[�̓W����i������ƁA���̉e���̂悤�Ȃ��̂��A�������Ă킩��قǂɕ\���Ă��܂���B������A�����ŏq�ׂ����Ƃ́A�܂������̌����͂���ŏo�L�ڂł���\���������̂ł��B����́A�ӂ��܂ł����̖ϑz�ł��B
 �u�����v�͂P�X�Q�T�N�̍�i�ł��B����͂����A㠈��̉Ԃ̓ŁX�����قǂ̐Ԃ��Ԃ�����Ɠ����ɁA���˂��˂Ƌ��Ȃ����s�̈ٗl�Ȏp�i�����ɂ͂��肦�Ȃ����A����Ȃɋ��Ȃ��āA�����Ă�����͂����Ȃ��j������ׂ���i�ł���Ǝv���܂��B����́A�֒������\���ł͂���͖̂����ŁA�������P���Ȏʎ��̉�ƂłȂ����Ƃ́A���̍�i���݂Ă�������܂��B����ɂ��Ă��A�s���N���A���邢�͓ŁX�����A�����Ƃ����ƉЁX��������ʂ���������̈�ۂ́A���̂��˂��˂̋��Ȃ����Ȑ����痈�Ă���̂́A�ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B���̂��˂��˂̋��Ȃ��S�̂��x�z���Ă��܂��Ă��āA�M�U�M�U�̗t���ۂ܂�����g�ł����肵�Ă���`�ʂ�A�Ԃɂ��Ă����J�ŃX�b�L���J�Ԃ��Ă���̂ł͂Ȃ��āA�^�̉Ԃ̓V�����g���[������Ă����Ⴍ����ȗl�q�ɂ��Ă��邵�A������̂ڂ݂���J�������Ă���Ԃ͊ی`�ł͂Ȃ��Ęc�`�ɂ��Ă��܂��B�����A�����́A���̍�i���s����`���n�߂��̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B����́A�s�����ׂ��A���˂��˂Ƌ��Ȃ��Ă���̂ɁA�܂�ō|�̂悤�ɓ��������ōd���p�ŕ`����Ă��邩��ł��B�܂�A���˂��˂Ƌ��Ȃ����p�ɏ_�炩���͂Ȃ��A���̊��D�Ōł܂��Ă���悤�Ȃ̂ł��B���̋��łȌs�ɗt��Ԃ����Ƃ��畍������āA㠈��̎p�ɂȂ��Ă���B����ł́A����́A���˂��˂̋��Ȃ��̗p��������A��i�������Ȃ����Ƃ������̂�����ɂ͂Ȃ�܂����A�̐S�̂ǂ����āA����Ȃ��˂��˂������Ȃ��A��ʂ��킴�Ƃ炵���Ȃ�ɂ�������炸�����č̗p�������ɂ͓����Ă��܂���B����́A���̏���ȑz���ł����A�ЂƂ͌`��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ЂƂ́A���̂悤�Ȃ��˂��˂̎p�ɓ����̗v�f�������Ă���悤�Ɋ������邩��ł��B�����t����������܂��A�����Ƃ����l�́A�����̂���Î~�����p�A�Ⴆ�ΐ��m�G��̍\���ł悭�����鉩����̃o�����X�Ƃ��A�ɂ͋������������A���Ƃ����ă_�C�i�~�b�N�Ȗ����������ʂ�����i������܂���B���i��ł悭�`�����̂͐�̕��i�Ő��̗����l�q�ł�������A��������Ŏ}��t�����ɐ�����ėh���l�q�i�W������Ă�����i�Łu�f�R�̉��v�i�Ƃ�����i���܂��ɂ����ŁA�f�R�ɂւ���悤�ɐ����Ă�����̎}���A�܂�ŋ����ɐ����Ă���悤�ɋ��Ȃ��Ă���̂ł��B������݂�ƁA��ōl���Ă݂܂����h�C�c�E���}���h�̃t���[�h���b�q�̐��E�ɒʂ���Ƃ��낪����悤�Ɏv���܂��B�i���Ƃ��u�I�[�N�̐X�̏C���@�v�j�j�A�X�C�̊G�ł͉����h���l�q�ł��B�܂�A�����Ƃ��A�h���Ƃ������A�����ă_�C�i�~�b�N�ł͂Ȃ�����ǁA�܂����A���炩�ȓ������A�悭�̂�グ�Ă���悤�Ɏv����̂ł��B���̂悤�ȓ�������Œǂ�������ƁA���˂��˂Ƌ��Ȃ����Ȑ��ɋ߂��O�Ղ�`���̂ł��B��ʂ́A���̋��Ȃ����邱�ƂŐÎ~������Ԃ��A�������ȓ�����^�����邱�ƂɂȂ�܂��B�u�����ɂ������摜�v�ɂ����Ă��A���݂̋␞���h���l�q��`�����Ƃ��āA���˂��˂ɂȂ��Ă��܂����ƍl�����Ȃ��ł��傤���B�����āA���̍�i�ł������ł����B���́u�����v�ł��ו��̕`�ʂ̗͂̓�����Ƃ�������B�Ⴆ�ΉԂɂ��Ă͉Ԃт�̖��܂ōׂ����`�����܂�A�������Ō��Ă���悤�ȋC���ɂ������܂��B�l�����ʂɉԂ�����ꍇ�ɂ́A�����܂ł͌��Ȃ����A�Ԃ�`�������A�����܂ŕ`�����Ƃ͂��Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�����͕`���Ă��܂��B�`�����ɂ͂����Ȃ��A����������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�u�����v�͂P�X�Q�T�N�̍�i�ł��B����͂����A㠈��̉Ԃ̓ŁX�����قǂ̐Ԃ��Ԃ�����Ɠ����ɁA���˂��˂Ƌ��Ȃ����s�̈ٗl�Ȏp�i�����ɂ͂��肦�Ȃ����A����Ȃɋ��Ȃ��āA�����Ă�����͂����Ȃ��j������ׂ���i�ł���Ǝv���܂��B����́A�֒������\���ł͂���͖̂����ŁA�������P���Ȏʎ��̉�ƂłȂ����Ƃ́A���̍�i���݂Ă�������܂��B����ɂ��Ă��A�s���N���A���邢�͓ŁX�����A�����Ƃ����ƉЁX��������ʂ���������̈�ۂ́A���̂��˂��˂̋��Ȃ����Ȑ����痈�Ă���̂́A�ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B���̂��˂��˂̋��Ȃ��S�̂��x�z���Ă��܂��Ă��āA�M�U�M�U�̗t���ۂ܂�����g�ł����肵�Ă���`�ʂ�A�Ԃɂ��Ă����J�ŃX�b�L���J�Ԃ��Ă���̂ł͂Ȃ��āA�^�̉Ԃ̓V�����g���[������Ă����Ⴍ����ȗl�q�ɂ��Ă��邵�A������̂ڂ݂���J�������Ă���Ԃ͊ی`�ł͂Ȃ��Ęc�`�ɂ��Ă��܂��B�����A�����́A���̍�i���s����`���n�߂��̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B����́A�s�����ׂ��A���˂��˂Ƌ��Ȃ��Ă���̂ɁA�܂�ō|�̂悤�ɓ��������ōd���p�ŕ`����Ă��邩��ł��B�܂�A���˂��˂Ƌ��Ȃ����p�ɏ_�炩���͂Ȃ��A���̊��D�Ōł܂��Ă���悤�Ȃ̂ł��B���̋��łȌs�ɗt��Ԃ����Ƃ��畍������āA㠈��̎p�ɂȂ��Ă���B����ł́A����́A���˂��˂̋��Ȃ��̗p��������A��i�������Ȃ����Ƃ������̂�����ɂ͂Ȃ�܂����A�̐S�̂ǂ����āA����Ȃ��˂��˂������Ȃ��A��ʂ��킴�Ƃ炵���Ȃ�ɂ�������炸�����č̗p�������ɂ͓����Ă��܂���B����́A���̏���ȑz���ł����A�ЂƂ͌`��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ЂƂ́A���̂悤�Ȃ��˂��˂̎p�ɓ����̗v�f�������Ă���悤�Ɋ������邩��ł��B�����t����������܂��A�����Ƃ����l�́A�����̂���Î~�����p�A�Ⴆ�ΐ��m�G��̍\���ł悭�����鉩����̃o�����X�Ƃ��A�ɂ͋������������A���Ƃ����ă_�C�i�~�b�N�Ȗ����������ʂ�����i������܂���B���i��ł悭�`�����̂͐�̕��i�Ő��̗����l�q�ł�������A��������Ŏ}��t�����ɐ�����ėh���l�q�i�W������Ă�����i�Łu�f�R�̉��v�i�Ƃ�����i���܂��ɂ����ŁA�f�R�ɂւ���悤�ɐ����Ă�����̎}���A�܂�ŋ����ɐ����Ă���悤�ɋ��Ȃ��Ă���̂ł��B������݂�ƁA��ōl���Ă݂܂����h�C�c�E���}���h�̃t���[�h���b�q�̐��E�ɒʂ���Ƃ��낪����悤�Ɏv���܂��B�i���Ƃ��u�I�[�N�̐X�̏C���@�v�j�j�A�X�C�̊G�ł͉����h���l�q�ł��B�܂�A�����Ƃ��A�h���Ƃ������A�����ă_�C�i�~�b�N�ł͂Ȃ�����ǁA�܂����A���炩�ȓ������A�悭�̂�グ�Ă���悤�Ɏv����̂ł��B���̂悤�ȓ�������Œǂ�������ƁA���˂��˂Ƌ��Ȃ����Ȑ��ɋ߂��O�Ղ�`���̂ł��B��ʂ́A���̋��Ȃ����邱�ƂŐÎ~������Ԃ��A�������ȓ�����^�����邱�ƂɂȂ�܂��B�u�����ɂ������摜�v�ɂ����Ă��A���݂̋␞���h���l�q��`�����Ƃ��āA���˂��˂ɂȂ��Ă��܂����ƍl�����Ȃ��ł��傤���B�����āA���̍�i�ł������ł����B���́u�����v�ł��ו��̕`�ʂ̗͂̓�����Ƃ�������B�Ⴆ�ΉԂɂ��Ă͉Ԃт�̖��܂ōׂ����`�����܂�A�������Ō��Ă���悤�ȋC���ɂ������܂��B�l�����ʂɉԂ�����ꍇ�ɂ́A�����܂ł͌��Ȃ����A�Ԃ�`�������A�����܂ŕ`�����Ƃ͂��Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�����͕`���Ă��܂��B�`�����ɂ͂����Ȃ��A����������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

 �u�J���i�ƃR�X���X�v�Ƃ����P�X�T�S�N�̍�i�ł��B�u�����v����R�O�N�o�߂��A��ʂ͖��邭�Ȃ�A�`�����A���̎�ނ��Ⴂ�܂����A�s���܂������ɂȂ�A���˂��ː��͉e����߂܂��B�����薼�̑�P�͂Ō����P�X�U�V�N�́u�����v�ł͌s���܂������ɂȂ��Ă��܂��B���́u�J���i�ƃR�X���X�v�͂P�X�U�V�N�́u�����v�Ɋ������i�ŁA���̊Ԃɍ����̉敗�ɕω����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�P�X�U�V�N�́u�����v�̂Ƃ���ŁA�A�����E���\�[�ɐG�ꂽ�Ƃ���ŁA���\�[�̕`���A���͎ʎ��Ƃ͂������ăf�t�H�������ꂽ�p�ɂȂ��Ă��܂����A�A���̐����͂��ʎ��I�Ȃ��̂�����������Ĕ����Ă���Ƃ��낪����܂��B�����̕`���A���ɂ́A���̐����͂���p���A�ߏ�ƂȂ��ăO���e�X�N�����O�̕s�C���ȓŁX�����ɔ���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B���ꂪ�悭�������i�ł��B�������A�P�X�Q�T�N�́u�����v�Ƃ͈Ⴂ�܂����A���������\�[�ƈႤ�̂́A���\�[�̂悤�ȃf�t�H�������قƂ�ǎ{���Ă��Ȃ��_�ł��B���̍�i�ŕ`����Ă���R�X���X��J���i�̉Ԃ͍ז��Ɏʎ��I�ɕ`����Ă��܂��B�������A���̍ז�������`�ʂ́A���ʂɐl���A��������ۂɖڂɈڂ�p�Ƃ͂��������Ⴄ�悤�Ȃ̂ł��B�ז�������悤�Ȃ��̎p�́A���i�͌��Ȃ����A�������Ȃ��悤�ȕs�C�����A�ŁX�����̈�ۂł��B����ɉ�ʑS�̂�N�H����悤�ȁA���鑤�ɔɖ��Ă���悤�Ȕ��͂�����܂��B���̐A���̎p�Ɍ����B�ꂷ��̂́A���˂��˂Ƌ��Ȃ�����Ȃ̂ł��B����̓R�X���X�̌s�ł�������A�J���i�̉ԕقł�������A���̐���������^���Ă���̂ł��B����ɉ����čז��ȃX�[�p�[���A���ȐA������ʂɏ[�������Ă������ȉߏ�ȂƂ��낪�A���͂𑝂��Ă���Ƃ����܂��B�����炭�A�A�����E���\�[�͉�ʍ\�����v�Z���Đ��삵�Ă���̂ŁA��ʂ�A�������������Ă��܂����ӓׂƂ������͂͂���قǂł�����܂��A�����̍�i�ł͍\�����ו��̌X�̉Ԃ�t�̕`�ʂ��`���Ă��邤���ɉߏ�ɖ\�����Ă���悤�ŁA�v�Z�𗽉킵�Ă��܂��悤�ɟӓׂƂ������͂�ł��܂��B���ꂪ���s�C����������҂Ɉ�ۂÂ��Ă���Ǝv���܂��B
�u�J���i�ƃR�X���X�v�Ƃ����P�X�T�S�N�̍�i�ł��B�u�����v����R�O�N�o�߂��A��ʂ͖��邭�Ȃ�A�`�����A���̎�ނ��Ⴂ�܂����A�s���܂������ɂȂ�A���˂��ː��͉e����߂܂��B�����薼�̑�P�͂Ō����P�X�U�V�N�́u�����v�ł͌s���܂������ɂȂ��Ă��܂��B���́u�J���i�ƃR�X���X�v�͂P�X�U�V�N�́u�����v�Ɋ������i�ŁA���̊Ԃɍ����̉敗�ɕω����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�P�X�U�V�N�́u�����v�̂Ƃ���ŁA�A�����E���\�[�ɐG�ꂽ�Ƃ���ŁA���\�[�̕`���A���͎ʎ��Ƃ͂������ăf�t�H�������ꂽ�p�ɂȂ��Ă��܂����A�A���̐����͂��ʎ��I�Ȃ��̂�����������Ĕ����Ă���Ƃ��낪����܂��B�����̕`���A���ɂ́A���̐����͂���p���A�ߏ�ƂȂ��ăO���e�X�N�����O�̕s�C���ȓŁX�����ɔ���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B���ꂪ�悭�������i�ł��B�������A�P�X�Q�T�N�́u�����v�Ƃ͈Ⴂ�܂����A���������\�[�ƈႤ�̂́A���\�[�̂悤�ȃf�t�H�������قƂ�ǎ{���Ă��Ȃ��_�ł��B���̍�i�ŕ`����Ă���R�X���X��J���i�̉Ԃ͍ז��Ɏʎ��I�ɕ`����Ă��܂��B�������A���̍ז�������`�ʂ́A���ʂɐl���A��������ۂɖڂɈڂ�p�Ƃ͂��������Ⴄ�悤�Ȃ̂ł��B�ז�������悤�Ȃ��̎p�́A���i�͌��Ȃ����A�������Ȃ��悤�ȕs�C�����A�ŁX�����̈�ۂł��B����ɉ�ʑS�̂�N�H����悤�ȁA���鑤�ɔɖ��Ă���悤�Ȕ��͂�����܂��B���̐A���̎p�Ɍ����B�ꂷ��̂́A���˂��˂Ƌ��Ȃ�����Ȃ̂ł��B����̓R�X���X�̌s�ł�������A�J���i�̉ԕقł�������A���̐���������^���Ă���̂ł��B����ɉ����čז��ȃX�[�p�[���A���ȐA������ʂɏ[�������Ă������ȉߏ�ȂƂ��낪�A���͂𑝂��Ă���Ƃ����܂��B�����炭�A�A�����E���\�[�͉�ʍ\�����v�Z���Đ��삵�Ă���̂ŁA��ʂ�A�������������Ă��܂����ӓׂƂ������͂͂���قǂł�����܂��A�����̍�i�ł͍\�����ו��̌X�̉Ԃ�t�̕`�ʂ��`���Ă��邤���ɉߏ�ɖ\�����Ă���悤�ŁA�v�Z�𗽉킵�Ă��܂��悤�ɟӓׂƂ������͂�ł��܂��B���ꂪ���s�C����������҂Ɉ�ۂÂ��Ă���Ǝv���܂��B
 �����悤���u�H�̉ԁX�v�͂P�X�T�R�N�̍�i�ł��B�_��x�ƗL���C�̊����̂ڂ���Ƃ������i���o�b�N�Ƀn�Q�C�g�E��J���i�A�R�X���X�Ȃǂ̏H���ʂ�ԁX���炭�̂��Aῂ����قǑN�₩�ȐF�ʂŁA��������Ƃ����֊s�ōז��ɕ`�����܂�Ă��܂��B�ڂ���Ƃ����o�b�N�Ƃ̃R���g���X�g���▭�ł��B
�����悤���u�H�̉ԁX�v�͂P�X�T�R�N�̍�i�ł��B�_��x�ƗL���C�̊����̂ڂ���Ƃ������i���o�b�N�Ƀn�Q�C�g�E��J���i�A�R�X���X�Ȃǂ̏H���ʂ�ԁX���炭�̂��Aῂ����قǑN�₩�ȐF�ʂŁA��������Ƃ����֊s�ōז��ɕ`�����܂�Ă��܂��B�ڂ���Ƃ����o�b�N�Ƃ̃R���g���X�g���▭�ł��B

 �u�G���o�Â�X�v�i�����j�͂P�X�U�R�N�̍�i�B���t�̐X�̕��i����t�̈ꖇ�ꖇ�A�����̂ЂƂЂƂ܂œ_�`�̂悤�ɍז��ɕ`�����܂ꂽ��i�ł��B���̈������m�ȗ֊s�ōׂ����`�����܂�Ă���̂ŁA�������đS�̂����ʓI�ɉf���Ă��܂��Ă��܂��B�����āA�����̐X�Ƃ����̂́A����قǂ܂łɃX�b�L�����Ă��Ȃ��ŁA�����ƎG�R�Ƃ��Ă�����̂��낤�Ǝv���܂��B���̍�i�̉�ʂ̐X�̖X�͂��ꂢ�ɏ�ɐL�тĂ��āA�܂�Ă�����A�߂ɂȂ��Ă�����Ƃ����̂͌����܂���B�܂�A�`����Ă�����̂͐������ꂽ���i�A�܂�͊G��Ƃ��ĉf����悤�ɐ�������Ă���B�����̂悤�Ȃ��Ƃ���A���̍�i�̕��i�ɂ͎��݊��Ƃ����̂��H���ŁA�ǂ����������悤�ȁA���I�Ȋ��������܂��B���l�E�}�O���b�g���u�����ϔC��v�i�E���j�ŕ`���ꂽ�X�̃M�~�b�N�Ȋ����Ɉ�ۂ��߂����̂ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�u�G���o�Â�X�v�i�����j�͂P�X�U�R�N�̍�i�B���t�̐X�̕��i����t�̈ꖇ�ꖇ�A�����̂ЂƂЂƂ܂œ_�`�̂悤�ɍז��ɕ`�����܂ꂽ��i�ł��B���̈������m�ȗ֊s�ōׂ����`�����܂�Ă���̂ŁA�������đS�̂����ʓI�ɉf���Ă��܂��Ă��܂��B�����āA�����̐X�Ƃ����̂́A����قǂ܂łɃX�b�L�����Ă��Ȃ��ŁA�����ƎG�R�Ƃ��Ă�����̂��낤�Ǝv���܂��B���̍�i�̉�ʂ̐X�̖X�͂��ꂢ�ɏ�ɐL�тĂ��āA�܂�Ă�����A�߂ɂȂ��Ă�����Ƃ����̂͌����܂���B�܂�A�`����Ă�����̂͐������ꂽ���i�A�܂�͊G��Ƃ��ĉf����悤�ɐ�������Ă���B�����̂悤�Ȃ��Ƃ���A���̍�i�̕��i�ɂ͎��݊��Ƃ����̂��H���ŁA�ǂ����������悤�ȁA���I�Ȋ��������܂��B���l�E�}�O���b�g���u�����ϔC��v�i�E���j�ŕ`���ꂽ�X�̃M�~�b�N�Ȋ����Ɉ�ۂ��߂����̂ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
��R�́@���ƂƂ���
�����́A���B���w���ɉ��B�̕��i��`���A�A�����Đ��ɂȂ�Ɠ��{�S���𗷂��ĕ��i��`�����ƌ����܂��B
���̂��镗�i
 �u�t�J�v�͂P�X�R�R�N���̍�i�B�薼�́u�t�J�v�ł����A��ʂł͉J���~���Ă͂��܂���B�~���I����ďt�̉J���~������́A�������ʂ��Ă����Ⴊ�����A�킸���ɐႪ�c�����������ʂ��Ă����Ⴊ�����A��i��`���Ă��܂��B�܂�A���̍�i�ł͌����Ȃ��t�J��`�����Ƃ��Ă���Ƃ����킯�ł��B�����̕`�����Ƃ��������Ȃ����̂Ƃ����̂́A���ʂƂ����_�ȂǂƂ��������ۓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̂悤�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł��B
�u�t�J�v�͂P�X�R�R�N���̍�i�B�薼�́u�t�J�v�ł����A��ʂł͉J���~���Ă͂��܂���B�~���I����ďt�̉J���~������́A�������ʂ��Ă����Ⴊ�����A�킸���ɐႪ�c�����������ʂ��Ă����Ⴊ�����A��i��`���Ă��܂��B�܂�A���̍�i�ł͌����Ȃ��t�J��`�����Ƃ��Ă���Ƃ����킯�ł��B�����̕`�����Ƃ��������Ȃ����̂Ƃ����̂́A���ʂƂ����_�ȂǂƂ��������ۓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̂悤�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł��B
 �u�����v�͂P�X�S�P�N�̍�i�ł��B
�g�ǂ��ɂł�����悤�ȕ��}�ȕ��i�B���ꂾ���ɒ����ŔG�ꂽ�͑��̎�������Ԃ▶�ɉB���ؗ��̗l�q�A�����Ď��C�������Ղ�܂�C�̊��o���X�g���[�g�Ɋ�������B�͑��⍕�y���ׂ����`�ʂ���Ă���̂ŁA���̎R�̋�C�╵�͋C����������Ă���B�`�Ƃ��Č����Ă��Ȃ����̂�\�����悤�Ƃ��Ă���B�h�Ɛ�������Ă��܂����B������A��C�Ƃ����͋C�Ƃ��A�ǂ��ɂł�����悤�ȕ��}�ȕ��i�B���ꂾ���ɒ����ŔG�ꂽ�͑��̎�������Ԃ▶�ɉB���ؗ��̗l�q�A�����Ď��C�������Ղ�܂�C�̊��o���X�g���[�g�Ɋ�������B�͑��⍕�y���ׂ����`�ʂ���Ă���̂ŁA���̎R�̋�C�╵�͋C����������Ă���B�`�Ƃ��Č����Ă��Ȃ����̂�\�����悤�Ƃ��Ă���B�u�t�J�v�Ɠ����悤�ɁA�����Ȃ����̂�`�����Ƃ��Ă����i�ł��B
�u�����v�͂P�X�S�P�N�̍�i�ł��B
�g�ǂ��ɂł�����悤�ȕ��}�ȕ��i�B���ꂾ���ɒ����ŔG�ꂽ�͑��̎�������Ԃ▶�ɉB���ؗ��̗l�q�A�����Ď��C�������Ղ�܂�C�̊��o���X�g���[�g�Ɋ�������B�͑��⍕�y���ׂ����`�ʂ���Ă���̂ŁA���̎R�̋�C�╵�͋C����������Ă���B�`�Ƃ��Č����Ă��Ȃ����̂�\�����悤�Ƃ��Ă���B�h�Ɛ�������Ă��܂����B������A��C�Ƃ����͋C�Ƃ��A�ǂ��ɂł�����悤�ȕ��}�ȕ��i�B���ꂾ���ɒ����ŔG�ꂽ�͑��̎�������Ԃ▶�ɉB���ؗ��̗l�q�A�����Ď��C�������Ղ�܂�C�̊��o���X�g���[�g�Ɋ�������B�͑��⍕�y���ׂ����`�ʂ���Ă���̂ŁA���̎R�̋�C�╵�͋C����������Ă���B�`�Ƃ��Č����Ă��Ȃ����̂�\�����悤�Ƃ��Ă���B�u�t�J�v�Ɠ����悤�ɁA�����Ȃ����̂�`�����Ƃ��Ă����i�ł��B
���̂��镗�i

 �u���Ă̖�H�v�͂P�X�T�T�N�̍�i�B�u�t�J�v��u�����v�Ɠ����悤�ɁA�����Ƃ���i�̂悤�ȕ��i�ł͂Ȃ��A���}�Ȃǂ��ɂł����肻���ȕ��i�ł��B���Ƃ����Ă��A����������l�̎p���Ȃ��A�쌴�̐^�ɓ�������Ƃ��������̍�i�B����́A�ݓc�������u���H�Ɠy��ƕ��i�ؒʎʐ��j�v�̉e��������悤�Ɏv���܂��B�ݓc�ɂƂ��Ďʐ��ւ̊J��ƂȂ����ƌ������i���A�ɒǂ�����������A�Ƃ����̂͂����ɂ������Ƃ����l�Ɏ����킵���v����̂ł����B
�u���Ă̖�H�v�͂P�X�T�T�N�̍�i�B�u�t�J�v��u�����v�Ɠ����悤�ɁA�����Ƃ���i�̂悤�ȕ��i�ł͂Ȃ��A���}�Ȃǂ��ɂł����肻���ȕ��i�ł��B���Ƃ����Ă��A����������l�̎p���Ȃ��A�쌴�̐^�ɓ�������Ƃ��������̍�i�B����́A�ݓc�������u���H�Ɠy��ƕ��i�ؒʎʐ��j�v�̉e��������悤�Ɏv���܂��B�ݓc�ɂƂ��Ďʐ��ւ̊J��ƂȂ����ƌ������i���A�ɒǂ�����������A�Ƃ����̂͂����ɂ������Ƃ����l�Ɏ����킵���v����̂ł����B
�l�G�̕��i
 �u�Ђ܂��v�Ƃ����P�X�T�S�N�̍�i�ł��B�g�^�Ă̐��V�̉��A��������Đg����������Ђ܂�肪�`����Ă���B�Ԃт�͈ꖇ�ꖇ���k�ɕ`����A�t��s�ɂ͓Ɠ��̉A�e�\�����{����Ȃ�����A��ʂ͂܂������e�����������Ȃ��قǖ��邢���ɖ����A��n�ɍ������ė��Ђ܂�萶�������ӂ��p����������Ă���B�Ђ܂��̌s�̕����ɂ́A�c�ɐL�т�֊s�������ĂɈ�����Ă��邪�A���̂悤�ȓƓ��̗֊s���̕\���́A��\�Y�̊G��̓����ł���u�㏸���v������������ʂ������炵�Ă���B�h�ƓW���̐���������Ă��܂����B�������ɁA���̍�i�ȊO�ɂ������̍�i�ɂ͏�֏�ւƌ������ď㏸���Ă������͋C�̂�����̂��A�X�̂��镗�i��A����`�������̂𒆐S�ɁA�悭�����܂��B���łɌ����u�䉑�̏t�v�̂悤�ɉ�ʂ̒��S�ɒ�����������V�����g���[�炵���`�����̂�A�u�����v��u�x�j�X�̊C�v���邢�́u�X�C�v�̏���ȂǁA�Ԃ̌s�A�D�̔��A�X�C�̉����A�����Ƃ��˂�Ȃ����Ɍ������ĐL�т�悤�ɕ`����Ă���̂��A�����ł��B�����āA���́u�Ђ܂��v�������ł��B�����āA�Ɠ��̗֊s���g�������A��������������������Ă���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�Ђ܂��̒�������s�ɂ͖��m�ȗ֊s�����A�悭����ƌs��`���̂ƓƗ������悤�Ɉ�����Ă��܂��B����͏c�̐������ŁA�}�����ꂵ�ĉ��ɐL�т��s�ɂ͈�����Ă��܂���B����͈Ӑ}�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����ɂ���ď㏸������������邱�ƂŁA��Ɍ������ĐL�тĂ������Ƃ���Ђ܂��̐��������Ƃ�������������������邱�ƂɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�����āA���m�Ɉ����ꂽ�֊s��������ƕ����邱�ƂŁA��ʑS�̂���������Ƃ��āA�ǂ��܂ł����m�ɁA�Ƃ��Ɂu�Ђ܂��v�ł́A��ʂ̋��X�܂Ō����������Ă���悤�ȁA�f��ł����ƃp���t�H�[�J�X�̂悤�Ȉ�ۂ�^������̂ƂȂ��Ă��܂��B����͔��ʂł́A�A�e�����킹�邱�Ƃɂ��Ȃ��āA����قǂ܂łɖ��m�ɕ`�����܂�A�ǂ��܂ł����m�Ȃ̂ɁA�S�̂Ƃ��Ă͂̂���Ƃ�����ۂƂȂ��Ă��܂��B�����I�߂��āA�������Ĕ��Ă��ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ�����̂ł��B
�u�Ђ܂��v�Ƃ����P�X�T�S�N�̍�i�ł��B�g�^�Ă̐��V�̉��A��������Đg����������Ђ܂�肪�`����Ă���B�Ԃт�͈ꖇ�ꖇ���k�ɕ`����A�t��s�ɂ͓Ɠ��̉A�e�\�����{����Ȃ�����A��ʂ͂܂������e�����������Ȃ��قǖ��邢���ɖ����A��n�ɍ������ė��Ђ܂�萶�������ӂ��p����������Ă���B�Ђ܂��̌s�̕����ɂ́A�c�ɐL�т�֊s�������ĂɈ�����Ă��邪�A���̂悤�ȓƓ��̗֊s���̕\���́A��\�Y�̊G��̓����ł���u�㏸���v������������ʂ������炵�Ă���B�h�ƓW���̐���������Ă��܂����B�������ɁA���̍�i�ȊO�ɂ������̍�i�ɂ͏�֏�ւƌ������ď㏸���Ă������͋C�̂�����̂��A�X�̂��镗�i��A����`�������̂𒆐S�ɁA�悭�����܂��B���łɌ����u�䉑�̏t�v�̂悤�ɉ�ʂ̒��S�ɒ�����������V�����g���[�炵���`�����̂�A�u�����v��u�x�j�X�̊C�v���邢�́u�X�C�v�̏���ȂǁA�Ԃ̌s�A�D�̔��A�X�C�̉����A�����Ƃ��˂�Ȃ����Ɍ������ĐL�т�悤�ɕ`����Ă���̂��A�����ł��B�����āA���́u�Ђ܂��v�������ł��B�����āA�Ɠ��̗֊s���g�������A��������������������Ă���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�Ђ܂��̒�������s�ɂ͖��m�ȗ֊s�����A�悭����ƌs��`���̂ƓƗ������悤�Ɉ�����Ă��܂��B����͏c�̐������ŁA�}�����ꂵ�ĉ��ɐL�т��s�ɂ͈�����Ă��܂���B����͈Ӑ}�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����ɂ���ď㏸������������邱�ƂŁA��Ɍ������ĐL�тĂ������Ƃ���Ђ܂��̐��������Ƃ�������������������邱�ƂɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�����āA���m�Ɉ����ꂽ�֊s��������ƕ����邱�ƂŁA��ʑS�̂���������Ƃ��āA�ǂ��܂ł����m�ɁA�Ƃ��Ɂu�Ђ܂��v�ł́A��ʂ̋��X�܂Ō����������Ă���悤�ȁA�f��ł����ƃp���t�H�[�J�X�̂悤�Ȉ�ۂ�^������̂ƂȂ��Ă��܂��B����͔��ʂł́A�A�e�����킹�邱�Ƃɂ��Ȃ��āA����قǂ܂łɖ��m�ɕ`�����܂�A�ǂ��܂ł����m�Ȃ̂ɁA�S�̂Ƃ��Ă͂̂���Ƃ�����ۂƂȂ��Ă��܂��B�����I�߂��āA�������Ĕ��Ă��ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ�����̂ł��B

 �u��̑��v�i�����j�͂P�X�T�W�N�̍�i�B�G�t���I�Ƃ����Ă������i�ł��B�܂�����䏁�g�̃m�X�^���W�b�N�Ȗ��Ƃ̕��i���i�E���j�����Ă��邩�̂悤�ł��B
�u��̑��v�i�����j�͂P�X�T�W�N�̍�i�B�G�t���I�Ƃ����Ă������i�ł��B�܂�����䏁�g�̃m�X�^���W�b�N�Ȗ��Ƃ̕��i���i�E���j�����Ă��邩�̂悤�ł��B
�u�ς�v�i�E���j�Ƃ����P�X�S�W�N���̍�i�ł��B�摜�Ō��镪�ɂ́A��̂���ƍ~��ς����i��`������i�Ɍ����܂��B��ʂɐ�̍~��ς���␢�E�̂Ȃ��ꌬ�̖��ƂƖh��т��A���̐�ɉ��ނ悤�ɉf���Ă���B�܂�ł���Ɛ�̍~��ς��鉹�������������Ă���Î�Ɏx�z���ꂽ����I�Ȑ��E�A����Ȋ����ł��傤���B�������A��������ۂɉ��ł݂�ƁA���̐U����ς������Ⴊ�傫����`��ς��ē_�`�łЂƂЂƂ��`����Ă���̂ł��B���̈ٗl�Ȕ��́A���̂ЂƂЂƂ���Ƃ����J�ɕM�ŕ`���Ă���p��z�����āA���̎��O�̂悤�Ȃ��̂����낵���Ȃ�悤�ł��B��ʑS�̂�����F�̐��E�ŁA���̔��̓_�`������ƕ�����Ƃ����̂��������Z�I�Ǝv���܂����A����ɂ���Ĕ��̔����ő��ʂȃo���G�[�V�������p�����A���̔������E�ʼnA�e�����܂�Ă���̂ł��B����ɂ́A���������B����A�����Ă���_�`�̎�@��p���邱�Ƃ������Ǝv���܂����A���̓_�`�ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B���̍����̓_�`�̎�@�̃��[�c�����߂�ƈ�۔h�ɁA���̂ЂƂ̌�������悤�Ɏv��
 �܂��B��۔h�́A����\�����悤�Ƃ����Ƃ����܂��B���̈�۔h�̓����I�ȋZ�@�Ƃ��ĐF�ʕ����Ƃ������̂�����܂��B���i�������͉��C�Ȃ����R���̒��ł��̂����Ă��܂����A���̌��͒P��ł͂Ȃ��A�l�X�Ȕg���̌��ɕ����ł���̂ł��B�Ƃ��ɉ������͕�����Ղ�����ΎO���F�ɕ����ł��܂��B�v���Y���Ɍ���ʂ��Ƃ��ꂪ�����܂��B����́A�E�ԁE�̎O�F�B�@����ɔ䂵�ĐF�i�G�̋�j�̎O���F�́A�E�ԁE���ƂȂ�܂��B�J�N�e�������ƌ�����悤�ɁA���͎O���F��������Δ����P���܂����A�G�̋�͎O���F��������O���[�ɑ����āA�Â��F�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���͍����������قǖ��邭�P���܂����A�G�̋�͈Â�����ł��܂��̂ł��B���m�ł͓��Ƀ��l�T���X�ȗ��A��ԕ\���̂��߂ɉ��ߖ@����g������A���܂��܂ȊG�̋���l�Ă�����ƁA�Z�p�I�ȒNj��ɂ͗]�O���Ȃ������킯�ł��B�������A���̌��ƊG�̋�̎O���F�̓����ɈႢ�͔@���Ƃ����������A���݂Ɏ�����������̂܂܂Ȃ̂ł��B�F�ʕ����Ƃ́A�G�̋�������Ē��ԐF����낤�Ƃ���Ƃǂ����Ă������Ă��܂��̂ŁA�G�̋���������ɐ��F�̂܂܃L�����o�X�ɏ悹�A�אڂ��镔���ɖ{�������悤�Ƃ���F���悹�E�E�E�Ƃ��邱�ƂŁA�����܂ł��h��F���̂͐��F�E�E�E�@��M���Ƃɐ��F���悹�邱�ƂŁA��ʑS�̂Ƃ��Ă͖��邭���F�̏W���̂Ƃ���̂ł��B�������Ă������甭����������ς�҂̖ڂ�������Ƃ��ɁA�ς�҂̖ڂ̒��ō����āA�{����Ƃ��\���������ƍl�����F�ɍ������ĊςĂ��炨���Ƃ������̂ł��B�i�������۔h�̊G�́A�����[�g���A���ɂ͂P�O���[�g���ȏ㗣��Ċς�ƁA���ɐ[�����킢�ɂȂ�܂��j���̌������̂��͈̂�۔h��҂����Ƃ����łɊm������Ă����̂ł����A�������Ȃ��炻�������`�@�́A������e�ւ́A�F����F�ւ́A���炩�Ȉڍs�Ƃ����ۑ�ɂ͓K�����A�G���͂����肵����M�X�X�̏W���̂ł��邱�Ƃ���������Ă��܂��E�E�E�����������_�������āA��ʓI�ɂ͍̗p����Ȃ��������̂������̂ł��B������A��۔h�̉�ʂ�����ƌ��F�̊G�̋����グ���Ēu���ꂽ�悤�ɂȂ��Ă���悤�Ɍ�����Ƃ��낪����܂��B�ߊ���Ă݂�Ƒe�����������܂����A�F�ʕ����̌��ʂ��l���āA�G�̋�̐���グ���ɂ���Č��̃j���A���X���ς���Ă��邩��Ȃ̂ł��B�������A����ł͂ǂ����Ă��S�̂Ƃ��đe�����̂ƂȂ��đ�G�c�ɂȂ肪���ł��B����������ƍׂ����Ƃ���܂ŕ\���ł���悤�ɓ˂��l�߂��̂��_�`�i�Ⴆ�X�[���u�O�����h�E�W���b�g���̓��j���̌ߌ�v�i�����j�j�Ȃ̂ł��B�����������̗��q��_�ɂ��邱�Ƃɂ���đe���������̕\�����ׂ������̂ɂ��Ă����܂����B�Ƃ������Ƃ́A���̓_�`�̓_���ׂ������Ă����A����ɏ]���Č��̔����ȕ\�����\�ɂȂ��Ă���Ƃ����̂������ł��B�������A����ɂ͉�Ƃ̘J�͂͑�ςȂ��̂ɂȂ��Ă����܂��B��M�œh��Ă��܂��Ƃ���𐔏\�A���S�A����̓_���������F��ς��Ȃ���_�`����킯�ł�����A�J�͂͐��\�{�A���S�{�A����{�ɂȂ�킯�ł��B������A��۔h����A���̔��W�n�Ƃ�����V��۔h�̉�Ƃ����ł��_�`��ϋɓI�ɂ�����̂̓X�[�����炢�ł͂Ȃ������ł��傤���B����������́A�����I�ɁA���邢�͂��́u�ς�v�ł́A�قڑS�ʓI�ɓ_�`���s�Ȃ����Ƃ�����̂ł��B�����ɂ́A��۔h�̂悤�ȊG�̋�̍����������Ƃ������Ƃ����A�������������Ă��܂��Ƃ����悤�ȁA�����̂��Ƃ��Ƃ����Ă��������A���邢�ׂ͍����Ƃ�������X�ɕ`���Ă��܂��u���������𗱎q�ɕ������Ă��܂����Ƃɍs���������̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B�����������Ƃ��l����ƁA���́u�ς�v�Ƃ�����i�́A�����̎u�������Ïk���Ă���ƁA���ɂ͎v���Ă���̂ł��B�{���ɁA���̔��͐����ł��B
�܂��B��۔h�́A����\�����悤�Ƃ����Ƃ����܂��B���̈�۔h�̓����I�ȋZ�@�Ƃ��ĐF�ʕ����Ƃ������̂�����܂��B���i�������͉��C�Ȃ����R���̒��ł��̂����Ă��܂����A���̌��͒P��ł͂Ȃ��A�l�X�Ȕg���̌��ɕ����ł���̂ł��B�Ƃ��ɉ������͕�����Ղ�����ΎO���F�ɕ����ł��܂��B�v���Y���Ɍ���ʂ��Ƃ��ꂪ�����܂��B����́A�E�ԁE�̎O�F�B�@����ɔ䂵�ĐF�i�G�̋�j�̎O���F�́A�E�ԁE���ƂȂ�܂��B�J�N�e�������ƌ�����悤�ɁA���͎O���F��������Δ����P���܂����A�G�̋�͎O���F��������O���[�ɑ����āA�Â��F�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���͍����������قǖ��邭�P���܂����A�G�̋�͈Â�����ł��܂��̂ł��B���m�ł͓��Ƀ��l�T���X�ȗ��A��ԕ\���̂��߂ɉ��ߖ@����g������A���܂��܂ȊG�̋���l�Ă�����ƁA�Z�p�I�ȒNj��ɂ͗]�O���Ȃ������킯�ł��B�������A���̌��ƊG�̋�̎O���F�̓����ɈႢ�͔@���Ƃ����������A���݂Ɏ�����������̂܂܂Ȃ̂ł��B�F�ʕ����Ƃ́A�G�̋�������Ē��ԐF����낤�Ƃ���Ƃǂ����Ă������Ă��܂��̂ŁA�G�̋���������ɐ��F�̂܂܃L�����o�X�ɏ悹�A�אڂ��镔���ɖ{�������悤�Ƃ���F���悹�E�E�E�Ƃ��邱�ƂŁA�����܂ł��h��F���̂͐��F�E�E�E�@��M���Ƃɐ��F���悹�邱�ƂŁA��ʑS�̂Ƃ��Ă͖��邭���F�̏W���̂Ƃ���̂ł��B�������Ă������甭����������ς�҂̖ڂ�������Ƃ��ɁA�ς�҂̖ڂ̒��ō����āA�{����Ƃ��\���������ƍl�����F�ɍ������ĊςĂ��炨���Ƃ������̂ł��B�i�������۔h�̊G�́A�����[�g���A���ɂ͂P�O���[�g���ȏ㗣��Ċς�ƁA���ɐ[�����킢�ɂȂ�܂��j���̌������̂��͈̂�۔h��҂����Ƃ����łɊm������Ă����̂ł����A�������Ȃ��炻�������`�@�́A������e�ւ́A�F����F�ւ́A���炩�Ȉڍs�Ƃ����ۑ�ɂ͓K�����A�G���͂����肵����M�X�X�̏W���̂ł��邱�Ƃ���������Ă��܂��E�E�E�����������_�������āA��ʓI�ɂ͍̗p����Ȃ��������̂������̂ł��B������A��۔h�̉�ʂ�����ƌ��F�̊G�̋����グ���Ēu���ꂽ�悤�ɂȂ��Ă���悤�Ɍ�����Ƃ��낪����܂��B�ߊ���Ă݂�Ƒe�����������܂����A�F�ʕ����̌��ʂ��l���āA�G�̋�̐���グ���ɂ���Č��̃j���A���X���ς���Ă��邩��Ȃ̂ł��B�������A����ł͂ǂ����Ă��S�̂Ƃ��đe�����̂ƂȂ��đ�G�c�ɂȂ肪���ł��B����������ƍׂ����Ƃ���܂ŕ\���ł���悤�ɓ˂��l�߂��̂��_�`�i�Ⴆ�X�[���u�O�����h�E�W���b�g���̓��j���̌ߌ�v�i�����j�j�Ȃ̂ł��B�����������̗��q��_�ɂ��邱�Ƃɂ���đe���������̕\�����ׂ������̂ɂ��Ă����܂����B�Ƃ������Ƃ́A���̓_�`�̓_���ׂ������Ă����A����ɏ]���Č��̔����ȕ\�����\�ɂȂ��Ă���Ƃ����̂������ł��B�������A����ɂ͉�Ƃ̘J�͂͑�ςȂ��̂ɂȂ��Ă����܂��B��M�œh��Ă��܂��Ƃ���𐔏\�A���S�A����̓_���������F��ς��Ȃ���_�`����킯�ł�����A�J�͂͐��\�{�A���S�{�A����{�ɂȂ�킯�ł��B������A��۔h����A���̔��W�n�Ƃ�����V��۔h�̉�Ƃ����ł��_�`��ϋɓI�ɂ�����̂̓X�[�����炢�ł͂Ȃ������ł��傤���B����������́A�����I�ɁA���邢�͂��́u�ς�v�ł́A�قڑS�ʓI�ɓ_�`���s�Ȃ����Ƃ�����̂ł��B�����ɂ́A��۔h�̂悤�ȊG�̋�̍����������Ƃ������Ƃ����A�������������Ă��܂��Ƃ����悤�ȁA�����̂��Ƃ��Ƃ����Ă��������A���邢�ׂ͍����Ƃ�������X�ɕ`���Ă��܂��u���������𗱎q�ɕ������Ă��܂����Ƃɍs���������̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B�����������Ƃ��l����ƁA���́u�ς�v�Ƃ�����i�́A�����̎u�������Ïk���Ă���ƁA���ɂ͎v���Ă���̂ł��B�{���ɁA���̔��͐����ł��B
��S�́@���̐S�ƂƂ���
�_���t��`��

 �u�J�y�̏t�v�Ƃ����P�X�T�R�N�̍�i�B�ޗnj��ɂ���L������t���̓����ł��B�O�w�̉����̉��ɏ֊K�������ĘZ�d�̓��Ɍ�����Ɠ��ɃV���G�b�g���A���̂܂ܕ`���Ă���A���O���́A�����ɂ��u�F�����m�v�Ƃł�������X�e���I�^�C�v�A�G�t���I�ł��B�����́A�܂�Ńr���̍H������ɂ���悤�Ȋ����\�z�}�̂悤�ȁA���m�����}���I�ȕ`�����ł��B�������A�����͖�t���̎ʐ^�����Ă�������Ǝv���܂����A�u�J�y�̏t�v�͎ʐ^�̂悤�ɖ�t���̕��i�����̂܂ܕ`���Ă���킯�ł͂Ȃ��A���ۂ̓������鉾���ɂ́u�J�y�̏t�v�̉�ʂ̂悤�ɑ��͐����Ă��܂���B������A�u�J�y�̏t�v�͍�������t���������g���Ă��肾�����ˋ�̕��i�ł��B�����Ė�t�������ɁA�����ɂ͂Ȃ�����`���������̂́A�����͕`��������������Ƃ������Ƃł��傤�B����͉�ʂ�����Δ[���ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��ʂ̑O�ʂɏo�Ă��Ĉ�ۓI�Ȃ̂́A�܂�œ����B���悤�ɖ��J�ɉԊJ���}�����ł���A���̉��̈�ۓI�ȐԂ̂��̉Ԃł��B�����āA�}�����̍����ɂ́A�����̏�����i�Ō����݂́g���˂��ˁh�����̎Ⴂ���̖œo�ꂵ�Ă��܂��B���̓o�b�N�̔w�i�ŁA���̎p���Ȃ������Ƃ���A�O�i�̎}��������������ď��̖₻�̎}�̔ɖ���ʂ̊O�g�̂悤�ɂȂ��Ă��āA�S�̂ɑ��ɕ���������Ă���̂ł��B����́A���̕Ό���������܂��A�����̕M�͌��z�ɑ��ẮA�����Ō��łɍ\�����ꂽ�\�z����`���̂ɁA�������狏�S�n�̈����̂悤�Ȃ��̂������āA���ꂪ�����p�Ƃ��Ö��Ƃ̂悤�Ȑl�̐����̂Ȃ��Ŏ���������Ă��̃v���|�[�V�����̋ϐ������ꂽ�悤�Ȃ��̂��D��ŕ`���Ă����悤�Ɏv���܂��B�����ł��A�������V�����g���[�ɂ͕`�����A�ϐ��̂Ƃꂽ�v���|�[�V������O�ʂɏo�����A���̌�i�ɂ��āA�ꕔ���B���Ă��܂��܂��B�ϐ��̂Ƃꂽ���肵���p�́A����Ŏ~�܂��Ă��܂��āA�������瓮���͐��܂�Ă��Ȃ��ł��傤�B�����ɍ������S�O������Ƃ��낪�������Ƃ��낪�������̂�������܂���B�����́A���̑��ɂ��@�����̌d����`�����肵�Ă��܂����A�������J����ۓI��������ƁA���ɂ́A���܂�p�b�Ƃ��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B���́u�J�y�̏t�v�ł��A�_�`�̂悤�Ȏ}�����̃s���N�F�̏����ȉԂ̂ЂƂЂƂ��ۗ����Ă���Ƃ���ł��B
�u�J�y�̏t�v�Ƃ����P�X�T�R�N�̍�i�B�ޗnj��ɂ���L������t���̓����ł��B�O�w�̉����̉��ɏ֊K�������ĘZ�d�̓��Ɍ�����Ɠ��ɃV���G�b�g���A���̂܂ܕ`���Ă���A���O���́A�����ɂ��u�F�����m�v�Ƃł�������X�e���I�^�C�v�A�G�t���I�ł��B�����́A�܂�Ńr���̍H������ɂ���悤�Ȋ����\�z�}�̂悤�ȁA���m�����}���I�ȕ`�����ł��B�������A�����͖�t���̎ʐ^�����Ă�������Ǝv���܂����A�u�J�y�̏t�v�͎ʐ^�̂悤�ɖ�t���̕��i�����̂܂ܕ`���Ă���킯�ł͂Ȃ��A���ۂ̓������鉾���ɂ́u�J�y�̏t�v�̉�ʂ̂悤�ɑ��͐����Ă��܂���B������A�u�J�y�̏t�v�͍�������t���������g���Ă��肾�����ˋ�̕��i�ł��B�����Ė�t�������ɁA�����ɂ͂Ȃ�����`���������̂́A�����͕`��������������Ƃ������Ƃł��傤�B����͉�ʂ�����Δ[���ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��ʂ̑O�ʂɏo�Ă��Ĉ�ۓI�Ȃ̂́A�܂�œ����B���悤�ɖ��J�ɉԊJ���}�����ł���A���̉��̈�ۓI�ȐԂ̂��̉Ԃł��B�����āA�}�����̍����ɂ́A�����̏�����i�Ō����݂́g���˂��ˁh�����̎Ⴂ���̖œo�ꂵ�Ă��܂��B���̓o�b�N�̔w�i�ŁA���̎p���Ȃ������Ƃ���A�O�i�̎}��������������ď��̖₻�̎}�̔ɖ���ʂ̊O�g�̂悤�ɂȂ��Ă��āA�S�̂ɑ��ɕ���������Ă���̂ł��B����́A���̕Ό���������܂��A�����̕M�͌��z�ɑ��ẮA�����Ō��łɍ\�����ꂽ�\�z����`���̂ɁA�������狏�S�n�̈����̂悤�Ȃ��̂������āA���ꂪ�����p�Ƃ��Ö��Ƃ̂悤�Ȑl�̐����̂Ȃ��Ŏ���������Ă��̃v���|�[�V�����̋ϐ������ꂽ�悤�Ȃ��̂��D��ŕ`���Ă����悤�Ɏv���܂��B�����ł��A�������V�����g���[�ɂ͕`�����A�ϐ��̂Ƃꂽ�v���|�[�V������O�ʂɏo�����A���̌�i�ɂ��āA�ꕔ���B���Ă��܂��܂��B�ϐ��̂Ƃꂽ���肵���p�́A����Ŏ~�܂��Ă��܂��āA�������瓮���͐��܂�Ă��Ȃ��ł��傤�B�����ɍ������S�O������Ƃ��낪�������Ƃ��낪�������̂�������܂���B�����́A���̑��ɂ��@�����̌d����`�����肵�Ă��܂����A�������J����ۓI��������ƁA���ɂ́A���܂�p�b�Ƃ��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B���́u�J�y�̏t�v�ł��A�_�`�̂悤�Ȏ}�����̃s���N�F�̏����ȉԂ̂ЂƂЂƂ��ۗ����Ă���Ƃ���ł��B
���̂������E�_�̂�����

 �u�e�̉ԁv�i�����j�Ƃ����P�X�T�U�N�́A�ԕr�Ɋ������e�̉Ԃ�`������i�ł��B�Ƃɂ����A�e�̉Ԃ̈�ֈ�ւ̉Ԃт�̈ꖇ�ꖇ�J�ɕ`���Ă��鎷�X���Ɉ��|������i�ł��B��Ƃ��וM�������āA�ꖇ�̉Ԃт�̏����ȂƂ���̈ꕔ�ɊG�̋�����x���h��d�˂Ă����p��z������ƁA��ɂ����o���܂��B�������A���̂悤�Ɉ�ւ̉Ԃ́A�ꖇ�̉Ԃт�����a���ɂ��Ȃ��ŁA���ׂĂɂ��܂˂����J�ɍs���n��悤�ɕ`���ꂽ���ʂƂ��āA���Ȉ�ۂƂȂ��Ă��邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B�����n�����Ȃ��̂ł��B������m�b�y���Ƃ��ē��{��̉Ԓ�������Ă���悤�Ȉ�ۂł��B���̍�i�����Ă���ƁA�����͋e�̉Ԃ̐������𔗗͂������ĕ`�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�e�̉Ԃ��ނɔ��͂̂����ʂ���낤�Ƃ��Ă������Ƃ�������܂��B���Ƃ��A�����E�u�����[�Q���͐Õ���̒��ł��ז��ȉԂ�`���̂Œ�]�̂����Ƃł����A�����u�ԙ��v�i�E���j�Ƃ�����i�Ɣ�ׂĂ݂�ƁA�A�e������������ʂ̒��ŁA�Ԃ̐������ے��I�ɕ`����Ă���ƌ����Ă��܂��B�X���̈قȂ��ƂȂ̂ŁA�P�ɕ��ׂ邾���ŗD���₤����͂���܂��A�u�����[�Q���͉Ԃ̏������ے��I�ɕ`�������Ă��܂����A�����̕`���Ă���e�̉Ԃ́A�ЂƂЂƂ̓u�����[�Q���ȏ�ɒ��J�Ȃ̂ł��傤���A���ꂼ��Ɍ����Ȃ��āA���̈�ւƂ����B�ꂳ���Ȃ��̂ł��B�R���s���[�^�̉�ʂł����A�R�s�[�E�A���h�E�y�[�X�g�����悤�Ɉ�l�Ȃ̂ł��B������A�����ō����̍�i���犴�����锗�͂Ƃ����̂́A���������J�͂��}�킸�ɂ�萋������Ƃ̘J�͂ɂ����̂ł��B�ȑO�ɂ��A�����q�ׂ܂������A�����͕`���Ƃ����v���Z�X�A�܂莩�����s�ׂ���Ƃ������ƁA�����ƌ����A�������n����ƂȂ��ĉF����n�����邱�Ƃ��d�v�ł����āA�o���オ�������̂ɑ��ẮA��o�������Ȃ��B����́A�����ɏ�����Ă���L���X�g���̐_���l���͂��ߖ�����n���������ƁA�l�X���l�X�Ȏ������āA�_�ɑ��ċ~�������߁A�₢������^���ɍs�Ȃ��Ă��A��ؓ����Ȃ��̂ƁA�悭���Ă��܂��B
�u�e�̉ԁv�i�����j�Ƃ����P�X�T�U�N�́A�ԕr�Ɋ������e�̉Ԃ�`������i�ł��B�Ƃɂ����A�e�̉Ԃ̈�ֈ�ւ̉Ԃт�̈ꖇ�ꖇ�J�ɕ`���Ă��鎷�X���Ɉ��|������i�ł��B��Ƃ��וM�������āA�ꖇ�̉Ԃт�̏����ȂƂ���̈ꕔ�ɊG�̋�����x���h��d�˂Ă����p��z������ƁA��ɂ����o���܂��B�������A���̂悤�Ɉ�ւ̉Ԃ́A�ꖇ�̉Ԃт�����a���ɂ��Ȃ��ŁA���ׂĂɂ��܂˂����J�ɍs���n��悤�ɕ`���ꂽ���ʂƂ��āA���Ȉ�ۂƂȂ��Ă��邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B�����n�����Ȃ��̂ł��B������m�b�y���Ƃ��ē��{��̉Ԓ�������Ă���悤�Ȉ�ۂł��B���̍�i�����Ă���ƁA�����͋e�̉Ԃ̐������𔗗͂������ĕ`�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�e�̉Ԃ��ނɔ��͂̂����ʂ���낤�Ƃ��Ă������Ƃ�������܂��B���Ƃ��A�����E�u�����[�Q���͐Õ���̒��ł��ז��ȉԂ�`���̂Œ�]�̂����Ƃł����A�����u�ԙ��v�i�E���j�Ƃ�����i�Ɣ�ׂĂ݂�ƁA�A�e������������ʂ̒��ŁA�Ԃ̐������ے��I�ɕ`����Ă���ƌ����Ă��܂��B�X���̈قȂ��ƂȂ̂ŁA�P�ɕ��ׂ邾���ŗD���₤����͂���܂��A�u�����[�Q���͉Ԃ̏������ے��I�ɕ`�������Ă��܂����A�����̕`���Ă���e�̉Ԃ́A�ЂƂЂƂ̓u�����[�Q���ȏ�ɒ��J�Ȃ̂ł��傤���A���ꂼ��Ɍ����Ȃ��āA���̈�ւƂ����B�ꂳ���Ȃ��̂ł��B�R���s���[�^�̉�ʂł����A�R�s�[�E�A���h�E�y�[�X�g�����悤�Ɉ�l�Ȃ̂ł��B������A�����ō����̍�i���犴�����锗�͂Ƃ����̂́A���������J�͂��}�킸�ɂ�萋������Ƃ̘J�͂ɂ����̂ł��B�ȑO�ɂ��A�����q�ׂ܂������A�����͕`���Ƃ����v���Z�X�A�܂莩�����s�ׂ���Ƃ������ƁA�����ƌ����A�������n����ƂȂ��ĉF����n�����邱�Ƃ��d�v�ł����āA�o���オ�������̂ɑ��ẮA��o�������Ȃ��B����́A�����ɏ�����Ă���L���X�g���̐_���l���͂��ߖ�����n���������ƁA�l�X���l�X�Ȏ������āA�_�ɑ��ċ~�������߁A�₢������^���ɍs�Ȃ��Ă��A��ؓ����Ȃ��̂ƁA�悭���Ă��܂��B
 �u�̉ԁv�͂P�X�U�T�N�̍�i�B�u�e�̉ԁv�͉ԕr�Ɋ�����ꂽ�ԂƂ������i�ł������A���̍�i�͈�ʂɍ炭�̉Ԃ̕��i�Ƃ����K�͂̑傫�ȍ�i�ŁA����Ɂu�e�̉ԁv�ɂ������Ȃ��قǂ̎��X���ň�Ԉ�ԁA���ꂾ���ĂȂ��s���t���ז��ɕ`�����܂�Ă��܂��B���̔��͂��������B�g�_�炩�ȑ��z�̌��������ċP���悤�ɍ炭�����̍̉Ԃ��A�u�e�̉ԁv�Ɠ��l�ɁA������������A�G������҂��t�Ɍ��߂�悤�ɑΛ����Ă���B��������ӂꂽ�t�̌��i�ł���Ȃ���A����z���������̂�����X�Ɋ���������B�h�Ɛ�������Ă��܂��B���̍�i�́A�u�e�̉ԁv�ɉ����āu�Ђ܂��v�ł݂������̗֊s���ɂ��㏸���������܂��B�����ɍ炫���ꂽ�̉Ԃ̌s�̂ЂƂЂƂɁA�c�ɐL�т�֊s�����Z��������Ă��܂��B��ʂł͉����������t��A���F���̉ԁA�ΐF�̗t��s�A�����Ċ��F�̒n�ʂƂ����悤�ɁA�F�̍��قɂ���Đ����I�ȑя�̐F�ʂ����o����āA�����ɍ̉Ԃ̌s�̏c�ɐL�т�֊s�����Δ䂳��A�������Ɛ��������d�Ȃ荇�����Ƃʼn�ʂɐ▭�Ȉ��芴�����܂�Ă��܂��B
�u�̉ԁv�͂P�X�U�T�N�̍�i�B�u�e�̉ԁv�͉ԕr�Ɋ�����ꂽ�ԂƂ������i�ł������A���̍�i�͈�ʂɍ炭�̉Ԃ̕��i�Ƃ����K�͂̑傫�ȍ�i�ŁA����Ɂu�e�̉ԁv�ɂ������Ȃ��قǂ̎��X���ň�Ԉ�ԁA���ꂾ���ĂȂ��s���t���ז��ɕ`�����܂�Ă��܂��B���̔��͂��������B�g�_�炩�ȑ��z�̌��������ċP���悤�ɍ炭�����̍̉Ԃ��A�u�e�̉ԁv�Ɠ��l�ɁA������������A�G������҂��t�Ɍ��߂�悤�ɑΛ����Ă���B��������ӂꂽ�t�̌��i�ł���Ȃ���A����z���������̂�����X�Ɋ���������B�h�Ɛ�������Ă��܂��B���̍�i�́A�u�e�̉ԁv�ɉ����āu�Ђ܂��v�ł݂������̗֊s���ɂ��㏸���������܂��B�����ɍ炫���ꂽ�̉Ԃ̌s�̂ЂƂЂƂɁA�c�ɐL�т�֊s�����Z��������Ă��܂��B��ʂł͉����������t��A���F���̉ԁA�ΐF�̗t��s�A�����Ċ��F�̒n�ʂƂ����悤�ɁA�F�̍��قɂ���Đ����I�ȑя�̐F�ʂ����o����āA�����ɍ̉Ԃ̌s�̏c�ɐL�т�֊s�����Δ䂳��A�������Ɛ��������d�Ȃ荇�����Ƃʼn�ʂɐ▭�Ȉ��芴�����܂�Ă��܂��B
 �u���v�͂P�X�T�V�N�̍�i�ł��B�ݕӂɗ����ė��������������k���߂Ă���ƁA��������̐����~�܂�A���ɂ����͂̊ނ������o���悤�Ɍ������o����\�������Ɛ�������Ă��܂��B���ꂾ����ł��傤���A��ʂł̐��̗���͂ǂ������@�I�ŁA�������ĐԒ�������݂̊�̕������߂����������o�������Ɍ����Ă��܂��B
�u���v�͂P�X�T�V�N�̍�i�ł��B�ݕӂɗ����ė��������������k���߂Ă���ƁA��������̐����~�܂�A���ɂ����͂̊ނ������o���悤�Ɍ������o����\�������Ɛ�������Ă��܂��B���ꂾ����ł��傤���A��ʂł̐��̗���͂ǂ������@�I�ŁA�������ĐԒ�������݂̊�̕������߂����������o�������Ɍ����Ă��܂��B
���ƈŁ@���z�ƌ��A�X�C
�g�u���ł͂Ȃ��ł�`�����������B�ł�`�����߂Ɍ���`�����B���͈ł�`�����߂ɊJ�������ł��v�Ɩ�\�Y�͏q�ׂ�B���͈ł��ۗ������邽�߂̃A�N�Z���g�ƍl�����邪�A�����P���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��Ǝv����B�łɐ����ꂽ�������炾�B�����ɖ�\�Y�̉F���ς������Ă���B�����łɐ����ꂽ�����Ƃ���A�ł͌��ɕ�܂�Ă��邱�ƂɂȂ�B���ƈł͓���q�̍\�����Ȃ��Ă���B���̌��Ƃ͉����낤���B�ЂƂ����邱�Ƃ͈ňȑO�Ɍ����������Ƃ������Ƃ��B�ՏƂ�����̒��Ɉł������Ă���B�F����Ԃ��łł���Ƃ���Ȃ���̉ʂĂɂ͌��̐��E������̂ł͂Ȃ����Ƃ����v�O�ɋ����B�F���̉ʂĂ��瓞��������A���ꂪ���Ƃ��ĊϏƂ���Ă���B�F���̚��O�́A����Ύ���̂Ȃ��F���J蓂͈ȑO�̌��ł���A�łݏo�����{���ł���B����Č���҂ɖ������������������������̂�������Ȃ��B�ł͂Ȃ��ł����܂ꂽ�̂��낤���B�ł͕�����������v���ł͂Ȃ����낤���B���̂ɂ͐₦���e�����Y���B�����̂Ɋ��Y�����ɂ̉e���łł���Ƃ���Ȃ�A�łɂ���Č��͂��̂ւƕϊ������B�����͂��ׂČ��Ɖe�̔z���Ō��܂�̂ł͂Ȃ����B��\�Y�́u�Ԉ���A���ꗱ��l�ԂƓ����Ɍ��鎖�c�v�Əq�ׂ�B�ނ͉Ԉ�A������ɂ��_�����o���Ă���B���݂̂Ȃ��ׂĂɌ����h���Ă���̂��B��\�Y�̍�i�̓J���o�X�̋��X�܂Ō����ϓ��ɓn���Ă���B����͈ł��܂��݂��Ă��邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B�����͂�ł͌`���Ȃ��ΏۂƂ��ĕ`�����B�����͒��z�I�Ȍ����h�����̂Ƃ��Ď���P���Ă��邩�̂悤�Ɍ�����B�Ώۂ͂������ɓ��̌��ɏƂ炳��Ď���ɑi�������邪�A��\�Y�̏ꍇ�A���z���ł͂Ȃ������ɏے����ꂽ�F���ɐ����ꂽ����蓞��������Ɉˋ����ĕ`���Ă���B����͓��݂�����ł��邽�ߎ���P���Ă���̂ł���B�O������Ƃ炳�ꂻ�̎p������ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A���ꎩ�̂��u�����́v�Ȃ̂��B���̍ł�����̂����z�ł���A��\�Y�ɂƂ��Ă͕`������Ȃ��Ώۂł������͂����B���������������z�����e�B�[�t�Ƃ��邱�Ǝ��́A��ƂƂ��ē��قł���B�i�]�K���u������̉������v�j�h�Ƃ����z���͂����̂����������������߂�����܂����A����ł͎��ۂɍ�i�����鎖���痣��āA���t���Ƃ�������Ă��܂��Ă��āA��̓I�ɂǂ��������Ȃ̂��H�Ɩ����ƁA�s���l�܂��Ă��܂������Ȃ̂ŁA�����A�����̑��z�⌎��X�C��`������i�́A���̂悤�Ȏ��Ԃ������Ղ��Ƃ��낪����Ǝv���܂��B
 �u�����v�Ƃ����P�X�U�R�N�̍�i�B����͓����^�C�g���̍�i�����_���`���Ă���悤�ł����A����͂��̒��̈�_�ł��B���ɖ�����������ł���Ƃ������ɃV���v���Ȃ��̂ł����A�����̌������̔g�y����悤�ɂЂ낪���Ă������܂́A�Ƃ��Ɍ��̂܂��̌��̔��f���邳�܂Ȃǂ͔��ɍׂ����A���ꂱ�����̗��q���ꗱ���`���悤�ɕ`���Ă��܂��B�����炭���̑��z��`���Ă������������āA�������X�ɂЂ낪��A����ƂƂ��ɏ��X�Ɏ�܂��Ă����i�K�̂悤�Ȃ��͕̂`�����Ƃ��ł��Ȃ��ł��傤�B��̈Â��e����ƂȂ��Ă��邱�ƂŁA�R���g���X�g�����Ղ��Ƃ����s���̂悳���������Ǝv���܂��B����ł́A�����ƌ���傫���������āA���Ɖe�̃R���g���X�g��傫�Ȍ����x�[�X�ɂ����Ɛ��k�ɕ`�����Ƃ��ł����ł��낤�ɁA����͂������Ă��܂���B�ނ���A�e�ƂȂ����̗t��}�����Č��̌��Ɖe�̕`�ʂ��ז�����悤�Ȃ��Ƃ������čs�Ȃ��Ă��܂��B���Ԃ�A���̍�i�̍\�}�Ƃ��\���͓��{��ł悭�Ƃ��錎���ނƂ������̂ł͈�ʓI�Ƃ�������̂ł��B���ꂪ�A����̂��̍�i�ł͈�a�����o����̂ł��B
�u�����v�Ƃ����P�X�U�R�N�̍�i�B����͓����^�C�g���̍�i�����_���`���Ă���悤�ł����A����͂��̒��̈�_�ł��B���ɖ�����������ł���Ƃ������ɃV���v���Ȃ��̂ł����A�����̌������̔g�y����悤�ɂЂ낪���Ă������܂́A�Ƃ��Ɍ��̂܂��̌��̔��f���邳�܂Ȃǂ͔��ɍׂ����A���ꂱ�����̗��q���ꗱ���`���悤�ɕ`���Ă��܂��B�����炭���̑��z��`���Ă������������āA�������X�ɂЂ낪��A����ƂƂ��ɏ��X�Ɏ�܂��Ă����i�K�̂悤�Ȃ��͕̂`�����Ƃ��ł��Ȃ��ł��傤�B��̈Â��e����ƂȂ��Ă��邱�ƂŁA�R���g���X�g�����Ղ��Ƃ����s���̂悳���������Ǝv���܂��B����ł́A�����ƌ���傫���������āA���Ɖe�̃R���g���X�g��傫�Ȍ����x�[�X�ɂ����Ɛ��k�ɕ`�����Ƃ��ł����ł��낤�ɁA����͂������Ă��܂���B�ނ���A�e�ƂȂ����̗t��}�����Č��̌��Ɖe�̕`�ʂ��ז�����悤�Ȃ��Ƃ������čs�Ȃ��Ă��܂��B���Ԃ�A���̍�i�̍\�}�Ƃ��\���͓��{��ł悭�Ƃ��錎���ނƂ������̂ł͈�ʓI�Ƃ�������̂ł��B���ꂪ�A����̂��̍�i�ł͈�a�����o����̂ł��B
 ����ɑ����u���v�Ƃ����P�X�U�R�N�̍�i�́A���̌����������グ����i�ł��B�u�����v��肳��ɃV���v���ł��B�u�����v�������Ȃ̂ł����A���̂悤�Ȉꌩ�V���v���ŁA���{��ł���ʓI�ƂȂ��Ă���悤�ȍ\���ŁA��т��тƂ����Ɖe�Ƃ�����������Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɁA�����i�̓�����������Ă���Ǝv���܂��B����́A��������̕��i�ɃV���{���C�Y����悤�ɉ��炩�̕���Ƃ����킢���������ĕ\�����悤�Ƃ��邱�Ƃł͂Ȃ��āA�����Ɖߏ�Ȃ��́A��̈ł̐��E���L�����o�X�̂Ȃ��Ŏ��炪�n�����Ă��܂����Ƃ�����S�̂悤�Ȃ��̂ł��B
����ɑ����u���v�Ƃ����P�X�U�R�N�̍�i�́A���̌����������グ����i�ł��B�u�����v��肳��ɃV���v���ł��B�u�����v�������Ȃ̂ł����A���̂悤�Ȉꌩ�V���v���ŁA���{��ł���ʓI�ƂȂ��Ă���悤�ȍ\���ŁA��т��тƂ����Ɖe�Ƃ�����������Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɁA�����i�̓�����������Ă���Ǝv���܂��B����́A��������̕��i�ɃV���{���C�Y����悤�ɉ��炩�̕���Ƃ����킢���������ĕ\�����悤�Ƃ��邱�Ƃł͂Ȃ��āA�����Ɖߏ�Ȃ��́A��̈ł̐��E���L�����o�X�̂Ȃ��Ŏ��炪�n�����Ă��܂����Ƃ�����S�̂悤�Ȃ��̂ł��B
���ɑ��đ��z�ł��B�u���z�v�Ƃ����薼�̂P�X�V�T�N�̍�i�B���łɌ����P�X�U�P�N���u���z�v�́A���S���͊G�̋����̂悤�ɐ����āA��������l���֖����ׂ̍�������ˏ�ɕ`���d�˂Ă��܂��B���ꂪ�A���̌�����A���ӂɂނ��Č����s���n��l���ے��I�ɕ`���Ă���悤�ŁA���z�Ȃ̂ł��悤���A����͌��������I�ɑS�̂��Ƃ炵�Ă���l�ł��B�����ŁA�����͂��̍s���n������ׂ����ɂȂ��炦�āA���̈�{��{���k�ɁA�܂�ł��ꂼ�ꂪ�Ɨ����Ă��邩�̂悤�ɕ`���Ă����܂��B���̈�{��{�̐��́A���S������ӂɍs���ɏ]���Č� �͏��X�Ɏ�܂��Ă����܂��B���̕ω���F�ʂ�h�蕪���Ĉ�{�̐��Ƃ��āA���ꂼ��̐��ɕω������ĕ`���Ă��܂��B���̈�{��{�̐��́A���S������ӂɍs���ɏ]���Č��͏��X�Ɏ�܂��Ă����܂��B���̕ω���F�ʂ�h�蕪���Ĉ�{�̐��Ƃ��āA���ꂼ��̐��ɕω������ĕ`���Ă��܂��B����́A�ȑO�ɍ��������i��ɂ����ē_�`�̎�@�Ō������̂ɓ͂����_��F�ʂ�������Ȃ��悤�ɔL�_���d�˂邱�Ƃŕ`�������Ă������Ƃ��A���̌��ł͍�����Ȃ����ŕ`���Ă���A�Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B�Ƃ��ɁA���̌��̐����A��ʉ��̏��̖ɍ~�蒍���悤�ɓ͂��āA�̗t���Ă����l�q�A�̗t���Ƃ炳���l�q���ׂ��ɕ`����Ă��܂����B����ɑ��āA���̂P�X�V�T�N�́u���z�v�́A�����ł��鑾�z�̐F�ʂ̑��ʂ��̓_�ł͌�ނ��A�P�X�U�P�N�́u���z�v�ł́A�v���Y���Ō���悤�ɑ����̐F�������Ɋ܂܂�Ă����̂ɑ��āA������̍�i�ł͒��S�𔒂ɂ��āA���F�̍L����Ƃ����V���v���Ȃ��̂ɓ]�����Ă��܂��B���̑���ɁA���z�̌������̖ɓ͂������[�̂Ƃ���̕`�ʂ��A�P�X�U�P�N�̍�i�ɔ�ׂďd����u���Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂�A���z�̌����́A���z�̌��ɂ���Đ�����ł�`�����Ƃ����ƌ����Ȃ��ł��傤���B
�͏��X�Ɏ�܂��Ă����܂��B���̕ω���F�ʂ�h�蕪���Ĉ�{�̐��Ƃ��āA���ꂼ��̐��ɕω������ĕ`���Ă��܂��B���̈�{��{�̐��́A���S������ӂɍs���ɏ]���Č��͏��X�Ɏ�܂��Ă����܂��B���̕ω���F�ʂ�h�蕪���Ĉ�{�̐��Ƃ��āA���ꂼ��̐��ɕω������ĕ`���Ă��܂��B����́A�ȑO�ɍ��������i��ɂ����ē_�`�̎�@�Ō������̂ɓ͂����_��F�ʂ�������Ȃ��悤�ɔL�_���d�˂邱�Ƃŕ`�������Ă������Ƃ��A���̌��ł͍�����Ȃ����ŕ`���Ă���A�Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B�Ƃ��ɁA���̌��̐����A��ʉ��̏��̖ɍ~�蒍���悤�ɓ͂��āA�̗t���Ă����l�q�A�̗t���Ƃ炳���l�q���ׂ��ɕ`����Ă��܂����B����ɑ��āA���̂P�X�V�T�N�́u���z�v�́A�����ł��鑾�z�̐F�ʂ̑��ʂ��̓_�ł͌�ނ��A�P�X�U�P�N�́u���z�v�ł́A�v���Y���Ō���悤�ɑ����̐F�������Ɋ܂܂�Ă����̂ɑ��āA������̍�i�ł͒��S�𔒂ɂ��āA���F�̍L����Ƃ����V���v���Ȃ��̂ɓ]�����Ă��܂��B���̑���ɁA���z�̌������̖ɓ͂������[�̂Ƃ���̕`�ʂ��A�P�X�U�P�N�̍�i�ɔ�ׂďd����u���Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂�A���z�̌����́A���z�̌��ɂ���Đ�����ł�`�����Ƃ����ƌ����Ȃ��ł��傤���B
 �P�X�U�V�N���u����v�́A���z�������Ȃ��Ȃ��Č������ɂȂ�����i�B�l�X�ȐF�̓_�ɂ���č\������Ă���A�l��̒��ۉ�̂悤�ȍ�i�B�g���z�Ƃ�����ΓI�Ȍ������߂��̂��ɖڂ���āA���̎c����c���������A�����`�����h���̂Ɛ�������Ă��܂����B���ƈł�`���̂Ȃ�A�������Ɍ������v��Ȃ��͂��ł��ˁB�������ɗ����ł��B��������g�̓��ɋP�����ȂǂƂ��������Ƃ��炵�����������˂��肵�Ȃ��ŁA���z�̌������Ėڂ��Ԃ����Ԗ��ɉf�������̂�`�����ƁA�ʎ��ł��邵�Ă���Ƃ��낪�A�����炵���Ǝv���܂��B����́A���ۂ��ۂ������܂����A�����܂ł��ʎ��I�ȍ�i�Ƃ����킯�ł��B
�P�X�U�V�N���u����v�́A���z�������Ȃ��Ȃ��Č������ɂȂ�����i�B�l�X�ȐF�̓_�ɂ���č\������Ă���A�l��̒��ۉ�̂悤�ȍ�i�B�g���z�Ƃ�����ΓI�Ȍ������߂��̂��ɖڂ���āA���̎c����c���������A�����`�����h���̂Ɛ�������Ă��܂����B���ƈł�`���̂Ȃ�A�������Ɍ������v��Ȃ��͂��ł��ˁB�������ɗ����ł��B��������g�̓��ɋP�����ȂǂƂ��������Ƃ��炵�����������˂��肵�Ȃ��ŁA���z�̌������Ėڂ��Ԃ����Ԗ��ɉf�������̂�`�����ƁA�ʎ��ł��邵�Ă���Ƃ��낪�A�����炵���Ǝv���܂��B����́A���ۂ��ۂ������܂����A�����܂ł��ʎ��I�ȍ�i�Ƃ����킯�ł��B
 �u�X�C�v�Ƃ�����Q�̍�i�͍�����\�Y�Ƃ�����Ƃ̃g���[�h�}�[�N�Ƃ�������ƁA�P�O�N�O�̖ڍ�����p�قł̓W����ł́A���\�_�́u�X�C�v���ꎺ�ɏW�߂����ׂ��Ă��܂����B����͈����ł������A�����ɁA�ЂƂЂƂ̍�i���������茩��C���N����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�������A����́A�K���ɕ����ēW������Ă����̂ŁA�\���邱�ƂȂ��A��i�����邱�Ƃ��ł��܂����B���āA�X�C�Ƃ�����ނ̓��[���b�p�ł��o���b�N�̌��Ɖe�̑Δ���I�݂ɕ`������Ƃ������ǂ����グ�Ă��܂��B�Ⴆ�J�����@�b�W���̉e��������Ƃ������W�����W���E��=�g�D�[���A���邢�̓����u�����g�Ȃǂ������ł��傤�B�������A���̂悤�ȉ�Ƃ����͘X�C����i�̒��̈ꕔ�Ƃ��āA���S�͘X�C�ł͂Ȃ��ĘX�C�ɂ���ďƂ炵�o���ꂽ�l���������肷��̂ł��B����ɑ��āA�����̏ꍇ�ɂ͘X�C���̂��̂��A����������ȊO���͉̂�ʂ���r������Ă���Ƃ����_�Ń��j�[�N�ł��B����́A�����܂��~�X�q�ׂĂ����悤�ɁA���������o���b�N�G��̌��Ɖe�̃h���}�Ƃ͈Ⴄ���z�ŕ`����Ă��邩��ł��B���̂悤�ȍ����̍�i�ɑ��ẮA���鑤�ɂ͂��̂�������������ߑ����邱�ƂɂȂ肪���ł��B�Ⴆ�A�g�X�C����̉����Ƃ炵�Ă���̂��A�G�̒��ł͖�������Ă��Ȃ����䂦�ɁA��i�͏ے�����тсA���̐_��I�ŏ@���I�ȕ��͋C�Ƒ��ւ��āA����҂̐S��h���Ԃ�̂ł���B�܂���X�̐S����A��т�߂��݂ȂǗl�X�Ȋ���������o���A���₩�ȓ���_���Ă����悤�ȏ�p��������ƌ�����B�����܂ł��Ȃ��u�X�C�v�����́A����������ƈł̕\����T������������\�Y�̐^�����ł���B�i���R�S���u������\�Y�s�X�C�t�̒m��ꂴ����v�j�h�Ƃ�����ł��B�����炭�A�������g���A���̂悤�Ȃ��Ƃ����g�ŐM���Ă����̂�������܂���B���͍����Ƃ����l�����ۂǂ��������̂��ɂ́A���܂苻��������܂��A���������t�@�i�e�B�b�N�Ȑ��i�͂�������������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�e�Ղɑz�������܂��B������A����҂�����Ɉ��������邱
�u�X�C�v�Ƃ�����Q�̍�i�͍�����\�Y�Ƃ�����Ƃ̃g���[�h�}�[�N�Ƃ�������ƁA�P�O�N�O�̖ڍ�����p�قł̓W����ł́A���\�_�́u�X�C�v���ꎺ�ɏW�߂����ׂ��Ă��܂����B����͈����ł������A�����ɁA�ЂƂЂƂ̍�i���������茩��C���N����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�������A����́A�K���ɕ����ēW������Ă����̂ŁA�\���邱�ƂȂ��A��i�����邱�Ƃ��ł��܂����B���āA�X�C�Ƃ�����ނ̓��[���b�p�ł��o���b�N�̌��Ɖe�̑Δ���I�݂ɕ`������Ƃ������ǂ����グ�Ă��܂��B�Ⴆ�J�����@�b�W���̉e��������Ƃ������W�����W���E��=�g�D�[���A���邢�̓����u�����g�Ȃǂ������ł��傤�B�������A���̂悤�ȉ�Ƃ����͘X�C����i�̒��̈ꕔ�Ƃ��āA���S�͘X�C�ł͂Ȃ��ĘX�C�ɂ���ďƂ炵�o���ꂽ�l���������肷��̂ł��B����ɑ��āA�����̏ꍇ�ɂ͘X�C���̂��̂��A����������ȊO���͉̂�ʂ���r������Ă���Ƃ����_�Ń��j�[�N�ł��B����́A�����܂��~�X�q�ׂĂ����悤�ɁA���������o���b�N�G��̌��Ɖe�̃h���}�Ƃ͈Ⴄ���z�ŕ`����Ă��邩��ł��B���̂悤�ȍ����̍�i�ɑ��ẮA���鑤�ɂ͂��̂�������������ߑ����邱�ƂɂȂ肪���ł��B�Ⴆ�A�g�X�C����̉����Ƃ炵�Ă���̂��A�G�̒��ł͖�������Ă��Ȃ����䂦�ɁA��i�͏ے�����тсA���̐_��I�ŏ@���I�ȕ��͋C�Ƒ��ւ��āA����҂̐S��h���Ԃ�̂ł���B�܂���X�̐S����A��т�߂��݂ȂǗl�X�Ȋ���������o���A���₩�ȓ���_���Ă����悤�ȏ�p��������ƌ�����B�����܂ł��Ȃ��u�X�C�v�����́A����������ƈł̕\����T������������\�Y�̐^�����ł���B�i���R�S���u������\�Y�s�X�C�t�̒m��ꂴ����v�j�h�Ƃ�����ł��B�����炭�A�������g���A���̂悤�Ȃ��Ƃ����g�ŐM���Ă����̂�������܂���B���͍����Ƃ����l�����ۂǂ��������̂��ɂ́A���܂苻��������܂��A���������t�@�i�e�B�b�N�Ȑ��i�͂�������������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�e�Ղɑz�������܂��B������A����҂�����Ɉ��������邱 �Ƃɂ́A�Ƃ��ɔے肷�����͂���܂���B�������A����͉�ʂ����Ă���̂��Ƃ����A��ʂ����Ă��āA�����Ɍ����Ă��Ȃ����̂������Č��悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��ʂ̏�Ɍ����Ă���̂͘X�C�ł��B��A�́u�X�C�v�̂قƂ�ǃT���z�[���Ƃ����Q�T�~�P�U�p�T�C�Y�̏����ȉ�ʂŁA���S�Ɉ�{�̉̓����ꂽ�X�C���`����Ă��邾���Ƃ�������߂ăV���v���ȍ�i�ł��B�����ŕ`����Ă���̂́A�X�C�̉��̐��܂�������̔��ׂȕ`�����݂ł��B���̒��S�����[�Ɍ������Ă̌�����ʏ�ł͐F�ʂ̃~�N���P�ʂ̕ω��A���������̌����X�y�N�g�����͂���悤�Ɉ�l�łȂ��v�f�������ĕ`�����܂�Ă��܂��B�����āA���̉����R���Ă����C�Ɖ��̌������̋�C�ɉf���Č������͂ɓ`�d�����C�̕ω��A����͌������łȂ��A�X�C�̉��ɂ���ĔM����������C�̑Η����N����A��C�������o���̂����̓`�d�ւ̉e���ŕ\�킵�Ă���B��������ۂɌ����Ă���ȏ�ɁA�Ƃ������Ƃ͓��R��Ƃ̂��育�ƂƂ��ăt�B�N�V���i���ɑn�����Ă���B����͑����A�ʎ��ł���Δ��ׂ����ċC�����Ȃ����Ƃ��������Ŋg�債�ĉ�������悤�ɁA����ΐj���_��Ȍ֒����{���đ����Ă���Ƃ����܂��B�����ł͏Ƃ炵�o���ꂽ���̂�`���Ȃ��������䂦�ɏے�����тт�Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�Ƃ炵�Ă�����������`���Ă����Ƃ��������������Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B���̂��߂ɗ]�v�Ȃ��̂��킬���Ƃ��āA���̍�i�A�Ⴆ�u���v�Ȃ猎�ȊO�̂��͉̂�ʂ���r�����āA����Ɍ���������̂悤�ɂ��Ă��܂��A�̂Ɠ����悤�ɁA���̂Ƃ��̌��̂��߂Ɍ����ł���X�C�͕`���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ȊO�͔r�����Ă��܂��B����ɂ̓T���z�[���Ƃ��������ȉ�ʂ��s���������ł��傤�B�����āA�X�C�͔r���ł��Ȃ����̂́A�Œ���A�܂�A��^���ɋ߂��`�����ɂ��āA���Ƃ��̌�����������B����ƁA����҂͉��Ɏ������W��������Ȃ��Ȃ�܂��B���ہA���͎Ⴂ���A�o�R���D���ŁA�R�̏�Ńe���g���ĐQ�āA�R�����c���������Ƃ�����܂��B���̍ہA�e���g�ɂ͓d��Ȃǂ���܂���A��͘X�C�ɉ��Ƃ����ē���Ƃ���킯�ł��B�e���g�̖�A�X�C�̉����Ă���ƁA���R�Ɏ������z������悤�ŁA���炭���߂Ă��Ď��Ԃ��o���Ă��܂����Ƃ������ŁA�����ł��낢��Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂����ƂɗU����̂ł��B�����̘X�C�̉ɂ͂��������Ƃ��낪����܂��B�����́u�X�C�v�͐}�炸���Ȃ̂��A�Ӑ}���ĂȂ̂��A������܂��A�������������̘X�C�ɏ�������̂��p�ӂ���Ă���Ǝv���܂��B
�Ƃɂ́A�Ƃ��ɔے肷�����͂���܂���B�������A����͉�ʂ����Ă���̂��Ƃ����A��ʂ����Ă��āA�����Ɍ����Ă��Ȃ����̂������Č��悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��ʂ̏�Ɍ����Ă���̂͘X�C�ł��B��A�́u�X�C�v�̂قƂ�ǃT���z�[���Ƃ����Q�T�~�P�U�p�T�C�Y�̏����ȉ�ʂŁA���S�Ɉ�{�̉̓����ꂽ�X�C���`����Ă��邾���Ƃ�������߂ăV���v���ȍ�i�ł��B�����ŕ`����Ă���̂́A�X�C�̉��̐��܂�������̔��ׂȕ`�����݂ł��B���̒��S�����[�Ɍ������Ă̌�����ʏ�ł͐F�ʂ̃~�N���P�ʂ̕ω��A���������̌����X�y�N�g�����͂���悤�Ɉ�l�łȂ��v�f�������ĕ`�����܂�Ă��܂��B�����āA���̉����R���Ă����C�Ɖ��̌������̋�C�ɉf���Č������͂ɓ`�d�����C�̕ω��A����͌������łȂ��A�X�C�̉��ɂ���ĔM����������C�̑Η����N����A��C�������o���̂����̓`�d�ւ̉e���ŕ\�킵�Ă���B��������ۂɌ����Ă���ȏ�ɁA�Ƃ������Ƃ͓��R��Ƃ̂��育�ƂƂ��ăt�B�N�V���i���ɑn�����Ă���B����͑����A�ʎ��ł���Δ��ׂ����ċC�����Ȃ����Ƃ��������Ŋg�債�ĉ�������悤�ɁA����ΐj���_��Ȍ֒����{���đ����Ă���Ƃ����܂��B�����ł͏Ƃ炵�o���ꂽ���̂�`���Ȃ��������䂦�ɏے�����тт�Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�Ƃ炵�Ă�����������`���Ă����Ƃ��������������Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B���̂��߂ɗ]�v�Ȃ��̂��킬���Ƃ��āA���̍�i�A�Ⴆ�u���v�Ȃ猎�ȊO�̂��͉̂�ʂ���r�����āA����Ɍ���������̂悤�ɂ��Ă��܂��A�̂Ɠ����悤�ɁA���̂Ƃ��̌��̂��߂Ɍ����ł���X�C�͕`���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ȊO�͔r�����Ă��܂��B����ɂ̓T���z�[���Ƃ��������ȉ�ʂ��s���������ł��傤�B�����āA�X�C�͔r���ł��Ȃ����̂́A�Œ���A�܂�A��^���ɋ߂��`�����ɂ��āA���Ƃ��̌�����������B����ƁA����҂͉��Ɏ������W��������Ȃ��Ȃ�܂��B���ہA���͎Ⴂ���A�o�R���D���ŁA�R�̏�Ńe���g���ĐQ�āA�R�����c���������Ƃ�����܂��B���̍ہA�e���g�ɂ͓d��Ȃǂ���܂���A��͘X�C�ɉ��Ƃ����ē���Ƃ���킯�ł��B�e���g�̖�A�X�C�̉����Ă���ƁA���R�Ɏ������z������悤�ŁA���炭���߂Ă��Ď��Ԃ��o���Ă��܂����Ƃ������ŁA�����ł��낢��Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂����ƂɗU����̂ł��B�����̘X�C�̉ɂ͂��������Ƃ��낪����܂��B�����́u�X�C�v�͐}�炸���Ȃ̂��A�Ӑ}���ĂȂ̂��A������܂��A�������������̘X�C�ɏ�������̂��p�ӂ���Ă���Ǝv���܂��B
�G�s���[�O
�v�����[�O�͍����Ƃ�����Ƃ͂���������i��`���Ƃ����T�v�̏Љ�ł������A�G�s���[�O�͉��ł��傤���B�{�҂ŏЉ����Ȃ���������Ђ낢�̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B���������A����܂ŐÕ���̓W���́A���܂�Ȃ������悤�Ɏv���܂��B
 �@�u�S���ƃ��@�C�I�����v�Ƃ����P�X�Q�O�N���̍�i�B�ꌩ�A�����������F���̐Õ���̂悤�ł�����܂����A��ȍ�i�ł��B�S���̐؉ԁA���@�C�I�����A�|�̂��ꂼ�ꂪ�c��ł��āA���ꂼ�ꂪ�Ⴄ��Ԃɕ�����ł���悤�Ɍ����܂��B�Ⴆ���@�C�I�����̎�O�����́A�{�̂̒�̉��t�̍ۂɌ��ɓ����镔�����˂��o���悤�ȋȐ���`���Ă��܂��B���@�C�I�����͉��̃l�b�N�̕����ɍs���ƁA���傤�ǕS���̉Ԃ�����Ƃ���œ�܂�ɂȂ����悤�ɋ��Ȃ��Ă��܂��B�����č����l�b�N���s���R�ɒZ���A�e�[���s�[�X�̍������������������܂��B����|������ƁA���i�сj�̕����̓s���ƒ����Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ɁA���˂��˂Ƌ��Ȃ��Ă��܂��B������Ƃ����āA�_�����Ƃ��Ē����Ă��Ȃ���Ԃł��Ȃ��B������A�{�����肦�Ȃ��`�ɂȂ��Ă��܂��B�����āA�S���̉Ԃ́A�����Č����܂ł��Ȃ��A�s���s���R�Ȃقǂ��˂��˂Ƌ��Ȃ��Ă��܂��B�����āA����ɁA�S���ƃ��@�C�I�����̈ʒu�W������ƁA�S���̓��@�C�I�����̏�ɏ���Ă��܂���B���҂̐ڐG�������Ȃ��̂ł��B�����A�S���̉Ԃ����@�C�I�����̏�ɏ���Ă���A���̐ڐG�����͕S���̏d�����������ăx�^�b�ƕό`����͂��ł����A���ꂪ����܂���B�܂�A�S���̉Ԃ͒��ɕ����Ă���̂ł��B�����̂��Ƃ���A���́u�S���ƃ��@�C�I���v�́A�u���ƒ��q�v��u�����v�Ƃ�������i�Ɠ����悤�ɁA�����ɂ�����̂��A���̂܂܂Ɍ��āA�`������i�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�Ƃ͂����Ă��������z����̌��i��`�����̂ł͂Ȃ��A���ۂɁA�ڑO�Ƀ��@�C�I�����ƕS���̉Ԃ�u���āA��������ĕ`���Ă͂����̂��Ǝv���܂��B�g�ꌩ�ʎ��I�ɕ`���ꂽ�Õ���̂悤�Ɍ����āA���͊G���̗v���ɏ]���Đ����ɈӐ}�I�Șc�݂��^����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��킩��B�ΏۂƉ�ʁA��̕\�ʂ����X�ɒǂ���\�Y�́A�`�����Ώۂƕ`�����G����O���瓝���I�ɂ͒��߂Ȃ��B��ԂƂ��̂Ȃ��ɒu���ꂽ�������A�����ƌv��ɏ]���G��ɕ\������̂ł͂Ȃ��A���̕��@�͔����I�ŁA�G��̕\�ʂ̐����ɂ�Ă����Ɏ������V���ɐ��������B���z���̂悤�ɐv�}�ɏ]���Ē������\�ߗ\�肳�ꂽ�ʒu���������̂ł͂Ȃ��A�זE���ׂ̍זE�Ƃ̊W���Ŏ��X�ɐ��������悤�ɁA�������܂��A�����Đ�������֍s����B���̃��[���́A�G���̃O���t�B�J���ȊW���ƈ�̖̂�\�Y�̎��o���G�o����Z�������u�v�l�v�ɂ��B�����ɖ�\�Y�̊G��̕��@�̒[��������B��\�Y�́u�ʎ��v�͘X�C�ɂ��Ă����i�ɂ��Ă��A�D��āu��ϓI�v�Łu���ۓI�v�Ȃ̂��B�i�R�c�֗Y�u�s�S���ƃ��@�C�I�����t�܂��͎֍s���钼���v�j�h�Ƃ����w�E�́A�������낤�Ǝv���܂��B
�@�u�S���ƃ��@�C�I�����v�Ƃ����P�X�Q�O�N���̍�i�B�ꌩ�A�����������F���̐Õ���̂悤�ł�����܂����A��ȍ�i�ł��B�S���̐؉ԁA���@�C�I�����A�|�̂��ꂼ�ꂪ�c��ł��āA���ꂼ�ꂪ�Ⴄ��Ԃɕ�����ł���悤�Ɍ����܂��B�Ⴆ���@�C�I�����̎�O�����́A�{�̂̒�̉��t�̍ۂɌ��ɓ����镔�����˂��o���悤�ȋȐ���`���Ă��܂��B���@�C�I�����͉��̃l�b�N�̕����ɍs���ƁA���傤�ǕS���̉Ԃ�����Ƃ���œ�܂�ɂȂ����悤�ɋ��Ȃ��Ă��܂��B�����č����l�b�N���s���R�ɒZ���A�e�[���s�[�X�̍������������������܂��B����|������ƁA���i�сj�̕����̓s���ƒ����Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ɁA���˂��˂Ƌ��Ȃ��Ă��܂��B������Ƃ����āA�_�����Ƃ��Ē����Ă��Ȃ���Ԃł��Ȃ��B������A�{�����肦�Ȃ��`�ɂȂ��Ă��܂��B�����āA�S���̉Ԃ́A�����Č����܂ł��Ȃ��A�s���s���R�Ȃقǂ��˂��˂Ƌ��Ȃ��Ă��܂��B�����āA����ɁA�S���ƃ��@�C�I�����̈ʒu�W������ƁA�S���̓��@�C�I�����̏�ɏ���Ă��܂���B���҂̐ڐG�������Ȃ��̂ł��B�����A�S���̉Ԃ����@�C�I�����̏�ɏ���Ă���A���̐ڐG�����͕S���̏d�����������ăx�^�b�ƕό`����͂��ł����A���ꂪ����܂���B�܂�A�S���̉Ԃ͒��ɕ����Ă���̂ł��B�����̂��Ƃ���A���́u�S���ƃ��@�C�I���v�́A�u���ƒ��q�v��u�����v�Ƃ�������i�Ɠ����悤�ɁA�����ɂ�����̂��A���̂܂܂Ɍ��āA�`������i�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�Ƃ͂����Ă��������z����̌��i��`�����̂ł͂Ȃ��A���ۂɁA�ڑO�Ƀ��@�C�I�����ƕS���̉Ԃ�u���āA��������ĕ`���Ă͂����̂��Ǝv���܂��B�g�ꌩ�ʎ��I�ɕ`���ꂽ�Õ���̂悤�Ɍ����āA���͊G���̗v���ɏ]���Đ����ɈӐ}�I�Șc�݂��^����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��킩��B�ΏۂƉ�ʁA��̕\�ʂ����X�ɒǂ���\�Y�́A�`�����Ώۂƕ`�����G����O���瓝���I�ɂ͒��߂Ȃ��B��ԂƂ��̂Ȃ��ɒu���ꂽ�������A�����ƌv��ɏ]���G��ɕ\������̂ł͂Ȃ��A���̕��@�͔����I�ŁA�G��̕\�ʂ̐����ɂ�Ă����Ɏ������V���ɐ��������B���z���̂悤�ɐv�}�ɏ]���Ē������\�ߗ\�肳�ꂽ�ʒu���������̂ł͂Ȃ��A�זE���ׂ̍זE�Ƃ̊W���Ŏ��X�ɐ��������悤�ɁA�������܂��A�����Đ�������֍s����B���̃��[���́A�G���̃O���t�B�J���ȊW���ƈ�̖̂�\�Y�̎��o���G�o����Z�������u�v�l�v�ɂ��B�����ɖ�\�Y�̊G��̕��@�̒[��������B��\�Y�́u�ʎ��v�͘X�C�ɂ��Ă����i�ɂ��Ă��A�D��āu��ϓI�v�Łu���ۓI�v�Ȃ̂��B�i�R�c�֗Y�u�s�S���ƃ��@�C�I�����t�܂��͎֍s���钼���v�j�h�Ƃ����w�E�́A�������낤�Ǝv���܂��B
 �u���Ƃ������v�Ƃ����P�X�U�P�N�̍�i�ł��B�g�݂��݂������A���߂����������铍�ƃX�������A��ʂ̒��ł������̂u�����\�����Ȃ���z�u����Ă���B�{����͂��߁A���̂̔z�u�▾�Â������Ɍv�悳��Ă����\�Y�̐Õ���́A���l�܂�قǂْ̋����Ɉ��Ă���B���ɂ͎v�킸�ӂ�Ă݂����Ȃ�悤�Ȃ��炩�Ȏ������^�����A�\�ʂɐ������т܂ł������ɕ`����Ă���B����X�����͍d���A���̂���l�q�����������ƂƂ炦���Ă���B���G�Ȗ͗l��������̕z��M�ȂǁA������ʂɖ�\�Y�̉�͂������Ă���B�w�i�ɈӖ����肰�ȂԂ牺�������ΐF�̋ʂ��ڂ������B�h�Ɛ�������Ă��܂������A�ǂ�w�i�ɂ����e�[�u���̏�ɉʕ����z�u����A���̉ʕ���z���ז��ɋϓ��ɕ\������Ă���B�����́u���߁v�ɂ�����悤�ȕՂ������������ɒ����A���ꂼ�����ׂȂƂ���ɂ��a���ɂ����\�����Ă���B���������悤�Ȃ��Ƃ�������Ǝv���܂����A��i�����Ă���ƁA����͂���ŁA�����̓���X���������Ă���ƕ�����̂ł����A��i�Ƃ��Ă݂�ƁA�ǂ����`�O�n�O�Ȉ�ۂ��܂��B�������A���A���Ȋ��������Ȃ��ŁA��ʂɕ`���ꂽ����X�����ɑ��݊����Ȃ��̂ł��B����́A�t���E�R���s���[�^�E�O���t�B�b�N�X�̐��k�ȉ�ʂ��݂āA���m�ɕ`�ʂ���Ă���ɂ��ւ�炸���ʂƂ͑S���������ʂɂȂ��Ă��ă��A���Ȋ��������ĂȂ��������ƂɎ��Ă��܂��B�Ⴆ�A��ʎ�O�����̂Q�̓��ƂS�̃X�����͂��ꂼ��ׂ������J�ɕ`����Ă��܂��B�������A�e�[�u���̏�ɏ���č݂�悤�ɂ͌����܂���B�܂��A�^�������č����̓��Ƃ��̉E��O�̗ΐF�̃X�����͐ڐG���Ă���̂��A�ڐG�����ɗ���Ēu����Ă���̂�������܂���B�܂�A�e�[�u���Ƃ��̏�̂U�̉ʕ��̓o���o���ł��ꂼ��̊W���`�ʂ���Ă��Ȃ��̂ł��B�ǂ��������Ƃ��ƌ����ƁA���ׂȂ��ƂȂ̂�������܂��A�_�炩������̕z�̏�ɓ����u����Ă���A���̂Ƃ��낪�����ɉ���ᰂ�������肷����̂ł��B�܂��A�ی`�̉ʕ����]���炸�ɁA��O�̗ΐF�̃X�����Ȃǂ͈���̂����͂��̉��̃w�^�Ŏx����悤�ɒu���ꂸ�ɉ������ɒu����Ă��܂��B�����ł���A�]�����Ă��܂�Ȃ��悤�Ɍ��̓��Ɋ�肩����悤�ɂȂ��Ă���͂��ł��B���̂Ƃ��ɁA�_�炩�����́A�X�����̏d����a���邱�ƂɂȂ�̂ŁA�����ȕω����N����͂��ł��B���ꂾ���łȂ��A����ɂ���ĉe���ω�����͂��ł��B�������A��ʂ����Ă���ƁA�z�A���A�X�����͓Ɨ����������Ȃقǐ��k�ȕ`�ʂŕ`����Ă��܂����A���ꂪ�ʁX�ɉ�ʂ̔z�u���ꂽ�ꏊ�ɂ͂ߍ��܂�Ă���悤�Ȃ̂ł��B�����悤�ɉ�ʒ�����̎M�̂R�̓��́A�M�ɍڂ��Ă���悤�Ɍ������A�����Œ��ɕ����Ă���悤�Ȃ̂ł��B����炪�A��ʂ�S�̂Ƃ��Ă݂�Ɓg���ʓI�h�Ȋ���������̂ł��B�܂�A�����̍�i�ɑ��āA�������ʓI�ƌ����Ă���̂́A���I�Ƃ��������łȂ��A��ʂ̂Ȃ��ɂ�����̂Ƃ��̂Ƃ̊W���`����Ă��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B��Ԃ̒��ɁA���̂̂��镨�̂��݂�A����͂��̋�Ԃ�Ɛ肷�邾���łȂ��A�����Ղ�����A�����ɋ�C�͑��݂ł��Ȃ���C�̗��ꂪ�ς������A���̏d�ʂ��ڐG���鑼�̕��̂ɉe����^������A�Ǝ��͂ƂȂ�炩�̊W���\�z���Ă���͂��Ȃ̂ł��B�G��̉��ߖ@�́A���̊W�̈ꕔ��`�ʂ��悤�Ƃ����Z�@�Ƃ��������Ƃ��ł���Ǝv���܂��B���̊W�̂��ׂĂł͂Ȃ��ɂ��Ă��A������x�ȏ�\�킷���Ƃ��ł��Ă���̂��A�l�͗��̓I�ƌ��邱�Ƃ�����ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���s���Ƃ����̂́A���̎�߂Ȋ������ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�����̍�i�A���i����Õ���������ł����A�����Ă���ƁA���̂悤�ȊW���l������Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B�Ƃ��ɁA�Õ���͑ΏۂƂ���̈悪�����i���Ă���̂ŁA���̓������n�b�L�������Ă��܂��B
�u���Ƃ������v�Ƃ����P�X�U�P�N�̍�i�ł��B�g�݂��݂������A���߂����������铍�ƃX�������A��ʂ̒��ł������̂u�����\�����Ȃ���z�u����Ă���B�{����͂��߁A���̂̔z�u�▾�Â������Ɍv�悳��Ă����\�Y�̐Õ���́A���l�܂�قǂْ̋����Ɉ��Ă���B���ɂ͎v�킸�ӂ�Ă݂����Ȃ�悤�Ȃ��炩�Ȏ������^�����A�\�ʂɐ������т܂ł������ɕ`����Ă���B����X�����͍d���A���̂���l�q�����������ƂƂ炦���Ă���B���G�Ȗ͗l��������̕z��M�ȂǁA������ʂɖ�\�Y�̉�͂������Ă���B�w�i�ɈӖ����肰�ȂԂ牺�������ΐF�̋ʂ��ڂ������B�h�Ɛ�������Ă��܂������A�ǂ�w�i�ɂ����e�[�u���̏�ɉʕ����z�u����A���̉ʕ���z���ז��ɋϓ��ɕ\������Ă���B�����́u���߁v�ɂ�����悤�ȕՂ������������ɒ����A���ꂼ�����ׂȂƂ���ɂ��a���ɂ����\�����Ă���B���������悤�Ȃ��Ƃ�������Ǝv���܂����A��i�����Ă���ƁA����͂���ŁA�����̓���X���������Ă���ƕ�����̂ł����A��i�Ƃ��Ă݂�ƁA�ǂ����`�O�n�O�Ȉ�ۂ��܂��B�������A���A���Ȋ��������Ȃ��ŁA��ʂɕ`���ꂽ����X�����ɑ��݊����Ȃ��̂ł��B����́A�t���E�R���s���[�^�E�O���t�B�b�N�X�̐��k�ȉ�ʂ��݂āA���m�ɕ`�ʂ���Ă���ɂ��ւ�炸���ʂƂ͑S���������ʂɂȂ��Ă��ă��A���Ȋ��������ĂȂ��������ƂɎ��Ă��܂��B�Ⴆ�A��ʎ�O�����̂Q�̓��ƂS�̃X�����͂��ꂼ��ׂ������J�ɕ`����Ă��܂��B�������A�e�[�u���̏�ɏ���č݂�悤�ɂ͌����܂���B�܂��A�^�������č����̓��Ƃ��̉E��O�̗ΐF�̃X�����͐ڐG���Ă���̂��A�ڐG�����ɗ���Ēu����Ă���̂�������܂���B�܂�A�e�[�u���Ƃ��̏�̂U�̉ʕ��̓o���o���ł��ꂼ��̊W���`�ʂ���Ă��Ȃ��̂ł��B�ǂ��������Ƃ��ƌ����ƁA���ׂȂ��ƂȂ̂�������܂��A�_�炩������̕z�̏�ɓ����u����Ă���A���̂Ƃ��낪�����ɉ���ᰂ�������肷����̂ł��B�܂��A�ی`�̉ʕ����]���炸�ɁA��O�̗ΐF�̃X�����Ȃǂ͈���̂����͂��̉��̃w�^�Ŏx����悤�ɒu���ꂸ�ɉ������ɒu����Ă��܂��B�����ł���A�]�����Ă��܂�Ȃ��悤�Ɍ��̓��Ɋ�肩����悤�ɂȂ��Ă���͂��ł��B���̂Ƃ��ɁA�_�炩�����́A�X�����̏d����a���邱�ƂɂȂ�̂ŁA�����ȕω����N����͂��ł��B���ꂾ���łȂ��A����ɂ���ĉe���ω�����͂��ł��B�������A��ʂ����Ă���ƁA�z�A���A�X�����͓Ɨ����������Ȃقǐ��k�ȕ`�ʂŕ`����Ă��܂����A���ꂪ�ʁX�ɉ�ʂ̔z�u���ꂽ�ꏊ�ɂ͂ߍ��܂�Ă���悤�Ȃ̂ł��B�����悤�ɉ�ʒ�����̎M�̂R�̓��́A�M�ɍڂ��Ă���悤�Ɍ������A�����Œ��ɕ����Ă���悤�Ȃ̂ł��B����炪�A��ʂ�S�̂Ƃ��Ă݂�Ɓg���ʓI�h�Ȋ���������̂ł��B�܂�A�����̍�i�ɑ��āA�������ʓI�ƌ����Ă���̂́A���I�Ƃ��������łȂ��A��ʂ̂Ȃ��ɂ�����̂Ƃ��̂Ƃ̊W���`����Ă��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B��Ԃ̒��ɁA���̂̂��镨�̂��݂�A����͂��̋�Ԃ�Ɛ肷�邾���łȂ��A�����Ղ�����A�����ɋ�C�͑��݂ł��Ȃ���C�̗��ꂪ�ς������A���̏d�ʂ��ڐG���鑼�̕��̂ɉe����^������A�Ǝ��͂ƂȂ�炩�̊W���\�z���Ă���͂��Ȃ̂ł��B�G��̉��ߖ@�́A���̊W�̈ꕔ��`�ʂ��悤�Ƃ����Z�@�Ƃ��������Ƃ��ł���Ǝv���܂��B���̊W�̂��ׂĂł͂Ȃ��ɂ��Ă��A������x�ȏ�\�킷���Ƃ��ł��Ă���̂��A�l�͗��̓I�ƌ��邱�Ƃ�����ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���s���Ƃ����̂́A���̎�߂Ȋ������ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�����̍�i�A���i����Õ���������ł����A�����Ă���ƁA���̂悤�ȊW���l������Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B�Ƃ��ɁA�Õ���͑ΏۂƂ���̈悪�����i���Ă���̂ŁA���̓������n�b�L�������Ă��܂��B
 �u�������v�Ƃ����P�X�S�W�N�̍�i�́A�ȑf�ƌ����قǃV���v���ŁA�����z�ƂP�P�̃X���������`����Ă��܂���B�������A���ꂼ�ꂪ�ז��ɕ`�ʂ���A�����z�̃V����̂���Ȃ��A�e���`�����܂�Ă��܂��B�������A���̕z�ƂP�P�̃X�����͕����Ă���̂ł��B���̏ꍇ�A���ʂ̕z��~���āA���̏�ɃX������u���Ďߏォ�猩�Ă���̂ŁA���s���������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł����A������Ƃ����āu���Ƃ������v�̂悤�ɕ��ʓI�Ɍ����Ă��܂��̂ł��B����́A���������i��ł͐������Ăł��Ȃ��������Ƃ�Õ���ł́A���̐����Ȃ����߂Ɏ��s�������Ƃɂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������������Ԃ��������������Ă��܂����A�����̐Õ�������Ă���ƁA���i��ł͊����邱�Ƃ̏��Ȃ�������ׂ����Ă��܂��̂ł��B��ׂ����邱�Ƃ̑P�������������Ŏ�X�ɘ_�����Ă����͂���܂��A�����̐Õ���͐��k�Ń��A���ɕ`���Ă���悤�ŁA�S�̂Ƃ��Ă͂��育�Ƃ̔����炳�������Ă��܂��̂́A���̂����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����āA��������ꂸ�ɁA�����ĕ�������A�������㔼���Ől������قƂ�Ǖ`���Ȃ������̂́A���̂����ł͂Ȃ����Ƒz�����Ă��܂��܂��B�l�Ƃ����̂́A�W���̑��݂�����ł��B�ނ��o���̗��̒P�Ƃȑ��݂Ƃ��Ă͐����Ă����Ȃ����̂ŁA�K�����҂Ƃ̊W���玩��������Ă������̂ł��B�T���g���̑������݂ƑΎ����݂̊T�O�������o���܂ł��Ȃ����Ƃł��B������ɁA�����̍�i�ɂ́A�W�Ƃ����v�f�����������Ă��܂��B�����͑����I�ȕ��̂�`�����Ƃ͂ł��Ă��A�Ύ��I�Ȑl��`�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������o���������̂ł͂Ȃ����A�Ƒz������̂ł��B
�u�������v�Ƃ����P�X�S�W�N�̍�i�́A�ȑf�ƌ����قǃV���v���ŁA�����z�ƂP�P�̃X���������`����Ă��܂���B�������A���ꂼ�ꂪ�ז��ɕ`�ʂ���A�����z�̃V����̂���Ȃ��A�e���`�����܂�Ă��܂��B�������A���̕z�ƂP�P�̃X�����͕����Ă���̂ł��B���̏ꍇ�A���ʂ̕z��~���āA���̏�ɃX������u���Ďߏォ�猩�Ă���̂ŁA���s���������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł����A������Ƃ����āu���Ƃ������v�̂悤�ɕ��ʓI�Ɍ����Ă��܂��̂ł��B����́A���������i��ł͐������Ăł��Ȃ��������Ƃ�Õ���ł́A���̐����Ȃ����߂Ɏ��s�������Ƃɂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������������Ԃ��������������Ă��܂����A�����̐Õ�������Ă���ƁA���i��ł͊����邱�Ƃ̏��Ȃ�������ׂ����Ă��܂��̂ł��B��ׂ����邱�Ƃ̑P�������������Ŏ�X�ɘ_�����Ă����͂���܂��A�����̐Õ���͐��k�Ń��A���ɕ`���Ă���悤�ŁA�S�̂Ƃ��Ă͂��育�Ƃ̔����炳�������Ă��܂��̂́A���̂����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����āA��������ꂸ�ɁA�����ĕ�������A�������㔼���Ől������قƂ�Ǖ`���Ȃ������̂́A���̂����ł͂Ȃ����Ƒz�����Ă��܂��܂��B�l�Ƃ����̂́A�W���̑��݂�����ł��B�ނ��o���̗��̒P�Ƃȑ��݂Ƃ��Ă͐����Ă����Ȃ����̂ŁA�K�����҂Ƃ̊W���玩��������Ă������̂ł��B�T���g���̑������݂ƑΎ����݂̊T�O�������o���܂ł��Ȃ����Ƃł��B������ɁA�����̍�i�ɂ́A�W�Ƃ����v�f�����������Ă��܂��B�����͑����I�ȕ��̂�`�����Ƃ͂ł��Ă��A�Ύ��I�Ȑl��`�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������o���������̂ł͂Ȃ����A�Ƒz������̂ł��B
 ���āA�b����Ă��܂����̂Ō��ɖ߂��܂��傤�B�����͐Õ���ł͍�ׂ��{���Ă���Əq�ׂ܂����B����́A�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA�[�I�Ɍ����āg�����Ă���h�Ƃ������Ƃł��B�Õ���ł͒N�ł�����Ă���A���R�̂��ƂƂ��������������Ă������ł��B�������ɁA�`�����߂ɂ��傤�ǂ����z�u�Ƃ��g�ݍ��킹���l���đΏۂ���邱�Ƃ͈�ʓI�ł��B�Ⴆ���W�����W���E�������f�B�̐Õ����́A�����������p�^�[�������ʂ�������āA���ꂼ���`���āA�܂�ŐÕ���̔z�u�̎��������Ă���悤�ł����B�����̏ꍇ�́A�������f�B�̂悤�Ȃ����ъ��o�͂Ȃ��āA�������������n����Ƃ��ĂЂƂ̉F����n�낤�Ƃ��Ă���悤�Ɍ����܂��B���̍ۂɊ��D�Ȏ�i�Ƃ��ĐÕ��悪�������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����̂ł��B���ꂪ�ے��I�Ɍ����Ă���̂��A���p���������ŐG����Ă���u���߁v�Ƃ������t�ł��B���������\�̐_�ł��邩�炱���A��������̂ɕՂ������𒍂��ōז��ȕ`�ʂ��ł���Ƃ����킯�ł��B�Ƃ����̂��A�ז��ɕ`�ʂ���Ă���͍̂����Ɍ�����Ƃ���ŁA�����Ȃ�����Ǒ��݂��Ă���͂��̂Ƃ���͖�������Ă���킯�ł��B���̎����̌��E�̎��o�͍�i�����Ă�����芴�����܂���B�����ɍ����̎���̋����܂ŋc�_���Ђ낰�邱�Ƃ��ł��Ȃ�������܂���B�������A�����Ɏ����������̂́A�����������O�ꂽ���O�Ƃ����̂ł��傤���B���������ċ���ȖϔO�ƌ����Ă������ł��傤�B���ꂪ�q��łȂ��Ƃ������Ƃł��B�����̍�i�ɟ����Ă��锗�́A��ʂ�����Ă��܂������Ɋ������邻�����������̂Ȃ̂ł��B����́A���ɂ̓L���C�S�g�ōς܂����悤�ȁA�W����̉����]�`�ɐ�������Ă���悤�Ȍ��O�ł͂Ȃ��A�����Ɖ����A�{�l�ɂ�����ł��Ȃ��悤�ȁA�ǂ����悤���Ȃ��A����Ȃ��̂ɓ˂���������Ă��܂��悤�Ȃ��́A����Ȃ��̂������Ă��܂��̂ł��B���������}���`�b�N�Ȍ����ł����A�O�ɊÂ邱�ƂȂ��A�Ƃ��������A���ʂ̐l�Ƃ��Đ������Ă������Ƃ�݂点��悤�Ȉُ�Ȃ��́A����Ȃ̂�����悤�Ɏv����̂ł��B
���āA�b����Ă��܂����̂Ō��ɖ߂��܂��傤�B�����͐Õ���ł͍�ׂ��{���Ă���Əq�ׂ܂����B����́A�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA�[�I�Ɍ����āg�����Ă���h�Ƃ������Ƃł��B�Õ���ł͒N�ł�����Ă���A���R�̂��ƂƂ��������������Ă������ł��B�������ɁA�`�����߂ɂ��傤�ǂ����z�u�Ƃ��g�ݍ��킹���l���đΏۂ���邱�Ƃ͈�ʓI�ł��B�Ⴆ���W�����W���E�������f�B�̐Õ����́A�����������p�^�[�������ʂ�������āA���ꂼ���`���āA�܂�ŐÕ���̔z�u�̎��������Ă���悤�ł����B�����̏ꍇ�́A�������f�B�̂悤�Ȃ����ъ��o�͂Ȃ��āA�������������n����Ƃ��ĂЂƂ̉F����n�낤�Ƃ��Ă���悤�Ɍ����܂��B���̍ۂɊ��D�Ȏ�i�Ƃ��ĐÕ��悪�������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����̂ł��B���ꂪ�ے��I�Ɍ����Ă���̂��A���p���������ŐG����Ă���u���߁v�Ƃ������t�ł��B���������\�̐_�ł��邩�炱���A��������̂ɕՂ������𒍂��ōז��ȕ`�ʂ��ł���Ƃ����킯�ł��B�Ƃ����̂��A�ז��ɕ`�ʂ���Ă���͍̂����Ɍ�����Ƃ���ŁA�����Ȃ�����Ǒ��݂��Ă���͂��̂Ƃ���͖�������Ă���킯�ł��B���̎����̌��E�̎��o�͍�i�����Ă�����芴�����܂���B�����ɍ����̎���̋����܂ŋc�_���Ђ낰�邱�Ƃ��ł��Ȃ�������܂���B�������A�����Ɏ����������̂́A�����������O�ꂽ���O�Ƃ����̂ł��傤���B���������ċ���ȖϔO�ƌ����Ă������ł��傤�B���ꂪ�q��łȂ��Ƃ������Ƃł��B�����̍�i�ɟ����Ă��锗�́A��ʂ�����Ă��܂������Ɋ������邻�����������̂Ȃ̂ł��B����́A���ɂ̓L���C�S�g�ōς܂����悤�ȁA�W����̉����]�`�ɐ�������Ă���悤�Ȍ��O�ł͂Ȃ��A�����Ɖ����A�{�l�ɂ�����ł��Ȃ��悤�ȁA�ǂ����悤���Ȃ��A����Ȃ��̂ɓ˂���������Ă��܂��悤�Ȃ��́A����Ȃ��̂������Ă��܂��̂ł��B���������}���`�b�N�Ȍ����ł����A�O�ɊÂ邱�ƂȂ��A�Ƃ��������A���ʂ̐l�Ƃ��Đ������Ă������Ƃ�݂点��悤�Ȉُ�Ȃ��́A����Ȃ̂�����悤�Ɏv����̂ł��B
���ۂ̐Õ��悪�`����Ă����ʂ�z�����Ă݂ĉ������B�e�[�u���̏�ɂ��������u����Ă���B�������Ƃ����ĕ`���Ă���킯�ł��B���̎��A��Ƃ͂��ׂĂ����Ă���ł��傤���B�Ƃ������A�����Ă���ł��傤���B�Ⴆ�A��Ƃ����Ă��邷�����͗��̂ł��B���R�A��Ƃ������Ă��锽�Α��͌����Ă��܂���B������A���݂��Ă�����̂����悤�ƋÎ����Ă���A�����Ă��Ȃ����������邱�ƂɋC�Â��͂��ł��B�ʏ�́A���̋C�Ȃ��ɒ��߂Ă���̂ł���A�����Ă��Ȃ��Ƃ���́A�����Ă���Ƃ���Ɠ����悤�ɁA�����Ă���Ƃ���ƘA�����Ă��邾�낤�ƁA�����A�����܂ōl���邱�Ƃ������ɁA�^���������Ƃ��Ȃ��ł��傤�B�������A�����Ă���Ƃ�����Î�����悤�ɒ��Ӑ[�����Ă���A�����Ă���Ƃ��낾���ł��A�����Ƀ��j�[�������Ď���킯�ŁA�����Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����悤�ɂ���ȂǂƂ͈��Ղɍl���铙�Ƃ����Ƃ͂ł��Ȃ��͂��ł��B�����������Ă�����̂����𒉎��Ɏʂ�����Ƃł���A����ŏ\���Ȃ̂ł��傤���A�u���߁v�Ƃ������Ƃ������o������A�Õ���ʼnF�����������n����ɂȂ������̂悤�ɑn�邱�Ƃ��u�����Ă���ЂƂł���A���̌����Ă��Ȃ��Ƃ�������悤�Ƃ���A�����Č����Ă�����`�����Ƃ���B���������u��������͓̂��R�Ɏv���܂��B������A���_�ŋ����Ɏ��݂悤�Ƃ����̂��L���r�X���ł�������A�Z�U���k�̕����̎��_�������肷��̂ł����A�����͂����������Ƃɂ͌����������܂���ł����B�X�^�C���Ƃ��Ă̎ʎ����痣��邱�Ƃ����܂���ł����B�����ł́A�����͎��g�̎������Ή����Ă����̂ł͂Ȃ����A�[�I�Ɍ����A���g��_�Ɠ��ꎋ���Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����A���͂��������ϑz��}���邱�Ƃ͂ł��܂���B�����̂Ȃ��ϑz�Śo���Ă��������Č��\�ł����A�����łȂ���A���ɂ́A�����̍�i�ɂ���t�@�i�e�B�b�N�Ȃ܂ł̔��͂�������闝����������Ȃ��̂ł��B
 ���āA�u�������v�ɂ��Ă͂��������B���̂悤�Ȏ��̍����̐Õ���ɑ��錩���́A�����̕Ό�������ł��傤���A���������������炷��ƁA�u�������v�̌`�����Ă���ƁA���s���������̗L���ȐΒ��Ɏ��Ă���悤�Ɏv���Ă��܂��B�����̏�ɐ��̐��u����Ă���B�������ے����Ă���̂��A�悭������܂��A�����P�ɍ��ƐƂ������̂��̂��̂ł����Ȃ��ƌ���ƁA���̒�̉��l�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ�����ł��傤�B�����ɉ�������ƕt�����l�����Č��鎖���A�����ɗ����l�͋��������Ƃ����V�X�e���ł��B�����u�������v�ɗ������Ƃ̗ގ��������̂́A���̍�i�Ƀ��A�������������Ȃ����Ƃ��Ӑ}�I�ł͂Ȃ����ƍl��������ł��B���A���Ɍ����Ă��܂��A�Β�̂悤�ɏے��I�Ȍ������ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�����ɖϑz�i�z���͂Ƃ����Ă������ł��傤�j������悤�ɁA����𑣂����Ƃ��Ӑ}����Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B
���āA�u�������v�ɂ��Ă͂��������B���̂悤�Ȏ��̍����̐Õ���ɑ��錩���́A�����̕Ό�������ł��傤���A���������������炷��ƁA�u�������v�̌`�����Ă���ƁA���s���������̗L���ȐΒ��Ɏ��Ă���悤�Ɏv���Ă��܂��B�����̏�ɐ��̐��u����Ă���B�������ے����Ă���̂��A�悭������܂��A�����P�ɍ��ƐƂ������̂��̂��̂ł����Ȃ��ƌ���ƁA���̒�̉��l�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ�����ł��傤�B�����ɉ�������ƕt�����l�����Č��鎖���A�����ɗ����l�͋��������Ƃ����V�X�e���ł��B�����u�������v�ɗ������Ƃ̗ގ��������̂́A���̍�i�Ƀ��A�������������Ȃ����Ƃ��Ӑ}�I�ł͂Ȃ����ƍl��������ł��B���A���Ɍ����Ă��܂��A�Β�̂悤�ɏے��I�Ȍ������ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�����ɖϑz�i�z���͂Ƃ����Ă������ł��傤�j������悤�ɁA����𑣂����Ƃ��Ӑ}����Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B
����́A�Õ���Ƃ����`�������炱���A�����Ƃ�����Ƃ̓����������₷�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����̑��̍�i�A�Ⴆ�Ό������`�[�t�ɂ��Č��ƈł�`������i�ɂ��ẮA���̌��̗��q���ꗱ���_�`���邩�̂悤�ɁA���̌��̈ꗱ����ʂ̒��őn�����悤�Ƃ���悤�Ɍ�����̂ł��B����Ȃ�A���ƌ����������N���[�Y�A�b�v���ĕ`���悢�̂ɁA�����Ă������Ă��Ȃ��̂́A��̈ł��Ƃ炵�o���A�����Ɍ�����悤�Ɍ�����Ƃ������E�����X�܂ŁA���炪�n�����Ă��܂����Ƃ��Ă̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B