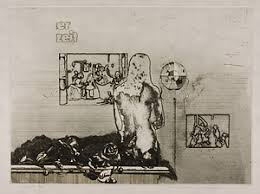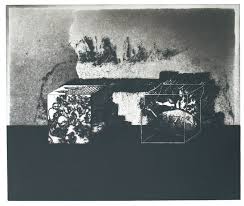|
2019年11月14日(木) O美術館
さて、いつものように、私は美術界については無知なので、中林という作家についての予備知識がないので、この人の紹介を兼ねて、展覧会の主催者あいさつを引用します。“中林忠良は東京藝術大学絵画科油画専攻在学中の1960年に集中講義で「版画」と出会いました。油絵とは全く異なる版画の世界に魅了されて以来、銅版画の主に腐蝕技法による表現手法を用いて制作研究を重ね、多くの優れた版画作品を発表。母校東京藝術大学をはじめ、日本の美術大学に於ける版画研究、教育普及や多くの後進の指導に幅広く尽力・貢献しています。人間や自然に対しての深い洞察から生まれる詩情溢れるその作品画面は、理知的で文学的な香気に彩られ、作家自身の折々の思念の象徴として、モノクロームの奥深い世界に見る者を誘います。「囚われ」シリーズ全16点の同時公開やモノタイプによるカラー作品8点、未公開最新作を含む約100点の代表作を一堂に展示。その他、腐蝕銅版画の作品成立過程や素材・道具へのこだわり、そこから派生する社会的貢献や教育スタンス、印象派有縁のフランス渡来プレス機やミュージシャンのコーネリアス・小山田圭吾氏との関わリなど人間・中林忠良の存在が持つ多面的な魅力と影響力も併せて展示紹介いたします。” A.はじめの一歩1960~1966
B.一里塚 青春の軌跡1970~1975 まずは、『白い部屋』という連作から「薄明」(右下図)という作品。室内に立つ、裸婦の後姿が写真のネガフィルムのような白黒の反転した図像。とくに、その反転した白黒のグラデーションが特に強調されるようになっています。そこでは裸婦の形態とか、身体の柔らかな質感とかいったようなことは、捨て去られるように、残ったものがグラデーションで、しかも反転させられているので、人体の立体的な存在感も捨て去られたようになっている。全体として、背中を向けた裸婦であることが。かろうじてわかるが、そうであることを表現する、美しい作品とする要素を悉く捨て去ったと言えます。画面では、裸婦の手前のテーブルとそこに乗っているバラの花も同じです。あるいは、背景の壁に絵画かけられていて、それを裸婦が見ているような位置関係にあります。それもネガの状態にあって、分かりにくいのですが、よく見ると、おそらくスペイン・バロックの
C.原点への回帰1976~1977
「師・駒井哲郎に捧ぐ」(右図)を見てみましょう。画面真ん中にあるのは墓標ということでしょうか。その周囲、つまり画面の縁にかけて枠で囲むかのように、花束が絵描かれていて、時折その枠を断ち切るように白い棒状のものが挿入されています。これまでの作品では画面の中心には、変化させられているとはいえ、何らかの事物が具象的に描かれていました。しかし、この作品ではモヤモヤした雲のような意味不明なものが描かれていて、その中心部が白い棒状のものが挿入されています。具体的な事物を指しているとは思えません。このコーナーの展示タイトルが原点への回帰とされているので、中林は、銅板の表面を腐食されたりして生まれる効果を、制作の中心に置いて、それを使って作品の画面を作っていくということになったのか。そうだとすれば、たまたま刷ってみたら、こんなものが刷られたので、それを土台に作品を作ってみた。その中心の描かれたものが、墓標と思えなくもないので、作品タイトルにして、まわりに花を描き足した。その花の枠を断ち切るように挿入される白い棒状の物体は卒塔婆に見えてきます。中心が墓標ならば、です。そんな想像をします。
「Position77-5」(右図)という作品を見てみましょう。草と花を転写したものなのでしょうが、これは、草の細かさと茎とか葉とか花というヴァリエーションがありながら、同じような形態が繰り返しているという反復と変化が同時にあるという素材を見つけたという方が、画面のイメージに合うように思います。それは、転写した銅板の表面に腐食を加えて、画面を変質させていく効果が活きてくる。それに適した題材。草の置かれた転写が茫洋として模様のようになっている白い面と上半分の黒い部分が表面を腐食させたカオスのような模様が並べられ。それを対照させて見ることができる作品です。
D.逍遥と拾い物1974~ 1975年に出版社の企画による金子光晴の詩と中林の版画作品の組み合わせによってつくられた『大腐爛頌』という詩画集は、はからずも中林作品を読み解く上での重要なカギとなっていると説明されています。そこに収められた光晴の詩に次のような一節があるといいます。 すべて、腐爛(くさ)らないものはない! 谿(たに)のかげ、森の窪地、うちしめった納屋の片すみに、去年の晴衣(モード)はすたれてゆく。 骨々とした針の杪(こずえ)を、饑(う)えた鴉(からす)が、一丈もある翼を落してわたる。 この詩を読んだ時、中林は“それまで地球全体の状況がひとつの終局に向かって動いているという気持ちをずっといだきつづけていた”と、その詩から受けるビジョンと、気持ちがピタリと一致したと言います。それ以来、この“すべて腐らないものはない”という世界観が、すべての中林の作品のテーマとして背景に流れているということです。でも、この詩画集の中林の作品が、それに見合うような腐っていくような様相を明確に表しているか。私には、そうは見えません。銅版画の腐食の手法を駆使して制作するのと、金子光晴の腐食に光を当てた詩句とで、コンセプトが共通していると思ったということだけのように私には、思えます。というのも、中林の作品には、腐食が世界観にまで徹底されているとは見えない。感覚的に、世界が腐っていくようなものは見えてこないと思います。というのも、画面の形の輪郭はしっかりしていて崩れることは決してないからです。だから“すべて腐らないものはない”というように、腐っていくということは爛れたように崩壊していくことです。そういう場面が描かれているようには、私には見えません。そういう深読みをするよりは、表層で腐食した銅板の効果を愛でている、遊戯的な要素、それがこの人の作品の特徴ではないかと思います。 E.覚醒の視線1980~1992
「転位‘88-地-Ⅱ(横浜A)」(右図)という作品です。石かコンクリートの表面に草か何かが散らばっている。下半分は泡のようでしょうか。それを接写レンズで精細に撮ったような、その表面の質感と変化を捉えているという作品のようです。石かコンクリートの硬い面から連続するように下側の泡立っているようなところに変化していく、そのつなぎが滑らかです。そこに断絶がなくて一連のように見えます。 「転位‘82-地-Ⅱ(秋)」(左下図)という作品。草地か雑木林の枯草となった地面に葉っぱが数枚落ちているのを接写したというような作品。枯草で敷き詰められたようなところは、無数の枯草が細い線が絡み合うように見えて、そこにアクセントのように枯葉が線の絡みに被さっている。目を凝らしていると、線の絡みは、かなり複雑な様相で、ときには激しくもつれるようなところもある。そういうところをクローズアップしてみせた、といえると思います。
一方で、中林自身の方向性は、画面をデザインするとかいう方法を捨てて、いわば作品について、様々な要素を捨て去って、方法を限定していったわけです。今の流行の言葉でいえば、断捨離です。そこで残ったのは、いろいろ理屈をつけて理論化されているような解説を無視すれば、どこかにある事物をもってきて、それを加工して作品としてこしらえるというものです。ほとんど。作家の手が入っていないので、持ってくる題材の強度によって作品が決まってしまう要素が大きい。そこでは、何を持ってくるかという中林のセンスが命ということになります。そういうように、私は見えます。それゆえに、私には、後半の作品はシンプルでした。それを簡素とか、よい意味にとる人は、この展覧会のチラシにあるような単純ゆえに奥深いと感じ事ができるのだろうと思います。それは、見る人の好みの問題だと思うのですが、私の好みでは退屈と感じました。そして、作品のタイトルがシンプルなんだけれど深読みを誘うようなところがあったり、作品のサイズが大きくなったりして、これはごまかしているのでは、と勘繰ったりしました。繰り返しますが、これは私の個人的な感じ方による感想です。それで、この後の展示は横目でサラッと流してしまいました。 |