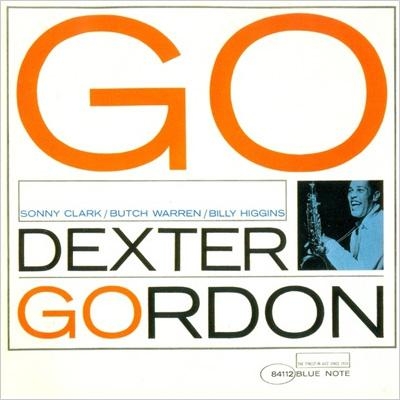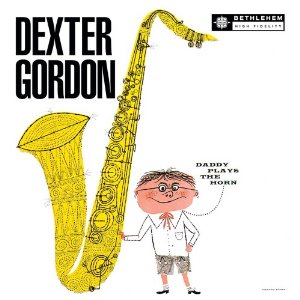|
そして、第二の面は、演奏の仕方、もっと絞ればアドリブ、すなわち原曲のメロディをどう破壊し再構築して独自の演奏内容を繰り広げるか、というところで、目立った特徴はレイド・バックすなわち、リズムに対する極端な後ノリと言われる。これ以上遅れるともたついてしまうという寸前のタイミングで出てくる彼の音は、聞き手をリラックスさせまた、一つ一つの音に重みとインパクトを与える効果をもたらす。 第一面での伸びやかで豊かに響き渡る音が、第二の面での"ため"を作ったうえで心地よいアドリブのメロディを奏でるからこそ、聴き手を飽きさせないのだと思う。したがって、デクスターのサックスが奏でる音を追い続けながら聴くと、わくわくして楽しい時間があっという間に過ぎていく。 そしてさらに、デクスターのプレイを引き立てている特徴的なこととして、ジャズのスタンダードのみならず、クラシックや流行のポップスまで、確信犯的な引用をプレイの随所で挿入することだ。それを絶妙なタイミングで挿入することによって自在に緩急を使い分け、聞き手にグルーブ感とリラクゼイションを与える。この点が彼のファンにとってはたまらない魅力ではないかと思う。
バイオグラフィー
デクスター・ゴードンは、3度のカムバック等のハリウッド映画にもなりそうな、色鮮やかで波乱にとんだ人生を送った。ビ・バップの時代に現れた最高のテナー・サックス奏者で、特徴的な独自のサウンドの持ち主。ゴードンは時には諄くて他の曲からの引用が過ぎることもあったが、スケールの大きな優れた演奏を創造し、ジャムセッションでは誰とでも火花の散るような共演をすることができた。彼の最初の重要なギグは1940年〜43年のライオネル・ハンプトンとのものだったが、サックスにはイリノイ・ジャケがいたためにゴードンはソロをとることができなかった。1943年にナット・キンク・コールのレコーディング・セッションで、彼は初めて伸び伸びと自由にプレイすることができた。リー・ヤング、フレッチャー・ヘンダーソン楽団、ルイ・アームストロングのビック・バンドとの短期間のプレイをこなし、1944年12月にニュー・ヨークに移り、ビリー・エクスタイン楽団の一員となった。エクスタインの「Blowin' the Blues Away」のレコーディングでジーン・アモンズと契約をした。ゴードンは1946年、ロサンゼルスに戻る前にサボイ・レーベルのために、リーダーとしてディジー・ガレスピーと共にレコーディングをした。彼はシーンのメインストリームの中心にいた。数多くの伝説的なテナー奏者とのバトルはワーデル・グレーやテディ・エドワーズとの契約に至り、チェーズやディアルのスタジオ・レコーディングは時代の雰囲気を残す助けとなった。 1952年以後、麻薬問題のために50年代を通じて、数回の短期間の囚役を含めて活動停止の状態が続いた(1955年の2枚のアルバムを録音しているが)。1960年にカムバックすると、すぐにブルー・ノートにレコーディングを行っている。人気が回復してきた1962年にヨーロッパに渡り、1972年までとどまった。ヨーロッパにいる間、彼は絶好調だったと言える。スティープルチェース・レーベルでの数多くの録音は彼のキャリアの中でも最も素晴らしいものだ。1965、69〜70、72年と不定期にアメリカに戻りレコーディングしていたが、故国ではほとんど忘れられてしまっていた。それゆえ、1976年の彼の復帰がマスコミに大きく取り上げられたのは、大きな驚きだった。クラブで彼を見るための人々の長い行列は生きた伝説となった、彼に対する突然湧きあがった大きな関心を表わしている。ゴードンはコロンビアと契約し、80年代前半までに徐々に健康を害して活動を半減させてしまうまで高い人気を保っていた。彼の3回目のカムバックは、映画「Round
Midnight」の主演に指名されたことによる。彼の演技はリアルで感動的だった。非常に充実した人生を送り亡くなる4年前にアカデミー賞にノミネートされた。彼のプレイは様々なレーベルでレコーディングされ、現在でも、その多くを聴くことができる。
|
 黒人テナー・サックス奏者。
黒人テナー・サックス奏者。