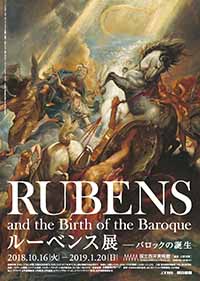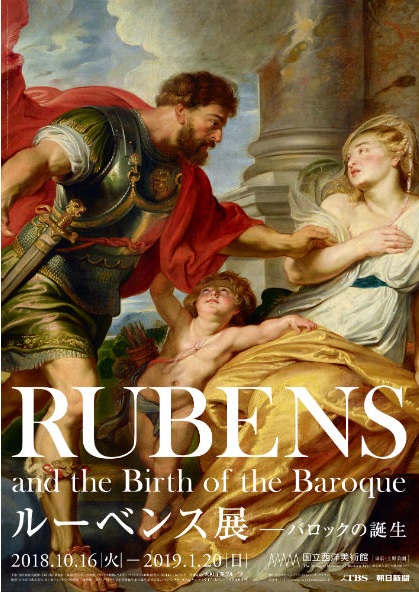�Q�O�P�W�N�P�O���Q�U���i���j�������m���p��
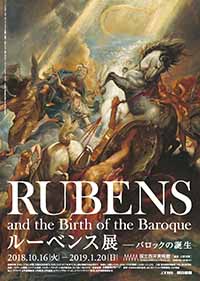 �y�[�e���E���[�x���X�Ƃ�����ƁA�o���b�N�̋����ƌ����Ă���l�ł����A�����ǂ���̂Ȃ��Ƃ����̂ł��傤���A�Ƃɂ�����i�̐��͑������A���̑�\�I�Ȃ��̂͋���ȍ�i�ʼn^������̂͑�ς��낤����A���{�ō�i���W�߂ēW������͕̂����I�ɓ���i�����łȂ��Ă��A��i���̂���{�Ɏ����Ă���̂͑�ς��낤�j���낤�ƁB�T�N�ʑO�ɁA�������̃U��~���[�W�A���Ƃ����V��̒Ⴂ�A��r�I�����Ƃ���Ń��[�x���X�W������Ă����̂����܂������A���̎��́A�ё���⏬�i�𒆐S�ɂ��āA���Ƃ͍H�[�̐��삵�����̂ŁA�{�l�̑��Ƃ����̂́A���܂�Ȃ������Ɗo���Ă��܂��B���̎��W������Ă�����i�̂������́A����A�ĉ�ł����̂�����܂������A����ł��A�ё���̂��炵���ɁA���̎��ł������̂��o���Ă��܂��B�������A���̐l�̖{�̂͑��ł͂Ȃ����Ǝv�����Ƃ��ɁA������Ȃ����o�������̂ł����B���ꂪ�A����́A�H�[����炵�����̂��r�̂��߂ɑ��̉�Ƃ̍�i������܂����A�قƂ�ǖ{�l�̍�ŁA��������ꂾ���̓_���i�S�O�_����Ƃ������Ƃł��j�A�������A���m���p�ق̒n���̑傫�ȓV��̍�����ԂɁA�@����̑�삪���ׂ��Ă����̂͑s�ψȊO�̂Ȃɂ��̂ł���܂���ł����B�܂��A������͂��܂��ĂP�O���ڂŁA���j���̗[���ŁA��r�I���܂Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂������B�ӏ܂Ɏx��̂���قǂł͂���܂��A���������ӏ҂͑����āA��i�ɂ���Ă͑O�ɐl�����肪�ł��Ă���قǂł����B���ꂩ�������i�ނɘA��āA���Ȃ荬�G����̂ł͂Ȃ����A�������A���ꂾ���̓��e�ł���܂����B
�y�[�e���E���[�x���X�Ƃ�����ƁA�o���b�N�̋����ƌ����Ă���l�ł����A�����ǂ���̂Ȃ��Ƃ����̂ł��傤���A�Ƃɂ�����i�̐��͑������A���̑�\�I�Ȃ��̂͋���ȍ�i�ʼn^������̂͑�ς��낤����A���{�ō�i���W�߂ēW������͕̂����I�ɓ���i�����łȂ��Ă��A��i���̂���{�Ɏ����Ă���̂͑�ς��낤�j���낤�ƁB�T�N�ʑO�ɁA�������̃U��~���[�W�A���Ƃ����V��̒Ⴂ�A��r�I�����Ƃ���Ń��[�x���X�W������Ă����̂����܂������A���̎��́A�ё���⏬�i�𒆐S�ɂ��āA���Ƃ͍H�[�̐��삵�����̂ŁA�{�l�̑��Ƃ����̂́A���܂�Ȃ������Ɗo���Ă��܂��B���̎��W������Ă�����i�̂������́A����A�ĉ�ł����̂�����܂������A����ł��A�ё���̂��炵���ɁA���̎��ł������̂��o���Ă��܂��B�������A���̐l�̖{�̂͑��ł͂Ȃ����Ǝv�����Ƃ��ɁA������Ȃ����o�������̂ł����B���ꂪ�A����́A�H�[����炵�����̂��r�̂��߂ɑ��̉�Ƃ̍�i������܂����A�قƂ�ǖ{�l�̍�ŁA��������ꂾ���̓_���i�S�O�_����Ƃ������Ƃł��j�A�������A���m���p�ق̒n���̑傫�ȓV��̍�����ԂɁA�@����̑�삪���ׂ��Ă����̂͑s�ψȊO�̂Ȃɂ��̂ł���܂���ł����B�܂��A������͂��܂��ĂP�O���ڂŁA���j���̗[���ŁA��r�I���܂Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂������B�ӏ܂Ɏx��̂���قǂł͂���܂��A���������ӏ҂͑����āA��i�ɂ���Ă͑O�ɐl�����肪�ł��Ă���قǂł����B���ꂩ�������i�ނɘA��āA���Ȃ荬�G����̂ł͂Ȃ����A�������A���ꂾ���̓��e�ł���܂����B
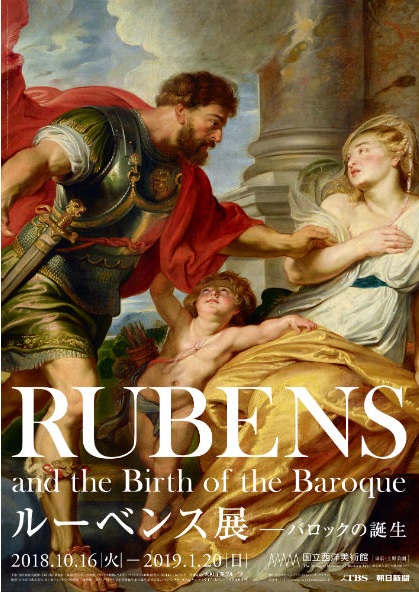 ���āA���[�x���X�Ƃ�����Ƃɂ��ẮA���p�j�̒��ł��ЂƂ���傫���P�������̂悤�Ȑl�ŁA���܂���Љ��K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂����A�������A���̐l�̑S�e�𖾂炩�ɂ���͕̂s�\�ɋ߂��̂ŁA�ǂ����Ă����鎋�_�ɂ��������āA��i��������Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B���̓_�Ŏ�Î҂̂����������p���܂��B
���āA���[�x���X�Ƃ�����Ƃɂ��ẮA���p�j�̒��ł��ЂƂ���傫���P�������̂悤�Ȑl�ŁA���܂���Љ��K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂����A�������A���̐l�̑S�e�𖾂炩�ɂ���͕̂s�\�ɋ߂��̂ŁA�ǂ����Ă����鎋�_�ɂ��������āA��i��������Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B���̓_�Ŏ�Î҂̂����������p���܂��B
�g�P�V���I�o���b�N���\�����ƁA�y�[�e���E�p�E���E���[�x���X�i�P�T�V�V�`�P�U�S�O�j�B�ނ͌��݂̃x���M�[�̒��A���g�E�F���y���ŏC�Ƃ��A��H�[���\���������܂����B�������A��ƂƂ��ēƂ藧����������̂P�U�O�O�N����O�W�N�܂ŁA�����ɃC�^���A�ʼn߂��������Ƃ́A�킪���ł͂��܂�m���Ă��܂���B���[�x���X�̓��F�l�c�B�A��}���g���@�A�����ĂƂ�킯���[�}�ł��܂��܂ȕ\�����z�����ĉ敗���m�����A�A����͂���W�������̂ł��B�������ꂽ���{�l�������ނɂƂ��āA�C�^���A�͌|�p�ɂ����闝�z�̒n�ł���Ɠ����ɁA�Ñ�Ƃ������z�̐��E�ɋ߂Â�����n�ł����B�A�����ĂQ�O�N�ȏ�o�������A���[�x���X�͎莆�ɂ����L���Ă��܂��B
�u�C�^���A�ɍs���]�݂������邱�Ƃ���߂��킯�ł͂���܂���B����ǂ��납�A���̋C�����͍��X���܂�̂ł��B�f���������܂����A�����^�������̖]�݂������Ȃ��̂ł���A���͖������Đ����邱�Ƃ��A��������Ď��ʂ��Ƃ��Ȃ��ł��傤�B�v
�{�W�́A���[�x���X������C�^���A�̉�ƂƂ��ďЉ�鎎�݂ł��B�ނ̍�i�́A���̒n�̌|�p��i�ƂƂ��ɓW������܂��B�Ñ��l�T���X�A�����Ď��̐���̍�i�ƃ��[�x���X�̍�i���r���邱�Ƃɂ���āA�ނ��C�^���A����w���ƁA�����ĂƂ�킯�A�ނ��^�������̂͂Ȃ�ł������̂����𖾂��܂��B���[�x���X�ƃC�^���A��o���b�N���p�Ƃ����A���m���p�̂ӂ��̃n�C���C�g�ɑ���V���Ȋ፷�����A���{�̊ϏO�ɗ^����ŗǂ̋@��ƂȂ�ł��傤�B�h
�T�D���[�x���X�̐��E
 �������̃��r�[�̍L�ԂŃ��[�x���X�Љ�̉f��炵�����̂�����Ă��܂������p�X���āA����������i�ցB�܂��ڂɕt���ẮA���i�Ƃ��������i�B���[�x���X�̐��E�Ƃ����R�[�i�[�ŁA�ŏ��ɂ���炵�����ł͂Ȃ��āA����ȏ����ȁA���������炵����i�ŁA������ƌ��������Ƃ����܂����B����ŁA�O�̂߂�ɂȂ�܂����B�I�݂ȓW���̉��o�A�ƌ����Ă����܂��傤�B�u�N�����E�Z���[�i�E���[�x���X�̏ё��v�i���}�j�Ƃ�����Ǝ��g�̖���`�����Ƃ�����i�ł��B�f��̃N���[�Y�E�A�b�v�̂悤�ɁA��̐��ʂɂł������ߊ���āA��Ɣ��̖т̕�����O�O�ɕ`������ŁA����ȊO�̈ߕ���w�i�͂ڂ���Ƃ����`����Ă��܂���B���ꂾ���ɁA����҂̎����͊�ɏW�܂�܂��B���̊�͂Ƃ����ƁA�Ԃ�Ȗڂ͂��������J����āA�������^�������Ɍ��߂Ă��܂��B������������ɂނ��āA�������������ȁA���ɂ�����ׂ肾�������ȕ���ł��B�c���q���Ƃ����̂́A���ʂ͂����Ƃ��Ă���ꂸ�l�Z�������������̂ł��B�����C������ɕω����āA�������܂ʼn��₩�ɏ��Ă����̂ɓˑR�����o���Ă��܂�����Ƃ�����
�������̃��r�[�̍L�ԂŃ��[�x���X�Љ�̉f��炵�����̂�����Ă��܂������p�X���āA����������i�ցB�܂��ڂɕt���ẮA���i�Ƃ��������i�B���[�x���X�̐��E�Ƃ����R�[�i�[�ŁA�ŏ��ɂ���炵�����ł͂Ȃ��āA����ȏ����ȁA���������炵����i�ŁA������ƌ��������Ƃ����܂����B����ŁA�O�̂߂�ɂȂ�܂����B�I�݂ȓW���̉��o�A�ƌ����Ă����܂��傤�B�u�N�����E�Z���[�i�E���[�x���X�̏ё��v�i���}�j�Ƃ�����Ǝ��g�̖���`�����Ƃ�����i�ł��B�f��̃N���[�Y�E�A�b�v�̂悤�ɁA��̐��ʂɂł������ߊ���āA��Ɣ��̖т̕�����O�O�ɕ`������ŁA����ȊO�̈ߕ���w�i�͂ڂ���Ƃ����`����Ă��܂���B���ꂾ���ɁA����҂̎����͊�ɏW�܂�܂��B���̊�͂Ƃ����ƁA�Ԃ�Ȗڂ͂��������J����āA�������^�������Ɍ��߂Ă��܂��B������������ɂނ��āA�������������ȁA���ɂ�����ׂ肾�������ȕ���ł��B�c���q���Ƃ����̂́A���ʂ͂����Ƃ��Ă���ꂸ�l�Z�������������̂ł��B�����C������ɕω����āA�������܂ʼn��₩�ɏ��Ă����̂ɓˑR�����o���Ă��܂�����Ƃ����� �Ƃ͓��풃�ю��ł��B���̂悤�ȁA��ɕω�����\��̈�u�̓��������̂܂ʂ�������悤�ȉ�ʂł��B�����ɓW������Ă����u�J�X�p�[��V���b�y�̏ё��v�i�E�}�j�̂悤�ɁA��u�̕\��̓��������ʂ���̂ł͂Ȃ��āA���f���̐l���𗝑z�������p��`���܂��B���ꂾ���ɐl���͓����̂Ȃ��������悤�ŁA���������������킷�\��̓�������ɂ͕\���Ă��Ȃ��A�M���V���_�b�̑��z�_�A�|���̂悤�ȁA�܂�l�ԓI�ȕ\��Ȃ��āA�_�l�̂悤�Ȓ��R�Ƃ����l�q�ŕ\�����A�Ƃ����̂��ё���A�l����ł��B���������]���̈�ʓI�Ȑl����ɔ�ׂāA���̍�i�̎q���̐e�����ȕ\��Ƃ����̂́A���z�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͍L���l�X�Ɍ������Ă̂��̂ł͂Ȃ��A����̐l���A�����炭��Ƃł��镃�e�Ɍ����ẮA�e�����A���邢�͈���\��ꂽ���̂ł��B���̂悤�ȓ���̐l�Ɍ��������̂Ƃ����̂́A����܂ł̐l����ɂȂ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�قړ�����̃X�y�C����o���b�N�̋����x���X�P�X�����z������Ȃ��A�l�Ԃ̌������A���ɕ`�����Ƃ����Ă��܂����A�x���X�P�X�̕`�����X�y�C�����Ƃ̉��q�≤���Ƃ������q�ǂ��̏ё���ɂ́A���̂悤�Ȑe���ȕ\��̈ڂ낢�̂悤�Ȃ��̂͌����܂���B��_�ȋ�ԍ\���̑��𐧍삵�Ă�������ŁA���[�x���X�Ƃ�����Ƃ́A����ȂƂ���Ŋv�V�I�ȍ�i��`���Ă����Ƃ����̂́A���̓W����ł̔����ł����B���Ƃ����C���[�W�������Ă����̂ɁA���̍�i�ɂ������┯�̖т̕`�����́A�Ȃ�ƍׂ����O�O�ɕ`�����܂�Ă��邱�Ƃ��B�����̔��̖т̈�{��{��@�ׂȐ��ŕ`����Ă��āA�������A�����o�̂ɂ��������č��X�ƕω�������Ɖe�̃O���f�[�V���������̋����̔����ȐF���̒��ŕ`���������Ă��܂��B����A���̔��̖тƓ����悤�Ɋ�̗֊s��@��O�̂��ڂ݂Ƃӂ���݂̃R���g���X�g���A�Ⴆ�A���F�̃O���f�[�V�����ׂ̍����`���킯���A�_�炩�Ȏq���̊�̔��ɂ���قǍׂ������ʂ�����̂��Ƌ����قǁi�j�̐ԁI�j�ŁA�������A���������������邽�߂ɁA�����Ƀo����
�Ƃ͓��풃�ю��ł��B���̂悤�ȁA��ɕω�����\��̈�u�̓��������̂܂ʂ�������悤�ȉ�ʂł��B�����ɓW������Ă����u�J�X�p�[��V���b�y�̏ё��v�i�E�}�j�̂悤�ɁA��u�̕\��̓��������ʂ���̂ł͂Ȃ��āA���f���̐l���𗝑z�������p��`���܂��B���ꂾ���ɐl���͓����̂Ȃ��������悤�ŁA���������������킷�\��̓�������ɂ͕\���Ă��Ȃ��A�M���V���_�b�̑��z�_�A�|���̂悤�ȁA�܂�l�ԓI�ȕ\��Ȃ��āA�_�l�̂悤�Ȓ��R�Ƃ����l�q�ŕ\�����A�Ƃ����̂��ё���A�l����ł��B���������]���̈�ʓI�Ȑl����ɔ�ׂāA���̍�i�̎q���̐e�����ȕ\��Ƃ����̂́A���z�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͍L���l�X�Ɍ������Ă̂��̂ł͂Ȃ��A����̐l���A�����炭��Ƃł��镃�e�Ɍ����ẮA�e�����A���邢�͈���\��ꂽ���̂ł��B���̂悤�ȓ���̐l�Ɍ��������̂Ƃ����̂́A����܂ł̐l����ɂȂ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�قړ�����̃X�y�C����o���b�N�̋����x���X�P�X�����z������Ȃ��A�l�Ԃ̌������A���ɕ`�����Ƃ����Ă��܂����A�x���X�P�X�̕`�����X�y�C�����Ƃ̉��q�≤���Ƃ������q�ǂ��̏ё���ɂ́A���̂悤�Ȑe���ȕ\��̈ڂ낢�̂悤�Ȃ��̂͌����܂���B��_�ȋ�ԍ\���̑��𐧍삵�Ă�������ŁA���[�x���X�Ƃ�����Ƃ́A����ȂƂ���Ŋv�V�I�ȍ�i��`���Ă����Ƃ����̂́A���̓W����ł̔����ł����B���Ƃ����C���[�W�������Ă����̂ɁA���̍�i�ɂ������┯�̖т̕`�����́A�Ȃ�ƍׂ����O�O�ɕ`�����܂�Ă��邱�Ƃ��B�����̔��̖т̈�{��{��@�ׂȐ��ŕ`����Ă��āA�������A�����o�̂ɂ��������č��X�ƕω�������Ɖe�̃O���f�[�V���������̋����̔����ȐF���̒��ŕ`���������Ă��܂��B����A���̔��̖тƓ����悤�Ɋ�̗֊s��@��O�̂��ڂ݂Ƃӂ���݂̃R���g���X�g���A�Ⴆ�A���F�̃O���f�[�V�����ׂ̍����`���킯���A�_�炩�Ȏq���̊�̔��ɂ���قǍׂ������ʂ�����̂��Ƌ����قǁi�j�̐ԁI�j�ŁA�������A���������������邽�߂ɁA�����Ƀo���� �X������Ă��āA���E�̓���@�͋ύt�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ��낪�A�p���Đl�Ԃ炵���������������������̂ƂȂ��Ă��܂��B�܂�A����قǏ����ȍ�i�ł���̂ł����A���l�T���X�ȗ��̗��z�������ύt�����l���\���Ƃ������Ƃ���A�����������X�̐l���̗��z������Ă��Ȃ��s���S�ȂƂ���ɁA���̌����\����Ƃ����Ƃ���ƁA���������l�ԂƂ����͓̂������̂Ƃ����̂ŁA���̈ڂ낢��\�킻���Ƃ����Ƃ����_�ŁA����܂łƂ͈�����悵���A�ߑ�̌l��`�̑O��ƂȂ�悤�Ȑl�ԑ��̒A������ߑ�I�ȃ��A���Y���A�Ƃ�����悤�ȍ�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
�X������Ă��āA���E�̓���@�͋ύt�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ��낪�A�p���Đl�Ԃ炵���������������������̂ƂȂ��Ă��܂��B�܂�A����قǏ����ȍ�i�ł���̂ł����A���l�T���X�ȗ��̗��z�������ύt�����l���\���Ƃ������Ƃ���A�����������X�̐l���̗��z������Ă��Ȃ��s���S�ȂƂ���ɁA���̌����\����Ƃ����Ƃ���ƁA���������l�ԂƂ����͓̂������̂Ƃ����̂ŁA���̈ڂ낢��\�킻���Ƃ����Ƃ����_�ŁA����܂łƂ͈�����悵���A�ߑ�̌l��`�̑O��ƂȂ�悤�Ȑl�ԑ��̒A������ߑ�I�ȃ��A���Y���A�Ƃ�����悤�ȍ�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
����œW������Ă����u�����l�̎q���v�i���}�j�������悤�Ɏq����`���Ă��܂��B���𗐂����܂ܐԂ��Ŗ��邠�ǂ��Ȃ��\���g�F�Ɗ��F�̍I�݂Ȏg�������́A�����̂����Ƃ�����������قǂł����A�����т̗��ꂽ�l�q�ׂ̍��ȕ`�ʂƑ��ւ��āA�悭�����ꂾ�� �O�O�ɕ`�������̂��ƁA���̂��ƂɃ��[�x���X�̃��f���̎q���ւ̕��X�Ȃ�ʈ���`����Ă���悤�ł��B���̉�����̋p�ł͊炪�h���Č����Ȃ��̂������Ă���Ă���̂́A�_�b��@���I�ȑ�ނŎq����V�g��`���Ƃ��Ƃ́A�S�R�Ⴄ�̂ŁA������Ƃ��Ƌ^�킵���Ȃ�قǂł��B
�O�O�ɕ`�������̂��ƁA���̂��ƂɃ��[�x���X�̃��f���̎q���ւ̕��X�Ȃ�ʈ���`����Ă���悤�ł��B���̉�����̋p�ł͊炪�h���Č����Ȃ��̂������Ă���Ă���̂́A�_�b��@���I�ȑ�ނŎq����V�g��`���Ƃ��Ƃ́A�S�R�Ⴄ�̂ŁA������Ƃ��Ƌ^�킵���Ȃ�قǂł��B
�u�c���C�G�X�Ɛ���Ґ����n�l�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�B�c���̐����n�l�̉E���ŗc���̃C�G�X���Ԃ��z�̏�ɍ������낵�A��l�͏]���Ȕ����q�r�łĂ��܂��B���̎q�r�̓��n�l�̏ے��ŁA�C�G�X�̏����̋]�����Î�������̂������ł��B���̗c���C�G�X�͎���̏ے��ŁA���̗c���̕\��͎���]���ɂȂ鎖�����m���Ă��邱�Ƃ��\���Ă���ƌ����܂��B���ꂾ����ł��傤���A���̓�l�̗c���̕\��́A��q�̍�i�Ɣ�ׂāA��l���ۂ��Ƃ��낪�����āA�������A�ڂ낤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��Ċm�łƂ����֊s������܂��B�܂�A�`�����܂��Ă���X�^�e�B�b�N�Ȃ��̂ł��B��̕\��ői��������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B���ۂ̂Ƃ���A���̑�ނł��̕`�����ł���A�C�G�X�Ɛ����n�l��c���ɂ��Ȃ��Ă��A��l�ŕ`���Ă��A���܂�ς��͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�q���łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ł͂Ȃ��A�����������܂��B�������A�C�G�X�̉����⑫�̓��������ł���Ƃ���Ȃǂ́A�P���ɗ��z�����Ă���Ƃ͌����Ȃ��Ƃ��낪����܂��B�c���̔��̏_�炩���̂悤�Ȃ��̂́A�I���Ǝv�킹���܂��B
�U�D�ߋ��̓`��
 ���̓W����̎�Î҂������ŏq�ׂ��Ă����g�{�W�́A���[�x���X������C�^���A�̉�ƂƂ��ďЉ�鎎�݂ł��B�h�Ƃ������Ƃ��A���ʂɂ����Ď�舵�����R�[�i�[�ł��B�����ł́A���[�x���X���C�^���A���w�ŕ������Ñネ�[�}�̌ÓT�Ƃ������邨��{�ƁA��������[�x���X���ǂ̂悤�ɏ������������r���Č�����Ƃ������Ƃ����Ă��܂��B�܂��A���l�T���X��C�^���A��o���b�N�����[�x���X���͎ʂ������̂ƁA���̌�����r�ƍ����Ă݂��悤�Ƃ����W���ł��B��i�Ƃ��āA���_�}�́A���̌�̓W���łĂ��܂����A�W��������Ƃ��ẮA���̃R�[�i�[�����C���Ƃ������ׂ����̂��Ǝv���܂��B
���̓W����̎�Î҂������ŏq�ׂ��Ă����g�{�W�́A���[�x���X������C�^���A�̉�ƂƂ��ďЉ�鎎�݂ł��B�h�Ƃ������Ƃ��A���ʂɂ����Ď�舵�����R�[�i�[�ł��B�����ł́A���[�x���X���C�^���A���w�ŕ������Ñネ�[�}�̌ÓT�Ƃ������邨��{�ƁA��������[�x���X���ǂ̂悤�ɏ������������r���Č�����Ƃ������Ƃ����Ă��܂��B�܂��A���l�T���X��C�^���A��o���b�N�����[�x���X���͎ʂ������̂ƁA���̌�����r�ƍ����Ă݂��悤�Ƃ����W���ł��B��i�Ƃ��āA���_�}�́A���̌�̓W���łĂ��܂����A�W��������Ƃ��ẮA���̃R�[�i�[�����C���Ƃ������ׂ����̂��Ǝv���܂��B
 �u�є���܂Ƃ����w�l���v�i���}�j���Ă݂����Ǝv���܂��B����́A���[�x���X���T�O���߂������n���ɖK�ꂽ�X�y�C���Ō����e�B�c�B�A�[�m���u�є�̏����v�i�E�}�j�����Ƃɐ��삵���i�͎ʂ����j��i�������ł��i�c�O�Ȃ���A���̍�i�̓W���͂���܂���ł����B�܂��A�e�B�c�B�A�[�m�ł�����A���{�Ɏ����Ă���͓̂���ł��傤�j�B�������ɁA��������ŏ�肢�ł��B�������A��̍�i�̔����ȈႢ�����[�x���X�̓������オ�点�Ă��܂��B�܂��ڂɕt���̂́A���[�x���X�̍�i�̉�ʂ̃T�C�Y�����ΓI�ɉ��L�Ƃ������Ƃł��B����ɂ���ĉ�ʑS�̂ɗ]�T�����܂�Ă��܂��B�e�B�c�B�A�[�m�̍�i�͒P�ƂŌ���Ɗ����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł����A���[�x���X�̂Ɣ�ׂ�Ə��������Ȉ�ۂ��܂��B���̂��Ƃ̓��[�x���X�Ƃ�����Ƃ̓��O������Ƃ������Ƃ���������܂���B�����āA��ʂɗ]�T���ł����Ԃ�w�l�̓��t�����悭���Ăӂ����炵�������ɂ��āA�ڂ�S�����傫�ڂɕ`���āB�傫�Ȗڂ��p�b�`���ƊJ����Ă���Ɗ�̕\����邭�Ȃ�A��ɃX�|�b�g���C�g���������悤�Ɉ�ۂ��ς��܂��B��̉摜������ׂĂ݂�ƃ��[�x���X�̍�i�����炩�ɁA������肵�Ă��āA���邢�A�Ⴂ���͂�����ƕ�����Ǝv���܂��B���ꂪ�A���[�x���X�̍�i���]�V�C�Ȃقǖ��邭�A������肵����ۂݏo���ЂƂ̗v����������Ȃ��Ǝv���܂��B�����āA���̂悤�ȃ��[�x���X�̍�i�̕w�l�͐��������Ƃ��Ď��݂̐l�ԂƂ��Ă̑��݊��A��̓I�ɒN�Ɩ��w�����ł���悤�Ȏ��݂̐l�Ԃ̂悤�Ȑ��C�����Ă��܂��B����ɑ��āA�e�B�c�B�A�[�m�̍�i�̏����͉e�������̂ł��B�Â��w�i�ɖ�����Ă���悤�Ȉ�ۂŁA���[�x���X�̕w�l�ɔ�ׂ�ƁA�͎ʂ������̂Ƃ��ꂽ���̂ł������Ă���͂��Ȃ�ł����A������͐������痧���ɂȂ��Ă��܂��B���̕��₽�����������āA���C�����܂芴�����Ȃ������������āA���ۂɑ��Â��Ă���l�ԂƂ��������́A���[�x���X�ɔ�ׂ�Ɣ����Ȃ��Ă��܂��B�����Ƃ��A���[�x���X�̉�������i�Ɣ�ׂ邩��A����������̂ł����āA�������������o���Č���A����Ȃ��Ƃ͎v������炸�A���R�Ɍ��邱�Ƃ��ł��ł��傤�B�Ⴆ�A���̕t�����̕`�������ׂČ��ĉ������B�e�B�c�B�A�[�m�̏ꍇ�̓X�D�b�Ɣ������~�̃X�b�L���Ƃ������C���ƂȂ��ĕ`����Ă���̂ɑ��āA���[�x���X�͕t�����̎n�_���������A�����Ĕ��̔��т������Ă��邱�Ƃ��L�`���Ɩэ��������邩�̂悤�ɕ`���Ă��܂��B����́A�e�B�c�B�A�[�m���l�Ԃ̊��
�u�є���܂Ƃ����w�l���v�i���}�j���Ă݂����Ǝv���܂��B����́A���[�x���X���T�O���߂������n���ɖK�ꂽ�X�y�C���Ō����e�B�c�B�A�[�m���u�є�̏����v�i�E�}�j�����Ƃɐ��삵���i�͎ʂ����j��i�������ł��i�c�O�Ȃ���A���̍�i�̓W���͂���܂���ł����B�܂��A�e�B�c�B�A�[�m�ł�����A���{�Ɏ����Ă���͓̂���ł��傤�j�B�������ɁA��������ŏ�肢�ł��B�������A��̍�i�̔����ȈႢ�����[�x���X�̓������オ�点�Ă��܂��B�܂��ڂɕt���̂́A���[�x���X�̍�i�̉�ʂ̃T�C�Y�����ΓI�ɉ��L�Ƃ������Ƃł��B����ɂ���ĉ�ʑS�̂ɗ]�T�����܂�Ă��܂��B�e�B�c�B�A�[�m�̍�i�͒P�ƂŌ���Ɗ����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł����A���[�x���X�̂Ɣ�ׂ�Ə��������Ȉ�ۂ��܂��B���̂��Ƃ̓��[�x���X�Ƃ�����Ƃ̓��O������Ƃ������Ƃ���������܂���B�����āA��ʂɗ]�T���ł����Ԃ�w�l�̓��t�����悭���Ăӂ����炵�������ɂ��āA�ڂ�S�����傫�ڂɕ`���āB�傫�Ȗڂ��p�b�`���ƊJ����Ă���Ɗ�̕\����邭�Ȃ�A��ɃX�|�b�g���C�g���������悤�Ɉ�ۂ��ς��܂��B��̉摜������ׂĂ݂�ƃ��[�x���X�̍�i�����炩�ɁA������肵�Ă��āA���邢�A�Ⴂ���͂�����ƕ�����Ǝv���܂��B���ꂪ�A���[�x���X�̍�i���]�V�C�Ȃقǖ��邭�A������肵����ۂݏo���ЂƂ̗v����������Ȃ��Ǝv���܂��B�����āA���̂悤�ȃ��[�x���X�̍�i�̕w�l�͐��������Ƃ��Ď��݂̐l�ԂƂ��Ă̑��݊��A��̓I�ɒN�Ɩ��w�����ł���悤�Ȏ��݂̐l�Ԃ̂悤�Ȑ��C�����Ă��܂��B����ɑ��āA�e�B�c�B�A�[�m�̍�i�̏����͉e�������̂ł��B�Â��w�i�ɖ�����Ă���悤�Ȉ�ۂŁA���[�x���X�̕w�l�ɔ�ׂ�ƁA�͎ʂ������̂Ƃ��ꂽ���̂ł������Ă���͂��Ȃ�ł����A������͐������痧���ɂȂ��Ă��܂��B���̕��₽�����������āA���C�����܂芴�����Ȃ������������āA���ۂɑ��Â��Ă���l�ԂƂ��������́A���[�x���X�ɔ�ׂ�Ɣ����Ȃ��Ă��܂��B�����Ƃ��A���[�x���X�̉�������i�Ɣ�ׂ邩��A����������̂ł����āA�������������o���Č���A����Ȃ��Ƃ͎v������炸�A���R�Ɍ��邱�Ƃ��ł��ł��傤�B�Ⴆ�A���̕t�����̕`�������ׂČ��ĉ������B�e�B�c�B�A�[�m�̏ꍇ�̓X�D�b�Ɣ������~�̃X�b�L���Ƃ������C���ƂȂ��ĕ`����Ă���̂ɑ��āA���[�x���X�͕t�����̎n�_���������A�����Ĕ��̔��т������Ă��邱�Ƃ��L�`���Ɩэ��������邩�̂悤�ɕ`���Ă��܂��B����́A�e�B�c�B�A�[�m���l�Ԃ̊�� �`�Ԃɖڂ��s���Ă���̂ɑ��āA���[�x���X�͎��݂̐������l�Ԃ̐��X�������A�����ɖڂ��s���Ă���Ƃ����Ⴂ�ɂ����̂ł��傤�B����́A�e�B�c�B�A�[�m���}�j�G���X���̉e�����甲���ꂸ���O�I�Ƃ����̂����z�̏������̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ă��̏�����`���Ă���悤�ɋC�����܂��B�e�B�c�B�A�[�m�̏����̕\����݂�ƒX���Ă�����݂͐l�Ԃ̂Ƃ������̓j���t��V�g�̂悤�Ȉ�ۂł��B�������Ĕ�ׂČ���ƁA���[�x���X�Ƃ�����Ƃ��C�^���A���p�̗l����Z�@�ɏK�n���Ă������A�x�[�X�̓��A���Y���̐l�ł��邱�Ƃ����炩�ł��B�������A���̍D�݂͉e�����e�B�c�B�A�[�m�`�������̕��ł��B�����烋�[�x���X�͋��c�Ƃ͂����Ă��A���������������o���Ă���l�����䂫�t������̂������Ă���̂ł��B
�`�Ԃɖڂ��s���Ă���̂ɑ��āA���[�x���X�͎��݂̐������l�Ԃ̐��X�������A�����ɖڂ��s���Ă���Ƃ����Ⴂ�ɂ����̂ł��傤�B����́A�e�B�c�B�A�[�m���}�j�G���X���̉e�����甲���ꂸ���O�I�Ƃ����̂����z�̏������̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ă��̏�����`���Ă���悤�ɋC�����܂��B�e�B�c�B�A�[�m�̏����̕\����݂�ƒX���Ă�����݂͐l�Ԃ̂Ƃ������̓j���t��V�g�̂悤�Ȉ�ۂł��B�������Ĕ�ׂČ���ƁA���[�x���X�Ƃ�����Ƃ��C�^���A���p�̗l����Z�@�ɏK�n���Ă������A�x�[�X�̓��A���Y���̐l�ł��邱�Ƃ����炩�ł��B�������A���̍D�݂͉e�����e�B�c�B�A�[�m�`�������̕��ł��B�����烋�[�x���X�͋��c�Ƃ͂����Ă��A���������������o���Ă���l�����䂫�t������̂������Ă���̂ł��B
�u�E�₵���j�̓����v�i���}�j�B�����铪���Ƃ����炵���A���f���̐l�Ԃ�M�ʂ��ė��z���i�p�^�[�����j�������č�i�f�ނƂ��Đ}�ĉ��̂悤�ȍ�Ƃ��Ă����āA���ۂɎg��ꂽ�炵�������ł��B�܂�A�H�[�œ�����Ƃ��������ɕ`�������l���̂���{�Ƃ��Ďg��ꂽ�炵���ł��B�Z�ʂ����[�x���X�ɓ͂��Ȃ���Ƃ����͑��̒��̕�����S���������Ɉ�背�x�������߂��̂ŁA���[�x���X�̕`��������{���ʂ��ė��p���邱�ƂŁA���̃��x�����N���A���Ă����B���̂悤�ɁA���l���R�s�[���Ďg���܂킷���߂̐}�ďW�̂悤�ȋ@�\���ʂ������߂ɂ́A����̐l���̓������Ƃ炦�Ă��邱�Ƃ��́A�V�l�̈�ʐ��������Ă���������p�͈͂��L�܂邵�A�ʂ��₷���B���̂悤�Ȏ��p�I�ȗv�����A���͍�i�ɓ���Ɨ��z�����ꂽ���Ր����������\���ɂȂ��Ă���A�Ȃ�ƌ����I�Ȏ����B�Ƃ͂����Ă��A���ۂɂ��̍�i���A���A����ƁA�������a�V�Ȋ��������܂����B���̗��z���Ƃ����̂́A�Ñ�̏ё������̗ތ^�\���̃p�^�[���ɓ��Ă͂߂�悤�ɂ��āA���A���ȃ��f���̕`�ʂ��V���{���b�N�Ȃ��̂ɏ��������Ƃ����B��������ƁA�Ñ�̐_�b��`���A���j�I�ȏ�ʂɓK�������̂ƂȂ�B�������A����Ȃ��Ƃ��ɂ��āA���̒j�̓���������ƁA�z�͋����A�����E�悤�Ȗڂƕ@�ȊO�͔��̖тƕE�ɕ����Ă���B�������g�ł��A�����ꂽ�A�����Ⴖ��̔��̖тƕE�ɋ����n�C���C�g������A�܂�ŋ����̂悤�Ȏ����ƃ_�C�i�b�N�Ȗ�����������̂́A�f�����M�����ƁA�F�����ɂ����̂ł��傤���A���̔��̖т̗l�����Ă��邾���Ő��ۗ�������ۂ̗ǂ��ɂ����Ƃ肵�Ă��܂��̂ł��B�������A������j�̐��ʂɌ������Ă��āA�����̔��̖т��Ƃ�f����̂ƌ㓪���̉e�̃R���g���X�g���Â���ʂŃX�|�b�g���C�g�Ă�ꂽ�悤�ɕ����яオ��̂́A�J�����@�W���̂悤�ȃh���}�`�b�N����������܂��A�܂��Ƀo���b�N�G��̌��{�̂悤�ł��B����ȑf�ޏW�̂悤�ȃX�P�b�`�ł���Ă��܂��̂ł�����B���[�x���X�{�l���A���̂悤�ȃX�s�[�f�B�[�ȕM�����ł����ƍ�i���d�グ�Ă��܂��l�q�����ƂȂ��z�����Ă��܂��܂����B
 ���[�x���X�ɂ��f�`���W������Ă��܂������A���̓����̂悤�ɑf�ނƂ��邽�߂̂��̂�A���G�̂��߂̂��́A���邢�̓C�^���A�ł̖͎ʂ̂悤�ȏK��̂悤�ȖړI�Ȃ̂��͕�����܂��A�����Ă��͍�i�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�����҂�M���I�ȃt�@���ł��Ȃ���A�ʔ����Ȃ��̂ł����A����̓W���ł́A���̃X�P�b�`�����Ώۂ̌Ñ�̒��������ׂēW������Ă��܂����B����������ׂ�ƁA���[�x���X�Ƃ����l�́A�`���̂����܂��͓̂��R�̂��Ƃł����A�S�̑���c������̂��I���A��������o����悤�Ɏ��̏�ɍČ����Ă����A������X�P�b�`�̒i�K�ł���Ă��܂��l���Ƃ����̂��悭������܂����B
���[�x���X�ɂ��f�`���W������Ă��܂������A���̓����̂悤�ɑf�ނƂ��邽�߂̂��̂�A���G�̂��߂̂��́A���邢�̓C�^���A�ł̖͎ʂ̂悤�ȏK��̂悤�ȖړI�Ȃ̂��͕�����܂��A�����Ă��͍�i�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�����҂�M���I�ȃt�@���ł��Ȃ���A�ʔ����Ȃ��̂ł����A����̓W���ł́A���̃X�P�b�`�����Ώۂ̌Ñ�̒��������ׂēW������Ă��܂����B����������ׂ�ƁA���[�x���X�Ƃ����l�́A�`���̂����܂��͓̂��R�̂��Ƃł����A�S�̑���c������̂��I���A��������o����悤�Ɏ��̏�ɍČ����Ă����A������X�P�b�`�̒i�K�ł���Ă��܂��l���Ƃ����̂��悭������܂����B
 �u�Z�l�J�̎��v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���[�x���X�̍H�[�Ő��삳�ꂽ��i�ŁA�����炭�����̓��[�x���X�{�l�̕M�������Ă���Ƃ��������ł����B�Z�l�J�͌Ñネ�[�}�̃X�g�A�N�w�ҁi�X�g�C�V�Y���̌ꌹ�ɂȂ����֗~��`�������j�Łg�\�N�h�l���̉��Ŏ��E�����v���ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�P.�W�~�P.�Qm�Ƃ����傫�ȍ�i�ł��B���̉�ʂ����ς��ɒj���̐��ʂ̑S�g�����`����Ă��đ唗�͂ł��B���j�I�ȏ�ʂł���͂��ł����A�w�i�͏ȗ����ꂽ�ÈłŁA�^�̃Z�l�J�ɏォ������~�蒍���悤�ɓ��Ă��Ă��܂��B����ɑ��āA�Z�l�J�̎�����p���́A���̏ォ��̌��Ɍ������Ă��܂��B�r����āA�o�����Ă���ɂ�������炸��ɂ̕\��͂Ȃ��A�ォ��̌��Ɉӎu�I�Ɍ������Ă���A�܂�ŁA�����炻����֍s���Ƒi���Ă��邩�̂悤�ȕ\��ł��B���̏������グ��l�q�͏}���҂��霂Ƃ����A���̒���ꂽ᷂͐���Ղ��v�킹��Ɖ������Ă��܂����B�w�i���ȗ�����Ă���̂́A�Ñネ�[�}�̏�ʂɂ��Ă��܂��ƁA�}���҂ɂȂ��炦��ے������\���Ă��Ȃ��ŁA�����̎��E�̏�ʂɂȂ��Ă��܂�����ł��傤���B���̉�ʂ����ς��ɁA�^�̃Z�l�J�����͂ނ悤�ɂS�l�̐l�����`����Ă��܂����A�����̐l�X�͌����������Ă��Ȃ����A���ɋC�t���Ă��Ȃ��B�ނ�̎����͏�Ɍ������Ă��Ȃ��ŁA�Z�l�J�Ɍ������Ă��܂��B���̂��߂��p���͉������ɂȂ��Ă��āA�Ƃ����Ɍ������Z�l�J�ƁA���̉��Ɍ����l�X�Ƃ����ΏƊW������悤�ł��B�܂�ŁA�Z�l�J�ȊO�̐l�X�͓V���牺�̌����ł����߂��Ă���Ƃ����ΏƂł��B�������A���̂S�l�̐l���́A���ꂼ��̎v�f�Ƃ����̂��A���̕`�������͂������肳��Ă��āA���̒��S�ɃZ�l�J�����āA���̃Z�l�J�́A�ނ�̌��������W���璴�R�Ƃ��āA��Ɍ������Ă���B���[�x���X�Ƃ����l�͉�ʍ\���ł̉��o�ɏG�ł��l�ł��邱�Ƃ�������܂��B�����炭�A��ʍ\����v���āA���̃f�U�C���̂��ƂɍH�[�̉�Ƃ����ɕ`�������̂ł��傤���A���̐v�}���I�݂Ȃ̂ŁA�Ⴆ�A�Z�l�J�̓����Ɛg�̂ɃM���b�v������̂ł����A���܂�ڗ����܂���B�Z�l�J�̐g�́A�Ƃ��������̂́A���[�x���X�̖L�`�ŗ͋������̂Ƃ������́A�C�^���A�G��̃X�}�[�g�Ȋ����ŁA���̓_�͖ʔ����̂ł����A��ɔ�ׂċْ����Ɍ����āA�o��ł���悤�Ȋ��������܂��B�r����Ă���A����������@���Ƃ������؉H�l�������̂��Ȃ��āA�₽��ؓ��̓ʉ�����������Ă���悤�Ȋ����ŁA�V�l�̓��̂ɂ������܂���B���N�O�̃��[�x���X�W�Ō����u�����̃L���X�g�v�i�E��}�j�̎����悤�ȍ\�}�ŕ`���ꂽ���̕\���Ɣ�ׂĂ��܂��ƁA�����Ⴄ�Ɗ����Ă��܂��̂ł��B
�u�Z�l�J�̎��v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���[�x���X�̍H�[�Ő��삳�ꂽ��i�ŁA�����炭�����̓��[�x���X�{�l�̕M�������Ă���Ƃ��������ł����B�Z�l�J�͌Ñネ�[�}�̃X�g�A�N�w�ҁi�X�g�C�V�Y���̌ꌹ�ɂȂ����֗~��`�������j�Łg�\�N�h�l���̉��Ŏ��E�����v���ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�P.�W�~�P.�Qm�Ƃ����傫�ȍ�i�ł��B���̉�ʂ����ς��ɒj���̐��ʂ̑S�g�����`����Ă��đ唗�͂ł��B���j�I�ȏ�ʂł���͂��ł����A�w�i�͏ȗ����ꂽ�ÈłŁA�^�̃Z�l�J�ɏォ������~�蒍���悤�ɓ��Ă��Ă��܂��B����ɑ��āA�Z�l�J�̎�����p���́A���̏ォ��̌��Ɍ������Ă��܂��B�r����āA�o�����Ă���ɂ�������炸��ɂ̕\��͂Ȃ��A�ォ��̌��Ɉӎu�I�Ɍ������Ă���A�܂�ŁA�����炻����֍s���Ƒi���Ă��邩�̂悤�ȕ\��ł��B���̏������グ��l�q�͏}���҂��霂Ƃ����A���̒���ꂽ᷂͐���Ղ��v�킹��Ɖ������Ă��܂����B�w�i���ȗ�����Ă���̂́A�Ñネ�[�}�̏�ʂɂ��Ă��܂��ƁA�}���҂ɂȂ��炦��ے������\���Ă��Ȃ��ŁA�����̎��E�̏�ʂɂȂ��Ă��܂�����ł��傤���B���̉�ʂ����ς��ɁA�^�̃Z�l�J�����͂ނ悤�ɂS�l�̐l�����`����Ă��܂����A�����̐l�X�͌����������Ă��Ȃ����A���ɋC�t���Ă��Ȃ��B�ނ�̎����͏�Ɍ������Ă��Ȃ��ŁA�Z�l�J�Ɍ������Ă��܂��B���̂��߂��p���͉������ɂȂ��Ă��āA�Ƃ����Ɍ������Z�l�J�ƁA���̉��Ɍ����l�X�Ƃ����ΏƊW������悤�ł��B�܂�ŁA�Z�l�J�ȊO�̐l�X�͓V���牺�̌����ł����߂��Ă���Ƃ����ΏƂł��B�������A���̂S�l�̐l���́A���ꂼ��̎v�f�Ƃ����̂��A���̕`�������͂������肳��Ă��āA���̒��S�ɃZ�l�J�����āA���̃Z�l�J�́A�ނ�̌��������W���璴�R�Ƃ��āA��Ɍ������Ă���B���[�x���X�Ƃ����l�͉�ʍ\���ł̉��o�ɏG�ł��l�ł��邱�Ƃ�������܂��B�����炭�A��ʍ\����v���āA���̃f�U�C���̂��ƂɍH�[�̉�Ƃ����ɕ`�������̂ł��傤���A���̐v�}���I�݂Ȃ̂ŁA�Ⴆ�A�Z�l�J�̓����Ɛg�̂ɃM���b�v������̂ł����A���܂�ڗ����܂���B�Z�l�J�̐g�́A�Ƃ��������̂́A���[�x���X�̖L�`�ŗ͋������̂Ƃ������́A�C�^���A�G��̃X�}�[�g�Ȋ����ŁA���̓_�͖ʔ����̂ł����A��ɔ�ׂċْ����Ɍ����āA�o��ł���悤�Ȋ��������܂��B�r����Ă���A����������@���Ƃ������؉H�l�������̂��Ȃ��āA�₽��ؓ��̓ʉ�����������Ă���悤�Ȋ����ŁA�V�l�̓��̂ɂ������܂���B���N�O�̃��[�x���X�W�Ō����u�����̃L���X�g�v�i�E��}�j�̎����悤�ȍ\�}�ŕ`���ꂽ���̕\���Ɣ�ׂĂ��܂��ƁA�����Ⴄ�Ɗ����Ă��܂��̂ł��B
�V�D�p�Y�Ƃ��Ă̐��l�������@����ƃo���b�N
 ��������̓��[�x���X�̍�i���e�[�}�ʁA��ޕʂɌ��Ă������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��������́A��i�̃I���p���[�h�ł��B
��������̓��[�x���X�̍�i���e�[�}�ʁA��ޕʂɌ��Ă������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��������́A��i�̃I���p���[�h�ł��B
�u���h�~�e�B���v�i���}�j�B�����V���c�𒅂āA�����ɖє���|���A�҂ݏグ���������̑тƃ��{���ŏ���t���������́A�E��ɏ}���҂̃A�g���r���[�g�i�����j�ł��鞡�L�̗t���������p�ŕ`����A�����������Ɍ����Ă���B���������_�炩�����̊��G�����Ď��邩�̂悤�Ȍ���������������g�̏����̕`�ʂ��B������Ă���B���̈���ŁA�ޏ��̊�͌��i�ȉ���Ƃ��ĕ\�킳��Ă���B�܂�A���̊�̕\���́A���_����J���I�ɕ\�킳�ꂽ������z�N������悤�ȈЌ������L���Ă���̂ł���A�Ñ���p�̑��`�������ӎ����Ȃ���A���g�̃��f���Ɋ�Â��Đ��삳�ꂽ��i�Ƃ������Ƃ��ł���B�����ƞ��L�̗t���A�������`������悤�ɔz����Ă���_����������\���ӎ������Ď���悤�ł��B�C�^���A���w ���̃��[�x���X�͂��̂悤�ȉ��G�ł���܂Ŋw�K�������Ƃ�l�X�Ɏ��݂Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B��̕`�������݂�ƃ^�b�`�͂��������e�ڂł���ɂ�������炸�A���L�̗t������̎w��̒��J�ȕ`������A�Ñ�̃J���I�̂悤�Ȍ��i�ȃv���t�B�[���ł���Ȃ���A��̐��̓��̒o�݂������I�Ɍ�����ȂǁA�`���I�ȍ\���ƃ��A���Ȏ����̌������͂�����ƕ\���Ă��āA���[�x���X�Ƃ�����Ƃ������̕������������Ă��āA����炪�h�R���ĂȂ��Ȃ��܂Ƃ܂炸�A��i�̒��ɑΗ��I�ȗv�f�������Ă���̂���ϋ����[���ł��B���[�x���X�̍�i������o����邠�̃G�l���M�[�̌��̂ЂƂɁA���̂悤�Ȋ������������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ə����l���������܂����B
���̃��[�x���X�͂��̂悤�ȉ��G�ł���܂Ŋw�K�������Ƃ�l�X�Ɏ��݂Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B��̕`�������݂�ƃ^�b�`�͂��������e�ڂł���ɂ�������炸�A���L�̗t������̎w��̒��J�ȕ`������A�Ñ�̃J���I�̂悤�Ȍ��i�ȃv���t�B�[���ł���Ȃ���A��̐��̓��̒o�݂������I�Ɍ�����ȂǁA�`���I�ȍ\���ƃ��A���Ȏ����̌������͂�����ƕ\���Ă��āA���[�x���X�Ƃ�����Ƃ������̕������������Ă��āA����炪�h�R���ĂȂ��Ȃ��܂Ƃ܂炸�A��i�̒��ɑΗ��I�ȗv�f�������Ă���̂���ϋ����[���ł��B���[�x���X�̍�i������o����邠�̃G�l���M�[�̌��̂ЂƂɁA���̂悤�Ȋ������������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ə����l���������܂����B
�u�V�g�Ɏ��Â���鐹�Z�o�X�e�B�A�k�X�v�i�����}�j�Ƃ�����i�ł��B���Z�o�X�e�B�A�k�X�̓��[�}�̌R�l�ŁA�L���X�g���k�ƂȂ������Ƃ��烍�[�}�c��ɗ��؎҂������������A�Y�ɔ���t�����ăn���l�Y�~�̂悤�ɂȂ�܂Ŗ���˂������Ă��܂��܂��B�������A��ՓI�ɔނ͏�����A���C���[�l�ɂ���ĉ������܂��B����ŁA�|��Ŏ˂��ď}�������������҂̑��Ƃ��Ă悭�`����A�u�a�ɑ����쐹�l�Ƃ���Ă���Ƃ������Ƃł��B���̍�i�ł́A������Ă���̂����C���[�l�ł͂Ȃ��ēV�g�ł��B����œW������Ă����V�����E���[�G���u���C���l�Ɏ��Â���鐹�Z�o�X�e�B�A�k�X�v�i�E�}�j�̒j���̓��̂Ɣ�ׂ�ƁA���[�x���X�̕`�����̂��S�c�S�c���Ă��Đ��X�����̂�������܂��B���[�G�̕`�����̂͂��ׂ��ׂ��Ă��Ē����̂悤�ł��B����͂���ŗ��z�����ꂽ�l���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B���ꂾ���ɁA���Z�o�X�e�B�A�k�X�����Ɏ蓖�Ă����Ă��鐹�C���l�Ƃ����Đl�����w��̑�������m�ɕ`����Ă��܂����A����͂���Ӗ��A�ʐF���ꂽ�����̂悤�ɁA���m�Ȍ`������B�܂��A��ʑS�̂��A�� ���̏����Ȃ܂Ƃ܂�̂悤�ɂ����܂��Ă��܂��Ă��āA��Ԃ����܂芴�������Ȃ��A����Ȋ��������܂��B�Ƃ͂����A���̂悤�ɖ��m�ɂ����Ɣj�]�Ȃ��`�����Ă����Ƃ̋Z�ʂ͂����ւ�Ȃ��̂ł���Ǝv���܂����B���[�x���X�̏ꍇ�́A�����r���܂œ����悤�ɒNj����Ă���Ƃ͎v���܂��B���Z�o�X�e�B�A�k�X�̃v���|�[�V�����Ȃǂ͒������Q�l�ɂ��Ă��邾�낤���Ƃ͕�����܂��B�������A����Ƃ��납��A�������痣��āA�Ⴆ�A�l�̔��̍ʐF�Ȃǂ̓��[�G�ɔ�ׂāA���Ȃ�ׂ����g�������Ă��܂����A��ʑS�̂ɋ�C���Ƃ����܂����A�Ȃ�ƂȂ�������C�̃��F�[�������������悤�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���Z�o�X�e�B�A�k�X����肩�������̌������͉_���Q�����悤�ȁA�E�����ɂ́A�͂邩�����ɐX�т�����Ƃ����悤�ȁA���̐��łȂ��悤�Ɍ��z�I�ȕ��i�����ւƍL�����Ă���B���ꂪ�_�b�I�ȋ�Ԃ�����Ă���Ǝv���܂��B���ꂪ�A���Ȃ��悤�ȉ�ʍ\���A�\�}�łP�X���I���M���X�^�[���E�����[�ɒʂ���悤�Ȍ��z�I�ȕ��͋C�����o���Ă���Ǝv���܂��B�l�I�Ȗϑz��������܂��A���[�x���X�̕`�����Z�o�X�e�B�A�k�X�̃|�[�Y�A�Ⴆ�Γ��̂��������Ȃǂ͂Ƃ��ɁA�����[�̊G��̃|�[�Y�̕Ȃɒʂ��Ă���悤�ȋC�����܂��B
���̏����Ȃ܂Ƃ܂�̂悤�ɂ����܂��Ă��܂��Ă��āA��Ԃ����܂芴�������Ȃ��A����Ȋ��������܂��B�Ƃ͂����A���̂悤�ɖ��m�ɂ����Ɣj�]�Ȃ��`�����Ă����Ƃ̋Z�ʂ͂����ւ�Ȃ��̂ł���Ǝv���܂����B���[�x���X�̏ꍇ�́A�����r���܂œ����悤�ɒNj����Ă���Ƃ͎v���܂��B���Z�o�X�e�B�A�k�X�̃v���|�[�V�����Ȃǂ͒������Q�l�ɂ��Ă��邾�낤���Ƃ͕�����܂��B�������A����Ƃ��납��A�������痣��āA�Ⴆ�A�l�̔��̍ʐF�Ȃǂ̓��[�G�ɔ�ׂāA���Ȃ�ׂ����g�������Ă��܂����A��ʑS�̂ɋ�C���Ƃ����܂����A�Ȃ�ƂȂ�������C�̃��F�[�������������悤�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���Z�o�X�e�B�A�k�X����肩�������̌������͉_���Q�����悤�ȁA�E�����ɂ́A�͂邩�����ɐX�т�����Ƃ����悤�ȁA���̐��łȂ��悤�Ɍ��z�I�ȕ��i�����ւƍL�����Ă���B���ꂪ�_�b�I�ȋ�Ԃ�����Ă���Ǝv���܂��B���ꂪ�A���Ȃ��悤�ȉ�ʍ\���A�\�}�łP�X���I���M���X�^�[���E�����[�ɒʂ���悤�Ȍ��z�I�ȕ��͋C�����o���Ă���Ǝv���܂��B�l�I�Ȗϑz��������܂��A���[�x���X�̕`�����Z�o�X�e�B�A�k�X�̃|�[�Y�A�Ⴆ�Γ��̂��������Ȃǂ͂Ƃ��ɁA�����[�̊G��̃|�[�Y�̕Ȃɒʂ��Ă���悤�ȋC�����܂��B
 ��������A�t���A���ς���ĊK�i���~��Ēn���q�ɂ݂����ȍL���W�����ł́A�����̓W�����A�����炩�ɁA����̃N���C�}�b�N�X�Ƃ����Ă����A��삪�X�_�A�����̏@����̑��ʂɈ��|����܂����B���[�x���X�̖{�̂̈�[���A�����Ō��邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B���[���b�p�̋���ɓW������Ă�����́A�����炭�A�����Ɣ��^�ł��������Ƃ͑z���ł��܂����A���̈�[�ɂł��ӂ�邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
��������A�t���A���ς���ĊK�i���~��Ēn���q�ɂ݂����ȍL���W�����ł́A�����̓W�����A�����炩�ɁA����̃N���C�}�b�N�X�Ƃ����Ă����A��삪�X�_�A�����̏@����̑��ʂɈ��|����܂����B���[�x���X�̖{�̂̈�[���A�����Ō��邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B���[���b�p�̋���ɓW������Ă�����́A�����炭�A�����Ɣ��^�ł��������Ƃ͑z���ł��܂����A���̈�[�ɂł��ӂ�邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
���̂ЂƂ��u�@�x�̃}�O�_���̃}���A�v�i�����}�j�Ƃ�����i�B�R�~�Q.�Qm�̑��ʂŁA��������グ��悤�ɓW������Ă��܂����B��������Ɍ����Ĕ������ɂ����A�����̊፷����V��Ɍ����A�����葫����͗͂������A���͂قǂ��Ă���B�@�x�ɂ�莸�_�����}�O�_���̃}���A�̎p�ł��B����Ɠ����悤�ȃ}�O�_���̃}���A��`���Ă���̂��J�����@�b�W���i�E�}�j�ł����i���N�́A�������m���p�ق̂��̕����Ō��܂����B�j�B�������A�J�����@�W���̏ꍇ�ɂ́A�}�O�_���̃}���A�������`����āA�ޏ��̖@�x�̎p�ɒ��ڂ�����i�ł����B����ɑ��āA���̃��[�x���X�̍�i�́A�����炭�J�����@�W�����Q�l�ɂ��Ă���̂ł��傤���A�}���A�̏���̋�Ԃ�傫���Ƃ��āA������������~��Ă��ă}���A���Ƃ炵�o���Ƃ�����ʂɂȂ��Ă��܂��B������ƃJ�����@�W���̍�i���v���o���Ă݂�ƁA�Èł̒��Ń}���A�̎p�������яオ���Ă��܂��B�������A�����ɋP�������͂Ȃ��āA�łɂƂ荞�܂�Ă��܂������ȕ��͋C����Y���Ă��܂��B���̖тȂǂ͈łɂƂ�����Ō����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��邩�̂悤�ł��B�}���A�̊�ɐ��C���������A�炩����ċ����܂ŘI�o���Ă��锧���y�C�F�ŁA���̂Ƌ�ʂł��܂���B�������Δ��ڂ��āA���͔��J���ɂȂ������肪����܂���B���̃}���A�ɑ��āA���̊{�̕����猩�グ��悤�Ɍ������Ă��A���{�Ȃǂ̊�̉����� �͂͂����茩���܂����A�\��̃|�C���g�ƂȂ�ڂ₻�̎��ӂ�����㔼���͉e�ɂȂ��āi�Èłɕ���āj���܂��Ă��܂��B���ꂾ���ɁA���m�ɕ\��ǂݎ�ꂸ�A�������A���J���̌����ڗ����A�����Ă���̂��A�ӎ����Ȃ��̂��A�Ƃ������������܂��B���̉�ʂɂ��鏗���́A���l�ɂ͌����܂���B�J�����@�W�����`�����̂͏��w�Ƃ����ߐ[���l�Ԃł��B��������������ƌ����Ă��A�O�����ς���Ă��܂��킯�ł͂���܂���B�}�O�_���̃}���A�����������̂́A�{�l�̖��ŁA�����T���猩�Ă��A�{�l�ł͂Ȃ��̂ŁA���w�ȊO�̉����̂ł�����܂���B������܂��A�L�b�`���`�����B�������A���w�ł����Ƃ����̂��A�ȒP�ɉ����ł�����̂ł͂Ȃ��ł��傤�B����́A���܂ł̎����̍s������ے肷�邱�Ƃł�����͂��ł��B���ʂɉ߂����Ă���A���̂悤�Ȃ��Ƃ͍l�������Ȃ����A���Ȃ��B������q��ł͂Ȃ��̂ł��B���ꂱ���A���܂�ς��悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����Ȃǂƌ��t�ɂ���̂͊ȒP�ł����A����܂ł̎�����ے肷��Ƃ������Ƃ́A�ȑO�̎������E���Ă��܂����ƂƓ����ŁA����܂ł̎����̎��Ƃ������琶�܂�ς��A�܂�Đ��Ƃ������ƁB����́A�C�G�X�������ǁA���ɂȂ��Ď����ƁA�������邱�Ƃƃp�������ƌ��邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B�J�����@�b�W���̓s�G�^�̉�ʂ�����ɓ���Ȃ���A�}�O�_���̃}���A�̉�ʂ��l�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B�����āA�}���A�̕������悤�Ȋ�̕\���@�x�Ƃ��āA�����ɐ����̋��ڂɂ���E���I�ȏ�ԁA����Ӗ��ł͉�����Ԃ̂悤�Ȃ��̂ł��A�ŕ`���Ă���B�܂�A�������A�܂��Ƀ}�O�_���̃}���A���@�x��Ԃɂ����āA���܂ł̎���������ŁA�V���ɍĐ����悤���Ă���u�Ԃ��A��l�̏��w�̌����̎p�Ƃ��ĕ`�����B����������i�ł�����A�P�������͕K�v�Ȃ����A�V�g�����Ȃ��B����̓}�O�_���̃}���A�Ƃ����l�Ԃ̓]��̃h���}�Ȃ̂ł��B�������A����ł͋����K��鑽���̐l�X�ɂƂ��ĕ�����Ղ��Ƃ͌����Ȃ��B�����ŁA�J�����@�W���̕`�����}�O�_���̃}���A�̓��S�̃h���}���A�����Ƒ����̐l�X�ɂƂ��ĕ�����Ղ����̂Ƃ���ɂ͂ǂ�������悢���B���[�x���X�́A�J�����@�W�����}���A�݂̂���ʂɁA�ޏ��̓��ʂ̃h���}�Ƃ��ĕ`�����̂��A�L����Ԃɒu�������āA�}���A�̓��ʂɃh���}�ɑ��āA���L������ŁA����������_�̎��_����ʂɉ������B����́A�P�Ƀ}���A��_���j�������P�������Ƃ������̂ł͂Ȃ��āA�}���A���g�̓J�����@�W�����`���Ă݂����p�Ɠ����悤�Ɏ��ƍĐ��Ƃ����M���M���̂Ƃ���ʼn��S�����p�Ȃ̂ł��B�����ɂ͂邩���������������Ă���B�J�����@�b�W���̏ꍇ�ɂ́A�ł���ޏ��̎p�������яオ��̂ł����A���[�x���X�͌��ɏƂ炵�o����܂��B����ɂ���āA�}���A�̓]���l�X�ɍL���m�炵�߁A�_�������������Ă���Ƃ������Ƃ������ňÂɎ����Ă���B���ꂪ�A�����̓W�����ł͍�i�����グ��悤�W������Ă��܂�������A�}���A�ɒ������A�������Ă���҂����т�悤�ȍ��o�ɑ�����B�܂�A���̍�i�̉B���ꂽ���͏������̌��ŁA����́A�}�O�_���̃}���A�̂悤�Ȃ��ď��w�ł������l�ɒ�����Ă���A���ꂪ���Ă�����̂ɂ��~�蒍���悤�ȍ��o�ɂƂ����B����������i�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B
�͂͂����茩���܂����A�\��̃|�C���g�ƂȂ�ڂ₻�̎��ӂ�����㔼���͉e�ɂȂ��āi�Èłɕ���āj���܂��Ă��܂��B���ꂾ���ɁA���m�ɕ\��ǂݎ�ꂸ�A�������A���J���̌����ڗ����A�����Ă���̂��A�ӎ����Ȃ��̂��A�Ƃ������������܂��B���̉�ʂɂ��鏗���́A���l�ɂ͌����܂���B�J�����@�W�����`�����̂͏��w�Ƃ����ߐ[���l�Ԃł��B��������������ƌ����Ă��A�O�����ς���Ă��܂��킯�ł͂���܂���B�}�O�_���̃}���A�����������̂́A�{�l�̖��ŁA�����T���猩�Ă��A�{�l�ł͂Ȃ��̂ŁA���w�ȊO�̉����̂ł�����܂���B������܂��A�L�b�`���`�����B�������A���w�ł����Ƃ����̂��A�ȒP�ɉ����ł�����̂ł͂Ȃ��ł��傤�B����́A���܂ł̎����̍s������ے肷�邱�Ƃł�����͂��ł��B���ʂɉ߂����Ă���A���̂悤�Ȃ��Ƃ͍l�������Ȃ����A���Ȃ��B������q��ł͂Ȃ��̂ł��B���ꂱ���A���܂�ς��悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����Ȃǂƌ��t�ɂ���̂͊ȒP�ł����A����܂ł̎�����ے肷��Ƃ������Ƃ́A�ȑO�̎������E���Ă��܂����ƂƓ����ŁA����܂ł̎����̎��Ƃ������琶�܂�ς��A�܂�Đ��Ƃ������ƁB����́A�C�G�X�������ǁA���ɂȂ��Ď����ƁA�������邱�Ƃƃp�������ƌ��邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B�J�����@�b�W���̓s�G�^�̉�ʂ�����ɓ���Ȃ���A�}�O�_���̃}���A�̉�ʂ��l�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B�����āA�}���A�̕������悤�Ȋ�̕\���@�x�Ƃ��āA�����ɐ����̋��ڂɂ���E���I�ȏ�ԁA����Ӗ��ł͉�����Ԃ̂悤�Ȃ��̂ł��A�ŕ`���Ă���B�܂�A�������A�܂��Ƀ}�O�_���̃}���A���@�x��Ԃɂ����āA���܂ł̎���������ŁA�V���ɍĐ����悤���Ă���u�Ԃ��A��l�̏��w�̌����̎p�Ƃ��ĕ`�����B����������i�ł�����A�P�������͕K�v�Ȃ����A�V�g�����Ȃ��B����̓}�O�_���̃}���A�Ƃ����l�Ԃ̓]��̃h���}�Ȃ̂ł��B�������A����ł͋����K��鑽���̐l�X�ɂƂ��ĕ�����Ղ��Ƃ͌����Ȃ��B�����ŁA�J�����@�W���̕`�����}�O�_���̃}���A�̓��S�̃h���}���A�����Ƒ����̐l�X�ɂƂ��ĕ�����Ղ����̂Ƃ���ɂ͂ǂ�������悢���B���[�x���X�́A�J�����@�W�����}���A�݂̂���ʂɁA�ޏ��̓��ʂ̃h���}�Ƃ��ĕ`�����̂��A�L����Ԃɒu�������āA�}���A�̓��ʂɃh���}�ɑ��āA���L������ŁA����������_�̎��_����ʂɉ������B����́A�P�Ƀ}���A��_���j�������P�������Ƃ������̂ł͂Ȃ��āA�}���A���g�̓J�����@�W�����`���Ă݂����p�Ɠ����悤�Ɏ��ƍĐ��Ƃ����M���M���̂Ƃ���ʼn��S�����p�Ȃ̂ł��B�����ɂ͂邩���������������Ă���B�J�����@�b�W���̏ꍇ�ɂ́A�ł���ޏ��̎p�������яオ��̂ł����A���[�x���X�͌��ɏƂ炵�o����܂��B����ɂ���āA�}���A�̓]���l�X�ɍL���m�炵�߁A�_�������������Ă���Ƃ������Ƃ������ňÂɎ����Ă���B���ꂪ�A�����̓W�����ł͍�i�����グ��悤�W������Ă��܂�������A�}���A�ɒ������A�������Ă���҂����т�悤�ȍ��o�ɑ�����B�܂�A���̍�i�̉B���ꂽ���͏������̌��ŁA����́A�}�O�_���̃}���A�̂悤�Ȃ��ď��w�ł������l�ɒ�����Ă���A���ꂪ���Ă�����̂ɂ��~�蒍���悤�ȍ��o�ɂƂ����B����������i�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B
 ���[���b�p�̃L���X�g���Љ�ɂ����Ē����A�ߑ��ʂ��āA���Ƃ����̂͒P�Ȃ鎩�R���ۂ̂ЂƂł��邱�Ƃɗ��܂炸�A�g�_�̌�Ɓh�A�܂�_�̗�I�ȗ͂��ڂɌ�����`�Ō����������̂Ƃ��đ������Ă����ƌ����܂��B���͎��R�ɑ��݂��镨�̗̂l�X�ȉ^���������N�����͂ł���A�l�Ԃ��m���ł�����̌`�ۂł���A�l�Ԃ̒m�����\�ɂ���_�̏Ɩ��ł������Ƃ����܂��A���͂܂��A�������ɑP������o����ł��������B����������I�A�܂萔�w�I�ɒNj����悤�Ƃ����̂����w�ƌ�����w��ŁA����́A���l�T���X�̎���ɂ͉��ߖ@�ƌ����Ă����Ƃ����܂��B�����̉��ߖ@�̊w�҂ł���O���[�e�X�g�Ƃ����l�́A�F���ɑ��݂��镨�̂͂��ꎩ�g�̖��m�Ȍ`�ۂ������̌`�Ŕ�����Ǝ咣���Ă��������ł��B�����t����������܂��A���l�T���X�̊G�悪���ߖ@�ʼn�ʂ��\�����Ă����̂́A�P�ɉ�ʂ𗧑̓I�ɂ��邾���ł͂Ȃ��āA�_�̌�Ƃł�������A���l�T���X�̍����I�v�l�Ɋ�Â��āA��ʂɕ\�킻���Ƃ������̂������ƌ����邩������܂���B������A�����ƒ��ړI�ɁA����҂̊����ɑi����悤�ɂȂ����̂́A�J�����@�b�W�����͂��߂Ƃ��Č��Ɖe�̋���ȃR���g���X�g�Ō��I�Ȍ��ʂ���ʂɐ��G��ŁA�����炭�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�̏@���Η��ŁA���O���x���ł̎x�����W�߂Ă������߂ɐ��I�Ƃ�������悤�Ȓ��ړI�Ŏh���ɕx���̂����߂�ꂽ���߂�������܂���B������ɂ��Ă��A���Ƃ����͓̂��ʂȂ��̂Ƃ��āA�������B���[�x���X���A���̓_�ł͗�O�ł͂Ȃ��āA�������A�J�����@�b�W���̌�̐���ɂ����āA�J�����@�W�������Ɖe�̃R���g���X�g�������Ƃ��قǂɋ������邽�߂ɖ����̂悤�ɋ�Ԃ���ċÏk��������A�G����O���R���e�B���g���b�g�̂悤�ɉ�ʑS�̂��Â����Č����ۗ��悤�ɁA�Ƃ�������ʑS�̂��Â��Ȃ��Ă��܂����Ƃ�����܂���B���[�x���X�̍�i�͖��邭�J�����ɖ�������Ă��܂��B�����ŃJ�����@�W���ȗ��̌��̋���������Ă���̂ł��B����́A���[�x���X�Ƃ����l����ʑS�̂̋�ԍ\���ɓƓ��ȍ˔\����������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂪ�u�@�x�̃}�O�_���̃}���A�v�̉�ʏ㔼���̋�Ԃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A�u�V�g�Ɏ��Â���鐹�Z�o�X�e�B�A�k�X�v�ł͐��Z�o�X�e�B�A�k�X�ɉ�ʍ���������������Ă��܂����A�ނ͉E���ɘ낢�Ă���̂ł��B����A���[�G�́u���C���l�Ɏ��Â���鐹�Z�o�X�e�B�A�k�X�v�ł͐��Z�o�X�e�B�A�k�X�͏�������āA�������̌���S�g�Ō}���Ă��܂��B�u�@�x�̃}�O�_���̃}���A�v�̏ꍇ�́A���_���Ă��܂�����A�{�l�̈ӎu�͌��Ɍ���
���[���b�p�̃L���X�g���Љ�ɂ����Ē����A�ߑ��ʂ��āA���Ƃ����̂͒P�Ȃ鎩�R���ۂ̂ЂƂł��邱�Ƃɗ��܂炸�A�g�_�̌�Ɓh�A�܂�_�̗�I�ȗ͂��ڂɌ�����`�Ō����������̂Ƃ��đ������Ă����ƌ����܂��B���͎��R�ɑ��݂��镨�̗̂l�X�ȉ^���������N�����͂ł���A�l�Ԃ��m���ł�����̌`�ۂł���A�l�Ԃ̒m�����\�ɂ���_�̏Ɩ��ł������Ƃ����܂��A���͂܂��A�������ɑP������o����ł��������B����������I�A�܂萔�w�I�ɒNj����悤�Ƃ����̂����w�ƌ�����w��ŁA����́A���l�T���X�̎���ɂ͉��ߖ@�ƌ����Ă����Ƃ����܂��B�����̉��ߖ@�̊w�҂ł���O���[�e�X�g�Ƃ����l�́A�F���ɑ��݂��镨�̂͂��ꎩ�g�̖��m�Ȍ`�ۂ������̌`�Ŕ�����Ǝ咣���Ă��������ł��B�����t����������܂��A���l�T���X�̊G�悪���ߖ@�ʼn�ʂ��\�����Ă����̂́A�P�ɉ�ʂ𗧑̓I�ɂ��邾���ł͂Ȃ��āA�_�̌�Ƃł�������A���l�T���X�̍����I�v�l�Ɋ�Â��āA��ʂɕ\�킻���Ƃ������̂������ƌ����邩������܂���B������A�����ƒ��ړI�ɁA����҂̊����ɑi����悤�ɂȂ����̂́A�J�����@�b�W�����͂��߂Ƃ��Č��Ɖe�̋���ȃR���g���X�g�Ō��I�Ȍ��ʂ���ʂɐ��G��ŁA�����炭�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�̏@���Η��ŁA���O���x���ł̎x�����W�߂Ă������߂ɐ��I�Ƃ�������悤�Ȓ��ړI�Ŏh���ɕx���̂����߂�ꂽ���߂�������܂���B������ɂ��Ă��A���Ƃ����͓̂��ʂȂ��̂Ƃ��āA�������B���[�x���X���A���̓_�ł͗�O�ł͂Ȃ��āA�������A�J�����@�b�W���̌�̐���ɂ����āA�J�����@�W�������Ɖe�̃R���g���X�g�������Ƃ��قǂɋ������邽�߂ɖ����̂悤�ɋ�Ԃ���ċÏk��������A�G����O���R���e�B���g���b�g�̂悤�ɉ�ʑS�̂��Â����Č����ۗ��悤�ɁA�Ƃ�������ʑS�̂��Â��Ȃ��Ă��܂����Ƃ�����܂���B���[�x���X�̍�i�͖��邭�J�����ɖ�������Ă��܂��B�����ŃJ�����@�W���ȗ��̌��̋���������Ă���̂ł��B����́A���[�x���X�Ƃ����l����ʑS�̂̋�ԍ\���ɓƓ��ȍ˔\����������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂪ�u�@�x�̃}�O�_���̃}���A�v�̉�ʏ㔼���̋�Ԃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A�u�V�g�Ɏ��Â���鐹�Z�o�X�e�B�A�k�X�v�ł͐��Z�o�X�e�B�A�k�X�ɉ�ʍ���������������Ă��܂����A�ނ͉E���ɘ낢�Ă���̂ł��B����A���[�G�́u���C���l�Ɏ��Â���鐹�Z�o�X�e�B�A�k�X�v�ł͐��Z�o�X�e�B�A�k�X�͏�������āA�������̌���S�g�Ō}���Ă��܂��B�u�@�x�̃}�O�_���̃}���A�v�̏ꍇ�́A���_���Ă��܂�����A�{�l�̈ӎu�͌��Ɍ��� �Ă��Ȃ��B���[�x���X�̏ꍇ�́A�����}�����l���̕�����ؓ�ł͂Ȃ��̂ł��B���������\�}��̕��G�����A�Ɠ��ȋ�ԍ\���Ƃ����܂��āA�P���łȂ����ɂ��h���}�������Ă���̂ł��B
�Ă��Ȃ��B���[�x���X�̏ꍇ�́A�����}�����l���̕�����ؓ�ł͂Ȃ��̂ł��B���������\�}��̕��G�����A�Ɠ��ȋ�ԍ\���Ƃ����܂��āA�P���łȂ����ɂ��h���}�������Ă���̂ł��B
�u�L���X�g�����v�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B�����薼�œ�̍�i���W������Ă��܂������A������͐���N�オ��̕��ł��B�\�}�́A�u�@�x�̃}�O�_���̃}���A�v�Ƃ悭���Ă��āA�傫�ȈႢ�́A�u�@�x�̃}�O�_���̃}���A�v�ɂ������㔼���̋�Ԃ��u�L���X�g�����v�ɂ͂Ȃ��āA��Ԃ����Ă���悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��B���̉����̉�ʂ̍��ォ��E���ւ̑Ίp���ɃL���X�g�̈�[�������ɉ�������Ă��܂��B�L���X�g�̐g�ْ̂͋����Ȃ��J����������͂Ȃ����ꂽ���r���A���������̋C�̎������y�C�F�̔������̂ł��邱�Ƃ�e�͂Ȃ�������Ă��܂��B�L���X�g�̉E��ɂ͐���}���A�����Y���A�E��Ŋz�Ɏh�����������A����ł킸���ɊJ�����܂܂̊����悤�Ƃ��Ă��܂��B���� �ق��ɂ��A��[�����͂ސl�X���A�L���X�g�̎��𓉂ގp�����ꂼ��ɕ`�������Ă��āA���ꂼ��̃h���}��������Ă���Ƃ��������ł��B���́A���ꂼ��̃h���}����ʂ̒��S�ł���L���X�g�̈�[�Ɍ������āA����҂̎����������Ɉ������ނ悤�ɂ��āA������U���悤�ȍ\�}�ɂȂ��Ă��܂��B���̒��ŁA��ʉE��̏��������́A�L���X�g�̈�[�������ɁA��������Ɍ����Ă��܂��B����́A��ʑS�̂��Â����ɂ���Ȃ��ŁA����̋�Ԃ����Ă��ĉB���ꂽ�`�ɂȂ��Ă��܂����A���̏����̎����́A�����Ɍ������Ă��āA�����ɉ��������鎖���Î����Ă���̂ł��傤���B���̍�i�ɂ́A�������͒�����Ă��܂���B������A�����͂͂邩����Ɋ�������Ă���̂́A���̈Î��Ȃ̂ł��傤���B
�ق��ɂ��A��[�����͂ސl�X���A�L���X�g�̎��𓉂ގp�����ꂼ��ɕ`�������Ă��āA���ꂼ��̃h���}��������Ă���Ƃ��������ł��B���́A���ꂼ��̃h���}����ʂ̒��S�ł���L���X�g�̈�[�Ɍ������āA����҂̎����������Ɉ������ނ悤�ɂ��āA������U���悤�ȍ\�}�ɂȂ��Ă��܂��B���̒��ŁA��ʉE��̏��������́A�L���X�g�̈�[�������ɁA��������Ɍ����Ă��܂��B����́A��ʑS�̂��Â����ɂ���Ȃ��ŁA����̋�Ԃ����Ă��ĉB���ꂽ�`�ɂȂ��Ă��܂����A���̏����̎����́A�����Ɍ������Ă��āA�����ɉ��������鎖���Î����Ă���̂ł��傤���B���̍�i�ɂ́A�������͒�����Ă��܂���B������A�����͂͂邩����Ɋ�������Ă���̂́A���̈Î��Ȃ̂ł��傤���B
�u���ƍ߂ɏ�������L���X�g�v�i����}�j�́A�����畜�������L���X�g�ŁA�悩��h�����Ƃ���̃L���X�g�̎p�ł��B�Ԃ��}���g���͂������L���X�g�͐Ί��̏�ɍ������āA���̓��X�Ƃ����g�̂��̂��̂����ɑ��鏟�������̂������Ă���Ƃ����܂��B�����Ɋ[���Ǝւ����݂����A����ے�����Ă��܂��B����Ǝ����悤�Ȃ��̂��ȑO�̃��[�x���X�W�ł��u�����̃L���X�g�v�i��E�}�j�Ƃ�����i�����܂����B���������Ă���ƌ`���I�Ƃ��l���I�Ƃł������悤�Ȋ��������܂��B���A���Ƃ����ʂƂ����ȑO�ɁA����̍Ւd�Ȃǂɏ��邽�߂ɂ�����x���܂�̃p�^�[���ɂ܂Ƃ߂�Ƃ����̂��B���ꂾ����Ƃ����̂ł��Ȃ��̂ł����A��R�̍�i���A�������H�[�Ƃ����V�X�e���ŗʎY���Ă������߂�����̂�������܂��A��ʂ� �I�݂ȍ\���Ȃ̂ɂ�������炸�A�V���v���ŁA���܂�˔�Ȃ��Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł��B���̍�i�ł́A���S�ɃL���X�g���������Ă��āA����ʼn�ʂ͈��肵�Ă��܂��B���̗����ɓV�g��z���Ă��܂����A�������ɃV�����g���[�͕����Ă��܂����A���S�����肵�Ă���̂ŁA�����ŃV�����g���[������čd���Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��Ă���B�����āA�L���X�g�����|���Ă���Ί��̏㉺�őΔ������A���ɂ��鐂�ւ݂��Ă���B�܂�A�L���X�g��������������̕������p���Â��Ƃ���ɕ`����Ă��܂��B�����ď�́A�L���X�g�̏�����V�g���j�����閾�邢��ʂɂ��Ă���B������₷���A�Ƃ����킯�ł��B
�I�݂ȍ\���Ȃ̂ɂ�������炸�A�V���v���ŁA���܂�˔�Ȃ��Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł��B���̍�i�ł́A���S�ɃL���X�g���������Ă��āA����ʼn�ʂ͈��肵�Ă��܂��B���̗����ɓV�g��z���Ă��܂����A�������ɃV�����g���[�͕����Ă��܂����A���S�����肵�Ă���̂ŁA�����ŃV�����g���[������čd���Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��Ă���B�����āA�L���X�g�����|���Ă���Ί��̏㉺�őΔ������A���ɂ��鐂�ւ݂��Ă���B�܂�A�L���X�g��������������̕������p���Â��Ƃ���ɕ`����Ă��܂��B�����ď�́A�L���X�g�̏�����V�g���j�����閾�邢��ʂɂ��Ă���B������₷���A�Ƃ����킯�ł��B
�����āA���łЂƂ���ڗ����Ă����̂��u���A���f���̏}���v�i���}�j�ł��B�y�e���̌Z��ŋ��t�̃A���f���̓��[�}�鍑�̑��ɂ���ď\���˂����ɂ���A���̂Q���̂������ނ���芪�����l�X�ɋ�����������B���̌�œV������������āA���̗�͌��ƂƂ��ɏ��V�����Ƃ����`����`�������̂������ł��B��ʂ́A�w���̏\���˂𒆐S�ɍ\������Ă��܂��B���̏\���˂ɂ���āA����͑Ίp����ɕ�������A��ʉE���ɂ͐g��k�킹�Ĕn�ɏ�郍�[�}���̎p���z����A�����ł͓�l�̏��������ɍ��肵�Ă���l�q���`����Ă��܂��B���̈�l�̓A���f���ɂ���ăL���X�g���ɉ��@�������̍ȂƂ������Ƃł��B���ɂ��ꂽ�A���f���͏�������ċF��������Ă��܂����A����Ɣ��̉E���������������A���̌��̂��ɓV�g�����āA���j���ƞ��L�̎}����ɂ��Ă��܂��B���̍\�}���ʍ\���́A�ނ��t���ɂ�����I�b�g�[�E�t�@���E�t�F�[�����u���A���f���̏}���v�i�E��}�j�Ƃ�������ŁA���̃I�}�[�W���ł�����Ƃ��������ł��B�������A���҂̍\���͋��ʂ��Ă��Ă����ۂ͐����ł��B�t�F�[�����X�^�e�B�b�N�ȉ�ʂ��k���Ɏd�グ�āA�����������D���Ȉ�ۂ�^����̂ɑ��āA���[�x���X�̍�i�͐l���͌��I�Ŋ���I�ȃ|�[�Y�ŁA�����������e�߂̕M�G���G�M�̓������c���Ă��āA���ꎩ�̂������������Ă��邩�̂悤�ɁA�l�X�ɖ�������^���Ă��܂��B���̓����ɁA���̊G�����Ă���l�͎䂫���܂�Ă��܂��悤�ȁA����I�ȎQ�����Ă��܂��悤�ȉ�ʂɂȂ��Ă��܂��B���̍r�X�����M�����Ń��A���e�B����ʂɐ��ݏo���Ă���̂́A������̃x���X�P�X�ɂ����ʂ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���ꂾ���̑��ʂꂵ���M�����Ō�����Ƃ����̂ł́A�����炭�H�[�ŕ����̉�Ƃ����S���ĕ`������͓̂���̂ŁA�H�[�ō�i��ʎY�������[�x���X�̒��ł́A���̂悤�ȍ�i�͒������̂�������܂���B������������ɂ��ẮA���ƂŐG��邩������܂���B
�W�D�_�b�̗͂P���w���N���X�ƒj���k�[�h

 ��������A�K�i�ŏ�̃t���A�ɏオ��܂��B�����͈�̕����Ɍ����������悤�ɒj���k�[�h�ƁA���̃R�[�i�[�̏����k�[�h���W������Ă��܂����B�����Ă݂�ΐl�̕\���A���������z�����ꂽ���̂��W�߂�ꂽ�ƌ����ׂ��ł��傤�B���̒j���k�[�h�̊i�D�̑�ނƂ��ă��[�x���X���悭���グ���̂��M���V���_�b�̃w���N���X�ł��B
��������A�K�i�ŏ�̃t���A�ɏオ��܂��B�����͈�̕����Ɍ����������悤�ɒj���k�[�h�ƁA���̃R�[�i�[�̏����k�[�h���W������Ă��܂����B�����Ă݂�ΐl�̕\���A���������z�����ꂽ���̂��W�߂�ꂽ�ƌ����ׂ��ł��傤�B���̒j���k�[�h�̊i�D�̑�ނƂ��ă��[�x���X���悭���グ���̂��M���V���_�b�̃w���N���X�ł��B
�u�w�X�y���f�X�̉��̃w���N���X�v�i���}�j�Ƃ�����i�́A�Q.�T�~�P.�Rm�Ƃ����T�C�Y�́A����قǂ̑��ʂł͂Ȃ��A���[�x���X�������M�����ł����ƕ`�������̂ƍl�����܂��B���ꂾ���ɁA�r�������锽�ʂŖ������Ɉ��Ă��܂��B�M���V���_�b�ŁA�w���N���X�̓w�X�y���f�X�̉��̃[�E�X�̍Ȃł���w���̏��L��������物���̗ь����ɓ����Ƃ������ɒ��킵�āA�݂��Ƃɐ��������܂��B���̍�i�ł̃w���N���X�́A�����Ɏ�����闳�݂��߁A�E�r��L���A����ƃo�����X����邽�߂Ɋ��ȓ��̂̑̏d���E���ɂ����āA����̍����͗͂����ċȂ��Ă��܂��B���̎p���́A�����̓t�@���[�l�[�[�{�a�ɂ������A�Ñ�M���V���̒����ƃ����V�b�|�X�ɂ���Đ��삳�ꂽ�u�t�@���l�[�[�̃w���N���X�v�i�E�}�j������p���ꂽ���̂Ɛ�������Ă��܂����B�҂��ɁA�|�[�Y�͂悭���Ă��܂��B���̒����́A���͂�Ⴍ�Ȃ��p�Y���A���Ƃ̌��ʔ�J���ނ����p��\�킵�����̂Ƃ���Ă��邻���ł����A���[�x���X�́A���̒����ɑ��đ�R�̑f�`���A���X�̈قȂ鎋�_����s���A�ו��Ɏ���܂ŕ��͂��A�n���̍��{����A�C�f�B�A��m�邽�߂ɁA�e�������w�I�Ȍ`�ԂɊ��������}�������݂������ł��B���̌Ñ㒤���ɂ̓~�N���R�X���X�Ƃł������悤�Ȗ������x�z���钲�a�̒��������f�������䂦�ɕ��Ր�����������S�Ȏp�ł���Ƃ��āA���[�x���X�́A���̔閧���Ñ�̐l�X�ɕ���Ċw�����p���ĕ��͂��悤�Ƃ����B���ꂪ�����`�Ⓑ���`��O�p�`�Ƃ����w�I�}�`�Ă͂߂āA�����̃X�P�b�`���s�����Ƃ����܂��B���̎p�����p����悤�ɕ`�����A���̍�i�̃w���N���X�́A���������ĕ��Ր��̂��銮�S�����̗��z��\�킻���Ƃ������̂ƌ����邩������܂���B�������ɁA��ʂ����ς��ɕ`���ꂽ�w���N���X�́A��ʂ��̂��̂͑��ʂł��Ȃ��̂ɋ��傳��������ەt�����܂��B�l�Ԃ̎p�`�ŕ`����Ă��܂����A�l�Ԃ�������� ��ۂł��B����́A�����ɓW������Ă����O�C�h�E���[�j���u�q���h���E�Q��x������w���N���X�v�i�E�}�j�������悤�ɌÑ㒤���̃|�[�Y���Ƃ��Ă���̂ł����A���[�x���X�ɔ�ׂ�ƁA��������Ƃ��Ă��āA�������l�̂̎p�Ƃ�����ۂŋ��傳�����������Ȃ��̂ƑΏƓI�ł��B�܂�A�����悤�ɗ��z�I�Ȑl�Ԃ̓��̂��l�Ƃ��`���Ă���̂ɁA�O�C�h����[�j�͔������l�̂̈�ۂȂ̂ɑ��āA���[�x���X�͐l�Ԃ̎p�����Ă���̂ɐl�Ԃ�������ȉ����̂��ɂȂ��Ă���̂ł��B���̈Ⴂ�͂ǂ��ɂ���̂��A���ɂ͖��m�Ȃ��Ƃ͌����܂���B�����܂ł���ۂ̈Ⴂ�Ƃ��������܂���B
��ۂł��B����́A�����ɓW������Ă����O�C�h�E���[�j���u�q���h���E�Q��x������w���N���X�v�i�E�}�j�������悤�ɌÑ㒤���̃|�[�Y���Ƃ��Ă���̂ł����A���[�x���X�ɔ�ׂ�ƁA��������Ƃ��Ă��āA�������l�̂̎p�Ƃ�����ۂŋ��傳�����������Ȃ��̂ƑΏƓI�ł��B�܂�A�����悤�ɗ��z�I�Ȑl�Ԃ̓��̂��l�Ƃ��`���Ă���̂ɁA�O�C�h����[�j�͔������l�̂̈�ۂȂ̂ɑ��āA���[�x���X�͐l�Ԃ̎p�����Ă���̂ɐl�Ԃ�������ȉ����̂��ɂȂ��Ă���̂ł��B���̈Ⴂ�͂ǂ��ɂ���̂��A���ɂ͖��m�Ȃ��Ƃ͌����܂���B�����܂ł���ۂ̈Ⴂ�Ƃ��������܂���B
�X�D�_�b�̗͂Q�����B�[�i�X�Ə����k�[�h
�j���k�[�h�̗��z�����w���N���X�Ȃ珗���k�[�h�̓��B�[�i�X�Ƃ����킯�ł����B�u�o���̞��ɏ������B�[�i�X�v�i�����}�j�Ƃ�����i�B���B�[�i�X�]�X�������O�ɁA���̖L���œ��t���̂悢�A�Ƃ������������������Đ���Č�����قǂ̎��b�̉�̂悤�ȓ��́A���ꂱ���������v���`���Ă������[�x���X�̏��̂ł��B�Ƃ��ɁA�ł��Ղ�Ƃ��Đ��ꉺ�������悤�ȐK���A�s���N�F�̔��������Ă���悤�Ɍ�����B���z�Ƃ����N�I��ʂ�z���āA�ߏ肳���A�s���߂��Ɍ����āA� �ꂽ�p�����p�I�Ƃ͂����܂��A�����̎�O�Ɏ���d�ŗ��܂��Ă���B�w���N���X���l�Ԃ̎p�����Ă��Ȃ���l�Ԃ�������Ȉ�ۂ�^����̂ƁA��������݂ŁA���̃��B�[�i�X������Ȉ�ۂ�^����B�������A���{�l�̎����猩����A�Q�b�v���o�����ȁB���[�x���X���Q�Ƃ����Ƃ����W�����{���[�j���̒����u���B�[�i�X�ƃL���[�s�b�h�v�i�E���}�j�̃��B�[�i�X�̃|�[�Y�͋��ʂ���Ƃ���͂���܂����A�����̃��B�[�i�X�̓��[�x���X�̊G��ɔ�ׂ�Ɖؚ��ŏ����̂悤�Ɍ����Ă��܂��A�ƂĂ����_�ɂ͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�ꂽ�p�����p�I�Ƃ͂����܂��A�����̎�O�Ɏ���d�ŗ��܂��Ă���B�w���N���X���l�Ԃ̎p�����Ă��Ȃ���l�Ԃ�������Ȉ�ۂ�^����̂ƁA��������݂ŁA���̃��B�[�i�X������Ȉ�ۂ�^����B�������A���{�l�̎����猩����A�Q�b�v���o�����ȁB���[�x���X���Q�Ƃ����Ƃ����W�����{���[�j���̒����u���B�[�i�X�ƃL���[�s�b�h�v�i�E���}�j�̃��B�[�i�X�̃|�[�Y�͋��ʂ���Ƃ���͂���܂����A�����̃��B�[�i�X�̓��[�x���X�̊G��ɔ�ׂ�Ɖؚ��ŏ����̂悤�Ɍ����Ă��܂��A�ƂĂ����_�ɂ͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�����炭�A���[�x���X�̍�i�̒��ł͏��i�̕��ނɓ���T�C�Y�ŁA���B�[�i�X�͕`���Ă��܂����A�������M�v�͍r�����i���ꂪ�p���ă��B�[�i�X�̓��̂̋ؓ��̂��������悤�ȓ����I�Ȑ��X�����̕\�������������Ă���Ǝv���܂��B�������A�㔼�g���Ђ˂�p�����琶�܂ꂽ�������₭�ڂ݂��₯�ɋ�������Ă��āA�Ⴆ�A�������r�̊Ԃɋ��܂�Ă��ڂ肾�����悤�ȓ��[�Ȃ́A�܂�œ������霂Ƃ�����قǂł��B�j�A�����Ɋ��Y���v�b�g�[�����͎d�グ���Ă��Ȃ��̂ŁA�����M�����ł����ƕ`���ꂽ���ʃX�P�b�`�̂悤�ȍ�i�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�Y�D�G�M�̔M��
 ���̃t���A�ł̏@����̑��ʂ�����L�Ԃ��A���̓W����̃N���C�}�b�N�X�������Ƃ���A���̓W���͍Ō�̑O�ɁA�����ЂƐ���オ��Ƃ������Ƃ���ł��傤���B���ʂ̑�삱������܂����x�̔Z����ʂ̌��삪�ڔ������ŁA�v�킸�䂫���܂�Ă��܂��܂��B�g���[�x���X�̌|�p�͓�����̔��p���_���ɂ����āA�����u���ՓI�v�Ƃ������t�ƂƂ��ɐ������ꂽ�B���̏ꍇ�̕��ՓI�Ƃ����̂́A����I�������I�Ȑ��i�̂��ƂŁA��ʂɕ`�����܂ꂽ���܂��܂Ȃ��̂��A�S�̂Ƃ��Ă͐��������Ƃ��Ĕ�����������ƌ����Ă���̂ł���B���̔錍�́A�F�ʂƁA�������ʂɗ^����f�����M���I�ȕM�����ɂ������B���݂������P�V���I�̔��p���_�ƃx�b���[���́A�u�G�M�̔M���v�Ƃ������t�Ń��[�x���X�̊G���������Ă���B���[�x���X�̕M�����́A�ו����ȗ����A�t�Ɍ֒���p���A��ʂɓ��ꊴ�̂��錃��ȃ��B�W�����ݏo���āA����҂̋�z�Ƒz����~�����Ă�B����̓��F�l�c�B�A�̃e�B���g���b�g��}���g���@�̃W�����I�E���}�[�m��A�C�^���A�̐�s���鎞��̍�i���������邱�Ƃɂ���ē���ꂽ���̂ł������B�����������[�x���X�|�p�̐��i�̍ł��킩��₷���`�Ō�����̂́A�͂Ɨ͂��Ԃ��荇���A�����Ɉ��A�l�ԂƔn�A�������ݍ�����ʂł���B�h�Ɛ�������Ă��܂��B�������A����͂����炭���[�x���X�̍�i�S�ʂɂ��Č����邱�Ƃł͂Ȃ��āA�ꕔ�̌X���ł���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�W�����ɓ���O�Ƀr�f�I�ʼnf�ʂ���Ă����A���g���[�v�吹���Ɍf����ꂽ���Ƃ�������\��ł́A�H�[�ő��̉�Ƃɕ��S�����ĕ`���������̂ł��B���̏ꍇ�A���̉�Ƃ����Ƀ��[
���̃t���A�ł̏@����̑��ʂ�����L�Ԃ��A���̓W����̃N���C�}�b�N�X�������Ƃ���A���̓W���͍Ō�̑O�ɁA�����ЂƐ���オ��Ƃ������Ƃ���ł��傤���B���ʂ̑�삱������܂����x�̔Z����ʂ̌��삪�ڔ������ŁA�v�킸�䂫���܂�Ă��܂��܂��B�g���[�x���X�̌|�p�͓�����̔��p���_���ɂ����āA�����u���ՓI�v�Ƃ������t�ƂƂ��ɐ������ꂽ�B���̏ꍇ�̕��ՓI�Ƃ����̂́A����I�������I�Ȑ��i�̂��ƂŁA��ʂɕ`�����܂ꂽ���܂��܂Ȃ��̂��A�S�̂Ƃ��Ă͐��������Ƃ��Ĕ�����������ƌ����Ă���̂ł���B���̔錍�́A�F�ʂƁA�������ʂɗ^����f�����M���I�ȕM�����ɂ������B���݂������P�V���I�̔��p���_�ƃx�b���[���́A�u�G�M�̔M���v�Ƃ������t�Ń��[�x���X�̊G���������Ă���B���[�x���X�̕M�����́A�ו����ȗ����A�t�Ɍ֒���p���A��ʂɓ��ꊴ�̂��錃��ȃ��B�W�����ݏo���āA����҂̋�z�Ƒz����~�����Ă�B����̓��F�l�c�B�A�̃e�B���g���b�g��}���g���@�̃W�����I�E���}�[�m��A�C�^���A�̐�s���鎞��̍�i���������邱�Ƃɂ���ē���ꂽ���̂ł������B�����������[�x���X�|�p�̐��i�̍ł��킩��₷���`�Ō�����̂́A�͂Ɨ͂��Ԃ��荇���A�����Ɉ��A�l�ԂƔn�A�������ݍ�����ʂł���B�h�Ɛ�������Ă��܂��B�������A����͂����炭���[�x���X�̍�i�S�ʂɂ��Č����邱�Ƃł͂Ȃ��āA�ꕔ�̌X���ł���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�W�����ɓ���O�Ƀr�f�I�ʼnf�ʂ���Ă����A���g���[�v�吹���Ɍf����ꂽ���Ƃ�������\��ł́A�H�[�ő��̉�Ƃɕ��S�����ĕ`���������̂ł��B���̏ꍇ�A���̉�Ƃ����Ƀ��[ �x���X�Ɠ����悤�ȏn�B�����M�������ꗥ�ɋ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B�܂��A�C�^���A�̐l�X�ɂ̓��F�l�c�B�A�h�̂悤�ȍr���ۂ��M�����͊��}���ꂽ��������܂��A���[�x���X�̒n���ł���t�����h���n���̓t�@���E�A�C�N�̂悤�Ȑ��k�ȊG��̓`�����p����Ă���Ƃ���ł��B���̂悤�Ȏ����u�G�M�̔M���v�ƌ�����悤�ȌX�����}�����ꂽ��i���c����Ă��܂��B����́A���̌�̃R�[�i�[�œW������Ă����u�}���X�ƃ��A�E�V���E�B�A�v�Ƃ�������i�ɂ����Ă͂܂�܂��B
�x���X�Ɠ����悤�ȏn�B�����M�������ꗥ�ɋ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B�܂��A�C�^���A�̐l�X�ɂ̓��F�l�c�B�A�h�̂悤�ȍr���ۂ��M�����͊��}���ꂽ��������܂��A���[�x���X�̒n���ł���t�����h���n���̓t�@���E�A�C�N�̂悤�Ȑ��k�ȊG��̓`�����p����Ă���Ƃ���ł��B���̂悤�Ȏ����u�G�M�̔M���v�ƌ�����悤�ȌX�����}�����ꂽ��i���c����Ă��܂��B����́A���̌�̃R�[�i�[�œW������Ă����u�}���X�ƃ��A�E�V���E�B�A�v�Ƃ�������i�ɂ����Ă͂܂�܂��B
���͍H�[�ő��̉�Ƃɕ��S�����ĕ`������K�v������܂������A���̂��߂̉��G��K�͂̏����ȍ�i�́A�����炭���l�ɔC�����ƂȂ����[�x���X�{�l���`�����̂ł��傤�B���������āA�����ɓW������Ă�����i�͔�r�I�����K�͂̍�i����ł��B�������A���ł͂ǂ����Ă����l�ɕ`�����邩��A�P�O�O�������̎v�����ʂ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A������x�̂Ƃ���őË����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�A���i�≺�G�͎����ŕ`������A���̂悤�ȑË������ɍςށA�����Ŏv����H����L���悤�ɕ`�����Ƃ�����̂��A�����ɓW������Ă����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂾ���ɁA���Ȃ�U�߂Ă����i������ł����Ǝv���܂��B
 �u���E���X���̏}���v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���Pm�قǂ̉��������珬������i�ł��B�����Ɏ���Ȃ�������i�̉��G�ł���Ɛ�������Ă��܂����A�����炭�A�S�̂̍\�z�̃f�U�C���̂悤�Ȃ��̂ł��傤�B�M�����Ȃǂ͍r���ۂ��āA���Ԃ��������ɂ����ƕ`�����悤�Ɍ����܂��B�ʐF�����ę{���ʂɂ���Ă���悤�ɂ������Ȃ��B��ʐ^�̔����߂𒅂��E���X�����V�����ł���Ƃ���Ɍ��������āA���̌��̒��ɘr���L���Ď~�߂�悤�Ȏp���̃L���X�g��V�g���������Ă��܂��B����ȊO�̂Ƃ���͌��̂Ȃ��ł̂悤�ȂȂ��ŎE�C�̏�ʂɂȂ��Ă��܂��B��ʂ��ɒ[�Ɍ��Ɖe�ɓ��A���̕����Ƀe���R����ŃL���X�g��V�g���l�ߍ���Ő_�X�����̍^���̂悤�ł��B���̋ɒ[�ȑΏƁA���������\�}�̓e�B���g���b�g������̉e���i�Ⴆ�A�e�B���g���b�g���u���J�^���i�̏}���v�i�E�}�j�j�Ƃ������ƂȂ̂�������܂��A���[�x���X�̉�ʂ̕����A��ʂɉ��s����L���肪�����ĈÈł̌����i�E�C�̏�ʁA���̌����̏�ʂ��f�����M�����ő�_�ȏȗ����ĕ`����Ă��邽�߂��A���̏�ʂ̐l���������A�܂�ŗH��̂悤�Ɍ�����̂ł��B���ꂪ�䂦�Ɍ����̏�ʂł���Ȃ���A���Ɍ����Ă���j�ɑΏƂ��Č��̕�������������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�����ŁA���Ɍ������f��ɑΏƂ��āA���z�ł���L���X�g�̋~�������A���ɉf���Ă���Ƃ����]�|�����܂��B�������A�E�C�̃_�C�i�~�b�N�Ȑ��X����������A���ꂪ�����Ă����V�ォ��V�g���E�����Ă���悤�ɃE���X���ɔ����Ă���B������A�e�B���g���b�g�̍�i�ɔ�ׂāA�ł�����ɂ�������炸�A�S�̂Ƃ��ĈÂ���ʂɂ͌��Ȃ��̂ł��B
�u���E���X���̏}���v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���Pm�قǂ̉��������珬������i�ł��B�����Ɏ���Ȃ�������i�̉��G�ł���Ɛ�������Ă��܂����A�����炭�A�S�̂̍\�z�̃f�U�C���̂悤�Ȃ��̂ł��傤�B�M�����Ȃǂ͍r���ۂ��āA���Ԃ��������ɂ����ƕ`�����悤�Ɍ����܂��B�ʐF�����ę{���ʂɂ���Ă���悤�ɂ������Ȃ��B��ʐ^�̔����߂𒅂��E���X�����V�����ł���Ƃ���Ɍ��������āA���̌��̒��ɘr���L���Ď~�߂�悤�Ȏp���̃L���X�g��V�g���������Ă��܂��B����ȊO�̂Ƃ���͌��̂Ȃ��ł̂悤�ȂȂ��ŎE�C�̏�ʂɂȂ��Ă��܂��B��ʂ��ɒ[�Ɍ��Ɖe�ɓ��A���̕����Ƀe���R����ŃL���X�g��V�g���l�ߍ���Ő_�X�����̍^���̂悤�ł��B���̋ɒ[�ȑΏƁA���������\�}�̓e�B���g���b�g������̉e���i�Ⴆ�A�e�B���g���b�g���u���J�^���i�̏}���v�i�E�}�j�j�Ƃ������ƂȂ̂�������܂��A���[�x���X�̉�ʂ̕����A��ʂɉ��s����L���肪�����ĈÈł̌����i�E�C�̏�ʁA���̌����̏�ʂ��f�����M�����ő�_�ȏȗ����ĕ`����Ă��邽�߂��A���̏�ʂ̐l���������A�܂�ŗH��̂悤�Ɍ�����̂ł��B���ꂪ�䂦�Ɍ����̏�ʂł���Ȃ���A���Ɍ����Ă���j�ɑΏƂ��Č��̕�������������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�����ŁA���Ɍ������f��ɑΏƂ��āA���z�ł���L���X�g�̋~�������A���ɉf���Ă���Ƃ����]�|�����܂��B�������A�E�C�̃_�C�i�~�b�N�Ȑ��X����������A���ꂪ�����Ă����V�ォ��V�g���E�����Ă���悤�ɃE���X���ɔ����Ă���B������A�e�B���g���b�g�̍�i�ɔ�ׂāA�ł�����ɂ�������炸�A�S�̂Ƃ��ĈÂ���ʂɂ͌��Ȃ��̂ł��B
 �u�p�G�g���̒ė��v�i���}�j�Ƃ�����i�B������傫���Ȃ��B�������A���̌����đ傫���͂Ȃ���ʂɔn�Ɛl�����藐��āA�Ђ�����Ԃ����肵�āA�ォ����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��悤�Ȃ���l���A�܂Ƃ܂��Ď��߂Ă���̂������\���͂��Ǝv���܂��B�M���V���_�b�ŁA�p�G�g���͑��z�_�A�|�����̎Ⴋ���q�ł���Ȃ��畃��m�炸�l�̎q�Ƃ��Ĉ炿�܂��B���鎞�A�^����m��A����o�������̍߈����ɑi���āA���z�_�̐�Ԃ���鋖�����߂܂��B���q�ł͐�Ԃ𑀂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɗm�M���镃�͐��������݂邪���s���܂��B�p�G�g���͓��X���E���Ƃ炷��ԁi�M���V���_�b�ł͑��z�_�A�|�������A���̐�Ԃ𑖂点��̂����Ԃ̑��z�̋O���̓����Ȃ̂ł��j�ɏ�荞�ނ��̂́A�����ɐ���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ŁA�\�����琢�E����邽�߁A���s�e�������d�𓊂����A��҂͖��𗎂Ƃ��B���̌��I�ȏ�ʂ�
�u�p�G�g���̒ė��v�i���}�j�Ƃ�����i�B������傫���Ȃ��B�������A���̌����đ傫���͂Ȃ���ʂɔn�Ɛl�����藐��āA�Ђ�����Ԃ����肵�āA�ォ����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��悤�Ȃ���l���A�܂Ƃ܂��Ď��߂Ă���̂������\���͂��Ǝv���܂��B�M���V���_�b�ŁA�p�G�g���͑��z�_�A�|�����̎Ⴋ���q�ł���Ȃ��畃��m�炸�l�̎q�Ƃ��Ĉ炿�܂��B���鎞�A�^����m��A����o�������̍߈����ɑi���āA���z�_�̐�Ԃ���鋖�����߂܂��B���q�ł͐�Ԃ𑀂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɗm�M���镃�͐��������݂邪���s���܂��B�p�G�g���͓��X���E���Ƃ炷��ԁi�M���V���_�b�ł͑��z�_�A�|�������A���̐�Ԃ𑖂点��̂����Ԃ̑��z�̋O���̓����Ȃ̂ł��j�ɏ�荞�ނ��̂́A�����ɐ���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ŁA�\�����琢�E����邽�߁A���s�e�������d�𓊂����A��҂͖��𗎂Ƃ��B���̌��I�ȏ�ʂ� �`������i�ł��B��ʂł́A�]��������Ԃ���l�X�i��Ԃ��䂷�p�G�g���ƃz�������j�����ɓ����o����A�p�G�g�����^���t���܂ɑ��Ă����A����҂͉_�ɂ����݂����Ƃ��Ă��܂��B���̐l���Ɠ����̑̐��͋����قǑ��l�ł��B�������A���̗l�q�̓|�[�Y�ߏ�Ƃ�����قǂŁA�}���K�`�b�N�Ȃقǂ킴�Ƃ炵���B�����̐l����n�A�n�ԂȂǂ̂��ׂĂ̗v�f���ӓ�Ԃ̂悤�ł���Ȃ���A���z�̌��ւƉQ�������ď㏸���A����ɂ͉����ւƗ������铮���ɓ��������悤�ɔz�u����A��u�̔ߌ��I�Ȍ������Ɏ��ʂ���悤�ɂȂ��āA���ꂪ����҂Ɍ������ĉ�ʂ��甲���o���Ĕ����Ă���悤�ɍ\������Ă��܂��B�܂�A���ꂾ���ӓׂƂ��Ă���悤�ȁA�ɒ[�ȃ|�[�Y�̐l��n�����藐��ł���Ȃ���A��ʉE�ォ�獶���ɑΊp����ɍ������ɕ��Ԃ悤�ɔz�u����邱�ƂŁA�ӊO�ȂقǃV���v���ȍ\���ɂȂ��Ă���̂ŁA����҂͂���ɂ��������āA�����ǂ�������悤�Ɍ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B����ɂ��Ă��A�X�̐l��n�̕`���������Ă���Ɩʔ����B�Ⴆ�A��ʉE��̔��n������Ђ˂��đO�����������グ�Ă���|�[�Y�ȂǁA���ۂɂ���قǎ���Ђ˂邱�Ƃ��ł���̂�������Ȃ��قNjɒ[�ł����A���Ă��݂�������قNjt���ĂĂ���l�����I��
�`������i�ł��B��ʂł́A�]��������Ԃ���l�X�i��Ԃ��䂷�p�G�g���ƃz�������j�����ɓ����o����A�p�G�g�����^���t���܂ɑ��Ă����A����҂͉_�ɂ����݂����Ƃ��Ă��܂��B���̐l���Ɠ����̑̐��͋����قǑ��l�ł��B�������A���̗l�q�̓|�[�Y�ߏ�Ƃ�����قǂŁA�}���K�`�b�N�Ȃقǂ킴�Ƃ炵���B�����̐l����n�A�n�ԂȂǂ̂��ׂĂ̗v�f���ӓ�Ԃ̂悤�ł���Ȃ���A���z�̌��ւƉQ�������ď㏸���A����ɂ͉����ւƗ������铮���ɓ��������悤�ɔz�u����A��u�̔ߌ��I�Ȍ������Ɏ��ʂ���悤�ɂȂ��āA���ꂪ����҂Ɍ������ĉ�ʂ��甲���o���Ĕ����Ă���悤�ɍ\������Ă��܂��B�܂�A���ꂾ���ӓׂƂ��Ă���悤�ȁA�ɒ[�ȃ|�[�Y�̐l��n�����藐��ł���Ȃ���A��ʉE�ォ�獶���ɑΊp����ɍ������ɕ��Ԃ悤�ɔz�u����邱�ƂŁA�ӊO�ȂقǃV���v���ȍ\���ɂȂ��Ă���̂ŁA����҂͂���ɂ��������āA�����ǂ�������悤�Ɍ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B����ɂ��Ă��A�X�̐l��n�̕`���������Ă���Ɩʔ����B�Ⴆ�A��ʉE��̔��n������Ђ˂��đO�����������グ�Ă���|�[�Y�ȂǁA���ۂɂ���قǎ���Ђ˂邱�Ƃ��ł���̂�������Ȃ��قNjɒ[�ł����A���Ă��݂�������قNjt���ĂĂ���l�����I�� �����A�r���ۂ��������ɖ����Ă��āA�u�Ԃ��ɒ[�Ƀf�t�H���������悤�ȃ|�[�Y�ł��B���̑��̐l��n�̃|�[�Y�́A�Ⴆ�A�~�P�����W�F�����u�Ō�̐R���v�i�E�}�j�̂悤�Ƀ��A���Ȑl�̐g�̂̓����ȏ�ɓ���̓r���̎p�̈�u�����o���āA����ɉ��o��������|�[�W���O�������悤�Ȃ̂ɏK�����悤�Ȋ����ł��B�������ʂ̌��̐��Ƃ������i������̂ŁA���̏�ŌX�̐l��n���_�Ȏ��������݂��B����ł́A���̍�i�͍\�}�����p�̏K��ł͂Ȃ����������q�ׂĂ��܂����A�M�̓��������J�Ɏd�グ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�����r���ۂ��āA���ꂪ�r�X������������ł��܂��B
�����A�r���ۂ��������ɖ����Ă��āA�u�Ԃ��ɒ[�Ƀf�t�H���������悤�ȃ|�[�Y�ł��B���̑��̐l��n�̃|�[�Y�́A�Ⴆ�A�~�P�����W�F�����u�Ō�̐R���v�i�E�}�j�̂悤�Ƀ��A���Ȑl�̐g�̂̓����ȏ�ɓ���̓r���̎p�̈�u�����o���āA����ɉ��o��������|�[�W���O�������悤�Ȃ̂ɏK�����悤�Ȋ����ł��B�������ʂ̌��̐��Ƃ������i������̂ŁA���̏�ŌX�̐l��n���_�Ȏ��������݂��B����ł́A���̍�i�͍\�}�����p�̏K��ł͂Ȃ����������q�ׂĂ��܂����A�M�̓��������J�Ɏd�グ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�����r���ۂ��āA���ꂪ�r�X������������ł��܂��B
�u���Q�I���M�E�X�Ɨ��v�i���}�j�Ƃ�����i�́A�W�����̂Ȃ��łЂƂ���ڗ����Ă��܂����B����ł̓��[�x���X�̍�Ƃ����Ƃ���ɁH���t����Ă��āA�{�l�̍삩�ǂ����^�₪����悤�ł��B�����薼�Ńv���h���p�قɂ���̂͐^��Ƃ������ƂŗL���炵���ł����A��Ńl�b�g�Œ��ׂĂ݂��A�����v���h���p�ق̍��i�E�}�j�Ɣ�ׂ�ƁA�������̕�����_�Ŕj�i�Ȃ��߁A�{�l�̍삩�ǂ����^�킵���v���͓̂��R�Ǝv���܂��B����i�͍\����\�}�͂�������� �悤�ł����A���炩�Ƀv���h���p�ق̍�i�̕����l��n�ɓ������������邵�A���������Ƃ��Ă���B����ɔ�ׂāA�������̍�i�̐l��n�͗ތ^�I�ŁA���ꎩ�̂Ƀ_�C�i�~�b�N�Ȗ��������Ȃ��āA�p�^�[�����Ȃ����Ă���Ƃ��낪����܂��B������Ƒ}�G�Ƃ������C���X�g���ۂ����������܂��B���ꂾ���ɖ��m�ɉ���������Ă��邩�킩��₷���Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B���ȃp���f�B������Ă��邩�̂悤�ɁA���[�x���X�̉�ʂ̂��肪��������̂ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�[�I�Ɍ����ƁA�\���͂������ăV���v���ŁA����҂͎��������̃V���v�����ɓ������̂ŁA��������͂��܂���B���̏�ŁA��ʂ̋�Ԃߐs�����悤�Ɏ�����`������ł����B����͐��ʂŖ��ߐs�����ꍇ������A�X�̎���������ɂ��邱�ƂŖ��ߐs�����ꍇ������܂��B������ɂ���{�����[���ň��|����킯�ł��B�����ɁA�F�ʂ�A�����̎����̑�_�ȃ|�[�Y�ŕ��G�ő����Ȉ�ۂݏo���B����҂�ދ������Ȃ��B���������Ƃ��낪�A�������̍�i�̓X�g���[�g�ɁA���ɒ[�ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B�F�ʂ́A���A���Ƃ��������Ƃ�ʂ�z���āA�h��Ō��h��������悤�ɂȂ��Ă��āA����ō�i���ڗ����Ă��܂��B���邢�́A�����̍b�h�p�̐��Q�I���M�E�X�̎p�́A�v���h���p�ق̍�i�Ɠ����|�[�Y�ł����A�����Ə㔼�g���o�����X�������قǑ傫���ċɒ[�ȃf�t�H�������{����Ă��܂��B���̗��Ƃ̋������ڋ߂������Ă��āA����ŋR�n�ł̐킢���ł���̂��Ƃ����قǂł��B��̕����͎Ȃ��قǏ�̂ɂ������Ă��܂��B�������A����ŁA��Ə�̂̕����Ɍ���҂̎����͏W�܂�܂��B���ꂾ���A���Q�I���M�E�X�̋��傳���A�������R���Ƃ��Ƃ�����܂߂čۗ��������Ă��܂��B���[�x���X�Ƃ����l�́A����������炳�܂łȂ��A����C�Ȃ��A����ƋC�t���Ȃ��悤�Ɏ{���Ă���B�������������̓v���h���p�ق̍�i�ɂ悭������Ǝv���܂��B�������������́A���[���b�p�Ɖ�������āA�����I�ȃ��[�c�̈قȂ���{�ł́A�p���ĕ��������̂ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B
�悤�ł����A���炩�Ƀv���h���p�ق̍�i�̕����l��n�ɓ������������邵�A���������Ƃ��Ă���B����ɔ�ׂāA�������̍�i�̐l��n�͗ތ^�I�ŁA���ꎩ�̂Ƀ_�C�i�~�b�N�Ȗ��������Ȃ��āA�p�^�[�����Ȃ����Ă���Ƃ��낪����܂��B������Ƒ}�G�Ƃ������C���X�g���ۂ����������܂��B���ꂾ���ɖ��m�ɉ���������Ă��邩�킩��₷���Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B���ȃp���f�B������Ă��邩�̂悤�ɁA���[�x���X�̉�ʂ̂��肪��������̂ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�[�I�Ɍ����ƁA�\���͂������ăV���v���ŁA����҂͎��������̃V���v�����ɓ������̂ŁA��������͂��܂���B���̏�ŁA��ʂ̋�Ԃߐs�����悤�Ɏ�����`������ł����B����͐��ʂŖ��ߐs�����ꍇ������A�X�̎���������ɂ��邱�ƂŖ��ߐs�����ꍇ������܂��B������ɂ���{�����[���ň��|����킯�ł��B�����ɁA�F�ʂ�A�����̎����̑�_�ȃ|�[�Y�ŕ��G�ő����Ȉ�ۂݏo���B����҂�ދ������Ȃ��B���������Ƃ��낪�A�������̍�i�̓X�g���[�g�ɁA���ɒ[�ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B�F�ʂ́A���A���Ƃ��������Ƃ�ʂ�z���āA�h��Ō��h��������悤�ɂȂ��Ă��āA����ō�i���ڗ����Ă��܂��B���邢�́A�����̍b�h�p�̐��Q�I���M�E�X�̎p�́A�v���h���p�ق̍�i�Ɠ����|�[�Y�ł����A�����Ə㔼�g���o�����X�������قǑ傫���ċɒ[�ȃf�t�H�������{����Ă��܂��B���̗��Ƃ̋������ڋ߂������Ă��āA����ŋR�n�ł̐킢���ł���̂��Ƃ����قǂł��B��̕����͎Ȃ��قǏ�̂ɂ������Ă��܂��B�������A����ŁA��Ə�̂̕����Ɍ���҂̎����͏W�܂�܂��B���ꂾ���A���Q�I���M�E�X�̋��傳���A�������R���Ƃ��Ƃ�����܂߂čۗ��������Ă��܂��B���[�x���X�Ƃ����l�́A����������炳�܂łȂ��A����C�Ȃ��A����ƋC�t���Ȃ��悤�Ɏ{���Ă���B�������������̓v���h���p�ق̍�i�ɂ悭������Ǝv���܂��B�������������́A���[���b�p�Ɖ�������āA�����I�ȃ��[�c�̈قȂ���{�ł́A�p���ĕ��������̂ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B
 ���J��W�����_�[�m���u�p�g���X���̕������L�Ґ����n�l�v�i���}�j�Ƃ�����i�́A���[�x���X�ȊO�̉�Ƃ����[�x���X���ɕ`������i�ƌ�����Ǝv���܂��B���̐l�́A�Z���X����������Ă��āA���[�x���X�̂悤�ȃS�e�S�e�ƃe���R����ɂ����悤�ȃ{�����[�����������Ȃ��āA�X�b�L���Ƃ�����ʂɂȂ��Ă��܂��B
���J��W�����_�[�m���u�p�g���X���̕������L�Ґ����n�l�v�i���}�j�Ƃ�����i�́A���[�x���X�ȊO�̉�Ƃ����[�x���X���ɕ`������i�ƌ�����Ǝv���܂��B���̐l�́A�Z���X����������Ă��āA���[�x���X�̂悤�ȃS�e�S�e�ƃe���R����ɂ����悤�ȃ{�����[�����������Ȃ��āA�X�b�L���Ƃ�����ʂɂȂ��Ă��܂��B
�Z�D���ӂƋ��ӓI���b
�Ō�̓W���R�[�i�[�́A�����镨���ł��B����Ƃ����Ӗ��Â�������A�Ⴆ�^�u�[�ł��������̉���������Ƃ����̂ŁA�M���̎���������Ƃ��A���������������ɉ����Đ��삳�ꂽ���̂ƌ����܂��B���������Ӗ���[�ǂ݂��Ċӏ܂���̂������̂ł��傤���A�ׂɂ��̂悤�ȕ��������Ȃ��Ă��ʔ�����i���W������Ă��܂��B
 �u�G���N�g�j�I�X������P�N���v�X�̖������v�i�E�}�j�Ƃ�����i�B��Q�~�Rm�Ƃ����A���̓W���R�[�i�[�̒��ł͑傫�ȍ�i�ł��B���[�x���X�̍�i�̒��ł́A�������قlj�ʂ��쉢�̖L���Ȍ��Ɉ�ꂽ�悤�Ȗ��邢��ʂŁA���Ɖe�̑ΏƂ͉e����߂āA���邭�J�����҂낰�ȉ�ʂł��B�o���b�N���p�Ƃ�����胋�l�T���X�̋ύt�̂Ƃꂽ�悤�ȉ��₩�ȉ�ʂł��B�����������Ñ㒤���̂悤�Ȏp�ł��B�L�A�X�N�[���܂ł͂����Ȃ��܂ł��A���J�Ŋ��炩�ȕM�v�ŕ`����Ă��āA�W���̝{��������ɑ���������i���Ǝv���܂��B���낢��ȃM���V���_�b�Ɋ�Â��V���{�������낢���ʂɎ�������Ă���悤�ł����A���[�x���X�炵�������������\���邾���ŏ\���ȍ�i�ł��B���l�T���X���Ƃ͂����Ȃ���A�����͂���ς胋�[�x���X�ŁA�����̗��̂͋ؓ��ŃS�c�S�c���Ă���痂����ł����A��ʉE�̌�p�̏������\���̖L�����Ȃǂ̓��[�x���X�炵�����A�����̘V�k�̊�Ȃǂ́A�����I�ȘV�k�̃��A���Ȋ�ł��B
�u�G���N�g�j�I�X������P�N���v�X�̖������v�i�E�}�j�Ƃ�����i�B��Q�~�Rm�Ƃ����A���̓W���R�[�i�[�̒��ł͑傫�ȍ�i�ł��B���[�x���X�̍�i�̒��ł́A�������قlj�ʂ��쉢�̖L���Ȍ��Ɉ�ꂽ�悤�Ȗ��邢��ʂŁA���Ɖe�̑ΏƂ͉e����߂āA���邭�J�����҂낰�ȉ�ʂł��B�o���b�N���p�Ƃ�����胋�l�T���X�̋ύt�̂Ƃꂽ�悤�ȉ��₩�ȉ�ʂł��B�����������Ñ㒤���̂悤�Ȏp�ł��B�L�A�X�N�[���܂ł͂����Ȃ��܂ł��A���J�Ŋ��炩�ȕM�v�ŕ`����Ă��āA�W���̝{��������ɑ���������i���Ǝv���܂��B���낢��ȃM���V���_�b�Ɋ�Â��V���{�������낢���ʂɎ�������Ă���悤�ł����A���[�x���X�炵�������������\���邾���ŏ\���ȍ�i�ł��B���l�T���X���Ƃ͂����Ȃ���A�����͂���ς胋�[�x���X�ŁA�����̗��̂͋ؓ��ŃS�c�S�c���Ă���痂����ł����A��ʉE�̌�p�̏������\���̖L�����Ȃǂ̓��[�x���X�炵�����A�����̘V�k�̊�Ȃǂ́A�����I�ȘV�k�̃��A���Ȋ�ł��B
�u�}���X�ƃ��A�E�V�����B�A�v�i�����}�j�Ƃ�����i�ł��B�Q�~�Q.�Vm�̔�r�I�傫�ȍ�i�ƁA�����炭���^�̂悤�ȉ��������낤�����ȍ�i�̂Q�_�����ׂēW������Ă��܂����B�摜�͑傫�Ȃق��ł��B�����ȍ�i�̕����A�����̕\����G�ŁA��������Ċ������̂ƕs���Ō˘f���Ă���̂ƁA�����Ɏ���悤�ȕ\������Ă���̂ƁA�����̈ߕ��������ʂ�悤�ɏ_�炩���`����Ă���̂��Ⴂ�܂��B������̑傫���ق��̍�i�ł́A�����͐Ȃ��悤�ȕ\������Ă��܂��B�܂��ߑ��͕����I�ȑ��݊����悭��������悤�ɕ`����Ă��܂��B���̂悤�ɂ�������ƕ`����Ă���̂́A����ς��肢�Ǝv���܂��B
 ���[�x���X�Ƃ�����Ƃ͊G�M�������X�s�[�h�ł������Ɠ����Ă��܂��悤�ȁA�`���̂��I�݂Ȑl�ŁA��ƂƂ����̂͂����������ƂɏG�łĂ��邩���ƂɂȂ����̂œ�����O�̂��ƂȂ̂�������܂��A���̒��ł���ۏG�łĂ����l�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����ɂ��ւ�炸�A���̐l�́A����蕨�ɂ��Ȃ��ŁA��ʐv�Ƃ��\���ŏ��������l�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂪ�������ꂽ�̂́A�@����̂悤�ȋK�͂̑傫�ȑ��ʂł��B����͑吨�̐E�l���w�����ĕ`������H�[���o�c����Ƃ��������I�ȗv�����炫�Ă���̂�������܂��B�����������[�x���X�̍�i���A���n�Ō����ڊ�ɂ��邱�Ƃ��ł����A�ʐ^�Ȃǂ̕����ŏk���Đ��Y���ꂽ���̂����邵���Ȃ����{�ł́A�Ȃ��Ȃ����͂ɐG��邱�Ƃ͓����Ƃł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����̓x���X�P�X�Ȃǂ�������Ӗ��ŁA���{�ł͐e���ݓ��Ƃ������Ǝv���܂��B�����o���b�N�̉�Ƃł��A�J�����@�b�W���̂悤�Ȍ��Ɖe�̑ΏƂ̌��I���ʂɓ��������悤�ȉ�Ƃł���A���̓��������m�ŃR�s�[�ł��\�������ł���̂ł����B���[�x���X�̏ꍇ�́A���ՓI�Ƃ������Ă�������A���[���b�p�ł͎����̂��ƂȂ̂ł��傤���A���ꂪ�����ł͂Ȃ����{�ł́A�������Ă��炦��y�낪����Ă��Ȃ������B����ŁA�����ł��邱�Ƃ͉\�ɕ����Ă��Ă��Ă��A��i�̓����͂ǂ��ɂ���̂��A�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B���[���b�p�I�ȊG�炵���̂��낤�A���炢�������Ǝv���܂��B���̊����ł́A�K�̓��̐��ꉺ�������悤�ȃS�c�S�c���������̗��̉���݂āA�����ɗ��z�I�Ŕ������Ƃ͎v���܂��A���ꂪ���[�x���X�I�ȁA���[���b�p�I�Ȋ����Ȃ̂��낤�Ƒz�����邱�Ƃ͂ł���悤�ɂȂ�܂����B����ȊO�ɁA���́A���̐l�͂��Ȃ�m�I�ȍ�i��`���Ă����Ƃ������Ƃ��A���̓W���Ŋ����邱�Ƃ��ł��܂����B
���[�x���X�Ƃ�����Ƃ͊G�M�������X�s�[�h�ł������Ɠ����Ă��܂��悤�ȁA�`���̂��I�݂Ȑl�ŁA��ƂƂ����̂͂����������ƂɏG�łĂ��邩���ƂɂȂ����̂œ�����O�̂��ƂȂ̂�������܂��A���̒��ł���ۏG�łĂ����l�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����ɂ��ւ�炸�A���̐l�́A����蕨�ɂ��Ȃ��ŁA��ʐv�Ƃ��\���ŏ��������l�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂪ�������ꂽ�̂́A�@����̂悤�ȋK�͂̑傫�ȑ��ʂł��B����͑吨�̐E�l���w�����ĕ`������H�[���o�c����Ƃ��������I�ȗv�����炫�Ă���̂�������܂��B�����������[�x���X�̍�i���A���n�Ō����ڊ�ɂ��邱�Ƃ��ł����A�ʐ^�Ȃǂ̕����ŏk���Đ��Y���ꂽ���̂����邵���Ȃ����{�ł́A�Ȃ��Ȃ����͂ɐG��邱�Ƃ͓����Ƃł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����̓x���X�P�X�Ȃǂ�������Ӗ��ŁA���{�ł͐e���ݓ��Ƃ������Ǝv���܂��B�����o���b�N�̉�Ƃł��A�J�����@�b�W���̂悤�Ȍ��Ɖe�̑ΏƂ̌��I���ʂɓ��������悤�ȉ�Ƃł���A���̓��������m�ŃR�s�[�ł��\�������ł���̂ł����B���[�x���X�̏ꍇ�́A���ՓI�Ƃ������Ă�������A���[���b�p�ł͎����̂��ƂȂ̂ł��傤���A���ꂪ�����ł͂Ȃ����{�ł́A�������Ă��炦��y�낪����Ă��Ȃ������B����ŁA�����ł��邱�Ƃ͉\�ɕ����Ă��Ă��Ă��A��i�̓����͂ǂ��ɂ���̂��A�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B���[���b�p�I�ȊG�炵���̂��낤�A���炢�������Ǝv���܂��B���̊����ł́A�K�̓��̐��ꉺ�������悤�ȃS�c�S�c���������̗��̉���݂āA�����ɗ��z�I�Ŕ������Ƃ͎v���܂��A���ꂪ���[�x���X�I�ȁA���[���b�p�I�Ȋ����Ȃ̂��낤�Ƒz�����邱�Ƃ͂ł���悤�ɂȂ�܂����B����ȊO�ɁA���́A���̐l�͂��Ȃ�m�I�ȍ�i��`���Ă����Ƃ������Ƃ��A���̓W���Ŋ����邱�Ƃ��ł��܂����B