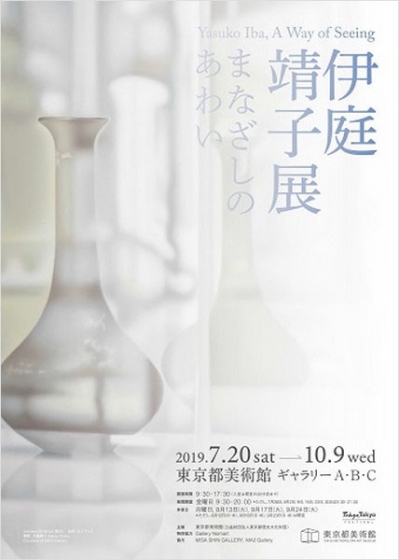2019年7月26日(金) 東京都美術館
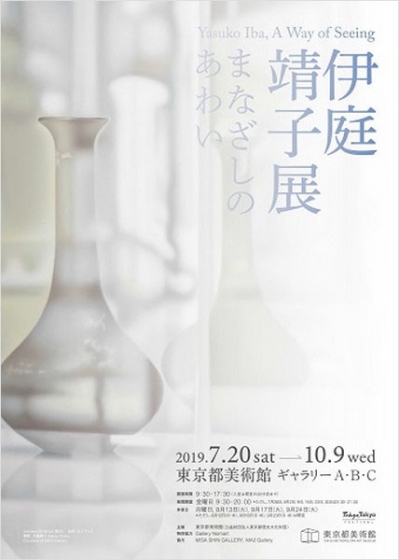 この本州の南で熱帯低気圧が発生し、台風となって今夜にも上陸との予報。昨日までは、いよいよ天気が好転して梅雨明けなどと言っていたのに。しかし、以前から今夕は東京駅近くで約束があるので出かけざるを得ない。台風が接近しているにもかかわらず、昼間は快晴で、真夏の日差しが暑い。これなら、生けると考え、約束の時間よりはやめに都心に出て、上野に寄ることにした。上野公園は夏休みに入ったばかりで、天気もよかったので人は多かった。西洋美術館などは入場券売り場に長蛇の列ができていたので、パス。この先の東京都美術館は、対照的に静かで閑散としていた。この展覧会の案内も目立たないので、暇そうな総合受付にきくと、奥のギャラリーだという。入場券はギャラリーの入口で、エスカレータを降りて展示室へ。入場者は少なく、展示室が細かく仕切られているため、その要所で係員が案内してくれるので、係員と入場者は同数くらいという静かな雰囲気。それは、展示されている作品の雰囲気に似合う感じ、個々の作品もそうだけれど、全体としての空気感が、入場者を含めて一貫していて、入場者はそこに知らないうちにコミットしている、という展覧会だった。
この本州の南で熱帯低気圧が発生し、台風となって今夜にも上陸との予報。昨日までは、いよいよ天気が好転して梅雨明けなどと言っていたのに。しかし、以前から今夕は東京駅近くで約束があるので出かけざるを得ない。台風が接近しているにもかかわらず、昼間は快晴で、真夏の日差しが暑い。これなら、生けると考え、約束の時間よりはやめに都心に出て、上野に寄ることにした。上野公園は夏休みに入ったばかりで、天気もよかったので人は多かった。西洋美術館などは入場券売り場に長蛇の列ができていたので、パス。この先の東京都美術館は、対照的に静かで閑散としていた。この展覧会の案内も目立たないので、暇そうな総合受付にきくと、奥のギャラリーだという。入場券はギャラリーの入口で、エスカレータを降りて展示室へ。入場者は少なく、展示室が細かく仕切られているため、その要所で係員が案内してくれるので、係員と入場者は同数くらいという静かな雰囲気。それは、展示されている作品の雰囲気に似合う感じ、個々の作品もそうだけれど、全体としての空気感が、入場者を含めて一貫していて、入場者はそこに知らないうちにコミットしている、という展覧会だった。
いつものことながら、この作家のことは、何の予備知識もなく、どういう人かは分からないので、その紹介もかねて、主催者のあいさつを引用します。“画家の眼とモティーフのあわいにある世界に魅せられた伊庭靖子(1967-)は、触れたくなるようなモティーフの質感やそれがまとう光を描くことで、その景色を表現し続けてきました。自ら撮影した写真をもとに制作するスタイルは変わりませんが、近年、それまで接近していたモティーフとの距離が少しずつ広がってきました。空間や風景への関心が高まり、まわりの風景が広がることで、伊庭の絵画は新たな展開を見せています。東京都美術館で撮影した写真をもとにした絵画をはじめ、版画、さらに新たな試みとして映像作品を発表します。伊庭の個展は、2009年の「伊庭靖子──まばゆさの在処──」(神奈川県立近代美術館)以来、美術館では10年ぶりの開催となります。本展覧会では、近作・新作を中心に紹介しながら、そこに至る以前の作品も併せて展示することで、この10年の変化とともに伊庭靖子の変わらない関心の核に迫ります。”ということで、どうやら、この人は対象を写真に撮って、それをもとに描くというやり方の人のようだということは分かりました。展覧会チラシに引用されている壺を描いた作品は、写真の露光の技法、二重露光とか焦点のぼかしを使ったものをキャンバスに写し替えたのか、ちょっと違う気がする。などと思いながら、展示室に入りました。展示されているスペースは広いギャラリーの室内をコーナーごとに区画し、広間はパーティーションで小さく区切られ、そのコーナーごとに、ひとつのシリーズをまとめて展示するようになっていて、コーナーから次のコーナーに行くのに、案内の係員がいて、導いてくれるようになっていました。
 Ⅰ
Ⅰ
最初のコーナーは、階段の踊り場のようなテラスになっているスペースにはクッション寝具のシリーズというのが展示されていました。たとえば、「Untitled2009-01」(右図)という作品。これは、画像では分かりませんが、展示室の壁にかけられていると見上げてしまうほど大きな作品です。それが、クッションの角の部分を接写したようなものが、この大画面でいっぱいに描かれています。これはクッションの形には興味がなくて、その表面に対して、見るというよりも触るような感覚で接したいのではないか、という感じがしました。それは、接近するにしても、そのアングルがクッションの形を捉えるというのではなくて、それだったら正面からにすればいいのに、そうことはなくて、角のところを斜めから捉えている。これは、最初から部分しか見ようとしていないと思えるからです。そうやって部分を拡大するように、接近して、よく見えてくるのか、クッションの表面です。さっき触れると述べましたが、表面の布地の柔らかくてフワフワした、ちょっとささくれ立っているような感じ、それがクッション表面を拡大したことで表面の細かい繊維の感じなどが顕微鏡でみるように細かく描かれているように見えます。その布地がクッションの形につくられていて、ちょうど角の縫い合わされたところでは、平面の布地が曲げられて部分的に襞のように皺がよっている。それが布地の表面に凸凹の変化をつくり、光と影を、そして表面の感触が変化する。さらに、花柄の模様が刺繍されていて、刺繍の糸が表面の布地とはちがった質感で表面から盛り上がっている。しかも、色彩も違う。その対象と、模様も、布地の襞にあわせてその形が歪んで、そこに光と影ができ色彩も変化する。それが静物であるはずなのにダイナミックな動感を作り出している。そういう、具象でありながら、抽象画を見ているようなイメージにとらわれるのでした。

 「Untitled2006-06」(左図右)と「Untitled2007-01」(左図左)というふたつの作品を並べて見ると、クッションの刺繍の模様の柄が同じで、色違いになっているので、そういう襞による変化を対照して見比べることができます。
「Untitled2006-06」(左図右)と「Untitled2007-01」(左図左)というふたつの作品を並べて見ると、クッションの刺繍の模様の柄が同じで、色違いになっているので、そういう襞による変化を対照して見比べることができます。
ところで、私たちは日頃クッションに対して、どのように接しているでしょうか。リビングのソファーなんかに置いてあって、インテリアの一部になっていたりしますが、それを眺めたりはしないでしょう。座るときに下に敷いたり、寝転がるときに枕にしたり、手持ち無沙汰の時には弄んだり、機嫌が悪いときは八つ当たりして投げ飛ばしたりなどなど。それらのときには、必ず手で持ったり、身体の下に敷いたり、身体で触れています。その柔らかくて、フワフワした感触を感じている。そういう時に視覚に入ってくるのは、枕として頭の下でへこんでいて、隅がはみでているように見えていたり、のような一部のみが、もとの形から変形して、襞や皺が強調されるような様子です。それは、ここで展示されている作品のクッションの一部しか描かれていないとか、襞が光と影で動感が生まれているのと、何か似ている、通じているように思えるのです。
Ⅱ
次のコーナーは、最初のコーナーからエスカレータの反対側の小部屋で、テラスの開放的な空間から、低い天井の狭い空間に環境が変わります。そのため、ちょっと閉塞感がある。そこに、白いパーティーションで区画をつくって、長方形の部屋を曲がり角のある展示コースのように空間をしつらえてありました。ここでは器のシリーズというのが展示されていました。最初のコーナーとは打って変わって比較的小さなサイズの作品で、中には水彩の作品もありました。ところが、その水彩の作品と油彩の作品の区別がよく分からないのです。この人は油絵を水彩のように使っているといえばいいのでしょうか。薄く溶いた絵の具を透き通るような感じで、油絵の具の物質感があまりなくて、色彩に芯がな くてフワフワ漂っているような感じが、水彩絵の具のにじんだりぼけたりする感じと、区別がつきにくくなっている。そういうので陶器の器をモティーフに描いた作品です。「Untitled2012-02」(右図)という作品。陶器の物質感というか光を遮って、つるつるの冷たい感触のモノとして在るという感じがしなくて、ガラスの透明な器に色で模様をつけたような感じがあります。ここで、さっきまでのクッションのシリーズとは、なんか違う。その違いはけっこう大きい。そう感じたのですが、それというのも、この作品では、これまで見てきたクッションのシリーズとは違って、器の形、つまり全体像がはっきり分かるのです。つまり、クッションのときのような布地の感触が目に見えるような接写ではなくて、少し距離をおいて器のかたちを画面に収めているのです。その代わりにクッションのシリーズの触覚的な質感が稀薄になってしまっている。それが、さっきも少し述べた陶器の物質感というか光を遮って、つるつるの冷たい感触のモノとして在るという感じがしないということです。その代わりに、クッションでは襞という表面の歪みが光と影をつくりだしていましたが、ここでは、襞による光と影ではなくて、というのも陶器の表面に襞はできないでしょうから、つるつるとして表面を光の反射バリエーション、つまり、光が反射して光るところと、それほどあたらないで影になる、しかも、器に水が少し入れられているみたいに光を吸い込んで通しているところと、その光への対し方の違いで変化つくっています。それゆえに、陶器の物質というよりも、その光に対している表面が、結果として器の形に見えるという。それゆえに、物質感というより、光に映っているように見えている。
くてフワフワ漂っているような感じが、水彩絵の具のにじんだりぼけたりする感じと、区別がつきにくくなっている。そういうので陶器の器をモティーフに描いた作品です。「Untitled2012-02」(右図)という作品。陶器の物質感というか光を遮って、つるつるの冷たい感触のモノとして在るという感じがしなくて、ガラスの透明な器に色で模様をつけたような感じがあります。ここで、さっきまでのクッションのシリーズとは、なんか違う。その違いはけっこう大きい。そう感じたのですが、それというのも、この作品では、これまで見てきたクッションのシリーズとは違って、器の形、つまり全体像がはっきり分かるのです。つまり、クッションのときのような布地の感触が目に見えるような接写ではなくて、少し距離をおいて器のかたちを画面に収めているのです。その代わりにクッションのシリーズの触覚的な質感が稀薄になってしまっている。それが、さっきも少し述べた陶器の物質感というか光を遮って、つるつるの冷たい感触のモノとして在るという感じがしないということです。その代わりに、クッションでは襞という表面の歪みが光と影をつくりだしていましたが、ここでは、襞による光と影ではなくて、というのも陶器の表面に襞はできないでしょうから、つるつるとして表面を光の反射バリエーション、つまり、光が反射して光るところと、それほどあたらないで影になる、しかも、器に水が少し入れられているみたいに光を吸い込んで通しているところと、その光への対し方の違いで変化つくっています。それゆえに、陶器の物質というよりも、その光に対している表面が、結果として器の形に見えるという。それゆえに、物質感というより、光に映っているように見えている。
 それを、描くという面で見ていくと、クッションの作品では、淡い色彩のグラデーションによって柔らかい感触を作り出していたのが、この作品では、色彩のバリエーションは抑えられて、白(クリーム色)と青の二色に限定されていて、しかも、ほとんど画面は白の部分で占められています。見方によれば、青はその白を引き立たせるものでしかないように感じられてきます。そう、この作品は、色彩だけでみていくと白のグラデーションとして、光のさまざまな状態を白の濃淡と、かすれやにじみなどと表われていると言えます。そのためにか、作品が展示されている壁面も、本来の煉瓦色のような壁に直接掛けることをせずに、真っ白のパーティションを立てて、そこに掛けてある。さらに照明についても部屋の照明を抑えて、白色のライトを当てている。それは、白のグラデーションをしっかり見せるとともに、作品の画面と同質の空間を展示室に作ろうとしているように思えるのです。この展示空間の工夫については、この後のギャラリーAの展示では、もっとあからさまな様子になります(実は、そこで、私は、そのことに気づいて、その後で、こちらに戻って、なるほどと思ったのです)。
それを、描くという面で見ていくと、クッションの作品では、淡い色彩のグラデーションによって柔らかい感触を作り出していたのが、この作品では、色彩のバリエーションは抑えられて、白(クリーム色)と青の二色に限定されていて、しかも、ほとんど画面は白の部分で占められています。見方によれば、青はその白を引き立たせるものでしかないように感じられてきます。そう、この作品は、色彩だけでみていくと白のグラデーションとして、光のさまざまな状態を白の濃淡と、かすれやにじみなどと表われていると言えます。そのためにか、作品が展示されている壁面も、本来の煉瓦色のような壁に直接掛けることをせずに、真っ白のパーティションを立てて、そこに掛けてある。さらに照明についても部屋の照明を抑えて、白色のライトを当てている。それは、白のグラデーションをしっかり見せるとともに、作品の画面と同質の空間を展示室に作ろうとしているように思えるのです。この展示空間の工夫については、この後のギャラリーAの展示では、もっとあからさまな様子になります(実は、そこで、私は、そのことに気づいて、その後で、こちらに戻って、なるほどと思ったのです)。
 「Untitled2014-11」(左図)という作品。上で述べた傾向が、さらにエスカレートしています。コーヒーカップなんでしょう。絵具の滲みや掠れがさらに目立ち、また絵具が明らかに隆起している箇所もあります。ステイニング、また水墨画としたら言い過ぎでしょうか。大胆なストロークの結果として、画面ではコーヒーカップに見えてくる。そういう作品になってくる。クッションの作品が、クッションを、私たちは日常的には、とくにそれと意識することなく、用いている、それをそのまま描いてみようとしたと言えるのではないかということを述べました。ここでは、私たちは陶器の器やカップを、クッションのようにわざわざ触って冷たく硬い表面を意識しているでしょうか、その表面を触って愛でる人もいるかもしれませんが、それは陶器に特別の愛着を抱いているような人で、ふつうは、とくにそれと意識せずに、そこにお茶を注いだり、食べ物を置いたりする。そのことが主となります。つまり、器の質感も外見も、メインとして認識しているわけではない。そこにある、見えるということで用は足りるわけです。ただ、サイズや全体のかたちが分からないと、器の中のお茶をこぼしてしまうかもしれない。逆にそれは最低限、認識している。そう考えると、この人の描いている画面は、静物画とか芸術の視点とかいうものではなくて、そういう先入観のないところで、日常の生活のなかで、こういうのをどのように認識しているのかを純粋に抽象したといえるのではないかと思えてきました。
「Untitled2014-11」(左図)という作品。上で述べた傾向が、さらにエスカレートしています。コーヒーカップなんでしょう。絵具の滲みや掠れがさらに目立ち、また絵具が明らかに隆起している箇所もあります。ステイニング、また水墨画としたら言い過ぎでしょうか。大胆なストロークの結果として、画面ではコーヒーカップに見えてくる。そういう作品になってくる。クッションの作品が、クッションを、私たちは日常的には、とくにそれと意識することなく、用いている、それをそのまま描いてみようとしたと言えるのではないかということを述べました。ここでは、私たちは陶器の器やカップを、クッションのようにわざわざ触って冷たく硬い表面を意識しているでしょうか、その表面を触って愛でる人もいるかもしれませんが、それは陶器に特別の愛着を抱いているような人で、ふつうは、とくにそれと意識せずに、そこにお茶を注いだり、食べ物を置いたりする。そのことが主となります。つまり、器の質感も外見も、メインとして認識しているわけではない。そこにある、見えるということで用は足りるわけです。ただ、サイズや全体のかたちが分からないと、器の中のお茶をこぼしてしまうかもしれない。逆にそれは最低限、認識している。そう考えると、この人の描いている画面は、静物画とか芸術の視点とかいうものではなくて、そういう先入観のないところで、日常の生活のなかで、こういうのをどのように認識しているのかを純粋に抽象したといえるのではないかと思えてきました。
「Untitled2015-01」(右上図)という作品です。これまで見てきた作品には稀薄だったパースペクティブがはっきりしていて、それぞれの器の位置関係が明確で、それぞれの質感の違いも描き分けられて物質としての存在感があります。普通に静物画です。それが、ここに展示されている作品とは妙に異質に感じられます。何か、形式的というのか、タテマエみたいな印象を受けてしまう。おそらく、この作品だけを取り出せば、モランディのような思索的な性格を湛えた静物画と、何の違和感もないのでしょうが。
Ⅲ
さて、次のコーナーは、小部屋をでて、眼下に大広間のようにひろがっているギャラリーAの展示室をパーテーションで迷路のように仕切っている空間です。前の小部屋とはちがって、この広間では、その作為を隠すことができず、あからさまです。部屋の照明はオレンジ色っぽい色がついているからでしょう点灯されておらず、したがって部屋全体は薄暗い空間で、白いパーティーションで仕切られて、わざと空間を狭くして迷路のように先が見えない、しかし、パーティーションで上方が開かれているために閉塞感はない。上方には薄暗い空間が広がっている。では作品が見えないかというと、各作品の前に白い光のスポットライト照明が当てられています。しかも、その角度やライトの本数などをかなり神経質に考慮されているのではないかと見える節があります。例えば、スポットライトを照明当てると影ができますが、その影の処理をかなり気にしていたり、白い光が作品の画面の白をどのように照らしているかに、かなり気を遣っている様子が見て取れる。しかし、展示されている作品は、前のコーナーの白のバリエーションという色遣いではなくて、たくさんの色を使った多彩な作品です。しかし、そういう展示のしかたから、実は白を主体とした画面なのかもしれないと思えてきました。ということで、作品に当たっていきたいと思います。ここで展示されている作品は、モティーフを透明なア クリルの箱の中に入れて、そこに光が差し込んでくると、アクリルが光を反射して周囲の光景が映ったり、透明に透過したりする。それを撮影して、キャンバスに描き替えたというシリーズだそうです。モティーフとなっている壺には、透明なアクリルボックスをかぶせることで、壺を見ようとすると、アクリルボックスに光が反射したり、前後の像が写り込んだりする。アクリルボックスがあることで、その手前に前後左右の光や風景を中に閉じ込めるような感じになる。壺を見るには、光や写り込んだ風景を一度無視しないといけない。逆に、光の方が気になり始めると壺の存在はふっと消えていくような感覚になる、ということです。展覧会チラシで使われている作品も、そのひとつですね。その前に、「Untitled2016-03」(左図)という作品を見てみましょう。前のコーナーで見た白い地に青の模様が入った陶器をモティーフしているところは同じです。しかし、背景が白一色ではなくなっています。陶器にかぶせた透明のアクリルボックスに映った風景が描かれているということなのでしょうが、陶器の置いてある白い台に陶器の姿が反射して映っていることもあって、画面のすべてが透き通って蜃気楼のように見えてきます。その中で、中央の陶器だけが透き通っていない。陶器のシリーズは狭い空間に展示されていたせいもあるかもしれません。その画面は白一色で完結していたというのか、空間の閉塞感に似た、ひろがりにかけるところが、たしかにあったと思います。それに対して、この作品は、白一色の背景に、ぼんやり映った風景が、重なり合って、それらが透き通っていることで、白一色で閉ざされていた、画面の向こう側が開けた印象がとてもあります。逆に、中心の陶器は、前のシリーズでは物質としての存在感が稀薄で透明な印象だったのが、この作品の壺は冷たい陶器の質感がはっきりしていてモノとしてきっちり描かれています。従って、前のシリーズとは方向性が正反対になっていると言えます。前のコーナーから、次の、このコーナーに移って、真っ先に目に入ってくるところで、この作品を置いたのは、前のコーナーの作品では正反対の方向に、変わっていることをシンボリックに示すものではないか、と深読みしたくなるのですが、そういう変化が、おそらくあると思います。それは、しかし、全体としては、これまでの方向をより極めようとするものであるような気がします。
クリルの箱の中に入れて、そこに光が差し込んでくると、アクリルが光を反射して周囲の光景が映ったり、透明に透過したりする。それを撮影して、キャンバスに描き替えたというシリーズだそうです。モティーフとなっている壺には、透明なアクリルボックスをかぶせることで、壺を見ようとすると、アクリルボックスに光が反射したり、前後の像が写り込んだりする。アクリルボックスがあることで、その手前に前後左右の光や風景を中に閉じ込めるような感じになる。壺を見るには、光や写り込んだ風景を一度無視しないといけない。逆に、光の方が気になり始めると壺の存在はふっと消えていくような感覚になる、ということです。展覧会チラシで使われている作品も、そのひとつですね。その前に、「Untitled2016-03」(左図)という作品を見てみましょう。前のコーナーで見た白い地に青の模様が入った陶器をモティーフしているところは同じです。しかし、背景が白一色ではなくなっています。陶器にかぶせた透明のアクリルボックスに映った風景が描かれているということなのでしょうが、陶器の置いてある白い台に陶器の姿が反射して映っていることもあって、画面のすべてが透き通って蜃気楼のように見えてきます。その中で、中央の陶器だけが透き通っていない。陶器のシリーズは狭い空間に展示されていたせいもあるかもしれません。その画面は白一色で完結していたというのか、空間の閉塞感に似た、ひろがりにかけるところが、たしかにあったと思います。それに対して、この作品は、白一色の背景に、ぼんやり映った風景が、重なり合って、それらが透き通っていることで、白一色で閉ざされていた、画面の向こう側が開けた印象がとてもあります。逆に、中心の陶器は、前のシリーズでは物質としての存在感が稀薄で透明な印象だったのが、この作品の壺は冷たい陶器の質感がはっきりしていてモノとしてきっちり描かれています。従って、前のシリーズとは方向性が正反対になっていると言えます。前のコーナーから、次の、このコーナーに移って、真っ先に目に入ってくるところで、この作品を置いたのは、前のコーナーの作品では正反対の方向に、変わっていることをシンボリックに示すものではないか、と深読みしたくなるのですが、そういう変化が、おそらくあると思います。それは、しかし、全体としては、これまでの方向をより極めようとするものであるような気がします。
 それまでの作品は描く対象をクッションだったり陶器だったりと、それを作家が見て描くという接し方ではなくて、そういう視点を持っていない人が、日頃の振る舞いのなかで、クッションや器をとくに意識することなく接している仕方を、そのまま描くということに置き換えようとしたらああなった、という作品だったと思います。それに対して、ここで展示されている様品は、モティーフにアクリルの透明な箱をかぶせるということをしています。そこで、いままでのように人がモティーフに接するという空間が遮断された。そこで、人がモティーフに接するという関係がなくなった。それによって、人とモティーフが対するのではなくて、同格になったと考えられます。つまり、描いているのはモティーフであり、同時に人であるというように。それは、背景が描かれているのはアクリルの箱の内側と外側の両方です。それが、鏡像のように映しあって何重にも重なって見えたりするのですが。接する方向は外に向かうのと内に向かう。その中心に陶器の壺がある。いわば、クラインの壺のような画面になっている。それを描こうとすれば、その中にいて、それを外から描くということをやっている。そういう作品に見えます。何か、言葉にすると、ややこしくなってしまうように印象ですが。
それまでの作品は描く対象をクッションだったり陶器だったりと、それを作家が見て描くという接し方ではなくて、そういう視点を持っていない人が、日頃の振る舞いのなかで、クッションや器をとくに意識することなく接している仕方を、そのまま描くということに置き換えようとしたらああなった、という作品だったと思います。それに対して、ここで展示されている様品は、モティーフにアクリルの透明な箱をかぶせるということをしています。そこで、いままでのように人がモティーフに接するという空間が遮断された。そこで、人がモティーフに接するという関係がなくなった。それによって、人とモティーフが対するのではなくて、同格になったと考えられます。つまり、描いているのはモティーフであり、同時に人であるというように。それは、背景が描かれているのはアクリルの箱の内側と外側の両方です。それが、鏡像のように映しあって何重にも重なって見えたりするのですが。接する方向は外に向かうのと内に向かう。その中心に陶器の壺がある。いわば、クラインの壺のような画面になっている。それを描こうとすれば、その中にいて、それを外から描くということをやっている。そういう作品に見えます。何か、言葉にすると、ややこしくなってしまうように印象ですが。
そして、チラシにも引用された「Untitled2018-02」(右図)という作品では、中心となっていた花瓶の物質的な存在感が稀薄になり、背景と同じように透明になってしまいました。ここでは、もはや人とモティーフを区別することもなくなってしまった状態。一般論的な言い方にすれば主語と目的語の区別がなくなって、同格になってしまった。だから、この画面に描かれている背景は中心の花瓶が見た(接した)背景でもある、ということになってしまっている。敢えて、見当外れの誹りを覚悟の上でいえば、この作品は触れるとか見るとか、人がモティーフに接することを描いていたそれまでの作品に対して、存在するということを描いている、と感じられます。
Ⅳ
 同じ広い展示室で白いパーティーションで囲われた一画を出るようにして、部屋の出口の壁際の一画です。ここは、雰囲気がかわり、白いパーティーションがなくなります。作品が直接部屋の壁にかけられています。照明も、白いライトが当てられることがなくなりました。作品をとりまく空間が転換したという印象です。作品も変化していますが、なによりも、空間が変わったという印象です。そのために作品対する見方も変わってくるのかもしれません。印象としては、それまでの作品に共通していた、明るさと明晰さ、とくに明晰さというのは透明さに繋がっていると思うのですが。それがなくなって、薄暗い画面になり、全体にヴェールがかかったようなボンヤリとしたものに変わりました。それまでの作品は、たしかに輪郭がはっきりしたというものではありませんでしたが、クッションにせよ陶器にせよ、明晰に描かれていました。しかし、その明晰なものが何重に重ねられたり、淡い色遣いで透き通るように描かれていたので、それと意識することはあまりありませんでした。しかし、モティーフははっきりしていました。また、最初に見たクッションや陶器をモティーフにした作品では、背景というのは描かれていなかった。また、モティーフにアクリルの箱を被せたのを描いた作品では、モティーフとアクリルボックスを基本的に描いているので、背景は、やはりありませんでした。それに対して、例えば「Untitled2018-01」(左図)という作品です。モティーフの陶器は、空間に在るという作品で、相変わらず、陶器が置かれている台とか背後の壁といった具体物は描かれていませんが、現実にあるのではないでしょうけれど、陶器の描かれている以外の画面に縦にヴェールがかけられているように、色分けされている。ここで、今までなかったモ
同じ広い展示室で白いパーティーションで囲われた一画を出るようにして、部屋の出口の壁際の一画です。ここは、雰囲気がかわり、白いパーティーションがなくなります。作品が直接部屋の壁にかけられています。照明も、白いライトが当てられることがなくなりました。作品をとりまく空間が転換したという印象です。作品も変化していますが、なによりも、空間が変わったという印象です。そのために作品対する見方も変わってくるのかもしれません。印象としては、それまでの作品に共通していた、明るさと明晰さ、とくに明晰さというのは透明さに繋がっていると思うのですが。それがなくなって、薄暗い画面になり、全体にヴェールがかかったようなボンヤリとしたものに変わりました。それまでの作品は、たしかに輪郭がはっきりしたというものではありませんでしたが、クッションにせよ陶器にせよ、明晰に描かれていました。しかし、その明晰なものが何重に重ねられたり、淡い色遣いで透き通るように描かれていたので、それと意識することはあまりありませんでした。しかし、モティーフははっきりしていました。また、最初に見たクッションや陶器をモティーフにした作品では、背景というのは描かれていなかった。また、モティーフにアクリルの箱を被せたのを描いた作品では、モティーフとアクリルボックスを基本的に描いているので、背景は、やはりありませんでした。それに対して、例えば「Untitled2018-01」(左図)という作品です。モティーフの陶器は、空間に在るという作品で、相変わらず、陶器が置かれている台とか背後の壁といった具体物は描かれていませんが、現実にあるのではないでしょうけれど、陶器の描かれている以外の画面に縦にヴェールがかけられているように、色分けされている。ここで、今までなかったモ ティーフ以外の部分が描かれている。それは、モティーフを空間に置いたということ、わざわざアクリルの箱という、もうひとつのモティーフを加えないで、という作品です。一般論で言うと、地と図という平面の扱いについて、これまでの作品は図しかなかったのが、はじめて図が表われたといえると思います。おそらく、それと、これらの作品が直接部屋の壁にかけられたのは関係があるように思います。つまり、それまでの作品は、白い展示空間が作品画面では表われなかった地の代わりをしていたのではないかと妄想してしまうのです。しかし、この作品では、画面に地がちゃんと表われたので、展示する壁や空間を配慮する必要がなくなったというわけです。それで、画面を改めて見ると、図だけでなく地も表われたので、作者の注意も図だけだったのが、地にもいくことになり、図をきっちり、細かく描き込むほどの力が届かなくなった。それで陶器にはヴェールがかかってボンヤリしたものとなった。また、背景は得かがれるようになったので、白とするわけにもいかなくなった。私には、これまでの作品を連続して見てきて、ここの展示されている作品で変化を感じて、それまでの作品に比べて、ここで作品では、作者がどこにいるのか隠れてしまったように感じられます。最初に見た作品では、作者はモティーフに寄り添っていました。次の陶器では正対していました。そして、アクリルボックスを被せたことで、モティーフと重なろうとした。しかし、ここでの作品では、モティーフ以外に背景というモティーフのある空間も表わしています。作者には、モティーフ以外に空間にも対するようになっている。そこで、モティーフとの関係が間接的になったような感じがします。それゆえか、モティーフと作者の直接的な関係が見えてこなくなった。その反面、作品は独立して完結したものになってきている感が強くなったと思います。
ティーフ以外の部分が描かれている。それは、モティーフを空間に置いたということ、わざわざアクリルの箱という、もうひとつのモティーフを加えないで、という作品です。一般論で言うと、地と図という平面の扱いについて、これまでの作品は図しかなかったのが、はじめて図が表われたといえると思います。おそらく、それと、これらの作品が直接部屋の壁にかけられたのは関係があるように思います。つまり、それまでの作品は、白い展示空間が作品画面では表われなかった地の代わりをしていたのではないかと妄想してしまうのです。しかし、この作品では、画面に地がちゃんと表われたので、展示する壁や空間を配慮する必要がなくなったというわけです。それで、画面を改めて見ると、図だけでなく地も表われたので、作者の注意も図だけだったのが、地にもいくことになり、図をきっちり、細かく描き込むほどの力が届かなくなった。それで陶器にはヴェールがかかってボンヤリしたものとなった。また、背景は得かがれるようになったので、白とするわけにもいかなくなった。私には、これまでの作品を連続して見てきて、ここの展示されている作品で変化を感じて、それまでの作品に比べて、ここで作品では、作者がどこにいるのか隠れてしまったように感じられます。最初に見た作品では、作者はモティーフに寄り添っていました。次の陶器では正対していました。そして、アクリルボックスを被せたことで、モティーフと重なろうとした。しかし、ここでの作品では、モティーフ以外に背景というモティーフのある空間も表わしています。作者には、モティーフ以外に空間にも対するようになっている。そこで、モティーフとの関係が間接的になったような感じがします。それゆえか、モティーフと作者の直接的な関係が見えてこなくなった。その反面、作品は独立して完結したものになってきている感が強くなったと思います。
Ⅴ
広いギャラリー展示室を出た廊下のようなところに、いままでとは描かれているのものぜんぜん違うし、版画という方法も違う、異質な作品が並んでいました。私は、伊庭という人の作品には、この展覧会がはじめで、この作家を見てきたわけではないので、もともと、どのような作品を制作していたのかわかりませんから、最後近くのコーナーで風景の版画(右図)を見た時には、驚きました。表面がざらざらした感じで、透明さとか明晰さがなくて、この作家の違う面を見たような気がしました。