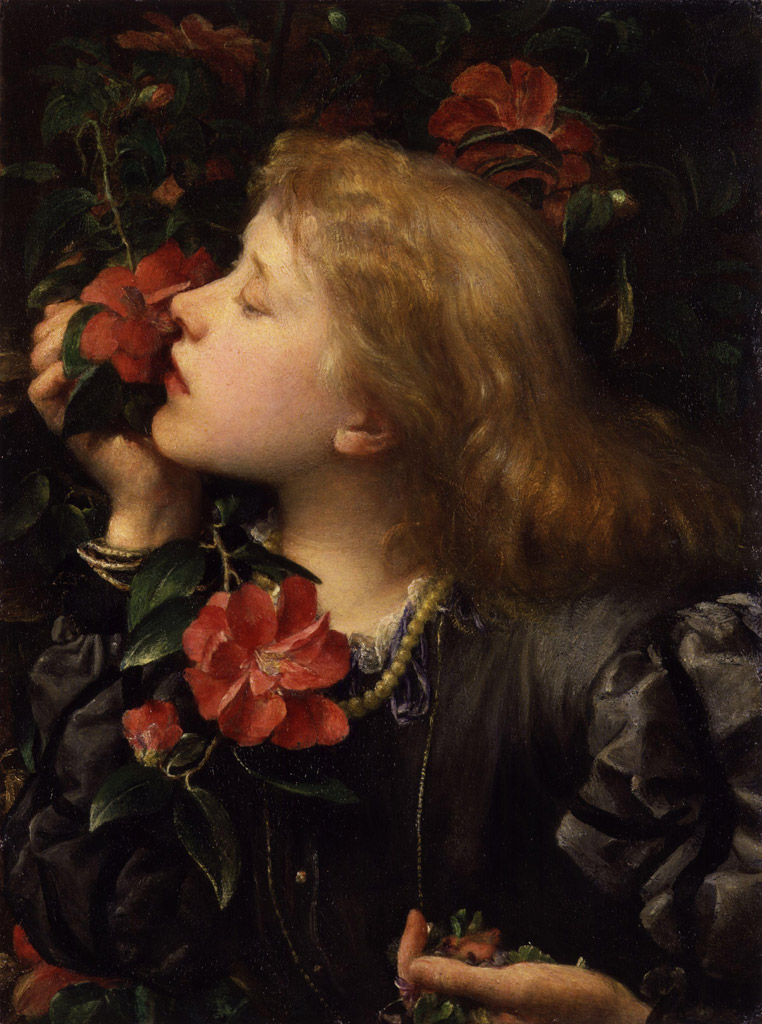|
�O�G���`�[�m�W
��݂�����o���b�N�̉�� |
|
�@ �Q�O�P�T�N�R���P�W���i���j�@�������m���p�� ��N�̂X���ȗ��̒ʉ@���A���N�U��̌����Ōo�߂�����B�傫�ȕω��Ȃ��Ƃ������ƂŁA�P�N��ɗl�q�����܂��傤�Ƃ�����t�̌��t�ɁA�ق��ƈ��S�����B�\�z���Ă�����葁���f�@���I������̂ŁA�����Ԃŏ����������ď��܂ő���L�����B�ꑫ�����t�̂悤�ȃ|�J�|�J�z�C�ŁA�V�C���悩�������߂����̌������͕����Ƃ����̂ɂ��������l�����������B������O���l�̎p�����������悤���B�Ԍ��ł�����̂��낤���B�W����̂́A�����n�܂��ĊԂ��Ȃ��A�����̒��߂��Ƃ������Ƃ������āA�l�e�����Ȃ��A�Â��ɂ�������ƍ�i�����\���邱�Ƃ��ł����B��i�̃T�C�Y���傫���A���̂��߂��W���_�����S�O���_�Ƃ������Ȃ����Ƃ������āA�������Ƃ������͋C���A�Â����Ƒ��ւ��āA�ƂĂ�������������ۂ̓W��������B
�g�O�G���`�[�m�i�P�T�X�P�`�P�U�U�U�N�j�̓C�^���A��o���b�N���p���\�����ƂƂ��Ēm���܂��B�J�����@�b�W����J���b�`�ꑰ�ɂ���Ė����J����ꂽ�o���b�N���p�W�����܂����B����A�ނ̓A�J�f�~�b�N�ȉ�@�̊�b��z������l�ł���A���Ă̓C�^���A���p�j�ɂ�����ł��L���ȉ�Ƃɐ������܂����B�P�X���I���A���p���V���ȉ��l�ς�\�����n�߂�ƁA�ے肳��Y����Ă��܂��܂������A�Q�O���I���Έȍ~�A�ĕ]���̎��݂��������Ă���A���ɋߔN�ł̓C�^���A�𒆐S�ɁA�傫�ȓW����������J�Â���Ă��܂��B�h �@�����A�N�G���`�[�m�Ƃ������́A�͂��߂ĕ������̂ł����B�W����̃T�u�^�C�g�����g��݂�����o���b�N�̉�Ɓh�Ƃ������̂������̂ŁA�����������������̂��W����ɍs�������@�ł��B�������Ɉ��p�����p���t�̐����ɂ���悤�ɃJ�����@�b�W���̋���Ȗ��Â̑ΏƂɔ�ׂ�ƁA�O�G���`�[�m�́A�悭�����ΌÓT�I�ň��肵������������A���������Δ����I�ł��̑���Ȃ��B�J�����@�b�W���̔�ׂ�ƍ���������܂��A�O�G���`�[�m�̓J�����@�b�W���̂悤�ȍ˔\�ɐU���čs�������Ƃ���܂Ő����Ă��܂����l�ł͂Ȃ��āA���ʂ́i�Ƃ͂����L�\�ȁj�l���n���ɓw�͂��d�˂āA������x�̃��x���̍�i���c�����Ƃ��ł����A�Ƃ�����ۂ��܂����B���������A�O�G���`�[�m�Ƃ����l�̓����͈��̃o�����X���o�̂悤�Ȃ��̂ł��B�S���̔��Ⴂ�ł����A�N���V�b�N���y�̐��E�łQ�O���I�̍�ȉƂɃ��q�����g��V���g���E�X�Ƃ�����ȉƂ����܂��B�L���ȃO�X�^�t��}�[���[�̌���p���悤�ɁA�����K�𑽗p���A�s���a�����_�Ɏg�p������[�I�ȃI�y��������A���c�����������Ƃ������Ƃł����A���̌�̈�������ɒ����邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ����l�ł��B���̈�����Ē�����ے肷���i���������̂̓V�F�[���x���N�Ƃ�����ȉƁA�ނ��炢�������ȃQ���_�C�I���K�N���n�܂����ƌ�����̂����m���y�j�ƂȂ��Ă��܂��B���āA���̃��q�����g��V���g���E�X�͈���݉z����O�ŗ��܂�����́A�Y�ÓT�I�ȍ�i�ɕς���Đl�C��ȉƂƂȂ�܂��B���܂ł��A�N���V�b�N���y�̐��E�ł͔�r�I�l�C�̂����ȉƂł����A�]���Ƃ��Ă̓h�C�c����[�J���ȃ}�j�A�����ŁA�����鋐���̂悤�ȍ�ȉƂɔ�ׂĐ������Ƃ����ʒu�Â��ł��B�����A�ނ̍�i�����Ƃ�����܂����A�I�[�P�X�g����炷�̂ɍI�݂Ȃ͕̂�����̂ł����A����ɋ����Ă��邾���Ƃ�����ۂŁA�������Ƃ����������Ƃ��[�����邱�Ƃ����Ȃ��̂ŁA�a�f�l�Ƃ����ʒu�Â��ɂ���܂��B�b����߂��܂��ƁA�O�G���`�[�m�̍�i�����Ă���ƁA�����悤�ȁA�F�X�����Ċ撣���Ă���悤�Ȃ̂ł����A���ꂪ�O�b�Ƃ�����ɔ����Ă��Ȃ��ŁA�ǂ������̑���Ȃ��Ƃ������������܂����B
�����A���̂悤�ȃO�G���`�[�m�ƃO���R���ׂāA�O���R�̕�����ŃO�G���`�[�m�͂��̈�ɓ͂��Ȃ��Ƃ����̂ł͂���܂���B���ꂪ�A��l�̉�Ƃ̕������̈Ⴂ�ł�����킯�ł��B���̂ЂƂ��A�O�G���`�[�m�ƌ�����Ƃ̎����Ă���o�����X���o�̓O���R�ɂ͊������悤�ł��傤���A���A���Y���Ƃ܂ł͂����Ȃ��ł��傤���A�e���݂₷���Ƃ��A�O�G���`�[�m�͗l�X�ȗv���ɉ����悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ����Ƒz�����邱�Ƃ��\�ł��B���������_�ł݂�ƁA�O�G���`�[�m�Ƃ�����Ƃ́A�O���R���ɔ�ׂ�ƌ���I�Ȏ��_������e���݂₷���l�ƌ����邩������Ȃ��̂ł��B���̂悤�Ȍ����ŁA���ꂩ���̓I�ȍ�i�����čs�������Ǝv���܂��B ���ł̓W���͎��̂悤�ȏ͗��Ă������̂ŁA����ɏ]���Č��čs�������Ǝv���܂��B �T�D���������߂� �U�D�˔\�̊J�� �V�D�|�p�̓s���[�}�Ƃ̏o� �W�D����@���Ƒ��̂͂��܂̏��������O�G���`�[�m�ƃO�C�h�E���[�j �X�D����A�@����Ɨ��z�̒Nj�
�T�D���������߂��@
����ȓW���ŁA�ŏ��ɔ����Ă����̂́A���̃O�G���`�[�m�̍�i�ł͂Ȃ��A�ނ�����{�ɂ����Ƃ������h���B�R�E�J���b�`���w���Ƒ��Ɛ��t�����`�F�X�R�A��i�҂����x�i�E�}�j�Ƃ������ł��B����͎��̏���ȑz���ł����A��Q�O�ōH�[�𗦂��闧��ɗ����āA��Ɩ{�l�Ƃ��Ă͒�����Ďd���ɗ�̂ł��傤���A���̔��ʁA�H�[�̐l�X�₻�̉Ƒ���H�ׂ����Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ӔC���ނ̌��ɕ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂Ƃ��A�Z�ʂ�F�߂��Ă����Ƃ͂����A�t���ɋ�������Ƃ������Ƃ��Ȃ��A�Ɗw�ŕ`���Ă������Ƃɕs�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�C�^���A�̂���n���̓s�s�Ƃ��������Ƃ���ł́A�Z�ʂ�F�߂��Ă�����������܂��A��̒��̊^�ł͂Ȃ��ƁA���̊X�̒N���ؖ����Ă����ł��傤���B�����A�����ł����āA�ގ��g�����̎��o���Ȃ���Ή�ƂƂ��čs���l��͖̂ڂɌ����Ă��邵�A�H�[�̐l�X��H���ɖ��킷���ƂɂȂ肩�˂܂���B���̃v���b�V���[�͎Ⴂ��Ƃ̑o���ɏd���̂��������Ă��Ȃ������ƒN��������ł��傤���B����ȉ�Ƃ�������悤�ɂ���{�ɂ����̂��A���̍�i�������Ƃ��������́A������ƍ�肷����������܂��A�O�G���`�[�m�����̍�i�̗l�X�ȗv�f�����ꂱ���ЂƂ��������ƂȂ��z�����悤�Ƃ����̂��A���ƂȂ�������悤�ȋC�����܂��B
�O�G���`�[�m���w����q�Ɛ��x�i���}�j�Ƃ������炵����i�B���̗c�q�̃C�G�X�����������}���A�̎p�́A�w���Ƒ��Ɛ��t�����`�F�X�R�A��i�҂����x�̒����㕔�̍Ւd��̐���q�̎p�Ƃ悭���Ă��܂��B�������A�J���b�`�̕`������q�����̂܂܈��p����悤�Ɏ����Ă����Ƃ����̂ł͂���܂���B�Ⴆ�A�J���b�`�̐���q�͉�ʑS�̂̒��ł̃X�|�b�g���C�g��q�ɓ��ĂĂ��邽�߂ɕ�q�̎p�S�̂����邭�Ƃ炵�o����Ă��܂����A�O�G���`�[�m�̍�i�ł́A��q�̔w�ォ����Ă�悤�ɂ��āA�������Ă���L���X�g�̕\��͉e�ɂȂ�A�}���A�̊�������B���悤�ł��B�܂��A�}���A�̉E��́A�����~�܂点�邽�߂ɁA�J���b�`�̂悤�ɃL���X�g�������������i�D�Ƃ͈���Ă��܂��B����́A�O�G���`�[�m���J���b�`�̐���q��y��ɂ��āA�����ɔނȂ�̑n�ӂ������č�i�Ƃ��Đ��삵�����̂ƍl�����܂��B����́A�P�Ɋۂ��ƈ��p��������A�y�䂵�Ă����Ɏ����Ȃ�̑n�ӂ�������Ƃ������ƂŁA���ꂾ���e���͐[�����̂ƍl���Ă��܂��B�܂�A�O�G���`�[�m�̓J���b�`�̍�i�̐���q�̕`����������������قǎ�荞��ł��܂����̂ŁA��������Ƃɉ��p���ł��Ă��܂���قǂɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃł��B�����炭�A�O�G���`�[�m�̓J���b�`�̍�i�̉�ʂ��G�Ȃ��r�߂�悤�ɁA�z�����Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ŁA�l�̂̕`�����Ƃ��A�����̊痧���Ƃ��A�O�G���`�[�m�ɂƂ��ẮA���̃J���b�`�̂���{�����W���[�ɒʂ����{���Ɍ������̂������̂ł͂Ȃ����B���ꂾ���ɁA���炵�����i�̂悤�ɂ�������A���̍�i�́A����q�̃A�g���r���[�g�i�V���{���b�N�ȏ�����j���Ȃ��A�_�X�����p�ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��āA�J���b�`�̐���q�̎p�̈��p�ŁA���̃|�[�Y�ȂǂŐ���q�ƌ����Ă���Ƃ������ƂŁA�J���b�`�̍�i�̔h���I�ȍ�i�ɂȂ��Ă���A�ƍl�����܂��B�܂�A���̍�i�����̂��̂Ƃ��Ď������Ă���ƌ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�w�F�鐹�J�����E�{�b�����[�I�Ɠ�l�̓V�g�x�i�E�}�j�Ƃ�����i�͂ǂ��ł��傤���B���ɂ́A�Ԃ��}���g���H�D���삭���J�����E�{�b�����[�I�̎p�́A�w���Ƒ��Ɛ��t�����`�F�X�R�A��i�҂����x�̉�ʍ����Ő���q���삭���t�����`�F�X�R�̎p�Əd�Ȃ��Ă���̂ł��B�l���͈قȂ邵�A���J�����E�{�b�����[�I�͎�����킹�Ă���̂ɑ��āA���t�����`�F�X�R�͗�����L���Ă��܂����A�g�̂̎p����Ւd�ɑ���ʒu�W�A���邢�͕`���Ă���p�x��Ԑ��Ƃ������x�[�V�b�N�ȂƂ���͋��ʂ��Ă��܂��B
�܂��A����ŁA���ꂾ���[�r�ȉe�����J���b�`����Ȃ���A�O�G���`�[�m���J���b�`�ɂȂ�Ȃ������_�A�܂�A�J���b�`�ƃO�G���`�[�m�̈Ⴂ�Ƃ��Ė��炩�Ɍ�������̂�����܂��B����́A�O�G���`�[�m�ɂ́A�V���v�����ւ̎w��������Ƃ������Ƃł��B�J���b�`�̍�i�Ɍ�����S�`���S�`�����������ɑ��āA�O�G���`�[�m�̓p�[�c����낤�Ƃ����w�����͂����茩�Ď�邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B����́A�w�F�鐹�J�����E�{�b�����[�I�Ɠ�l�̓V�g�x�ɂ�������Ǝv���܂��B�V�g�̎p�J�����E�{�b�����[�I�̔w��̓�l�ɍi���āA�A�g���r���[�g���`������邱�Ƃ����Ă��܂���B�����ɂ́A�S�̂̍\���ƃ��C���̓o��l���ʼn�ʂ��\�z����Ƃ����A���̌�Ŗ��炩�ɂȂ��Ă���O�G���`�[�m�̓����̖G�肪������Ǝv���܂��B �Ȃ��A�]�k�ł����J���b�`�́w���Ƒ��Ɛ��t�����`�F�X�R�A��i�҂����x�̐��t�����`�F�X�R����A�����J�����@�b�W�����w�ґz���鐹�t�����`�F�X�R�x�i���}�j�̎p���_�Ԍ����Ă��܂��B���̗��҂��ׂĂ݂�ƁA�J���b�`�̍�i��ˏo�����Ƃ��낪�Ȃ��ƁA�����q�ׂ闝�R���������Ă���������Ǝv���܂��B
�U�D�˔\�̊J���@
�W�����̃t���A���ς���āA�����K�i��ʂ�A�L�������ɏo��ƁA�@���I�Ȏ��̑����肪�A�h�b�J���ƓW������Ă��āA���p�قƂ��������A����Ƃ��@���{�݂̒��ɂ���悤�ȕ��͋C�ɂȂ��Ă��܂����B�܂��āA���w�҂̐��������Ȃ��āA�Â��ȕ��͋C�������̂ŁA�Ȃ�����ł����B
���āA���ۓI�őދ��Ȃ��ƂX�Ə����܂����B���ł��̂悤�Ȃ��Ƃ������̂��ƌ����A�O�G���`�[�m�́A���̂悤�Ȋ��ł��������炱���A���ɏo�邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ������̂��A�Ǝv��������ł��B�����ŃO�G���`�[�m�̍�i�����āA�������ɂ悢��i�ł����āA����Ȃ�Ɋy���߂���̂ł��邵�A�i�����������̂��Ǝv���܂��B�������A�����Ɍ����A�����̍�i��N�̍�i�Ƌ�����ꂸ�Ɍ������āA��҂Ă�ȂǂƖ��ꂽ�Ƃ��āA�O�G���`�[�m�ł���Ɩ��킸�ɓ����邱�Ƃ��ł���قǂɁA���ɂƂ��ċ���Ȍ������o�����Ƃ͂ł��܂���ł����B���̉�ƂƔ�ׂĂǂ������������Ƃ��A���܂肻�����������N�t���̂悤�Ȃ��Ƃ͍D���ł͂Ȃ��̂ł����A�����o���b�N���p�ɕ��ނ����悤�ȃ��[�x���X�Ƃ��J�����@�b�W���̂悤�Ȉ�ڂł���ƌ�����������Ƃł́A�O�G���`�[�m�́A���ɂƂ��ẮA�Ȃ������̂ł����B���������v��������A���ՓI�ɂ������Ƃ͌����܂��A
���ۓI�ȋc�_�������Ȃ��Ă��܂��܂����B��i�����čs���܂��傤�B�w�����[�g�̐�����q����V�G�i�̐��x���i�[���Ɛ��t�����`�F�X�R�x�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B�Q.�S�~�P.�T���Ƃ������̍Ւd��ł��B�c���̍\�}�Ō��グ��悤�Ȋp�x�ŕ`����Ă��܂��B�����[�g�̐���Ƃ́A�C�^���A�̈�n���ɂ����T���^�E�J�[�T�ɕ�[���ꂽ�c���L���X�g�����������}���A�̑��i����}�j�������ł��B�i�U���̒n�Ő���}���A�ƉƑ�����炵�Ă����Ƃ��V�g�����ɂ���ăC�^���A�̃����[�g�ɉ^��A���̊�Ղ��L�O���Đ��������Ă��A����ȍ~�͏���n�ƂȂ����Ƃ������Ƃł��B�܂�A���̍�i�ŗ�q����鐹��͑��ŁA���̍�i�͂��̃}���A�����̂��̂̐_�X������\�킷�C�R���̂悤�Ȃ��̂Ƃ������A�����_�X�����ɗ�q�����ʂ�`���Ă�����̂ŁA�����Ɍ��̈��ʂ̂悤�ȁA�����ɂ��o���b�N�G��炵�����̂ƌ����܂��B�Ⴆ�A�E���̔w�i�̋�̕`�����������ɂ������̔w�i�ł��邩�̂悤�ɕ`����Ă�����A�S�̓I�ȋ�Ԃ̍L����������������A�ނ���R���p�N�g�ɉ�ʂɎ��߂悤�Ƃ���A�����̋����ȋ�Ԃ́A�܂�Ō���̕���̂悤�ȓs���̗ǂ��܂Ƃߕ�����������Ǝv���܂��B����́A�����ɂ�����ɏ���Ƃ����������̗v���ɉ����悤�Ƃ��Ă���ƍl������B�����ɁA�O�G���`�[�m�̃N���C�A���g�̋��߂ɐ����ɉ����� �������A������ނ̍�i�ɂ��āA�Ⴆ�J�����@�b�W�����w���[�g�̐���x�@�i�E��}�j�Ɣ�ׂ�Ƃǂ��ł��傤���B�J�����@�b�W���̍�i�ł͐��ꑜ�͌����̐��g�̏����̂悤�ɕ`����A�����[�g�̐���ł��邱�Ƃ�������悤�Ȃ��̕`����Ă��܂���B����̌��ւ��炩�낤���Đ���q�ł��邱�Ƃ������邾���ŁA�����̐Α���̌����̑O�ŁA��q�ɉ��ꂽ�g�Ȃ�̒j�����삱���Ƃ��Ă���u�Ԃ��A�܂��ɂ��̃_�C�i�~�b�N�ȓ��������ʂ���Ă���悤�Ɍ����A����Ƀ}���A���삭�j���ɖڂ����Ƃ��납��A�F�鑤�ƋF���鑤�̊W�������ɂ���Ƃ������Ƃ����A���ɕ`����Ă��܂��B�����ɂ͐M�Ƃ����s�ׂ������̏�ʂƂ��Ċ��ʂ���Ă���ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���Ƃ��A�ߑ�I�Ȍl�����ʂ̐M�Ƃ������Ƃ��c�_����ꍇ�ɁA���̂悤�ȉ摜�͌l�ɖ₢������悤�ȋ������_���������Ă���Ƃ����邩������܂���B�������A�����ł͗ތ^�I�Ȑ_�X�����Ƃ��Đ����ɏ���͈͂���E���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����B�l�̎��o�Ƃ������ȑO�ɐ����ɉ��Q�W�ɃA�s�[������ɂ̓p�^�[�����O��Ă��܂��Ă��邩������܂���B���̂悤�ȁA��E�͌㐢�̌��݂���݂�A�J�����@�b�W���̈��̕\���̉ߏ�Ƃ��āA�ނ̓����Ƃ��Č��鎖���ł�����̂ł��B�������A�O�G���`�[�m�́A����A�J�����@�b�W���͉z���Ă��܂�������̑O�ŗ��܂��Ă���̂ł��B����͓����̐l�X�ւ̌��ʂ��l����Ζ����̂Ȃ����ƂȂ̂ł����A�㐢�̎��Ȃǂ��猩��A������z�����J�����@�b�W���Ɣ�r���Ă��܂��̂ł��B�����ɂ��̑���Ȃ��������Ă��܂��̂��ւ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B
�V�D�|�p�̓s���[�}�Ƃ̏o�
�R�O���߂��āA�O�G���`�[�m�̓��[�J���ȉ�Ƃ���A���[�}�ɏo�Ă��܂��B�Q�N������ƂŁA�܂��n���ɂ��ǂ����Ƃ������Ƃł����A���ꂪ�ނ̉敗���ω����Ă������������ɂȂ����Ƃ����܂��B�g�ނ̍\�}�͎���ɒP�������Ă����A�l���̗֊s�͖��m�ɂȂ�B������ԑS�̂�W���Ƃ炷�悤�ɂȂ�A�l���̃��H�����[������������悤�ɂȂ�B�܂�A�ÓT��`�I�ȗl���ɋ߂Â��Ă����B�h�������������́A���̂悤�Ȕ��p��i������f�{�̂Ȃ��҂ɂƂ��ẮA�Ⴂ����̓I�ɂ͕�����܂���B
�W�D����@���Ƒ��̂͂��܂̏��������O�G���`�[�m�ƃO�C�h�E���[�j�@
����ɑ��āA�O�C�h�E���[�j�̍�i�i�E��}�j�́A�w�i�͓����悤�ɈÂ��Ȃ��Ă��܂����A�ޏ��͐Q���ɂ���V�`���G�[�V�����̂悤�Ȃ̂ŁA�O�G���`�[�m�̏ꍇ�̂悤�ȈÈłƌ���ΏƓI�Ɉ����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�Q���̈Â����w�i���ȗ����Ă���Ӑ}�̂悤�Ɍ����܂��B��l���ł��鏗���̓O�G���`�[�m�̍�i�ɔ�ׂ�Ɩ��ĂɌG�Ȃ��`����Ă��܂��B����́A���Ǝ��̏�ʂ̓o��l���Ƃ��Ẵ��N���e�B�A��`���Ă���̂ł͂Ȃ��A��l�̔�����������`���Ă���ƌ����������߂���������܂���B���̔���������i�Ƃ��ĕ`�����߂Ƀ��N���e�B�A�̕���̎��Q�̏�ʂƂ����� ���̂悤�Ɍ��t�ɂ���ƁA��l�̉�Ƃ̍앗��傫���قȂ�ƌ������Ă��܂������ł����A����͈Ⴂ���������Ă̂��ƂŁA����قLjႤ�̂��Ƃ�����A���͂悭���Ă���Ǝv���܂��B����́A�Ⴆ�A�L���ȃp���~�W���j�[�m���w���N���e�B�A�x�i���}�j�Ɣ�ׂ�ƁA�ނ��뗼�҂̋߂���������Ǝv���܂��B �����ЂƂA�O�G���`�[�m�ƃ��[�j���ׂĂ݂܂��傤�B��ނ͓���ł͂���܂��A���Ă�����̂Ƃ��āA�O�G���`�[�m���w�T���X�̛ޏ��x�i���}�j�ƃO�C�h�E���[�j���w�ޏ��x�i�E���}�j�����Ă݂܂��傤�B�����悤�ȕ����̏������ł����A���[�j�̕��̓_�C���N�g�ɏ�����`���Ă���Ƃ�����i�ł��B���S�͏������Ȃ� �w�N���I�p�g���x�i�E���}�j�Ƃ�����i�����Ă݂܂��傤�B���ɂ́A�����͈���Ă��A�\���|�[�Y�́w���N���e�B�A�x��w�T���X�̛ޏ��x�Ɠ����悤�Ɍ����Ă��܂��B����Ɍ��Ă����ƁA�O��Ɍ����w����̂��ƂɌ���镜�������L���X�g�x�ŃL���X�g�ɂ�����悤���삭����}���A�̕\��Ə㔼�g�̃|�[�Y�ɂ��ʂ��Ă���悤�Ɏv����̂ł��B�O�C�h�E���[�j�̕`���������́A�����̑��`�I�Ȕ�������`���Ă��āA�ߑ���ݒ�͂��̂��߂̕t���i�ŃR�X�`���[���E�v���C�̂悤�Ȃ��̂��Ƃ����܂������A�O�G���`�[�m�̏ꍇ�͈�����Ӗ��ł�͂�R�X�`���[���E�v���C������Ă���̂ł͂Ȃ�
�@ �X�D����A�@����Ɨ��z�̒Nj�
�����āA�w�S���A�e�̎�����_���B�f�x�i�������}�j�ł��B��ʂ̍\���́A�����Ō��Ă�����i�ɋ��ʂ����V���v���Ȃ��̂ł��B��l���ł���_���B�f�́A����܂ł��O�G���`�[�m�̍�i�ɕp�o���������������|�[�Y�ł��B�������A����܂ł̍�i�͂��̃|�[�Y�̐l�ƂƂ��ɋ�������Ώ� �����̂Ƃ���ɁA����܂ł��A�����G��Ă��܂������A�O�G���`�[�m�Ƃ�����Ƃ̈ꕗ�ς���������A���͌��܂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�W����̉���ɂ��A�W����ɂ��ď����ꂽ���z��ǂ�ł��w�E����Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���̌l�I�ȕΌ���������܂���B���̃O�G���`�[�m�̕ςȂƂ���Ƃ����̂́A�J�����@�b�W����O���R�̂悤�Ȑl�X�̖����ɕ��ʂłȂ����̂Ƃ͈���āA�ꌩ�A�܂��������ʂȂ̂�����ǁA�悭����ƁA�ق�̋�ɕЋ��ɂ��肰�Ȃ������悤�ɂ��̂ŁA���i�͋C�����Ȃ��悤�Ȃ��̂ł��B�J�����@�b�W����O���R�̂悤�Ȍ��������ŕ��ʂłȂ��ƕ�������̂́A�ނ�̓V�˂������ɗe�ՂɌ��Ď�����̂ŁA�v�͂�����e��邱�Ƃ��ł��邩�ۂ��Ƃ����_�ŁA����Ӗ�������₷���Ƃ������܂��B����ɑ��āA�O�G���`�[�m�̏ꍇ�ɂ́A���i�͂��̕��ʂłȂ��Ƃ���͉B����āA����ł͑��̕��ʂ̐l�Ɠ����悤�ɂ��邯��ǁA���鎞�B�����ꂸ�ɂ��̕З������Ă��܂��B�����Ă݂�ΉA���Ƃ����̂ł��傤���B�������������t�Ō����A����ɉB���ꂽ���C�Ƃł���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂾ���ɁA�p���ĕs�C���ȂƂ��낪����̂ł��B����Ɉ�x�C�����Ă��܂��ƁA�C�ɂȂ��Ă��傤���Ȃ��B�O�G���`�[�m�̍�i�����Ă��āA���ׂĂ̍�i�ɂ���Ƃ͌��炸�A�������Ƃ��Ă��T���Ă��Ȃ��Ȃ��������Ȃ��B�������A�C�������炠��{��������悤�ɒT���Ă��鎩���̎p������̂ł��B
|













 �Ƃ͂����A�w����Əj����������c���L���X�g�x���݂Ă��āA��ʂ̌������č��ɑ��������āA����������������A���̂��ߑS�̂Ƃ��ĕǍۂ̍\�}�ō������ǂŐ��ĉE���ɋ�Ԃ��L����V�`���G�[�V�����₻�̕ǂɂ��悤�Ƀe�[�u�����ݒu����Ă���z�u�A�������������A���̑��Ɍ������Ă���|�[�W���O�ȂǁA�t�F�����[���i�����}�j���v���N����������̂ł��B�������A���̑@�ׂȕ`�������Ƃ��A��ʂ̐��ׂ��̓t�F�����[���ɋy�Ԃׂ�������܂���B����A�w����q�Ɛ��x�̗֊s�𖾗Ăɂ��邱�Ƃ��]���ɂ������ɁA���Â̑ΏƂ����������h���}����ʂɍ��o���Ă����̂Ȃ�A
�Ƃ͂����A�w����Əj����������c���L���X�g�x���݂Ă��āA��ʂ̌������č��ɑ��������āA����������������A���̂��ߑS�̂Ƃ��ĕǍۂ̍\�}�ō������ǂŐ��ĉE���ɋ�Ԃ��L����V�`���G�[�V�����₻�̕ǂɂ��悤�Ƀe�[�u�����ݒu����Ă���z�u�A�������������A���̑��Ɍ������Ă���|�[�W���O�ȂǁA�t�F�����[���i�����}�j���v���N����������̂ł��B�������A���̑@�ׂȕ`�������Ƃ��A��ʂ̐��ׂ��̓t�F�����[���ɋy�Ԃׂ�������܂���B����A�w����q�Ɛ��x�̗֊s�𖾗Ăɂ��邱�Ƃ��]���ɂ������ɁA���Â̑ΏƂ����������h���}����ʂɍ��o���Ă����̂Ȃ�A