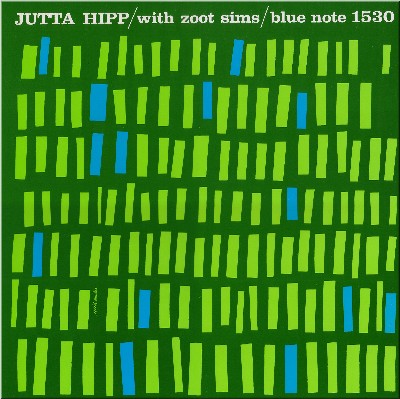|
1925〜1985年 カリフォルニア州イングルウッド生まれ。 サックス奏者。そのプレイの特徴を一言で、“朴訥さ”と言う人がいる。曰く、“田舎の純朴なお百姓さんのような語り口で、一言一言をしっかりとかみしめるように、律儀にフレーズに組み立てて行く。結構ハイスピードの演奏もやるがあんまり軽薄な感じがしない”。ズート自身は高い音を好み、長ずるに及んでテナー・サックスに加えてソプラノ・サックスも吹くようになったという。しかし。イメージとしてズートの音は線が太く、どっしりと腰を据えたような重量感があるように受け取られる。それだから「クール」と反対の「ウォーム」と言われたりするのではないか。 ズートは若いころにビック・バンドにいた経験のせいなのか、アンサンブルの中で自分を生かしていくタイプで、共演者や伴奏者を生かしながら、全体としてコンセプトを実現させていくタイプだと思う。彼のプレイをよく聴いていると、同じような節を同じように繰り返していることが多い。まあ、一部の天才を除けば、毎度ハッとするようなフレーズを差し挟むことなどできない。そうであれば、手持ちのフレーズをうまく使いまわすこということになるだろう。要は、その使い方の問題で、ズートは、それほど豊富でないフレーズを何度も繰り返して積み重ねる。その繰り返しがリズムを作り、彼独特の推進力あるノリを作り出す。繰り返すことによって耳になじんだ節によって、スウィングのビックバンドで培われた、ストレートでスウィンギンなノリが生み出されると、それが聴く者に親近感を抱かせてノリに誘われるような心持ちにさせられる。それが、ズート・シムズの特徴であると思う。それが、朴訥と言われるのではないだろうか。 繰り返しとは、すなわち継続であり、継続するためには安定していなければならない。これは、詰まる所ジャズの大きな魅力であるアドリブの即興的なスリル、この先何が出てくるか分からない展開の読めない楽しみというのはない。節が繰り返し続いていくことを前提に、その繰り返しの安定感が、だからこそ単調に聞こえてしまう人もいるだろう。しかし、それがウォームテイストの源となっていると思う。
バイオグラフィー
ズート・シムズはクール・ジャズにカテゴライズされるスタイルのテナー・サックス・プレイヤーだった。彼のテナーはスウィングのエナジーとブルージーな熱さに充ち溢れながらも、滑らかでリラックスしたフィーリングをも兼ね備えていた。ビック・バンドやボーカルもまじえたジャム・セッションで舞い上がるように目立つことも出来たが、合わせものでは過度に出しゃばることなく、その上手さを発揮していた。シムズはレスター・ヤングの影響を受けていたが、盲目的な模倣者ではなかった。たしかに、彼のキャリアの最後近くでは、レスター・ヤングやビ・バップに影響されたアプローチよりも、むしろ、原点に戻るようにベン・ウェブスターのモードでプレイしていた。 シムズの家族は寄席芸人で、彼自身も小さい頃からドラムスとクラリネットを演奏し始め、13歳でテナー・サックスを手に取った。2年後にプロとなり、ダンスバンドのツァーに参加した。1943年にベニー・グッドマンに加入する前の40年代前半にはボビー・シャーウッドともプレイしている。1944年にはビル・ハリスとニュー・ヨークのカフェ・ソサイエティでプレイしている。その一方、ジョー・ブシュキンのリーダー・アルバムのレコーディングに参加している。 その後、カリフォルニアに移り、シット・ギャレットと共演する。軍務に就いた後の1946年には再びグッドマンのもとでプレイし、47年にはジーン・ローランドのもとに加わった。そのころ、スタン・ゲッツ、ジミー・ジェフリーそしてハービー・スチュワードとプレイしている。ハーマンのもとを去ると同時に、短期間バディ・リッチと活動を共にし、50年にはグッドマンに復帰している。1951年にはエリオット・ローレンスに加入した。50年代前半になってプレスティジ・レーベルでソリストとしてデビューし、1953年には、スタン・ケントンのグループでプレイしていた。1954年から56年にかけて、ヨーロッパに渡り、ジェリー・マリガンのバンドに加わり、それ以降のマリガンのバンドのソリストとなった。他方で、50年代前半にアル・コーンとの間でコラボレーションを始め、これが後々まで長く続くことになった。2人はコラボはフレンドリーでありながら、ほどよい緊張関係を保っていて、素晴らしいツイン・サックスのレコーディングを何点も残している。彼らは、70年代にスカジナビアと日本にツァーを行っている。シムズがボブ・ブルックマイヤーとのクインテットでプレイしたセッションは5枚の異なる録音となって残されている。彼は、50年代には、ユナイテッド・アーティスツ、リバーサイド、ABCパラマウントでレコーディングした。70年代に入るとソプラノ・サックスを演奏し始め、ソプラノ・サックスによる優れた録音をパブロ・レコードに残している。60年代以降は様々なレーベルで多くのレコーディングに参加している。 ※カフェ・ソサイエティ 1938年にニューヨーク、グリニッジ・ヴィレッジにオープンしたナイトクラブ。名プロデューサーのジョン・ハモンドの肝いりで、当時のコットン・クラブのように黒人のショーを売り物にしながら、客は白人しか入場させないといった差別的な待遇を一切排除して人気を博し、文化人達のサロンのような存在になった。ビリー・ホリデイもこの店を好み、レスター・ヤング、アート・テイタム、エラ・フィッツジェラルドなども出演した。時として、かなり過激な政治的イベントも行なわれたので、47年、反アメリカ活動の疑いをかけられ、客離れと共に翌年閉店する。
|
 ズート・シムズ(テナーサックス)
ズート・シムズ(テナーサックス)