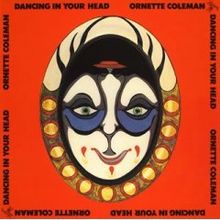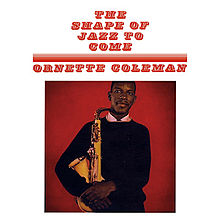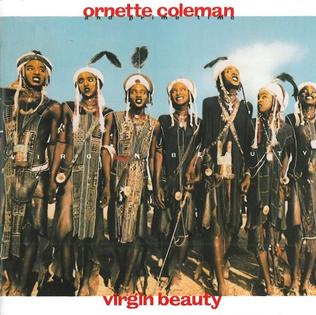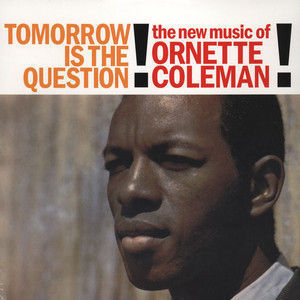|
があると思う。
バイオグラフィー ジャズの前衛的な改革者のうちで最も重要と思われるものの1人、オーネット・コールマンは1959年に従来のフォーマットを破壊してしまってから、忠実なファンと敵対するアンチを両方ともか抱え込むことになってしまった。彼と彼のオリジナル・カルテットのメンバーだったドン・チェリーは、共に曲の始まりと終わりのメロディーを演奏するけれど、かれらのソロは、テーマの雰囲気に全く縛られることのない演奏する代わりに、コード進行に基づいた即興とハーモニーを不要とするものだった。コールマンのトーンは故意にピッチが揺れらされるもので、リスナーを戸惑わせ、彼のソロは感情的で彼の独特の論理に従うものだった。やがい、彼のアプローチは大きな影響力を持つものとなり、彼のカルテットの初期のレコードは、この先何十年もの間先進的であり続けるだろう。 残念なことに、コールマンの初期の試みは記録に残っていない。もともとは、チャーリー・パーカーに触発されて14歳でアルト・サックスを始め、その2年後にテナー・サックスを始めた。彼の初期の経験は、レッド・コナーズとピー・ウィー・クレイトンのバンドを含むテキサスのR&Bバンドでのものだ。しかし、彼の初期のオリジナルなスタイルで演奏しようという試みは聴衆や仲間のミュージシャンからは敵意で迎えられた。コールマンは50年代初頭にロサンゼルスに移り、そこで音楽の本を勉強しながらエレベーターのオペレーターとして働いた。彼は、途中で、ドン・チェリー、チャーリー・ヘイデン、エド・ブラックウェル、ボビー・ブラッドフォード、チャールス・モフェットそしてビリー・ヒギンズといった気の合う仲間と出会った。しかし、彼の音楽を演奏することのできる中軸となる音楽家たちで出会ったのは1958年以降の、LAのトップミュージシャンたちとの数多くの試みの不成功を経てのことだった。彼は、ヒルクレスト・クラブでのポール・ブレイのクインテットの一員として現われ、同時代の人たちにむけて2枚の興味深いアルバムを録音した。ジョン・ルイスの助けを借りて、コールマンとドン・チェリーは1959年に「レノックス・スクール・オブ・ジャズ」のセッションに参加し、ニューヨークのファイブ・スポットに長期に止まることができた。この契約は根本的な新しい音楽に向けてジャズの世界に警告を発することになった。そして、毎晩、客席はコールマンを天才か詐欺師のレッテルを交互に貼り付けようとする好奇心の強い音楽家たちでいっぱいになった。 1959年から1961年の間、「ジャズ来るべきもの」をはじめとして、コールマンはアトランティック・レーベルのために一連のいまや古典となった驚くべきカルテット・アルバムを録音した。ドン・チェリーそしてベースのチャーリー・ヘイデン、スコット・ラファロ、ジミー・ギャルソンそしてドラムスのビリー・ヒギンズ、エド・ブラックウェルたちと、コールマンは、ジョン・コルトレーン、エリック・ドルフィーを含む1960年代の彼以外の先進的な即興演奏をするミュージシャンや60年代中盤のフリー・ジャズの演奏家の殆どに大きな影響を及ぼす音楽を創造した。「フリー・ジャズ」というアルバムでは約40分近いジャムセッションではワンセットが、コールマン、チェリー、ヘイデン、ラファロ、ヒギンズ、ブラックウェル、ドルフィーそしてフレディ・ハバードの8人をダブル・カルテットに編成したもので、そこで2、3短いテーマ以外はグループの即興を基本とした演奏を行なった。 1962年、コールマンはクラブやレコードレーベルが彼に支払っている金銭よりもはるかに価値を創出していると感じて、一時的な引退をしたことでジャズの世界を驚かした。彼はトランペットとバイオリンを演奏し始めた、とくにバイオリンはドラムスみたいに演奏した。1965年、彼はベースのデヴィッド・アイゼンソン、ドラムスのチャールス・モフェットによるとくに強力なトリオで、彼の演奏できるすべての楽器をつかって数枚のすばらしいレコードを録音した。その後10年間、彼を補完するようなテナー・サックスのデューイ・レッドマン、ベースのヘイデン、そしてドラムスはブラックウェルか彼自身の若い息子ドナルド・コールマンのいずれかによるカルテットを組んでいた。それに加えて、コールマンは小編成グループのためのいくつかの無調作品と穏やかで古典的なさ作品を作曲し、そのいくつかで、ドン・チェリーと再会した。 70年代のはじめ、彼のキャリアは後半にさしかかる。彼は「ダブル・カルテット」を編成し、そこにいたのは2人のギター、2人のエレキ・ベース、2人のドラムスと彼自身によるアルト・サックスだった。このグループはプライム・タイムと呼ばれ、晦渋で、雑音みたいで、しばしば機知に富むアンサンブルを特徴としていた。そこではメンバー全員が平等に役割を担っていたようだが、結局のところリーダーのアルト・サックスが常に目立つことになってしまった。いまや、彼は自身の音楽をハーモディクスというハーモニー、メロディーとリズムを同等の重要度として扱う象徴的な呼び方で呼んだ。しかし、ルーズなファンクのリズムにフリー・フォームな即興を組み合わせたフリー・ファンクの方が適している。プライム・タイムのサイド・ミュージシャンとして彼の息子のドナルドに加えて、ドラマーのロナルド・シャノン・ジャクソンとベーシストのジャマラディーン・タクマがいた。プライム・タイムは、スティーヴ・コールマンとグレッグ・オスビーのMベース-ミュージックに大きな影響を与えた。パット・メセニーは生涯を通じてのオーネットのファンだが、「ソングX」でコールマンと協演している。またジェリー・ガルシアは一度のレコーディングで第3のギターを演奏した。コールマンは198年代になって最初に編成したカルテットを不定期に再開した。
|