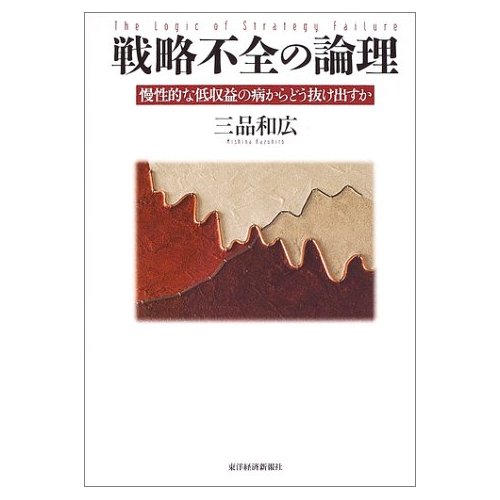 第一部 戦略不全の実態 第一部 戦略不全の実態第一章 日本企業の戦略不全性 第二章 データに見る戦略不全 第三章 ケースに見る戦略不全 第二部 戦略とは何か 第四章 演繹的マクロ戦略論 第五章 帰納的ミクロ戦略論 第六章 大局的判断の戦略論 第三部 戦略不全の背景と処方箋 第七章 経営戦略の3要件 第八章 日本企業の経営者 第一部 戦略不全の実態 第一章 日本企業の戦略不全性 1.戦略を何とみるのか 戦略という言葉の語源は、軍事用語で2500年前の古代ギリシャまで遡る。ところが、戦略が独自の概念として生まれるのは18世紀から19世紀初頭にかけてのことだという。武力衝突は人類の長い歴史と不可分であったにもかかわらず、近代に入って初めて戦略という概念を要するに至った変化とは何か。この戦略ということと表裏一体にあるのは、大規模複雑性である。近代以前の紛争では敵対する武力衝突に突入し、どちらかが勝利を収めた時点で終結するのが常であったが、動員兵力が大規模化した近代戦は1回の交戦で簡単に終わるものではなくなった。そこで、交戦における軍隊の使い方を戦術と呼び、戦争目的の遂行に向けた個別交戦の用い方を戦略という区別が生ずる。ここに来て、局所的な武力衝突に勝つことよりも、継続性を帯びる戦争の中で上位の目的を満たすことが関心の焦点に浮上した。 経営の場合も、軍事の場合と事情はかわらないだろう。商業や工業は本源的に戦略を必要とするものではなく。供給のあるところから需要のあるところへ機敏にモノを運ぶ、または安く上手にモノを造る。そういったことさえ確実にこなしていれば、本来はそれでよかったのである。そこに戦略の必要はないし、戦略がオペレーションの失敗を救うわけでもない。経営の問題の大半は、オペレーションの管理、すなわち出来て当たり前のことをいかにきちんとやり遂げるかにある。経営学も、ヒトとモノとカネの管理手法から出発している。オペレーションが工夫を要するのは確かだが、頭を使うことがすべて戦略ということではないのである。経営の世界に戦略というものが導入されたのは、巨大企業の多角化と、それに伴う事業部制組織の導入である。新しい市場を科学技術の力で作り出した企業は、新規需要が一巡するまで半ば必然的に成長と繁栄を約束されたが、市場は遅かれ早かれ飽和に向かい、大型発明も枯渇する。そこで潤沢な資金を持て余す巨大企業は多角化に打って出た。その結果として複数の事業を統括する本社機能が生まれ、経営は初めてオペレーション以外の課題に直面するに至った。ここでも鍵は大規模複雑性にある。多角化の矛先をどこに向けるべきか、事業間の資源配分をどうすべきか、こういった本社機構に固有の新しい課題が、戦略という概念を新たに呼び込んだ。そして、戦略という概念がいったん生まれると、同じく大規模複雑性を増していった個別の事業でもそれが用いられるにいたったのである。 戦略というと、「戦いに勝つ」という目的か想起されやすいが、それは誤解である。目の前の敵にいかに勝つのかという関心は、時間の流れの下流である戦術の領域である。戦略固有の領域は、同じ時間の流れの上流のほうに位置する。そこでは戦う相手を選ぶ選択肢もあれば、戦いを回避する選択肢もある。戦うことなく相手を屈服させる可能性すら視野に入ってくる。軍事戦略の場合、戦略を要する主体は国家にあり、その国家の目的、すなわち国の繁栄に資することが国家戦略の機能と広く解釈すればよいであろう。 経営戦略の場合、戦略を要する主体は企業であり、企業が内包するところの事業である。企業や事業の目的は、長期の視点から最大限の利益を確保することにある。したがって、長期収益の最大化に資することが企業戦略、または事業戦略の固有事業ということになる。例えば、売上、またはその成長が重視されることもあるが、それは売上を拡大すれば利益も拡大するという暗黙の前提があってのことである、究極の目的は、あくまでも収益である。いくら単年度の収益が巨額にのぼろうが、それが爆発的な現象にすぎず、将来の収益を犠牲にしたものであれば、戦略性を認めるわけにはいかない。逆に、今の収益を削って投資に回し、それ以上の収益を後で刈り取るという行動は、戦略的と言える。戦略が見据えるべきは、長期にわたって実現する収益の実質総額なのである。 ところで、戦略と経営はどう違うのか、企業は、長期収益の最大化を図る前に自社の存続を保障しなければならず、そのためにはやって当たり前という業務を無視するわけにはいかない。こうした業務は、うまくやらなければ企業の存亡にかかわるかもしれないが、うまくやっても長期収益の増大に積極的につながることはない。企業の中で執り行われる日常業務の大半は、そういうものである。経営とは後ろ向きの営為も含めてすべての業務を対象とするものである。それに対して戦略とは、長期収益の最大化に直接関与する営為だけを切り離したものと考えればよい。 2.なぜ不全をとうのか 3.なぜ日本企業なのか 日本企業と米国企業を概念モデルとして比較しながら、なぜ慢性の戦略不全が日本型企業に起こりやすく、逆に日本型企業のアキレス腱が戦略の慢性不全になりやすいのかを整理する。その答えは、企業という制度のきわめて根源的な設計思想の中に存在すると著者はいう。 人が自分の幸せだけを追求して利己的に行動するとき、需要と供給はあたかも“神の見えざる手”に導かれるようにして一致し、社会全体の秩序は政府の指揮なくして保たれる。アダム・スミスが『国富論』で論じた有名な命題である。しかし、近代的な大企業は、スミスの命題に反する存在となっている。実際に、大企業が業務を推考するうえで必要とするモノやサービスを自社内で調達するとき、スミスが必要と論じた指揮権が発動されている。これは、市場を介した交換を置き換える行為となっている。これが市場と違うのは、大企業の中では、指揮を受ける側も、指揮を発動する側も、市場経済の原動力たる利己心を一時的にサスペンド、または保留している。企業内でみんなが利己心に基づく行動を維持するならば、指揮というものが成り立たなくなる。このようにして、大企業は、利害を一にしない多数の人の間の、利己心を保留した継続的な協業の上に初めて成立する。そうであるがゆえに、ここには宿命的な問題がついて回る。「人を動かすうえで何が利己心にとって代わるのか」「利害を一にしない構成員をいかに動機づけ、共通の目標に導くのか」という問題がそれである。この二重の問題の前の部分が企業のモチベーションの問題、後の部分が企業のコーディネーションの問題である。この二つの問題は、協業の成果を決定的に左右する。協業の成果の大きさは、それを構成する要素ベクトルの大きさと、要素ベクトルの方向が一致する度合いで決まってくる。いくら要素ベクトルが大きくても、お互いに逆方向を向いていれば、協業の成果は上がらない。また、いくら方向が一致していても、各々の要素ベクトルが小さければ協業の成果は上がらない。企業はこういうモチベーション問題とコーディネーション問題を同時に解くことを迫られている。コーディネーションは一般に指揮官が持つ権限とともに強化されるが、モチベーションは各構成員が持つ権限とともに強化される。ここに、限られた権限、または決定の自由度の配分をめぐるトレードオフが生まれるのである。特に規模が大きく複雑を極める大企業ともなると、これはかなり深刻な難題としてのしかかってくる。 日本型の企業モデルと米国型の企業モデルを比較すると、企業の根元的なトレードオフに対してとりうるアプローチが両極といえるほど対照的だ。日本型企業モデルは、2つの問題のうち、モチベーション問題に対して最強の解を用意するものと見ることができる。長期にわたって関連性のある仕事、または技能蓄積やキャリアパスを構成員に提供し、その中で構成員が自らの仕事の意味を深く理解、さらには創造することを尊重する。そして、本来は生活の顧客や仲間の評価を判断基準にして構成員が仕事に立ち向かう後押しをする。金銭報酬が伴わないのに仕事に没頭するのは、仕事に内在する喜びが心的報酬として機能している証であろう。これに対して米国型企業モデルは、コーディネーション問題に対して最強の解を用意することができる。そのために、最上位指揮者の育成と選任に多大なコストをかけ、いったん指名した指揮者には絶対的な権限を与える組織間のコーディネーションにおいても、資本の論理を貫徹するため、誰が決定権を握るのかは絶えず明確であり、疑問の余地は残さない。こうした米国型の企業モデルでは、絶大な権限を握る最上位指揮者をいかに統制するのかというガバナンスの問題に加えて、本質的に置き換え可能と位置づけられる構成員をいかに動機づけるかというやっかいな課題が残る。米国企業の特徴として衆目を引く高額の金銭報酬は、このようなモチベーション問題への苦肉の対応策という可能性がある。金銭報酬が強調されるのは、それだけ押し付けられてする仕事が面白くないからであろう。 これに対して日本型企業モデルにも、とくにコーディネーション問題に固有の課題がある。深く同じ方向にコミットしている構成員を上から一方的に押さえつけることなく、如何に同じ方向に向かわせるのか、である。これは一つの職場の内部に限らず、使命と機能を異にする部門・部署間でも持ち上がる。日本企業が和やコンセンサスを重視するのは、米国企業にとって金銭報酬と同じ意味で、突き付けられた課題への後ろ向きの対応と見るのが妥当かもしれない。 コーディネーションとモチベーションのうち、慢性戦略不全に関係するのは前者の方である。コーディネーションがうきくいかないので、チグハグとバラバラが起こるというのが、慢性戦略不全の徴候にほかならない。コーディネーションを第一義とする米国型企業モデルは、こうした慢性戦略不全を未然に防ぐことを主目的として設計されている。だから、慢性の戦略不全には陥りにくい。反面、モチベーションに弱点があるので、戦略の決定に必要な情報が下部階層から上がってこない可能性や、策定された戦略が下部階層によって狙い通りに遂行されない可能性に悩まされるのである。モチベーションを第一義とする日本型企業モデルでは、慢性戦略不全のリスクを甘受して、構成員の技能の蓄積と活用を最大限に促進するという別の目的のために設計されていることになる。慢性戦略不全が日本型企業モデルにおいて多発するのはそのためである。平易に表現すれば、日本の企業はエンジンは強力だけれどもハンドルのきかない自動車のようで、米国の企業はハンドルは精巧だけれどもエンジンの馬力が足りない自動車のようなものだ。どちらがいいかは一概に言えるものではない。 こうした特性の相違が現実にどのように投影されているかを見てみる。日本では、まるで四季に合わせるように新製品が登場して、派手な広告宣伝合戦を繰り広げる。新商品が次々と生まれは消えていくというのは、米国では考えられない。このような新商品を投入し続ける企業に目を向けると低収益に喘いでいるところが多い。ヒット商品に恵まれている企業ですら、高収益と呼ぶのにふさわしい水準に業績が全く届かないことも珍しいことではない。翻って米国を見ると、成熟分野には大型の長寿定番商品が存在する。バドワイザー、クリネックス、コーク、といったどれも商品名が辞書に掲載されるほどの存在感を持っている。米国の企業は、こういう大型定番商品を大事に育て、そのマーケティングに力を注ぐのが一般的である。そういう企業は持続的に高収益を上げていることが多い。日本企業の商品企画志向と米国企業のマーケティング志向、収益という視点から見れば、軍配が上がるのは米国企業のほうであろう。新商品は固定投資を必要とする分だけ収益上は不利にならざるを得ない。枯れた商品の方でも収益に貢献するのは、プロダクト・ポートフォリオの理論が教えるところでもある。製造や物流や販売促進策をコーディネートして、また商品を群れとしてコーディネートして、そして市場をグローバルにコーディネートして、枯れた商品を収益源に仕立てていくのは米国企業が得意とする技である。 ところが視点を変えて仕事の面白さを競うならば。軍配の上がるのは日本企業の方になる。新規に商品を企画して、市場に投入するともなると、多くの社員が開発、製造、営業の実務部隊から動員され、具体的な目標と明確な終わりを持つ仕事に従事することになる。この仕事は商品という目に見える形に結実し、うまくいけばその成果は社会的にも評価される。日本企業が収益を犠牲にしてでもヒット商品作りに明け暮れるのは、その設計思想によるものと考えられる。モチベーションを第一義に据えるため、実務を司る課やチームレベルの集団が主体性を持って仕事に取り組めるように組織全体ができている。しかし、彼らには担当する商品しか見えず、隣の商品や事業は見えない。会社のために良かれと思って、彼らにできるのは、その商品を成功させるだけで、その結果、個別商品レベルの企画が独り歩きすることになる。 マーケティングの本質は、こういう課やチーム単位の活動をいかに水平横断的に、そして人の異動を越えた異時点間で、うまくコーディネートするかにかかっている。これができて初めて商品間の統一性や、進化を遂げる商品の一貫性が生まれ、買い手の信頼を集めるブランドの育成も可能になる。これはコーディネーションを第一義に据える米国企業が得意とするところである。 要するに日本型企業モデルでは、現場の独走を防ぐのが難しいのである。営業や開発では、これが収益を軽視した新商品の過剰投入に現われる。製造や開発では、同じ傾向が収益を軽視した過剰品質、過剰機能に現われる。製品機能や品質を造り込む力では国際的に注目される日本企業が低収益に甘んじるのは、ここに原因がある。まさに慢性戦略不全である。 第二章 データに見る戦略不全 1.全上場企業の時系列業績推移 著者は1960年以降の40年間にわたる上場企業の業績データを分析して次のように結論付ける。 上場企業の売上高成長率はGDPの成長率をはるかに上回っている。その意味でき、日本の経済成長を牽引してきたのは間違いなく製造業の大手企業である。ただし、問題は、これが利益を伴わない拡大であったことにある。それこそが戦略不全の現われである。 日本の製造業に対して我々が抱いているイメージは幻想と呼ぶのがふさわしいほど現実から乖離してしまっている、と言わざるを得ない。日本には「モノ造り大国」という自負があるが、それはあくまでも製品開発や開発効率における競争力の高さが証明されたからのことにすぎない。実際には、製造立国という考え方が成立するほど日本の製造業は儲かっていない。それどころか収益力の長期低落傾向に歯止めがかからなかった結果として、日本の製造業は今や資金コストの負担能力が問われるところまで追い詰められている。利益なき成長の陰には、戦略不全が存在する。 2.有料大企業の産業別日米比較 日米企業で収益力を比較してみると、日本企業はほぼ完敗という状態である。産業別の比較でも、製造業を含む全部門で日本企業が劣位にあることは明らかである。より細かな産業分類で見ても事情は変わらない。日本に比較優位があると言われてきた鉄鋼、電気・電子、電子部品・電気計測器、家電・家庭用耐久消費財をはじめとして、ほとんど全教種で日本企業の収益力は米国企業と比べ物にならないほど低い。 ここにモノ造り大国の幻想が現れている。製造業は日本のお家芸で、米国は空洞化が進んだかのような印象があるが、実態はどうも違う。真相はこういうことであろう。日本が参入した分野では確かに日本勢が市場を席巻したが、そういう分野はえてして儲からない構造にある。それに対して米国勢は、日本が参入できていない高収益分野をしっかりと押さえ込んでいる。日本企業の収益力の低さは今に始まった話ではなく、日本企業が絶頂期にあった1980年代にも低かったしも続くバブルのピークにおいてもそうであった。 このような日本企業の低収益の原因はどこにあるのかを考えると、日本企業の劣位は資産効率より、むしろ売上効率において顕著である。そこで、問題の核心は利益なき拡大、または利益を犠牲にした成長の追求にある。米国との相対比較ではそう言わざるを得ない。そこでの、日米比較から見えてくるのは、日本の大企業は、規模の優位性を生かし切れない状態に陥っている。もともとの優位が構造的な要因に依拠していないのか、時代の変化に取り残されたのか、そのどちらかとしか考えようがない。 日本企業に典型的に見られる戦略不全の症候群は、まとめると以下のように記述できるであろう。まず表に出るのは収益力の低さである。それも、売上のいたずらな拡大からくる低収益にほかならない。開発部隊が新製品を造れば作るほど、製造部隊がモノを造れば造るほど、営業部隊がそれを売れば売るほど、どんどん深みにはまっていくような低収益の図式である。実務部隊の第一線が一生懸命努力しても、その努力を収益という果実に結びつけるための何かがここでは欠けている。戦略の欠落を感じさせる症候と言ってよい。戦略の欠落は、環境の良しあしを問わずに低収益を体質化する。追い風の吹く環境で、実務部隊が合議で合意を形成するとしたら、共通して認識された合意しやすい選択肢、いわゆる「流れにつく」選択に落ち着く。こういう選択肢は、実は競合他社にとっても合意しやすいことが多い。その結果、同類の企業は市場で正面衝突を繰り返し、差別化の努力も小手先で終わることになる。一方、向かい風の吹く環境で、何かをするとしたら選択肢は多岐にわたり、容易には合意に至らないであろうが、ひとつだけ共通して意識にのぼる選択肢がある。様子見である。かくして逆風下における戦略の欠如は無為無策を半ば保証することになる。これに対して、米国企業で目立つのは、暴走型といえるような経営トップの戦略構想が現実にそぐわなかったり、実務部隊による遂行が伴わないようなケースである。 3.特定産業内の企業別業績比較 こんどは、特定の儀洋酒というくくりの中で日本企業同士を比較する。これまで言及した戦略不全の構図が正しければ、歴史が古い企業であればあるほど、そして売上が大きい企業であればあるほど、無為無策型の戦略不全に陥りやすく、その結果として収益力も低いことが予想される。それをデータによって検証を試みる。 ここで取り上げる特定産業は、精密・電機産業である。そこで高収益業は比較的新しい企業で、事業ドメインが定まっていて、明快な得意技を持ち、それによって基幹事業を深耕することで、安易な多角化に走ることなく成長を遂げている企業である。これに対して、業界を代表すると自他ともに認めるような企業は、多角化を推し進めた結果として規模で他社を圧倒するにもかかわらず、収益力では劣っている。 全体を展望すると、事実はおそらく次のようなところではないかと考えられる。即ち、企業は成長を指向するが、一般的傾向としては収穫逓減の法則に晒されている。したがって、創業以来時が経過すると共に規模は拡大すれども利益率は低下する。ただし、これは不可抗力というものではなく、むしろ無為無策の為せる業である。この傾向に打ち克つということこそが、戦略の本質と考えるべきであろう。伝統ある大企業が慢性的な低収益に甘んずるとすれば、それは戦略不全の繁栄に他にならない。 ここから見て取れるのは、規模の拡大と共に収益力が悪化する現実、そして、規模の大きい企業の方が低収益に甘んじている現実が浮上してくる。本来ならば、規模の経済という概念が存在するように、規模は企業にとって福音のはずである。例えば、規模が拡大すれば、それに合わせて比例的に増やす必要のない固定費を相対的に削減したり、増大する交渉力を背景に変動費を削減したり、増大する市場支配力を背景に価格の下落を阻止するなど、利益率を引き上げるなど、利益率を引き上げる可能性がいろいろ開けてくるとされている。 しかし、規模は成功の原因ではなく、むしろ成功の結果であると考えると、規模は両刃の刃として考えられて来る。規模は利益率を引き上げるテコにはなりうるが、引き下げる重力としても作用するからである。例えば、一つの市場を制覇した企業が規模を拡大するためには、企業の活動範囲を水平的に拡大するか(多角化)、垂直的に拡大するか(垂直統合)、地理的に拡大するか(国際化)のいずれかしかない。どの道を選んでも、企業の経営は複雑さを増していく、経営の枠組みがそれに伴って進化していかない限り、経営が規模に負けて効率を落とすことは避けられない。規模の不経済とも言うべき現象がここに発生する。規模の不経済は主に企業の間接部門で問題となる。直接部門で規模の経済が働くのとは好対照と言えよう。およそ企業という存在は、その効率を業務プロセスの定型化に負っている。定型化するがゆえに、企業は経済性を発揮すると言ってよい。この定型化をする時に企業は一定の範囲の企業活動を想定して最適化を図るが企保の拡大はこの想定範囲を結果的に無効にし、定型化のやり直しを多くの間接部門分野に要求する。グローバリゼーションに伴う人事制度や経理制度の改訂は、その良い例であろう。規模の飛躍的な拡大を狙う合併ともなると、さらに大幅な改訂を必要とするのが常である。再定型化は、その努力自体がコストを発生させるだけでなく、それがうまくいかないことに伴う間接的な、測定されないコストをも随所に発生させる。この後者にあたる部分が意外と大きいのである。規模の経済は、拡大する前から存在する資産に追加投資することなく拡大後もこれを使い続けることから発生するが、再定型化は逆に拡大する前から存在する資産を無効にし、一からの再投資を要求するのである。これが規模の不経済にほかならない。その大きさは、再投資の深度と頻度にもよるが、それ自体は企業の持つインフラストラクチャーの頑健性で決まるものと考えられる。 日本の電機業界には円高と、そこから発生するグローバリゼーションが鬼門となっていることが明白である。これに的確に対処することなくいたずらに規模の拡大を指向したことが、劇的と言ってよいほどの規模の不経済を生んでいるのではなかろうか。これも無為無策型の慢性戦略不全にほかならない。
第三章 ケースに見る戦略不全 利益率については、コマツは長期的なジリ貧傾向にあり、これに対してキャタピラーは高収益を確保している。最終利益の累計では両者間に大きな差が開いている。また、コマツは本義用の建機ではキャタピラーに水を開けられ、脱建機もならず戦略不全に陥ったと言える。 ここで、両社の違いを見てみる。両社の決定的な差の一つは建機事業に対して抱く事業観である。米国では1960年代に高速道路網の建設が一巡し、日本でも石油危機を境に高度成長が終焉を迎えている。母国における建機事業の春は過ぎ去ったという認識では両社ともおなじであろう。問題は発展途上国の市場をどう見るかにあった。コマツは悲観論を貫いている。中南米政府の過剰債務問題に敏感に反応したからである。これに対し、キャタピラーは、発展途上国が世界人口の81%と地上面積の74%を占めることを見据えていた。しかるに同社の途上国売上比率が23%にとどまることから、ここに未来の事業があると喝破したのである。キャタピラーは「21世紀の最初の10年はグローバルな競争力が企業を選別する」との認識の下に着々とオペレーションをグローバルに拡充し、他方で一時的な景気後退に備えるために、製品ラインや事業地域の多様化と、コストや資産の管理強化を怠らなかった。同時に開発途上国の市場を開拓するために、中古建機のグローバルな流通や購入資金のファイナンスを司るサービス事業を自ら整備していったのである。 これに対して、コマツの年次報告書を見てみると事業に対する大局観が見当たらず、基本的には今期の業績を分析して、来期の方針を確認するというだけである。その意味で、期待値に基づいて長い未来を最適化するというよりも、t期の出力に反応してt+1期の制御をするという印象がある。日本企業は長期的視野から経営にあたると言われてきたが、実態は異なると思わせるものである。たしかに、t期の業績が悪いからと言って、製造や研究開発に対する投資を絞ったり、人件費に手を付けるということはしていない。 意思決定のアルゴリズムという点では、両社の間には別の差がある。キャタピラーは農機から建機に転進したり、工場を大胆に閉鎖したり、過去にこだわるそぶりを見せない企業である。これに対して、コマツには、「すでにあるものは生かす」という発想が根づいている。建機事業で世界第2位の地位を手に入れた時点では、創業時の多角化に着手した時点とは状況が大きく異なったはずであるにもかかわらず、「今まで蓄積した技術があるから」というように理由で、非建機事業を投資対象とし続け、そこには非建機事業のプレーリアップ・バリューを検討した痕跡はない。同様に、新規成長事業の育成を図るときも、種をいろいろまいてみて、芽が出たところに水をやるというのがコマツのスタイルになっている。すなわちコマツが将来どういう企業になるのかは、種まきの結果次第、お天道様次第なのである。自らの意志の力で自らなりたい企業になるという強固な姿勢を貫くキャタピラーとは、根元的な違いがある。 両社の対比でもう一つ目立つのは、企業と経営者の関係である。日本の企業はボトムアップとよく言われるが、トップの「個性」が意外と大きな影響力を持っているようである。実際にコマツでは社長が変わるたびに新社長の「思い(または意思)」が前面に押し出され、それがコマツという企業のカラーを染め上げている。その意味で、コマツをどういう企業にしたいのかという意思は、コマツにも存在した。意思というのは、それぞれの社長の心の中に存在したからである。さらに歴代社長が「なりたい企業像」を語るときは、「良い会社」に代表されるような、きわめて抽象的な言語が使われる。その点でも「思い」という言葉がぴったりであろう。 他方のキャタピラーでは、価値判断を含む言語は見当たらない。歴代の経営者が理想とする企業を語るときは、あくまでも事業のポートフォリオと各々の事業における市場地位というきわめて具体的な戦略の言語が用いられているのである。経営者の語り口には、企業は先達から受け継いだ公の人為機関、経営者といっても一個人が好き勝手にしてよいものではない、企業は株主に買ってもらう商品として磨かねばならない、という基本認識がにじみ出ている。
第二部 戦略とは何か 第四章 演繹的マクロ戦略論 まず、著者は理論と実務の違いから見ていく。理論と実務の間に距離があるように見えるのは、両者の間に厳然として時間尺度の相違があるからである。実務の世界では、土岐は連続に流れるものである。卑近な言い方をすれば、仕事は毎日ある。日々の活動、これらに付随するカネの流れやヒトの働きを管理する業務など、日々刻々と動いている。こうした業務では、様々な工夫を凝らす余地が担当者レベルでは無尽蔵にある。創造的な意思決定を休みなく下す人たちが、企業は自分が動かすと認識しても無理はないし、企業というものは膨大な数に上る意思決定変数を持つものだと考えるのは当然と言える。問題は、そういう業務上の意思決定と、企業の長期収益の関係である。業務は絶えず動いているが故に個別の意思決定はやり直しがきくし、修正も随時迫られる。それに加えて企業の意思決定は複数の人を経て組織的に下される。これを高い見地から、長い目で見たときに、本当に企業間の業績差異を生み出すことになるのだろうか。おそらく、そうではあるまい。経済学が企業をモデル化するときは、業務上の意思決定は合理的に下されるものという前提に立ち、それを企業の利益最大化行動として表現する。戦略論が取り上げるべきは、こうして最大化された利益の大小を左右する要因に他ならない。言い換えれば、企業で働く人たちが最善を尽くした後に決まる利益の多寡を何が決めるのかという問である。枝葉を取り去ったのちに見える幹の姿こそ問題なのである。経済学は、その何たるかを教えてくれる。 企業収益を究極的に規定するのは、自社と競合他社のコスト、市場への参加企業数、及び需要曲線と費用曲線の形状である。それがモデル分析から得られる直接の結論になる。このうち、コストと競合企業数は完全には外生変数とは言い難い。コスト優位が利益につながるとしたら、企業はコストを従属変数もそしてコスト低減に向けた投資額を独立変数とするゲームに従事するであろう。競合企業数も、長期的には企業の自由意思による参入と退出の結果、内生的に決まってくるものである。そうなると、均衡状態で残るパラメーターは需要構造と費用構造に限られると言ってよい。こういう構想を選ぶことは、企業が長期収益を拡大するためにできることのうちでもっとも基本的な手段である。では、構造を選ぶとは具体的に何をすることをいうのであろうか。ひとつには新たな市場へ新規に参入するという大きな決断がそうである。ほかにも、すでに参加している市場から撤退するとか、その中でセグメンテーションの取捨選択をすることがそれにあたる。こういう選択にあたって考慮すべき事情は多岐にわたる。その個々の事情の分析は本書に当たるとして、世の中には構造が好ましい市場と、そうではない市場が並存している。企業の戦略を考える時にもっとも重要なポイントは、避けるべき市場を避けて、いかに好ましい市場に経営資源を集めるか、ということになる。「自らに有利なゲームを選んでプレーせよ」と俗に言うが、大事なのは自社の強みを生かすことだけではない。それとは別に、利益の出やすい構造を選択するという発想も重要なのである。 費用と需要の構造は、企業にとって確かに基本的な戦略変数である。ただし、これを選択するという行為自体は、かなり受動的な色彩が濃い。それに対して、もう少し能動的な戦略変数として、競合企業数を上げることができる。この変数自体は内生的に決まる側面もあるものの、企業はこれに参入制限という形で働きかける手段を持つのである。競合企業数を減らすことは、費用や需要の構造いかんにかかわらず、収益性の向上に貢献する。参入制限には、競争と協同という2つの側面がある。競争の方は、既存の競合相手とは袂を分かち、新しい市場を自社のみで構成しようと動くことである。その成功には何らかの有効な差別化が必要不可欠であり、同業他社の追随を振り切るという意味で、競争が必然となる。それがうまくいけば、たとえ市場は小さくても、企業は新しい市場で独占利益を手にすることができる。協働の側面は、新規参入を阻止するという点において既存企業が利害を一にすることから発生する。例えば、市場を新規参入から守るためには、参入企業がクリアすることを迫られるバーを上げればよい。ここで言うバーとは、たとえば品質やサービスについて顧客が抱く期待の高さ、安全性や環境対策について行政当局が持つ要求水準の高さ、または参入に際して必要となる一般的な投資の大きさのことである。利害を共有する企業は、ここで共同戦線を張ると相互に得をする。念のために補足しておくと、新規参入を阻止する方法は製品自体の差別化に限定されるわけではない。参入障壁そのものは、変動費用や固定費用にあってもかまわない。潜在的参入企業に対して決定的な非対称性を何らかの形で作り込めばよいのである。参入すれば強硬な反攻措置が待ち受けると既存企業が参入を検討する企業に信じ込ませることができれば、それが有効な参入障壁になることは十分に考えられる。 差別化という概念は、一般に競合企業数を小さくするための行為として理解されている。これは企業間の水平的な差別化という話であるが、実は対顧客の垂直的な差別化も利益の拡大に別のルートで貢献する。最後にこの可能性を吟味する。クールノーのモデルでは均衡状態において大きな消費者余剰が発生している。消費者余剰とは、消費者は払ってもよいと思っていたのに、実際には払わなくても済んだ金額の合計に相当する。これが企業の隠れた利益の源泉になりうる。そもそも、需要曲線が右下がりということは、その市場で売買される製品に対して消費者が支払う意思のある最高基準価格が一様でないことを意味している。その製品に高い価値を認める人から、価値をほとんど認めない人まで、色々な人がいるということである。そういう中で、均衡価格より低い最高基準価格を持つ消費者は、結果的に購入を見送ることになる。逆に均衡価格より高い最高基準価格を持つ消費者は喜んで購入に踏み切る。彼らにとっては実際の取引価格が自らの最高基準価格を下回る分だけ「儲け」になるからである。この「儲け」をすべての消費者について合計したのが消費者余剰、すなわち消費者の節約額を示す尺度となる。この消費者の「儲け」は、取りも直さず企業の損失、利益の取りこぼしである。このような取りこぼしが回避できないのは、個々の消費者の持つ最高基準価格を見破る術を企業が持たないが故に、誰に対しても均一の価格で売ることを余儀なくされるからである。すなわち、消費者余剰は一物一価の裏返しなのである。こうした事情を理解すれば、企業が利益を拡大する第3の道が見えてくる。他社を相手にするのではなく、ここでの焦点は顧客との駆け引きになる。企業が消費者余剰を取り込むには、最高基準価格の高低に応じた複数の価格、すなわち「差別価格」を導入する必要がある。問題は、個別消費者の最高基準価格に関する情報がないままで、いかにこれを実現するかである。工夫の一つは、酒匂基準価格の高低に相関する代理変数を見出し、これに価格を連動させることである。携帯電話などの学生割引は、この典型例として知られている。もう一つの工夫は、能動的に差別価格を設定しに行くのではなく、異なる価格を用意しておいて消費者が自己選択するのを受動的に待つといういき方である。最高基準価格を見破る術がないのなら、消費者に「自白」させればよいのである。
第五章 帰納的ミクロ戦略論 このようなマッチングペア分析の結果を見て、第一に頭に浮かぶのは、前章から持ち込んだ「構造の選択」という視点である。これまで分析の俎上にのせたペアは、需要や費用の構造を一にする事業を営むか、またはそういう事業の集積を営んでいる。構造が利益率を支配的に規定すると考えれば、データの説明はすべてうまくいく。ここで構造支配仮説を受け入れると、構造が利益率の上限を決めてしまうことになり、企業がその下でできることは、その上限以下に利益を落とさないことだけである。となると企業にできる戦略は、自らを翻弄する環境を選ぶことに収斂する。すなわち、構造の選択である。同じ構造を選択する限り、ペアを構成する企業間で利益率の変動パターンと水準に大差は見られない。大差が見られるのは、むしろペアとペアの間である。となれば企業にとって重要なのは、選択した構造の下であがくことよりも、選択する構造そのものをうまく選ぶことになる。そして、構造をうまく選べば、参入もおのずと制限される。これが戦略論の原点に他ならない。構造は、本当にそこまで利益率を規定するのであろうか。データ分析の結果は、需要構造は、利益率の水準に決定的な影響を及ぼしているというものであった。構造が決まれば、利益率はほとんど決まってしまうのである。これらの結果から読み取れることは、個々の企業が戦略不全に陥っているとも読むこともできるし、経営環境を共有する企業が逐次適応の経営にベストを尽くすとき、結果は基本的に横並びになると読むこともできる。だから、最初から有利な構造を選べというのは、一つの考え方である。だから逐次適応の経営に終始するのはダメであるという考え方も成立する。前者を採れば、すでに悪い構造を選択してしまった企業は大胆な商売替えを模索するしかないことになる。また後者をとれば、それとは別の道があることになる。しかし、例外的に、ペアの業績が全く交わらないケースも存在する。戦略とは、そのような乖離に見て取るべきかもしれない。 ここで、本書では例外事象として四つのケースを分析しているが(個々のケースは本書を参照すると興味深い)、そこには一つの共通点があると著者は言う。すなわち、いずれの企業も決して競争から隔離されているわけではないのに、同じ競合企業といってもぶつかり合うという姿が見られない。言うなれば競争はあっても「宿敵」がいないのである。マッチングペアの相手方の企業には不可解、または不当な比較と映る可能性が高いのである。この現象を著者は「異質化」と呼ぶ。宿敵がいないゆえに、このような企業は結果的に構造の選択や参入の制限や価値の捕捉をしたように見えるのである。必ずしも意図してそういう選択や補足をしているわけではない、だから、演繹的なマクロ戦略論に違和感が残るのである。意図してなされることがあるとすれば、単なる製品の「差別化」を超えて、事業の構えを微妙にずらす「異質化」と捉えた方がよい。そこで、著者は事例を分析して、異質化にかかわる戦略の四つの類型を見出している。まず、異端一貫型は、量産を手掛ける大手競合相手がいる業界で、大手とは全く競合しないビジネスを展開する事例である。カスタム製品を取りそろえ、ソリューション営業を展開し、モノ造りへの固定投資を最小限に絞るなど、企業の構えが一貫しているところに鍵がある。継続一貫型は、潜在的な競合相手がいる業界で、徐々に競合を振り切って、独壇場を築き上げた事例である。早い時期からやることを絞り込み、わき目も振らずにそれを徹底してやりぬいているところに鍵がある。営業能力型と製造能力型は、やはり競合相手のいる業界で、独自の能力によって局所的に競争を中立化している事例である。鍵になる営業能力や製造能力は、天賦の才というよりも競合他社とは違う発想で投資を振り向けた効果によるところが大きい。以上の分類では、運や偶然ではなく、企業の主体的な判断と営為がある。有利な構造を人為的に作り出しているという意味で、まさに戦略性が高い長期収益率を齎している事例と言える。
第六章 大局的判断の戦略論 企業が異質化を遂げるプロセスを追いかける。まず、その主体として、戦略を担うのは経営トップに限られる(Who)。異質化の発想は、成否を論じることができるものでもなければ、合議で決められるものでもない。些細な優劣を正すことに比べれば、全体の統合性を保つことの方がけた違いに重要である。であるが故に、異質化の発想は一人の人間の頭の中で生み出されるべきものなのである。ここで、前章でとりあげた長期の高利益を実現している企業を見てみると、立役者のような経営者が存在する。高収益企業が高収益たるゆえんは、戦略を担いうる強い経営者の存在を抜きに語ることはできない。 次に、異質化を遂げるタイミング(When)を考えてみる。まず、予め戦略という大きな塊があって、その通りにトップダウンで動くという構図は現実的ではない。経営者の机の上にあるディスプレイには日々刻々と現場から営業日報が集まってくる一方で、部屋の外には決裁を求める社員たちが行列をなす。そして、数ある会議の最中にすべての予定を吹き飛ばすような緊急案件もたまに飛び込んでくる。戦略の実体とは、こうして無秩序にやってくる、1つ1つの小さな判断の、長い期間にわたる積み重ねに他ならない。だから、戦略は事後的に浮かび上がるものであって、事前に鎮座するものではないのである。特に異質化は事業の構えに関わることであるが故に、第一歩が肝心であることは間違いない。ただし、いつ、どこからでも、それは容易に風化する。せっかく築いた土手が、そこに開いた小さな穴からやがて決壊するのと事情は変わらない。築いたらおしまいではなく、むしろその後が勝負とすら言ってよい。 所在(Where)の意味でも、これとよく似ている。戦略は、よく知られたPDCAのサイクルのようなフィードバックループを持つものである。そうなるのは、ひとつにはすべてを最初からみ切ることは不可能だという事情が関係している、さらには、すべてが最初から思い通りに運ぶとは限らないという事情もある。いずれにせよ、戦略とは事後的な微調整を必要とするものであり、そのためには経営者がフィードバックのかかる現場にいなければうまくいくものでない。 戦略の営為(What)は、経営者が能動的に仕掛けるループと経営者が受動的に迫られる一連の判断の組み合わせと考えるのが良い。戦略とは、能動的に構えることであり、受動的に判断することである。勿論、より具体的なレベルに降りていくと、核心や判断が何に作用するか、また作用すべきなのかという問題に直面する。収束不能なくらいに、具体的な決定事項は多岐にわたる。 次に戦略の論理(Why)と手法(How)を考える前に、戦略プロセスにおいて変わらないものは、戦略の主体である経営者の頭の中にあって、彼が個々の判断を下すにあたって参照する、判断の拠り所のようなものである。個別判断の中身は時と状況に応じていようにも変わるものであるが、その背後に控える判断の拠り所のほうはそう簡単に大きく変わるものではない。しかも、それは1つの塊として存在する。ここではそこに注目して、個々の判断を間接的に規定する準拠枠のことを広く「事業観」と呼ぶことにする。事業観とは、人が頭の中に持つ基本辞書のようなものである。この辞書が、情報から判断へり「翻訳」を司る。我々の周囲に存在する事物や、我々の周囲で起きる様々の出来事は、それ自体意味を持たない客観情報として頭の中に飛び込んでくる。それに主観的な意味を付与するのが基本辞書で、意味がいったん定まるとそこから半ば自動的に判断が導かれる。だとすると、問うべきは個別の判断よりも基本辞書ということになる。例えば、工場の床に落ちているボルトを見て、ただのボルトと受け止めるのか、清掃の不行き届きと見るのか、ボルトが抜け落ちたはずの機械の故障を心配するのか、は人が持つ基本辞書次第である。元は同じ情報でも、翻訳次第で大きく判断が変わりうることは、これらの例から明らかである。基本辞書が人によって異なるのは、それが「意訳」を含むからである。そして、単なる意味解釈の体系から始まる基本辞書が膨らんで、何をどうするとどうなるという因果関係の体系を含むようになり、そして何は何より大事かという優先順位の体系を含むところまで拡大すると、翻訳は深い理由に裏付けされた判断、そして行動に直結する。さらに優先順位の体系が頭の中で充実して来ると、その上に自らが携わる事業の見方とでも言うべき基本認識が成立する。これが更に強くなると「この事業はかくあるべし」という核心に最後は発展するのである。事業観とは、このような体系の階層を網羅する概念に他ならない。基本辞書の中にこういう体系の階層がどこまで積み重なっているかは、人によって様々であろう。そういう中で経営者を経営者たらしめるのは、基本辞書の厚みになければならない。この体系の階層の積み重ねが稠密で、かつ厚い時、そこから生まれる判断は大局的と呼ぶにふさわしくなる。 議論はこの後、企業戦略論の系譜と事業戦略論の系譜として戦略論の系譜を振り返りますが、興味ある方は本書を参照願います。 第三部 戦略不全の背景と処方箋 第七章 経営戦略の3要件 1.非合理性 戦略は、ある種の非合理性を必要とする。どういう事業に魅力を感じ取るのか、事業のどこに広がりを見出すのか、事業の収益構造をどう読み取るのか、事業を左右する組織能力をどう見るのか。こういう天下分け目の判断を、単純な理に照らし下してはならない。これが、戦略に課せられた要件の1つであり、戦略を難しくするもっとも高いハードルである。 経営で迫られる判断は、純粋に数理でも道理でも割り切れるものではない。カネとヒトの両方をインプットとして用いる以上、経営はむしろ数理と道理の間で折り合いをつけるように宿命づけられている。絶対性を帯びる真理はここでは判断の基準にはならないのである。だとすれば、人はどこに理を求めるのであろうか。これを読み解く鍵は人間社会性という原理にある。人間は一般に人の同意や共感をえること、社会に広く受容されることに価値を見出す。だから、それなりに筋道を立てて物事を判断しようとする。人に受容されたければ、人に理解されやすい筋道を立てるのが一番の早道であろう。ここで心理に代わって判断の基準となるのは情理であろう。しかし、情理そうものを合理的とは言わない。情理の問題は筋道を取り違えている点と、ローカル性の組み合わせにある。経営のコンテクストに限って言えば、企業や事業の長期収益が最優先されてしかるべきなのに、情理を理とすると、一事業所や一個人の利益を守るために大本の目的が犠牲にされかねない。また、他方では、全体の長期収益につながるとされる筋道は、それを受け入れる人が自ら検証する心理ではなく、世間一般で受け入れられているから自分も受け入れるという類のものが多いはずである。これは一般常識を重んじることから常理と言ってよい。このような常理はたしかに真理を含むこともある。逆に真理の顔をした嘘もそこに紛れ込んでいる。たとえば、規模の経済の関する通説がそうである。我々が合理というとき、実はこういう常理にかなうことを指している場合が多い。合理がこのような常理にかなうことを意味するのであれば、戦略はそれを否定する非合理でなければならないということである。戦略を司る人間には、少なくとも合理を部分否定することが求められている。理由は2つある。1つは常理が常に正しいとは限らないからである。もう1つは、常理がまさに大方の人の判断を形成するからである。戦略は、どこかで多数との同質競争を回避しなければならない。常理が良しとすることは他社も良しとする可能性が極めて高いということ自体に、すでに致命的な問題があるとしるべきで、戦略は、どこかでもっともらしい嘘の虚を衝くときに、最大の威力を発揮するものなのである。ここで常理に代わる理が「理外の理」、すなわち常識に潜む嘘の虚を衝く妙理に他ならない。良い戦略とは、常理に照らせば非合理であると同時に、理外の理に照らせば合理でなければならないのである。これが戦略に課せられた最大の要件である。このハードルは難関である。理外の理は、それを見抜くこと自体が難しいうえに、死優位の理解を得るとなるとさらに難しい。それに対して多くの人が知的理解を共有する常理に基づく判断は、社内でも合意を取り付けやすい。しかし、社内で合意を取り付けやすいということは、他社でも事情は同じと知るべきであろう。とういうやすき判断につけば、結局は多数による同質競争に陥るだけである。ただし、その悲惨な帰結が露呈するのはずっと後になってからのことなので、常理は無傷で生き延びるのである。 2.不可分性 戦略は、オペレーションのパッケージである。分業に付された「部分」のコーディネーションを司るためにこそ、戦略は存在すると言ってよい。だから戦略は、絶えず「全体」の一体性を保証するものではなくてはならない。たとえ見ていても戦略を模倣することが難ししいのは、それが大きな塊として初めて意味を持つからなのである。 現代の大企業の規模と生産性を支えているのは分業というシステムである。その分業の大きなメリットの理由として、アダム・スミスは次の3点をあげている。作業の単純化が手先の習熟を促すと言うのが1点。作業の専業化が段取りを固定費用化する、即ち、作業から作業へと移るたびに段取りをしなくてもよくなると言うのが2点目。そして、作業の単純化と専業化が作業者自身による作業の機械化を後押しするというのが3点目である。スミスのあげる理由はこれだけだが、著書はこれらに加えて、分業が許容する知識の多様化を指摘する。現代の社会は1人1人が異なる知識を持っていても機能する分業社会を我々が発展させたからこそ、社会全体の生産力が飛躍的に増大したと言う。そして、企業の巨大化を支えるのは、実はこの知識の分業に他ならないという。現代の大企業は、事業、職能、地域に応じて人が分かれ、精緻な分業の体系を築き上げている。企業として抱える知識の総体は、確実に上昇の一途にある。それが生産性の向上をもたらし、企業の巨大化を可能にするのである。 しかし、企業内分業は、良いこと尽くしでしない。スミスが指摘するように、分業は人の注意の焦点を限定するのである。限定された領域の中では注意の密度が上がるため望ましい効果も見込めるが、その外側では深刻な弊害が発生しかねない。現代の大企業は、研究、開発、生技、品質、購買、製造、物流、営業、情報、人事、経理、法務といった職能部門にあたかも当然の如く分かれている。必要とされる専門知識に応じて要素的に仕事を分解しているわけである。ここでは注意の焦点が局所化される。視野が限定されると、人はどうしてもその中で物事を判断するようになる。視野の内と外では入ってくる情報量に圧倒的な差ができるため、一種の非対称性がここで生まれるのである。自分下す判断が視野の外で何らかの影響を持つことは分かっていても、その影響に関する情報が入ってこなければ、あたかもむ視野の外は存在しないがことくに振る舞うしかないのである。そこで、担当外職務のパフォーマンスを傷つけるような判断を、分業は善意の人にさせてしまう。部分最適化という現象である。 分業は、本当にそれを生かすためには、他方で統合を必要とする。統合、またはコーディネーションによって部分最適の弊害を抑制しないと、分業の利を害が上回ることになりかねない。戦略の存在理由は、ここにあると言ってよい。経営は分業するものであるが、戦略を分業するということは原理的にあり得ないのである。戦略は、高度に統合されたパッケージでなくてはならない。さらに、戦略とオペレーションは不可分に結びついていなければならない。戦略なきオペレーションは、いくら斗力を積み重ねても長期の高収益に結びつかないし、戦略がオペレーションから遊離すれば空理空論に陥る。 その象徴が経営トップである・長期に高収益を実現している企業では経営者が現場に強いことも共通している。現場が部分最適に陥ることを防ぎ、全体の統合を保つためには、経営者が雲の上に鎮座していては話にならない。組織がいくら巨大なっても、視野に制限がかからないのは、経営者だけなのである。分業の枠によって与えられた役割に制限されることなく、自由に動き回れるのも経営者だけなのである。経営者が全体と部分間を上下動することによって、初めて戦略は統合の要件をみたすことができるのである。 3.非可逆性 戦略は、取り消しや、やり直しが可能なものではない。簡単に手を戻すことができるならば、試行錯誤を通して逐次最適を図ればよいだけである。そういう施策が競合他社との間に決定的な収益力の差を齎すことはあり得ない。戦略は、それが有効であるためには、後戻りができない選択に自らを縛り付けるコミットメントでなくてはならないのである。これが第3の要件になるのである。 企業は、単年度を基本サイクルとして活動する。中期計画といっても、たかだか向こう3年をにらむ程度である。それを超えてプランニングをしても、市場や技術がダイナミックに変化していくために、プランの仮定が崩れてしまい、意味がないと言う。組織的なプランニングをしようとすれば、確かにそのとおりであろう。ただし、戦略とプランニングは別物である。戦略を考えるとき、もっと長期の因果関係に依拠した上で、強い企業や事業をつくるという発想を持たねばならない。企業の命運や長期収益は、新商品の開発や市場投入、マーケティングのようなところで決まるのではない。商品を超越する次元にある企業や事業の構え、そしてそういう構えを左右する大局的な判断、商品のはるか以前に来る判断なのである。 大局的な判断は、あとから振り返れば、どの意思決定がそれに相当するのかを特定することは可能であろう。ただし、判断を下す当事者にしてみれば、事後的にあれがそうだったと指摘されても仕方がない。これがそうに違いないという具合に、どの意思決定が戦略性を帯びる大局的な判断に相当するのか、事前にわかるものではない。当初は小さな意思決定が結果的に大きな差につながるということは、経営においてはよくある現象である。 最初の判断は、小さな偶然に見えるかもしれない。しかし、判断が蓄積に転化するプロラスを経て、その功罪は何倍にも拡大されることになる。そういう判断こそが、結局のところ超長期的における企業の業績を決定的に左右するのである。それを大局的な観点から的確に下し、その意図を貫徹することは、社員が何十人いようが、経営者その人にしかできない仕事である。
第八章 日本企業の経営者 戦略は、非合理、非可分、非可逆でなければならないが、その要件を満たすのは尋常な努力の範囲では難しい。戦略を司る経営者に、強靭な頭脳と幅広い経験と長期の在任、すなわち若くしての着任が同時に求められるのである。日本型の企業モデルにおいては、一般社員のモチベーションが優先される陰で、そういう経営者を育て上げると言う発想は後手に回りがちになる。それが、慢性の戦略不全を招くのである。 日本企業の多くが慢性の戦略不全を患う最大の理由は、社長の在任期間が戦略の最低スパンに届かないことにある。その結果、経営は短命社長からから短命社長へのバケツリレーに委ねられ、戦略の非可逆性原則を満たすことはできない。これを本書では、精密・電機業界でデータにより検証している。 このような、日本の企業において社長の任期が著しい短縮化の方向に向かった背景には、所有と経営の分離という現象がある。そして日本企業は、この変化に適用する術をいまだに持てないままでいる。それが戦略不全の核心的な病原に他ならない。実際に、電機・精密機器業界の1部上場企業のうち、創業経営者が戦後の立ち上げに関与したところが7割を占め、日本は20世紀後半幕開けを所有と経営が未分離のまま迎えたという、現代日本の企業社会が成立過程において大きな歴史的特殊性を内包しているのである。それが1970年代以降、所有と経営が分離する方向に動き出した。試に在任期間が30年を超える経営者が存在する企業を見てみると、個性の明確な企業が多い。これは強力な社長が一貫して30年以上も企業を牽引する中で、明快な構えが現実のものとして定着し、成功した後もその構えから逸脱することがなかったためと考えられる。 これを踏まえて、著者は次のような仮説を提出する。即ち、終戦直後の日本は瓦礫の山から再スタートすることを余儀なくされたが、これが近来稀にみる創業、または第2創業の機会を提供した。この機会をものにした創業経営者が20年、30年と指揮を執る中で競争に勝ち残った企業は、そういう長命社長の下で強固な事業基盤を整備していった。こういう企業を中心にして、日本の企業は世界の檜舞台に躍り出ていったのである。ところが、創業経営者もいつかは第一線を引く運命にある。創業一族から後継社長が出ない、または出さないと決めた企業では、創業者の引退をもって所有と経営が分離する。ここで登場する専門経営者は、一社員として入社して、多くの上司に仕え、仕事で成果を上げてきた人である。初めから守るべきものを背負って登板するため、なかでもリスク回避を得意とする賢明な人物が指名されやすい。リスクを取って裸一貫からスタートし、ずっと経営に携わってきた創業者とはまるで好対照な人の手に、経営の主導権がここでシフトする。こういう専門経営者は、就任時点で他の社員よりも年長であることが一般的で、任期が数年しかないことを本人も周りも了解している。そういう体制の下で、専門経営者は創業者が残した事業基盤を継承して守ることに終始するが、いくら出来の良い事業基盤でも、時代の変化に伴って陳腐化することは避けがたい。ところが、4年や6年で交替していく専門経営者には、変化に対して本格的な手を打つ理由も、意欲も、能力も欠けている。こうして戦略不全が慢性化し、収益率は全体として長期低落の傾向を示すに到るのである。 2.事業経営責任者の管理職化傾向 社長の短命化もさることながら、社長の下で事業を営む事業経営責任者の階層まで降りていくと、経営職の管理職化傾向がそれに輪をかけて深刻なのである。そこには、制度が管理職になることを促す側面と、人自身が管理職になりきっている側面と、両面が存在する。 著者はある企業の事業部長を対象にした実態調査のデータをもとに分析する。その結果として。約70%が何らかの切り口をもって事業経営に当たっているが、事業全体のあるべき姿、あるいは方向性を見究めている人は10%に止まった。これが事業レベルにおける戦略不全の真相と著者は指摘する。現状を改善する切り口までは持っているのだけれど、戦略には手が届いていないのである。彼らの口から戦略を聞くことができないのは、彼ら自身の役割認識にあると著者は言う。かれらは、人を生かすこと、人を育てること、目標を設定すると、彼らは口にする。要するに、日本企業の事業経営責任者は、経営者というよりも、組織を構成する役割の一つを務めているのである。そこに、トップが戦略を決めるという発想はない、大事なことは職場の長が発案し、彼らの合議で決まる。これが分業経営の実相に他ならない。 事業部は、その運営には資金が必要で、そういう資金を企業の内外から調達して事業観に配分するのは本社の役割である。ところが、ここで事業部と本社との間に利害の不一致と情報の非対称性が存在し、それが事業統治の問題となっている。当地の問題は一種の二律背反を含んでいる。一方で縛りを設けないと資金を拠出する側の利益が守られないが、縛り過ぎると今度は経営に無用な制約を課すことになる。そうなれば、かえって資金拠出する側の利益が損なわれることになる。制度設計上の要諦は、いかに軽い縛りで効果的な利益保護を実現するかにかかっている。しかし、事業統治の縛りは重量級である。事業統治の本流を成すのは、本社による直接モニタリングである。これは人事権とキャッシュ、すなわち生殺与奪の権に裏付けられているだけに、事業部側に抵抗する術はない。実際のモニタリングは定常的には事業計画を中心にして進むことが多い。本社側は事業計画の策定段階でチェックして、あとは月次決算の対予算比をモニターする。そこで異常が検知されれば、原因の精査に乗り出す。このような事業統治の下で、事業経営責任者にフリーハンドの経営者として振る舞うのは無理と言える。長期の戦略より、月次の事業計画ということになる。しかも、事業経営責任者の任期は社長以上に短い。その理由は、本社による人事権の発動である。それは、企業本体の経営陣への人材供給のパイプラインを確保する必要からである。事業部長就任時の平均年齢が50歳を超えているため、役員昇進の可能性を考えると、一刻も早く事業部長職を卒業させないと後が続かないのである。 日本企業の事業経営責任者が管理職に成り下がっているのは、何も期待任期が短いからだけでない。上位に絶大な権限が存在するからだけでもない。本人の問題もそこにはある。さらに言えば、その背後に人事政策の問題もある。問題の一端は内部昇進の図式である。 |