といっても、学術的な研究論文の体裁をとらずに、一般読者向けに音楽を巡る探究物語のような書き方をしている。著述の性格上、どうしても脳科学的な専門用語が出てきてしまうが、私は一切無視して、脳科学的な探究をする際の構成が、音楽を認知するときのストーリーに即した形になっているので、そっちに興味を持って読んだ。ここで、この本の魅力の一つになっているのが、著者が音楽を単なる研究対象の死体(生き生きとした楽しみを失った形骸)として扱っていないこと。音楽を楽しむことを失わずにいることが、著述からも分かる。それは、音楽に関する記述が、具体的であること。研究のよる探究の説明も、個々の音楽を譬えにして、実際に音楽が聞こえてくるように書こうとしている姿勢がこの本の魅力といっていい。 まず、筆者は音楽の用語(パーツ)の解明から始めます。 ・
ピッチ(音の高低) ・
リズム ・
音調曲線 ・
音質 ・
音の大きさ ・
反響 ・
拍子 ・
調(キー) ・
メロディー ・
ハーモニー 音楽の主な要素の説明をした後で、しかし、現実の音楽の作曲や演奏では、これらの要素を切り離して考えることはせずに、相互の関係で考えます。このような要素の間の関係を研究するアプローチとして先駆的な役目を果たしたのがゲシュタルト心理学だと言います。ゲシュタルト心理学者たちが問題としたのは、特定のピッチの集まりであるメロディーは、ピッチ全体が上がったり下がったりしたとき、どのように同じメロディーのまま認識されるのかという点でした。これについては満足のいく理論的説明を加えることはできず、最終的には細部に対して形態が、部分に対して全体が、勝利しているということでした。一定のピッチの集まりを使ってメロディーを演奏するとき、ピッチの間の関係が同じなら、どれも同じメロディーになる。別の楽器で演奏してみても、やはり同じメロディーです。半分の速さにしてみても、こうした変化をいっぺんに加えてみても、聴く人はまったく問題なく元の曲がわかる。ゲシュタルト心理学は、この答えを導くことはできなかったものの、「ゲシュタルト群化原理」と呼ばれる原則を見出しました。もともと、視覚の世界においてたくさん木々の集まりを森として見るように、オーケストラの演奏で、トランペット一本の音だけを聞き分ける人はほとんどいません.同じ楽器の響きはひとつの群を構成しているし、オーケストラ全体で一つの群を構成することもありえます。人の聴覚系は、音の群化に倍音列を利用していると考えられます。個々の楽器から生まれた様々に異なる響きが、ひとつの楽器の知覚に結びつく。例えば、私たちにはオーボエやトランペットから出ている個々の倍音が聞こえるわけではなく、オーボエの音色、トランペットの音色として聞こえてきます。人間の脳は耳に届くいくつもの異なる振動数を分析し、きちんと正しいやり方で組み立てることができるわけです。浮遊するいくつもの倍音という印象を受けるのではないし、合成されたひとつの楽器の音に聞こえてしまうわけでもなく、脳はオーボエとトランペットに別々の心像を確立しており、両方がいっしょに演奏されている心像ももっています。それが音楽を聴いたときに音質の組み合せを認識する基礎となります。これらはそれぞれの楽器からの異なる基本振動数から異なる倍音の集まりが生まれるので、脳はコンピュータのような計算処理によって、何と何が組み合わさるかを判断します。このように音の属性に対応する神経生物学的サブシステムは、早い時期に、脳の低いレベルで分離することが判明しています。しかし、属性ははある一定の方向で結びつくと協調することも反発することもあるのは明らかな上、経験と注目が群化に影響を及ぼすこともわかっているので、群化のプロセスの一部は意識的な認知制御の下で行われていることになります。
認知科学者にとって「心」とは、私たちひとりひとりの一部で、それぞれの思考、希望、願望、記憶、信念、経験を具現するものを言います。それに対して「脳」は頭の中にあって、細胞と水、化学物質と血管が集まってできた体の器官です。脳内で起こる活動が心の中身を生み出すと考えます。彼らはときに脳をコンピュータのCPU、つまりハードウェアに譬え、基本的に同じハードウェアでも異なるプログラムを実行できる(だから、とてもよく似た脳からまったく異なる心が生まれる)のです。長年にわたる神経心理学の調査から、ハードウェアとしての脳の各部位の機能を示す地図を作れるようになり、個々の認知活動に関わっている場所を突き止められるようになってきました。このようなことから、脳の捉え方として、脳を計算システムになぞらえて、一種のコンピュータだと考える。そしてつながり合ったニューロンのネットワークは、情報の計算を実行するとともに、その計算結果を思考、決意、認識、そして最終的には意識というものにつながる方法に組み合わせていく。さらに認知の異なる側面を、それぞれ異なるサブシステムが受け持っている、というものです。音楽的な活動には、すでに知られている脳のほとんどの領域、ほとんどの神経のサブシステムが総動員されることになります。音楽の異なる側面には、異なる神経領域が対応します─脳は機能分離の方法を用いて音楽を処理し、音楽信号のピット、テンポ、音質などの個々の側面を専門に分析する特徴検知システムを採用していると言えます。平均的な脳は1000億のニューロンで構成されていると言われています。こり膨大な数のニューロンが様々な組み合せでつながっています。脳の処理能力は、このような相互接続の膨大な可能性ばかりでなく、脳が逐次処理ではなく並列処理を行うためでもあります。 ここで、一般には、脳の中では周りに見える世界とまったく同じ形の世界が表現されていると直感的に信じられていると思われますが、少なくともアリストテレスの時代から、人間の感覚は世界を歪めてとらえることがあるのは知られていました。それは進化の上での適応だった考えるのが妥当でしょう。私たちが見たり聞いたりするものからは、一部の情報が欠けているものが多い。狩猟採集生活をしていた祖先は、木の陰に一部が隠れたトラの姿を見たり、近くにある木の葉のざわめきでかき消されそうなライオンの唸り声を聞いたりしたに違いありません。音や光景は、身のまわりの別のもので曖昧にされた、部分的な情報として耳や目に届くため、かけた情報を復元できる知覚システムがあれば危うい状況でもすばやい決断に役立ちます。聴覚系も独自の知覚的補完機能を備えています。音楽を聞く場合には、このような知覚補完的機能、特徴抽出のプロセスに続いて特徴統合というプロセスを別に用いているようです。脳はまず、音楽から基本的な低レベルの特徴を抽出します。それには専門の神経ネットワークを使い、信号をピッチ、音質、空間的位置、大きさ、反響の環境、長さ、異なる音符の開始時間という情報に分解する。こうした活動は、これらの値を計算するいくつもの神経回路によって同時進行する。それらの神経回路はだいたい互いに独立して活動できるので、ピッチを判断する回路は、長さを判断する回路の仕事が終わるまで待つ必要はない。このように、刺激に含まれている情報だけを神経回路が考慮する処理を、ボトムアップ型の処理と呼ぶ。この間、これと並行して脳のもっと高いレベルの中枢は、それまでに抽出されたものに関する情報の流れを絶えず受け取っている。この情報は常に更新され、古い情報が書き換えられていくのが普通だ。さらに高度な思考の中枢(ほとんどが前頭皮質にある)はこれらの更新情報を受け取りながら、次のようないくつかの要素を用いて、音楽がどんなふうに展開していくかを懸命に予想する。 〜聴いている曲の、それまでの内容 〜よく知っている曲なら、次にどう展開するかの記憶 〜よく知っているジャンルや礼式なら、以前に聴いた同じ形式の音楽に基づく、次にどう展開するかの予想 〜そのほかに与えられた情報、たとえば本書でせつめいしてきた音楽の概要、演奏者の急な動き、隣人の合図など こうした前頭葉での計算はトップダウン型の処理と呼ばれ、ボトムアップ型の計算を実行している低レベルのモジュールに影響を与えることができる。トップダウン型の処理で生じた期待は、ボトムアップ型の処理機構にある回路の一部をリセットして、誤解を生じさせることがある。これが知覚的補完などの錯覚が起こる神経面から見た原因のひとつだと思います。また、トップダウン型の処理とボトムアップ型の処理は、処理をしながら情報を交換する。特徴を個々に分析する一方で、脳のより高度な部分(系統発生的に新しく、低レベルの脳領域から連絡を受け取る部分)はそれらの特徴をまとめ知覚の全体像を作り上げている。その過程で情報が不足したり、曖昧だったりすることがあるので、脳はさまざまな推定を行う。そしてときにはその推定が誤っていて、視覚や聴覚の錯覚を生み出す。 音楽における究極の錯覚と言えば、構成と形式の錯覚だろう。音符の順序そのものには、私たちが音楽から感じる豊かな感情のつながりを生み出すものは何もない。音階にも和音にも、本能的に解決を期待してしまう和音の進行にも、それはない。私たちが音楽を理解できるのは経験のたまもので、新しい曲を聴くたびに、それを覚えて変化できる神経構造があるからだ。脳は、子どもが自分の文化の言葉を話すことを学んでいくように、それぞれの文化の音楽に特有の音楽の文法のようなものを学んでいく。人はみな世界中のどの音楽でも学べる能力をもって生まれる。人間の脳では誕生前後から急速な神経の発達が始まり、幼児の間はそれがずっと続く。この期間には人生のどの時期よりも急速に、新しい神経のつながりが生み出されていくが、小児期中期になるとそれらのつながりを刈り込んで整理する作業が始まり、最も大切な、最もよく使われるものだけが残っていく。こうしてできあがった神経のつながりが、音楽を理解できる私たちの基礎となり、最終的にはどんな音楽が好きか、どんな音楽に感動するか、どんなふうに心を動かされるかを決めていくことになる。大人になってからは新しい音楽を楽しめるようにならないと言っているのではない。幼い時期に音楽を耳にすることによって、基本的な構成要素が、脳の配線そのものに組み込まれていくのだ。つまり音楽は一種の錯覚で、私たちの脳が、一連の音に構成と順序を当てはめていると考えることができる。 音楽は組織化された音響だと書いたが、その組織には、予想を裏切る要素が何か含まれていなければならない。そうでなければ感情表現が単調で、機械的になってしまう。私たちが音楽を味わえるのは、好きな音楽の基本となる構成(話し言葉や手話の文法に相当するもの)を学ぶ力と、次の展開を予想できる力を実っていることに深く関係している。作曲家は聴き手の期待を知り、その期待をいつ満たすか、いつ裏切るかを意図的にコントロールすることによって、音楽に感情を吹き込む。音楽を聴いたワクワク感、ゾクゾクする気持ち、思わず溢れる涙は、腕のいい作曲家とその曲を解釈する演奏家によって私たちの期待が巧みに操られた結果だ。音楽のこうした特性は、脳の中にそのまま表現されているわけではない。少なくとも、音楽を処理する最初の段階では、表現されていない、脳はひとつにはそこに何があるかに基づいて、またひとつには、学習した音楽体系の中で耳に届いた音が果たす役割を考えながらどう解釈するかに基づいて、独自のバージョンの現実を作り上げている。会話を解釈する場合と同じだ。「猫」という言葉に猫らしさはまったくないし、その言葉を作り上げている文字のどこにも、猫らしさはない。私たちはただ、この音の集まりがネコ科のペットと表わすと学習したにすぎない。同様に、私たちは一連の音がひとまとまりになることを学習し、それがいつもまとまっていると予測する。一定のピッチ、リズム、音質などが過去にどれだけの頻度でまとまっていたかを脳が統計分析し、その結果に基づいて、どんなふうにまとまって登場するかを期待する。外界とまったく同じ構造の表現が脳の中の記憶にあるという、直観的に信じてしまいそうな考え方を、ここではすっかり捨てなければならない。脳はある程度まで、知覚による歪みや錯覚を記憶し、各要素間の関係を引き出している。そして私たちのために、複雑さと美しさがいっぱいの現実を計算している。そのような考え方の基本的な証拠として、現実の光線は一次元(波長)で変化しているのに、人の知覚システムは色を二次元として扱っているという単純な事実がある。ピッチでも同じことだ。異なる速さで振動する分子の一次元の連続体から、私たちの脳は(学習した内容に応じて)三次元、四次元、あるいは五次元と、豊かな多次元ピッチ空間を生み出す。現実世界にあるものに、脳がこれだけ多くの次元を追加しているなら、正しい組み立てと巧みな結びつきをもつ響きに対して、私たちが抱く深い思いにも説明がつくだろう。 私たちは音楽のスキーマをもっている。それらは母親の胎内にいるときに生まれ、音楽を聴くたびに練り上げられたり、修正されたり、さまざまな情報を受け取ったりする。西欧音楽のスキーマには、一般に使用されている音階の知識が暗黙のうちに含まれている。たとえばインドやパキスタンの音楽を初めて聞くと耳慣れない感じがしてしまうのは、そのためだ。インドやパキスタンの人たちは耳慣れないとは感じないし、赤ちゃんもそう感じない(少なくとも、どの音楽でも耳慣れない感じは同じ程度だろう)。明らかに、自分が音楽として学習してきたものと矛盾しているから、耳慣れないわけだ。赤ちゃんは五歳になるまで、それぞれの文化的コード進行を認識できるようになる─この間にスキーマを作り出す。私たちは音楽の特定のジャンルやスタイルについて、スキーマを発達させて行く。スタイルとは、「反復」の別名ともいえる。私たちは以前耳にしたことがある何かを聴けば分かるし、同じ曲で聴いたことがあるのか、それとも違う曲で聴いたことがあるのかも区別がつく。音楽を聴くには、耳に届いたばかりの音符の知識を記憶に止める力と同時に、聴いている曲のスタイルに近い、よく知っているほかのあらゆる局の知識を記憶している力ももっていなければならない。後者の記憶は、耳に届いたばかりの音符ほど正確で鮮明でなくてもいいが、聞いている音符の文脈を確立するために必要なものだ。私たちが発達される主なスキーマは、ジャンルとスタイルの表現形式のほか、時代、リズム、コード進行、フレーズ構成(ひとつのフレーズが何小節からなるか)、曲の長さ、どの音符の後には普通どの音符が続くか、といったものが含まれる。 ここまでのところで、音楽を処理する神経構造についての図式をまとめてみよう。あらゆる音は鼓膜から始まる。するとすぐに、音はピッチごとに分解される。まもなく、言葉と音楽とは別々の処理回路に枝分かれするのだろう。会話の回路は個々の音素(文字と音声の体系を構成している子音と母音)を識別できるように信号を分解する。音楽の回路は、信号を分解し、ピッチ、音質、音調曲線、リズムを個別に分析し始める。これらの仕事を実行しているニューロンからのアウトプットが前頭葉にある領域に送られると、その領域はそれら全部をひとまとめにして、全体の時間的パターンに応じた構造や秩序があるかどうかを見つけ出そうとする。前頭葉は海馬や側頭葉の内部にある領域にアクセスして、この信号を理解するのに役立つ記憶があるかどうかを問い合わせる。
私たちの身の回りの世界に対する理解は、まず特定の個々のもの(人、木、曲)から始まる。そして周囲と関わる経験を通し、それらの特定のものを脳内でほとんど例外なく、あるカテゴリーのメンバーとして処理する。ロジャー・シェパードは、これまでここで考えてきたこと全体の一般的な問題を、進化の観点から説明した。すべての高等動物は、外面と事実について、三つの基本的な問題を解決する必要があるとシェパードは言う。生き延び、食べられる物と水と隠れ家を見つけ、捕食者から逃げ、子孫を残すために、生き物は三つのシナリオに対応しなければならない。第一に、二つのものがそっくりに感じられるときでも、それらは本質的に別のもののことがある。鼓膜、網膜、味蕾、触覚センサーに同じパターン、またはほとんど同じパターンの刺激を与えても、それぞれ違うものかもしれない。木になっているのが見えるリンゴの実は、今、この手にあるリンゴとは違う。交響曲から流れてくるヴァイオリンの音色は、すべてのヴァイオリンが同じ音符を演奏していても、何挺もの異なる楽器の音が集まったものだ。第二に、二つのものが異なっているように感じられるときでも、それらは本質的に同じもののことがある。ひとつのリンゴを上から見るのと横から見るのとでは、まったく違って見える。正しく認知するためには、このような別々の見え方を、筋の通ったひとつのものの表現にまとめあげられる計算体系が必要となる。感覚受容器が、重なり合わないまったく別々の活性化パターンを受け取っても、私たちはそのものの統一された表現を作り上げるのに欠かせない情報を抜き出さなければならない。私は、いつも話をする友だちの声を両耳で聞き慣れているかもしれないが、電話を通して声を聞いたときにも、片方の耳で、それが同じ人物だとわかる必要がある。外面と事実についての第三の問題には、さらに高次元の認知プロセスが関わっている。第一と第二は近くのプロセスで、ひとつのものにもいくつもの見え方や聞こえ方がある、また、複数のものが(ほとんど)同じ見え方や聞こえ方をすることもあると理解していく。そして第三は、外面が異なるものでも、同じ種類に属しているという考え方だ。これはカテゴリー化の問題で、最も強力で最も高度な原則になる。高等哺乳動物や鳥でも多くは、さらには魚さえ、カテゴリー化する力をもっている。カテゴリー化では、外面の異なるものを同じ種類として扱う。赤いリンゴは青いリンゴと違って見えるかもしれないが、どちらもリンゴだし、私の母親は父親は似ていないが、とぢらも私の保護者で、いざというときには頼れる存在だ。適応行動には、体の感覚器官が受け取った情報を分析できる計算体系が必要で、情報から(1)まわりにあるものや場面の不変の性質と(2)そのものや場面が示している瞬間的な状況を把握しなければならない。レナード・メイヤーは、作曲家、演奏家、聴き手が音楽的な関係の基準となっているきまりごとを内面的に自分のものにし、その結果としてパターンの意味するものを理解して、形式のきまりごとからの逸脱がわかるようになるには、分類が絶対不可欠だとしている。 音楽が基本的な特徴からの変形や歪みにとても強いということだ。曲で使われているピッチを変え(移調)、そのうえテンポと楽器を変えてしまっても、まだ同じ曲だとわかる。音程、音階、さらに長調から短調へ、短調から長調へと調性まで変えることができる。さらに例えばブルーグラスからロックへ、クラシックへとアレンジを変えても、歌は同じままだ。これほど劇的な変化があっても、まだその曲だとわかる。それならば、私たちの脳にある記憶装置は、こうした変形を経ても曲を聞き分けられるようにする何らかの計算式や計算記述を導き出しているように思える。 私たちの音楽の記憶が、階層的にコード化されていることを示すものだ─すべての単語が等しく目立っているわけでも、曲のフレーズのすべての部分が等しい立場をもっているわけでもない。私たちが歌を途中から始められる場所や止められる場所は決まっていて、それは音楽のフレーズに対応している。これも、テープレコーダーとは違う点だ。この階層的なコード化という考え方は、ミュージシャンを対象にした実験によって、別の方法で確認されている。ほとんどのミュージシャンは、よく知っている曲を演奏するにあたって、途中のどこからでも始められるわけではない。ミュージシャンたちは曲を、階層的にフレーズ構造に従って覚えている。音符の集まりが練習の単位となり、小さい単位が集まってもっと大きい単位になり、それが集まってフレーズになり、さらにフレーズが集まってヴァースやコーラスや楽章になり、最後にはすべてが集まってひとつの曲になる。演奏家や歌手に、自然なフレーズの区切りの二、三個前や後の音符から始めるように言っても、普通は無理だろうし、楽譜を読むときでさえ同じことだ。別の実験では、ある音符が曲に出てくるかどうかをミュージシャンに思い出してもらうと、その音符がフレーズの先頭やダウンビートにあるときのほうが、フレーズの中間やウィークビートにあるときより、早く正確に思い出せることがわかった。音符も、その音符が曲にとって「重要な」音符かどうかに応じて、カテゴリーに振り分けられているようだ。素人が歌を歌うとき、曲のすべての音符を記憶しているわけではない。「重要な」音─音楽の訓練を受けなくても、どの音が重要かについては誰もが正確で直観的な感覚をもっている─と音調曲線だけを記憶している。そして歌う時点で、ひとつの音から別の音に進む必要があるのを知っていて、間の抜けている音は個々に覚えずに、その場で埋めていく。この方法によって記憶の負荷は大幅に減り、効率も高まる。 多痕跡記憶モデルは、私たちが曲を聴きながらメロディーの不変の特性だけを抜き出せるという事実を、どのように説明するだろうか?メロディーについて考えてみると、私たちは計算を行っていることは間違いないだろう。絶対値、表現の詳細─ピッチ、リズム、テンポ、音質などの細部─を登録しているほかに、私たちはメロディーの音程や、テンポを除いたリズム情報について、計算しているにちがいないのだ。マギル大学のロバート・ザトーアらの神経画像研究が、これを示唆している。側頭葉の背側(上部)─ちょうど両耳の上あたり─にあるメロディー「計算センター」が、音楽を聴いているときにピッチとピッチの間の音程の差と距離に注意を払い、移調した曲も分かるために必要となる、ピッチを取り除いたメロディーの値だけのテンプレートを作っているらしい。私が行った神経画像研究では、よく知っている曲によってこれらの領域と海馬の両方が活性化する。海馬は脳の中心深くにある構造で、記憶のコード化と取り出しに不可欠であることが知られている。こうしたさまざまな実験結果は、私たちがメロディーに含まれている抽象的な情報と固有の情報のどちらも蓄えていることを示している。これは、感覚に対するあらゆる種類の刺激に共通していると思われる。記憶は文脈も保存するので、多痕跡記憶モデルは、私たちがほとんど忘れかけていた古い記憶を呼び戻すことがあるのも説明できる。通りを歩いていたら、長く嗅いだことのなかった香りが漂ってきて、それがきっかけとなって遠い昔の出来事を思い出したことはないだろうか?または、ラジオから流れてきた古い歌を耳にした途端、心の奥深くに埋もれていた、その歌が流行ったころの思い出が、急に頭に浮かんできたことはないだろうか?こうした現象は、記憶というものの核心に迫るものだ。たいていの人は、アルバムやスクラップブックのように一連の記憶をもっている。友だちや家族に何度も話したエピソードや、苦しいとき、悲しいとき、落ち込んだとき自然に想い浮かぶ過去の経験は、自分が誰なのか、どこからやってきたのかを思い起こさせてくれる。これは自分の記憶のレパートリーで、ミュージシャンのレパートリーや演奏方法を知っている曲のように、何度も再生を繰り返している記憶だと考えることができる。多痕跡記憶モデルに従えば、すべての経験が潜在的に記憶の中でコード化されている。脳の特定の場所に保管されているわけではない。脳は倉庫のようなものではないからだ。記憶はニューロンのグループによってコード化され、それらが正しい値に設定されて一定の方法で構成されると、記憶が呼び戻されて、心の劇場で再生される。思い出したくても思い出せない壁があるのは、それが記憶に「保管」されていないからではない。問題は、該当する記憶にたどり着く正しい手かがリが見つからず、神経回路を適切に構成できないことにある。同じ記憶に何度もたどり着けば着くほど、思い出を呼び戻して回想する回路が活発になり、その記憶を呼び戻すために必要な手がかりを簡単に見つけられるようになる。理論的には、正しい手かがりさえあれば、どんな過去の経験でも思い出せるということだ。多痕跡記憶モデルでは、記憶の痕跡とともに文脈もコード化されていると見なすので、人生を歩みながらことあるごとに耳にしてきた音楽は、それを聞いたときの出来事と組み合わせて保存されている。だから、音楽はあるときの出来事に結びつき、それらの出来事は音楽に結びついている。 記憶は音楽を聴くという経験に、あまりにも深遠な影響を与えるため、記憶がなければ音楽はないと言っても過言ではない。たくさんの理論家や哲学者が言ったように、音楽の土台は繰り返しだ。音楽は、私たちが聞いたばかりの音を記憶に蓄え、それを耳から入ってきている音と関連づけることで、成り立っている。そうした音の集まり(フレーズ)が、変奏や移調という変化を伴って後からもう一度聞こえてくれば、記憶システムが喜ぶと同時に感情センターが刺激される。神経科学者たちはこの10年間で、記憶システムが感情システムにいかに密接にむすびついているかを明らかにしてきた。長いこと哺乳動物の感情の在り処と見なされてきた扁桃体は、海馬のすぐ隣にある。そしてその海馬は長いこと、記憶の呼び戻しではないにしても、記憶の保管に不可欠な構造だと見なされてきた。今では、扁桃体が記憶に関与していることがわかっており、とくに強烈な感情を伴う出来事や記憶によって強く活性化される。私の研究室で行ってきた神経画像の研究ではいつも、扁桃体は音楽に反応して活性化するのに、ただの音や音楽的な音を、でたらめに寄せ集めただけのものには反応しないという結果が出ている。大作曲家によって巧みに作り上げられた繰り返しが、私たちの脳を感情的に満足させ、音楽を聴くという経験をこんなに楽しいものにしているのだ。
すでに論じてきたように、ほとんどの曲は、聴きながら足で拍子をとれるものだ。耳から入ってくる音楽には鼓動があって、それに合わせて足先をトントンとリズミカルに動かせるし、少なくとも心の中で足先を動かしているような気持ちになれる。この鼓動は、ほとんど例外なく規則正しく、均等な時間間隔で続いていく。こうした規則的な鼓動によって、私たちは一定の時点で何かが起こるだろうと予測するようになる。電車の線路から響いてくるガタンゴトンという音のように、それは私たちが前へ前へと進んでいること、動いていること、そしてすべてがうまくいっていることを知らせてくれる。 クラシック音楽の話では、普通はグルーヴという表現を使わないが、オペラや交響曲、ソナタ、コンチェルト、弦楽四重奏も、ほとんど明確な拍子と鼓動をもち、それは一般に指揮者の動きに対応している。指揮者はどこにビートがあるかを演奏者に知らせ、感情を表現するためにその間隔を広げたり縮めたりする。人と人との実際の会話、現実に許しを乞う言葉、怒りの爆発、求愛、物語、計画、子育て─どれをとっても、機械が刻むような正確なペースで起こるわけではない。音楽が私たちの感情の動きや人と人とのやりとりに見られる力学を映し出す限り、膨らんだり縮んだり、速くなったり遅くなったりも立ち止まったり考え込んだりする必要がある。このようなタイミングの変化を感じる、またはしるには、次にいつビートが聞こえるかについて、脳内の計算システムが予想情報を手にしていなければならない。規則的な鼓動のモデル(スキーマ)を脳が作り上げるからこそ、演奏者がそこから逸脱したのに気づけるわけだ。これはメロディーの変奏に似ている。演奏者がメロディーを勝手に変えても同じ曲だと分かるためには、私たちの心の中に、元のメロディーの表現が存在していなければならない。拍子を抽出すること、つまり曲の鼓動がどんなもので、それがいつ起きると期待できるかを知ることは、音楽的感情に不可欠な部分だ。音楽は、期待を体系的に裏切ることによって私たちの感情に語りかけてくる。このような期待への裏切りは、どの領域─ピッチ、音質、音調曲線、リズム、テンポなど─でも構わないが、必ず起こらねばならない。音楽では、整った音の響きでありながら、その整った構成のどこかに何らかの意外性が必要になる。さもなければ感情の起伏がなく、機械的になってしまう.整いすぎた響きも技術的には音楽かもしれないが、そんな音楽は誰も聞きたいと思わない。たとえば、ただの音階は、たしかに整ってはいる。それでも、子どもが音階ばかりを飽きもせず弾いているのを聞けば、親は五分もしないうちにうんざりしてしまうにちがいない。このように拍子を抽出できる神経的な基礎は、どこにあるのだろうか?脳を損傷した患者の研究から、リズムと拍子は、神経の上で関係がないことが分かっている。脳の左半球に損傷を受けた患者が、リズムを把握することも、自分でリズムを作ることもできなくなりながら、拍子はわかることがある。右半球に損傷を受けた患者は、その逆のことがある。リズムも拍子も、神経の上ではメロディーとは別の場所で処理されるものだ。 音楽は言語の特徴の一部を真似ていて、言葉によるコミュニケーションと同じ感情の一部を伝えるように感じるが、何かを意味したり、何か特別なものを指しているわけではない。また、言語と同じ神経領域の一部を呼び覚ますが、音楽の場合は言語よりずっと、動議づけ、報酬、感情に関わる原始的な脳構造に深く入り込んでいく。「ホンキー・トンク・ウィメン」の出だしで聞こえるカウベルの響きで、「シェーラザード」の冒頭のいくつかの音符で、もう脳内の計算システムニューラル発振器を曲の調子に同期させて、次の強拍がいつ聞こえるかを予想し始める。曲が展開するにつれ、脳は新しいビートが聞こえる予測をつねに更新していて,心の中のビートと実際に聞こえてくるビートが一致することに満足を覚え、巧みなミュージシャンがその期待をおもしろく裏切ると楽しく感じる─それは誰でも知っている音楽のジョークのようなものだ。曲が呼吸し、まわりの世界と同じようにスピードを上げたりゆっくりになったりすると、私たちの小脳はそれと同期を保つことに快楽を見出す。印象的な─グルーヴのある─音楽は、タイミングをわずかに外している。巣の屋根を叩く木の枝のリズムが変化すると、ネズミが感情的に反応するように、私たちもグルーヴのある音楽ではタイミングのずれに感情的に反応する。ネズミはタイミングの規則違反に何の知識もないわけだが、それを恐怖として経験している。文化と経験を通して音楽は少しも脅威ではないことを知っている私たちの場合は、認知システムが規則違反を快楽や喜びの源として解釈することになる。グルーヴに対するこうした感情的反応は、耳と聴覚皮質という回路ではなく、耳─小脳─側坐核─辺縁系という回路で生じる。グルーヴに対する私たちの反応が前意識または無意識のうちに起こるのは、前頭葉ではなく小脳を経由しているからだ。そして何より目覚しいのは、これらの異なった経路すべてが統合されて、たった一曲の音楽の経験に注ぎ込まれることだろう。音楽を聴くのストーリーは、脳のいくつもの領域が、管弦楽を奏でるかのように絶妙な調和をとりながら機能していくストーリーだ。そこには、人の脳の最も古い部分と最も新しい部分がともに関わり、後頭部にある小脳から両目のすぐ後にある前頭葉まで、遠く離れた領域が加わっている。そこでは、論理的な予測システムと感情的な報酬システムとの間の神経化学伝達物質の放出と取り込みに、綿密な演出が施されている。私たちがある曲を好きになるのは、以前に聴いた別の曲を連想し、それが人生の感傷的な思い出にまつわる記憶痕跡を活性化させるからだ。
人はどうやって音楽家になるのだろうか?音楽のレッスンを受けている子どもたちは大勢いるのに、なぜ大人になって楽器の演奏を続ける人はわずかになってしまうのだろうか?私の仕事を知って、音楽を聴くのは大好きだけれど、「何にもならなかった」と話しかけてくる人多い。私は、そういう人たちが自分に厳しすぎるのではないかと思う。私たちの文化では、音楽のエキスパートとただの音楽好きの間にある溝が広がりすぎて、みんなが弱気になっているのだ。そしてなぜかわからないが、それは音楽の世界だけの現象のように見える。ほとんどの人はシャキール・オニールみたいにバスケットボールをできないし、ジュリア・チャイルドのように料理できないのに、裏庭でバスケットを楽しんだり、友人や家族のためにご馳走を作ったりしている。音楽での溝の深さどうやら文化的なものらしく、現代の西欧社会に限られている。多くの人が音楽のレッスンは何にもならなかったと言うが、認知神経科学者の研究によれば、そんなことはない。子ども時代にほんの少しでも音楽のレッスンを受けると、まったく訓練を受けなかった人より効率的で発達した音楽処理用の神経回路が作られる。音楽のレッスンは上手な聴き方を教え、曲の構造と形式を聞き分ける力を伸ばし、好きな音楽と嫌いな音楽を区別しやすくする。 才能という考え方を正当化する最も強力な証拠は、音楽的な技能を、ほかの人より短時間で身につけてしまう人がいることだ。それに対して、才能には関係ないという見方─というより、練習によって完璧になるという見方─の証拠は、専門家や演奏の名手たちが実際にどれだけの訓練を積むかという研究から見えてくる。数学やチェスやスポーツのエキスパートたちと同様、音楽のエキスパートも、本当に卓越した技能を身につけるためには長い時間をかけて教えを受け、練習しなければならない。いくつかの研究によると、音楽学校の最も優秀な生徒は最も練習量が多く、優秀ではないと見なされた生徒の練習量の二倍にのぼることもあるという。 音楽のように学習の要素をもつ技能について、遺伝の影響を環境の影響と区別するのは難しい。音楽は親から子へと受け継がれる傾向がある。それでも、音楽家を親に持つ子どもは、音楽に縁のない家に生まれた子どもより、幼児期から音楽を学ぶように励まされる可能性か高い。たとえて言えば、フランス語を話す両親が育てる子どもはフランス語を話す可能性が高く、そうでない両親の子どもはそうでない可能性が高い。このとき、フランス語は「親から子へ受け継がれる」と言えるが、フランス語を話すのが遺伝の影響だと主張する人はいない。 音楽のエキスパートにはさまざまな側面がある。楽器を演奏する腕の冴え、感情を伝える力、創造性、曲を暗譜する特別な精神構造など。そして聴き手のエキスパートは、大半の人が六歳でもうこのエキスパートになっているわけだが、音楽的文化の文法を精神的なスキーマに組み込み、音楽的な期待を抱けるようになっている。それが音楽に美しさを感じる経験の核心なのだ。こうした多彩な専門技術を人はどのようにして身につけていくのか、神経科学は者はまだ解き明かしていない。それでも最近では、音楽の専門技術はひとつのまとまったものではなく、数多くの要素から成り立っていて、音楽のエキスパート全員がそうした異なった要素を等しく備えているわけではないということで、意見が一致してきている。なかにはアーヴィング・バーリンのように、誰もが音楽家なら当然もっているはずだと思う基本的要素をもたない音楽家もいる。彼は楽器をうまく演奏することができなかった。これまでにわかっていることから考えて、音楽の専門技術がほかの分野の専門技術とまったく違うことはなさそうだ。音楽はたしかに、他の活動では使わない脳の構造と神経回路を使うとはいえ、音楽のエキスパートになるプロセスには─作曲家でも演奏家でも─ほかの分野のエキスパートになるのと同じ性格的特徴の多く貸せ必要になる。なかでも、勤勉さ、忍耐力、やる気、そして昔ながらの根気強さをあげることができる。有名なミュージシャンになるのはまったく別の問題で、もって生まれた要素や能力より、カリスマ性やチャンス、幸運がものを言う世界だ。それでももう一度、大切なことを言っておきたい。私たちは誰でもが音楽の聴き手としてエキスパートであり、曲の好き嫌いに、ごく微妙な判断を下すことができる。理由をはっきり言えなくても、好きなものはわかる。
科学には、私たちが好きだと感じる音楽をなぜ好きかについて、言うことがあるらしい。そしてその話は、ニューロンと音符とが見せる相互作用の、もうひとつの興味深い側面を明らかにしてくれる。 人間の脳と、人間が使っている音階とは、共進化してきたと言える。長音階の音符が均整のとれていないおかしな配置になっているのは、偶然ではない。この配置のほうがメロディーを覚えるのが簡単で、それは音の発生に関する物的な現象から導かれた(この本ですでに取り上げた倍音列を通しての)結論だったのだ。私たちが長音階で使っている音のピッチは、倍音列を構成している音のピッチは、倍音列を構成している音のピッチに非常に近い。ほとんどの子どもたちは生まれて間もないころから自然に声を出し始め、そうした初期の発声はまるで歌っているように聞こえる。赤ちゃんは自分の声の範囲を探り、まわりの世界から取り入れる音に応えながら、発音する方法を探る。赤ちゃんの耳にたくさんの音楽が届けば届くほど、自然に起こる発声に含まれるピッチやリズムのバリエーションは増えていくだろう。 何歳になっても新しい音楽を好きになれるようには思えるが、大多数の人の好みは18歳か20歳までに固まる。なぜかはまだはっきりしていないものの、いくつかの研究によって実証されてきた。人は敏を重ねるにつれ、どちらかというと新しい経験の影響を受けにくくなっていくのが、その理由のひとつだろう。私たちは十代の間に、違う考え方、違う文化、違う人たちの世界が存在することに気づき始める。そして自分の人生や個性、あるいは決意を、親から教えられたことや育ってきた道に閉じ込めなくてすむよう、違う考え方を試して見る。同じようにして、新しい種類の音楽を探す。とくに西欧の文化では、どんな音楽を選ぶかは社会的に大きな意味を持つ。私たちは友だちと同じ音楽を聴く。若くて、自己を確立しようともがいている間ならなおさら、自分も同じようになりたい人、どこかに共通点があると感じられる人と、社会的な集団を作って絆を結ぶ。その絆を結ぶ。その絆を具体的に表す方法として、同じような服装をし、いっしょに活動し、同じ音楽を聴く。自分のグループはこんな音楽を聴いているけど、あいつらはあんな音楽を聴いている。こうして、音楽は社会的な結びつきや社会行動の結束を強める働きをするという進化論的な考え方につながっていく。音楽と音楽の好みは個人とグループのアイデンティティーを表わし、それぞれ区別する目印になるのだ。好きな音楽はその人の個性とつながりがある、その人の個性を表わしていると、ある程度までは言っていいだろう。それでも大体の場合、そうした好みは多かれ少なかれ偶然の要素に導かれて決まるものだ─どこで学校に通ったか、誰と仲良くしていたか、そしてその仲間がどんな音楽を聴いていたのかが大きく影響する。 音楽の単純さと複雑さのバランスも、好みの要因になる。さまざまな芸術分野─絵画、詩、ダンス、音楽─の好き嫌いに関する科学的研究によれば、芸術作品の複雑さとそれを好きになる程度の間には、規則的な関係がある。複雑さというのは、もちろんまったく主観的な概念になる。この概念をきちんと理解するには、ある人にとっては計り知れない程複雑に思えるものが、別の人の好みにピッタリはまることがあるかもしれないのを、知っておく必要がある。同じように、誰かがおそろしく単純で味気ないと思ったものを、別の人は難しくて理解できないと感じるかもしれない。それはひとりひとりの経歴、経験、理解力、認知のスキーマの違いによるものだ。ある意味ではスキーマが最も大切になる。それは私たちの理解力の枠組みを作るもので、その体系の中に、ある芸術作品の要素やそれに対する解釈を当てはめていく。スキーマは人が持っている認知モデルと期待に関する情報を伝える。あるスキーマを持っていれば、マーラーの第5番は完全に解釈できるもので、たとえ生まれて初めて聞いた場合でも大丈夫だ。それは交響曲であり、四楽章をもつ交響曲の形式に従っている.メインテーマとサブテーマをもち、テーマの反復がある。テーマはオーケストラの楽器によって奏でられ、アフリカのトーキングドラムやファズベースは使われない。マーラーの交響曲第4番を聴きなれている人は、第5番が同じテーマの変奏で始まり、ピッチまで同じだと分かる。マーラーの作品に詳しい人は、この作曲家が自分の作曲した三つの歌曲から、曲調の一部をこの交響曲に取り入れているのが分かる。音楽教育を受けた聴き手なら、ハイドンからブラームス、ブルックナーに至るほとんどの交響曲で、通常は始まりと終わりが同じ調性あることに気づく。マーラーは第5番でこの慣習を破り、嬰ハ短調で始め、イ短調を経てから、最後をニ長調で締めくくった。交響曲の進行とともに調性を追うことを学んでいなければ、あるいは交響曲の標準的な軌跡を知っていなければ、このことは意味がない。しかし、年季の入った聴き手にとっては、この慣習の無視は満足感を伴う驚きをもたらし、期待を裏切る。調性の変更が耳ざわりにならない巧みな演奏なら、なおさら素晴らしい。ところが、適切な交響曲のスキーマをもっていない聴き手、あるいは別のスキーマ、インドのラーガの熱烈なファンというようなスキーマをもっている聴き手にとっては、マーラーの第5番は意味のない、またはとりとめのない音楽で、ひとつの音楽的意図が、始まりや終わりの境界もなしに次のものと曖昧に混ざり合って、まとまりのある全体をなしているにすぎない。スキーマは、私たちの知覚の、認知処理の、最終的には私たちの経験の、枠組みをつくる。曲が単純すぎれば、つまらないものに見えてしまい、あまり好まれない。複雑すぎても、今度は理解できなくて、やっぱり好まれない傾向がある─私たちにはそれが、何かよく知っているものに根ざしていると感じられないからだ。音楽は、ついでに言うならどんな芸術も、好まれるためには単純さと複雑さのバランスをうまくとっていなければならない。単純さと複雑さは知っているかどうかに関係し、知っているかどうかは、スキーマの別名にすぎない。 私たちの音楽の好みはほかの好みと同様に、以前の経験と、その経験の結果がよかったか悪かったかによっても影響される。心地よいと感じるサウンド、リズム、音楽的味わいの種類は、人生における音楽的体験のなかでプラスの要素をもった経験の延長であることが多い。好きな曲を聴くことは、ほかの心地よい感覚経験とよく似ているからだ。チョコレートや摘みたてのラズベリーを食べる、朝のコーヒーの香りを嗅ぐ、芸術作品や、愛する者が眠る平和な顔を見るなど、心地よい感覚経験はいろいろある。その感覚経験を楽しむと、よく知っている感覚と、よく知っていることがもたらす安全に、心地よさを覚える。私は熟したラズベリーを見て香りを嗅ぐだけで、おいしいであろうことも、食べても安全でお腹をこわしたりしないことも、予想できる。ローガンベリーをはじめて見たときにも、ラズベリーとよく似ているので、食べてみようと思い、安全だろうと予想できる。安全なことは、多くの人が音楽を選ぶ際のポイントだ。私たちは聴いている音楽に、ある程度まで身をゆだねることになる。作曲家と演奏家を信頼して、自分の心を許すことになるのだ─音楽は自分自身を、どこか外の世界に連れ出してしまう。素晴らしい音楽が自分をもっと大きい何かに、他の人々に、あるいは神に結びつけてくれると感じる人は多い。音楽が感情をどこか超越したところに連れこんでくれないとしても、いやな気分を一新することはできる。そういうときには、誰にも隙を見せたくない、心の鎧をはずしたくないと感じているものだ。もし演奏家と作曲家が安全な気持ちにさせてくれるなら、心を許す気持ちになる。偉大な作曲家の音楽を聴くとき、私はどこかでその作曲家と一体になるような、または作曲家の一部を自分の中に引き入れるような、そんな気持ちになる。このような聴き手の脆弱さ、すべてをゆだねる感覚は、この40年間、ロックやポップ音楽ではおなじみの光景だ。これでポップ・ミュージックを取り巻くファンの説明がつく。私たちはミュージシャンに、感情をゆだね、時には生き方までまかせてしまう。ミュージシャンは私たちの気分を高揚させ、落ち込ませ、安らぎをもたらし、閃きを与える。ほかに誰もいない私たちの居間や寝室にも、自由に入ってくる。そして私たちは彼らを、直接、イヤフォンで、ヘッドフォンで、耳の中にまで招き入れ、その間は世界じゅうのほかの誰とも話をしない。赤の他人にここまで身をさらけ出すことなど、そうそうあることではない。それに対して、好きなミュージシャンには進んで自分自身をさらけ出してしまう理由のひとつは、ミュージシャンのほうが私たちに自分をさらけ出してくることにある。(作品を通してわが身の弱さを伝える─実際に弱いのか、またはただ芸術的に表現しているのかの区別は、ここでは重要ではない)芸術の力は、私たちを互いに結びつけ、また生きていることの意味、人間であることの意味についての、もっと大きい真実へと結びつけることにある。アーティストとのつながり、またはアーティストが支持していることへのつながりは、こうして音楽を好きになるひとつの要因となる。 私たちは音楽を聴くことによって、音楽のジャンルや形式に関するスキーマを作り上げている。何気なく耳に入ってきているだけでも、とくに音楽を分析しようと思わなくていい。ごく幼いころから、人は自分の文化の音楽で決められた、正しい音の動きを知っている。やがて生まれる音楽の好き嫌いは、たいていの場合、子どものころ耳にした音楽によって出来上がった認知スキーマの種類で決まってくる。ただし必ずしも、子どもの頃聴く音楽によって人生を通した音楽の好みが決まってしまうという意味ではない。多くの人々は異なる文化や様式の音楽を聴いたり学んだりして、それに同化していくとともに、スキーマも身に付けていく。重要なのは、私たちの幼いころの音楽とのふれあいは心の最も奥深いに根をおろすことが多く、将来にわたって音楽を理解していく土台になるという点だ。音楽の好みには社会的な要素も大きく影響し、歌手や音楽家についての知識、家族や友だちが何を好きかという知識、そしてその曲が何を支持しているかという知識に左右される。歴史的に見て、とくに進化的に見て、音楽は社会活動に関わりをもってきた。最も多い音楽表現がラブソングであること、そしてほとんどの人のお気に入りにラブソングが入っているのは、そんな理由かもしれない。 |
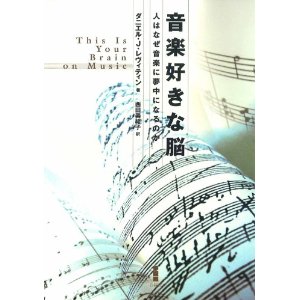 著者は、ミュージシャンとして活動や音楽プロデューサーとしての活動の後、大学に入り直して研究生活に入った人。その主な関心は“私はだんだん、一生芽が出ないミュージシャンもいるのに、一部のミュージシャンはなぜあんなに人気が出るのだろうかと疑問に思い始めた。それに、作曲などできない人もいれば、いとも簡単に曲を作れる人がいることも不思議だった。創造力というものは、たったいどこからやって来るのだろうか?心を動かされる歌があるのに、何も感じない歌もあるのはなぜだろうか?そのすべてにおいて、音を聞き分ける「知覚」の役割は何だろう?ほとんどの人には聞こえないニュアンスが聞こえる、有能なミュージシャンやエンジニアたちの並外れた能力は、いったいどうなっているのだろうか?”それで、筆者は神経心理学を学び始める。その後、同じ関心を持ちつづけ心理学と神経学を交わったところにある認知神経科学の視点から、音楽の科学について本書を書いているという。
著者は、ミュージシャンとして活動や音楽プロデューサーとしての活動の後、大学に入り直して研究生活に入った人。その主な関心は“私はだんだん、一生芽が出ないミュージシャンもいるのに、一部のミュージシャンはなぜあんなに人気が出るのだろうかと疑問に思い始めた。それに、作曲などできない人もいれば、いとも簡単に曲を作れる人がいることも不思議だった。創造力というものは、たったいどこからやって来るのだろうか?心を動かされる歌があるのに、何も感じない歌もあるのはなぜだろうか?そのすべてにおいて、音を聞き分ける「知覚」の役割は何だろう?ほとんどの人には聞こえないニュアンスが聞こえる、有能なミュージシャンやエンジニアたちの並外れた能力は、いったいどうなっているのだろうか?”それで、筆者は神経心理学を学び始める。その後、同じ関心を持ちつづけ心理学と神経学を交わったところにある認知神経科学の視点から、音楽の科学について本書を書いているという。