|
�@ ��P�́@�₢���� �v���ɁA�u�u���b�N�i�[�I�v�Ƃ����ꂫ�́A���y���������y�̋����E������ł͂��߂ĉ\�ƂȂ鉹�y�Ƃ͖��W�̙ꂫ�ƌ����Ȃ��ł��傤���B���̂悤�Ȃ��Ƃ�\���Ό����߂��Ƃ̔������Ă��܂����Ƃ����m�ŁA���ɂƂ��ẮA�u���b�N�i�[�̉��y�������ɒ�������u�ԁA�u�u���b�N�i�[�I�v�Ȃǂƒ��C�əꂢ�Ă��邱�ƂȂǂł��Ȃ��̂ł��B�Ƃ����̂��A�u���b�N�i�[�̉��y�̋����̂ǂ����Ƃ��Ă��A����܂�̌`�e�����������u�u���b�N�i�[�I�v�̙ꂫ�i���̏ꍇ�̙ꂫ�ƌ`�e���͓��i�ł��傤���j�ɓK�������̂Ɍ����Ď��Ă���Ƃ͎v���Ȃ�����ł��B�ɂ�������炸�A�u���b�N�i�[�̉��y�������u�u���b�N�i�[�I�v�ƙꂢ�Ă��邾���Ȃ̂��Ȃ��āA�u�u���b�N�i�[��m���Ă���B�v�Ɠ�������̂́A�����̎��ʼn��y�̋��������Ƃ�������Ă��邩��ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�����ɒ����Ă���͂��̉��y�̋����E���Ȃ���A�u�u���b�N�i�[�I�v�̙ꂫ�Ƃ��������Ƃ͂������ꂽ�_�b�ƋY��Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B�u���b�N�i�[�̈��D�҂Ȃ�N�����Öق̂����ɋ��L���Ă���_�b�ɁA�����̃u���b�N�i�[�̉��y�̋������]�������Ă��邩����A������C�܂������قɏP���邱�Ƃ͂Ȃ��A���S���Ă����܂��B�������Ƃɂ���āA�����Ă��鎩���̎��͂����Ȃ�ω���ւ�C����������܂���B�_�b�͖����ʼn��������킯�ł��B�����ł́A�����������҂̂���ɐg��u���A�u���b�N�i�[�̉��y���Ă��������Ǝv���܂��B �Ƃ͌������̂́A���́A���܁A�����ɁA�u���b�N�i�[�̉��y���Ă���킯�ł͂���܂���B������A�ǂ��炩�Ƃ����A�_�b�̑��ɗ����ău���b�N�i�[�̉��y�ɂ��čl���悤�Ƃ��Ă���킯�ł��B�ɂ�������炸�A�ł��邱�ƂȂ�A�\�Ȃ����肸��̒��ɐg��u���čl����i�߂����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A�����ɉ��y�̋���������u�ԂɁA�u���b�N�i�[�̉��y�́A���̎��ɁA�������ϗe����ƌ�肩���Ă��邩�̂悤�ɁA�l�X�Ɉ���ĕ������Ă��邩��ł��B���������悤�ɒ����Ă��ẮA���̓s�x�̋����������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��A���ɂƂ��Ă͎c���Ƃ��ĂԂׂ��^���������ɂ͂���̂ł��B�u���b�N�i�[�̉��y�́A��������̎��ɁA���i�ْ̋����������ɂ͂����܂���B������Ă������A�_�b�̒��ɉ����Ƃǂ܂��Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł��B�i���ꂱ�����A���O�ɂƂ��Ă̐_�b�ƌ����Ȃ����Ƃ����ᔻ�͖ނ��Ȃ��Ƃ��ƊÎ����܂��B�������A�����炱����Œf���Ă���͂��ł��B�j���y���y���ނ��Ƃ��A�p��ł͂��������Ƃ����P���p���܂��B�܂�A�V�тł��B�V�тɂ́A���X�؏����Ȃǂ���܂���B�u���b�N�i�[�̉��y�̋��������Ƃ������Ƃ́A���y�Ƃ����V�т��̂��̂ł���悤�Ɏv������ł��B ��Q�́@���_ ���āA����܂Ō����̂Ƃ���̓I�ɂƂ������Ă����킯�ł����A���������̓I�ɂǂ��Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ��܂���B����ł́A�u�̂����Ȃ��Ƃ����������s�s��v�ł͂Ȃ����v�Ǝ����Ă��܂������ł��B�����ł܂��A�u���b�N�i�[�̌����Ȃ��Ƃ����Ƃ��ɁA�����̃t�@���𖣗����Ă�����̂Ɋɏ��y�͂�����̂́A�N�����ˑ��̂Ȃ����Ƃ��낤�Ǝv���܂��B�����ŁA�Ƃ肠������Ƃ��āA�����ȑ�U�Ԃ̑�Q�y�͂��Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B �ŏ��Ƀ`�F���ɂ��ቹ����n�܂�A�ꔏ�����ă��@�C�I���������Ԃ���悤�Ƀ��K�[�g�Ő��������t���܂��B���̍ŏ��̂Ƃ���ŁA�`�F���ɂ���P������ꔏ��̃��@�C�I�����ւƁA�܂�łЂƘA�Ȃ�̂悤�ɁA���ɂ͕������Ă��܂��܂��B�ŏ��̉��Ƒ������̉��F���}�ς���̂ŁA�������͋�������܂��B�܂��A���̌�A�`�F���ƃ��@�C�I�����͊e�X�̃p�[�g�𑱂���̂ŁA��P������o�����ɗ��ꂪ�}�����ꂵ�Ă����悤�ɂ��������Ƃ��ł��܂��B���@�C�I�����̐�������ߑt���I���ƁA�J��Ԃ��ł�����x�e����܂��B�����āA���̏�ŃI�[�{�G�����y�l�d�t�̑�P���@�C�I�������e���J�f���c�@�̂悤�ȉ��t�����܂��B�J�f���c�@�̂悤�ȁA�Ƃ����̂̓I�[�{�G�̐����ɑ��������������邩��ł��B�܂��Q�̉��ɂ�鉺�~�t���[�Y�B���ɔ{�߂��Ƀt���[�Y���L�сA�X�ɂ��̔{�ƒi�X�ƃt���[�Y���L�тĂ����܂��B�ŏ��̂Q�̉����J��Ԃ����x�ɁA���������������A�i�X�ƂЂƂ܂Ƃ܂�̐������������Â����Ă����̂��A�����҂͓����̌��ł���Ƃ����킯�ł��B�S��ڂ͂�����{�I�[�{�G���d�˂��A���̌�A���̂ЂƂ����肪��������܂��B�����͂�����x�ŁA���x�͂Q�{�̃I�[�{�G�ʼn��t����܂��B�����āA�I�[�P�X�g���S�̂ł��̐߂�������������鏬���ȃN���C�}�b�N�X�ƂȂ�A�z�����Ɩ؊NJy��̊|�������ɂ��Ȃ����o�āA���y���ɂ��V���Ȑ������J�n���܂��B�g�����邢�z�����ŁA���@�C�I�����ƃ`�F�����Έʖ@�I�ɑ�Q�������������B�h�Ɖ������Ă�������ł��B���ʂŌ����ƂQ���ߒ��x�̒Z�������������@���A�ŏ��̓`�F���A���̃`�F���ł̈�߂��I���Ȃ������Ƀ��@�C�I�������ǂ��|���܂��B��̃p�[�g���|������������悤�ɉ��t�����ƁA���݂����x�~�ߍ����悤�ŁA�X�ɂ��̌��Ԃ��Q���@�C�I���������ɂ͊��Y���悤�Ɏ��ɂ͑����I�ɖ��߂čs���܂��B����ŁA�����Ă�����ł́A�����̓�������A�̐����̂悤�ɂ�������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���̎��A�ЂƂЂƂ̓��@�����͐����́A���̂��̂Ƃ��āA�ЂƂЂƂ̓��@�����͐����Ƃ��č݂�Ȃ���A�����ɑ��ׂ��铮�@�����͐����Ɗ|��������������A�Ȃ邱�ƂŁA���̂��̂Ƃ��ĂƂَ͈��̐����ƂȂ�̂ł��B�������ɂƂ��āA���̂��Ƃ͋Ȃ̈�ۂ��ω���^����^����_�@�ƂȂ�܂��B�����u���b�N�i�[�̉��y����������̉Ȋw�@���̂悤�Ȓ��ۓI���̌���������Ă���̂́A��������̂��̌������A���̂悤�ȕω���^���ɐG�m����̂�W���Ă��܂�����ł��B������ł́A�ЂƂЂƂ̓��@�����͐����́A�����܂ŁA�ЂƂЂƂ̓��@�����͐������ꎩ�̂ł�������܂���B�ЂƂЂƂ̓��@�����͐������ꎩ�̂́A������������A���邩������A�߂���������Ɗ����邱�Ƃ͂��邩������܂���B�������A����͉����u���b�N�i�[�̉��y�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A���y��������h���U��悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�܂��A�P�ɁA���̐������������ƌ��������Ȃ��������̂��̌����ɓƂ茾���������������ɉ߂��܂���B���������������ł́A���̐�����������Ƃ͎v��Ȃ��Ƃ����َ��Ȓ�����Ƃ̋���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B���ꂪ�����ɁA�َ��Ȑ����ƂȂ��Ă��������Ă��邱�ƂŁA���̎��͓��h����̂ł��B�u���b�N�i�[���Ƃ������Ƃ́A���̂悤�ȓ����ɋ������Ă����̂��̂�G�m���邱�Ƃ�����̂ł��B�����ɋ������������̓�̂��̂��A�O�A�l�ƕ���������Ă䂭�Ƃ��A�����ɂ͖L���ȉ��y�I��Ԃ��`�������͂��ł��B�����ł́A�l�X�Ȏ��_�ɂ���Č`������鉹�̈Ӗ����P��ȉ��y�̂������ɊҌ������̂�W���Ă���ƍl�����܂��B�܂�A�u���b�N�i�[�̉��y�́A���̂悤�ȓ_���������������̂ł��B���̂悤�ȑ��l�ȉ��̈Ӗ��̋����̒��ɁA�u���b�N�i�[�̉��y�̊J���I�Ȏ��R舒B�������o���܂��B�u���b�N�i�[�̉��y���������Ǝv���̂́A�������܂��A���̎��R���������邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B�ȉ��A���̂悤�Ȏ��_�ŁA�����ȑ�R�Ԃ��Ă��������Ǝv���܂��B ��R�́@��P�y�͊J�n��
������A�P�Ɂg���̈Â��g�̂悤�ȓ����Ɏn�܂�A�܂��Ȃ��A�g�����y�b�g�����t�̊J�n�̐����������B�܂������u���b�N�i�[�J�n���̂��̂ł���B�h
�i���ȉƕʖ��ȉ�����C�u�����[�T �u���b�N�i�[����y�V�F�� P.�T�V
�P�X�s�j�Ȃǂƌ����Ă��܂��Ă��܂�����̂ł��傤���B�Ⴆ�A�g���̈Â��g�̂悤�ȓ����h�ňꊇ����Ă��܂����U�a���̍��݂Ȃǂ́A�NJy��őt����铮�@�̔��t���z���āA�����܂ł̊Ԃ̋ȑS�̗̂���̎哱�̈ꗃ��S���Ă���Ǝv���܂��B���̕��U�a���̃A�N�Z���g�ʒu�̕ϓ��ɂ���ċȑS�̗̂��ꂪ������藬�ꂽ�肵�Ă���̂ł��B�������g���̈Â��g�̂悤�ȓ����h�ƒP���ɂЂƂ̓����Ƃ���Ă��܂��Ă���̂��A���͒ጷ�̑O�̂߂�̏z�ƁA���@�C�I�����̑O�֑O�ցc�Ƃ����㏸�ƌ��ցc�Ƃ������~�̕��U�a���̌���������̂ł��B�����َ̈��ȗv�f���������ɔr�˂��������ƂȂ��������Ă���̂ł��B�ǂꂩ�ЂƂ̗v�f����ƂȂ��āA���̗v�f���]�ƂȂ�悤�ȌJ��Ԃ��͂����ɂ͂���܂���B�����̗v�f�����݂��ɉ���đΗ����邱�ƂȂ��A���ݐZ���I�ɂ܂�łЂƂ́g���̈Â��g�̂悤�ȓ����h�ɕ������Ă��܂��̂ł��B����͌��y��̓����݂̂ɗ��܂邱�ƂȂ��A���y��̕��U�a���ƃg�����y�b�g��z�����Ȃǂ̊NJy��ɂ�铮�@�ɂ��������Ƃ��ł��܂��B�����������ۂ������u���b�N�i�[�̉��y������Â�����̂ƌ������Ƃ��ł���̂ł��B���v�f���݂��ɔے肷�邱�ƂȂ��m�肵�����Ȃ���L���ȗZ�����������Ă����B�u���b�N�i�[�̉��y�͑S�̂߂邩�ו��ɖڂ炷���Ƃ����c�_���Ў藎���Ȃ̂́A���������_����Ȃ̂ł��B�����āA���̗Z������̓I�Ȑ����⋿���Ƃ��ĐG�m�\�ƂȂ����Ƃ��A�L���ȍL�����^���A���y�S�̂̎����ɐ��X�������Y���ݏo���̂ł��B�u���b�N�i�[�̉��y���A�����ς特�̉^���Ƃ��Ē����҂̎��ɔ����Ă���̂͂��������Ƃ��ł��B ���̂悤�ȃu���b�N�i�[�̉��y�̓Ǝ����́A���̍�ȉƂ̍�i�ƒ�����ׂĂ݂�Ƃ͂����蕪����܂��B���U�a���ŋȂ��J�n���Ă��̌�Ɏ�肪���������̂Ƃ��āA�Ⴆ���[�c�@���g�̌����ȑ�S�O�Ԃ��L���ł��B���B�I���̍��ރV���R�y�[�V�����̃��Y���ɏ���āA���@�C�I���������яG�Y���g�߂��݂���������h�ƕ]�����L���Ȏ������t���܂��B�����ł̕��U�a���́A�����܂ł����Y��������S��������̂ł��B���̓��@�C�I�����ʼn��t�����g�߂��݂���������h�����f�B�ł��B���U�a���ō��܂�郊�Y���͔߂��݂̎���y��Ŏx���Ă���ƌ����܂��B �@�܂��A���̋ȁA�Ⴆ�A�V���[�}���̌����ȑ�Q�Ԃ����̕��U�a���ƃz�����ɂ��t�@���t�@�[���̂悤�ȓ��@����\�������Ƃ����A�ꌩ�A���̃u���b�N�i�[�̌����ȑ�R�ԂɎ��Ă���悤�ɕ�������Ȃł��B�������A�V���[�}���̏ꍇ�́A���̕��U�a���ƃz�����ɂ�铮�@�̃T�C�N��������Ă���̂������I�ł��B�܂�A���̕��U�a���̂P�t���[�Y�ƃz�����ɂ�铮�@�̂P�t���[�Y�̒������Ⴄ�̂ł��B�����Ńz�����ɂ�铮�@�̂P�t���[�Y�I������Ƃ��ɁA���̕��U�a���Q�t���[�Y�߂̓r���ɂ��܂��B���̗��҂ɊԂɃY���������āA���ꂪ�Ȃ̐i�s�ɂ�ď��X�ɍL�����Ă䂭�̂ł��B���̃Y���̂Ђ낪�肩��s���ꊴ�������Ă��܂��B�܂��A�V���[�}���̏ꍇ�̌��̕��U�a���ƃz�����ɂ�铮�@�Ƃ̊W�́A�����܂ł����t�Ǝ�����̊W�ŁA���t��������ɓ������Ȃ����������ΑO�ʂɏo�悤�Ƃ���ْ��W�ł�����܂��B�s����ȃ��Y�����Ƒ��ւ��āA�������犴�����闎�������̂Ȃ��́A�����N��ԂƂ��Ē����҂Ɉ�ەt������̂ł��B�V���[�}���ɂ́u�ӓ��Ձv�Ƃ����s�A�m�Ȃ�����܂����A�܂��ɃJ�[�j�o���Ƃł��ĂԂׂ����m�ȑ����ɏI�n��т���Ƃ���ɁA���̍�ȉƂ̋��C���\��Ă���Ǝv���܂��B�����ɁA�V���[�}���̉��y�̑�햡�ƌ�������̂�����Ǝv���܂��B �����̉��y�ɂ́A�u���b�N�i�[�̉��y�Ɍ�����悤�ȁA���ׂĂ̗v�f���m�肵�Ă��܂��悤�ȑ傫���͊������܂���B
��S�́@�u���b�N�i�[�ƃS�V�b�N���z�H
���āA�����Ŋ�蓹�����܂��B�u���b�N�i�[�̉��y���̂��̂Ƃ͗���܂��̂ŁA�����̂Ȃ����͎��͂܂łƂ��Ă��܂��ĉ������B��q�����u���b�N�i�[�̉��y�̑��w�I�ȊK�w�\���Ƃ����ƁA���͒����̃S�V�b�N���z�Ƃ�킯�吹���i�J�e�h�����j��A�z���Ă��܂��̂ł��i�������ł�����u���b�N�i�[�̉��y�����z�ɚg���Ă���͎̂��ȊO�ɂ��I�[�X�g���A�̃J�g���b�N����̃o���b�N���z�Ɍ����ĂĂ���g�c�G�a(�LP300�I��V������
P.205)�̂悤�ȗ������܂��������S�V�b�N���z�������o���Ȃ�Γ�����̃m�[�g���_���y�h�ɑ���(�F��B�v���������l�T���X�̉��y��u�k�Ќ���V��
P.91)���K����������܂�����̕��͂͂����܂ł����̓ƒf�ƕΌ��̒������Ɋ�Â����̂ł����硁j�B�p���x�O�̃V�����g���̑吹����A�~�A���̑吹���ȂǂP�Q���I����P�R���I�ɂ����Ă̎����̌��z�ł��B�傫�ȓ����Ƃ��āA���ł������ƁA�����̐듃�������ނ��Ă��邱�ƁA�o�����ƌĂ��傫�ȉ~�`�̃X�e���h�O���X�����ʂɂ��邱�ƂȂǁA��������Ɣ���܂��B���̃S�V�b�N���z�̍\���ɂ��ăA�[�E�B���E�p�m�t�X�L�[�Ƃ������p�j�Ƃ́u�S�V�b�N���z�ƃX�R���N�w�v�i�O�쓹�Y��@���}�Ёj�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�Ȏw�E�����Ă��܂��B�p�m�t�X�L�[�̓S�V�b�N���z�ƃX�R���N�w�̊ԂɁA���������s�W�����邱�Ƃ��w�E���Ă��܂��B�ނ̋����镽�s���Ƃ́A�����ƑS�̂̊W�ɂ�������̂ł��B�ނɂ��A�X�R���N�w�̋L�q�`���̓����͂܂��A�_�͑��݂���Ƃ������ɂŗB��̖��肩�炷�ׂĂ̋L�q���W�J�����Ƃ�����㈂���Ƃ��ėp���Ă��邱�Ƃł���A�܂����̓W�J�̍ۂ̐����œO��I�ȊK�w���ł���A�����Ă��̌����ȊK�w�I�ȓW�J�̌��ʂƂ��Đ�����A����K�w�ɏ�������e�����̓������ł��B�S�̂͂܂����ɕ�������A���͂���ɏ͂ɕ�������A�͂͂���ɍ��ɕ������A�_�q�͉�㈓I�Ȏ葱�����o�Ȃ���A�ו��������Č���Ȃ��K�w�I�ɕ�������Ă����B���ꂪ�A�ނ̌����X�R���N�w�ł��B�����āA���̊K�w�I�����������A�S�V�b�N���z�̍\���_���ł������ƁA�p�m�t�X�L�[�͎w�E���܂��B�܂��S�̂͐g�L�A���f�A�V�����F�i����̓��[���A���w�Ǝ��f�̂��Ɓj�Ƃ����O�̕����ɕ�������܂��B�������ꂽ���ꂼ��̕����́A����ɍĕ�������܂��B�g�f�͒����̎�f�𒆐S�ɂ��ė����ɑ��f�����`���ɍĕ�������A�V�����F�̕������܂�����̌`���ɏ]���āA���w�Ǝ��f�Ƃɍĕ�������܂��B���̂悤�ȊK�w���̓S�V�b�N���z�̂��ׂĂ��s�����Ă���ƁA�ނ͌����܂��B�x���͑和�i�s�A�j�֕�������A�和�͂���ɏ����i�V���t�g�j�ւƕ�������A�����͂���ɍׂ��������ւƍĕ�������܂��B���̂悤�ȓ������������S�V�b�N���z�ƁA�Ⴆ�A�e�l�̃A�N���|���X�̋u�̏�Ɍ��p���e�m���_�a�ɑ�\�����M���V���ÓT��`���z�ƌ���ׂĂ݂ĉ������B�_�a�̎x���͎��̕����s�\�ł���A�S�V�b�N�̏d�w���͌�����܂���B�_�a�́A�c�ɂ͒��i�x������́j���ɂ͂܂����i�x��������́j�Ƃ̑g�ݍ��킹�ō\������Ă��āA���Ƃ܂����͍\���I�ɕs�����ł��B�����āA���̕s�������䂦�ɐ_�a�̒��̗͋�����ے������������邱�ƂɂȂ�̂ł��B����ɑ��āA�S�V�b�N�̓����I�ȃA�[�`�́A������\������ЂƂЂƂ̐��\���I�ɓ����Ȃ̂ł��B�܂�A�ǂ̐ɂ������悤�ȗ͂��������Ă��邽�߁A�x������̂Ǝx��������̂̋�ʂ��Ȃ��̂ł��B�܂�A�S�V�b�N���z�̍\���I�ȊK�w���ƃG�������g�̓������͊e�������Ƃ��Ɍ��������Ƃ�}���Ă��܂��܂��B����͌��z���ǂ�ǂ�������Ē��ۓI�ȋ�ԂƂȂ��Ē��̐l�Ԃ��ݍ��ނ��ƂɂȂ�܂��B
���āA������蓹�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�O�̃y�[�W�ŊC�̔g�ɗႦ���u���b�N�i�[�̉��y�Ɏ���������K�w���́A���̂悤�ȃS�V�b�N�̊K�w���Ƃ�������h�����镨���̔ے�y�ю�ϐ��ɒʂ���Ƃ��낪����Ǝv���̂ł��B�u���b�N�i�[�̉��y���A���̍�ȉƂ̃V���p����o�b�n�ƈ���č�ȉƂ̃p�[�\�i���e�B�ƈꏏ�ɂȂ��Č���Ă��܂��₷���̂́A�����������_��������ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�A���A������ƌ����Ď��̓u���b�N�i�[�̉��y���A���̂悤�Ɍ�����͂���܂��A�u���b�N�i�[�̉��y���̂��̂悤�Șg�Ɏ��܂��Ă��܂��悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B����ł́A���̂悤�Șg����͂ݏo�Ă��܂����̂Ƃ͉��Ȃ̂ł��傤���B����ɂ��ẮA��ōl���Ă��������Ǝv���܂��B
��T�́@��P�y�́i�P�j �O�͂ł̊�蓹�ŁA�u���b�N�i�[�̉��y�͊K�w�\�������Ă��āA���ꂪ�����̃S�V�b�N���z�̊����ɒʂ���Ƃ��낪����Ƃ������Ƃ��q�ׂ܂����B�������܂��A�K�w�\���ƌ����������ł͎��܂肫��Ȃ��Ƃ������Ƃ������ďq�ׂ܂����B����͂��ꂼ��̊K�w�������I������ł��B�O�X�͂̏����u�Â��g�̂悤�ȓ����v�͕����̕��U�a���ł���Ɠ����ɁA�ʑt�ቹ�ł�����A���NJy��̓��@�����@�ł��������肷��킯�ł��B������A�u�b�N�i�[�̉��y�́A�����ɋ��������������̉��y�G�������g�i�Ⴆ�g�Â��g�̂悤�ȓ����h�����肾�����U�a���j�����̓s�x�D�肠���Ă͉����ق����Ă䂭����ΊK�w��̗L�@�I�g�D�ƌ������Ƃ��ł��܂��B�X�Ȃ̌����Ȃ̊e�X�ɖ��m�Ȍ�������Ƃ͌������A�����p�^�[�����J��Ԃ��Ă��邩�̂悤�Ɍ���������ȂƂ����`���A�����̓A�_�[�W�H���̃X�P���c�H���̂Ƃ��������̂́A���̊K�w��̑g�D�ɂ��܂��܂Ȏh����^����_�@�ɂ����Ȃ��ƌ����Ă������Ǝv���܂��B�i���͌_�@�ƌ����܂������A�u�b�N�i�[���g���������������Ƃ��Č����Ȃ��l���Ă����ȂǂƎ咣�������킯�ł͂���܂���B���Ԃ�A��ȉƃu���b�N�i�[�́A����Ȃ��Ƃ͍l���Ă����Ȃ������ł��傤����B�j�u���b�N�i�[�̌����Ȃ������p�^�[���̂悤�ɌJ��Ԃ����̂́A�u�Â��g�̂悤�ȓ����v�����肾�����U�a�����͂��߂Ƃ��镡���̉��y�G�������g�̋���p���������߂ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�f�ł��B�����A�����̕����̉��y�G�������g�̒��ɓ����I�Ɏ�肾�̎�������̂Ƃ����悤�ȓ����I�G�������g���Ђ���ł��āA���̐i�W��L���Ɏx����ׂ����̃G�������g�����p�����Ƃ������W�͂����ł͕������Ă��܂���B������G�������g���A�S�V�b�N���z�̃A�[�`������̂悤�ɓ������i�ō�i�ɉ��S���Ă���̂ƌ����Ă����ł��B���̊W�́A�����܂ł������I�ȋ����Ȃ̂ł��B���́A�����ȂƂ��A�_�[�W�H�Ƃ��X�P���c�H�Ƃ����������̂��A�u���b�N�i�[�̍�i�݂̂Ȃ炸�A�u���[���X�ł��x�[�g�[���F���ł��A�N���V�b�N���y�����D����҂Ȃ�N�ł��[����������̂ł���̂ɑ��āA�����g�Â��g�̂悤�ȓ����h�́A�����܂ł��u���b�N�i�[�̍�i�̓����ł̂ݒ������̂�[����������̂Ȃ̂ł����āA���̈Ӗ��ŁA���������u���b�N�i�[�̍�i�̓����ƌ���������̂�N���Ɏ����ƌ������Ƃ��ł���̂ł��B �Ƃ���ŁA�O�X�͂͏����u���b�N�i�[�J�n�̕����ł����̂ŁA�����I�ɒǂ��|���Ă݂܂����B�������S�҂ɂ킽���Ă�����s�Ȃ��̂́A���̎��ł͕s�\�ł��B����ŁA����ȍ~�͓K���Ƀs�b�N�A�b�v���Ē����Ă��������Ǝv���܂��B��i�`���̕��U�a���́g�Â��g�̂悤�ȓ����h�ɏ���āA�g�����y�b�g����P�����L������������~��Ă���悤�ȓ��@���J�n�̃t�@���t�@�[���̂悤�Ɏn�߂�B������t���[�g�����n�����āA�z����������ɉ����牞������悤�ɑ�P����L���C���ɋp�I�ȁi�㏸�C���̐����j���@�ő����܂��B���̌�A�ŏ��̃N���C�}�b�N�X�ƂȂ�܂�[0:00�`1:00�@�b�c�ɃJ�E���g����Ă��鉉�t���ԁA�����ł͊J�n��0:00�Ȃ̂ŁA�J�n����1���̂łƂ������ƁA�ȉ��A���̖}��ɂ��������Ď��Ԃ�ڈ��Ƃ��Ē��L���Ă����܂�]�B���̃N���C�}�b�N�X�ɂ����ăI�[�P�X�g���̃��j�]���i�H�j��ff�̑�P�����L�����㉺�~���铮�@���A����Ɉꔏ�����Č��ɂ��㉹�̓����̏��Ȃ����@�����t����܂��B���̓��@�͑O���ƌ㔼�Ő��ɓ��ƐÂ̂悤�ȑΔ�ł������Ƃ��ł��āA���ł���O�̓��@�͖`���̃g�����y�b�g�̓��@�̃��Y�����l�߂ĉ����̏㉺�������������悤�ɓ������Ïk�����A�Âł���㔼�̓��@�̓z�����̓��@�̉����̏㉺�̓�����}���Đ������Â��ɉ��ɗ����悤�ɂ��Ă���悤�ɂ������܂��B�܂��A�O���ƌ㔼�̂��ꂼ��̖����ʼnC��ł��邩�̂悤�ɍׂ����㉺�̓��������邱�Ƃœ��@�S�̂̓��ꊴ�����߂Ă���A�܂�A�g�����y�b�g�ƃz�����̓��@��Z�������Đ������������̂̂悤�ɕ�������킯�ł��B���̃��j�]���̓��@�͂�����x�J��Ԃ��ꂽ���ƁA�z�����̒Z�����n������A�I�[�{�G���Z�����j�]���̓��@�㔼�̐Â̕��������t���I���̉��~���K���J��Ԃ��ƁA���x�͌��������������Ƃ�e���A���ǂ̍��݂�������ĉ��~���K�̏����ȃN���C�}�b�N�X�ɒB���܂��B[1:00�`2:35]���������́A���̃��j�]���̓��@�������Ȃ̑�P���Ƃ��Ă��܂�(���ȉƕʖ��ȉ�����C�u�����[�T �u���b�N�i�[����y�V�F��
P.�T�V �Q�R�s)�B�܂��A�ʂ̂������ł́A�`���̃g�����y�b�g�̓��@���P���Ƃ��Ă��܂�(��u���b�N�[/�}�[���[���T���������)�B���̂悤�ɉ�����ɂ���đ�P���̎������S���Ⴄ�̂��A�u���b�N�i�[�̎��̓����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̏ꍇ�A�ǂꂪ��P��肩�Ɩ₤�͖̂��Ӗ��Ƃ����v���܂���B�ǂꂪ��P��肩�ȂǂƂ����̂́A�ǂ��ł��������ƂȂ̂ł��B��������A���̐�A�Ȃ��i�s���Ă����Ə��X���炩�ɂȂ�܂����A�Ⴆ�g�����y�b�g�̓��@�ƃz�����̓��@�����̂܂܌����鎞�ƁA����炪�Z�����ă��j�]���̓��@�Ƃ��Č����鎞�Ƃ��A����ł��Ȃ��S���̕ʕ��ł��Ȃ��Ƃ����悤�ȁA�ʒꂵ�����A���������Ȃ�����L���Ȓ��a���邱�ƂŁA���y�S�̂̊K�w��̑g�D�ɔ����Ȑk����g�y������Ƃ��A�u���b�N�i�[�̉��y�͐��������Ƃ������ʂ�тт�̂ł��B�ŏ��̃g�����y�b�g�̓��@���������Ă���ƁA���ꂪ��P�y�͑S�҂ɂ킽���Ď��X�ɌJ��Ԃ����P�����ɁA���͂����܂����ƍ�������Ȃ�Ƃ��Ȃ�����A�܂����̈���ŁA�z�����̓��@�⌷�y��̕��U�a���Ȃǂ̂悤�Ȋւ��������̂��A�ǂ̂悤�ɂ��Ă���Ɨ���ł���̂��A���̎�������邱�ƂɂȂ�̂ł��B�܂�A�����Ȃ̃\�i�^�`���̃v���O�������A���ɂ̓g�����y�b�g�̓��@�����Ɨ���ŕς�����肷��S�̗̂���Ƃ��Č����Ă���킯�ł��B���̏ꍇ�A���������ꌩ�A�P�Ƀ\�i�^�`���̃p�^�[���ł����Ȃ����Ɋ������鉹�y�̓����̔w��ɁA�g�����y�b�g�̓��@�Ƒ��Ƃ̋Y�ꂪ���肽�Ă�T�X�y���X��߂��炳���ɂ͂����Ȃ��̂ł��B���̋Y�ꂪ�A�����ȓI�Ȏ��Ƃ��̓W�J�Ƃ����ʂł̃u���b�N�i�[�̉��y�͒P���ɕ������Ă��܂��ɂ�������炸�A�L���Ȋg����ƕ��G����^���Ă���̂ł��B ��U���x�~������A�`���̌J��Ԃ��������ɓ]�����ĒႭ�Z���ēo�ꂵ�܂��B�g�����y�b�g�̓��@������ɑ����܂����A���x�̓z�����̓��@�ɑ����Ȃ��ŁA�g�����y�b�g�̓��@���g�����y�b�g�ƃt���[�g�����݂ɐ����܂��B�����āA���҂̎n���̊��o������ɒZ���Ȃ葼�̋��NJy��������N���C�}�b�N�X�ɒB����ƁA���j�]���̓��@���O���Ⴂ�����ʼn��t����܂��B�z�����ƃt���[�g���㔼�����̖�����Z�������ĂȂ��ƁA���y���ɂ���Ă��̖����̉��`���ɓ]�������āA���y�l���Ŋ|������������悤�ɉ��t����܂��B[2:30�`4:30]�����̉��`�͂S���ɂ�鉺�~�ł����A��������@�C�I�������₢�|����悤�ɉ��t����ƁA����ɉ�����悤�Ƀ��B�I���Ȃǂ̓������̉��������オ���Ă���̂��A�ЂƂ̒����ǂ��납������܂���B�u���[���X�Ȃǂ͓������̉����������āA���ꂪ�S�̂̋����̊�ƂȂ��ăI�[�P�X�g���̊e�����̊Ԃ̐ڒ��܂̖�ڂ����Ă��܂��B���̂��ߑS�̂̋������������𒆐S�ɏd���������Ȃ��Ă���̂ł��B�u���b�N�i�[�̏ꍇ�ł́A�ނ�����������Ɨ����ē������Ƃ������A�S�̂̋����ɂ̓u���[���X�̂悤�ȏa����d���͊�����ꂸ�A�J��u���[���X�ɂ͂Ȃ��������⋿���̔������������܂��B���ꂪ���̕����ł͂悭�����Ă���Ǝv���܂��B���H���t���g�����ɐ��ݏo����A�݂��Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ���̃����f�B�����������B���҂݂͌��Ɉ������č����i���F���i�[����H���t��u���b�N�i�[���Ȃ��l��쑽�����~����ԗY�O�� ���y�V�F�Ё@P.163 �P�P�s�j�B�h�Ə����Ă���̂́A���̂悤�ȉӏ��̂��Ƃł��傤���B�X�̃p�[�g�̃����f�B�����ꂼ�ꃔ�H���t�̌����悤�Ɂg�������Ƃ��ł��Ȃ��h���݂ŁA����炪�݂��ɋ������ĂЂƂ̏�����肠���Ă���B�����ɁA���y�̖L���Ȃӂ���݂������Ă���̂́A����܂łɉ��x���q�ׂĂ������Ƃł��B�������A�����ł̓����f�B�̗��ꂪ�ǂ���㉺�̓����������ɗ���铮�����L���ŁA�S�̂ɋ����ă����f�B�̐����L�тĂ������������܂��B���̈Ӗ��Ń��j�]���̓��@�̌㔼�����y���ɔ��f���Ă���Ǝv���Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���āA���y�l���̊|�������ɂ̓z�����Ȃǂ̊NJy�킪����艽�x���J��Ԃ���܂��B�S�̉�����Ẳ��~�ɂ�郔�@�C�I�����̖₢�|�����d�˂Ă��������ɑS�̂̉��ʂ��傫���Ȃ菬���ȃN���C�}�b�N�X������܂��B[4:30�`5:45]�ˑR�㉹�ƂȂ�A�܂������Ȃ��ăR���g���X�g��������ƁA�����ȃN���C�}�b�N�X�ł���܂łƂ͑S���َ��ȓ��@���n�܂�܂��Bff�Ō��y���Ƌ��NJy��ɂ���ĂQ���P�ʂ̕��̏��Ȃ����~�̉��̓���������A����ɑΈʖ@�I�ɗ��ނ悤�Ɍ��y�������������`�����܂��B���ꂪ�����Q���ߒ��x�̒����ŁA���̌�ˑRpp�ƂȂ��ď㏸�̉��̓����������āA�O�Ƌ����ΏƂ���ەt�����܂��B���@���g�̒��ɑΗ������Ă���̂ł��B������J��Ԃ��āA�g�����y�b�g���h������悤�Ɏキ�����ׂ����㏸�����₢�|��������Ǝc��̐�������������L���C���ɉ��~�̓����ʼn����܂��B[5:45�`7:00]���̈�A�̓������J��Ԃ��Ĉ�x����オ�蒸�_�Ŗ`���̃g�����y�b�g�̓��@����h�������悤�ȉ��`��������ƁA�㉹�ƂȂ肱�̉��`���e�����Ŏn���Ȃ����������悤�Ɏキ�Ȃ��Ă����܂��B[7:00�`9:00]���āA��q�َ̈��ȓ��@�́A�����ΏƁi�R���g���X�g�j�����Ă��܂��Bff�^pp�A���~�̉��̓����^�㏸�̉��̓����A�������^�ׂ������B�ȏ�̂悤�ȑΏƂ��|������������̂ł��B����ɂŏq�ׂ��悤�ȃu���b�N�i�[�̃I�[�P�X�g���C�V�����̓u���[���X�̂悤�ȓ��������ڒ��܂ƂȂ��Ċe�����̋��������S�I�ɂ܂Ƃ߂����邱�Ƃ��Ȃ��e�����̓Ɨ��������ɂȂ邽�߂ɑS�̂Ƃ��Ă̋����͔�����ɂȂ��Ă��܂����߁A���̂悤�ȃR���g���X�g���Ȃ���w��������ĕ������Ă��܂��B���ꂪ�K�w��̑g�D�Ƃ��Ẵu���b�N�i�[�̉��y�ɃA�N�Z���g��^����̂ł��B�l�X�ȍו����ςݏオ���ĕ��G�ȊK�w����Ȃ��Ă���ƕ����āA�X�^�e�B�b�N�Ȉ�ۂ������ꂽ���ƂƎv���܂��B����ɃA�N�Z���g��^���_�C�i�~�b�N�ɂ��Ă���̂��A�����ł̋����ΏƂƂ������Ƃ��ł��܂��B�����َ��Əq�ׂ��̂́A���������킯�ł��B�����āA���̂悤�Ȉَ��ȗv�f�����肱�ނ��ƂŁA�����Ȃ̎��I�ȓ��ꐫ�͕s�ύt�ƂȂ��Ă��܂��܂����A���ʃu���b�N�i�[�̉��y�ɐ��������Ƃ���������^���Ă���̂ł��B���ꂪ�܂��A�u���b�N�i�[�̉��y�̕�e�̖͂L�����������Ă���Ƃ�������Ǝv���܂��B
��U�́@�u���b�N�i�[�ƃt���[�h���b�q�H
�P�W���I����P�X���I�ɂ����ăh�C�c�Ŋ����J�X�p�[�E�_���B�b�h�E�t���[�h���b�q�Ƃ�����Ƃ����܂��B���̉�Ƃ̕`�����i��ɂ͂���߂ċ����R���g���X�g�������Ă���A���ꂪ�ς�҂ɑi�������Ă��܂��B���Ƃ��A�s�R��̏\���ˁi�ʖ��F�e�b�`�F���̍Ւd��j�t�Ƃ�����i�B�[�Ղ���X�̒��ŁA���v�̒W���Ό����ĎR�̒��ɏ\���˂������Ă���Ƃ������̂ł��B�������A�\���˂̓L���X�g�����Y�ɂ���Ă��鑜�Ȃ̂ł��傤���A�^���ʂłȂ��ߌォ��̊p�x����`����āA�ς�҂ɔw�������Ă��܂��B���ĉ�����Ƃ�����ɂȂ�Ǝv���܂����A�O�i�̎R�̒��㕔���̓V���G�b�g�ƂȂ��ĕǂ̂悤���ނ��Ă��āA���ւ̎��E���Ղ��Ă��܂��B�܂�A���̎R�̌��������ɊJ���Ă���ł��낤���]�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��킯�ł��B�����āA���̎R�̔w��ɂ͗y���ɗ[�Ă��̋Ђ낪���Ă��܂��B�����ɂ́A���푽�l�Ȃ��̂�����Ώ������蕗�ɑO�i�A���i�A���i�A�Ɣz�u���ꂽ���ߖ@�ɂ���Ԃ̉��s�̃p�[�X�y�N�e�B�������@���Ă��܂��B�O�i�ł���R�̒���Ɖ��i�ł����̊Ԃɋ�ԓI�ȂȂ��肪�������܂���B���҂͂܂�ŕʁX�̂悤�ɉ�ʏ�ŋ����R���g���X�g���`�����܂��B����ɁA�O�i�ł���R�̒���̎��ӂ̐A������͍ו��ɂ킽���Đ����ɕ`����Ă���̂��A�R���g���X�g�������X����܂��B�܂��A�O�i�̎R�͂��������y���ȋ��璭�߂��悤�Ɍ�����̂ɁA�X�̗v�f�͂���������ώ@�����悤�Ɍ����܂��B����ł́A���̊G������ꍇ�̎��_�Ƃ������̂��A�͂�����ƒ�߂��܂���B���̂悤�ɏ����Ă����ƁA�������̊G���Ȃ��Ă���悤�ɂ݂���ł��傤���A���͂��ꂪ���͂ł�����̂ł��B���ߖ@�Ƃ����͎̂��_�����������߂āA���肵���p�[�X�y�N�e�B���̂��ƂŎO�����̋�ԓI���s��\�����܂��B���̂悤�ȊG���ς�ꍇ�́A��̓����I�Ȏ��_����ώ@���邪�@����ʂ�Î~�I�ɋ��邱�Ƃ��ł���Ƃ����킯�ł��B�������A�s�R��̏\���ˁt�ł́A����炵�����_���Ȃ��̂ł��B����ɁA���̊G�̂܂��z���������I�ŁA�z���Ƃ������͑��g�̂悤�Ȍ`�����Ă��܂��B���̊G�̎��_�͊G�̓����ɂ���̂ł͂Ȃ��āA�O�������̎�O�ɂ���ƍl�����܂��B��̓I�Ɍ����ƁA���̊G���ς�҂͊z�������g�z���Ɋς邱�ƂɂȂ�B���̉��ɂ͑��ݓ���邱�Ƃ͂ł��܂���B�������A�����͑��ɓ������悤�ɁA�O�i�A�����ĉ��i�Ƃ�����ł����܂��B�����őO�i�̎R���̏�ɗ��\���ˁA���Y�ɂȂ��Ă���L���X�g�͐^���ʂł͂Ȃ��A�ߌ��̊p�x����`����A�ς�҂ɔw�������Ă��܂��B���̂��Ƃ��A�ς�҂̎������撆�̃L���X�g�̎����Əd�Ȃ邩�̂悤�ɉ�ʂ̒��Ɉ������ލ�p���ʂ����Ă���Ɠ����ɁA���i�Ƃ̕��������Ӗ����Ă���̂ł��B�܂�A���̊G���ς�҂́A���߂邱�Ƃ͂ł��Ă��A���ݓ���邱�Ƃ��A���G��邱�Ƃ��ł��Ȃ����E��������������܂���B�܂��A�t���[�h���b�q�̂��̍�i�ł́A�[�Ă��̌��ɋP�����i�ƈÂ��V���G�b�g�ɂȂ��Ă���O�i�Ƃ������Ɖe�̃R���g���X�g���`�����Ă��܂��B�������A�����ł����̒��S�Ɍ������ē��S�~���d�˂�悤�ɔ����G�����d�ɂ��d�˂邱�Ƃɂ���āA�����킸�����ϓ��ɖ��邳�������Ă����悤�ȁA�����Ȍ��̏W���I���ʂ����ݏo����Ă���̂����邱�Ƃ��ł��܂��B��ʂ̉��ւƏ����������Ă����悤�ȉ��߂̉��s�������Ă����Ԃ́A�P���ƃV���G�b�g�ɂ���Ċu�Ă���ƂƂ��ɁA���̋P���̏W���ɂ���Ĉ������߂��A���ꊴ��^�����Ă���̂ł��B �u���b�N�i�[�̉��y�Ɍ������Ƃ��s������������Ƃ������A�O�͂ŐG�ꂽ�悤�ȃR���g���X�g�̋����ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̓_�ŁA�t���[�h���b�q�̊G��͂���߂ăR���g���X�g�������A�����������o���ɂȂ��Ă��āA���i��ł���͂��̂��̂�����̍Ւd�ɒu����Ă��܂��Ƃ����A�ς�҂ɏ@���I�Ȋ����������Ă��܂����̂ŁA�u���b�N�i�[�̉��y�ƒʂ���Ƃ��낪����̂ł͂Ȃ����Ǝv�����Ƃ��ł��܂��B�������A�t���[�h���b�q�̍�i���ςĊ�������̂́A�҂��Ƀu���b�N�i�[�̉��y�ɂ��ꖬ�ʂ���悤�ȃR���g���X�g�̋������E�ł����A�Ԃ��Ȃ����i�̌����������P�����i�ƈÂ��V���G�b�g�̑O�i�Ƃ̒f��Ƃ����悤�Ɏ�̓͂��Ȃ��������E�����o����������Ȃ��̂ł��B�y���Ȍ��P�����E�ւ̓���͂��ł�����ɗ��܂邩�炱������ł��肤��̂ł����āA�����Đ��A���ꂦ�Ȃ����̂Ɉӎ��I�Ɍ����������Ƃ����A�A�C���j�J���Ȉӎ��̂��̈�_�Ɏ~�܂��Ă���̂ł��B����Ώu�Ԃ̐��E�Ȃ̂ł��B������A�ς�҂͋����R���g���X�g�ْ̋��ɑς�����킯�ł��B�����A�Z���Ă��P���ԋ߂�������u���b�N�i�[�̌����Ȃɂ��̂悤�ȋْ�����������Ƃ�����A�ς����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ȃ��Ƃ��A���͑ς����܂���B���݂��ɋ����R���g���X�g����ْ��̍������E���`������_�ŋ��ʂ��Ȃ���A�u���b�N�i�[�̉��y�ɂ����ăt���[�h���b�q�̊G��ɂȂ����̂�����悤�ł��B����ɂ��ẮA��̏͂ōl���Ă��������Ǝv���܂��B
��V�́@��P�y�́i�Q�j �������̕��͂������n�߂����ɂ͑�P�y�͂ɂ��āA���̂悤�ɊJ�n���Ɓi�P�j�A�i�Q�j�Ƃ����悤�ɕ��������͂���܂���ł����B�\��ɔ����Ē����Ȃ��Ă��܂����A���t�������������B�O�͂̊�蓹�ł́A�u���b�N�i�[�̉��y�ɂ���R���g���X�g�������ْ����ݏo���_�Ńt���[�h���b�q�̕��i��̐��E�Ƌ��ʂ�����̂������Ă��邱�Ƃ��q�ׂ܂����B�������A�t���[�h���b�q�ɂ͂Ȃ��āA�u���b�N�i�[�����������Ă�����̂�����B���ꂪ�����u���b�N�i�[�̌����Ȃ��ʂ������ŁA���ꂪ�Ȃ��ƍ�����́A����ɂ��čl���Ȃ����P�y�͂̑������Ă������Ƃɂ��܂��B �㉹�Łu�Â��g�̓����v�̕��U�a���������܂��B�؊NJy�킪���݂܂��B�g�����y�b�g�̓��@�͖؊NJy��Ŕ����ɑt����A�����ă��j�]�����@�����y��̃s�`�J�[�g�ɏ���Ė؊NJy��Œf�Ђ�����܂��B�㉹�Ŋe���������ꂼ�ꚑ�������悤�Ɍ��y��̍��ރs�`�J�[�g�̃��Y���ɂ̂��đ����I�Ƀ��j�]�����@�̒f�Ђ��|���������܂��B[9:00�`11:20]�����ŁA�������낢���Ƃɓ��@���f�Ђɕ�������Ă����̓��@�̐����̂��������ϗe����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��āA�x�[�g�[���F���̌����Ȃ̎��̓W�J�̂悤�Ɏ�肪��������ĕϗe���Ă����Ƃ������Ƃ́A�u���b�N�i�[�̌����Ȃł͌����܂���B���@�́A�Έʖ@�I�ȑ��������������]�������肵�Ă��A�����܂ł��������͌��̂܂܂ł����āA����̓V���[�x���g�̌��z�ȕ��̓W�J��f�i�Ƃ�����悤�Ɏv���܂��B�ł����炱���ł́A�����ȂƂ��Ă̎��̓W�J��_���I�ɒǂ��|����Ƃ����悤�ȁA�����ǂނ悤�Ȓ������͕K�v�Ȃ��킯�ł��B���̎��X�̑����I�Ȋ����ɐg��C����S�n�悳�Ƃł���������悢�ł��傤���B���̗F�l�́A���̊y���݂��Ԃŗ��s���Ă��āA�ԑ��̎��X�Ɍ����Ă͏�����i�F�����C�Ȃ����߂Ă���y�������ƌ����܂��B�F�X�Ȍi�F���y����ł��邤���ɗ�Ԃ͖ړI�n�ɒ����Ă��܂��̂ł��B�x�[�g�[���F���̌����Ȃ͖ړI�n�𗧂ĂāA������Ƃ����v��ɏ]���ė��s������c�[���X�g�Ȃ�A�u���b�N�i�[�̏ꍇ�͎��ɓ��ɖ�������������蓹�����Ȃ��痷�����郏���_���[�ƌ������Ƃ��ł��܂��i�e�I�h�[���W��A�h���m��y���̎���O�������� ������
���̒��Ť�V���[�x���g�̉��y�𢂳���炢�l�I���i��ƕ]���Ă���Ƃ��납��ؗp���܂�����j�B�x�[�g�[���F���̌����Ȃ̂悤�Ȏ��̓W�J���Ȃ��A���i�����ŁA����܂Ō���Ȃ��������Ƃ�����������o���܂������A����͂����܂ł��x�[�g�[���F���̌����ȂƑΔ䂷�邽�߂����ɕX�I�ɗp���������̂��Ƃł��B������A�����ȊO�ł͂���܂Œʂ蓮�@�Ƃ������p���܂���j����������肻�̂��̂��͂�����Ƃ����ɒP�ƂŖ��m�Ȏ��ł͂Ȃ��A�������̂���炵�����̂��W�܂��Ď��̌Q����`�����Ă���B�����F�X�Ǝ�������i�������o�Ă���̂ł��B�܂�A��肪���������Ɯf�r�i�����_�����O�j���Ă�������O�ւ͐i�܂��A���̏�œ��X��������Ă���킯�ł��B���̂悤�Ȉ��̏z���̓u���b�N�i�[�̌����ȑS�̂̍\���ɂ������邱�Ƃł��B�ŏI�y�͂ł́A�ȑO�̊y�͂̎�肪��ړI�ɍČ�����܂��B�����āA�Ō�͂܂�ŊJ�n�����ɖ߂邩�̂悤�ɊJ�n�̓��@�ŏI��邱�Ƃ������B�ł�����A�u���b�N�i�[�̌����Ȃ̓W�J�������I�Ƃ͌����Ă��A�Z���j�A�X�E�����N��`���[���[�E�p�[�J�[�Ȃǂ̃W���Y��z�����B�b�c��|�S�����b�`�̉��t����V���p���̃s�A�m�Ȃ̂悤�ɐ悪�ǂ��Ȃ邩�\�z�����Ȃ��悤�Ȍ������ْ�������킯�ł͂���܂���B��͊��ɒ�܂��Ă��Ă��̌o�H�̑I���ɕ�������Ƃ������x�̂��̂ł��B�����炱���A���̏u�Ԗ��Ɉ��S���Đg��C���邱�Ƃ��ł�����̂Ȃ̂ł��B �����ŁA���̃W���Y��V���p���̑������ƃu���b�N�i�[�̂���Ƃł́A�ǂ����ǂ��قȂ�̂��Ƃ����̂͒��X�������ɂ������̂�����܂��B����͑����A�V���ɏo������t���[�Y�����ۂ̎��Ԉӎ��̈Ⴂ�ɂ��Ⴂ���Ǝv���܂��B�W���Y��V���p���̏ꍇ�́A�ӎ��̎��Ԃ����t�̎��ԂɈ�v����Ƃ�����Ԃɂ��邽�߁A�����҂ɏ�ɐV�N�Ȉ�ۂ�^����Ɠ����ɂ��̉��������Ȃ��悤�ɋْ�����������̂ł��B���Ԉӎ��ȂǂƂ���������Ȍ��t�������Ă��܂��܂������A����l����K�v�͂���܂���B���̈Ӗ�����Ƃ���́A���퐶���̒��œ����o�����Ă��Ă悭�����m�̂͂��̂��ƂȂ̂ł�����B�Ⴆ�A�F�l�̌������ɏ��҂��ꂽ�Ƃ��܂��傤�B��I���Ō��܂��Ă��闈�o�̏j���B�܂�Ȃ��ł��ˁB�ǂ����ĂȂ̂ł��傤���B����́A���܂�����p�^�[���ɑ����đO���ɂł��������������ł��낤���e���Ȃ�Ƃ��ËL���āA�Ƃɂ������s���Ȃ��悤�Ɍ^�ʂ�ɂ�낤�Ƃ��邩��ł͂Ȃ��ł��傤���B�����������̗��o�̈ӎ��́A�����̃X�s�[�`���Ă��鎞�ԂƂ͈�v���Ă��܂���B���ł͌��ݒ���Ȃ�����A�ӎ��̕��͌��e�̗v�_�͑S�����������낤���A�V�Y�̏o�g�Z�������ԈႦ�Ȃ����낤���Ƃ���ʂƂ���֍s���Ă��܂��Ă���̂ł��B�Ƃ��낪����A�}�ɗ\��O�Ɏw�����ꏀ�����܂܂Ȃ�ʕ���̊w������̈��F�̂悤�Ȑl���A�n�߂̂��������{�\�{�\�Ɩ����e�Ȃ��Ƃ�ꂫ�Ȃ�����A�ˑR�b�����ɏ���āA������l���v�킸�H���̎���~�߂Ęb�ɕ��������Ă��܂����Ƃ����X����܂��B�����������̈��F�̈ӎ��̎��Ԃ́A�܂������b�����Ă��邢�܌��݂̎��Ԃƃs�^����v���Ă���ƌ������Ƃ��ł��܂��B�����Ă�����o�Ȏ҂������A�{���ɂ��̘b�͂��܂��̏�ŏ��߂Č����̂��Ƃ������X���������I�̌����������邱�Ƃ��ł���B�܂�A�W���Y��V���p���̑������Ƃ����̂́A���̈��F�̏j���̂悤�ɁA���y�Ƃ̉��t�̎��Ԃƒ����҂̌o���̎��Ԃ���v���āA���N�������V�����o���������L������Ɗ�������ʔ���������̂ł��B����ɑ��ău���b�N�i�[�̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ�̂��l���Ă݂܂��傤�B�ނ͐������^�ʖڂȐ��Ȃ̂ŁA�F�l�̌������j���ɂ͏\��������قǂ̏��������ėՂ݂܂����B�ނ͖{���ɐ��^�ʖڂȂ̂ŁA���e���ۈËL�A�_�ǂ݂���悤�Ȃ���������Ȃ��Ƃ͂��܂���B�L�`���Ƃ��̎��̎����̒��S�̌��t�Řb�����悤�Ƃ��܂��B�������A�^�ʖڂ�����ނɂ́A���������ܒ��������Ƃ��s�\���ł���Ƃ�����������ɂ��܂Ƃ��̂ł��B�u�V�Y�́�����w��D�G�Ȑ��тő��Ƃ��c�v�ƌ����A�Ȃɂ����܂̌������͌^�ʂ�̂������Ǝ��ꂻ�����ƁA�����Ɂu�{���̘b�ŁA���̏؋��ɂS�N�Ԃł`���R�O������āc�v�ƌ����������Ǝv���ƁA���x�͂���ł͐��т����������̃K���ׂ��ƌ����Ă��邾�Ǝv�������A�u���т���łȂ��X�|�[�c�����\�ŁA�Ƃ�킯�e�j�X�Ȃǂ́c�v�Ȃǂƌ����o���n�߂āA�Ƃ��Ă����ԓ��ɏj���͏I��肻���ɂȂ��A�i��҂ɑ������������Ăނ���Ȃɖ߂��ꂽ�肵�Ă��܂��B�ނ̎��Ԉӎ��́A���������������Ă��܂������ƁA���łɌ��킵�Ă��܂����t���[�Y�A�܂�ߋ��̕����Ɍ����Ă��܂��i�㓡��m��W���Y��I�u��p���_�C�X��u�k�� P.�P�O�U���@�Ȃ�����Ԉӎ��ɂ��Ăͤ��Y�×Y����ԣ��g�V��
���Q�l�Ƃ��܂�����j�B������ǂ����Ă��ӎ��������̉��t�̌��ǂ��Ă��܂����ǂ�������w�����Ă���̂ł��B�������u���b�N�i�[�̉��y�̓W�J���A�ǂ��������������Ƃ��������Ă��Ȃ��A������������Ȃ��悤�Ȋ�������A�������Ƃ���������ǂ��ǂƌJ��Ԃ��A���̂��߂ǂ�ǂt���Ԃ������Ȃ��Ă��܂��Ƃ�����ۂɂȂ���̂ł��傤���B�ł�����A�u���b�N�i�[�̉��y�̓W�J�̑������Ƃ����̂́A�ꉹ�ł����������܂��Ƃ��������������悤�ȋْ��͔���Ȃ��ōςނ̂ł��B���̂悤�ɁA�������Ƀu���b�N�i�[�̉��y�ɂ͋����ْ�������܂����A���̔��ʁA�ƂĂ������b�N�X���Ă�������̂ł��B���ꂪ�Ȃ��ƁA�S���Ŗ�P���Ԃ��邱�̋Ȃ��ʂ����Ƃ͂ł��܂���B ���j�]���̓��@�̊|�������̊Ԃ��Z���Ȃ��Ă���ɂ�āA���ʂ����X�ɑ傫���Ȃ��Ă��āA�N���C�}�b�N�X�̓��j�]���̓��@���I�[�P�X�g�������t���܂��B[11:00�`12:40] ����܂ł̃N���C�}�b�N�X�̂������Ƃ́A�����̂͂�����ƈ���Ă��āA���̓_�������������P�y�͂̎R��̃N���C�}�b�N�X�̂ЂƂ��`�����Ă��܂��B���̈Ⴂ�Ƃ͉����A�u���b�N�i�[�̃N���C�}�b�N�X�̕������A�ǂ��ł��������璮���Ă݂ĉ������B���������A�u���b�N�i�[�̃����f�B�\�����̃����f�B�̗Z���Ƃ����\���I�ȓ��������\���A���̕����̃����f�B�̕����ɕ������āA���ꂼ������y��Q�Ƌ��NJy��̂݁i���邢�͖؊NJy������܂߂āj�̌Q���|�����������Ă��������ɁA�|�������̕������߂Ă����đo���̊Ԃ̚�G�����̂ċ���Η��������߂Ă����܂��B�|�������̕������܂�Ƃ������Ƃ͉��y�S�̂̑��x�������Ƃ������Ƃł�����A����ɂ�ĉ��ʂ������Ă������ƂɂȂ�킯�ł��B�܂�A�Η����̍��܂��S�̂̑��x�Ɖ��ʂ̑��ʂ������ċْ������߂Ă����A���̍s�������Ƃ��낪�N���C�}�b�N�X�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B�����Ē��_�ɒB�������f�B������Ċ|�����������Ă����e�y��Q���A��Q�ƂȂ��ă��j�]���Ń����f�B�����炩�ɑt���邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�g���y�̃N���C�}�b�N�X���ْ��̐Ⓒ�ł���Ɠ����ɁA�傫�ȁA��m��Ȃ��قǂ̐[�������̂₷�炬�ł�����Ƃ������ƁB�i�g�c�G�a����̍D���ȋȣ�V������
P.�P�T�W�j�h�Ƌg�c�G�a�������Ă���̂́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��w���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂�A�����f�B�����Ċ|������������悤�ɑΗ����Ă������̂��A���̑Η��ɂ��ْ��̒��_�őΗ����~�g�����悤�ȃ��j�]���̉��t������Ƃ������Ƃł��B�������A�������ڂ���̂͂��̂��Ƃł͂���܂���B�ْ��������߂ăN���C�}�b�N�X�Ɏ���v���Z�X�͂����Ƃ��āA���̐Ⓒ�̏u�ԂɃt�b�Ƒ����悤�ɂق�̏������ʂ���߂āA�ْ��������̂ł��B�����A�u���b�N�i�[�̉��t���ꍇ�A�w���҂̍D����������̂́A���̔������ɂ��Ƃ��낪�傫���Ǝv���܂��B���̐Ⓒ�ł̔����ɂ���āA���j�]���őt����郁���f�B�͐��i�͂������ė����̂ł��B�u���b�N�i�[�̌����Ȃ̒��Ń����f�B���ł����������̂ЂƂ����̂悤�ȏ��ł��B���̈�_���ȂāA�u���b�N�i�[�̌����Ȃ̓��@�[�O�i�[�̊nj��y�ȂƂ͌���I���Ԃ��̂ł��B�i���Ȃ݂ɁA���ɂ̓u���b�N�i�[�ƃ��@�[�O�i�[���߂������y�Ƃ��闝�R�������ł��܂���B���x�����Ă��A���ɂ͗��҂͑S���ʂ̉��y�ł��B�j���āA�����ł̃N���C�}�b�N�X�͂��̔������Ȃ��A���j�]���̓��@���J��Ԃ����A���i�Ƃ��������Ύ���̕��́j�̂悤�ɂ�����i�����ْ��Ń����f�B���������܂��B�����́A�S�̂̉��t��v���Ă����𒆐S�ɉ��t��g�ݗ��Ă�悤�ȍ\�z�I�ȉ��t�ł͉Ύ���̕��͂̕��͋C���o�Ȃ����A���ƌ����ę��ߓI�ɔ�������悤�ȉ��t�ł͂��������̓��ʂȊ������o�Ȃ��Ƃ����킯�ŁA�����ł̉��t�ɂ͉�������ӎ����Ȃ�����߂��ꂽ�悤�ȗ�Âȍr�X�������~�����Ȃ�܂��B ���j�]���̓��@���I�[�P�X�g�������t���J��Ԃ��ƁA�ˑR�㉹�̃t���[�g���z�����𐁂��Ȃ��ŁA�I�[�P�X�g���̋��t�Ǝ㉹�̃t���[�g�̑Δ䂪�����āA���̌㌷�y���ɂ���ă��j�]���̓��@�̌㔼������������ς��Ȃ���Έʖ@�I�Ɋ|�����������Ȃ��牉�t���Ă����܂��B[13:00�`14:25] �g�Â��g�̂悤�ȓ����h�����镪�U�a������A�`���ɖ߂����悤�ȉ��t���n�܂�܂��B�����Č����̊J�n�炵���ł��B���̕��U�a���́A����܂Œ����Ă����悤�ɋȂ̊J�n�A�W�J���̊J�n�A�Č����̊J�n�A�����ăR�[�_�̊J�n�Ƃ��̋Ȃ̐ߖڂɂȂ��Ă���悤�ł��B�ɒ[�Ȃ��Ƃ������A���̍�i�͕��U�a���ɓ������悤�ɂ����Ă���̂�������܂���B[14:30�`19:40] ��ɂ���ĕ��U�a������J�n����ƃg�����y�b�g�̓��@�ƃt���[�g�ɂ��z�����̓��@���㉹�őΔ䂵�āA�Ō�̃N���C�}�b�N�X�ɂȂ��ă��j�]���̓��@�����t���đQ����P�y�͂��I���܂��B[19:40�`21:20]���̋L�q�ł́A�܂��܂��y��̏d�˕��̖ʔ����Ƃ��A�����I�ȗh�ꓮ���̋����ȂǍו��̖��͂���������̂ł����A����͒������̊����Ŋy����ł���̂ŕ��͂ɂ��悤�Ƃ���ƁA�ǂ����Ă��k��Ă��܂��܂��B�ł������ו��̗�O�I�ȓ������m�肵�Ȃ���A�u���b�N�i�[�̉��y�̖L�������L�q�������Ǝv���Ă���̂ł����A���X���܂������܂���B���ꂾ���A���ɂƂ��ĉ��y���Ƃ������Ƃ͑����I�Ȑ��i�������̂�������܂���B
��W�́@���}���e�B�V�Y���f�` ��Q�y�͂��O�ɁA�u���b�N�i�[�Ƃ͒��ڊW�Ȃ����Ƃł����A�����i�K�Ƃ��ď���������蓹�����ĉ������B�u���b�N�i�[�̉��y�ɂ��Ă͉��y�]�_�ƉF����F���̒�������X�ł悭����������A�e���Ō��y�����@��ɐڂ��邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B���������������ǂ肵�܂����B����͎��̌l�I�ȓǂ݂Ȃ̂ŁA�Ⴄ�Ǝv����������������Ǝv���܂����A�F�쎁�̒���ł́A�u���b�N�i�[�̉��y�ɂ��āA�g�l�Ԃ̂͂��Ȃ��Ɛ_�̈̑傳�ւ̔F���A���ꂪ�u���b�N�i�[�̉��y�̖{���ւƂȂ����Ă����B�ނ̌|�p�͌����Ď��R�̕`�ʂł͂Ȃ��B���R������S�ۂȂ̂ł���B�������Ȃ̂͋Ȃ̌`���ł��Ȃ��m�I�����ł��Ȃ��B��������S���Ɓ����ρ������ł���B�u���b�N�i�[�̖{���́������ȋ����ɉB���ꂽ�⛌���ł���A�����ȁ��ł���A���F�聄�ł���A�����������Ǎ��ȍ����ł���A���@���I�ȏ̋��n���ł���B�h�܂���W�����Ȃ̃A�_�[�W���ɂ��Ă��g��R�y�͂̃A�_�[�W���͐��ɂ�������������y���������̂��Ǝv���邭�炢�ł���B����A�F��A�Q���S�Ă��W�ꂽ�����ׂ����e�̃e�[�}�ƌ����悤�B�h�Ƃ܂��ʂ��Ă�������C�p���������Ȃ�悤�ȑ�U���ȕ������ɏo�������ƂɂȂ�܂��B�����ŁA�F�쎁���u���b�N�i�[�̉��y���g���R������S�ہh�ƒf���A��������g����A�F��A�Q���h�������Ƃ��Ă���悤�ɁA���̂悤�ȃu���b�N�i�[�̊������̍���ɂ́A���y������̕\�o�Ƃ��đ����Ă��銴��������������Ă���悤�Ɏv���܂��B�ł�����A�u���b�N�i�[�̉��y�ɑ���ԓx�Ƃ��ďd�v�Ȃ̂́A�g��������S���Ɓ����ρ������ł���B�h�Ƃ����킯�ł��B�����ł́A���̂��Ƃɂ��čl�������Ǝv���܂��B ����Ƃ������t�������o���܂������A�����Ō�������͓��퐶���Ŏ��B���̌����Ă��錻���̊���A�܂��{���y�Ƃ������ʓI����̂��Ƃł͂���܂���B���̂悤�ȌʓI����͖������ł���A���B�I�ɕ\�o�������̂ł��B�����Ō����Ă��銴��Ƃ́A���̂悤�ȌʓI����Ƃ͑ɓI�ȏ��������ꂽ��������Ƃł������ׂ����̂̂��Ƃł��B����́A���B�̌��������ł̊e�Ȗʂł̎�X�̌ʓI�l���������ē����S�̓�������J�����ꂽ���̂ł��B�܂���퐶���⌻���̑������������Ď��B�����Ă���銴��ł���A�Ώۉ������Ȃ��������z�������z�I����ł��B���̊���́A���w�ł́u���I����v�ƌĂ�Ă��āA�ȉ��̂悤�ɐ������邱�Ƃ��ł��܂��i�|���q�Y�ďC����w���T����ţ�O����
���w���I����x�̍��Q�Ɓj�B �@����E�����ł���Ɠ����ɁA�S�̂Ƃ��Đ�捁E���N�ł��邱�ƁB �A���̋������ʉ�����āu�[���v�̕����ɔ��W���邱�ƁB��������I����͖����Ő�捂ł��߂���ł���B�������Ă͂��߂Ċ���͐[���̎����ɕώ�����B���̐��x�Ɛ[�x�͓���̊���ɂ͋��߂��Ȃ��B �B���̊�{��������ĐU�����鑍�̊���Ƃ��Ă̋C���̂����ɗn�������܂�A����ɂ���ĐZ������A�F�Â����Ă��邱�ƁB �P�X���I�̋ߑネ�}����`�́A���̂悤�Ȋ���̂����ɍ��̉����̐������̂̐_��I����̉^���������Ƃ�A������含���z�������̂Ƃ��đ����A��I�Ȃ��̂Ƃ݂Ȃ��܂����B���̂悤�ȉ^���Ɖ��y�̓������d�Ȃ�킯�ł��B���}���h�̉��y�́A���������o�b�N�{�[���̋��ŏ������ꂽ�ƍl�����܂��B�Ⴆ�A���@�[�O�i�[���S�������Ƃ����V���[�y���n�E�G���͎��̂悤�Ɍ����܂��B�g���y���\�����Ă���̂͊�тƂ������́A�߈��Ƃ������́A��ɂƂ������́A�����Ƃ������́A����Ƃ������́A�����Ƃ������́A�S�̂₷�炬�Ƃ������̂��ꎩ�̂Ȃ̂ł���B�����特�y�͂����Ԃ͒��ۓI�ɁA�ȏ�̂��̖̂{����\�����A�悯���ȓY�����������ɁA�܂����@�����̂Ȃ��ɓ��ꂸ�ɕ\�����Ă���̂ł���B�i�V���[�y���n�E�G����ӎu�ƕ\�ۂƂ��Ă̐��E�������������_�� P.�S�W�S �Q�P�s�j�h �������A����ł͌l�̎�ϓI�Ȏv������Ɠ��ꎋ����Ă��܂��댯������܂��B���̓��}����`�̔��I����ɂ́A�J���g���u���f�͔ᔻ�v�œW�J�������ʊ��o�Ƃ����T�O�̔ᔻ�I�ێ悪��b�Ƃ��Ă���̂ł��B���ʊ��o�Ƃ͉����B�p��ł���Common
Sense���A�P���ɖΏ펯�ƂȂ�܂��B����𒀌����ʂ̊��o�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�J���g�͂��̋��ʂ̊��o��l�Ԃ͒N�ł��F�����Ă���B�����瓯���悤�ɔ߂���A���ł���̂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ł�����A�ނɂ��ΐl�Ԃ����ՓI�ɏ��L���鋤�ʊ��o�̓����̂������ŁA���y��G��̔��������A�E�v���I���Ɋ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������̂ł��i�J���g����f�͔ᔻ��c�p�Y���g���Ɂj�B���������}����`�ł͂��̂悤�ȁA�F���������Ǝv�����͖̂{���ɔ������A�Ƃ����f�p�ȋc�_�ɂ͖����ł��Ȃ��Ȃ��Ă����킯�ł��B�J���g�ւ̔������炩�A�t�B�q�e�͂��ׂĂ͊e�̎���̖��Ƃ��ĕЕt�����Ă��܂��܂����i�t�B�q�e��m���w�ւ̑�ꏘ�࣊�蕐�Y�����_�Ёj�B�������A����ł͌l�̎v������ł�������܂���B���}����`�̓N�w�҃V�F�����O�́A1800�N�ɔ��\���ꂽ�u�挱�I�ϔO�_�̑̌n�v�̒��ŁA���R�̐��E�̏�ɐ��藧���_�N�w�Ǝ��R�̐��E�̏�ɐ��藧���H�N�w�Ƃ��܂���A��荂����O�̓N�w����̓I�ɓW�J���悤�Ƃ��܂����B�܂�A���݂̐��E�ł��鎩�R�ƈӎ��̐��E�ł��鎩��ꉻ���ċ��ɂ̓���I���E��}�낤�Ƃ��܂����B���̍ō��̏�Ƃ��čl����ꂽ�̂��|�p�Ȃ̂ł��i�V�F�����O��挱�I�ϔO�_�̑̌n��ԏ����ʖ�O���������`�|�p�Ǝ��R�Ƃ̊W�ɂ��ģ�_�эP����(�h�C�c����}���h�S�W��9��)�}�����s��j�B�ł�����A�|�p�I�Ȕ��I����́A�����ł͐l�Ԃ̈ӎ��̖ʂ��z���ĕ��ՓI���E�ɑÓ�������̂ƂȂ�̂ł��B�Ⴆ�A���Ɉ��p����̂̓V���[�x���g�̃��[�g�ɂ��Ȃ����Q�[�e�́u���l�̖�̉́v�i���ǎ����j�ł��B ���ׂẮ@���� �e�Ђ��� ���ׂẮ@���� ���� �₦�� �����͐X�ɐ������킳�߂� ����@�₪�� �����@�e�͂� ���̎��̓��F�́A��̂Ƌq�́A�܂莩��ƑΏہA���̗��҂̒��Ԃ̋������������Ă��܂��Ă��邱�Ƃł��B���t�͗[��̏�̒��ɉ������Ă��܂��A�[��͌��t�̒��ɉ������Ă��܂��B�܂�[�邪���̂��ƌ��t�ɂȂ��Ă���̂ł��B�����Ď���͂��낢�䂭���̂̒��ŕY���Ă���悤�Ɏ�邱�Ƃ��ł��܂��B����͎�q���Z�����Ă����Ԃƌ������Ƃ��ł��܂��B�����ł́A���I����̂��Ƃɐl�ԂƎ��R�Ƃ��������Ă���̂ł��B���ʓI�Ȃ��̂ƊO�ʓI�Ȃ��̂������悤�Ȓ��q�ɐ������āA���I����̂��Ƃɂ����Ă͂����鑶�݂̖{������ɂȂ��Ē��a����̂ł��B�����āA�G�ɂ������܂����悤�ɏ�������̕\���Ƃ��ĉ��y���ł��K�������̂Ƃ����咣���ׂ��ꂽ�킯�ł��B ���āA���y�̒��ŏ��������\�������Ŏ�Ȗ�����S���͎̂��ۂɂ͐����ł��B���������āA���������\�o���鉹�y�Ƃ����̂͐����D�ʂ̉��y�ƌ������Ƃ��ł��܂��B�܂����y�ɏ�����������Ƃ������Ƃ͎�ɐ������Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�܂���B�G�ɑ����āA�V���[�y���n�E�G���́A�����́g�S�̂��A�S������Ȃ����R�ӎu�o�A��̎v�z�̐₦���Ӗ�����֘A��ۂ������Ȃ���A�n�߂���I���܂Ői�s���āA��S�̂�\�킷�吺���h�ł���ƌ����܂��B�ނɂƂ��ĉ��y�͍ō��̌|�p�I�\���ł��B������\�ɂ��Ă���͎̂��ۂɂ͐����Ȃ̂ł����B�܂�A�����́g�l�Ԃ̎v�����o�������Ɠw�͂���A�ӎu�̋q�ω��̍ō��i�K�h�Ȃ̂ł��B�����ĉ��y������̕\���ł���A�����ɗ����̕\���ł���̂��A�����ɗR�����܂��B�������g�����͂���ȏ�������\�킷�B�����͍ł���߂₩�ȗ��j���A�ӎu�̂����Ȃ銴�������A�����Ȃ�w�͂����A�����Ȃ铮�������`���A�܂�A����������Ƃ����L�����ɓI�ȊT�O�����āA����ȏ�͂��̒��ۍ�p�Ɏ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ׂĂ̂��̂�`���̂ł���B����̂ɁA���ł��A���y�͊���ƌ���̌��t�ł���A����͗����̌��t�ł���ƌ���ꂽ�B�i�V���[�y���n�E�G�� �O�f���j�h ����ł́A���̂悤�ȉ��y���Ƃ����̂͋�̓I�ɂǂ̂悤�Ȓ������ƂȂ�̂ł��傤���B���y�͒����҂̓��ʂɍ�p���ē������܂��B����������̂͐��_�Ƃ��含�ւł͂Ȃ��āA�l�Ԃ̎�ϓI�Ȓ��S�Ƃ��Ă̐S�ł���A����̓����ɉM���m��ʐ[�݂����S��ɑ��Ăł��B���y�͐S��̉���ɗ]�����Ƃǂߊ�����S��̐[���Ƃ��납��ĂыN�����܂��B����͐S�Ɖ��y�Ƃ̋������邢�͊���̌�Z�ł��B�����҂̐S��P�Ɉ��|���ꂽ��h�����������łȂ��A���I���ɂ���ĉ��y�Ƌ������Ƃ������Ƃł��B���̋����ɑ��ė��R��₤���Ƃ͕s�\�Ƃ���܂��B���R��₤�̂͋������Ȃ��l�Ȃ̂ł��B�����ł͒����҂͉��y������ɋz�����ē���������Ɠ����ɁA�����҂����y�ɗn������ʼn��Y��S��D����킯�ł��B�����̋�ʂ͉������A���Y��邱�ƂŎ��Ȃ͎����A�S��D��ꂽ�l�̈ӎ��͍ő������Ȃ�q�̂ɂ��Η����邱�ƂȂ��A���ꂩ�痣�E�����y�̟�X���闬��ɐZ���Ă����킯�ł��B���̎����y������Ƃ������Ƃ́A�����̋�ʂ͉������Ă��邱�Ƃ��玩�ȋ���ł�����킯�ł��B���y�͒����҂̒��ɂ���̂ł��B����g���̊��S�Ȃ�I�A�ˁh�A���y�̒��ւ̒����A����͍�i��ڂ̑O�ɂ�����̂Ƃ��đ�����̂ł͂Ȃ��A���ڂɂ����̌����邱�ƂȂ̂ł��i���@�b�P�����[�_�[����ۂƊ���ړ����g���Ɂj�B �F�쎁���u���b�N�i�[�̉��y���g���R������S�ہh�ƒf���A���������̂ɑ�Ȃ̂́g��������S���Ɓ����ρ������ł���B�h�ƌ����Ă���̂́A�F�쎁�������ōl�������}����`�̉��y�̌��̉e�����ɂ��邱�Ƃ͖����ł���悤�ɍl�����܂��B�������F�쎁�ɂ��āA���̂��Ƃɂ͊����Ėڂ��Ԃ邱�Ƃɂ��܂����A���̂悤�Ȃ������Ńu���b�N�i�[��[���������Ƃ��āA�ǂ����Ă���قǂ܂łɒ��Ȍ��t�ł������邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���B�@���d�F�́A���ĕ���͒m�ɏ]�����A�m���Ă���҂������m��Ȃ��҂Ɍ������ē����I�Ɍ�肦���̂ɁA�t�����X�v���̑��鐭���i1852�`1870�N�j�ȗ��A�N�������ɒm���Ă��邱�Ƃ��m�F���������߂ɕ����悤�ɂȂ�A�����ʂ��Ēm���Ă�����̂����m�낤�Ƃ��Ȃ������b�_�I�Ȏ��ꁄ���`�����ꂽ�ƁA���b�_�I�ȍ\���ɂ��ďq�ׂĂ��܂��B�ނɂ��A���́����b�_�I�Ȏ��ꁄ�ɐ�����������Ȃ�����̐l�Ԃ́A�����̌��t�Ō���Ă�����肪�A���̊Ԃɂ����l�̌��t�ő��l�̖�����炳��Ă��܂��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̂悤�Ɍ��ꂽ���t��ނ́���،^���ƌĂсA�}�f�ł���Ƃ����܂��i�@���d�F�����ᔻ���࣒������� P.30�`�j�B����Ƃ����̂́A�{���A���I����Ƃ����ǂ��I�Ȃ��̂ł���͂��ł��B�J���g�̋��ʂ̊��o�̑f�p���ɖ�������Ȃ��������}����`�҂����������̂Ȃ��l�̌I�Ȋ�����o�����̂ɑ��āA�F�쎁�͂��܂�ɖ�،^�Ō���Ă��܂�����̎�̂ł���l�����E���Ă��܂��܂����B�������X�ɑ�Ɍ��̂�����ɂ����������邱�Ƃ������čs�Ȃ����R�������ł��܂���B�J��Ԃ��悤�ł����A����Ƃ������͔̂��I����Ƃ����ǂ��A�ǓƂȂ��̂̂͂��ł��B�����҂Ɖ��y�Ƃ̊Ԃɂ͐e���Ȉ����Ȃ���ΐ��藧�����Ȃ����̂ł��B�������炱�����̉��y��������̂����A���̉��y�����炱�̉��y��������̂ł��B�u���b�N�i�[�̉��y�͂��ׂĂ̐l�Ɍ�肩���鉹�y�ł͂���܂���B����������Ē��Ȋ���\���̌��t�Ō���Ă��܂����ƂŃu���b�N�i�[�ƒ����҂̐e�����ւ̗���������Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�F�쎁�̎p�����̂��̂ɑ傫�Ȏ��Ȗ���������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂����̉F�쎁�ɑ���ᔻ�̗v�_�ł��B�u���b�N�i�[�͌��������y���ƌ����Ȃ���A������Č���Ă��鎩�����S�R�������Ȃ��̂́A�����Ă��邱�Ƃƍs�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��H������Ă���Ƃ����킯�ł��B ��蓹���A�܂������Ȃ��Ă��܂��܂����B���Ƃ��A���̓u���b�N�i�[�̉��y�ɂ��Ă��̂悤�ȑԓx�͎��܂���B���ɂ��ꂩ��̑�Q�y�͂̂悤�ȉ��y�ɂ��āA�ǂ����Ă��F�쎁�̂悤�Ɍ���Ă��܂����Ɋׂ�Ȃ��悤���������߂ďq�ׂ����Ē����܂����B
��X�́@��Q�y�́i�P�j �O�͂�ǂ܂ꂽ��ۂł́A���̓u���b�N�i�[�̉��y�Ɋ���ړ������邱�Ƃ��Ȃ��Ǝ��ꂽ��������������Ǝv���܂��B�҂��ɁA���͉F����F�̂悤�Ƀu���b�N�i�[�̉��y�Ɂg����A�F��A�Q���h�Ƃ��g�������ȋ����ɉB���ꂽ�⛌���ł���A�����ȁ��ł���A���F�聄�ł���A�����������Ǎ��ȍ����ł���A���@���I�ȏ̋��n���ł���B�h�Ƃ����悤�Ɍ�邱�Ƃ�������Ă��܂��B����́A�g����A�F��A�Q���h�ȂǂƂ����R�����g�������o�����ƂŁA��������Ȃ�����I�ȋN����s�����邱�ƂŁA���y�̉��̋��������͉��̓����Ɏ��܂����ƂȂ��R�����g�ɉ����܂ǂ�킹�A�S���I�Ȕ[��������ɋ��v���A���������ꂪ���ȃR�����g�Ȃǂɓ���[�܂����̂łȂ��s���R�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ���Y�p�����Ă��܂����Ƃ�|��邩��ł��B���̂悤�ȃR�����g�ɛZ�т鉹�y�A�Ⴆ�ΕW�艹�y�ƌ�������́A�́g����A�F��A�Q���h�Ƃ������Œ����҂��z�����镵�͋C����̓I�ɋ����Ɖ����邱�ƂŁA���y�Ƃ��Ăǂ�قǕs���R�ŁA���̕s���R�����R�ƍ��o�����邽�߂̉��y�I�Z�@���A���y�̋����⓮�����ǂ�قǒ����A�}�f�����Ă��܂����Ƃ��B�i����I�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���̕W�艹�y�ւ̏�q�̂悤�ȃR�����g�͎����g�̉��y�̒������ɗR��������̂ł��B�j�u���b�N�i�[�̉��y�����̗ނ̂��̂ł�����A�ŏ����炱�̂悤�ȋL�����������ȂǂƂ����C�����ɂȂ�܂���B����ł́A���̑�Q�y�͂͊����\�킷���t�̎g�p��������Ȃ�����͍̂���ł����A�����Ďn�߂Ă݂����Ǝv���܂��B �y�͖`���̋͂��P�O�b�قǁA�y���Ȃ�Q���ߒ��x�̊Ԃ̃����t���[�Y�B���@�C�I�������V���[�x���g�̎q��̂̎�����ɂ悭���������f�B���A�������ƃ��K�[�g�őt�ł܂��B�Ђ�`�F�����A�K�b�V���ƒቹ���x�������łȂ��A�܂�ł�����̕������y�S�̗̂�������[�h���Ă���ƌ�������Ɏ��Ȏ咣�����邩�̂悤�ɁA�ቹ�̓������A�s�[�����܂��B���̎��_�ł͗��҂̓�̐����Δ�I�ɂ悭�������Ă��܂��B���̃t���[�Y�̌㔼�ŁA���@�C�I�����͓��ɕ������ƁA��@�C�I�����͎�����Ɏ��Y����悤�ȓ��������܂��B����Ǝ㉹�ɂȂ��Ă����o�߂̒��ł̂��̕���͐▭�ŁA���̎㉹�̕���͂ƂĂ���ۂɎc��܂��B���@�C�I�����̓����ɑ��āA�`�F���̕��͎キ�Ȃ炸�ɂ��܂��B�����t���[�Y���I��莟�ւƈڂ鎞�A���̃`�F�����瑱���Ă���悤�Ȏ��ւ̋��n���ׂ̍��ȉ��~�̓�������ɒጷ�Œe����܂��B���̋��n�����I��邩�I���Ȃ������Ɉ�x�݂������@�C�I�������A���̋��n���Ɍĉ�����悤�ɉ��K�������㏸���Ă����悤�ȃ����f�B��t�ł܂��B���̃����f�B�̊Ԃ̓`�F���͋x��ł��āA���B�I�����@�C�I���������Y���悤�Ƀ��@�C�I�����̎�����ɐ����]���܂��B���̓Y�����̓����ł����A�O�̃t���[�Y�̌㔼�Ŏ���������@�C�I�������������A����Ɏ��̂��̃t���[�Y�Ń��B�I����������ĕ��傫���Ȃ�A����ɏ]��������̕�������Ɗg�����Ă���킯�ł��B�͂��ł����A����ɂ�ď������S�̂��N���b�V�F���h���čs���܂��B�܂�A�t���[�Y���i�ނɂ�āA���y������Ɗg����傫���Ȃ��Ă����̂ł��B�����āA���̃t���[�Y�̌�A�`�F�����͂��߂Ƃ����ጷ���������Ɠ����悤�ȋ��n�������܂��B����Ƀ��@�C�I���������܂荂���Ȃ��Ƃ���ŁA�`�F���Ƃ͑ΏƓI�ɒ����Q���ʼn����܂��B����ɂ܂��`�F�����������ƑS���ς�炸�ɋ��n�����J��Ԃ��B���@�C�I�������w�Ǖς�炸�ɉ�����B����Ƀz�����������������ނ̂ł����A���ꂪ���@�C�I�����ƃ`�F���̊|�������̓x�ɁA���������ݕ���ω������邪�ƂĂ��N�₩�Ȉ�ۂ��܂��B���̂悤�Ȋ|���������R��A�S��ƌJ��Ԃ���܂��B[0:00�`0:50]�����Œ�����郁���f�B�̈�ۂɂ��āA�l���Ă݂܂��傤�B�܂��A�P��̊y��ň����̓��j�]���ʼn��t����郁���f�B�̒����ł��B�ӊO�ɒZ���̂ł��B�������A�����f�B���̂ɐL�т�͂��������Ȃ��Ƃ������A���郁���f�B���ЂƂ����艉�t����Ă����ŗ��ꂪ��U�r�₦�Ă��܂��B���̍�ȉƁA�Ⴆ�V���[�x���g�̏ꍇ�̓����f�B���ǂ�ǂ��̕��ւƐL�тĂ����ɏ]���āA���y�S�̗̂��ꂪ�i�s����킯�ł��B�n�����́u�O���[�g�v�̖����������Ȃ́A�`���Ńz�����̃����f�B�������P�ɐ�����邾���ŁA�Ȃ͐i�s���A���̃����f�B���i�ނɂ�Ĕh���I�ȃ����f�B�����܂�A����炪�܂��Ȃ�i�߂Ă����Ƃ����A�����҂̓����f�B�̐��i�͂ɖ|�M����邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�V���[�x���g�̉��y�̖��͂̂ЂƂƌ������Ƃ��ł��܂��B����ɃV���[�x���g�̏ꍇ�́A�����f�B�����͂ŐL�т邱�Ƃł�����x�̒����Ȃ����Ƃ���Ń��Y���̗h��ƌ��т��āA�������̂ł��B�u���b�N�i�[�ɂ́A�c�O�Ȃ��炱�������y���݂͂��܂���҂ł��܂���B���̑�Q�y�̖͂`���Ō����Ȃ�A���y���̊e�p�[�g�Ŋe�X���t�����Z���r��r��̃����f�B���A�ꏏ�ɂł��Ȃ��A�e�X���ʁX�ɂĂ��Ȃ��A�ЂƂ̃p�[�g�̃����f�B���I��邩�I���Ȃ������ɕʂ̃p�[�g���͂��܂�B�e�X�̃p�[�g�̃����f�C�̐�������Q��悤�ɍ��킳���đS�̂Ń����f�B�ƂȂ��Ă���悤�ɕ������Ă���B���̒��ɂ́A�p�[�g���m�̊|������������A�R���g���X�g�������Η�������A�����I�ȗv�f���܂܂�Ă���킯�ł��B���̂悤�ɁA�������Ă��郁���f�B�ɃV���[�x���g�̏ꍇ�̂悤�ȒP��̗͋�������͂Ȃ��̂ŁA�����f�B���������Ƃ������Ƃ̓u���b�N�i�[�̏ꍇ�́A������Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�Ⴆ���@�C�I�������������e���Ȃ���A�r���ő�@�C�I�������㉹�ŕ���ꃔ�@�C�I�����̎�����ɔ����Ɏ��Y����悤�ȓ���������Ƃ���Ȃǂ́A�V���[�x���g�ł͐�ɂ��ڂɂ�����Ȃ��Ƃ���ł��B�S�̂Ƃ��Ă̎�����ƕ���������̂ł��A���������E���Ă��܂����̐����̓����������āA���̈�X�̓����ɂ��ڂ������Ȃ��̂��A�u���b�N�i�[�̃����f�B�́A�V���[�x���g�Ƃ͈�������͂̂ЂƂł��B�{���͂����œr��Ă��܂��͂��̒Z�������f�B���A�������Q��W�܂�����ɔz��邱�ƂőS�̂Ƃ��Čq�����Ă��܂��B�A���ƒf��Ƃ��������Η����鐫�i�������ɋ������Ă���A���x�������悤�ł����A�u���b�N�i�[�̉��y�ɒ�ӂ��瓮����^���Ă���̂͂����������̂ł��邵�A������ł��鎄������A�ʏ�ł͂��肦�Ȃ��s���R���r�����m���ł���܂��B�����Ă܂��A�����f�B�̂������ɂ���P�y�͂̂Ƃ���ŐG�ꂽ���w�I�Ȑ��i�������Ă���ƌ������Ƃ��ł��܂��B �]���������̂ł��傤���A�z�����A�t�@�S�b�g�Ƒ����Č����鎝�������A�Ȗʂ̓W�J�������A����ɓ������悤�Ɍ��y������P�����L������P�y�͂̃��j�]���̓��@���v���N������悤�ȃ����f�B��e���܂��B���̃����f�B�̑�P�����L���̂ɁA�����ÂY���Ȃ���A�w�ǑΈʖ@�̂悤�ɕ������������āA�z�����A�t�@�S�b�g�A�I�[�{�G������ς�肽���ς�藍�݂܂��B������J��Ԃ��Ȃ���S�̂ɃN���b�V�F���h���Ă����āA�����̃��j�]���Ō��̃����f�B��炵�܂��B[0:50�`2:00]�ŏ��Ɏ��グ�������̌㔼�������ł����A�����Ŏ��グ�������̃N���b�V�F���h���Ă����J��Ԃ��������ł����A�J��Ԃ������ꔽ���̂悤�ɕ�������̂ł��B�����܂ł̒��ł��x�X�݂�ꂽ���Ƃł����A�u���b�N�i�[�͕����̊y�킪�|���������s�Ȃ��悤�ȌJ��Ԃ����s�Ȃ��܂����A���̊|�������ɂ͊���I�Ȑ��i���S�������Ă���悤�Ɏv���܂��B�e�y�킪���݂��Ƀ����f�B���̂������Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA���������������x�ƂȂ��J��Ԃ��_���Ԃ��̂悤�ɔ��@�B�I�ɐi�s���Ă��܂��B�����́A�R���g���X�g���ۗ������ċ����ْ��������o���킯�ł��Ȃ��A�n�������Ęa���Ƃ��ėZ�����Ă��܂��čŏI�I�Ȍ��_�ɓ��B����킯�ł�����܂���B���������A���݂��̃p�[�g�̑��݂��m�F�������Ă��邩�̂悤�ł��B�����ɕ\��Ƃ�����Ƃ��������{���̈Ӗ��ł̊|�������̑�ނƂȂ���̂͂Ȃ��A�������͕�I���邢�͋V���I�ł���悤�ł��B�������A�u�b�N�i�[�̉��y�̑f���炵���́A�܂����������_���Ԃ��̔����̒��ɑ��݂��Ă��܂��B���̂悤�ȋH���ŞB���ȑ��e�̂��Ƃŋ��������Ƃ������Ƃ́A�O�ꂵ�ČǓƂȃ��m���[�O�Ƃ��݂��Ɉӎu��a�ʂ�����_�C�A���[�O�Ƃ��َ��́A�V���Ȍ������l�����邱�ƂɂȂ�܂��B����́A�����̕\�ʂ���������悤�Ɍ����ĕ\�����e�i�܂芴��Ƃ����b�Z�[�W�Ƃ��j�Ȃǂɂ͓��ݍ��݂悤���Ȃ��A�|�������̒��œ��̎������g��͕킷�邵���Ȃ��A�\�����e�Ƃ������ʂ��ɓx�ɋH���������A���̋����̕\�w�I�ȋY��Ƃł��������Ȃ������Ȃ̂ł��B�����|�������Ƃ��đz�肳�ꂽ���̂��J��Ԃ����Ƃŕ\��Ƃ�����̃L���b�`�{�[���̂悤�ȏ�ʂ⌀�I�ȗL�������咣����̂Ƃ͈���āA�V���Ƃ������w�Ǎr�����m�̉��Z�Ƃł��������A�Ƃɂ�������̓i���Z���X�ȉ��̋������̂��̂̐��X�����I��Ԃ�Ȃ̂ł��B����قǁA�����ł̉��̋����́A�ނ��炵���|�������̌`�������Ȃ���A�y�X�ƕ\�����e�̌���𗣒E���Ē��ɕ����Ă���̂ł��B����Ȗ��Ӗ��ȋ����Ӗ��Ƃ��ĘI���Ɍ��킵�Ă��܂��u���b�N�i�[�̉��y�Ɏ��͋��C���������ɂ͂����܂���B �����̃��j�]���ŏ�q�̃����f�B���e������NJy��������ČJ��Ԃ����ƁA�ˑR�㉹�ɂȂ茷�y�킪�Ⴍ�Ȃ��̃t���[�Y�B�����Ă܂��A�ˑR�����ɂȂ��ă��j�]���Ō��̃����f�B���J��Ԃ��܂��B�����ēˑR�㉹�ɂȂ��āB���y��̂Ȃ����A�t���[�g���J��Ԃ��ƁA���y�킪���̌�͂�����Ƒt�ł��郁���f�B����肷�邩�̂悤�ɁA���̕�����đ̈ʖ@�I�ɗ��ݍ����Ȃ���e�������܂��B�I�[�{�G���J��Ԃ��A���y��A�z�������Ȃ������܂��B[1:50�`3:40]�����ł̃��j�]���Ǝ㉹�̂Ȃ����A�����҂���������悤�ɓˑR����ւ��A���ꂪ�J��Ԃ���܂��B�܂��A�J��Ԃ��ł��ˁB�悭�悭�v���o���Ă݂�A�悭���������f�B��������ǂ�ȋ����ƍT���߂Ȏ㉹���J��Ԃ��܂��B�u���b�N�i�[�̉��y�ɓx�X������J��Ԃ��B�\��ɖR�����悤�ȕ����̃p�[�g�����x�������������J��Ԃ����ƁB������A�@�B�I�ɁA�����ߒ����ɔ��������邱�ƁB���ꂪ�A�ǂ����Ă���قǖ��͓I�Ȃ̂ł��傤���B�P���Ƃ������̏�Ȃ��P���ŁA�w�Nj@�B�I�Ƃ��v����قǂ̕s���R�ƌ����Ă����������̔������A���̂܂܂����ƒ��������Ă������Ǝv�����Ƃ�����܂��B�����ł́A�ǂ̃p�[�g�̊y��̋������A�S�Ă����̒��ۓI�ȓ������̂��̂Ɖ����Ă��܂��āA���̓����𑨂��钮�����o���̂��̂������ɓ������āA�J��Ԃ��̐��ݏo�����Y���ɗn�������Ă��܂��āA�܂�Œ������Ƃ���߂Ă��܂������̂悤�Ɋ�������̂ł��B�܂�ŁA����鎞�Ԃ��̂��̂��A��C�̐U���Ƃ��Ĕ畆�̕\�w�ł����Ƃ߂Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂȂ̂ł��B�����Ă��鎩���́A������������W�Ȃ̂ł͂Ȃ����e�y��Ƃ��I�[�P�X�g���̋����Ȃǂ������ς�Ɣ��������āA�������̂��̂̒��ɐ����Ă���A����ȑ̌�������̂ł��B�����A����ȂɐS�n�ǂ������i���ɑ����͂����Ȃ��Ƃ����v�����]���������߂Ă��܂��B������́A���̌J��Ԃ��̎��Ԃ͏I���A�Ȃ͎��̋ȖʂɈڂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������Ȃ���A���̉��y�͍�i�Ƃ��Đ��藧���Ȃ��B�����������ꂵ���v�����A���Âňڂ�䂭�ɏ��y�͂̌o�߂̕����ɂЂƂْ̋����������̂ł��B �u���b�N�i�[�̉��y�ɂ����Ē�����������������̂́A�R���[�����̋F��ɚg������悤�ȏ��������[���h���U��ƃR�����g�����悤�ȃA�_�[�W�H�̘Ȃ܂��ł͂���܂���B�����������̂ɐS��h���U���邽��A���ɂ܂�̂͂��̐l�̎��R�ŁA����������������ދ؍����̂��̂ł͂���܂���B�u���b�N�i�[�̍�i�����肽�Ă鋿���̎h���́A��蒊�ۓI�ł���Ɠ����ɒ��ړI�ȁA�܂�͒N�����ԈႢ�Ȃ����ɂ��Ă��Ȃ�������₷���͝R��Ƃ͐܂荇�������ʂ��̂ɐ�̂Ă��Ă��܂������ȃC���[�W�̗͂��痈����̂ƍl���܂��B�u���b�N�i�[�̉��y���҈ꗥ�̃����p�^�[���̑ދ�������~���Ă���̂́A�\�w�ɘI�悵�������̂������⓮���̋Y�ꂪ�A���y���x����ƍl�����Ă���悤�Ȍ`�����������}��I�ȉ^����������ɔg�y������Ƃ����A���y�̌��̐��X�����ɑ��Ȃ�܂���B�����炱���A�u���b�N�i�[���ۂɂ́A�����ȂƂ����`�������ɖ��v���邱�Ƃ̂Ȃ��X�̋����⓮�����A�s�f�̌��݂Ƃ��Ĕ�䍂��邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B�u���b�N�i�[�Ɍ��炸���y���Ƃ����̌��́A�������܂��A���������e�����܂��������\�w�Ƃ��ẴC���[�W���A�S�ʓI�ȕ\�w���ɂ����ĎƂ߁A���y�̌`�������ɂƂ��Ă͐₦���ߏ�Ȃ鉽���̂��A���邢�͐�ΓI�Ȍ����̂��Ƃ����̂Ƃ��āA���̌����Ԃ�ɋ����邱�Ƃł����Ȃ��̂�������܂���B
��P�O�́@�u���b�N�i�[�ƃ��}���e�B�V�Y���H �\��ɔ����āA��P�y�͂ɑ����đ�Q�y�͂ɂ��Ă̋L�q�������Ȃ��Ă��܂��܂����B��Q�y�͂ɂ��Ă͓r���łЂƂ܂����x�݂����邱�Ƃɂ��܂��傤�B�O�X�͂ŁA���Ȃ�Ƀ��}���e�B�V�Y���ɂ��Ă������v���܂������A����ł̓u���b�N�i�[�Ɗ֘A�Â��čl���邱�Ƃ͂ł���̂��Ƃ����^�₪�c�������ƂƎv���܂��B�u���b�N�i�[�ɂ́u���}���e�B�b�N�v�̃j�b�N�l�[�������������Ȃ����邱�Ƃł����A����ŁA�����ł͂��̂��Ƃɂ��Ă����肳���ĉ������B ���}����`�͐l�Ԃ̊���Ƃ������̂��d�v�����܂����B�������A���̊���Ƃ͌X�̊������Ƃ��߂����Ƃ��������퐶���ł̋�̓I����ł͂Ȃ��A���퐶���z���������Ȕ��I����Ƃ������̂ł��B���y�̓����́A���̊���̓����ɏd�Ȃ��Ă���̂ł��B�����āA�Ƃ�킯�����Ƃ����v�f���A���ۂɊ���ƌ��т�������S���Ă���A�Ƃ����̂��O�X�͂ŏq�ׂ����}���e�B�V�Y���̗v�|�ł��B�Ƃ������Ƃ́A�u���b�N�i�[�̃��}���e�B�V�Y���ɂ��čl���悤�Ƃ���ꍇ�A��̓I�ɂ̓u���b�N�i�[�̉��y�̐����ɂ��čl���Ă݂�悢���ƂɂȂ�킯�ł��B�u���b�N�i�[�̐����ɂ��Ă̎��̈�ۂ͑O�͂ŐG��܂����̂ŁA�����ł͊ȒP�ɂ��Ă����܂��B�܂��A�t���[�Y���Z�����ƁB�V���[�x���g�̂悤�Ȃ͂�����Ƃ��������f�B�̂����������邱�Ƃ͂Ȃ��āA�����f�B���̂��̂ɐL�т悤�Ƃ���͂��������Ȃ����ƁB�����āA�P���ł͂Ȃ��āA�F�X�Ȑ����ŕ��S���ꂽ�����̒Z�������f�B���Q��W�܂������ʂƂ��Ĉ�̃����f�B�Ƃ��Ē������Ƃ��\�ł���Ƃ������ƁB����炪��ȓ����ł��B�������A����ł̓u���b�N�i�[�̃����f�B�����ۂɊ���ƌ��т��̂��A�Ƃ������Ƃɂ͋^���悹��������܂���B ���Ă����œ��˂�������܂��A�V���[�}���̃s�A�m�Ȃ������o�����Ƃɂ��܂��B���́A�V���[�}���̃s�A�m�Ȃ̒��Ƀu���b�N�i�[�̃����f�B�Ǝ����悤�ȓ��������o�����Ȃ�����A��������̓����Ƃǂ����Ă����т��Ē����Ă��܂��Ƃ��낪����̂ł��B ���͑S���y���������Ȃ��̂Œ��삩��̑������ɂȂ��Ă��܂��̂ł����A�Ⴆ�V���[�}���̃s�A�m�ȁ��t�����X�P���̒��Ɋy���ɂ͉�����������Ă��邾����ǁA���ۂɂ͉��t����Ȃ�����������̂������ł��i�~�V�F����V���l�[�f����V���[�}�������̃A���A���t���v��
�}�����[
P.�P�P�R�j�B���ꂪ�����̐��Ƃ�����ӏ��ł��B�����ŏ����ꂽ�����́A�s�A�j�X�g�̍���ƉE��Ŗ炳���s�A�m�̉��̌�����ʂ��āA���R�ƒ�����̎��ɗ���Ă���̂ł��B���̗F�l�Ńs�A�m��e���҂������ɂ́A�V���[�}���̃s�A�m�Ȃ͑��̍�ȉƂ̂悤�ɉE�肪�e�i�[�ƂȂ��Ď������e���č��肪���t���߂�̂ł͂Ȃ��A�E��ƍ���̉����������Đ����������Ă���̂ŏ����ł͒e���ɂ����̂������ł��B���̂悤�ɃV���[�}���̃����f�B�͊m���Ŗ��m�ȑ��݂Ƃ��Ēe�����ł͂���܂���B�E��Œe����鉹�ƍ���Œe����鉹�̒��ԂŕY���Ă���̂ł��B�x�[�g�[���F���ł��V���[�x���g�ł��A������͂͂����肵�Ă��܂��B�����̒����������̂Ȃ�A�y����ɓ����ŋL�����ł��傤�B�������A�V���[�}���́A����̔��������ƉE��̏\�Z�������̌����̂����ɁA�����Ǝl����������Ȃ邤�����������Ă��܂��̂ł��B���̂悤�ȁA�݂邩�݂�ʂ����͂����肹���A�ӂ��Y���Ă���悤�ɞB���Ɏ��Ŋ�����Ƃ����̂��V���[�}���̃����f�B�̓����ł��B����͑O�X�͂ōl�����C���݂̍���ƍ������Ă���Ǝv���܂��B����ƉE��̌����̋�ɂ���ẮA���Ԃ�Y�������f�B���S���ϗe���Ă��܂��܂��B�������тɔ����ȕω�����ɔ����̂́A���낢�Ղ��C���Ƃ������̂Ƒ��ʂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����V���[�}���̃s�A�m�Ȃɑ��āA����̓��������ѕt�����ɂ͂����Ȃ��̂͂��̂悤�ȗ��R�ł��B�܂��ɑO�łŏq�ׂ����}����`�̓������̂��̂ł͂Ȃ��ł����B �Ƃ���ŁA�V���[�}���ƃu���b�N�i�[�̃����f�B�́A�͂�����Ƃ��Ă��Ȃ����ƁA�P�Ƃł͂Ȃ��ĕ����̐����̓����̌��ʂƂ��ĕ������Ă��邱�ƁA�ȂNj��ʂ���Ƃ��낪�傫���Ǝv���܂��B�����A����Ƀu���b�N�i�[�Ƀ��}���e�B�V�Y����������Ƃ�����A���̂悤�ȃV���[�}���Ƃ̋��ʓ_���o�R���Ăł��傤���B �������A�u���b�N�i�[�ƃV���[�}���Ƃ͈Ⴂ�܂��B�V���[�}���̃����f�B�͂͂�����Ƃ��Ă��Ȃ��Ȃ�����A��q�̂悤�ɉ��t����Ȃ������Ƃ��Ċy���ɏ�����Ă��܂��B�����ł́A���ۂɋ������ƁA�����̐��Ƃ����y���ɋL���ꂽ�p�Ƃ̐H���Ⴂ�����m�Ɉӎ�����A�����ɍ��x�̌��ʂ��Ӑ}�I�ɑ�����Ă���ƌ����Ă������Ǝv���܂��B�܂�A�C���̂悤�ȕY�������f�B�͈ӎ��I�ɍ�ׂ��ꂽ���̂ƍl�����܂��B�����ł̎��ۂɉ��t����鉹�́A�����̐��̂��߂̈���Ήe�ł����āA�����̂��̂��������Ă��Ȃ��̂ł��B�ł�����A�E��ƍ���Ƃ����s�A�m�̊e�����̉��F�ɂ͓����������߂���킯�ł��B�V���[�}���ɂƂ��Ẳ��y�Ƃ́A�V���p���̂���̂悤�ȃs�A�m�̉����q�ϓI�ɑ��݂��Ă��āA�����ςݏd�˂ĉ��y���\�z�����Ƃ������̉����ł͂Ȃ��̂ł��B��������A�����̊���Ƃ��C���Ƃ��������̂������āA���̈ӎ��̉e�Ƃ��ăs�A�m�̉��ɑ������A�����������̂Ƃ��ĉ��y������ƍl�����܂��B�V���[�}���̃s�A�m�Ȃ̃����f�B�̍\���́A���̂悤�ȃV���[�}���̉��y�̓����Ɍ����������̂��Ǝv���܂��B�ȑO�ɃS�V�b�N���z�̎�ϐ��̂��Ƃ�\���܂������A���z�̑f�ނ̐̋�̓I�ȕ��������H���ɂȂ��Ă����̂��S�V�b�N���z�̎�ϐ����Ƃ���A�s�A�m�Ȃ̃s�A�m�̉��̌��������H���ɂȂ��Ă����_�ɃV���[�}���̉��y�̎�ϐ����w�E�ł���Ǝv���܂��B ����ł́A�u���b�N�i�[�̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B���̓u���b�N�i�[�̋Ȃ̊y���������Ɍ������Ƃ͂���܂���̂ŁA�m���Ȃ��Ƃ͔���܂��A�V���[�}���̏ꍇ�̂悤�ȉ��t����Ȃ������̐��Ƃ����悤�ȉ����͏�����Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�V���[�}���ɔ�ׂău���b�N�i�[�̉��y�̕����e�p�[�g�̓Ɨ����������悤�Ɏv������ł��B�V���[�}���̏ꍇ�A�e�������Ɨ����������Ă��܂��Ɠ����̐������Ă��܂��A�]���ċC���̎傽��V���[�}���l�̐l�i�����Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B�i���̂悤�ȕ���̌X���́A���ɔӔN�̍�i�Ɋ������܂��B���̕������Ȋ�Ȃ����V���[�}���̉��y�̑傫�Ȗ��͂ł͂���܂��B�j�u���b�N�i�[�̌����Ȃ̓V���[�}���̏ꍇ���͂邩�ɃI�[�P�X�g���̊e�y��̉��F�̈��������ʂŁA���ꂼ��̊y��̐F����������Ă���ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�V���[�}���̎��ۂɋ����E��ƍ���̂��ꂼ��̉��͒P�ƂƂ��Ď��o�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł����A�u���b�N�i�[�̏ꍇ�͂ЂƂ̃p�[�g��P�ƂŒ������Ƃ��\�ł��B�O�̂Ƃ���ŁA�u���b�N�i�[�̉��y�̓S�V�b�N���z�ɊK�w���Ƃ����_�Ŏ��Ă���Ƃ��낪����Ȃ���A�e�K�w�̗Z�ʖ��V�ȗ�����������_�ňႤ�ƌ��������Ƃ��A�����ł̃u���b�N�i�[�ƃV���[�}���̃����f�B�\���̈Ⴂ�ɂ�������Ǝv���܂��B ����ƁA�����ЂƂA�V���[�}���̏ꍇ�͓����̐����`�����邽�߂ɁA����ƉE��Ƃ�����̃p�[�g�̌���������ӎ��������͂��炢�Ă���A������ߑ�̌l�̃A�C�f���e�e�B�ɂȂ��炦�邱�Ƃ��\�ł��B�u���b�N�i�[�ɂ́A�V���[�}���̏ꍇ�̂悤�Ȉӎ�������܂���B���������A�s�������������Ȃ̂ł��B�V���[�}���̃����f�B�͓����̐��Ƃ��ĈӐ}���ꂽ���̂ł����A���������_�Ńu���b�N�i�[�̃����f�B�͍ŏ��̈Ӑ}�͈ӎ�����Ă��Ȃ��悤�Ɋ������܂��B���}���e�B�V�Y���̊̐S�̂Ƃ��낪�A�u���b�N�i�[�̃����f�B�ł͋Ȃ̂ł��B�ł́A�u���b�N�i�[�̃����f�B�͖{���ɋȂ̂��Ƃ����ƁA����̓V���[�}���̎��_����̂��ƂŁA�V���[�}���̋ߑ�I�Ȍl�Ƃ����g�ɂ͔[�܂肫��Ȃ��Ӑ}��������̂�����悤�Ɏv���܂��B�Ӑ}��������́A���邢�͍�ȉƌl�̈Ӑ}���z�������́B�i���̋ȁA�l�̈Ӑ}�������̂��A�����͖��Ƃ��_�Ƃ��Ƃł������̂��A����͂ǂ��ł��������Ƃł����B�j�u���b�N�i�[�̉��y�ɂ��鑦���I���i�̌��ʂƂ��āA��ȉƂ̈Ӑ}���č�i���o���オ���Ă��܂����Ƃł������悤�Ȃ��Ƃ͂���Ǝv���܂��B���ꂪ�A�S�̂Ƃ��Č`�����������肵�Ă��Ȃ��Ƃ��A�ו����c�����Ă��܂����Ƃ��Ƃ������ʂɂłĂ���Ǝv���܂��B�������A������̂悤�ȕs���R����s���R���Ƃ��Ē�����̑O�ɒ�o���Ă��܂���݂��ɁA�u���b�N�i�[�̉��y�̃��j�[�N�����������͂��Ȃ��ł��傤���B ���S�ƂȂ��Ȑ������������������f�B�B����́A���y�Ƃ��Ă͍r�����m�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤���B����܂ł́A�ǂ�ȍ�ȉƂ�����Ȃ��̂�z�����ɂ��Ȃ��������Ƃł��傤���A����Ȃ��̂����ɂ������Ƃ��Ȃ������ł��傤�B������������Ȃ��̂Ɉ�т��Ď��܂��Ă����u���b�N�i�[�Ƃ�����ȉƂ́A�Ƒn�I�ȉ��y�ƂƂ�����蓮�����݂���݂��ɓO�������݂Ƃł������邩������܂���B�����炱���A�N���V�b�N���y�̗��j�͈̑�ȍ�ȉƃu���b�N�i�[���Ƃ��ւ�����A����ȉ��y���������ł��܂������Ƃŋ����A�˘f���A�����ēr���ɕ��邵���Ȃ��̂ł��B
��P�P�́@�u���b�N�i�[�Ɖ̕���H ���ۓI�Șb�������Ă��܂��đ�Q�y�͂̑����������Ƃ���ł����A���������h�����ĉ�����悤���肢���܂��B���S�ƂȂ��Ȑ������������������f�B�B�Ȃǂƌ�����Ɖ��̂��Ƃ��Ǝ����������A�Ƃ����������������邩������܂���B�Ⴆ�Α�P�y�͂́g���̈Â��g�̂悤�ȓ����h���v���o���Ă݂ĉ������B�V�Ő\���܂����悤�ɁA���́g���̈Â��g�̂悤�ȓ����h�́A�ጷ�̑O�̂߂�̏z�ƃ��@�C�I�����̑O�֑O�ցc�Ə㏸���镪�U�a���ƌ��ցc�Ɖ��~���镪�U�a���Ƃ��������̂��̂������ɋ����āA���̂悤�ɕ������Ă�����̂Ȃ̂ł��B���Ƃ��ƁA�g���̈Â��g�̂悤�ȓ����h���̂��̂������Ă��������悤�ɒጷ�̏z�⃔�@�C�I�����̕��U�a��������̂ł͂���܂���B ���̂悤�ȃu���b�N�i�[�̐����̓����ɂ��āA�˔�ł͂���܂����吳����̉̕���̖��D���ڎs��i�l�Y�̃G�s�\�[�h���v���o���̂ł��B�i�l�Y�́A����Ƃ������g��Łu���b���v�������ė����Ƃɏo���Ƃ��̂��Ƃł��B����̒��ɖ����̖��D���ڎs��c�\�Y�̏����s��O�������āA�ܒi�ڂ̒��Y���Ƃ߂Ă��܂����B�Ƃ��낪�ǂ������킯�����̒��Y���q�ɂ����Ƃ��Ȃ��B�s��O���͋��ڂ̏����Ƃ͂������̋ߐl����}�ɖ��҂ɂȂ����l�ŁA���܂肤�܂��l�ł͂Ȃ����������ł��B���Y���q�ɎȂ��̂����R�̂��Ƃ�������܂���B���������Y�́u���b���v�̒��̂��������ł��B�S�z�����i�l�Y���ܒi�ڂ����āA�悵�A�����͂��ꂪ�^�s���q����낤�ƌ����������B�����āA�{���ɂ��̗����A����܂ł̑啔���̉��^�̂���Ă����^�s���q��i�l�Y���g��������Ă�邱�ƂɂȂ����̂ł����B���̗����A�����̂悤�ɐ��ʂ̊|�����Y���^�s���q���h���ďo�Ă���B�����܂ł͍���Ƃ����܂���B���Y���������h�����^�s���q�̑̂ɑ��������ē����Ƃ�ƁA�|���ƍ������ӂݏo���Č���������B�����ꂽ�^�s���q�́A�����M��̂Ƃ���܂ł����ē|��Ď��ʂƂ����̂��A���̕���ł��B�Ƃ��낪����܂ł͉��̔��������Ȃ������q�Ȃ��A���Y�������������Ƃ���ɑ�Ɏ��Ƃ������Ƃł��B
���̎��A�q�͒��Y�����Ă���Ǝv���Ȃ�����͒��Y�Ɨ^�s���q�̊W�����Ă����ƍl�����܂��B���Y�͍���Ƃ������ĕς��Ȃ������B�����q�����Y���������Ă����Ȃ�A����Ƃ܂������Ⴄ����������͂�������܂���B�������^�s���q�͍���܂łƂ͑傫���ς��܂����B�����q���^�s���q���������Ă����̂Ȃ�A����Ƃ܂������Ⴄ����������͂��ŁA���������Ȃ�܂����B�����Ŗ��Ȃ̂́A����ɂ�������炸�q�͗^�s���q�ɑ��Ăł͂Ȃ��A���Y�ɑ��Ĕ������������Ƃ������Ƃł��B�q�͒��Y���������Ă���ƈӎ����Ă����̂�������܂��A���͒��Y�Ɨ^�s���q�̊W���邢�͗^�s���q�Ƃ̊W�ɂ�������Y�����Ă����̂ł��B �����ŁA�O���ƒi�l�Y�̂��������Y�Ɨ^�s���q�̊W�ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B�����P�ɓ�l������̏�ɂ��邾���ł͕��̂Ɠ����ŁA�ϋq�����o�Ɋׂ点��悤�ȊW�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�܂��A�ϋq�̑�����ɂ��Ă��A���Y�Ɨ^�s���q�̊W�����Ă����Ƃ����Ă��A���̂ǂ��Ƀ|�C���g������̂����m�łȂ���Ύ����������ɏW�����邱�Ƃ͓���͂��ł��B���]�Ƃ̓n�ӕۂ́w���`�̉^���x�ŁA���̃|�C���g����Y�������������Ƃ���l���w�����킹�ɂȂ�_��������N�����܂��B���A���Y������l����ΎE�l�҂Ɣ�Q�҂��w�����킹�ɂȂ邱�ƂȂǂ��肦�Ȃ����Ƃł��B���A���Y���Ƃ͈Ⴄ�̕���̓����������ɂ���Ɠn�ӂ͌����܂��B�����̓�l�́A�P�ɋq�ȂɌ�������A������̕����ނ��Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��B������A���Y�Ɨ^�s���q�̊W�͓�l�����ԒP���Ȓ����ł͂Ȃ����A�|�C���g�����̒�����ɂ���̂ł͂Ȃ��B ���́A�W�̃|�C���g�́A�����ݏo�������Y�̉E������_�Ƃ��āA�����Ƃ̊ԂɌ���钼���̉������ƁA��͂���Y�Ƃ͋t�̎p���ō����ݏo���Ă���^�s���q�̉E������_�Ƃ��āA�����Ƃ̊ԂɌ���钼���̉������Ƃ����Q�{�̒����̌�_�ɂ������̂ł��B���̓_�_�Ƃ��ē�l�̉E�����̊p�Ƃ���ƁA�����ɂ͎O�p�`���ł���̂ł��B���Y���^�s���q���A�P���ɋq�Ȃɑ��Ă���̂ł��A������ɑ��Ă���̂ł��Ȃ��A���̎O�p�`�̒��_�ɑ��Ă����̂ł��B��l�����C�ŋq�Ȃ⑊��ɔw�����������̂́A���̎O�p�`�̒��_�ɒ����ł��������߂Ȃ̂ł��B���̎O�p�`�̒��_���W�̃|�C���g�ł���A�ϋq�̎����̏W���_�������̂ł��B����܂̂ł̑啔���̉��^�̗^�s���q�́A���Y�������������Ƃ��A���������ɂ͂��Ȃ������B��_�������Ă��܂����ȏ�A�����ɎO�p�`�͌�����͂����Ȃ��B�i�l�Y�̗^�s���q�́A���̎O�p�`���ɂ����Ă݂����킯�ł��B�����āA���̒��_�ɂ͉�������܂��A�ʏ킱�̒��_�ɓ��̂����炷���Ƃ̂ł�����҂͋͂��̗�O�������Ă��܂���B �n�ӂɂ��A���̎O�p�`�͉̕���ŋ��̍\���̊�{�I�Ȃ��̂ŁA�ǂ̎ŋ��ɂ�����̂ł��B�u�O�ԙՁv�ʼn��ɂȂ��������́A���̒��_�ł��镑�䐳�ʂ֗��ĕ������܂��B���̗�͊ϋq�Ȃ̉����̏�ɂ���E�ɑ��čs�Ȃ����ŁA���̘E�͋��Ƌ��̕\���ł���Ɠ����ɐ_�̍~�Ղ���ꏊ���������̂ł��B�ł�����A���̗�͈���~�Ղ���_�ւ̔q��ł���A�_���������̔q��ɉ�����Ƃ���Ȃ�A���̐_�̊፷��������ɍ~���ꏊ�������O�p�`�̒��_�Ƃ������ƂɂȂ�܂��i�܌��M�v�ͤ�|�\�̔�����_���Ƃɏ����܂�ɋ��߂܂���܌��ɂ��Τ�������q����ɏ������߂ɒ�ɂ��炦���q�a������̂��ƂɂȂ邻���ł�����̕���ɂͤ�_��������l�Ə����ꂽ�_�݂̂�����킯�Ť�����ł̕��͎�l���_���������邽�߂̂��̂������킯�ł�������ł̐_�͉����̐_�Ƃ�������̐^�Ɉʒu����̂ł����(�܌��M�v����{�|�\�j�Z�u� �u�k�Њw�p����)�j�B�܂�A�̕���̕���𐬂藧�����Ă��钆�S�����͉��̎��̂������Ȃ��ȓ_�ł���A���������ꂾ���炱���A���̓_�������_�ƂȂ���_�ł�����̂ł��B�����Ă܂��A�̕���͂��̂悤�Ȓ��S�̓_���ł���Ƃ������ƂŁA���̂����l�����S�Ƃ��đ��݂���ߑ㉉���Ƃ͈�����悷��̂ł��B�l��O�ʂɉ����o�����m�t�H�j�b�N�ȋߑ㉉���i���}���h�̉��y���P��̉��̗�ł��郁���f�B���ł���̂Ɗ֘A���Ă���Ǝv���܂��j�ɑ��āA�̕���͒P�Ɍl��\������̂ł͂Ȃ����I�Ȑ��E�S�̂�l�X�Ȋp�x����\�����邱�Ƃ���|���t�H�j�b�N�Ȃ̂��ƌ������Ƃ��ł��܂��i�n�ӕۢ���`�̉^����}�����[ P.�P�Q�`�P�W�j�B ���āA�����ōĂуu���b�N�i�[�̐����ɖ߂�܂��傤�B��q�̒��Y�Ɨ^�s���q�Ƃ�����l�̖��҂́A�u���b�N�i�[�̐�����D�肠���镔���̐����ɗႦ���Ȃ��ł��傤���B���̏͂̍ŏ��ŏq�ׂ���ɖ߂�Ȃ�A�ጷ�̑O�̂߂�̏z�⃔�@�C�I�����̑O�֑O�ցc�Ə㏸���镪�U�a������ցc�Ɖ��~���镪�U�a��������ɓ�����킯�ł��B�����Ă����̊W�̃|�C���g�Ƃ��ċȓ_�Ƃ��āA�����Ă��鎄�̎����œ_�����Ă�悤�ɂ���̂��g���̈Â��g�̂悤�ȓ����h�ł���킯�ł��B�Ƃ����̂́A�O�͂Ő\���܂����悤�ɒP�Ƃł́g���̈Â��g�̂悤�ȓ����h���A���̂Ƃ��Ă̋����������Ă��Ȃ����Ƃł��B�ł�����A���̂悤�ȃu���b�N�i�[�̐����͋ߑ�I�Ȍl�𒆐S�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��āA���������O�̎���̃|���t�H�j�b�N�Ȋ����ɂ��������̂ł���ƌ������Ƃ��ł��܂��B�̕���ł̒��S�̓_�́A�ȋ�Ԃł��邪�䂦�ɐ_�ɒʂ���ꏊ�ɂȂ肦�܂����B�܂��A�S�V�b�N�̑吹���ɑ��ݓ����A�y���ɍ����V��̉��ɂЂ낪�鋐��ȋ�Ԃɋ�������A�����낮���Ƃł��傤�B���̋�Ԃɂ͋�̓I�ȕ����͉�������܂���B�����ɐl�����o���̂́A���̂������Ȃ����̂̈������ɍ~�蒍�����B���Ƃ́A�܂��ɐ_�̌��ł��B�S�V�b�N�̑吹���̓����͋���ȋł��邩�炱���A�_�̌��ŏ[������邱�Ƃ��ł����Ԃł���̂ł��B���̋́����Ȃ���i�p�E����e�B���b�q������̎��w�(�J�����m�Y��) �w�e�B���b�q����W�x��7�������Ёj�Ȃ̂ł��B�����āA�S�V�b�N���z�S�̂̊K�w�\�����A���́����Ȃ���l�����̂ł��B�o�V���J�Ƃ����吹���̗l���͒ʘH���Ӗ����Ă��܂��B�吹���́����Ȃ���ւƌ������ʘH�ƌ������Ƃ��ł���̂ł��B���āA�u���b�N�i�[�̐��������S���������ȍ\���ł��邱�Ƃ̈Ӗ����A�����ǂ������Ă���̂��A���Ƃł����肢�����������ƂƎv���܂��B�u���b�N�i�[�̉��y���A�_�Ƃ������̂ɘA�Ȃ��Ă���Ƃ���A���ɂ́A���̂悤�ȓ_�ȊO�ɂ͍l�����܂���B�u���b�N�i�[�̐����̋��́A�S�V�b�N�̑吹���Ɠ��l�ɊK�w�\���Ɛ[����������Ă���ƍl�����܂��B�������A���Ƃ��Ă̓u���b�N�i�[�̐����̋��͐_�ɒʂ��Ă���Ƃ͎v���Ă��܂���B�i����ɂ��Ă͌�ŏڂ������b���v���܂��B�j���āA�u���b�N�i�[�̌����ȑ�R�Ԃ������߂Ă����ƁA����ɋ������ƂɂȂ�܂��B����ɂ��ẮA���̒�����蓹���I���A�悤�₭�����ɖ߂邱�ƂŖ��炩�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B ���̕�������Â��|�\�ɔ\������܂��B�\�ɂ̓V�e�ƃ��L�A��l���ł���V�e�ƁA��������Ă��郏�L�ƌĂ���������܂��B���ʁA�\�ł͂��̃��L���ŏ��ɏo�Ă��āA���ꂩ��V�e���o�Ă��ď����ⓚ�������āA���Ƃ̓��L�͂��������W�b�ƃV�e�̂��邱�Ƃ����Ă��邾���̂悤�ɂ��Ă��邱�Ƃ������ł��B����ɂ��āu�ށi���L�j�͎����������l�ɑ�\�Ƃ��āi����Ɂj�o�Ă���̂ł���B�i���L��Y��\�����Ɣ���� ��g���X�j�v�Ƃ��Č����l�̑�\�Ƃ����l��������܂����A�͂����Ă����ł��傤���B�؉�����ɂ��A�V�e�͑����̏ꍇ�����Ɛ̂̂��Ƃ����`�Ō��܂��B����́A���S�N�Ƃ������Ԃ���u�ɋÏk�����悤�ȕs�v�c�Ȍ`�ŏ�O����邱�Ƃł��B���̂��Ƃ͌����i�q�ȁj�ɂ����X�ɂƂ��Ă͒��ڂɃ��A���Ȃ��Ƃł͂���܂���B�Ƃ��낪�����Ō��Ă��郏�L�ɂƂ��ẮA����͂܂��Ƀ��A���Ȃ̂ł��B�����v���Ă��郏�L�ƁA���ꂩ��V�e�Ƃ������ɂ����X�͂Ђ�����߂Č��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂�A���ܕ���ōs�Ȃ��Ă��邱�ƁA�V�e�̕��A����͌����ɂ����X�ɂ͂����ɂ����I�Ȃ��ƂȂ̂�����ǁA���������̔����A���ɏ����ɋÏk���ꂽ��̏�O�Ƃ������̂����A�����Ǝv���Č��Ă��郏�L�A�ނ��������̉�X�͌��Ă���킯�ł��B�����ŏ��߂āA�V�e�̂���Ă��邱�Ƃ����s�v�c�Ȑ^���Ƃ��Č����̉�X�𝓂��Ă���̂ł��i�؉�����I�Ƃͣ ��g�V���j�B���̂悤�ȃ��L�Ƃ�������Ă���ϋq�̍\���́A�̕���̏ꍇ�ɍ������Ă��܂��B����ɓn�ӕۂɂ��A��l�̔\���҂ł���V�e�������Ȃ���A�������̖��̂���ӂ�w���Ă����Ǝv���Ǝ��ɂ͎������O�҂Ƃ��Č��A�����S�̂̌���ƂȂ�A���̂�����ɂ��v�����Ă��܂��Ď��Ȃ�r���Ƃ������Ƃ��Ȃ��i�n�ӕۑO�f���j�B����́A�܂��ɉ̕���ƃu���b�N�i�[�ɋ��ʂ���\���ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A�������ł��傤���B
��P�Q�́@��Q�y�́i�Q�j �ł́A�u���b�N�i�[���Ă��鎄�́A�ǂ̂悤�ɂ��ċ����̍s����H�蓾��̂ł��傤���B����ɂ́A��͂�Ȏ�����Ɍ����Ď��܂������Ȃ���Ȃ�܂���B�Ȑ����A����́����Ȃ���Ƃ��Đ_�̒��z�I�ȉF���ɂȂ���ʘH�ł���܂����B���������g�̐l�ԂɂƂ��āA����Ȓ��z�Ǝl�Z�������������Ă��邱�Ƃ͂ł��܂���B����Ȏ��ł���͂��̐����͂ǂ�Ȃ��ƂɂȂ�̂��B�����������ϓ_���炱�̋ȑS�̂ɒ��ӂ������Ă����ƁA���̎��������Ă���̂́A���̑�Q�y�͂̒��Ń��@�C�I�����̍��݂ɂ̂��Ē������̌������̒��������f�B��P��̐����Œe�����Ă��܂��Ƃ���Ȃ̂ł��B[3:45�`4:25]���̎����ɁA���͐S�̒ꂩ��������Ǝv���܂��B������������Ȃ��Ƃ������Ă����̂��낤���A�ƁB�������A���̃����f�B�́A����܂őS�������Ȃ������悭�̂������f�B�ł�����܂��B���Ԃ̓u���b�N�i�[�ɂƂ��Đq��Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł��B�Ƃ肽�ĂĔ������Ƃ��v���Ȃ����̃����f�B���P��̐����Ŕ����o���̂܂n�܂鎞�A�������͂��̖��}��I�Ȕ��͈����͐��X�����Ɉ��|����A�v�킸�����̂܂��ɂ͂����Ȃ��Ȃ�܂��B���S�ƂȂ�������Ȃ��ꍇ�i���̋Ȃł����A���ꂪ�q��Ȃ킯�ł��j���͉��̓����⋿���S�ĂɌ������Ď��܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A��U���ꂪ�o�����Ă��܂��₢�Ȃ�����̐[���Ɏ����ǂ����ƂƂȂ�̂ł��B�X�Ɍ����Ȃ�A�u���b�N�i�[�̑�V�ԈȌ�̌����Ȃ̐����ɂ́A���̂悤�ȏu�Ԃ����X����A�����Ƃ������̂̈Ӗ���ώ������Ă��܂��Ƃ����������ɉՍ��ȑ̌���������̂ł��B���̈Ӗ��Ńu���b�N�i�[�̌���Ƃ́A����ׂ����̂�r��������ŁA���̔r�����̂��̂�r�����Ă��܂����Ƃ����_�ŁA���̉��y�Ƃ͐�ΓI�Ɋu�����Ă�����̂Ȃ̂ł��B �������Ƃɑ����āA�X�ɒ��������߂Ă����ƁA�ȑz�̏����ȃM���b�v�̌�ɍ��x�́u�u���b�N�i�[�炵���v�i����܂Ő\���ďグ�Ă����Ӗ��ɂ����ł��j�������҂��Ă��܂��B�����Œ����Ă��鎄�́A�����h���̌�Ńz�b�Ƌ����Ȃł��낷���Ƃ��ł��܂��傤�B�������A���̂悤�ȋ����̌�ł��B���S���Ă��Ă����̂ł��傤���B�����≽������̂ł͂Ȃ����A������b��ɂ��������҂��Ȃ��킯�ł͂���܂���B�u���b�N�i�[�̉��y�Ƃ́A���̂悤�ɒ����҂ɁA�s�f�ْ̋����������ɂ͂����Ȃ��̂ł��B �g�Â��N���X�}�X�̉̂ɗR������h�g�_��I�h�Ɖ�����i���ȉƕʖ��ȉ�����C�u�����[�T�u���b�N�i�[����y�V�F�Ёj�ɂ�����������y���ɂ���Ď㉹�Ś����悤�Ɏn�܂�܂��B�܂��A���@�C�I�����ɂ���ĂQ�̉������s�ɖ�܂��B�ꔏ�[���āA����ɉ�����悤�ɏ㉺�̓����̏��Ȃ���߂���܂��B�����āA�ׂ����������O�̈�A�̉������ݍ��ނ悤�ɑ����Ƃ����A����܂Œ����Ă����u���b�N�i�[�p�^�[���Ƃł��\�������قǃ����p�^�[���̐����̂���ł��B[5:10�`6:10]���́A���y�̒m�����Ȃ̂ŁA���̐����̌��̂́g�Â��N���X�}�X�̉́h��m��܂���B�i�����Ƃ��A���y����Œm���ȂǂƂ������͎̂ז��ȊO�̉����ł��Ȃ��Ƃ����̂����̃X�^���X�ł͂���̂ł����j����ɂ��Ă��A���̐����͑�Q�y�͖`���̐�������A�Ƃ������Ƃ͂��̌����Ȗ`���̓��@����h���������̂̂悤�ɕ������Ă��Ȃ��ł��傤���B���̐�������N���X�}�X��A�z����悤�Ȃ��Ƃ��A���ɂ͂ł��܂���B����Ɍ����Ȃ�A�G���A�t�E�C���o���w���̃t�����N�t���g�����̂b�c�ŕ������悤�ȃ��@�[�O�i�[�̊y������̈��p�ɂ��Ă��A��q�̃u���b�N�i�[�p�^�[���ɑ����������ŁA���X�̃��@�[�O�i�[�̊y���̒��ł̈ʒu�Ƃ��Ӗ������ȂǂƂ͐藣����Đ����̃p�^�[���݂̂����ӓI�Ɉ��p����Ă���B�܂�A�Â��N���X�}�X�̉̂ɂ��냔�@�[�O�i�[�̊y������ɂ���A���X�̈Ӗ�����̂���ċ����Ƀu���b�N�i�[�E�p�^�[���ɓ��ěƂ߂��Ă���̂ł��B�����u���b�N�i�[���h������l�̌�����ދ��Ƃ������p�^�[���Ƃ������t���k��Ă���̂��܂��B����͎��ɂ́A�i���m�̃N���V�b�N�j���y�Ƃ������̂��̂��̂ɗR�����Ă��邱�Ƃ̂悤�Ɏv���̂ł��B�����̖}�f�ȉ��y�Ƃ��������̑ދ����⋭������B���ɂ�肷���������ʼn��y�����肠���Ă���Ƃ��A��l�u���b�N�i�[�͊����Ă��̑ދ����⋭�������֒����Ă݂����ƍl���Ă��܂��B �Â��N���X�}�X�̉̂ɂ��냔�@�[�O�i�[�̊y������ɂ�����p����̂Ȃ�A�����Ɣ����������͑�R���邾�낤�ɁA�����Ɖ̂����������āA���Y�~�J���Ȑ��������āA���I�Ȑ��������Ă��邶��Ȃ��ł����B�������E�}�[�[����������悤�Ɂi����قlj���ł����ǂ��Ȃ��Ă��j�w�֎l����̊nj��y�������q�����킹�Č�����i�ɂ��炦�邱�Ƃ����Ăł����ł��傤�ɁB�����A�u���b�N�i�[�́A���ꂪ����������̌`���I�K�R���Ƃ����������ɁA�����܂ł̐������u���b�N�i�[�p�^�[���ʼn������Ă��܂��܂��B���ꂪ�`���I�ȕK�R�ł���̂Ȃ�A�܂�Ō`�����̂��̂��ދ��ł��苭���Ȃ̂��Ƃ����l�����Ȃ����̂悤�ɁB�ɂ�������炸�u���b�N�i�[�p�^�[���̃S���������`���I�K�R���Ƃ����Ȃ�A����ɂ́A�Â��̂⃔�@�[�O�i�[�̒����Ƃَ͈��̗v�������ƂȂ��Ă���͂��ł��B�u���b�N�i�[�p�^�[�����Â��̂⃔�@�[�O�i�[�̈Ӗ�����̂��Ă��܂����Ƃ��Ă��A���}����`�f�`�̂Ƃ���Ō����悤�Ƀu���b�N�i�[�̉��y�ɂ��H���ł͂��邯��LjӖ��I�v�f�͂��邱�Ƃ͂���܂��B���y�Ƃ������̂́A�����̉��𒊏ۉ������y���ɂ���č\������A�����ɂ͑��݂����Ȃ����ۓI�ȑ��ݎ҂ł��邱�Ƃ͊m���ł͂���܂��B�������A����������ɒ����̂͐��g�̐l�Ԃł��鎄�ł��B�����A�����ɂ�����x�̈Ӗ���t�^���Ȃ���A��������l������̂Ƃ��Đg�߂Ɋ����邱�Ƃ͕s�\�ł��B�u���b�N�i�[�Ƃė�O�ł͂���܂���B�������A���̈Ӗ��������̉��̋�������Ă�������킵���Ȃ����y�̏ꍇ�A��Ȃ̍�i�ɂ͂��̈Ӗ��̍\���ɓ��������肳��������肷������鍡��̍\�������݂��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B����́A���̋����̈Ӗ��I�ȘA�����āA�Ӗ��̐��ڂƂَ͈��̗̈�Ō�������ו��̕\��Ƃ����Ă������̂ł���͂��ł��B����̓u���b�N�i�[�ɂƂǂ܂炸�����鉹�y�Ƃ��A�����Ŏv���莩��̑z���͂��J�������ł���킯�ł����A�u���b�N�i�[�̏ꍇ�A�ދ��ȃ����p�^�[���Ƃ��������}�����ꂽ�Ӗ��I�ȍ\���Ƃ͑ΏƓI�ɁA���̍ו��ɂ����Ă͔J���ŋ��\�Ȃ܂łɎ��Ȃ��咣���A�S�Ȃ̋ύt��������˂Ȃ����Ƃ�������Ƃ����܂��B ���b�V���O�������u���I�R�[���v�̒��Ō����Ĉȗ��A���y�͎��Ԍ|�p�ł���iG.E.���b�V���O����I�R�I��-�G��ƕ��w�Ƃ̌��E�ɂ��ģ(�֓��h����)��g���Ɂ@���m�Ɍ����Τ���b�V���O�͒���̒��łͤ���y�ɂ͐G��Ă͂��Ȃ���ނ͌|�p���ۂ𒁏��Â��Ă��鎞�ԂƋ�Ԃ̌����𒊏o���邱�Ƃɂ���Ģ���Ԍ|�p��Ƣ��Ԍ|�p��̈Ⴂ�������炩�ɂ�������y�ͤ���w�≉�����ƂƂ��ɤ���Ԃ̑��̂��ƂɎ���������Ԃ̒��œW�J���邱�Ƃ��碎��Ԍ|�p��ɕ��ނ���顁j�Ƃ����Ό����܂��B�ߋ����ݖ����ƈ꒼���̎��Ԃ̗���ɉ����āA���̉��̌�ɂ��̉����A���̃t���[�Y�̌�ɂ��̃t���[�Y����������ɉ��y�Ƃ͑S�Ă��Ԍ��Ȃ��g�D���Ȃ����i�͐��藧�����܂���B�������A�ǂ�ȉ���I�����ǂ�ȃt���[�Y��r�����邩�ɂ��Ă͍�ȉƂ����㌠�������Ă���킯�ŁA���̌���ɂ����Ď��R�����Ă���Ƃ͌�������킯�ł��B�������Ȃ���A���̎��R�́A�n�܂�̏u�Ԃ���I���܂ł̂��ׂĂ̏u�Ԃ��ߏ���������Ȃ��p�N�I�ɔz�đg�D���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�������Ɋr�ׂ�Α��ΓI�ł������肦�܂���B���y�Ƃ������̂ɂ͎��Ԃ����Ƃ��������I�Ȓ����Ƃ������̂����R�Ƒ��݂��Ă���A�u���b�N�i�[�Ƃ����ǂ����ꂩ��͂�����������E���Ă��Ȃ��͂��ŁA�u���b�N�i�[�p�^�[���̐��������̒����ɂ��������Ĕz�ꂽ��A�̉��̋�������Ȃ��Ă���A�܂��t�ɂ��̐����������ɂ��������Ă���ƍl�����܂��B�������Ȃ���A�u���b�N�i�[�̉��y�ɂ����ẮA�ЂƂ̏u�Ԃɐ��肱�܂ꂽ���̏��͂��܂��ĕ����ł����āA���̎��Ԃɂ킽���Čp�����Ă���Ƃ����_����A�����I�Ȓ����ւƑf���ɊҌ������̂����ނƂ������Ƃ�����܂��B�Ⴆ�A�����ł́g�Â��N���X�}�X�̉́h����̐����B���@�C�I�����ɏ㉺�̓��������Ȃ��A���̕��ጷ����������ď㉺�ɓ����̂ŁA�����̃e�i�[�������Ȃ��܂ܓ]�������悤�ȁA�����Ȃ��낢�̈�ۂ��܂��B�i�}�[���[�̌����Ȃł̓R���g���o�X�Ȃǂ̒ጷ�����Ɨ����Đ�����S�����Ƃ�����܂����u���b�N�i�[�̉��y�̓}�[���[�Ƃ͈�����Ӗ������łł����A�ጷ�����ቹ���œy����x����ȏ�̓Ǝ�������������Ă���̂��A���������ӏ��Ŕ���܂��B�j�g�Â��N���X�}�X�̉́h����̐����Œ������Ƃ̂ł���̂́A�g�_��I�h�Ȑ����ł��邱�ƂɂƂǂ܂炸�A�����Ȃ��e�i�[���̃��@�C�I�����ł���A�ቹ���x����ȏ�ɓƗ��̐������������Â���ጷ���̓����ł�����̂ł��B���́A�����ɁA�����I�Ȓ�������ł������u���b�N�i�[�̎��R�����I�o���Ă���Ǝv���̂ł��B������������ܖ��ӎ��̒��������Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A�����ɂ�������ӎ��̂�����m���̔��ȓI�ȓ���������������ꂽ�ߌ�������������ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�ߏ肳�䂦��E�����ו��́A�����I�����̘A�����A����ɂ͈�̍�i�Ƃ������E���č��ׂȗގ�����ĕʂ̍ו��Ƌ����������B�g�Â��N���X�}�X�̉́h����ጷ���̓��������Ƃ��ł���A��P�y�͖`���́g�Â��g�̂悤�ȓ����h�����镪�U�a���̌�����̃��@�C�I�����̓����Ɛe�����A�q�������Ă���̂ɗ����������Ƃ��ł���킯�ł��B����ɁA��������Ⴆ�Α�T�����ȑ�Q�y�͂̒��قǂ̕��U�a���ɐe�������𓊂������Ă���̂ɂ��������Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�����āA���̎����̓u���b�N�i�[�̂ЂƂ̍�i�̐������A�P�Ɂg�Â��N���X�}�X�̉́h�ɂƂǂ܂炸�A�ጷ���̓����Ƃ����\�ʓI�ȉ��̓����łł����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ�����̂ł��B��R�����Ȃł́g�Â��N���X�}�X�̉́h�̒ጷ���̓������A��T�����ȑ�Q�y�͂̒��قǂł͕��U�a���Ɛe�����������邱�ƂɂȂ�B�܂�A���ꂼ��̍�i�ł͒f�Ђł��������̂��A���˂ɘA�т������̂ł��B�������������ƘA�т��\�ɂ���W���A�X�̍�i���Ē���߂��炳��Ă���ו��̖ԏ�g�D���������Â���A������^���Ă���̂ł��B���ꂪ�����I�Ȓ����ƋY��邱�ƂŒ����҂Ɏh����^����̂ł��B����Ƀu���b�N�i�[�ɂ����ē����I�Ȃ̂́A�ގ��ɂ���ĘA�q�������ו����z���͂̓�������Č�����悤�Ȑ��ݓI�ȑ��݂ł͂Ȃ��A�����܂ł����݂ł����Ă��ꂪ�����̕\�w�ŋY�ꂠ�����ƂȂ̂ł��B���̂悤�ȉ^���A���ꂱ�����u���b�N�i�[�����Ƃɂ�������I�ȑ̌��Ƃ͍l�����Ȃ��ł��傤���B
��P�R�́@�u���b�N�i�[�ƃu���[���X ���Ƃ����l�Ԃ��u���b�N�i�[�̉��y���ǂ̂悤�ɒ����Ă��邩����̓I�ɂ��b���Ă�������ł����A�����Ńu���b�N�i�[�̓����Ɛ\���܂��Ă����ǂ͎��̌l�I�Ȋ����̂��̂Ȃ̂ŁA���̍�ȉƂƔ�r���邱�ƂŁA���u���b�N�i�[�̓����������яオ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ��ɂ����ł́A�I�[�P�X�g���̒��ቹ���������邱�Ƃŏd�ʊ����鋿��������_��A�����̓������a���̕��������t���_�A�\�i�^�`�����̉��y�̂������ŃK�b�`���g�����肻�̒��ʼn��������I�ɓ������Ă������Ƃʼn��y������_�ȂǂŃu���b�N�i�[�Ƌ��ʓ_�̑����u���[���X�Ɣ�r���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B �u���[���X�ӔN�̃s�A�m���i���u�ԑt�ȏW�v�Ƃ����^�C�g���̂��ƂɃO�����E�O�[���h�����t�������R�[�h�i�O������O�[���h��u���[���X�ԑt�ȏW��j������܂��B���̒��́A�Ⴆ�Εσz�����̂n���P�P�V�|�P�Ƃ�����i�͉E��ŃX�R�b�g�����h���w�������킹��f�p�ȃ����f�B��W�X�ƒe���A����Řa���̔��t������Ƃ����A�S�̂Ƃ��Ă�������Ƃ����O���`���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�A�����ĒP���Ȃ��̂ł��B������O�[���h�͍���̘a�����t������Ƃ��A�a�����\�����鉹���������炵�Ēe���܂��B���U�a���Ƃ������ł͂Ȃ��̂ł����A����ɂ���āA����̉����r��Ȃ��A�����Ă���悤�ɕ������Ă��܂��B���ꂾ���ł͂Ȃ��A�P���ɘa����e���Ă����Ƃ��́A�^�[���@�^�[���Ɖ��ɋK���I�Ȍ��Ԃ��ł��Ă��āA���ꂪ���Y�������ނ悤�ɍ�i�S�̂𒁏��t���Ă����̂ɋC�Â�����܂��B����́A�����ĕ�߂ċC���t���̂̂��̂ŁA�ŋ߃����[�X���ꂽ���@�����E�A�t�@�i�V�G�t�̉��t�i���@�����[��A�t�@�i�V�G�t��u���[���X����s�A�m��i�W�
[COCO-75090]�j�Ȃǂł͌����ɕ���������̂ł��B������O�[���h�͏������炵�Ēe�����ƂŁA���̋K���I�ȃ��Y��������Ă��܂��܂��B����Ƃǂ��ł��傤�B��i�S�̂̈�ۂ��A�܂�ō��ɂ����Ă��܂������ȁA�͂��Ȃ��Ȃ��̂ɕϖe���Ă��܂��̂ł��B�����āA�a�������炵�C���ɒe�����ƂŁA����܂Řa���̋����̒��ɉB��Ă����A���̈��̉���������ɂ�āA�x�d�Ȃ�]���Ȃǂ̍ۂɁA�������Ɏv�������Ȃ����������f�B����������Ă���̂ł��B���̂悤�ȁA���m�̃����f�B�̔����͑f���炵���̌��Ȃ̂ł����A���ꂾ����A���̉��t�������Ƃ����̂ł͂���܂���B�u���[���X�Ƃ������i�Ȃقǂ�������Ƃ����\���ō�Ȃ����l�̔ӔN�̌`�������Ō���ɂȂ��Ă���悤�ȍ�i���A���͂�����Ƃ̂��Ƃŕ��Ă��܂������Ȋ낤���������Ă������ƁA�܂������`�����̗��ɂ͋����قǖL���ȃ����f�B���B����Ă������ƁA���ꂪ�`��������邱�Ƃň�C�ɉԊJ�������ƁA�����������̏��i�ɃX�g�C�b�N�Ȍ`���ƖL���ȃ����f�B�Ƃ̂���قǂ܂ł̋����ْ������������Ƃ��A���̉��t���܂��܂��ƌ����t���Ă��ꂽ���Ƃł��B �u���[���X�̉��y�̖��͓I�ȕ����́A�����Ă��鎄�ɂ́A��ɉB����Ă�����̂ł��B���}���e�B�V�Y���̐��v�ł�����S��\�킵�������́A�u���[���X�̉��y�ł́A�����炳�܂ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�������̏[�����������������̂Ȃ��ɁA����͖�����Ă��܂��B������A��d���̋��������������킯�Ȃ���T���Ă����A���ꂪ�u���[���X�̉��y����햡�ł��B ���������������[�����Ă��邱�ƂŐڒ��܂̂悤�ɋ@�\���āA�e�i�[�̍������ƃo�X�őS�̂��x����ቹ������̂ƂȂ�A�S�̂��ЂƂ̉�̂悤�ɕ������Ă���B�u���[���X�̉��y�Ɋ�������d�����Ƃ��a���Ƃ��������̂́A�����������Â��肩�琶�܂����̂ƍl�����܂��B���G�̋���p���b�g�̏�ō����Ă����ƍŏI�I�ɂ͏a���d�X�����O���[�ɂȂ�܂��B�l�X�ȊG�̋��l�X�ɍ����邱�Ƃɂ���āA���̂悤�ȃO���[�ɗl�X�ȃj���A���X��^���A������g�������Ĕ����Ȍ��Ɖe�̃j���A���X��\��������ƂɃ����u�����g�����܂��B�ނ̑�\��u��x�v�͖�̈łƖ�x�̐l�X�̎�������̐D�萬�������ȉA�e���`����Ă��܂��B�����ł̖�̈ł�\�����Ă��鍕��O���[�̐F���A��ʂ̏�ň�l�ł͂Ȃ��̂ł��B��ʏ�̏ꏊ�ɂ���ĐF�������قȂ��Ă���̂��킩��̂ł��B�����G�̋�̍�������S���Ⴄ�̂ł��傤�B����O���[�Ƃ��ĕ\�ʂɂ�����Ă���F�̔w��ɗl�X�ȐF���l�X�ɉB����Ă���B�ꌩ����ƁA��ʂɍ���O���[���h���Ă���n���ňÂ���i�̂悤�ł����A���̔w��ɂ͋����قǃo���G�e�B�ɕx���E���B����Ă���B�C���t���Ă݂�A���̋��߂ǂ��s�����ʖL�����̗��ɂȂ��Ă��܂��Ă���B���ꂪ�����u�����g�̖��͂ł��B���ԐF�ɏI�n����悤�ȃu���[���X�̃I�[�P�X�g���C�V�����ɂ́A�����u�����g�̐F�ʂ̂悤�ȉB���ꂽ�L����������܂��B���ꂪ�A�Ⴆ�O�����E�O�[���h�̉��t�̂悤�ɂ͂��炸���I�悳�ꂽ���A���܂�̖L�����Ɍ˘f���̂ł��B ���̂悤�Ƀu���[���X�̉��y�́A�������ꂽ���́��Ɓ��B���ꂽ���́��̓�ɍ\���ɂȂ��Ă��āA���͌�҂ɂ���܂��B��ł��\���܂����悤�ɁA�����T�����߂邱�Ƃ��u���[���X�̉��y���A�ЂƂ̑�햡�ƌ������Ƃ��ł��܂��B����ɑ��āA�u���b�N�i�[�̉��y�ɂ́��B���ꂽ���́������݂��܂���B�ǂ��܂ł��������炩��Ƃ��āA���ׂĂ͕\�w�ɘI��ɂȂ��Ă���̂ł��B�A���A���̂��ׂĂ����ۂ��͒����҂ɔC����Ă���̂ł��B���̈Ӗ��Ńu���[���X�ȂǂɊr�ׂ�A������ɂƂ��Ă͂Ȃ�Ǝc���ȉ��y�Ȃ̂ł��傤���B
��P�S�́@��R�y�́i�P�j ����܂ŁA�ו��ɍS�D������A��蓹��������ő啪���������Ă��܂��Ă���܂��B���̑�R�y�͂ŁA�S�̂̔�����ʉ߂������ƂɂȂ�܂��B�������A�u���b�N�i�[�̂��̌����Ȃ͑O���Ɋr�ׂČ㔼�͐K���ڂ݂̂悤�ɒZ���Ȃ��Ă���̂ŁA���̋L�����\��̂V���ʉ߂Ƃ��������ł��B���������ł̂ŁA���t�������肢�܂��B ���@�C�I�����̏z���郂�`�[�t�̌J��Ԃ��ŁA��R�y�͂͊J�n����܂��B����͑�P�y�͖`���́g�Â��g�̂悤�ȓ����h�̒ጷ�̑O�̂߂�̏㏸���K�ɂ悭���Ă��āA���҂̂Ȃ�����҂ɑz�킹�܂��B��P�y�͂ł́A���̏㏸���K�ɏ������킳��悤�Ƀ��@�C�I�����̉��~���K���~��āA�o���̓��������ݍ����܂��B���āA���̑�R�y�͂ł͏������̉��~���K�̑���ɁA�ጷ�̃s�`�J�[�g���Ή����Ă��܂��B�܂����@�C�I���������`�[�t���P������������Ȃ��₢�|���̂悤�Ȃ������Œe���ƁA���@�C�I�����̋x�~�ɍ������ނ悤�ɒጷ�̃s�`�J�[�g������ɉ������܂��B����������P��B�A���A���̂Q��ڂ̓��@�C�I�����͓����悤�ɖ₢�|����̂ł����A������s�`�J�[�g�͂ق�̏��������g�[���������Ȃ�܂��B���̌�R��ڂɎ����ă��@�C�I�����̓��`�[�t�̌�����グ�ċx�~���邱�ƂȂ����`�[�t���z�����܂��B�Ή����邩�̂悤�Ƀs�`�J�[�g���ǂ��|����悤�ɉ����̃��`�[�t���z������B�����ă��@�C�I�����̃��`�[�t�����y��̊e�p�[�g���n��������悤�ɏd�Ȃ�Ȃ���A�N���b�V�F���h���Ă����ď����ȃN���C�}�b�N�X�ɒB���܂��B�����ł́A�O�������y���ɂ���ă��@�C�I�����̏z���`�[�t�����̂悤�ɋ����ʼn��t�����ƁA�㔼�ł͋��Ǖ����Ή�����s�`�J�[�g�̃��`�[�t�����݂܂��B[0:00�`0:50]��P�y�͂́g�Â��g�̂悤�ȓ����h�ł́A���U�a���̏㏸���K�ɑ��ĉ��~���K�A�O���ɑ��Č㔏�A�Ƃ����悤�ɑΔ�I�ȗv�f������Ă��܂����B���̑�R�y�͂ł́A���@�C�I�����̏z���`�[�t�����i�͂������đO�ցc�ƍs�����Ƃ���X��������A�ጷ�̃s�`�J�[�g�͂��̓����������~�߂悤�Ƃ���悤�ȐÎ~����X���������āA���҂̕��������I�ȓ��������������܂��B�܂�A�����ł��B�ŏ��̂Ƃ���̓��@�C�I�����̃��`�[�t�������t���[�Y�ŁA���ꂪ�O�֍s�����Ƃ��闬�������܂��B�������A�x�~�ƂƂ��ɒጷ�̃s�`�J�[�g�����̗���������~�߂�B�����P��B����ǂ͗���̐����������Ȃ����̂��s�`�J�[�g�̃g�[�����������������Ȃ�܂��B�����Ă��鎄�́A���@�C�I�����̕ω��ɂ͋C���t���܂���ł������A�s�`�J�[�g�̃g�[�����������������Ȃ����̂Ń��@�C�I�����̕ω����������̂�������Ȃ��Ɖ�z���Ă��܂��̂ł����B�i���̂悤�ɌJ��Ԃ��ɒ��ڂ��Ă݂�ƁA�������Ƃ��ɐ�ɌJ��Ԃ��Ȃ���ȉƂ����āA�u���b�N�i�[���V���p����[�c�@���g�ȂǂƋ��ɂ��̒��Ԃɓ���Ǝ��͎v���܂��B�j�����ĂR��ځB���@�C�I�����̃��`�[�t���z���͂��߂�Ɨ���͎~�܂邱�ƂȂ������Â��͂��߂܂��B�Î~����X���̃s�`�J�[�g�͐����Â��������ǂ��|�������~�߂悤�Ɖ��x���J��Ԃ��܂��B�����āA�����ł̖z���̂悤�ȉ��̍^���A�����ł̏z���`�[�t�����̂悤�ɒ���܂��B����́A���x�������~�߂��邱�ƂŁA�s�`�J�[�g�Ƃ������ɐ��������߂��܂��B���̉���j��A�����������ė�����ĊJ���܂��B�����P�ɑO�i�ނ����Ȃ�X�D�[�b�Ɨ���Ă����Ă��܂��̂��A��U�������Ƃǂ߂邱�ƂŃO�b�Ɛ��������߂āA�Ïk������������C�ɕ��o���邱�ƂŃJ�^���V�X�ݏo���B�����炭�����ŁA�u���b�N�i�[���l�́A���̓������Ƃ߂邱�Ƃ̂����ɉ��y�̉^�������ݏo�����Ƃ����t���ɋC�t�����ɂ͂����Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��āA�u���b�N�i�[�̌����Ȃɂ́A�I�[�P�X�g���̑S�y�킪�����~�߂Ă��܂��Ƃ����u�Ԃ��m���ɑ��݂��Ă���킯�ł��B�����܂ł��Ȃ��A����̓u���b�N�i�[�x�~�̂��Ƃł��B���̏u�ԁA���y�̉��t�Ƃ������Ƃɂ��č�ȉƂ����������ɉ�����Ă������ׂĂ��A�ꋓ�ɋ�����Ă��܂��Ă��邱�ƂŁA��������r�����Ȃ����h������̂ł��B�Ɠ����ɁA�Ⴆ�Ή��t���ŃI�[�P�X�g���������o���̂���߂Ă��܂������A�q�Ȃɂ��鎄�͕����Ɏ������g�Ɠ������̂�F�߂��ɂ͂���ꂸ�A���̂��Ƃɂ���Ďv�킸�l�R�Ƃ���ق��͂Ȃ��̂ł��B���܂܂��ɉ��t��Ƃ���������L�����鎩���́A����̏�Ŋy����O���I�[�P�X�g���Ɠ����p���ň֎q�ɍ����āA�����悤�Ɏ��特���邱�Ƃ�������A�Î�̂Ȃ��Œ��o���W�����Ă���킯�ł��B���y���Ƃ́A���x�~�̂Ƃ��̂悤�Ɏ���͉�����Ƃ����������~�߂��܂܁A�W�����Ē�������Ƃ����p���̏�ɐ�������̌��̂��Ƃł��B������A�X�I�ȕ��ނł����A�����鑤����鑤�����̏u�ԑS�������ɋ��L���Ă��܂��B�܂�ł��݂��̋��E����蕥���Ă��܂��悤�Ȍo���ł��B�����v���ƁA���͂����ʼn��y�̉��t���̂��̂̌��E�ɐG��Ă��܂������̂悤�ɋْ�����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�������A���y���Ƃ����̌��́A���퐶���̂Ȃ��ł̂ق�̈�u�ɂ����܂���B���t��I���A���͐Ȃ��K�T�K�T�Ɨ����F�l�Ɗ��z����荇���ł��傤�B����̓����̂Ȃ��ŐF�X�ȕ����ӎ��̂����ɔ����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�����ł��A����ȑ̌��͂��������͑����Ȃ��̂ł��B�����ł����ł̉��t�͂��������ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��傤���B ���̂Ƃ��A��̓]�|��������̂ł��B�x�~�͉��y�̗������U�����~�߂邱�ƂŁA���߂����萨����������̂ł͂Ȃ��B���̉��y�͋x�~�Ƃ������̂������Ă��܂������̂ɁA���̓����Ƃ�����O�I�Ȃ��Ƃ��J�n���Ȃ���Ȃ��Ȃ��Ƃ����W�����藧���Ă��܂��B���̂悤�ȓ]�|�Ƃ������ۂɂ���āA���y�����̌����̎��ԂƉ��y���Ƃ������ԂƂ��d�Ȃ荇���Ƃ��A�����邱�Ƃ���߂��I�[�P�X�g���̊e�p�[�g���A���̓O�ꂵ���Î~�䂦�ɋp���ĉ��y�S�̂ɓ�����^����_�@�ƂȂ�B���̏ꍇ�̓����Ƃ́A���y�Ƃ�������Ƃ̊W������܂łƂ͈قȂ����Ӗ��������Ă��܂����Ƃ����ܗL���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�A���X�g�e���X�́u���w�v�̂Ȃ��Ńh���}�ɂ͔����Ƌt�]���K�v�ł���ƌ����Ă��܂��B�����Ĕ����Ƌt�]�������ɋN����̂��]�܂����B���Ƃ��\�t�H�N���X�́u�I�C�f�B�v�X���v�ł́A�I�C�f�B�v�X�͎������悫���ƂȂ邱�Ƃ�]�ނ��̂ɁA���������e�E���ł����e�ƌ����������Ƃ�����B����Ȃ��Ƃ�m���Ă��܂�����A�����J��Ԃ炴������Ȃ��B�܂�A�ނ̐l�ԂƂ��Ă̑��݂��t�]���Ă��܂��̂ł��B�u���b�N�i�[�̉��y���A����قǂ̐[�����������Ă���Ƃ͌�����܂���B�������A�����҂ƒ�����鉹�y�Ƃ̊W��]�|�����Ă��܂������̂��̂́A�m���ɔF�߂�������܂���B���̈Ӗ��ŁA���̋x�~�͌��I�ȓ����ݏo���Ă���ƌ������Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�ł����A�����҂ɂ��̂悤�Ȏ����Ƃ�����������̂��ۂ��u���b�N�i�[�Ƃ������y�́A�P�ɂ��炵�����y�Ƃ��čς܂��Ă��܂����Ƃ͂ł���̂ł��傤���B �N���C�}�b�N�X�̌�A���@�C�I�����̏z���`�[�t�̌J��Ԃ����o�b�N�ɒ��ԕ���\�����邩�̂悤�ȕ��ȕ��̐������t�ł���Z���o�ߕ����B�����āA�O�͂̕������J��Ԃ��܂��B[0:50�`2:20]���̊y�͂̓��@�C�I�����̏z���`�[�t�̌J��Ԃ��łĂ��Ă���Ǝv���܂��B���̃��`�[�t�͂���قǒ����͂Ȃ��A�܂��悭�����������f�B�Ƃ����̂ł��Ȃ��̂ŁA���̃��`�[�t�̌J��Ԃ�������Βʑt�ቹ�̂悤�Ɋy�͑S�̂̃��Y�������肾���Ă���悤�ɕ�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����Ńu���b�N�i�[�̌J��Ԃ����Ƃ������Ƃ��A���̊y�͂ł͈�̃|�C���g�ƂȂ��Ă��܂��B�J��Ԃ����Ƃ������Ƃł́A�O�͂ł��\���グ�܂����������Ƃ��悤�ɌJ��Ԃ����ۂ��Ƃ����_�A���̓_�ɂ����Ă̓u���b�N�i�[�̌J��Ԃ��͉�������O��Ƃ͕ω���������Ƃ������Ƃ�����܂��B�O�͂̋L�q�ł͕����I�Ȃ��ƂɏI�n���܂������A���̊y�͑S�̂ɂ����Ă͒ʑt�ቹ�ƂȂ��Ă��郔�@�C�I�����̏z���`�[�t���J�m�����ɕϑt����Ă���B�u���b�N�i�[�ɂ͒������ϑt�ȂƂ��Ē������Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��������܂��B�ʑt�ቹ�̕ϑt�Ƃ����A�o�b�n���ŗL���ȃp�b�T�J���A�Ƃ����`��������܂����A�����܂Ō��i�Ɏ��K�v�͂Ȃ��A���}���h�̍�i�ɑ������i�ϑt�i�o�b�n�̃S�[���h�x���N�ϑt�ȂƂ��u���[���X�̃n�C�h���E�o���G�B�V�������j�I�Ȏ��������Ăق����Ǝv���܂��B�����ł́A���̑��̓_�ɂ��ďq�ׂ����ĉ������B ���āA�����Řb���u���b�N�i�[���痣��܂��B���[�c�@���g�̃s�A�m�E�\�i�^��W�ԃC�P���j�R�P�O���}���A�E�W���A�I�E�s���X�Ƃ����s�A�j�X�g�̂P�X�V�S�N�̘^���Œ������Ƃ��̈�ۂł��B��P�y�͂̒��̂��ƓW�J���ւ̊Ԃ̒Z���o�ߋ�̉��t�ł��i[C37-7387] 19 0:40�`2:20�j�B�t�_���Y���̘a���ɏ���đO�ʼn��̓����ő�P���A�����Ē����ɓ]�����đ�Q���̒��s�Ȃ��܂��B���̌�A����̃o�X���h�\�~�\�Ƃ������U�a���������ƒe��������Ƃ��낪����܂��B
��P�T�́@�u���b�N�i�[�Ƒ�F���m ��F���m�́u�A�L���v��u�����v�Ƃ�������i���������܂Ƃł��B�|�p�ƃu���b�N�i�[�ƒᑭ�Ȗ���Ƃ�ɕ��ׂ�͕̂s�ސT�Ƃ̐������邱�Ƃł��傤���A���̓_�͎��̓ƒf�ƕΌ��ł��̂łǂ����������������B
����ɁA�E�}�A�E�����l�Ԃ��Ԃ�ɂ��ė①�ɂɓ��ꂽ�Ƃ�����ʂł��B���ɂ͐l���E���Ă��܂����Ƃ��������L���̂悤�Ȃ��̂��S���������܂���B���̂���������Ƃ��ɗ�����錌�͂����̑�ʂ̉t�̂ɂȂ��Ă��āA���͓̂O��I�ɂ����̕����ɂȂ��Ă���̂ł��B�����ŕ`����Ă���l�Ԃ́A�����M���O�̑Ώۂɂ͂Ȃ肦�܂���B�ނ���A�l�ԁ������I���̂Ƃł������悤�ȕ`����������Ă��܂��B�܂��A�①�ɂ̒������Ă݂ĉ������B��������̃r�������̂ƈꏏ�ɕ`����Ă��܂��B�܂Ƃ������̂́A�K�v�łȂ����̂͏ȗ����Ă��܂����̂ł����A�����ł͂��������f�B�e�[�����`�����܂�Ă��܂��B����͈Ӑ}�I�Ȃ��̂ł��B�܂�A�l�Ԃ̎��̂ƃr���������Ɉ����Ă���Ƃ����킯�ł��B���������l�Ԃ�`���̂ɁA�ׂ��ċώ��Ȑ����p�����Ă��܂��B������ǂ��Ƃ������Ƃ��ϗ��I�ɔ��f���Ȃ��A�ϗ����щz���Ă��̃L���̂��������l�Ԃ╨����\�����Ă���B�ʂ̌�����������ƁA�����Ƃ���V�}�̂Ȃ��Ƃ������������܂��B������v�������r������A���ꂪ��F���m�̌y�݂̐��̂��Ǝv���܂��B
���������A�l�Ԃ����ʂ�L����Ƃ����l���ɂ́A�����Ƃ����֊s��ݒ肵�āi��������ӎ��Ƃ����ȂƂ������̂ł��傤���j���̗֊s�̊O���Ɠ����������āA�����͈Ⴄ���̂��Ƃ����O�ݒ肳��Ă��܂��B���̈Ⴂ���g�債�Ă����ƁA�O���ő��l�Ɛڂ��Ă��鎩���͋U�̎����ŁA�{���̎����͓����ɂ���̂��Ƃ����F���Ɍ��ѕt���Ă��܂����̂ł��B���l�ƊW���鎩���͋U�ŁA�������g���F�����鎩���݂̂��{���Ȃ̂��Ƃ������ƂɂȂ�B��������ƁA�����̓��ʂƂ������̂������[���������̂������Ă��邩�̂悤�Ɏv���Ă���̂ł��B���Ƃ��A�N�������𗝉����Ă���Ȃ��Ƃ����悤�Ȋ���́A���������Ƃ��납��o�ė��Ղ��B������������Ƃ����̂͏\��̎v�t���̎q�����ׂ�₷���B�ŋ߂ł́A����L�̉̂Ȃǂɒ[�I�ɂ������Ă��܂��B�i������ƌ����āA����L�̉̂��ǂ��Ƃ������Ƃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ŁA������Ȃ��łق����Ǝv���܂��B�j���̏ꍇ����O�ł͂���܂���ł����B�������A����Ȃ��Ƃ͎Љ�ɏo�Đ������ׂ��Ȃ��ő��l�Ɛڂ��鎩��������邱�Ƃňӎ����Ȃ��Ȃ��Ă������̂Ǝv���܂��B���̏ꍇ�́A�����ɂ����������ӎ����������Ƃ͂ł��Ȃ��ł͂��܂��B�����A�w�{���̎����x�ȂǂƂ������̂͂ǂ��ɂ��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B �����Ƃ������w�{���̎����x�ȂǂƂ������̂��A�ꎞ���̎��ɂ̓v���b�V���[�ł������A����Ȃ��̂͂Ƃ��ɂ��Ȃ��Ǝv�����ƂŋC���y�ɂȂ����̂ł����B�w�{���̎����x�Ƃ������̂������āA��������Ƃ̋����������āA�Y�����ӎ�����������Ȃ��Ȃ��āA���̂����w�{���̎����x�����Ȃ̂��Ȃǂ͞B���Ŕ���킯���Ȃ��ł�����B�N�������̂��Ƃ�������Ă���A�����킩���Ă��Ȃ����Ƃ����Ԃ��Ă݂Ă��A���̎��������Ă킩���Ă͂��Ȃ��̂ł��B����ŗ�������ł��܂��B����ǂ��A�w�{���̎����x�Ȃ�Ă��̂͂Ȃ��āA�������l�⎩���̖ڂɉf�鎩�������邾���Ȃ̂ł��B����Ńv���b�V���[�������邱�Ƃ��ł�����ł��B�����ł͓����I�Ƃ������Ă��Ă��A���l���Ќ�I���ƌ��Ă���̂Ȃ炻��͎����Ȃ킯�ł��B�����ƌ����A�����ȂǂƂ������̂́A��A���I�ɃX�g���{�̂悤�ɓ_�ł��Ă���u�ԏu�Ԃ̓_�̏W���̂悤�Ȃ��̂ŁA���ꂪ���������A�����Ă��邩�̂悤�ɘA�Ȃ��Č����Ă��邾���Ȃ̂��A�Ƃ����悤�ɁB�����ł������Ǝv���Ȃ��s��������A���l�i��������������Ƃ��ɂ��Ώۉ����Ă���킯�ł�����A���R�������l�Ɋ܂܂�܂��B�j�ɂ͂����������̂Ƃ��Č�����B����͉R�ł��U�ł��Ȃ��A���̌���Ŏ����Ȃ������B����Ȃ炻��ł����ł͂Ȃ����B�����v���A������ł�������ς��邱�Ƃ��ł���A�������Ă������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �������Ă݂�ƁA��F���m�̂܂̃N�[�����A�~���t�^���Ȃ������A���������A�y�݁A����炪�A���ɂƂ��Ă̑��肾�������ʐ��Ƃ����b�Z�[�W�Ƃ��e�[�}�ȂǂƂ������̂��]�|���Ċ������܂����B���ʂ����]����Ε\�ʂȂ킯�ŁA�������̂ł���͂��Ȃ̂ɂǂ�������Ɍ����Ă��܂����̂ł��B����Α�F���m�̂܂Ƀ~���t�^���Ȃ�����Ǔ��g��̎��������邱�Ƃ��ł��܂����B�g���܂��Ȃ�āA����Ȃ��B�h�Ƃ�����ɂł��B�u���b�N�i�[�̉��y������ɒʂ���Ƃ��낪����̂ł��B���z�̂Ȃ��Ƃ��A�s��ȉ��̍\�z�����Ȃ�����͓����͋ł��邱�ƂƂ��A�f�ނƂ��Ẳ����ǂꂪ��łǂꂪ�]�Ƃ������ƂȂ������ł��邱�Ƃ�A�f�B�e�[���ɌŎ����邱�ƂƂ��A���̑����X�������Č����Δ���L�̂悤�Ȃ��̂���̉�ō܂̖����͂����Ă��ꂽ�̂ł����B���ꂪ�A���̂悤�ȏ����𑐂������@�ł�����܂��B���̈Ӗ��ŁA�u���b�N�i�[�̉��y�̑��ĉߏ�Ȏv�������ނ��炵���Ӗ��t����_�b���ɂɕ�ݍ���ł��܂��̂�����鏊�Ȃł��B�~���t�^���Ȃ����y�ł��A�~���t�^���Ȃ��������ł͂���܂��B ���̂����Ȃ��Ƃ�ނ��炵�������܂������A���͖����ɂӂ���Ă͂���܂���B�Ⴆ�u�݂ɂ������Ђ�̂��v�Ƃ������b������܂��B�X���ƌ���ꑱ�����q�������͔����̎q���������Ƃ����b�B�����͔��������ł��傤�B������ƌ����ĒN�̖ڂɂ��X�����̎q���������̎q������������̂��ƕ]�����ς��킯�͂Ȃ��̂ł��B�������A�{�l�ɂƂ��Ă͏X���Ƃ���������F�߂�̂͋ꂵ�����Ƃł��B�����̎q���Ƃ����w�{���̎����x�@�͔������Ƃ����̂́A����ȓ��l�ɂƂ��ēs���̂���������ł��B������������������̂͐h�����ƂŁA�ǂ����Ă����S�������˂�畏����Ă���̂�����ł��B |

 �O�͂ŐG����Ȃ��������Ƃ�����܂��B�����ł́A���̂��Ƃ������������b���������Ǝv���܂��B�J�n�����̕��U�a���́u�Â��g�̂悤�ȓ����v���A���͒ጷ�̑O�̂߂�̏z�ƁA���@�C�I�����̑O�֑O�ցc�̏㏸�ƌ��ցc�̉��~�Ƃ�������̓������܂��Ă��邱�Ƃ͑O�͂ŏq�ׂ܂����B���̂��ƂŃu���b�N�i�[�̉��̓����ɑ傫�ȍL�����������������킯�ł��B�����Ă܂������ł́A���́u�Â��g�̂悤�ȓ����v���ȑS�̂����Ă���Ƃ�������̂ł��B�O�͂ŊJ�n�����̎��Ȃ�̑f�`���s�Ȃ����ہA�u���y�̗���v�Ƃ��������������܂����B��g�I�Ȍ������ɂȂ�܂����u�Â��g�v�����������W�܂��āA�S�̂́u����v������Ƃ����킯�ł��B��̓I�ɂ͂ǂ����A�Ƃ������Ƃ͑O�͂̋L�q���Q�Ƃ��ĉ������B���@�C�I�����̑O�ւ̉��~�̓������D���ɂȂ�ƁA�u�Â��g�v�͐��i�͂������A�܂��NJy�킪��Ɉ������悤�ȃA�N�Z���g�ł̓����ƁA���鎞�_�ł͓����̕������ύt���ċȑS�̂��Î~������A���̎��_�ł͑傫���O�i��Ƃ�����ł��B���́u�Â��g�̂悤�ȓ����v�����镪�U�a�����ȑS�̂̐ߖڐߖڂ̎��鏊�Ɍ�����̂ł��B�Ⴆ�Α�P�y�͂ł́A���y�̗���̐ߖڂɂ͕K���Ƃ����Ă����قnj����Ă��܂��B��R�y�͂̃X�P���c�H���ȂǕ��U�a���̕ό`�ƂƂ�Ȃ����Ƃ�����܂���B��S�y�͂��`���͕��U�a���ł��B�������Ă݂�ƁA�u���b�N�i�[�̉��y�̗���͈��̊K�w�\���������Ă��邱�ƂɋC���t���܂��B�K�w�\���ȂǂƂ����Ɠ���������邩������܂���B�Ⴆ�A�C��z�����Ă݂Ă��������B�C�݂ɗ����Ă���Ƒ�g���g���Ă͕Ԃ����킩��܂��B�C���̎��鏊�ɏ����Ȕg���N���肻�ꂪ�Ă���킯�ł��B�����̏����Ȕg��ۂݍ��ނ悤�ȑ傫�Ȕg���N����A���̑傫�Ȕg������W�܂��đ傫�ȊC�̗��ꂪ�N����A���ꂪ�C���ł��B�����Ȕg����C���܂ŐF�X�Ȕg�����i�K�ɂ��o���G�[�V����������A����炪�݂��Ɋւ�荇���ĂƂ������Ƃł��B�����čX�ɗl�X�ȊK�w�̔g�����ׂĕ����Ɉ����Ă���̂��������u���b�N�i�[�̉��y�̓����ƌ������Ƃ��ł��܂��B�����Ȕg�͍ő�̊C���̕��i�ł͂Ȃ��̂ł��B��̗�͂���܂ł̂Ƃ���ʼn��x���G��Ă��Ă���̂ŎQ�Ƃ��ĉ�����K���ł��B
�O�͂ŐG����Ȃ��������Ƃ�����܂��B�����ł́A���̂��Ƃ������������b���������Ǝv���܂��B�J�n�����̕��U�a���́u�Â��g�̂悤�ȓ����v���A���͒ጷ�̑O�̂߂�̏z�ƁA���@�C�I�����̑O�֑O�ցc�̏㏸�ƌ��ցc�̉��~�Ƃ�������̓������܂��Ă��邱�Ƃ͑O�͂ŏq�ׂ܂����B���̂��ƂŃu���b�N�i�[�̉��̓����ɑ傫�ȍL�����������������킯�ł��B�����Ă܂������ł́A���́u�Â��g�̂悤�ȓ����v���ȑS�̂����Ă���Ƃ�������̂ł��B�O�͂ŊJ�n�����̎��Ȃ�̑f�`���s�Ȃ����ہA�u���y�̗���v�Ƃ��������������܂����B��g�I�Ȍ������ɂȂ�܂����u�Â��g�v�����������W�܂��āA�S�̂́u����v������Ƃ����킯�ł��B��̓I�ɂ͂ǂ����A�Ƃ������Ƃ͑O�͂̋L�q���Q�Ƃ��ĉ������B���@�C�I�����̑O�ւ̉��~�̓������D���ɂȂ�ƁA�u�Â��g�v�͐��i�͂������A�܂��NJy�킪��Ɉ������悤�ȃA�N�Z���g�ł̓����ƁA���鎞�_�ł͓����̕������ύt���ċȑS�̂��Î~������A���̎��_�ł͑傫���O�i��Ƃ�����ł��B���́u�Â��g�̂悤�ȓ����v�����镪�U�a�����ȑS�̂̐ߖڐߖڂ̎��鏊�Ɍ�����̂ł��B�Ⴆ�Α�P�y�͂ł́A���y�̗���̐ߖڂɂ͕K���Ƃ����Ă����قnj����Ă��܂��B��R�y�͂̃X�P���c�H���ȂǕ��U�a���̕ό`�ƂƂ�Ȃ����Ƃ�����܂���B��S�y�͂��`���͕��U�a���ł��B�������Ă݂�ƁA�u���b�N�i�[�̉��y�̗���͈��̊K�w�\���������Ă��邱�ƂɋC���t���܂��B�K�w�\���ȂǂƂ����Ɠ���������邩������܂���B�Ⴆ�A�C��z�����Ă݂Ă��������B�C�݂ɗ����Ă���Ƒ�g���g���Ă͕Ԃ����킩��܂��B�C���̎��鏊�ɏ����Ȕg���N���肻�ꂪ�Ă���킯�ł��B�����̏����Ȕg��ۂݍ��ނ悤�ȑ傫�Ȕg���N����A���̑傫�Ȕg������W�܂��đ傫�ȊC�̗��ꂪ�N����A���ꂪ�C���ł��B�����Ȕg����C���܂ŐF�X�Ȕg�����i�K�ɂ��o���G�[�V����������A����炪�݂��Ɋւ�荇���ĂƂ������Ƃł��B�����čX�ɗl�X�ȊK�w�̔g�����ׂĕ����Ɉ����Ă���̂��������u���b�N�i�[�̉��y�̓����ƌ������Ƃ��ł��܂��B�����Ȕg�͍ő�̊C���̕��i�ł͂Ȃ��̂ł��B��̗�͂���܂ł̂Ƃ���ʼn��x���G��Ă��Ă���̂ŎQ�Ƃ��ĉ�����K���ł��B ���āA�p�m�t�X�L�[�̎w�E�ɂ͂���܂��A�S�V�b�N���z�ƃX�R���N�w�������o�����̂͂�������R������܂��B�X�R���N�w�Ƃ����̂́A���̓A���X�g�e���X�̒����L���X�g���I�ȓǂݑւ��Ȃ̂ł��B�A�N�e�B�[�m�̐��g�}�X�i�g�}�X�E�A�N�B�i�X�j�ɑ�\�����X�R���N�w�̈ȑO�͐��A�E�O�X�e�B�k�X�̋���������A������͐V�v���g����`�Ńv���g���̓ǂݑւ��ł��B���Ȃ苭���ȗޔ�ł����A���̓����܂ł̓v���g���ƃA���X�g�e���X�Ƃ�����̋����̒��������݂��Ă����ƌ����Ă����Ǝv���܂��i�N�w�j�̊ȒP�ȊT�������Q�Ƃ��Ă�������Τ����Ǝv���܂�����Ƃ��Τ�o�[�g�����h����b�Z������m�N�w�j�Q��s��O�Y��݂������[�j�B�v���g���ƃA���X�g�e���X�͋��ɃC�f�A�Ƃ������z�I�Ȃ��̂��w������_�ŋ��ʂ��Ă��܂����A�����Ɏ���v���Z�X�͑S���قȂ��Ă��܂��B�悸�v���g���ɂƂ��āA�C�f�A�Ƃ͒��z�I�ł���Ɠ����ɂ���߂ċq�ϓI�Ȃ��̂ł��B����́A�����Ƃ��l�ԂƂ��藣���ꂽ�A���ꎩ�̂����݂��邫��߂ċq�ϓI�Ȃ��́A���O�ł��B�܂�v���g�j�Y���͈��̋q�ώ�`�ł��B�ÓT��`���z�ł���p���e�m���_�a�́A�v���g�j�Y���̌��z�̐��E�ɂ�����Ή����ƌ������Ƃ��ł��܂��B�����͌��z�e���̐��@���x�z������̌n���͂��߂Ƃ��āA����߂ċq�ϓI�Ȕ��̊�i�C�f�A�j���S�Ă��x�z����ꏊ�ł���A���A�e�l�̌����̓s�s�Ƃ͖��m�ɋ�ʂ��ꂽ���z�I�Ȑ_�b�̐��E�Ȃ̂ł��B����A�A���X�g�e���X�̓v���g���ɔ�ׂČ����I�ł���A���͓I�ł���ƌ����܂��B�ނ́A�v���g�j�Y���̃C�f�A�̒��z�����A�����C�f�A�ƌ����̐ؒf��ᔻ���܂��B�ނɂ��A�C�f�A�͂��̐��̂����錻���̒��ɑ��݂��Ă���̂ł��B�C�f�A�͌��ƂƂ��ɂ���Ƃ����킯�ł��B�C�f�A�̎��ɖ��ƂȂ�̂̓C�f�A�ւ̓��B���@�ł��B�v���g���̓C�f�A�Ƃ������z�I���q�ϓI���E�Ɍ������Đl�Ԃ͗����I�ɏ㏸����Ɛ����܂����B����ɑ��A���X�g�e���X�́A���̒��ɂ���C�f�A��l�Ԃ͌l�̊��o�ɂ���Ĕc������ƍl�����̂ł��B�v���g���̋q�ώ�`�ɑ��ăA���X�g�e���X�͎�ώ�`�Ȃ̂ł��B����ɔނ́A�������o�Ŕc�����鎞�A�l�Ԃ͕��̎����i�f�ށj����ł͂Ȃ��`�������p��������ƍl���܂����B���̈Ӗ��ɂ����āA�A���X�g�e���X�̋����ƃS�V�b�N�̌��z��Ԃ͎��Ă��邱�Ƃ��w�E�ł��܂��B�O�y�[�W�̗�ŃA�[�`�̐̓����ł��邽�ߌX�̐̍ގ��Ƃ��Ă̌����}�����Ĕ������Ă������Ƃ���������炩�Ȃ悤�ɁA�S�V�b�N���z�͔���̂ł���A��ϓI�Ȃ̂ł��B�A���X�g�e���X�����o���ĂыN�����������`���ɋ��߂Ď����i���́j��ے肵���悤�ɁA�S�V�b�N�̌��z���܂��O��I�Ɏ��̊��A�f�ފ���ے肵�܂����B���̂̂����Ɋ�d�ɂ��K�w�����ꂽ�\���Ƃ������ۓI�Ȍ`���Ƃ��Č��z���\�����܂����B�K�w�Ƃ͑�����̌��ł��B�K�w�Ƃ�������ςݏグ�Ă����S�V�b�N���z�́A�P��ȊK�w���S�̂��x�z����p���e�m���_�a�Ƃ͂܂��ɑɓI�ȍ\���@�ƌ������Ƃ��ł��܂��B�����̐_�w�҂����́A�_�Ƃ����B���Ȃ���̂_�Ƃ���K�w�I�ȑ̌n��z�������悤�Ƃ����킯�ł���A���̃X�^�e�B�b�N�ŊK�w�I�ȑ̌n�͎�ώ�`�Ő�����^����ꂽ�킯�ł��B���ꂪ�X�R���N�w�ł���A�S�V�b�N���z�̑吹���Ȃ̂ł����B�X�^�e�B�b�N�Ńq�G�����L�J���ȑ̌n�Ǝ�ώ�`��g�ݍ��킹���Ƃ���ɃA���X�g�e���X�̓N�w�̖{��������A�����ɂ����ė��҂͂�����p�������̂ł����i�n���@�v��吹���̃R�X�����W�[��u�k��
���āA�p�m�t�X�L�[�̎w�E�ɂ͂���܂��A�S�V�b�N���z�ƃX�R���N�w�������o�����̂͂�������R������܂��B�X�R���N�w�Ƃ����̂́A���̓A���X�g�e���X�̒����L���X�g���I�ȓǂݑւ��Ȃ̂ł��B�A�N�e�B�[�m�̐��g�}�X�i�g�}�X�E�A�N�B�i�X�j�ɑ�\�����X�R���N�w�̈ȑO�͐��A�E�O�X�e�B�k�X�̋���������A������͐V�v���g����`�Ńv���g���̓ǂݑւ��ł��B���Ȃ苭���ȗޔ�ł����A���̓����܂ł̓v���g���ƃA���X�g�e���X�Ƃ�����̋����̒��������݂��Ă����ƌ����Ă����Ǝv���܂��i�N�w�j�̊ȒP�ȊT�������Q�Ƃ��Ă�������Τ����Ǝv���܂�����Ƃ��Τ�o�[�g�����h����b�Z������m�N�w�j�Q��s��O�Y��݂������[�j�B�v���g���ƃA���X�g�e���X�͋��ɃC�f�A�Ƃ������z�I�Ȃ��̂��w������_�ŋ��ʂ��Ă��܂����A�����Ɏ���v���Z�X�͑S���قȂ��Ă��܂��B�悸�v���g���ɂƂ��āA�C�f�A�Ƃ͒��z�I�ł���Ɠ����ɂ���߂ċq�ϓI�Ȃ��̂ł��B����́A�����Ƃ��l�ԂƂ��藣���ꂽ�A���ꎩ�̂����݂��邫��߂ċq�ϓI�Ȃ��́A���O�ł��B�܂�v���g�j�Y���͈��̋q�ώ�`�ł��B�ÓT��`���z�ł���p���e�m���_�a�́A�v���g�j�Y���̌��z�̐��E�ɂ�����Ή����ƌ������Ƃ��ł��܂��B�����͌��z�e���̐��@���x�z������̌n���͂��߂Ƃ��āA����߂ċq�ϓI�Ȕ��̊�i�C�f�A�j���S�Ă��x�z����ꏊ�ł���A���A�e�l�̌����̓s�s�Ƃ͖��m�ɋ�ʂ��ꂽ���z�I�Ȑ_�b�̐��E�Ȃ̂ł��B����A�A���X�g�e���X�̓v���g���ɔ�ׂČ����I�ł���A���͓I�ł���ƌ����܂��B�ނ́A�v���g�j�Y���̃C�f�A�̒��z�����A�����C�f�A�ƌ����̐ؒf��ᔻ���܂��B�ނɂ��A�C�f�A�͂��̐��̂����錻���̒��ɑ��݂��Ă���̂ł��B�C�f�A�͌��ƂƂ��ɂ���Ƃ����킯�ł��B�C�f�A�̎��ɖ��ƂȂ�̂̓C�f�A�ւ̓��B���@�ł��B�v���g���̓C�f�A�Ƃ������z�I���q�ϓI���E�Ɍ������Đl�Ԃ͗����I�ɏ㏸����Ɛ����܂����B����ɑ��A���X�g�e���X�́A���̒��ɂ���C�f�A��l�Ԃ͌l�̊��o�ɂ���Ĕc������ƍl�����̂ł��B�v���g���̋q�ώ�`�ɑ��ăA���X�g�e���X�͎�ώ�`�Ȃ̂ł��B����ɔނ́A�������o�Ŕc�����鎞�A�l�Ԃ͕��̎����i�f�ށj����ł͂Ȃ��`�������p��������ƍl���܂����B���̈Ӗ��ɂ����āA�A���X�g�e���X�̋����ƃS�V�b�N�̌��z��Ԃ͎��Ă��邱�Ƃ��w�E�ł��܂��B�O�y�[�W�̗�ŃA�[�`�̐̓����ł��邽�ߌX�̐̍ގ��Ƃ��Ă̌����}�����Ĕ������Ă������Ƃ���������炩�Ȃ悤�ɁA�S�V�b�N���z�͔���̂ł���A��ϓI�Ȃ̂ł��B�A���X�g�e���X�����o���ĂыN�����������`���ɋ��߂Ď����i���́j��ے肵���悤�ɁA�S�V�b�N�̌��z���܂��O��I�Ɏ��̊��A�f�ފ���ے肵�܂����B���̂̂����Ɋ�d�ɂ��K�w�����ꂽ�\���Ƃ������ۓI�Ȍ`���Ƃ��Č��z���\�����܂����B�K�w�Ƃ͑�����̌��ł��B�K�w�Ƃ�������ςݏグ�Ă����S�V�b�N���z�́A�P��ȊK�w���S�̂��x�z����p���e�m���_�a�Ƃ͂܂��ɑɓI�ȍ\���@�ƌ������Ƃ��ł��܂��B�����̐_�w�҂����́A�_�Ƃ����B���Ȃ���̂_�Ƃ���K�w�I�ȑ̌n��z�������悤�Ƃ����킯�ł���A���̃X�^�e�B�b�N�ŊK�w�I�ȑ̌n�͎�ώ�`�Ő�����^����ꂽ�킯�ł��B���ꂪ�X�R���N�w�ł���A�S�V�b�N���z�̑吹���Ȃ̂ł����B�X�^�e�B�b�N�Ńq�G�����L�J���ȑ̌n�Ǝ�ώ�`��g�ݍ��킹���Ƃ���ɃA���X�g�e���X�̓N�w�̖{��������A�����ɂ����ė��҂͂�����p�������̂ł����i�n���@�v��吹���̃R�X�����W�[��u�k��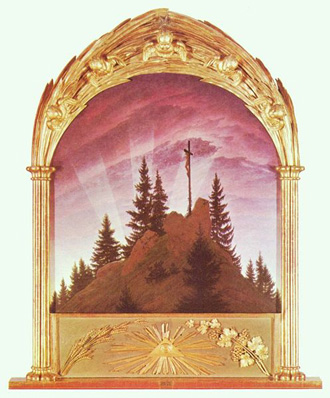 �O�͂̍Ō�̂Ƃ���ŁA�u���b�N�i�[�̉��y�̒��ɋ����R���g���X�g�������������鏈�����邱�Ƃ��q�ׂ܂����B�����ł́A���̂��Ƃɂ��ď�����蓹�����܂��B
�O�͂̍Ō�̂Ƃ���ŁA�u���b�N�i�[�̉��y�̒��ɋ����R���g���X�g�������������鏈�����邱�Ƃ��q�ׂ܂����B�����ł́A���̂��Ƃɂ��ď�����蓹�����܂��B ���̏͂ɂ����O�ɁA�u���b�N�i�[�ƃt���[�h���b�q���Ԃ����̂Ƃ��āA�t���[�h���b�q�̑�����s�C�ӂ̑m���t�Ƃ�����i�������邱�Ƃ��ł��܂��B���̍�i�́s�R��̏\���ˁt�����X�ɗv�f���l�ߒP�������ꂽ��Ԃ��\�����܂��B��ʂ̑唼���V��ɕ����A����䩔������Ԃ̒��Ɉ�l�̏C���m�Ɛ��H�̉��A���ꂪ���̍�i�ɕ`����Ă�����̂̂��ׂĂł��B��ʂ̘Z���̌܂��܂����߂Ă��܂��B���̋�͐��ݐÂ܂肩�����Ă��܂��B���̋C�z���Ȃ���A�z���˂����A���̌����Ȃ��A���������̍�����������܂���B�܂��A��̉��ɍL����C���ɂ́A�x���D�e��������������܂���B���u�ɂ͗̑��ЂƂ����Ă����Ȃ��B�s�R��̏\���ˁt�ł͑O�i�Ɖ��i�����}��ɑΛ���������ʍ\���ɂ���āA���߂̃R���g���X�g�����������Ɠ����ɁA���i�͔��������Ă��܂��Ĉ���Ή�ʂ̐[���Ƃ��ċ�Ԃ̕�����ӎ��������܂��B����ɑ��ās�C�ӂ̑m���t�ł͒��i���g�傳��傫���g�����ƊC�������̕��i�Ƃ��ĉ�������A�[���̏ے��Ƃ��Ċς�҂ɔ����Ă���̂ł��B�������A���̋����̂Ђ낪�肪��ʂ̒��Ő����ɐL�тĂ��ĊG�̉��Ō��肳��Ă��Ȃ����߁A�ʂĂ��Ȃ���ۂ�^���܂��B�����āA��ʂ̐����̖����̍L����ɑ��āA�B��̐����Ɍ����̂��m���ł��B���̑m���͍L��ȕ��i�̒��ł������Ƃ�ŗ����Ă��܂��B����ɁA���̑m���͌�����ŁA������������A����{�ɂ̂����������R���b�N�ȃ|�[�Y���Ƃ��Ă��āA�Ǘ�����������ەt�����܂��B���̊G���]��������Ƃ̃N���C�X�g�́g�c�����g�����̃J�v�`���m�ɂȂ����i�Q���g���[�g��t�B�[�Q��J�X�p�[��_�[���B�h��t���[�h���b�q������䂤�q��
�p���R���p�V��
���̏͂ɂ����O�ɁA�u���b�N�i�[�ƃt���[�h���b�q���Ԃ����̂Ƃ��āA�t���[�h���b�q�̑�����s�C�ӂ̑m���t�Ƃ�����i�������邱�Ƃ��ł��܂��B���̍�i�́s�R��̏\���ˁt�����X�ɗv�f���l�ߒP�������ꂽ��Ԃ��\�����܂��B��ʂ̑唼���V��ɕ����A����䩔������Ԃ̒��Ɉ�l�̏C���m�Ɛ��H�̉��A���ꂪ���̍�i�ɕ`����Ă�����̂̂��ׂĂł��B��ʂ̘Z���̌܂��܂����߂Ă��܂��B���̋�͐��ݐÂ܂肩�����Ă��܂��B���̋C�z���Ȃ���A�z���˂����A���̌����Ȃ��A���������̍�����������܂���B�܂��A��̉��ɍL����C���ɂ́A�x���D�e��������������܂���B���u�ɂ͗̑��ЂƂ����Ă����Ȃ��B�s�R��̏\���ˁt�ł͑O�i�Ɖ��i�����}��ɑΛ���������ʍ\���ɂ���āA���߂̃R���g���X�g�����������Ɠ����ɁA���i�͔��������Ă��܂��Ĉ���Ή�ʂ̐[���Ƃ��ċ�Ԃ̕�����ӎ��������܂��B����ɑ��ās�C�ӂ̑m���t�ł͒��i���g�傳��傫���g�����ƊC�������̕��i�Ƃ��ĉ�������A�[���̏ے��Ƃ��Ċς�҂ɔ����Ă���̂ł��B�������A���̋����̂Ђ낪�肪��ʂ̒��Ő����ɐL�тĂ��ĊG�̉��Ō��肳��Ă��Ȃ����߁A�ʂĂ��Ȃ���ۂ�^���܂��B�����āA��ʂ̐����̖����̍L����ɑ��āA�B��̐����Ɍ����̂��m���ł��B���̑m���͍L��ȕ��i�̒��ł������Ƃ�ŗ����Ă��܂��B����ɁA���̑m���͌�����ŁA������������A����{�ɂ̂����������R���b�N�ȃ|�[�Y���Ƃ��Ă��āA�Ǘ�����������ەt�����܂��B���̊G���]��������Ƃ̃N���C�X�g�́g�c�����g�����̃J�v�`���m�ɂȂ����i�Q���g���[�g��t�B�[�Q��J�X�p�[��_�[���B�h��t���[�h���b�q������䂤�q��
�p���R���p�V�� ��������ƍ���܂łƂ��̓��Ƃ́A�������������ς�����̂ł��傤���B�i�l�Y��������ĉ������̂͗^�s���q�ł��B����܂ł̉��^�̗^�s���q�́A���Y�������Ƃ����ɓ|��Ă��܂��������ł��B�T�b�T�Ɠ|��āA�T�b�T�Ɗy���ֈ�������ł��܂��܂����B�Ƃ��낪�i�l�Y�̗^�s���q�́A�����ꂽ�����ł͓|��Ȃ������B�g���g�����M��̍ۂ܂ʼn����Ă��āA�W�b�Ƃ����������Ă��āA���Y�������������Ƃ���ɓ|�ꂽ�̂������ł��B����ł��̓��́A���Y�̌��������̂������ł��B
��������ƍ���܂łƂ��̓��Ƃ́A�������������ς�����̂ł��傤���B�i�l�Y��������ĉ������̂͗^�s���q�ł��B����܂ł̉��^�̗^�s���q�́A���Y�������Ƃ����ɓ|��Ă��܂��������ł��B�T�b�T�Ɠ|��āA�T�b�T�Ɗy���ֈ�������ł��܂��܂����B�Ƃ��낪�i�l�Y�̗^�s���q�́A�����ꂽ�����ł͓|��Ȃ������B�g���g�����M��̍ۂ܂ʼn����Ă��āA�W�b�Ƃ����������Ă��āA���Y�������������Ƃ���ɓ|�ꂽ�̂������ł��B����ł��̓��́A���Y�̌��������̂������ł��B ���}�̏��̎q�̊G�������������B���̎q�́A����̒��ł͈ꉞ�������̎q�Ƃ���Ă͂���̂ł��������͌����܂���B�ڂ��������Ē݂�オ���Ă���A�@���Ⴂ�A�悭�O���̖���ɂ���悤�ȓT�^�I�ȓ��{�l�̊�ɋ߂��A�v����Ƀ~���t�^���Ȃ����{�l�̊�ɂȂ��Ă��܂��B�����܂�����܂ł��Ȃ����̂܂̏ꍇ�Ȃ�A�������̎q��`���Ƃ��́A�ڂ��傫���p�b�`�����Ă��āi���ɐ����P���Ă���j�@���ʂ��Ă���̂����ʂł��B�܂Ƃ����̂͒P�Ȃ�G�����ł͂Ȃ��Ė�����R����܂��āA���ꂪ�������̎q���Ƃ����Ƃ��ɂ́A���̏��̎q�ɊG�ɉ������̎q�̋L����`�����Ƃ��K�v�ł��B���ꂪ���̐���������A���̑��ł���킯�ł��B�̂܂ƂȂ�A���Ƃ��G������ł����̋L���Ƙb�̏�ł������Ƃ����ɂȂ��Ă���A�ǎ҂͂����������̂Ƃ��ēǂނ��̂Ȃ̂ł��B�ɒ[�Ȃ��Ƃ������A���̎q�͔��l�ƃu�X�̓�ʂ肢��A�G�Ƃ��Ă̂܂͐������Ă��܂��܂��B���l�͓���̑ΏہA�u�X�̓M���O�̑Ώۂł��B�����ŁA���l�ɂ͓���A�u�X�ɂ��~悂Ƃ����L��������������̂ł��B�������A��F���m�͐}�̂悤�ɂǂ���ł��Ȃ����̎q��`���܂����B�܂�A������~悂���F���m�̂܂ɂ͂Ȃ��̂ł��B
���}�̏��̎q�̊G�������������B���̎q�́A����̒��ł͈ꉞ�������̎q�Ƃ���Ă͂���̂ł��������͌����܂���B�ڂ��������Ē݂�オ���Ă���A�@���Ⴂ�A�悭�O���̖���ɂ���悤�ȓT�^�I�ȓ��{�l�̊�ɋ߂��A�v����Ƀ~���t�^���Ȃ����{�l�̊�ɂȂ��Ă��܂��B�����܂�����܂ł��Ȃ����̂܂̏ꍇ�Ȃ�A�������̎q��`���Ƃ��́A�ڂ��傫���p�b�`�����Ă��āi���ɐ����P���Ă���j�@���ʂ��Ă���̂����ʂł��B�܂Ƃ����̂͒P�Ȃ�G�����ł͂Ȃ��Ė�����R����܂��āA���ꂪ�������̎q���Ƃ����Ƃ��ɂ́A���̏��̎q�ɊG�ɉ������̎q�̋L����`�����Ƃ��K�v�ł��B���ꂪ���̐���������A���̑��ł���킯�ł��B�̂܂ƂȂ�A���Ƃ��G������ł����̋L���Ƙb�̏�ł������Ƃ����ɂȂ��Ă���A�ǎ҂͂����������̂Ƃ��ēǂނ��̂Ȃ̂ł��B�ɒ[�Ȃ��Ƃ������A���̎q�͔��l�ƃu�X�̓�ʂ肢��A�G�Ƃ��Ă̂܂͐������Ă��܂��܂��B���l�͓���̑ΏہA�u�X�̓M���O�̑Ώۂł��B�����ŁA���l�ɂ͓���A�u�X�ɂ��~悂Ƃ����L��������������̂ł��B�������A��F���m�͐}�̂悤�ɂǂ���ł��Ȃ����̎q��`���܂����B�܂�A������~悂���F���m�̂܂ɂ͂Ȃ��̂ł��B �l�Ԃ̓��ʂ̂�����Ƃ��Ă̊����\������������ł��邱�ƁA�f�ނƂ��Ẳ����S�V�b�N�̃A�[�`�̂悤�ɓ����Ɉ����Ă��邱�ƁB����ȂƂ���ɁA�u���b�N�i�[�Ƒ�F���m�̐ړ_�����o���Ă���̂ł��B�\�w�I�ȑ��݂ȂǂƂ����Ɠ����������ł��傤���c�B
�l�Ԃ̓��ʂ̂�����Ƃ��Ă̊����\������������ł��邱�ƁA�f�ނƂ��Ẳ����S�V�b�N�̃A�[�`�̂悤�ɓ����Ɉ����Ă��邱�ƁB����ȂƂ���ɁA�u���b�N�i�[�Ƒ�F���m�̐ړ_�����o���Ă���̂ł��B�\�w�I�ȑ��݂ȂǂƂ����Ɠ����������ł��傤���c�B