�@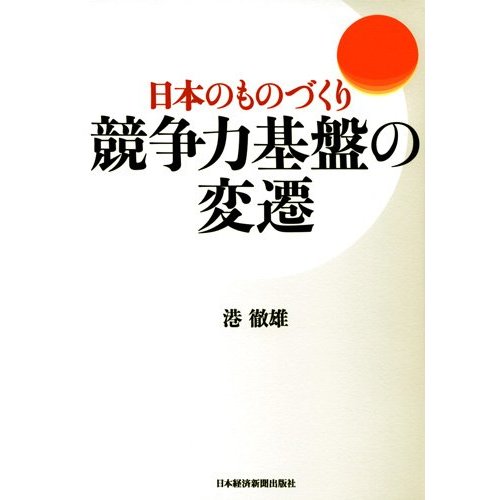
���́@���̂Â���卑�̉��� �P�D�����͂Ƃ��Ă̕��ƃV�X�e�� �Q�D�R�c�E�h�b�s�v�V�̏Ռ� �R�D���i�]�ŗ͂̒ቺ �S�D���{�Ԃ̕i���]���ቺ �T�D���Y�Z�p�̍��ۊg�U �U�D���W���[�����ƃA�W�A�n�d�l�r��Ƃ̑䓪 �V�D��Ռ^�Y�Ƃ̒��� �W�D���x�����钆���̐��Y�Z�p �X�D���Y�Z�p�ړ]�Ǝ��{���A�o �P�O�D�E�u�����v�͉\�� ��1�́@�����͊�Ղƍ��ە��� �P�D���ۋ����͂̃����L���O �R�D�Y�Ɛ��f�ՂƐV�f�_ �S�D��ƊԐ��Y���i���Ɓu�V�X�f���_�v �T�D�V�X�f���_�̎��،��� �U�D�����͊�ՂƐ��Y��7�D�ڍs�o�ύ��̈�����Ɗ�� �X�D�����͊�ՂƂ��Ă̗v�f������� �P�D�P�O�O�N�̎O�x�̑�]�� �R�D���̎Y�ƕ�����̏I�� �U�D3D�EICT�v�V�Ƒ��̎Y�ƕ�����̏I�� ��R�́@���ƃV�X�e���]���Ɛ��E�s�� �R�D���I���ɉh���x����ICT�v�V �S�D3D�EICT�v�V�Ɛ��E�s�� �P�D�P�X�U�O�N��̋����͗v�� �Q�D�P�X�V�O�N��̍��ۋ������ω� ���́@���̂Â���卑�̉��� �P�D�����͂Ƃ��Ă̕��ƃV�X�e�� 1970 �N�㒆������90�N�㒆���܂ł̖�20�N�Ԃ́A���{�̐����ƁA�Ƃ�킯�A�����̕��i����\������鍂�x�g���^�@�B�H�Ƃ̉������ł������B�����āA80�N�㒆���ɂ͂��̐Ⓒ���ɒB���A���i���ő��l���ɕx���i��v���ɋ�����������{�̐��Y�V�X�e���͐��E�I�ȏ̎^���A��i�����̋@�B�H�ƕ���ł́A�������ē��{�^���Y�V�X�e��������W���p�i�C�[�[�V�������ۂ��݂���܂łɂȂ����B���̎���ɂ����ẮA�����ԍH�Ƃ��͂��ߓ��{�̋@�B�H�Ɛ��i�́A���̈��|�I�ȕi���D�ʂɎx����ꂽ�i�����͂ɂ���āA�����ɂ킽��啝�ȉ~���V�t�g�ɂ�������炸�������Y�͊g�債�A�A�o��L�������Ă����B�����������{�̋@�B�H�ƕ���̋��͂ȍ��ۋ����͂��x���Ă�����{�I�v�f�́A������ƃV�X�e���iDomestic Division of Labor�j�ɂ������B������ƃV�X�e���Ƃ́A���Y�v�f�i�J���Ǝ��{�j�����R�Ɉړ��ł������̌o�ό����ō\������镪�ƃV�X�e���ł���B������ƃV�X�e���̒��ł��A�����i���[�J�[�ƕ��i�T�v���C���[�Ƃ̊�Ɗԕ��ƃV�X�e���A���̂Â���̊�Ղ��Ȃ����̂ł���B�܂��A���{�̉������ƃV�X�e���͊�Ɗԕ��Ƃ̈�`�Ԃł��邪�A���肳�ꂽ��ƊԂ̒����p������A�e��Ƃɂ�鉺������Ƃɑ���R���g���[���̑��ݓ��̎���W�̓��ِ������݂��Ă���B�����������ِ��́A���܂��܂Ȍo�ό��ʂ�h�������A��ƊԐ��Y�������߂Ă���B �������ƃV�X�e������ƊԐ��Y�������߂��v���́A���ɁA���̂悤�ȏ�����ƊԂ̒����p������ɂ���āA��ƊԂ̒����p������ɂ���āA��Ɗԕ��ƂɕK�v�Ƃ�������R�X�g��啝�ɏk���������B�Ƃ�킯�A���`�B�R�X�g�����߂邱�ƂȂ���ƊԂ̔Z���ȏ��������\�ɂ����B���ɁA��������Ƃ́A���Y�̎����������߂��p�@�B�E�ݔ����̎�����莑�Y�ւ̓�����ϋɓI�ɍs���A�R�X�g�ጸ�ƕi������Ƃ��I�ɒB�����Ă����B��O�ɁA������Ƃ́A����̐��Y�H���ɐ�剻���邱�Ƃɂ���āA���̐��̈�̉��H�Z�p��[�k�����Ă����B��l�ɁA���肵������W�ɂ���āA������Ƃł������I�ٗp���\�ƂȂ�A�]�ƈ��͎������Z�\���������x���������B �Q�D�R�c�E�h�b�s�v�V�̏Ռ� �p�\�R�����O�����ł̏���\�͂��l������悤�ɂȂ�ƁA�p�\�R����ʏ�őn����T�C�o�[���E�ƁA�l�Ԃ����Y�������s�������̐��E�Ƃ����ꎟ�������邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B�O�����ł̃R���s���[�^�����p�����v�Ɛ��Y�iCAD/CAM�j���p�\�R���E���x���ł������ł���悤�ɂȂ������ƂŁA��Ɗԕ��Ƃɂ���ČX�̊�ƂŐ��Y���ꂽ�e�p�[�c��R���|�[�l���g�����邽�߂̒����i���肠�킹�j�̏d�v���͑��ΓI�ɒቺ�����B�Ȃ��Ȃ�A�e�p�[�c�����i�ɂ��܂��K���ł��邩�́A�O�����̐v�}�ʏ�ŌJ��Ԃ��V�~�����[�V�������邱�Ƃ��ł��邩��ł���B�܂��A���v�̎���ɂ͕K�{�ł���������i������ȗ��ł���P�[�X�������Ă���B�O�����ł̋@�B���H���s���}�V�j���O�E�Z���T�[�iMC�j�𐧌䂷��R���s���[�^�[�̔\�͂��}���ɐi���������Ƃɂ����MC�̎������䐸�x���i�i�Ɍ��サ�A����܂ł͏n�������Z�\�H�ł��������ł��Ȃ����������x���H�����n�����x���̃I�y���[�^�[�ł����s�\�ƂȂ����B ����ɁA����܂ł͐l�Ԃ̎��o�@�\�͕��G�ł��̉摜�����\�͂��R���s���[�^�[�ɂ���đ�ւ��邱�Ƃ͍���ł��������A�Q�O���I���ɂȂ�Ɛl�Ԃ̖Ԗ��@�\���ւ���悤�ȍ��掿�A�����ǂݎ��\�͂����b�b�c�Z���T�[��b�l�c�Z���T�[���J�������悤�ɂȂ����B�����̍��@�\�̃C���[�W�E�Z���T�[�́A�X�`�[���J������r�f�I�J�����ɗp����ꂽ�����łȂ��A�e��̐����ݔ��A�Ƃ�킯�A����܂œ���ɗ����Ă��������H�������������鑕�u�Ƃ��ėp������悤�ɂȂ����B���@�\�̃C���[�W�E�Z���T�[��g�ݍ��������u�̓����ɂ���āA�����H���̏ȗ͉����}�������łȂ��A����ł͌����Ƃ������Ȕ��ׂȕs������o���邱�Ƃ��\�ɂȂ����B���̌��ʁA���x�ȕi���Ǘ����A�p�b�T�[�N�����ɂ��Ȃ��Ă������ł���悤�ɂȂ�A���{���i�̈��|�I�ȕi���ɂ��D�ʐ������ΓI�ɒቺ�����B �܂�A�Q�O���I���ȍ~�̃f�W�^���Z�p�̔��W�́A�n���Z�\��l�Ԃ̌܊�������ւ���i�K�ɓ��B���Ă���B �Q�O���I���ɂȂ�ƁA�C���^�[�l�b�g�̐��E�ł��v���I�ȕω����N�����B���t�@�C�o�[�E�P�[�u���Ԃ̕��y�ɂ���āA���b�P�O�O���K�E�r�b�g�̑���M���\�ƂȂ����B���̌��ʁA�O�����v�}���ʂ̃f�[�^���u���ɁA�������A�قƂ�ǒlj��I��p�Ȃ��Ő��E���ɑ���M�����悤�ɂȂ����B���̂��Ƃ́A���E���ɏ���`�B���邽�߂̐_�o�n���������������Ƃ��܈ӂ��Ă���B�܂�A�p�\�R�����O�����̏���\�͂��l���������ƁA�l�Ԃ̋Z�\��ꊴ���f�W�^���Z�p�ɂ���đ�ւ����悤�ɂȂ������ƁA�C���^�[�l�b�g���O�����̉摜��̑�e�ʏ��𐢊E���ɏu���ɓ`�B����_�o�n���̖������ʂ����悤�ɂȂ������Ƃ��A3D�EICT�v�V�̖{���I�����ł���B3D�EICT�v�V�́A�Q�O���I���ɐ�i�o�Ϗ����ŕ��y�������A�Q�P���I�ɓ���ƁA���W�r�㏔���ɂ܂ŕ��y����悤�ɂȂ�A���ۋ�������傫���ϖe������悤�ɂȂ����B �R�D���i�]�ŗ͂̒ቺ �Q�O�O�O�N�㔼�܂ł͋��x�Ȕi�I�����͂��ێ����Ă������{�̎�v�A�o�Y�Ƃł���A���p�@��́A�Q�O�O�O�N��㔼�ɂȂ�ƁA�i���D�ʐ��̒��x�́A���O���̃��C�o���E���[�J�[�̕i������ɂ���đ��ΓI�ɒቺ�����B���̂��߉~���̉e����A�o���i�����グ�ɂ���ē]�ł��邱�Ƃ�����ƂȂ��Ă���B �S�D���{�Ԃ̕i���]���ቺ �T�D���Y�Z�p�̍��ۊg�U ���̗v���́A���Y�Z�p�̑����������\�̃f�W�^�������ꂽ���Y�ݔ��ɂ���đ�ւ��ꂽ���Ƃɂ���āA���Y�Z�p�̍��ۈړ]�������߂�ꂽ���Ƃł���B���ē��{�̐��Y�Z�p�͈Öْm�̕����������A�Z�p�҂�Z�\�Ҍl�ɑ̉�����Ă��邽�߂ɁA���̐��Y�Z�p�̊g�U�͂�������������ƂɌ��肳��Ă����B���̂悤�ɁA���{�̎Y�ƎЉ�ɌŗL�ō��ۈړ]�����Ⴂ�Ƃ������Y�Z�p�������A�Q�O���I���܂łɓ��{�Y��p�̎����I�ȍ��ۋ����͂Ɋ�^���Ă����ƌ�����B�Ƃ��낪�A�Öْm������Ă����Z�\�̂��Ȃ�̕��������Y�@�B�̍��x�Ȕ��B�ɂ���ăf�W�^��������A���ۈړ]���̍����`���m�������ɂȂ������߂ł���B ���ɁA��i�I�Ȑ��Y�@��������Ă��Ă���ւ���Ȃ��Öْm�ɂ��ẮA���{�̋Z�p�҂�n���J���҂ڌٗp���邱�Ƃňړ]���悤�Ƃ��錻�n��Ƃ��A�؍��A��p����łȂ��A������^�C�ł��������Ă���A���{�l�Z�p�҂�n���J���Ҏ��v�����A�W�A�S��ō��܂��Ă���B�����ɓ��{�l�Z�p�҂�n���J���҂̌��n��Ƃւ̋����𑣐i����v�����P�X�X�O�N��ȍ~���܂��Ă���B���{�A�o�Y�ƁA�Ƃ�킯�A���d�C�E�d�q�@�탁�[�J�[�͂X�O�N��ȍ~�A�����I�Ȍo�c�s�U�ɂ���đ�K�͂ȃ��X�g�������{���Ă����B�������Ď�������ق��ꂽ�]�ƈ����V���Ȍٗp������n��Ƃɋ��߂��̂ł���B ��O�ɁA���Y�Z�p��Z�\�W��^�Y�Ƃł̊C�O��ƂƂ̍��َ��Ƃ�A�Z�p��g�̑����ɂ�鐶�Y�Z�p�̍��ۈړ]���i�W���Ă��邱�Ƃł���B����������g��ʂ��āA���n��Ƃɓ��{��Ƃ���Z�p�҂�Z�\�J���҂��h������Ă���B���ے�g�̑��������Y�Z�p�ړ]�̏d�v�ȃ`���l���ƂȂ��Ă���B ��l�ɁA����܂Œ��ԍ����[�J�[��Y�ݔ����[�J�[�̑����́A���{��Ƃ̐��Y�n��P���ɂ���A�n��O��Ƃւ̔̔�������Ă����B�������A�P�X�X�O�N��ȍ~�ɂȂ�ƌn���̂̓��������܂����̎��R�x�����������߁A���ԍ����[�J�[��Y�ݔ����[�J�[�͊C�O��Ƃւ̔̔����g�債�n�߂��B���̔w�i�ɂ́A�����̊����i���[�J�[�̐����݉��ɂ���āA�n�[�J�[����̍w�������������Ƃɂ���B�܂��A�t���e���r�̂悤�ɐ��i�C�m�x�[�V�����ɂ���āA�]���̃A�i���O���i�̎���Ƃ͈قȂ������ԍ���Y�ݔ��T�v���C���[�ւ̎��v�����������B���������V���ȃT�v���C���[�͏]���̌n��P���ł͂Ȃ����߁A�C�O��Ƃɂ����R�ɂ��̐��i�������ł����B�t���e���r�┼���̐��Y�ɂƂ��Đ��Y�ݔ��̐��\�͋����͂ɒ�������B���{�̐��Y�ݔ����[�J�[�́A�X�O�N�㖖�ȍ~�ɋZ�p�J���ɂ���Ă��̐��i�̍����\������i�Ɛi�W���������A���{�̃��[�J�[�͐ݔ������ӗ~���₦����ł���A���������ŐV�s�̍����\�@��͓��{��Ƃ����؍��E��p�Ȃǂ̓��A�W�A�n��̊�Ƃɂ���ĐϋɓI�ɓ������ꂽ�B���̌��ʁA�����̊�ƂŔ����̐��Y�┖�^�e���r�̍��ۋ����͂����܂����B �U�D���W���[�����ƃA�W�A�n�d�l�r��Ƃ̑䓪 �d�q�@��Y�Ƃł̃��W���[�����͕��i�̌݊����Ɛ��i�̕W������i�W���������A���̂��Ƃ͓����ɐ��i���x���ł̍��ʉ��̗]�n���傫�����܂������Ƃ����܈ӂ��Ă���B���̌��ʁA�p�\�R����I�[�f�B�I�@�퓙�ł̓u�����h�Ԃł̐��i���ʉ�������ɂȂ��Ă���B �d�q�@��̃��W���[�����̐i�W�́A���i�Ԃ̐����Z�p�̓Ǝ����������������Ă���B�Ⴆ�A���W���[�������i�W����ȑO�ł́A�p�\�R���Ɠd�b�@���邢�̓r�f�I�Q�[���@�̐����H���͂��ꂼ�ꑊ�Ⴊ����A��Ƃ͂��ꂼ��̐��i��ʌ̍H��Ő������Ă����B�Ƃ��낪�A���W���[�������i�W����Ƃ����������i�Ԃ̐����H���̍��ق͑啝�ɋ��܂�A������ʌ̍H��Ő��Y����Ӗ��͂Ȃ��Ȃ�A���Y�H��̓������i�W�����B���̌��ʁA����܂œ���̐��i�Y����H�ꂩ��d�������Ă�������������Ƃ̂Ȃ��ɂ́A�e�H��̓����ɍ��킹�Đ����������ꂽ���̂����Ȃ��Ȃ��B ���W���[�����̐i�W�ɔ����ĂP�X�W�O�N��ɓ���ƁA���Y�H���̈ꕔ�𐿂������`���I�ȉ�����Ƃɑ����āA�d�q���i�̐v����ŏI�g�ݗ��Ă܂ł��K�͂ɐ��������d�l�r�iElectronics Manufacturing
Services�j�ƑԂ��o�ꂵ�A�d�q���i�̐��������������d�l�r��ƂɈꊇ���������悤�ɂȂ����B�Q�P���I�ɓ���ƁA�d�q���i����ł͔̔��ʂ��̔������ɂ���Ă̂��܂�Ƃ����A��ʏ��i�i�R���f�B�e�B�j������w�i�ݐ��i���i�ቺ�����������B���̂��߂d�l�r��Ƃ͑啝�ȃR�X�g�팸�v���ɒ��ʂ���悤�ɂȂ�A�l����̍�����i�����ł̐��Y�ł͍̎Z���m�ۂ��邱�Ƃ�����ƂȂ����B�܂��A�f�W�^�������ꂽ���Y�@�킪��荂���\�����@�퉿�i�������������߁A�����ɋ���K�͂̐��Y�q��Ђ�L����A�W�A�n�d�l�r��Ƃ��}���ɑ䓪����悤�ɂȂ����B �d�l�r��Ƃ͂Ȃ����̂悤�ɋ}���Ȑ����������������̂ł��낤���B�܂����ɁA�d�q�@��Y�Ƃł̃��W���[�����̐i�W�ɂ���ēd�q���i�̐����v���Z�X���A���[�J�[��@�킪�قȂ��Ă����������������߁A�����̃��[�J�[������Ă����Y���C����傫���ύX����K�v�����Ȃ������I�ɐ��Y���s�����Ƃ��ł��邱�Ƃł���B�������A���琶�Y�E�o�ׂɎ���S�H�����ŐV�̏��ʐM�Z�p�ɂ���ēI�m�ɊǗ�����邽�߁A�K�͂̌o�ϐ����ő�������ł���悤�ɂȂ��Ă���B����ɁA���Ⴂ�̑�ʎɂ���Ĕ����̓��f�o�C�X�̎������B�ɂ����ċ����o�C�C���O�E�p���[���t�^����A�L���ȉ��i�Ŏ��ނB�ł��邱�Ƃ��R�X�g�����͂����߂Ă���B �V�D��Ռ^�Y�Ƃ̒��� �W�D���x�����钆���̐��Y�Z�p ���������ƁA����܂ňړ]���̒Ⴉ�����Z�\��Öْm���f�W�^��������邱�Ƃɂ���č��ۓI�Ɉړ]�i�g�U�j�\�ƂȂ������ƁA�Ƃ�킯�A�O����CAD/CAM�̓����������x�Ȑ�[�I���Y�Z�p�ړ]�ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă��邱�ƁA�f�W�^����������ȋZ�p��Z�\�Ɋւ��ẮA���{�E�Z�p��g���邢�͓��{�l�n���Z�\�҂̒��ڌٗp�ɂ���Ĉړ]����Ă���Ƃ����咣���m�F��������̂ł���B �Q�O���I�̎Y�ƊE�ɂ����ẮA���ۋ����͂�������H�Ɛ��i�̐��Y�ɕK�v�Ƃ���鐶�Y�Z�p�̏K�����Ռ^�Y�Ƃ̈琬�ɂ́A�Q�O�N���x�̊��Ԃ��K�v�Ƃ���Ă����B���ہA�펞�o�ω��ł̋@�B�H�Ƃ̋Z�p��Y���p���������{�ɂ����Ă��A�@�B�H�ƕ��傪���ۋ����͂��m���������̂͂P�X�U�O�N��㔼�ȍ~�ł���B�������A3D�EICT�v�V�ȍ~�̐��E�ł́A���Y�Z�p�K���A��Ռ^�Y�ƈ琬�ɕK�v�Ȏ��Ԃ͑啝�ɒZ�k����P�O�N�O��ō��ۋ����ɑς��鐶�Y�Z�p�������m�ۂ�����悤�ɕω����Ă���B �X�D���Y�Z�p�ړ]�Ǝ��{���A�o �����A�؍��ł́A������Ɗ�Ղ̌`���E�������i�W���Ă���A���^�⒒���A�v���X���H���̊�Ռ^�Y�ƕ���ł͗A�o���A���𗽉킷��D�ʎY�ƂւƓ]�����Ă���B�������A�A�o�i�ڂ̍������E���t�����l���ɔ����āA���@�\���ށA�Ⴆ�A�t���e���r�p�̕Ό��t�B�������̗A�����v���g�債�Ă���B�؍����{�́A���{����̗A���ɑ傫���ˑ����Ă��钆�ԍ��̗A����֍H�Ɖ����Y�Ɛ���̏d�_�̈�ɂ��Ă���B�����R�N�͊؍��̗A�o���}�g�債�����ߑΓ��Ԏ��͊g�債�����A�؍����{�̂������������w�͂͏��X�Ɍ������Ă��Ă���B �P�O�D�E�u�����v�͉\�� ���{�Y�Ƃ́A���̋����͂��ێ�����Ă��鍂�@�\�E���i����������������i����ƁA�ߔN�A�o���}���Ɋg�債�Ă��鍂�@�\���ԍ�����ֈ�w�̃V�t�g��}��ׂ��ł���B�܂��A���i�A��×p�@��̂悤�ɍ��t�����l�ł��邪�A�K���i�I�ȓ��������킹�����A���������āA���E�i�C�̕ϓ��Ɏ��v�����E����ɂ������i����A�܂�A�K���I���t�����l�Y�ƕ���̍��ۋ����͊m����D�悷�ׂ��ł���B���������o�C�I�֘A�Y�Ɠ��̍��t�����l�Y�ƕ���ō��ۋ����͂����߂�ɂ́A���̋����͊�Ղł���m�I���Y�v�f�����\�͂����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��i�����́A�������ĎY�Ƃ̒m�I���Y������ɍł����͂��Ă���B ���{�����̎Y�Ƃ́u�����v��������邽�߂ɂ́A�����i����A���@�\���ԍ�����A�Ƃ�킯�K���I���t�����l�Y�ƕ���ō��ۋ����͂��������邱�Ƃ��A�قƂ�ǗB��̓��ł���ƍl������B����ɂ́A����܂ŕ��I���Y�ō�����ƊԐ��Y����B�����Ă������{�̕��ƃV�X�e���́A�m�I���Y�ʂł̊�ƊԐ��Y�������߂邱�Ƃ��s���̏����ł���B
��1�́@�����͊�Ղƍ��ە��� �P�D���ۋ����͂̃����L���O �Q�D�`���I�f���_ �P�W�P�V�N�̃f�r�b�g�E���J�[�h�́w�o�ϊw����щېł̌����x�ɂ����āA���Ƃ����Y�R�X�g�̖ʂŐ�ΓI�ȗD�ʂȎY�Ƃ��Ȃ��Ă��A���ΓI�ɗD�ʐ���������ە��Ƃ̗��v�����݂��邱�Ƃ��������B���̔�r�D�ʘ_�ɍ��{�I�C�����������̂��A�w�N�V���[���I���[���̍��ە��Ƙ_�ł������B�e���̐��Y�v�f�i�y�n�A�J���A���{�j�̕��^��Ԃ̑��Ⴊ���ە��Ƃ̗v���ł��邵���B�����A���鐶�Y�v�f�A�Ⴆ�ΘJ�����L�x�ɕ������Ă��鍑�ł͂��̓����R�X�g�ł���������͒Ⴍ�Ȃ邩��A�J���Ƃ������Y�v�f�𑽂���������ނ̐��Y�R�X�g�͒Ⴍ�Ȃ�B���̂��ߘJ���W��^�Y�Ƃ���r�D�ʎY�ƂɂȂ�Ɛ��������B �R�D�Y�Ɛ��f�ՂƐV�f�_ �|�[���E�N���[�O�}���́A�P�X�V�X�N�ɋK�͂̌o�ϐ������鐶�Y�K�͂̑傫�Ȋ�Ƃ��A�K�͂̌o�ϐ��������Ȃ���Ƃ𓑑����ēƐ�I������ԂƂȂ邱�ƁB�����č����s�ꋣ���ŏ����c������Ƃ͐��Y�K�͂�����Ɋg�傷�邱�Ƃɂ���āA���̐��Y�R�X�g���A�o�ɔ����A����p�����������Ă��Ȃ����ۓI�ȉ��i�����͂��l���ł���܂łɒቺ�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����B�܂�A�f�Ղ́A�Z�p��Y�v�f�����̍��ۓI�ȑ����K�v�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A����ɑւ���āA�f�Ղ͒P�Ɏs����g�債�K�͂̌o�ϐ�����������̂ł���A���̖f�Ղ̌��ʂ͘J���͂̑����y�ђn��I�ȎY�ƏW�ς������炷���ʂƓ��l�ł���B����ɁA�N���[�O�}���͂P�X�W�O�N�ɁA����Y�Ɠ��ō��ۖf�Ղ��s���闝�R�Ƃ��āA���R�f�Ղɂ���Ďs��K�͂��g�債�A���Y�K�͂���w�g�債���A�o��Ƃł͂��̐��i���C���𑽗l�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�����A�o�ϐ����ɂ���ĖL���ɂȂ�������҂́A���ʉ�����o���G�e�B�ɕx���i�Q�̒�����I�����邱�Ƃɂ��傫�Ȍ��p�悤�Ƃ���悤�ɂȂ�B���̌��ʁB����҂͓���̏��i�Q�̒�����A�w�����鏤�i�ł����Ă��A�A�����ꂽ���i�Q�ƍ������[�J�[�̏��i�Q�̒�����A�w�����鏤�i�����R�ɑI������悤�ɂȂ�B���̂悤�ɓƐ�I�����Ɛ��i���ʉ��Ƃ������̐�i���Ԗf�Ղ̎嗬�ł���Y�Ɠ��f�Ղ̗v���ł���Ƃ����B���̗��_�͓��荑�̑��Ƃɂ���Đ��Y���ꂽ���i���f�Վs����x�z����\�����������Ă���B �S�D��ƊԐ��Y���i���Ɓu�V�X�f���_�v �܂��A����Y�ƕ���ɑ������Ƃł����Ă��A�A�o��C�O���ړ������s���Ă��鍑�ۉ����ꂽ��ƂƁA�A�o��C�O���ړ������s���Ă��Ȃ��ۉ���ƂƂ��������Ă��鎖����������闝�_�Ƃ��ĐV�X�f���_���o�ꂵ���B�����b�c�͂Q�O�O�R�N�ɁA����̎Y�Ɠ��ɐ��Y���̈قȂ����َ��Ȋ�Ƃ����݂��邱�Ƃ�O��ɁA���Y���̍����ɂ���č����s��ɐ��i�����������ƂɂƂǂ܂���̂ƁA�A�o���s����ƂƂɕ�����A���Y���̍ł��Ⴂ��Ƃ͑ޏo��]�V�Ȃ������Ƃ���f�Ճ��f�����N�����B���̂悤�ɐ��Y���̍�����Ƃ������A�o��Ɖ����闝�R�Ƃ��āA�����Y����Ƃ������A�o�`���l���`�����ɕK�v�Ƃ����Œ�I�ȗA�o�R�X�g���x�������Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B ���̂悤�ɐV�X�f���_�ł́A��Ƃ̐��Y���i�������ۉ���ƂƔۉ���ƂƂ����������v���Ƃ��Ă���B�������A�����̗��_�ł͗A�o��Ƃ̐��Y������A�o��Ƃ̐��Y���ɔ�r���č����Ƃ����������m�F���Ă��邪�A��ƊԂ̐��Y���i�����ǂ̂悤�ȗv���ɂ���Ĕh������̂��ɂ��ẮA���ړI�ɂ͘_�����Ă��Ȃ��B �T�D�V�X�f���_�̎��،��� �U�D�����͊�ՂƐ��Y�� �i�P�j�}�C�P���d.�|�[�^�[�̋����D�ʐ� ���ۋ����͂̍����ƍ��ە��ƃp�^�[���̌���v���͂���ꍇ�ɍł��d�v�ȉۑ�́A���ۓI�ȋ����D�ʂ��l������ꍇ�ɍł��d�v�ȉۑ�́A���ۓI�ȋ����D�ʂ��l�����邱�Ƃ��ł���悤�ȍ����t�����l���Y�����A�ǂ̂悤�ȃ��J�j�Y���őn��o�����̂��Ƃ������Ƃł���B�܂��A���̍����t�����l���Y����n�o���Ă����v�����A�ǂ̂悤�ȍ��ۓI�ȋ������ω��ɂ���ĕώ�����̂��B����ɂ́A�ω��������ۋ������ɓK�����邽�߂̏����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł���B �}�C�P���d.�|�[�^�[�͂P�X�W�T�N�́w���̋����D�ʁx�ɂ����āA�����͂��L���o���l�̗v���ł���u�v�f�����v�u���v�����v�u�֘A�Y�ƁE�x���Y�Ɓv�u�N�Ɛ헪�y�ы������v�������A�ނ��_�C�������h�ƌĂԐ}�̊e���_�Ɉʒu���A���ꂼ�ꑊ�݂Ɋ֘A���邱�Ƃ���������Ă���B �|�[�^�[�̋����D�ʘ_�ł́A�e�v�����ǂ̂悤�ɂ��ē��荑�̎Y�Ƃ̍��ۋ����͂����߂邩�ɂ��Ă͖��m�Ɏ�����Ă���B�������A���ꂼ��̋����v�����ǂ̂悤�Ȍo�܂ŕҐ����ꂽ�̂��A�܂��A���ꂪ�ǂ̂悤�ȗv���ɂ���ĕϑJ����̂��ɂ��Ă͂قƂ�ǐ�������Ă��Ȃ��B����ɁA�������������v��������̎Y�Ƃɑ������Ƃɋϓ��Ɋ�^���邱�Ƃ��Öق̑O��ɂȂ��Ă���悤�ł���B �i�Q�j�����͂̕��w�\�� ��X�̕��͂́A��Ƃ̍��ۋ����͂́A��ƌŗL�̋����\�͂ƁA�Y�ƃ��x���̋����͂̓�w����`������Ă���B�Y�ƃ��x���̋����͂́A���ɁA���Y�Y�Ƃɂ������Ɗԕ��Ƃɂ���Ď���������ƊԐ��Y���̍����ł���A���ɁA���Y�Y�ƂɕK�v�Ƃ���鐶�Y�v�f�i���{�A�J���́j�̎������߂�v�f�����V�X�e���Ɉˑ����Ă���B�]���āA�Y�Ƃ̋����͊�Ղ́A���̊�Ɗԕ��ƃV�X�e���Ɛ��Y�v�f�����V�X�e������\������Ă���B �����͊�Ղ͂��̒n��i���j�ɗ��n���邷�ׂĂ̊�Ƃ����p�\�ł��邪�A���̊�Ղ��狟��������ƊԐ��Y��������ʂ��ǂ̒��x����ł��邩�͊�Ƃ��ƂɈقȂ��Ă���B�܂�A�����͊�Ղ���̎�v����������Ƃ́A���̊�Ƃ̑������\�͂����߂邱�Ƃ��ł��邪�A�����͊�Ղ�L���Ɋ��p�ł��Ȃ���Ƃ́A���̌��ʂ���Ƃ̑������\�͂ɏ����������f���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂悤�ɁA�Y�Ƃ̋����͊�Ղ������炷���ʂ́A�e��Ƃ̎�v�\�͂ɂ���ĐL�k���Ă���B �����A��ƌŗL�̋����\�͂́A���̊�Ƃ����Y���鐻�i�̍��ʉ��̒��x�ɂ���ċK�肳��Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����I�s��ł͓����I�ȏ��i�͌��������i�����Ɋ������܂�āA���E��p�ȏ�̉��i���ێ����邱�Ƃ�����ł��邩��ł���B���i���ʉ�����������̂͊e��Ƃ̃C�m�x�[�V�����\�͂ł��邪�A����͊e��Ƃ̕ێ�����m�I���Y�̒~�ϓx�Ɉˑ����Ă���B�]���āA���ۉ��ɂ���ċK�͂��g�債����Ƃ́A���̒~�ς����m�I��Y��lj���p�Ȃ��ɗ��p�͈͂��g��ł��邩��A���̊�Ƃ̐��Y���͈�w���シ�邱�ƂƂȂ�B �܂��A���ۋ����͂���ƌŗL�̋����͂ƎY�ƃ��x���̋����͊�ՂƂ̕��w�\������c�����鎎�݂́A��ƃ��x���ł̍��ۉ��͂����茻���I�Șg�g�݂ł������łȂ��A�Y�ƊԖf�Ղ̐����ɂƂ��Ă��L�p�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�����͊�Ղ���h�������ƊԐ��Y���̍����́A�����ƂɁA�܂��Y�Ƃ��ƂɈقȂ��Ă���A��ƊԐ��Y���������Y�Ƃ��A�o�Y�Ɖ����邩��ł���B�܂�A���鍑�̎Y�Ƃ����ۋ����͂����߂ėA�o�Y�Ɖ����ĂƂ������Ƃ́A��ƌŗL�̋����\�͂ƂƂ��ɁA���̎Y�ƃ��x���Ŋ�ƊԐ��Y�������ۓI�Ȑ����ȏ�ɍ��܂������Ƃ��Ӗ����Ă���B �i�R�j���ۋ������Ƌ����͊�Ղ̑��݈ˑ� �݂鍑�̋����͊�Ղ���h��������ƊԐ��Y���̌��ʂ́A�����ɂ킽���Ĉ���I�ɐ��ڂ�����̂ł͂Ȃ��A���̗L�����͍��ۓI�Ȋ��ω��ɂ���đ傫���ϓ����Ă���B�ߔN�A���{�̃��m�Â���\�͂ɉA�肪������̂́A���{�̋����͊�Ղ̎�v�ȍ\���v�f�ł��鉺�����ƃV�X�e���ɂ���Ď�������Ă���������ƊԐ��Y�����A3D�EICT�v�V�Ƃ������ۊ��ω��ɂ���đ��ΓI�ɒቺ�������ʂł�����B ���ۓI�ȋ������ω��́A�Z�p�̌n�̑傫�ȕϊv�⍪�ؓI�Ȏs��i���v�j�\���̓]�����ɂ���Ă����炳��邪�A���̍��ۋ������ω��͊e���̋����͊�Ղ�ω������A����͊e���Y�Ƃ̊�ƊԐ��Y����ω������邱�Ƃ�ʂ��āA���̎Y�ƕʂ̍��ۋ����͏���ɕω���^����B���ە��ƍ\���͊e���̎Y�ƕʂ̍��ۋ����͏���̏W���ł��邩��A�e���̋����͏���ω��͍��ە��ƍ\���ω��������炷�B���ە��ƍ\���ω��́A�����ɍ��ێs��\���̕ω��𑣂�����A�Ăэ��ۋ������ω����B���̂悤�ɁA���ۋ������ω��A���������͊�ՁA���ە��ƍ\���͑��݂Ɋ֘A���A�ݐϓI�ȉe���������炷�̂ł���B 7�D�ڍs�o�ύ��̈�����Ɗ�� �����ƃ��V�A�́A���ꂼ��s��o�ϑ̐��Ɉڍs���ĔN�����o�߂����B���̊ԁA�����͍��x�ɐ��������I�Ȋ�ƌo�c�����߁A������Ɗ�Ղ̐����ɒ��͂��Ă����B���_����q�ׂ�ƁA�����o�ς͑��푽�l�Ȏx���Y�Ƃ�֘A�Y�Ƃ��Ɛ����A���łȈ�����Ɗ�Ղ̌`���ɐ����A�H�Ɛ��i�̋��łȍ��ۋ����͂��l�������B�����B���V�A�ł́A�x���Y�ƁE�֘A�Y�Ƃ̔��W���i�W�����A�ˑR�Ƃ��Đ��������I�Ȑ��Y�V�X�e����ϊv�ł����ɂ���B���̌��ʁA�H�Ɛ��i�̍��ۋ����͂͐Ǝ�Ȃ܂܂ŁA���V�A�̖f�Ս\���́A�H�ƕ���̍��ۋ����͂��Ǝ�ȊJ���r�㍑�̍\���ɗގ����Ă���B ���̂悤�Ƀ��V�A�o�ςŁA������Ɗ�Ղ̌`�����e�ՂłȂ��̂́A�@�Љ��`�v��o�ϑ̐����V�O�N�Ԃ��������A�s��o�ς��o���������オ���݂��Ȃ����ƁA�A�n���i�ȁj�����I�Ȍo�ϓ����V�X�e���̒����ƈقȂ��āA�����ňꌳ�I�Ȍo�όv��E���������{����Ă������ƁA�B�����ł̈ꌳ�I�o�ϓ��������s���邽�߂ɓ������ׂ���Ɛ���O��I�Ɍ��炷�K�v������A�قƂ�ǂ̋Ǝ�łP��Ƃ��琔��ƂɏW��Ă������ƁA�C���̌��ʁA��ƋK�͂����剻���A�֘A�Y�ƕ����������������x�Ȑ��������^�̐��Y�̐��ƂȂ������Ƃ��グ����B�\�r�G�g�A�M����A�e��Ƃ��֘A�Y�ƕ���܂ŋ��剻�����w�i�ɂ́A�v��o�ς̂��ƂŁA�e��Ƃ��K�v�Ƃ���l�X�Ȓ��ԍ��͌v�擖�ǂ̎w���ɂ���Ĕz������錚�O�ł��������A�����ɂ͒��ԍ���Y�ݔ��̔z���͕s�\���ł���A�܂��A�����Βx���������Ƃ���������B���̂��߁A�e��Ƃ͂��̐��Y�ɕK�v�Ȓ��ԍ��⎡�H�����łȂ����Y�ݔ���������Ɠ����Ő�������悤�ɂȂ�A�����ɒ���ȃT�v���C�E�`�F�[�����`�������B�e��Ƃɓ��������ꂽ�T�|�[�e�B���O�E�C���_���X�g���[����͂��̊�Ƃɂ̂ݐ��i������������̂ł���A���̐��Y�K�͂͏������Z�p�i���������Ă����B���̂��ߐ��Y���͒�ʂɂƂǂ܂��Ă����B�������A��������A���������^�̋���Ȋ�Ƒ̐����m�������o�ςŁA�T�|�[�e�B���O�E�C���_�X�g���[�����S����Ƃ��琬���邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B �����A�����ň�����Ɗ�Ղ���r�I���₩�Ɍ`�����ꂽ�w�i�Ƃ��ẮA�ȉ��̌܂���������B�@�Љ��`�v��o�ς̊��Ԃ��R�O�N�ƃ��V�A�ɔ�גZ���A�s��o�ς��o���������ォ���������Ă������ƁB�A�\�r�G�g�̂悤�ȋ��͂Ȓ����W���I�v��o�ςł͂Ȃ��A�e�n��i�ȁj�ɂ��Ȃ�ٗʌ����c�����n�敪���I�v��o�ςł��������ƁB�B�_�����͐l�����Ђ𒆐S�Ƃ������������I���Y�̐��ŁA���̌��Ђ��K�v�Ƃ���_�@���엿����шꕔ�̏�����Y���Ă������ƁB���̐��Y��S�����̂��l�����Г��̎Б���Ƃł���A�Б���Ƃ͏㕔�@�ւ̖��߂ł͂Ȃ��A���Ȃ�Ǝ��Ȍo�c�Ǘ����s���Ă���������������I�Ȍo�c�Ǘ��̌o�������v�J����ɔ_���n��Őݗ����ꂽ������Ɓi������Ɓj�̌o�c�Ɋ������ꂽ�B�C�Љ��`�v��o�ώ���ɐݗ����ꂽ���L��Ƃ́A�����̐��Y�H����������������������^�̐��Y�̐��ł��������A���\�A�̌v��o�ςƂ͈قȂ��āA����Ǝ��Ƃ���������邱�ƂȂ��e�n�ɑ����̒����K�͊�Ƃ����݂��Ă������Ƃ��s��o�ψڍs��̒����@�B�H�Ƃɂ������Ɗԕ��ƃV�X�e���\�z�Ɋ�^�����B�D�A���o�o�E�h�b�g�R���̂悤��B to B����T�C�g�^�c��Ƃ��}���ɔ��W�������Ƃɂ���āA��ƊԎ��������������̂ɕK�v�Ȏ���l�b�g���[�N���`�����ꂽ���Ƃ��A�����̈�����Ɗ�Ղ̔��W�Ɋ�^���Ă���B���̈Ӗ��ŁA3D�EICT�v�V�́A�����̐��Y�����Ɋ�^��������łȂ��A��Ƒ��ŕ��Ƃ��ꂽ���̂����邽�߂̎���V�X�e���̔��W�ɂ���^���Ă���̂ł���B �W�D������ƂƊ�ƊԐ��Y�� ��X�́A���Ƃ�S����ƊԃV�X�e���̂�����A�܂�A��ƊԂ̏�L�̂�������ƊԂ̌����W�A����ю������i�K�o�i���X�j���J�j�Y���̓��ِ����A�ǂ̂悤�ɍ���Y�Ƃ̍��ۋ����͂����߂�̂��ɏœ_�����킹�Ă���B�܂�A��ƊԐ��Y�V�X�e�����A���I���Y����ђm�I���Y�̐��ʂł����炷������ƊԐ��Y���̋N���A���ۋ����͂ɋy�ڂ����ʁA����т��̕ϑJ�ɊS���W�����Ă���̂ł���B ���̊�ƊԐ��Y���́A��{�I�ɂ͑����̐��Y�𑽐��̊�Ƃɂ���ĕ��S��������Ƃ�������o�������ʂł���B���Ƃɂ����ʂ́A�A�_���E�X�~�X�ɂ���āw�������̕x�x�̌���ł���Ǝw�E����Ă���B�����āA��̓I�ȕ��Ƃ̌��ʂɂ��āA���Ƃɂ���ē����l�������������̐��Y�ʂ��啝�ɑ�������̂́A�O�̗v���̂��߂ł���B���ɁA�X�l�̋Z�\�����シ��B���ɁA��̎�ނ̍�Ƃ���ڂ�ۂɕK�v�Ȏ��Ԃ�ߌ��ł���A��O�ɁA�����̋@�킪��������d�����e�ՂɂȂ�A���Ԃ�ߖ�ł���悤�ɂȂ��āA��l�ʼn��l�����̎d�����ł���悤�ɂȂ�B����ɁA����ɂ����Ċ�ƊԐ��Y�������߂��ł��d�v�Ȗ������ʂ����Ă���̂́A���ƃV�X�e�����\�������ƊԂŁA���i�m�I�j����n�o�����L���郁�J�j�Y���ł���B�Ȃ��Ȃ�A�����̐�i�o�Ϗ����ɂ����鍑�ۋ����͂́A�����I�ȃC�m�x�[�V�����\�͂����߂邱�Ƃ�����@�ɏd�v�ł���A���̂��߂ɂ͈�����Ɗ�Փ����ɃC�m�x�[�V�����̘A�������������N�������J�j�Y�����g�ݍ��܂�Ă��邩�ǂ������A��ƊԂ̒m�I���Y���̍��������肵�A���̎Y�Ƃ̍��ۋ����͂��K�肵�Ă���̂ł���B �Q�O�O�X�N�̌����ł́A������Ƃ̑��݈ˑ����A�Ƃ�킯����i�T�v���C���[�̏W�ό��ʂ��u�Y�ƃR�����Y�v�Ɩ��t���Ă���B�����Ă��̎Y�ƃR�����Y�̐Z�H���A�����J�̃n�C�e�N�Y�Ƃ̋����͒ቺ�Ɍ��т��Ă���Ƃ����w�E������B���̌����́A�����H���̊C�O�ւ̃A�E�g�\�[�V���O�ɂ���Ƃ����B �P�X�X�O�N�㖖�ȍ~��3D�EICT�v�V�̐i�W�ɂ���ċ����\���͑傫���ϗe���A���Y��Ղ̂����d�v���̒Ⴂ�����I�ȊC�O�ړ]�ł����Ă��A�������������N�������Ƃɂ���āA���Y��ՑS�̂̊C�O�ړ]�Ɍq���鎖�Ⴊ�������Ă���B�Ⴆ�A���{�̃p�\�R�����Y�̂����ŏ��ɊC�O�ɃA�E�g�\�[�V���O���ꂽ�̂͘J���W��I�Ȋ�Ցg�ݗ��Ă̕��������ł������B�������A�C�O�A�E�g�\�[�V���O�͈̔͂͂ǂ�ǂ�g�傳��A�ŏI�I�ɂ͑S�H�����A�E�g�\�[�V���O�����悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�d�q�@��̐��Y�ɕK�v�Ȃ��ׂĂ̐��Y�Z�p���l��������ƁA�Ⴆ�Α�p�̍��C�����H�Ƃ͐��E�ő�̂d�l�r�ւƔ��W���A�p�\�R���Ɍ��炸�����鏑�ނ̓d�q�@��̕�I�Ȏ�����Y���K�͂ɐi�߂Ă���B �X�D�����͊�ՂƂ��Ă̗v�f������� �����������̍����l�ނ��������鋳��V�X�e����Z�p�҂⌤���҂̊Ԃ̒m�I���𗬂������ɂ���q���[�}���E�l�b�g���[�N�́A�n��i���j�ɌŗL�̋����͊�Ղł���A���X�N�E�}�l�[���~���ɋ������A�������������v������������悤�ȃx���`���[�E�L���s�^���̔\�͂����l�ɍ��ۓI�ɖ͕킪�e�Ղł͂Ȃ��n��i���j�ɌŗL�̋����͊�Ղł���B ��Q�́@���ƃV�X�e���]���ƍ��ۋ����� �P�D�P�O�O�N�̎O�x�̑�]�� �P�X�V�O�N�ȍ~�ɂȂ�ƁA�C�^���A����{���̎Y�ƏW�ϒn��i�Y�n�j�Ŕ��W�����A���x�ȋZ�\�J���͂�L�����剻���ꂽ��Ɓi���̑啔���͒�����Ɓj�Ԃ̕��ƃV�X�e�����A���������D�ʐ�������悤�ɂȂ����B����������Ɗԕ��Ƃ̂�������u�_��Ȑ�剻�v�Ɩ��t���A���̏_��Ȑ�剻�������D�ʐ������鎞�����̎Y�ƕ�����Ƃ����A �Ƃ��낪�P�X�X�O�N��㔼�ȍ~�ɂȂ��āA�}���Ȑi���𐋂��Ă����R���s���[�^�[�̐S�����ł���MPU�̔\�͂��M�K�E���x���ɂȂ�ƐV����臒l�ɓ���A�O�����̏���������ʼn\�ƂȂ����B����3D�EICT�v�V�ɂ���Ĉ�����ƃV�X�e���͑傫���]�����n�߂��B������O�̕�����Ƃ���B ����̎���ɂ����Ă��A���ۓI�ȋ����D�ʂ��������A���A�Y�Ƃ���ъ�Ƃ́A���ꂼ��̎���敪�ɂ����ē����I�ȍ��ۓI�ȋ������A����͋Z�p�I���Ǝs��I���ɂ���č\�������A�ɂ����Ƃ��悭�K�����������ƃV�X�e�����\�z���������̂ł���B 2�D���̎Y�ƕ����� �w�����[�E�t�H�[�h�͂���܂Ō��ʂŌ�y�ړI�Ƃ��Č���ꂽ�x�T�w��Ώۂɂ��������Ԕ̔����A��O���K�v�Ƃ���֗��Ȉړ���i�ƈʒu�Â��A��O���w���\�ȉ��i�ł̎����Ԑ��Y��ڎw�����B���̂��߂ɁA���Y�H���̕ϊv�����{�����B�t�H�[�h���Y�V�X�e���̍ő�̓����́A�]���̌Œ萶�Y�����ł͂Ȃ��A�ړ����̑g�ݗ��ă��C�������̗̍p�ɂ������B�����āA���̈ړ������C����p���Ċ�Ɗԕ��Ƃ�O�ꂵ���B�܂��A�s�^�t�H�[�h�͂���܂ł̎����Ԃɔ�r����ƁA�����͂̃o�i�W�E���|��p���邱�Ƃɂ���ċ��x���ێ����Ȃ���y�ʉ�����A�܂��A�������ȑf�����ꂽ�����i���͂���ł��T��_�𐔂����B�������������̕��i�̑啔�����t�H�[�h�H����œ��Ȃ��鍂�x�Ȑ��������^�̐��Y�������̗p���ꂽ�B����́A�]���̂悤�ɐ�啔�i���[�J�[����̍w���Ɉˑ��������Y�ł́A�i���̂�����傫���A�܂��A�t�F�[�h�Ђ̑�ʔ����Ɉ���I�ɃT�v���C���[�����Ȃ��������߂ł���B�t�H�[�h�͓���̕��i���Y�ɐ�p�����ꂽ�H��@�B���ʂɓ������A�܂��A�}�C�N���Q�[�W�K��p���ĕi�����x���m�ۂ��A���i�̌݊������m���Ȃ��̂Ƃ����B ���̎Y�ƕ���������t�H�[�h���Y�V�X�e���̓�����v��ƁA�ړ������Y���C���̗̍p�A���Y�H���̍ו����ɂ���Ƃ̒P�����E�n���J���҂̕K�v���̒ቺ�A���x�ȓ������Ɛ�p�@�B�E�@��̑��p�ł���B ��������A���̎Y�ƕ�����ɂ����āA�d�v�Ƃ���鐶�Y�v�f�́A��ʂ̐�p�@�B�����ɕK�v�Ȏ��{���B�́A��ʂ̔��n���J���͂Ƃ����e�͓I�ɂƂ��ɂイ���邽�߂̌ٗp�V�X�e���A���Y�Ǘ���S������Z�p�҂���ё�ʐ��Y���ꂽ���i��̔�����c�ƒS���҂ł������B �R�D���̎Y�ƕ�����̏I�� �Ȃ��č��^��ʐ��Y�V�X�e�����P�X�V�O�N��Ɍ��E�ɒB���A�V�O�N��㔼�ɂ͓��{�^���Y�V�X�e���������D�ʂ��m���ł����̂ł��낤���B�t�H�[�f�B�Y���̌��E�́A���͂��̌������̌���Ɩ��ڂɊW���Ă���B�܂�A�H����ł̐��Y�������߂邽�߂ɁA�����镔�i����������A�H������Ƃ��Ɍ��܂łɍו������A�e���Y�H���ɂ͓���Ԏ�̉��H�����ɐ�p�����ꂽ�e�퐶�Y�@�킪�p����ꂽ�B�܂��A����J���҂̉ۋƂ��ו�������A�P����Ƃ����S�ƂȂ�n���`����Y����̒m�b�����������ӂ̋@��͂܂������^�����Ȃ������̂ł���B���̌��ʁA���Y�Ԏ�̑��p���͂قƂ�Ǎ���ƂȂ�A���Y�͍��h��̂s�^�t�H�[�h�P�Ԏ�Ɍ��肳�ꂽ�B���̂悤�Ƀt�H�[�h���Y�V�X�e���̌��^�ł́A�Z�p��s��̕ω��ɑΉ����邽�߂̏_����]���ɂ���Ă����̂ł���B���������ٗp�E���ƃV�X�e���̂��Ƃł́A�v���Z�X�E�C�m�x�[�V�����͋N���ɂ����Z�p�i������ؓI�ɂȂ�B�܂��A�Z�p��s��ω��ɐv���ɑΉ������V���i�̊J���E���Y������ɂȂ�B ���̂悤�ɃA�����J�̐��Y�V�X�e�����D�ʐ��������̂́A��ʂœ����I�Ȏ��v������ꍇ�A�܂��A�Z�p�i������鉮���œ��ꐻ�i���Ԑ��Y����ꍇ�ɑ傫�Ȑ��ʂ�B�������B�������A�o�ς�����ɔ��W���l�X�̎��v�����l�����A�Z�p�i���������v���_�N�g�E�T�C�N�����Z�k�����悤�ɋ��������ω�����ƁA���̋����D�ʐ���ቺ�������B�A�����J�^���Y�V�X�e���̋����D�ʐ����ቺ����ɂ�āA�A�����J�̖f�Վ��x�͈��������B �S�D���̎Y�ƕ����� �Z�[�u���̏_��Ƃ́A���Y�v�f�̍Ĕz�u�ɂ���āA���Y�H����₦����������\�͂ł���B�܂��A��Ɓi���̑����͒�����Ɓj�́A���ꂼ���啪��ɐ��Y��������Ă���A���̐��I���Y������S���̂́A�����I�Ȍٗp���s�̂��ƂŌ`�����ꂽ��Ɠ���I�n���Z�\�����Z�\�H�ł���B�����āA�����̐��������������̊�Ƃɂ�镪�Ƃ̃l�b�g���[�N�ɂ���ď_��Ȑ�剻�����������̂ł���B ����ɁA���̏_��Ȑ�剻�̑g�D�I�ȓ����́A���̎Q�������o�[������i�����j����Ă��邱�Ƃł���A�Z�p�v�V�𐄐i����悤�ȋ����͏��コ��邪�A�v�f��p�i�Ƃ��ɒ����ƘJ�������j�̈��������ɂ����Ȃ���Ȃ��悤�ȋ����͐��������B �P�X�V�O�N��ȍ~�A�_��Ȑ�剻�������D�ʐ����m�������Z�p�I�w�i�ɂ́A��啪��ɓ�������������Ƃ̕��ƃl�b�g���[�N���V�O�N�ォ��}���ɋZ�p���i�������R���s���[�^�[����̍H��@�B�i�m�b�H��@�B�j�̕��y�ɂ���āA��w���̏_������߂����Ƃɂ��B�s�I���E�Z�[�u���ɂ��ƁA�R���s���[�^�[�Z�p�̏ꍇ�A���u�i�n�[�h�E�F�A�j����Ƃɍ��킹��ɂ̓v���O���~���O�i�\�t�g�E�F�A�j���g���B���������ĕ����I�ύX�Ȃ��Ʉ��P�Ƀv���O�����̕ύX�ɂ���Ą��@�B��V�����p�r�Ɏg����B���̂悤�Ȏ���̉��ł́A���_�I�Ɍ����āA���Y�ʂ̑����ꍇ�����A���Y�ʂ����Ȃ������A���邢�͒������Y�̕����L���ł���Ǝw�E����B����ɁA�{�i�I�ȑ�ʐ��Y�ł͐�p�@�B�̕����R�X�g�I�ɂ͗L���ɂȂ�A���Y�ʂ����Ȃ��������Y�ɋ߂��悤�ȏꍇ�ɂ́A�蓮�ɂ��N���t�g�I���Y�̕����R�X�g���Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ��w�E���A�m�b�H��@�B��p�������Y�̃R�X�g�́A���i��E�����b�g���Y�ōł������I�ł���Ƃ��Ă���B�܂��A����J���҂̏n���Z�\���A��i���Y�̂悤�Ȏi���Y��m�b�H��@�B�̃v���O���~���O�쐬�Ŋ��������]�n���傫���c����Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B �m�b�H��@�B�̕��y�ɂ���Đ��Y�̏_��͍��܂�A�Z�p�v�V�̉������ɂ���Đ��i�̃��C�t�T�C�N���̒Z�k���������ɂȂ����B�������A���̎Y�ƕ�����ł́A�ˑR�Ƃ��đ�ʐ��Y�ɂ����Ă͐�p�@�B�̃R�X�g�D�ʐ����������Ă���A�����ɁA�N���t�g�I�Z�\���d�v�Ȗ������ێ����Ă���B���ꂪ���̎Y�ƕ�����̋Z�p�ʂł̑傫�ȓ����ł���B �T�D���̎Y�ƕ�����Ɖ����V�X�e�� ���̂悤�ɑ�̎Y�ƕ�����ɂ�����č���ƂƑ��̎Y�ƕ�����ɂ�������{��ƂƂ̃A�v���[�`�̈Ⴂ�ɂ��āA���̂悤�Ȃ��Ƃ�������B�č���Ƃł́A���Y�����̏_����m�ۂ��邽�߂ɂ͐��Y�H����������i�����������j���邱�Ƃ��s���ł���A�O���̃T�v���C���[�ւ̈ˑ��͐��Y�����̏_��ƑΗ��W�ɂ���Ƃ����ԓx�������Ă����B�܂��A���i���Ȑ��i�Y���邽�߂ɂ̓R�X�g�㏸�������������A���i���Ɛ��Y�R�X�g�̊W���Η��I�ł���Ƃ��Ă����B����ɑ��ē��{��Ƃ́A���Y�R�X�g�̒ጸ�͎�v�Ȍo�c�w�W�ł���A�i���Ǘ����������߂邱�Ƃ́A���Y�R�X�g�팸�̎�i�ł���Ƃ��鐶�Y�A�v���[�`��Nj����Ă����B���ہA�i���Ǘ������̌���́A���ʂ̍����ł���s�Ǖi�����������A�̔���̃A�t�^�[�T�[�r�X��p���ጸ�����邱�Ƃ�ʂ��ăR�X�g�팸�̗L�͂Ȏ�i�ƂȂ����B�܂��A�O���̃T�v���C���[�ɐ��Y�H���̑������ˑ����Ă��A�����i���[�J�[�i�A�b�T�Z���u���j�Ɖ�����ƂƂ̊Ԃ̏������I�Ȏ���W�ƔZ���ȏ������Ƃɂ���āA���Y�����̏_������܂葹�Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�O���ˑ��Ɛ��Y�̏_��̊m�ۂƂ́A�č���Ƃ̂悤�ɐ����i�P�W�O�x�j�̊W�ł��Ȃ��A�R�O�x���x�̍��ł����Ȃ��B �U�D3D�EICT�v�V�Ƒ��̎Y�ƕ�����̏I�� �Ƃ��낪�A�Q�O���I���ɂȂ�ƁA���ʐM�Z�p�v�V�̃��x����臒l���x������Ɗԕ��ƃV�X�e���̗D�ʐ�����������h�邪���܂łɂȂ�A���̎Y�ƕ�����̏I���������炵���B 3D�EICT�v�V�ɂ���āA�T�C�o�[��ł��������E�Ɠ��l�ɎO�����Őv�������s�ł���悤�ɂȂ�ƁA�܂��A���ł̐v�ŕK�v�Ƃ��ꂽ����ߒ��̑������ȗ������悤�ɂȂ����B����i�̐����1�i���Y�ł���A�[���͂����Z���Ԃł��������߁A��s�s�ߍx�̒��H��Ƃ̂Ƃ��Ă͗L�͂ȑ�����Ղ̈�ł��������A3D�EICT�v�V�͂�����������i���Y�⎎��p���^�����ɓ�������������Ƃ̑�����Ղ�Ǝ㉻�����B�܂��A�v�}�ʂ����̒i�K�ł͐v�i�K�⎎��i�K�ł芮���i���[�J�[�ƃT�v���C���[�Ƃ̊Ԃł̐��荇�킹���d�v�ł��������A3D�EICT�v�V�i�K�ł͊����i���[�J�[�ƃT�v���C���[�Ƃ͓���̎O�����v��ʂ����L���A���u�n�Ԃł����Ă��T�C�o�[��Őv�̓���������������悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�T�C�o�[��ŌJ��Ԃ��ăV�~�����[�V�������邱�Ƃɂ���ĕs����Ȃ������Ƃ��\�ɂȂ�A���[�J�[�ƃT�v���C���[�Ƃ̐��荇�킹�̕K�v����傫�������������B ����ɁA�O�����̎������H���\�ɂ��鑽�@�\�̍H��@�B�ł���}�V�j���O�E�Z���^�[�i�l�b�j���A�P�X�X�O�N��ȍ~�ɂ͋}���ɕ��y����悤�ɂȂ�A�����ɂl�b�̉��H���x���d�q����@��̔��B�ɂ���đ啝�Ɍ��サ�A�d�オ�萸�x�����~�N�����P�ʂ̉��H�����n���J���ł���������悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�����ٗp��O��ɂ����n���`���̕K�v����ቺ�����A�ٗp�̗������i�s���艻�j�������炵���B �܂��A���̎Y�ƕ�����ł́A���{�̉�����Ƃ͔�����Ƃ̂��ߐ�p�@�B�������s���A���Y���㏸�i�R�X�g�팸�j�ƕi����������Ƃ𗼗������Ă����B���̎�����莑�Y��ۗL���鉺����Ƃ́A�������ł���e��ƂɂƂ��Ă��s���ȑ��݂ł��邩��A���̎���W�Œ艻������������ʂ����Ă����B���������āA3D�EICT�v�V�ɂ���āA������莑�Y�����̕K�v�����ቺ�������Ƃɂ���āA��������W�͗������i�s���艻�j�����߂邱�ƂƂȂ����B���̂��Ƃ́A�����ٗp�W�ɂ��N���t�g�}���V�b�v�Ɗ�ƊԂ̈���I�Ȏ���W�Ƃ����A���̎Y�ƕ�����̋����D�ʂ̑O������̂ł���B ���̎Y�ƕ�����̏I���������炵��������̗v���́A����܂ŏ_��Ȑ�剻�́A�ȒP�ɂ͒n��O�A�Ƃ�킯�A�C�O�ɈڐA�ł��Ȃ����̂ł���A���荑�i�n��j�Y�ƂɌŗL�̍��ۋ����͗v���ƂȂ��Ă����B�������A3D�EICT�v�V�̐i�W�ɂ���āA���x�ȏn���J���̑w�������A�L�@�I�Ȋ�ƊԎ���l�b�g���[�N���`������Ă��Ȃ����i�n��j�ł��A�_��Ȑ�剻�Ɠ��l�̍������Y�����l���ł���悤�ɂȂ����̂ł���B �V�D��O�̎Y�ƕ������ ���̎Y�ƕ�����ł́A��ʐ��Y�̂��߂ɂ͐�p�����ꂽ���Y�ݔ��i��Ɠ��莑�Y�j�������K�v�ƂȂ�B�����āA��Ɠ��莑�Y�͊����i���[�J�[���炪�������s���A�O������T�v���C���[��������莑�Y��K�v�Ƃ���ꍇ�ɂ́A���[�J�[���T�v���C���[�ɑݗ^���邩�A���̓�����p�S����̂���ʓI�ł������B�܂��A���E���ʐ��Y�̂��߂ɂ͏n���H���}�j���A�����삷��ėp�I�Ȑ��Y�ݔ����p����ꂽ�B���̎Y�ƕ�����ł́A��ʐ��Y�̂��߂ɂ́A���̎Y�ƕ�����Ɠ��l�ɐ�p�I�Ȑ��Y�ݔ����p����ꂽ�B�������A�O����̃T�v���C���[����ʐ��Y�̂��߂ɓ��莑�Y������K�v�Ƃ���ꍇ�ɂ́A�T�v���C���[���g��������莑�Y���������s����P�[�X����ʉ������B�܂��A���E���ʐ��Y�ł͂m�b�H��@�B���ėp�I�Ȑ��Y�@�킪�p�����A���Y�̏_��ƘJ�����Y���̌���Ƃ����������悤�ɂȂ����B ����ɑ��đ�O�̎Y�ƕ�����ł́A�O�����ł̊J���E�v���\�ƂȂ�A�����i���[�J�[�ƕ��i�T�v���C���[�Ƃ��������s�I�ɊJ���E�v���s���A���i�v�f�Ԃ́u���荇�킹�v���T�C�o�[��Ŏ��{���邱�Ƃ��\�ɂȂ����B�����āA���������O�����v�}�ʂ͂��̂܂܃}�V�j���O�E�Z���^�[�i�l�b�j�̂悤�Ȕėp�I�Ȑ��Y�ݔ��ɑ����Ăقڎ����I�ɐ��Y���Ȃ����B���̂��ߎ�����莑�Y������ƊԂٖ̋��ȃR�~���j�P�[�V�����̕K�v����傫���ቺ�����A��ƊԎ���W�������������B���Ƒ�O�̎Y�ƕ�����́A���ɑ�ʐ��Y�ɂ����鐶�Y���̔���I�Ȍ���ł���B�����āA���̎Y�ƕ�����ł͐��Y�@��͍��x�ɐ�p������邱�Ƃɂ���āA�n���J���ɑ�ւ��A��O�̎Y�ƕ�����ł́A�f�W�^�����䂳�ꂽ���Y�@�킪�n���J���ɑ�ւ����B���̌��ʁA�����ٗp�Ɋ�Â��n���`���̖������ቺ�������߁A�ٗp�͗����������A���̎Y�ƕ�����Ƒ�O�̎Y�ƕ�����Ƃ̂�����̋��ʓ_�́A��ƊԂŕ��Ƃ��ꂽ���̂�����V�X�e������{�I�ɂ͎s��i���i�j���J�j�Y����ʂ��ĂȂ���邱�Ƃł���B����͑��̎Y�ƕ�����ɂ����ẮA��Ɗԕ��Ƃ������p�������O��ɂ��Ă���A���̎�����������I�ȃ��J�j�Y���ɂ���ē��䂳���̂Ƃ͑ΏƂ��Ȃ��Ă���B���̎Y�ƕ�����Ƒ�O�̎Y�ƕ�����̂R�Ԗڂ̋��ʓ_�́A�O���[�o���K�͂ł̐��Y�g��Ƌ��������ł���B���̎Y�ƕ�����ł́A�d�q�@����͂��߂Ƃ���n�C�e�N�@�B���i�̐��Y�́A���x�Ȑ��Y�Z�p�Ɛ��i�J���Z�p��K�v�Ƃ��Ă���B���̂��߁A���̐��Y�̑����͐�i�o�Ϗ����Ɍ��肳���i�o�Ϗ����Ԃł̋����ɏI�n�����B�������Ȃ���A3D�EICT�v�V�ɂ���āA�n���Z�\��Y�Ǘ��Z�p���f�W�^���Z�p�ɂ���đ�ւ����悤�ɂȂ�A�l�b�g���[�N�̊O�������l�����邽�߂ɐ�i�Z�p�̑��������J����A�Z�p�̕W�������i�W����悤�ɂȂ�ƁA����܂Ő�i�����ȊO�̎Q����j�~���Ă����Z�p�I�ȎQ����ǂ��啝�ɒ�܂�A�V���H�Ə������͂��ߐ��E�I�K�͂ŐV�K�Q�����g�債���B���̌��ʁA�Z�p�W�����m���������i�́A�p�\�R���̂悤�ȃn�C�e�N���i�ł����Ă����i���ʉ��͍���ƂȂ�A���i�ł̎��v�ʂ����肳���s�����i�i�R���f�B�e�B�j�����i�W���A���E�I�K�͂ʼn��i���������������B�R���f�B�e�B���������i�͋}���ȉ��i�ƕt�����l���̒ቺ�ɒ��ʂ���悤�ɂȂ�A��i�o�Ϗ����̊�Ƃ����������R���f�B�e�B�������Y�ƕ���ŗ��v���m�ۂ��邱�Ƃ�����ƂȂ����B���ہA�R���f�B�e�B��������ł��Ȃ���Ƃ͎��v���̒ቺ�ɒ��ʂ��Ă���B���i�̃R���f�B�e�B�����������قƂ�ǗB��̕��@�́A��b�i�K����̌����J���̌����������߁A�v�V���̍����v���_�N�g�E�C�m�x�[�V�������������Đ��i���ʉ���}�邱�Ƃł���B���������āA��O�̎Y�ƕ�����́A���l�̌���Ƃ��Ă̒m�I���Y�~�ς�����I�ɏd�v�ƂȂ�i�K�ł�����B ��O�̎Y�ƕ�����̏d�v�ȓ����́A���̎Y�ƕ�����Ō���ꂽ�悤�ȁA��ƊԘA�g�ɂ��m�I���Y����������A���ړI�ɒm�I���Y�������A���ړI�ɒm�I���Y���l������l���`�i��Ƃ̔����E�����j���I�D�����X�����������Ƃł���B�܂��J���Ҍl�Ԃ̃l�b�g���[�N�̏d�v�����i�i�ɍ��܂������Ƃ��傫�ȓ������Ȃ��Ă���B�Z�p�̃I�[�v�����E�W�����̐i�W�ɂ���āA���̂Â���A�Ƃ��ꊮ���i���x���ł̍��t�����l�����������邽�߂ɂ́A�v�V�I�ȋ@�\���i�i�f�o�C�X�j��V�@�\���������f�ނ̊J�������d�v�ɂȂ��Ă���B�܂��A���̎Y�ƕ�������哱�����g���^�H�Ƃ����A�t�@�C���E�P�~�J���i���i���j�̂悤�ȃv���Z�X�^�Y�Ƃ���荂���t�����l�ݏo������ւƕω����Ă���B�g���^�@�B�H�Ƃ��o�ϐ������哱�������̎Y�ƕ�����ł́A��ƊԂ̒m�I�A�g���m�I���Y���̌���ɂƂ��čł��d�v�ł������B�Ȃ��Ȃ�A�g���^�@�B���i�͔�r�I���Ȋ����������������̕��i�ɂ���č\������Ă���A�����̕��i���[�J�[�Ɗ����i���[�J�[�Ƃ������J���A�g���s�����Ƃɂ���āA���t�����l���V�@�\���i��V�f�ނ��̂��̂̊J���Ɉڂ�悤�ɂȂ�ƁA��ƊԂ̒m�I�A�g�̗]�n�͋��߂���悤�ɂȂ����B��O�̎Y�ƕ�����ɂ����ẮA�����t�����l�ސV�@�\���i��V�f�ށA���邢�͈��i���̊J���ł͊J���v���Z�X�̑��ݘA���������A��ƊԘA�g�������ꂵ���Ǘ��@�\�̋��ň�̓I�ȋZ�p�J���𐄐i���������������I�ł���B�Ȃ��Ȃ�A���������Y�ƕ���ŋZ�p�J���ɕK�v�Ƃ����̂̓e�N�m���W�[�i�Z�p�j�����T�C�G���X�i�Ȋw�j�ɋ߂���b�I�����ł���B��b�I�����͋Z�p�J���ɔ�r���āA���̉��p�̈悪�L���Ƃ���������L���Ă���B���̂��߁A��ƊԘA�g�ɂ�鋤���J���̏ꍇ�A���̌������ʂ����������ۑ�ȊO�ɓ]�p����郊�X�N�͍����A��ƊԘA�g������Ɣ����i�l���`�j�ɂ�錤���J���v���Z�X�̓��������I�D�����B �܂��A��O�̎Y�ƕ�����ō����������ʂ�B������̂́A�ݐρiIncremental�j�^�J���Ƃ������͓˔j�iBreakthrough�j�^�J���ł���B���������˔j�^�Z�p�J���ł́A�J���Ҍl�ɂ���Đ��s����镔���̏d�v���������A�g�D�i�`�[���j�̖��������ΓI�ɒቺ���Ă���B�����āA�J���Ҍl�̒m�I���Y���̍�������Ƃ̊J�����ʂɒ������Ă���A�J���Ҍl�̒m�I���Y���́A���̌l�̎����Ƌ��ɁA���̌l���`������m�I�l�b�g���[�N�̎��ɂ��ˑ����Ă���B���ہA�V���R���o���[�̒m�I���Y�������̒m�I�N���X�^�[�ɔ�r���Ĉ��|�I�ɍ����̂́A�J���Ҍl�Ԃ̃l�b�g���[�N�����x�ɔ��W���Ă��邩��ł���B ��R�́@���ƃV�X�e���]���Ɛ��E�s�� ���E�K�͂ł̕s���́A���Y�Z�p����v�\���̕ω��ɂ���Ĉ����N�����ꂽ���ۓI�ȋ������ω��ɑ��āA�����̈�����ƃV�X�e���̓K�����������s�I�ɂ͐i�W�����Ȃ����Ƃɂ��l�X�Ȗ��C�����݉����Ă��̂ł���ƍl������B��������A�Y�ƕ�����̈ڍs�ߒ��ɐ����錻�ۂł���Ƃ����悤�B �P�D���̎Y�ƕ�����Ɛ��E�s�� �s�^�t�H�[�h�ɑ�\����鎩���ԍH�Ƃł̑�̐��Y�V�X�e���́A�P�X�P�O�N�㒆���ɂ͊m���E���y�����B��ꎟ����̐��N�Ԃ͑�ʐ��Y�V�X�e���ɂ���Ċg�債�������͂̉ߏ�͕������v�ɂ���ċz�����ꂽ���A�P�X�Q�O�N��ɂȂ�Ƌ����͂̉ߏ肪�\�ʉ�����悤�ɂȂ�A�f�t�����͂����߂�悤�ɂȂ����B���̂悤�ɑ�ʐ��Y�V�X�e���̖{�i�I�ȕ��y�ɂ�鋟���\�͂̋}�g��Ɍ�������ʏ���s��͖����m������Ă��Ȃ��������߁A�f�t�����͂����܂����B��Ƃ͉ߏ艻���������\�͂����k���邽�߂ɁA�J���҂����ق������߂ɑ�ʂ̎��Ǝ҂����������B���̂��ߏ�����v�͂���ɏk�����A���Ƃ����Ƃ��ĂԈ��z���������B ���������āA���̐��E���Q�̌����ł���啝�Ȏ����M���b�v�����P�������Ƃ̘A����f�����Čٗp���g�傷�邽�߂ɂ́A�P�C���Y���̗L�����v����͌��ʓI�ł������B�������A�t�H�[�h���Y�V�X�e���̕��y�ɂ��A�����\�͂̔���I�g��Ƒ�ʐ��Y���ꂽ���i�̋}���ȉ��i�ቺ�́A�Z���I�ȗL�����v����ł͉�������Ȃ����ł���B���d�v�ȉۑ�́A��ʐ��Y�V�X�e���ɂ���ċ}�����������\�͂ɑΉ������A�V���ȑ�ʗ��ʃV�X�e�����ʏ���V�X�e�����\�z����邱�Ƃł������B�܂��A��ʐ��Y�V�X�e�������y�����Y�ƕ���̏��i���i�ƁA��ʐ��Y�V�X�e��������c���ꂽ�Y�ƕ���A�Ƃ�킯�A�T�[�r�X�Y�ƕ���ł́A���E�T�[�r�X���i�Ƃ̊Ԃɐ������傫�ȑ��Ή��i������������A�V���ȉ��i�̌n�ɏ���s�����K�����邱�Ƃ��K�v�ł������B�����A�V���ȎY�ƃV�X�e���֓K�����邽�߂̌o�ύ\�������́A���E���Q���_�@�ɐi�W�����B�܂�A�P�X�R�O�N��ɂ͑�ʏ���̏ے��ł���X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ƃ����V���ȗ��ʌ`�Ԃ����܂�A���W�I���̃}�X���f�B�A�����p�����L�����Ƃ����������A�}�[�P�e�B���O�Z�@���傫���i�������B����ɂ���ʐ��Y���ꂽ���i�̑�ʗ��ʁE��ʏ���̊�b���z���ꂽ�̂ł���B �Q�D���̎Y�ƕ�����Ɛ��E�s�� ���̑��̗v���́A���̎Y�ƕ�����́A���Y�K�͂̋}���Ȋg����V�X�e���]���ł͂Ȃ��������Ƃɂ���B�܂�A���̎Y�ƕ�����́A�Z�p�v�V����v�\���ω��̉������Ƃ������ۋ������ɑ��āA�����K���\�͂�����_��̍�����Ɗԕ��ƃV�X�e������i�o�Ϗ����𒆐S�ɕ��y�������Ƃɂ���Đ������Ƃ�����B���������āA���̎Y�ƕ�����̂悤�ɁA���Y�Z�p�̌n�̑�ϊv�ɂ�鋟���\�͂̑啝�Ȋg���j��I�Ȑ��i���i���������̂ł͂Ȃ��������߂ł���B ���̗v���́A���̎Y�ƕ�����̓��F�́A�R�~���j�e�B�I�Ȓ����p��������d�����邱�Ƃɂ���B���������āA�i�C�z�ɂ��s�����ł��A����I�Ȏ���W�̈ێ����D�悳�ꂽ�B�܂��A�����ٗp��O��ɂ����n���`�����d�����ꂽ���߂ɁA�i�C�ϓ��ɂ��ٗp�ʂ̒����͌����I�Ɏ��{����Ȃ������B����ɁA������Y�����i������������悤�Ȍ������s�ꋣ�����A���i���ʉ��ɂ���ĉ�����悤�Ƃ���X�����F�߂�ꂽ���߂ł���B ��O�̗v���́A�_��Ȑ�剻�͎Q�������o�[���������ꂽ����̒n��i�R�~���j�e�B�j���Ŏ�������A���̒n����L�̃l�b�g���[�N�`����O��ɂ��Ă���B����A�n��i���n�j���莑�i�~�ςɂ��o�ό��ʂł���B���̂��߁A���������o�ό��ʂ͒n��O�ւ̃X�s���E�I�[�o�[�͌���I�ł���A���̖͕���e�Ղł͂Ȃ��B���l�ɁA���{�̉������ƃV�X�e���́A���{�̓��قȎY�Ɣ��W�ߒ��ł��̎�����s���`�����ꂽ���ʂ�����A���̃V�X�e���B�ɊC�O�Ɉړ]���邱�Ƃ͍���ł���B ���̂悤�ɑ��̎Y�ƕ�����ɂ������Ɗԕ��ƃV�X�e���́A�������e���i�n��j�̓��ِ��ɂ��Ƃ��낪�傫���B���������āA����������Ɗԕ��ƃV�X�e�����A���E�e���Œ蒅���邽�߂ɂ͈��̎��Ԍo�߂�K�v�Ƃ��邽�߁A�Y�ƃV�X�e���]���̐��E�I�e�������U�I�ƂȂ�B���̂悤�ɑ��̎Y�ƕ�����̓��F�ł���_��Ȑ�含�������������Ɗԕ��ƃV�X�e�����m�����A����ɂ�鉶�b�����������͌���I�ł������B ���̂��߁A�_��Ȑ�剻���������������ƃV�X�e���Ґ����i�����������i�n��j�ƁA���̎Y�ƕ�����ɏ��x�ꂽ�����i�n��j�Ƃł͍��ۋ����͊i�����g�債���B �R�D���I���ɉh���x����ICT�v�V �Ƃ��ɁA�č��V���R���o���[�𒆐S�ɃC���^�փl�b�g�֘A�̃T�[�o�[������C���^�[�l�b�g�ʐM�֘A�\�t�g�J���A����ɃC���^�[�l�b�g�����T�[�r�X�����l�Ȏ��ƕ���ő����̃x���`���[���n�o���ꂽ�B�����̃x���`���[�͂X�O�N��ɋ}�����𐋂��A�ٗp���g�傳�����B�C���^�[�l�b�g�̔��W���哱�����č��o�ς͂P�X�X�Q�N�ȍ~�Q�O�O�O�N�܂łX�N�Ԃɂ킽���Ĉ��肵���i�C�g������������B�Q�O���I���̂��������č��o�ς̍D����w�i�ɁA�č��G�R�m�~�X�g�̂Ȃ��Ɂu�j���[�G�R�m�~�[�v�_�����𗘂�����悤�ɂȂ����B�܂�A�\�t�g�E�F�A�E���ʐM�Y�Ƃ��哱�Y�ƂƂȂ����V�����o�ςł́A�Ꮈ�Ɨ��ƕ�������Ƃ𗼗������������I�Ȍo�ϐ���������������Ƃ����咣�ł���B���̃j���[�G�R�m�~�[�_�̘_���Ƃ��āA�܂��A���ʐM�Y�Ƃ͊����Y�ƂƂ͈قȂ��āA���E���Y��̓[���Ɍ���Ȃ��߂��A���Y�K�͂�������g�債�Ă����v���͏㏸�𑱂���u���n�����v�^�Y�Ƃł��邱�ƁB���ɁA���E�\�t�g�E�F�A�Y�Ƃ͐����ƂƂ͈قȂ��čɂ��̂��̂�K�v�Ƃ��Ȃ��Y�Ƃł���A�܂��A�����̐����Ƃł��ŐV�̏��Z�p�����p���邱�Ƃɂ���čɊǗ��\�͂�����I�Ɍ��サ�A��ɓK���ɐ������ێ��ł���悤�ɂȂ������߁A�i�C�ϓ��̎�v���ł���ɏz�������Ȃ����Ƃ��w�E���Ă���B �������A�j���[�G�R�m�~�[�_�҂̐��������_�ɂ��ւ�炸�A�A�����J�̌i�C�́A�Q�P���I�ɓ���Ƒ傫�����������B�Q�O���I���ɕč��o�ς̐����������������ʐM�Z�p�v�V���A���̂Q�P���I�ɓ���Ƌ}���ɂ��̃p���[�����ނ������̂��B���̑��̗��R�́A�C���^�[�l�b�g�̋}���ȕ��y�Ɛ��n���ɂ���B���p�C���^�[�l�b�g�l���͂P�X�X�O�N����Q�O�O�O�N�܂ł̂P�O�N�ԂŔ����I�Ȗc���𐋂������A�Q�P���I�ȍ~�͐�i�����ł͂��łɐ��n�Y�Ɖ����A�L�ї����啝�ɓ݉����Ă��邱�Ƃ����������͂̒ቺ�̗v���Ƃ��Ďw�E�����B���I���ŐV�K�̊v�V�I���i���J�����ꂽ�Ƃ��Ă��A���̓������琬�n�܂łɂ͂Q�O�N�߂����Ԃ�v���邱�Ƃ����Ă���ƁAICT�Y�Ƃ̃��C�t�T�C�N���͒������Z���ƌ�����B���̗��R�́A�\�t�g�E�F�A�Ȃǂ̏����ɂ͍X�V���������݂��Ȃ����Ƃł���B�\�t�g�E�F�A���̏����̌o�ϓ��������v�̓݉��Ƒ傫���W���Ă���B�܂�A�ʏ�̋@�B�ݔ����̕��I���͎g�p�ɂ���Ċm���Ɍ��Ղ��A���̑ϗp�N�����o��ƍX�V�����������܂�邪�A�\�t�g�E�F�A�̂悤�ȏ����̏ꍇ�ɂ͎g�p�ɂ�錸�Ղ͐������A���������āA������̍X�V�����͊��҂ł��Ȃ��B�\�t�g�E�F�A�����́A�R���s���[�^�E�V�X�e���̔��{�I�ȕύX�̂Ȃ�����A�lj�������K�v�Ƃ��Ȃ��B�p�\�R���ɗp������\�t�g�E�F�A�ɂ��Ă����l�ł���A�g�p�ɂ�錸�Ղ��Ȃ�����A���̋@�\������I�Ɍ��サ���V�o�[�W�������J������Ȃ�����A�V�����\�t�g�E�F�A�̐�ւ����v�͔������Ȃ��B�Ƃ��ɁA�Q�O�O�O�N�ȍ~�ɐV�K�ɊJ�����ꂽ�\�t�g�E�F�A�͂Q�O���I��Windows98�Ȃǂ̂悤�Ȃ��̂ɔ�ׂ�Ɗv�V���͒Ⴍ�A�����ւ����v���傫���͐���オ��Ȃ������B���̂��Ƃ����I���������x�����\�t�g�E�F�A�Y�Ƃ��Q�P���I�ɓ����Ă���͐��������З͂�ቺ�������v���ł���B �S�D3D�EICT�v�V�Ɛ��E�s�� �P�X�X�O�N�㖖������i�W����3D�EICT�v�V�́A���̎Y�ƕ�����ɂ����āA�t�����l�����̌���ł������u�_��Ȑ�剻�v�ɂ��o�ό��ʂ̑啔�����f�W�^���Z�p�ő�ւ���܂łɂȂ����B�����Ă���3D�EICT�v�V�ɂ���Ď哱�����V���Ȑ��Y�Z�p�̌n�ɂ͕��Ր�������A����܂ō��x�ȋ@�B���Y�Ɩ����ł��������W�r�㏔���ɂ��}���ɕ��y����悤�ɂȂ����B���̌��ʁA���E�̋������͈�ς��A�������͂��߂Ƃ��铌�A�W�A�����̋����\�͂͋}���Ɋg�債���B���̂悤�ɁA���E���̎Y�ƕ����䂪��i�o�Ϗ����̌o�ϔ��W�ɗL���ɍ�p�����̂ɑ��āA��O�̎Y�ƕ�����́A���W�r�㍑�̎Y�ƁA�Ƃ�킯��������̔��W�ɂƂ��Ă��L���ɍ�p���Ă���B���̂��Ƃ��A��O�̎Y�ƕ�����̑��̓����ł���A�ߔN�A��i�����ɂ�����o�ϐ����݉��ƁA�V���H�Ə����ɂ����鍂���o�ϐ����Ƃ����������̓�ɉ����Y��ł����v�ȗv���ƂȂ��Ă���B �܂��A3D�EICT�v�V�����E�o�ςy�ڂ��e���ɂ��ẮA���ɂ́A���i�Z�p�̕W�����E���J���Ɛ��Y�Z�p�̃f�W�^���@��ɂ���։��́A���Y�����A�Ƃ�킯�A�@�B���Y�̃O���[�o���Ȋg��Ƃ���ɔ������i���i�̋}���Ȓᗎ�������炵�����Ƃł���B�@�B�H�Ƃ͐�i�o�ς̒��j�Y�Ƃł���A�]���͋Z�p�̒~�ϕs���͔��W�r��o�ς��@�B�Y�ƕ���֎Q�����邤���ł̍�����ǂƂȂ��Ă����B�Ƃ��낪�A�C���^�[�l�b�g�̕��y�́u�l�b�g���[�N�̊O�����v�̏d�v�������߁A�����̋@��ŋZ�p�̌݊����m�ۂ����߂���悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�Z�p�̕W�����ƋZ�p���̉�����i�W�����B�W����������J���ꂽ�Z�p��p���邱�ƂŁA��i�o�ςłȂ��Ă��e�Ղɍ��x�ȋ@�B�@�킪���Y�\�ƂȂ����B�܂��A���ۓI�ȋ����ɑς���@�B�@��̐��Y�ɕK�v�ȏn���Z�\��Y�Ǘ��Z�p�A�܂�A�u���̂Â���v�Z�p���O����CAD/CAM�V�X�e����Y�Ǘ��\�t�g�E�F�A�ɂ���đ�ւ����悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�n�[�h�E�F�A�̐��Y�Ǘ��@�\�͓��A�W�A�����𒆐S�ɃO���[�o���Ɋg�債�A���i���i�̗ݐϓI�ቺ�������炵���B ���̉e���́A�n���Z�\���Ɠ���Z�\�̕K�v�����ቺ�������Ƃɂ�钷���ٗp�̏k���ƌٗp�̕s���艻���ٗp�ҏ����̌����Ə���x�o�̒���������炵�A�s�����������Ă��邱�Ƃł���B ��O�̉e���́A���̎Y�ƕ�����ɂ����đ傫�Ȗ������ʂ������������W�̗������Ɗ�ƊԎ����̌����������炵���B�̕s���艻�ɒ��ʂ����T�v���C���[�͐ݔ���������T���A�K�J���ւ̈ˑ�����w���߂�悤�ɂȂ����B �T�D�s��n���Ȃ��V���Ƒn�o �C���^�[�l�b�g�͗l�X�ȕ���ŐV���ȏ��T�[�r�X���Ƃ�n�o�����A�l�X�̗��������I�ɍ��߂��B�������A�C���^�[�l�b�g�֘A�̐V���Ƃ̑����́A�V�s���n������̂ł͂Ȃ��A�����s��ł̃p�C�̑��D�ɏI�n���Ă���B�C���^�[�l�b�g�ɂ��V���Ƃ̑n�o�́A���K�I�Ή����o�ω��l�i�s��j�n�����ʂ��������A�����s��̑�ւɂƂǂ܂��Ă���B�f�c�o���v�Ɍv�コ��鐶�Y�z�́A��������Ȃnjo�ό��p���̂��̂̌���ł͂Ȃ��A�o�ώ���ɔ������K�I�ȕt�����l�z�̑����ł���B���������āA�C���^�[�l�b�g�ɂ���Đl�X�̗����������Ɍ��サ�Ă��A���ꂪ���K�I�Ή��킸�A�����̌o�ϊ����̑�ւł���Ƃ���ƁA�o�ϐ����ւ̍v���͂قƂ�ǂȂ��̂ł���B���������C���^�[�l�b�g�ɂ��s��n���Ȃ��V���Ƒn�o��������O�̎Y�ƕ�����ւ̈ڍs�ɔ����\���s���̍����ł���Ƃ�����B �U�D���E�s��̈�̉��ƃf�t������ �C���^�[�l�b�g�̃u���[�ƃo���h���ɂ���āA�����̔̔��T�C�g�����Ԃ������Ĕ�r�����ł���ƂƂ��ɁA��e�ʂ̉摜���`�B�ɂ���āA���i��������������̓X���Ō���悤�ɏڍׂɂȂ�A���i���Ƃ̔̔����i�̔�r���e�Ղɍs����悤�ɂȂ�A�ň������i��e�Ղɔ����ł���悤�ɂȂ������߁A�d�q������ł̔̔����z�͋}���Ɋg�債�Ă���B�����āA�����̏��Ƃ̉c�Ɗ�Ղ�h�邪������ł͂Ȃ��A�������X�̔̔����i���C���^�[�l�b�g���i�Ɉ�������������X���ɂ���f�t�����͂����߂Ă���B �Q�P���I�ȍ~�A�C���^�[�l�b�g�ʐM�̃u���[�h�o���h���A�ʐM�����̒�z���ɂ���āA�C���^�[�l�b�g�֘A�T�[�r�X�Ƃ����X�ƒa�����A�܂��A�d�q������ie-�R�}�[�X�j�̎�������}�����������B�������A�����̃C���^�[�l�b�g�֘A���Ƃ́A���̃T�[�r�X�������̏ꍇ�����ōs���Ă���A�V���Ƒn�o���o�ω��l�n�o�ƌ��т��Ȃ��Ƃ����A����܂ł̌o�ς��o���������Ƃ̂Ȃ��������Ă���B�܂��A�C���^�[�l�b�g�֘A���Ƃŋ��K�I�Ή������̂��A�����͊����̃T�[�r�X�Y�Ƃ◬�ʎY�Ƃ̌o�ϊ��������Ⴂ�}�[�W�����ő�ւ�����̂����Ȃ��Ȃ��B���̂��߁A�����Y�Ƃ̕t�����l���͒ቺ�����B ���̎Y�ƕ����䂪��ʐ��Y�����̊m���ɂ�鋟���ʂ̒������g���Ɛ��i���i�̋}���ȉ����Ƃɂ���Đ��E���Q�������N�������̂Ɠ��l�ɁA��O�̎Y�ƕ�������A�V���ȑ�ʐ��Y�V�X�e���̃O���[�o���Ȉړ]�E�g�U�ɂ�鐻�i�����ʂ̒����Ɛ��i���i�̑啝�ȉ����������A���E�I�ȃf�t�����͋��߂Ă���B ���{�o�ς͑��̎Y�ƕ����䂪�����炷�։v�������Ƃ����A�u���̂Â���卑�v�Ƃ��Đ��E�o�ςɑ傫�ȑ��݊��������Ă����B�������A����䂦�ɑ��̎Y�ƕ�����̏I���Ƒ�O�̎Y�ƕ�����ւ̓]���ɂ���čł��傫�ȑŌ����Ă���B
��S�́@���{�Y�Ƃ̋����͗v������ �P�D�P�X�U�O�N��̋����͗v�� �P�X�U�O�N�����܂ł̓��{�̗A�o��Ƃ́A�V�X�f���_�������悤�ȍ������Y��������Ƃł͂Ȃ������B�ނ���A�U�O�N�㏉���܂ł́A���Y���̍������ƕ���ł͗A�o�䗦���Ⴍ�A�����𑱂��鍑�����v�ւ̔̔��ɒ��͂��Ă����B���{�̍����s��͑��Ƃɂ�闬�ʌn���i�W���Ă���A������ƂɂƂ��čŏI���i�̍����̔��`���l�����m�����邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ������B�����̒�����ƂɂƂ��āA�����s��ɎQ����������A�o�s��ɎQ����������Q����ǂ͒Ⴉ�����̂ł���B �Q�D�P�X�V�O�N��̍��ۋ������ω� �P�X�V�O�N��܂ł̐��E�̎��R�f�Ց̐����x�������̍��یo�ϒ����́A��ʐ��Y�V�X�e���������炷�A�����J�̈��|�I�ȍ��ۋ����͂�O��ɍ\�z����Ă����B�Ƃ��낪�A�t�H�[�h���Y�V�X�e���̖{�i�ғ����甼���I���o�߂����P�X�U�O�N��ɂȂ�ƁA�č��^��ʐ��Y�V�X�e���̐�ΓI�ȋ����D�ʐ��͗h�炬�n�߁A�V�O�N��ɓ���ƃA�����J�̖f�Վ��x�͐Ԏ��ɓ]�������B����ɔ����A�A�����J�̐��Y�͂ƃC�j�V�A�e�B�u�ɂ���Ďx�����Ă������̍��یo�ϒ����A���Ȃ킿�A�h�l�e�E�f�`�s�s�i�u���g���E�E�b�Y�j�̐��́A�P�X�V�O�N��ɓ���Ƌ}���ɕώ����n�߂��B�܂��A�f�`�s�s�͂V�P�N���甭�W�r�㍑�����Y���Ƃ���Y�i�̗A���ł����Ƃ����ʓ��b�Ő��x�������B����ɂ��A�����r�㍑�ɋ敪����H�Ɖ����n�����n�߂��؍��A��p�A���`�A�V���K�|�[���Ȃǂ��H�Ɛ��i�łŐ�i�����ɗA�o�ł���悤�ɂȂ����̂ɑ��āA���{�͂��łɐ�i���O���[�v�ɂ���ł��x����Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�����̍��Ƃ̉��i�����ŗ�ʂɗ�������邱�ƂƂȂ����B �܂��A�P�X�V�P�N�Ƀj�N�\���哝�̂͋��ƃh���̌�����~�\�����B������j�N�\���E�V���b�N�ł���B���̌�A���E�̊O���ב֎s��͕ϓ����ꐧ�Ɉڍs���A�~������������ƂɂȂ����B ����Ɍ������Y�̓��W���[�ƌĂꂽ�Čn���S�̋���Ζ���Ƃ��x�z���A�P�o�[�����R�h���O��̈��肵�����i�ŋ�������A�u���������̖����̒e�͐��v�_�b�ݓ��{�̌o�c�҂̋��C�̓������ӗ~���x���A�����ݔ��������������B�������A�P�X�V�O�N��ɂ́A���̃��W���[�̎x�z�͂��ቺ�������̎Y�������͂��l�����I�C���V���b�N���_�@�Ɍ������i�����������B �ȏ�̎O�̏o�����́A��ɉ��i�����͂Ɉˑ����Ă������{�̗A�o������ƂɌ���I�ȑŌ���^���A������Ƃ͒��ړI�ȗA�o�Y�Ƃ���̓P����]�V�Ȃ����ꂽ�B �i�Q�j���{�̗A�o�\���̓]�� �P�X�V�O�N��͒�����Ɛ����i�̗A�o�z�̏k���ɑ��āA�i�I�����͂�啝�ɋ����������Ɛ����i�̗A�o�������������߁A���{�̗A�o�z�͑��������B���ہA�V�O�N�㔼�ɂȂ�Ɠ��{�A�o���z�̖�V�O�������{�ƋZ�p���W�����x�g���^�@�B�ނŐ�߂���悤�ɂȂ�A�@�ې��i���J���W��I�Y�Ƃ͗A���Y�Ɖ������B ���̂悤�ɗA�o�̑啔�������Ƃɂ���ĒS����悤�ɂȂ�A���ۋ����͂��傫���ቺ����������Ƃ́A�����ւ̓]���ɂ��̊��H�����o�����B���̓T�^�I�ȃP�[�X�́A�P�X�V�O�N��Ɋg�������}���Ă����X�[�p�[�}�[�P�b�g�ւ̔[����ƂƂȂ邱�Ƃł������B�����ł̉����ȍ������v���A��r�D�ʐ����Ȃ������A�o������Ƃ̎Y�ƒ����ɔ������C���ɘa�������B�܂����ɁA�����s��ƗA�o�s��̗����Ŏ��v���g�債�������ԁA�Ɠd�A�����@�B�H�Ɠ��̑�芮���i���[�J�[�̉�����ƂƂȂ邱�Ƃł������B �i�R�j�����͊�ՂƂ��Ẳ������ƃV�X�e�� ���{�̉������ƃV�X�e���́A���̍��x�o�ϐ������Ɋg�����ꂽ���A�P�X�U�O�N�㒆���܂ł��̎���W�͕s����ł���A���s������o�ĂU�O�N�㖖�ȍ~�ɂ͈��肵�A�������ƃV�X�e�����p�̌������͏㏸����悤�ɂȂ�A�V�O�N��ɂȂ�ƁA�@�B�H�ƕ���̎����I�Ȑ����Ɏx�����āA��������W�͂���Ɉ��艻�������p���_��ʉ������B ���̂悤�ȉ�������W�̒����p�����̈�ʉ��́A�����ƊԂ̐M�����~�ς𑣂����B���̐M�����~�ς�w�i�ɁA���X�N�̍���������莑�Y������������Ƃɂ���ĐϋɓI�Ɏ��s�����悤�ɂȂ�A�������ƃV�X�e���������炷��ƊԐ��Y���͂܂��܂��㏸����悤�ɂȂ����B���̌��ʁA���{�̋@�B�H�Ƃ͉������ƃV�X�e�������̋����͊�ՂƂ��ėA�o��L�������邱�ƂƂȂ����B �R�D�O���ˑ��x�ƗA�o�����̉�A���� �i�Q�j�P�X�V�P�N�f�[�^�̕��� �P�X�V�O�N��ȍ~�A���{�̋@�B�H�Ƃ𒆐S�Ƃ���A�o�Y�Ƃ͋}���ɍ��ۋ����͂��������A���̗A�o�g��e���|�͉�������ƂƂ��ɁA�A�o�Y�Ƃ̎��v�����D�]�������B�����������ƕ���𒆐S�Ƃ���A�o�Y�Ƃ̍D����������Ƃɂ��g�y���A������Ƃ̎��v�������P���ꂽ�B����ɁA�U�O�N�㖖����̒�������I����̌p���ɂ���āA������Ƃ̑��ł́A���̏œ_�̍i��ꂽ�����H����ł̐��Y�Z�p�̐i���������ɐi�W�����B���̌��ʁA�V�O�N�㖖�ɂȂ�Ɖ�����Ƃ̂Ȃ��ɂ͂��̉��H�Z�p�����ɂ����āA�e��Ƃł�����Ƃ̐�����������̂����������B�V�O�N���ʂ�����������̗ʓI�g��Ǝ��I����ɂ���āA�������ƃV�X�e���͗A�o�Y�Ƃ̋N�p���͊�ՂƂ��Ă̊�b���ł߂��ƕ]���ł���B �i�R�j�P�X�W�O�N��̍��ۋ����� �P�X�W�O�N��㔼�́A�v���U���ӈȍ~�̋}���ȉ~���Ɛ[���ȑΊO�o�ϖ��C�Ƃ��i�s���A�A�o��ƂɂƂ��ċɂ߂Č������o�c���ɂ������B�������A�������������������ɒ��ʂ����A�o��Ƃ́A�R�X�g�팸�Ɣi�����͂̈�w�̋����Ɍ��������͂�������Ƃɗv�������B�e��Ƃ���̌������R�X�g�_�E���v���ɒ��ʂ���������Ƃł́A�u�`�iValue Analysis�j�^�u�d�iValue
Engineering�j��@����g���ăv���Z�X�E�C�m�x�[�V�����𐄂��i�߁A���Y�R�X�g�̑啝�ȍ팸�����������B�������ĒB�����ꂽ�R�X�g�팸�ɂ�闘�����̔z���ɂ��ẮA���łɎ�����s�����Ă����B�܂�A�u�`�^�u�d�ɂ��R�X�g�팸���ʂ̓��A�����̌_�ɂ��Ă͂Q���̂P�����[�����i���팸���A����ȍ~�̓R�X�g�팸���ʂ̂��ׂĂ�[�����i�ጸ�ɔ��f������Ƃ������̂ł���B���̂悤�ɉ�����Ƃւ̃R�X�g�팸���ʂ̔z���䗦�͏��Ȃ����A�R�X�g�팸���ʂ̍��������C��Ƃɂ͔����ʂ��d�_�I�ɑ��傳��邽�߁A������Ƃ̓R�X�g�팸�ɌX��������Ȃ������B�܂��A�P�X�W�O�N��ɂ����ẮA���l����iNC�j�H��@�B�ނ̐��\����i�ƌ��サ���̉��i���ቺ�������Ƃ���A����������Ƃł��A���������ŐV�̐��Y�ݔ���ϋɓI�ɓ������ĘJ�����Y�������コ���邱�Ƃɂ���āA���Y�R�X�g�팸�����������Ă���B �i�S�j�P�X�W�O�N��̃f�[�^���� �i�T�j�P�X�X�O�N��̍��ۋ����� �P�X�X�O�N��ɓ���ƁA�o�ς̃O���[�o�����Ɛ��Y�Z�p�̃f�W�^��������w�i�W�����B�����������ۋ������ω��̉e���́A�Y�Ƃ��ƂɔZ�W�͌�������̂̓��{�̊�Ɗԕ��ƃV�X�e���ɍ��{�I�ȕώ��������炵�n�߂��B�Ƃ�킯�A�X�O�N��㔼�ȍ~��3D�EICT�v�V�́A���̎Y�ƕ�����̏I���������炵���B 3D�EICT�v�V�ɂ���Ă����炳�ꂽ���ۓI�ȋ����\���ω��̉e���́A�P�X�X�O�N�㖖�̒i�K�ł͈ꕔ�̋Ǝ�Ɍ��肳��Ă����B�������A�Q�P���I�ȍ~�ɂȂ�Ƌ������ω��̉e���͍L�͂ȎY�Ƃɔg�y����悤�ɂȂ�A���{�̕��ƃV�X�e���͏d��Ȋ�H�ɗ�������Ă���B ���̂��ƁA�C�O�����⌤���J�������Ȃǂׂ̍��ȕ��͂��܂��܂������܂����A�X�̎w�E�ɋ����[�����̂�����A��ǂ�E�߂�ə傩�ł͂���܂���B�����A�p�����ÊϓI�Ȃ̂ŁA���̕��͂����ƂɁA���ꂩ����l����Q�l�ɂ���Ƃ������̂ł͂Ȃ��悤�ł��B���Y�Z�p�̊v�V�ɂ�萶�Y�ʂ������I�Ɋg�債�o�����X������āA�����̂��߂ɕs�i�C����������Ƃ������͂͂��܂������Ƃ͎v���܂����A�����܂ł�����܂ł̐����ɂ͗L���ł����A���̃X�P�[��������Ɍ����Ďg���邩�Ƃ����ƁA�����܂ł̕��Ր��͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B �Ƃ����̂��A���̒��҂Ȃ�̃p���_�C���Ƃ����̂������ݒ�̑O���m�Ɏ�����Ă��Ȃ��̂ŁA�f�[�^�͂��Ă���̂ɏI�n���Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ������Ă��܂��B����𗝘_�����A�W�J����Ƃ����{���̊w��̕����Ɏア�悤�Ɏv���܂��B�Ǐ��̑ΏۂƂ��ẮA�G�˂̂悭�ł������|�[�g�ŁA�܂Ƃ܂��Ă��邪�A�ʔ����̂Ȃ��{�ł����B |