第一章 無数のビオトープが生まれている 第二章 背伸び記号消費の終焉 第三章 「視座にチェックインする」という新たなパラダイム 第四章 キュレーションの時代 第五章 私たちはグローバルな世界とつながっていく 感想
プロローグ ジョゼフ・ヨアキムの物語 生涯のほとんどを放浪者として過ごしたジョゼフ・ヨアキムは70歳を過ぎると、過去の心象風景を自分自身の手で残そうと、自己流の絵を描き始める。それをシカゴのサウスサイドに借りていたアパートの窓ガラスに飾っていた。これをジョン・ホップグッドというカフェの経営者が目に留め、自分の店で個展をおこなった。この個展を出版社主のトム・ブランドが訪れ、これがヨアキムがアートシーンにデビューするきっかけとなった。ヨアキムは、晩年に「わたしが描いた絵に価値があるなんて、まったく想像もしていなかったよ」 自身ですら価値を見出していなかった作品を、ジョン・ホップグッドが見出したからこそ、アートとして認められるきっかけとなった。そう考えると、ヨアキムの作品というアートは、ヨアキムと彼を見出したポップグッドとの共同制作だったとも言える。美術の世界に限らず、インターネットの普及ということもあり、プロじゃない人の表現や発信が増えている。そういう世の中では、よい作品を生み出すためには、「つくる人」がいるだけでは難しい。それらの素晴らしい作品を「見出す人」が必要になって来る。これからの世界は、このような「つくる人」と「見出す人」が互いに認め合いながら、ひとつの場を一緒につくるようにして共同作業していくようになる。
第一章 無数のビオトープが生まれている ここで、著者はエグベルト・ジスモンチというブラジル出身のミュージシャンと、彼の来日コンサートを開催した女性プロモーターの話をする。ジスモンチの音楽はブラジルの音楽をベースにワールドワイドな広がりをもったものだったが、日本では一部のコアな音楽マニアを除いて無名に近かった。この人の来日公演を考えた女性プロモーターがいた。しかし、新譜も出ていなければ、来日もずっとしていない、さらにジャンルもハッキリしないようなジスモンチの公演を、日本でやって成功できるのか。彼女は、まずチラシを作った。それは、ジスモンチの簡単な紹介とウェブサイトのURLのみが記されたシンプルなものだった。ウェブサイトには、メーリングリストの登録フォームが用意されていた。これらは情報を絞り込み、受け手の飢餓感を煽ることを意図してつくられていた。そして、この情報の告知が最も重要な問題。テレビや新聞に公告を出す予算はなく、チラシをバラまいてもジスモンチのファンに情報が届くわけではない。では、どこに情報を投げるか。とくに音楽のような言語の違いを超えてしまう文化は、いまや国ごと民族ごとの違いよりも、文化圏域ごとの違いの方がずっと大きくなってしまっている。ジスモンチの音楽はアマゾンの奥深くに分け入った民族的根源性を秘めながらも、しかしそこには日本人にも欧州人にも、そしてアフリカ人にも生理的に理解できるグローバル性を内包していると言える。しかし、そのグローバル性とは決して全世界のすべての開かれているものではなく、クラシック・ジャズ。ワールドミュージックの境界的な領域に生息する特異なサウンドを、皮膚感覚的に認知できるような、ある特定の文化圏域の人たちに対してのみ開け放たれていると言える。つまり、今や国ごとの垂直統合は解かれ、グローバルな音楽市場の中で再結合されているのだ。 となると、なおさら、次にあげる3点が情報の流れの究極の課題として浮き上がってくる。 ・ある情報を求める人が、いったいどの場所に存在しているのか。 ・そこにどうやって情報を放り込むのか。 ・そして、その情報にどうやって感銘をもらうのか。 情報を共有する圏域のサイズが国ごとにはどんどん小さくなっている。今、その場所を押さえるのは、とても困難になってきている。そして、この情報を求める人が存在している場所を、ビオトープと呼ぶ。 かつては、国ごとに音楽が垂直統合され、音楽プロモーターがビオトープを容易に見つけることができた。マスである多くの国民に向けてであればテレビや全国紙。特定の地域に情報を送り込みたい時は地方紙や全国紙の地方版、折込広告。そして、趣味や業界の各分野に対しては雑誌や業界紙。それは人々のビオトープが整然と切り分けられて、可視化され、整頓されたメディア空間であり、どこに情報を投げれば誰に届くのかを、ある程度推し量ることができた。ところがインターネットの出現によって、この巨大で大雑把なビオトープは拡散してしまう。最初はウェブサイトから、検索エンジンの普及がこれを加速し、ブログやツイッター等の膨大なソーシャルメディアが参入した。これにより、ビオトープは、デジタル空間の内外で無限大の広がりを持ち、さらにはあふれた情報がビオトープの再生産を促し、あるいはソーシャルメディアの中でアドホックに生滅を繰り返すようになる。それは、一見捉えどころのないかのようだ。音楽の世界においても、ビオトープはグローバル市場の中でうたかたのようにあちこちに生まれ、時には消え、そして再生成されている。ある時にはコンサート会場に突然生まれるときもあり、永続的に固定されたコミュニティもどこかに存在するかもしれない。 ここで、プロモーターは、マリーザ・モンチというブラジルの女性シンガーのコンサートでチラシを配布した。いわば狙い撃ちである。彼女は、音楽性の深さや方向性は似通っていて、彼女のコンサートに集まるコアなファンをターゲットとしたところ、手応えはあった。さらに、「現代ギター」という雑誌に着目する。これはクラシックギターの専門誌で、ギターを軸とした情報が詰め込まれている。この雑誌の読者であるギターの愛好者には特徴的な傾向として、ギターを聴く人が、同時に弾く人である場合が多く、年齢的には40〜60代の男性で比較的収入は高い。だから、ビオトープとしては圏域が小さいが、ファン同士の情報流通は非常に濃い。このような関係性は、実は、インターネットと高い親和性がある。実際、クラシックギターファンの多くはミクシィにかなりの数が集まって、コミュを形成していた。だから、ギターファンというのは、一般的な音楽ファンとは異質なビオトープを形成していた。そして、プロモーターはこのようなコミュに情報を投げ込んでいった。結局は、まず、狭いクラシックギターファンの間で話題となり、次第にレア感となってマスメディア業界のアンテナを刺戟し取材申し込みが舞い込むほどになり、結果は、チケット完売、このライブについては、かなりの人がブログで感想を書いている。 情報の流れは、いまや劇的にこのような方向に流れている。大衆と呼ばれるような膨大な数の人に対してまとめて情報を投げ込み、皆それに釣られてモノを買ったり映画を見たり音楽を聴いたり、というような消費行動は2000年代以降、もう成り立たなくなってきている。 このプロモーターが採ったのは、新聞やテレビ、雑誌を介して情報をただ流すのではない。目を皿のようにして、その情報を求めている人たちの特質をつかみ、そのような人たちがどのようにして情報を得ているのかということを調べ上げ、その小さな支流のような情報の流れを特定していく。それは自然の中にある本物のビオトープのように、小さな水たまりに細い細い水流が流れ込んでいるような世界。どこが上流なのか、どこが下流なのかも判然としていません。水はゆるやかにたゆって集まり、分かれ、再び集まって複雑な水域を形成していく。その網の目のように張り巡らされた水流のあちこちに生まれる水たまりには、エビやカニや小魚や虫たちがひっそりと生息し、小さな生態系を形成している。それぞれの水たまりは沼や川にも繋がり、ある場所では森の中にひっそりと隠れ、別の場所では広い草地に埋もれるようにして夏の強い日差しを受けている。この多様で複雑な生態系の全体像を見渡すのは、容易なことではない。 今、我々の情報社会も、このように小さなビオトープが無数に集まって生態系をかたちづくり、それが連結を繰り返しながら全体を構成させている。それを、ソーシャルメディアの普及がさらに促し、一層の拡大と進化を続けている。この広大な情報の森の中へ、このプロモーターは足を踏み入れ、優れた狩猟者よろしく、あちこちに罠を仕掛け、川の一部をせき止めて簗をつくり、ピンポイントでそこに生息するジスモンチの音楽の消費者たちを探し出した。 このジスモンチの公演の例に象徴的なように、情報のビオトープ化はマスの衰退とともに劇的に進行している。そして、このような混沌とした状況には、ひとつの大きな難題が横たわっている。それは、ビオトープのありかを特定していくのが容易ではないということだ。まず、情報を受ける消費者の側から言うと、自分が求めている情報がどこに行けば得られるかが明確ではなくなってきている。ネット時代に入り情報の量は指数関数的に増え、情報の質も以前より濃く深くなってきている、だからピンポイントで探し出すことができれば、そこに必ず有用な情報がある。しかし、それを探し出すのが容易ではない。 これは情報を送り出す側に言える。この例のプロモーターのようにビオトープを的確に探し当てれば、的確な情報を的確な場所に流し込むことができる。しかし、これこそ天賦の才能とスキルとノウハウの世界であって、だれにでもできるというものではない。 しかし、このような混沌にも、様々な法則が見出されようとしている。どんな混沌にも必ず法則はあり、その法則に基づいて情報は流れていくはずだ。しかし、それらの法則は未だ断片的でしかない。これを解き明かすのが本書のゴールというわけだ。
第二章 背伸び記号消費の終焉 以前ならば、誰もが観に行くヒット作の世界とマニアックな単館上映館が両立していた。『シティロード』や映画雑誌のような圏域が細分化された雑誌群がメディアとして成立し、それ以上に先端的な情報を求める人にはリアルな人的ネットワークが用意されていて、そこに参加すれば情報が必ず流れ込む構造ができていた。 しかし、このような構造は2000年ころを境に大きく変わってしまった。その要因の一つはDVDプレーヤーの普及が映画業界にバブルの幻影を引き起こし、無残な結末を招いたこと。これは1980年代のビデオの普及で大きなバブルを経験したことが遠因であった。当時、ビデオプレイヤーを購入した消費者は映画を求めてレンタルビデオ店に走り、コンテンツの揃っていなかったビデオレンタルの世界から映画コンテンツの需要が急速に高まり、配給会社は未公開の作品を片っ端から買い漁りビデオ化され、それがビデオ店に買い取られた。これによって配給会社は莫大な収入を得ることができたのだった。そして、2000年のDVDの普及により、配給会社はビデオの再来とばかりに未公開作品を買い漁った。しかも、シネコンの開館により単館で上映されていたマニアックな作品もシネコンで全国展開すれば、多くの観客に見てもらえるという期待が生まれた時期とも重なっていた。しかし、この結果は無残なものだった。DVDはビデオの時のようなインパクトを消費者に与えることもなく、レンタルビデオ店と配給会社の支払いのシステムも買取からレンタル実績の応じたリース料を支払う形になり配給会社が利益を稼げなくなっていた。そしてインターネットの普及によって、コンテンツに対する飢餓感が消滅していた。ビデオの時のようなバブルを期待していた配給会社はマス消費を期待して自らの手で作品の買い付け額を高騰させ、DVDからの収益が上がらず経営を悪化させていった。それが中小の独立系の配給会社は買い付け額の高騰に引き摺られて、碌な買い付けができなくなりジリ貧になっていった。 バブルを期待せず、手作りで小さく買い付け、小さく上映し、そこから少しずつ上映館を拡大していって一万人程度の集客を方向を作り出すことができれば映画マニアの多い日本では、採算が取れていた。しかし、マス消費を期待して、みずからバブルに突入し、自業自得となった映画業界。その結果が、この章冒頭の貧しい状態を招いた。 これは映画業界に限ったことではなく、1990年代の音楽業界にも同じことが言える。これは、当時CDラジカセの普及により、従来のステレオ装置から、個室でもCDを聴くことが可能となった結果、CDの購入意欲が急速に高まった。つまり、新しい再生装置への感動が、そのうえで再生される新しいコンテンツを求めたということだ。しかし、CDが日常品化することにつれて、さらにインターネットの出現により、CDの売上、とくにミリオンセラー激減した。ミリオンセラーが生み出す豊かな原資が壊滅した結果、資金が回らなくなり、売れないが才能あるミュージシャンを支援するシステムは崩壊する。広告費が回らなくなり、周辺で情報を供給していた音楽雑誌は休刊に追い込まれていった。ただし、音楽を志す若者は減っておらず、音楽そのものが衰退したわけではない。決定的なのは、音楽とリスナーを接続する回路が組み換わって、ミリオンセラーを生み出すマス消費が衰退し、代わって好みが細分化された音楽圏域が生まれたのに、音楽業界はこの圏域にうまく情報を送り込めていない。 これら映画や音楽業界に共通することは、テクノロジーの進化とそれによる視聴機器・媒体というプラットフォームの変化が新しいコンテンツをもとめ、一時的なバブル(大量生産・大量消費)を引き起こした。これよって、コンテンツ業界は次のネット時代への対応を遅らせた結果、ネットによって細分化していく圏域に対応できないまま、大量消費のマスモデルにしがみつかせることとなった。テクノロジーの進化によるプラットフォームの変化は、ただ視聴のメディアを変えるだけでなく、メディアの変化はコンテンツの配信形態の流動化、つまりオープン化に繋がる。その後のインターネットによりデジタル配信が劇的な流通モデルの変化を引き起こすことになった。これがアンビエント化である。我々が触れる動画や音楽、書籍等のコンテンツが全てオープンに流動化し、いつでもどこでも手に入るようなかたちであたり一面に漂っている状態、例えばアップルの音楽配信サービス、iTunesである。これは利便性が高まったというだけでなく、曲のジャンルや年代といった区別の意味を失わせることになる。すべてのコンテンツがフラットに並び換えられ、コンテンツの背景となるウンチクまでも共有化され、大きな共有空間を生み出した。そこでは、コンテンツの流通形態からあり方そのものまで180度の転換となった。これらに対応して、マス消費のようなどんぶり勘定ではなく、ピンポイントでその映画や音楽に接してくれる人のビオトープを探し当て、そこに情報を送り込んでいく緻密な戦略を本当は構築しなければならなかったはずだったのだ。 同じような例として、2010年のHMV渋谷店の閉店も象徴的だ。この店は、ある時期バイヤーとスばれる店員の見識とセンスの高さにより新たしい音楽をいち早く紹介し、独自の批評を盛り込んだポップを、消費者はこれにより知識を広め、この店はメディアとして機能し、文化発信基地の役割を担っていた。それが、画一化され無個性な店に陥った結果、その店でなくてもよくなっていった。つまり、マス消費が消滅し、新たなビオトープが無数に生まれてきている情報圏域においては、情報の流れ方は決定的に変わり、人から人へと、人のつながりを介してしか流れなくなる。HMVにはその新たな情報流通の胎動が全く理解できなかったことになる。 このように、マス消費が消滅していこうとしていることは、いまや厳然たる事実である。かつては、画一的な情報が大量に泣かせされ、これに「他の人も買っているので、自分も買う」といった背伸び的な記号消費が重なり、大量消費が行われていた。記号消費とは、商品そのものではなく、商品が持っている社会的価値(記号)を消費すること。商品がもともと持っている機能的価値とは別に、現代の消費社会ではその社会的価値の方が重視されるようになっており、その記号的な付加価値を消費するようになっているということだ。 消費のあり方は社会の中の人と人との関係性によっている。消費は、一人の人間と社会の間の関係をどう形成するかという関係性の確認の手段という側面もある。例えば、戦後社会の時代には息苦しいムラ社会から背伸びし、脱出するための措置としての消費が行われていた。例えば永山則夫(連続射殺魔)は実家の青森では極貧を馬鹿にされ、集団就職で東京に出ると貧しい田舎者としかみられず、周囲にはそのような定型イメージでアイデンティティを規定され、そのパッケージでしか見てもらえず「まなざしの囚人」に陥り、彼自身、そこから抜け出そうとして行ったのは、別のパッケージを身にまとうことだった。例えば外国産のたばこ(洋モク)「ポールモール」を吸う。これは記号消費といえる。彼のような極端な例に止まらず、一般的にも、自動車で言えば、今はカローラに乗っているけれど、課長になったらコロナに乗り換えて、いつかはクラウンに乗りたいというような乗用車のグレードが上がり、自分の出世していけば、この息苦しい空気に支配される世界で、支配に回ることができる。あるいは逃げられるかもしれない。そのような欲求が、消費をコントロールしていた。こうしたモノと自分を重ね合わせるようなことを可能にするためには、そのモノの持っている記号としての価値を社会全体で共有するような基盤が存在していなければならない。そして、この記号価値の共有はマスメディアに情報が一元化されることによって成立していた。例えば、テレビCM、新聞や雑誌の広告。消費の情報をマスメディアで入手し、服装や持ち物といった具象的な表層性によって自分をパッケージし、そのパッケージ、の基盤をマスメディアによって国民の多くが共有していた。そこで、背伸び消費のような記号消費が成立したのだった。 90年代行は、右肩上がり経済成長が終わりをつげ、収入が増えて肩書が上昇することは期待できない時代となった。このよう社会では、さっきのような所有する乗用車のグレードがステータスという幻想が成り立たなくなることを意味する。加えてインターネットのよって情報流通が変化し、マスメディアが衰退し情報はビオトープ化する。記号消費をマスメディアという情報のマス回路による共通認識が支えていたが、これが分解していくことになる。そうした時代にあって、消費するという行為の向こう側に、他者の存在を認知し、他者と繋がり承認してもらうというあり方に変わっていった。消費が承認と接続のツールとなっていった。そしてその承認と接続は、お互いが共鳴できるという土台があってこそ成り立っていく。この「共鳴できる」「共感できる」という土台をコンテキストという。コンテキストは消費を通じて人と人とが繋がるための空間、その圏域を作るある種の物語のような文脈のことである。例えば商品を買いたいという欲求だけでなく、作り手が持っているポリシーや、購入することでそれが作り手の側に「良いこと」として伝わるというようなことが加味されて、お金を払うという消費行動も生まれてきている。これは消費の向こう側に人の存在を見るということ。他者の存在を確認するということになる。例えば大好きなレストランで食事をするというとき、我々は単にサービスと対価を交換しているだけではなく、「素晴らしい食事を作ってくれる人」「食事をおいしく食べてくれる人」という相互のリスペクトがあって、お金だけでなくそうしたリスペクトも交換している。そこでは消費は、そうした人々のつながりに過ぎない。 一方で、シンプルかつ十分な機能さえあれば、それで十分という機能だけを消費するというあり方も広がっている。マスメディアの衰退とともに記号消費は消滅していくことになり、21世紀は機能消費とつながり消費に二分された世界となっていくと考えられる。このように二つの方向に消費が向かっていくとすれば、その行動はモノの購入という消費の行動に強く繋ぎ止められる必然性さえなくなっていく可能性がある。極言すれば、機能がほしいのなら、モノを買わなくても借りたり共有すればいい。つながりがほしいのなら、モノを買わなくてもつながれる場があればいい。これは当然の進化の方向性と言える。この行きつく先が「クラウド」と「シェア」ということではないか。手元のモノはどんどん少なくなり、身の回りは極限までシンプルになる。人と人とのつながりがきちんと存在して、コミュニケィションを活き活きと楽しむことができれば、余計なものはいらない。そういう時代にはモノではなく、互いにつながるモノガタリを紡ぐ時代となる。このような文化になっていけば、従来の大量消費の文脈で語られていたような消費動向が変化するのは当然だ。 使用久恵も不要である無所有の方向性。「つながり」を求める場はモノの購入ではなく、何かを「行う」という行為へと変移してきている。実際に、消費が伸び悩む一方で、農業や登山といった「行為」に対する関心が高まっている。また、商品そのものよりも、ツイッター等の「場」に興味が移って来ている。商品の消費から、「行為」や「場」の消費へ。モノから、何かをする「コト」へ。記号消費による逃走から、接続と承認の象徴としての共鳴へ。この消費社会の変容は、我々の社会の強い背景放射となっている。そしてこの背景放射が広く世界を覆っていき、そのうえで様々な情報はやり取りされ、マスメディアではないミクロなビオトープが無数に生まれていっている。そして、つながりという背景放射の影響を受けて、情報の流れもつながりに強く引き寄せられていかざるを得ない。 第三章 「視座にチェックインする」という新たなパラダイム 第一の点では、ツイッターやフェイスブックと提携する、いわば巨大プラットフォームの生態系に「おんぶにだっこ」的にモジュールとして参加し、共存共栄を図っている。このようなフェイスブックやツイッターをプラットフォームとして利用するが、フラットフォームの参加者にとっては、ツイッターやフェイスブックに参加するする付加価値が高まることになる。フォースクエア以外でもフラッシュマーケットと呼ばれるサービスもそうだ。これは一言でいえば共同購入で、例えば場所を登録してアカウントを取得すると、その場所の地域のクーポン情報が得られる。しかし、このクーポンには最低申込人数や期限が設定されている。これにより、売る側は一定人数の売上を得られる。一方消費者の側では、期限内に最低申込数に達するためユーザー同士での協力が必要で、この情報をツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアに流すと、ユーザー同士の様々なやり取りが行われる。フラッシュマーケットの自前のウェブサイトではそのようなやり取りの場は用意されておらず、その仕組みさえない。完全にプラットフォームに依存していると言っていい。ここには、ソーシャルメディアの新たなヒエラルキー構造が現われてきている。それは大きく分けると次の三つの階層に分けられる。ひとつめは、超巨大プラットフォーム。数億人というユーザーが登録し、それらのユーザーがどのように友人や知人と繋がっているのかというソーシャルグラフをすべて抱え込んでいるツイッターやフェイスブック。次の階層が、中規模モジュールで、超巨大プラットフォームのソーシャルグラフを再利用するかたちで、特化したサービスを運営するフォースクエアのようなビジネス。そして、小規模モジュールは、さらにその裾野に、例えばツイッターを使い易いアプリケーションを開発したり、フェイスブックやツイッターの自分のアカウントを解析する等の様々なツールを開発したり、といったスモールビジネスで運営さているビジネス。逆目で見れば、フォースクエアは、自らソーシャルグラフを擁しているという有利さは最初から放棄している。そのため、他の部分でユーザーを惹きつけることが必要になる。そこで、三つの仕掛けのうち残りの二つをうまく盛り込むことにより、非常に魅力あるサービスに仕立てている。
第2の仕掛けは、場所と情報の交差点をうまく作り出したこと。これにより、フォースクエアは類似のサービスとの差別化を図った。例えばグーグル・ラチチュードは位置情報を通知するサービスを行う。これに対してフォースクエアは居場所としての「位置」ではなく「場所」と考える。居場所を検知すると、その周囲の様々な店や施設などを候補としてリスト表示し、その中からユーザーが選べるようにした。このことで、通知を受けた友人は、例えば「彼はいま渋谷の東急百貨店東横店にいるのか。夕方だし、晩御飯おかずでも買っているのかな」という付加情報を認知することができる。そして、フォースクエアはこの「場所」を単なる施設名や店名として利用するだけでなく、そこに付加価値としての情報を加えることを考えた。つまり、レストランの口コミ情報が掲載される。このような場所と情報の連携というのは、つきつめて言えば、リアル空間とバーチャル空間の連携に他ならない。リアル空間のある一点である「場所」と、インターネットというバーチャルな空間に存在しているコードである「情報」。この二つが接合されるというのは、実は新たな世界の幕明けにもつながっている。フォースクエアのようなサービスは空間と時間とウェブと人間関係を同時に結びつけることによって、バーチャルとリアルの境界線はあいまいになり、例えば、ネットが屋外で人々が活動するための基盤にもなっていく可能性がある。屋外に出て活動しているときにも様々な利用シーンがあり得るという可能性を開いたと言える。似た例で、ニューヨークの「フードトラック」というトラックを利用した屋台が人気を博している。この大きな特徴は、ツイッターやフェイスブックにアカウントを持ってひっきりなしに情報を発信していることである。実はフードトラックの屋台は神出鬼没で同じ場所に屋台を出すとは限らず、そのため馴染み客でも美味しいフードトラックとの出会いは偶然の産物だった。これは一期一会ともいえる出会いで特徴的であったが、ツイッターやフェイスブックに屋台の出没情報やメニューが発信されると、それを追いかけ、客と屋台の持続的関係が樹ち立てられ、さらに客はアカウントに感想をリプライすることができると、今度は会話も成立することになる。このことにより、客とフードトラックの関係性は刹那的な関係から、持続する関係性になっていく。「場所」と「情報」の交差点をうまく作り出すことによって、そこに移動屋台と客の新しい回路が開かれた。その新たな回路こそが、これまでとは異なったフラットな関係性を生み出している。それは常に互いの存在を意識し、「そこにあなたがいるんだ」という存在を確認し合う関係。単なるカネもモノの交換だけでなく、そこに何らかの共感や共鳴が存在する関係がうまれてくる。この持続的な関係のことをエンゲージメントと呼ぶ。これは広告用語で、企業と消費者の間にきちんとした信頼関係を形成し、その信頼関係の中でモノを買ってもらう、広告の世界では、そういう関係性がマスメディア衰退後の世界では非常に重要なことだとここ数年強く認識されるようになっていて、それがエンゲージメントという言葉で呼ばれている。かつてのマスメディア広告の世界では、消費者と企業の関係は「与えられた関係」で、絞られた情報が、消費者にはテレビ、ラジオ、新聞や雑誌というわずかな媒体の前で、向こうから流れてくる大波のような情報を受け入れるだけであった。そうした一方的な情報の流れしか存在しないところでは、一方的な関係性にすぎず、消費者の側が能動的に選択する余地はなかった。しかし、ソーシャルメディアを介してつながる企業と消費者の関係は、持続的にものへ変わっていく。どのフードトラックをツイッターでフォローするかという選択は消費者の手に委ねられ、そこでフードトラックの情報をただ得るだけなのか、それともリプライして会話をやり取りし、より強い紐帯を持とうとするのかについても消費者は選ぶことができる。勿論企業の側も、どこまで消費者と個別に付き合うかというのは自由な選択として用意されている。つまり、互いにとって自由なエンゲージメント(契約)ということになる。そこにはフラットであるけれど、互いに尊敬する関係が生まれてきている。 エンゲージメント言う関係の中では、「個人か企業か」といった「誰が主体なのか」という枠組みは融解していくことになる。言い方を換えれば、企業も個人も一人の独立したキャラクターとして人格を持って語らなければ、エンゲージメントを誰かと生み出すことはできない。自分の言葉で語っている存在だけが、お互いにエンゲージメントによってつながることができるということなのだ。例えばツイッターは、そうした「自分の言葉で語っているかどうか」ということが非常に重要視される世界だ。企業で公式アカウントを取得しても、無味乾燥な公式コメントのようなツイートばかりしていては、フォローしてくれる人はごくわずか。逆に、短い140字の向こう側に温かみのある人の存在を感じられる企業アカウントに対しては、多くの人が愛情を抱き、結果的にたくさんのフォロワー数となって現われる。だからエンゲージメントに必要なのは、マイメディア広告のように強引に情報を送り届けることではなく、そこにコンテキストが共有されるような場を作っていくことが大切なのだ。そしてそのような場に、「情報を流す側」「情報を受け取る側」という固定された関係性ではなく、主客一体となって互いに情報を交換する関係性を作っていくことだ。そうした場は情報を配信する側によって一方的に作られるのではなく、使用飛車と企業の相互の了解のもとに、場は生み出される。つまりは、消費者の側が一定の積極性を持ってそこに参加し、そこで企業に対してエンゲージを求めるという「行い」が必要になって来る。ここで、話はフォースクエアに戻る。 フォースクエアの第3の仕掛けは、この「行い」に関連する。フォースクエアは、「場所」と「情報」を結び付け、その結び付けによって、企業や個人の間に新たに回路が開き、そこにエンゲージメントが形成されていく。そして、その場所と情報が結びついたポイントに消費者がたどり着くため、フォースクエアが用意したのは、「チェックイン」というコンセプトだ。どこかの場所に到着して、どこかでチェックインすることによって、様々な情報をそこで得て、誰かと繋がることができる。このチェックインこそが第3の仕掛けというわけだ。「チェックイン」とは、この場所にいるという通知手続をユーザーが行うことによって、その情報を友人に通知したり、その場所の情報を得ることになる。類似のグーグル・ラチチュードには、このような機能はなく、自動的に自分の居場所を友人に通知するように設定されていたことから、プライバシーの問題を引き起こしてしまった。実は、このプライバシー問題はインターネット広告にとって非常に重要な懸念となっている。というのも、多くのネット広告が勝手に客の情報を収集し、勝手に客に情報を送りつけるという仕組みを取っているからだ。ライフログという手法で、例えばアマゾンは客が購入したデータやページを閲覧した履歴から関連商品のおすすめのような機能を付けている。このような動きが全般にある。しかし、自分のあずかり知らないところで自分の情報を奪われているというプライバシー不安をどうしても呼び起こしてしまう。そこで、自分の行動をきちんと自分が意識したうえで、他者に教えることを同意していれば、そのような問題の起こることはない。そのカギとなるのが、フォースクエアの「チェックイン」と言うことができる。フォースクエアでは、自分がいる場所は暗黙的には配信されず、チェックインという行為を通して初めて配信される。これにより、「自分が今いる場所」言う考えようによっては非常に危険な情報を、ユーザーの側が不安に感じることなく安心して友人たちに送信できるようになっている。類似のグーグル・ラチチュードが居場所情報を自動配信する、つまり暗黙の裡にやってしまうことに比べると、両者の違いは明白になる。そして、このチェックインは、明治的であることにより、プライバシー不安を解消してくけると同時に、もう一つの重要な意味として、「自分がどのように情報を得るのか」という立ち位置を、ユーザーの側が自分自身で選べるようにしていることである。つまり、自主性を情報取集に持ち込んでいるということだ。そして、このチェックインという機能はほかの分野への広がりの可能性がある。例えば、フェイスブックの「いいね!」ボタンもそうだろう。このように考えると、チェックインは、場所以外にも情報を集めるためのブイのようなものをネットの海に差し込む行為ということも可能だ。膨大な情報ノイズの海から、何の手懸りもなく情報を拾い集めてくることはとても難しい。しかし、「今自分が居る場所」「面白そうなブログ」といった手懸りがあれば、それを軸にして情報を的確に拾い集めることができる。それは、検索エンジンのキーワードに似ている。言うなれば、情報を集めるための「視点」のようなものだ。この「視点」によってインターネットの情報をフィルタリングすることができる。しかし、この方法には「視点」ということで視野角や立ち位置や方角が固定化され、「タコツボ化」する危険性が潜んでいる。視点の固定化とタコツボ化は表裏一体で、視点を固定しないと情報はうまく得られないが、視点を固定した瞬間に情報はタコツボ化してしまうというジレンマがある。 しかし、これは一人の人間に限ったことで、二人の人物がまったく同じ価値観、同じ世界観を持つということはあり得ない。どんなに近しい人でも、そこには微妙な差異があって、その差異が情報の集め方の揺らぎを生じさせる契機となる。そのことがタコツボ化を乗り越えるための突破口となっている。検索キーワードや場所、ブログは人格のない無機物であり、そうした無機物に依拠する限り視点は固定されてしまい、タコツボ化に進んでしまう。しかし、人が一人ひとり別の価値観、世界観を持っていて、その人間を視点とすると、揺らぎがうまれタコツボ化を使用時させない可能性がある。これは日常生活でも、他人との出会いによって、今まで思いもしなかった視野が開けるという経験は誰でもあるはずだ。ブログの場合なら、キーワードで検索してたどり着いたブログのエントリーには、自分が探したキーワードに関わる話しか書かれていないかもしれない。しかし、そのブログが気に入って、ブロガーのファンになり、毎日読んでみると、日ごろは絶対に興味を持たなそうな分野の話をそのブロガーが書いていて、急に自分も好奇心を掻き立てられることもあるだろう。さらに、ブログならトラックバック、ツイッターならツイートしている人を関連して新たにフォローしてみれば、情報はさらに広がり、情報をフォローしていることを宣言することにもなる。これは、ソーシャルメディアですでに行われている。 これをまとめてみると、つぎのようになる。視座にチェックインし、視座を得るという行為るこれは自分自身の視座とは常にずれ、小さな差異を生じつつけている。「自分が求める情報」と「チェックインされた視座」は微妙に異なっていて、そのズレは収集された情報に常にノイズを齎すことになる。そして、このノイズこそが、セレンディピティを生み出すものとなる。期待していなかった情報が、その「ズレ」の中に宝物のように埋まっている可能性があるということだ。第二に、視座にチェックインするという行為では、情報そのものを取得するのではなく、その情報を得るための視座を得るだけでよく、だからフィルタリングのハードルが大幅に下がる。情報のノイズの海から一かけらの情報を掬い上げるのは、干し藁の中から一本の針を探すような作業であって、非常に困難を伴い高い技量が求められる。でもその海の中に点在している視座は、情報全体の量と比べればごくわずかであって、それを探す作業は比較すればかなり容易になる。第三に、この明示的で自主的な「視座へのチェックイン」という行為はプライバシー不安を回避している。自らの手で誰かの視座を選択し、その人の目で世界を見るという行為は、自分自身をさらけ出す必要は全くない。視座にチェックインすることで、我々は広大な情報のノイズの海をわたり、圏域が細分化された湿地帯のビオトープの中へと歩みを進め、そこに生息するカニやエビや小魚たちと共鳴しあい、その小さく豊かな空間の中で生きていくことができる。 第四章 キュレーションの時代 人のつながりによってこそ、我々は情報を的確に受け取ることができる。そしていま我々は、モノの消費よりも人のつながりを求めている。これは消費社会と情報社会を大統合させる大きな流れの可能性もある。ソーシャルメディアによって細分化されたコンテキストが絶え間なく生成され、そのコンテキストが絶え間なく生成され、そのコンテクストという物語を通じて我々は共鳴し、共感し、そして接続してお互いの承認を受けることができる。そういう時代の中に足を踏み入れつつある。例えば眼鏡を買うという行為は、即物的には単に「見えないものを見えやすくする」という機能を購入するだけだが、しかしそこには「眼鏡を売ってくれた田中さんの笑顔を思い出す」というつながりをも差し挟まれていく。つまり2010年代の消費の本質は 商品の機能+人と人とのつながり と言うことができる。それと同様に情報が流れているということは、情報を得るという即物的な機能だけではなく、そこに「情報をやりとりすることで人と人がつながる」という共鳴が同時に成り立つような時代になってきている。 情報収集+人と人とのつながり ということになれば、そこには共鳴と共感を生み出すためのコンテキストの空間が絶対不可欠であって、そしてそのコンテキストを生み出すためには、検索キーワードや場所や番組といった「視点」の杭だけでは成り立たず、だからこそそこに「人」が介在する必要がある。人が介在することによって、「杭」は立ち位置や見る角度といった「視点」だけではなく、世界をどう見るのか、どう評価するのかという世界観や価値観という「視座」に進化する。そして、人格をもった人間という視座につながることによって、我々は情報を得るのと同時に、視座=人とつながることができる。言い換えれば、視座とはすなわち、コンテキストを付与する人々の行為に他ならない。そして我々はその視座=人にチェックインすることによって、その人のコンテキストという窓から世界を見る。 そもそも、我々は情報のノイズの海に真っ向から向き合うことはできない。インターネットが社会に普及し始めると、マスメディアが情報を絞っていた時代に比べれば、情報の量は数百倍か数千倍、それ以上になっている。その膨大な情報のノイズの海の中には、正しい情報も間違った情報も混在している。これまでは新聞やテレビがある程度はフィルタリングしていたので、それを概ね信じていればよかった。ところがネットにはフィルタリングシステムがないので、自分で真贋を見極めなければならなくなった。ところが、それは不可能なのだ。一時情報の真贋を自分では判断できず、その情報を利用しているブログでも事実であることを前提に議論していれば、それを読む人は真贋の判断はさらにできない。一方で、田原総一朗の著名記事に書かれていれば多くの人は信頼するに違いない。その理由は、これまで田原氏の書いてきた記事が信頼に足る記事が多かったからだ。つまり、事実の真贋を見極めることは難しいが、それに比べれば、人の信頼度を見極めることの方が容易であるということだ。さらに、人の信頼を得るということは、ソーシャルメディアの時代になって依然と比べものにならないほど容易になっている。それは、過去の投稿や記事が検索によって容易に過去にどのようなことを書き、どんな発言をしていたかをわかってしまうからだ。ネットで活動するということは、つねに自分の行動が過去の行動履歴も含めてすべて透明化され、検索することで容易に読まれてしまう。そういう自分をとりまくコンテキストがつねに自分についてまわってしまう世界なのだ。それは、きちんと真っ当なことを言って世界観を一貫させて語っていれば、つねに自分の信頼をバックグラウンドで保持できる安定感のある世界であると言える。くだらないパッケージを被せたりしなくても、ちゃんと語っていれば、ちゃんと信頼される世界といえる。このようにしてソーシャルメディア上では、「人の信頼」というものが可視化され、すぐに確認できるような構想になっている。我々は情報そのものの真贋を見極めることはほとんど不可能だけれども、その情報を流している人の信頼はある程度推し量ることができるようになってきている。だからこそ、「人」を視座とする情報流通は、いまや圧倒的な有用性を持つようになり、我々の前に現れてきている。 この「視座」を提供する人を、英語圏ではキュレーターと呼び、キュレーターが行う「視座の提供」がキュレーションである。日本では慣用的に博物館や美術館の学芸員の意味で使われている。世界中にある様々な藝術作品の情報を収集し、それらを借りてくるなどして集め、それらに一貫した何らかの意味、企画展として成り立たせる仕事である。これは、これまで述べられてきた情報のノイズの海からあるコンテキストに沿って情報を拾い上げ、口コミのようにしてソーシャルメディア上で流通させるような行いと、非常に通底している。だからキュレーターということばは美術展の枠からはみ出て、今や情報を司る存在という意味にも使われるようになってきている。例えば美術展では、2010年夏の東京藝大美術館でのシャガール展では愛と幻想の画家という見慣れたイメージとは異なる、ロシアの民族的根源性とアバンギャルドとの関係が浮かび上がり、シャガールというコンテンツから既存のパッケージを引きはがし、そこに新たなコンテキストを付与する。そして、このコンテキストを付与したのは、ポンピドー・センターのキュレーターで、彼の持っているシャガールやロシア前衛主義への知識と教養、そして彼が持っているアートへの深く豊かな世界観があってこそ、このコンテキストは豊饒な意味をもって、我々の前に立ち並ぶことができた。 コンテンツとコンテキストという両方の要素があってこそ、我々はコンテンツをさらに深く豊かに愛することができる。そして、コンテンツとコンテキストは相互補完的な関係であって、コンテキストは決してコンテンツのおまけ程度の副次的な存在ではない。勿論、シャガールというコンテンツは、ポンピドー・センターのキュレーターのコンテキストがなくても、天才の作り出した素晴らしい作品として屹立しており、予備知識がなくても、見た瞬間に心が躍り素晴らしい感動と衝撃を与えてくれる。その意味では、コンテキストは所詮コンテンツに寄り添うだけの存在であって、単独に成り立つ要素ではないかもしれない。しかしアートの世界には、最初に紹介したヨアキムのように、コンテンツがなければ決して誰にも認知されずに終わってしまいかねないコンテンツも存在する。その典型がアウトサイダーアートである。 現代アートのメインストリームでは、作り手は表現者であるのと同時に自分の作品がどのようにして今の時代に受け入れられるのか、どこにその場を求めればいいのか、そしてどうプロモーションしていけばいいのかという編集的、ビジネス的センスまでもが求められている。作り手であると同時にキュレーターであり、エディターであり、プロデューサーであり、プロモーターでもなければならない。その方向性を突き詰めているのが、現代日本でいえば村上隆と言える。彼は世界市場で自分の作品を売っていくために徹底して歴史と市場を分析し、計算し、緻密な戦略を立てた。彼の『芸術起業論』では「藝術作品単体だけで自立はできません。鑑賞者がいなければ成立しないものです。もちろん作品版倍もお客様あってのものです。どんな分野でも当然の営業の鉄則が、芸術の世界でだけは『なし』で済むなんていう都合のいいことはありません。」「欧米では芸術にいわゆる日本的な、曖昧な『色がきれい…』的な感動は求められていません。知的な『しかけ』や『ゲーム』を楽しむというのが、芸術に対する基本的な姿勢なのです。欧米で芸術作品を制作するうえでの不文律は、『作品を通して世界芸術での文脈を作ること』です。僕の作品に高値がつけられたのは、ぼくがこれまで作り上げた美術史における文脈が、アメリカ・ヨーロッパで浸透してきた証なのです」つまり、彼は自分で自分の作品にコンテキストを付与し、そのコンテキストがアメリカ・ヨーロッパの美術シーンに接続できるような戦略を立てていったということで、彼は天才的なアーティストであると同時に、極めて優秀なキュレーターでもある。しかし、アウトサイダーアートの作り手たちは、そのような戦略的発想は一切持っていない。自分以外には興味がなく、ただ自分のためだけに作品を作っているような人たちと言える。だからこそ、キュレーターという存在が必要になって来る。キュレーターがアウトサイダーアートにコンテキストを付与し、それを現代の芸術界に重ね合わせていく作業を行っている。つまりは、アートと言う巨大なプラットフォームの上で、表現とキュレーションが分離し、それをモジュール化して存在しているという構図になっているのだ。 このようなアウトサイダー/インサイダーの境界、そしてその境界を設定するキュレーションの方向性は我々を取り巻く情報の海そのものにも適用される概念になっている。情報のノイズの海から、特定のコンテキストを付与することによって、新たな情報を生み出すという存在としてキュレーターが要請されてきている。一次情報を発信することよりも、その情報が持つ意味、その情報が持つ可能性、その情報が持つ「あなただけにとっての価値」そういうコンテキストを付与できる存在の方が重要性を増してきているということなのだ。情報爆発が進み、膨大な情報が我々の周りをアンビエントに取り囲むようになってきている中で、情報そのものと同じぐらいに、そこから情報をフィルタリングするキュレーションの価値が高まってきている。 セマンティックボーダー(言葉の壁)と言う言葉がある。世界の複雑さは無限で、その無限である複雑をすべて自分の世界に取り込むことはできません。ノイズの海と私たちが直接向き合うことは、とうてい不可能だ。だから動物や人間は、様々な情報の壁を設けて、その障壁の内側に自分だけのルールを保っている。言い換えれば、外はノイズの海の中から、自分のルールに則っている情報だけを取り込むようにしている。ノイズの海には様々なルールが無限に存在しているけれど、そこから自分に合ったルールだけを取り出すということをしている。言い換えれば、一人の個人が社会の中で生きていくためには、社会から情報を取り入れることが必要だけれども、社会に存在しているすべての情報を取り込んでしまうと、情報のノイズに埋もれて、どのような変化が社会で起きているかを見通すことができなくなってしまう危険性がある。だからそこに「意味の境界」として、セマンティックボーダーを作らなければならなくなる。つまりは情報のフィルタリングシステムである。これまで述べられてきた「視座」へのチェックインと、その視座を提供する無数のキュレーターという流れに沿って言えば、ソーシャルメディアの世界ではセマンティックボーダーはキュレーターによって絶え間なく組み替えられていく。小さなビオトープの圏域がつくられ、そこにある法則性が生まれ、そのコンテキストに沿ったセマンティックボーダーによって情報は外部から取り入れられていくことになる。キュレーションがノイズの中から情報を取り出し、その情報にコンテキストを付与しているということは、すなわち、それまでアウトサイダーの情報だったものを意味をあたえることによってインサイダーに変換する、というようにセマンティックボーダーを再設定するで、そこに意味を与えている。そこで大切なのは、このセマンティックボーダーが正常に働くためには、二つの要件があることだ。第一は、セマンティックボーダーし常に組み替えられ続けるということ。硬直しないということ。第二は、セマンティックボーダーは内側の論理によってではなく、外部のだれかによって作られるべきだということ。 これは、これまで扱ってきたコンテンツとコンテキスト、そしてコンテキストを生み出すキュレーターの視座と、その視座にチェックインする人々という構造。つまり、第三者であるキュレーターが付与するコンテキストによって、視座は常に組み替えられ、キュレーターがソーシャルメディアの普及の中で無数に立ち上がってくれば来るほど、その視座は無限に拡張されていく。それこそがセマンティックボーダーの組み替えに他ならない。そしてこのセマンティックボーダーの不安定化は「ゆらぎ」を生み出し、その「ゆらぎ」こそがセレンディピティの源泉ということだ。マスメディアにあるパッケージ消費の時代は、「マスメディアが生成した情報だけを読んでいればいい」というセマンティックボーダーが設定されていたが、このボーダーは既に硬直し、内部論理だけによる自閉的で独善的な行き方がマスメディアという組織に起きてしまったからと言える。しかし、2000年ころから、マスメディアが発信した情報と個人が発信した情報の境界線が曖昧になってきた。自己完結的なマスメディア言論は著しく劣化し始めており、専門家ブロガーの言説に対抗できないというようなケースは多く起きている。 アウトサイダーアーティストの表現は、キュレーターによりフィルタリングされ、そこに新たなコンテキストが付される。その新たなコンテキストによって、インサイダーとアウトサイダーのセマンティックボーダーは拡張され、新たな血がつねにインサイダーの中へと流れ込んでくる、これがアートを活性化させていくということなのだ。それと同じように、我々の世界の膨大な情報のノイズの海から、それぞれの小さなビオトープに適した情報は、無数のキュレーターたちによってフィルタリングされていき、それらの情報にはコンテキストが付与され、そのコンテキストがキュレーターによって人それぞれであるがゆえに「何が有用な情報なのか」というセマンティックボーダーはゆらいでいく。そのゆらぎこそが、セレンディピティの源泉となる。美術のキュレーションと異なり、ソーシャルメディアにおけるキュレーションは、無数のキュレーターと無数のコンテキストによって常に組み替えられていく。だからこそ、セマンティックボーダーが常に新鮮であることを約束させられているということになる。ソーシャルメディアには無数のキュレーターが存在する。ツイッターには様々な分野で影響力のあるユーザーがそれぞれのフォロワーに情報を流し、ミクシィやフェイスブックには様々なコミュニティが立ち上がってきている。ブログにはそれぞれの分野に興味ある読者が固定されている。そういう複雑な山脈のようなソーシャルメディアには、様々な尾根、谷、テラスにそれぞれのビオトープがあり、そうしたビオトープに膨大な数のキュレーターが存在していて、それぞれに生息している人々に向けて日々情報を流し続けている。そこでは無数のキュレーターと無数のフォロワーが、日々接続を繰り返しながら情報の交換を行っている。 これは社会の関係構造が大きく変わったことに対応したものだ。以前の経済成長をバックにした「いつかは誰でも豊かになれる」という幻想を持てた時代では、360度の関係性という家族、会社、国家というような同心円的な共同体のピラミッド的な秩序に丸抱えで依存していた。例えば、学卒で企業に入社し、年齢とともに肩書があがり、乗用車もカローラからコロナ、クラウンへと乗り換えるというような人生プランが描けた。決まりきったような人生だけれど、その中に漬かっている人には安心感があり、繭にくるまれたように住みやすい場所であった。これは「言葉を口にしなくても分かり合える」ような暗黙的な関係性の社会であって、このような「暗黙」を支えていたのが、新聞やテレビ等のマスメディアによって作られた共同幻想だった。同じテレビ番組やCMを見て同じ商品を購入することでたったひとつのメディア空間に国民全員がくるまれ、それが暗黙的な相互理解の礎になっていたと言える。そこでの、「業界」や「会社」あるいは「営業部」といった共同体はそれぞれ同心円的な囲い込みを進めタコツボ化することになる。 しかし、現在では会社や業界のような、自分を繭のように包んでくれるようなコミュニティなど存在しないことは明白になった。その代わりに我々の社会の人間と人間の関係は多層化し、多方向化し、複雑な山脈のように構造が変化してきている。我々は、もはや「同心円」的な関係性ではなく、もっと「多心円」的な関係の中に生きている。関係は無数に立ち現われては消え、つねにアドホックなに存在する。そうした人と人との時々の新鮮な関係はつねに確認していかなければならない。つまりは明示的な関係へ変わりつつある。 マスメディアが支援する暗黙的で同心円的で自己完結的な関係から、ソーシャルメディアが支援する、明示的で多心円的で不確定な関係へ。このように我々の関係は変化してきている。自己完結的な閉鎖系は、情報の流れを固定化させ、そしてまた情報が内部の法則によってコントロールされてしまうことで、硬直してしまう。この硬直は、同心円的な戦後のムラ社会には都合がよかった。しかし、グローバリゼーションの中でアウトサイドの世界が変化していっているとき、こうした情報の硬直化は間尺に合わなくなってきている。一方で、ソーシャルメディアの不確定に情報流通は、外部から情報が流れ込み、セマンティックボーダーが常に組み替えられて、それによって内部の法則が次々に変わっていくことで、常に情報に「ゆらぎ」が生じている。絶え間なくセマンティックボーダーは組み替えられて、固定されない。そこがマスメディアによる閉鎖系によって硬直化していた情報流通が再現性を持っていたのと、全く異なり、ソーシャルメディアの中の情報は、決して二度と再現しない「ゆらぎ」とともに流れている。ということは、ソーシャルメディアでの情報流通とつながりは、つねに「一回性」というただ一度の出会いの中にある一期一会なのだ。
第五章 私たちはグローバルな世界とつながっていく しかし、その一方で、このようなアンビエント化の動きとはまるで矛盾するようにして、普遍主義の崩壊が言われ続けている。普遍主義とは、ヨーロッパで近代市民主義が成立してから、このヨーロッパ市民社会を「普遍的」であるとする、民主主義という政治体制、友愛や平等といった理念、これらは世界のすべてをおおいつくすことができる普遍的なシステムだという考え方のことをいう。文化でいえば、ヨーロッパの美術、クラシック音楽が理想的な藝術として世界文化の標準として君臨していた。しかし、よく考えてみれば、これはヨーロッパと言う一ローカルの考え方であるに過ぎない。さらにいえば、ヨーロッパの中でも、普遍として一概に言えなくなる事態が発生し、何が普遍か、ということがはっきりしなくなってきている。このように普遍主義が崩壊し、細分化した圏域で閉鎖的になっていく文化と、インターネットによってアンビエント化し、開放的になっていく文化、ひとつは断絶で一つは共有とは、文化のそれぞれ別のレイヤーのことを説明している。つまり、我々の文化は断絶し、共有されている。 ユーチューブやアイチューンなど、コンテンツを共有するためのプラットフォームがグローバル化していく中で、アメリカに住んでようが中国に住んでいようが、安価にコンテンツを発信し、楽しみ、共有することは世界中のだれもが可能になっていく。そのためのコストは低下し、国ごとの違いは関係ない。従来は発信力の強い国の文化が配給力を持っていた。それが、普遍文化の背景ともなっていたわけだ。ところが、インターネットのメディアが普及し、コストが低下していくと、情報発信パワーにはあまり意味がなくなってくる。そもそも情報発信がパワーたり得たのは、情報発信が絞られていたマスメディアの時代で、この時代までは、情報の供給に需要が追い付かなかったからなのだ。しかし、今や情報量は膨大な量となり、供給が需要を完全に上回った状態となった。このようなメディアの環境の中では情報発信のパワーは相対的に失われたようになる。もとろん良質なコンテンツが価値を失うということではない。しかし、情報の量が多くなるに従い、そういった良質のコンテンツも数が増える。今では、プロが作った少数のコンテンツを映画メジャーや出版、メジャーレコードが配信していただけだったのが、ソーシャルメディアを介して続々と配信されるようになった。これこそがインターネットのプラットフォームのパワーと言える。 このことは情報アクセスのパラダイム転換を促すだろう。メディアのコンテンツ発信のパワーは弱まり、その一方でコンテンツ共有のプラットフォームがグローバル化し、巨大な基盤となっていく。我々はその巨大なグローバル化したプラットフォームの上で、無数のビオトープを形成し、そこに無数間キュレーターを生み出し、いたるところに生息しているキュレーターに我々はチェックインし、その視座によって情報を縦横に得ていく。グローバルなプラットフォームの上で、コンテンツやキュレーター、それに影響を受けるフォロワー等が無数の小規模モジュールとなって存在するという生態系が生まれる。このようなグローバルなプラットフォームの上で、より細分化された文化圏域のコンテンツが縦横無尽に流通することが可能になる。また国ごとの垂直な情報圏域では、マスメディアは崩壊し、ミドルメディア化して細分化していく、その一方で、その細分化されたミドルメディアは、グローバルな方向へは水平に流動化していく。 それが進むと一つの国の国民が全員で同じ文化を共有するという考え方が幻想だったことが明らかになり、国内でも、都市と地方、富裕層と貧困層などで文化の分断が進み、それぞれが違う文化圏を形成するようになってきて、それぞれの細分化それた圏域によって必要とされる情報は異なり、そうした情報は同時にグローバル化される。そのような時代においては、プラットフォームという大きな船に乗ることによって、文化圏域も同じようにたやすく国境を越えていく。同じ国に住んでいる、でも異なる文化圏域の人よりも、国は異なるが同じ文化圏域に属している人の方が近いと思えるようになってきている。 グローバルなプラットフォームが普及していけば、民族性やそれぞれの国の独自性が失われるのではないか、という批判もある。例えばハリウッド映画やアメリカの音楽やマクドナルドやGAPのファッションが世界中を席巻したように。世界中の若者がアメリカ発の映画や音楽やファッションにどっぷりと浸かる。いわゆる文化帝国主義に浸食されてしまうという危険。しかし、そうした文化帝国主義が成立するためには、実はマスメディアによる情報の独占が絶対に必要だ。常和鵜の供給が絞られ、その細い情報流路に沿って、帝国主義的な文化が集中豪雨のように流し込まれるということが必要なのだ。 逆に、グローバル化したシステムでは、情報の伝達は今までよりずっと容易になり、だからこそローカルカルチャーの重要性がいつそう高まってくる。歴史や地理、文化の多様性を受け入れることによって、いくつものシステムやモデルが共存し、進化し、互いに影響し合って、そして分裂し、融合していくような、そういう新たな文化の世界。つまり、グローバルプラットフォームの上で情報が流れるということは、多様性がそこに内包され、自立・共存・発展するローカル文化の集合体を生み出していくことになる。 グローバリゼーションと画一化は、決してイコールではない。多様性を許容するプラットフォームが確立していけば、我々の文化は多様性を保ったまま、他の文化と融合して新たな文化を生み出すことができる。その世界で新たなまだ見ぬ文化は、キュレーションによって常に再発見されて続けていく。 この本は、著者が今、このような動きの真っただ中にいて、その渦中で書いているような本で、よく言えば、ビビッドに伝わるものです。その反面、考えが十分に整理されていないため、結構熱く読んでいても、結局何を言っているのかがよくわからなかったりする、ところがあります。全体の論旨というのも、可能性の議論に乗っかっているため、展開があるというよりは、例示が後から後から出てくるという感じで、興味が先へ先へと進むというのではないので、部分を拾い読みして、それぞれの事例というのかエピソードがそれぞれ面白く、それぞれが独立した内容として読めるので、ピンポイントで味わうくらいが程良い読み方ではないかと思います。なお、この本での議論は、このブログで同時並行のようにアップしてきたIR担当者の雑感の中で参考のネタとして使わせていただいています。
|
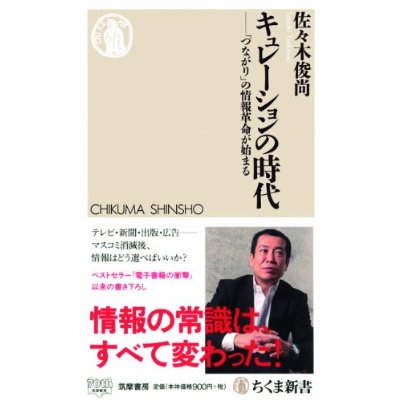 プロローグ ジョゼフ・ヨアキムの物語
プロローグ ジョゼフ・ヨアキムの物語