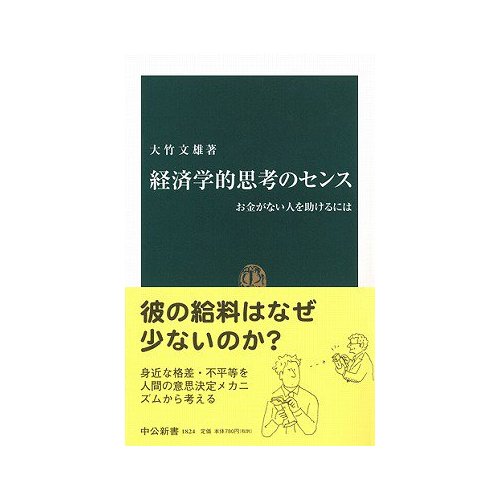 「お金のない人を助けるには、どうしたらいいのですか?」という小学5年生の発した問いに答えるところから、著者は、金持ちと貧乏人という所得格差の発生理由を明らかにし、貧困を解消するための方法を考えることは、経済学に課せられた大きな仕事の一つであると言う。この所得の重要な部分を占める賃金に格差が生じる基本的な原因は、生産性の差である。個人間に生産性の差が生じるのは、生まれつきの才能、教育、努力、運などが個人により異なるから。しかし、生まれや才能で収入に差についてしまえば、人々は意欲(インセンティブ)をなくしてしまうだろう。他方で、努力して成果をあげても収入が同じあれば、また人々は意欲をなくすであろう。これが、経済学でリスクとインセンティブのトレードオフ(二律背反)という問題という。所得再分配の問題が難しいのは、このトレードオフの問題と同じであると筆者は言う。そして、社会における様々な現象を、人々のインセンティブを重視した意思決定メカニズムから考え直すことが、経済学的思考法であると著者はいう。貧しい人を助けなければならない、というだけで思考を停止するのではなく、その発生理由まで、人々の意思決定メカニズムまで踏み込んで考える。これが経済学的思考法であると著者言います。さらにもう一つ、著者が強調するのは、因果関係をはっきりさせることである。これらのことを含めて、この本の目的は、お金がない人を助ける具体的方法を提示することではなく、お金がない人を助けることの経済学的な意味を考えていくことで、その場合のキーワードとなるのは、インセンティブと因果関係である。
「お金のない人を助けるには、どうしたらいいのですか?」という小学5年生の発した問いに答えるところから、著者は、金持ちと貧乏人という所得格差の発生理由を明らかにし、貧困を解消するための方法を考えることは、経済学に課せられた大きな仕事の一つであると言う。この所得の重要な部分を占める賃金に格差が生じる基本的な原因は、生産性の差である。個人間に生産性の差が生じるのは、生まれつきの才能、教育、努力、運などが個人により異なるから。しかし、生まれや才能で収入に差についてしまえば、人々は意欲(インセンティブ)をなくしてしまうだろう。他方で、努力して成果をあげても収入が同じあれば、また人々は意欲をなくすであろう。これが、経済学でリスクとインセンティブのトレードオフ(二律背反)という問題という。所得再分配の問題が難しいのは、このトレードオフの問題と同じであると筆者は言う。そして、社会における様々な現象を、人々のインセンティブを重視した意思決定メカニズムから考え直すことが、経済学的思考法であると著者はいう。貧しい人を助けなければならない、というだけで思考を停止するのではなく、その発生理由まで、人々の意思決定メカニズムまで踏み込んで考える。これが経済学的思考法であると著者言います。さらにもう一つ、著者が強調するのは、因果関係をはっきりさせることである。これらのことを含めて、この本の目的は、お金がない人を助ける具体的方法を提示することではなく、お金がない人を助けることの経済学的な意味を考えていくことで、その場合のキーワードとなるのは、インセンティブと因果関係である。
著者は、生活の身近な話題に対して、このような経済的思考で切り込んでいきます。例えば、「女性は、なぜ背の高い男性を好むのか?」「美男美女は本当に得か?」「イイ男は結婚しているのか?」「プロ野球は戦力均衡がいいのか、巨人のような特定球団の一人勝ちがいいのか?」「プロ野球の監督の評価」「賞金とプロゴルファーのやる気」などなど。
このような議論を前提に著者は専門である賃金の話に入っていく。
日本的賃金慣行は、一般に、終身雇用、年功賃金、企業別組合であると言われてきた。それが1990年代以降、景気低迷が続いたことにより、かつては高生産性の源であるとされてきたものが非効率で間接費の肥大の原因と、評価が変わってしまった。
最初に、終身雇用について、実際に、日本企業はすべての社員を終身雇用制度で雇用しているかといえば、実態として長期雇用慣行の労働者の比率は、もともと20〜30%にすぎない。長期雇用慣行は大企業を中心として機能してきた。しかし、大企業は、本社従業員の数を少なくしている。その代わりに、長期雇用ではない、子会社や関連会社、パートタイマー、期間工、季節工といった従業員を多く雇用している。また、多くの女性労働者は雇用期間が短く、結婚や出産を機会に退職することが多かった。つまり、20〜30%の長期雇用が成り立つためには、その周囲に流動的な労働者層が必要だったのだ。また、大企業の正社員だからと言って、確実に定年まで雇用が保障されていたわけでもなく、過去にも例えば赤字が二期続くような経営危機の際には解雇や希望退職が行われてきている。1990年代以降の日本企業でリストラという名の解雇が多数生じたのは、日本企業の行動様式が根本的に変化したというよりも、多くの企業が赤字に陥るほどの経営危機に直面していたためと考えられる。
次に年功賃金について、年功賃金制度とは、勤続年数が延びるにしたがって賃金も上がっていく制度だと考えられている。年功賃金に関する議論の中で、労働者の生産性と賃金の関係という視点が抜け落ちることが多い。勤続年数が長くなると労働者の生産性が高くなるから賃金も高くなるという可能性である。この視点が欠けている人の議論においては、年功賃金制度を年金制度と同じように見て、企業の中で若い人たちが中高年を養っていると考えているように考えているように見える。つまり、年功賃金を賦課方式の公的年金制度と同じように見ている。賦課方式とは、勤労者が支払う公的年金がそのまま退職者への公的年金給付として支払われるシステムである。賦課方式の年金制度はねずみ講に似ている。ねずみ講のように新たな加入者が増えれば増えるほど、元の加入者は得をしていく。もし、このような企業の若い人が、中高年の高い給与を支えていることが年功賃金の理由であれば、従業員数が減少している企業で、年功賃金が成り立つとは考えられない。しかし、現実には従業員数の減少が続く企業でも年功賃金が成立しているのである。そのような企業では年功賃金をねずみ講として捉えることはできない。もし、ねずみ講型賃金制度としての年功賃金を保ってきたために過去の日本企業の人件費が安く抑えられ、高い利潤を生みたすことができ、その結果として株価も高かったとすれば、それは単に株価の評価が正当になされていなかったということである。
このような年功賃金制度は、日本特有のものであると考えられることが多い。しかし、このような賃金制度はホワイトカラーにおいては世界共通に見られることが分かってきた。このような年功的な賃金制度が存在してきた理由に関しての代表的な考え方が4つある。第1は人的資本論で、勤続年数と共に技能が上がっていくため、それに応じて賃金も上がっていくというものだ。第2はインセンティブ論で、若いときは生産性以下、年を取ると生産性以上の賃金制度で、労働者がまじめに働かなかった場合には解雇するという仕組みにして、労働者の規律を高めるというものだ。第3は、適職探し理論で、企業の中で従業員は生産性を発揮できるような職を見つけていくのであり、その過程で生産性が上がっていくという考えだ。第4は生計費理論で、生活費が年齢と共に上がっていくので、それに応じて賃金を支払うというものだ。まず、第1の理論について、勤続を重ねると技能が上がっていくという人的資本理論の考え方である。人は学校を出た時とまったく同じ技能レベルにとどまるのではなくて、毎年いろいろな経験を積んで、技能が上がっていく。人々の生産性が上がっていくということであるから、賃金が上がっていくのは当然である。もしそうであれば、中高年がふえるということは、より高い技能を持った人が増えるということを意味するので、生産性が増加することになり、年功賃金は問題なく維持できるはずだ。次に第2のインセンティブ理論は、労働者がまじめに働いているかどうかを常に監視し続けるのしコストがかかって難しいので、「まじめに働きます」と誓約書を書かせる代わりに、若い時の働きの成果の一部分を供託金として、その企業に捧げさせる。そして、長期間まじめに働いた場合には、企業はそれを返却するというシステムで、これが年功賃金システムだと考えられる。途中で、さぼっていることが発覚して解雇された場合には、供託金としての将来の年功賃金の部分を失うことになる。このようにして、長期間真剣に働こうと思っている労働者に入社してもらい、まじめに働いてもらう制度として考えられる。勤続年数が短いときには生産性が賃金より高いが、勤続年数が長くなると逆に賃金の方が生産性より高くなる。ここで、生涯の賃金と生産性合計は等しい。これがインセンティブ理論である。この場合、企業は必然的に定年を必要とする。なぜなら、年功賃金による中高年労働者は、生産性より高い賃金をもらっているため、この企業を辞める動機がない。したがって、あらかじめ決められた定年でこま企業から退出することを決めておかないと、生涯の生産性と賃金の収支が合わなくなってしまう。ただし、このモデルが成り立つためには三つの条件がある。第一に、企業が倒産しないこと、第二に、企業が年功賃金の約束を破らないこと、第三に、労働者が生産性よりも高い賃金を受け取る段階になって、労働者の技能に予想外の陳腐化が発生していないこと。この三つである。ただし、本当に技能の陳腐化の範囲が当初の想定の範囲に入るのか否か、を判定するのは非常に難しい。第3は、人は勤務を経るに従って、だんだん自分に適した職を見つけていくという考え方である。企業内には色々な職種があり、様々な職種を経験していくうちに、自分が最も生産性を発揮しやすい職に移っていく。そうすると、生産性の上昇に従って賃金も上がっていく。労働者の潜在能力は変わらなくても、適職を見つけることができれば、その労働は高い生産性を発揮できるのである。第4は、労働者の必要な生計費のパターンに合わせて賃金を支払うと考える生計費理論といわれるものである。このような生計費理論が年功賃金の理由であったとすれば、従業員の年齢構成の変化は、年功賃金の崩壊につながるだろうか。そうではない。生計理論においては、年功賃金は貯蓄の一形態であるから、企業は労働者に代わって賃金の一部を貯蓄していただけで、従業員の年齢構成が変わっても、その分、従業員から預かった賃金による貯蓄が多いはずだ。これらのことから、ねずみ講型の賃金制度が民間企業で成り立っていたと考えることに無理があり、年功賃金の経済的説明からも、高齢化と年功賃金崩壊は無関係だということが分かる。労働者は勤続年数が長くなると技能を蓄積する。労働者がまじめに働いているかどうかを監視するコストは大きい。労働者の能力を短期間で見分けることも難しい。生計費に応じた賃金パターンを支払うのが好まれるのも自然だろう。つまり、年功賃金制には合理性がある。では、なぜ年功賃金制が崩壊しているように見えるのか。
まず考えられることは、技能そのものが陳腐化しまう可能性だ。技術革新が目まぐるしく起こっている場合に、例えば、長期勤務してコツコツ積み上げてきた経験が、コンピュータを中心とした技術革新によってまったく役に立たなくなる場合のように、長い間積み上げてきた経験や技能が十分に発揮できなくなってしまうことは日常的に起こっている。技能に応じた賃金を支払うシステムであれば、技能が低下してしまえば賃金は上がらなくなってしまう。その段階ではたしかに年功賃金制度は崩壊したように見える。しかし、このような技術革新が常に生じているのであれば、企業と労働者はそのリスクにあらかじめ備えて置き、そのための暗黙的な保険制度を賃金制度に組み込んでいてもおかしくない。また、インセンティブ理論のように年功賃金を供託金制度として考える場合、例えば定年間近になって供託金をすでにほとんど返してもらった人たちは働く意欲が大きく低下してしまうだろう。定年間近の人たちにやる気を持たせるシステムを導入しないと、この人たちのやる気は出ない、それは若い人たちに悪い影響を与える。そういう人たちに対しては、業績によって賃金を変えるというシステムを付加することで、このような年功賃金システムの弱点を補強することができる。例えば、管理職に対する業績主義的な人事制度をとったり、年俸制を導入するケースは年功賃金制が崩壊する証拠ではなくて、むしろ、年功賃金制度がもつ中高年労働者への意欲低下効果を補うためのシステムだということである。一方、新たな方向性として成果主義的な賃金制度がある。ただし、日本企業が市場主義的な度合いを高めたことが、成果主義でなかった賃金制度を成果主義的賃金制度に変えてきた理由だと考えるのは明らかに間違いだ。むしろ、長期的な雇用期間全体にわたる成果主義的な賃金制度や昇進制度を用いた成果主義的な賃金制度から、より短期的な成果主義的賃金制度への変更というのが、このような状態の正しい説明だ。長期的な成果主義には数多くのメリットがあるが、企業の倒産可能性が高まったり、成果と昇進の関係があいまいになると、まったく機能しなくなる。このような状態に対応するため、新たなインセンティブ制度として、各時点の市場価値により近い賃金を支払うという成果主義的賃金制度が導入されてきたと考えられる。
今度は、反対の側面から見てみよう。年功賃金が経済合理的に説明できる4つの理論をさきに説明したが、これらには、それぞれ問題点がある。第1の人的資本理論は、技能が勤続年数とともに技能が必ずしも上昇するとは限らない職場、例えば、技術革新の急激な職場では、ベテラン労働者の技能が陳腐化して若い人の生産性の方が高いという場合も多い。第2のインセンティブ理論は、そもそも解雇が困難な日本の企業でどこまで、この理論が妥当するか難しい。第3の適職探しの理論は、職種がそれほど多くない企業であっても年功的な賃金制度が存在することを説明できない。第4の生計費理論は、そもそも家族形態が多様化している中で特定の生計費に合わせた賃金構造を作ること自体が難しくなってきている。このような点を考慮して、年功賃金を説明するための近年の理論として、習慣形成理論がある。人々は賃金(生活水準)が上がっていくことそのものを喜ぶ、その反面として、そういう生活習慣に慣れてしまうとそれが当たり前になって、その後生活水準を下げる辛さを知っているから生活水準を徐々に上げていくこと選んでいるというものだ。実際に、2002年に意識調査を試みた結果として、生活水準を上げていくことが楽しみで、そういう生活費の変化のパターンを選びたいから年功賃金がいいという解釈もできるようなものだった。そのため、賃金総額が変わらないことが分かっていても、毎年、賃金が上がっていくほうが仕事への意欲をもたらすという解釈も可能だ。つまり、賃金総額を引き下げても年功賃金でも人々の満足は得られるわけである。
賃金の結果というわけでもないが、所得格差の拡大がよく言われる。各種の調査では、格差を実感する人が増えているというデータがある。このような実感は、所得格差の統計と整合的なのだろうかと著者は投げかける。まず、その原因として考えられるのが、世帯形態の変化だ。日本における世帯規模の変化は近年著しい。1980年代には、四人世帯が最も普通の世帯だった。90年代では二人世帯が最も多く、次に単身世帯が多くなっている。世帯規模が変化すると、世帯所得の不平等度と人々の生活水準の格差の間に乖離が生じてくる。例えば、75歳で年収300万円の親、50歳で年収1000万円の子、20歳で年収400万円の孫という3世代同居の世帯が全部なら、世帯としての年収は1700万円で、個人の収入格差はあっても世帯間の格差はない。これが、各世代が別居した場合、300万の世帯、1000万円の世帯と400万円の3種類の世帯が発生し格差が大きくなる。このように、世帯形態が
所得の状況に応じて変化しやすい社会になってくると、それぞれの個人レベルでみると豊かになっているにもかかわらず、世帯で測った所得では低所得世帯が増加して見える場合がある。また、女性の働き方の変化も世帯間所得格差に与えた影響が大きい。以前は、低所得男性の配偶者は、生活水準を高めるために共稼ぎをし、高所得男性の配偶者は専業主婦になるというのが一般的だった。しかし、現在では男女の賃金獲得能力差が小さくなり、優秀な女性が能力を発揮する機会が増え、高所得男性の配偶者が専業主婦でなく高所得を得て働くケースが増えている。こうなると、世帯間での所得格差は拡大する。
また、人口の高齢化の影響も統計と実態を見る必要がある。筆者は、人口の高齢化の影響を給与の支払い形態の変化と同じ性質のものと見る。例えば、平均寿命が50歳で、人々は、十分に働ける間だけを生きている世界から、寿命が80歳になって、引退後20年間は貯蓄を取り崩して生きていかなければならない世界になったとすると、寿命50歳の時代は平等度が高く、80歳の時代は引退後所得のない人が出てきて不平等度が増すように見える。しかし、引退した人たちは、最初から人生80年の人生設計をしているはずで、きちんと貯蓄して引退後の生活に備えているので、別に勤労所得がなくても、実際に貧困になるわけではない。
つまり、所得の不平等度は、その時点の所得だけの格差を示している。そうでなくて、現在時点の所得の格差が小さくても、生涯所得の格差が大きいのであれば、その社会は平等であるとは言えない。場合によっては、一時点の所得の不平等度が高くても、所得階層間の移動率が非常に大きい場合、つまり、ある時点で低所得であった人が次の時点で高所得になるということが頻繁にある場合には、一時点で見た所得格差が大きくても、生涯の所得格差は小さくなる可能性がある。例えば、アメリカのような転職が比較的容易な社会では、現在の賃金水準が低くても、転職により将来よい条件の仕事に就く可能性があり、生涯賃金で見た賃金格差は一時点での賃金格差に比べると小さくなる。
このように所得の不平等度は、所得の一時的変動の影響を受けるため、必ずしも真の所得格差を反映しないという問題点がある。また、現時点で賃金所得はなくても、多額の資産を保有していたり、将来遺産をもらうことが確実な人もいる。そういう人たちは、所得は低くても高い水準の消費生活を楽しむことができる。だから、貧困や生活水準の格差を知るうえで、最もすぐれた指標は、消費水準の格差と言える。これらの統計で見てみると、日本の年間所得の不平等度よりも消費の不平等度が小さいことを示している。このことから、一時的な所得変動の拡大が日本の所得不平等を高めたわけではないことが分かる。所得格差の拡大は消費格差の拡大と同時に発生している。筆者は、日本の所得不平等度の上昇の原因を高齢化と世帯構造の変化にあるとみている。
ただし、90年代後半から更に変化が生じている。若年層で所得格差が拡大する傾向である。これは、現在の所得不平等度に現れない将来所得の格差拡大を反映したものである可能性がある。具体的には、遺産相続を通じた所得格差や将来賃金の格差拡大を反映していると考えられる。低成長・少子化社会では、遺産相続が生涯所得に大きな影響を与える。少子化社会では子供の数が少ない分、子供一人当たりの相続の受け取り額が大きくなる。経済成長が低くなれば、子供世代が自ら稼ぐフローの所得は親から受け取る相続資産に比べて小さくなる。また、成果主義賃金制度が導入から数年を経過すると運用が本格化し、格差をもたらす可能性がある。さらに若年層の失業率の上昇は、一度失業すると、なかなか賃金の高い仕事を見つけるのが難しい日本の状況が変わらなければ、生涯賃金の大きな格差を招いてしまう。
日本で所得格差が拡大していると感じている人々が多いこと、勤労世代で消費の格差拡大が進展してきた。このように資産や将来所得の格差が拡大しているなかで、人々は税制や社会保障を通じた所得再配分政策の強化を指示しているのだろうか。これに対して、低所得者は再配分政策の受益者なので支持するだろう。しかし、今は低所得者でも、将来高所得になると予想している人は再配分制度の強化によって逆に生涯所得が低下してしまう可能性がある。逆に、現在は高所得でも、失業の不安を持っている場合のように将来低所得になる可能性が高い場合再配分政策の強化を支持するだろう。このように所得再分配政策は所得に対する保険制度と考えることもできる。そうすると、所得再分配政策を支持するのは、危険回避的な人だということになる。このように人々の所得再分配政策に対する考え方は、現在と将来の所得水準、リスクに対する態度などの経済的要因で決まるが、現実の所得再分配政策がそれを反映するとは限らない。たとえば、このような経済的要因以外にも、人々の中には、運が貧困の原因なら再分配政策を支持するが、怠惰が貧困の原因なら、自らを怠惰でないと信じている人は再分配政策を支持しないだろう。
統計的に見ると、日本の所得格差が大きく上昇したのは80年代であって90年代ではない。この点は、所得格差拡大論が90年代末から注目されだしたことは異なる。しかも、日本で80年代に格差が拡大した最大の理由は、人口の高齢化であった。もともと所得格差が大きい高齢層の人口比率が上昇したのである。90年代には、労働人口の高齢化が収まったため賃金の不平等化の速度は低下してきた。それでは、人々は、格差拡大を最近になって実感しているのであろうか。それは、中高年を中心に成果主義的な賃金制度の導入による今後の賃金格差拡大予想や、失業・ホームレスの増加が、人々に格差拡大を実感させているためと考えられる。しかし、所得格差の格差が生じていることを認識している人が多いにもかかわらず、小さな政府を目指す政策への支持も高い。
今まで経験で、学歴や持っている情報量とは関係なく、本当に頭のいい人だと感じるのは、自分の言葉で話すことができる人であることが多いです。自分の言葉で話すというのは、知識を本に書かれたそのままを暗記しているのではなくて、いったん自分の中で消化しているために、必然的に自分なりの言い方に変換されて話すことになる。自分の中で消化されているということは、例えば、実践の中でその知識をまく活用できる準備ができているということです。だから、具体的な場面でどうするかという考察が背後に含まれている。この著者には、それを強く感じます。付け焼刃の文献からの引用で、書いている人も本当はよく分かっていないのではないかと思わせるような、単に難解な言葉が並んでいるだけの文章とは正反対のものです。そして、この本の特徴は、そういった生きた知識が述べられているだけに、読書メモが書きにくいことです。些細な語句でも日常の具体的な場面での実践を踏まえた考察がされているので、深読みができてしまうので、単に語句を知識としてメモしておこうとすると、背後の膨大なものも書きたくなってしまう。実際の実践の場では状況が整理されているわけではないので、バラエティを考慮して、様々な部分で関連性が張られている。だから、読み返すたびに発見がある著作だと思います。生きた知識というのは、こういうものだ。