�U�D�\���Ƃ��Ă̐l�i �V�D�l�i����ԕ��� ���z
�T�D���炩���ߑr��ꂽ���ǂ��� �����Œ��҂́A�吳�P�P�N�́u���{���_�j�����v�̒��́u�����̑��D�ɂ��Ă̈�l�@�v�ɒ��ڂ���B�a�҂́A���P�E�V�����̕����ɋ�������������A���Ȃ킿�u���Ɩڂ̈ٗl�Ȓ����A�j�̋ȖL�����A��d���A��̂�����A���̂̕s���R�Ȓނ荇���v�Ƃ��������̓������A�d���̐l�̂̔������𑨂������̂ł��邱�Ƃ�����B�����ł̉d���Ƃ͑r������Q�q�̂��Ƃł͂Ȃ����A�����_�l�̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ�B�u�Ƃ���ʼn�X�́A�������F���ɂ����ĉd���̍Č�������̂ł͂Ȃ��B��Ƃ��߂����̂́A�d�����̂��̂̔������ł͂Ȃ����āA�d���Ɍ���ꂽ�l�̂̔������ł���B�v���҂́A�a�҂��A���́u�d�����̂��̂̔������v�Ɓu�d���Ɍ���ꂽ�l�̂̔������v�����������A���ꂼ���ʁX�̉����Ƃ��Ĉ����Ǝw�E����B����́A����A�\�����ꂽ�u���́v�Ƃ��Ẳd���i�d�����̂��́j�ƕ\�����ꂽ�u���Ɓv�Ƃ��Ẳd���i�d���Ɍ���ꂽ�l�́j�Ƃ������͂������ƂŁA�����ɂ͕s���ł���͂��́u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ�a�҂͋�ʂ��A�����͂����Ă��܂��B���̂��Ƃɂ��Ē��҂́A�u���Ɓv�Ɓu���́v�Ƃ̋敪�́A�P���ɍl����ƁA�����I�����ɂ��ẮA���̕\�ʐ����Ӗ����ƁA���ݐ��Ƃٕ̕ʂɉ����������I�ȋ敪�ł���悤�Ɍ����邪�A���͂����ł͂Ȃ��Ƃ����B�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ���ʂ��邱�Ǝ��̂��A�\�ʁ��Ӗ��Ǝ��݂Ƃ����悤�Ȏ����̈قȂ����Η��Ȃ̂ł͂Ȃ��A�ŏ�����A���Ƃ̖��A���邢�͕\���̖��̔��e�ɂ���ƔF�����Ă����_�Ŏ��e�Ȃ̂��B�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ������͂������̂��Ƃ��A���ƂA�\���̖��̈�̂��Ƃ���Ȃ̂��B �ł́A�a�҂͕\���ɂ��Ăǂ̂悤�ɍl���Ă������B�N���̘a�҂́u�����ċ��v�ɂ����āA�\���Ƃ͐����邱�Ƃ��̂��́A�������邻�̂��̂ł���Ƃ���Ă����B���̐����邱�Ƃ��̂��̂ł���\���ɂ����āA�����͎��Ȃ̓�����\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���̂��Ƃ��l�i���l�����߂�̂ł���ƁA�N�a�҂͒P���ɐ錾���Ă����B���̕\���ɂ��Ă̍l�����́A�u�����̑��D�ɂ��Ă̈�l�@�v�ɂȂ�ƁA���Ƃ��炾����\������悤�ȕ\�����l���A�\�������u���́v�A���Ƃ��Γ����ȂǂƂ����u���́v��\������Ƃ������Ƃ�������}�����Ă����̂��B�u�\���v�ɂ����āu���́v�͗}������A��������āA�u���Ɓv�������Ɨ����悤�Ƃ��͂��߂�̂ł���B���̘_�l�̒��ŁA�u���́v�Ɓu���Ɓv�̈����͂����Ƃ����\���`�Ԃ��A�M���V�����p�Ƃ̑R�W�ɂ����Č��o����Ă���B�d���ɂ����Ĕ������ꂽ�����Ɠ��̔������Ƃ́A�M���V���̗���������m���p�̎ʎ��I�Ȕ������ɐe���҂ɂ́A�����̕s���R�Ƌ̊�����^������̂ł����Ȃ������B�����A���������s���R�Ƌɋp���Ĕ����������o�����Ƃ������_�A�܂�M���V�����p�Ƃ͕ʗl�̕\�������悤�Ƃ��鎋�_�������A�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̂Ђ��͂����Ƃ������Ƃ�������o�����邱�ƂɂȂ�B�܂�A�\���̕ϗe�Ƃ́A�M���V�����p�̗l������A����Ƃ͕ʗl�ȗl���ւ̏d�_�̈ړ��Ƃ��Ă���A����m�ȍ��قƂ��Č��������ꂽ�j����Q�q�̑r���ł������̂��B ����Ȃ�A�u���́v�Ɓu���Ɓv�̈����͂��������o�����錴���ƂȂ����M���V�����p�Ƃ̑R�Ƃ́A���������ǂ�Ȃ��̂��̂ł������̂��B�a�҂��吳�P�S�N�́u���ÓV�����p�̗l���v�̂Ȃ��ŁA�M���V���̐_����l�̂����̎p�ɍ��߂�ߒ��A�V���̕���F����_��l�̎p�ɕ\������ߒ��ƑΏƂ����ČĂB�܂�A�M���V���_���̍�҂́A�����I�ȏ��̂ɂ����Ĕނ������������z�̎p�����̑I�������Đ_����o���B�ǂꂾ����̑I�����悤�ƁA���̂��ƂɂȂ�͈̂�̌����̎p�ł���B���̈�����̎p����̂���Ƃ��ɁA��̑I���̊���̂��̂Ƃ��ăC�f�A�����o�����Ƃ����B�����̂��Ƃ����a�҂́A�l�̂�_�̎p�ɍ��߂�ƌĂB��́A�\�����ꂽ�u���Ɓv�ƕ\�����ꂽ�u���́v�Ƃ����_�ł݂�Ȃ�A�M���V���_���ɂ�����\�����ꂽ�u���Ɓv�́A�ǂꂾ����̂���A�ǂꂾ���_�X�������낤�Ƃ��A�A���̕\�����ꂽ�u���́v�Ƙ������Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�����A����̐��ÓV�����̕���F���́A��̓I�Ȉ�̌����̎p����ł͂Ȃ������̌����I�̎p������яo����\�����ꂽ�d���̓��̂ɂ���č��o���ꂽ�B����F�����\������d���̓��̂Ƃ����\���́A�\�����ꂽ���̂Ƃ��Ẳd�����̂��̂Ƃ͘A�����Ȃ��B�܂�\�����ꂽ�u���Ɓv�ł���d���̓��͕̂���F�����������Â��邪�A����͕\�����ꂽ�u���́v�ł���d�����̂��̂Ƃ͘������Ă���Ƃ����̂ł���B���̂��Ƃ�a�҂͐_��l�̎p�ɕ\������ƌĂB �M���V���_���ƌÕ����Ƃ̊Ԃɍ��ق����o�����Ƃ����Ƃɂ��āA�a�҂͂���ɂ���𓌗m���p�̓����Ƃ��đ��������Ă����B�吳�P�Q�N����́u���{���p�j�m�[�g�v�ł́B���F���t�����́w���p�j�̊�b�T�O�x�����グ�A�����Ŏ����ꂽ�ܑ̔��p�T�O�ɂ��ďڍׂɌ������Ȃ���Ă���B���F���t�����́A���o��p���ꎩ�g�ɗ��j�I�ϑJ�����蓾��ƍl���A���o�̏��w�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����p�j�̊�{�I�ȉۑ�ł���Ƃ���B���F���t�����ɂ����̎��o�̏��w�͌܂̑��Ȃ��Ă���B����́A���I�^�G��I�A���ʁ^���s�A�����`���^����`���A���l���^����A�����^�s�����A�Ƃ����ł���A�����̑O�҂����҂ւƕϑJ���邱�ƂɃ��F���t�����̓��l�T���X����o���b�N�ւ̗l���I�ϑJ������B�a�҂͂��̔��p�T�O�̑𒀈ꌟ�����A����炪���m���p�ɂ͓K�p�ł��Ȃ����Ƃ��������Ƃ��Ă����B���m���p�ɂ�����`���́A���F���t�����̌����悤�Ȑ��I���G��I������ʂł�����̂ł͂��A���I�ł���Ȃ��瓯���ɊG��I�ł���悤�Ȃ��Ƃ���Ƃ��Ă������B���̂悤�ȕ`�����A�a�҂́u���Y�������킷���ƕ��̖��m�Ȍ`�����킷�悫���Ƃ��������A������ɂ��Ȃ�炸���Ԃɉ����ĐV�����Ӗ��̐��ƂȂ��Ă���v�Ɖ������B���̕`���̂���悤�͓��m���p�̓����Ɍ��ѕt������B����́A�u�`���g�ɉ�����������A�`��ʂ��Č��킳���Ӗ����d��v�Ƃ������Ƃ������B���m���p�Ƃ́A�`���g�ł͂Ȃ��`�ɂ���Ď������u�Ӗ��v�A�`���̂��̂ł͂Ȃ����ꂪ�D��Ȃ��u���Y���v�̎咣�ł���B���̂悤�ȓ��m���p�͐��m�I�Ȕ��p�l���Ƃ͕ʂ́u�l���v�ł���Ƃ��ꂽ�B�����Ă��������̂́A���̕ʂ́u�l���v�́A�ʏ�̈Ӗ��́A���邢�͊G��I�l���ȂǂƓ��i�ɕ��ׂ���悤�ȗl���̂ЂƂł͂Ȃ������Ƃ������Ƃł���B���m���p�́u�l���v�́A�G��I�l���Ƃ����悤�ȗl���̋�ʂ��̂��̂����f����̂�����̂Ƃ��āA���F���t�������l����l���̊O���ɂ���悤�Ȏ����ł������B����̓��F���t�����̗l���̋敪���̂��̂Ƃ��̍����I�ȑO��Ƃ�₤�u�l���v�ł������B ����͂܂�A���o��p�����j�I�ɔ��W����Ƃ������Ƃ���̂���Ȃ鍪��ł���B���o��p���g�����j�I�ɔ��W���邱�ƂȂǂ͂��蓾�Ȃ��B���j�I���W������Ƃ������̂��l�̉c�ׂɑ����邩��ł���B�܂�A���o��p�̗��j�I���W�Ƃ́A�P�Ƃł��蓾��̂ł͂Ȃ��A���̔w��̐l�i�I���̗��j�I���W�Ɋ��Y�����̂ł����Ȃ��B������A��荪��I�Ȗ��Ƃ��ׂ��Ȃ̂́A�ނ���l�i�I�����ǂ̂悤�Ɏ��o��p�ւƌ�������̂��Ƃ������ƂȂ̂��B���F���t�����ɑ����Č����A�Ȃ����F���t�����͎��o��p���̂��̂������������j�I�ɔ��W�ł�����̂ł��邩�̂悤�ɁA�l�i�I���Ǝ��o��p�Ƃ��҂�����\�荇�����Ă���̂������Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���F���t���������o��p�ɂ̂ݒ��ڂ���̂́A���Ƃ��ƃM���V���I�Ȏ��o��p�̂���悤�ӎ��ɑO��ɂ��Ă�������ł���B�M���V���I�ł���Ƃ́A���o��p���l�i��p�Ƃ҂�����Əd�˂�ꌋ�����邱�Ƃ������B������������I�ȁA���o��p�Ɛl�i��p�Ƃ̌����̂������������A�Ώە��̂����������̓��e�Ƙ����������Ɍ��鎋����ۏ��A���R�ɒ����ɕ`�ʂ��邱�Ƃ�~����悤�Ȕ��p�Ƃ��A���邢�́A���o��p���̂��̂��Ɨ��I�ɓW�J�ł���悤�Ȏv�҂��x����Ƙa�҂͍l����B����ɑ��ē��m���p�́A���R�Ȓ����ȕ`�ʂ͕K�������~�����Ȃ��u�l���v�Ƃ��āA���F���t�����̂����l���̊O���ɗ��B����́A�Ώە��̂������ƕ`�������e�Ƃ��������Ă��ڒ������ɁA�`�����d�_��Ώە����̂��̂ɂł͂Ȃ��A�Ȃ�炩�̃��Y����Ӗ��ɒu���u�l���v�ł���Ƃ����B�����������m���p�̓������A�u���́v�Ɓu���Ɓv�̈����͂����ł���Ƃ������Ƃ͗e�ՂɊm�F�ł���B�܂�A���m���p�̓����Ƃ́A�Ώە����́u���́v���`�����̂ł͂Ȃ��A���Y����Ӗ��Ƃ������A�u���́v�������ꂽ�����ȁu���Ɓv�������d�_�I�ɕ`����邱�ƂȂ̂ł���B �������A�M���V�����p�͐l�i�I��p�������Ɏ��o��p�ɂȂ�낤�Ƃ���A�`�ۂ�����ɂ���Đ��_������Ƃ�����B����A���m���p�́A�l�i��p�͎��o��p�ɂȂ�낤�Ƃ͂����ɁA���o��p��P�Ȃ�ʘH�Ƃ��Ă܂�������Ɍ����悤�Ƃ���A���o���`�ۂɂ���Ċ��o�������ƌ�����B�����A�������邱�Ƃ����A���������T�O�ɂ�鍷�ق̔c���͐������Ă��Ȃ��B���҂̊T�O���ǂ̂悤�ɈႤ�̂��\���ׂ����Ă��Ȃ��̂ł���B
�U�D�\���Ƃ��Ă̐l�i �������A�a�҂̂��̐l�i�ς́A��N�A�Ⴆ�Ώ��a�P�O�N�́u�ʂƃy���\�i�v�ɂ����Ă͕ϗe���Ă���B�����ẮA�܂��A�炪�l�̑��݂ɂƂ��Ă����ɒ��S�I�n�ʂ����������A��͐l�̑��݂ɂƂ��Ċj�S�I�ȈӋ`�������́A�P�Ȃ���̂̈ꕔ�ł͂Ȃ��A���̑S�����]�����̓I�Ȃ���̂̍����Ȃ����ƁA����𒊏ۂ������̂������u�ʁv�ł���B�����A�u�l�i�v�̌���ł��郉�e����y���\�i�Ƃ͂��Ƃ��ƌ��ɗp�����鉼�ʂ̂��Ƃ������B���ʂ̈ӂł���y���\�i���A�����̖����A�����̐l���������Ӗ��ւƓ]���A����ɓ���ɂ������E���E�ނƂ��������A�Љ�ɂ�����n�ʁE�g���E���i�Ȃǂ̖����̈ӂɓ]���āA�ŏI�I�ɍs�ׂ̎�́E�����̎�̂Ƃ��Ă̐l�i�̈Ӗ��ɋA�������̂��A�������B�v����ɘa�҂̓y���\�i�Ƃ������t�ɂ���āA��Ɛl�i�Ƃ��A��Ɖ��ʂƂ����т��A�����̊֘A�̂���悤����ɂ���B���̂Ȃ��ŁA�\�ʂ��ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ�B�ʂ��������҂��葫�̓���ɂ���ĉ�������\������A�����ɕ\������ꂽ���Ƃ͂��łɖʂ̕\��ƂȂ��Ă���B�����ł́A���ʂ��������Ҏ��g�̓�������ʐ������}������Ă���B���҂̎��̂ɂ��\���́A���҂̓��ʁA���邢�͓�����\�������A�ʂ���������ē������҂̎��̂⓮����Ȃ̓����ɋz�����Ă��܂��A�ʂ̕\��ƂȂ�Ƃ����B�a�҂��d�v������̂́A���́A�����ɂ����Ė��҂̎��̂̕\�����z�����Ă��܂��͂ł���B���̗͂������A���ʂ̈Ӗ���l�i�̈Ӗ��ɓ]���������}������������ł���B�╔�b�ɂ��A���ʂƂ��Ẵy���\�i�́A���I���ꐫ�ł͂Ȃ��A�W�̑��╿�̑��������B�a�҂̐l�i�ς́u�����ċ��v���ɂ͎��I���ꐫ�Ƃ���߂Đe�a�I�ȁA�l�I�ȓ��ʐ��Ƃ��Ă̐l�i�ł��������A�u�ʂƃy���\�i�v���ɂ́A�W�̑��Ƃ��Ă̐l�i�ւƔ��]���A�ϗe���Ă��܂����̂ł���B�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A���̕ϗe���\���Ɋ֘A���Ă����Ƃ������Ƃł���B�u�������q�v���̐l�i���\���̖��ɋ����ւ����̂ł������Ɠ��l�ɁA�u�ʂƃy���\�i�v�ɂ����Ă��l�i�͕\���̖��ɂ�������Ă���B�\�������u���́v�ƕ\�������u���Ɓv�Ƃ̋�ʂł����A�u�����ċ��v���̐l�i�Ƃ́A���|�ɂ���ĕ`�����ׂ����e�̖{�́A���Ȃ킿�\�������u���́v�ł���A����u�ʂƃy���\�i�v���̐l�i�͕\�������u���Ɓv�̏W�ςł���B�܂�A�l�i�ɂ��Ă̍l�����܂��A�\�������u���́v����\�������u���Ɓv�ւƕϗe���A�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ������͂�����Ă���ƌ�����B ���̂悤�ȁA�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̈����͂����͖{���I�ɁA���Ƃ̖��ł���A�\���̖��ł���B�����ł���A�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̈����͂����Ƃ������Ƃ��A�ł��d�v�ŁA���܂����ՓI�Ȗ��ɂ�����̂́A�����̃e�N�X�g�̉��߂Ƃ�����ʂɂ����Ăł���B�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̈����͂����Ƃ������Ƃ��炪�A�a�҂ɂ����Ă͐l�i�_�̕ϗe�ɂ����Ă������邪�A�Ⴆ�A���̉ߒ��͑吳10�N����12�N�ɂ����Ă�2�̃e�N�X�g�lj��̂��悤�̔�r�ɂ����Č��邱�Ƃ��ł���B2�̃e�N�X�g�Ƃ́A�w�������x�Ɓw���@�ᑠ�x�ł������B�����̓C�G�X�y�ѓ����̐l�i�ɂ��ꂼ�ꒅ�ڂ��A��������o�����q����Ƃ������Ƃ�ړI�Ƃ���B�����A���̎��o���悤���قȂ��Ă����B �a�҂ɂ��A�w�������x�ɂ̓C�G�X�̐l�i�����̉��ɌN�Ղ��Ă���B�����Řa�҂����߂悤�Ƃ��Ă���̂́A�������ɕ`���ꂽ�C�G�X�ł͂Ȃ��āA���̉���̕�������`�������C�G�X�A�M�������N�������l�C�G�X�ł���Ƃ��āA���ٕ̕ʂɂ͐����I�ȉ��ߊw�I�����K�v�Ƃ���Ƃ��āA���ߊw�I���@�ɂ��ڍׂȃe�N�X�g���߂����݂�B����ɑ��āw���@�ᑠ�x�̏ꍇ�ɂ́A�����̐l�i�͊��ɒ���̕\�����̂��̂ɘI��ɂȂ��Ă���Ƃ����̂ŁA�w�������x�̏ꍇ�̂悤�ȐT�d���͕K�v�Ȃ��Ƃ��Ă���B���̗��҂̈Ⴂ�́A�ЂƂɂ̓e�L�X�g���̂̐����̈Ⴂ�ɋN������B���Ȃ킿�A�w�������x�̓C�G�X�̒�q�������Ԃ����C�G�X�̌��s�^�ł���̂ɑ��āA�w���@�ᑠ�x�͓������g�������A������e�N�X�g�ł���_���B�������A���ꂾ���ł͂Ȃ��B�a�҂͌��n�L���X�g���́A���_��������o������Ȃ��̂ł͂Ȃ����āA�M���V�����̋��y�I�����p�I�����ɔ���������Ƃ��Č����ė������Ƃ���������B����͖��炩�ɕs���R�ł���A�����ɂ͗\�ߖڂ���Ă���O�������B����́A�M���V���_���ƌÕ����̗l���̍��ق̈ӎ��������ƒ��҂͎w�E����B�w�������x�̏��q���ǂ�قǍr�����m�ł��낤�Ƃ��A�C�G�X�̐l�i�Ƙ��������Ɍ������Ă���Ǝ咣�����̂́A�M���V���I�Ȃ���̂ɂ����ẮA�\�������u���́v�ƕ\�������u���Ɓv�����������������Ă���Ƃ����l���̈ӎ����O��Ă��邩��B�M���V���_���̗l���́u�l�Ԃ�_�̎p�ɍ��߂�v�Ƃ܂Ƃ߂��Ă��邩�A���̈ӎ��������A���n�L���X�g���̒�����l�ԃC�G�X����_�C�G�X�ւ̍��܂�Ƒ����Ă䂭���_�̗��t���ƂȂ���̂ł������Ƃ�������B�d�v�Ȃ̂́A���̘_�l�ɂ����ẮA�l�i�́w�������x�̓����ɂ���A���邢�͐_�C�G�X�ւ̕ϗe�������炵���j�Ƃ���Ă��邱�Ƃ��B�����Ől�i�́A�l�I�ȓ��ʐ��A�\�������u���́v�Ƃ��Ă����Ȃ��B����́A�u�ʂƃy���\�i�v�Ɍ����Q�̐l�i�ς̑O�҂Ɛe�a���������Ă��邱�Ƃ͖��炩���B ����A�w���@�ᑠ�x�ɑ��Ă͐l�i�͕ʂ̈�����������Ă���B�����̐l�i�͓��ʐ��Ɏ��k���邱�ƂȂ��w���@�ᑠ�x�⑼�̌�^�̍s�ԂɁA�\�ʂɁA���@�Ƃ��Č����Ă���ƌ�����B�����Ŏ�����Ă���̂́A�\�������u���́v���Ȃ킿�l�I�ȓ��ʐ��Ɍ��肳��邱�ƂȂ��A�\�ʉ����Ă���\�������u���Ɓv�̏W�ςƂ��ē����̐l�i���������悤�ł���B�\�����l�i�ɂ�����u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̈����͂����́A�܂������A���́u���哹���v�ɂ����ċN�����Ă���B���̘_�l�������a�ғN�Y�̕\�����l�i�̕ϗe�̚���ł���ƒ���͌����B �a�҂́w���@�ᑠ�x���̒�����ɂ�����^���̕\���ł���Ƃ���B�ʏ�̑T�@�̓`���ɔ����āA�a�҂͐^���͌��t�ɂ���āA���邢�͘_���I�\���ɂ���ĕ\������邱�Ƃ��\�ł���A�����łȂ���Γ��������ʂ̐����̏��������c���킯�͂Ȃ��A�ƒf������B�܂�A�w���@�ᑠ�x�Ȃǂɕ\������Ă���u���Ɓv�́A�^���̕\���ł���A����ɐ^���̋�Ƃ��Ă̓����̐l�i�ł���B���̂悤�Ȏ咣�́A��̋^��_���B ��́A�����̒�����^�Ɍ����Ă��鎖�����A�����̐l�i�Ƃ����A�^�����Ƃ����ꍇ�A����͏����̈ʒu�t���lj��ɂ���Č���Ȃ����ӓI�ɕύX��ւ��Ă��܂�Ȃ����Ƃ����_�ł���B�w���@�ᑠ�x���̂��A���̃o�C�A�X���������Ă��Ȃ��P���ȏ��M�\���̏��Ȃ̂ł͂Ȃ��B�܂��Ă╶�͂̓lj����̂��A�獷���ʂŁA����Ȃ����Ӑ��ɗh��ꑱ����B�ƂȂ�ƁA�l�i���^���������������ӓI�Ȃ��̂Ȃ̂��B���������ł͂Ȃ��A��������m�łƂ������̂ł���Ǝ咣����Ȃ�A�����������Ӑ��������̕��@�ŏ������Ă����K�v������B������́A�����̐l�i�ɐ^���������Ă���A����Ă���Ƃ������Ƃ̖��ł���B�����ɂƂ��ĕ��̌��ł������肦�Ȃ��B�����A���̌��������Ƃ͂����ɕ���������Ƃ������Ƃł���B����͕��g�̖����@��N���A���̖��Ɠ����Ƃ̊ւ�荇���ɂ��Ę_�����邱�Ƃ�a�҂ɔ��邱�ƂɂȂ邾�낤�B�܂��A�l�i�Ƃ����p�ꎩ�̂��L���X�g���ɐ[���e�����ꂽ���̂ł����āA���̏ꍇ�^���̔����Ƃ͐_�̔����Ƃقړ��`�ł���B���̂��ߐ_���Ȃ킿���z�҂��̂��̂��������E�ɔ�������Ƃ������n�ɐG��A�L���X�g���ƕ����ɂ����鍷�ق�₤�v�l��U�����ƂɂȂ邾�낤�B�����̋^��_�́A�����̉��߂ɂ����霓�Ӑ��̖��ƁA���z�҂̔����̖��ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B �a�҂́A�����̎v�z�̓��������̂悤�ɑ����Ă݂���B�����ɂ����Ă͒��z�I�Ȗ@�͐l�ɜ߂��ē���������B�����Œ��ӂ��ׂ��Ȃ̂́A���z�I�ȕ���l�Ƃ��Ă̓��̂ɂ���ĕ\�����Ă������Ƃł�����ƌ����Ă��邱�Ƃł���B����͐e�a�̂悤�ȁA�l�Ƃ͊u�₵������ɕ��Ƃ������z�҂ւ̋A�˂Ȃ̂ł͂Ȃ��A�����̏�Ɍ����Ă���l�Ɍ���������������Ƃ����咣�Ȃ̂��Ƃ����B���̖@�Ɛl�Ƃ̊֘A�ɂ��Ē��ڂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ӂ��ׂ��Ȃ̂́A���������@���l�ɜ߂��ē��������邱�ƂƂ́A���z�I�ȕ���l�Ƃ��Ă̓��̂ɂ���ĕ\�����Ă������Ƃł���ƌ����Ă��邱�Ƃł���B�\�������u���Ɓv�Ƃ��Ă̖@�́A�\�������u���́v�Ƃ��ē��̗���邱�Ƃ͂Ȃ��B�����ł́u���́v�Ɓu���Ɓv�̈����͂����Ƃ������Ƃ���͖������炩�ɂ���Ă��Ȃ��B�����A�^�����\�������̂͐l�̓��̂�l�i�ɂ����Ă����ł͂Ȃ��A���Ƃɂ����Ă��\���Ɍ�����̂ł���B����́A�w���@�ᑠ�x�⑼�̒���ɓ����̐^�����\��Ă���ƒf���������Ƃ̓��R�̋A���ł������B�a�҂́u�����v�̉���ɂ����āA���Ƃɂ��^���̕\���̂��Ȃ��ɁA�\�������u���́v�ł���l�i��l�������Ƃ��A�\�������u���Ɓv�݂̂��������Ă������܂�`���̂ł���B�����́u�����v�Ƃ������t���d���B�a�҂͂�����A�^����\�����邱�Ƃ��́u���Ɓv�̏d���ł���ƌ���B�\���͂��͂����̐l�i�Ɍ��肳��Ȃ��B�l�i�̓��萫�͎�菜����A�\�������u���Ɓv���̂��������A�t�ɐl�i��ۂݍ���ł��܂��B�a�҂́A�u�����v�����S�X�̎��ȓW�J�ƌĂԁB���̌��t�́A�����E���_�Ƃ������Ȃɂ����ݓI�Ȃ��̂����j�I�ɓW�J���Ă��������Ƃ��ė�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���S�X�Ƃ͂܂����t�ł���A�^���ł���A�\���ł���B���S�X�̎��ȓW�J�Ƃ́A��i�I�Ȑl�i�ɏ]������ׂ����t�E�^���E�\�����A�l�i�̎x�z��U�蕥���Ď������Ă������ƁA����ɂ͋t�ɐl�i���A�l�i���K�肵�Ă䂭���܂Ƃ��đ����Ȃ�Ȃ�Ȃ��B�u���́v�Ɓu���Ɓv�̈����͂������A�����ŁA���S�X�̎��ȓW�J�Ƃ����������Řa�҂ɖ��m�Ɉӎ�����Ă������Ƃ͏d�v�ł���B�\�������u���Ɓv���甲���������i�Ƃ́A�����炩�ɁA�l�I�ȓ��ʐ��Ȃ̂ł���A��i�Ƃ��ē����l�i���w���Ă���B�܂肻��́A���Ắw�����ċ��x���Ɍ�����l�i�A���Ȃ킿�u���_�A����I����A�́A�b�m�I���i�v�ɓ����Â�����l�i�Ȃ̂ł���B�����Œ��ӂ��Ă��������̂́A���������}���������̂ɂ́A�P�Ȃ�M���V�����_�����ł͂Ȃ��A�M���V�����_�̐������z�������L���X�g���ł���A�܂����̃L���X�g���ɋߎ����Ă���Ƃ���e�a�̍l�����ł������B���̂悤�Ɂu�����v�̉���ɂ���Ď�i�̔�������A���S�X�̎��ȓW�J�Ƃ����Ăѕ��ŕ\�������u���Ɓv�̎������咣�����a�҂́A����Ɂu�����v�̉���ɂ����āA�\�������u���Ɓv�̎����������Ă��܂����ɂ��čl�@�̎�����B�܂�A�\���ɂ́A���R�Ȃ��畡���̕\�������肦�A�����݂͌��ɖ������ďՓ˂��Ă��܂��B�l�i���\��������ꍇ�ɂ́A�\���̕������͕����̐l�i�̍��قɉ������Ă��܂����A�\���������i�I�Ȑl�i��r�����ĕ\�������u���Ɓv���ꎩ�̂���������ƂȂ�ƁA�����̑��݂̖�����Փ˂͎��Ȗ����ł���A���ȏՓ˂Ƃ��������Ȃ����ƂɂȂ�B���̕\�������u���Ɓv���m�̖�����Փ˂ُ͕ؖ@�I�Ɏ~�g�����B�a�҂͂�����C�f�[�ُؖ̕@�I�W�J�ƌĂB���̂��Ƃ����S�X�̎��ȓW�J���l�ɁA���ʓI�ȊϔO�����j�I�ɓW�J���Ă䂭���ƂƂ��đ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B����͕\�������u���́v�ł͂Ȃ��A��������\�������u���Ɓv���m���R���ے肵�����A���̂��~�g���Ă����l���w���Ă���B���̎~�g�������A�a�҂ɂƂ��āu�E���v�Ȃ̂������B�����̍l���̍����Ƃ����u�E���v�́A�A�E�t�w�[�x���ƌ�����������B ���ɏq�ׂ��悤�ɐl�i�T�O�ɂ����āA�a�҂͓����A�������Y����ă��b�v�X����e�����Ă����B�����A�l�i�ς̕ϗe�ƘA�����ă}�b�N�X�E�V�F�[���[���d�����n�߂�A�V�F�[���[�͊��o���\�ۂ������~���]����Ȃǂ�����ʓI�{����l�i�Ƃ��郊�b�v�X�̂悤�ȍl����˂���B����͒P�Ɍo����Ȃ����l��Ƃ��Ă̎����l�i�Ɠ��肵�Ă���ɉ߂��Ȃ�����ł���B�V�F�[���[�͂�����������Ƃ͕ʗl�̂Ƃ���ɐl�i���J�����Ƃ����B���ꂪ��X�ȍ�p�̋�̓I�ȑ��ݓ����l�i�Ƃ����`�ł���B�����A�a�҂̌���Ƃ���V�F�[���[�̒�`�ɂ���肪�������B���Ȃ킿�A�l�i���o����Ɍ��肷�邱�Ƃ���߁A�������̓I�ȍ�p�̓���ւƊJ���V�F�[���[�̍l���ɂ͉���I�ȂƂ��낪����ɂ��Ă��A��������Ă���̂́A���������o����⏔��p���A�Ȃ���Ƃ��ĔF�����ꓝ��I�ɔc�������̂��A�ƌ����_�ł���B�a�҂ɂ��A�����l�i�Ƃ���ɂ͌o���䂾���ł͂Ȃ�������̑��ʂ�����B����͒��z��Ȃ������Չ�ƌĂ����̂ł���B�o���䂪�l�I���ʂɏI�n����̂ɑ��āA���Չ�͂���z���A���g�͎��̉����Ȃ��B�����o����ɂ����Đ����̌o���̒��S�ɉ䂪�������A�����ꂷ�邱�Ƃ��ł���̂́A���̕��Չ�ɂ��̂ł���B����̍����Ƃ��Ă̕��Չ䂪�����Ă���̂͂���Ɍo����ɂ����Ă����ł͂Ȃ��B�V�F�[���[����������p�̓���Ƃ����l�i�ɂ����Ă��܂��A����ꂵ��ւƘA�����鍪���Ƃ��ĕ��Չ䂪�����Ă���ƌ����ׂ��ł���B�V�F�[���[�͌o�����l�i�Ƃ���l����˂��悤�Ƃ������A�a�҂̍l���ł͌o�����r�����邾���ł͐l�i�͎��䂩��������Ȃ��B�����ɂ͕��Չ�̖�肪�c����Ă��邩��ł���B�l�i�����䂩�犮�S�ɉ������ɂ́A���Չ�Ƃ͕ʂ̎d���Ől�i�ɓ����^�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�V�F�[���[�̘_�_���p���Ȃ���A�a�҂����̕s�\�������w�E�����̂͂��̓_�ł������B �a�҂ɂ��A�V�F�[���[���s�\���ł�����������������̔��������O�ꂳ�����v�z�����������v�z�ł������B�w���n�����̎��H�N�w�x�ɂ����ẮA���n�����̘_���I���S���A���Չ�ƌo����Ƃ��Ƃ��ɗ��E���邱�Ƃɂ������Ƙ_�����A�a�҂ɂ����ꂱ�������n�����̍��{�I����Ȃ̂������B�ł͗��҂���̗��E�Ƃ͂ǂ̂悤�ɂȂ������̂������̂��B���Չ�ƌo����Ƃ����ꂼ��咣�����̎v�z�́A���̑Η��ɂ�������炸��̎v�z�́A���̑Η��Ɋւ�炸��̋��ʓ_�����B��͗��O�����̉�����Ƃ����_�ł���A������͔F���̑ΏۂƂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂�ΏۂƂ���_�ł���B�������A���̓�̗�����ɗ��E����Ƃ́A�����̋��ʓ_�ɑ��ċt�̎咣�����Ă����Ƃ������Ƃł���B�܂��A���O�����̉����Ȃ����ƁA����ɔF���̑ΏۂƂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂͑ΏۂƂ��Ȃ����ƁB����������A�F���ɂ����Čo���Ɨ��O�Ƃ���ʂ��A�F�����o���̌��E�����߂邱�ƁA�܂��A�F���̑ΏۂƂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��悤�Ȗ₢�ɑ��ẮA�u�����Ȃ��v�Ƃ����ԓx���Ƃ邱�Ƃł���B�܂�A���҂̗���ɑ��Ē��z�_�I�ȗ���ɗ����ƁA���ꂪ�����̗���A�u���R����]��_�v�ł���Ƙa�҂͍l����̂ł���B�����ŁA���́A�����������z�_�I�Ȍ��������镧��������̐��Ƃ��ĉ������������Ƃ������Ƃ��B�a�҂����n�����v�z�̒��S�Ƃ��Ă�����̂́u���̐��͖���ł���v�Ƃ����O��̂��ƂɎ����ꂽ���]���ł������B ���]���Ƃ́A��ʓI�ɂ́A���]�A���Ȃ킿�܂v�f�̏W�܂�̈Ӗ��ł���A��X�l�̑��݂��\������F�E��E�z�E�s�E���̌܂̗v�f�̂��Ƃ������B�u�F�v�Ƃ͓��́A�g�̂̂��ƁB�u��v�͊��o�������͊����p�A�u�z�v�͕\�ۍ�p���Ȃ킿�z�����邱�ƊϔO��������ƁA�u�s�v�Ƃ��ӎu���邢�͏Փ��I�~���̂��ƁA�u���v�Ƃ͔F����p���邢�͔��f�̂��Ƃł���Ƃ����B���]���͂܂���X�̔F���̐��E��Ώۂɂ���B�u���͖���ł���v�Ƃ́A�ϑJ���ω����Ă����F���̐��E�݂̂�Ώۂɂ��A���ɂ̉i���Ȃ���̂Ȃǂ͈���Ȃ��Ƃ������Ƃ̌��������ł���B�F�����������A�Ⴆ�Ή�␢�E�̋N���ƏI���ɂ��āA���邢�͐��E�̗L�����������ɂ��ĂȂǂ̋c�_�ɂ͂��݂��Ȃ��B�u�����Ȃ��v �Ƃ����ԓx�́A�F���̐��E�ɗ̈�����肵�A���z�I�ȕ��Չ�͍l�@�̑Ώۂ���O�����Ƃ��Ӗ�����B�a�҂́A��������n�����̖��m�Ȏv�z�I���f�ł���Ɨ͐�����B�����A�F���̐��E�Ɍ��肵�A���Չ��ɂ��Ȃ��ƁA�o�����i�삷�邱�ƂɂȂ�B����ɑ��Ęa�҂́A���]���ł�������͎̂��̓I�ȗv�f�Ȃ̂ł͂Ȃ��A���̐��̂Ȃ����e�ł���Ƙ_����B�܂�A���]���͔��e�_�ł���A���e���Ȃ킿���O�łƂǂ܂��Ă���Ǝ咣����B�킽�����Ԃ�������v���B���̂Ƃ��A�킽���Ƃ�����̂��ԂƂ����q�̂���e���A��������������Ƃ���Ȃ�A�Ԃ͎�̑��Ƌq�̑��ƂɁA���Ƃ��ΔF�����ꂽ���Ƃ��̎��̂Ƃ�����ɁA���Ȃ��Ƃ�����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������ۂɂ͂����ł͂Ȃ��A�Ԃ́A�������ԂƂ��Ă����������肾�B�Ƃ͂������̂�����́u����v�Ƃ͂ǂ���������悤�Ȃ̂��B�a�҂ɂ��A����́u��̓���Ȃ��납�������y��ɂ����đ�����v�����ł���B�܂�A���́u����v�Ƃ́A�킽���̔F���Ƌq�ϓI�Ȏ��̂Ƃ������O�ɂ��邠��悤�Ȃ̂ł����āA�o���Ƒ��݂̎d������ɂȂ������̂��Ƃ����̂��B�a�҂́A���̂悤�ɂ��āu��v�Ƃ��̔��ʂ̋q�̉����A���Ȃ킿�A�������̂Ƌq�̂Ƃ��A�����ɉ�����悤�Ƃ���B���ƂȂ�̂́A���̔F���ł��q�̂ł��Ȃ��A���邢�͂��̂ǂ���ł�������̂Ƃ́A���lj����A�Ƃ������Ƃł���B�a�҂́A���̂���悤���u���݂�����̖̂@�v�Ɩ��t����B�a�҂͂�����u�����v�Ɖ��߂���B�u�����v�Ƃ́A�u���́v���u���́v���炵�߂�u���Ɓv�ł���B����������A�F�����́u���́v����̂��́u���́v�ł͂Ȃ��A�F������̂����̂悤�ɂ��炵�߂���e���邢�͌`���́u���Ɓv�A���ꂪ�u�����v�Ȃ̂��B�u�����v�Ƃ��Ă̖@�́A���݂�����̂̔��e�E�`���ł���A���݂��̂��̂���͓����B���ꂪ���݂�����̖̂@�ł���B�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̈����͂����́A���̂悤�Ɍ��]���̌����ɂ����Ė��m�Ɍ`��������l�@�����̂ł���B ���̂悤�Ɍ��]���́A�a�҂ɂ��A�F�������݂ɂ������ނ́u�@�v������B���]���͂������ɂ������ĕ��Չ��������A�o����ɂ�����u���v�u�킪�v���܂̖@�ɉ�̂����B�������ꂾ���ł͎���͉�̂��Ȃ��B����́u��v��ے肵�������ł���A�u��v�ɑ�����̂�ł��Ă��Ȃ�����ł���B�u��v�̍�p�A���ɕ��Չ䂪�����Ă��铝��̍�p���Ȃ�炩�̂������Ō�����ł��Ȃ���A����̍����Ƃ��ĕ��Չ䂪�Ăь����Ă��܂��B�a�҂͂����Ɍ��]���̕s�\���������Ă����B�a�҂ɂ��A�����̕s�\�����̕�U���������N���̉ۑ�ł������B ���N���Ƃ́A���ۓI���݂����݂Ɉˑ��������Đ����Ă��邱�ƁA����������̊�{�I�ȋ����̂��Ƃł���B���ׂĂ̌��ۂ͗l�X�Ȍ����E���������݂ɊW�������Đ�������̂ł���A��������������������Ȃ��Ȃ�Ό��ʂ����̂����������Ƃ����B�a�҂͉��N����P��̂��݂̂Ȃ����A�x�A�Z�x�A��x�A�\�x�A�\��x�̊e���N�����A���ꂼ��Ǝ��̍l�@���܂ޕʁX�̎v�z�ɂ����̂ƍl����B���̈قȂ����v�z�ɂ�鉏�N�����A�e����^�������A����_�̘_���I�Ȗ��W�J�ɉ������ƂŁA�P���Ȃ��̂��畡�G�Ȏ҂֔��W�����ƌ��Ă����B���]���ł͌܂́u���݂��̂��̖̂@�v�������ꂽ���A�����̖@�Ɩ@�Ƃ��ǂ̂悤�ȊW�ɂ����Ă���̂��͘_�����Ȃ������B���N���Ŗ��ɂ���̂́A�܂��ɂ������������̖@�̊W�Â��̎d���ł���B�a�҂͉��N�_�̊�b�Ƃ��Ă̂��̓�_�A���Ȃ킿����_�ƁA����_����b�Ƃ���@�Ɩ@�Ƃ̊W�Â��Ƃ����_����A����܂ł̓`���I�ȉ��߂ɂ���Č������A���̂��߂ɔ��Ɍ�������̂ƂȂ����Ɣᔻ����B �a�҂͌��]�����N���ɑg�ݍ���ł������Ƃɂ��A�O���͑��݂��Ȃ��͂��̌��]���ɓ��@���قɂ���ʂ̎v�z�����荞�ނ��Ƃ��w�E����B���̌��ʂƂ��Č��]���̉�̂ƁA����܂̗v�f�̉��N���ł̍č\�����i�߂��A���]�����̂ɂ����Ă͍l�@����Ȃ������ܖ@�̂������ł̊W�𖾂炩�ɂ���Ƃ����ۑ�ւƘA������B���̂��Ƃ͘Z�����Ƃ����ʂ̎v�z�������悹�錋�ʂƂȂ����B����͘a�ғƎ��̉��ߖ₦��B�Z�����Ƃ͘Z�̊��o�튯���邢�͊��o���̂̂��Ƃł���A��E���E�@�E��E�g�E�ӂ��w���B�Z�����ɂ����ĉۑ�ƂȂ�̂́A�����̊��o���ǂ̂悤�ɑΏۂł���u�F�v�ɊW���A��e���Ƃ��Ắu���v�Ƒg�ݍ����A�܂�����ɑ��Ĕ��f�Ƃ��Ắu���v���ǂ̂悤�Ɋ֘A���Ă������𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ������B�����炻��́A���N������݂�A���]���̂����́u�F�v�u��v�u���v�O�̗v�f����x��̂��A���]���Ƃ͕ʂ̎v�z�̉��Ŋ֘A�t����Ƃ������Ƃ������B �Z�����́u��v�����邱�Ƃɂ��Ă͗D��Ă��邪�A����_�ɓO����ɂ͖�������Ă����B����͘Z��������̓I���o�튯�⊴�o���̂ɂ��Ă̘_�ł��邪���߂ɁA���o���u�Ȃɂ��̂��́v�ɑ��銴�o�ł��邱�ƁA���́u���́v��_�̑O��ɂ��Ă��܂��Ă��邱�Ƃł���B�F���̂��������Ώۂ̂��Ƃ��A���Ɂu���v�ƌĂԁB�u���v���A�v���I���ɋK�肵�ċq�ϓI���̂�Ώۂ����炸���炸�O��ɂ���Ȃ�A���������q�̂ɑΉ������̂�m�炸�Ăэ���ł��܂��A����_��O�ꂳ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�B�����ŁA�a�҂͘Z�����̌n��͉��N����荞�܂��Ƃ��ɋt�]���邱�Ƃ��l�����B���Ƃ��A�u��������́v�Ƃ������Ƃ��������邽�߂ɂ́A�u��������́v�Ƃ����p����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�́A������u���́v�����藧�ɂ́A������u���Ɓv����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����킯���B����A���N�����̂��Z�����̍l���ɉe�����������B���̌��ʁA���N���̍�����Ȃ��u���v�Ɓu���F�v�Ƃ��A���݂Ɋ�b�Â��������ˊW�Ƃ��ċK�肳��邱�ƂɂȂ����A���̂悤�Ȃ��Ƃ��������̂́A�n�����Ȃ����ƁA���ɂ̍������Ȃ����Ƃ������ɂ͓s���������B���N�����Z�����ɂ����鑊�ˊW�������ꂽ�̂͂��̂��߂������ƌ�����B�������A�n���⍪���A���邢�́u��v����菜�����Ƃɂ͂�����Ă��Ă��A���ˊW���̂͘_���I�z�Ƃ��ĉ��N�n�̂��̂��낤�����Ă��܂��B�����ł���Α��ˊW����������ɂ́A�������������������Ȃ��瓯���ɏz����̂��邱�Ƃ����߂���B���̉�̂ɂ�����ۑ��a�҂͓������B��́A���ˊW�ɂȂ����̏����Ƃ͉����B��́A�����������̏����́A���ˊW���s�����悤�ɖ��������������Ƃ��ł��邩�B���̓�̉ۑ�����A���ˊW�̏z���������́A���ꂱ�����u�s�v�̊T�O�ł������Ƃ����B �u���v�͗��ʍ�p�ł��邪���߂ɁA���ʂ���u���Ɓv�ɂ����Ăǂ����Ă��u���́v�����t�����Ă��܂��B���߂���͕̂t�����Ă���u���́v�������S�Ɉ����͂������u���Ɓv�A����u���v�ɂ�����u���Ɓv�̂���Ȃ�u���Ɓv���̂悤�ȊT�O�ł���B���ꂱ�����u�s�v�Ƃ��āu���v�̎�O�ɂ��̏����Ƃ��ĉ�荞�ނ̂ł���B���̂悤�ɂ��āu�s�v�͐͏o�����B�������A���N���ł́A����Ɂu�s�v�̏����Ƃ��āu�����v�����Ă���B ����ɂ��ẮA�u�s�v�́A�u���́v���̊��S�Ȕ��D�ɂ���āA�u���ʂ����u���́v�������Ȃ������ȍ�p�v���Ȃ킿�u���Ɓv�́u���Ɓv���Ƃ��Č��o���ꂽ���A���������ꂪ���N�̍ŏI�����ƂȂ�ƂȂ�A�u���Ɓv�ł��邱�Ǝ��̂��A���������ꂪ���N�̍ŏI�����ƂȂ�ƂȂ�A�u���Ɓv�ł��邱�Ǝ��̂��u���́v�����Ă��܂��\��������B����������Η��O�����̉����Ă��܂��B�����ŁA�ŏI���������̉����邱�Ƃ��邽�߂ɓ������ꂽ�̂�����Ƃ��Ắu�����v�̍l���ł������Ƙa�҂͒f������B ���������A���N�n�I�����A������������Ƃ́A���݂��邱�Ƃ̖@���ł��A�ꂩ��̉�E���ׂ����Ƃ������Ƃ��B�܂�A���N���́A�@�Ɩ@�Ƃ̐����̂���悤�ƁA���ꂪ����ǂ̂悤�ɐ��ނ̂��̏������l�@����Ă���̂ł��邪�A����ł͂��̍l�@��]�p���邱�Ƃɂ���āA������]�p���邱�Ƃɂ���āA�������~�ߊ֘A����̂��@�̘A����h���ŋꂩ�瓦�����@�����邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��B�O�҂̌��������N�́u���ρv�A��҂��u�t�ρv�Ƃ����B�����ŏd�v�Ȃ̂́A���̏��t��ςǂ����̊W�ł���B���҂́A�m��̌n��Ɣے�̌n��Ƃ��đ��݂ɓƗ����đɂȂ��Ă���Ƃ͂����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�z�́u����������v�ƔF�����邱�Ƃɂ���Ď����I�Ɂu�����v��ł��A�t�ς֔��]���Ă��܂��B���ςƂ͖ł�����ׂ����R�I����̍������������̂ł���A�܂�͉�X�̔F�������݂̖@�̌n��ł���B����A�t�ς͎ߑ��̗���������n��ł���B�����̓�́A�ꌩ�S���������Ă���悤�Ɏv���邪�A���ۂɂ͂����ł͂Ȃ��A���R�I����́A���ς��t�ςւƔ��]���Ă��܂��悤�ɁA�����F������Ƃ����_�ɂ����Ĕ��]���ߑ��̗���ɂ������ܐڑ����Ă��܂��Ƙa�҂͎w�E����B ���������u�s�v�ƁA�u�s�v����n�܂鉏�N�n�������ł��邱�Ƃ��Ӗ�����u�����v�̋K��ɂ���āA���N���͐������A�ۂ��ꂽ�������̖��ɓ������Ƙa�҂͌���B����ɂ܂��A�����������N�������]���ɂ�����ĒS�����̂́A���ɒ��z�䂪������̍�p�̌����������Ƃ������ƂƁA���ɋꂩ��̉�E���v���̂�����邱�Ƃł������B���̉ۑ�ɑ��Ắu�s�v�ɂ���Ă���ɓ������B���̉ۑ�ɂ́A�u�s�v���������ł��邱�Ƃ��u�����v�Ƃ��đ������A�u����������v�ƔF�����邱�Ƃ������u�����v�ł��A�ꂩ��̉�E���v�����̂ł���Ƃ��� ���n���������ɂ����āu�s�v��̍���Ƃ��Č��o�������ƂŁA����܂ł̌l�I�ȓ��ʐ��Ƃ��Ă̐l�i�T�O�����S�ɕ��@�����B���n�����́u�s�v�̓��ꂪ�A�l�i�݉z����T�O�ł���Ƙ_�����B�l�i����p�̑��ݓ���Ƃ��Ă̌̂ł���Ƃ���ƁA�u�s�v�ɂ�铝��͂���݉z����B�Ȃ��Ȃ�u�s�v�͌X�̌̂Ƃ���Ƃ��Ă��炵�߂�@�ł����Ă��A���ꎩ�g�̂ł͂Ȃ�����ł���B�܂�A�u�s�v�́A���ꂻ�̂��̂Ȃ̂ł���A���ꂳ�ꂽ�u���́v���܂ފT�O�ł͂Ȃ��B���̈Ӗ��ɂ����āu�s�v�͌̐����Ȃ킿�u���́v����K�������l�i�Ƃ͋�ʂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̐l�i�ς͂����ɔp������A�V���Ȑl�i�ρA�u���Ɓv�̓���Ƃ��Ắu�s�v�Ƃ����l�i�ς֎���đ���B �a�ғN�Y�́A���n�����ɂ�������]���́A�����̖ڕW�ł���ꂩ��̉�E�Ƃ����ۑ�ɂ͓����Ă��炸�A���̉ۑ��S���͉̂��N���ł������B���̉��N���͔F���_�ł���Ɠ����Ɏ��H�_�ł�����Ƙa�҂͍l�����B�������A���H�_�Ƃ��ĕ����̒��S�ɂ���͔̂������ł���B�������Ƃ́A�����k�A�C�s�҂ɂ����鐶���̖ڕW�A����ɂ���ĉ�E�̎��H�ւƓ�����锪�̕��@�̂��Ƃł���B�u����������i�����j�v�u�������v���i���v�j�v�u���������i����j�v�u�������s�ׂ���i���Ɓj�v�u��������������i�����j�v�u���������i����i�����i�j�v�u�������O����i���O�j�v�u�������ґz����i����j�v�Ƃ������̕��@�́A�ʏ�͑m���̏C�s�����̖ڕW�Ƃ����B�������A�a�҂͈�ʂɌ�����ꂽ�l�Ԃ̓��ł���A���������̓��ł���������B�����āA�������̖`���Ɂu�����v�����邱�Ƃ��ɂ߂ďd������B�����͐^���̔F���̈Ӗ��ɉ�����A����́u�����v�̖łƂ�������������B�^���̔F���͐����ɂ���Ĉ����N�������ʂ̂��̂ł͂Ȃ��A�������̂��̂ł���B�������͐������Ȃ킿�^���̔F�����A���ꎩ�g�������A���ꎩ�g�ɂȂ�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ����B����Ɏ��̂悤�Ɍ����B�������́A�����̎����Ƃ��Ă̐������g�̉^���Ƃ����B�a�҂́A�������𐳌��ɂ��ׂĕ�܂��Ă��܂��̂ł���B�����́A�������@�Ƃ��Ď������������̂ł���A���ꂱ�����u�ł̓��v�ł���B�a�҂͎��H�_�Ƃ��Ă̔��������A�������F���̂���悤�A���Ɍ��邱�ƂɏW����B�������A�ʏ�ł͔F���Ǝ��H�͕ʂ̂��̂��B�����A�F�����邱�Ƃ����H���邱�Ƃł���Ƃ���Ȃ�A����͂����̗̈�ɂ����Ăł������肦�Ȃ��B���Ȃ킿�u���邱�Ɓv���̂����ȓW�J���Ă����̈�A�F������Ƃ������H�ȊO�Ɏ��H���Ȃ�����悤�ɂ����Ăł���B����������ΔF���Ǝ��H�Ƃ̎��R�ȕϊ��́A�ӏ܁E���߂����ȖړI�������������p��ɂ����Ă����ʗp����Ƃ������Ƃ��B���ꂢ�A���܂Ō��Ă������N���ł����������u����v�Ƃ�������悤�̋����ł������B�a�҂ɂƂ��āu����v�Ƃ́A�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ������͂����āA�u���Ɓv���F�������H���鎩�ȖړI�I�̈����������Ƃ��������Ƃ��Ă������B�u����v�́A�F�������H�̗̈�̎����̗v�Ƃ��Ă���B�������āu���́v�Ɓu���Ɓv�̈����͂����Ƃ������Ƃ���́A���j�I�l�@�̂��Ȃ��Ř_���I�ȋɓ_���}���邱�ƂɂȂ����B���̋ɓ_�͎O�̃|�C���g������Ă���B�܂��A��ڂ́A�u���́v�ƈ����͂����ꂽ�u���Ɓv���A����ł��t�������Ă���u���́v��������ɔr�����ꂽ���ʁA�u���Ɓv�́u���Ɓv���Ƃ������ׂ������ȁu���Ɓv���u�������Ƃ����_�ł���B���N���ɂ�����u�s�v�̉��߂����̗�ł���B�܂���ڂ́A���̏����ȁu���Ɓv���Ăсu���́v�����Ȃ��悤�ȑ��u�Ƃ��āA�u���Ɓv�̖�������������킷�L���̂悤�ȊT�O���l����ꂽ�Ƃ����_�ł���B���N���ɂ�����u�����v�̉��߂����̗�ł���B����ɎO�ڂ́A���������u���Ɓv�����ȖړI���������邽�߂̗v�ɗl�ȊT�O���l����ꂽ�_�ł���B���N���ɂ����閳�����s�̑g�ݍ��킹������ł���B
�V�D�l�i����ԕ��� �u�l�i�Ɛl�ސ��v�ň�����̂̓J���g�̐l�i�_�ł���B�����ł̓J���g�̓����_�̒��j���Ȃ��L���Ȓ茾���@�̉��߂ɏI�n����B���̍l�@�ɂ����ĉ��~���ɂ��ꂽ�̂̓n�C�f�b�K�[�̃J���g���߂ł������B���̒茾���@�ɂ��Ă̓��{�ł̈�ʓI�ȉ��߁u�l����i�Ƃ��Ď�舵���ȁA���ׂĂ̐l�����ȖړI�Ƃ��Ď�舵���v�ɑ��āA�a�҂͂Q�̖��_���w�E����B���A�l�i�Ɛl�ސ��Ƃ̋�ʂ��Ȃ���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���A��i�Ƃ��Ăł͂Ȃ��u�����Ɂv�ړI�Ƃ��Ĉ����A�Ƃ����u�����Ɂv�̓_���������Ă��Ȃ����B�Ƃ��ɑ��̖�肩��A�a�҂́A�����l�i����i�łȂ��ړI�Ƃ��Ĉ����Ɨ������Ă��܂��ƁA�O��I�Ȍl��`�������Ă��܂����ƂɂȂ�Ƃ����B�Ȃ��Ȃ�A�������l�ɕ�d���邱�Ƃ��A�l�i�̎�i���ł���̂Ŕے肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B���̌���́A��i�ł���Ɠ����ɖړI�ł���Ƃ��ĂƂ��������̗������ԈႦ�����ƂɋN������B�����ɂƂ����_�����ӂ��ēǂ܂��Ȃ�A�茾���@�͂ނ���A�������A�����đ�����A���ȖړI�Ȑl�i�Ƃ��đ��d�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����Ɏ�������i�Ƃ��Ďg�������A�܂����l����i�Ƃ��Ďg�����Ȃ���ΐl�ԊW�͐������Ȃ��B���̂悤�ɍl����A�茾���@���͐l�ԊW�̌����Ƃ��ēǂ܂��ׂ��ł���B�������A����͎�������Ȃ����O�ł͂Ȃ��Ƃ����B�J���g���l�ސ��̌��������o�����̂͌����̎Љ�ɂ����Ăł���A������l�ސ��̌������܂����̎Љ�ɕ����I�Ɏ�������Ă���B������肩�A���Ƃ��l�ސ��̌����������x�z����u�ړI�̍��v�ɂ����Ăł����Ă��A�l�i�͂�����Ƃ��āu���v�ł�����A�l�i����i�Ƃ��Ď�舵���邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B�a�҂���������̂́A��X�������݁A���łɖړI�Ǝ�i�Ƃ̓�d���ɂ����āu����v�Ƃ����_�ł���B���̂悤�Ȑl�i�Ɛl�ސ��Ƃ́A���Ȃ킿�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̓�d���̋����́A����܂ł̘_���ɂ˂���������炷���ƂɂȂ�B�܂�A�w���n�����̎��H�N�w�x�ɂ����āA�u��v�͕�������A�u���́v����O�ꂵ�Ĕr�����ꂽ�u���Ɓv���̂̎�������̈�A�Ƃ��ɂ��ꂪ�u�s�v�ɂ���ē��ꂳ��Ă䂭����悤�����o���ꂽ�B�������������ȓ����p�Ƃ��Ắu��v���y���\�i�ł������B�����ň�т��Č��o�����̂́A�l�i����u���́v����r�������ƁA���邢�͕\�����ꂽ�u���Ɓv����\�����ꂽ�u���́v���Ƃ낤�Ƃ����Ƃł���B����ɑ��āA�J���g�̒茾���@�ɂ����Đl�i�Ɛl�ސ��Ƃ̓�d�����������邱�Ƃ́A�ނ���l�i�́u���́v�����������A��������_�Ƃ��Ē�o���ꂽ�B�茾���@�ɂ��Ă̈�ʓI�ȉ��߂ɂ����Đl�ސ��̗��O���Ȃ킿�u���Ɓv�����肪�d������Ă��܂��Ă���A����ɑ��ē�d�����������邽�߂ɂ́A�u���Ɓv�̑��ʂł͂Ȃ��u���́v�̑��ʂ������A�܂���������K�v������B������������˂���ݏo���B�u���Ɓv�͒P�ɗ��O�ł͂Ȃ��A�u���́v�������Ȃ炸�����̂ł���A�l�ސ��͕K�����́u�����v�Ƃ��Ă̐l�i��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����咣����a�҂́A�w���n�����̎��H�N�w�x�ł̍l�@�Ƃ͐����̎咣���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B �a�҂́A�茾���@�ɂ�����l�i�Ɛl�ސ��Ƃ̋�ʂ́A�J���g�̑��ᔻ�́u���������̌�T�����ɂ��āv�Ŋ��ɂȂ���Ă���A�����S���w�I�l�i���ƒ��z�_�I�l�i���Ƃ̋�ʂł���Ƃ����B���z�_�I�l�i���Ƃ́u��v���v�̎�̂ł���A�v�ҍ�p���N�����_�̂��Ƃ���ł͂Ȃ��A�v�҂��̂��̂̍����I�����I����ł���Ɖ�������B����̏����S���w�I�l�i���Ƃ́u��v���v�̎�̂ł���A�ΏۂƂ��Ă͋ȁA����Έ��̌`���ł���B���̌`���ɏ[�U�������̂����������S���w�I�l�i���ƌĂ��B����́A�l�i���邢�͋q�̉�Ƃ��Ă�A�l�i�����Ȃ킿���o��ƑΏƂ����B�����̋K��̓n�C�f�b�K�[�̒��ړI�ȉe���������̂ƌ�����B�n�C�f�b�K�[�̓J���g�lj��ɂ����ĐS���w�I�l�i���z�_�I�l�i���Ƌ�ʂ��ċK�肵���B����͊o�m�̎���ł���A�m�o�̌o���A�����ɂ�鏔�X�̐S�I�ȉߒ����o������u���䄟�q�ρv�̂��Ƃł���Ƃ����B����͒��z�_�I�l�i�����Ȃ킿���o�A���邢�́u���䄟��ρv�Ƃ͑ΏƓI�ȋK��ł���B������A�a�҂́A���������l�i�Ɛl�i���̍��ق��A�u�l�i�́u���́v�ł���A�l�i���͂��́u���́v���u���́v���炵�߂�u���Ɓv�ł���B�v�܂�A�u���́v�Ɓu���Ɓv�̈����͂����Ƃ����v�l�����͂������Ől�i�_��S���l�i�Ɛl�i���Ƃ̋敪�ƂȂ��Č����Ă���B�n�C�f�b�K�[�̃J���g���߂Ƙa�҂́u���́v�Ɓu���Ɓv�̈����͂����Ƃ́A�������Ă���B �������A���҂̉��߂œ����I�l�i���̉��߂��߂����Ă͘��������炩�ɂȂ�B�����I�l�i���͈Ӗ��I�ɋ������肪�ׂ���A����̎��Ȉӎ��A����A�Ƃ��ɑ��h����ɓ��肳��Ă���B�J���g�́A�������̕��͂��A���̍������鑸�h����̕��͂Ƃ��Ē�o����B���̑��h�͓����I�s�ׂ̖@���ɑ��鑸�h�̊���ł���B����A���h����ɂ���Ė@�����@���Ƃ��Ă͂��߂Đ�������B�܂葸�h�Ɩ@���Ƃ́A��b�Â��𑊌ݓI�ɍs���W�ɂ���B�n�C�f�b�K�[�ɂ��A�J���g�̑��h����Ƃ́A�@���ɑ��đ��h���銴��������䂪�A�����Ɏ��Ȏ��g�ɂƂ��Ă����ɂȂ邱�Ƃł���B�܂�A���Ȃɂ���Ė@���Ƃ����u�����v������Ȃ���A���́u�����v�ɂ���ċt�Ɏ��Ȃ��K�肳��A�������悤�ȏd�w�I�Ȏ��Ȃ̂���悤�̑S�̂ł���B�n�C�f�b�K�[�ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A�@�����̂��̂ł͂Ȃ��A�d�w�I�ȏɂ����Ăǂ̂悤�ȍs�ׂ���X���s�����ł������B����ɑ��āA�a�҂̏ꍇ�́A���h����͉�X���{���I�Ȏ��Ȃ����o����d���ł���A�@���ւ̑��h����́A�{���I�Ȏ��Ȃւ̎��o�ł������B�a�҂̓n�C�f�b�K�[�����͂����������u���Ɓv���u�����v�Ɏ��ʂ����Ă��܂��B�����ōő�̖��ƂȂ�̂́A�u���Ɓv���̂̎����Ƃ������Ƃ���������p���Ȃ���A���������u���Ɓv������ɐi�߂āu�{���I�Ȏ��ȁv�ւƌĂъ����Ă���_�ł���B�a�҂̓J���g�̑��h����͂�����Ƃ����̂ɂ��Ă̍l�@�Ƃ��Ď��ʂ�����B�a�҂͖{���I�Ȏ��ȂƂ́A�����I�l�i���ł��蒴�z�_�I�l�i���ł���Ƃ��āA�n�C�f�b�K�[�̂悤�ɋ敪���Ȃ��B�����������ꂪ�قȂ��Ă���ɉ߂��Ȃ��Ƃ����B���̗���̑���Ƃ̓J���g���v�ٓN�w�i���ᔻ�j�Ǝ��H�N�w�i���ᔻ�j�Ƃ̋�ʂ��s�����Ƃɂ�鑊��ł���Ƃ����B�{���I���Ȃ��ӎ�����Ƃ́A�s�ׂ��邱�Ƃ��̂��̂ł���Ƃ����B�܂�A�{���I���Ȃ�F�����邱�Ƃ����̂܂܍s�ׂ��邱�ƂȂ̂��B�����Ŏv���o���̂́A�w���n�����̎��H�N�w�x�ɂ����āA���N���́u������F�����邱�Ɓi���ρj�v���A�u������ł��邱�Ɓi�t�ρj�v�ւƗe�Ղɔ��]���Ă��܂����ƁA�F�������̂܂��H�ƂȂ�Ƃ����咣���낤�B�s�ׂ��邱�Ƃ͖{���I���Ȃ̂���悤�ɑg�ݍ��܂��B�Ƃ���Řa�҂ɂ��A�{���I���ȂƂ͓����I�l�i���̂��Ƃł���A�܂�����͒��z�_�I�l�i���A����ɂ͐l�i���l�ސ��Ɠ������̂Ƃ��ꂽ�B����͐l�i�Ƃ����u���́v���\�ɂ���u���Ɓv���u�����v�ł���B�܂�A�u���Ɓv�Ƃ��Ă̖{���I���ȂȂ��������I�l�i���́A���łɁu�s�ׁv���܂�ł���Ƙa�҂͍l����B���̍l���ɂ��ẮA��͂�w���n�����̎��H�N�w�x�ɂ����āA���N���́u�ŏI���ꌴ���v�Ƃ��āA�u���Ɓv�Ƃ��Ắu�s�v�Ƃ����K��������Ă������߂��v���o�����Ƃ��ł��邾�낤�B���̂悤�Șa�҂̃J���g���߂́A�u���Ɓv�Ƃ��Ă̐l�i���Ƃ����w���n�����̎��H�N�w�x�ȗ��̐l�i�T�O�ɏꏊ��^���悤�Ƃ��鎎�݂ł������Ƃ����邾�낤�B �����Łu�l�i�Ɛl�ސ��v�Ƃ����_�l��ǂގ҂͒��r���[�ł���̂���������Ȃ��B����́A�����̈Ӑ}�A���Ȃ킿�l�i�Ɛl�i���l�ސ��Ƃ���ʂ��悤�Ƃ���Ӑ}�ƁA���ۂ̍s�_�Ƃ��˂���Ă��܂��Ă��邱�ƂɈ����Ă���B�����Ɍ����Ă�������A���Ȃ킿�u���Ɓv�Ƃ��Ă̐l�i���̒��o�Ƃ����Ӑ}����O��Ă���s�_���A�O�̓_�ɂ����Ē��ڂ��Ă��������B���ɂ́A�l�i�́u���́v���̋����̓_�ł���B���ɂ́A�_�l�̏I�Ոȍ~�ŋ}�ɕ��サ�Ă����̂ւ̏d���̓_�ł���B�����đ�O�ɁA�_�l���������}���A�������Ō�܂Ř_���s�������Ƃ��ł��Ȃ������l�i���̋����Ԑ��ւ̊֘A�̓_�ł���B �܂��A�u���́v���̋����Ƃ����_���猩�čs�����B�w���n�����̎��H�N�w�x�ɂ����Ắu���Ɓv�Ƃ��Ă̑��ʂ𒊏o���鎎�݂��Ȃ���A����́u���́v���̓O��I�Ȕ����Ƃ�ɂ���čs��ꂽ�B�����A�����Ӑ}���p�����Ȃ�����A�u�l�i�Ɛl�ސ��v�ɂ����ẮA�t�Ɂu���́v���Ƃ��Ă̐l�i���������A�i�삷��Ƃ����_��������Ă����B�u���́v���̂��̉����́A�ǂ����痈�����̂ł��������낤���B����ɂ́A���a�Q�N�̃n�C�f�b�K�[�́w���݂Ǝ��ԁx�̊��s�Řa�҂��h�C�c���w���ɓǂ��Ƃ��N�����Ă���B������@�Ƃ��Ęa�҂͕��y���̍l�@���n�߂�B�a�Ҏ��g�́w���݂Ǝ��ԁx�̌��E�̕�U�̎��݂̂悤�Ȃ��Ƃ��q�����Ă��邪�A���́A�L���ȓ���̍l�@���q���g�ɂ����p���A�g�債�����̂����y���̍l�@�̍��{�ƂȂ��Ă���B����͒P�Ȃ�u���́v�ł͂Ȃ��A����Ɋւ���X���A��X���g�̂���悤�������ɔ���������̂Ƃ��Ă���B���ꂪ����Ɠ����o���Ƃ�������̓�d�\���ł���B�a�҂ɂƂ��Ă��̍\���͕��y�ɂ����Ă����l�ł������B�a�҂͂��������ւ��̍�����A��X���O�ɏo�Ă��邱�Ƃ��Ƃ���B���̃n�C�f�b�K�[�̉e����Ǝ��Ɋg�傷�邱�Ƃɂ��A�a�҂́A��X���K�肵�Ă���u���Ɓv����łȂ��A�K�肷��u���́v�ɒ��ڂ��ׂ��ł���ƍl����B���̂��Ƃ��a�҂ɕ��y������������̂��B�����ł̕��y�ւ̒��ڂ́A���̒��ɂ���u���́v�Ƃ��Ắu���́v�ւ̒��ڂł���B�_�l�u���y�v�ɂ����āu���́v�Ƃ́A�܂�����A���Ȃ킿��X���g�p������A���Ȃ킿�ւ����̂Ƃ��āA��X�����Ȃ��J��������̂Ƃ��āA�O�ɏo�邠��悤�ł���B���̂悤�Ɍ���A�u���́v���̋����Ƃ́A�����������y�ւ̒��ڂƋ��ɂ����āA���̒��̂��̂ɂ��łɉ�X���O�ɏo�Ď��Ȃ��J�����Ă���Ƃ����_�ւ̒��ڂł���B����͖��炩�Ƀn�C�f�b�K�[�̍l�@�̌p���ł���B�Ɠ����ɐ��c�����Y�̕\�����l�i�̍l���ɋ߂Â��Ă���B�����ő��̘_�_�ł���u��́v�̖��̕���Ƃ��������ɂ��Ă����Ă����B���̋}���ȁu��́v�̕���́A�����l�i���l�ސ��ł���Ƃ������z�_�I�l�i���Ɠ����I�l�i���Ƃɂ����āA�O�҂���҂Ɉڍs�������Ƃ��q�ς̐��������̖�肩���̂̎��ȋK��̖��ֈڂ������ƂƂ��Ęa�҂������������Ƃɂ��B��������a�҂͐l�ސ��͐l�i�̎�̓I�ȍ���Ȃ̂ł���Ǝ咣�����B�����āA�������̌����I����ł���Ȃ��炻�ꎩ�̂͑ΏۓI�ɂ���̂ł͂Ȃ��悤�Ȏ�̂̍���A�����a�҂͐l�i���l�ސ��ƌĂڂ��Ƃ���B�����Ŏ������Ƃ��Ă���̂́A�u���Ɓv�ɂƂǂ܂邱�Ƃ̂Ȃ��A�����ɂ���u���́v�����������ꂽ��̓I�����I�Ȏ�̂̍���Ȃ̂ł������B �d�v�Ȃ̂́A�������čĐ����ꂽ��̂ɂ��āA���̍�����J���g�̑�����v�z�����ɂ͑����Ȃ��A��̌������̎�̓I�ȍ����Ƃ��Ắu��v�̂��Ƃ����̂ƌ������_�ł���B���́u��v�Ƃ͉����B�u�����N�w�ɂ�����u�@�v�̊T�O�Ƌ�ُؖ̕@�v�ɂ����āA�a�҂́u�����v�Ƃ��́u�@�v�Ƃ����l�����ӂ����ѓ_�����A������u��v�̍l�@�ƂȂ����B�ʏ�̖@�̉��߂́A�@���u���́v�Ƃ���f�p���ݘ_�I�ȍl�����Ɛ^���ݓI���z�҂Ƃ��錩�����l�����邪�A�a�҂͑o���Ƃ��ᔻ����B�����ł͂Ȃ��A���n�����̓N�w�ɂ����Ă��łɌ����Ă���u�����v�Ƃ��̖@�̊T�O�A�܂�A�@���u�����v�Ƃ������߂�O��ɂ��Ă��̍���Ȃ����S�̂�z�肷��ے�̓��������o���B���̔ے�̓����������u��v�̓����ɘA������B�����Œ��ڂ��ׂ��Ȃ͖̂����̈Ӗ��Â��ł���B�w���n�����̎��H�N�w�x�ɂ����āA�����́u�s�v���ꔲ�����A�������ł��邻�̂��Ƃ������Ă���ɂ����Ȃ������B�����������ł́u�s�v���S���Ă������ꌴ���̓���������������ƂȂ�A����ɉ^�����A��p�������Ȃ������ʁA�ے�ɂ�铝�ꍪ���A�ے�̉^�����̂��̂ɂ���Ă���B�������ĕω����������̍l�����u��v�ɂ����Đ�������Ă���Ƙa�҂͌����B�����ł���u��v�����ꌴ���ł���A�ے�̉^���̂��Ƃ��B�ے�̉^���Ƃ��č��ʂ̐��E�Ɩ����ʂ̐��E�ꂷ�鍪���Ƃ��Ắu��v�B�a�҂̍l���Ă����u��v�Ƃ͂������������������̂ł���A������u��v�ُؖ̕@�ƌĂB�����ł̍��ʂƂ͏��ς̂��Ƃł���A�����ʂ��t�ς̂��Ƃł���B�܂�A���ʂƖ����ʂ̓���Ƃ́A�ȒP�Ɍ����ΔF���Ǝ��H�Ƃꂷ��Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�����Łu�l�i�Ɛl�ސ��v�ɂ�����̂̍���ɁA�����̍l����������ƁA��̂̍���ɂ́A�ے�^���ɂ���ĔF���Ǝ��H�Ƃꂷ��悤�ȕُؖ@�I����������A���ꂪ��̌������̎�̓I�����ł���Ƃ������Ƃł���B����́A�l�i�ɂ����ĒP�ɒ��ۓI�ȁu���Ɓv���u�����v�ł͂Ȃ��A�����ɋ�̓I���ۓI�ȁu���́v�����������ꂽ���Ƃ���łȂ���Ȃ�Ȃ��B����Ɂu���́v�Ƃ́A������g�p���A�g�p���Ă��鎩���F������Ƃ����u�������v�ɂ����Č��o�������̂ł����āA����͎��炪�u�O��o�邱�Ɓv�ł��������B�܂�A�u��̂̍���v�Ƃ́A�ے�^���Ƃ����ُؖ@�ɂ���ĔF���Ǝ��H�Ƃꂷ�邪�A����͋�̓I�ɂ́A���������ُؖ@�ɂ���Ď��炪�u�O�ɏo�邱�Ɓv���̂��̂ł���Ƃ���́A�u���́v���Ƃ́u�������v���x����u����v���Ƃ������Ƃ��B�u�l�i�Ɛl�ސ��v�ɂ����āA�啔�����l�i�Ɛl�i���l�ސ��A����������u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ�����ɍ\���Ɏ~�܂��Ă����͂��̂��̂��A�ŏI�̕����ɂ����ēˑR�u��̂̍���v�Ƃ��āu��v�Ƃ����l�����o����A���̌��ʂ��̓�ɍ\�����h��n�߂��̂��B �a�҂͈ȑO�u���哹���v�ɂ����āA�l�i�́A�\����^������i�I�E���ʓI�ɃR���g���[������u���́v�ł͂Ȃ��A�\����^���ɓۂݍ��܂�A���̂��Ȃ��ɂ���\�ʓI�ȁu���Ɓv�Ƃ��Ē�o���ꂽ�B����������āw���n�����̎��H�N�w�x�ɂ����ẮA��i�̔����������ꂽ�l�i�A���Ȃ킿����_�̍l�@�Ƃ��Č��n�������l�@���邱�ƂŁA�u���́v�����Ƃ�ꂽ�u���Ɓv���u�����v�ł���u�@�v�����o���ꂽ�B��i�������o���ꂽ�l�i���A����ł��l�i�Ƃ��Đ�������j�S�Ƃ͓���̍�p�ł��邪�A���̓���̋��ɍ����́A�u�s�v�ɂ���Č��o�����B���̎��_�Řa�҂̕\�����l�i�ɂ��Ă̍l���́A�u���Ɓv�́u���Ɓv���Ƃ��Ắu�s�v�A����u���Ɓv�̈�ɓI�Ȃ��̂ł����Ȃ������B�����A�n�C�f�b�K�[�̍l���́A����������ɓI�Ȑl�i�ςɕϗe�������炷���ƂɂȂ����B�n�C�f�b�K�[������e���Ƃ́A�[�I�ɁA�u���́v�̏d�v���̎w�E�ł���B�n�C�f�b�K�[�̓���ɂ��Ă̕��́A�܂�u���́v�ւ̕��͂̎d���́A�a�҂Ɂu���́v�̉����Ƃ��Ă̕��y���Ƃ������ɋC�t�����A���̉e���ɂ���Đl�i�ςɂ����ẮA�u���́v������������B�u���Ɓv�Ɓu���́v�Ƃ̓�ɍ\��������邱�ƂɂȂ����B �u���{��ɉ����鑶�݂̗����v�ɂ����āA�u���́v�Ɓu���Ɓv�̓�ɍ\�����ƁA����ɂ�������̎O�ɉ��̐�G�ꂪ������B�a�҂��_���悤�Ƃ���̂́A���݂̎d������{��Ŗ₤�u����Ƃ������Ƃ͂ǂ��������Ƃł��邩�v�Ƃ����₢���̂��̂̌�@�I���͂ł��������A����͎l�ɕ�����Ă����B���Ɂu���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̍��قɂ��āA���Ɂu�������Ɓv�Ɓu���邱�Ɓv�Ƃ̍��قɂ��āA��O�Ɂu�������Ɓv�͒N�������̂��A��l�Ɂu����v�Ƃ͉����Ƃ����₢�ł���B�����ł͑��Ƒ�l�𒆐S�Ɍ��Ă����B�a�҂́u���Ɓv�̈Ӌ`���O�̕����ɕ��ނ���B���Ɂu�������Ɓv�̂悤�ɓ����ƌ������ē������������A�u�Â��ɂ��邱�Ɓv�ƌ������ď�Ԃ�\�����ʁB���Ɂu�ς�������Ƃ��N�������v�̂悤�ɏo������\�����ʁB��O�Ɂu���邱�Ƃ������v�̂悤�Ɂu����ꂩ���邱�Ɓv��\�����ʂł���B�����̕��ʂɋ��ʂ���u���Ɓv�Ɓu���́v�Ƃ̍��قɂ��āA�a�҂͂��ׂ��̂��̂��w�ɕ�����B���w�́A�����I�E�S���I�E���j�I�E�Љ�I�ȁu���́v�A���Ȃ킿�ΏۂƂ��Ắu���́v�ƁA������u���́v�Ƃ��Ă��炵�߂��b�Ƃ��Ắu���Ɓv�̋�ʂł���B�a�҂́u���Ɓv���u���́v�����A�v���I���ł���Ƃ����B�����A���w�ɂ����ẮA���̂���悤�͋t�]����B�u���Ɓv�͂��ꎩ�̂Ƃ��Ă�����̂ł͂Ȃ��A�u���́v�ւ̂����������{�ɑ�����u���Ƃ̗����v�ɂ����Ă̂݉�X�ɗ^������̂ł���A�l�Ƃ����u���́v�̂�����ɂ����Ă̂�����Ƃ����B�܂�A�u���Ɓv�͂��̂���Ȃ鍪��Ƃ��āu���́v�Ɋ�b�Â�����Ƃ����̂ł���B���̑��w�Ƒ��w�����������āA�u���́v���u���Ɓv���u���́v�Ƃ����֘A�}���������B�������A�����Łu���Ɓv�Ƃ��̍��ꂽ��u���́v�Ƃ����}�����������w�ƁA�u���Ɓv�Ƃ��̍��ꂽ��u���́v�̐}�����������w�̊ԂŔ��]������A�ꗂ�����B���̉����ɂ��ẮA�u����v�Ƃ������t�̕��͂ɂ���ĂȂ����B ����̓n�C�f�b�K�[�̕��͂��ӂ܂������̂ŁA�{���Ƒ��݂Ƃ����n�C�f�b�K�[�́uSein�v�̋�ʂ��A�a�҂͓��{��́u������v�Ɓu�ł���v�Ɉ����A�u���݁v���Ȃ킿�u�ł���v���d������n�C�f�b�K�[�̍l�����t�|������B�a�҂͓��{��ɉ����Ắu������v�̕����u�ł���v��������I�ł���Ƃ���B�Ƃ���ł��̋�ʂ́A�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̋�ʂɑΉ����Ă���ƌ�����B�u������v�Ƃ͉����́u���́v������Ƃ������ƂŁA�܂��A�u�ł���v�Ƃ́u���́v�ɊҌ�����Ȃ������̂���悤�������_�ɂ����āA�u���Ɓv�Ɠ����ł���B���{��ɉ����āu������v���u�ł���v��������I�Ƃ��镪�͂́A�u���́v�Ɓu���Ɓv�̕��͂ɂ�������w�̂���悤�A���Ȃ킿�u���́v������I�ł���Ƃ��邠��悤�ƘA�����Ă���ƌ�����B���������ŏd�v�Ȃ̂́A�u������v���u�ł���v��������I�ł���Ƃ͂��Ă��Ă��A����͑��ΓI�ȍ��ɂ����Ȃ������Ƃ����_�_�ł���B���̎w�E���u���́v�Ɓu���Ɓv�ɏd�˂�ꍇ�A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��炪������邩�B���łɂ������u���́v���u���Ɓv�ɂ��Ă̑��w�Ƒ��w�Ƃ��ꗂ́A�u���́v���u���Ɓv���u���́v�Ƃ����d�w�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��A�����Łu���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̐[�x�̊W���m��ł��Ȃ��Ƃ������ԂށB�����A����炪�P�ɑ��ΓI�ȍ��قɂ������A�u���Ɓv�Ɓu���́v�̂ǂ���ɂ����Ă��^�́u����v��������Ȃ��ꍇ�A�u���Ɓv�Ɓu���́v�Ƃ́A����ɂ́u���́v���u���Ɓv���u���́v�Ƃ����A�́A�[�x�̍��قł��邱�Ƃ���߁A���̐����I�ȘA������ΐ����I�ɂ��āA��C�ɕ\�ʂɕ��サ�A�����ɂȂ�B�����ō���Ȃ���͎̂�����Ȃ��̂��B�����Ń|�C���g�ƂȂ�̂��u���́v���̉����ɂ������B�u�l�i�̋����ԁv���猩��A�l�i�Ɛl�ސ��Ƃ́A�݂��ɑ���̔ے�̏�ɏ��߂ċK�肳���B���Ȃ킿�u�l�i�̋����ԁv����A�u���́v�����l�i��ے肵�����ɁA�͂��߂āu���Ɓv�����l�ސ��͌�����B�t�ɂ܂��A�u�l�i�̋����ԁv����u���Ɓv�����l�ސ���ے肷��A�u���́v�����l�i��������B�u�l�i�Ɛl�ސ��v�ő��ݓ]���ƌĂ��Ƃ�����A�����炭�����ł���B�l�i�Ɛl�ސ��Ƃ́A�����ɑ���̔ے萫�ɂ����Ă��̂��̂��K�肳��A����ɂ܂��A���̂��̂����Ȕے肷�邱�Ƃő���ɖ߂�Ƃ����A�ے萫�ɂ���Ĕ}���鑊�ݓ]���̊W�����B���̊W�ɂ��邱�Ƃɂ����ď��߂āA�u��v�Ƃ�����萫�����肠����̂��B�������ċK�肳��鍪��Ƃ��Ắu��v�́A�l�i�Ɛl�ސ��Ƃ̊ϔO�̂ǂ���ɂ������Ȃ����ƂɂȂ�B�Ȃ��Ȃ炻��͐l�i�Ɛl�ސ��Ƃ�ے�I�ɑ��ݓ]����������̂����炾�B�a�҂͐l�ސ����u��v�Ƃ��Ď������Ƃ��邪�A�u��v�͐l�ސ��ɂƂǂ܂��Ă͂����A�l�ސ��Ɛl�i�̒��ԂɁA���邢�͂��̍���ɔ����ꗎ���Ă��܂��B�u��v������ւƔ����ꗎ���邱�Ƃɂ����āA�l�i�Ɛl�ސ��Ƃ̓�ɍ\���͎O�ɍ\���ւƓ]������B�l�i�̍l�@�ɂ����āA�u���Ɓv���u�������v�̈�ɓI�Ȃ��̂���A�u���́v���̉����ɂ����ē�ɍ\���ɓ]�����A����ɂ�������u��v���z�肳�ꍪ��ւƔ����ꗎ���邱�ƂŎO�ɍ\���ւƓ]������B �a�ғN�Y���m�������ϗ��w�̓����Ƃ́A�l�Ƃ��Đl������̂ł͂Ȃ��A���łɎЉ���܂����̐���S���Ă��鑶�݂Ƃ��Đl������Ƃ����Ƃ���ɂ������B���̎Љ�⋤���̐��̂��Ƃ��A�ԕ��A���̒��A���ԂȂǂƓ��{��ɂ���Ď����A����ɐl�������������������ԕ��ɖ��ߍ��܂�Ă��鑶�݂ł��邱�Ƃ��A�l�ԂƂ������{��Ŏ������Ƃ����Ƃ������Ƃ��A���łɂ悭�m���Ă���B�l�ԂƂ������t���A�l�Ƃ��Ă̈Ӗ��ƂƂ��ɑS�̂̈Ӗ����������Ă���悤�ɁA�������ɑS�̂ł�����A�S�̂������Ɍł�����Ƃ�������悤�������l�ԑ��݂ł���Ƙa�҂͎咣����B���̘a�җϗ��w�ƌĂ��Ɠ��̗ϗ��w�̍\���̑f�̂́A���a�T�N�ɂ͊m�����Ă����ƍl�����Ă���B�����Ȃ�ƁA����܂ʼn�X���l�@�����_�l�Ƃ̌��ˍ����������Ȃ��B���̂悤�Ȋԕ��\���Ƃ���܂Ō��Ă����l�i�\���Ƃ̌��ˍ����ɂ��āA���_���猾���A���҂͏d�ˍ��킳��A���荇�킳��Ă����B�a�җϗ��w�́A�P�Ɋԕ��\���������ꂽ���Ƃɂ��a������̂ł͂Ȃ��A�㔭�̊ԕ��\�����A�攭�̐l�i�\���Ƃ��荇�킳��A�ڂ������Ƃ��ɏ��߂Ēa������B���̐������̂���悤�����Ă����B �a�҂̌ƑS�̂ɂ��Ă̍l�@�A���Ȃ킿�Љ�ɂ��Ă̍l�@���A�}���N�X����̉e���ɂ���Ĉ����N�����ꂽ���Ƃ͂悭�m���Ă���B�u�l�ԁv�u�ԕ��v�̍l���́A���̃}���N�X�ւ̌��y�ɂ����ĕ��シ��B����͏��a�U�N�́u�ϗ��w�v�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B�a�҂́A�}���N�X�����R�Ɛl�ԁA�l�ԂƓ����Ƃm�ɋ�ʂ������Ƃɍő�̏d�v��������B�l�ԂƎ��R����ʂ����̂͂ǂ��ɂ����Ă��B���R�͔F���I�ɔc������邪�A�l�Ԃ͎��H�I�E�����I�ɔc�������B�l�Ԃ����H�I�E�����I���ʂ�����߂��邱�Ƃ������}���N�X�̈Ӑ}�ł������B�}���N�X�ɂƂ��Đl�Ԃ̎��H�I�E�����I���ʂƂ͐��������Y���邱�Ƃɂ������B���Y�Ƃ́A���������l�Ԃ��A���̐l�ԂƂ̊W�̒��ɂ��邱�Ƃ�O��Ƃ���B�܂�A���������Y����l�ԂƂ́A���炩���߂��łɎЉ�I���݂ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���Ƙa�҂͉��߂���B���̂悤�ɁA�}���N�X���l�Ԃ̓����𑼂Ƃ́u��ʁv�ɂ����Č��o���A�����I�ȏ���l�@���n�߂Ă��邱�Ƃ��d������B���������A���łɐl�Ԃ��u��ʁv�ɂ����āA�܂�A�u�W�v�ɂ����Ă���_���������āA�a�҂́u�W�v���u�ԕ��v�Ɩ̂ł���B�Ƃ͂����A�a�҂̓}���N�X��S�ʓI�ɍm�肵�����̂ł͂Ȃ������B�a�҂ɂ��A�}���N�X��Material�ƌĂԋ�̓I�ȎЉ�݁A�l�ԑ��݂ɂ����ẮA�o�ϖ��Ɨϗ����Ƃ̗��ʂ�����B�}���N�X�͂��̕Жʂ̌o�ϖ�肵����舵���Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�o�ϕ��͂̂��Ƃŗϗ����f�����킹�čs���Ă���A���ꂪ�����������A�܂��}���N�X�̌��ׂ������ɂ���Ƃ���B�܂�A�}���N�X���Љ���̗��j�I���H�I���i���������Ȃ�����A���̌�������ӎu�ⓖ�ׂ�ߏo�����Ƃ������Ƃ��A�}���N�X�̊Ջp�����d��Ȗ��ł���Ǝw�E����B�}���N�X�����݂ɂ��ĉs���l�@���Ȃ�����A���ׂ���ɂ��Ȃ��������̂��Ƃ��}���N�X�̌��ׂȂ̂ł���B���������}���N�X�̌��ׂƂ��Ď����ꂽ����悤�A���Ȃ킿�u���݁v�Ɓu���ׁv�̗��������͂����ׂ��ł���Ƃ������Ƃ������A�O�q�����l�i�\���Ɗԕ��\���Ƃ̂��荇�킹�Ɍq�����Ă䂭�B�a�҂́A�w�l�Ԃ̊w�Ƃ��Ă̗ϗ��w�x�ɂ����āA�u���݁v�̖��Ƃ́A�q�̓I�ȑ��݂������ɐ��������邩�̖��ł���Ƃ����B����̓n�C�f�b�K�[�̉e�������u�l�i�Ɛl�ސ��v�������p�����̂ƌ�����B���̂悤�Ɂu���݁v�̂ق������ɂ����ẮA�l�i�\������̕��͂������p�����B����A�u���ׁv�̖��Ƃ́A���ׂ̈ӎ��������ɂ��Đ������邩�̖��ł���A����͐l�ԑ��݂̍\���������Ɏ��o�����邩�����ǂ邱�Ƃɂ���ē�������Ƃ����B�l�ԑ��݂̍\���Ƃ́A�ԕ��\�����̂��̂ł���B�܂�A�u���ׁv�̕����ɂ����ẮA�ԕ��\���̕��͂��Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƙa�҂͍l����B���̂悤�ɂ��Ċԕ��\���͐l�i�\���̕��͂ɋ߂Â��A���荇�킳��Ă����B �a�҂́u�ϗ��w�v�ɂ����Đl�i�\���Ɗԕ��\�����肠�킹�����݂�B�܂��A�l�Ԃ̊w�Ƃ́u�l�ԂƂ͉��ł��邩�v��₤���Ƃƒ�`����B�������̖₢�́A�Ȃɂ��́u���́v��₤���ƂƂ͑S���قȂ�Ƃ����B�Ȃ��Ȃ�₤�Ώۂ��l�Ԃł��邩��ł���B�u���́v��₤�Ƃ́A�ʏ�͋q�ςɑ��Ă̔F���ł���B�����A�l�ԂƂ͔F���̎�ςł�����킯������A�q�ς̔F���ɂ����Č��邾���ł́A�^�ɐl�Ԃ������Ă���Ƃ͂����Ȃ��B��ϑ̋q�ςƂ����F���̂���悤���A��ϑ̎�ς̂���悤�ւƕϗe�����Ȃ���ΐl�Ԃ��������ƂɂȂ�Ȃ��B�����ł́A�u���́v�Ɓu���Ɓv�̋敪�Ɂu�l�i�Ɛl�ސ��v�ɂ�����l�i�Ɛl�ސ��̋敪����肩����s�_�̑O��ƂȂ��Ă���B�u���Ɓv���l�ސ������z�_�I�l�i���ɂ���āA�u���́v���l�i�������S���w�I�l�i����F������舵���Ƃ����ʏ�̔F���̐}����ϗe�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l�Ԃ�₤�Ƃ������Ƃɂ����ċ��߂���̂́A�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ����}������b�ɂ��āA�����ɂ�����u���́v�̈ʒu�Ɂu���Ɓv�������邱�Ƃł������Ƃ�����B�����A�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ����}���ɂ����ĕϗe�����̂́u���́v�����ł͂Ȃ��B�l�Ԃ�₤���ƂƂ́A�����₤�u���Ɓv���́A�u���Ɓv�����z�_�I�l�i�����̂̕ϗe�������炷�Ƃ����B�a�҂́u���Ɓv�����z�_�I�l�i�����F������Ƃ������Ƃ��獪����A�u�����Ɍ���B�u���́v�͒P�ɋq�ϓI�ɂ���̂ł͂Ȃ��āA����Ɍ����āu���Ɓv�����z�_�I�l�i�����u���I�Ɍ���Ƃ��������̓��ɁA���Ȃ킿�u�����̂����ɂ͂��߂Ă��肤��B�d�v�Ȃ̂́A�u���́v������̂ł͂Ȃ��l�Ԃ����悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A���̎u�������ϗe����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�u���́v�����鎞�ɂ́A���邱�Ƃ͂��́u���́v����͌����Ȃ��B�����A�l������Ƃ��ɂ́A���邱�Ƃ����̐l���猩����B�u������������I�ł���̂ɑ��āA�l������ꍇ�ɂ͂��łɑ��ݕ����I�ł���B���̂悤�ɘa�҂́A�u�������ԕ��\���ւƂ��荇�킹��B�������ꂾ���ł́A�ԕ��\���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�ԕ��ɂ����Ă͌���Ƃ������Ƃ���̂����̗l�X�Ȍ��������ƂȂ邩��ł���B�u�����̕ϗe�́A�u�����𑊌ݓI�ɍl����̂ł͂Ȃ��A�ނ��뉽����F������Ƃ������̒P�ꐫ���̂̒��g��c��܂��A�{���I�ɑ��ݓI�ł���悤�Ȍ�����z�肷�邱�ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�����Ŏ咣�����u�����̕ϗe�Ƃ́A�F������u���Ɓv�́A�܂�u���Ɓv�����z�_�I�l�i�����̂́A�P���Ɍ����Ή�̕ϗe���Ȃ����ׂ����Ƃ������Ƃł���B �a�҂̓f�J���g�ȍ~�̎���̍l����ᔻ���A�u�ԕ��v�ɂ���ēN�w�E�v�z�̑g�݊��������݂�̂ł���B�������̑Η��͌�Ő������ꂽ���̂ł��邱�Ƃ͒��ӂ��ׂ����낤�B���Ƃ��Ɗԕ����\�����ł����̂́A�l�i�\���A���Ȃ킿�Ǘ��I��ς̍l���ɂ��u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̍l������A���̗v�f�����ւ��邱�Ƃɂ���Ă����B���̂��荇�킹�A�\�����̂��ƂŁu�ϗ��w�v�������u�ԕ��v�ɂ�鎩��̔ᔻ�����肦���̂ł���B���������l�i�\������ԕ��\���ւ̂��荇�킹�̉ߒ��ɂ́A�������Ɏ���z�_�I�Ɍ����]�������蓾�Ă���B �������A���̂��荇�����̂ɖ�肪����B����́A�l�Ԃ�₤���Ƃ����̎��Ȍ��y�I�Ȑ}���Ƃ��Ď�����Ă���_�ł���B�l�Ԃ�₤���Ƃ͖₤�҂Ɩ����҂Ƃ�̎҂Ƃ���Ƃ����O��̂��Ƃ���ł���A���̈Ӗ��Ŏ��Ȍ��y�I�Ȗ�ł������B���̓��ꐫ�́u�ԕ��v�ɂ���āA���Ȃ킿�₤�҂������҂����łɑS�̐��ɐZ�����ꂽ�ł���Ƃ������Ƃɂ���ĒS�ۂ���Ă���B�₢�����̂́A���̎��Ȍ��y���Ƃ́A�u���́v�Ɓu���Ɓv�ɂ����Ăǂ̂悤�Ȃ��Ƃ���ƂȂ������Ƃ������Ƃł���B�a�҂͈ȑO�u���{��ƓN�w�̖��v�ɂ����ē��{��ɉ����Ắu���́i���j�v���u���Ɓv���u���́i�ҁj�v�Ƃ����֘A���\�������Ă���ƕ��͂��Ă����B�����āu�ϗ��w�v�ɂ����Đl�Ԃ�₤���ƂƂ��čs�������Ȍ��y�I�Ȃ��荇�킹�Ƃ́A���́u���́i���j�v�����S�Ɂu���́i�ҁj�v�ւƓ���ւ����Ƃ������B���̓���ւ��ɂ���ē�����̂́A�u���́i�ҁj�v���u���Ɓv���u���́i�ҁj�v�Ƃ����}���ł���A��ϑ̎�ς��W�������\���͂����ɐ��荞�܂��B�����A�����Ȃ���Ζ��ƂȂ�̂́A��ϑΎ�ς��W���������S���u���́i�ҁj�v�Ɓu���́i�ҁj�v�ɋ��܂�Ă���u���Ɓv�ւƎ��ʂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ��B�܂�A�l�Ԃ�₤���Ƃ͎�ϑ̎�ς̂������́u���Ɓv���ǂ̂悤�ɔc�����邩�Ƃ����₢�ւƎ��ʂ��Ă����̂��B�����Łu���Ɓv�ɑ�����Ă���͎̂O�̑��ʂł������B���Ȃ킿�A���ɂӂ�܂���ԓx�A���ɂ����ɂ��邱�ƁA��O�Ɂu���v�Ƃ��Ď��ȗ��𐫂��������Ƃł���B�����́u���Ɓv�̑��ʂ́A���ߊw�̑̌����\���������̃g���I�ƑΉ����Ă���B�ԕ��\���������Ȍ��y�����O�ꂳ���ƁA�����̃g���I�͈��k�����B�܂�A���炪�����₤���Ƃ́A�ӂ�܂���ԓx���A�����ɂ��邱�Ƃ��A�u���v�Ƃ��Ď��ȗ������������Ƃ��A���ׂĎ���̔��e�ƂȂ�A���k����A�������Ă��܂��Ƃ������Ƃ��B��������͖��炩�Ɏ���̂����ւ̎��ł���B���Ȍ��y���ɂ�鈳�k�́A�̌����\���������̃g���I���瑼�ւ̌_�@��U�藎���Ă��܂��A��������S�ȃ��m���[�O���Ă��܂��B���������̌����\���������́A���ꂪ�킽���ł͂Ȃ��N���̑̌��E�\���E�����ł��邱�Ƃɂ���āA����ɂ́A�����킽���ł���܂�ŕʐl�ł��邩�̂悤�ȑ̌��E�\���E���������邱�Ƃɂ���ď��߂āA���قݏo��������z��������ɕʗl�̍��قւƕϗe���āA�g���I���̂��̂������ɗ͓����g�債�Ă����Ƃ������Ƃ����蓾���B�������A�a�҂ɂ͂��̓_���������Ă����B���̌����́A�̌����\���������̏z�����Ȍ��y�I�Ɉ��k�������̓��R�̋A���ł������Ƃ�����B �u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ��K���ɗZ�������l�ԑ��݂�����킻���Ƃ���u�ϗ��w�v�̂��킾�ẮA�������A�u���Ɓv����������̈�݂̂��������A�ӂ����сu���́v���Ђ��͂�����Ă��܂����ʂƂȂ����B����͋��������A���킾�Ă̗��Y�ł���A�u�ϗ��w�v�͂��̂��Ƃɂ���āA�\�߉�����r���Đ��܂�ė����̂ł͂Ȃ��������B�r��ꂽ�����Ƃ́A�����炩�ɂ����ނ́u���Ƃv�ł���B����͂��Ƃ��A�s�����Ă��鎩�����g�����̍s���̈Ӗ������ʂ����炸�ɐ��E�ɑΛ�����Ƃ��̂��̐g�k������悤�ȋ����Ƌ��|�ƁA�����ē����Ɋ����鎩��̊�ȗ�O���ɂӂ�Ă��邱�ƂA���邢�́A���̂ɐG��Ă��̗₽�������Ɋ����鎞�̈��������ƈؕ|�ƁA��Âł���Ȃ������Ŏv�l����~���Ă��܂��悤�Ȋ��o�Ƃ����݂ɂ��邢�͓����ɉ����Ă����ʂɐG��Ă���悤�Ȃ��Ƃł���B�l�ԑ��݂͂��Ƃɂ���Č��s������Ă���̂ł���A�܂����s�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����u�ϗ��w�v�̍\�z���炷��A���R�ɂ���������ʂւ̂��Ƃ��������グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A�a�҂́u�ϗ��w�v�͂���������ʂG��邱�Ƃ��������グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����͂����̏�ʂ��A�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃ̋敪��ʂ��A�u���́v�Ɓu���Ɓv�Ƃɋ敪�����̂Ƃ͕ʂ̂���悤�ɐG��Ă��܂��Ă����ʂ�����ł���B�����������̏�ʂɂ͂����ẮA�G��Ă��鑊����l�ԑ��݂̔��e�ɂ��邩�ǂ���������肩�łȂ��̂ł���B ����A�������̂͂��Ȃ�ׂ��ȃ����ɂȂ����̂ŁA�ǂ݂ɂ������̂ɂȂ����Ǝv���܂��B�ǂ݂ɂ����Ǝv������A�{����̖{���ƎQ�Ƃ��Ȃ���A��������ǂݐi�߂邱�Ƃ������߂��܂��B�ǂ݂ɂ����{�ł����A�������ĕ���ɂ����{�ł͂���܂���B���҂̕��͂⏖�q�����k�Ȃ̂ŁA������ƒǂ������Ă����Ȃ��Ǝ~�܂��Ă��܂��̂ŁA�~�܂��Ă��܂���������Ԃ��ēǂݒ����Ȃǂ��Ă��������Ǝv���܂��B���̏ꍇ�́A�ŏ��A�����������{�ł��Ȃ������̂ŁA�C�y�ɓǂݎn�߂܂������A���̎������ɁA�p���𐳂��ēǂݕԂ��܂������A���܂̂Ƃ���ǂ�������̂�����Ƃł��B�Ƃ��ɁA�ŏ��̑��q��r�����������Ō�̍Ō�̌��_�ɏo�Ă���Ƃ����悤�Ȓ��҂̉���ȍ\���ɁA���Ă�����Ă��܂���B�������A���̒��g�͘a�җϗ��w�S�ʂ�c�q����̂ł͂Ȃ��A�a�җϗ��w�̑ΏۂƂȂ��Ă���l�ԂƂ������̂̑������ɏœ_���i���Đi�߂Ă��܂��B�����Ƃ������z�ł����A���ʂ̐�������܂��A�u�l�i����ԕ��ցv�Ƃ����T�u�^�C�g���̊��ɂ́A���e�̑唼�͐l�i�ɂ��Ă̕��͂ł���A�ԕ��ɂ��Ă̌��y�͍Ō�ɋ߂��Ȃ����Ƃ���ł悤�₭�A�Ƃ������ł����B�������ɁA�l�i�̑������ɂ����Ċԕ��̎��_���`���z���Ƃ͊_�Ԍ����܂������A������a�җϗ��w���l�i����ԕ��ւƐi��ł����v���Z�X�A���邢�͊ԕ��Ƃ������_����A�l�i��k���Č���Ƃ������͂������ƌ����������Ǝv���܂��B�����Ȃ�ƁA���̔{�̌������K�v�ɂȂ�ł��傤����ǁB���̂��ߏI�Ղ͋삯���̈�ۂ������A���_�Ƃ���ɑ��钘�҂̈ӌ���������ƕ����Ă��邵�܂��Ă���悤�ł��B���҂��Ō�ɂ����r��ꂽ���t�̂��Ƃ��A���˂Ȉ�ۂ������A���܂��������͂Ɍ�����悤�Ɏv���܂��B�Ⴆ�A�ł́A�a�҂͂ǂ��œ���������̂��A�Ƃ��������Ƃ܂Ō���Ȃ��Ă��A�����܂ł�����̂�����A�����܂œ˂�����ė~���������Ɗ����܂����B����́A�ǂސl�������Ȃ�ɂ���ĉ������Ƃ������Ƃł��傤���B |
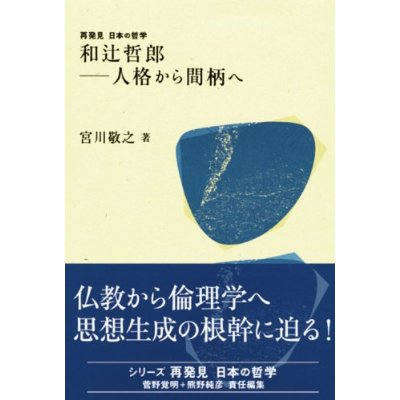 �T�D���炩���ߑr��ꂽ���ǂ���
�T�D���炩���ߑr��ꂽ���ǂ���