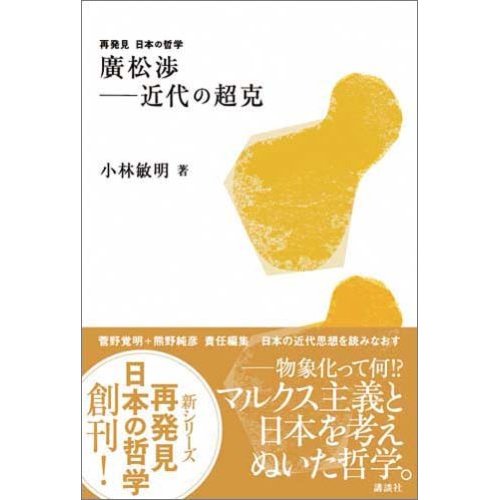
まず、廣松らが乗り越えようとした「近代」とは何かを問うことから始める。日本では単線の時代区分が自明に為されているが、欧州ではそうではない。そこで、「近代」を単なる単線的な時間系列の上に位置する便宜的な一歴史区分とみなすに終わらないで、ある共通の発想パターン、科学史家などのいう「パラダイム」をもったひとつのエポックとして捉えて見る方がいいと著者は言います。そこでしばらくは、概略的に「近代」の代表的なメルクマールを検討していきます。 まず「近代」を成立させた具体的条件として重要なのが産業資本主義の社会です。この産業資本主義の特徴は商品経済ないし貨幣経済が一般に流布し、その結果人間の労働までが「商品」となることがあげられます。商品となった労働は貨幣と同じように計算され、文字通りその貨幣と直接交換されるようになるのがそうです。これは、本来それぞれに性格や質を異にする労働がさしあたりその固有の質を度外視されて、「量」としてのみ扱われる。これを可能であるかのように(イデオロギー)が出てきて、労働はそれがかかった時間量で量られうることになります。この背景には、その尺度となる時間が比較計量可能なものであるという一般抽象的な考えが前提されているわけです。『資本論』の「抽象的人間労働」とはそういう意味です。 こうしたシステムが成立可能となったのは、同一の人間が一方で家族や共同体に所属しながらも、他方でそうした紐帯から分離した「自立的個人」と機能し共同体とは別の次元にある仕事を引き受けることができるということです。この自立した個人どうしが作り上げる社会、一般に「市民社会」、は旧来の共同体的人間関係を前提にしない独自の論理や倫理に従います。一方、生産関係が資本利潤の追求に向かう「資本─賃労働」の関係は、相互に対等な関係ではない。それは、賃労働者は自らの労働力の他には生産手段を持たず、資本の側から提供される生産手段を借用しながら自分の労働を提供しなければなりません。賃労働者は、もはや土地も機械も道具も持たない「無産者」となってしまっているためです。そのような人間は旧来の共同体から出てしまった人間であり、それにともない「都市化」が進んだと言えます。こうした経済上の社会変化と平行して、「ネーション・ステート」と呼ばれる国民国家の成立という重要な変化が起こりました。 このような経済社会の変化は、人々の考え方やメンタリティにも大きな変化を与えました。それは近代合理主義の登場です。とくに資本主義ないし産業社会との関連で合理主義に注目したのが、マックス・ヴェーバーです。簿記をもとに営まれる合理的な産業経営は、直接自然科学からもたらされたものではなく、むしろピューリタニズムの禁欲的倫理から出てきたものだ分析して見せました。その端的な例が、「天職beruf」の概念です。もともとは「神からの召命」を意味するギリシャ語のクレーシスをルターがドイツ語のberufに翻訳したときに意味が変容し、ちょうど「労働」を社会原理とする新しい時代を先取りすることになり、カルヴァン派がその転換を実質的に進めたものです。ウェーバーはさらに合理主義が近代的パラダイムの中で広がり「官僚化」が進むことを認識していました。つまり、労働者の管理を合理的に管理する、ひいては住民そのものの管理まで波及する。それは、広く社会的行為が創造的エネルギーを失って「凝固」したときに生ずる現象です。それがさらに進んで、人々を隷属させる容器ともなってしまう。これは後に「制度化」「物象化」という問題になっていきます。どうしてそのようなことが起こるのか。それは、世界観、社会観、国家観そして人間観を考えるときの発想モデルとして、近代に入る前は「有機体」がモデルとなっていたのに対して、近代では「機械」のイメージが支配的になっていきます。さらに「機械」は、効率を求めて絶え間なく改良を加えられたり、新機軸が発明されたりします。ここから現れてくるのが「進歩」という発想です。 最後に哲学や思想に与えた影響について考えてみます。産業社会が旧来の共同体から分離した「自立的個人」を多数生み出していったことにより、哲学的にも「個人」という概念が重要な意味を帯びてきます。これに伴い、ギリシャ語のヒュポケイメノン「基体」概念が「実体」と訳され、当初、神と同一視されていたものが、デカルトになると精神と物体も実体とみなすなど、概念が変容してきます。これに乗じて精神と物体はそれぞれ独立した別々の世界を為し、それぞれが主体と客体の関係に重ね合わされ、主体の支配下に置いたということです。その結果、人間が主体と客体の関係を取りまとめるような特別の存在となってくるのです。 廣松の思想は基本的に「マルクス主義」とともに始まり、その基本姿勢は終始変わることはありませんでした。廣松 は1960年代後半の当時の流行であった疎外論を批判します。疎外論とは、現代の人間は機械やシステムの歯車として自主的な主体性を失った存在に成り下がってしまっている、だから、今こそその失われた人間性を取り戻さなければならないという議論です。これは『経済学哲学草稿』が遅まきながら出版され脚光を浴びたことにより現われてきたものです。これに対して、廣松は疎外という議論が成立するためには、まず主体としての人間がいて、それが労働という行為を通して自分の本質を対象に外化するというプロセスが前提となっています。これは、マルクス主義が克服したとされるヘーゲルの理論装置そのもので、実は疎外論を支えているのは近代的ブルジョア・イデオロギー以外の何ものでもないというのが廣松の批判です。廣松によれば、マルクスは自己批判的にそうした発想を超えていくところに思想上の転換点があるといいます。その契機となったのが『ドイツ・イデオロギー』にあると言います。廣松によれば、ここでは人間は初めからアプリオリに「主体」として存在するものとは捉えられておらず、「社会的関係」としての人間をとらえているのです。ここでの「個体」は論議の出発点ではなく、反対に関係的行為ないと行為的連関の所産であり、結果と言えます。ここでは「実践」という概念が人間存在のベースをなす哲学的行為概念にまで鋳造し直されています。この『ドイツ・イデオロギー』はマルクス主義思想の真の出発点があると廣松はみなしているように考えられます。では、廣松はこのような新たな発想を実際にマルクスのどのような議論に見出し、近代を超える内実があるとみなしたのでしょうか。この意味で重要なのが「物象化」という概念です。発端は『資本論』に出てくる「物化」という言葉です。商品が労働の産物であることは、当時の経済学の常識でした。しかし、その商品の価値は他の商品と交換される際の「交換価値」がそうです。それは食べられるとか、見て楽しむなどという直接消費者の欲求に奉仕する使用価値とは全く異次元のところに成立する価値なのです。それでは、それまでの経済学の常識であった人間の労働が価値の源泉というのは、フィクションにすぎない。これは、逆の方向で考えて見れば、一人の人間が汗水たらして作った米を売って得た金額と、別の人間がわずか数分の電話取引で得た株売買の利益との間に、理不尽なほどの差が生ずることは、「価値」が決して単純な人間の労働量などで決まっているのではないことは明白です。一個の人間の主体的行為としての労働ではなく、はじめからシステムという関係の網の目に組み込まれた人間たちの総労働から逆算して個々の労働の価値が決められている。マルクスは、これが取り違えられて、あたかも「抽象的労働」が「凝結」するように見えてくると言います。これが物象化です。 廣松は『資本論』の再解釈を通じて得られた商品の価値的性格を他の価値一般にまで広げていきます。経済的価値を超えて、あらゆる文化的社会的価値は多かれ少なかれ「感性的・超感性的」の二重性格を帯びているのです。これを認識論の場面に適用してみせたのが、初期の主著『世界の共同主観的存在構造』です。われわれは一般に物事をそのまま知覚し、認識していると思い込んでいるふしがあるけれど、よく見てみると、そこに二重構造がある。例えばいま聞こえている音はたしかに物理的に発せられた音、その意味で感性的に近くされたものには違いないが、普通にはそれを自動車のクラクションの音「として」聞いている。つまり、そこには初めから何らかの「意味付け」が働いている。このような文化的社会的に与えられた意味は明らかに感性的次元に成立するものではなく、そもそも「意味」という存在自体が超感性的といえる。廣松は、このような認識される側の二重構造とは別に、知覚認識する側の二重構造を持ち出してくるのです。われわれがふだん、物事を見たり聞いたりする時に、その都度異なった「誰々として」立ち現われていると言います。これは言い換えれば、認識の実践化、行為論化とでも呼ぶべきものです。その都度の状況を超越して初めから「主観」なるものが存在しているわけではなく、主観はむしろその認識というひとつの「行為」が置かれる、その都度の状況ごとに規定されるものと考えられます。こうした対象面と主体面のそれぞれの二重性から入れ子型の四肢構造なるものが導き出されます。これが最も見易い形で現われるのが言語ないし言語認識の場面です。さらには相対性理論解釈にもこれか広がります。これらの議論を踏まえた廣松の「唯物論」は「物」を動態的な関係や函数の所産として捉えるものとなるのです。 廣松の認識存在論とも言うべき四肢構造論は、社会的行為論にまで進みます。認識論は主に「者と物」の関係を取り上げましたが「者と者」の関係はたんに認識にとどまらず、相互の行為となることが普通だからです。ここでは認識論と実践行為論がつながっていると言えます。例えば、今、通りを歩いていて目の前に怪我をして助けを求めている他者に遭遇したとします。私はこの助けを求める「当事他者」の期待に応えなければならないような状況に置かれています。つまり、私の行為はさしあたりこの期待の理解とそれへの呼応として発生します。そして、他の通行人たちは「環視的第三者」として私におおいかぶさってきます。私はこの人たちの期待にも応えなければならない。仮に誰もいなくても私自身の良心の呵責ということもあります。ここには「ひと」という見えない抽象的な匿名の他者が顔を出してくるのです。このように、われわれはその都度に応じて何らかの役割を演じながら日常生活を営んでいると廣松は言います。私の自己同一性はされらの役割群の束として保たれているのです。さらに役割とはその都度の状況に応じて発生するものですが、これに他者の反応を呼び起こすという「他者」との「共軛」関係において成り立つものです。しかし、問題はその後です。廣松にとって役割とは本来的にその都度の状況に制約された行動ですが、類似の状況が繰り返されるとルーティン化が起こり、さらにはルール化されと、その裏面としてルールに従わない場合のサンクション(罰)が生じます。まさに役割の物象化です。こうした態勢ができると、こんどは役割の「脱人化」が起こる。つまり、大工さんは人が替っても大工さんです。つまり地位の既成化です。こうして役割や地位が協働連関の度合いを増すと一定のまとまりをもった「機構」を形成するまでに至ります。この機構がひとり歩きをし始めると、人を拘束するような転倒した事態が生じるわけです。
さて、ここからが本題に入ります。『〈近代の超克〉論』を足掛かりにして、廣松を日本近現代思想史の流れの中に位置づけるというのが、筆者の意図です。 日本思想との直接的対決はほとんどない中で、この著作は異彩を放っていると言えます。あえてその廣松が取り上げたのは、近代の超克というテーマゆえで、そもそも廣松にとってマルクス主義を標榜することは、そのまま資本主義社会及びそれと表裏をなす近代的世界観そのものへの根本的な挑戦であったからだ、と著者はいいます。戦時における近代の超克は「文学界」グループ、「日本浪漫派」そして「京都学派」の三つのグループを中心に展開されました。しかし、廣松は、このうち京都学派に特に目を向けています。廣松の関心は何よりも京都学派のもつ「近代」観にありました。京都学派の歴史観はヘーゲルやランケなどのプロイセン系の歴史観をベースにして、当時の皇国史観とは真っ向から対立していました。この、例えばランケの歴史観の大きな特徴は、古代、中世、近代という時代区分をそれぞれのパラダイムとしてとらえようという態度です。また、高山岩男の「世界史的世界観」はそれまでのヨーロッパ中心主義の枠にはおさまりきれないような多様性が生まれ、これに見合ったヨーロッパ中心ではない歴史観がひつようになったという認識です。高山によれば、このような歴史は、マルクス主義のような経済的下部構造ではなく、「文化」、一定の類型を備えた民族文化、が機動力となって動かされていることになります。そこにも世界史的世界を支える多元性の根拠があり、また「世界史の哲学」「哲学的人間学」と結ぶ理由がある。このような基本的歴史認識の上に立って、彼らは同時代を「近代」、しかも内的な爛熟を経て今や衰退の危機に直面している近代とみなします。 では、廣松はというと、このような京都学派に対する容赦ない批判は『〈近代の超克〉論』の中で一貫して行われていますが、どこかで京都学派に対する敬意が感じられるのも確かだと著者は言います。その理由は、廣松が京都学派の近代観をそれなりに認めたうえで、その「超克」の仕方において彼らとの決定的な決別点を見出すという姿勢をとっているためです。 明治以降の近代思想史を考える上で重要な問題のひとつは、日本は既に近代化されているのか、それとも未だ近代以前なのかという現状認識の問題です。『〈近代の超克〉論』の中の議論をみれば、廣松は日本が近代化されているか否かにかかわらず、すでにわれわれが「世界史の時代に生きる」かぎり、近代の超克はどこから出てきてもよいと考えていると考えられます。つまり、「外来思想の単なる翻訳紹介に終始することなく」自分の頭で近代という巨大なパダイムに立ち向かおうとした、その姿勢において廣松は京都学派に共感を覚えているようだ著者は言います。廣松にとって重要なことは、日本の近代化云々ではなく、世界をグローバルに見れば、近代は明確な姿を現し、すでにその限界さえも示しており、とこからであれ、根本的克服の道を探らねばならない時期にきているということです。つまり、近代を限界をもったひとつのパラダイムとして捉えているということです。 廣松と比較する意味で、近代の超克に対してもっとも厳しい批判を行った戦後民主主義良識派を見ていきます。ここでは、その代表者の一人として丸山真男の「近代」観を見ていきます。丸山にとって、日本は近代を獲得していないといいますが、彼のいう「近代」とは、西洋近代とも違います。それは、ヨーロッパとか出生の地の特殊性に還元することのできない普遍的理念としての「近代」で、地球上のどこかですでに存在しているような既存の体制や制度ではなく、今ある現実を不断に改良することを通して目指される目標となります。具体的に当時の政治に見られる基本的な動向として、丸山が1953年の講演で述べているのは、テクノロジーの飛躍的発達、大衆の勃興、アジアの覚醒という三点です。これは廣松や京都学派の近代観とかなり重なり合う、これには、丸山の思想形成にヘーゲル主義の強いバイアスがかかっているためだと筆者は言います。しかし、丸山は三点を「それ自体は必ずしも価値を内包していない」「社会的現実」として捉えています。これは京都学派や廣松では考えられないことで、彼らにとっては丸山の言う「社会的現実」は丸山が言うようなイデオロギーから自由な代物などではなく、むしろ近代イデオロギーと直結した現象だからです。丸山の、イデオロギーから自由な「社会的現実」から出発して、それをコントロールするイデオロギーを求めるというのは、彼がリアル・ポリティクスから離れていないことを意味しています。丸山の認識において「近代」は閉じたパラダイムではなく、あくまでイデオロギーから自由な「開かれたシステム」ないし「未完のプロジェクト」なのです。だから、まとまった全体として対象化されることはない。京都学派からみれば、それは近代の内部に取り込まれることを意味するけれど、「開かれたシステム」であるならば、そもそも内部など成立しなくなる。丸山のような近代主義者は、このような「社会的現実」を与件として、その都度現実的問題を克服しながら、そこに何らかのバランスを見出していくということになります。だから、実際には資本主義の体制を全面的に批判し、転覆させるという発想は出て来ることはなく、資本主義がその都度発生させる問題や矛盾を、ひとつひとつ克服しながら、その資本主義に不断の修正改良を加えていくというものです。
ここで、近代の超克の議論に戻ることにします。この「超克」とは超えることで、そこに超えられるべき「境界」なり「限界」が想定されていなければなりません。超えられるべき地平を備えたものは閉じられたシステムとみなされます。これは、さきの丸山の視点とは正反対で、全体化され、ひとつの対象として捉えられます。これが近代の超克で議論された基本的な「近代」像です。「超克」はその境界を超えて外部に出る、つまりは「近代の彼岸」を求めることを意味します。これは廣松にも共通することで、著者は「体質」の問題といいます。廣松は『〈近代の超克〉論』の中で、近代主義に対する反撥、京都学派に対するアンビヴァレントな態度を明らかにしていますが、このアンビヴァレント(両面)の片面をなす共感について、廣松本人は理論的共通性の中に見出しています。しかし、著者は一歩進めて、このようなことを発想させる土壌があると言います。このような土壌の自覚的な立ち入りは廣松が遠ざけた日本浪漫派に見られます。それは近代をひとつの限界あるシステムとして捉え、そこからの脱出を図るということです。そして、この基本姿勢を背景的原因に著者は斬り込もうとします。その手掛りとして、ドイツでは近代化に遅れたところで反近代の風潮が生まれて来るということから、近代化の遅れという条件は「近代の超克」という発想を生み出す土壌にもなりうると著者は言います。「遅れて来た」ということは、すでに近代を体現した先行する国や地域を「外部」にモデルとして持っているということです。だから近代は初めから「他者」として立ち現われる。逆にいえば、自らが近代という世界の中にどっぷりと浸かりこんでいたら、それを対象化したり、それを全体として超克するというような発想は生まれてきません。これは、マルクス主義の資本主義批判にも言えることです。近代の超克という議論は、すでに近代が矛盾を露呈し終焉期に向かっていると考えていながら、その発想自身が誕生したのは、まさにこれから近代に向かうところだったということです。ここで、廣松の境遇を考えてみると、「田舎」という日本内部での「遅れ」と、今度は日本自体が抱えた「遅れ」という二重の遅れを体験していたことになります。同じことが総じて地方出身者であった京都学派の近代の超克推進者にも当てはまるのです。遅れの側にある者には、自分たちが破壊ないし解体されるという危機に面している意識があり、近代の側から破壊者が侵入してくるということへの抵抗の意識が生ずるわけです。しかし、その一方で前近代から脱出を図ろうとする彼らには、近代は憧憬の対象でもあるので、そこに反発と憧憬の入り混じったアンビヴェレントな「敵」が生まれることになります。このような廣松や京都学派にとって近代を超克するかぎりは近代の彼岸という問題が生ずるわけですが、この彼岸は実現されていないわけで、必然的にユートピアのような性格を帯びてくることになります。著者は、廣松と京都学派がともに「田舎」という辺境に原点をもっていて、世界をそこから「遠心的」に見ていたという原点遠心的な発想スタイルできわめてよく似ていると言います。 つまり、著者は近代の超克と近代主義は人々が思い込んでいるほど簡単に二つの陣営に分かれてどちらかに腑分けできるような単純なものではなく、一人の思想家の内部においてさえ拮抗し合い、その拮抗の処理においてその思想家の個性を決定しているものと言います。この両者の拮抗関係は当面続くし、この拮抗関係の中からこそ真に鍛えられた思想が生まれると筆者は言います。このような拮抗に値する超克論を提示しえた廣松という思想家の営為があると言います。 最後の結論に向けて、それまでのペースから急に駆け足になったきらいはありますが、先に主体のゆくえとも関連するところがあり、その関連が理解を助けてくれました。としても、結論はいまひとつ分かりにくいもので、著者の廣松にたいするスタンスから、これが精一杯のところだったのではないかということは分かります。断言をするのはここでは形骸化のおそれがあるし、なかなか難しいのは分かりますが、ここまで京都学派と廣松の思想上の相克を追いかけたのだから、では、京都学派と廣松とはどうなのかということを、触れて欲しかった。そうでないと、結局のところ、みんな根っこは一緒というような、まぁまぁ…、というような受け取られ方をされてしまう恐れも感じる。しかし、本書の魅力は、ここに至るまでのプロセスで、当初の著者の意図である廣松の日本思想史に対する位置というのか、思想史上の相克はある程度、このプロセスで見えてくると思う。これを廣松のすべて言説から引き出してくる著者の廣松に対する読み込みに対しては、脱帽するしかない。
|