第1章 生命・人格・象徴 2.「煩悶」青年の精神世界 3.Formの神秘 第2章 古代日本とデモクラシーの発見 1.古代日本との出会い 2.デモクラシーの再現 3.文明を超えて 第3章 倫理学と政治 1.倫理学体系の形成 (1)人格より人間へ (2)見出された〈日本〉 (3)「人間の学」と時代情勢 2.和辻倫理学の構造 3.戦時体制と「思慮の政治」 終章 光と闇 感想 序章「土下座」をめぐって 本書の課題を著者は、次の点として挙げている。第一の課題として、その原点の一つである和辻哲郎に即して、<日本的なるもの>の生成過程を跡づけようとする。従来の<日本的なるもの>を語る言説が時々の状況で行ってきた問題提起も、それなりの意義を持つはもちろんだが、それが自明視してきた思考枠組みをいったん離れて歴史に切り込むことを通じて、見過ごされてきた様々な問題を星起こしてゆこうというのである。次の課題の台には、和辻哲郎の思想を同時代の思想状況・政治状況の文脈に置いてとらえながら、それが抱えていた問題を再考察することにある。 本書が最終的に目指すのは、和辻哲郎の仕事をたどり、どこに問題があったのか、同時代の言説状況と対比してどういう意義かあったのかを具体的に解き明かすことである。人間の視点から政治の本質を考え、その向かうべきありようを指定することが極めて困難になった現代社会においても、政治活動の公共性や正当性をめぐる問いかけが消え去るわけではない。むしろさまざまな社会運動や制度改革論議の形を取って生き続けていると言える。現代的な諸条件を踏まえたうえで、人間生活の全体に政治をどう新たに位置づけ、政治の意味とその限界をいかに確定するかを考えることは、依然として課題であり続けよう。本書は<人間と政治>をめぐる和辻の思考の跡を、その矛盾や欠落を含めて検証しようとする。これは同時に、和辻が身を置いていた問題圏から、現代人がまだ脱け出していないことの確認作業なのである。
第1章 生命・人格・象徴 1.<光>の原風景 しかし、この光の世界を脅かすものとして、死をめぐる問題が登場する人が死ぬということを否応なく思い知らされるいくつかの出来事が、少年和辻を襲っていたこの時代の和辻にとって死は文化の<光>への憧れを絶対的に脅かすものとして立ち現われた。確かにこれまでも村の子に生まれたという現実が、彼の憧憬を常に挫いてきたが、その不満は自分の内面生活を工夫すればいくぶん慰められる。周囲の村の現実は無視して内面で文化的教養に努めていれば、都会と共通の精神共同体に生きていると信じられるものだから。しかし死については条件がまったく異なる。死はすべてを空無に帰し、文化の<光>を浴びて精神共同体に生きる内面生活もその可能性を絶対的に奪われる。イルミネーションの背後に広がる夜間のように、死の黒々とした領域が<光>を常に取り巻いているのである。それは<光>にのみ目をやっている限りは実感せずともすむ。だがいくつかの死は、和辻に闇の領域の存在をまざまざと見せつけたのであった。こうした経験は、往々にして人を宗教に向かわせるものであろう。しかし和辻はすでに<光>の希求者である。超越的なものを指し示す宗教は、人間の世界を越えた領域を感得させることはあっても、真に人間のものである<光>をさらに輝かせることはない。いかにすれば、この闇を封じ込め、<光>に満ちた人間の生の領域を確かなものにできるか。もちろん少年時代から突き詰めて問題化していたわけではなく、当初は朧げな不安の形をしか取らせないにせよ。これが和辻の生涯を通じて思想の根底に横たわる主題となっていく。 2.「煩悶」青年の精神世界 そして、第二の傾向として、理想を追求する自己の確実性すらをも懐疑の対象とせずにはやまないような煩悶・虚無の傾向が、彼らを根強く支配していた。社会に対して自己の確立や解放を主張するだけでは満足できず、その自我すらも不確実であることに気付いた以上、懐疑と煩悶に陥らざるを得ない。もはや立身出世を保証する国家秩序と自己を同一化することはおろか、秩序に反抗する自己の確実性に頼ることもできない。青年達は統一的なアイデンティティの喪失と自己分裂に悩むようになる。それがかれらの煩悶である。したがって深刻な神経衰弱が根強い持病となった。そういった不安を振り払うべく、教養を通じての内面向上というスローガンに自らを辛うじて繋ぎ止めていた。しかし、統一した目標を欠く以上、そこで求められる教養の内容も分裂したものとならざるを得ない。当時、美的趣味に関して彼ら青年たちを魅了し、その感性に深く刻印を残したのは、神秘的題材や官能的モチーフに美を見出すヨーロッパの世紀末の美術・文芸であった。デカダンスの頽廃的・享楽的傾向とその美意識が、遠く日本まで同時代に影響を及ぼしていたのである。 3.Formの神秘 象徴は、これ以降、和辻の青年期テクストでよく使用される。和辻は機械的と生命を二項対立的に捉え、物象の背後にある生命、もしくは作者の内面に潜む生命を表現するとき、その現象形態たる現実を微細に分析し部分部分を逐一写し取るやり方では、生命の生き生きとした全一性を破壊してしまい、機械的な死んだ造形しか作れない。これに対して、象徴による表現は、ある一つの物象を選び、それにより生命の有機的の全体を暗示する。一方、リアリズムを批判し、生命を十全に輝かせることを目指すとはいっても、生の根源的な力にひたすら耽溺し、その情調を自由奔放に表現するのではない。その意味でのロマン主義もまた否定対象である。ここでは感情の無形式な表出は排除され、形式を意識的に彫琢すること、すなわちFormの洗練が求められる。和辻のドゥーゼ論はそれをよく示している。このような象徴主義の潮流において、形式の厳密さは、美的価値のみならず一種の倫理的価値も付与される、作品制作にあたってFormを磨き上げることは、自己の霊魂を支配することと等しいからである。こうした象徴主義との出会いが、美的享楽から人格主義への和辻の転回の発端を成したと言える。 もともと、和辻が耽美派に近づいたのは、生の意義を追い求める青年の焦燥をともにし得ると思ったからであった。煩悶から享楽へという道筋がよく現われている。そして、彼らに共犯者の愛着を抱き、親しく交わるようになったが、やがて生の冒険のごとく見えたのは、遊蕩者の気ままな無責任な移り気にすぎなかった。と気づく。そして自らの内にあるSollenを再発見して彼らと決別し、自己を高めることに努めるようになったのである。それは心の内の欲望を抑制し、生まれつき潜在的に備わっている真の自己を発現させること、すなわち人格を高めることと同義である。そして人格が十全に向上したとき、人は利己的に生きることを止め、他者との調和の内に暮らすことができるはずだと和辻は説くようになっていく。 人格主義への転向の後、1913年『ニイチェ研究』を世に問う。ここには人格主義のマニュフェストという側面をもつものであった。それは「権力意志」を中心にニーチェの哲学を体系的に叙述しようとするもので、特徴的なのは、ニーチェとベルグソンの類似が随所で強調され、さらにはニーチェが人格主義・象徴主義者として描かれている点である。和辻はニーチェの「権力意志」を、人間の意識の深層の「根本生命」と説明する。そしてそれは客観。主観の区別を超えた「永久の生成」であり、表象された世界の根底の神秘な現実をなすと説く。藝術家の創作活動は、この流動的な生命を象徴たる作品に結晶させることに他ならない。こうした点でニーチェはベルグソンの先駆者とされ、さらに科学的客観主義を越え内生活を深めた思想家としてメーテルリンクになぞらえられるのである。 つまり、ニーチェによればあらゆる人間の内に宇宙の生命が潜在的に備わっていて、彼の説く貴族と平民、少数者と群衆の違いは、その生命が自由に発現しているかの違い、すなわち権力意志の強度による段階の差にすぎない。和辻はこうまとめた上で、その段階を人格の段階、人格の強弱、霊性の質と言い換えるのである。したがって、ニーチェは人間の内面的生活における価値の尊重を説いた人格主義者ということになる。この人格の向上に努めることによって、利己主義と利他主義をともに超えた、生活の本質の上に立つ新しい道徳が可能になる。ニーチェが旧来の利他主義の道徳を攻撃するのは、決して道徳一般の拒否ではなく、むしろ新たな道徳の提唱であると和辻は考える。優れた少数者や超人として描かれる人間像は、理性的人格ではなくても、生の向上の理想に基づいた道徳的人格なのである。したがって利己主義や快楽主義の主張と重なるものではない。 和辻の人格主義は1915年の『ゼエレン・キエルケゴオル』で確立する。この人格主義は教養主義と必然的に連関する。和辻の場合、その結節点を成すのが象徴に基づく藝術創作論である。自然主義は、人間生活の赤裸々な事実を克明に描こうとし、人の食欲・性欲・名誉欲などを暴き立てる。だがそれは、自然の外形を観察しているに過ぎない。必要なのは、その内奥に潜む生の豊富な活動を把握することである。すなわち、外形を象徴として現れて来る内部の生命を感得することが、藝術創作にはまず必要である。万物の奥底にも、自己の内にも生が息づいている。藝術家の使命は、この内的な生命の光を「象徴」としての作品に形象化することである。この作業を通じて、藝術家自身の人格価値は高まってゆく。したがって藝術の真正なる内容は人格的生命である。鑑賞者の美的感動は、作品の美に理想的な自己の本質を見ることに等しい。偉大な作品の享受を通じて、鑑賞者の人格もまた高められるのである。このような和辻の人格主義、人格を高めて他者との調和にいたるという道筋は、キリスト教のような超越的な神ではなくこの世界に遍満する生命の源泉となっていて、文化作品を媒介とする個人の陶冶の過程を詳述するのみで社会・国家との合一を解くまでは至っていない。そして、和辻は、西洋文化の精髄を本格的に受容し、日本文化を改造することを提唱する。 大正期教養派知識人のコスモポリタニズムをここに見ることができる。西洋の精神文化を吸収し、人格・個性の陶冶に努めることは、そのまま全人類の文化的向上、和辻の言う第2のルネサンスに直結する。しかもそれは、現代的な物質主義に惑わされ世界戦争に狂奔する今の西洋人よりも西洋的になることなのである。彼らが忘れた西洋の偉大な合理的・精神的文化の伝統を、日本に住む知識人が古典の読解を通じて身に着け、新しい生命を吹き込むというものだ。教養派知識人たちは、日本国内にとどまり現実の西洋との接触を欠いたまま、膨大な書物の読破や、画集とレコードによる音楽鑑賞を通じて、すてに西洋の文化の中に生きていたのであった。 しかしこれは、よく見れば奇妙なことで、このような世界の文化の蜜を集める生活をする知識人は日本の全人口のごく一部に過ぎない。日常生活において彼らを取り囲むのは、高尚な教養とは無縁な大衆なのであった。日本人のうちのごく少数が、読書生活にはげみ、世界人を自任して日本文化全体の改造を夢見ていたというのが実情であった。この時期の和辻の文章には衆愚たる大衆を見下す態度が露骨である。 逆に言えば、このような傲慢の裏面には自らが社会の少数者に過ぎないという不安がある。周囲の大衆と教養人たる自分を区別するために、人格の向上は、熱烈に、執拗に追求されなくてはならない。その構図は、自分と周囲の大衆との関係だけでなく、自らの内面においても同様である。かつて享楽と頽廃に魅かれた経験を持ち、そうした邪悪な傾向を自覚しているからこそ、人格を高めよというスローガンは、ますます偏執的な調子を帯びてくる。従って、この努力には終わりがない。人は自己分裂や過剰な欲望に悩む自分を永遠に鞭打ち続け、その苦しみの中で自己の高貴性を確認するのである。「内的緊張」は当時の和辻の常用語であるが、緊張の維持は同時に不安の連続である。この不安定な心境に対して、のどかな桃源郷のイメージを提示し、静かに安らう先をもたらしたのが、古代日本の発見であった。
第2章 古代日本とデモクラシーの発見 1.古代日本との出会い さらに、和辻の想像は、古代人の仏像体験から演劇体験に向かう。このように古代文化にじかに触れた体験が、古い日本についてのイメージを一新させた。無味乾燥なものに見えた古代史は、実は華やかな色彩に満ち、生命感あふれるエキゾティックな世界なのであった。これが和辻の古代日本の発見であった。和辻をまず魅了したのは、古代の仏教信仰が美術・演劇・舞踏を多く手段とし、人を感覚的陶酔に巻き込む点だった。感覚の放埓な開放は、人格主義への展開を経た和辻にとっては否定的対象であったが、古代日本に潜んでいた「ディオニゾス的」性格の発見は、従来抱いていた日本歴史像との違いの大きさのせいもあって、心の奥に抑圧していたかつての耽美的傾向を刺戟し、和辻を魅惑の虜としたのである。しかし、ここで和辻が最も評価するのは、単なる写実を超えて「宇宙人生の間に体得した神秘を、人間の体に具体化」した薬師寺聖観音像の理想美ということになる。すでに確立した人格主義の藝術観が、ここでも貫かれるのである。 和辻の議論は古代藝術の特徴を論ずるだけにとどまらず、このような文化の光こそが大和王権による統一国家成立を可能にしたと説明することになる。和辻にとっては、地方征服に向かう天皇と軍将の甲冑は鮮やかな黄金の光を放つものであった。中国の高度な文化を手にし「金人の如く美しい」輝きを放つ天皇の姿を目にした時、未開人たる地方豪族は驚嘆して畏れおののき、その光にひれふす。和辻の描く古代国家統一の原初的イメージはこのようなものであった。そして、全国統一以前、地方王権の段階でも、邪馬台国や大和王権の王権自がそもそも光を放つ儀式によって成立したと和辻は考える。それが、占い・神がかり・厄除けといった儀式によって、神の命令を伝え、あるいは神の祟りを防ぐ祭司の姿が、その神秘感によって人々を圧倒し、尊敬を集める。これかせ王権の始まりである。このような経過を通じて生まれた祭政一致が政治的支配の原初的形態だと和辻は考える。決して赤裸々な暴力による征服や威嚇が最初にあるのではない。 日本に限らず原始社会では一般に、神を祭る祭司が統治者の役割を兼ねるようになって王権と国家が発生したという考えは、当時にあっては西欧の社会学・人類学からの流れとして、日本史研究において珍しい説ではなくなっていった。しかし和辻の場合は、同じ祭政一致でも、君主が儀式を主宰し、そのきらびやかさで人心を惹きつける側面を強調するのである。儀式における祭器の輝き、進んだ文化の光を通じた国民的信仰の成立によって国民が誕生したと主張する。このようなイメージは、和辻自らがかつて文化の光を渇望しイルミネーションや演劇に陶酔した体験と重なっている。そして仏像や伎楽面を目にした瞬間、古代人も同じ感動を味わったものと直感したのである。 かつては西洋文化一辺倒で日本の古い文化など顧みなかった和辻は、ここで古代日本を賛美するようになったのである。これは、理想的な文化が、実は自らの足元で、祖先たちの手によってかつて開花していたと考えるようになった点のみに着目すれば、日本への回帰とひとまず呼ぶこともできよう。だが、この時期の和辻には、俗に日本回帰と呼ばれるような、時代を超えて持続する日本人の民族的特殊性といったものの存在を認め、それを称揚する姿勢は皆無である。和辻が強調するのは、連綿たる伝統の確認の喜びでなく、むしろ古代人との不連続感なのである。 そして、古代日本文化の性格についても、和辻が指摘するのはその日本的特殊性ではなく、コスモポリタンな色彩なのである。とりわけ、和辻が強調するのは古代の日本とギリシャの共通性である。古代日本にギリシャの影響を見ることから、それだけにとどまらず、そもそも両者は自然環境や心性の点で似ている 2.デモクラシーの再現 和辻は、この中で三つの潮流を批判している。天皇に対する忠君を国民個人の強制しようとする国民道徳論と、君主の神権を力説する古新道及び民本主義を敵視する国体擁護運動である。和辻の戦略は、政府が思想統制に当たって掲げる日本古来の国体の主張に対し、全く異質な古代日本像を提示して、いわば国体論を逆手にとってデモクラシーを擁護することにあった。つまり、すでに古代日本において民本主義の政治が行われ、その理想を綿々と保持してきたからこそ天皇家は日本国の中心として存続できたと説くのである。さらに和辻は、民本主義を国体の継続の理由と位置付けるのである。 しかし、和辻にとってデモクラシーは戦略上の手段ではなく、それ自体推奨されるべきものであった。言論の自由や政治参加の保証を通じて、心と心の交通が円滑となり、初めて政治社会全体の有機的共同が実現される。デモクラシーは、民意を統治に直結させる回路の機能を果たすだけでなく、政治参加を通じて人と人との真の共同を可能にする倫理的意義を持つ。和辻のデモクラシー観は、デモクラティックな制度の保障する動態的な政治過程よりも、そうした制度が実現する共同性に重きを置くものである。そして、国家が個々人を型で束縛するような思想政策は、この観点からも排撃されることになる。それは民衆の奴隷化をもたらすのみで、真の共同の実現を妨げるのである。和辻は、たとえば教育勅語を利用することにより、天皇の絶対化と忠君の名目化による思想統制を批判した。教育勅語の各論部分に見える普遍的なモラルは思想的立場の違いを越えて通用するものであり、「衆議」の尊重は、天皇を含めて政府は勅語の普遍的な道を尊重するとともに、言論の自由を保障する義務があるということになる。和辻は教育勅語を天皇と政府を束縛するものとして取り上げたのである。ここで天皇が普遍的な道を尊重するということは、特定の政治的立場や宗教の味方には立たないことと同義である。こうした議論は、天皇大権を事実上形骸化させ、議会に直結した内閣の指導性を強調する点で、美濃部達吉の天皇機関説と共通する。 このように、和辻が古い日本を取り上げる際、課題としているのは、政府の思想政策や保守的論客が古代日本を説くのを逆手に取り、自らが読み替えた古代日本のイメージによって、現代のデモクラシーをいかに弁証できるかということなのであった。 3.文明を超えて 個人も国家も利欲と享楽に走り、自己拡大欲に支配されて闘争しあい、国内では貧富の差が拡大し、国際世界では弱小なアジア諸国がヨーロッパ列強の餌食となっている。現代の世界をおおっているこうした文明をいかにして超え、理想的な文化に裏付けされた世界を築いてゆくか。これが1920年代の和辻の課題となる。 その対象は国際政治から、植民地の独立と国際平和の確保を主張する。その中で欧米諸国のアジア支配を批判し、このような白禍に対抗できるのは日本しかいないと主張するに至る。ここでの和辻には台湾や朝鮮の事態が眼中に入っていない。これは日露戦争の勝利によって日本が白禍を初めて食い止めた事実に対する賞賛の念からである。しかも、これはアナトール・フランスの『白き石の上にて』に触発されたもので、西欧人自身の自己批判と日本評価に出会ったのだった。日本人としてのりナショナリズムの心情から出発して日露戦争を評価しているのではなく、人類の立場からして、植民地支配を撃退した日露戦争は重大な意義を持つ、しかもそのことが西欧人自身の自己批判によって論証されていた。これは、後年支配勢力である英米への不信と、日本の任務に対する自負とが、日中戦争や太平洋戦争に対する支持への和辻を導くことになる。 そして、和辻は日本国内の政治や社会にも現代文明の堕落傾向を見た。一部の富裕者層によって選出された議員が党利党略によって政治を左右し、思想政策については従来の言論統制と忠君道徳注入を踏襲している現実は、和辻のデモクラシーの理想とは徹底的に相容れず、政党政治家にたいする不信の念を強めていく。従って、これ以後の和辻の政治論の第一の重点は、思想政策批判から、特権階級の改造、すなわち、普通選挙制と社会政策の実行へと移っていく。このような政治参加と生存保障の平等化とそれを政策として進める内閣のリーダーシップは強調されるが、政党は顧みられなくなっていく。それは、理想を実現する政治家のあり方として、「日本文化史」の中で、和辻は民の生存を保障する道徳的理想に基づき、全体的な見通しを持って一国の政治を担う大臣を哲人政治家の理想と説く。さらに、支配と統率の区別を説く。支配は兵力や経済的実力によって民を統制することであり、統率は民の福祉要求を実現して指導者としての信頼を集めることである。統率が十分に行われ、民の生存が保障されていて、初めて権威が生まれる。従って支配は統率の要素を含まない限り正当化されえないと主張した。現代においても大臣(内閣)のリーダーシップを通じてこそ改造が実現できるというのが和辻のメッセージだ。 さらに政治が実現すべき道の内容が人々の生存の保障に具体化されるのに応じて、天皇についての力点も移動させていく。天皇が道の理想を体現し政治家はそれを実現する義務があると強調する。これは代々の天皇が個人的信条としての道を信じていることではなく、天皇という位が、政治的理想を代表し象徴する。和辻は青年時代から生命を具体的に表す媒介として考え愛用してきた象徴の概念を使い、国民の生存を保障する理想の実行を政治家に迫る点を強調しているのである。したがって、統治権を代行する政治家は天皇からの委任という形式を踏む限り、この理想の実現に努めなくてはならない。天皇の存在は統治活動の権威にかかわり、天皇位の体現する理念を実行する限りで、政治家による支配は、正当的な統率たりえる。しかし、このように道を説いても、デモクラシーとの関係がもんだいになるはずだ。しかし、それは和辻の考慮の外にあった。デモクラシーは必然的に道の実現に結びつくものと考えられていた。 このような和辻のデモクラシー観はサミュエル・ブッチャーの『ギリシャ精神の諸相』に由来するもので、そこでは、人々は利己的な自己を捨て、真の自己を顕現させて他者との調和に生きる。政治参加の討論の過程においてロゴス=理性が輝きだし、全体の有機体的調和を生み出すのである。これは人間の調和的本性を前提に、デモクラシーが共同性を実現する側面を極めて強調したものと言えるが、和辻の人格主義の発想には極めて適合的なのであった。この人格主義の立場が理論的基礎としたのが、テオドール・リップスの『倫理学の根本問題』であった。リップスの倫理学説は心理学をすべての基礎に置く立場に基づいてカントの学説を継承したものであった。つまり、行為が正しい行為となるための字用件は、その際の客観的な道徳法則に自己の意志を従わせることであり、それは同時に自己の本性に従うことを意味するというカントの立場が踏襲されるが、その際に意志が道徳法則に従うようになるためには、それを表象するだけでは不十分で、道徳法則に対する尊敬の感情が必要である。ここまではカントも説いていることであるが、リップスこの動機づけに関して独自の心理主義的な基礎づけを行う。まず、道徳法則は人の道徳的本性の表現であり、道徳的人格の本質なのだから、道徳法則に対する尊敬は道徳的人格に対する尊敬のことであるとする。このようにリップスはカントにもまして人格を強調し、自分だけでなく他人の人格を高めることに重点を置く。その意味で人格的価値が最高の価値であるという。こうした尊敬感情を基礎づけるのが感情移入の心理作用である。すなわち、他人の喜びや悲しみに同情する作用が人間の本性に備わっている。つまり、他人の表情の外的変化を見て、その知覚像に自己の心的体験を投射することから同情が生ずる。従って他我のむ存在を知ることには、自己の二重化によるものに他ならない。このことによって、行為が道徳法則に合致しているかどうかを本人の自己判断に委ねざるを得ないという主観主義の問題を回避できることになる。しかし、ここで注目すべきは、自律道徳の峻厳さ和らげ、人と人との関係の理想的な在り方をきわめて融和的なものに描いていることである。これは、融和的な共同性に基づいたデモクラシーの理想像を見る和辻の考え方に適合的である。
第3章 倫理学と政治 1.倫理学体系の形成 1934年の『人間の学としての倫理学』、1937年の『倫理学』などで表明された和辻の倫理学体系の基本的特徴は、従来の人格の立場の根本否定として、独自の意味を帯びた人間の立場への移行がなされている。これまで、見てきたような人格主義から人間への移行はどのように行われたのか。 実は、1921年の『原始基督教の文化的意義』にも、その兆候が見えたのであった、第一に、かつて追い払ったはずの死の闇が再び和辻の心に付きまとうようになっていったのであった。親しい人の相次ぐ死を通じて次第に醸し出されていったと思われる。いくら教養を積んで人格を高めても、人を死の不安から免れさせることはできない。人格・生命・文化の光の背後にある死の闇は、人格主義をその内奥から脅かすものである。この時期、和辻は一時的に宗教への接近を見せる。それは生死を超える超越的なものへのひそかな思慕となって表れたもの。和辻自身は信仰に対しては両義的な感情を示し続けるが、人格主義を支える自律的個人のイメージは、内側から崩壊の危機にさらされ、超越的なものの影が、その自己完結性を脅かすこととなった。そして、第二に社会生活に存在する型の発見が別方向から和辻の人格主義を揺さぶる。和辻の人格主義の発想において、調和的共存は、個人が教養を身につけて人格を高め、人間本来の融和的性質を発揮することで可能となるものであった。つまり、外からの強制を廃し、内面的な心の修養に努めることが、真の調和を達成するのである。しかし、序章で紹介した土下座はこれを逆転させたものであった。そこでは身体を形に沿わせることが、逆に人の内面に変化をもたらし、他人との心の交通を感得させる。人格主義の立場からすると、これは二重の意味で脅威である。まず、心情さえ謙遜になっていれば、形は必ずしも等に及ばぬとの主張に反して、外面的な形が内面の謙遜な心情を生む以上、かえって内面の方こそ問うに及ばぬということになってしまう。さらに、この形はすぐれた哲学や藝術を学ぶことで培われたものではない。その意味で無教養な村人たちが、村落生活で古くから共有されてきた行為の定型を、ごく手軽になぞっているだけである。したがって教養を通じて人格を高めようという人格主義の主張は深い疑義にさらさられることとなる。現実の社会生活においては、教養などとは無関係なところで、人々の共存を可能にする型がしっかり根付いているのである。この時、和辻に対して、人と人とが交渉しあう領域としての社会が、初めて姿を示した。個々人の意識を超えたところで型を保存し、その行動を規定して集合的一体性を保つ生きた社会に見える表現の発見である。そして第三に、人格主義の限界を決定的に知らしめた事件が和辻を襲った。関東大震災である。震災後数日、余震と火災波及の不安におびえ、日常生活を支えていた電気・通信網の決定的な遮断として和辻に衝撃を与えた。減退生活を支える文明的基盤が消滅した状態に突如放り出され、和辻も流言蛮語に踊らされる。しかし、同時のこのような極限状況の中で人々が見せた行動は「純粋な人間の情緒へ感動」を起こさせるものだった。これは和辻にとっては衝撃的であった。文化を伝える情報伝達網が失われ、教養による人格陶冶とはおよそ無縁に状況下で、人々がごく当たり前に営利を離れ、互いに苦しみを救おうと行動しているのである。では、彼らが純粋な人間の情緒を生み出しえたのは何によってなのか。問題を再び内面的心情に回収することは、文化の遮断を身を以て味わった和辻には、人格の向上が教養と直結していたがゆえに不可能である。人格主義の立場は、ここに破綻を余儀なくされる。人格主義の立場は、死の不安と生きた社会における実践との両面から挟撃され、大震災体験に至って完全に破砕されたのである。 それは和辻にとって、哲学上の理論枠組みの根本転換を迫るものであった。人格主義はデカルト以後の近代西欧哲学が出発点としたコギトの立場を前提とする。すなわち、ただ一人思うものとしての自我が学にとって唯一確実なものであり、この自我が認識主観として客観的な世界を知覚する。これが知の基本構造であるとされていた。和辻の人格主義も、理想世界と現実世界との断絶を強調し、理想世界における他者や自然との調和に憧れる、いわゆるロマン主義的傾向を帯びているものの、その立脚点は外界を観照し感情移入するコギトだった言える。しかし、今や、内面の閉域で文化作品を鑑賞し理性的向上に努めていた自我は、その外部に蠢くものとの関わりを意識せざるをえない。それは、対象世界を知覚しつつ一人思う前に、超越的なものの影や、人々の社会的実践との連関にすでにさらされている。人格主義が思い描く個人の内的意識のドラマの領域が破られ、新たな立場が求められてゆくのである。この新しい枠組みは、後に『人間の学としての倫理学』において「観照の立場に先立ってすでに実践的連関の立場がある」ことの発見として定式化される。「実践的連関」はこの段階ででは人と人との行為的連関に限定されることになるが、和辻にとってさしあたり問題になるのは、自我は、孤立した認識主観として自らを対象化する以前に、その根底で外界の事物や他者との実践的なかかわりに組み込まれているという事態である。主観・客観の峻別を前提とする認識枠組の以前に展開する生き生きとした日常的経験においては、人間主体は自ら知らぬ間に己の外に出て、己を取り巻く諸々のものと出会い、それらと交流する世界において己を発見している。コギトの解体と実践的世界の発見とも言うべきこうした論題は、20世紀初頭以降のドイツ哲学が取り上げつつあったものである。 (2)見出された〈日本〉 和辻の留学中の観察の中心は人々の生活よりも自然環境に置かれる。和辻はしばしば、日本の気候の細かな変化に対するヨーロッパの単調さを強調し、日本では自然自身が人生を豊富にしてくれる。いくら暴風や地震があっても我々には日本の方がいいと、日本の自然環境に対する郷愁を露わにする。国民性の相違についての議論が、自然環境決定論の色彩が強い『風土』に結実するのも、外国生活における関心のあり方に規定されていたのである。そして、自然環境と人との関わり方に注目するとことから、和辻は日本人の国民性に対する強い共感を表明するに至る。当時ヨーロッパに留学した日本人はそうであるが、和辻の場合はとりわけ、現地人との交わりを欠いていた。そのため、ヨーロッパにおける観察は自然環境に限定され、自然の差異についての認識が、国民性についての見解を固着させていったのである。日本人の国民性のイメージは、現代日本人の行動観察ではなく、異国で過去の日本人のテクストを読むという特殊な体験を通じて描き出されたのであった。かつての理想的共同体としての古代日本のイメージが、古代ギリシャとの類推による幻想の産物であったとすれば、この時の日本的なるものの発見もまた同種の幻想性を帯びていたといえる。しかし和辻本人にとっては、日本的なるものは決して空想の所産ではない。それは数千年来変わらぬ日本列島の風土に基づいて、日本人が築いた生活様式によって培われてきた心性である。したがって日本人が物事を観察し、何らかの行為を行い、ものを考える時、その意識は日本的な国民性によって原初的に染め上げられている。それが和辻自身が新たに得た実感であった。 こうした実感を理論化し、「人間の学」としての倫理学体系への発展させる基礎を与えたのが、和辻が留学中、1927年に読んだハイデッガーの『存在と時間』であった。とりわけ和辻にとって重要な意義を持ったのは、その中で展開された世界内存在の分析である。現存在の基本的なあり方の基本構造として描かれるもので、現存在とそれを取り巻く事物や他者との関係は、もともと、認識する主体と客体的対象という図式が分解して見せるようなものではない。人が周囲世界の知覚像を獲得できるのは、すでに世界と出会い事物と関係しているからである。つまり主客二元論の認識枠組みが成り立つ以前の具体的体験では、現存在は環境的に出会う諸々の存在者と交流し、それぞれの意味を了解しつつ生きており、その諸関係のネットワークが織りなす世界において自己を見出す。これが世界内存在である。人が周囲世界のむ知覚像を獲得できるものとしても、そうした作用を行う人間主体はいかなるあり方で存在しているかをハイデッガーは問題にする。現に生きて活動する自己の事実的なありように即してみれば、世界は客体的な事物の集合では決してなく、主体はいわば世界に埋め込まれた形になっている。実践的世界の発見を最も鮮やかに定式化したものと言ってよい。そして、ハイデッガーが世界内存在に備わるあり方の一つとして情状性を取り上げたところに和辻は注目する。人は様々な物や他者と交流するあり方において、常にその都度何らかの気分を帯びており、喜ばしいとか恐ろしいとかいった気分の内に世界内存在としての己を発見する。和辻はこれを自然環境と人間との関係にあてはめ、自らの風土論へと発展させていく。和辻によれば、我々がたとえば寒さを感じる時、その体験は主観の境界外にある空気の冷たさを感じるというのではない。その時は自己と寒気との区別はなく、寒いという気分において、我々自身が寒さの内に出ているのである。そして、気候のみならず地形や風景なども含めた総合自然環境たる風土と交渉する中で人は自らを発見し、生活様式を築いてゆく。国民性とは、民族が長年の風土との関わりにおいて蓄積してきた生活様式によって培われたものにほかならない。『存在と時間』はその体験を風土論へと定式化する媒介をなしたのであった。 和辻にとっては、ハイデッガーが世界内存在を論じる際に、現存在が物と関わる環境世界のみならず、他者と関わる共同世界を取り上げたことが決定的な意味を持った。情状性において、道具的な世界と共同現存在すなわち他者との両方に出会う。したがって現存在は他者とともにある共同存在であり、他者が現われず孤独でいるという体験も、実はすでに自らが共同存在であるがゆえに、その不足状態として成立する。例えば、人が特定の環境において何らかの振る舞いをする時、その人は自らを孤立した自我として対象化する以前に人のうちに出ている。すなわち他者との関わりの中で自己を了解している。土下座体験において振る舞いの型の持つ力に衝撃を受け、その意味を考え続けていた和辻にとって、魅力的な考え方であったと言える。「私がある」という意識の根底には自己がすでに「世の中に表立ちてあること」の了解がある。「世の中」とは人と人との交渉関係すなわち間柄を意味する。人間という言葉はもともと人の間すなわち「世の中」の意味を持っていたということは、まさしく人が本質的に世の中における存在であることを示している。このことから、和辻の間柄としての人間観、人間の学としての哲学体系が生まれてくる。だが、ハイデッガーの分析は和辻にとって不満を残すものであった。和辻の関心は形而上的な存在についての問いにはなく、そうした問いの主体となる人間存在の身体的・実践的なありようにあり、環境世界よりも共同世界をより根底的に位置付ける必要がある。 (3)「人間の学」と時代情勢 一方、和辻が日本的なるものに目覚めたのは、民族協調が積極的に説かれ出した時期と重なる。和辻は明治維新を賛美し、ナショナリズムの存在を日本史全体に拡張して認めるようになる。和辻にとり、明治維新の第一の意味は、絶対主義の確立でも天皇政治の復活でもなく、ナショナリズムの政治運動化である。以前の和辻は大和王権による祭祀の統一が古代の国民的統合を生んだとまでは考えていたが、これに加えて、その原始的な信仰に基づく教団としての結合が、武家政権の成立や戦国時代の分裂にもかかわらず存続してきたと説き、その一貫性に日本の特殊性を見るのである。和辻が、日本におけるナショナリズムの超歴史的な持続性を確信した背景には留学体験に由来する特殊な事情があった。和辻は留学の途中上海に立ち寄った。27年のちょうどそのころ蒋介石の北伐軍が迫る混乱状態にあった。そこでの中国人と外国人態度の違いを目の当たりにする。中国人は動乱の噂に頓着せず、今現在の金儲けのことのみを考えているように映った。かれらは国家の権力の保護などは求めようとはせず、自分の金のみを頼りにする無政府の生活に徹するのである。これは、震災後の東京市民とは対照的に映った。震災と同様の一種の無政府状態において中国人は、互いに苦しみを分かち合い、助け合うどころか、他人の運命には無頓着に各人勝手に物を売り、危険が迫ると我先に逃げ出す。ここで和辻が発見した中国人の国民性は、まさしく現代文明の行動様式と共通するものであった。これと対比して、和辻は西欧留学を経て自覚した日本人の国民性を称賛することになる。日本人は、互いに助け合い、民族としての団結を基盤に全体の共生に配慮する社会的正義の実現に親和的な心情を備えている。従って日本人の国民性は、和辻にとって、よりギリシャ人的で人間性に近いのである。かつて古代日本─古代ギリシャに見出した湿やかな心情は、ここで現代日本人も超歴史的に共有する国民性へと位置を変更し、さらにナショナリズムの基盤と見なされるようになる。論文「国民道徳論」の中で、和辻は日本人の国民性の特徴を「しめやかな情愛」「距てなき結合」と規定し、その感情が古代以来綿々と続く「国民的団結」を支えたと説く。そしてこれが民族の伝統の根幹をなすとされるのだが、その時、同時に天皇位の持つ権威の超時代的持続が強調される。和辻によれば日本人のナショナリズム感情は、従来尊皇心として言い表されてきたのである。こう語るとき、単に過去の伝統の所在を確認しているだけではない。和辻の説くところでは、日本人の国民的団結の伝統は重大な現代的意義をも備える。 具体的には、民族の一体性を実現する組織としての国民国家への信頼が、以降の和辻の秩序構想の基盤をなすことになる。ここで国民国家は、単に国家の候成員と一民族が重なっただけの存在ではない。和辻の考えでは、日本に限らず、およそナショナリズムは社会的不正に対してとみに苦しみとともに憤る感情と結合し、道徳的理想を紐帯とすることで真のものとなるのであって、民族全体の共生を保障する社会的正義の実現に努めない限り、国民国家は本当意味では成立しない。この時和辻は、他民族との関係においても、利己的闘争を廃し国際的な協調に努めることが正しいナショナリズムのあり方と考えるが、それはあくまでも民族的自覚を媒介として成り立つとし、キリスト教に基づいた近代西洋の人類全体、普遍的道徳の立場を抽象的と批判する。普遍的な人間性が、それぞれの民族のナショナリズムに具現されることを通じて、コスモポリタニズムは初めて具体的な形を取るのである。しかし、いくら普遍的人間性の具体化と規定するとは言え、和辻の議論が、それぞれの民族の特殊な伝統にそれなりの価値を認める文化多元主義の立場をとることは明らかなのである。他方、用語は変わっても、堕落した現代文明に理想的な文化を対置する大正時代の発想枠組がこの時期の和辻にも残っていることはすでにみた。この利己主義を超えて調和を可能にする文化は、同時に全人類が普遍的に目指すべきものと考えられていたはずである。すると民族的伝統の強調と文化対文明の普遍的基準とはどう折り合いがつけられるのか。とりわけ日本人の国民性を和辻が賛美する文脈において重大な問題となる。これについて、和辻は日本文化の重層性という議論を提示することで解決を図った。日本的特性として何らかの文化的特徴を具体的に列挙するのではなく、さまざまな要素が併存する重層性が日本文化の特性だというのである。 ここで和辻の主眼は、日本文化の特質を単純な一面的な魂のごときものに還元し、日本精神という標語を政治的運動のただ一つの方向にのみ独占する世上の日本精神論を批判し、排外主義的傾向を斥けることにある。さらに、主君に対する個人的忠誠をナショナリズムと混同し、天皇=政府への国民の無条件的追従を説く忠君愛国、家族国家、大和魂といったスローガンへの批判が繰り返される。他方。マルクス主義者も含めて重層性に対する理解を持たずに近代西洋を猿真似する知識人も攻撃対象ではある。だが、日本文化の今後のあり方についての具体案は、大正期のコスモポリタニズムの主張と事実上は変わらない。西洋のすぐれた文化の輸入による日本文化改造と見てよい。日本文化の持つ重層性を説くのは、そのための素養を日本人が備えているという主張に他ならない。日本人は外来文化の吸収に優れているということを和辻は、最も重要な性質として前面に押し出すことで、日本主義哲学や皇国史観の鼓吹する排外主義的態度を批判する。言わば、世界文化のコスモポリタニズムの理想郷が、日本文化の小宇宙に内在しうると説いたのである。多種多様な文化を包み込む基体という日本文化のイメージ─戦後に日本文化論、日本文化批判の双方が多く前提としたもの─が、ここで積極的に創唱された。そしてこの重層性を活用し西洋文化の合理性を導入せよと説くのが、以後、戦時中から戦後にかけての和辻の議論の基調をなす。こうした東西文化の統一の仕事は、和辻によれば、現代では日本人にのみ可能な、世界史的任務なのである。このことは、古代ギリシャ人と日本人との共通性を新たに確認することにもつながっていた。和辻の発見した日本的なるものとは、同時にギリシャ的なものと考えられていた。したがって他方、その議論は諸民族文化の多様性を表面的には認めても、ギリシャ由来の理性の光を頂点に置く価値序列を厳然と保持することになった。 2.和辻倫理学の構造 和辻の中観哲学理解によれば、空を実現することは、すなわち道徳的当為としての慈悲の実行なのであった。ナーガジュルナの理論を和辻は次のように解説する。存在のかたである様々なダルマは、それぞれ個別にアイデンティティを持つのではなく、互いの関係(縁起)に依存して存立する。したがって相互関係において働く否定(差異化)の運動としての空がダルマを根拠づけることになる。人間主体が事物や他者を把握し、それに働きかける作用は、根源的には空によって支えられるのである。人間の行為においては、この空を体現し、空に帰ろうとする働きが、即ち道徳的行為なのであり、それは一切の生きとし生けるものに対する慈悲を本質とする。 和辻の体系はこうした空を前提とする。従って、間柄において個人と社会の相互否定運動を続けることは、空の実現としてすべてを生き生きと生かしめることで、そのことが和辻倫理学における善なのである。そして反対に否定運動を停滞させて、社会全体を顧みない利己的個人主義に走ったり、逆に個人性を抑圧して有機体に近似する社会を作ったりすることが、悪と規定される。青年時代以来の生命の主題の変奏をここに読み取ることもできよう。だが今度は、生命の光が偉大な文化作品や人格から輝きだすというのではない。光は、主体から切り離された対象の輝きとして看取されるのでなく、主体が自ら行為する働きの内に埋め込められたものとなる。 和辻倫理学の第一の特徴は、空の否定運動が、個人による人倫的な全体への帰属として行われると説くことである。この時、個人の実体が否定されているのと同様に人倫的な全体もまた実体ではないとされる。家族を論じる際には、父親が父親らしく、子供が子供らしく、それぞれの資格に応じてふるまうことのうちに、家族の全体が現われると説明する。その集団に属する個人がそれぞれの地位に相応しい振る舞い方をすることが、人倫的な全体への帰属の具体的ないみであり、そのことが道徳理法の実現だということになる。従って、人間の道としての倫理は、社会生活におけるふるまいの型に実現する。つまり、それぞれの社会集団の習俗として共有される型が、倫理の具体的な現われだというのである。人間の二重性格については、その個人性とは個人が型から外れたふるまいをすること、社会性とは旧来の型に固執し他者にもそれを期待することと定義できる。そしいこの両極の相互運動から、具体的によりバランスのとれた型が形成されていくのである。集団が伝統的に伝えるふるまいの型は、こうした否定運動の積み重ねを通じて洗練されてきたものということになる。 第二の特徴は、人間の外的な行為に基盤を据えて議論を展開し、個人の内的な意識がどういう状態にあるかを問わない点である。和辻によれば、行為は個人の意志から説明されるべきものではない。たとえば、同じ石を投げるという身体動作は、河原や海岸で行われれば行為ではないが、学校内で窓ガラスに向けて行われれば、投げる本人の心づもりがどうであれ行為となる。すなわち、観察者の視点からして他者との何らかの連関を持っていることが、行為を単なる動作と区別する基準なのである。主体的な人間の主体性とは、その人自身が内的自覚によって実感するものではなく、第三者の目から観察しうる行為的連関における事実に示されたことで、初めて認められるものなのである。したがって、社会生活において個人が何らかの型に従うということは、その場面での役割に相応しいふるまいを他者に披露する、演技としての性格を帯びることになる。和辻は、人格(PERSON)の言葉がラテン語のpersonaすなわち仮面に由来することに注目する。つまり、人間の行為とは、常に何らかの役割を遂行することである。日常生活は、仮面をつけて他者の前に現れる演劇舞台である。そこで人々は仮面をかぶって互いに演技しあい、その役割にふさわしい型を忠実に演じたとき、行動は倫理的と賞賛される。人格主義の調和の幻想の崩壊は、新たな人格の捉え直しを迫った。ここで人格は、個人の内奥に秘められた意識ではなく、外に見える多様なペルソナの束なのである。その点で、間柄における倫理は、徹底して外の倫理といえる。もっとも、人間が倫理的にふるまうためには内面的な要素が全く不要だと説いているわけではない。行為が道徳的たりうるための基礎となる態度として、他者による信頼やまことといった心術のありようを指定している。和辻によれば、日常生活で人が他者との関係において行為できるのは、お互いの信頼を暗黙の裡に前提とするからである。ところが、ここに言う信頼とは、人が行為をする時には、あらかじめすでにその持ち場に応じての行為の仕方が期待されているのであり、信頼とは、その持ち場に相応しい行為の仕方でふるまうことに尽きている。同様にまことも、個人心理としてでなく、信頼にこたえる態度がまことに他ならない。つまりは、信頼もまことも、それぞれの場面に相応しい型を絶対的な倫理の現われ見なし、それに則って行為しようとする態度のことなのである。言わば、与えられた役割を忠実に演じるための演技者の心構えに等しい。しかしこうした演劇的社会観というべき考え方は、個々の場面で複数の役割、したがって複数の規範が存在しうる場合に一体どれを選択すべきかという問題を引き起こす。これに対して、和辻は規範の序列を一応提示することで曖昧に解決を図る 第三の特徴は、その規範の体系化である。家族・親族・地縁共同体・経済的組織・文化共同体・国家という順番で、様々な組織形態を検討していく。そして、家族における親愛、親族における相互扶助、地縁共同体における慎み、経済的組織における職分の自覚といったように、それぞれの組織について行為の型を列挙する。そして、人が家族を出発点として、文化共同体・国家へとより広範囲の共同性に参与するにつれて、そこで従うべき規範は、より上位で根底的なものと位置付けられる。したがって、文化共同体の内で最も広い集団である民族と、民族の全体を具体的に実現する組織としての国家が、最高位を占めることになる。国民国家において、一方では統治者が全体の共生を確保する正義の実現に努め、他方では被治者が国法を遵守して防衛戦争への従軍義務を負うことが、最も優先されるべきモラルということになる。その意味で、国家は有限なる人間存在の究極的な全体性と規定されるのである。しかし、和辻の国家論の独自な点は民族と国家とを原則的に分離したことにある。民族は言語活動の所産である文化産物の共有を通じて成立する社会集団として、共同の法律秩序の下における組織的団体たる国家とは峻別される。従って、国家の活動の実質内容たる為政者の行動が、民族の共通の利益としての一般意志から離反する可能性も生じる。民族の共生に配慮しない恣意による統治は統率ではなく、単に権力を行使するだけの、非正当的な支配に過ぎない。従って国民が従軍義務の遂行を通じて国家に忠誠を尽くすことも、無条件の随順ではなく、国家が人倫の道を実現することへの参与であるべきだとされる。 3.戦時体制と「思慮の政治」 和辻は、政治体制についての見解と並行する形で、『倫理学』における秩序構想や日本倫理思想史研究の歴史的叙述が生まれている。まず、『尊皇思想とその伝統』は尊皇思想、つまり日本のナショナリズム思想の系譜を古代から徳川時代までたどったなかで、大和王権による祭祀的統一以来、日本人の国民的統一感が尊皇心として存続したという歴史叙述が繰り返されるが、ここで重要なのは、和辻が国民国家日本の原型をなすとして古代国家に関し、その祭祀=政治手続きについての言及が補足されていることである。つまり、律令体制成立以前の大和王権では、天皇は神意を占う太占によって政治決定を下した。それは記紀の記述に見る限り、八百万神や諸豪族が集まった前で行われる公の祭儀であった。そこで鹿の骨を炙って現われるヒビの形を解釈するのは祭司=天皇に任務であるが、恣意的解釈は許されない。人々の注視が外からの威圧を加え、その団体の解釈、その団体の意志によって天皇は束縛され、それを天皇より上位の「神の意志」として宣言するのである。つまり、神意とは人々の団体的意志に他ならない。こうした形で天皇が国民の全体性を表現することで、権力の支配と区別された権威による統率が可能となる。天皇の役割のこうした性格が、古代人が天皇を現人神と呼ぶ場合の神聖性の内容だったのである。ここに天皇機関説の論理の持続を見ることができる。天皇の位は国民の一般意志を表現すべきものであり、一般意志の具体的発見には議会による衆議が不可欠である。ちょうど、軍人・官僚による一元的支配に対抗して議会勢力を復権させようとする姿勢と重なっている。これと共に、古代王権における祭祀のイメージも修正されてくる。崇神天皇や垂仁天皇かアマテラス以外の神を祭った様子を記紀は語っている。これを和辻は、大和王権による祭祀の統一が、地方の神々の信仰を排除するのではなく、それを寛大に包容する形で行われたことを示すものとして重視する。日本の神道を一神教のように考え、他の宗教・信条を一切排除しようとする動向に対する批判がここに見える。和辻によれば、天皇=国家に対する宗教的帰依を国民の絶対的義務と説くのは日本の伝統に反する。尊皇の道は信仰の多元性を前提とし、あらゆる世界宗教に対する自由寛容な受容性を保障するものでなくてはならない。ここには日本文化の重層性の議論との関連もうかがえるだろう。 さらに『倫理学』中巻では、「経済的組織」の節を設け経済社会を人倫的組織の一つとして取り扱っている。それは、同時代の戦時体制をめぐる論争と関連する議論であった。1938年の日中戦争とそれに続く国家総動員法の成立によって戦時体制確立が合意事項となり、政府の計画・統制が資源配分を大幅に制御するシステムが現実化したのである。和辻の経済的組織論は、統制経済をめぐる問題にかかわっていた。『倫理学』中巻では、無秩序な営利の競争という経済社会像は、経済活動の本質を逆倒した見方だと主張する。つまり、マリノフスキーの未開社会研究を根拠に、物の生産・流通は、部族の紐帯や部族間交流など人倫的組織を形成する媒介として始まったと説く。従って経済活動は本来的には人倫的意義を持つとされる。ただ、現代経済における営利競争に対しては、人倫的意義を忘却し自己利益拡大の欲求におおわれたものとして、否定的な姿勢を維持してはいる。しかし他方、経済活動が否定的傾向を克服して人倫的意義を自ら回復する能力を、現代産業社会においても一定程度認めるのである。そして、統制経済については、政府による指令が自由競争を全面的に排する単なる外的強制を批判し、経済祖組織の本来の面目が人倫域組織にあることを自覚するが統制の前提として必要だと述べる。経済社会自身の自浄能力を尊重しなくては統制経済の実行は覚束ないという。これは同時代の統制経済を巡る論争の文脈から言えば、統制の実行に当たり、国家による一元的統制を廃し、経済界自身の自主統制を重視する構想と言える。 さらに『倫理学』中巻では、ヘーゲルが『法哲学要綱』で分化した多元的な秩序として市民社会─国家を描いたのと同様に、単純なポリス=国民国家の一体性イメージから離れ、多様な間柄が織りなす複雑に分化した秩序像を提起するに至る。ここでは、民族すわなち言語の共同を基盤として、家族・村・町・私企業・労働組合など多種多様な社会集団が折り重なって全体秩序を作り上げる。国家は、こり諸々の社会集団の集合に対し、外側からその全体を保護する役割を担うとされる。ほかの社会集団が個人を束ねたものであるのとは異なり、国家は諸々の集団を統合する機能を担う。そうした人倫的組織の人倫的組織として国家は唯一の存在であり、この意味でおおやけと見なされる。従って、国家が法を通じて強制力を発動する対象は、諸集団の活動に対する輪郭的・形式的な領域にすぎない。各集団のふるまいに関しては国家は介入せず、全集団の存続を外護することがその存在理由である。そして、国家において、国民個々人の政府に対するふるまいの型が法律の遵守と防衛戦争への従軍であるのに対して、政府の側は正義の実現に努める義務があると和辻は説くが、その正義の内容は、諸集団を維持・発展させ、全体の調和と存続を図ることなのであった。そして。和辻によれば、こうした正義を具体的状況において実現するための思慮である。それでは、和辻は思慮の政治をいかなるものと考えているのか。1933年のインタビューの中で政治を造園術のようなものだと説明する。つまり、政治とは、多様な人々を多様なままに統一して生かす技術なのである。個々の人間の多様性は、様々な草木に喩えられる。それらを巧みに配置し、全体の美観を作り出す営みが、造園術としての政治である。自ら運動する意志を持たない植物群の上に秩序を打ち立てる、一方向的な統御のイメージがここにある。したがって、この発想は庭園の作者ため政治家=指導者の力量へと収斂することになる。政治家の施す造園術とは、多くの人々を一つの気合いに合わせることである。気合いの統一とは『風土』で日本の造園藝術の特徴として述べたところであった。それは、植物の形状も気候変化も穏やかで規則正しい自然を相手にするヨーロッパ人とは対照的に、不規則で予測しがたい日本の自然の変化に適用しつつ人工の秩序を作り上げる方法である。そこでは自然の微妙な起伏を生かしつつ、それを一つの美しい全体に、しかも人工的の印象を与えない全体にまとめ上げることが重視される。気合いの統一とは、予断の許されない、非合理的な、従って運に支配された統一であり、柔らかな統一なのである。ここに見えるキウイの統一の観念は、和辻が政治の本質として説いた思慮のあり方に重なってくる。思慮もまた不断に変動し予断を許さない個別状況において統一を実現する知の働きであった。そして、すべてを一元的に統制する強権的秩序ではなく、個々人の信条や諸集団の活動の多様性を認めつつ、それらを柔らかく統合して生かしめることを目指すのである。しかし、この思慮は人々すべてが共有する能力ではなく、庭園作者たる指導者のみに期待され、指導者が全体を上からまとめる能力と考えられている。
終章 光と闇 しかし、とりわけ詳しく批判するのは、ハイデッガーの『存在と時間』である。存在の週末である死に対する不安は、匿名の誰かの死亡事件という一般的な出来事ではなく、ほかならぬ自分一人に固有なものとして体得される。そして人は孤独に死の不安に向き合うことを通じて他人によっては代わりえない己のみに限られた可能性を自覚し、存在の意味を真に了解できる。この考えに対して、和辻は激しい拒絶反応を示す。人間の死は、単に一人の個人の消滅ではなく、葬儀・一周忌など、消滅という事実に周囲の人々がかかわる一連の出来事を含む経過である。つまり、個人の死は間柄の作り上げる舞台の上で演じられるエピソードの一つに過ぎない。ハイデッガーの説く不安が指し示す死の闇は、「人間存在の全体性」の放つ光の明るみにかき消されたかのようである。ここで重視されてるのは、個々人の死よりも、彼らを人間的に生かしめる人倫秩序が持続してゆくことである。和辻は人間の本質を死への存在に見るハイデッガーの考えを否定し、徹頭徹尾生への存在を語る。しかもそれは、アトム的個人の孤立した生ではなく、間柄における生の保持に努めるという意味での生への存在なのである。この関連でも、文化共同体としての民族が、人倫組織の中で最も重視される。民族の一員であることにおいて、人は断片的なペルソナに解消されない真の人格を実現できる。すでに虚無や死の闇に脅かされる孤立した主体という考えを拒否した以上、それは他と断絶した独我論的な自己ではない。言語と文化産物の共有によって成り立つ精神共同体において互いに交流することを通じて、役割とは異なる自己の内なる本来的なるものが完成されるのである。役割=ペルソナの背後にある自己への問いに、和辻は一応こうした解答を提示した。ここで、和辻倫理学において民族とは、血縁や地縁を媒介にして、その一員であることに特別な意味を了解させるような実質を帯びたコミュニティではない。それは地域間の交通を通じて文化産物の伝達が行われる範囲であり、一定の言語の共有が構成要件となるのは、それが伝達範囲の限界を画するからに過ぎない。つまり、和辻にとって民族とは一種の情報空間である。人々は、メディアの支えるコミュニケーション網を通じて互いに情報を伝え合い、共通に文化を享受することによって、初めて人間らしく生きられる。自覚的に民族の一員となることが真の人格の実現であるとは、こうした意味に他ならない。さて、ここに言う真の人格とは、和辻によれば相互に信頼し合う友人として行為することだと規定する。ここでの信頼とは様々な型を演じる演技者の心構えにすぎない。ペルソナの奥にある真の人格とは、いかなる具体的な型からも切り離され、明瞭な顔を失ったまま、メディアの供給する文化情報の波に漂い続ける存在なのである。型の喪失の時代に育ちながら、それを克服すべく型の倫理学の構築を和辻は目指した。だがそれが社会生活における様々な型を並べたのちに最後に提示する人間の心のかたちは、仮面の裏側のうつろな空隙にすぎなかった。『存在と時間』は、大衆社会においてメディアがもたらす情報を受け売りにし、身近な接触から独自に事柄を判断することを忘れて平均化・画一化してゆく人々を、das
Manと呼ぶ。それは、ハイデッガーによれば、自己自身であろうとすることを忘れた、根無し草の頽落した人間あり方なのである。民族=情報空間における友人たちは、まさしくこのdas Manの姿に酷似している。 人格が断片的なペルソナの群れへと解体し、後には空隙しか残らない様子は、19世紀末以来指摘されてきた現代社会の病理現象と、まさしく重なっている。和辻倫理学の描く人間像は、一面、こうした状況をなぞったものであろう。だが、それは、人格の複雑化を積極的に受け入れ、自己矛盾を力強く引き受けること、あるいぱ軽やかに謳歌することを推奨することにはない。和辻の倫理体系において、様々な社会交渉の原型をなす基底的な共同性は、人々が画然とした表情を示さず穏やかに共存している。つまり、人々が互いに奉仕し合い、透明な心境で交流する感情融合的な共同体なのである。ここに住むのは鮮明な個性を持たない均質的な人々で、互いの葛藤や軋轢は存在せず、それゆえ自由が問題になることもない。いかに定義するにせよ、自由は自己と対峙する何ものかに直面する経験を通じて意義が実感されるものだからである。しずかに光の沁みわたった明るい空間で、人々は朗らかに文化情報を送受する。この情報空間を基盤に様々な人倫組織が並び立つ秩序が放つ光─ペルソナの亀裂が覗かせる闇から目を背けた和辻は、人間の生への存在を支えるそうした光の中へと向かっていったのである。したがって、秩序の全体を下支えする国家の権力もまた、この光を保障する生の権力ととらえられ、それが場合によっては構成員を否応なく全体戦争に巻き込む死の権力でもあることには注意が向けられない。ここでは、国家権力は常に聖なるものとの原初的結合を根底に保持し、威力であると同時に武力であるとされる。つまり、権力と権威の区別は実質的に消滅すると言ってよい。国家権力の発動が権威を帯び正当化されるのは全体性に配慮する限りにおいてであるが、組織としての国家それ自体がもともと権威を内在させているのである。こうした光を秘めた国家権力への信頼が和辻の秩序構想を根底で支えていた。政治権力の限界や、そのコントロールの問題は最後まで追求されずに終わることになる。 よく、ここまで読み込んでまとめたという作業の努力には、頭が下がります。ただ、この著作を読んでいて、これが和辻のすべてだとは思いませんが、和辻という人の考えは、かなり主観的というのか、かれの思想の根拠は全部彼個人の「これが好き」というように好き嫌いであるように見えて、あれだけ壮大な体系をくみ上げたとしても、それは、今でいえば思想オタクの独り言のようにイメージしてしまうのです。さらに、そのような独り言が、現実の人々や社会から離れたところで、個人の自己完結したものとしてくみ上げられ、それが現実に参加していくなかで、現実から攻撃され、妥協と転進を繰り返した挙句、戦時体制という現実に押し切られ、その本人は被害者意識から、その事実を認めようとしない。そんなように見えてしまうのです。そういう文脈で読むと、例えば『古寺巡礼』にような著作も、世間知らずの青臭い学生が思春期特有の悩みを抱えて、奈良に逃避し、減退から遠く離れた古代に憧れることで目を逸らし、あたかも、自分は人生に悩んでいるというような単純な屈折によるエリート意識の自己満足に浸っているような鼻持ちならない著作にも見えてくるのです。これは、著者である苅部氏が和辻に対して置いている距離感のようなものがそう感じさせるのかもしれません。 いずれにせよ、もう一度、和辻のものを読み直してみることも考えたいと思いました。 |
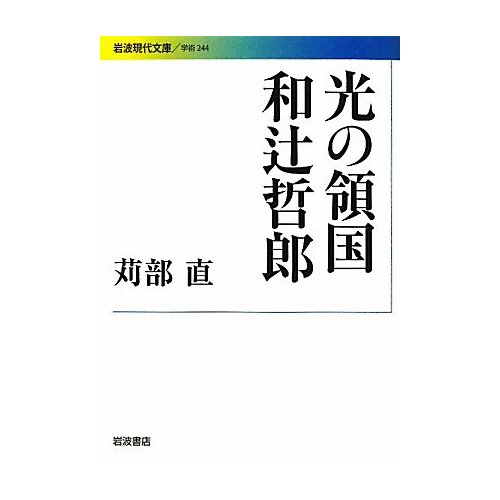 序章「土下座」をめぐって
序章「土下座」をめぐって